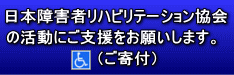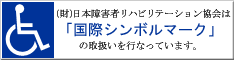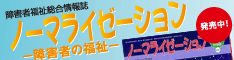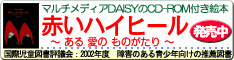障がい者制度改革推進会議 第35回(H23.9.26) 大濱眞委員提出資料
平成23年9月26日
障がい者制度改革推進会議
構成員 各位
社団法人全国脊髄損傷者連合会
副理事長 大濱 眞
24時間介護の確保と利用者負担の在り方について
地域で暮らす最重度障害者(1日24時間の重度訪問介護が必要な障害者)は、訪問系サービス利用者全体(12万人)の0.25%で300人以下に過ぎない。その総費用額は年額65.5億円である。今後、10年や20年をかけて地域移行が増えてもせいぜい1000人、総費用額の増分は年額130億円(国庫負担分は65億円)程度と考えられる。
よって、最重度障害者が1日24時間の重度訪問介護を受けられるように予算を確保してから、そのあとで、利用者負担の無料化など「命にかかわらない」課題に取り組むべきである。
このような意見は障害者全体の0.25%で、99.75%の障害者が利用者負担ゼロを支持するだろう。しかし、この0.25%の最重度障害者の命を無視しても良いのだろうか? この0.25%の最重度障害者の「地域で生活したい」という要望を無視しても良いのであろうか?
多くの障害者が「生きていくために必要な介護サービスに利用者負担があるは権利条約の理念と反する」と唱えていることについては、私も同感である。しかし、真の福祉の有り様とは、最弱者であっても「他の者と平等」に生きることが出来ることではないか。従って、99.75%の障害者のみなさんにも、この0.25%の最重度障害者のことを考えていただきたい。
現在、介護の時間が足りないために重度の障害者が、障害者が重くなればなるほど地域で生活できない。過重な負担が家族にかかる。このために年間数十件の介護殺人が起こっている。このように、わずかな0.25%の最重度障害者が差別的な状況にあることと、予算が限られている現状を踏まえて、まずはこの部分にスポットを当て、利用者負担ゼロの予算を最重度障害者の介護保障に充てるべきだと考えている。
その意味で、上記の「0.25%」に配慮し、当面の原則として現行の応能負担を維持する方向を、今回の骨格提言で打ち出していることを改めて評価する。
また「0.25%」の立場にあるのは、肢体不自由者のなかでは私たち1日24時間以上の重度訪問介護を必要とする障害者であるが、重症心身障害児・者が置かれている状況でも同じことが言える。
彼らに必要な環境は何か。ただ「地域へ」とは言い切れない。現行の福祉制度が未成熟な中で、高度な医療と手厚い介護を備えた入所施設以外の選択肢がないという重症心身障害児・者の要望を無視することはできない。
このような重度障害者を取り巻く「重い課題」の解決なくして、利用者負担ゼロなどの「次の課題」に取り組むことは出来ないと考える。しかしながら、今回の骨格提言に至る過程で議論を尽くせなかったので、重度障害者の問題を引き続き議論していただきたい。
参考1
相模原事件
ALSの息子殺害、心中図った母親に猶予判決
(読売新聞)-2005年2月14日
運動神経が侵され、体が動かせなくなる難病「筋委縮性側索硬化症(ALS)」の長男(当時40歳)の人工呼吸器を切って殺害し、心中を図ったとして、殺人罪に問われた神奈川県相模原市宮下本町、主婦菅野初子被告(60)の判決公判が14日、横浜地裁で開かれた。
小倉正三裁判長は「長男の嘱託を受けた」と、殺人罪より刑の軽い嘱託殺人罪の成立を認め、菅野被告に懲役3年・執行猶予5年(求刑・懲役5年)の判決を言い渡した。
判決などによると、長男は2000年秋にALSを発病。2001年3月に人工呼吸器を装着し、菅野被告が自宅で介護していたが、2004年8月26日、人工呼吸器の電源を切って長男を窒息死させた。菅野被告は、手首を切って倒れているのが発見された。
判決では、長男が人との意思疎通も困難になり、死を望むのも無理からぬ病状になっていた。訪問看護師や医師らの前でも死にたいとの意思を繰り返し表明していた――ことなどを重視。「被告は、これ以上長男を苦しませたくないと考え、自分も自殺することで、長男の日ごろの懇願を受け入れることを決意した」とした。
弁護側は、「長男本人に死を望む意思があった」と、承諾殺人罪を主張。検察側は、長男が文字盤を目で追って伝えた「おふくろ、ごめん。ありがとう」という言葉では、殺人を承諾したとは言えないとしていた。小倉裁判長は「母親が懇願を受け入れたことへの感謝と解するべき」とした。
(注:数年後に今度は母親が亡くなり記事になった)
「死にたい」妻殺害容疑で夫逮捕 難病の息子殺害後、うつ病に
(共同通信)-2009年10月13日
神奈川県警相模原署は12日、「死にたい」と願う妻を包丁で刺して殺害したとして、殺人容疑で相模原市宮下本町1丁目、無職菅野幸信容疑者(66)を逮捕した。
同署幹部によると、妻の初子さん(65)は、難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった長男=当時(40)=を自宅で介護していた2004年8月、長男の求めで人工呼吸器の電源を切って窒息死させ、自らも自殺を図ったとして、05年2月に嘱託殺人罪で懲役3年、執行猶予5年の判決を受けた。
菅野容疑者は「妻は事件後からうつ病になり、『死にたい』と言い続けるのをずっとなだめていた。『死にたい』と言うので刺した」と供述している。自宅からは「これで楽になれる」との書き置きが見つかり、同署は初子さんの遺書とみて調べている。
逮捕容疑は12日午後2時半ごろ、自宅の寝室で、初子さんの首を包丁で刺して殺害した疑い。菅野容疑者は約1時間後に相模原署に自首した。
参考(心中で記事になるのは氷山の一角という説明)
【介護社会】介護殺人、心中400件 制度10年やまぬ悲劇
(東京新聞)-2009年11月20日
介護保険制度が始まった2000年から09年10月までに、全国で高齢者介護をめぐる家族や親族間での殺人、心中など被介護者が死に至る事件が少なくとも400件に上ることが、中日新聞の調べで明らかになった。加害者の4分の3が男性で、夫や息子が1人で介護を背負い込み行き詰まるケースが多い。件数は増加傾向にあり、06年からは年間50件以上のペースで発生している。(シリーズ「介護社会」取材班)
過去10年の新聞報道をもとに調査。被害者が介護保険の利用対象となる65歳以上の殺人、傷害致死、保護責任者遺棄致死、心中など「致死」事件を拾い上げた。判明した400件のうち、殺人59%(うち承諾6%、嘱託3%)、傷害致死11%、保護責任者遺棄致死4%、心中は24%だった。
加害者の続柄は、夫と息子がいずれも33%。婿や孫などを合わせ、男性が4分の3を占めた。一方、被害者は妻が34%、母が33%。祖母などを合わせると、女性が7割以上を占めた。
加害者の年代は50代が25%と最多。60代22%、70代23%、80代13%となっており、60代以上の老老介護が6割を占める。
加害者の職業は、無職の割合が息子で62%。20代から50代に絞っても、61%とほぼ同じで、働き盛りの男性が介護のため職に就けず、経済的にも追い詰められていく構図が浮き彫りになった。
被告となった加害者の58%が実刑判決、41%が執行猶予判決を受けている。
調査は中日新聞、東京新聞(中日新聞東京本社)、共同通信と、北海道新聞、河北新報、西日本新聞など友好紙の過去記事をデータベースで検索。介護をめぐる事件を調べている湯原悦子日本福祉大准教授の資料も参考にした。
◆埋もれている事例も
介護をめぐる事件は自治体報告をまとめた厚生労働省のデータも警察発表された事例が漏れており、信頼できる公式統計がない。
警察発表も、心中の場合は「死亡が1人なら発表しないこともある」(警視庁、愛知県警)。「10年で400件」は文字通り、氷山の一角といえる。また、殺人未遂や傷害、暴行事件は警察発表がないか、あっても新聞掲載が見送られることも珍しくないため、今回は調査対象としなかった。
事件が家族間で起きていることも、表面化を難しくする。日本高齢者虐待防止センター(東京都)は「命にかかわるような虐待があっても埋もれているケースは確かにある」と話す。介護を受ける高齢者が「家庭の恥をさらしたくない」との気持ちから口をつぐむ場合や、近所の人が兆候をつかんでも通報に踏み切れない場合が多い。同センターには「警察や行政が動いてくれない」との相談もある。
◆先手先手の支援を
「介護殺人」の著書がある日本福祉大の湯原悦子准教授(司法福祉論)の話 介護殺人・心中事件には「2人暮らし」「心理的孤立」「経済的困窮」などいくつかの典型的な要素がある。保健、福祉、医療担当者が介護者の体調不良やうつ傾向に気づき、将来を予測した支援を先手先手で打っていく必要がある。
以下はCILリングリングHPより
高機能自閉症をめぐる現状と課題 家族の苦悩 浮き彫り
(神戸新聞)-2003年7月25日
パニック症状を起こす高機能自閉症の長男=当時(14)=の将来を悲観し、殺害した父親(57)に神戸地裁は今年五月、執行猶予付きの判決を言い渡した。判決理由で笹野明義裁判長は、高機能自閉症の現状について「社会的認知度および治療・療養施設などの公的支援体制がいずれもかなり不十分」と指摘。深刻な悩みを抱えながらも孤立せざるを得ない家族の現状が、裁判を通じて浮き彫りになった。高機能自閉症をめぐる課題などを追った。(社会部 藪中伸一)
筋ジス娘殺害 父親に猶予刑 大阪地裁 介護27年「同情の余地」
(神戸新聞)-2003年11月8日
筋ジストロフィーの長女=当時(27)=の将来を悲観し、人工呼吸を止めて殺害したとして殺人罪に問われた父親(51)に対し、大阪地裁は七日、懲役三年、執行猶予五年(求刑懲役五年)の判決を言い渡した。
並木正男裁判長は判決理由で「悪質な犯行だが、被告は二十七年間、愛情を注いで娘を養育してきた。ふびんに思う気持ちや介護による苦痛は相当で、同情の余地がある」と述べた。
判決によると、被告は五月八日午前六時ごろ、大阪市内の自宅で、寝たきりで食事も取れない長女の寝顔を見ながら「これ以上つらい思いをさせられない」と考え、長女の人工呼吸の管を手でふさいで窒息死させた。
判決言い渡し後、並木裁判長は父親に「長女はまだ生きたかったと思う。とむらいの念を一生持って生きてほしい」と語り掛けた。
無理心中?母が長男刺殺--神戸・垂水区
(毎日新聞・大阪朝刊)-2005年2月19日
18日午後7時45分ごろ、神戸市垂水区内の民家で、勤務先から帰宅した夫(60)が1階居間で妻(55)と長男(27)が血を流して倒れているのを見つけ、119番通報した。長男の腹部には包丁が刺さっており、まもなく死亡。妻は左手首などに切り傷を負ったが、命に別条はない。県警垂水署は妻が無理心中を図ったとみて、事情を聴いている。長男は自閉症で、近所の人によると、数年前まで通所施設に通っていたようだという。
神戸・垂水区の長男刺殺 殺人容疑で母親を逮捕 /兵庫
(毎日新聞・神戸版)-2005年2月22日
神戸市垂水区の民家で無職男性(27)が刺殺された事件で、垂水署は21日、男性の母親(55)を殺人容疑で逮捕した。
調べでは、母親は18日夜、自宅居間で、自閉症だった長男の胸を刃物で刺して殺害した疑い。
母親は左手首などに切り傷を負い入院していたが、21日に退院した。母親は精神科の病院に通院しているが、同署は殺人容疑に問えるとしている。【山下貴史】
入退院繰り返す 22歳息子を絞殺 中村、自首の父逮捕
(読売新聞)-2006年3月13日
愛知県警中村署は12日、名古屋市中村区西米野町、社会保険労務士河西滝夫容疑者(58)を殺人容疑で緊急逮捕した。調べでは、河西容疑者は同日午前4時ごろ、自宅居間で寝ていた無職の二男(22)の首をロープで絞めて殺害した疑い。二男の殺害後、玄関先で首をつって死のうとしたが、妻(50)に止められ、同日午前8時半ごろ、同署に自首した。二男は、統合失調症で約5年前から入退院を繰り返し、現在も通院中だった。「二男の将来を悲観して殺害した」と話している。
判決について、横浜地検の北村道夫次席検事は「主張が入れられず残念。判決内容をよく検討して対応を決めたい」としている。
知的障害の娘殺害 宮城県警が容疑で母逮捕 「介護に疲れた」
(神戸新聞)-2006年5月7日
宮城県警角田署は6日、自宅で長女(33)を殺害したとして、殺人容疑で同県角田市枝野寄井、無職佐藤隆子容疑者(55)を逮捕した。
調べでは、佐藤容疑者は5日夜、自宅1階の寝室で長女の首を絞めて殺害した疑い。
長女は知的障害者で角田市内の知的障害者介護施設に入所、佐藤容疑者も介護していた。調べに対し「介護に疲れた。娘をふびんに思った」などと供述している。長女が入所する施設によると、施設は3日から一週間の休暇になり、入所者が一時的に帰宅していたという。角田署によると、佐藤容疑者は普段は母親と2人で暮らしている。長女を殺害した後、佐藤容疑者らは同市内に住む妹に連絡、妹が5日午後11時頃「姉が娘を殺した」と同署に通報した。
その他
障害持つ36歳長男と63歳母が無理心中か 二男が発見
(読売新聞)-2004年1月4日
4日午前9時35分ごろ、東京都武蔵野市関前4の無職生駒良子さん(63)方を訪れた長男(36)から、「母親と弟が死んでいる」と110番通報があった。
警視庁武蔵野署員が駆けつけたところ、1階で二男の良さん(30)が顔に白いタオルをかけられ、布団にあおむけになって死んでおり、2階では良子さん(63)が首をつって死亡していた。2人とも死後1日以上経過しており、良さんは窒息死の疑いが強いとみられる。
1階の部屋から「自分が病気で、良を置いていけないので連れていきます」と書かれた良子さんの遺書が見つかっており、同署では、良子さんが無理心中をはかったとみている。
良子さんは障害を持つ良さんと2人暮らしだったが、良子さん自身も病気で悩んでいたという。
近所に住む主婦は「お母さんは、良さんが自立できるように、小さいころから洗濯など身の回りのことを教え、一生懸命だった」と話していた。
障害の29歳長女絞殺、父も首つり 川崎
(毎日新聞)-2005年3月26日
25日、川崎市のマンションの一室で、住人の無職男性(59)が首をつり、男性の長女(29)がふとんの上で、いずれも死亡しているのを、訪れた二女(26)が発見、110番した。高津署の調べでは、長女は首に電気コードのようなもので絞められた跡があった。同署は無理心中の可能性が高いとみて調べている。
障害25歳長男と母親が無理心中…遺書には「ごめんなさい」
(読売新聞)-2007年8月25日
24日午後9時10分ごろ、茨城県小美玉(おみたま)市下吉影、ちょうちん職人山下義弘さん(53)方の玄関脇の部屋で、長男康弘さん(25)があおむけに倒れ、妻正子さん(50)が首をつってるのを、帰宅した山下さんが発見した。
2人はすでに死亡しており、死因は窒息死とみられる。自宅からは正子さんが書いたとみられる遺書がみつかり、石岡署は、正子さんが康弘さんを絞殺した後、首つり自殺した可能性が高いとみて調べている。
調べによると、康弘さんの首には白いビニールひもが巻き付けられていた。山下さん方は3人家族で、康弘さんは障害を抱え、正子さんが身の回りの世話をしていたという。遺書には「ごめんなさい」などと書かれていた。
心中事件裁判員裁判 両親、長男殺害認める
(琉球新報)-2010年3月3日
2009年8月に名護市の海で無理心中を図って、身体・知的障害者の長男=当時(35)=を殺害したとして、殺人罪に問われた金武町金武の無職の父親(67)と無職の母親(62)の裁判員裁判初公判が2日、那覇地裁(吉井広幸裁判長)であった。2人は起訴事実を認めた。県内5件目の裁判員裁判で判決は5日に言い渡される。
公判前に裁判員選任手続きが行われたが、出席率は約63.3%だった。これまで全国で開かれた裁判員裁判で最低だったとみられる県内2件目の約69.8%をさらに下回った。
検察側の冒頭陳述によると、2人は自殺して得た保険金をマンション建設でつくった借金の返済に充てるとともに、長女ら子どもたちに残りの金を残そうと、自殺を考えた。一方で、自殺した後、面倒を見る人がいない身体・知的障害者の長男を残すのは忍びないなどと、道連れにすることを決めた。名護市の海岸に到着後、2人は睡眠薬を飲料水に入れて飲み、長男にも飲ませ、海に入っていった。母親は自殺を考えた時点で約3千万円の借金があったという。検察側は「自殺以外の選択肢はあった」と指摘した。
母親の弁護側は母親が長男を健康に生んであげなかったことに責任を感じていたなど、背景などを説明し、量刑を考慮するよう訴えた。
無理心中:障害の長男、介護疲れ 母子が車内で--東松山の関越SA /埼玉
(毎日新聞)-2010年3月25日
◇「もうがんばれない」
24日午前8時半ごろ、東松山市田木の関越道上り線高坂サービスエリア(SA)駐車場で、軽乗用車の中で男女がぐったりしているのを男性清掃員が発見し、道路管理会社が通報した。東松山署員が駆けつけると、駐車場の運転席でさいたま市西区の無職女性(52)、助手席で女性の長男(23)が死亡しており、トランクから練炭を燃やした跡が見つかった。
同署によると、長男は重度の知的障害があり、母親が介護していたという。自宅から「もうがんばれない」という内容が書かれたメモが見つかり、同署は母親が長男の介護に疲れ、無理心中を図ったとみている。【浅野翔太郎】
参考2
論考
「パーソン論」は、「人格」を有さないとする「生命」の抹殺を求める
びわこ学園医療福祉センター草津
髙谷 清
最近「パーソン論」という言葉が、書籍や雑誌に見ることが増えた。まだ一般的には広がっていないが、アメリカなどから輸入されているこの「思想」は、重症心身障害児・者にとって重大な問題であるので、この問題での執筆を依頼された編集者の先見性に敬意を表しつつ、「パーソン論」の内容と問題点を叙述したい。そのうえで、重い心身の障害のある人のことをどのように考えればよいのかについて述べたい。「パーソン」というのは、「人格」という意味であるが、「パーソン論」の内容は「人格」的であるどころか、重症心身障害児・者のみならず、「自意識」と「理性」を有しないとされた人間の抹殺を主張する「理論」である。
Ⅰ 「パーソン論」とはなにか
パーソン論の人たち
バイオエシックスという言葉は直訳すると「生命倫理」となるが、日本でもバイオエシックスという言葉のままで本の題名などになっている。1978年にアメリカで「バイオエシックス百科事典」が出版され、そのあたりからこの言葉は市民権を得たようである。安楽死、クローン、遺伝子治療、脳死、臓器移植などさまざまな問題を含んで考えを深めている。それらにかかわる一つの立場として「パーソン論」がある。1970~80年代から一部で蔓延してきた「思想」である。
パーソン論で有名なのは、ピーター・シンガー(オーストラリア出身の哲学者、米国プリンストン大学教授)、H・トリストラム・エンゲルハート(米国テキサス州ベイラー医科大学・医学哲学教授)、マイケル・トゥーリー(西オーストラリア大学哲学教授)、ロバート・トゥルオグ(米国ハーバート大学麻酔学教授)などである。
「人格」は、自己意識と理性的な存在とする
この人たちに共通している主張は次のようである。人間というのは「人格」を有している存在で、人格とは「自己意識をもち理性的な状態」である。それをもたないのは人間とは言えず、それは生物学的な「ヒト」である。つまり人間には、人格的生命(人間)と生物学的生命(ヒト)があるとする。
人格(パーソン)でないのは、次のような状態であると主張する。「植物状態、認知症、重度の統合失調症、生後1週間以内の新生児、無脳児、小頭症の新生児、重度の知的障害、広汎な大脳機能を失った患者など」である。「重症心身障害児・者」がないのは、それらの国ではその状態にある人も少なく、その名称もないためであり、その状態の人を知ったならば、当然というかまっさきに槍玉に挙げられるであろう。
もはや本当に生きているとはいえない-殺しても殺人罪にはあたらない
つぎのような文章がある。「小頭症の新生児、脳の損傷をうけた交通事故犠牲者、広範な大脳機能を失った患者などは、たとえ呼吸を続けていても、もはや人間でも人格でもなく、もはや本当に生きているとは言えない」「非人間化された単に生物学的な生命を、……死を歓迎したり、さらには死を導き招いたりするのを拒否することは、むしろ道徳的に全く悪いことになるだろう(ジョーセフ・フレッシャー、米国バージニア大学医学部・医学倫理学教授)」1)。
ロバート・トゥルオグは、「正当化された殺人」を主張する。「遷延性植物状態の患者」と「無脳児」からの「臓器移植」を「正当化された殺人」として法的に認めるという意見である2)。
ピーター・シンガーも言う。「人間の幼児や知能的に正常値に達しない人々を殺すことはそれ自体として間違ったことではなく、おそらく自分の時間を通じて存在しているという感覚を持つ高等な哺乳類を殺すことに比べれば重大なことではないと考えなければならないだろう」3)。「たとえばチンパンジーを殺すのは、重度の障害者で人格のないものを殺すのに比べて、より悪いように思われる」4)。さらに「無脳児と皮質死の乳児は死んでいないが、ドナーになりうる」5)と述べている。
シンガーを「読み解く」という本では、「もし今死ぬことが引き延ばされた痛みに満ちた過程で苦しむよりも患者の最善の利益になるならば、殺人はもはや悪ではない」「親が新生児の死を選択することが正当化できる場合がある」と紹介している6)。
研究用の利用を
エンゲルハートは、厳密な意味での人格は「自己意識をもつ理性的な行為者」であるとし、それがないのは「生物学的なヒト」であるとしているが、それとは別に「社会的な意味での人格」をもうけている。それは虚弱、病弱である人、障害のある人のことでがあるが、この人たちを「人格」として扱うのは、「厳密な人格」である個人に対して、利益があるかどうかということで決められる。決めるのは「厳密な人格」の人である1)7)。
「医学は人格の医学である」「生物学的生命の単なる延長を目指すのではない」「高次脳中枢が死んだ人間の身体には心的生命・人格はない」「殺人とは人格の生命を奪うこと(髙谷注:したがって人格でない生命を奪っても殺人ではないという意味)」7)
さらに、殺すだけではもったいないから、研究用に使うという提案をする。エンゲルハートは、「脳死状態に陥った後にも人間の生物学的生命が存続するということで、ウイラード・ゲーリン博士が『医学上の実験および教育のためのすぐれた材料源を提供しうる〈脳死状態〉で生命を維持することを推奨している』と公言している」1)ことを紹介している。
文献7)の訳者は「解説」で次のように述べている。「人格が非人格を所有するという概念枠によって、人工中絶を正当化することは、所有権=処分権をもつ者の自己決定権に根拠をおくことになる。胎児は所有物だという理由である。胎児の研究用の利用、売買、代理母などは、すべて正当化可能である」と書いている。
「人格をもたない」とされる「人間」の臓器移植用のドナーから、輸血の供給源、移植皮膚の供給源、薬の開発用、医学生などの教育用などの意見がだされている。書くのもおぞましい話である。
Ⅱ 重症心身障害児・者はどういう存在か
重症心身障害児・者は「パーソン論」の最右翼の対象にされる
知的に重度の障害があり、しかも身体的に重度の障害を伴い、さらにさまざまな合併症のある「重症心身障害児・者」は、上記の「パーソン論」では、「人格はまったく存在しない」「生物学的なヒト」の最右翼に位置されてしまうであろう。ましてや自発呼吸のおぼつかない「超重症児・者」の存在は論外であろう。「パーソン論」によると、すべて抹殺されてしまうことになる。殺すだけではもったいないので、臓器移植のドナーにしたり、輸血源や移植皮膚源にされ、教育や実験材料として役立てることにされるかもしれない。
なんともおぞましく、恐ろしいことである。このようなことになるはずがないと思いたい。人間はこのように重い障害をかかえて生きている人に憐憫の情や愛情を感じ、大事にしようと思う心をもっている生き物であると信じたい。しかし状況次第では、このような人が生きている値打ちがないと思う風潮に支配されてしまいかねないとも思う。
過日、びわこ学園に見学に来た外国人グループが、さかんに「かわいそうに」と言っていたということである。その場にいた職員は、この人たちも「重い障害をかかえて生きているこの子らがかわいそうだ」と感じていると思ったそうだ。しかしよく聞くと「障害が重いからかわいそうだ」ということではなく、「これだけ重い障害があるのに生かされているのがかわいそうだ」という意味であったと、その場にいなかった私に憤然として語ってくれた。私もそのことは腹立たしかったが、そのような考えもありうると思った。たぶんそのように語っていた見学者は、「抹殺するのがよい」と思ったのではなく、「この状態で生きていて幸せなのか」という気持ちであったと思いたい。私自身も超重症と呼ばれる子を前にして立っていると、「生きているのが本当に幸せなのか」と本人にも自分自身にも問いたくなることがある。そして、生きていることが幸せであるという状態になるようにするのが、自分たちの役割であり、仕事であると気をとりなおすのである。
重い心身の障害で苦しんでいる状態が、そのままでよいとは誰も思わないであろう。「死んだほうがましなのではないか」と思うのか、「生きているのが幸せだと思うようになるにはどうしたらよいか」と思うかの差であると感じる。それは個人的にはどちらに感じても批判されることはない。それは個人の感じ方であり、どのように感じようとそれが実行されないあいだは、重い障害のある人にとってなんら影響がないのである。しかしそれを実行しようとすると、たちまち、対象とされるその人にとっては「死」か「生」かという問題になる。そのことを実行しようとする人と、そのようなことに反対の人は、許しあうことができない関係になる。しかし一般的には、感じたり考えたりする内容はさまざまであっても、それ以上にことはおこらないであろうし、また人の考えは変わっていくものである。
恐ろしいのは、その考えを正しいと信じ、「理論化」し、現実に「抹殺」を謀ろうとする動きであり、そのような狂信的な集団の出現であり、ときにはその時代の「権力」と結びつき実行に至ることである。「パーソン論」は、人間を二種類(「人格をもつ人間」と「生物学的なヒト」)に分かち、「ヒト」を殺しても殺人罪にはあたらないとし、「自意識と理性という人格があるとする人間」のために利用しようとする危険な動向である。この「パーソン論」に人間抹殺の危険性を感じるのは、けっして過敏な反応ではないと思う。
かつて、カント・ヘーゲル・マルクスなど人間と社会を洞察し、近代を切り開いた多くの思想家を輩出したドイツにおいても時代の流れのなかで、ユダヤ人を「劣等人種」と称して抹殺するナチズムという「思想」が勢力を得て、権力を掌握し、600万人といわれるユダヤ人を文字どおり抹殺した歴史的な事実は消し去ることはできないのである。障害者も抹殺の対象とされた。
「パーソン論」を批判するとともに、私たちは「重症心身障害」という状態をどのように考え、その状態にある人にどのように取り組んでいったらよいのかを明らかにし、そのことによってこの人たちが幸せな人生をおくることができることを求めて、とりくみをすすめることが大事であると思うのである。
重症心身障害児・者は「自己」として存在している
この人たちは、脳に重大な障害を受けたために心身の重い障害をもち、理解する能力が損なわれ、身体を自由に動かすことができない状態にある。年齢を重ねても「自己意識」は育っていないことが多いと思われる。しかし、「意識」は育っていないかもしれないが、「自己」は育っている。
「自己」とは何か。この人たちは重い障害があるが、感覚があり、身体があり、外界とつながっている。「自己」は、感覚や身体を通じて外界の環境の影響を受け、彼を介護し身体の維持にとりくんでいる他者から、感覚や身体を通じて大きな刺激を受ける。そこに「快」や「不快」が生じる。「自己」は、それらを感じ、変化していく。原初的な「快」や「不快」は、徐々に複雑な感覚になり、やがて感情といえる何かが育っていくであろう。この人たちは、こうした「自己」があり、本人が意識しようがしまいが、人間として人間のなかで育ち、変化し、そこに「快」を感じ、「自己」として存在する。
脳の損傷のために、存在し変化する「自己」を意識する「自意識」は育ちにくいであろう。しかしそれは「人間として存在していない」ということではない。その人は人間の関係のなかでひとりの人間として「自己」が育っているのである。その「自己」の育ちによって、その人をとりまく人びとの意識も育つ。重い心身の障害のある人が「人間」として存在していることを感じ、ともに人間として生きていくという気持ちが育つのである。「自己と他者の共同こそが人格の本質であり、実在するものの真の姿」8)なのである。
「この子らを世の光に」
糸賀一雄9)10)は、こうした重い心身の障害のある子らと接して、彼らが「光」を湛えているのを感じた。それは何も欲張らず、何も我が儘(まま)を言わず、ひたすら「いのち」を生きる姿である。「いのち」そのものの大事さを、その「からだ」が表現している、訴えている。そして糸賀は、その子らにとりくむ職員のなかにも同じ「光」をみている。それは他者を「可能性自己」として犠牲にする「利己的な自己実現」ではなく、排他的でない「他者実現とともにある自己実現」である11)。
だれもが人間としての「光」を、そのままに生きることができるようでありたい。そのような世の中でありたいと糸賀のねがいが「この子らを世の光に」の言葉に凝縮されている。
「いのち」「からだ」「こころ」そして「脳」
「いのち」そのものは、すがたかたちがない。「いのち」は「からだ」とともにある。そして「いのち」は「こころ」をもっている。「こころ」は、「からだ」の動きや表情、声、そして言葉で「こころ」自らを表現する。人間は、500万年前のその生成当初から弱い生き物であったから、お互いに「協力、分配」して、「共感」しあって自然界に働きかけ、「からだ」と「こころ」を発展させた。そしてこころの表現はだんだんと巧みになり、豊かになり、「ことば」を発展させてきた。さらにお互いに「共感」することが深くなった。そうしたことで「脳」が徐々に形成された。
「脳」は「からだ」や「外界」(自然環境、社会環境、人間関係)からの「刺激」(情報)を得て、「からだ」の反応をおこす。「脳」は「からだ」や「外界」からの刺激(情報)を得て、「こころ」の反応をおこす。
「反応」は「反射的」から「統合的」になった。「脳」は、「からだ」や「こころ」の「統合的器官」となり、過剰にも「中枢」と呼ばれるようになった。「中枢」には、情緒、感情、知能が発展した。意識も発展し、「意識」が「意識」されるようになり、「自意識」が生まれた。
そして「パーソン論」者は、この「自意識」こそが人間である証(あかし)だという。だが人間形成の過程を考えてもそうではない。人間の「自意識」や「理性」といわれるものは、人間が「からだ」を使って、「協力・共同」し、得たものを「分かちあう」ことによって「こころ」を豊かにし、「共感」する「こころ」を育ててきた。けっして突然「脳内」に「自意識」や「理性」が生まれたものではない。「協力・共同・分配・共感」という基盤があってこそ「人間」が生成してきたのであり、そのことなしには抽象的な「自意識」も「理性」もない。その基盤にこそ、人間の特質がある。個々人には「障害」のために「自意識」が育たないこともあるであろう。だが重い障害のある人とのあいだで、人類が経験してきた「協力・分配」がなされ「共感」することこそが人間の特質であり、協力する人も、される人も人間として存在し、人間的な「こころ」が成熟していくのである(ただし動物にはないというわけではない)。
身体器官は、心臓・肺臓・肝臓・膵臓などの内臓、眼・耳・鼻・舌などの感覚器官、外界と隔て守り・感覚機能も有する皮膚、身体を支え・運動をつかさどる骨・筋・腱、それに神経系、血管系、内分泌系、免疫をつかさどる等のさまざまの系、それぞれの役割をもつ器官・機能が総合的にはたらくことによって支えられている。それぞれの器官が総合のなかで独自のはたらきをもっているように、「脳」という器官は身体機能、精神機能を「統合する」という独自の役割をもっている。それはけっして他の器官や働きを「支配」している「中枢」器官ではなく、「統合」するという役割を有しているのである。
器官的には「脳」が、そして機能的には「自意識」や「理性」が人間ということではなく、人間の各器官が、総合的に有機的にはたらくことが大事であり、そのなかで脳は「統合する」という役割を分担しているということである。人間全体として人間なのであり、「からだ」も「こころ」も、そして「脳」も含めて、「いのち」であり、「人間」であり、そのことが大事なのである。「脳」だけが大事であるという「脳」人間は、健全な人間ではないのである。
「いのち」は、「脳」ではなく、「からだ」と「こころ」にやどる。「脳」もまたからだの一部であり、それは「統合」の役割を担っているということである。「脳」の障害が重くても、「いのち」が生き、「こころ」が存在し、その「いのち」や「こころ」は「からだ」で表現される。
「生きるよろこび」と「生きがい」について
重い心身の障害があり、生きていく困難があるとき、その身体機能はうまく働らかず、その状態は本人にとっても「不快」であろう。その心身の障害のために多くの介助や医療的な処置や機器の使用も必要となる。そしてそれらの支え、援助によって身体機能が改善するとき、その存在は「不快」から「快」に転化する。この「快」の状態が人間にとってもっとも基本的で、大事なことであろう。自己の存在そのものが気持ちがよいということが人間(あらゆる生き物)の存在にとってもっとも基本的なことであろう。
重症心身障害といわれる状態があって、身体が「快」の状態になるということは困難ではあっても不可能ではない。すでに多くの経験が積み重ねられている。そしてその「快」の状態が、それぞれの「生きがい」につながっていくであろう。
私たちの仕事を深め、社会へ発信することの大事さ
「パーソン論」はなんとも恐ろしい「考え」である。今のところ日本であからさまにこの主張をしている人はないであろう。だが文献6)の著作は、シンガーの「実践倫理」を日本に紹介する形をとっているが、その内容に賛同しているがための紹介である。また「パーソン論」がたくみに近寄ってくるとき、とくにこのような心身ともに重度である人たちの実際を知らない人のなかには、善意から「そのように重い心身の障害があり、苦しんでいる人たちは生きていること自体が苦痛なのだ」と誤ってとらえて、「死なせるのが本人のしあわせである」という考えに影響をうけたり、その考えに表面的な「共感」をすることがないとは言えない。
こうしたことを考えても、直接重い心身の障害のある人に接している私たちが、人間の人格・人権を奪うどころか、まさに生命を抹殺することを合理化・合法化しようとするこのような「論」に反論し、だれにも存在する「人格」「人権」「生命」を守っていくとりくみをすることが必要であろう。そのためにも私たちが日頃接している重い心身の障害のある人たちのことや、その人たちにかかわっている仕事の役割や意義をきちんと位置づけて、その内容や大事さを明らかにし、分かりやすく表現し、一方で「パーソン論」などの問題点を指摘し、世の中に発信していかなくてはならないと思うのである。
〔追記〕
自意識・理性と人権・人格
封建制度の時代、資本主義社会の初期の時代に、あまりにも悲惨な状態におかれた人間の生活状態、人間の尊厳をないがしろにする扱いをうけている状態に対して、「人権」を確立する社会運動が起こった。その犠牲と努力の結果、人権の確立がすすみ、それは大きく次の三つの時期と内容に要約される。18世紀後半のアメリカの独立宣言やフランス革命で確立した「自由権」、20世紀初頭のドイツ・ワイマール憲法(1919)に象徴される「社会権」、そして第三世代の人権と言われる、1980年代からの「発達権」(平和・環境保全・生存・健康権等を含む)である。
また思想的にも、多くの人びとによって人権や人格の確立へ向けた努力がなされた。「理性、認識、自己意識、倫理、人権、人格、社会」などの問題が深められた。
これらの社会的発展、思想的な深化は、それまでの時代の人権・人格侵害に対して「理性や自己意識」を強調したのであり、その思想の本質には「人権」「人格」の確立があった。こうした流れのなかで、障害のある人、重い障害のある人たちの人権・人格の確立がなされてきた。
「パーソン論」は、「理性と自己意識」を他から切り離し、孤立させ強調することによって、多くの犠牲をはらって確立し、定着させてきた「人権・人格」の思想と制度的確立を破壊する「思想」である。人間の「理性と自己意識」を尊重するように見せかけて、人間の「人権・人格」を奪い、「高齢」「疾病」「障害」の状態にある人間を排除する思想であり、そのような社会運動であると言える。
生きていて「かわいそう」か
「重症心身障害」という状態は、身体的に重い障害があり、移動ができない「ねたきり」の状態が多く、重い精神発達遅滞を伴い、さらに今日では呼吸や消化という生命維持機能が強く障害され、生きていくそのこと自体にも困難が生じる状態もある。
このことには次の二つのことが含まれている。一つは、身体的および精神的に障害が重いために機能的な不自由さが存在するということであり、もう一つは、その障害の状態が、その人にどのような苦痛を与えているのかということである。
重い心身の障害のある人が、どういう状態が自分にとって良好であるかの自覚はないであろうが、本人の機能的制限や苦痛が軽減され、安心した人間的関係という雰囲気や状態が存在することが、その人が生きていくのに「快適な」状態となるであろう。「からだ」自体が自分の存在を「気持ちがよい」と感じる状態にあることが、生きているもっとも基本的なよろこびがあるのだろうと思う。気持ちがよい「からだ」は、「いのち」が気持ちよく存在していることであろうし、「こころ」が安心しているのであろうと思う。
「生かされていてかわいそうだ」「生きているほうがよいのであろうか」ではなく、「生きていることが快適である」「生きているよろこびがある」という状態が可能であり、そのように実現をしていくことが、直接かかわっている人の役割であり、そのようなことがなされうるようにしていくことが、社会の役割であり人間社会の在りようではないかと思うのである。
文献
1)H.T.エンゲルハート他、加藤尚武他編「バイオエシックスの基礎」東海大学出版会1988
2)黒瀬勉「ドイツにおける脳死論議の現状」医学・生命と倫理・社会 Vol.2 No.1 2002
3)ピーター・シンガー、浅井篤他監訳「人命の脱神聖化」晃洋書房 2007
4)ピーター・シンガー、山内友三郎他訳「実践の倫理」昭和堂 1991
5)ピーター・シンガー、樫則章訳「生と死の論理」昭和堂 1998
6)山内友三郎・浅井篤編「シンガーの実践倫理を読み解く」昭和堂 2008
7)H・T・エンゲルハート、加藤尚武他訳「バイオエシックスの基礎づけ」朝日出版社 1989
8)波多野精一「宗教哲学」波多野精一全集 第4 巻 岩波書店 1949
9)糸賀一雄「この子らを世の光に」柏樹社 1965、日本放送出版協会(復刻版) 2003
10)糸賀一雄「福祉の思想」日本放送出版協会 1968
11)髙谷清「異質の光─糸賀一雄の魂と思想」大月書店 2005
参考文献
1.加藤尚武・加茂直樹(編)「生命倫理を学ぶ人のために」世界思想社 1998
2.木村利人他「バイオエシックス ハンドブック」法研 2003
3.陀安広二「パーソン論はどのような倫理か─シンガーを中心に─」医療・生命と倫理・社会 Vol.3 No.2 2004
4.ピーター・シンガー、山内友三郎他訳「実践の倫理〔新版〕」昭和堂 1999
5.小松美彦「脳死・臓器移植の本当の話」PHP新書 2004
6.江口 聡「国内の生命倫理学における『パーソン論の受容』」京都女子大学現代社会研究 第10号 2007
出所:『西日本重症心身障害児施設協議会広報』第9号、2011年。
参考3
「この章ではALSの家族にも目を向けてみよう。長期にわたる介護により持病の悪化、進学、就労、結婚の機会喪失、離婚、貧困、暴言暴力などが深刻だ。他者の介入が難しいケースも少なくない。
だが、家族の問題を放置すれば患者に危険が及ぶ。家族関係に風穴を開けるためにもヘルパーの滞在は不可欠だ。だが、家族は他人が家に入ることに抵抗を示すことがある。患者も家族にしか介護をさせたくないなどと言う。でも、それでは長生きするほど迷惑な存在になってしまう。
家族が患者に病名を伏せたくなるのは、自分たちの負担を考えてしまうからでもある。生計を共にする家族は、患者に生きてほしいなどとは気軽に励ませなくなってしまう。負担を考えれば当然のことだ。家族がすべてを投げ捨てて介護に没頭する覚悟を示さなければ、家族がいるALS患者は呼吸器を付けられない。医師にしてみれば。呼吸器を付けた後になって、家族に恨まれることがあるから、励ます言葉もでてこないばかりか、家族を呼んで、そっと厳しい現実を示すことにもなってしまう。
こうして、家族と医師とで相談して、治療方針もほぼ決められてしまうのだが、それでもALSの患者は生き延びてきた。自己決定を迫られても白黒はっきりさせないことが唯一の救命への道なのだ。無策無援にもかかわらず、救急車で運ばれて呼吸器がつき、生き永らえることになったALS患者たち。そんな彼らの要望に応えるようにして、社会の仕組みが後追いで作られてきたのである。幸いなことに、人類には弱者の声に耳を傾け、呼応し解決しようとする本能があり、そのおかげでたった1人のALS患者が生きられる道を模索していくことになるのだが、これが倫理というものの本質ではないか。」
「この男性患者は生存を懸けて県の障害福祉や病院の体質を改善するつもりでいたが、関係者にはそれぞれの建前があり誰も味方についてくれず、達成できずに死んでいった。これは決して特殊な事例ではなく、各地で同様のことがいつも起きている。ALS患者が地域で生きていくためには、生存を運動に発展させ、自分で各方面に交渉しなければならない。生存に必要な財は自分で勝ち取らなければ得られないのだ。
長期療養のALS患者のほとんどは、自治体や関係者と個別交渉を繰り返し生き延びてきたツワモノたちである。夢破れて無念のうちに亡くなる者は後を絶たないが、現在の重度障害者のための介護制度が市町村の税を多く使う仕組みである以上、市町村は長時間介護を必要とする個人への多額な分配には理解を示せないことになっている。
介護制度の財源の在り方を市町村の負担にならぬよう、国が責任を持てる仕組みに抜本的に変えるべきであるが、これは政治の話でもある。」
「要するに、支援の欠如で絶望させられる前のALS患者が求めているのは、重度障害者としての人生を豊かにするための、さまざまな法整備・支援技術である。*12 家族に頼らない介護保障を充実させるまでは、命にかかわる人工呼吸器治療の選択を、倫理や医療経済の練習問題などにしないことだ。難治性疾患の患者が抱える問題は、安楽な死を帰結としては決して解決できないと知ることである。これはこの時代に生きる私たちの務めである。」
出所:川口有美子「人工呼吸器の当事者からみたALS」
『生命倫理』第八巻、丸善(近日刊行予定)から抜粋。