発達臨床-人間関係の領野から-
NO.2
第1部 発達臨床の基本的な考え方
第1章 発達臨床法
1.児童臨床における発達的アプローチ
「発達臨床」という言葉は、現在ではそれほど耳新しいものではなくなったが、実践的にも理論的にもまだ体系化されているとは言えない新しい概念である。とはいっても、まったく一から構築することが求められているという意味で新しいということではない。これまで積み重ねられてきた、医学・心理学・教育学など多くの近接諸領域の臨床的成果をその土壌において共有しながらも、そのどれかに従属したりあるいは包含されたりすることのできない、この領域独自の学問的枠組みと方法論の確立への現実的要請に応えうる新しい体系の構築が必要とされてきているのである。
「臨床」という言葉はそもそもは医学用語に由来し、‘病床に臨んで診断、処置する’ということからきている。心理学の分野においても、従来は、臨床という語は、“問題をもった個人に関し、その原因、状態などの全貌を理解し、問題像を診断し、それに対する適切な処置を決定していくというような一連の実践的活動”(戸川行夫、1963)に対して用いられてきており、そのような臨床的実践的活動のために用いられる技術方法が「臨床法」であると定義され、臨床心理学として独自の学的、実践的体系を発展させてきた。しかし現在では、臨床という言葉も、臨床法という方法も、もう少し広い意味に解釈されて用いられているようである。たとえば、発達心理学などの分野においては、研究の一方法として、特定の個人あるいは集団について何らかの形で関与しながら追跡的に観察を行い、分析や考察が加えらえる方法を臨床法と呼び、たとえばピアジェの研究方法もその範囲にいれている。
「発達臨床」は、このような発達研究における臨床的アプローチともいえる側面からの体系化も可能であろう。研究方法という点から、客観的・実験的手法にいわば対置するともいえるような臨床法を適用して人間発達の諸現象を解明していこうとする立場の重要性は今後ますます認識されていくにちがいない。しかし、本書の立場はそれとはやや異なる。従来の臨床活動、特に児童臨床の分野において発達という概念が重視されるようになってきた背景をふまえ、児童臨床における発達的アプローチという側面から発達臨床の概念の構築に寄与できればと考えている。
いま私は、たまたまふたつのアプローチ、発達研究における臨床的アプローチおよび児童臨床における発達的アブローチというフレーズにおいて、発達という言葉を共通に用いてきた。もちろん、語義的には同一概念を有するものであるが、どこに関与する人の視点をおくかということにより、発達のとらえ方にいささかの違いが生じるように思われる。比喩的ではあるが次の例について考えながら、発達という言葉のとらえ方や用い方も一様でないことをあらかじめ確認しておきたい。
発達研究においては、人間の発達の本質について述べようとする場合、発達というものが生得的要因に導かれて自動的に進んでいくわけではなく、生まれ育つ社会での経験や後天的環境要因が不可欠であるということを説明するために、偶然にも人間社会から隔離され、通常の生育環境を剥奪されて育ったケース-いわゆる野生児など-などを例にあげてコメントをすることがよくある。ある発達研究者は、それらのケースにおける子どもたちは、その後の獲得された行動をみてみると、たとえば、言語についていえば、治療教育的かつ愛情あふれる保護と養育をうけたにもかかわらず、さらにコトバを覚えるのに必要な器官が健全であったにもかかわらず、数語にても言語を獲得した例は少なかったという事実から、‘「ヒト」に生まれても「ヒト」にはならない野生児’というキャッチフレーズをコメントに冠した。
それにしても、この‘「ヒト」に生まれても「ヒト」にならない’というフレーズは、これまでの発達研究の集大成における発達の基本概念を一言で言い得て妙であると思う。つまり、ここでは、「ヒト」概念は「人間発達における正常」という言葉と同義に用いられており、発達という脈絡における人間理解は一般的・普遍的な共通特性の把握に向けられていくことを示してくれることにおいて明解である。
一方、児童臨床の立場から上記のようなケースについて同様の比喩的な言い方をするとすれば、「ソノヨウナヒトになる」ということになるだろうか。つまり、ある行動-コトバならコトバが獲得される場合、獲得された結果も大切であるが、むしろその過程において人間存在の多様性を認め、そして、ドノヨウな枠にも組みされ得ないひとりひとりの全人的・個別的な特異性、いってみれば「ソノヒトになる」ということをも強調する人間理解を究極の目標としているといえるかもしれない。
本書では、大変欲張った言い方であるが、児童臨床の立場を基軸にしつつ、特定個人の全人的理解の過程が、人間発達一般の解明へと向かう道筋のどこかで接点をもっことも可能であろうという観点から、「発達臨床」あるいは「発達臨床法」の考え方と方法を明らかにしていくことを目的としたい。
2.臨床における子どもの理解
(1)量的考察-発達的変化の把握
私たちが、児童臨床に「発達」という概念を導入する限りにおいて、意識するとしないとにかかわらず、また、そこに価値性を付加するとしないとにかかわらず、さまざまな基準枠を設けて子どもを理解しようとする。では、「発達」という概念のもとに、どのような枠組みを設けて子どもを理解しようとしているのか、あるいは理解する傾向にあるのかということについて、具体的な子どもの行動に即して考えていきたいと思う。
‘かんしゃく’という情緒的反応は、年少の子どもによくみられる行動である。子どものこのような行動をまのあたりにしたとき、私たちはどのような枠組みを用意し、理解しようとするだろうか。図1-1を参照されたい。
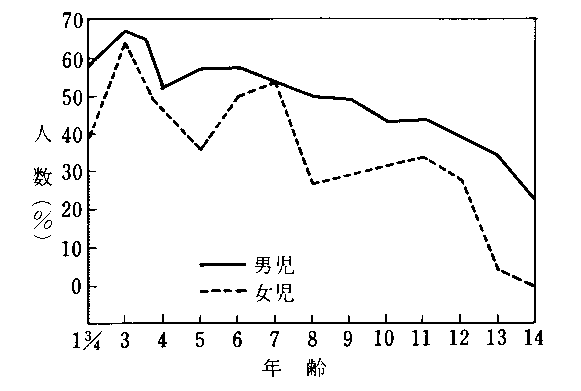
図1-1 かんしゃくの年齢的変化(マクファーレン、1954)
これは、‘かんしゃく’など、ある単独の行動にっいて、その起こり方が年齢と深い関係にあることを示唆するときによく用いられるもので、行動などの変化を量的に計測し、その値を縦軸に、年齢を横軸にとって構成し、発達曲線と呼ばれているもののひとつである。身体的成長、組織や器官の量の増大などは、ひとつの尺度による絶対量の変化で容易に示すことが可能なので、このような発達曲線は、各年齢の発達的特徴や発達過程を把握するのに都合のいいものとして考えられてきた。精神的機能の変化は、これらに比して、量的な変化としてとらえることが困難で、質的な変化としてしか把握されないものもあるのだが、検査や計測の操作の工夫により、量的記述が可能になるものもあり、さまざまな精神機能の発達曲線が描かれてきた。
私たちは、臨床の場において、検査などの道具を使用するしないにかかわらず、無意識にでも、発達曲線のような年齢など時間軸に対応する発達の一般的変化を思い描き、子どもの行動を発達の一般共通性において把握しようとする理解の仕方をよくしてきた。‘かんしゃく’の例に戻って考えてみよう。かんしゃくという情緒的反応がそれだけで臨床的間題となる場合は少ないが、表面的にはそのような形となってまずあらわれることもなくはない。そのような場合、その子どもがかんしゃくをよく起こすのは、まだかんしゃくのピークにある3歳だからそのうち治まるだろうとか、もう10歳なのにまるで幼児期のようなかんしゃくの起こり方が続いているなど、「かんしゃくの起こり方の強さ」や「持続期間の変化」、そして、それが日常の社会的生活にどのような影響を引き起こしているのかなどの「社会性」にも着目して、それが臨床的な問題であるか否かの判断の基準のひとつにしようとする。
一般化された基準枠のみが、「正常」か「異常」かという「区分」の基準になるのかといえば、それはほとんど否定されなければならない。児童期の精神医学的な対象とされる問題について疫学的研究を行った結果からも次のような主旨の報告が紹介されている(コックスCox,A.1982)。すなわち、「正常」といわれている子どもたちのかなりが、臨床的に「病的」と判断されてもよいようなタイプの、彼らの日常生活に支障を来すほどの情緒的、あるいは行動上の問題に悩んでいる。ふつうは正常と精神障害とのあいだに明確な一線をひくことは困難であり、精神医学的な「問題」とされる状態は、その重篤さと持続期間と社会性における障害という点で量的に「正常」から区別されているのであり、同じ行動の軽度なものの多くは正常な子どもたちにも見られるのである。
臨床的に「問題」とされる場合には、かんしゃくの例においてもあげたような発達の一般共通性の把握に照らし合わせて、そして、その行動の「起こり方の強さあるいは重篤さ」や「持続期間の変化」や「社会的な影響」といったような量的に特徴づけられるような発達の典型類似性の把握を同時に成立させているのである。さらに、その子どもが、なぜ、別のときにではなく、今、そのように行動するのかというその子どもに固有の発達の個別差異性の把握もそこに働かせているかもしれない。
発達という概念が臨床に導入されると、発達という変化のもつ方向性や順序性という性質にとらわれて、臨床における子どもの理解がとかく量的基準に基づいた評価へと向かいがちになるが、それはあくまでも量的考察であり、次にその行動の意味や機能を理解しようという質的考察へと向かわなければならない。
(2)質的考察-理解の定式化
私は、臨床において、子どもたちといるうえで、「病気」や「障害」への診断的定式化をそれほど必要としないとする立場であるが、次のような考え方も-主に最後の部分の理由で-無視しないですすめてきた。
“診断は障害の鍵となる特徴を取り出すことをふくんでおり、分類はある障害が他の同じような状態と共通してもっている分母に従って障害をグループわけし、記号をつけることを意味する。それは、原因、治療、予後に関係する領域を限定し、他の専門家とのコミュニケーションのための簡潔な用語を用意するというふたつの理由で有益なことである”(コックス、1982)
量的な評価とか診断的定義による安易な類型化や価値判断は、子どもたちのありのままの姿を無視してしまうような粗雑なグループ分けへと導くだけで、つつしまなければならないのは当然である。しかし、子どもの発達過程の理解は、時間をかけて行動を共にし、たとえ行動観察の方法を厳密にして単に事実を集積したからといってそこに何らかの意味が生じるとはかぎらない。
行動の出現の可能性を高めたり低めたりする子どもの側、環境の側の要因はさまざまであり、しかも、同じ行動は全く違った意味をもち、違った機能を果たすこともよくある。子どもの行動の意味や機能を質的に理解しようとする場合には、そこに、診断的定式化とは異なる、また量的評価では測れない、子どもの発達の過程に関する理解の何らかの定式化-枠組みと言った方が適切かもしれない-を進める必要がある。それはどのようなものか、ひきつづき‘かんしゃく’という行動を例にあげ、ある子どもの事例に即して考えていきたい。
1)時系の変化において
A子は4月から保育園に通いだした5歳の女児であるが、母親は、それ以前から、この子どもがほんのわずかのことに突然かんしゃくを起こし、ある場合には、よくいうところのパニック様にまで達する極度の不安状態を示すことがあることを非常に気にしていて、その適応を案じていた。母親の予感は的中し、入園当初から、A子は大声をあげて座り込んだり、他児を突然のように突きとばす、窓から遊具を投げ捨てるなどの行動のほかに、特に象徴的に思えるのは、自分が身につけている衣服をすばやく脱いで放り出すなど、新しい生活の始まりを大きな動揺とともに歩み出している様子を示す出来事が次々と母親から告げられた。
母親とよく話し合ってみると、彼女とごく幼い頃より付き合っている私たちの目には、各々の出来事において出現するかんしゃくは、その度合いや表現の仕方はさまざまであるが、彼女にとって次のような意味や機能の現れであることをうかがい知ることができた。
まず第一に、どの子どももこの年齢では、同様の力不足が多かれ少なかれ見られるものであるが、彼女の場合は、自分が感じたり思っていることを確かな言葉や行動で人に伝達したり、あるいは人から言葉や行動で示される内容を適切にくみ取るほどには、コミュニケーションの力がまだ十分に育っていない状態にあるということである。しかし、彼女のかんしゃくを、「言葉の遅れ」のある子どもによくみられる現象であるといって片付けるだけでは不十分である。彼女には、これまでの生活の中で、自分の言い方で気持ちがわかってもらえたという確信がもてたり、人がなぜそのように言ったり行動したりするのかよくわかって、安心して人と一緒に過ごすことができることが少ないという過去の経験の積み重ねがあった。このことは、彼女のかんしゃくという行動に先行する、長期間持続した状態、つまり、過去的条件がいま顕在化しているということを意味しているのではないか。
第二に、何が直接的に、そのかんしゃくの発現を誘発するかという現在的条件にも着目する必要がある。彼女は、母親以外の人に、とりわけ同年齢の子ども達に対し、視られたり、話しかけられたり、触れられたりのような心理的、物理的距離の近接さを感じるとき、著しく緊張が高まる傾向があった。保育園のような子ども集団では、突然、他の子どもから働きかけられたり、まだ親しくない子どもと手をつないで散歩に出かけることを促されたりなど、予測し得ない事態が次々に起こり、彼女にとっては息の詰まるような狭い空間で、子どもたちの視線が交錯するなかにいるということだけでも極度の緊張を強いられ、それは十分にかんしゃくが引き起こされる条件となっていた。
第三には、その行動に引き続くものという意味での未来的条件にも着目しなければならない。っまり、彼女のかんしゃくがどのような反応をもたらすかということが十分に予測されている状況において、引き起こされるまわりの反応である。彼女の母親は、かんしゃくが引き起こされないためにも、また、より激しく、より持続しないためにも、すばやく菓子をほおばらせたり、おぶったりして彼女の気持ちを安らげてきたため、かんしゃくは、大人への積極的な注意をひく有効な手段ともなっていた。
A子の事例をもとに示してきた行動の理解の枠組みは次のように整理することができる。
いま・ここに、過去を位置づけてとらえる過去的(歴史的)把握
いま・ここに、現在を位置づけてとらえる現在的(体系的)把握
いま・ここに、未来を位置づけてとらえる未来的(目的的)把握
これは、時系的な枠組みにおける行動の定式化である。私たちは、子どもの生育経過を重視して細かな情報を親たちから得ようとするが、それは上に述べたような、いま・ここに・ともにいる時間における理解を深めるために必要とされるのであって、診断的な目的が優先されるのではない。
2)状況の変化において
A子の事例から、さらに考察をすすめる。彼女のかんしゃくなど突出した個々の行動を理解の手がかりにしようとするとき、彼女がおかれている状況との関係において発達特性が顕在化するという観点は重要な意味をもっている。なぜなら、発達の本質からいっても、子どもは状況とのかかわりにおいて生きる関係的存在であるからであり、問題とされている行動も、子ども自身の内部にだけその原因を求めることはできない。
状況との関係からどのような枠組みをもちながらA子の発達の特性をとらえることができるだろうか。
第一には、どの状況においても、彼女においてどのような同一性が保たれながら成長しているかという、かけがえのないその子どもにおける存在の仕方を支えているような基盤的特性をとらえることである。A子の基盤的特性は、自らまとっている衣服でさえも‘外の世界’に位置づけて脱ぎ捨てたくなるような、自他の世界の境界に対する、あいまいにすることを許さない過敏なまでの自己主張である。このことから、彼女の行動を、感覚的な過敏性という彼女自身の内的、生理的特性に起因するとしてのみ考えることはあたらない。関係的存在である子どもの発達であるがゆえに、外界とのかかわり方にこだわりをみせるのである。A子の場合、この特性は、乳児期に、母親には抱かれたがるのだがモゾモゾして抱きにくい感じであったとか、父親にさえ‘人見知り’が激しく触られたがらなかったとか、あるいは、衣服、食物、トイレなどの自己の身体心理的に身近な生活活動ほど自らの選択の幅を狭めて妥協を許さなかったなど、彼女をとりまく人、物などの社会的関係の脈絡においてとりわけ発揮されるがゆえに、大多数の子どもの発達過程を「普通」として生活の基準にしている社会にあっては「問題行動」として著しく目立つところとなっていた。
第二には、状況の変化により、表出の仕方は異なっても、ある場合には正反対に見えても、持続的に見えかくれしながら顕在的にとらえることのできる典型的特性は何かということである。A子は、一見、人の接近を嫌い、それを回避することに終始しているように見えても、引きこもっている傾向はない。それどころか、人に向かう強烈な自己主張は、結果的にたえず人の関心を自分の側に引きつけておくこととなり、緊張に満ちたゾーンのみを手がかかりにしながら自分とまわりとの関係の調節をはからなければならなくなっていたが、結局は人に-この時期には、多くは母親にだったが-やすらぎを求めた。それは、ちょうど、見つかることを期待しながら必死に隠れている‘かくれんぼ’の緊張感を思い起こさせた。A子の対人指向性は、彼女が人に後ろで見ていてもらいながら好んでする人形遊びによく表れていて、「~ちゃんが~したからわたし泣いちゃったの。~ちゃんはいっちゃった」というように話しながら、日常の出来事や自分の経験をくりかえし人形に演じさせて飽きなかった。
第三は、状況の変化に応じて発揮されやすい個別的特性をとらえることである。A子は言葉を理解したり、話したりのいわゆる聴知覚系の学習は彼女なりに順調であったが、積み木で何かを構成したり、何かを描いたりというような視知覚系の学習はきわめて苦手な状態で成長していた。‘ひらひらのスカートをはいている女の子’を描くつもりでクレヨンを握っても、紙の上にはか細い糸屑のようなかたまりが描かれているだけであり、彼女は自分の行為の結果が、イメージしていることとかけ離れていることで自信を失い、母親に「やってちょうだい」と全面的に依存するか、言葉と人形の世界で自分のイメージを存分に実現させる傾向が次第に強くなっていた。その発達的なアンバランスが、状況の違いによって、人の彼女に対する印象を混乱させていた。たとえば、人から「こんなによくお話しができるのに、どうしてこの位の身の回りのことができないの」と強要されることが多く、それがかんしゃくを起こすひきがねともなっていた。彼女自身、自分に自信のあること、興味のもてること、対処できそうなことを選択して状況にかかわるようにもなってきていた。
以上述べたようなA子の状況における発達特性は次のような枠組みにおいて理解の定式化をすすめることが可能である。
状況の変化に共通して発揮される自己の基盤的特性
状況の変化に持続して発揮される自己の典型的特性
状況の変化に応じて発揮される自己の個別的特性
子どもと状況を共有し、その一端を担うことで状況の変化をともにつくりだしながら生かされてくる理解の定式化である。「障害」や「学習困難」を伴うといわれている子どもたちのなかには、A子のように、単に個性と片付けてしまうことのできない、発達の諸機能にアンバランスの様相をみせて育つ子どもは非常に多い。ひとりの子どものなかの、速度や過程を異にする諸機能の発達的変化を、たとえば言語機能、認知機能と分けていくら評価を精密にして付け合わせても、子どもの全体像を把握することはむずかしい。また、はじめから一定の評価の枠組みをもって臨んだり、あるいは対象として客観的視点を保とうとする姿勢の種類の行動観察からは、子どもの現実の姿はそう鮮明には浮かびあがってはこないと考える。
3.発達過程の評価
(1)臨床における発達評価の視点
前項で述べたような子どもの理解の基盤をまえつつ、次に臨床における発達の評価を行う場合の視点として何が必要かということについて、一般的にはどのように述べられているかを教科書的に引用したい(コックスほか、1982)。ここでは、これまでの精神医学や臨床心理学の分野において、発達的アプローチの必要性が表面的にしか理解されていないのではないかとの疑念のもとに念押しがされている。なお、文中の引用文献は省略した。
“子どもは発達しつつある生体であり、いかなる診断的評価も発達的評価の枠組みの中で行われる必要がある。発達的アプローチはいくつかの違った理由のために必要である。
第一に、子どもたちは年齢が違えば違った行動を示すし、もし臨床家が何が正常であり何が異常かという判定をするならば、かれはそれぞれの年齢で予想される行動の範囲を知っておく必要がある。
第二に、精神障害の程度を評価するためには、正常な心理学的発達がこれまでどの程度さまたげられてきたのかを考察することが有用である。座ること、立つこと、歩くことなどの発達上の道標が運動機能の発達の指標になるのと同様に、社会的および心理的な発達の比較可能な指標も存在する。つまり、子どもたちは、社会化の過程を促進する情緒結合や愛着を発達させる。ひとり遊びから平行遊びへ、さらに協同遊びへと移行し、成熟とともに深化に拡大しつつ存続する友情を発達させる。性的心理の発達も同様に前駆的段階を通して行われる。
第三に、異なった発達段階は異なったストレスや感受陸と関連しており、これらのことが考慮されなければいけない。たとえば、よちよち歩きの時期は、子どもたちが入院や分離体験によってもっとも悪い影響を受けやすいときである。そして青年期は抑うつ的気分の動揺が最もふつうに見られるときである。
第四に、もし臨床家が問題がどのように生じたかを理解しようとするならば、かれは正常および異常な発達の根底にある過程を理解しなければならない。したがって、診断的評価は現在の状況や現在の問題と同様に、子どもの発達過程の評価を含まねばならない”
次のいくつかの点について私自身の考えを強調しておきたい。まず、「正常」と「異常」の判定に関しては次章においてふれるので参照してほしい。次に、子どもが当該する年齢の正常発達の段階のみを基準にして考えているだけでは子どもの理解は深まらないし、適切な方法の適用を妨げることもあるということを言いたい。他の子どもたちの何倍もの年月を費やしはしても着実に発達上の道標を刻みながら成長している子どもたちについては、場合によっては、当該する生活年齢を無視して現在の発達段階における配慮を優先的に考慮しなければならないことも少なくない。たとえば、遅れて芽生えた人への愛着的行動は、とかく「依存」とみなされ、無視されて、当該の年齢の子どもたちに要求される「自立」を急がされることになる場合も多々あるが、それが3歳であっても4歳であっても、母親へのしきりのオンブは、人間関係の礎が形成される重要な行動だと判断されれば、むしろ勧められるということもあるのである。
その次に、子どもの発達途上において子ども自身にふりかかったいかなる緊急な事態にあっても、その発達段階における発達課題を著しく侵害するおそれのあるような場合には、そのことについて最大限の配慮がなされる必要があるということを強調したい。たとえば、乳幼児期の早期に、医療的なケアーを優先させて、長期に、あるいは断続的な入院をくりかえすことにより、情緒的な発達のみならず、食事や排泄などの社会行動の発達に著しい影響を受けて育つケースもあるのである。従来は、より発達の早期であったり、「病気」や「障害」が重度であったりして身体的ケアーの依存度が高いほど、精神的、社会的発達に対する配慮が希薄であるのは当然のように考えられていたが、現在では、人間の発達の全体性に目が向けられるようになり改善がなされつつある。
(2)発達過程の力動的把握
発達臨床において子どもの問題が呈示され、その解決の方向がめざされる臨床的変化は連続的なひとつの過程であり、それは心理療法の臨床過程とも対応するものであるが、同時に発達的変化を示す発達過程と対応した統合的な過程として把握されることが求められる。それだけではない。その子どもの発達環境としての生活場面においては、他の子どもたちの発達過程と交差しながら相互にかかわりあって成長しているわけで、目の前の子どもの変容だけを単眼的、個別的な軸のみを形づくりながら見ていくことなく、複眼的、力動的な把握をしながら子どもの発達過程の全体評価をしていくことも必要である。
ここに、小学校2年生の女児B子の母親からの手紙がある。
B子は幼児期より、両親が言葉の遅れを伴う対人行動の発達の遅れを心配して相談治療を継続していた。5歳で幼稚園に通いだした頃より変化がみられ、特に母親との情緒的関係も確かなものとなり、困ったとき助けにを求めたり、人の気持ちを察したりする場面も多くなり、それは両親にとって‘育てがいのある’うれしい発達の経過であった。小学校に入学し、1年生の間に同年齢の友達と一緒に過ごすことが楽しくてたまらなくなり、言葉を含めて情緒的にも人と交流する経験を飛躍的に増大させていった。学校外でも、クラスメートを見つけると名前を大声で呼びかけたり、彼らも呼び返したりしてそれに応えたりしている場面に母親も出会うことがしばしばあり、順調な発達を喜び合った。2年生に入って、クラスメートとの交流の様子が微妙に変化していることに母親は気づき始めた。手紙には次のように書かれてあった。
“娘が成長してくれて、心と身体が変化して今までとちがってきているのに、親は今までの娘と同じように扱ってしまい、娘から、予想していなかった反応が返ってきておどろいています。……最近、母親と一緒に家の近くを歩いていて、クラスの友達を見つけてその男の子の名前を呼んでも知らん顔され、後ろから歩いてきた他の男の子たちに振り向きざまに「ウルサーイ!」と大声で言われたりします。……そのためか外へ出たがらなくなり、仲のよい女の子が家の近くで遊んでいてもその子たちに「見つかるといやだから」と言って帰ってきてしまいます。……母親が様子を見に行くと「見に来ないで!」と大人の手助けを表だって借りたくない気持ちがあるようで。……娘の心がキズついたようすをなるべく明るく忘れるようにと気をつけていますが。……からかわれたり、いじめられたりしないために、たとえばいつも母親が横にいれぱ防げるかもしれません。でも、それは自立していくじゃまになりますか? 心がきずつかないようにすることとどちらを選んだらいいでしょうね。……学級担任の先生にご相談したところ、そういう(いじめの)場面には心当たりはないようです”
2年生の子どもたちの行動の規範が、これまでの親や先生との関係を重要なモーメントにしていた時期から、そろそろ仲間への適合が強くはたらく発達の段階にさしかかっている。同類をことさら強調し、そこからはずれることにもまた敏感にもなる。B子はB子ひとりの発達過程を歩んでいるわけではない。また、B子以外の他の子どもたちのそれのみが「正常」であるわけはない。B子とのかかわりにおいて顕在化されてくるクラスメートの発達的変化であり、そのクラスメートとのかかわりにおいて促されるA子の発達的変化でもある。またそのことにより新たに成立する母子関係の課題も見える。
発達臨床においては、個の発達過程、治療的プレイルーム内、母-子関係のような、時間的・空間的・関係的に狭い枠組みにおいてのみ頼ろうとする臨床的視点には限界があり、子どもをとりまく諸条件、諸関係における力動的変化過程に対応し得る理論と実践の方法が求められているのである。
(3)発達の代替過程
発達臨床において、きわめて重要であり、かっ興味深いことは、ウォルフ(wollf.P.H、1979)の次のような問題提起である。
“自然的だとか、あるいは「最適」だとかいわれてきた発達の順序は、一連の順序のうちのほんのひとつにすぎないこと、そして、ひどくゆがめられた(病的、社会的に)環境の諸状況のもとでは、同一の目標地点(発達の主な諸段階)に到達するための代替通路が前面に出てくることがあるのではないか”
まわりの事物を、自己の身体で感覚運動的に取り扱うことのほとんど不可能な重い脳性マヒをもって生まれた子どもが、認知機能の発達において操作的水準にまで到達する道筋は、ピアジェの発達論からはどのような説明を加えるべきか。また、スピッツは、感情の発達において、母親をひとつのまとまりをもった対象表象として成立させるのに必要な条件として、他の感覚様式から区別する視覚のもつ統合機能を強調しているが、目の不自由な子どもの母親への愛着的行動の育ちをどのように描写したらよいのか。これらの事例は、無人称の無選択に集められた一般普遍性の本質の中に埋没してしまうのか、あるいは特殊な状況におかれた例外として無視されるのか。
ウォルフの「代替通路」の仮説はこれにひとつの説明を与えてくれる。彼は、認知の発達にふれながら次のように述べている。
“最も規範的なものとされる発達は、自然的な状況(知性と物的な世界との間にあるほとんど全く安定した適応的関係)のもとで、最も一般的に観察されるものであるのに対して、代替的な過程は、環境がそのような通路をふさぎ(環境の剥奪、気質的な病気など)、そのため、子どもが常道をはなれた方向だと思われるような道を工夫せざるを得なくなったときのみ活発に活動するようになるのである”
さらにウォルフは続けて、発達研究の、臨床における実際的適用に関して果たすべき課題として、現在の治療機関や教育施設においても時に見られるようなとしながら、“あの同一の「規範的な」道筋にすべての子どもたちを矯正的にはめこもうとするのではなくて、むしろ、同一のゴールに到達する代替手段の範囲を決定するような方略を考慮しなければならない”と述べ、ある共通のゴール(発達的指標という意味において)に到達するのに幾通りもの手段があることを立証し、「代替通路」の中で、どれがその子どもに「最も自然」であるのか、その通路が一人ひとりの子どもたちの育ちを保障する環境と最も一致しているのかを発見することが、発達的アプローチの不可欠な側面であり、また、臨床的発達研究のもつべき意義であることを示唆している。
「代替通路」という呼び方のなかに、さまざまな臨床経験における具体的事実が思い起こされる。聴覚や視覚に障害をもって育つ子どもにその感覚経路とは異なる経路の機能を代替として用意するという意味では事例をあげると枚挙にいとまはないが、この場合の「代替通路」とは、もっと内部的な、子どもの存在の仕方、外界へのかかわり方に通ずるもののように受け取った方が適切だろう。
ある男児C夫は、2歳時からことばなど発達の遅れがみられ、言語および心理指導を継続していた。就学時においても、言語理解はかなり良好であったが、表出面においては簡単なジェスチャーも指差しすらおぼつかない状態であった。対人的に回避する傾向もあって、対面してカードなどを媒介にコミュニケーションを図ることも難しく、彼の言語指導は具体的思考つまり身体運動を介した遊びの段階をいったりきたりしていた。ところがまもなく時代が幸いして、言語治療士がワープロを試みさせてみたところ、すぐに単語と、まもなく簡単な文章を打つことができるようになった。このような状態になってみると、神経生理学的な観点も加えながら、彼の発達過程についてさまざまな仮説的解釈も可能であろう。何が「代替通路」かを見っけること自体そう容易なことではないが、いつかは子ども自身が示す標示案内を見過ごさないような心構えだけは常にしておかなくてはならない。
主題(副題):発達臨床-人間関係の領野から-
第1部 第1章 1頁~18頁
