発達臨床-人間関係の領野から-
NO.3
第2章 「発達障害」の臨床
1.「障害」をもつ子どもとの臨床活動
(1)基本的意識の変化
近年、発達臨床の一分野として、心身の発達に障害をもつ子どもとの臨床活動の実践が飛躍的に増大し、「障害」のとらえ方、障害をもつ子どもの発達への関心、その発達援助の方法などにおける基本的意識が大きく変わりつつある。そこで、本章では、この分野を「発達障害」の臨床と呼ぶことにして、そこでは何が強調されてきているのか、どのような内容が展開されてきたかに焦点をあてて述べていきたい。
なお、「障害」および「発達障害」などの用語については、のちに述べるように、1 その語義については多軸的であり、あいまいさが多いこと、2 その慣用化が差別的ニュアンスを伴うこと、3 筆者の立場が、まず個における性質からアプローチするものではないこと、などからすべてカッコつきで用いたいところであるが、以下それを省略する。
基本的意識の変化は、臨床心理学全般の歴史的動向とも関連しているので、まずその点について概観する。
臨床心理学においては、その課題が、科学性・客観性を求めて心理学的検査に重点がおかれていた段階を経て、およそ1960年代を過渡期としながら、次第に対象となる人間の全体性、力動性をとらえ、その望ましい方向への変容をめざす治療的接近へと変化してきた流れがある。障害をもつ子どもとの臨床活動の課題もその流れに対応して変化してきた。
まず、臨床活動の課題が心理検査による診断、判別の技術面からの要請に影響されていた段階では、子どもの有する障害の固定的、絶対的側面が着目され、正常といわれる発達過程から、どのようにそれが特異であるかを類別する診断的側面が強調されてきた。障害をもつ子どもは「特殊」児童、あるいは「欠陥」児童などと呼ばれて、障害の治療や克服のための努力が第一義的なものとされていた時代である。
そののち、多くの先駆的臨床者が、障害をもつ子どもの成長過程により深くかかわる機会をもつにつれて、その過程は、人間としてより望ましい方向への変容を志向することにおいては正常の発達のみちすじと共通であり、その発達をどのように援助するかという発達の治療的援助の側面が重要視されてきたのである。
さらに、近年では、発達の早期(胎児期、乳児期)への関心が高まり、障害の早期発見、早期療育のみならず、すべての子どもの健康な生活の実現を問題にし、それらを促す条件、阻む条件を明らかにしていく過程に、障害をもつ子どもの臨床を位置づけていこうという、いわば予防的側面にも関心が集まってきている。
(2)「正常」と「異常」
園原太郎らは、次のような理由により、障害を、障害者固有の固定的、絶対的なものとし、障害の概念を普遍的なものとして受けとることへの問題を提起している(園原太郎、1975)。すなわち、障害は、確かに客観的に個体がもっている条件としての側面があるが、第一に、われわれが障害と考えていることはきわめて相対的であり、認識者の側の問題でもあることを認識すべきであること。第二に、時代によって、また生活していく社会における社会的条件、社会的配慮により障害の内容と処遇は異なること。第三に、障害に対する治療教育的条件により障害が変化する可能性が明らかにされていること。
ここで、「障害」とは、一般にどのような概念をさしているのか、どのような基準によって「正常」と「異常」の区分をして「障害」を判定し、診断をしているのかを明確にしておく必要がある。
1)統計的基準
統計的に多数の者が示す平均的な行動や状態を「正常」とし、そこからどの程度逸脱しているかによって「異常」性を判別する考え方である。たとえば、「知的発達」の段階を、知能テストなどによる知能指数(IQ)の数値を基にして人為的に区切り、「正常」と「異常」の境界を機械的に設け、「知的発達の遅れ」を判定するやり方などにみられる基準である。この基準が用いられることに関しては、人間の個性的な活動も量的な程度の差に還元して、人為的に設ける段階づけであること、あるひとつの基準を用いて人間全体の価値をはかる物差しととられる危険性をもつことなどにより、きわめて多くの問題をはらむ考え方といえよう。
2)理想的・価値的基準
歴史的・社会的・文化的相違により、あるいは所属する集団の性質や目的により価値基準が異なり、個人の行動の意味内容が相対的に規定され、判断される場合である。ある社会文化圏においては「正常」な生活行動も、他では「異常」とされ得るということは容易に想像されるし、また特定の集団では、他よりもきわめて狭い価値基準がはたらくために、相対的に「問題」視される活動が増大するという場合もよく経験されることである。
3)病理的基準
心身の機能および構造に明らかに正常とは異なる病理的異変が認められ、それを基準に考える場合である。これはいかにも科学的、客観的な基準であるかのようにみえるが、現実には、人間の行動に関する病理的な解明にはまだ多くの課題があると考えられること、また、たとえば視力を眼鏡により矯正するなど、機能の改善や矯正により現在の環境に支障なく生活し得る状態を「異常」とする意味はどこにあるのかなど、問題も多い。
4)行政的基準
現在、わが国において施行されている行政的措置の拠りどころである、法的な判別基準である。今ある治療あるいは治療教育施設を前提とし、それらの種別に分類、ふりわけの基準としての役割にとどまっているのが現実である。
以上述べてきたように、どのように「正常」と「異常」を区別し、「障害」とみなしているかについては、問題の多いさまざまな基準が、その時に応じて使い分けられているにすぎないというのが現状であるということを認識しておかなければならない。
(3)「障害」のとらえ方
一般に、「障害」とは、“様々な原因によって、思考、言語、情緒などの精神作用の面で、あるいは手や足、目や耳などの身体面で、あるいはそれらが重複した形でなんらかのハンディキャップを負っている状態”と定義されている(文部省『心身障害児の理解のために』1981)。
一方、1981年、国際障害者年の10年間のスタート年の行動計画に、次のような障害の三つの異なったレベル(階層構造)が指摘され、この概念は、いまや国際的に定着しつつある。“個人に具わる損傷としての障害(impairment)と、それによって引き起こされる機能的制限としての障害(disability)と、それらの社会的結果である社会的不利(handicap)との間には区別があるという事実の確認を国際年は促進すべきである”
この定義をみると、英語においては多彩な意味あいをもっ同義語、同類語が、日本では、「障害」という単一概念の中にきわめてあいまいに使用されてきたことがわかる。具体的にどのような状況において使い分けがなされるのか、例をあげて考えよう。ピアニストが指に「損傷」を負ったとする。一般の人にとってはそれが実生活にさして影響を与える程度でなくも、ピアニストは演奏する能力に「機能的制限」を受け、そのことにより社会的活動に「不利」な事態も起こり得る。逆の例をあげれば、サリドマイドなどの原因により両上肢に損傷を受けた人が、その機能的制限をはねのけ、足を使って食事、書字なと生活上の諸能力を獲得し、社会の一員としての活動を日常的に行うことも可能なのである。
障害の三つのレベルのうち、第一の「損傷としての障害」は、生物学的レベルでとらえた障害の概念をあらわし、第二の「機能制限としての障害」は個人のレベルでとらえた概念、そして第三の「社会的不利」は社会的レベルでとらえた障害の概念をあらわしている。これら三つのレベルは別々のものではなく、相互関連的に規定しあいながら階層をなし、そしてひとつの「障害像」なる実態を形成しているのだという指摘は、障害および障害をもった人への一面的、固定的偏見を打破し、リハビリテーションの概念を広げることをも目的としていた。行動計画によれば、障害は、ある個人とその環境との関係において生ずるものであるとの考え方はようやく広まりつつあるので、これからは、「損傷」や「機能的制限」を「不利」ならしめている社会的条件をみつめなければならないことを強調している。
語源をたどると、あいまいになっていた事柄の意味や本質がみえてくるということがよくある。handicapという語の語源は‘hand-in-cap’で、昔、くじ引き遊びで勝った者が帽子の中に罰金を入れるということから派生して、いろいろな競技で力量的な優劣を平等にして、誰でもが参加し得るように配慮したことから用いられるようになったと言われている(宮本茂雄、1983)。強い者には不利な条件を、弱い者には有利な条件をつけて均衡をはかるルールは、ゴルフや囲碁にもみられることである。したがって、handicapをつけられた人という語源からの解釈から、handicappedを「障害者」と訳すようになったと考えられるが、handicapをつけるということは、そもそも、皆が平等に生活していくための条件や特別な配慮を指すと解釈すべきであり、handicapをつけられなければならないのは、すべての人が生活している社会それ自体であることが認識されなければならない。
2.発達援助を支える概念
(1)「療育」の理念-わが国において-
「療育」という用語は、現在、わが国においては日常的に用いられているといってもよいと思うが、その定義と内容は、よく知られているとおり、運動機能などの障害に対してそれまでの蔑視的呼称を排し、「肢体不自由」という語をはじめて主唱し、「肢体不自由児の父」と呼ばれている高木憲次によって提唱された。
高木自身によってなされた療育の定義は次のようである(以下、高木の引用は高木憲次、1967、による)。
“療育とは時代の科学を総動員して肢体の不自由を出来る丈克服し、それによって幸いにも快復したる快復能力と残存せる能力と代償能力の三者の総和(これを復活能力と呼称したい)であるところの復活能力を出来る丈有効に活用させ、以て自活の途の立つように育成することである”
現在では、療育という概念は、狭義には「肢体不自由」児・者のみならず、心身の発達に障害をもつ児・者への治療・教育・社会的援助を目的とする専門スタッフによる総合的アプローチを指すが、広義には、「リハビリテーション」の概念の発展と軌を一にし、保護対象者としてではなく、身体・精神・社会的に著しく不利な状況における生活主体者としての人間性の回復あるいは獲得の理念をも意味している。
高木が提唱した療育の理念および療育の体系には、今日、わが国で広く一般化されている治療教育、発達(障害児)臨床および児童福祉の分野における多くの理論と実践の源流を見出すことができる。そこで、ここでは、高木の療育理念の内容について、2つの側面においてその現代的意義を検討してみたい。
1)「肢体不自由」の呼称と「障害」の相対性(主観性と客観性の接点)
「肢体不自由」という用語は、昭和4(1929)年前後に高木によって案出され、後には学的にも法的にも正式に採択され、一般に漸次普及していったという経緯がある。
用語は、慣用化されていくうちに次第に人間価値的なニュアンスが付加されていく。その使用に関してはそのことが十分認識されなければならないので、現在この用語が使用されるのに最も適切という意味ではないが、用語案出の背景には、人々の意識のうえでも、社会的対応という面においても、何が問題とされてきてきたかを知るうえで興味深い点が多い。
高木は「本名称を提唱せる所以」として暫定的にとの余白を残しながら、次のように当時の事情を記している。
“決して単に、世に不具、片輪などの語を余りにも蔑視的なりと嘆くものある故、これにこたへ、これに代わるべき用語として提案せるものではなく、「肢体不自由」なる述語によって、所与の定義、意義、範囲を劃するところの一新構想を表現する為に、かかる一新用語を提唱せるものである”
「一新構想」は後の「療育」構想へと発展するわけであるが、「肢体不自由」の用語の案出の過程においてすでに流れの筋をあきらかにしはじめていたようだ。
高木は、名称命名の過程を詳細に述べた論文において、「肢体不自由なる名称の意義」として6項目をあげ、治療し育成する対象の名称であるために、形態の異常の表現ではなく機能障害を表現するものであること、その原因の所在箇所の表現ではなく結果として機能が侵犯されることを表現したいなどの項目と同列に「肢体不自由は主観的の問題である」の項目を挙げていることは、療育の源流におけるヒューマニスティックな視点として注目される。「障害」は、いつ、誰において、どのように確認されるものであるかという点に関しては、先の項で、人間発達の「正常」と「異常」の相対性、障害の成因論および治療論における主体と社会的・文化的生育環境との相互性の認識のもとに、そのあいまいさにふれてきたが、高木はそこに、「確認する者」と「される者」の関係の構図においてであるが、障害の確認の過程における科学的・客観的判断と体験的・主観的意識の共在を容認することにより障害者自身の主体性を強調した視点がうかがえる。
さらに高木は、6項目の最後に“以上で「肢体不自由」なる名称は、決して肢体疾患と同義の語でないことを容認しうるであろう”と結んでいる。つまり、障害名は即医学的診断名ではないとのニュアンスから、障害における病理的関心は内包しつつ、しかし障害を有する状態に関し、「医学モデル」を排し、いわゆる「生活モデル」への方向をめざす意図をそこから十分に読みとることができる。障害名は人が生きていく条件に関しての一種の類型に対しての命名であり、治療や教育に先立つ診断名と一致しないこと、障害者は「病者」の代名詞ではないことなど、半世紀以上たった今でもきわめて現代的な警告となりうる視点を提供しているものとして、意義深い。
2)体系的原理としての「発達段階」および「発達課題」
高木の療育論は、高木自身が大正13(1924)年にr教・療・職の三位一体の方策」と提唱して以来、慈恵的救貧の範囲を脱していなかった当時の肢体不自由者擁護のあり方に対して、治療のみならず教育および職業という生活全般にわたる総合的アプローチの体系の源流をなすものとしてその意義が評価されているものであるが、彼が提示した体系的原理は、それを横軸におきながら同時に縦軸としてきわめて現代的テーマである、人の長い生涯を見通しての「発達段階」と「発達課題」の概念を基軸にしているところも注目したい。
高木は、療育の支障となる「迷信・無智・誤診と無関心」を排し、「『隠匿するなかれ』運動の普及・徹底」をはかるため、療育施設の設置が最大の課題であったという時代であったので、療育施設内においてという限定はされていたのだが、「療育実施の五段階」を設定し、次のような概略とともに各段階についての解説を加えた。
“その第一段階は先ず医療から始めなければならないことは云う迄もないことだが、その他は必ずしも順位を踏むとは限らない。然し多くの場合、第二段階として学齢に近づくに従い躾と共に教育が主要となってくる。第三段階としては生活指導・更生指導、第四段階として職能指導、第五段階としては、大体15歳以上に始まるところの職業指導、社会生活への適応性を培養すること並びに憂世の荒波をのりきる気魄の涵養が必要になる”
療育段階説は昭和10(1935)年にはすでにその原型が現されており、その意図するところの斬新さと高さがうかがえる。
障害を有する発達の過程は、生物的成熟、病態の変化、治療的効果、社会的経験などが複合して、一般の発達的変化に比してはるかに複雑な様相を呈しながら進んでいくので、安易に人生のある期間を時問系列的によってのみ区切り、発達段階の概念の適用を試みることによってだけでは解決し得ない多くの課題を有する。しかし、現在では、生涯発達の観点から、重度障害をもつ人々の自立の問題を含めて、たとえば運動的側面・知的側面など能力のある側面のみに焦点をあてて社会における生活を限定してしまうのではなく、どの人にとっても人生のある段階には独特の経験があり、どのようにこれまでの経験が組み込まれてそれを導くのか、さらに、その段階での経験がその後の発達にどのように貢献するのかなど、人が生きていく方向性に対しての積極的な対応の視点を提供することにおいて、発達段階とそこにおける発達課題の概念が重視されるようになってきた。高木の療育論には、「発達」などという文字は一字も見あたらないが、高木の考えていた療育は、現在はその対象年齢においても、乳児から高齢者までと上下の段階へと大幅に拡大され、また運動の障害のみならずより複雑な心身の発達過程を巻き込むこととなったが、生涯療育論の展開の必要性を示唆していることにおいてきわめて現代的な課題をも提供していると考えることができる。
高木は療育構想を自身で図示(図2-1)している。これは療育施設内構想としてあらわされているものだが、システムにおける分化と統合という視点に移し変えてあらためてながめてみると、現在でも通用する地域システム構想の原型としてみることもできる。
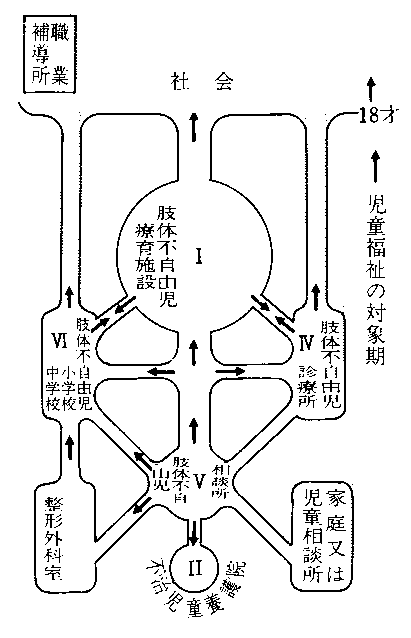
図2-1 療育の構造
高木の療育構想は、単なるその道の先駆者の事業という意味ではなく、その概念が、日本の土壌において育まれ、現在の発達臨床の基礎をなしているという点で意義深いと考えたので、その源流をやや詳しくたどってみた。
(2)「発達障害」の概念-アメリカから-
発達期に起こる心身の障害に対して「発達障害」という用語が用いられるようになったのは最近(1980年代)のことである。「障害」や「問題」を発達的に見ようという視点が社会的に了解されてきている流れの中で登場してきた言葉ではあるが、その定義や概念規定にはあいまいさを多く残しているというのが大方の考えである。しかし、新しく用いられるようになってきた用語の背景には、人々の意識や社会のありようの変動と、既成の内容が問われ直す過程が推測されることがある。そこで、本項では、障害をもつ子どもとの臨床-発達援助活動を支える概念としての発達障害についてふれておきたい。
発達障害という語が公式に登場したのはアメリカの公法上であるという。
1970年に「発達障害法」(Developmental disabilities Act of 1970)においてはじめて定義付けられ、1975年の改変を経て、1978年に下記のように再改変されるに至ったという(山下巧、1985)。
“発達障害(developmental disability)という用語は、次のような重度・慢性の障害を持った者を意味している。
(A)精神的障害(mental impairment)または身体的障害(Physical impairment)をもっている者、または精神的障害と身体的障害を合わせもっている者。
(B)22歳以前に障害が出現している者。
(C)将来とも障害が続くと思われる者。
(D)次のような主たる生活能力のうち、3つまたはそれ以上の項目で重大な機能上の制限がある者。
1 身辺の自立、2 受容言語と表出言語、3 学習能力、4 移動能力、5 自己統制、6 生活の自立、7 経済的自立
(E)特別な領域や2つ以上の頒域にわたる総合的な処置や療育や、個別に調査されたサービスを生涯にわたって、また継続期間を拡大して必要としている者”
発達障害という用語は、アメリカでは法律的にはこのように定義されているのであるが、その基本的特徴として、松野豊(1979)は次の二点をあげている。
“第1の特徴はそれが障害種別を示さない包括的用語であるという点である。ではなぜ包括的用語が用いられたのか。ひとつには、障害がきわめて多様であり、また同じ一人の人の中に同時に異なる種類の障害が発生する頻度が高いことによる。障害の種別でサービスをきめると、障害が多様なゆえに漏れてしまう者がでてくるし、また障害が重複しているときには、いずれのサービスも受けられないということがよく起こるのである。また、当人にとって実際に有効なサービスという点から見るとき、その人がどんな障害種別かを判定するより、むしろどんなサービスを必要とするかを判定する方が意味があることによる。
発達障害という用語のより基本的な第2の特徴は、単にその障害が発達期に生じたということを示すだけではなく、障害を発達においてみる、つまり障害はダイナミックに変化するものであるという観点をその用語が示していることである”
以上のことから、発達障害という概念は、常態化(normalization)あるいは主流化(main streaming)などと呼ばれる新しい社会福祉の理念に応えて、行政的、施策的に登場した実際的な背景をもつ用語であることがわかる。発達障害という用語を新しく用いることにより、これまで障害別に独立して機能していた機関をひとつに統合し、現実的な臨床的、福祉的援助を中心に据えた対策がとられるようになった点がより発展的と考えられている。
一方、わが国で用いられている発達障害という概念の周辺には、もうひとつの英語 developmental disorders からの訳の内容を含む場合が多い。
developmental disorders という用語の使用は、1980年に発表されたアメリカ精神医学会の「精神障害の診断と分類の手引き」(いわゆるDSM-3)に見られるものであり、従来からの「精神遅滞」「脳性まひ」「てんかん」のような診断名では分類しきれない、いわゆる自閉性障害、学習障害などさまざまな行動上、学習上の困難をみせる状態に対して、共通な概念規定をする必要性から生まれた臨床的、経験的な用語とされている。
宮本(1983)が指摘しているように、発達障害という語を用いる場合には、次の点について吟味してから臨床活用を展開していくことが必要である。1 アメリカ公法上の発達障害の概念は、DSM-3のそれよりはるかに広く、実際的であり、それぞれの本来の用いられ方の違いは、歴史的に何が問題とされてきたのかという事実の確認とともに認識されなければならないこと、2 また、語源にさかのぼって考えても、devel.opmental disability(発達の力の弱い状態)と developmental disorder(発達の混乱している状態)の意味のそれぞれが示すように、障害の種類を云々するといった硬直した考え方を脱し、それらの示す発達的事実は何かその力動性を考察し、機能的な観点で発達の障害をとらえていく必要があるということ、3 発達障害への対応は、狭い意味での治療という枠からぬけ出て、「発達援助」という観点でのかかわりが必要であること。
ラター(M.Rutter)は、1982年の来日講演のおり、「自閉症」をもつ子どもについて、「生物学的資質」という言葉で発達過程の違いに言及しながらも、「改善」については、“社会的な相互交渉をいかに発展させるか”が課題であり、それは“social skill や social behavior を教え込むことではなく、他の人の反応に即時反応する社会的な反応を育てることであり”、“自発的な応答、自発的なコミュニケーションが強調されるようになってきていてこれは世界的な傾向である”と述べている。このような考え方やアプローチの基本が、臨床方法を異にしても発達援助活動の本質として考えられていく必要がある。
(3)「特別な教育的ニーズ」の概念-イギリスから-
イギリスでは、1981年に制定された教育法(Education Act 1981)によって、特殊教育の基本概念が変わり、従来の障害種別の教育を廃して、その代わりに「特別な教育的ニーズ」(special educational needs)という言葉を採用し、そのようなニーズをもつ子どもたちを対象とする広義の特殊教育へと大きな転換があり、その後の経緯が注目されてきた。
この教育法は、1974年に設置された障害児・者の教育調査委員会(メンバー
は、教育、医学、社会福祉、産業界の関係者、および障害児の親から成る)によって1987年に提出された報告「特別な教育的ニーズ」、通称「ウォーノック・レポート Warnock Report」の勧告を盛り込んで法制化したもので、1983年に施行されている。
ウォーノック・レポートは、400ぺ一ジを超える膨大な報告書であるが、そのなかでは次のような重要な観点が概念化され、実現化が図られていった(山口薫、1988、Brennan.W.K、1987、Daniel.H.H、ほか、1987、Fish.J.、1985.)。
1)カテゴリーから連続へ(from categories to continuum)
障害のすべてのカテゴリーを廃し、「特別な教育的ニーズをもつ子ども」という一人ひとりの子どものニーズに関連したより広範な子どもの記述がなされるべきであること。
このベ一スには、「特別な教育的ニーズ」は子どもの側の要因によってのみ引き起こされるかのようなこれまでの考え方は改められ、それらは、子どものもつ特性と、子どもをとりまく環境の特性との相互性の結果として認識されなければならないという原則がおかれている。そこで、「特別な教育的ニーズ」は、連続したニードという言葉で記述され、いわゆる障害をもった子どもたちと、学習や適応において広範な難しさを経験している子どもとの間をはっきりと分けない。したがってこのなかには、たとえば「学習不振」「社会的不適応」「『情緒』障害」「家族の問題に関連したストレス(児童虐待や性的虐待)を経験している子ども」なども含まれるとされている。
「特別な教育的ニーズ」という概念について、ウォーノック・レポートを受けて政府白書(1980)では次のように述べられている。
“現在の分類形態は、障害児はすべて単一の能力障害をもつものと仮定しているが……いかなる分類体系をもってしても、一人ひとりの子どもの医学的、心理学的、教育的および社会的諸側面を一挙に記述することは容易にできることではない。しかも、医学的診断は、子どもの教育上の必要条件を適切に分析評価するものでもない。
ある意味では、一人ひとりの子どもの教育的ニーズは「特別」なのである。それらのニーズはその子どもに特有なものだからである”
1981年教育法では、“「特別な教育的ニーズ」をもつ子どもとは、彼のためにとられるべき特別な教育的措置を必要とするような学習上の困難をもつ子どもである”と定義されている。
2)インテグレーション(integration)
ウォーノック・レポートは、教育は可能な限り通常の学校で行われるべきであると提唱している。現実的に統合教育がどの程度推進されたかというデータは‘ゆっくりとした進歩状況’を示しているが、この理念を受けて、特別なニーズに応える教育の方法についての意識が非常に高まり、通常の学校における特別な教育的対応の編成方法にさまざまな形で反映されてきていて、その影響は大きいといわれている。以下、矢吹の論文を参照されたい(矢吹芙美子、1988)。
《統合教育のためのプロビジョン》
(1)普通学級や普通集団内でのブロビジョン
a)耳の聞こえない子どものための解説者、身体の不自由な子どもを支え、自立を助けるなどの社会的援助者
b)相談;特殊教育の専門家が訪問して、相談をする。たとえば、子どもを評価する、子どもの能力の損なわれている事柄について、担任教師の理解を助ける、学習計画に参加する、学習のために特別な材料を準備する、個々の子どもと出会って相談や援助をする、子どもの進歩を評価するなど、教師と子どもに専門的支援をする。
c)チーム指導(co-teaching,team teaching,collaborative teaching);特殊教育の教師が、あるブログラムを教える時間をもったか、担任教師とともに特殊教育の先生が常勤でいて、子どものグループのためにチームで教える。
(2)普通学級の教育に加えてなされるプロビジョン
a)特別教育;普通学級からひとりであるいは小グループで分化し、特殊教育の先生から子どもに即した技術訓練、計画的勉強や活動の教育を受ける。
b)セラピー;普通学校外のなかで、あるいはクリニックヘ行って、言語療法・物理療法・心理療法などを受ける。
C)普通学校外での特殊教育や特殊学校のクラスに参加する。
(3)普通学校のなかの特殊学級ユニット
(4)分離特殊教育ユニット;比較的短期間特殊教育ニードがなされることが望まれたり、異なった環境で子どもを評価する必要が考えられたときなどのユニット
(5)通学制特殊学級
(6)寮制特殊学級
(7)他の施設(たとえぱ、病院)での教育
(8)家庭での教育
《プロビジョンのひろがり》
義務教育前の準備が The Warnock Report により明らかにされたが、発展は今後に期待されるものである。
発見・診断・評価 これらについては病院や地域ヘルスサービスの役割は言うまでもないが、1981年の教育法では、議論の末、親が求めれば、2歳以下の子どもであっても義務教育前のすべての子どもたちのために、地方教育委員会は両親とともに、子どもを評価し教育する責任を分かちあうとされた。
家庭訪問教育 特殊教育の支援チーム(教師・セラピスト・OT・PT・ソーシャルワーカー)が家庭を訪れ、親とともに親と訪問教師との間でなされるべき活動のプログラムを決め、子どもの学習を助けるために必要な技術を親に教えている。また、心理学者や教師などのスーパーバイズのもとで、誰もが使える発達診断として Portage programme が広まっている。
巡回教育 ソーシャルサービス管轄の保育所やプレイグループにいる子どものために特殊教育の教師が巡回している。
Nursery School 統合教育の出発点であるが、普及率からいうと広範な教育状況とは言い難いが、専門家チームが相談を担っている。
特殊学級の NurSer yunit 適当な特別教育は受けないが、学校で治療を受けられる特色がある。統合の経験はできない。
義務教育後のプロビジョンとしては、19歳までの教育の権利が確立された。たとえぱ、特殊学校では、仕事の場への準傭教育がなされている。
3)多面的援助(multidisciplinary collaboration)
1981年教育法は、特別な教育的ニーズをもつ子どものために、正確なアセスメントと決定の手続きがとられるよう主張し、その際、両親の権利を保障するとともに、関与するあらゆる領域の専門家のコメントが反映されて決定が行われるよう配慮された。専門家とは、たとえば、医師、心理学者、スピーチ・セラピスト、理学療法士、作業療法士、ソーシャル・ワーカー、さらにその子どもや青年が出会うあらゆる機関のスタッフが、そのなかに含まれるといわれている。
ウォーノック・レポートは、教育的援助は、子どもの誕生とともに始まり、そして社会的自立に至るまで継続されるべきであるという継続教育の必要性を提唱している。当然、子どもの成長・発達のあらゆる過程における援助(発見・評価・教育)の総合性と一貫性を視野にいれたものであり、子どもおよびその両親を含めて、具体的な協力体制が発展してきていることは明らかのようである。
なお、イギリスにおけるこのような概念の転換がその後の10年にもたらしたもの、その具体的な変化などについては、次項において少しふれておいた。
3.発達援助の実践
(1)集団状況における子どもの発達
現在では、‘人間は関係的存在であり、個人は集団的存在である’という前提は、子どもの発達を考えるうえで不可欠な視点であり、発達研究の関心が、誕生以来の家庭の内外における「社会的ネットワーク」を重視してすすめる方向にも多く向けられてきている。障害をもつ子どもの乳幼児期の発達援助においては、ともすると「発達段階に応じて」を言葉どおりにとらえて、母子関係→家族関係→仲間関係というような継時的な発達観にとらわれた方法や、あるいは個別治療か集団の指導かというような二者択一的な治療観に左右された方法が選択されて、子どもたちをとりまく発達環境が固定化したり、発展性に乏しいものにとかくなりがちであることが従来より指摘されてきた。子どもたちがかかわりながら在る関係や集団の基盤をどのように用意しながら、しかも一人ひとりの発達がうながされる活動をどう展開するかということは、古くてしかも新しい発達援助の課題である。
吉川晴美は、統合保育の実践研究活動を継続してきて、‘個と集団の相即的発展をめざす集団活動’の重要性について次のように述べている(1987)。
“私たちは、集団活動を展開していくとき、個と集団の関係についてどのようにとらえ、その相即的発展をはかっていくか。一般的に、「集団」の指導をするとなると、1 指導者があらかじめ設定した枠や課題に個々がどのように参加するかという視点が先行しやすい。しかし、他に、2 集団に参加する個の各々の世界に成立する集団、3 人と人とがいること、即ち人間関係が展開することにおいて成立する集団、4 物、物理的領域、空間などがあることにおいて成立する集団、という特色があることをみのがしてはならない。したがって、集団を、1 2 3 4 の特性が相互に関連しあって展開されていく集団として多面的にとらえ、その特性に対応する個の自己、人、物との関係の統合的発達と集団全体のダイナミックな発展をはかっていこうとする”
0~2歳児や、発達援助を目的とする子ども達の集団活動には、吉川がふれているように、「集団」をどう考えるかという発想の転換と、そして一人ひとりののびやかな成長があっての集団であり、集団が発展することによりそこに参加する個の発達もうながされるという、個と集団の相即的関係を重視する理論と方法が展開されていることが必要である。このような理論と方法に基づいた実践は「集団指導」と呼ばれ、お茶の水女子大学の「児童集団研究会」にて1950年代より継続されてきているが(黒田淑子、1988)、現在では、幼児教育の場ばかりではなく、児童や成人の療育治療グループ、保健所など地域の母子活動などでも実践の輪が広がってきている。
発達援助の実践においては、どのような形であれ集団的基盤が用意される場合は「保育」と呼ばれているのが通常である。しかし、さまざまな専門領域の人々が「指導者」として参加することが多いこと。特に最近では、対象の年齢を乳幼児期に限らないことなどの理由から、もちろん呼び方だけの問題ではなく、その依拠する考え方と方法に、いわゆる「保育」に限定されない概念が求められてきた。そこで、東京のある療育機関において、20数年来続けられている「集団指導」の発達援助活動の実践について、事例的に次に紹介したい。
(2)「集団指導」の展開
日本肢体不自由児協会中央療育相談所通園部(現在は心身障害児総合医療療育センター通園部へ継続)の実践は、「集団指導」の原理と方法が生かされた発達援助活動の展開であるとともに、その設立、発展の過程が、わが国の乳幼児療育の変遷を具現しているとも考えられるので、主として集団指導の導入のプロセスにふれながら、さらに乳幼児療育の体系の枠組についても言及したい。
通園部の母体である中央療育相談所は、「療育」の提唱者高木憲次の構想により、わが国最初の肢体不自由児入所施設である整肢療護園(昭和17年開園)に続いて、在宅児の療育相談・療育指導の地域の拠点として、昭和27(1952)年に発足したものである。児童福祉法(昭和22年)および身体障害者福祉法(昭和24年)施行後というわが国の児童福祉の曙光期ともいえるこの時期に、「療育のあり方の普及・徹底」を目的として、高木を中心に療育チームが編成され、3年間(昭和24~26年)にわたる全国の巡回療育相談・指導が実施された。これが契機となり、肢体不自由児の療育に関する各府県の関心が急速に高まり、その後のわが国における療育の発展の大きな礎石となったわけであるが、その主旨を定着させるべく、中央療育相談所は開設され、「医療を中心とする関係スタッフの科学的、総合的診断と治療」「父母への療育指導」「一般への療育思想の普及」など、地域に根づいた療育相談機関としての機能は当初から明らかにされていた。
幼児の療育の方向について、特に検討の必要性が認識されだしたのは、昭和40(1965)年前後である。子どものもつ問題や障害といわれるものが、発達の早期に診断され、「早期療育」の必要性がつよく提唱されだしたが、現実にはその具体的方策は不十分であり、診断されて適切な治療関係も結ばれないまま不安な状態に子どもと家族がおかれていたり、あるいは、障害の側面に対する医学的治療、対処のみが強調されて、結果として、治療・訓練を名目にごく幼少時から障害の有無、種類別に分けられ、子どもたちが社会において相互に交流をもつ可能性も少ないまま育っていく療育の状況が次第に明らかにされはじめた。
中央療育相談所では、五味重春が早くからこの状況をみぬき、“児童の成長に必要な心身両面のサービスの手だてが、療育の途である”と後に述べている(1976)ような考えを抱いていた。そこで昭和40(1965)年から、幼児の新しい療育の方向を摸索しながら、治療・訓練に通所してくる子どもたちの社会的経験を配慮して「保育プログラム」も組まれるようになり、母子が参加しての集団活動が開始された。しかし、その時点では、集団の形態はとっていても、集団の意義と教育的かかわりは、治療・訓練効果を高める手段として位置づけられていたにすぎなかった。医療の補助として、あるいは、単に生活習慣の動機づけとしてではない、乳幼時期の心身の発達を統合的に援助する理論と方法が強く求められていた。
その頃、わが国の言語治療の草分け的存在である田口恒夫(当時お茶の水女子大学)を中心とする研究者グルーブにより、幼児の言語治療の方法に関する検討が継続的になされており、話す機会をふやすことの中で言語指導をすすめる技法論を主張、“関係者が「子どもの立場」を共通の基盤として協力する体制”をめざす方向(田口、1966)は、「集団指導」の主旨と一致するところであり、のちに協力的なチームワークを組むこととなった。
中央療育相談所において、多少の試行錯誤を生みながらも、医療(看護、運動療法)・言語治療・心理指導・保育・福祉などのスタッフが参加して「集団指導」の実践が開始されたのは、昭和44(1969)年である。
さらに、翌45年より、職種を問わず全国の幼児の療育にたずさわる人たちによびかけ療育集団指導の研究集会がもたれることとなった。その主旨は次のようなものであった。すなわち心身に障害のある子どもの療育の実践や研修を、どの子どもも、どの人もともにいる状況(集団)を、いま、ここに創ることから始めること。これまでのように障害の種類別や程度別に、あるいは、発達の諸領域別や、指導する側の専門領域別に、まず「分けて」から始めることをしないで、ともにいる状況を基盤とし、そこに参加している一人ひとりのかけがえのないあり方が肯定され、ともに育ちあう集団づくりを実現させていくこと。そのような集団づくりの実践を、療育の内側からの働きかけだけに終わらせず、一般の幼児教育の実践や研修との意識的、現実的連帯をよびおこす契機とすること。
この研究集会は、昭和54(1979)年の第10回まで、毎年100名を超す全国からの幼児療育の職種を超えた指導者の参加のもとに続けられた。その期間は、早期療育の新しいうねりの中で、全国的に現在ある幼児療育機関の量的・質的礎が築かれた時期でもあり、それぞれの地域や機関の特性を生かした幼児療育体系の理論と実践の確立に向けて、中央療育相談所の実践はひとつのモデルケースあるいはサンプル提示の役割を果たしてきたと考えられる。
その第1回の研究誌に、療育集団指導の実践報告のまえがきとして、私は、従来の保育や、心理臨床における集団遊戯療法の適用とは区別する新しい形の幼児療育としての「集団指導」を導入したその意義について次のような文を書いている(武藤、1970、一部修正)。
《集団指導の意義》
1 集団指導は、運動療法(PT、OT)、言語治療(ST)、心理治療、保育などの専門領域からの指導者が同時に参加し、複数の指導者がチームを組みながら活動がすすめられる。集団活動においては、各々の指導者が主として動く状況が、いくつか展開する。たとえば、PTが主として動いて動作活動の発展がもたらされる状況があって、次に、STが主として動いて言語活動の発展がもたらされる状況が展開する、というように。その場合、同一状況に参加している他の指導者は、その活動の補助促進者としてだけではなく、むしろ、そのような状況においても、自分の専門領域における活動の発展がもたらされるようなかかわり方をする。たとえば、主として動作活動の発展がもたらされる状況において、心理指導をいかにすすめるか。あるいは、保育活動の発展がもたらされる状況において、どのように運動療法がかかわることができるか。このことは、ある専門領域の活動の発展をもたらすために、他の専門領域が役だつということではない。指導者チームにおいて、相互促進的関係が成立することが必要である。
2 「遊びをとおしての訓練(治療)」ということばが、訓練の目的を達するために遊びを利用するとか、遊んでいる状態において訓練がしやすいという意味で使われていることがよくある。「遊び」という活動は、子どもの側の自発的、主体的存在の表出であり、どの子どもにおいても尊重されなければならない。一方、「訓練」という活動は、子どもにとって達成されることがのぞまれる発達の課題である。「遊び」という活動の発展がもたらされることが「訓練」という活動の発展をもたらす、そのことが、また「遊び」という活動をさらに発展させるのに役だつ。それが同時にすすめられるような「遊びと訓練」の統合状況が療育において必要である。
3 同一状況における各指導者のかかわり方(指導の目的)の違いは、子どもの全体的発達がめざされる方向において統合される。たとえば、座っている姿勢を保持している時に、たくさん話をしようとすると、その姿勢がくずれてしまうという場合に、姿勢の保持をさせるために話したい気持ちがおさえられたり、働きかけようする動きがとめられたりすることは、全体的発達がめざされている状況とはいえない。
4 子どもの、いまある状態(気持ち、態度、能力など)を、いま、ここに成立している状況においてはよいものとして受け入れる。そして、状況全体が発展することのなかで、今ある状態をさらに促進させる可能性を開発することを訓練・治療の目的とする。
たとえば、片まひのため立っている姿勢を保持することがまだ困難であり、左手をあまり使わない子どもがボードに絵をかく活動が展開しているとする。子どもは行いやすい姿勢、方法で絵をかいている。子どものそのような状態を矯正したり治療したりしようとする態度を優先させるのではなく、いま、ここに成立している状況をよいものとして受け入れ、その子どもの自発活動がさらに発展するよう働きかける。たとえば、集団状況においては、次のような活動が展開しうる。紙に絵を描いていた他の子どもが、自らあるいは促されてボードに気づき、「これバナナなの」と切りぬいた絵をもってくる。子どもはそれを受けとると、セロテープで自分の都合のよい位置に貼りつける。他の子もまたもってくる。また貼る。もってくる。子どもの中に、他の人を受け入れる気持ちがのびてくるほど、両手を使って貼る方が、ずっと速いし、よろこばしい体験をする。またもってくる。りんごであったり、おすしであったり、パンであったりする。指導者は「○○ちゃんのおみせにいっぱいね」とその活動を個の活動に止めず、集団活動のなかに意味づけ、位置づける。すると他の子どもたちも「おみせ」に気づき、絵を描く活動が活発になる。また誰かがもってくる。貼りやすい位置からだんだん貼られて、ついに立ち上がり、両手を使って、自分の丈より高い位置に背伸びしてまで貼りつけようとする活動が展開された、そういう事実がそこにいた指導者にも、子どもにも体験的にたしかめられる。その事実は、指導者の提示や促しによってのみもたらされたものではない。そのようにして貼っていった子どもの主体的な活動があって、そしてそこに働きかけてきた他の子どもがいて、その子どもが他の場所で展開していた絵をかく活動がある。
5 このようにして、ある子どもに成立した新しい事実は、集団活動全体の力動的な発展においてもたらされたものであるという認識が参加したどの人々も体験的にも成立し共有される。幼児においては、結果が訓練の目的と合致した事実があったとしても、その過程において培われる人格形成がその後の成長に大きな影響をもたらす。ここに、子どもの集団活動における意義がある。
6 新しい事実がもたらされるきっかけとなるものを集団技法とよび、それぞれの専門領域の技法とは別に療育チーム指導の専門技法として体系化されることが望まれる。また幼児の療育にたずさわる指導者は、以上のような集団全体の力動的発展をもたらすことの可能なチーム活動の一端を担える人が望ましいが、個別の指導においても、上に述べたようなあり方がどの専門指導の基本にもあることが望まれる。
(3)乳幼児のチーム療育体制
1)1970年代より
現在では、障害をもつ乳幼児のチーム療育が不可欠であるとの認識はすでに一般的であるが、療育の方法が専門科学的により細分化されてきており、その内容をどのように統合化していくか、あるいは、各専門領域間の連携をどのようにはかっていくかということについては、障害をもつ子ども個人の療育プログラムや、施設・機関内のチーム指導体制のレベルにおいても、また地域や社会のあり方のレベルにおいても、いまでも考えなければならない大きな課題である。
中央療育相談所は、在宅肢体不自由児の療育相談機関として発足したが、昭和40年代半ばには、相談・治療にあたり原則として障害の種類を問わず、子どもの総合療育の方向を明らかにしていたこと、それに対応すべく運動療法(PT、OT)・言語治療・心理指導・栄養指導・福祉指導などを担当する常勤のスタッフをおいていたことなどにより、通ってくる子どもの障害は多様であり、しかも、対象年齢は、障害の早期発見により、0~1歳という発達早期から主として就学前までという発達的に過敏な長期間にわたることとなった。一方、集団指導の導入により、乳幼児期の基礎的な社会集団としての地域通園の性格もあわせもつこととなり、関連する施設・機関も多岐にわたっていた。多様でしかも変化していく発達課題に応じて療育の内容や生活の基盤を柔軟的に組み替え、それらに段階的、発展的に対応しうる発達援助のための総合的なチーム療育体制の必要性が、必然的に生じてきた。
チーム指導の体制は、指導の内容をどのように組織するかという観点から2つの大きな柱をたてた。ひとつは、指導の内容を、指導の目的に焦点をあてて、運動療法、言語治療、心理指導など発達領域別に分類されるいわば発達課題領域の柱である。もうひとつは、子どもの生活が具体的に展開する場・状況を中心にして、日常の生活経験、集団の経験、個別指導のような課題状況における経験などに分類される生活経験領域の柱である。これらの指導内容をどのように関連させてのぞましいチーム指導体制を実現させていくことができるか。発達課題領域の内容が、発達領域別にばらばらに用意されて、全体的発達を促進するために必要な配慮が欠けてしまわないように。あるいは生活経験の場が生活経験領域の内容別に切り離され、相互に生かされにくく、生活全体が非常に発展性の乏しいものにならないように。
このような課題をふまえたチーム指導の体制を構造化して図に表したものが図2-2である。
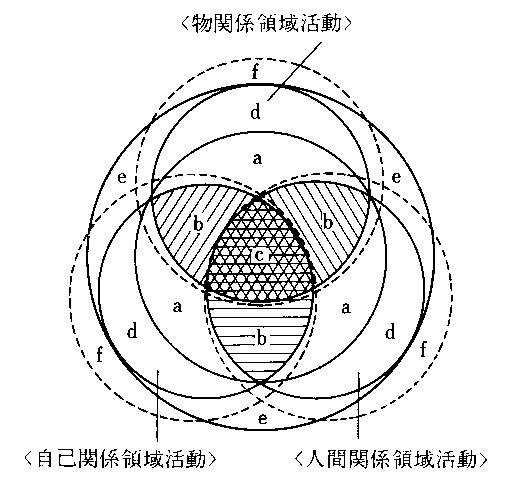
図2-2 チーム指導体制の構造
この構造図は、チーム指導の形態を領域的に明確化したもので、子どもの生活の共通基盤を充実させながら、個々の発達的課題、指導の専門性などの差異性が生かされ、たがいに交差して働きかけあいながら統合化をめざすために、少なくともa~fの6つの指導の形態が用意される必要があることを示してい
る。6領域は次のようにあらわされる。それらを具体的な活動と対応させると表2-1に示されているとおりである。
a.共通基盤領域における指導
b.交差連結領域における指導
c.統合領域における指導
d.分化独自領域における指導
e.関連集団領域における指導
f.発展社会領域における指導
表2-1 乳幼児の療育におけるチーム指導体制
-中央療育相談所の場合-
| チーム指導の形態 | 活動内容 |
|---|---|
| a.共通基盤領域における指導 共通の基盤の充実をはかる活動を展開 |
○生活基盤活動 施設内外の環境整備、通園バス、家庭療育、家庭保育 ○家庭訪問指導 ○保護者会、療育指導会 |
| b.交差連結領域における指導 交差、交流をはかりながら活動を展開 |
○母子小集団指導(母子単位のグループ指導) ○専門領域交差指導(他の専門領域への交流指導) |
| C.統合領域における指導 共存、共有をはかりながら活動を展開 |
○集団指導
|
| d.分化独自領域における指導 相対的に独立して活動を展開 |
○専門領域別指導 |
| e.関連集団領域における指導 関連的にある他の領域へ働きかけながら活動を展開 |
○他機関(施設、保育園、幼稚園、学校)との連携、交流 ○父母の会活動 ○療育キャンプ ○卒園児交流会 ○講演会 ○施設間連絡会 |
| f.発展社会領域における指導 規定する枠組を広げながら活動を展開 |
○社会地域活動(運動) ○障害児福祉対策(運動) ○児童福祉〈保育〉対策(運動) |
2)1990年代より
1971年から2年ばかり、私はロンドンに滞在する機会を得た。まだロンドンにおいても乳幼児を中心とする早期療育を総合的に行っている通所施設が数か所しかなかった頃であったが、その一か所に定期的に通って療育プログラムに参加したり、そこが主宰するワールドワイドの研修を受けたりした経験があるので、その後のイギリスにおける療育の発展の経緯には、関心をもっていた。1992年に訪れた際、ロンドンや近郊の地区において、療育の拠点となる施設や機関が、チーム療育体制という点に関して、自施設にかなりはっきりした特色を与えて共存している興味ある状況がうかがわれた。説明に先だって図2-3を参照されたい。これは関係学において、諸要成がかかわって関連体系がつくられる場合、どのような構造化の類型がみられるかということを三層構造的に図解したものであるが(松村、1979)、これを適用すると理解しやすい。すなわち、それらは大きく3つのスタイルに分けてとらえることができた。
Aスタイルは、子どもの発達課題あるいは専門性は類同あるいは近接構造化して、指導者個人のレベルにおいて統合されていることが理想とされる場合である。主として脳性まひの療育にとりいれられているコンダクティブ エデュケーション(conductive education、日本ではハンガリー式集団療育指導と訳され紹介されている)はこの代表的なものであろう。多くの国の療育が、とかく治療の専門別に細分化され、man to man 方式でなされている弊害を排し、子どもちには集団の man to man 的状況下において、医学的、教育的にすべての面の知識を修得した指導者-コンダクタ-により、日常生活に即して全面的な人間形成が行われることが目的とされているといわれる(ペトPeto,A.)。コンダクターチーム・子どものグループ・両親たちが、人種や言語の垣根を超えて、目的を一にした同質的なつながり特有の信頼の絆を形成しており、乳児クラス、幼児クラス、義務教育のクラスまで一貫した療育体系が整えられつつあった。
Bスタイルは、ちょうど中央療育相談所のケースがこれにあたると考えられるが、異なる専門領域が共通領域をもちながら、しかもそれぞれ相対的に独立した領域もありながら連結交差構造化している場合である。現在では、ロンドン周辺で、PT・OT・ST・心理などのスタッフが、個別指導と同時に一日のどこかで保母や教師とともに集団活動に参加するカリキュラムをもっ総合療育施設は多く、集団レベルにおける統合化をチーム療育体制の要としようとする姿勢が十分うかがえた。特に療育を開始する時点、あるいは発達の課題が変化する時期(たとえば、学齢期前の教育開始について、いつをその時期とするかなど)には、両親を含む関係者全員が、時間をかけて多面的に情報を交差させながら方向を選択できるメリットが強調されていた。
Cスタイルは、療育機関はそれぞれが個別的な機能や特質をあきらかにし、他と共有領域をつくろうというよりはむしろ自在であり、社会のレベルであるいは地域全体としての統合化をはかっていこうとする、形態あるいは閉合構造化の場合である。両親は、子どものニーズに応じて、たとえばボバース法のような特定のより専門性の高い療育機関を積極的に活用し、他のニーズがあれば他の機関を求めるという具合にその自主的な判断が尊重されていた。イギリスにおいて、1981年教育法、1988年教育改正法によりもたらされた変化を療育機関の側からながめるといくつか感じられることがある。ひとつは、子どもの「特別なニーズ」の評価過程のいかなる段階においても、両親がディスカッションや決定のすべてに参加できる権利が確立して以来、両親が、アセスメントのみではなく、それに続く療育の方向をも見通して、子どもの生き方について自分たちと考え方のうえでも協働していける機関なり治療者なりを選択してアセスメントを求めようという姿勢が強く感じられた。私の経験でも、両親のニーズは子どものニーズとはまた別な意味で多様である。両親が、子どものもつ発達の権利をそこなわない限りにおいて、家族としての生き方の独自性を主張する基盤があることが大切であると考えられる。ふたつめは、当初の理念には届いていないにしても、インテグレーションの実績とともに、療育機関の「リソースセンター」としての役割がより大きくなってきているということである。上記のいずれのスタイルでも他の一般教育、特殊教育の施設と平行して、おのおののニーズに応じた治療を求めて通ってくる子どもたちが増えているし、また教育の場において教師と協力態勢をとる専門家「助言・援助教師」の養成にも、各施設・機関内でかなりのウエイトをおいていることが感じられた。政府の「現有の資源のより効果的活用」をという財源の制約にもかかわらず、それぞれの療育機関は、地域のリソースセンターとしての役割において他機関とは異なる自機関の特質を強調しながらむしろ活気が増しているように感じられた。
わが国においても、地域的な差はあっても、かなり対応的な状況で進みつつあるとは思うが、現在のイギリスにおいては、どこへいっても公的用語としては、会話上においても「障害」という言葉および「障害名」を優先して述べることを意識的に避けようとする傾向がみられ、カテゴリーを排し、個を尊重する基盤にたって療育や教育的対応の編成を進めようとの努力は印象的であった。
発達臨床の体系が、現実的なシステムとして有効に機能する基盤には、障害をどうとらえるか、子どもをどのような存在としてとらえるか、そこで用いられる方法はどのような状況における人間のあり方をめざしているのかなどという実践を支える概念が問われなければならない。
主題(副題):発達臨床-人間関係の領野から-
第1部 第2章 19頁~46頁
