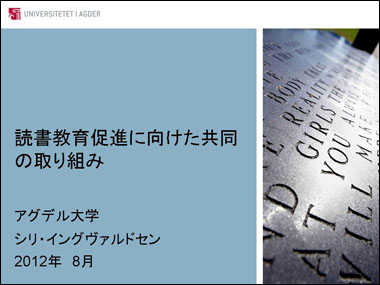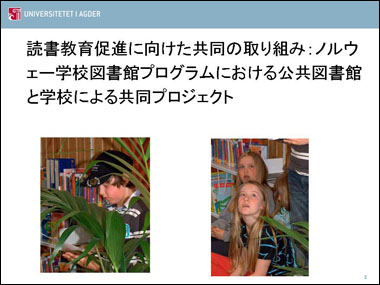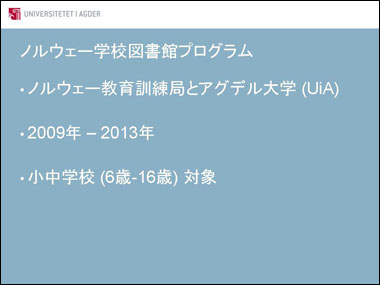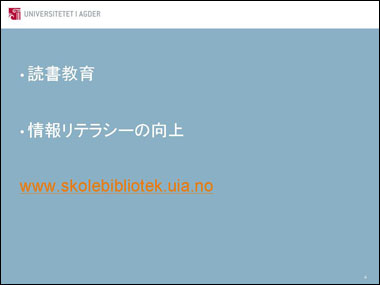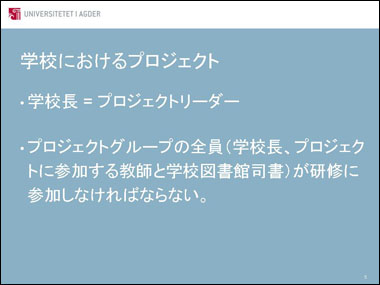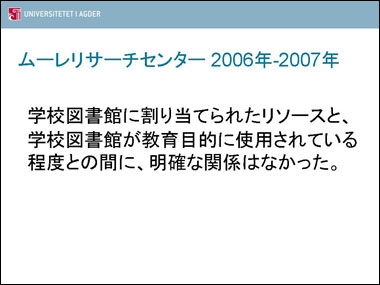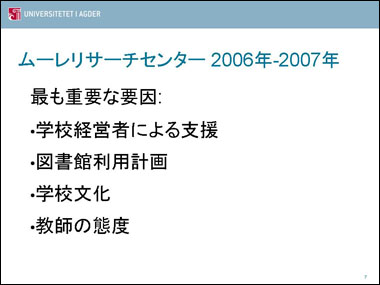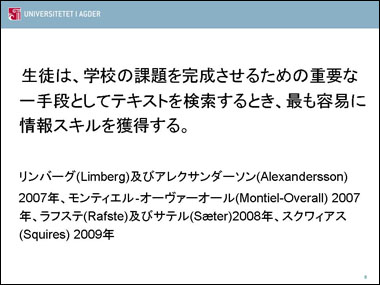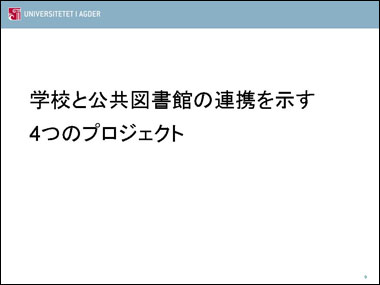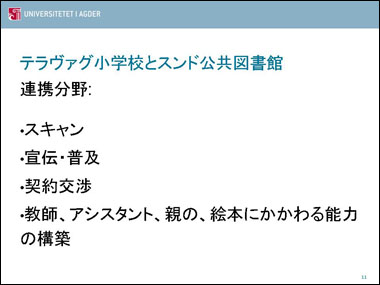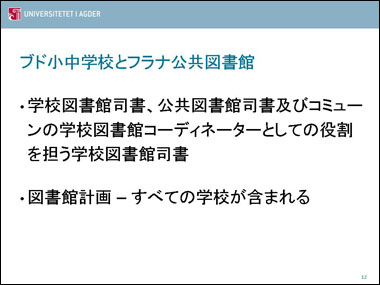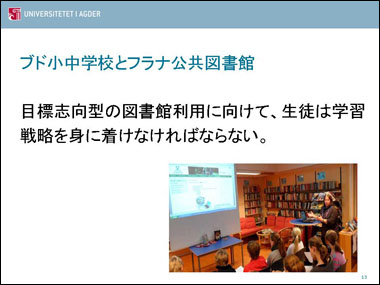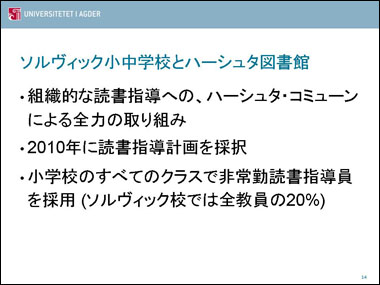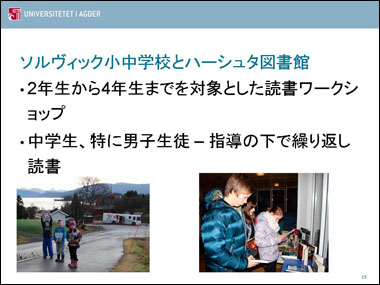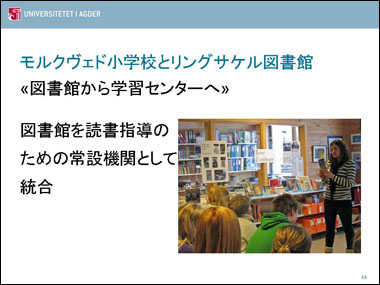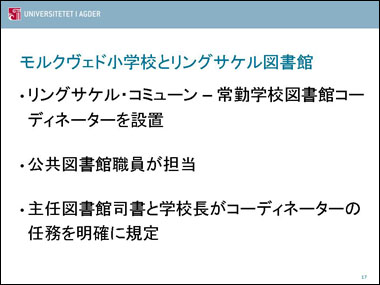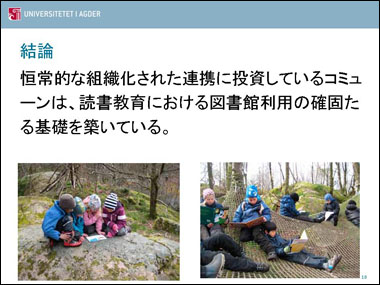読書教育促進に向けた共同の取り組み:ノルウェー学校図書館プログラムにおける公共図書館と学校による共同プロジェクト
ノルウェー クリスチャンサン
アグデル大学
シリ・イングヴァルドセン(Siri Ingvaldsen)
IFLA2012 ヘルシンキ(フィンランド)
資料
要旨:
本論文では、ノルウェー学校図書館プログラムにおいて、読書教育を支援するために、学校が地域の公共図書館とどのように連携しているかを論じる。このプログラム(2009年‐2013年)は、教育手段としての学校図書館の強化を目的としている。2006年から2007年にかけて実施されたノルウェー学校図書館調査からは、特に小中学校において、リソースへのアクセスが不足しており、職員の能力も十分でないことが明らかになった。そこでプロジェクト資金が支給され、学校が実務関連のプロジェクトの資金を申請できるようになった。プロジェクトでは、読書教育の促進と情報リテラシーの向上をめざし、学校図書館の積極的な統合が進められている。2011年-2012年の学年度末には、125校が上記プログラムから資金を受領し、プロジェクトを完了したが、プロジェクトグループ(学校長、学校図書館司書及び教師)は、プログラムが後援する継続教育講座に引き続き参加している。本論文ではさらに、ノルウェーにおける学校と公共図書館の間の、この種の連携に適した枠組みについても論じ、地域レベル及び県レベルでこれをどのように進めていくか、2、3コメントを提供する。その後、ノルウェー学校図書館プログラムを通じて実施された、共同プロジェクトの実例をいくつか紹介する。
序論
ノルウェー学校図書館プログラムは、プロジェクト校と公共図書館の連携実現を大いに重視している。多くの学校図書館(プロジェクト校の図書館を含む)では、リソースが限られており、資格のある職員が不足している。一方、公共図書館には、図書館関係の専門知識を備えた職員がおり、膨大な数の最新の物理的媒体とデジタル媒体が所蔵され、これらを組み合わせることで、学校側に貴重なリソースを提供することが可能である。同時に、学校との連携は、公共図書館の利用者を増やす手段でもある。小中学校レベルでは、6歳から16歳までのすべての子供達に会い、その親や教師にも接触することができる。学校は、図書館サービスを通常利用しない人々をも対象とした、重要な宣伝の場なのである。
図書館と学校は当然のことながら連携のパートナーである。両者は、知識獲得と民主的なプロセスへの参加に貢献するという社会的任務を共有している。ノルウェー学校図書館プログラムにおいて最も注目すべきは読書教育である。したがって、プロジェクト校と公共図書館との連携は、指導のためのリソースとしての図書館を強化する第一の、そして最大の手段なのである。本論文では、この種の共同プロジェクトの例を4件紹介するとともに、ノルウェーにおける学校と図書館の連携のためのガイドラインについてもコメントする。はじめに、ノルウェー学校図書館プログラムについて簡単に紹介する。
ノルウェー学校図書館プログラム
ノルウェー学校図書館プログラムは、教育手段としての学校図書館の強化を図る4年間(2009年‐2013年)の国家プロジェクトである。プログラムの目的は、学校図書館が読書教育の促進と情報リテラシーの向上に積極的な役割を果たすようになることである。プログラムは、ノルウェー教育訓練局の要請を受け、アグデル大学(UiA)が運営しており、教育による図書館利用スキルの向上、ウェブサイト(www.skolebibliotek.uia.no)の開発、教師、学校図書館司書と生徒の情報スキル獲得促進のためのアイディアと指導教材のデジタルバンク創設という、いくつかの重点分野から構成されている。
ノルウェー学校図書館プログラムの拠点がUiAに置かれた背景には、学校図書館司書教育に対するUiAの長年のコミットメントがあった。学校図書館司書教育を受けている学生の多くは、学校図書館学に関する継続教育講座を受講している教師である。2011年には、この研究プログラムが学校図書館学学士プログラムへと拡大され、図書館関連テーマ入門、児童・青少年文学、情報リテラシー及び読みの発達がおもに取り上げられている。
プログラムでは、学校開発プロジェクトの資金が確保されている。プロジェクト校は当初1年分の資金を受領するが、翌年の資金も申請することができる。2年分の資金を受領した学校は、プロジェクトをさらに発展させ、プログラムのリソース校とならなければならない。
プロジェクトへの支援を申請できるのは、小中学校だけである。つまり、高校が利用できる資金援助はない。この優先順位は、2006年から2007年にかけて、ムーレリサーチセンター(More Research Centre)によって実施された、ノルウェー学校図書館に関する総合調査の結果を受けて決定された。調査報告書は、学校図書館のための資金が最も少ないのは小中学校であると結論づけていた。高校には小中学校よりも質の高い職員がおり、学校図書館司書に任されている時間が多いという傾向が見られた。また、小中高の違いにより、図書館施設と蔵書の充実に充てられる資金に大きな差があった(バースタッド(Barstad)、アウダンソン(Audunson)、ヨルトサテル(Hjortsater)及びオストリー(Ostlie)2007年)。
ノルウェー学校図書館プログラムから資金提供を受けている小中学校には、地域の公共図書館との連携を模索する十分な理由がある。地域の公共図書館には、図書館に関する専門知識を備えた職員が存在するとともに、物理的媒体とデジタル媒体が充実しており、多くの場合、広範な専門家ネットワークとのつながりが認められる。プロジェクト校の多くは、プロジェクトを進めるに当たり、公共図書館から多大な支援を受けてきた。
しかし、ムーレリサーチセンターの調査からは、学校図書館に割り当てられたリソースと、学校図書館が教育目的に使用されている程度との間に、明確な関係は認められなかった。報告書は、学校図書館を学校に積極的に統合する上で最も重要な要因は、学校経営者による支援と、図書館利用計画、そして図書館のようなリソースを取り入れることを認める学校文化であると結論づけた。さらに、教師の態度も決め手となる。学校図書館の積極的な活用には、教師が指導に図書館利用を盛り込まなければならない(前掲書)。このため、ノルウェー学校図書館プログラムでは、学校長にプロジェクトマネージャーとなることと、プロジェクトグループの全員(学校長、学校図書館司書及び参加教師)に、プログラムが後援する継続教育講座を受講することを義務付けている。この2日間の講座は、秋学期と春学期に開催され、学校図書館の教育的利用、学校における情報リテラシーの向上、さまざまな印刷テキスト及びデジタルテキストの読み方などのテーマを取り上げる。また、学校と公共図書館の連携にも注目し、さまざまな連携の形を紹介する。
教師と図書館司書の協力
情報検索プロセスにおける生徒の学習成果に関する調査結果は、教師による各教科の指導と連携した図書館及び情報資源の利用について、研修が必要であることを示唆している。生徒は学校の課題を完成させるための重要な一手段としてテキストを検索するとき、最も容易に知識を獲得する。これは、学校図書館というリソースの利用を、教師と学校図書館司書が協力して計画・評価しなければならないことを意味している。学校と公共図書館との共同プロジェクトでは、公共図書館が計画のプロセスにも参加する必要がある(リンバーグ(Limberg)及びアレクサンダーソン(Alexandersson)2007年、モンティエル‐オーヴァーオール(Montiel-Overall)2007年、ラフステ(Rafste)及びサテル(Sater)2008年、スクワイアーズ(Squires)2009年など参照)。
「多様性プロジェクト(the Multiplicity Project)」(2007年‐2011年)の報告からは、地域の公共図書館と学校が読書推進に関して連携することで、生徒の読書への意欲を一層高められることが明らかになった。このプロジェクトは学際的な調査研究プロジェクトで、オスロユニバーシティカレッジとブスケルーユニバーシティカレッジの研究者が、2つの学校とドランメン公共図書館の協力を得て実施したものである。研究者、図書館及び教師らは4年以上にわたり、連携の形と、そのような連携が生徒の読書習慣にどのような影響を与えるかを調査した(オスロ・アーケシュフース大学 2012年)。
「情報リテラシーを備えた教師の教育(Educating the Information Literate Teacher)」という、ベルゲンユニバーシティカレッジとホルダラン県立図書館、そしてベルゲン地域の実習校との共同プロジェクトは、教師と生徒の情報リテラシーの向上を目標としている。プロジェクトに参加する教師は、情報検索と大学図書館の利用に関する指導を受け、生徒への指導を開始するに当たり、プロジェクトを通じて学んだことを今度は自分の生徒に教えていく。実習校は、学校図書館強化に向けて県立図書館の支援を受け、指導リソース校となる。ノルウェー学校図書館プログラムの対象校2校(フィエル・コミューンのフィエル校とトラネヴァゲン校)がこのプロジェクトに参加している(ベルゲン大学 2012年)。
2010年から2011年にかけて、ブスケルーユニバーシティカレッジとブスケルー県立図書館が、「相互交流による相乗効果(Interaction Creates Synergy)」という同様なプロジェクトを共同で実施した。このプロジェクトで学んだ教師は、児童及び若者の文学と文学の普及に関する知識を身に着けることができ、学校図書館に関する知識も増加した。一方、児童図書館司書は、児童と若者の多様な幼少期について、その読書習慣も含めて知識を深めた(ブスケルー県立図書館 2012年)。
図書館と学校の連携
1985年のノルウェー図書館法は、児童と若者に可能な限り最善の図書館サービスを提供するために、公共図書館と学校が連携することを定めている(1985年図書館法)。さらに、県レベルでは、図書館と学校部門の正式な連携が確立されるべきだとしている。しかし2012年3月、文化省はこの規定を撤回するべく現行図書館法の改正案を提出した。協議覚書には、地域及び県の機関に対し、お互いに協力するよう強制することは望ましくないと記載され、この動きが正当化されている(文化省 2012年)。地域と県がどのように内部提携を進めるかは、地域で選出された役人と公務員によって決定されるべきである。さらに、連携に関する規定は図書館法にのみ記載されており、学校法にはこれに匹敵する明確な記載は見つけられない。改正案により、この不均衡が修正されるであろう。しかし、改正案にもかかわらず、一般にコミューンレベルでの乏しいリソースをまとめることで、児童と若者によりよい図書館サービスを提供できることから、図書館と学校部門の今後も変わらぬ連携を国家政府が極めて重視していると信じるに足る理由が、引き続き存在する。
図書館と学校部門の連携のためのガイドラインが作成され、各参加コミュニティの連絡委員を任命することが提案されている。これらの連絡委員は、児童と若者を対象とした、可能な限り最善の図書館サービスを確保するが、これにはさまざまな種類の図書館の、企画と運営に関する共通の解決策の模索も含まれる。ノルウェーの429のコミューンのうち341のコミューンが、公共図書館と学校との組織的な連携について報告している。また、一定数のコミューンで学校図書館司書コーディネーターを採用しているが、その役割は、学校の蔵書追加に関する支援の提供、電子目録に関する協力の申し出、研修の実施、読書推進活動の立ち上げ、ネットワークによる連携の促進などである。
ノルウェーの公共図書館のおよそ3分の1は兼用図書館である。これは、公共図書館と学校図書館の両方の機能を果たしているということである。ノルウェー学校図書館プログラムに参加している学校図書館の中にも、この種の図書館がある。プログラム関連の研修や協議会では、兼用図書館が学校にサービスを提供する際には、実質的には学校図書館としての機能を果たさなければならないことが強調される。学校図書館と公共図書館では目的が異なる。図書館法によれば、公共図書館は社会のあらゆる集団にサービスを提供しなければならない。一方、学校図書館は、教育法と国の教育課程に定められている学校の任務と目的を同様に持つ(1998年教育法、2006 年知識向上カリキュラム(Knowledge Promotion))。兼用図書館の課題の一つは、これら二つの異なる機能を使い分け、すべてのターゲット集団をうまく満足させなければならないことである。
学校所有者‐そして図書館所有者としてのコミューン
前述のように、統合は、指導における一層意識的かつ組織的な図書館利用の成功の決め手となる。ノルウェー学校図書館プログラムが資金提供しているプロジェクトでは、図書館利用を学校経営者の計画と学校の教育課程に統合しなければならない。プロジェクトマネージャーとして学校長は、開発活動の経験が、プロジェクト終了後に学校の利益となるよう、全般的な責任を負う。
さらに、学校からのプロジェクト申請書をノルウェー学校図書館プログラムに提出するのは学校所有者であるため、学校所有者としてのコミューンの統合も同様に重要である。コミューンは学校から提出された申請書を点検し、ランク付けをしてから転送する。この二段階にわたる申請手続きにより、学校と地域の両方が学校図書館の役割と任務を確実に検討することができる。さらにこの手続きは、そのコミューンにおける学校間及び学校と公共図書館に共通する解決策を考えるきっかけとなる。学校と公共図書館の所有者は同じであるため、互いを関連付けて検討する適切な基盤が必要なのである。
申請手続き、学校プロジェクトの実施と報告制度を通じて、学校と公共図書館の関係及び連携が促進される。申請書には、学校が参加している他のプロジェクトに関する質問があり、学校とコミューンがプロジェクトの経験を他者とどのように共有していくかが重視されている。共同プロジェクトは、さまざまなタイプの図書館が経験を伝え合う重要な架け橋となる。
プロジェクト校‐共同プロジェクトの事例
以下のセクションでは、ノルウェー学校図書館プログラムにおける4件の開発プロジェクトを紹介する。いずれも学校と公共図書館の連携を示す事例である。内容は、学校による計画書と報告書、公共図書館とコーディネーターによる覚書と調査結果、学校長/学校図書館司書/コーディネーター/主任図書館司書との評価談話を基にしている。
ホルダラン県のテラヴァグ小学校には75人の生徒がいる。ノルウェー学校図書館プログラムのプロジェクトは「デジタル絵本の味(A Taste of Digital Picture Books)」という名称で、1年生から4年生までの読書の喜びとスキルを、絵本を通じて高めることを目的としている。学校はスンド公共図書館と密接に協力しており、プロジェクトの申請書は学校長と主任図書館司書が共同で作成した。
このプロジェクトでは、絵本のデジタル化が行われた。学校は公共図書館と相談の上、質と多様性を重視しながら絵本を収集した。公共図書館はテラヴァグ校に勤務するアシスタントとともに、絵本を選んでスキャンし、生徒と教師がデジタルフォーマット(パワーポイント)で利用できるようにした。図書館はさらに、これらの本を使用するに当たり、作者や画家との著作権関連の交渉に全責任を負った。デジタル版の絵本は、学校図書館のPCで利用できるようになったが、CDにもコピーされ、教師が教室に持ち込んで、自分のPCやプロジェクターまたは電子黒板で見せることもできるようになった。
学校図書館は絵本を見せる大画面を導入し、読み聞かせのための読書コーナーを設けた。絵本では言葉と絵が極めて密接にかかわりあっていることを考えれば、生徒が読み聞かせを聞きながら、絵を近くでじっくり見ることができれば、読書の効果を最大限上げられる。大画面で見られるこれらの絵本のことを広めれば、さらに多くの生徒が読み聞かせに参加できるだろう。さらに、デジタル化の長所として、これらの本が必要に応じて利用できるようになったことがあげられる。順番待ちリストの問題は解決された。スンドの主任図書館司書は、プロジェクト関連のイベントでプレゼンテーションを行い、教室での指導に参加して、生徒にノンフィクションやフィクションの文学について語った。
放課後の学童保育プログラム(SFO)のアシスタントやスタッフのプロジェクトへの参加も重視された。これらのアシスタントは、利用可能な時間をすべて読書教育に費やし、本の中の絵やシンボル、内容について、生徒とどのように議論したらよいか指導を受けた。そして、授業時間と学童保育プログラムの中で、このような議論が実際に交わされた。さらにプロジェクトでは、親や祖父母にも支援者として参加してもらうことの重要性が強調された。親は絵本の利用と読み聞かせの方法、また、読み手に内容への期待を持たせる方法や、絵について語る方法について指導を受けた。参加者がプロジェクトの活動について、常に最新の情報を得られるように、学校のホームページが積極的に利用された。
プロジェクトの結果、学校図書館の利用が大幅に増加し、図書館利用が学校の年間計画に盛り込まれるようになった。公共図書館側の利益は、学校の「中に入る」ことができたことであった。教師は今や公共図書館が提供するサービスに詳しくなり、図書館に相談することが以前よりもはるかに増えた。公共図書館でも、保育所の子供や幼い学齢期の子供向けの読み聞かせに、デジタル版の絵本を利用できるようになった。スンド公共図書館とスンド・コミューンの学校は、プロジェクト開始以前に、既にいくつかの分野で連携していた。たとえば公共図書館は、学校や保育所に分館を設け、地域共同電子目録システムを運営している。図書館目録には、スンドのすべての学校の蔵書が掲載され、分類されている。学校図書館プロジェクトに関する報告では、プロジェクト実施以前の連携と実施期間中の連携がどちらも、テラヴァグ校での読書指導の重要なリソースとして強調されている。
ムーレ・ロムスダール県のブド小中学校図書館は、兼用図書館である。学校図書館として機能すると同時に、フラナ公共図書館の分館でもあるのだ。学校には200人の生徒がいる。学校図書館司書は、学校図書館司書、公共図書館司書及びフラナ・コミューンの学校図書館コーディネーターとしての役割を担っている。最近、フラナは学校図書館への投資を徐々に増やしてきた。すべての学校が、現在、各学校図書館のコンテンツとサービス組織の枠組みをまとめた図書館計画に組み込まれている。フラナ・コミューンによる学校図書館関連の協力と協議は、おもにブド校で開発されたプログラムに基づいている。
ノルウェー学校図書館プログラムの下でのブド校の最初の開発プロジェクトは、6、7、8年生の教育プログラムへの図書館利用の統合であった。これらの教育プログラムで、生徒はあらゆる教科において、能力育成という目的に基づき、印刷版やデジタル版の参考資料を活用し、文献を評価し、調査課題を解決した。学校はプロジェクトの計画と実施には成功した。しかし、学校図書館司書や参加した教師らは、生徒が目標志向型の図書館利用を首尾よく行っていなかったことに気づき、この失敗を、これらの生徒に十分な学習戦略が欠けていたという事実と結び付けた。この経験から、学習戦略の開発と情報リテラシーの向上とをおもな目的とする、新たなプロジェクトの基盤が生み出された。
リソース校プロジェクトにおいて、学校側は図書館を学習の場としてさらに発展させるとともに、学校図書館司書と教師の連携を強化したいと考えた。さらに、より徹底した計画で、この連携を一層強力かつ目標志向型にできるものと期待した。目的は、プロジェクトの名称にもうたわれているように、「学びのための学校‐活かされる図書館(A Learning School - A Living Library)」であった。学校側は、生徒が積極的に図書館を利用できるようになるためには、学習戦略を習得しなければならないと考えている。プロジェクト実施期間中、1年生から10年生までを対象とした情報リテラシーに関するアイディアが集められ、読書と学習に関する戦略の例が出された。これらのアイディアと戦略が、各学年でさまざまな教科と結び付けられている。
学校と公共図書館の連携の確立は、プロジェクトへの投資の基礎を築くことに貢献した。学校図書館コーディネーターは、公共図書館と地域のすべての学校との架け橋となり、図書館計画で連携のレベルを決定する。この図書館計画には、あらゆる年齢及び学年の生徒にとって、学校図書館がリソースになると記されている。すべての生徒は学校図書館を通じて、新たな文献と、より多くの多様なソースへのアクセスを確実に得られるからである。さらに図書館は今後、創造的・予備的な学習プロセスを積極的に支援するために必要な設備を備え、それを基に、一人一人に対応したアダプテッド教育の創造にも貢献していく。図書館計画にはまた、学校図書館司書の目的として、管理及び運営、情報リテラシー及び教育学の分野における能力を身に着けなければならないと記載されている。
専門能力の開発を確保するために、地域の図書館ネットワークが設立された。公共図書館は学校図書館とともにこのネットワークに所属し、ネットワーク会議の準備と告示に共同で責任を負う。ネットワークは議論と知識共有のための重要な場である。フラナ・コミューンに関しては、公共図書館が「カルチャー・リュックサック」(ノルウェーの学校で専門家が芸術文化活動を行う国家プログラム)も一部担当しており、そのための資金が各コミュニティに直接支給され、利用されている。この資金は毎年、作家による5年生と8年生の全クラス訪問に充てられている。また図書館計画に即して連携活動の企画と評価が行われるが、計画とそれを進めるコーディネーターはともに、図書館間の連携を推進する力となり、また、児童と若者の学習を強化する手段となる。
トロムス県ソルヴィック小中学校には120人の生徒がおり、10学年に分かれている。同校はハーシュタ図書館と連携しており、ノルウェー学校図書館プログラムの別のプロジェクト校であるカネボゲン小学校の指導校にもなっている。ソルヴィック校の学校図書館プロジェクトは、「読書と学習への刺激としての学校図書館の組織的利用(Systematic Use of the School Library as Inspiration for Reading and Learning)」という名称である。プロジェクトへの参加を通じて学校は、構造化された学際的な活動を通じ、生徒の読書と学習を促進する取り組みを、早い段階から確実に行いたいと考えた。ここで重要な目的は、中学レベルの生徒、特に男子生徒の読書への興味を持続させ、すべての中学生の情報検索スキルを向上させることであった。
ハーシュタ・コミューンは、組織的な読書指導に全力で取り組んだ。2010年に市の読書指導計画が採択され、そのフォローアップとして、小学校のすべてのクラスで非常勤読書指導員が採用された。ソルヴィック校の場合、この指導員は全教員の20%を占めている。プロジェクト実施期間中に、この指導員が、2年生から4年生までの生徒を対象とした読書ワークショップの基礎を築いた。学校図書館はこの読書推進の取り組みにおいて、読書ワークショップの場としても、また、中学生が年齢相応の本を読む際に支援を受ける場としても、重要な役割を果たした。学校図書館はまた、中学生の男子生徒を対象としたプログラムでも中心的な役割を果たした。このプログラムは10月から4月まで続けられ、多くの場合、科学や社会に関連のあるテキストを、指導の下に繰り返し読むことが盛り込まれていた。テキストは、これらの男子生徒のクラスで翌週勉強するテーマから選ばれた。このプログラムの下で、授業で使用する資料を事前に読み終えていた参加者は、のちに授業でその資料が提示されたときに、さらに多くの内容を学習した。これらの生徒はまた、このテーマについての授業での討論に、より積極的に参加するようになった。この種のプログラムでは、生徒の能力がプログラム実施前後で評価される。
学校図書館プロジェクトは、この学校の別の優先分野(学習・学校開発評価(VSL)及び積極的な態度、支援的学習環境と学校の連携(PALS)など)にも非常に適していた。指導校であるソルヴィック校は、カネボゲン校と密接に協力し、職員への助言や経験談の交換などを行う定期的な会合を開催した。両校はまた、お互いにワークショップの企画と参加を通じて支援しあった。
公共図書館は、文献の寄贈によりプロジェクトを支援した。月に一度、移動図書館のバスがソルヴィック校を訪問し、プロジェクト開始後は図書の貸し出し数が大きく増加した。ソルヴィック校の学校図書館司書は公共図書館の蔵書に非常に詳しく、これを学校のリソースとして利用することができる。プロジェクトの課題の一つは、学校図書館による購入にふさわしい本を見つけることであった。この際、公共図書館の本が見本として役立てられた。ソルヴィック校の生徒はまた、児童・若者向けの新刊をおもに紹介する公共図書館のイベントにも参加し、その後、これらの本の中から何冊かを選んで同級生に紹介した。さらに、公共図書館と学校が同じ電子目録システムを使用しており、学校図書館のシステムに問題が生じた場合は公共図書館が支援している。特に、すべての教科における読書と蔵書構築などの経験談を紹介しあうことは、プロジェクト実施期間中、学校図書館司書と公共図書館との共同会議においてテーマとされた。
学校と公共図書館の連携は、ソルヴィック校における開発プロジェクトにも貢献した。プロジェクトに関する学校独自の評価では、生徒の知識の増加と、読書への欲求及び読書の喜びの増加につながったことが確認された。さらに、読書指導における親の協力の促進、レベルの高い職員の参加促進、学校の読書計画とプログラムの構成改善にも貢献した。
ヘドマルク県のモルクヴェド校は、生徒数300人の小学校である。同校はリングサケル図書館と連携している。ノルウェー学校図書館プログラムの開発プロジェクトの名称は「図書館から学習センターへ(From Library to Learning Centre)」で、図書館をまず低学年の読書指導のための常設機関として統合し、その後高学年も対象とし、上級の読書指導の重要な場とすることに取り組んだ。モルクヴェド校は読書指導プログラムを「早期識字プログラム(EYLP)」に従って実施している。学校図書館プロジェクトでは、生徒が個別の活動やプロジェクト、またはグループでの課題に取り組む際に、適切なガイダンスを利用できるようにすること、さらに、生徒が学校の活動に取り組む際、目標志向型の図書館利用ができるようにすることに重点が置かれた。プロジェクト実施期間中、小学5年生から7年生までが、おもに図書の時間を利用し、教師役の図書館司書の指導の下で読書を行った。多くの場合、極めて似たタイプの少人数の生徒で構成されたグループが活動単位とされた。さらに、教師役の図書館司書は、図書館に関する情報を、それぞれの生徒のレベルに合わせた独自の計画に従って指導した。この計画は、当時の生徒が取り組んでいた学習課題に可能な限り対応していた。
プロジェクト実施期間全体を通して、モルクヴェド校は、デンマーク、ドイツ、スロベニア及びルーマニアの学校も参加するコメニウスプロジェクトのコーディネーターを務めた。コメニウスプロジェクトの主要な目的の一つは「識字力の向上」で、連携校は学校図書館がこの目的にどう貢献できるかを研究した。またモルクヴェド校は、「二国間コメニウス‐地域プロジェクト」におけるリソース校としても利用された。このプロジェクトでは、リングサケル公共図書館が連携先機関であった。
カルチャー・リュックサックでは、学校は公共図書館や作家、画家、朗読者と協力して活動する。これは1週間から2週間続く年間プロジェクトで、文芸創作や物語の挿絵制作などのコースがある。リングサケルのモエルヴ中学校は、ノルウェー学校図書館プログラムの新規プロジェクト校で、モルクヴェド校に助言を求めてくることがある。モエルヴ校はまた、地域の公共図書館から毎週1時間ずつ支援を受けるという契約にも署名した。
リングサケル・コミューンが学校図書館の開発を優先してきたため、プロジェクト校はこれまで学校所有者から十分な支援を受けてきた。この地域は地理的にも人口的にも大きく、地域で運営を任されている学校組織として22の小中学校があるが、その大部分は、学校図書館に比較的限られたリソースしか割り当てていない。しかし、この地域では2010年に常勤学校図書館コーディネーターが設けられ、これまで以上に学校図書館を支援する基盤が築かれた。コーディネーター職には公共図書館の職員が任命された。リングサケルの主任図書館司書と学校長が協力し、図書館コーディネーターが果たすべき任務を、採用前に明確に定めた。
コーディネーターは「学校と公共図書館の連携のための連絡委員会」の運営を引き継ぎ、学校図書館司書のネットワークグループの支援に当たる。このような相談機関を通じて、学校図書館司書は、図書館関連スキルの開発のための支援を受ける。コーディネーターは学年度を通じて定期的に学校を訪問し、生徒と教師を対象にブックトークを行う。また、メディアコレクションの購入と更新に関して学校の相談にのり、図書目録や図書館の組織化、館内設計に関する質問に回答する。また、学校計画や連携フォーラムに図書館を組み込む学校図書館の活動を支援し、プロジェクト申請書の作成に関して助言を提供する。学校図書館コーディネーターは、講習及びその他の読書推進策も企画するが、これには公共図書館の児童図書館司書との協力も含まれる。リングサケルにおける図書館サービスの優先順位決定に関しては、図書館協力計画の策定が現在進められているが、公共図書館はこのプロセスにおいて、専門支援機関としての重要な役割を果たすであろう。
結論
ノルウェー学校図書館プログラムは、プロジェクト校と公共図書館の連携を促進するものである。いくつかの学校が共同プロジェクトを実施しており、その一部を本論文で紹介した。プログラムの背景にあるのは、学校図書館を読書教育促進と情報リテラシー向上のリソースとして活用するという考え方である。公共図書館との連携は、発展的な活動を達成するためのより強固な基盤をプロジェクト校にもたらすので重要である。公共図書館は、図書館関連の相談、図書及び電子リソースの点で貢献できる。また公共図書館は、学校によるイベントの企画や読書推進活動のよきパートナーでもある。特に、コーディネーター職の設置など、恒常的な組織化された連携に投資しているコミューンは、図書館発展の確固たる基礎を築いている。
さらに、学校と図書館の所有者は同じで、共通の社会的使命を持つため、当然のことながら両者は互いに連携のパートナーである。ノルウェーの当局は、この連携のための明確なガイドラインも提供してきた。これによりプロジェクト校は、連携に基づくプロジェクト開発の際に、確立された伝統を踏襲するのである。これは学校における持続的な変化の実現に向けたよき出発点である。学校図書館を教育手段として利用することは、図書館の学校への統合に左右される。学校経営を担当する官僚と教師の態度がここで決め手になるとともに、学校図書館の利用について具体的な計画が進められなければならない。プロジェクト実施期間が終了するとき、学校図書館が指導における明確な役割を担っていることが重要である。学校図書館が、外部の参加者をも含めた、より大きな正式な連携の一部となるとき、その脆弱性は弱まり、個人への依存も減少する。
ノルウェー学校図書館プログラムからプロジェクト資金の提供を受ける際の重要な基準の一つとして、プロジェクトに転用の価値があることがあげられる。他の学校がプロジェクトから学び、それを自校の発展的な取り組みへのインスピレーションの源として利用することが可能でなければならない。プロジェクト校は、その経験を地域社会で、また、地方や国、さらには国際社会のネットワークを通じて共有すると誓った。これには公共図書館との知識の共有も含まれる。プロジェクトが参加生徒の学習にどのような影響を与えたか、結論を出すのは時期尚早である。しかし、プロジェクト校からの報告と評価は、これらのプロジェクトが読書教育を支援し、公共図書館との連携が発展的な取り組みの強化に役立ったことを示唆している。
プレゼンテーション
原本の書誌情報
Ingvaldsen, Siri. "Joint efforts to improve reading education: cooperative projects between public libraries and schools in the Norwegian School Library Program". World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly. Meeting: 118. Friends or Foes. public and school libraries a force for change for creating smart communities. School Libraries and Resource Centers with Public Libraries. Helsinki, Finland, 2012-08-11/17. http://conference.ifla.org/past/ifla78/118-ingvaldsen-en.pdf, (accessed 2012-12-18).