大島町地域福祉計画
NO.2
第6章 老人保健福祉の推進
現況
現況
- 人口構成
- 高齢者のいる世帯の状況
- ねたきり・痴呆・虚弱高齢者の状況
- 住居の状況
- 高齢者の受診状況・疾病構造
- 就業構造等
目標年次の高齢者等の状況
目標年次の高齢者等の状況
- 人口推計
- 推計人数及び在宅人数
現況
1. 人口構成
(平成5年1月1日現在 住民基本台帳)
| - | 男 | 女 | 計 | 人口比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 4,974 | 5,098 | 10,072 | 100% | ||
| 40歳以上 | 2,755 | 3,033 | 5,788 | 57.5% | ||
| 65歳以上 | 873 | 1,231 | 2,104 | 20.9% | ||
| 65~69歳 | 326 | 373 | 699 | 6.9% | ||
| 70~74歳 | 218 | 324 | 542 | 5.4% | ||
| 75歳以上 | 329 | 534 | 863 | 8.5% | ||
2. 高齢者のいる世帯の状況
(平成2年国勢調査)
| 種類 | 世帯数 | 比率 | |
|---|---|---|---|
| 高齢者のいる世帯 | 1,451世帯 | 100% | |
| 内訳 | 単身高齢者世帯 | 490世帯 | 33.8 |
| 夫婦のみ高齢者世帯 | 480世帯 | 33.1 | |
| 高齢者を含む一般世帯 | 481世帯 | 33.1 | |
3. ねたきり・痴呆・虚弱高齢者の状況
(1) ねたきり・痴呆等の要介護高齢者の人数
ねたきり高齢者数 158人
痴呆高齢者数 116人のうち要介護 17人
(2) 要介護高齢者の実態
| 対象者数 | 197人 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 在宅 | 92人 |
| 特別養護老人ホーム | 99人 | |
| 老人保健施設 | 1人 | |
| 病院 | 5人 | |
(3) 虚弱高齢者数 412人
4. 住居の状況
(平成2年国勢調査)
| - | 全体 | 高齢者のいる世帯 |
|---|---|---|
| 種類 世帯数 |
3,986世帯 | 1,451世帯 |
| ア.持ち家 | 2,906世帯 | 1,319世帯 |
| イ.公営 | 233世帯 | 48世帯 |
| ウ.民営の借家 | 372世帯 | 68世帯 |
| エ.給与住宅 | 354世帯 | 4世帯 |
| オ.間借り | 31世帯 | 7世帯 |
| カ.その他 | 90世帯 | 5世帯 |
5. 高齢者の受診状況・疾病構造
受診状況(平成5年度 実績)
| 健康診査 | 1,359人 |
|---|---|
| 異常有 | 1,019人 |
| 異常無 | 340人 |
疾病構造
| 高血圧 | 51.7% |
|---|---|
| 貧血 | 4.7% |
| 肝臓病 | 14.9% |
| 糖尿病 | 8.0% |
| その他 | 20.7% |
6. 就業構造等
15歳以上就業者数 (平成2年国勢調査)
| 業種別内訳 | 男 | 女 | 労働人口 | 構成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 2,946 | 1,959 | 4,905 | 100% |
| 農林水産業 | 399 | 217 | 616 | 12.6% |
| 建設・製造業 | 586 | 140 | 726 | 14.8% |
| 卸売・小売業・飲食業 | 381 | 566 | 947 | 19.3% |
| 金融・保健・不動産業 | 51 | 45 | 96 | 1.9% |
| サービス業・その他 | 1,529 | 991 | 2,520 | 51.4% |
65歳以上就業者数 (平成2年国勢調査)
| 業種別内訳 | 男 | 女 | 労働人口 | 構成比率 |
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 311 | 225 | 536 | 100% |
| 農林水産業 | 106 | 66 | 172 | 32.1% |
| 建設・製造業 | 45 | 8 | 53 | 9.9% |
| 卸売・小売業・飲食業 | 57 | 64 | 121 | 22.6% |
| 金融・保健・不動産業 | 3 | 1 | 4 | 0.7% |
| サービス業・その他 | 100 | 86 | 186 | 34.7% |
目標年次の高齢者等の状況
1. 人口推計
(1) 目標年次
目標年次は、平成12年度とする。
(2) 目標年次の人口推計
国勢調査に基づき、昭和60年と平成2年のセンサス間コーホート変化率法による推計の結果を用いた。
目標年次における人口推計
(単位:人)
| - | 昭和60年度 (1985年) |
平成2年度 (1990年) |
平成12年度 (2000年) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
| 総人口 | 10,377 | 10,014 | 4,936 | 5,078 | 9,911 | 4,889 | 5,022 |
| 15歳未満 % |
2,070 | 1,700 | 830 | 870 | 1,244 | 706 | 538 |
| 19.9 | 17.0 | 16.8 | 17.1 | 12.5 | 14.4 | 10.7 | |
| 15歳以上 65歳未満% |
6,548 | 6,344 | 3,296 | 3,048 | 6,111 | 3,163 | 2,948 |
| 63.1 | 63.4 | 66.8 | 60.0 | 61.7 | 64.7 | 58.7 | |
| 65歳~69歳 | 568 | 617 | 258 | 359 | 703 | 318 | 385 |
| 70歳~74歳 | 475 | 520 | 220 | 300 | 700 | 312 | 388 |
| 75歳~79歳 | 357 | 385 | 152 | 233 | 505 | 181 | 324 |
| 80歳~85歳 | 216 | 253 | 115 | 138 | 346 | 115 | 231 |
| 85歳以上 | 143 | 185 | 58 | 127 | 302 | 94 | 208 |
| 65歳以上 % |
1,759 | 1,960 | 803 | 1,157 | 2,556 | 1,020 | 1,536 |
| 16.9 | 19.6 | 16.3 | 22.8 | 25.8 | 20.9 | 30.6 | |
| 40歳以上 % |
5,309 | 5,635 | 2,659 | 2,976 | 6,278 | 2,910 | 3,368 |
| 51.2 | 56.3 | 53.9 | 58.6 | 63.3 | 59.5 | 67.1 | |
2. 推計人数及び在宅人数
(1) ねたきり高齢者(ねたきり・比較的重い障害)
目標年次におけるねたきり高齢者の推計には、ねたきり等の高齢者及び比較的重い障害のある高齢者の出現率(平成2年度実施の東京都社会福祉基礎調査報告・高齢者の生活実態より)に、都における特別養護老人ホーム入所率(1.03%)を加算した率を用いた。
なお、在宅の人数は、特別養護老人ホーム入所者100名を除いた数とする。
ねたきり高齢者の年齢・性別推計人数
(単位:人)
| ねたきり | 比較的アモイ障害 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80歳以上 | 合計 | 65~69歳 | 70~79歳 | 75~79歳 | 80歳以上 | 合計 |
| 男 | 4.13 | 7.18 | 5.98 | 22.36 | 39.65 | 4.77 | 5.93 | 5.07 | 12.75 | 28.52 |
| 女 | 2.7 | 5.44 | 13.29 | 61.90 | 83.33 | 3.08 | 6.21 | 12.96 | 32.93 | 55.18 |
| 計 | 6.83 | 12.62 | 19.27 | 84.26 | 122.98 | 7.85 | 12.14 | 18.03 | 45.68 | 83.70 |
| - | 123人 | - | 84人 | |||||||
(2) 痴呆性高齢者
目標年次における痴呆性高齢者(要介護状態である者)の推計人数は、以下のとおりとする。
在宅痴呆性高齢者の推計
(単位:人)
| 年齢 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85歳以上 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 5.09 | 9.36 | 9.59 | 11.16 | 15.70 | 50.90 |
| 女 | 3.08 | 9.70 | 16.52 | 27.26 | 47.63 | 104.19 |
| 計 | 8.17 | 19.06 | 26.11 | 38.42 | 63.33 | 155.09 |
| - | 155人 | |||||
ここで求めた全体数と、「把握方法」における要介護状態である者の比率15%を掛け合わせ、目標年次における要介護の在宅痴呆性高齢者を推計した。
(3) ねたきり高齢者、痴呆高齢者、虚弱高齢者推計
(単位:人)
| 年 内容 |
平成5年 | 平成12年 | |
|---|---|---|---|
| 高齢者人口 | 2,104 | 2,556 | |
| 在宅寝たきり (要介護) |
ねたきり | 93 | 123 |
| 重い障害 | 65 | 84 | |
| 計(A) | 158 | 207 | |
| 在宅痴呆性高齢者 | 116 | 155 | |
| - | うち要介護者(15%)(B) | 17 | 23 |
| 特別養護老人ホーム入所者割合(1.03%)(C) | 22 | 27 | |
| 要介護高齢者(A+B+C)(D) | 197 | 257 | |
| 施設入所者等(E) | 105 | 100 | |
| 在宅要介護者(D+E) | 92 | 157 | |
| 虚弱高齢者 | 412 | 527 | |
サービスの目標量等
サービスの目標水準
- サービスの目標水準
- 健康診査の目標水準
サービスの目標量の推計
- 在宅福祉サービス
- 在宅保健サービス
- 施設サービス
サービスの目標量等
1. サービスの目標水準
(1) サービスの目標水準
目標年次における、サービスの目標水準は、以下のとおり設定した。
| 対象者 事業名 |
ねたきり 高齢者 |
痴呆性 高齢者 |
虚弱 高齢者 |
40歳 以上 |
|---|---|---|---|---|
| ホームヘルプ | 週3回 | 週3回 | 週2回 | - |
| デイサービス | 週2回 | 週2回 | 週2回 | - |
| ショートステイ | 7日/回 年8回 |
7日/回 年8回 |
7日/回 年2回 |
- |
| リハビリテーション | 週2日 6ヵ月 |
- | - | - |
| 訪問看護 | 週2回 | 週2回 | - | - |
| 訪問指導 | 年8回 | 年3回 | 年8回 | - |
| 歯科検診、保健指導 | 年1回 | 年1回 | 年1回 | - |
| 訪問栄養指導 | 年1回 | - | 年1回 | - |
| 健康教育 | 年30回 | 年30回 | 年30回 | 年30回 |
| 健康相談 | 年88回 | 年88回 | 年88回 | 年88回 |
(2) 健康診査の目標水準
※ 対象人口率については、東京都衛生局健康推進部(2衛高第434号)の通知を用いた。
目標年次における、健康診査の目標水準は、下記のとおり設定した。
平成12年度
| 対象者等 検診名 |
年齢別 人口 |
対象 人口率 |
受診 対象者 |
目標 受診率 |
目標 受診者数 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本健康診査 (30歳以上男・女) |
7,325人 | 36.1% | 2,644人 | 50.0% | 1,322人 | |
| 各種がん検診 | 胃がん (40歳以上男・女) |
6,278人 | 51.5% | 3,233人 | 30.0% | 970人 |
| 子宮がん (30歳以上・女) |
3,908人 | 67.2% | 2,626人 | 30.0% | 788人 | |
| 乳がん (30歳以上・女) |
3,908人 | 74.0% | 2,892人 | 30.0% | 868人 | |
| 肺ガン (30歳以上男・女) |
6,278人 | 57.2% | 3,591人 | 30.0% | 1,077人 | |
| 大腸がん (40歳以上男・女) |
6,278人 | 69.0% | 4,332人 | 30.0% | 1,300人 | |
2. サービスの目標量の推計
(1) 在宅福祉サービス
※ 必要割合については、原則として、大島町「家族の保健・福祉に関する調査報告書」(平成4年度)を用いた。
| 事項 事業名 |
目標量 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| ホームヘルプ事業 | 年間 15,881時間 |
1.要介護高齢者 157人×(3時間×3回×52週)=73,476時間 73,476時間×14.1%=10,360時間 2.虚弱高齢者 527人×(2時間×2回×52週)=109,616時間 109,616時間×5.0%=5,481時間 |
|
| デイサービス事業 | 基本事業 | 年間 5,762人 |
1.要介護高齢者 157人×(2回×52週)=16,328人 16,328人×8.1%=1,322人 2.虚弱高齢者 527人×(2回×52週)=54,808人 54,808人×8.1%=4,440人 |
| 入浴サービス | 年間 2,123人 |
要介護高齢者 157人×(2回×52週)=16,328人 16,328人×13.0%=2,123人 |
|
| 痴呆性デイホーム | 年間 2,392人 |
要介護高齢者 23人×(2回×52週)=2,392人 2,392人×100%=2,392人 |
|
| ショートステイ事業 | 年間 2,541人 |
1.要介護高齢者 157人×(7日×8回)=8,792日 8,792日×20.5%=1,803日 2.虚弱高齢者 527人×(7日×2回)=7,378人 7,378人×10.0%=738日 |
|
| 痴呆性 ショートステイ事業 |
年間 1,288日 |
要介護高齢者 23人×(7日×8回)=1,288人 1,288人×100%=1,288日 |
|
(2) 在宅保健サービス
※ 必要割合については、原則として、大島町「家族の保健・福祉に関する調査報告書」(平成4年度)を用いた。
| 事項 事業名 |
目標量 | 説明 |
|---|---|---|
| リハビリテーション | 年間 1,055日 |
要介護高齢者 157人×(2日×24週)=7,536回 7,536回×14.0%=1,055回 |
| 訪問看護 | 年間 1,943日 |
要介護高齢者 157人×(2日×52週) 16,328回×11.9%=1,943回 |
| 訪問指導 | 年間 385回 |
1.ねたきり高齢者 128人×8回=1,024回 1,024回×11.9%=122回 2.要介護痴呆高齢者 23人×3回=69回 69回×11.9%=9回 3.虚弱高齢者 527人×8回=4,224回 4,224回×6.0%=254回 |
(3) 施設サービス
| 事項 事業名 |
目標量 | 説明 |
|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム | ベット数 126床 |
12年度 高齢人口 2,556人×4.94%=126床 |
| 老人保健施設 | ベット数 26床 |
12年度 高齢人口 2,556人×1.0%=26床 |
| ケアハウス | ベット数 15床 |
12年度 高齢人口 2,556人×0.6%=15床 |
サービスの提供体制
サービス提供体制
- マンパワーの確保
- 施設の整備
- サービス利用を容易にするための方策
サービス提供体制
1. マンパワーの確保
(1) ホームヘルパー
1. 確保人員(平成12年度)
| 確保人員 | 算定方式 |
|---|---|
| 12人 | 6時間/日×20日×月×12月=1,440 時間 一人当たり 15,881時間・・・必要 15,881時間÷1,440時間=11.02≒12人 |
2. 確保対策
(イ) 養成研修の実施
特別養護老人ホームや高齢者在宅サービスセンターの協力を得てホームヘルパー養成研修を実施する。
(ロ) 登録ヘルパー制度
養成課程終了者をヘルパーとして登録する制度を新設する。
(ハ) ヘルパーの確保
資格ヘルパーは、町、社会福祉協議会、シルバー人材センター、特別養護老人ホーム併設高齢者在宅サービスセンター、もしくは介護支援センターで確保する。
現在4人の常勤ヘルパーで在宅福祉の一端を担っているが、サービス必要量を充足させるためには、確保数12人のうち常勤ヘルパー8人を確保する。併せて、常勤換算の4人分は登録ヘルパーで対応する。
3 質の向上
ホームヘルパーの質の向上については、現在行われている東京都の研修制度への積極的な参加を行うとともに、今後、介護福祉の研修等に参加させ、質の高い介護技術の導入を図りその水準を高めるものとする。
4 サービスの提供体制
多様なニーズに対応するため、パートタイムや委託等の形態をとりいれ、またチーム方式の導入により需要に即応したサービスの提供を図るものとする。
(2) 在宅介護支援センター職員の研修等
在宅介護支援センターは、要介護高齢者や要介護高齢者を抱える家族からいつでも相談を受け付けることは当然であるが、これにとどまらず、在宅介護相談協力員からの連絡を受けて動くことや、相談を受けた家庭を訪問するなど積極的に地域と接触し、地域に出ていく活動が必要である。相談に基づき、紹介・調整すべきサービスの範囲が、保健・医療・福祉に亘たるのでセンター職員の積極的な研修を実施し、センターとしての機能を充実させる。
(3) 保健医療の要員確保
1 保健婦の配置
訪問指導や訪問看護などの在宅保健・医療サービスの推進のため、保健婦を一人配置する。
2 看護婦の確保
(イ) 確保人員(平成12年度)
| 確保人員 | 算定方式 |
|---|---|
| 5人 | 2回/日×週5日×46週=460回 一人当たり 1943回 必要量 1943回÷460回=4.2≒5人 |
(ロ) 登録看護婦制度
看護婦の資格者を登録する制度を新設する。
(ハ) 看護婦の確保
看護婦は、高齢社会が進展していくなかで重要な役割を担うところから、今後大きな需要が見込まれているが、その養成機関が限られているため必要な人員を確保するには、相当の努力が必要である。このため勤務条件の改善や働きがいのある環境づくりに努めるとともに、奨学資金貸与制度を創設して人材の確保を図る。
また、登録看護婦の活用を図るためのパートタイムの導入などの勤務対応形態を検討する。
2. 施設の整備
(1) 高齢者在宅サービスセンター
1 デイサービス利用人員
| 利用人員 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 20人 (現状で可) |
12年度利用人員 5,762人 5,762×(1/(6日/週×50週))÷20人 |
現況 大島町高齢者 在宅サービスセンター 1日当たり 利用定員20人 |
2 入浴サービス(通所)利用人員
| 特浴利用人員 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 6人 (現状で可) |
12年度利用人員 2,123人 2,123×(1/(6日/週×50週))÷6人 大島町高齢者在宅サービスセンターで、 1800人利用残り323人については 入浴カーによる入浴で対応訪問 |
現況 大島町高齢者 在宅サービスセンター 1日当たり 特浴利用定員6人 |
3 ショートステイのベット数
| 必要ベット数 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 7床 (現状で可) |
12年度利用人員 2,541日 2,541×(1/(7日/週×52週))=6.9床 |
現況 大島町高齢者 在宅サービスセンター 特別養護大島 老人ホーム 1日当たり 利用ベット数12床 |
4 痴呆デイホーム利用人員
| 利用人員 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 10人 (現状で可) |
12年度利用人員 2,392人 2,392×(1/(6日/週×50週))÷10人 |
現況 大島町高齢者 在宅サービスセンター 1日当たり 利用定員10人 |
5 痴呆ショートステイのベット数
| 必要ベット数 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 4床 | 12年度利用日数 1,288日 1,288×(1/(7日/週×52週))=3.5床 ≒4床 現在3床であるが、残り1床については 増床を図る。 |
現況 大島町高齢者 在宅サービスセンター 特別養護大島 老人ホーム 1日当たり 利用ベット数3床 |
(2) 特別養護老人ホーム
| 必要ベット数 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 12床 (現状での97床で対応) |
12年度必要ベット数126床 2,556人×4.94% (平成5年4月1日の特別養護老人ホーム入所者及び 待機者)126床中97床老人ホームに措置、残余29床は、 在宅保健・福祉サービスの充実や 管外ホーム利用により対処 |
現況 特別養護大島 老人ホーム 確保枠 90床 8年度 97床 |
(3) 老人保健施設の整備
| 必要ベット数 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 26床 | 12年度必要ベット数26床 2,556人×0.1%=26床 |
現況 未整備 |
(4) ケアハウスの整備
| 必要ベット数 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 15床 | 12年度必要ベット数15床 2,556人×0.6%=15床 |
現況 未整備 |
(5) その他
| 施設名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 福祉センター 保健センター |
福祉センター、保健センターの 併合施設を1ヶ所整備する。 |
現況 未整備 |
| 看護ステーション | 1ヶ所整備する。 | 現況 未整備 |
| 憩いの家 | 2ヶ所整備する。 | 現況 未整備 |
| 地域コミュニティ施設 | 1ヶ所整備する。 | 現況 未整備 |
| コミュニティセンター | 1ヶ所整備する。 | 現況 未整備 |
3. サービスを容易にするための方策
(1) 地域トータルケアサービスの推進
介護支援センターが中心となり、在宅のねたきりの高齢者等の介護者に対し在宅介護に関する総合的な相談に応じ、また各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係機関と連絡調整を図る。
地域トータルケアーサービス システム図
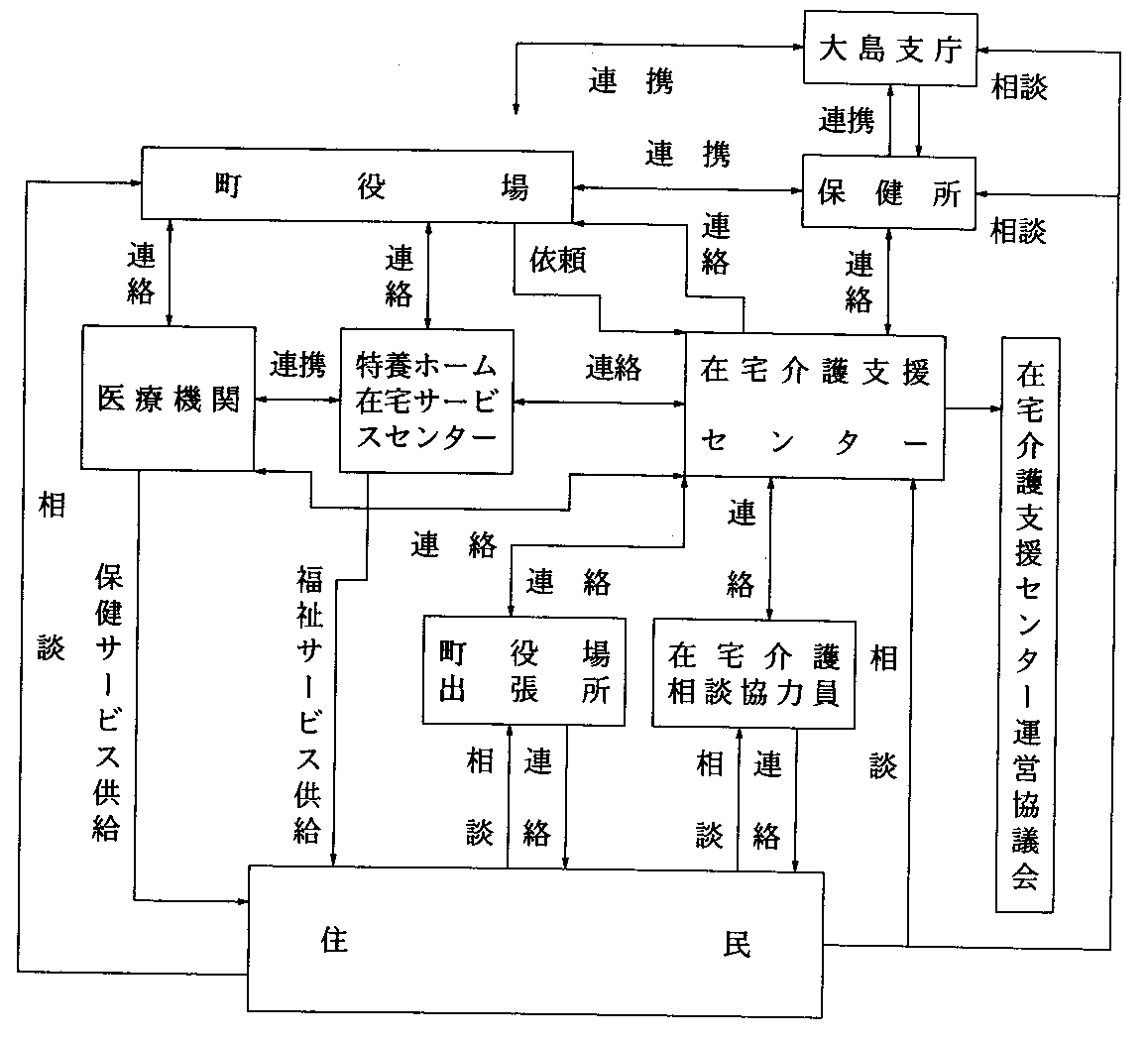
(2) 保健・福祉サービスの普及啓発
住民が真に適切なサービスを受けるためには、保健・福祉サービスの情報が正しく伝えられることが不可欠である。このため、これまでの広報誌に加え、分かりやすく紹介したパンフレットの発行やビデオテープにより情報提供等住民に対してきめ細かな情報提供を行う。
(3) 福祉機器等の情報提供
介護支援センターを福祉機器の情報拠点施設とし、展示品の充実拡大を図るとともに、東京都総合社会福祉センター(東京都福祉機器総合センター)と連携し、きめ細かな情報を町民に提供するシステムをつくっていく。
(4) 手続きの簡素化
申請に来た時がサービスを受けたい時であるという基本的認識に立ち、手続きの簡素化を推進する。このため、介護支援センターや出張所による手続き代行業務の活用や利用券方式の採用等について検討する。
保健・福祉の環境整備
保健・福祉の環境整備
- 高齢者サービス調整チーム
- 記録の共通利用
- 関係機関との連携
保健・福祉の環境整備
1. 高齢者サービス調整チーム
町民のもつ複雑かつ多様なニーズに応じた適切なサービスを提供するためには、高齢者のみならず福祉・保健医療の各分野におけるサービスの充実とともにそれらがシステム化され、総合的かつ効果的に提供される必要がある。現在設置してある高齢者サービス調整チームが各種協議会と協力し合って情報提供、相談体制の整備をする。
2. 記録の共通利用
保健・福祉及び医療の個人の情報をデータベース化し、それぞれの事業推進の必要に応じ、必要な情報を活用し、適切な処遇方法を決定する保健福祉情報提供システムの確立は、サービスの総合化、一体化を図るうえで大きな意義を有している。今後健康カードの整備とともに情報の一元化を検討していく。
3. 関係機関との連携
各種のサービスを町民に対し総合的、効果的に提供するための福祉のネットワークが必要となっている。各民間団体と行政とが連携を深め、地域福祉基盤の確立を図る。
ねたきりや痴呆性高齢者の問題の正しい理解を深めるために、保健機関、福祉機関、医療機関が連携し、福祉講座や講演会を計画的且つ継続的に行う。また、高齢者在宅サービスセンターによる介護教室等を充実し、在宅のねたきりや痴呆性高齢者に対して三者が連携し、サービスのネットワークの確立を図る。
高齢者の生きがい対策の推進
高齢者生きがい対策
- 老人クラブ活動の推進
- シルバー大学の開設
- 高齢者の就業促進
- シルバースポーツ・レクリェーションの推進
高齢者の生きがい対策の推進
高齢社会を迎えた大島町の高齢者が、豊かで楽しい自立した生活を送ることが出来、地域でのあらゆる分野の活動に参加出来るよう環境を整備する。
1. 老人クラブ活動の推進
老人クラブの現況
(平成5年12月1日)
| 地区 | クラブ数 | 会員数 |
|---|---|---|
| 元町 | 6 | 508 |
| 北の山 | 3 | 234 |
| 岡田 | 3 | 240 |
| 泉津 | 2 | 123 |
| 野増 | 2 | 151 |
| 間伏 | 1 | 62 |
| 差木地 | 4 | 362 |
| クダッチ | 2 | 111 |
| 波浮港 | 2 | 198 |
| 合計 | 25 | 1,989 |
(1) 時代に即応した老人クラブにするために、一般町民と接する行事や、機会を努めて創る。
(2) 女性のクラブ員が多い中で、女性のリーダーがかならずしも充分とはいえない状況にある。クラブ活動の活性化を図るうえから女性リーダーの育成に努める。
(3) クラブ員のもっている技術、能力を発揮し、シルバー大学の講師やシルバー人材センターの会員と協働して地域社会のために貢献するよう支援する。
2. シルバー大学の開設
高齢者の生きがい事業としてシルバー大学を開設する。
書道、民謡、墨絵、野草園芸、俳句等、ニーズに合った講座を開設し、福祉センターを拠点に各地区の施設を利用して活動する。
3. 高齢者の就業促進
(1) 就業の拡充
高齢者の就労ニーズの多様化と就労意欲の高揚に応えていくため、シルバー人材センターの就業の拡充について、町として支援する。
(2) 人材育成のための研修の実施
雇用側のニーズに応える人材育成を図るための研修を町として支援する。
4. シルバースポーツ・レクリェーションの推進
ゲートボール大会や健康づくりレクリェーション大会を推進するとともに、高齢者のスポーツやレクリェーション活動のニーズに対応するため、レクリェーションリーダーの育成を図る。
資料
1. 社会福祉の概況
2. 要介護高齢者の出現率
3. 大島町地域福祉計画策定委員会検討経過
4. 大島町地域福祉計画策定委員会要綱
5. 大島町地域福祉計画策定委員会組織
6. 大島町地域福祉計画策定委員会委員名簿
7. 社会福祉用語解説
1. 社会福祉の概況
(1)大島町の人口推移(全体) *各年1月1日現在 住民基本台帳*(単位:人%)
| 区分 年次 |
総数 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 | 75歳以上 | 従属 人口指数 |
年少 人口指数 |
老年 人口指数 |
老年化 指数 |
世帯数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 構成 割合 |
実数 | 構成 割合 |
実数 | 構成 割合 |
実数 | 構成 割合 |
実数 | 構成 割合 |
||||||
| 昭和45年 (1970) |
11,752 | 100 | 2,844 | 24.20 | 7,822 | 66.56 | 1,086 | 9.24 | 334 | 2.84 30.76 |
50.24 | 36.36 | 13.88 | 38.19 | 3,801 |
| 昭和46年 (1971) |
11,535 | 100 | 2,744 | 23.78 | 7,665 | 66.46 | 1,126 | 9.76 | 343 | 2.97 30.46 |
50.49 | 35.80 | 14.69 | 41.03 | 3,805 |
| 昭和47年 (1972) |
11,496 | 100 | 2,650 | 23.05 | 7,638 | 66.83 | 1,163 | 10.12 | 362 | 3.15 31.13 |
49.63 | 34.49 | 15.14 | 43.89 | 3,883 |
| 昭和48年 (1973) |
11,614 | 100 | 2,643 | 22.75 | 7,753 | 66.76 | 1,218 | 10.49 | 390 | 3.36 32.02 |
49.80 | 34.09 | 15.71 | 46.08 | 4,044 |
| 昭和49年 (1974) |
11,622 | 100 | 2,623 | 22.57 | 7,758 | 66.75 | 1,241 | 10.68 | 395 | 3.40 31.83 |
49.81 | 33.81 | 16.00 | 47.31 | 4,102 |
| 昭和50年 (1975) |
11,685 | 100 | 2,618 | 22.40 | 7,756 | 66.38 | 1,311 | 11.22 | 416 | 3.56 31.73 |
50.66 | 33.75 | 16.90 | 50.08 | 4,171 |
| 昭和51年 (1976) |
11,610 | 100 | 2,609 | 22.47 | 7,764 | 65.81 | 1,361 | 11.72 | 439 | 3.78 32.26 |
51.93 | 34.15 | 17.81 | 52.17 | 4,205 |
| 昭和52年 (1977) |
11,526 | 100 | 2,554 | 22.16 | 7,570 | 65.68 | 1,402 | 12.16 | 494 | 4.29 35.24 |
52.26 | 33.74 | 18.52 | 54.89 | 4,231 |
| 昭和53年 (1978) |
11,512 | 100 | 2,536 | 22.03 | 7,521 | 65.33 | 1,455 | 12.64 | 525 | 4.56 36.08 |
53.06 | 33.72 | 19.35 | 57.37 | 4,298 |
| 昭和54年 (1979) |
11,404 | 100 | 2,480 | 21.74 | 7,465 | 65.47 | 1,459 | 12.79 | 486 | 4.26 33.31 |
52.77 | 33.22 | 19.54 | 58.83 | 4,306 |
| 昭和55年 (1980) |
11,326 | 100 | 2,440 | 21.54 | 7,337 | 64.78 | 1,549 | 13.68 | 552 | 4.87 35.64 |
54.37 | 33.26 | 21.11 | 63.48 | 4,388 |
| 昭和56年 (1981) |
11,163 | 100 | 2,387 | 21.38 | 7,203 | 64.53 | 1,573 | 14.09 | 598 | 5.36 38.02 |
54.48 | 33.14 | 21.84 | 65.90 | 4,365 |
| 昭和57年 (1982) |
11,057 | 100 | 2,393 | 21.64 | 7,047 | 63.74 | 1,617 | 14.62 | 622 | 5.63 38.47 |
56.90 | 33.96 | 22.95 | 67.57 | 4,384 |
| 昭和58年 (1983) |
11,006 | 100 | 2,313 | 21.02 | 7,039 | 63.95 | 1,654 | 15.03 | 639 | 5.81 38.63 |
56.36 | 32.61 | 23.50 | 71.15 | 4,385 |
| 昭和59年 (1984) |
10,926 | 100 | 2,233 | 20.44 | 6,996 | 64.05 | 1,695 | 15.51 | 664 | 6.08 39.17 |
56.15 | 31.92 | 24.22 | 75.91 | 4,385 |
| 昭和60年 (1985) |
10,770 | 100 | 2,148 | 19.94 | 6,907 | 64,14 | 1,715 | 15.92 | 683 | 6.34 39.83 |
55.93 | 31.10 | 24.83 | 79.84 | 4,407 |
| 昭和61年 (1986) |
10,700 | 100 | 2,076 | 19.40 | 6,839 | 63.92 | 1,785 | 16.68 | 726 | 6.79 40.67 |
56.46 | 30.36 | 26.10 | 85.98 | 4,391 |
| 昭和62年 (1987) |
10,617 | 100 | 2,010 | 18.93 | 6,786 | 63.92 | 1,821 | 17.15 | 748 | 7.05 41.08 |
56.45 | 29.62 | 26.83 | 87.72 | 4,417 |
| 昭和63年 (1988) |
10,462 | 100 | 1,909 | 18.25 | 6,709 | 64.12 | 1,844 | 17.63 | 786 | 7.51 42.62 |
55.94 | 28.45 | 27.49 | 96.60 | 4,449 |
| 昭和64年 (1989) |
10,355 | 100 | 1,825 | 17.62 | 6,628 | 64.01 | 1,902 | 18.37 | 821 | 7.93 43.17 |
56.23 | 27.53 | 28.70 | 104.22 | 4,438 |
| 平成2年 (1990) |
10,392 | 100 | 1,779 | 17.12 | 6,655 | 64.04 | 1,958 | 18.84 | 846 | 8.17 43.21 |
56.15 | 26.73 | 29.83 | 110.06 | 4,561 |
| 平成3年 (1991) |
10,281 | 100 | 1,680 | 16.34 | 6,582 | 64.02 | 2,019 | 19.64 | 851 | 8.28 42.15 |
56.20 | 25.52 | 30.67 | 120.18 | 4,560 |
| 平成4年 (1992) |
10,165 | 100 | 1,641 | 16.14 | 6,455 | 63.51 | 2,069 | 20.35 | 863 | 8.49 41.71 |
57.47 | 25.42 | 32.05 | 126.08 | 4,568 |
| 平成5年 (1993) |
10,072 | 100 | 1,595 | 15.84 | 6,373 | 63.27 | 2,104 | 20.89 | 863 | 8.57 41.02 |
58.04 | 25.03 | 33.01 | 131.91 | 4,571 |
資料:「住民基本台帳人口」
(注)
- 従属人口指数={年少人口(0歳~14歳)+老年人口(65歳以上)}÷生産年齢人口(15歳~64歳)×100
- 年少人口指数=年少人口÷生産年齢人口×100
- 老年人口指数=老年人口÷生産年齢人口×100
- 老年化指数=老年人口÷年少人口×100
- 年少人口:0歳~14歳 生産年齢人口:15歳~64歳 老年人口:65歳以上 75以上:65歳以上に含まれる。
75歳以上の構成割合
- 上段:全体に対する割合
- 下段:65歳以上に対する割合
1 ショートステイ
| 年度 | 保護延実人員 | 保護延日数 | ベット数 |
|---|---|---|---|
| 2 | 71人 | 640日 | 3床 |
| 3 | 102人 | 804日 | 3床 |
| 4 | 134人 | 1,818日 | 3床 |
2 痴呆ショートステイ
| 年度 | 保護延実人員 | 保護延日数 | ベット数 |
|---|---|---|---|
| 3 | 38人 | 487日 | 2床 |
| 4 | 62人 | 834日 | 2床 |
3 ミドルステイ
| 年度 | 保護延実人員 | 保護延日数 |
|---|---|---|
| 2 | 23 | 482 |
| 3 | 55 | 744 |
| 4 | ショートステイに含まれる | |
4 入浴サービス (単位:人)
| 年度 | 保護延実人員 |
|---|---|
| 2 | 71 |
| 3 | 102 |
| 4 | 134 |
| 年度 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老人福祉手当 受給者数 |
49 | 60 | 70 | 62 | 61 | 53 | 38 |
(4) 特別障害者手当等支給状況(東京都大島支庁事業概要) (単位:人)
| 年度 内容 |
62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別障害者 | 特別障害者手当 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 障害児福祉手当 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 福祉手当(経過処置分) | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | |
| 合計 | 17 | 19 | 14 | 13 | 12 | 19 | 19 | |
(東京都大島支庁事業概要) (単位:人)
| 年度 内容 |
62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 心身障害者福祉手当受給者 | 90 | 102 | 102 | 105 | 95 | 99 | 101 | |
| 心身障害者医療受給者 | 107 | 120 | 119 | 118 | 111 | 119 | 127 | |
| 重度心身障害者 福祉手当受給者 |
7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
| 心身障害者 扶養手当 |
受給者 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 |
| 障害福祉年金 | 受給者 | 355 | 145 | 210 | 199 | 216 | 228 | 178 |
| 障害基礎年金 | 受給者 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 |
| 障害年金 | 受給者 | 45 | 43 | 42 | 42 | 36 | 36 | 34 |
(東京都大島支庁事業概要) (単位:人) ( )内児童
| 年度 内容 |
62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者 | 視覚障害 | 44 | 51 | 40 | 39 | 34 | 35 | 38 |
| 聴覚障害 | 39 | 45 | 45 | 45 | 35 | 37 | 37 | |
| 音声・言語障害 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
| 肢体不自由 | 202 | 226 | 172 | 172 | 167 | 181 | 180 | |
| 内部障害 | 41 | 47 | 40 | 41 | 36 | 40 | 47 | |
| 小計 | 334 | 378 | 306 | 304 | 279 | 298 | 308 | |
| 愛の手帳 | 1度(最重度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2度 | 15(1) | 16(1) | 17(1) | 16(1) | 15 | 16(1) | 16 | |
| 3度 | 24(4) | 25(5) | 26(4) | 28(5) | 26(4) | 28(2) | 27 | |
| 4度 | 9 | 10 | 11(1) | 11 | 12 | 13(1) | 11 | |
| 小計 | 51(5) | 54(6) | 57(6) | 58(6) | 54(4) | 57(4) | 54 | |
| 合計 | 385 | 432 | 363 | 362 | 333 | 355 | 362 | |
(7) ひとり親家庭医療証受給者数 (12月1日現在)
| 年度 内容 |
2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 医療証受給者 世帯数 | 45 | 51 | 57 | 62 |
| 医療証受給者 人数 | 123 | 137 | 151 | 170 |
(8) 機能回復訓練 (単位:人)
| 年度 内容 |
63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受診者人数 | 169 | 193 | 210 | 351 | 247 | 219 |
(9) 訪問指導 (単位:人)
| 年度 内容 |
63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 80 | 91 | 87 | 116 | 108 | 68 |
| 年度 | 家庭奉仕員数 | 派遣対象世帯数 | 派遣延回数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 被保護世帯 | その他の世帯 | 合計 | 被保護世帯 | その他の世帯 | ||||||
| 老人 世帯 |
その他 世帯 |
老人 世帯 |
その他 世帯 |
老人 世帯 |
その他 世帯 |
老人 世帯 |
その他 世帯 |
||||
| 昭和 45 |
人 2 |
11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 728 | 453 | 52 | 169 | 54 |
| 50 | 4 | 17 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1,834 | 936 | 3 | 841 | 54 |
| 55 | 4 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2,009 | 1,170 | 34 | 805 | 0 |
| 60 | 4 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2,233 | 552 | 56 | 1,383 | 242 |
| 61 | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1,771 | 160 | 32 | 1,579 | 0 |
| 62 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 2,237 | 444 | 60 | 1,733 | 0 |
| 63 | 4 | 24 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2,547 | 502 | 59 | 1,916 | 70 |
| 64 | 4 | 22 | 4 | 1 | 16 | 1 | 2,411 | 411 | 47 | 1,884 | 69 |
| 平成 2 |
4 | 20 | 4 | 0 | 13 | 3 | 2,385 | 394 | 2 | 1,768 | 221 |
| 3 | 4 | 21 | 4 | 0 | 14 | 3 | 2,155 | 545 | 0 | 1,392 | 218 |
| 4 | 4 | 23 | 3 | 0 | 15 | 5 | 2,196 | 543 | 0 | 1,368 | 286 |
| 5 | 4 | 18 | 3 | 0 | 11 | 4 | 2,445 | 398 | 0 | 1,464 | 383 |
*各年1月1日現在*
昭和44年8月1日 2名配置
昭和49年10月1日 2名増員
2. 要援護高齢者の出現率
◇ ねたきり高齢者
ねたきり高齢者の出現率は、東京都社会福祉基礎調査報告書(平成2年度)「高齢者の生活実態」を用いた。
ねたきり高齢者及び比較的重い障害高齢者の性別・年齢別出現率(%)
| 年度 内容 |
要介護者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ねたきり | 比較的重い障害 | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 65歳~69歳 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 |
| 70歳~74歳 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| 75歳~79歳 | 3.3 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 3.5 |
| 80歳以上 | 10.7 | 14.1 | 12.7 | 6.1 | 7.5 | 6.9 |
| 出現率(総数) | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.7 |
◇痴呆性高齢者
痴呆性高齢者の出現率は、地方老人保健福祉計画研究班痴呆性老人調査・ニーズ部会(平成3年度)による痴呆性老人の出現率を用いた。
痴呆性高齢者の性別・年齢別出現率(%)
| 年度 内容 |
在宅の痴呆性高齢者 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 65歳~69歳 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
| 70歳~74歳 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 75歳~79歳 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
| 80歳~54歳 | 9.7 | 11.8 | 11.0 |
| 85歳以上 | 16.7 | 22.9 | 20.9 |
| 出現率(総数) | 4.4 | 5.1 | 4.8 |
◇虚弱高齢者
虚弱高齢者の出現率は、東京都社会福祉基礎調査報告書(平成2年度)「高齢者の生活実態」
を用いた。
虚弱高齢者の性別・年齢別出現率(%)
| 年度 内容 |
在宅の虚弱高齢者 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | |
| 65歳~69歳 | 7.9 | 8.7 | 8.3 |
| 70歳~74歳 | 15.8 | 16.5 | 16.2 |
| 75歳~79歳 | 22.5 | 25.1 | 23.9 |
| 80歳~54歳 | 34.6 | 36.7 | 35.9 |
| 出現率(総数) | 17.0 | 8.9 | 18.0 |
3.検討経過
1 会議開催状況
平成4年
- 2月27日 策定委員会(第1回)
平成5年
- 2月12日 策定委員会(第2回)
- 2月12日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会、障害者福祉検討部会、高齢者福祉検討部会
- 2月19日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
- 2月22日 障害者福祉検討部会
- 2月25日 高齢者福祉検討部会
- 3月02日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
- 3月05日 障害者福祉検討部会
- 3月08日 高齢者福祉検討部会
- 3月22日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
- 3月24日 障害者福祉検討部会
- 3月24日 高齢者福祉検討部会
- 11月10日 障害者福祉検討部会
平成6年
- 2月09日 障害者福祉検討部会
- 2月10日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
- 2月14日 高齢者福祉検討部会
- 2月18日 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
平成6年
- 2月25日 策定委員会(第3回)
開催回数 策定委員会 3回
児童福祉・ひとり親福祉検討部会 6回
障害者福祉検討部会 6回
高齢者福祉検討部会 5回
2 検討経過
策定委員会(全体会議)
平成4年2月27日
- 会長選出
- 福祉計画を作成するうえでの内容説明
平成5年2月12日
- アンケートの集計状況について
- 今後の日程について検討
- 各部会の構成について検討
- 各部会長の選出
平成6年2月25日
- 報告書について検討・作成
児童福祉・ひとり親福祉検討部会
平成5年2月12日
- 部会長の選出
- 児童福祉・ひとり親福祉の現状説明
- 部会の方向性の検討
平成5年2月19日
- 部会長の代理選出
- 保育園、児童遊園等について意見交換
- ひとり親の現状について意見交換
平成5年3月2日
- 児童福祉のハード面について検討
- 特例保育について検討
平成5年3月22日
- 相談窓口について検討
- 部会案のまとめについて検討
平成6年2月10日
- 部会最終案のまとめ
平成6年2月18日
- 部会最終案のまとめ
障害者福祉検討部会
平成5年2月12日
- 部会長の選出
- 障害者福祉の現状について意見交換
- 部会の今後の進め方について検討
平成5年2月22日
- 部会長の代理選出
- 資料を基に現状の課題検討
平成5年3月5日
- 身体障害者相談員等の参考意見聴取及び意見交換
平成5年3月24日
- 部会報告の骨子整理、重点まとめ
平成5年11月10日
- 部会報告書の作成
平成6年2月9日
- 部会最終案のまとめ
高齢者福祉検討部会
平成5年2月12日
- 部会長の選出
- 高齢者福祉の現状について意見交換
- 部会の方向性の検討
平成5年2月25日
- 部会長の代理選出
- 施設福祉について検討
- 在宅福祉について検討
- 保健サービスについて検討
平成5年3月8日
- 施設整備の検討
- 在宅福祉対策の検討
- 福祉と保健の連携の検討
平成5年3月8日
- 部会のまとめ
平成6年2月14日
- 部会最終案のまとめ
1 調査の方法
第1次調査
配付・回収とも郵送法
第2次調査
配付は郵送法、回収は、民生委員による訪問回収
2 調査の対象者
第1次調査
世帯主全員
第2次調査
第1次調査において回収された有効調査票の抽出された「病気や障害のため世話が必要な町民」と「病気や障害のため見守りが必要な町民」
3 回収状況
第1次調査
対象者数 4,247票
回収数 2,061票
有効回収率 48.5%
第2次調査
対象者数 208票
回収数 185票
有効回収率 88.9%
4 調査の期間
第1次調査
平成4年3月
第2次調査
平成4年6月
5 調査の主体
東京都大島町
東京都大島町社会福祉協議会
4. 大島町地域福祉計画策定委員会設置要綱
(1) 目的
著しい高齢排の進展と、内地の福祉資源の活用が難しい地理的条件を踏まえ、高齢者、障害者、児童、ひとり親家庭等が地域生活をおくるうえで、必要とする福祉サービスに視点を置きながら、福祉を始めとする保健等関連施策を総合化、体系化し、地域の特性を生かした地域福祉を計画的に推進する。
(2) 設置
地域福祉に関する計画の策定にあたり、必要とする事項を調査検討するため「大島町地域福祉計画策定委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
(3) 所掌事項
委員会は、大島町における、在宅福祉を基調とした総合的な保健福祉サービスを展開するための各種施策のあり方について、調査検討し、町長に提言する。
(4) 組織(構成者)
委員会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
- 学歴経験のある者
- 関係団体の代表者
- 大島社会福祉協議会の代表
- 東京都大島支庁福祉関係職員(保健所も含む)
- 大島町福祉関係職員(保健医療も含む)
(5) 会長
委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(6) 会議
- 委員会は、会長が招集する。
- 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
- 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
- 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。
- 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会の議決があったときは、会議を非公開とすることができる。
(7) 専門部会
- 検討事項を専門的に調査検討するために、委員会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
- 部会は、会長の指名する委員会及び学歴経験者並びに職員を持って組織する。
- 部会に部会長を置き、部会長は、部会員の互選による。
- 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、調査検討経過及び結果を委員会に報告する。
- 部会長に事故あるときは、あらかじめ部会長の指名する部会委員が、その職務を代理する。
- 部会長は必要があると認めるときは、会議に部会委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は、説明を求めることができる。
(8) 庶務
- 委員会の庶務は大島町役場福祉課において処理する。
- 部会の庶務は部会長の指名する部会委員が担当する。
(9) 構成者の報償
大島支庁、島しょ保健所、社会福祉協議会、町職員等以外の構成者に対する報償は、別に定めるところにより予算の範囲内で支給する。
(10) 補則
この要綱に定めるもののほかに、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
付則 この要綱は平成4年2月1日から施行する。
5.大島町地域福祉計画策定委員会組織
(1) 組 織
策定委員会
- 高齢福祉検討部会 11名
- 障害者福祉検討部会 8名
- 児童福祉・ひとり親福祉検討部会 9名
(2) 策定委員会会長、副会長
会長 前田又吉(平成5年5月7日まで)
会長代理 高梨悦三
(3) 各部会長、部会長代理
- 高齢者福祉検討部会
- 部会長 高梨悦三
- 部会長代理 吉田隆弘
- 障害者福祉検討部会
- 部会長 川島理史
- 部会長代理 桜井芳與
- 児童福祉・ひとり親福祉検討部会
- 部会長 宇山正泰(平成5年5月7日まで)
- 部会長代理 藤井善弥
6. 大島町地域福祉計画策定委員会委員名簿 平成6年1月1日現在
| 番号 | 氏名 | 役職名 |
|---|---|---|
| 1 | 前田 又吉 | 大島町議会議員、民生委員会委員長 5.5.7まで |
| 2 | 佐藤 新吉 | 大島町議会議員、民生委員会委員長 5.5.7から |
| 3 | 白木 義三 | 大島町立第三中学校長(校長会長) 4.3.31まで |
| 4 | 森川 太喜治 | 大島町立北の山小学校長(校長会長) 5.3.31まで |
| 5 | 柳瀬 治男 | 大島町立第一中学校長(校長会長) 5.4.1から |
| 6 | 藤井 善弥 | 大島社会福祉協議会会長 |
| 7 | 原 タツ | 大島老人ホーム施設長 |
| 8 | 川村 千枝 | 大島町民生委員代表総務 |
| 9 | 白井 申子 | 大島町民生委員 |
| 10 | 坂上 豊吉 | 大島町民生委員 |
| 11 | 西川 松得 | 大島町老人クラブ連合会会長 5.9.17まで |
| 12 | 高橋 茂之助 | 大島町老人クラブ連合会会長 5.9.17から |
| 13 | 桜井 岩夫 | 大島町PTA連合会会長 4.6.4まで |
| 14 | 宇山 正泰 | 大島町PTA連合会会長 5.5.27まで |
| 15 | 柳瀬 清一 | 大島町PTA連合会会長 5.5.28から |
| 16 | 桜井 芳與 | 大島町手をつなぐ親の会代表 |
| 17 | 川島 理史 | ボランティア代表及び社協役員 |
| 18 | 吉田 隆弘 | シルバー人材センター事務局長 |
| 19 | 藤井 三枝 | 大島町婦人会会長 |
| 20 | 高梨 悦三 | 学識経験者 |
| 21 | 三辻 房子 | 大島町婦人会副会長及び大島町民生委員 |
| 22 | 西川 静子 | 大島町婦人会副会長 |
| 23 | 阿部 葉子 | 元東京都大島支庁福祉課係長 |
| 24 | 実川 吉樹 | 大島社会福祉協議会事務局長 |
| 25 | 濱野 浩司 | 東京都大島支庁福祉課長 4.11.30まで |
| 26 | 島田 久平 | 東京都大島支庁福祉課長 5.2.5から |
| 27 | 長田 隆一 | 東京都大島支庁福祉課厚生係長 4.3.31まで |
| 28 | 下司 克昭 | 東京都大島支庁福祉課厚生係長 5.2.5から |
| 29 | 坂下 賢司 | 東京都大島支庁福祉課係長 指導主事福祉司 |
| 30 | 大塚 孝子 | 東京都島しょ保健所保健婦 4.3.31まで |
| 31 | 小杉 眞紗人 | 東京都島しょ保健所保健指導係長 5.2.5から |
| 32 | 沖山 光男 | 大島町役場福祉課長 |
| 33 | 金城 寛 | 大島町役場保健衛生課長 |
| 34 | 内藤 康男 | 大島町役場福祉課主幹 5.3.31まで |
| 35 | 原田 浩 | 大島町役場企画財政課企画調整係長 4.9.30まで |
| 36 | 立木 有五 | 大島町役場企画財政課統括係長 5.12.20まで |
| 37 | 中山 登 | 大島町役場企画財政課企画調整担当主幹 5.12.20から |
| 38 | 福井 芳久 | 大島町役場保健衛生課医療係長 5.6.30まで |
| 39 | 石田 仲男 | 大島町役場保健衛生課医療係長 5.7.1から |
| 40 | 藤井 一世 | 大島町役場福祉課福祉係長 |
| 41 | 沖山 昭次 | 大島町役場福祉課高齢福祉係長 5.1.1から |
大島町地域福祉計画策定委員会各部会員名簿
平成6年1月1日現在
高齢者福祉検討部会
| 氏名 | 役職名 |
|---|---|
| 前田 又吉 | 大島町議会議員、民生委員会委員長 5.5.7まで |
| 佐藤 新吉 | 大島町議会議員、民生委員会委員長 5.5.7から |
| 原 タツ | 大島老人ホーム施設長 |
| 坂上 豊吉 | 大島町民生委員 |
| 西川 松得 | 大島町老人クラブ連合会会長 5.9.17まで |
| 高橋 茂之助 | 大島町老人クラブ連合会会長 5.9.17から |
| 吉田 隆弘 | シルバー人材センター事務局長 |
| 高梨 悦三 | 学識経験者 |
| 島田 久平 | 東京都大島支庁福祉課長 |
| 西川 静子 | 大島町婦人会副会長 |
| 沖山 光男 | 大島町役場福祉課長 |
| 内藤 康男 | 大島町役場福祉課主幹 5.3.31まで |
| 福井 芳久 | 大島町役場保健衛生課医療係長 5.6.30まで |
| 石田 仲男 | 大島町役場保健衛生課医療係長 5.7.1から |
障害者福祉検討部会
| 氏名 | 役職名 |
|---|---|
| 白井 申子 | 大島町民生委員 |
| 桜井 芳與 | 大島町手をつなぐ親の会代表 |
| 川島 理史 | ボランティア代表及び社協役員 |
| 阿部 葉子 | 元東京都大島支庁福祉課係長 |
| 実川 吉樹 | 大島社会福祉協議会事務局長 |
| 坂下 賢司 | 東京都大島支庁福祉課係長 指導主事福祉司 |
| 金城 寛 | 大島町役場保健衛生課長 |
| 藤井 一世 | 大島町役場福祉課福祉係長 |
児童福祉・ひとり親福祉検討部会
| 氏名 | 役職名 |
|---|---|
| 森川 太喜治 | 大島町立北の山小学校長(校長会長) 5.3.31まで |
| 柳瀬 治男 | 大島町立第一中学校長(校長会長) 5.4.1から |
| 藤井 善弥 | 大島社会福祉協議会会長 |
| 川村 千枝 | 大島町民生委員代表総務 |
| 宇山 正泰 | 大島町PTA連合会会長 5.5.27まで |
| 柳瀬 清一 | 大島町PTA連合会会長 5.5.28から |
| 藤井 三枝 | 大島町婦人会会長 |
| 三辻 房子 | 大島町婦人会副会長及び大島町民生委員 |
| 下司 克昭 | 東京都大島支庁福祉課厚生係長 5.2.5から |
| 小杉 眞紗人 | 東京都島しょ保健所保健指導係長 5.2.5から |
| 立木 有五 | 大島町役場企画財政課統括係長 5.12.20まで |
| 中山 登 | 大島町役場企画財政課企画調整担当主幹 5.12.20から |
| 沖山 昭次 | 大島町役場福祉課高齢福祉係長 5.1.1から |
7.社会福祉用語解説
ゴールドプラン
平成元年12月に公表された「高齢者保健福祉推進10ケ年戦略」(平成11年までの10ケ年の目標)の通称。
住民活動計画
社会福祉協議会が策定する基本計画。
ローリング
見直し。
ノーマライゼーション
障害をもつ者、もたない者もともに社会の構成員として生きがいを持って生活し、活動していくという考え方。
ライフステージ
人間の一生を、幼年期、少年期、青年期、壮年期といったように段階区分したもの。
ニーズ
住民が望むもの、要求するもの。
ライフスタイル
生活形態。
ネットワーク
網の目のような人と人とのつながり。
センサス間コーホート変化率法
将来人口の推計方法。センサスとは、国勢調査のことをいう。ある年齢集団の数と5年前の相当する年齢集団の数の比率を用いて、その年齢集団の5年後の数を推計する。このような計算を重ねて目標年次の人口を推計する方法。
システム
組織、体系
マンパワー
(福祉関係の)要員。
ボランティア
自主的に福祉などの事業活動に参加する人。
ホームヘルパー
家庭を訪れて、高齢者等の世話をする人。
ガイドヘルパー
在宅で重度の視覚障害者が社会生活上必要な外出をする場合に世話をする人
ショートステイ
介護者の負担を軽減するために、在宅のねたきり高齢者等を一時的に施設において預かること。
ケアハウス
自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は、高齢等のため独立して生活するには不安をもたれる人で、家族による援助を受けることが困難な高齢者が利用でき、自立した生活を確保出来るよう工夫された新たなタイプの老人ホーム。
リハビリテーション
(rehabilitation)
re(再び)、habilis(ラテン語で何かをするのに適した)、ation(にすること)が結合して出来た言葉である。何らかの原因で障害をもつ人に対し、身体的な機能回復はもちろんのこと、心理的、社会的、また職業的、経済的に個人のもつ力を最大限に回復させ人間らしく生きる権利を再び獲得して社会へ復帰させること。
プライマリケア
住民に一番身近な、個人や家庭に最初に接する保健医療サービス。
トータルケアサービス
在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、在宅のねたきり高齢者等、およびその介護者の介護等に関する、ニーズに対応した各種の保健・医療、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係機関との調整を行い、実施機関にてサービスを供与すること。
ジョブコーチ
職業指導専門職員
主題:
大島町地域福祉計画 No.2 1頁~97頁
(平成6年度~平成12年度)
発行者:
大島町:大島町福祉課
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
大島町:大島町福祉課
東京都大島町元町1丁目1番14号
TEL 04992(2)1441
