八女市障害者基本計画
平成8年 3月
八女市
3章
啓発広報の推進
| 障害者が住みなれた地域で普通に暮らしていくためには、市民一人ひとりが障害及び障害者に対し正しい理解と認識を深めることが最も重要です。 このため広報活動を推進し啓発に努め、幼少時から「ノーマライゼーション」を浸透させることが必要だと考えます。 |
|
<施策の体系>
┌1.啓発広報の推進 ───┬(1)啓発広報活動の充実
│ └(2)「障害者の日」等における啓発
├2.福祉教育による啓発 ─┬(1)学校等における福祉教育の充実
啓発広報の推進─┤ └(2)公務員に対する福祉教育の充実
├3.交流の促進 ─────┬(1)交流機会の充実
│ └(2)交流活動支援
└4.人権擁護の推進 ───┬(1)人権擁護の推進
├(2)用語の見直し
└(3)精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正
|
3章 啓発広報の推進
1.啓発広報の推進
【現状】
①情報収集手段
福祉施策について知る手がかりは、身体障害者、心身障害児、知的障害者等とも「八女市広報」が最も多く、いずれも60%以上の人が広報によって情報を収集しています。ついで「福祉事務所からのお知らせ」や「福祉相談委員」からの情報が多いようです。
| 福祉施策を知る手がかり |
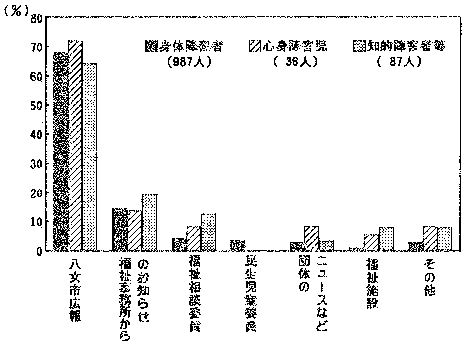
|
| 《資料》障害者(児)実態調査(平成7年) |
②広報
月2回発行の「市広報やめ」に月々の行事・連絡等を掲載しています。福祉に関しては、福祉事務所より“市民福祉あんない”として「ふれあい」を発行し各家庭に配布、福祉全般の情報を載せています。また、「身体障害者福祉のごあんない」を配布し、障害を持つ人への福祉サービスの紹介をしています。

【課題】
「障害者の日(12月9日)」や「ふれあいフェスタ」などの取り組みにより、人々の関心は高まってきましたが、市民全般の理解は必ずしも十分とはいえない状況にあります、「市広報やめ」は市民に広く利用されているようですが、そういった中で障害者にスポットをあてた広報のあり方も検討する必要があります。また「ふれあい」等の利用簡便性を考慮した上、市民への障害者福祉問題理解へのアプローチが必要です。このため、様々な広報媒体や行事等を通じて、積極的に啓発活動を展開し、市民の正しい理解と認識を深めることが重要です。
【施策】
1.啓発広報活動の充実
○市の広報誌の内容充実に努め、積極的な活用を促進します。
○広報誌以外の媒体においても障害者問題の正しい理解を図ります。
○障害者に対する広報誌等の配布方法の改善を図ります。
○パンフレット、案内冊子等は定期的に改訂を行い、個人あてに送付するなど情報提供の充実を図ります。
○視覚障害者のいる世帯には、市の広報等を点字や音声テープで配布するよう努めます。
2.「障害者の日」等における啓発
○「障害者の日」を意義あるものとするため、障害者週間(12月3日~12月9日)などに広報活動や、ふれあいフェスタ等各種行事等の実施を重点的に展開します。
2.福祉教育による啓発
【現状と課題】
障害者問題についての早期教育、とりわけ障害児が児童・生徒とともに学ぶことは、障害者問題を身近なこととしてとらえ、理解を深めるために重要です。現在市内には、福祉教育指定校が1校(福島中学校:H7~9年)、社会福祉協議会を通じて社会福祉協力校が4校(福島小学校、忠見小学校、川崎小学校、岡山小学校)あり、これらの学校において福祉教育が進められています。今後も交流教育の推進を図るなど、ノーマライゼーションの浸透を進める必要があります。
また、学校教育に限らず生涯にわたっての教育がなされることが、福祉教育を充実し、市民の健康に対する関心を高め、障害の予防にもつながっていくと考えられます。各分野での教育が重要なことから、行政の全職員に対する福祉教育の充実も必要となります。
【施策】
1.学校等における福祉教育の充実
○保育所・幼稚園及び小中学校並びに保健所などにおいて障害児と健常児の交流教育を行い、障害に対する認識と理解を深めるとともに、ボランティアの育成に努めます。
2.公務員に対する福祉教育の充実
○市職員の福祉教育を充実させるため、研修等の実施、充実に努めます。
3.交流の促進
【現状】
毎年、子どもから高齢者までの全世代及び障害者を対象とした「ふれあいゲートボール大会」を開催し、ふれあいのある街づくりを推進しています。また、昨年まで八女市ボランティア連絡協議会等の主催により、「村まつり」又は「福祉運芸大会」が開催されていましたが、本年より新しい取り組みとして、八女市主催による「八女市ふれあいフェスタ」を開催しました。
障害のある人と、そうでない人が“ふれあいの和を広げる”ことにより、障害者の社会参加を促進するとともに、障害に対する市民の意識高揚を図っています。
| ふれあいフェスタパンフレット |
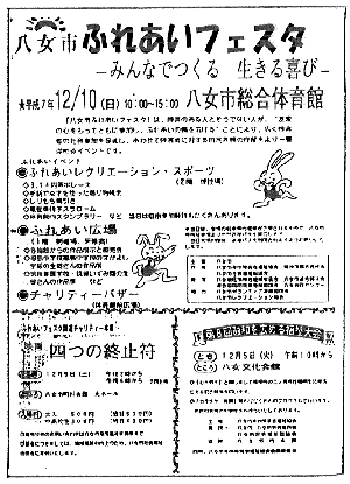
|
| ふれあいフェスタ会場風景 | |
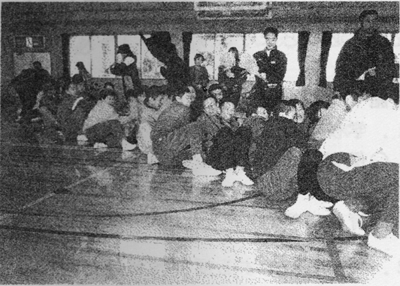 車椅子での”むかで競争 |
|
 車椅子での”むかで競争” |
|
【課題】
障害のある人もない人もともに集い、交流する場や機会をつくることは、障害者を理解し、障害者の社会参加を促進するうえで重要です。ただしそれが障害者に対してあるいは市民に対しての一方的な押しつけであっては全ての人の理解や参加は望めません。障害者が参加しやすく、また障害を持たない人にもわかりやすいイベントや地域行事を検討する必要があります。
行政機関をはじめ関係団体が連携・協力し、交流機会の拡大や施設の開放等よりよいふれあいの場が多くもたれるよう努めなければなりません。
【施策】
1.交流機会の充実
○ふれあいフェスタの内容充実とともに、日常的にふれあい、交流ができるような交流活動の推進に努めます。
○会場への移動が困難な障害著に対しては、移送サービスなど参加へのきっかけづくりにも配慮します。
2.交流活動支援
○障害者団体等の行う交流事業に対し、場の提供や支援に努めます。
4.人権擁護の推進
【現状】
すべての障害者は社会を構成する一人の人間として当然尊重されるべきものでなくてはなりません。しかしながら調査の結果4割弱の身体障害者が、多少にかかわらず障害者に対する差別や偏見はあると感じています。
差別や偏見があると感じる人は比較的若い世代に多く、20代~30代では70%以上の人が差別や偏見はあると回答しています。
また全体では「わからない」と答えた人や無回答の人があわせて約3割あるため、「あまりない」や「ない」という人はそれぞれ15%程度にとどまっています。
| 障害者への差別・偏見について |
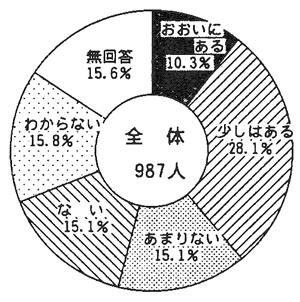
|
| 《資料》障害者(児)実態調査(平成7年) |
| (%) | |||||||
| おおいにある | 少しはある | あまりない | ない | わからない | 無回答 | ||
| 総数 | 103 | 28.1 | 15.1 | 15.1 | 15.8 | 15.6 | |
| 年代別 | 10代 | - | - | - | - | - | 100.0 |
| 20代 | 29.4 | 47.1 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | - | |
| 30代 | 33.3 | 36.7 | 13.3 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | |
| 40代 | 24.1 | 42.5 | 9.2 | 6.9 | 9.2 | 8.0 | |
| 50代 | 23.8 | 37.7 | 11.5 | 9.2 | 10.8 | 12.5 | |
| 60代 | 6.7 | 28.6 | 15.5 | 18.5 | 18.2 | 12.5 | |
| 70歳以上 | 6.3 | 20.7 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 22.9 | |
| 《資料》障害者(児)実態調査(平成7年) | |||||||
【課題】
障害のあるすべての人が、社会の中の隔離主義や温情主義的差別等でいやな思いをすることのないよう。市民に広く理解を求め、人権意識の高揚を図る必要があります。
また、日常使われる言葉や用語のうちで不快感を与えたりするものに対しても、正しい認識のために啓発をさらに推進していく必要があると思われます、
【施策】
1.人権擁護の推進
○障害者は健常者と変わりなく尊重されるものであるという基本に立って啓発に努めます。
○同情や隔離による差別の思想を廃止し、ノーマライゼーションの考え方が広く市民に浸透するよう啓発に努めます。
2.用語の見直し
○日常使われている用語について、当事者(障害者)や関係団体の意見を踏まえながら見直しを行います。
3.精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正
○精神障害者に対する誤解や偏見が、精神障害者の自立や社会参加の阻害要因とならないよう、地域住民に対する正しい知識の普及や啓発、交流を通して、その是正を図ります。
主題:
八女市障害者基本計画
発行者:
八女市
発行年月:
平成8年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒834
福岡県八女市大字本町647
八女市役所市民部福祉事務所
(TEL)0943-23-1111
(FAX)0943-22-2186
