八女市障害者基本計画
平成8年 3月
八女市
8 章
まちづくりの推進
| 障害者が積極的に社会に参加し生活していくためには、道路や交通、施設、住宅などさまざまな整備を推進する必要があります。又それらの安全を保ち、安心して暮らせるよう、防犯・防災対策が重要となります。 |
|
<施策の体系>
┌1.公共施設の整備 ─────(1)福祉施設整備の整備状況の点検・改善
├2.道路・交通の整備 ───┬(1)運行車両等の改善の促進
│ ├(2)路上の環境整備
まちづくりの推進 ─┤ └(3)意識の啓発
├3.住宅整備の促進 ────┬(1)公共住宅整備の促進
│ └(2)住宅改造支援制度の充実
└4.防犯・防災対策の推進 ─┬(1)防犯・防災器具の給付
├(2)地域の防犯・防災ネットワークの確立
└(3)防犯・防災知識の普及
|
8章 まちづくりの推進
1.公共施設の整備
【現状】
新八女市総合計画において、「日常生活のなかで、心身障害者(児)が可能な限り健常者と同じ社会活動が行えるよう、配慮することが必要である、そのため、主要な公共施設等の設備の改善・改築を進めていく。」と基本構想に掲げています。これに基づき、各施設の整備を進めており、現在以下のような整備状況となっています。
また、障害者や高齢者が気軽に集まって話し合ったり、レクリエーションや軽い運動ができるような公園の整備、広場の確保等を検討しています。
| 施設 | 設置内容 |
| 市役所 | 点字ブロック、スロープ、自動ドア、エレベーター 身体障害者用トイレ、障害者専用駐車場 |
| 八女総合庁舎 | 点字ブロック、スロープ、自動ドア、エレベーター 身体障害者用トイレ、障害者専用駐車場 |
| 警察署 | スロープ、自動ドア、エレベーター、身体障害者用トイレ |
| 保健センター | スロープ、エレベーター、身体障害者用トイレ |
| 社会福祉会館 | 点字ブロック、スロープ、自動ドア、エレベーター 24時間使用可能身体障害者用トイレ、障害者専用電話 |
| 児童センター | スロープ、身体障害者用トイレ |
| 伝統工芸館 | スロープ、自動ドア、エレベーター、身体障害者用トイレ |
| 図書館 | 点字ブロック、スロープ、自動ドア、エレベーター 身体障害者用トイレ |
| 文化会館 | 点字ブロック、自動ドア、舞台昇降機、身体障害者用トイレ |
| 総合体育館 | スロープ、身体障害者用トイレ |
| 勤労青少年ホーム | スロープ、身体障害者用トイレ |
| 東公民館 | スロープ |
| 西公民館 | 自動ドア、エレベーター、身体障害者用トイレ |
| 隣保館 | スロープ |
| 市町村会館 | 自動ドア、エレベーター、身体障害者用トイレ |
| 土橋四ツ角 | 音響信号機 |
| 福島小学校 | 身体障害者用トイレ、階段手すり、スロープ(管理棟及び渡り廊下) |
| 長峰小学校 | 階段手すり、身体障害者用トイレ及びスロープ(体育館) |
| 上妻小学校 | 正面玄関スロープ |
| 三河小学校 | 身体障害者用トイレ及びスロープ(体育館) |
| 八幡小学校 | 階段手すり、身体障害者用トイレ、渡り廊下にスロープ |
| 忠見小学校 | スロープ(体育館) |
| 川崎小学校 | 正面玄関スロープ |
| 岡山小学校 | 階段手すり、身体障害者用トイレ及びスロープ(体育館) |
| 福島中学校 | 玄関スロープ、階段手すり、身体障害者用トイレ |
| 南中学校 | 玄関スロープ、階段手すり、身体障害者用トイレ |
| 見崎中学校 | 玄関スロープ、階段手すり、身体障害者用トイレ、渡り廊下にスロープ |
| 西中学校 | 玄関スロープ、階段手すり |
| 山ノ井公園 | 身体障害者用トイレ |
| 宮野公園 | 非常ベル付き身体障害者用トイレ、スロープ、障害者専用電話 |
| 岡山公園 | 非常ベル付き身体障害者用トイレ、スロープ |
| 鉄道記念公園 | 身体障害者用トイレ、スロープ |
| 八女公園 | 非常ベル付き身体障害者用トイレ(予定) |
| 立山サッカー場 | 身体障害者用トイレ、スロープ |
| 八女簡易家庭裁判所 | スロープ、呼び出しブザー、身体障害者用トイレ |
| 中央公民館 | スロープ |
| 公共職業安定所 | スロープ、自動ドア、身体障害者用トイレ |
| 八女税務署 | スロープ、呼び出しブザー、身体障害者用トイレ |
| 八女郵便局 | スロープ、自動ドア |
| 老人福祉センター | 身体障害者用トイレ |
| 《資料》八女市福祉事務所 | |
【課題】
「バリアフリー」のまちづくりを目指して、物理的な障壁をなくし、障害者がどこへでも自由に移動できるよう、公共施設をはじめ公園などの多目的広場や、利用頻度の高い一般施設、商店等においても福祉整備を進める必要があります。
【施策】
1.福祉施設設備の整備状況の点検・改善
○整備がなされている公共施設について、有効な整備であるかどうかの点検・調査を行います。
○現存の設備で不十分なものは、随時整備の改善を図ります。
○障害者の利用希望や意見を参考にし、建築士や施工技術者及び民間事業者、関係団体等に対して、障害者に配慮した整備墓準を要請します。
○公共性の高い民間の建築物の建築主に対し必要な指導及び助言又は指示を行うとともに税制上の特例措置及び公益融資等による支援策の活用を通じて、建築物のバリアフリー化を促進します。
2.道路・交通の整備
【現状】
実態調査によると、自家用車を交通手段にしている人が最も多く、ついで身体障害者ではタクシー、心身障害児及び知的障害者等では自転車・バイクが多くなっています。これは、障害者が利用できる公共の交通機関が少ないことの裏返しでもあると考えられます。
外出するときに困ることは、道路の段差や障害物が多いことがあげられており、特に視覚障害者にとっては、危険が伴うことでもあります。
利用している交通手段(身体障害者・複数回答)
《資料》障害者(児)実態調査(平成7年)
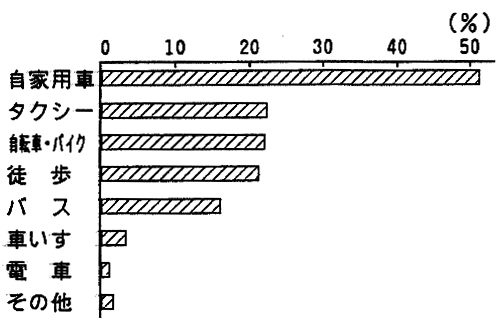
|
外出時に困ること:(身体障害者・複数回答)
《資料》障害者(児)実態調査(平成7年)
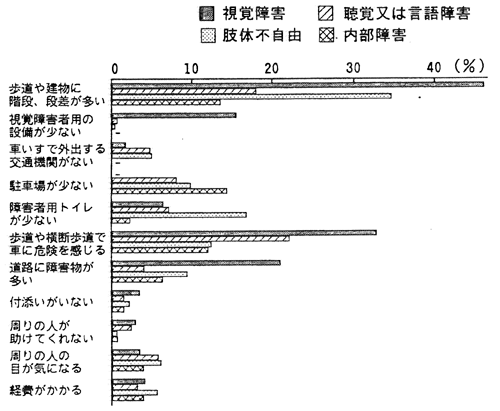
|
【課題】
障害者がどんなところでも安全に移動できるよう、移送サービス制度等交通手段の確保とともに公共交通機関の障害者に配慮した設備・改善を促進していく必要があります。路上には音声による誘導や案内版を設置するなど、障害の種類に応じた交通情報の提供も重要です。
また、設備の充実だけでなく、ちょっとした障害物でも障害者には大きな負担になることを人々に十分認識してもらわなければなりません。さらに、心身障害児、知的障害者等で「まわりの目が気になる」ことを外出時に困ることとして多くあげられており、健常者の態度が障害者の外出の妨げにならないよう意識の改革も重要です。
【施策】
1.運行車両等の改善の促進
○福祉バスの車椅子対策を図ります。
○障害者の利便のため、リフト付バス及びリフト付タクシーへの改造を各会社へ要請します。
○移送サービスの実現に向け努力します。
2.路上の環境整備
○歩道の段差の解消に努めます。
○障害者の歩行の妨げになる放置自転車、違法駐車車両等の排除に努めます。
○主要な道路については、点字ブロックの設置を行い、音響信号の設置を図ります。
3.意識の啓発
○障害者が安全に、かつ安心して外出できるよう、点字ブロックに物を置いたり、障害者に対し好奇の目を向けるなど障害者への配慮に欠ける行為が決して行われることのないよう意識の啓発・指導に努めます。
3.住宅整備の促進
【現状】
実態調査によると、4割以上の障害者(児)は住まいを改造する必要はないとしていますが、現在の家屋構造は健常な人の生活様式にあわせて設計されているものが多く、障害者にとって生活に支障をきたすことも考えられます。
高齢化社会に備えて、現在バリアフリー住宅の整備が進められているところですが、特定目的公営住宅は今後さらに必要と思われます。
増・改築したい場所では、風呂やトイレなど、作業を多く必要とする場所の改造を希望する声が多くあげられています。
| 贈・改築したい場所(複数回答) |
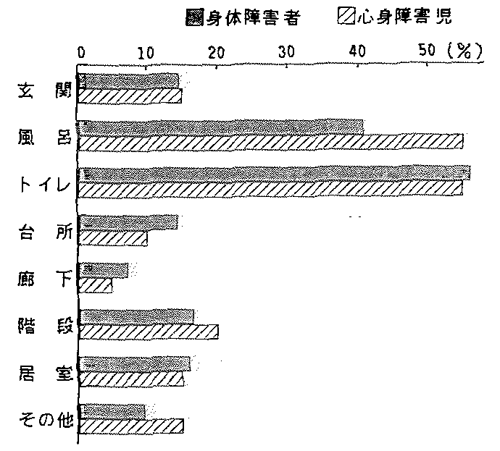
|
| 《資料》障害者(児)実態調査(平成7年) |
| 区分 | S61年 | S62年 | S63年 | H1年 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 |
| 市営住宅 | - | - | - | - | - | - | - | 2戸 | - | - |
| 県営住宅 | 2戸 | 2戸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 《資料》八女市福祉事務所 | ||||||||||
【課題】
障害者が地域のなかで生活していくためには、まず住宅が機能的で快適な空間であることが必要です。障害者が安心して生活でき、又介護者が介護しやすい公営住宅を整備していくことが必要です。
また、増改築には段差の解消、手すりの取付けや水まわりの改善等が必要となるため、その技術的な相談体制づくりを進めるとともに、財政的援助をしていく必要があります。
【施策】
1.公共住宅整備の促進
○障害者の生活に配慮した安全で住みよい公共住宅の建設や改善の促進に努め鵠ます。
○障害者の居住の安定を図るため、障害者優先入居の公共住宅の供給を推進し、ます。
○新設される住宅については、段差の解消等身体機能の低下に配慮した使用を推進し、居室だけでなく建物全体でのバリアフリー建築に努めます。また、民間の建設業者にも障害者向け住宅の整備を積極的に働きかけます。
○特定公営住宅の新設の際は当事者(障害者・使用者)の意見が反映できるよう事前に協議を行い、当事者の知識を活かせるよう努めます。
2.住宅改造支援制度の充実
○障害者に配慮した住宅の整備を支援し、融資制度等の活用を促進します。
○障害者世帯における手すりの設置、段差の解消等住宅改造に対する支援に努めめます。
○住宅の新築や増改築の相談に専門的に応じることができるよう専門家の相談体制を整えます。
4.防犯・防災対策の推進
【現状】
心身にハンディがある人たちは、犯罪に巻き込まれたり、災害が起きた場合に、身を守ったり、迅速に避難することが困難である人が多いのが現実です。しかし、防犯・防災対策はまだ十分とはいえず、用具の給付も下表の通りあまり多くありません。このほか緊急通報装置は、老人福祉において現在150台ほど設置されています。
| 品名 | H2年 | H3年 | H4年 | H5年 | H6年 | H7年 | 合計 |
| 火災警報機 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 自動消火器 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 屋内信号灯 | - | 1件 | - | - | - | - | 1件 |
| 屋内信号装置 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | - | - | 5件 |
| 聴覚障害者用通信装置 | - | - | 1件 | 1件 | - | - | 2件 |
| 合計 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | - | - | 8件 |
| 《資料》八女市福祉事務所 | |||||||
【課題】
障害者が安心して家庭や地域で生活していくためには、防犯・防災対策は基本的な課題です。また、万一の災害時の情報の伝達や避難誘導等が迅速かつ的確に行われなければなりません。
防災知識の普及、緊急通報体制の整備、防災設備の普及整備等、地域ぐるみでの整備が必要です。
【施策】
1.防犯体制の確立
○防犯に必要な日常生活用具の給付の充実を図ります。
○障害者が安心して暮らせるよう、地域防犯ネットワークの確立を図ります。
○手話のできる警察官等の配置を国や県に要請します。
2.防災体制の確立
○防災に必要な日常生活用具の給付の充実を図ります。
○地域住民及びボランティアグループ等との連携を密にし、地域安全活動の強化、防災ネットワークの確立を図ります。
○防災に関するパンフレット等の配布により、障害者の防災に関する知識の普及を図るとともに、地域住民の障害者への援助に関する知識の普及を図ります。
主題:
八女市障害者基本計画
発行者:
八女市
発行年月:
平成8年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒834
福岡県八女市大字本町647
八女市役所市民部福祉事務所
(TEL)0943-23-1111
(FAX)0943-22-2186
