八女市障害者基本計画
平成8年 3月
八女市
9 章
サービスの充実
| 障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送っていくためには、暮らしをサポートする福祉サービスは欠かせません。在宅福祉サービスをはじめ、施設の充実、福祉機器の普及又、経済面での援助など、ソフト面・ハード面双方のサービスの充実が望まれます。 |
|
<施策の体系>
┌1.在宅福祉サービスの充実 ─┬(1)サービスの充実
│ ├(2)相談機能の充実
│ └(3)デイサービスセンターの育成
├2.施設福祉サービスの充実 ─┬(1)施設の充実
サービスの充実 ─┤ ├(2)総合的福祉センターの建設
│ └(3)広報活動の推進
├3.福祉機器の普及 ──────(1)給付サービスの充実
└4.生活安定施策の充実 ───┬(1)年金・手当等の充実
└(2)経済的負担の軽減
|
9章 サービスの充実
1.在宅福祉サービスの充実
【現状】
実態調査の結果では、日常の生活動作で、入浴や外出に介助を必要としている身体障害者及び知的障害者等が多くなっています。
主な介護者のほとんどは家族で、特に入浴などの介助は重労働であるので家族の負担が懸念されます。
主な介護者の中でも、身体障害者は配偶者が最も多く、障害者本人の高齢化とともに介護者も高齢化してきているといえます。
知的障害者等では、親が主に介助しているケースが最も多く、親なき後の将来を不安に感じるという声が多く寄せられています。
在宅での福祉サービスの充実のためには、ホームヘルパーは今後ますます必要であるため、ホームヘルパーの人員の増加を進めているところです。
| 日常生活動作状況 |
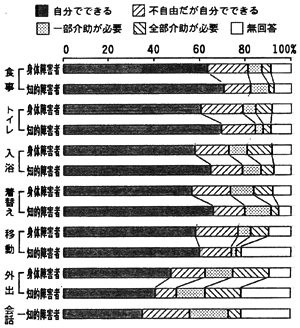
|
|
主な介護者 身体障害者 |
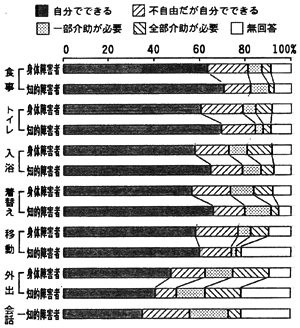
|
| 知的障害者 |
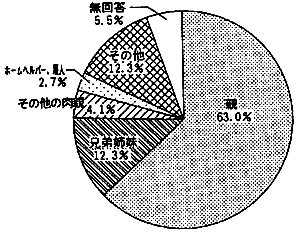
|
《資料》障害者(児)実態調査(平成7年)
| (人) | |||||||
| 年度 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 | 平成7 | |
| 主任 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 常勤 | - | - | 12 | 15 | 17 | 18 | |
| 非常勤 | 日額 | 8 | 15 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 時間給 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 合計 | 8 | 15 | 18 | 19 | 25 | 27 | |
| ※平成7年度は、12月1日現在の人員 | 《資料》八女市福祉事務所 | ||||||
| (%) | |||
| 身体障害者 | 心身障害児 | 知的障害者等 | |
| ▽家事援助など | |||
| 食事の支度 | 9.3 | 13.9 | 9.2 |
| 食事の後片付け | 3.7 | 2.8 | 1.1 |
| 家の中の掃除 | 10.0 | 2.8 | 5.7 |
| 洗濯 | 5.0 | - | 3.4 |
| 家具の上げ降ろし | 5.5 | - | - |
| 買物の代行 | 8.2 | 16.7 | 4.6 |
| 留守番・子供の世話 | 1.7 | 30.6 | - |
| その他の家事 | 1.6 | 8.3 | 4.6 |
| ▽身体介助など | |||
| 食事の介助 | 3.2 | 2.8 | 2.3 |
| 排泄の介助 | 2.8 | 8.3 | - |
| 入浴の介助 | 6.9 | 11.1 | 1.1 |
| 衣類などの着脱の介助 | 3.7 | 8.3 | 2.3 |
| 外出時の付添い | 9.3 | 33.3 | 8.0 |
| その他の介助 | 1.7 | 5.6 | 1.1 |
| その他 | 1.4 | 16.7 | 2.3 |
| 特に受けてみたいものはない | 32.1 | 19.4 | 37.9 |
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) | |||
【課題】
障害者が住みなれた地域で自立した生活を営むためには、障害者や介護にあたる家族に対して、きめ細かな福祉サービスの提供を行う必要があります。障害の重度化や障害者の高齢化等に伴うニーズの多様化を考慮し、その質・量について適切な対応が必要です。
今後もホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスを柱とした在宅福祉サービスを充実させていくとともに、障害者や介護家族の相談体制も充実させることが重要です。
【施策】
1.サービスの充実
○ホームヘルプサービスの充実に努め、ホームヘルパーの確保を図ります。
○介護家族の負担の軽減のため、ショートステイ事業の拡充、デイサービス事業の推進を図るなど、在宅介護支援体制の整備に努めます。
2.相談機能の充実
○障害者やその家族の各種相談に応じ、多様化するニーズ・要望を把握するとともに、必要な指導等を行う相談体制の充実を図ります。
○実体験からの相談を重視し、知的障害者も含めたピア・カウンセリングの実現を目指します。
3.デイサービスセンターの育成
○在宅福祉において重要な役割を果たすデイサービスセンターの育成に努めます。
2.施設福祉サービスの充実
【現状】
障害者(児)の施設措置は下表の通りですが、現在市内には身体障害者通所授産施設「若楠園」(定員30人)が1か所、老人対象デイサービスセンターのB型とE型がそれぞれ1か所づつあります。平成8年度には知的障害者通所施設と入所施設がそれぞれ1か所づつ建設の予定となっています。
| (人) | |||||
| 区分 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 身体障害者通所施設 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 身体障害者入所施設 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 知的障害者通所施設 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| 知的障害者入所施設 | 24 | 24 | 22 | 20 | 23 |
| 心身障害児通所施設 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 心身障害児入所施設 | 22 | 23 | 21 | 23 | 23 |
| 《資料》八女市福祉事務所 | |||||
| 利用施設上位5位:身体障害者(複数回答) |
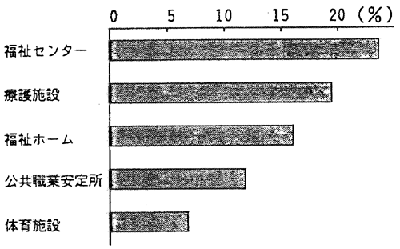
|
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) |
実態調査によると、身体障害者で施設を利用したことのある人は全体の12%にとどまっており、7割以上は利用したことがないと答えています。利用したことがない理由は、大半が必要がなかったからとしていますが、「利用したいが適当な施設がなかった」という人が約8%、「知らなかった」という人が約19%という結果がでています。
施設を利用したことのある人では、全体的に入所施設の利用が多いようです。
【課題】
住みなれた地域で障害者も健常者も区別なく暮らしていくことが重要視されているなか、在宅福祉のサービスの充実が図られていますが、その支援のためにも、また在宅では対応が困難な障害者のためにも、施設福祉サービスの充実も同様に重要であり、整備を推進する必要があります。
障害者のニーズに合わせ、既存施設のサービスの充実を図るとともに、医療ケアや機能訓練をはじめスポーツ、レクリエーション、文化活動等、障害者をはじめとするすべての人がいつでも利用できる総合的な福祉センターの建設が望まれます。
ただ、どれほど建設、整備を進めても、それが知られていなければ何もなりません。場所や内容をはじめわかりやすい広報に努める等施設の周知を図る必要があります。
【施策】
1.施設の充実
○障害者の適所施設・入所施設の整備を促進し、施設内サービスの充実に努めます。
○入所施設については、生活の質の向上を図ります。
○知的障害者等の生活自立のための訓練の場を施設の中に設置し、親なきあとも安心して暮らせるような施設の整備を推進します。
2.総合的福祉センターの建設
○地域福祉推進のための拠点施設として「総合福祉センター」(仮称)の建設・に向け調査検討を行い、情報の収集・提供、相談・指導、訓練・研修及び参加交流等の機能の充実を図り、障害者の多様なニーズに対応できる体制作りを推進します。
3.広報活動の推進
○障害者の有効なサービス利用のため、在宅福祉サービスとあわせ、施設をより多くの人が認知し、又利用できるよう広報活動に努めます。
3.福祉機器の普及
【現状】
現在の障害者の日常生活用具の給付状況は、下表の通りとなっています。
(※障害児については県給付となるため、八女市としての給付・交付の実績はありません。)
| 年度 | H2件 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 日常生活用具 | 8件 | 19件 | 14件 | 13件 | 30件 |
| 補装具 | 107件 | 83件 | 130件 | 130件 | 133件 |
| 《資料》八女市福祉事務所 | |||||
今後必要とする補装具・日常生活用具
《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年)
| <補装具> |
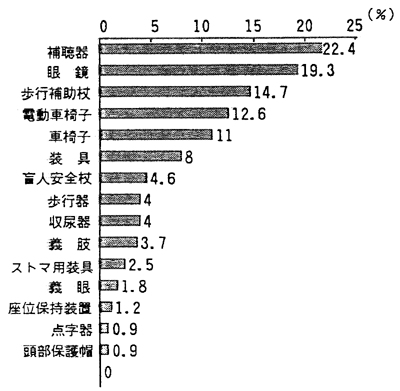
|
| <日常生活用具> |
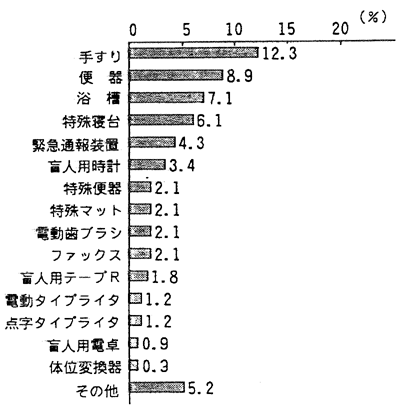
|
【課題】
福祉機器は、身体のハンディキャップを補うだけでなく、移動手段、コミュニケーションの手段、危険を回避する手段など、その役割は大変重要です。
今後は、障害者のニーズに合わせた補装具・日常生活用具の普及に努めるとともに情報提供を十分に行う必要があります。
【施策】
1.給付サービスの充実
○身体障害者に対し補装具の交付・修理を行うとともに、在宅の重度心身障害者に対し日常生活用具を給付し、障害者の日常生活の便宜を図ります。
○給付後の補装具、日常生活用具の使用状況、問題点等をリサーチし、よりよい福祉機器の普及に努めます。
4.生活安定施策の充実
【現状】
所得保障は、国全体で進めていかなければならない大切な事業です。実態調査によると、8割以上の身体障害者・知的障害者が公的年金を受けており、なかでも老齢又は障害による国民年金や老齢による厚生年金受給者が多くなっています。しかし、福祉サービスの要望について尋ねた結果では、所得保障の充実が身体障害者で第1位、知的障害者で第2位にあげられており、現在の制度では必ずしも十分ではないことを浮き彫りにしています。
また、本計画にあたり腎友会から提出された意見書にも、医療費の公費負担や通院保障対策を強く希望する声が寄せられています。
| (%) | ||||||
| 身体障害者 | 987人 | 心身障害者 | 36人 | 知的障害者 | 87人 | |
| 第1位 | 年金や手当などの増額や税金負担の軽減など所得保障の充実 | (38.0%) | 障害者・児が親なき後も安心して暮らせる生活(入所)施設 | (63.9%) | 障害者・児が親なき後も安心して暮らせる生活(入所)施設 | (44.8%) |
| 第2位 | 障害者・児が親なき後も安心して暮らせる生活(入所)施設 | (22.7%) | 障害福祉センターや通園施設などの早期療養体制の充実強化 | (38.9%) | 年金や手当などの増額や税金負担の軽減など所得保障の充実 | (33.3%) |
| 第3位 | 事故や病気で障害者・児となった人のリハビリテーションの充実 | (21.5%) | 雇用が困難な障害者のために通所授産施設などを増やす | (38.9%) | 重度障害者・児の医療費公費負担の充実をはかる | (28.7%) |
| 第4位 | 重度障害者・児の医療費公費負担の充実をはかる | (20.2%) | 緊急的に障害者・児を預かる保護制度の充実をはかる | (36.1%) | 雇用が困難な障害者のために通所授産施設などを増やす | (23.0%) |
| 第5位 | 階段、道路の段差を小さくし点字ブロック、信号機の設置など | (15.0%) | 年金や手当などの増額や税金負担の軽減など所得保障の充実 | (36.1%) | 障害者・児の正しい理解のため教育の充実と交流の促進 | (21.8%) |
| 第6位 | 歯科治療など障害に応じてきめ細かな医療体制を整備する | (14.8%) | 養護学校や特殊学級を卒業した後の進路指導の充実 | (30.6%) | 歯科治療など障害に応じてきめ細かな医療体制を整備する | (19.5%) |
| 第7位 | 日常生活援助の為、家事・身体介護のホームヘルプの充実 | (14.7%) | 障害者・児の正しい理解のため教育の充実と交流の促進 | (27.8%) | 障害福祉センターや通園施設などの早期療養体制の充実強化 | (16.1%) |
| 第8位 | JRやバスなどの設備を改善し障害者・児が利用しやすいように | (12.8%) | 歯科治療など障害に応じてきめ細かな医療体制を整備する | (25.0%) | 障害者が利用できる職業訓練校を整備し就職斡旋体制の充実強化 | (16.1%) |
| 第9位 | 障害者・児が住みやすいように改造する費用の助成制度の充実 | (12.6%) | 日常生活援助の為、家事・身体介護のホームヘルプの充実 | (19.4%) | 事故や病気で障害者・児となった人のリハビリテーションの充実 | (11.5%) |
| 第10位 | 養護学校や特殊学級を卒業した後の進路指導の充実 | (11.1%) | JRやバスなどの設備を改善し障害者・児が利用しやすいように | (19.4%) | 養護学校や特殊学級を卒業した後の進路指導の充実 | (11.5%) |
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) | ||||||
| 年金受給件数 |
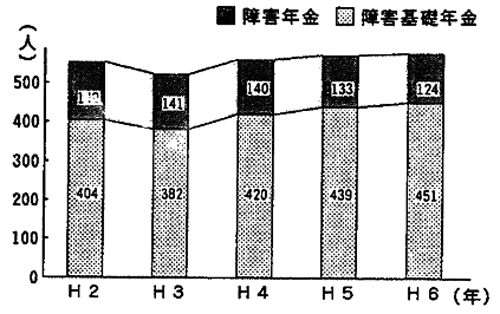
|
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) |
| 障害福祉のための関連施策 | |||
| 項目 | 身体障害者 | 精神薄弱者 | 精神障害者 |
| JRの旅客運賃割引 | ○ | ○ | × |
| その他の鉄道、バス等の運賃割引 | ○ | ○ | × |
| 航空運賃割引 | ○ | ○ | × |
| 有料道路の通行料金の割引 | ○ | ○ | × |
| 各種入館料の割引 | ○ | ○ | × |
| NHK放送受信料の免除 | ○ | ○ | × |
| 郵便料金の減額等 | ○ | ○ | × |
| NTT無料番号案内 | ○ | × | × |
| 電話設置料の分割払 | ○ | ○ | × |
| 福祉用電話機の利用料金等割引 | ○ | ○ | × |
| 公営住宅の優先入居 | ○ | ○ | ○ |
| 住宅金融公庫による割増融資 | ○ | ○ | × |
| 不在者投票 | ○ | × | × |
| 駐車禁止規制の適用除外 | ○ | × | × |
| 税の控除等 | ○ | ○ | △ |
| 障害者雇用促進法の雇用率制度 | ○ | ○ | × |
| 障害者職場適応訓練 | ○ | ○ | ○ |
【課題】
経済的にも負担の大きい障害者にとって、所得保障及びその他の経済的支援が必要なのはいうまでもありません。経済的に安定せず、将来の生活を不安に思う障害者やその家族が少しでも安心できるよう、今後一層の充実が望まれます。
加えて、年金や手当を受けていない人の約4人に1人は「制度を知らない」と答えており、制度の周知を図ることも必要です。
また、精神障害者の福祉施策が不十分であるので、よりよい生活が送れるよう、割引制度や免除制度の充実等精神障害者の福祉施策を見直す必要があります。
【施策】
1.年金・手当等の充実
○障害者の生活安定のための各種年金、手当等について、制度の周知を図るとともに、制度の充実・改善について県・国へ要望を行います。
2.経済負担の軽減
○障害者の経済負担軽減のため、税の減免や各種の割引制度等の周知を図ります。
○精神障害者に対する割引制度や免除制度を見直し、改善に努めます。
主題:
八女市障害者基本計画
発行者:
八女市
発行年月:
平成8年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒834
福岡県八女市大字本町647
八女市役所市民部福祉事務所
(TEL)0943-23-1111
(FAX)0943-22-2186
