八女市障害者基本計画
平成8年 3月
八女市
10 章
社会参加の促進
| 障害者が積極的に社会参加し、地域の人々と交流を広げることは、生きがいのある充実した生活を送るうえで重要です。 社会活動やスポーツ活動・文化活動などに障害者が自主的に参加できるような環境づくりが必要です。 |
|
<施策の体系>
┌1.地域福祉とコミュニケーションの促進 ─────┬(1)情報伝達手段の確保
│ └(2)情報提供の充実
├2.社会活動の参加促進 ─────────────┬(1)社会参加の推進
社会参加の促進 ─┤ ├(2)自主的参加意識の醸成
│ └(3)地域住民の意識の改革
└3.スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進 ─┬(1)スポーツ、レクリエーションの振興
└(2)文化活動への参加促進
|
10章 社会参加の促進
1.地域福祉とコミュニケーションの促進
【現状】
障害者が日常生活において自立し、主体的に社会参加するためには、誰もが必要な情報を同じように得ることができるようコミュニケーション手段が確保される必要があります。
人材育成のため、手話教室・点字教室等を定期的に行っており、手話、点訳、朗読についてはボランティアの協力を受けています。
近所とのコミュニケーションの程度は、会えば世間話をする程度の付き合いが約3割を占めて最も多くなっています(実態調査:身体障害者)。付き合いのない人は約6%と少なく、大半の人は程度の差はあれ、近所付き合いはあるようです。
| 近所付き合いの程度:身体障害者 |
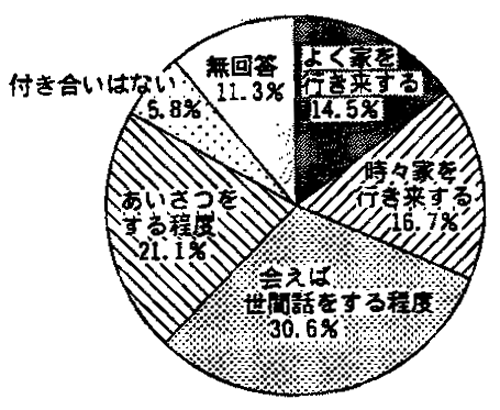
|
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) |
【課題】
コミュニケーションの重要な介助者である手話通訳者、点訳者等の増員を図るとともに、障害のある人とない人とのコミュニケーションによる相互理解を促進することが重要です。
地域の福祉サービスの充実のためにも、行政、関係機関・団体の連携はもちろん、障害者の地域での暮らしが損なわれないよう、地域住民の理解を十分図ることが大切です。
【施策】
1.情報伝達の手段確保
○情報伝達が困難な障害者の社会参加を促進するため、点訳ボランティアや朗読ボランティア、手話通訳ボランティア等の養成・確保を推進します。
2.情報提供の充実
○保健福祉に関する情報や身体障害者向け通信等に関する情報等、障害者が必要とする幅広い情報をデータベース化し、パソコン通信・ファクス通信等の活用により提供できる体制を整備します。
○行政上の手続きが点字で行えるような制度の設置を図ります。
2.社会活動の参加促進
【現状】
障害者の日常の社会参加を進めるうえで、制限を受けないよう配慮を重ねてきましたが、障害の重度化、障害者の高齢化などにより、実態調査において、身体障害者の約4割は地域活動に参加していない。と答えています。
| (%) | ||||||||||||
| 町内会の行事 | PTA活動 | 子供会などの世話 | 青年団体 | 婦人団体 | 障害者団体 | 老人団体 | ボランティア活動 | その他 | 参加していない | 無回答 | ||
| 総数 | 22.6 | 0.9 | 1.4 | 0.2 | 3.4 | 9.3 | 18.7 | 1.2 | 2.4 | 39.5 | 15.1 | |
| 年代別 | 10代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.0 | |
| 20代 | 17.6 | - | - | 5.9 | - | 5.9 | - | - | 5.9 | 58.8 | 5.9 | |
| 30代 | 30.0 | 10.0 | 20.0 | - | 6.7 | 13.3 | - | 6.7 | 6.7 | 33.3 | 3.3 | |
| 40代 | 34.5 | 6.9 | 8.0 | 1.1 | 4.6 | 13.8 | - | 3.4 | 2.3 | 42.5 | 10.3 | |
| 50代 | 37.7 | - | - | - | 5.4 | 13.1 | - | 1.5 | 2.3 | 39.2 | 9.2 | |
| 60代 | 25.9 | - | 0.3 | - | 5.7 | 5.7 | 11.4 | 1.0 | 2.7 | 42.8 | 15.8 | |
| 70歳以上 | 12.9 | - | - | - | 1.0 | 9.5 | 36.0 | 0.5 | 1.9 | 36.4 | 18.3 | |
| 性別 | 男性 | 27.7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | - | 11.7 | 19.1 | 0.9 | 3.0 | 38.1 | 14.0 |
| 女性 | 16.0 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 7.7 | 6.0 | 18.4 | 1.6 | 1.9 | 42.3 | 15.3 | |
| 《資料》八女市障害者(児)実態調査(平成7年) | ||||||||||||
【課題】
社会生活を進める上でガイドヘルパーの存在は欠かせません。今後ガイドヘルパー制度をさらに充実させるとともに、助け合い運動をなお一層推進していく必要があります。
また、障害者自身が自治活動などの地域活動に積極的に参加できるよう、障害者と自治会や地域団体に支援・啓発をしていくことが必要です。
これまで社会活動に参加できなかった人に対しては、その機会を増やしたり、問題解決に努める必要があります。さらに、障害者が社会参加できるための訓練・相談などが行えるように、既存の施設の充実を進めていかなければなりません。
【施策】
1.社会参加の推進
○遠距離での移動を容易にするガイドヘルプサービスネットワーク事業、盲導犬育成事業、知的障害者の社会参加活動の支援事業等を推進します。
2.自主的参加意識の醸成
○障害者が主体的・自主的に社会活動に参加できるよう条件整備を進め、支援・協力に努めます。
○地域における自立生活運動など、障害者リーダーの養成に努めます。
3.地域住民の意識の開発
○障害者の社会参加を妨げる最大の障害の1つである差別と偏見を、啓発を通じて是正に努めます。
○地域と精神障害者の壁を取り除くため、相互の理解のための啓発活動を推進します。
○啓発活動に際しては、当事者を交えて行い、計画だけが上すべりすることのないよう努めます。
3.スポーツ、レクリエーション、文化活動の促進
【現状】
スポーツ、レクリエーションおよび文化活動の活性化は、障害者の社会参加の促進を図るとともに、障害者に対する市民の理解を広め、交流の場を作る機会としても有効です。これまで「ふれあいフェスタ」「村まつり」「福祉運芸大会」などの開催により障害者のスポーツ、レクリエーション、文化・芸術活動の機会を提供してきました。
| (人) | ||||
| 年度 | 種目 | 男 | 女 | 合計 |
| H3 | ソフトボール投げ | 0 | 4 | 4 |
| 合計 | 0 | 4 | 4 | |
| H4 | 100メートル走 | 0 | 1 | 1 |
| ハンドボール投げ | 1 | 1 | 2 | |
| 水泳 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 2 | 2 | 4 | |
| H5 | 卓球 | 3 | 0 | 3 |
| 車いす競争 | 1 | 0 | 1 | |
| ハンドボール投げ | 2 | 2 | 2 | |
| 合計 | 4 | 2 | 6 | |
| H6 | 卓球 | 3 | 0 | 3 |
| 車いす競争 | 1 | 0 | 1 | |
| ハンドボール投げ | 0 | 2 | 2 | |
| 100メートル走 | 1 | 0 | 1 | |
| やり投げ | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 6 | 2 | 8 | |
| H7 | 車いす競争 | 1 | 0 | 1 |
| 砲丸投げ | 2 | 0 | 2 | |
| 水泳 | 0 | 1 | 1 | |
| ソフトボール投げ | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 4 | 1 | 5 | |
【課題】
今後、障害者の主体的・自主的な参加を促進するためには、単に場の提供だけでなく、参加促進のためのなお一層の取り組みが必要です。そのためには、誰もが参加できるような内容の充実、啓発の促進、自宅から会場への送迎といった移動手段の整備など、幅広い充実が望まれます。
また、これらの活動の拠点となる「総合福祉センター」(仮称)などの積極的な活用に努める必要があります。
【施策】
1.スポーツ・レクリエーションの振興
○スポーツを通じ、障害のある人とない人とのふれあい・交流の促進を図ります。
○障害の特性やニーズに適応した新たなスポーツの調査・研究に努め、障害者のスポーツ・レクリエーションの普及に努めます。
○スポーツ大会へのボランティアの参加を促進し、障害者スポーツに対する理解と関心の高揚を図ります。
2.文化活動への参加促進
○障害者の参加するイベント等の開催を支援し、障害者の生活を豊かにするとともに社会参加を促進する文化活動の振興を図ります。
○市で開催する各種催しについての情報提供を、点字広報や音声テープを通じて参加を呼び掛け、障害者の文化活動への参加促進に努めます。
○障害者が公共施設を積極的に利用できるよう公共施設等の整備・改善を図るとともに施設の利用方法や利用料減免制度等について情報提供等に努めます。
11 章
推進体制
| ◇推進体制組織図 |
付属資料
| ◇障害者基本計画策定委員会名簿 ◇策定経過 ◇障害者基本計画策定委員会規則 |
主題:
八女市障害者基本計画
発行者:
八女市
発行年月:
平成8年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒834
福岡県八女市大字本町647
八女市役所市民部福祉事務所
(TEL)0943-23-1111
(FAX)0943-22-2186
