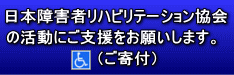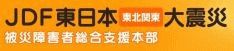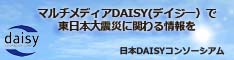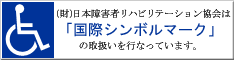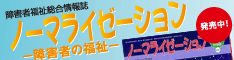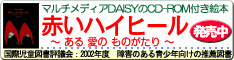障がい者制度改革推進会議 第28回(H22.12.13) 参考資料
委員提出資料
第28回障がい者制度改革推進会議(H22.12.13) 大久保常明委員提出
2010年12月7日
障がい者制度改革推進会議
議長 小川 榮一 様
日本発達障害ネットワーク
代表 市川 宏伸
「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第二次意見)」に対する意見
障がい者制度改革推進会議の皆さまにおかれましては、障害者権利条約の批准に向けてわが国における障害者制度改革に積極的、精力的な取り組みを行っていただいておりますことに深く感謝申し上げます。
またこの度は、第二次意見(素案)を取りまとめいただきありがとうございます。第二次意見についてならびに第一次意見における言葉の定義等につきまして,日本発達障害ネットワークからの意見を提出させていただきます。ご検討を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
今回の議論のあり方に関わる全体的な意見
非常に速いペースで、観点が提起されているため、発達障害当事者や関係者の権利を守っていくための意見表明をすることが十分にできない状況です。もっと十分な議論の時間をもち、意見集約をしていただくことを強く要望します。
項目に関しての意見
Ⅰ.3.2)労働及び雇用についての意見
現在、雇用義務制度(雇用率制度)の対象となる障害の範囲が知的障害者、精神障害者、身体障害者の範囲に限定されているので、発達障害やその他の障害も対象となるように、障害種別を撤廃し、あらゆる種類の障害者に拡大するべきである。
Ⅰ.3.5)障害原因の予防についての意見
ここで使われている「障害」とはなにを指しているのかが不明である。後天的な四肢障害や,聴覚障害,視覚障害も「障害」であるし,生来的な先天的な四肢障害や視覚,聴覚の障害も「障害」となる。また発達障害という表記に使用される「障害」もある。まず,どのような定義,視点からこの用語を使用したのかを明らかにすべきである。
また、予防概念が、時代遅れの前時代的な概念定義に根拠を置いており、世界的な考え方から乖離している。障害の予防という視点に対して,優性保護とか,差別とかの次元ではなく,国民の意識の向上,種々の障害に対して生じやすい生活の困難さの低減といった取り組みの方向性(例えば,駅のエレベーターの有無や介助員の常備)が議論されるべきである。
障害が存在していても,日常生活上での困難さを出来るだけ早期に,極力減少させることが,障害への早期対応になると思われる。つまり、健診体制の整備とか,その後の親子へのメンタルヘルス支援,具体的養育の場の提供,経済的支援が,予防となる。それは,決して「一般公衆衛生施策」ではなく,特別に配慮された「優れた発達支援」でないといけないはずである。
この項目に関しては、早期発見、早期対応が不可欠な発達障害領域の意見を尊重すべきである。早期に生物学的な脆弱性が明らかになることで、子育てのなかでの必要な工夫をすることが可能になり、子ども虐待やそれに伴う二次的な精神疾患リスクを低減できることは学術的な知見からも明らかである。推進会議の認識は明らかに現状のエビデンスに反しており、こうした認識をもとに、必要な予防の観点を矮小化させることは未来の子どもたちの可能性を狭め、偏見を助長するものに なることを懸念している。
さらにこの機会に,子どもの生活保障は,国家的責任のもとで行われるべきであるため,教育・福祉・行政が連携して途切れない支援を実施するために,国が果たすべき使命を明確に提言するべきである。
Ⅰ.3.7)障害児支援についての意見
【障害児にとっての最善の利益】に関して、家族が必要な支援を拒否する場合、障害児本人にとっての利益を最大にするべく、本人への支援が実現する体制をもつことは重要である。「障害」に対する偏見から支援を拒否する場合に、必要な理解を得つつ、必要な支援を提供できる枠組みをもたなければならない。
第二次意見については、他にも議論すべき点が非常にたくさんあるが、時間的な都合で以上とする。また、第一次意見の以下については、第二次意見の取りまとめにあたり考慮をお願いしたい。
1.言葉の定義や内容を明確にすべきこと
1.1 「地域」「地域での生活」という言葉・・・多頁
意見:この言葉の意味するところを別項で説明すべきである。
「地域での生活」は、「希望する地域で(あるいは、自ら選択した地域で)、その地域の住民の一員として生活すること」と丁寧に説明すべきである。
「住みたいと思うところに住む」ことを明文化すべきである。
理由:言葉の定義がきわめて不明瞭なため、解釈が自由であり、障害者に不利な施策につながったり、特定の生活様式を押し付けられることになる。
たとえば、「地域」が「住民票のあるところ」や「主な生育地」と解釈されると、入居者の出入りが多い都会のマンションが生育地の人の場合に、そこでの生活が幸せな「地域社会の一員」に結びつくとは限らないのである。(都会では「地域社会」そのものが崩壊している。)「住みたいと思うところに住む」ことが重要と考える。不明である。
1.2 「施設」という言葉・・・多頁
意見:この言葉の定義もきわめて不明確である。言葉の意味するところを別項で説明すべきである。
ここでいう「施設」とは、「集団生活でかつ日中も地域社会との交流が少ない管理統制された生活を強いられるところ」として説明すべきである。
理由:「地域での生活」の反対語として、「施設での生活」や「病院(社会的入院)での生活」が想定されているようだが、後者はほぼ特定の生活様式を指しているので理解できるとしても、「施設での生活」は特定されない。施設とは一般的には構造物の名称であり、規模も運営もさまざまである。
また、「施設での生活」が強制されたものと認識されているようであるが、それは運営の問題であって構造物の問題ではない。
一般の集合住宅であるマンション、アパート、寮、シェアハウス等々も一定の社会的掟のもとで暮らすのであるから施設的ともいえる。「施設」という言葉の意味する生活スタイルを定義すべきである。
1.3 「障害を理由とする差別」という表現・・・12、16 頁など
意見:「障害を根拠とした差別」、「障害が理由となっている差別」にする。
「理由とする」の表現を使うのなら、別項で「理由とする」が主観的な意味ではないことを明文化すべきである。
理由:日本語の「理由とする」という言葉の意味は二通りある。理由付けという意味と、客観的な原因になっているという意味。とくに、雇用職場の場合の差別では、雇用側は「障害を理由としなければよい」、「個別具体的行為を理由にすればよい」と解釈されかねない。そのため、差別禁止に有効とは言えない。
2.政策の方向性について
2.1 「地域で暮らす」権利ではなく、「暮らす場所を選べる」権利に・・・9、13頁など
意見:法で特定の生活を善とすべきではない。気の合う人(たち)と、一定の枠のある生活のほうが心地良い障害者もおられるのである。空間が広い現在の施設のようなところが落ち着く障害者もおられるのである。様々である。
9頁の「誰もが有する地域」という表現は明瞭ではない。「希望する地域」にすべきである。
理由:そもそも理不尽に強いられた入居生活の問題は、強いられていることが問題なのである。入所施設や病院に原因があるのではなく、現在、選択できる他の生活資源がないことが問題なのである。有効な資源がないままの強制移住は自己選択に反する。現在は、障害者が施設(前述の定義)以外で暮らしたい方が多いと思われるので、街の中に障害者の住まいを作ることを推進する。しかし、法で「○○で暮らす」を方向付けることは、結局、措置制度に戻るのと同一である。多様な選択肢を用意することが障害者の住む権利を保障することになる。
2.2 23頁の「一般施策を踏まえつつ」は意味不明であるとともに、この項が言わんとするところが表現されていない。
3.さらなる検討が必要な項目
3.1 障害の定義や擁護される対象の検討
意見:法律で擁護される範囲を決めることは重要であり、社会モデルに移る際にはこのことがいっそう問題になる。
障害は生活のあらゆる場面で出るわけではない。生活の特定の場面で困難をもたらす。私生活では困難はなくても、他人との関わりがとくに必要な職場や社会生活で困難が生じる障害もある。障害の定義においては、このことを考慮した定義にする検討が必要である。
3.2 緩和手段の関係・・・9 頁
意見:合理的配慮を行なう対象となる障害者であるかどうかの判断にあたって、緩和手段を考慮しないことを法で明文化する。
理由:緩和手段を使っているかどうか、障害の現れ方が時々か、障害が一時的に緩和していたり潜在化しているか、を障害の決定において考慮しないことを明文化すること。
3.3 自立、自己選択、コミュニケーション
意見:障害者が権利の主体であり、様々なことを自ら選択することをあらゆる障害においても保障するための検討がされていない。とくに、判断したり、判断するための適切な情報を取捨選択したり、施策提供側に相談したりするためには、言語能力のみならず、脳の判断や推論の能力、あるいは非言語(非音声ではない)コミュニケーション能力などが備わっていなければならない。その部分に障害がある方々をも念頭においた権利の法制化が必要である。非音声言語については記述されているが、多くを占める知的障害、自閉症などの発達障害、高次脳機能障害、精神障害などに対する自己決定・自己選択を支える仕組みの検討がされていない。この領域こそ、歴史的にも措置や分離、特定の生活の押し付けがされてきたことを考えれば、世界の先進事例を参考に推進会議で検討しなければならないもっとも重要なことである。
文言上は権利条約にあるように「自己決定を尊重する」ということとし、法律で「尊重する」ことを保障する仕組みを用意するということであろう。
その意味で31 頁の訴訟手続きの記述は適切と考える。
以上
第28回障がい者制度改革推進会議(H22.12.13) 久松委員参考資料
障害者制度改革推進会議担当室御中
2010年12月1日
特定非営利活動法人CS障害者放送統一機構
理事長 高田 英一
障害者の情報へのアクセス権保障について
国連「障害者権利条約」は、「障害のある人が新たな情報通信技術(情報通信機器)及び情報通信システムに関する設計、開発、生産及び分配を、それらを最小の費用でアクセシブルにするようにして促進すること」を国の義務としている。(9条のg)
障害者のコミュニケーションについて、「障害のある人が自立して生活すること及び生活のあらゆる側面に完全に参加することを可能とするため、―――物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信技術、情報通信機器及び情報通信システムを含む)――にアクセスすることを確保するための適切な処置をとる」ことは国の責務である。(権利条約9条の 1)
社会生活に参加する権利、政治に参加する権利、教育を受ける権利、医療を受ける権利、文化、芸術、スポーツに触れ楽しむ権利などが全ての国民=障害のある人々に保障されるための必要な処置(合理的処置を含む)を国と関係機関は取らなければならない。現在、議論されている障害者基本法は既存の情報アクセスのための放送・通信法など各種法律をも拘束する法でなければ意味をなさない。
この提言は、障害者の情報アクセス権を障害者基本法によって各種法律の面においても保障すべき課題についての問題提起としている。
情報アクセスの権利保障
1、 放送のバリアフリー化について法的に規定すべき具体課題
放送は、国民にとって主要かつ重要な情報源である。放送は世界的なデジタル化の時代に入り、情報量の拡大、情報の高品質化、付加価値の拡大などについて、障害者を含む全ての国民が享受するためにバリアフリー化を同時に進めなければならない。その責務は国と事業者が担っている。放送・通信法など関連法律と共に、障害者対応として法的に明確に規定することが必要である。
新放送・通信法は、放送と通信の融合の新しい時代の要請に応えるために整備されようとしている。そもそも放送のバリアフリー化は、コンテンツと設備を包括的に検討する必要があるにも関わらず、その改訂の過程において、コンテンツと設備の双方にかかわるアクセシビリティに関する検討がほとんどされておらず、ましてやその当事者の関与が保障されていないことは重大な問題である。
将来を見据えて今日までの法整備の問題点とこの間の教訓を生かし、障害者の関与を含む、恒久的な放送のバリアフリー化を実現する法的拘束力を持った処置をとることが不可欠である。
聴覚障害者対応の課題
聴覚障害者には音声の他、字幕、手話、遅延再生などが必要となる。
音響の中の人の音声の増幅、音質の変更、Wifi 出力、磁気ループ出力、遅延再生などを対応する技術の確立と、そのための必要性を明確にした、規格を制定すること。
「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」に基づく、キー局、地方局、その他放送局の 字幕達成最低基準を明確にし、また段階的達成計画を持つことを含め、放送局事業運営の 許認可基準とすること。
また、ラジオ放送番組も字幕放送の対象とすることを求める。
手話の付与について、手話の常時付与を不可能としているARIB 基準RT.B14 を廃止 し、クローズドサイン技術開発を国の責任で行うこと。
唯一、手話の常時付与放送を行っている「目で聴くテレビ」方式による放送を、補完放 送として位置づけ、国の責任による助成など「合理的配慮」「処置」を行うこと。
ARIBの不具合基準を廃止することは重要であるが、それによっても、現在の日本の デジタル放送システムの現状では、手話を常時放送するクローズドサイン放送を実現する ことはできない。上記補完放送と共通の課題として、それを補う手話アニメーションの開 発など代替え処置の必要性を明確にし、その技術開発に国が支援することを明確にする。
視覚障害者対応の課題
視覚障害者に対する音声解説を付与した放送は、「指針」目標そのものが10%であり、視覚障害者のアクセス権を保障する方向を目指すものとはいえず、適切な目標を掲げ、目標の達成は、国と事業者の義務とする。
現状のデジタル放送では、5.1 サラウンド放送時には音声解説を放送できない。5.1サラウンド放送が増えている現状のもとでは、解説放送の実施はますます困難になっており、常時放送することを可能とする技術開発と規格化による解決が必要である。
国の責任で解説放送を常時可能とする、技術開発を急ぐこと当面の政府責任として明確にすること。
あまりにも少ない解説放送の時間数を引き上げるために、手話と同様に解説放送が可能な「目で聴くテレビ」による放送を補完放送として位置づけ国による支援義務を合理的処置として明確にする。
デジタル放送のデータ放送は視覚障害者が全くアクセス出来ない。視覚障害者にも認識できるアクセス方法を保障するため、データ放送を音声認識に変換する技術開発を国と放送事業者の責任で行う。
視覚障害者が操作できるテレビジョン開発が部分的段階でとどまっている。視覚障害者対応のテレビジョンを開発・供給する義務を製造者に課すこと。
これらの機器の開発の必要性を明確にし、国と事業者の責務を明確にする。
法的処置
- 障害者の放送へのアクセスは権利であること、それを国と事業者が保障する義務があること明確にする。
- 字幕放送・手話放送・解説放送などの目標達成のために、補完放送の位置づけと国による支援を明確にし、現実に存在する手段への「合理的配慮」「処置」をとる責務が国にあることを明確にする。
また、事業者の努力だけでは実現困難な手話付与と解説音声放送には、補完放送によ るカバーを明確にする。 - 字幕放送・手話放送・解説放送などの付与責任は放送局の許認可規定とする。
- 放送、通信のバリアフリー化の障害となっている、各種法規、技術規定は廃棄する。
- 受信装置などのバリアフリー機器の開発と「新たな負担の発生しない」機器の開発・製造・配布は国の責任でおこなう。
- 放送に関するあらゆる検討課題に障害者の意見を反映させる制度を確立する。
- 障害者によるモニター制度を設置し、当事者の意見反映の機会を明確にする。
2、情報アクセス支援者の養成の制度化
情報アクセスの保障のためのリアルタイム字幕制作者、手話通訳者、解説制作者は通常の地域生活における字幕入力、手話通訳、音訳者とは異なる専門性と倫理性が求められる。
これらの情報アクセス支援者の養成に国は責任をもち、養成事業を行う事業者を支援する制度を設ける。
コミュニケーション支援者養成のための遠隔地教育の確立
障害者のコミュニケーションにとり、最も重要でまた最も遅れているのは、支援者養成である。最も進んでいる手話通訳の場合でも、地域間格差など、大きな問題を抱えている。特に、視覚障害者に対するコミュニケーション支援者の養成に大きな進展が見られない。
視覚障害者をサポートする音訳者研修会は、従来、年に一度、東京や関西で2泊3日で開催されてきた。しかし、対象者の多くが主婦や勤めを持っている人で、宿泊の伴う研修会への参加は、相対的に高齢者が多く、結果的に支援者の少なくなることは全ての障害者に共通した問題となっている。適切な研修を受ける機会をたくさんの人が受けるには、どうしても通信手段を利用した遠隔地研修が必要である。
視覚障害者のための字幕オペレータ・ガイドヘルパー・読み書き支援者・代読・代筆支援者養成、知的障害者の意思決定のための代弁・介護者の養成、盲ろう者向の通訳介護者養成など・各種研修を通じて早く必要な支援者を大量に育てるために、実証実験済みの遠隔地教育のための処置を国に求める。
遠隔地教育が有効手段であること、国の支援義務を明確にする。
3、その他の情報へのアクセス権の保障
教育機関、交通機関、医療機関、その他公共に開かれた施設などにおける、情報とサービスへのアクセスの保障(字幕や音声表示などの保障)。
書籍などのデジタル化は、急速に進んでいる。出版された書籍の自動デジタル化機器も誕生している。Ipadなどの誕生で、これまでになく、障害者のそれらへのアクセスは容易になりつつある。次世代デジタル機器の誕生によって、アクセシブルに障害者が情報を得るため、機器の開発、運営に対する国の支援を義務化する
次世代システムによる、アクセス権の保障と必要機器の給付などを制度化する。その保証の中には、著作権の権利制限、フエアーユース規定を導入する。
4、情報アクセス保障用電波の確保
無数の電波が様々な用途に利用されているが、障害者が専用して使える電波は、FM周波数帯に補聴用電波帯域が確保されているだけであり、広く情報アクセス保障用の電波は存在しない。
地上デジタル放送の完全移行に伴って空きが発生するが、障害者の情報アクセス保障に利用できる電波帯がないのは国民全体の財産である電波の利用という点でも巨額の国費を投入した事業の結果としても国民の理解が得られない。
補完放送用テレビ用電波の確保は国が責任を持って保障すべきである。
以上