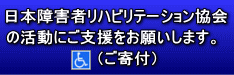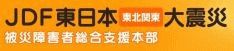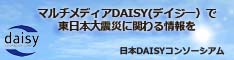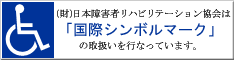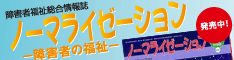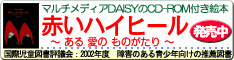障がい者制度改革推進会議 第32回(H23.5.23) 長瀬修委員提出資料
長瀬修委員 提出資料
障害者の権利委員会
第5会期
ジュネーブ、2011年4月11日―15日
障害者の権利条約と震災
長瀬修
国際障害同盟
全日本手をつなぐ育成会・国際育成会連盟
議長、そして、この重要な障害者の権利委員会の委員の皆様、国際障害同盟(IDA)を代表して発言する機会を頂き、ありがとうございます。私は国際障害同盟に所属する国際育成会連盟の一組織である全日本手をつなぐ育成会の長瀬修と申します。
3月11日に日本の東北地方を襲った震災について少しお話させて頂きます。今日はまさに、この災害からちょうど1カ月であり、多くの人が黙とうを捧げています。多くは日本人ですが、それ以外の国の方も含め、これまでに27000人以上の人が死亡もしくは行方不明となっています。
日本の者として、この機会に世界中から私どもに寄せられた、すべてのお見舞いの言葉と支援に対して、心からの感謝の気持ちを表します。また、原子力発電所から漏れている放射性物質による環境破壊について、一個人として謝罪いたします。
先週、私は福島の隣の宮城におり、日本障害フォーラムが設置した障害者の支援センターで支援員の活動をしておりました。日本障害フォーラムは、国際障害同盟の会員組織を多く含む、日本の障害組織の全国的ネットワークです。今、私たちの組織は全力を尽くしています。
宮城で津波の被害を受けた沿岸部を目の当たりにした時、自分の目を疑いました。被災の状況は、想像を絶し、筆舌に尽くせません。しかし、そこで私は障害者、家族、支援者、そして、市民全般がこの試練に立ち向かおうとする姿に心打たれました。
母親がいます。30年前の地震の際に、公立の保育所は閉まってしまいました。そのため、まだ幼かった知的障害の娘さんは家にいるしかありませんでした。今は通所施設を運営しているその母親は、必要としている人のために、自分の施設を開け続けるという決意を持っています。3月12日、まだ電気もガスもない時点で、その施設は開いていたのです。その上、家族や地域の人のための食料の提供までも行いました。
全盲の男性がいます。元炭鉱夫で80代後半です。自宅にいた時は、家や近所は頭の中に入っていて、自ら動くことができました。しかし、まだ新しかった自宅は津波で失われてしまいました。学校に避難し、今は体育館にいます。頭の中の地図は役に立たなくなってしまい、お孫さんをはじめとする家族からの支援が必要になっています。そのため、トイレにあまり行かなくてすむよう、水分をできる限り摂らないように努めています。合理的配慮、地域での支援、そしてアクセシビリティ、このどれもが欠けてしまっています。
これらはあくまで例に過ぎません。そして、勇気を示している人がいる反面、疎外されている人がいます。インクルージョンの事例があれば、排除と差別の事例があります。私たちの社会の強さと弱さ、その両面が示されています。この震災はインクルージョンと排除を何倍にもはっきりと露わにしています。
この震災は、障害者の権利条約を現実のものにすることの大切さと、締約国とこの委員会が持つ重要な責任を改めて、私たちの心に刻みました。例えば、11条の危険のある状況と人道上の緊急事態、9条のアクセシビリティ、19条の自立した生活と地域社会へのインクルージョン、32条の国際協力だけでなく、障害者の権利条約全体を現実のものにしなければなりません。私たちは、その大切さを痛みを伴いながら知ることになりました。私たちが学んでいる教訓が、この委員会の任務に活かされることを願うのみです。
最後になりますが、もう一度、国際社会からのすべての連帯のメッセージと支援に、日本からの心からの謝意を示します。そして、障害者の権利条約を実施するという大きな課題に、私たちの友人であり仲間である皆様とこれからも一緒に取り組ませていただきたいと思います。
発言の機会を頂き、ありがとうございました。
((毎日新聞朝刊10面2011年4月28日))
○これが言いたい
防災とバリアフリーを経済コストで測るな
被災障害者の危機は人災だ
福島 智
東京大先端科学技術研究センター教授
((顔写真))
空気ボンベを背負い海に潜るスキューバダイビングは、よく知られている。では、地上で暮らしながら、常に「目に見えない海水」に潜った状態で生活している人たちのことをご存知だろうか。重い病のために、酸素吸入器や人工呼吸器を常時使用している人たちのことだ。
仙台市太白区の土屋雅史さんもその一人で、4年前、全身の筋力が徐々に衰える筋萎縮性側索硬化症(ALS)を発症した。人工呼吸器やたんの吸引器が命綱だ。
53歳の今、全身で動くのは眼球だけだ。その目の動きでパソコンを操作し、一文字ずつ言葉を刻み、この度の震災体験をつづった。
「突然大きな横揺れ、すぐ停電。呼吸器の非常アラームがビーッと鳴った」
土屋さんが普段「潜水」を続けていられるのは、電気によって人工呼吸器などが動いているからだ。しかし停電になれば、頼りはバッテリーだけとなる。いわばバッテリーの残量が、「潜水時」の空気ボンベの残量だ。
「いきなり吸引器が止まった。40分のバッテリーだ」
幸い、土屋さんは周囲の人の綱渡りのようながんばりで助かった。他にもきわどい例は多く、今月初めには停電の影響で亡くなった人もいた。
これらの人たちが経験した生命の危機は、天災ではなく人災に属する。つまり、地震による長期の停電を、現行の福祉・医療施策が想定していなかったからである。
ところで今、防災や原発の関係者の口から、「想定外」という言葉がよく出される。それを聞きながら、私は「防災とバリアフリー」の共通点を考えた。
たとえば、障害を持つことは多くの人にとって想定外の出来事だろう。しかし、個人にとって想定外であっても、ある社会の中でどういう障害がどの程度の頻度で発生するのか、その全体的傾向は想定できる。その想定に従い、どんな人が人生のどの時期にどのように特殊な障害を持っても、きちんと生活できるように、最善の社会的取り組みを目指すのが、バリアフリーの基本理念である。
一方、地震や津波など自然災害も、いつどこでどんな災害が発生するか、正確には想定できない。しかし、歴史的・地理的観点で、どんな規模の災害が発生するか、その全体的傾向は想定できるはずだ。いつどこでどのようにまれな災害が発生しても、最善の社会的取り組みを目指すのが、防災の目標だろう。
*
両者には、さらに二つの共通点がある。第一は、防災もバリアフリーも安全と安心、言い換えれば、人の命や夢や希望を守る営みだということであり、第ニは、いずれも経済的コストがこれらの取り組みへの制約要因になる点だ。つまり、発生頻度の低い障害や災害であればあるほど、それらへの取り組みは「コスト的に現実的ではない」とされてしまうということである。
しかし、これはおかしな発想だ。本来命や夢や希望は、コストを計測できない価値である。それを経済的コストとてんびんにかける発想自体、根本的に誤っていないか。
この度の大震災を経験した日本は、従来の物質的な豊かさとしての経済成長を目指すのではなく、人の命と生活の真の豊かさに力点を置いた、社会・経済・科学技術の発展を目指すべきである。
3・11を人間中心の社会に向かう新たな日本のルネサンスの契機とすることこそ、生を断ち切られた人々の魂に報いる道なのだと思う。
ふくしま・さとし 9歳で失明、18歳で聴力も失い、盲ろう者となる。専攻は障害学、バリアフリー論。博士(学術)。
「これが言いたい」は毎週木曜日に掲載します
http://mainichi.jp/select/opinion/iitai/news/20110428ddm004070030000c.html
-----end