シリーズ/市町村障害者計画
台東区障害者福祉計画
中西由起子
台東区は東京23区のなかで面積が10Km2あまりと一番小さいが、NHKで放映されていた『ひまわり』の舞台となっている谷中や浅草、上野公園など古くからの名所をたくさん抱えている。その大きさや、歴史を残す下町の町並みや公園や墓地の緑あふれる落ち着いた雰囲気から、住民の声が行政にすぐにも届きそうな印象を受ける。
台東区での障害者プランに基づいた市町村障害者計画の策定への取り組みは早かった。すでに平成2年には「台東区長期総合計画」のなかで障害者の自立と福祉拡充について論じられていた。それに基づいて平成六年には、高齢者、障害者、医療などの分野をカバーする、平成2~12年までの「台東区地域保健福祉計画」が策定されていた。今回の計画づくりの基本方針がすでに存在していたのである。
平成5年には区内の心身障害児・者の実態調査が実施され、ニーズの把握が行われた。平成7年には策定のための3つのグループがつくられ、6月から活動が始まった。「台東区福祉計画検討委員会」は、冨安芳和慶應義塾大学教授を長として、学識経験者、民生委員代表、障害者団体代表、民間法人代表に区職員を加えた、計19人から編成された。「作業部会」は、そのうちの学識者と区職員を中心につくられた。「民間作業部会」のほうは、障害当事者の団体3つを含む、区内の障害関係五団体の推薦を受けた者から成っている。作業部会と民間作業部会のそれぞれ七回にわたる討議結果は委員会に報告され、検討委員会で計画の概要が絞られた。
計画は本年3月に最終的な完成をみた。区民の声がより反映されやすくかつ関係者の勉強の機会ともなるようにと、他の市町村で時にみられるような外部機関への委託は避けられた。区職員の手づくりの作業から始まったとのことである。
3つの基本的視点と7つの重点課題
「台東区障害者福祉計画」は、障害者が一般社会で普通の生活が送れるような条件整備を目指す「ノーマリゼイション」、障害者の教育、保健、福祉政策の総体とみなされる「リハビリテーション」、トータルケアシステムの構築を不可欠な条件とする「サービスの総合的提供」という3つの基本的視点に立って、以下の7つを重点課題としてあげている。
1 地域交流の促進と啓発活動の推進
(1)地域交流の促進
ア 福祉教育の推進
イ 区民との交流会の促進
ウ 開かれた施設運営を進める
エ 親善・交流の促進
(2)啓発活動の推進
ア 広報活動の展開
イ ボランティアの育成及び研修
ウ 地域福祉活動の支援
エ 区職員の研修
2 障害者施設の体系的整備
(1)松が谷福祉会館の再編
(2)障害者福祉課の見直し
(3)施設運営主体の責任と役割分担の明確化
(4)障害者施設の役割分担と利用基準
ア (仮)障害者福祉センター
イ 幼児通園施設
ウ 通所施設
エ 生活施設
オ 生活訓練施設
(5)新しい課題と施設間の連携
ア 授産作業の連携
イ 移送サービスの連携
ウ ショートステイの連携
エ 施設の適正運営と適正配置のための各種会議の設置
オ 入所型(24時間)施設の検討
3 高齢障害者への対応と障害者の高齢化対策
(1)障害者の高齢化と高齢期障害者の相関
(2)高齢障害者への対応
ア 法体系による縦割り事務の改善
イ 法体系から生ずる谷間の改善
―ショートステイ事業を通して―
ウ 縦割り事務の改善による効率化
―ホームヘルプサービスを通して―
エ 成人・壮年期受障者への施策充実
(3)障害者の高齢化対策
(4)資料
4 専門職の有効活用と支援者の育成
(1)専門職の有効活用
ア サービスシステムの変更
イ 福祉分野における専門職の現状
ウ 専門職活用の視点
エ 専門職の活用の具体策
オ 専門職の研修体制
カ サービス提供に関する課題
(2)支援者の育成
5 移動・移送手段の整備とシステム化
(1)障害者の移動
ア 障害者の交通バリアフリー
イ 公共交通とSTサービス
ウ 情報ソフトの開発
(2)台東区のSTサービスの現状
ア 障害者施設の送迎
イ ドア・ツー・ドア運行
ウ 固定ルート運行
(3)移送の整備とシステム化
ア 送迎バスの有効活用
イ ドア・ツー・ドア運行のシステム化
ウ 移送の集中管理システム
エ 他機関との連携
6 通信・情報システムの導入
(1)障害者自身の自立社会参加のための通信・情報システム
ア 通信・情報の社会的基盤整備
イ 既存情報システムの充実
ウ 情報ソフトの開発
(2)障害者福祉サービスの情報アクセス
(3)障害支援のための情報ネットワーク
(4)情報機器購入の補助
(5)移送交通システムと通信・情報ネットワーク
7 総合相談支援システムの構築
(1)総合相談支援システム
ア 発達支援機能
イ 自立生活支援機能
(2)地域支援システムの確立
ア 専門家の役割
イ 支援者の役割
ウ 支援ネットワーク
障害者のすべてのライフステージに及ぶような計画を策定するためには、既存の法体系や行政組織を見直していかなければならない。「計画の策定にあたって」で記されているように、そのような計画は長時間の作業を必要とする。医療や教育を含む関連領域との調整などは今後の課題とされている。数値目標に関しては、とりあえず平成9年度に改正される「長期総合計画」で示されることになっている。
行政の縦割りを越えて
行政の縦割りを越える計画が実行できるか否かが、今後の大きな問題である。計画の策定段階から縦割りの弊害に関する関係者の問題意識は強かったらしく、例えば小さなことでは朝夕の送迎に使用されている施設のバスの日中の他部門での利用にまで縦割りを越えた計画が随所で語られている。区でも財政状況が厳しくなっているなか、効率的なサービスの提供を考えない限り、計画の推進は難しくなろう。
推進役となるのは、台東区障害者福祉施策推進協議会、障害者福祉課内の計画推進担当、障害者福祉計画推進検討チームである。推進協議会は同じく冨安氏を委員に加え、心身障害者団体の代表を含めた21人から組織され、2年に1度福祉計画の推進状況をまとめることになっている。検討チームは企画課や予算課、社会福祉協議会を含む庁内の関連する部署から成る。図は協議会を中心とする推進体制を説明したものである。
図 障害者福祉計画推進体制
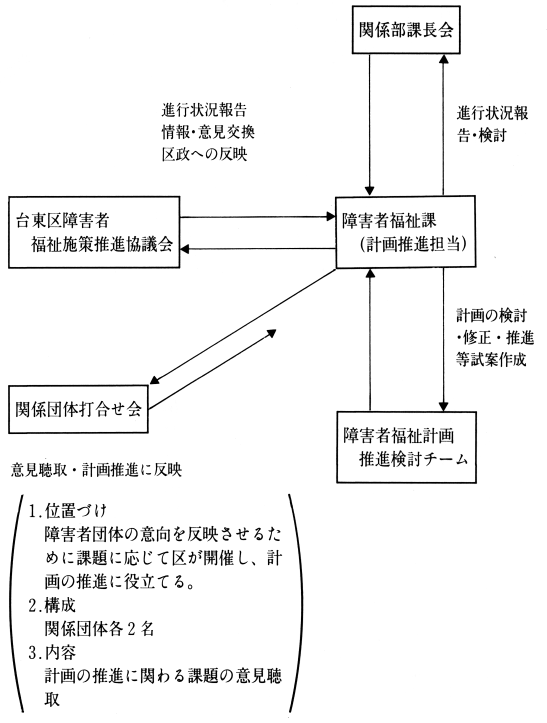
1 位置づけ
障害者団体の意向を反映させるために課題に応じて区が開催し、計画の推進に役立てる。
2 構成
関係団体各2名
3 内容
計画の推進に関わる課題の意見聴取
ちなみに台東区は23区のなかで最も高齢者の割合が多い。高齢者の問題は、一般的には地域保健福祉計画で論じられているが、高齢障害者問題は重要であるので、障害者福祉計画では多くのページをさいている。
計画の実現に向けて
ジョブコーチやパーソナルアシスタント、ソーシャルロールバロリゼーション、バリアフリー、CBR、パイロット・ペアレント、ST(スペシャル・トランスポート)サービスなど今のところ研究者の間でしか使われていない、国連の障害者に関する「基準規則」でいわれる障害者の機会の均等化を保障する横文字がこの計画には登場する。理想的であるとの批判もあると聞いたが、ある意味ではそれがユニークな台東区の計画の特徴といえよう。これらは、障害者の自己決定と自己管理の概念に裏打ちされている、最先端の哲学を伴った専門用語である。
その哲学に忠実であるためには、今後は、計画実施の過程で策定段階の時よりもさらに多くの障害者を入れた体制づくり、つまり台東区障害者福祉施策推進協議会の半数以上が障害当事者で占められるとか、行政の窓口での当事者のニードを最もよく知る障害者自身による応対などが当然必要とされるであろう。
それらは一朝一夕には実現不可能なことかもしれないが、障害者福祉課のイニシアチブにより、計画の実施段階で一歩でもその形態に近づけるように願っている。そのような草の根レベルでの努力が重ねられることによって、ぜひ来たるべき21世紀を障害者の世紀としていきたい。
最後に快く種々の質問に答えていただいた台東区の松野晋障害者福祉課長、同課の船越知行福祉主査にお礼を申し上げる。
(なかにしゆきこ アジア・ディスアビリティ・インスティテート[ADI]・本誌編集委員)
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1996年10月号(第16巻 通巻183号) 44頁~47頁
