THE TOKYO GAMES FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
PARALYMPIC
TOKYO 1964
パラリンピック 国際身体障害者スポーツ大会 写真集
No.3
参加することに意義がある
〈第一部 国際競技〉
オリンピックの再興者であるクーベルタン男爵が云った「参加することに意義がある」のことばは、むしろ、パラリンピックにこそふさわしいものであろう。身障者の競技会であるパラリンピックは、競技の記録をきそうのではなく、この競技会に参加して、自分の能力を高め、お互いに励ましあうことである。
第1部競技種目

| 洋弓 | 第5会場 |
| ダーチヤリー | 第5会場 |
| 槍正確投 | 第1会場 |
| 槍投 | 第1会場 |
| 砲丸投 | 第1会場 |
| 円盤投 | 第1会場 |
| 棍棒投 | 第1会場 |
| 車椅子競走 | 第1会場 |
| 車椅子リレー | 第1会場 |
| 車椅子スラローム | 第1会場 |
| バスケットボール | 会場3,4 |
| 重量挙 | 第2会場 |
| スヌーカー | 第2会場 |
| 卓球 | 第2会場 |
| フェンシング | 第7会場 |
| 水泳 | 第6会場 |
| 五種競技 | 会場1,5 |
| 表彰 | 第3会場 |
洋弓
騎士道華やかなりし頃……を思わせるのが洋弓場のムードである。その意味で、神宮の森を背景にしたことは効果的だった。真剣な射手たちの表情、ピュッと風をきる矢羽の音、この一瞬だけは、すべてを忘れる。

|
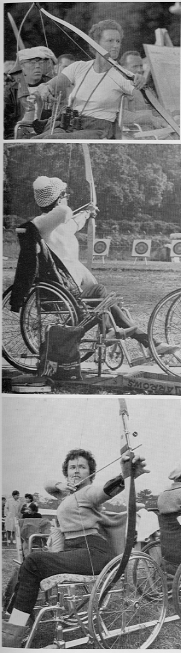
|
|

|

|
|
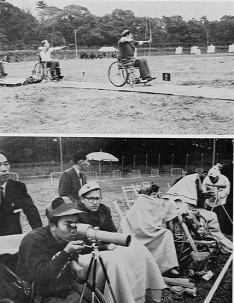
|
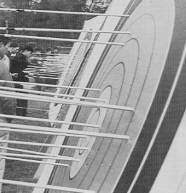
|
|
洋弓(アーチャリー)は、上肢、肩、体幹の筋力増強によく、精神集中に役立つ。アーチャリーの種目は、1年以内の初心者が行なうセントニコラス、4人1組の団体競技でやるコロンビア、アルピオン、それに国際弓道連盟の4つのラウンドがある。標的(上)の直径は1.22m、各ラウンドによって距離は違うが、1人6本の矢を射って得点をきそう。標的は中心が金色(9点)以下外側へ赤(7)淡青色(5)黒(3)白(1)で合計採点される。なおこの競技のF・I・T・Aラウンド男子団体で日本チーム(安藤、松本、斉藤)は2位。
ダーチャリー

|

|

|

|
||
各国2人で編成されたチーム2組が出場する。マトは1.22m、距離は13.7mのところから交互に射つ。1回1人3本ずつの矢をうって501点をきそうもの。上左、上右は優賞したローデシアのハリマン・GHマン組。下左は南アフリカ、右下はドイツの各選手。
ご熱心にご観戦皇后・皇太子・皇太子妃殿下
11月11日、会場においでになった皇后陛下は、バスケットボールをごらんになったあと洋弓場に移られ、皇太子ご夫妻の間に座わられて、仲よくダーチャリーをごらんになり、日本選手の活躍を期待された。
なお、松本(左下)安藤徳次(右下)組は、よく健闘して三位入賞、銅メダルを獲得した。

|

|

|
|

|

|
槍正確投げ
槍の投てきは、上半身のバランスと腕の力を訓練するもので、槍正確投げは、地面に直径3mのマトを画いて、男子は10mの距離から、女子は7mの距離から投げて命中させるようにする。いずれも日本陸連公認の女子用槍を使った。左上から、イスライル、アメリカ、日本(小笠原文代)、中上オーストリア各選手。

|
 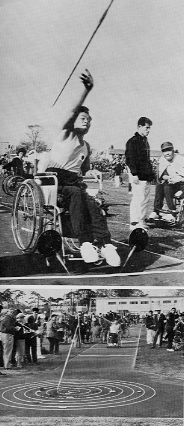 |

|

|
中上から2番目、日本チームは健闘したが及ばなかった。上、桑原、中下、須崎選手。右上、女子槍投A級1位ジルクリスト選手(ローデシア)下右、アメリカ選手。
槍投げ
槍投げは、からだのバランスと腕の力を訓練するもので、槍は長さ2.20m、重さ600gの女子用槍をつかう。障害の程度によって4階級に分けて行なわれる。車イスの上から尾をひいて投げられる槍さきは、みる人の心をつきさすようなすごみがある。

|

|

|

|
左上、アメリカ。右上、イスラエル。左下、オランダ。右下、オーストラリアの各選手。

|

|

|
上左、オーストリア。右上イスライルD級3位。左下、アルゼンチン。右下、アメリカの各選手。
棍棒投げ
棍棒投げは腕の力を強くする。長さ39cm、重さ397gのぶなの木でつくった、トックリ型の棍棒で底に10.7gの金属がついている。これを頭上から投げて距離をきそう。3回投げて最良のものが採用される。

|

|

|
|
上左、ローゼンバーグー選手(イスライル)。右、マルテーノ選手(イタリア)。左下、ウイルキンス選手(アメリカ)。右下、アルゼンチンの選手。

|
  |

|
上左、アメリカ。上右アメリカ。中左、競技用の棍棒。中右、仲間の活躍をみる選手たち。下、棍棒の会場(オダ・フィールド)
砲丸投げ
砲丸投げは男子4kgのもの、女子3kgのものを投げて距離をきそう。障害の程度によって4階級に分けて行なわれる。3回投げて一番よい記録が採用される。一見しただけで、外国選手の体格は、日本選手とくらべものにならないほどよい。筋肉のもりあがった太い腕から投げられる砲丸は、軽く8mはとぶ。

|

|

|
上左、コチェッティ(アルゼンチン)。上右チェロフィー(アメリカ)。左下、パターソン(アメリカ)。右下、クルーティニヤー(オランダ)の各選手。

|

|

|
|
上右、イタリア選手。上左、アルゼンチンのコチェティー選手。下、砲丸投げの会場(オダ フィールド)。 大会2日目のこの日は、曇天で気候も寒く、グランドの選手たちは毛布にくるまれて待機していた
円盤投げ
円盤投げは1kgのものを投げて距離をきそう。試技3回で、最もよい記録を採用する。日本選手もこの競技に参加したが、人種的な体格の相違はどうにもならず、苦斗した。

|

|
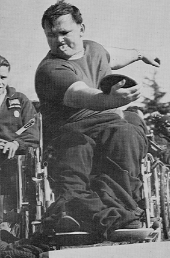
|

|
上左、アメリカ。上右、ローデシア(ハリーマン)。下左、オーストラリア。下右、アメリカの各選手

|

|

|

|
上左、オーストラリア。上右、フランス。下左、日本(杉浦)。下右、イギリスの各選手。
記録は2人で作られる

参加選手たちの記録に挑戦する真剣な表情、緊張した筋肉の躍動は、観るものの胸をうつ。ところでこの大会で特異な感慨を与えたのは、各種の競技に選手の世話をした介添え役の存在であったろう。
たとえば、槍や砲丸、円盤投げなどの投てき競技で、選手たちの車イスの後にうずくまって、車輸をしっかりと押えていたボーイスカウト諸君の姿である。これは全くカゲの力であるが、体格のよい外国選手の反動を止めるのは、たいへんな力がいる。いうまでもなく、普通、投てきに必要な力は、下半身のふんばり(きき足)いかんできまる。これが車イス選手の場合では、その車イスが下半身にあたり、きき足にあたる。そこで車イスがしっかりと止っていなければ、妙技をふるうことができない。したがって、車イスを固定する装置を使う場合があるのだが、東京大会ではその装置が無かったために、介添え役が車イスを固定することになったのだ。
つまり、記録は選手だけで作ったものではなく、介添えと二人でつくられたといってもよい。東京大会では、こうしたカゲの力となって奉仕した人が非常に多いが、それはそのままパラリンピックの精神として、あるいは人間社会の最も善意にみちた面として、永く記憶にとどめられるだろう。
競技部会の活動
競技運営の中核は、国際ストークマンデビル競技委員会(会長グットマン博士)の統轄によるものであるが、競技の実施は“競技部会”によってすすめられた。競技部会は競技本部長(高田秀道)以下、各種目ごとの8班にわかれ、それぞれ記録、設備用具、招集誘導、庶務進行などの各係に組織された。なお、審判をはじめ競技進行に必要な競技人は、東京都体育協会のあっせんで、東京オリンピックに活躍した各種競技団体員の協力を得たものであった。これらに動員された役職員は次のとおり。競技部会本部11名、本部付7名、トラック・フィールド班120名、卓球班106名、重量挙班10名、フェンシング班68名、スヌーカー班8名、弓班67名、水泳班88名、バスケットボール班93名。その他にボーイスカート諸君などの協力があった。

|
|

|

|

|
|
なにしろ体格の立派な外国選手、その反動を止めには、大変な力がいるし、呼吸がピッタリと合はなければならない。空腹ではとてもできる仕事ではない。上、イギリス、フリント選手。中左、オーストラリア、オブライン選手。(女子槍C組2位)。中右、アメリカバレッシー選手(女子円盤A級1位)。下、イタリア選手。
車イススラローム
車イス競技は、車イスの操作と注意力、順応性などの訓練に役立ち、選手たちの日常生活に密着したゲームである。
車イス競技の一つ、スラロームは、全長84mのコースの旗門を、ちようどスキーの回転競技のように通過する。白旗は前進、赤旗は後退してくぐり抜ける。さらに2カ所の障害物があって山形、平板形のむづかしいコースをとおりぬけるタイムレースである。

|
|

|

|

|
|
上、スラロームの全コース。中左、日本、高野選手。中右、フランス選手。下、イタリア選手。

|

|
上、難所をうまく行くイスライル、ガリーッキー選手。左、日本、提選手。下、開会式でSMG旗の旗手をつとめたママさん選手、小笠原文代さん。最大の難所、平板台を降りるところ(左)で、前方にバッタリと転倒。ハッと思って介添え役がかけよる(右)。スタンドでは二人のお嬢ちゃんがハラハラ。しかし健闘よく女子4位に喰いこんだ。最下左、日本、菅選手のゴール。最下右、オーストラリアのオブライエン選手、女子3位。
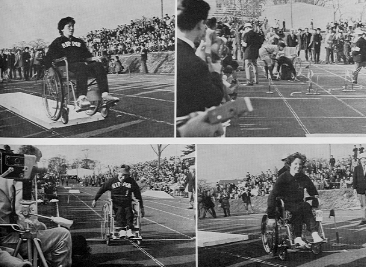
|
車イス競走
車イス競走は60mの直線コースを競走するもので、胸髄9以上のマヒとそれ以上のマヒ者に分けて行なわれる。腕によりをかけて、車輪を回転させる素早さは、相当の訓練と技術が必要である。
上から下へ、車イス競走のスタート。コース全景。スタートダッシュ。ゴール直前。

|

|

|

|
車イス競走は幾組かに分かれて行われるタイムレースである。そこで選手たちは、自己のベストに対して挑戦し、力走する。もっとも、力走といってもこの場合は腕力であろう(車イス選手の腕力は、常人よりも優れている者が多い。つまり脚力をもかねて発達している)。写真左は、力走する女子選手を、千分の1で撮ったもの。右は、ゴール寸前の男子選手のデッドヒート。こうした場合、胴体がテープ(毛糸)に先にふれた者が勝ち。


勝利に向って力走!
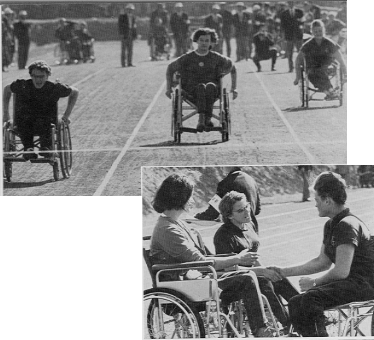
|
上、ゴール前の女子選手、左、からイギリス(ブライアント、第10胸髄以下組1位)。オーストラリア(サマーソァー)ローデシア(ギルクリユト)。その下は戦い終って、お互いの健闘をたたえあう三選手。
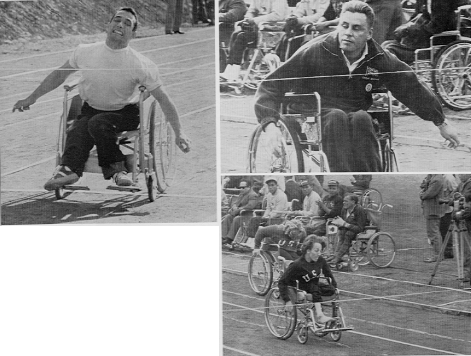
|
上、ゴールイン(テープは毛糸でできている)のアルゼンチン選手。右上、同、イギリス選手。左下、同、アメリカ選手。
パラリンピックは、反面、車イスそのものの競技会でもあった。それは、一見同じように見える車イスであっても、よくみると、各国それぞれ多少は違っていて、とうぜん“性能の差”というものがあるからである。たとえば、常用の優秀品とは、軽くて、回転性に富み、自分の意志どおりに操作できるもののことであろう。ところで、この車イス競走のようなスピードのみを必要とする場合では、ある程度重くなければ加速度が出ない。いわば競走専問車ということにもなろうか。
このように、車イス競技の根本には、車イスに対する研究が必要である。かえりみて、わが国の在来の車イスはどうであったろうか 残念ながら、外国品に優るものとは言えがたいであろう。そしてそれは、そのまま、わが国の身障者対策の立ちおくれを物語るものであるが、さらには“生活様式の違い”ということも遠因となっているだろう。たとえば日本の住居様式の多くは床ではなくタタミである。そこに、車イスの必要性が弱まり、発達を遅らせていた、ともいえるだろう。いうまでもなく外国では車イスが普及していて、日本の在来のような“いざり”的な生活行動はありえないことなのだ。ともあれ、このパラリンピックを機会として、関係者や業者が、車イスに対する認識を改めたであろうから、その意味からもこの大会での経験は貴重なものであろう。

|
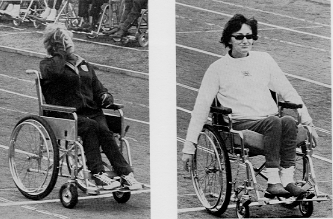 |
上左、加速度を利用して力走するアメリカ選手。上右、日本(浜本)選手の敢闘。下左、力及ばず残念とオランダ選手。下右、勝負は争わず、イギリス選手。
8日午後、秩父宮妃殿下、三笠宮ご夫妻は織田フィールドにおいでになりグットマン博士の説明をきかれながら、槍正確投げ、車イススラローム、5種競技などをごらんになった。

競技に先だって、自分の車イスの調整に余念のない選手たち。なお、選手村内にも、車イスの修理所が設けられた。
選手は、自分自身の一部として、車イスを愛し、可愛いがる。つねに油をさし、調整し、最良のコンデションで最高の機能が発揮できるようにしておく。

|

|
車イスリレー
車イスリレーは4人1組で、1人が40mを走り、ピストン・リレーする。これも胸髄9以上のマヒとそれ以下のマヒ者に分類して行う、タイム・レースである。

|
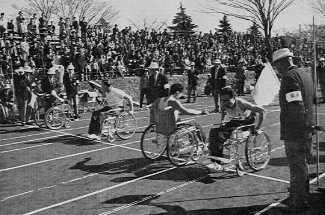
|

|
|
上左、車イスリレーのスタート。上右、イギリスチームと対戦する日本チーム(須崎勝己、山崎武範、小池正義、浜本勝行)。下、戦い終ってライバルと記念写真する外国選手たち。
国境を越えて…
どちらを向いても明るい顔、顔、顔。これがいわゆる身体障害者の表情であろうか。日本のある選手が「受傷して5年間、常にコンプレックスを感じていたが、パラリンピックの間は実にたのしかった。少しもコンプレックスを感じないですんだ。」と告白しているように、前をみても、隣をみても同じような条件の人々ばかりで、ことばや皮膚の色はちがうけれど、国境をこえた親しみ、懐かしさを感じるのは当然であろう。そしてまた自分も、その中の1人になって、陽気なふんいきの中にとけいってしまう。これこそパラリンピック開催の、大きな意義なのである。
外国選手と日本選手の、点数のひらきは、選手、すなわち、身障者のおかれている社会的環境のひらきだといわれた。選手村に集まったどこの国の選手の表情も態度も、そこ抜けに明るかった。きくところによると、日本の参加選手は、ほとんど施設にいる人たちであったが、外国の選手はこれまたほとんど社会に職をもっている人たちであるという。アメリカなどは、政府よりも民間団体が身障者のリハビリテーションに熱心であるが、イギリス、ドイツでは国立の病院、施設がたくさんあって、すべて無料、本人が希望すれば、いつまでいてもよい。しかも、治療、教育、訓練をして、働けるようになったものには職場、車椅子、車椅子が使える住宅、自動車などをくれる。まったく夢のような話である。もちろん、日本にもりっぱな施設があり、身障者雇用促進の法律もあるが、就職率は僅か35%で、イギリスの95%とはくらべものにならない。そうした明暗は、選手村の日本選手と外国選手の間にはあったが、それは日本ばかりでなく、参加したほかの小さな新興国の選手にもあったであろう。

|

|
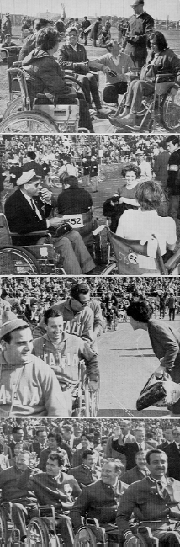
|

|
グランド風景

|
上左、通訳部会(語学奉仕団)の活躍、スエーデン選手に付添って。中左、付添いにいたわられるフランス選手。中右、ハッスルしすぎたかナ、イタリア選手。下左、卓球場で健闘をたたえあってアンブラッセするイスラエル選手。下右、イタリア選手は勝っても負けても陽気。
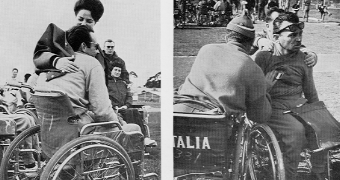
|

|

|

|

|
上右、競技準備をするイギリス選手。上左、アルゼンチンのグループに、イスラエルの監督さんが敵状偵察に来る。中左、フィリッピンの選手団のユニホームはプロ野球のそれに似ている。中右、砲丸投げの日本選手に、調子をきいている記者連。下左、自分たちの活躍がでている日本の新聞をみるドイツ選手。下右、出番待ちの間、ラジオ音楽を楽しむ選手たち。
モード拝見
パラリンピック・モード……そんなものはないかもしれない。しかし、われわれは見た。そこに展開した外国選手たちの多彩なコスチュームを…。それは生きることの楽しさを誇る各人各様のデザインである。

|

|

|

|
||
上左からイタリアのマルティーノさん、流行の製造地だけあって、空色のユニホームと帽子がすばらしい。右、グットマン博士の秘書で、いわば大会の花スクールトンさん。右、アルゼンチンのオラルティさん。この方は大会を通じて目立ち、マスコミの対象となったが、閉会式には和服で登場した。下へ、ローデシアのギリクリュトさん。こうしたポーズはオリンピックの依田選手を思わせるが、槍投げB級1位その他で活躍した。下、男子三名は、それぞれのお国ぶりをみせているが、右端は日本の大学生の帽子を貰って(?)得意がっている。

|

|

|
小さな声援
パラリンピックには、小さな児童たちも招待されて、さかんな声援をおくっていた。とくに、施設の子どもたちは、未来の自分たちの姿が想像されるのか、ほんとうに熱心だった。左上は母国の選手の応援にかけつけた在留外人学校の子どもたち。右上、その下は、施設の子どもたち。下右は、家族にはげまされて見に来た肢体不自由児。左上下は、外国選手のサインをねだる日本の子供たちで、このような英雄扱いには選手たちも驚いたらしい。

|
|

|

|

|
|
主題:
PARALYMPIC TOKYO 1964 パラリンピック 国際身体障害者スポーツ大会 写真集 No.3
53頁~85頁
編集発行者:
パラリンピック・国際身体障害者スポーツ大会編集委員会
発行年月:
文献に関する問い合わせ先:
財団法人 国際身体障害者スポーツ大会運営委員会
