身体運動のリハビリテーション
-運動生理学による体力の評価とトレ-ニング-
三田勝己(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所)
赤滝久美(愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所)
宮側敏明 (大阪市立大学)
石田直章(名古屋自由学院短期大学)
小山憲路(労災リハビリテーション工学センター)
目次
1.はじめに
障害者とは、国連総会の決議(1975)「障害者の権利宣言」の中で、「先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力不全のために、通常の個人または社会生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人」と定義している。障害者は疾患によって起こった機能の低下や欠損といった直接的な障害のみならず、障害をもっているという事実から派生する生活上の困難や社会的な不利益など二重、三重にも重なった問題をもっている。リハビリテ-ションとは、この複合的な問題の全面的解決つまり全人間的回復(total rehabilitation)の理念に立脚し、障害全体を構造的に把握し、総合的な対策を追究しようとするものである。運動生理学的アプロ-チにおいても部分的な身体機能の改善といった局所的な視野に偏在することなく、リハビリテ-ションの基本理念に立ってこの問題にどのように参画できるかを考えなければならない。
運動生理学では健常者や競技者を主たる対象として体力向上をめざした多くの研究が行なわれ、輝かしい成果を蓄積してきた。また、体力向上を主題とするこの科学はこれまでにもリハビリテ-ションへの参加が期待され、それなりの成果を生みだしてきた。しかし、それらは障害者のかかえる問題の所在を的確に把握し、その上に立った効果的な方法論を提供したとは言い難い。現状は従来の健常者を対象とした知見を援用した段階とみるべきであろう。運動生理学を障害者や高齢者のような低体力者にまで拡張したリハビリテ-ション支援科学・技術(rehabilitation support science & technology)とするためには新しい固有の方法論を構築することが必要である。
本稿では、第1に、運動生理学およびそこで主題となる体力の概念を理解することから入る。第2に、障害者の身体運動のリハビリテーションに必要な体力の要因を思索する。第3に、障害の内部構造すなわち問題の所在を把握し、リハビリテ-ションにおける運動生理学の役割と範囲を考える。
2.運動生理学と体力
2.1.運動生理学とは
運動生理学は生理学の分野に誕を発する科学である。元来、生理学は疾病の治療や健康の維持を役割とする医学という実践の中から一分野として誕生した。そこでは「生きる」ことを追究することをめざし、安静な状態における身体諸器官の機能を分析してきた。一方、さらに「より良く生きる」ためにはより高い能力を獲得するための積極的な身体活動を追究する生理学がなくてはならない。これが運動生理学(exercise physiology)の理念であり、これまで、スポ-ツや体育における身体運動を主題としてきた。
運動生理学は身体活動の高まった状態つまり運動時の生理学であり、その意味においては生理学の枠にとどまるかもしれない。しかしながら、身体活動が高まった状態では、安静状態にはない、そこで始めて出現する固有の変化がある。これを一つの法則として解明しようとする点で特長がある。さらに、運動を負荷するによってその器官や組織が構造を改造し、機能を改善していく。この過程を解明し、活用することも運動生理学の重要な課題である。すなわち、運動生理学は①運動時の身体活動能力いわゆる体力を分析、評価し、②運動トレ-ニングによってその向上を図かろうとする科学である。つまり、分析(analysis)と合成(synthesis)の二つの目的をもつ。今日、運動生理学は生理学から独立した別の分野として発展を遂げ、実用的価値をもつことから体育学の重要な基礎となっていることは論を俟たないところである。
2.2.体力とは
体力(physical fitness)とは一体何であろうか。猪飼(注1)は、体力とは生存(生きる)と活動(より良く生きる)の基礎をなす身体的および精神的能力であり、生存のための体力を防衛体力そして活動の体力を行動体力と呼んだ(表I(a))。名取(注2)は、体力を潜在性体力と活動性体力に分け、さらに、現在の体力はこれまでの履歴の上に獲得されたものであることから現在体力と体力履歴の二面から考えることを提案した(表I(b))。Balke(注3)は、身体的余裕(reserves)の大きさと強度な身体的要求に対する全体的な適応性 (general adaptability)が体力を決定するとし、行動体力のみならず防衛体力の重要性を強調した(表I(c))。
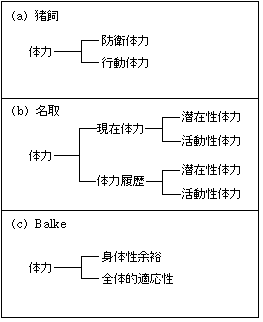
表1. 体力の構成
では、体力がどのような要因によって構成されるかを考える。Astrand & Rodahl(注4)によれば、体力はエネルギ-放出能力(有酸素的および無酸素的作業能力)、神経筋能力(筋力と技術)それに心理的要因(意欲や戦術など)によって決定されるとした。Clarke(注5)は、体力を筋力、筋持久力、呼吸循環能力の3つの要因からなるとし、なかでも筋力を最重要因子とした。さらに、瞬発力、敏捷性、速度、平衡能力の4つの要因を含めると運動体力になり、これに知覚による神経筋の協調能力を加えて総運動能力が構成されるとした。猪飼は自らの体力に関する考え方に沿って構成要因の系統的な分類を提案した(表II)(注6)。そして、運動生理学では機能面の要因が中心的課題になるとし、なかでも第一に筋力と筋パワ-をとりあげ、次いで、これを支配する神経系、さらに、これらを支える呼吸循環機能を指摘した。専門諸家の体力についての考え方や要因分類は細部において必ずしも一致しているとはいえない。しかしながら、全人間的なとらえ方をしようとする点では共通している。
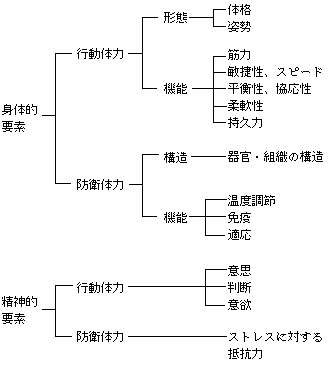
表2. 体力の構成要因(猪飼、1967)
3.障害者の体力
3.1.身体運動能力の獲得過程
本節では、障害者が体力を強化し、身体運動能力を獲得・向上させていく際に対象となる体力の要因とトレ-ニングの順位や考慮すべき問題について考える(図1)。
障害者は、疾病に起因するものか廃用性であるかに拘らず、身体活動量の低さから体力の低下を想定させる。障害の程度が重篤になれば集中的な健康管理の必要性や生命維持の危険性も発生する。障害者の体力を考える際にはその根幹をなす防衛体力からスタ-トすることを念頭に置くべきである。ここでは主として①調節(regulation)・適応(adaptation)といった自律神経機能を取り上げる。
「生存」の能力が確認されれば、次は基本的な運動能力の獲得である。運動の原点は四肢・体幹が他動的にでも「動く」ことである。その可動域は関節の構造や種類、関節周りの軟部組織によって決定される。これは行動体力の柔軟性に対応する。障害者の場合、関節の構築学的な欠陥や筋の拘縮によって関節の可動域が制限されることはしばしば観察されるところである。そこで②柔軟性(flexibility)を行動体力の最初に取り上げたい。これに続く要因は動くための駆動力である③筋力(muscle strength)であり、さらに敏捷な動きをするための④筋パワ-(muscle power)である。多くの人々が体力の中で最も重要なものとしてこれを指摘してきた。次いで、意のままに協応した身体運動を遂行するための⑤制御性(control)があげられる。
基本的な運動能力を日常生活のなかで実用的に活用できるまで向上するにはこれを長時間持続する能力いわゆる持久力を強化する必要がある。持久力は筋持久力と全身持久力に大別される。筋持久力は身体の局所的な部位における筋の持久力である。一方、全身持久力は呼吸循環系の動員を要求する全身運動の持久力である。ここではまず局所的な運動の強化を図るために⑥筋持久力(muscle endurance)に取り組み、その後、これらを統合した全身的な運動を確立するための⑦全身持久力(physical work capacity)の向上を図ることが必要である。
これらの要因に加えて、発育・発達の状態、疾病・機能障害の程度、訓練の過程などの履歴や彼らをとりまく環境といった時空間的諸条件を含めて総合的に体力を評価することを忘れてはならない。これがトレ-ニングの処方や将来のゴ-ルを予測する上で重要な示唆を与える。
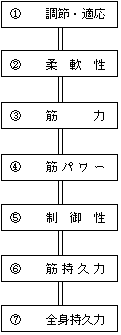
図1. 身体運動の獲得・向上に対象となる体力の要因
3.2.体力の構成要因
運動生理学では3.1.で取り上げた体力の構成要因に関する数多くの研究成果が蓄積されてきた。ここでは障害者の知見を一部混えながらこの要因の夫々について解説する。
①調節・適応
Astrandは、健康の維持や疾病の予防のための防衛体力を維持するには一日一時間、全身的な活動をするように提案している。その活動は歩行などの軽度なものでよく、さらに、連続したものでなくてもよい。健常者であれば僅かな注意を払えばこれを満たす身体活動を容易に確保できる。このため、運動生理学ではこれまで通常の環境下での防衛体力の問題はあまり注目しなかった。一方、登山や高地での競技を対象とした低圧・低酸素環境、スキュ-バダイビングのような水中の高圧環境、宇宙における無重力環境などの特殊環境に関しては防衛体力、行動体力共に積極的な取り組みがされてきた。
障害者の調節・適応を考える上に特に参考になるのは無重力環境に関する研究である。というのは、重度の障害者の中には長期臥床の者が少なくなく、彼らは疑似的に無重力状態にあるとみなされるからである。宇宙に関する研究(注7)では、無重力環境が体液の減少、骨からのカルシュウムの脱灰、筋の萎縮、循環調節能力の低下など調節・適応能力に変化を及ぼすことを明らかにしてきた。このような機能の低下は長期臥床の障害者にも当然起こり得ることである。
図2はその一例であるが、現在寝たきりの重症心身障害者を対象に臥位のままで疑似的な重力負荷を加える方法(下半身陰圧負荷法)によって循環調節機能を調べた結果である(注8)。一般に、人が起立姿勢をとると血液は重力の影響で下半身に移行し、貯留する。その結果、静脈還流および心臓の一回拍出量が減少する。この補償作用として心拍数が上昇して心拍出量の減少を防ぎ、末梢では血管収縮がおこり血圧の低下を防止するなどの調節が行われる。測定結果は、被検者が日常寄りかかりの座位によって重力刺激を受けているか否か、過去に抗重力姿勢(立位や座位)が可能であったか否かによって分けて示した(図の説明を参照)。図をみると、下半身陰圧負荷に伴う心拍数の上昇(ΔHR)および血圧の維持(ΔBP)がST1→ST2→BRの順に悪化している。この結果は現在重力の刺激を受けているか否かによって循環調節能力に違いのあることを示すものである。このことは心臓血管系のみならず他の諸器官についても共通すると推察される。単に臥床状態を放置すれば廃用性の機能低下を起すのみであり、受動的にでも常に刺激を負荷することの重要性を喚起するものである。また、この結果は過去の履歴が現在の能力に影響を及ぼすことを示しており、たとえ障害が重度であっても早期トレーニングの要請を確認、痛感させる。
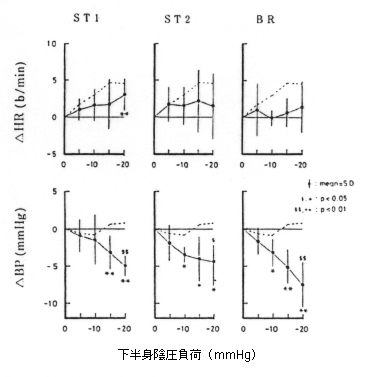
図2. 長期臥床の重症心身障害者の下半身陰圧負荷に対する心拍数(△HR)と平均血圧(△BP)の変化
実線は重症心身障害児、破線は健常者の反応
ST1:以前は立位や座位ができ、現在寄掛かりの座位の機会がある者
ST2:出生から寝たきりで、現在寄掛かりの座位の機会がある者
BR:出生から寝たきりで、現在も抗重力姿勢をとる機会をもたない者
②柔軟性
一流競技者の極度に柔軟な動きには目をみはらせるものがあり、柔軟性はスポ-ツをする上で重要な役割をもつ。また、スポ-ツ障害の予防とも深い関係がある。運動生理学にはBiomechnicsと呼ばれる分野があり、競技中の骨や関節の動きが力学的な手法によって解析されてきた。また、ストレッチングと呼ばれる筋の伸張性を改善する方法も開発され、広く用いられている。一方、健常者が日常の身体活動に必要な範囲の関節の可動域や筋の伸張性は通常備っている。このため、こうした目的でのトレ-ニングは必要性が低く、積極的な取り組みはほとんどなかった。
一方、整形外科領域ではこれを非常に重要視して、関節可動域(range of motion, ROM)という形でこの機能障害の評価法を確立してきた。また、理学療法の場では関節可動域回復訓練として柔軟性の回復が試みられている。運動生理学においても、この問題の重要性と所在を認識すれば新しい方法論を提供できるものと考える。
③筋力(注9)
筋力を規定する構造的因子は筋繊維断面積、筋繊維数および筋繊維タイプであり、機能的因子として大脳の興奮水準や反射の強度が考えられる。そのなかでも主要因は筋繊維の断面積である。一本の筋繊維はさらに細い多数の筋原繊維から構成されており、筋原繊維が太くそしてその数が多いほど筋繊維の断面積は大きいことになる。また、複数の筋繊維は一本の運動神経に支配され、機能的な単位(運動単位)を構成する。この運動単位が活動することによって筋力を発揮することになる。大脳の興奮水準が高く、活性化される運動単位の数が多いほど大きな筋力が発生する。さらに、筋繊維には大別して速筋と遅筋があり、速筋のほうが大きな筋力を発揮する。
筋の力発生能力は最大筋力によって評価される。最大筋力は随意努力下で発揮された値で評価されることが多く、これを随意最大筋力(maximum voluntary strength ; MVS)という。図3は二分脊椎症児の大腿四頭筋の最大筋力である(注10)。彼らは全員下腿に麻痺があるため、大腿四頭筋の筋力が歩行を決定する重要な因子となる。独立歩行者の結果からみると、歩行には少なくとも体重当り0.05kg・m/kgの最大筋力(トルクで表示してあるが)が必要である。杖歩行者であってもこの閾値を越す者がおり、彼らは技術的トレ-ニングによって独立歩行へと移行しうると考える。歩行不能者や閾値以下の杖歩行者はまず筋力を増大させるトレ-ニングが必要となる。このように筋力の評価はトレ-ニングの方向を決定する重要な示唆を与える。
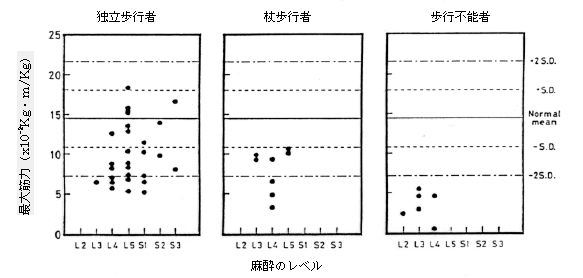
図3 二分脊椎症児の大腿四頭筋と歩行能力(石田ほか、1990)
最大筋力は体重あたりのトルクで示した。
図中の細い実線、破線、一点鎖線は健常者平均と±S.D.および±2S.D.
最大筋力を増大させるには現在の水準以上の筋力を一定期間以上続けることが必要である。これは過重負荷原理(overload principle)といわれている。この原理に基づいて最大筋力の増大を図るのが筋力トレーニングである。最大筋力の増大は筋繊維断面積の増大および収縮に参加する筋繊維数の増加によってもたらされ、筋繊維のタイプは変化しないと考えられている。筋力トレ-ニングには二つの側面があり、一つは筋繊維断面積を増大させることに重点をおいたトレ-ニングである。これにはボデ-ビルのトレ-ニングがあり、負荷を大きくしないで時間を長くする方法が挙げられる。もう一方は筋の能力を最大限発揮させることを中心としたトレ-ニングである。これはウエイトリフティングのように筋肥大を抑えた状態で筋力増強を図ろうとするものであり、大脳の活動水準を可能な限り高めて参加筋繊維の数を増やすことが必要である。そのためには強い負荷でトレ-ニングが行われる。
④筋パワー(注11)
筋収縮の様式は大別して静的収縮と動的収縮に大別される。静的筋収縮は筋の長さを変えないで張力を発揮するものであり、等尺性収縮といわれる。前述の随意最大収縮は静的収縮における最大値をさす。動的収縮には筋の長さを短縮させながら張力を発生させる短縮性収縮と筋が伸張しながら張力を発揮する伸張性収縮がある。動的収縮による機械的エネルギ-は筋力と収縮速度の積すなわちパワ-で表わされる。筋力(F)と速度(v)との間には「Hillの特性方程式」と呼ばれる有名な関係がある。
(F+a) (v+b) = (F0+a) b
F0:等尺性最大筋力, a,b:定数
収縮速度は負荷が重くなって発生筋力が大きくなるに従って減少する(図4)。逆に、収縮速度が上昇するに伴って筋力は低下する。筋パワ-は両者のいずれか一方が最大の時ゼロになり、極大値は最大筋力の30%および最大速度の30%の近傍で現れる。一般に、静的な最大筋力のすぐれた者は筋パワ-も大きい。また、速筋繊維は収縮速度および発生張力の大きいことから、この繊維が多いほど高い筋パワ-が発揮できるといえよう。収縮速度は筋の長さに比例するといわれている。
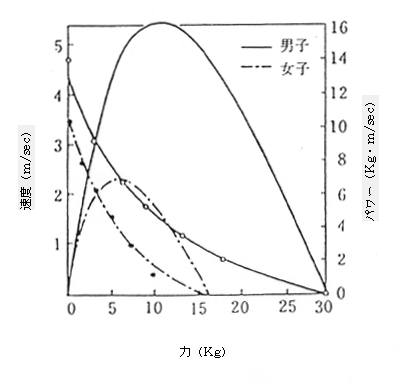
図4 ヒト上腕屈筋における力-速度および力-パワー関係(金子、1974)
では、筋パワ-を効果的に向上させるためのトレ-ニングとはどのような方法であろうか。金子は筋パワ-を向上させるには最大筋パワ-時の負荷(最大筋力の30%)をもってトレ-ニングをするのが最も有効であることを提唱している。さらに、最大筋力の向上には最大筋力を発揮するトレ-ニングを、収縮速度を高めるには最大速度を発揮するトレ-ニングが効果的であることを示した。
⑤制御性
神経系による運動の制御機構は大脳皮質→小脳・大脳基底核→脳幹・脊髄という階層的な制御システムから成る(注12)。脳幹・脊髄における機構は伸張反射に代表されるフィ-ドバック型の専用機能をもつシステムによって構成されている。小脳・大脳基底核は大脳皮質との連携をとりながら下位の制御系の協調と安定化を図る。運動の制御はここまでで自動的に遂行される部分がかなりある。しかし、運動の開始や停止などのプログラミングは大脳皮質からの意志の指令にもとづいて行われる。大脳皮質の運動に関する部分は運動野、前運動野、補足運動野、連合野にまたがっている。上位中枢の制御システムは固定化したものではなく、シナプスの可塑性によって可変的な機能をもつ。すなわち、ある神経細胞が死滅すると他の神経細胞から側枝が伸びて新しいシナプスを作り、これが消失した機能を代償するようになる。このように神経系は複雑な適応制御や自律分散制御によって協応性のある運動を可能にする。
障害者は上位中枢から末梢神経までのどこかに障害をもつ者が多く、随意運動ができないというだけでなく反射の昂進や不随意運動がみられる。臨床訓練の場では神経筋促通法と総称される運動の制御能力を高めるための様々な方法が開発されてきた。しかし、その有効性は科学的に証明されておらず、夫々の方法の統合も行われていない。また、バイオフィ-ドバックといわれるトレ-ニング法があり、運動系の神経のみならず自律神経機能の改善にも用いられている。さらに、これまでの運動制御機構に関する基礎的研究を積極的に導入した新しいトレ-ニング法が待たれるところである。
⑥筋持久力(注13)
筋持久力とは筋の有酸素的作業能をさす。つまり、筋への酸素の供給が筋持久力を決定する生理的因子であり、これには末梢の血液循環と筋の代謝が大きな影響を与える。筋の血流量が多いほど筋の酸素摂取量が大きく、筋持久力は高い。筋血流量は毛細血管の数や血流速度と関係する。筋持久力は筋に一定の張力を発揮させてその持続時間をみる静的筋持久力や一定のリズムで一定の張力を反復発揮する動的筋持久力によって評価される。なお、筋血流は最大筋力の60%以上になると遮断される。筋持久力の評価やトレ-ニングはこれ以下の負荷で行う必要がある。
筋持久力のトレ-ニングにおいて、最も効果的な負荷は最大筋力の20~30%であるといわれている。トレ-ニングの持続時間は長ければ長いほどよく、しかも疲労困憊まで行うことがよい。頻度は多いほうが有効であるという結果もみられる。しかし、低頻度であってもトレ-ニング期間が長期にわたれば同様な効果がみられたとの報告もあり、最終的な結論はでていない。
⑦全身持久力1)
全身持久力とは全身的な運動を長時間にわたって遂行できる有酸素作業能力をいう。全身持久力はその要因に筋持久力も一部に入るが内蔵諸器官の持久力を含んだものであり、特に呼吸循環系が重要な役割をなす。これの最もよい指標は最大酸素摂取量(Vo2max)である。最近、無酸素性作業閾値(anaerobic threshold; AT)によって全身持久力を評価する考えもある。ATとは運動に伴って有酸素的エネルギ-の産生過程に無酸素性代謝も参加してくる時点を指す。この閾値はVo2maxの55~65%という中程度の運動負荷時で現れ、この時の酸素摂取量をもって表す。また、最大酸素摂取量とATには正の相関がある。ATはVo2maxのように強い負荷を加えて測定する必要がなく、障害者には適した指標であるといえる。
全身持久力が向上する機構を考えよう。酸素摂取量はFickの原理によると次のように表わされる。
酸素摂取量=一回拍出量×心拍数×動静脈酸素較差
全身的な運動を行うと酸素輸送系が活発に働き、心臓から多くの血液が駆出されるようになる。心筋はこれに対応するために骨格筋のように肥大する。この結果、心容積の拡大と収縮力の増強がおこり、一回拍出量が増大する。一回拍出量の増加によって循環血液量の確保が容易になり、心拍数の低下がみられてくる。つまり余裕力が高まったのである。さらに、総血液量やヘモクロビン量の増加ともあいまって酸素輸送能力が増大し全身持久力が向上する。
全身持久力の向上を図るトレ-ニングの至適条件は専門諸家で必ずしも一致していない。一つの目安としては、運動強度が最大酸素摂取量の約60%(60%Vo2max)あれば日常生活に必要な持久力を高めるのに最高水準の強度であり、30%Vo2maxでも軽度の作業に対する余裕力を大きくするといわれている。持続時間については、呼吸循環機能がその負荷に対して定常状態になるのが運動開始から3分後であり、少なくともこれ以上の時間は必要である。頻度は一日おきが適当という意見が多い。しかしながら、高齢者など初期体力の低い者に対して比較的低い強度で長時間(50%Vo2max、60分)のトレ-ニングを行い、その効果を確認した報告もある。障害者は通常大きな運動負荷を経験することが少なく、廃用性の機能低下や易疲労性も高い。全身持久力のトレ-ニングは呼吸循環機能に負荷を与えるものであり、トレ-ニングの実施にあたっては安全面に充分注意して余裕をもったプログラムを処方するように心掛けなければならない。
4.運動生理学の役割と範囲
4.1.障害の内部構造
運動生理学における体力の概念と要因を概説し、身体運動を獲得・回復するための一つのプロセスを提案してきた。このような運動生理学の方法論が一連のリハビリテーションの実践のなかで果しうる役割とその範囲を探ることにする。そこで、まず問題の所在を把握するために、障害の内部構造を確認する。
WHOの国際障害分類では、疾患(disease)によって生じた障害を①機能・形態障害(impairment)、②能力障害(disability)、③社会的不利(handicap)の3つの階層として構造的にとらえることを提唱した(表III)(注14)。①機能・形態障害は障害の一次的レベルであり、疾患から直接起こってくる身体的および精神的な機能・形態の異常をさす。生物学的レベルでとらえた障害である。脳卒中であれば、疾患は脳血管に生じた出血や血栓などによる脳組織の破壊である。その結果、四肢の麻痺や言語障害などの脳機能障害が発生する。また、長期の安静によって起きる関節拘縮や廃用性筋萎縮などの合併症も疾患である。これは関節可動域の制限や筋力低下などの機能・形態障害を生む。
← 表III 挿入
②能力障害とは個人的生活のレベルにおける障害である。つまり、当然できると考えられる日常の行為を実用性をもって行うことが困難であったり、できない状態をさす。脊髄損傷では起立姿勢や歩行不能という形であらわれる。しかし、装具や松葉杖を用いて訓練すれば移動能力は再び獲得でき、能力障害は著しく減少する。重要なのは機能・形態障害が一義的に能力障害を引き起こすとは限らないことである。能力障害は機能・形態障害の程度、残存能力や潜在能力の活用、最適な補助具の利用、介助者の存在などによって規定されるものである。
障害の三次レベルである③社会的不利とは機能・形態障害や能力障害の結果としてその個人に生じた不利益であって、当然保障されるべき基本的人権が妨げられたり、正当な社会的役割を果すことができないことをいう。社会的不利とは社会的生活のレベルでとらえた障害である。例えば、切断者が義足によって通常の生活をするための歩行能力を獲得したとしても、満員電車で通勤できないために復職を断念せざるをえない場合には社会的不利となる。しかし、転居をすることによって、この通勤の問題を解決できたとしたら社会的不利とはならない。社会的不利は住居、家族、職場、法制度、福祉サ-ビスなどの社会的諸条件と能力障害の程度との相対的関係によって規定される。最終的に、リハビリテ-ションのゴ-ルは社会的不利の克服に他ならない。
4.2.運動トレ-ニングの意義
身体運動のリハビリテーションにおいて運動生理学が障害のそれぞれのレベルでどのような係わり合いがもてるかを考える。まず、機能・形態障害に対しては身体運動に必要な基本的機能を獲得することが課題である。この問題に対してこれまで医療分野からのアプロ-チが主要な役割を務めてきた。リハビリテ-ション医学では機能・形態障害に対する運動療法を中核的な治療手段として活用し、特に、治療訓練と呼んでいる。その訓練法は一部上述したように色々な方法が開発されており、実践の場で使い易く細かく配慮されている。しかし、その有効性が未だ科学的に明らかでないものもあり、今後の分析的証明が待たれる。一方、この問題を運動生理学的に体力の向上という観点からみると、リハビリテ-ションのプロセスとして①調節・適応→②柔軟性→③筋力→④筋パワ-→⑤制御性の流れに沿ったトレ-ニングが考えられる。運動生理学とリハビリテーション医学の双方が蓄積してきた成果や方法論を連携させることによってより効果的な方法が生れるうる。近年、運動生理学の分野では医療体育研究会なるものがあり、この面での系統的な研究活動が試みられている。運動生理学的手法を駆使した成果が期待されるところである。
能力障害の克服は個人レベルの日常生活の独立であり、リハビリテーション医学ではこのための運動療法を機能訓練と呼んでいる。その中心的なものは歩行などの能力回復訓練や日常生活動作訓練であり、実生活と結びついた応用的、実践的側面が強い。運動生理学的立場からみると、能力障害は上記の要因①~⑤を強化することによって相当克服できる。さらに、実用性の高い日常生活の行為を獲得するためには⑥筋持久力および⑦全身持久力の向上を図らなければならない。東京オリンピック以来、我が国の運動生理学はスポ-ツにおけるこの面での研究が特に進歩た。一方、残念ながら障害者へのアプロ-チは緒についたばかりであり、その成果も少ない。一方、臨床医学では近年、持久力の重要性をとりあげ、運動生理学的な取り組みが積極的にされ始めた。近い将来、障害者の持久力を分析・評価が詳細に行われ、これに基づいた効果的なトレ-ニング法が提案されるものと確信する。
体力の向上は身体運動の質と量を高め、運動をすること自体が一つの喜びとなる。そして、家の中や病院などの狭い社会から屋外に出てレクリエ-ションやスポ-ツを楽しむ。これが体力の向上を相乗的に加速させ、加齢に伴う体力の低下を自然な形で予防し、自信や競争心、自発性などの精神的高揚を図る。また、多くの仲間と友情を育み、一般社会の秩序を学び、社会参加への勇気と自信を確立する。これが社会的不利克服の一つであり、運動生理学がもてる力を最も有効に発揮できる場である。今日、障害者のスポ-ツ大会は国際身体障害者スポ-ツ大会や極東・南太平洋身体障害者スポ-ツ大会を始め多くの競技大会が開催されている(注15)。また、レクリエ-ションについても国際障害者レジャ-・レクリエ-ション・スポ-ツ大会を始め障害者の運動の底辺を拡大する活動が続けられている。極東・南太平洋身体障害者スポ-ツ大会の創始者故中村は「身障スポ-ツはあくまでリハビリテ-ションの一環としておこなわれるべきでありひとつのサイエンスである」と残している。この言葉は障害者のスポ-ツがリハビリテ-ションという道程に置かれたmilestoneの一つであることを考えさせるものである。
5.おわりに
運動生理学的方法論による障害者のリハビリテーションへの系統的な取り組みはまさにこれからである。著者らは運動生理学が身体運動のリハビリテーションにどのようにアプロ-チできるかを議論し、幾つかの研究を通して模索してきた。本稿では運動生理学の原点にもどってこの課題に対する方向の一つを提案した。偏見と独断に満ちた内容であるとも考えられるがご容赦願いたい。読者のご批判とご意見を期待するものである。
文献
(1) 猪飼道夫編:身体運動の生理学、杏林書院(1963) (本文に戻る)
(2)名取礼二:最新体力測定法、同文書院 (1970) (本文に戻る)
(3) Balke,B.:体育科学辞典(猪飼道夫他編)(引用)、第一法規出版 (1970) (本文に戻る)
(4) Astrand,P.-O & Rodahl,K. : Textbook of Work Physiology, McGraw-Hill (1970) (本文に戻る)
(5) Clarke,H.H.:教師のための体育測定(野口義之編)(引用)、第一法規出版 (1969) (本文に戻る)
(6) 猪飼道夫:日本人の体力、日本経済新聞社(1967) (本文に戻る)
(7) 大島正光、松田源彦:宇宙医学、同文書院(1986) (本文に戻る)
(8) 赤滝久美、三田勝己、宮側敏明、鈴木伸治、山川純:重症心身障害児(者)の下半身陰圧負荷(LBNP)に対する循環調節、リハ医学(印刷中) (本文に戻る)
(9) 福永哲夫:ヒトの絶対筋力、杏林書院 (1978) (本文に戻る)
(10) 石田直章、赤滝久美、三田勝己、村地俊二: 二分脊椎症児における脚伸展力と移動能力との関係、日本体力医学会抄録集、43(1990) (本文に戻る)
(11) 金子公宥:人体筋のダイナミックス、杏林書院 (1974) (本文に戻る)
(12) 伊藤正男:脳の設計図、中央公論社(1980) (本文に戻る)
(13) 加賀谷熈彦、加賀谷淳子:運動処方-その生理学的基礎-、杏林書院(1983) (本文に戻る)
(14) 上田敏:リハビリテーションを考える、青木書店 (1983) (本文に戻る)
(15)日本身体障害者スポ-ツ協会:創立20周年史、日本身体障害者スポ-ツ協会(1985) (本文に戻る)
文献情報
著者:三田勝己、赤滝久美、宮側敏明、石田直章、小山憲路
題目:「身体運動のリハビリテーション-運動生理学による体力の評価とトレーニング-」
雑誌名:『バイオメカニズム学会』15巻 pp.20-29
発行年:1991年
文献に関する問い合わせ:
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所
三田勝己
春日井市神屋町713-8
TEL & FAX:0568-88-0811
