肢体に障害をもつ子供の運動とその実践-リハビリテーションの運動生理学-
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所
三田勝己
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 転載元 | 『医療体育』(医療体育研究会)15巻 pp.80-88 |
目次
1. はじめに
運動機能障害のリハビリテーションにおける運動やスポーツの導入は英国ストーク・マンデビル病院で始った(注1)。当病院のグッドマンは理学療法士、作業療法士、医療体育士、養護学校教師らによるチームをつくり、個々の患者について最も適切な機能訓練に取り組んだ。それは運動を中心においた残存機能の回復と強化のダイナミックなトレーニングであった。その結果、重度脊損患者の85%が6カ月間の治療・訓練で社会復帰を果たした。さらに、1948年僅か26名ながら脊損患者のスポーツ競技大会を始めた。これがストーク・マンデビル競技大会の第1回目であり、後年、国際的な身体障害者競技大会にまで発展した。
グッドマンの活動は運動やスポーツがリハビリテーションに大きな役割を果たすことを如実に示したものといえよう。なお、ここでいうリハビリテーションとは単に障害を受けた機能を医療的な手段によって治療することをさすのではなく、生活の自立をはかり、社会参加を果たすための、障害者そして健常者を含めた全ての努力を意味する。つまり、トータル・リハビリテーションである(注2)。グッドマンの偉大さは運動を単に機能改善の手段として利用しただけでなく、トータル・リハビリテーシンの実践として導入したことである。
現在、医療の分野では運動を利用した機能回復が積極的に行われている。これは運動療法と呼ばれ、基本的な機能や形態の障害に対するリハビリテーションである(図1)。次に、障害者が行なうスポーツ的な運動を考えると、2つの段階に分けられる。第1は病院や施設内で行なわれるスポーツであり、日常生活に必要な身体活動能力の獲得、改善がねらいである。これは医療体育あるいは医療スポーツと呼ばれている。第2は障害者が勝敗を競う競技スポーツであり、社会参加の促進に重要な役割を果たす(注3)(注4)。
グッドマンの活動から50年経った今日、運動やスポーツはリハビリテーションにおいて不可欠なものにり、輝かしい効果をあげるに至った。しかし、機能が改善していくプロセスやメカニズムを明らかにし、これに基づいた運動やスポーツが導入されてきたとは言い切れない。一方、運動生理学では健常者を対象に運動やスポーツについて基礎的な研究を蓄積してきた。本稿では、運動生理学の概念と方法に触れるとともに、運動機能障害のリハビリテーションへの援用を試みる。なお、本稿の主題は「肢体に障害をもつ子供(肢体不自由児)」であり、子供を中心に述べるが、大人の場合とも多くの共通点をもつ。
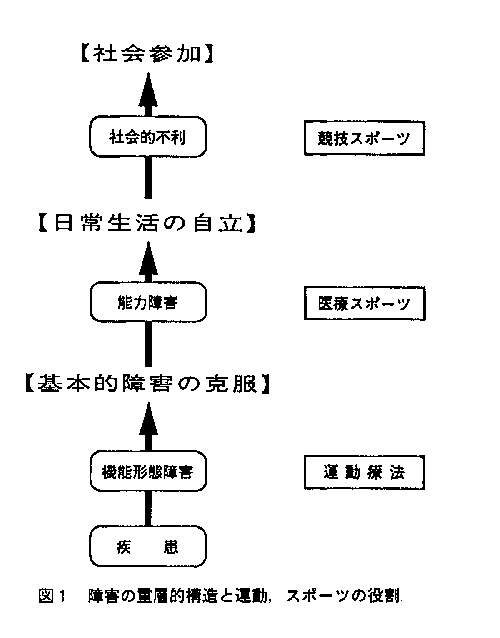
図1 障害の重層的構造と運動、スポーツの役割
2.運動生理学と体力
2.1.運動生理学とは
運動生理学は生理学の分野に端を発する科学であり、当然その一画を成すものであるが、これを区別して扱ったのは以下の理由による。元来、生理学は疾患の治療や健康の維持を役割とする医学の実践の中から一分野として誕生した。そこでは「生きる」ことを追究することをめざし、安静な状態における諸器官の機能を分析してきた。一方、さらに「より良く生きる」ためにはより高い能力を獲得するための積極的な身体活動を追究する生理学がなくてはならない。これが運動生理学の理念であり、これまでスポーツにおける身体運動を主題としてきた。身体活動が高まった状態(運動時)では、安静状態にはない、そこで始めて出現する固有の変化がある。運動生理学はこれを一つの法則として解明しようとする点で特徴がある。さらに、運動を負荷することによってその器官や組織が構造を改造し、機能を改善していく。この過程を解明し、活用することも重要な課題である。すなわち、運動生理学は運動時の身体活動能力いわゆる「体力」を計測、評価し、運動トレーニングによってその向上を図ろうとする科学である。今日、運動生理学は生理学から独立した別の分野として発展を遂げ、実用的価値をもつことから体育学の重要な基礎となっている。このような運動生理学を運動機能障害のリハビリテーションへ導入することは意義深く、これまでの医学的な機能訓練に加えてさらなる効果を期待させる。
2.2.体力とは
運動機能障害のリハビリテーションで対象となる機能要素を体系化する。このため、従来より運動生理学において論議されてきた体力の構成要素を運動機能障害に適用できるよう再構築する。猪飼(注5)は、体力とは生存(生きる)と活動の基礎(より良く生きる)をなす身体的および精神的能力であるとし、生存のための能力を防衛体力、活動のための能力を行動体力と呼んだ。図2(A)は猪飼が提案した体力の身体的要素を示している。健常者であれば各要素の基本的な能力は全て確保されていると想定でき、それぞれの要素が並列に位置している。そして、重量挙げであれば筋力を、マラソンであれば持久力といったように行動体力の要素が必要に応じて強化される。防衛体力については、登山や高地での競技を対象とした低圧・低酸素環境、スキューバダイビングのような水中の高圧環境、宇宙における無重力環境などの特殊環境に関しては行動体力と共に積極的な取り組みがされてきた。しかしながら、通常の環境下ではあまり注目されなかった。
(A)猪飼による分類(身体的要素のみ)
(B)運動機能障害のリハビリテーションで対象となる要素と流れ
一方、運動機能障害をもつ場合にはその程度によって複数の要素がリハビリテーションの対象になるので、健常者に対する機能向上の考え方は当てはまらない。極端な場合には全ての要素を考慮しなければならないこともある。そこで、障害者を対象とした体力の構成、特に機能面について再構築し、一定の順序づけを行なう必要がある。つまり、障害の程度が重篤になるほど集中的な健康管理が必要となったり、時には生命の危機にすら直面する。体力の要素にはまず生存の根源を成す防衛体力、すなわち、生命を維持するために必要な機能を取りだすことから始めなければならない。そこで、第1に調節・適応といった自律神経機能を選択し、これを「生存の要素」とする(図2(B))。生存の要素が獲得された段階では、運動をするための機能が必要となる。このためにはまず他動的であっても四肢や体幹が充分に動かし得る状態、つまり、柔軟性が要請される。次いで、動くための駆動力である筋力・筋パワーが加わり、さらに、意のままに運動をするための制御性があげられる。これら柔軟性、筋力・筋パワー、制御性を「動きの要素」としてまとめておく。最後に、獲得された動きを日常生活の中で実用的に活用させるためにはこれを長時間持続する能力すなわち「持続の要素」が必要となる。そこでは、まず局所的な筋持久力を確保し、続いて呼吸循環機能をも動員する全身持久力の向上を図る。このように、運動機能障害のリハビリテーションでは「生存の要素」→「動きの要素」→「持続の要素」という順序づけを行ない、各要素の改善をはかっていくことが肝要であると考える。次節以降では、運動生理学の知識そして肢体不自由児で蓄積されてきた知見を交えながら、夫々の体力の要素について解説する。
3.生存の要素
重度の肢体不自由児や重症心身障害児の中には長期臥床の者が少なくなく、彼らは疑似的に無重力状態にあるとみることができる。宇宙医学の分野では、無重力環境が骨からのカルシュウムの脱灰、筋の萎縮、体液の減少や循環調節能力の低下などを引き起こすことを明らかにしてきた(注6)。このような機能の低下は長期臥床者にも当然起こり得る。
その一例を示そう。一般に、我々が起立姿勢をとると血液は重力の影響で下半身に移行し、貯留する。その結果、静脈還流および心臓の一回拍出量が減少する。この補償作用として心拍数が上昇して心拍出量の減少を防ぎ、末梢では血管収縮がおこり血圧の低下を防止するなどの調節が行われる。図3は、寝たきりの重症心身障害児(重症児)を対象に、臥位のままで疑似的に重力負荷を加えられる下半身陰圧負荷法を使って、心拍数の反応を調べた結果である(注7)。結果は重症児が日常寄りかかりの座位によって重力の刺激を受けているか(H1群)あるいは否か(H2群)によって2群に分けてある。図をみると、H1群の心拍数は陰圧負荷に対して増大しているが、健常者ほどではなく、機能の低下を推察させる。H2群では逆に減少傾向がみられ、機能不全を窺わせる。また、この結果は日々起こすことによる重力の刺激が循環機能の維持に大きな役割を果たすことを示したといえる。さらに、こうしたことは循環系のみならず他の諸器官についても共通する。寝たきり状態を放置すれば廃用症侯群に陥るのみであり、他動的にでも座ること、立つことの重要性を喚起する結果である。
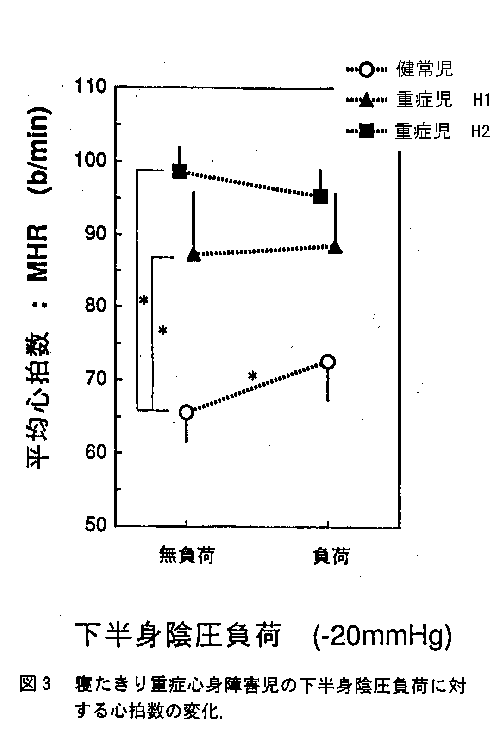
図3 寝たきり重症心身障害児の下半身陰圧負荷に対する心拍数の変化
4.動きの要素
4.1.柔軟性
一流競技者の極度に柔軟な動きには目をみはらせるものがあり、柔軟性はスポーツをする上で重要な要因である。また、スポーツ障害の予防とも深い関係がある。運動生理学にはBiomechnicsと呼ばれる分野があり、競技中の骨や関節の動きが力学的な手法によって解析されてきた。また、ストレッチングと呼ばれる筋の伸張性を改善する方法も開発され、広く用いられている。一方、健常者が日常の生活動作に必要な範囲の関節可動域や筋の伸張性は通常備っている。そのため、柔軟性を目的としたトレーニングは必要性が低く、積極的な取り組みはほとんどなかった。
しかし、肢体不自由児では柔軟性の障害がしばしばみられる。整形外科領域ではこれを非常に重要視して、関節可動域(range of motion, ROM)という形でこの機能障害の評価法を確立してきた。また、理学療法の場では関節可動域回復訓練として柔軟性の回復が試みられている。柔軟性つまり関節の可動性を制限する機能障害は関節拘縮と呼ばれる。関節拘縮は関節を構成する軟部組織の短縮によるものと、筋の短縮によるものとに大別される。関節可動域制限を評価する際には、関節角度の測定つまり量的な値に加えて、その病態や部位など質的な内容を把握することが大切である。特に大腿四頭筋などの二関節筋が関与する関節では、一方の関節が伸展あるいは屈曲した場合、他方の関節の可動域が変化する。このことは関節可動域制限の病態を知る上で一つの手がかりとなる。
我々は、関節可動域制限に関する量と質を同時に評価できる非線形幾何モデルなる方法を提案してきた(注8)。これを二関節筋の関与が大きい股関節と膝関節を例にとって説明する(図4)。股関節角と膝関節角の相互関係をXY平面に描くと六角形で近似できる。つまり、1-1点は股関節および膝関節を最大に屈曲した際の角度である。一方、これに対応するのが2-1点であり、両関節を最大に伸展した時の角度を示しめす。この2つの肢位での関節角度を測定すれば両関節の最大可動域を知ることができる。さて、一般に、1-1点の肢位から膝関節を伸展させると、これ以上伸展できない1-2点に到達する。もう一方、2-1点から股関節を屈曲していくと、同様に、これ以上屈曲できない1-3点に到達する。これら2つの限界点は二関節筋であるハムストリングスの筋長によることはいうまでもない。そして、この2点間は2つの関節の形状によって定まる複雑な経路を経て結ばれる。ここではその一次近似をとって直線で表した。なお、これに対応する2-2点、2-3点に関しても大腿四頭筋の影響によって同様なことがいえる。
次に、このモデルを使うと、関節可動域制限がどの様に表現されるかを説明する。今、太い実線の外枠が正常な関節の可動域であるとし、可動域制限のある場合には内側の六角形に縮小されると想定する。そこで、A、Bと示した部分は股関節の屈曲あるいは伸展制限を表し、C、Dは膝関節の屈曲あるいは伸展制限を表す。また、Eの部分はハムストリングスの短縮によって引き起こされる股関節屈曲・膝関節伸展の複合制限を意味する。Fも大腿四頭筋による複合制限を表す。このように関節可動域の幾何モデルによって柔軟性の障害の質と量を一目でとらえられることが理解されよう。
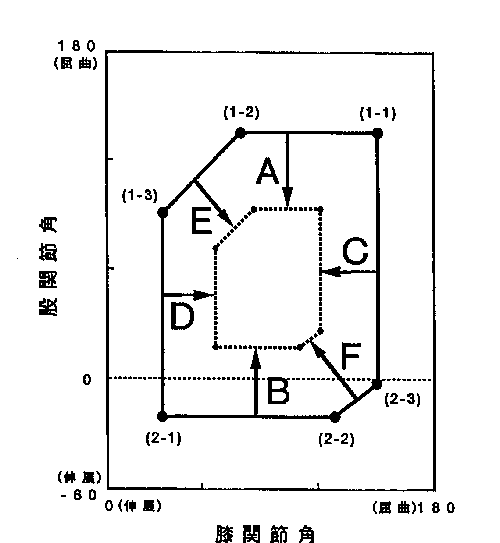
図4 非線形幾何モデルによる股関節・膝関節の可動域表示とその制限.
A.股関節屈曲制限
B.股関節伸展制限
C.膝関節屈曲制限
D.膝関節伸展制限
E.股関節屈曲・膝関節伸展複合制限(ハムストリングス短縮)
F.股関節伸展・膝関節屈曲複合制限(大腿四頭筋短縮)
4.2.筋力(注9)
筋力を規定する構造的因子は筋線維断面積、筋線維数および筋線維タイプであり、機能的因子として大脳の興奮水準や反射の強度が考えられる。そのなかでも主要因は筋線維の断面積である。一本の筋線維はさらに細い多数の筋原線維から構成されており、筋原線維が太くそしてその数が多いほど筋線維の断面積は大きいことになる。また、複数の筋線維は一本の運動神経に支配され、機能的な単位(運動単位)を構成する。この運動単位が活動することによって筋力を発揮することになる。大脳の興奮水準が高く、活性化される運動単位の数が多いほど大きな筋力が発生する。さらに、筋線維には大別して速筋と遅筋があり、速筋のほうが大きな筋力を発揮する。
筋の力発生能力は最大筋力によって評価される。最大筋力は随意努力下で発揮された値で評価されることが多く、これを随意最大筋力という。図5は二分脊椎症児の大腿四頭筋の最大筋力である(注10)。(A)図は体重と最大筋力(トルクで表示)との関係を示しており、健常児の回帰直線と比較すると、体重の増加に伴って健常児より筋力の発達が悪い。これを体重とは独立して定量的に評価するために以下のような「筋力指標:MSI」を定義する((B)図)。すなわち、被検者「i」の体重および最大筋力がWi、Tiであるとし、また、健常児の体重と最大筋力との回帰直線をTr(W)とする。(1)式のように、被検者「i」の筋力Tiについて回帰直線からの偏り{Ti-Tr(Wi)}を求め、これを体重Wiで除した値Riを考える。さらに、健常児のRiの標準偏差をσNで表すと、(2)式の筋力指標MSIiが求まる。
Ri={Ti-Tr(Wi)}/Wi (1)
MSIi=Ri/σN (2)
(B)図は二分脊椎症児のMSIを示すが、この指標の特徴は体重と無関係に±2以内が健常域を示し、二分脊椎症児の筋力発達の異常を健常発達との相対値として定量的に評価できる。二分脊椎症児は多くが下腿に麻痺があり、大腿四頭筋の筋力が歩行を決定する重要な因子となる。この図より、二分脊椎症児のMSIの回帰直線が-2レベルを横切る体重は32Kgである。この体重に対応する年齢は10歳であり、さらに、この年齢は歩行能力の低下が始まるとされる時期と一致していた。
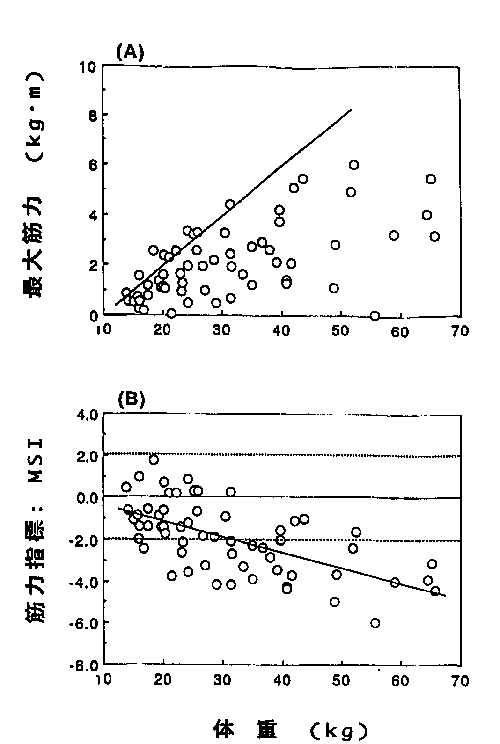
図5 二分脊椎症児の大腿四頭筋の(A)最大 筋力(トルク表示)と(B)筋力指標:MSI.
(A)図の回帰直線は健常児の体重と最大筋力から算出.
(B)図の回帰直線は二分脊椎症児の筋力指標から算出.
-2レベルとの交点に注意.
次に、筋力増強を考える。最大筋力を増大させるには現在の水準以上の筋力を一定期間以上続けることが必要である。これは過重負荷原理といわれ、この原理に基づいて最大筋力の増大を図るのが筋力トレーニングである。最大筋力の増大は筋線維断面積の増大および収縮に参加する筋線維数の増加によってもたらされ、筋線維のタイプは変化しないと考えられている。筋力トレーニングには二つの側面があり、一つは筋線維断面積を増大させることに重点をおいたトレーニングである。これにはボデービルのトレーニングがあり、負荷を大きくしないで時間を長くする方法があげられる。もう一方は筋の能力を最大限発揮させることを中心としたトレーニングである。これはウエイトリフティングのように筋肥大を抑えた状態で筋力増強を図ろうとするものであり、大脳の活動水準を可能な限り高めて参加筋線維の数を増やすことが必要である。そのためには強い負荷でトレーニングが行われる。
4.3.筋パワー(注11)
筋収縮の様式は静的収縮と動的収縮に大別される。静的筋収縮は筋の長さを変えないで張力を発揮するものであり、等尺性収縮といわれる。前述の随意最大収縮は静的収縮における最大値をさす。動的収縮には筋の長さを短縮させながら張力を発生させる短縮性収縮と筋が伸張しながら張力を発揮する伸張性収縮がある。動的収縮による機械的エネルギーは筋力と収縮速度の積すなわちパワーで表わされる。筋力(F)と速度(v)との間には「Hillの特性方程式」と呼ばれる有名な関係がある。
(F+a)(v+b)=b(F0+a) (3)
F0:等尺性最大筋力, a,b:定数
収縮速度は負荷が重くなって発生筋力が大きくなるに従って減少する。逆に、収縮速度が上昇するに伴って筋力は低下する。筋パワーは両者のいずれか一方が最大の時ゼロになり、最大値は最大筋力の30%および最大速度の30%の近傍で現れる。一般に、静的な最大筋力のすぐれた者は筋パワーも大きい。また、速筋線維は収縮速度および発生張力の大きいことから、この線維が多いほど高い筋パワーが発揮できるといえよう。収縮速度は筋の長さに比例するといわれている。
図6は脳性麻痺児(片麻痺)が脚伸展運動を行った際の動的筋力と筋パワーを健側と麻痺側で比較したものである。当然のことながら、麻痺側の方が運動速度、動的筋力、筋パワー共に小さい。また、健側では、動的筋力(●)から推定した最大筋力(運動速度ゼロの時の筋力)と実測した最大筋力(○)とが概ね一致したが、麻痺側ではその隔たりが大きい。つまり、この結果は脳性麻痺児が静的な筋力より動的な筋力を発揮することの難しさを示したといえる。
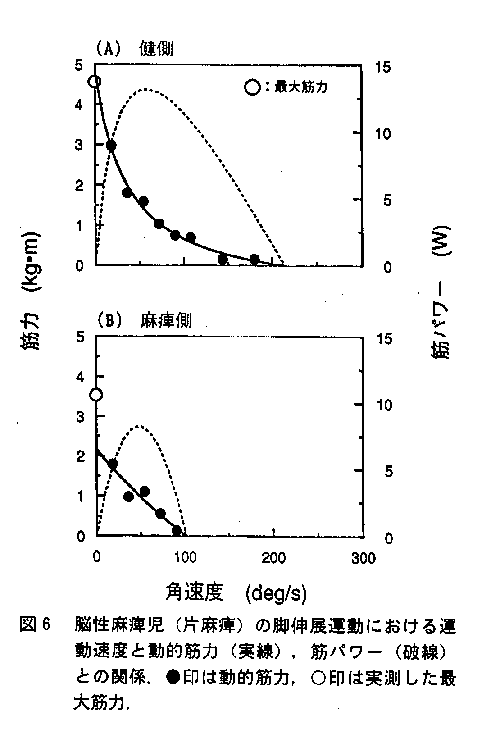
図6 脳性麻痺児(片麻痺)の脚伸展運動における運動速度と動的筋力(実線)、筋パワー(破線)との関係.
●印は動的筋力、○印は実測した最大筋力.
さて、筋パワーを効果的に向上させるためのトレーニングとはどのような方法であろうか。金子は筋パワーを向上させるには最大筋パワー時の負荷(最大筋力の30%)をもってトレーニングをするのが最も有効であることを提唱している。さらに、最大筋力の向上には最大筋力を発揮するトレーニングを、収縮速度を高めるには最大速度を発揮するトレーニングが効果的であることを示している。
4.4.制御性
神経系による運動の制御機構は大脳皮質→小脳・大脳基底核→脳幹・脊髄という階層的な制御システムから成る(注12)。脳幹・脊髄における機構は伸張反射に代表されるフィードバック型の専用機能をもつシステムによって構成されている。小脳・大脳基底核は大脳皮質との連携をとりながら下位の制御系の協調と安定化を図る。運動の制御はここまでで自動的に遂行される部分がかなりある。しかし、運動の開始や停止などのプログラミングは大脳皮質からの意志の指令にもとづいて行われる。大脳皮質の運動に関する部分は運動野、前運動野、補足運動野、連合野にまたがっている。上位中枢の制御システムは固定化したものではなく、シナプスの可塑性によって可変的な機能をもつ。すなわち、ある神経細胞が死滅すると他の神経細胞から側枝が伸びて新しいシナプスを作り、これが消失した機能を代償するようになる。このように神経系は複雑な適応制御や自律分散制御によって協応性のある運動を可能にする。
障害者は上位中枢から末梢神経までのどこかに障害をもつ者が多く、随意運動ができないというだけでなく反射の昂進や不随意運動がみられる。臨床訓練の場では神経筋促通法と総称される運動の制御能力を高めるための様々な方法が開発されてきた。しかし、その有効性は科学的に証明されておらず、夫々の方法の統合も行われていない。また、バイオフィードバックといわれるトレーニング法があり、運動系の神経のみならず自律神経機能の改善にも用いられている。さらに、これまでの運動制御機構に関する基礎的研究を積極的に導入した新しいトレーニング法が待たれるところである。
5.持続の要素
5.1.筋持久力(注13)
筋持久力とは筋の有酸素的作業能をさす。つまり、筋への酸素の供給が筋持久力を決定する生理的因子であり、これには末梢の血液循環と筋の代謝が大きな影響を与える。筋の血流量が多いほど筋の酸素摂取量が大きく、筋持久力は高い。筋血流量は毛細血管の数や血流速度と関係する。筋持久力は筋に一定の張力を発揮させてその持続時間をみる静的筋持久力や一定のリズムで一定の張力を反復発揮する動的筋持久力によって評価される。なお、筋血流は最大筋力の60%以上になると遮断されるので、筋持久力の評価やトレーニングはこれ以下の負荷で行う必要がある。
筋持久力のトレーニングにおいて、最も効果的な負荷は最大筋力の20~30%であるといわれている。トレーニングの持続時間は長ければ長いほどよく、しかも疲労困憊まで行うことがよい。頻度は多いほうが有効であるという結果もみられる。しかし、低頻度であってもトレーニング期間が長期にわたれば同様な効果がみられたとの報告もあり、最終的な結論はでていない。
5.2.全身持久力
全身持久力とは全身的な運動を長時間にわたって遂行できる有酸素作業能力をいう。全身持久力はその要因に筋持久力も一部に入るが内蔵諸器官の持久力を含んだものであり、特に呼吸循環系が重要な役割をなす。これの最もよい指標は最大酸素摂取量(Vo2max)である。また、無酸素性作業閾値(anaerobic threshold; AT)によって全身持久力を評価する考えもある。ATとは運動に伴って有酸素的エネルギーの産生過程に無酸素性代謝も参加してくる時点を指す。この閾値はVo2maxの55~65%という中程度の運動負荷時で現れ、この時の酸素摂取量をもって表す。最大酸素摂取量とATには正の相関がある。ATはVo2maxのように強い負荷を加えて測定する必要がなく、障害者には適した指標であるといえる。
全身持久力が向上する機構を考えよう。酸素摂取量はFickの原理によると次のように表わされる。
酸素摂取量=一回拍出量×心拍数×動静脈酸素較差 (4)
全身的な運動を行うと酸素輸送系が活発に働き、心臓から多くの血液が駆出されるようになる。心筋はこれに対応するために骨格筋のように肥大する。この結果、心容積の拡大と収縮力の増強がおこり、一回拍出量が増大する。一回拍出量の増加によって循環血液量の確保が容易になり、心拍数の低下がみられてくる。つまり余裕力が高まったのである。さらに、総血液量やヘモクロビン量の増加ともあいまって酸素輸送能力が増大し全身持久力が向上する。
全身持久力の向上を図るトレーニングの至適条件は専門諸家で必ずしも一致していない。一つの目安としては、運動強度が最大酸素摂取量の約60%(60%Vo2max)あれば日常生活に必要な持久力を高めるのに最高水準の強度であり、30%Vo2maxでも軽度の作業に対する余裕力を大きくするといわれている。持続時間については、呼吸循環機能がその負荷に対して定常状態になるのが運動開始から3分後であり、少なくともこれ以上の時間は必要である。頻度は一日おきが適当という意見が多い。しかしながら、高齢者など初期体力の低い者に対して比較的低い強度で長時間(50%Vo2max、60分)のトレーニングを行い、その効果を確認した報告もある。障害者は通常大きな運動負荷を経験することが少なく、廃用性の機能低下や易疲労性も高い。全身持久力のトレーニングは呼吸循環機能に負荷を与えるものであり、トレーニングの実施にあたっては安全面に充分注意して余裕をもったプログラムを処方するように心掛けなければならない。
6.おわりに
我が国の障害者スポーツの創始者故中村裕は「身障スポーツはあくまでリハビリテーションの一環としておこなわれるべきでありひとつのサイエンスである」と述べている。肢体に障害をもつ子供を含め障害者の運動とその実践に関する系統的、科学的な取り組みはこれからの課題である。我々は運動によるリハビリテーションの基礎を運動生理学に求め、また、幾つかの研究を通してリハビリテーション運動生理学、障害運動生理学なる領域の必要性を痛感した。本稿は著者の一つの提案である。多くの研究と実践の蓄積によって新しいリハビリテーションのサイエンスが確立することを期待する。
文献
(1) 中村裕:国際身体障害者スポーツ大会を終りて.整形外科16: 459-480 (1965) (本文に戻る)
(2) WHO: International classification of impairments, disabilities, and handicaps. Geneva (1981)(本文に戻る)
(3) 中村裕伝刊行委員会(編):中村裕伝.中村裕伝刊行委員会 (1988)(本文に戻る)
(4) 日本身体障害者スポーツ協会(編):創立20周年史.日本身体障害者スポーツ協会 (1985)(本文に戻る)
(5) 猪飼道夫(編):身体運動の生理学, 杏林書院, 東京 (1973)(本文に戻る)
(6) 大島正光、松田源彦(監訳):宇宙医学.同文書院 (1986)(本文に戻る)
(7) 赤滝久美、三田勝己、伊藤晋彦、鈴木伸治:下半身陰圧負荷法による循環調節機能の評価-長期臥床の重症心身障害者を対象として-.医用電子と生体工学 30:14-21 (1992)(本文に戻る)
(8) 鈴木伸治、赤滝久美、三田勝己、渡壁誠:非線形幾何学モデルを用いた下肢関 節可動域の定量的評価.第33回リハビリテーション医学会学術集会予稿集(1996)(本文に戻る)
(9) 福永哲夫:ヒトの絶対筋力.杏林書院 (1978)(本文に戻る)
(10) 三田勝己、石田直章、赤滝久美、伊藤晋彦、小野芳裕、沖高司:二分脊椎症児における大腿四頭筋筋力の分析と歩行能力の推定.リハビリテーション医学 30:54-62 (1993)(本文に戻る)
(11) 金子公宥:人体筋のダイナミックス.杏林書院 (1974)(本文に戻る)
(12) 伊藤正男:脳の設計図.中央公論社 (1980)(本文に戻る)
(13) 加賀谷熈彦、加賀谷淳子:運動処方-その生理学的基礎-.杏林書院 (1983)(本文に戻る)
文献情報
著者:三田勝己
題目:「肢体に障害をもつ子供の運動とその実践」
雑誌名:『医療体育』(医療体育研究会)15巻 pp.80-88
文献に関する問い合わせ先:
愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所
三田勝己
春日井市神屋町713-8
TEL & FAX:0568-88-0811
