親の障害の認識と受容に関する考察-受容の段階説と慢性的悲哀
中田洋二郎
国立精神・神経センター精神保健研究所
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表年月 | 1995年12月 |
| 備考 | 早稲田心理学年報第27号 |
A Parental Response to Having a Child with Developmental Disorders:A Stage Model or Chronic Sorrow?
Yujiro Nakata(National Institute of Mental Health,NCNP,Japan)
Waseda Psychol.Rep.,1995 Vol.27 83~92
はじめに
発達に障害のある子どもの親はどのように障害の状態を認識し受容するのだろうか。これまでの研究ではいくつかの異なる見解が論じられてきた。この論文では、それらの見解を概観し私たちが行った障害の告知と障害の認識に関する調査の結果から障害児の親の障害受容の過程について考察する。
1.障害受容についての段階説
障害受容の過程は混乱から回復までの段階的な過程として説明されることが多い。図1は、我が国で頻繁に引用されるDrotar,et al. (1975)の段階説である。この図では先天性奇形を持つ子どもの誕生に対してその親の反応を、ショック、否認、悲しみと怒り、適応、再起の5段階に分類している。
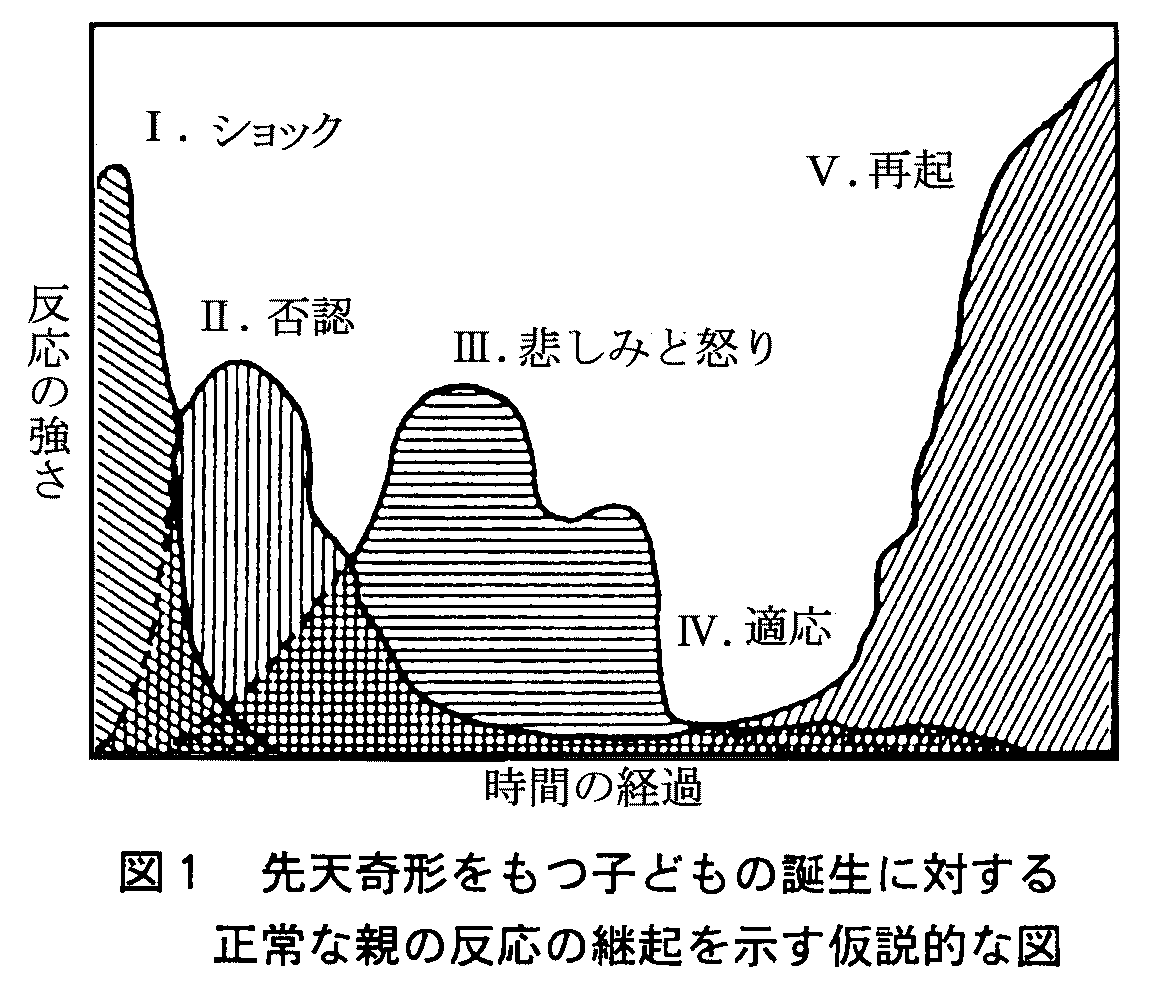
他にも多くの段階説があるが、Blacher (1984)は親の障害受容の段階に言及した24の論文を概括して、これらの段階区分が大きく3つの段階にまとめられることを見いだしている。すなわち、最初の危機反応、持続する感情と反応、適応と受容の3つの部分である。
障害受容の段階説は久保 (1982)が指摘するように、「均衡-不均衡-再均衡」という過程と専門家の介入法について論じる点でクライシス論の一部であると考えられる。しかし、主なクライシス論がストレス・コーピングやサポート・システムという鍵概念を用いて介入法を論じるのに対し、段階説は主として障害者の親の心の軌跡に焦点を当てている。そしてもっとも異なる点はその生い立ちであろう。初期の段階説は、Freud (1917)の「悲哀とメランコリー」で述べられた対象喪失と喪の作業を基礎に発展したといえる。SolinitとStark (1961)は「障害児の誕生と喪」と題した論文で、「Freudが貢献したナルシズムとその推移に関する理解は対象喪失(我々の場合、切望した健康な子どもの喪失)の研究の本質である」と述べ、障害受容をリビドー論によって論じている。
彼らの説はFreudの理論を障害受容の過程へ単にひき写したものであるが、障害児が誕生することを親にとっての「期待した子どもの死」と見なしたことに特徴があった。その考えは、「もし喪の過程が家族の持続した雰囲気として安定しなければ、切望し期待した健康な子どもの亡霊が、家族が障害の子になじむのを妨げつづける」という表現に端的に現れている。また、過去の愛着の対象(理想の子ども)の喪が完成してはじめて現実の子(障害を持つわが子)との関係が形成されるという考えの背景にはBowlbyのアッタチメント理論の影響がある。
私たちは、愛する肉親を失ったときの悲哀とそれから回復する過程を経験的に理解している。対象喪失論に基づく段階説は、人々に障害児の親の苦悩の深さと親の悲嘆や怒りが正常な反応であることを理解させる点で優れている。しかし、障害児を持つことがすべての親にとってこのように理想の子の喪失感として受けとめられるのだろうか。また、対象喪失論は、障害を知った時から生じるわが子の将来を愁いあぐねる親の苦悩を軽視し過ぎないだろうか。とくに後者の疑問は障害を知った後の家族をどうケアするかという問題と直接的に関わっていると思える。
たとえば、Kennedy (1970)は「障害児の誕生後の2ないし3ヵ月の間ケースワーク面接は妊娠中のファンタジーに焦点を合わせるべきであり、デカセクシスが完成するまでは現実的な事柄を話し合うのはみあわせるべきだ」と述べ、母親の喪を完成するために子どもと分離される期間が必要だろうと論じている。これは母子の愛着形成のためにも一時的に母子を分離すべきだという主張である。しかし、多くの親は早い時期から障害の子をどのように育てればよいのか迷い、具体的な智恵を求めているのが現実であろう。
障害児の誕生が理想の子の死であるとういう仮定はその後の論文でも散見される。この考えに従えば、親が障害を受容できない状態は、死んでしまった過去の子ども(理想の子ども)のイメージにしがみついている病理的な状態ということになる。
我が国にも障害の受容の段階を記載した研究がいくつか認められる。鑪 (1963)は障害児の親の手記を材料に受容の段階を1.子どもが精神薄弱児であることの認知過程、2.盲目的に行われる無駄な骨折り、3.苦悩的体験の過程、4.同じ精神薄弱児をもつ親の発見、5.精神薄弱児への見通しと本格的努力、6.努力や苦悩を支える夫婦・家族の協力、7.努力を通して親自身の人間的な成長を子どもに感謝する段階、8.親自身の人間的成長、精神薄弱児に関する取扱いなどを啓蒙する社会活動の段階、に区分している。
他にダウン症の母親の障害受容の過程について論じたものに要田 (1989)や田中 (1990)がある。これらの説は、いずれも対象喪失論を基礎としない点、また再適応をさらに越えた最終段階を主張する点で欧米の諸説と色合いを異にする。彼らは、最終段階を人間的成長、価値の変換、価値観の転換などと表現し、障害児の存在が必ずしも負の影響だけを家族に与えるものでないことを示唆した。
障害児をもつことが家族のストレスとなり負担となることにこれまでの多くの研究は注目した(新見ほか 1981、谷口 1985、新見ほか 1985、橋本 1980,Orr et al. 1991、Dyson 1991、Sloper et al. 1991)。しかし、障害受容の過程で障害児の家族が人間的に成長するという事実にはあまり関心がはらわれてこなかったようである。障害児を持つことが負担ばかりでなくその家族の人生に肯定的な影響を与えることは、障害児の家族を援助する立場にある専門家が見逃してはならない観点であると思う。
ところで、以上の諸段階説の共通する特徴は、総称として「経過・躍進モデル time bound model」(Wikler, et al. 1981, Damrosch et al. 1989, Clubb, 1991)と呼ばれるように、障害を知ったために生じる混乱は時間の経過のうちに回復する、つまり終了が約束された正常な反応であると規定する点にある。別な見方をすると、障害児のすべての親がいずれは受容の段階に達することを前提としているといえる。しかし、通常どのくらいで悲哀から回復するのかという疑問が解決されないかぎり、ある時期、悲哀から抜け出せない状態が正常か異常かはそれぞれの専門家の判断にゆだねられる。また、障害の受容をすべての親にとって越えなければならない課題と見なした場合には、その段階に達していない親に過酷な要求をすることにもなる。そのため専門家の恣意的な判断が親の苦悩をより深める結果ともなりうる。障害受容の過程における段階説はこのような危険性を内包しているといえる。
2.障害児の親の慢性的悲哀
再適応を前提としている段階説とはほぼ逆の見解がOlshansky (1962)によって主張された。それは精神遅滞の子どもの親の慢性的悲哀 chronic sorrow についての論述である。この言葉の邦訳は「絶えざる悲しみ」(Olshansky 松本訳 1968)あるいは「慢性的悲嘆」(渡辺 1982)と訳されているが、邦訳と原語のどちらも障害児の親が子どもの障害を知った後に絶え間なく悲しみ続けている状態という響きをもっている。
おそらくそのためであろうが、この状態は正常な状態ではなく、<親がさまざまな防衛機制を働かせる状態>(渡辺 1982)、あるいは<「真の」受容に達していない状態>(要田 1989)など、否定的に受けとめられる傾向がある。しかし、Olshanskyの発表の主旨は慢性的悲哀を正常な反応として認めることにあった。
その主張をかいつまんで述べると次のようになる。精神薄弱児の大多数の親は広範な精神的な反応、つまり慢性的な悲哀に苦しんでおり、医師や臨床心理士やソーシャル・ワーカーなどの専門家はそのことにあまり気づいていない。そのため、専門家は親に悲哀を乗り越えることをはげまし、親がこの自然な感情を表明することを妨げる。また、精神遅滞児の親にとって自然な反応(慢性的悲嘆)をむしろ神経症的な症状と見なし、かえって、親が現実を否認する傾向を強める要因となっている。
彼の論説は多くの実践家の共感を得たようであるが、研究すべき対象として慢性的悲哀に関心が向けられたのはWikler,et al. (1981)が実証的な調査を行ってからであった。彼らは調査の対象となった障害児の親の1/4が段階説のような一過性の悲哀の時期を経験したが、残りの親は落胆と回復の過程の繰り返し、つまり慢性的悲哀を経験したと報告している。また、Damrosch,et al.(1989)は図2のような段階説と慢性的悲哀を図式化した対照図を用いて、ダウン症の親を対象にWiklerらの調査を追跡している。そこでは、父親の17%に、母親の64%に慢性的悲哀が経験されたと報告されている。
Wiklerらの研究でいっそう明確になったことは、子どもが一般に歩き始める時期や言葉が出る時期また進学する時期など発達の節目に悲哀が再起することであった。すなわち慢性的悲哀は、常に悲哀の状態にあるのではなく、健常児では当たり前の発達的な事象や社会的な出来事が障害児の家族の悲哀を再燃させるきっかけとして潜在的にあり、そのために周期的な表れかたを示すということである。
現在、この概念は精神遅滞の親を支える専門家だけでなく慢性疾患の患者の看護や家族をケアする領域の人々の関心を呼んでいる(Worthington 1989, Phillips 1991, Hummel 1991, Eakes 1993)。このような広がりを見せる背景には、慢性疾患が家族にとっての絶え間ないストレスであり、同時に病状の変化など家族の悲哀が再燃するきっかけを内包している点で、障害児の親の生活と非常に近い状況にあるからではないだろうか。
慢性的悲哀への関心は広がりつつあるがその概念はいまだ明確ではない。これまでの障害児の親また慢性疾患や未熟児の親の慢性的悲哀について述べた論文を対象に、慢性的悲哀について共通する特徴を要約すると以下のようになる(Fraley 1990, Teel 1991, Cluub 1991, Lindgren et al. 1992)。
1.慢性的な疾患や障害のような終結する事がない状況では悲哀や悲嘆が常に内面に存在する。
2.悲嘆は常には顕現しないが、ときに再起するかあるいは周期的に顕現する。
3.反応の再起は内的な要因が引き金になることもあるが、外的な要因、例えば就学など子どもが迎える新たな出来事がストレスとして働きそれが引き金となる。
4.この反応には、喪失感、失望、落胆、恐れなどの感情が含まれる。また事実の否認という態度も並存することがある。
以上、障害の受容に関するふたつの見解について述べた。概括したようにどちらの理論も臨床的経験から構築された仮説である。その点では実証性に欠け今後検証しなければならない事柄を多く残している。とくに、論文のなかには障害の種類が不詳であったり種々の障害を一括して論じている傾向があり、そのため、あらゆる種類の障害にそれぞれの見解が適合するかのように見える。障害の発見や診断の経過は障害の種類によって異なると思われる。したがって、障害を認識し受容する過程もその影響を受けることが予想される。そこで、障害の種類による障害受容の過程を検討することが必要と考えられる。 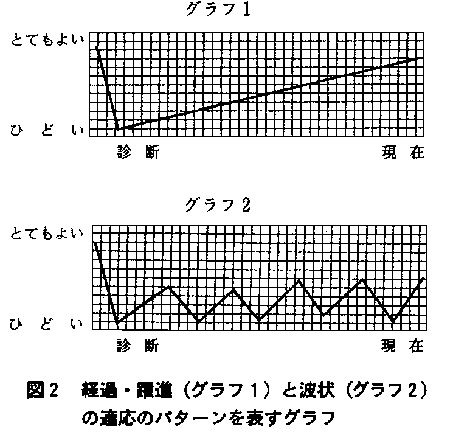
3.障害の告知と認識の調査について
障害の種類による障害の発見・受診・診断の経過
と障害認知の経過の違いを分析することで障害の受容の過程を明らかにできると考えここに私たちの調査を紹介する。
調査の概要
この調査の概要を表1に示した。これにみるように、調査の対象は当時6歳(就学児)以上、20歳以下の発達障害児・者の母親である。調査に協力したのは、障害児の親の会の加入者686世帯のうち72家族であった。それは調査の対象とした年齢に該当する子どもを持つ会員の22.4%にあたる。
調査対象となった子どもの平均年齢は13.2歳、男子52名女子20名であった。障害の程度は現在の療育手帳の判定により判断した。重度と判定されているものが36名、中度が14名、軽度が13名であった。療育手帳の未申請のものが9名(12.5%)で、これらの障害の程度は不明である。対象児の診断は大きく分類して、ダウン症や小頭症など病理型の精神遅滞17名、精神遅滞を伴う広汎性発達障害44名、それ以外の精神遅滞11名であった(以下、順に病理群、自閉群、精神遅滞群と呼ぶ)。
調査は半構成的面接法で、対象児・者の障害の程度や診断名また子どもの異常に気づいてから障害を認識するまでの経過について質問項目に従い面接者が口頭で質問し、被面接者である障害児の母親が自由に口述する形式を採用した。なお、調査は平成6年1月~4月に行われ、調査員はいずれも障害児の相談・評価業務に携わっている臨床心理士・ソーシャルワーカーであった。
以下の結果はこの面接で口述された内容を分類した資料を基礎にしている。
| 調査方式 | 半構成的面接法 |
| 調査協力母体 | 千葉県東葛地区の自閉症親の会 手をつなぐ親の会 |
| 調査協力者 | 72人 |
| 被面接者 | 母親 |
| 障害児(者)の年齢 | 6歳~20歳 |
| 平均年齢 | 13.2歳 |
| 男児 | 52名 |
| 女児 | 20名 |
| 障害種別 | 病理型精神遅滞 17人 広汎性発達障害 44人 その他の精神遅滞 11人 |
| 障害の程度 (療育手帳から) |
軽度 13人 中度 14人 重度 36人 手帳未申請 9人 |
結果
(1)異常を発見し診断を受けるまでの経緯
図3は各群が障害に気づいた時期、最初に医療・相談機関を受診した時期、診断を告知された時期の平均を示したものである。この図のように病理群の大半の例はこの3つの出来事が出生時からほぼ1ヵ月ころまでに生じている。しかし、自閉群と精神遅滞群が異常に気づくのは平均的には1歳半から2歳までの時期であり病理群より1年以上遅い。また両群とも異常に気づいてから、最初に医療・相談機関を受診するまでに平均してさらに約半年ほど経過している。診断の告知を受けた時期も最初に受診した時期から自閉群で平均1年2ヵ月、精神遅滞群で平均1年10ヵ月ほどを経過した。
このような結果から、病理群は障害の発見と受診と確定診断という出来事がほぼ出生直後に連続して生じ、病理群の親はいちどきにそれらを経験するといえる。それとは対照的に、自閉群と精神遅滞群は異常に気づく時期、それに対処する時期、確定診断の時期は生後1年ないし2年以降で、これらの群の親はそれらの出来事を時間的に緩やかに経験していくといえる。
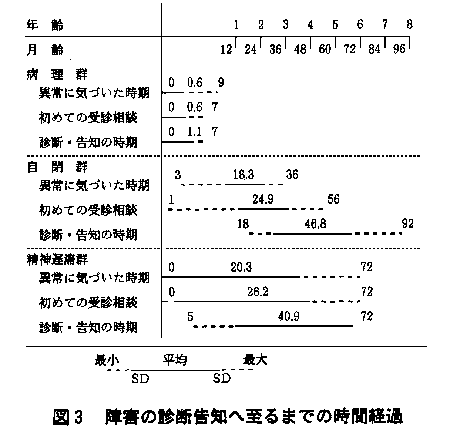
(2)異常に気づいた人物
最初に異常に気づいた人物を表2に示した。病理群では大半が医師等によって異常を発見されている。
| 医師など 専門家 |
父・母 両親 |
親と専門家 の両方 |
親と親戚 | 親戚や 知人 |
|
| 病理群 | 14(82.4) | 2(11.8) | 1(5.9) | - | - |
| 自閉群 | 3( 6.8) | 33(75.0) | 5(11.4) | 2(4.5) | 1(2.3) |
| 精神遅滞 | 3(27.3) | 6(54.5) | - | 1(9.1) | 1(9.1) |
(括弧内は各群の事例総数に対するパーセント)
それに対し、自閉群・精神遅滞群の多くは家族が最初に異常に気づいている。親が最初に異常に気づくことは、そのことによって障害を予測した行動がとれ、突然に障害を伝えられる親よりも告知に対して心の準備ができている状態といえる。その点で、病理群は自閉群や精神遅滞群よりも告知の衝撃を強く受けやすいといえる。
(3)最初に受診した機関と障害告知
各群が最初に受診した機関を表3に示した。病理群では子どもを出産した病院で異常を発見された例や検査のために出生後他の小児科のある病院に紹介された例が多い。一方、自閉群や精神遅滞群が最初に受診した機関は、保健所あるいは乳幼児健診、小児科・内科、耳鼻科、眼科、神経・精神科、児童相談所、療育センター、教育センター、大学の発達相談室など多岐にわたっている。とくに自閉群では23例(52.3%)が保健所や乳幼児健診が最初の受診機関であり、この点では精神遅滞群とも異なった。
最初の機関で診断名を伝えられた例は病理群で15例(88.2%)、自閉群では5例(11.4%)、精神遅滞群では1例(9.1%)であった。しかも、最初に受診した機関で問題ないと言われた事例が自閉群に10例(22.7%)、精神遅滞群に3例(27.3%)あり、この点は病理群と明らかに異なった。
| 時期 | 産婦人科 | 内科 小児科 |
神経科 精神科 |
眼科 耳鼻科 |
乳幼児検診等 | 児童相談所 | その他 | 計 |
| 病理群 | 12 70.6 |
5 29.4 |
- | - | - | - | - | 17 |
| 自閉群 | - | 3 13.6 |
5 11.4 |
4 9.1 |
23 52.2 |
3 6.8 |
3 6.8 |
44 |
| 精神遅滞群 | 1 9.1 |
5 45.5 |
- | - | 2 18.2 |
1 9.1 |
2 18.2 |
11 |
| 13 18.1 |
16 22.2 |
5 6.9 |
4 5.6 |
25 34.7 |
4 5.6 |
5 6.9 |
72 |
(4)障害の認識の時期とそのきっかけ
障害を認識した時期は何歳何ヵ月と特定することが困難な場合が多い。多くの事例では幼稚園や通園施設の入園や就学の時とか、それからどれくらい経ってからというように語られた。そのため本報告では障害の認識の時期を大きく、乳幼児期0~2歳、幼児期3~4歳、幼児期5~6歳、小学校1~2学年、3~4学年、5~6学年、中学校以降という7つの時期に区分した。
それぞれの群の障害の認識の時期は図4に示されている。病理群は17例全員が0~2歳の時に障害を認識している。それに対し、自閉群や精神遅滞群が障害を認識する時期は0~2歳から中学校以降まで広範囲にわたった。
表4は各群の障害を認識するきっかけを示している。「医療・相談機関で診断されて障害を認識した」のカテゴリーに属する回答が病理群は13例(76.5%)あり、病理群の大半が診断告知とほぼ同時期に障害を認識している。しかし、自閉群・精神遅滞群では「健常児の成長と比較して」、あるいは「他の障害児の行動や発達を見て」という<他の子との比較>のカテゴリーに入る回答が、自閉群28例(63.6%)、精神遅滞群7例(63.6%)で最も多かった。「医療・相談機関で診断告知されて」をきっかけとしてあげた事例は、自閉群で13例(29.5%)・精神遅滞群で3例(27.3%)あったが、これらの大半は他のカテゴリーと重複する口述であった。
| 病理群 | 自閉群 | 精神遅滞群 | |
| 医療・相談機関で診断告知されて | 13(76.5) | 13(29.5) | 3(27.3) |
| 健常児の成長と比較して、あるいは 他の障害児の行動や発達を見て |
1(5.9) | 28(63.6) | 7(63.6) |
| 本や他のメディアの情報から 理解して |
4(23.5) | 12(27.3) | 1(9.1) |
| 入園・就学など進路を決めたり変更 する際に、諦めあるいは覚悟を 定めて |
- | 10(22.8) | 4(36.4) |
| 子どもの発達が標準へ追いつかな い、あるいは異常な行動が続くこと から |
- | 3(6.8) | - |
| 障害を認めたうえで個人の自立を 促そうと決心して |
1(5.9) | 3(6.8) | - |
| 無回答 | 2(11.8) | - | - |
(左は実数、括弧内は各群のパーセント)
(5)障害告知と障害認識の時期のずれ
次に診断告知と障害の認識の関連をこの二つの出来事が起きた時期で比較する。図5に示すように、病理群では障害の認識と診断告知は全例が同じ時期区分であった。しかし、自閉群では12例(27.2%)、精神遅滞群では5例(45,5%)が診断告知と障害の認識が同じ時期であったが、自閉群の事例の大半、また精神遅滞群の半数以上は障害の認識の時期が診断告知の時期よりも遅れた。また、自閉群の中には診断の告知以前に障害を認識していたという事例が9例あった。
4.障害受容の過程に関する考察
以上のように障害の種類によって親が子どもの異常に気づき障害を認識するまでの過程は明らかに異なる。このような結果には家族状況をはじめとしてさまざまな事柄が関連しているが、もっとも共通する要因としては確定診断の難易の問題があるように思われる。
(1)早期の確定診断と障害告知の衝撃の関連
ダウン症をはじめとして多くの病理型の精神遅滞の場合、染色体検査やその他諸検査によって早期に診断が確定できる。一方、自閉症や精神遅滞の多くは自閉症状や知的な遅れの程度がある年齢になるまで確定しにくい。このように診断を確定する困難度の違いは親が障害について知る時期に影響を与える。
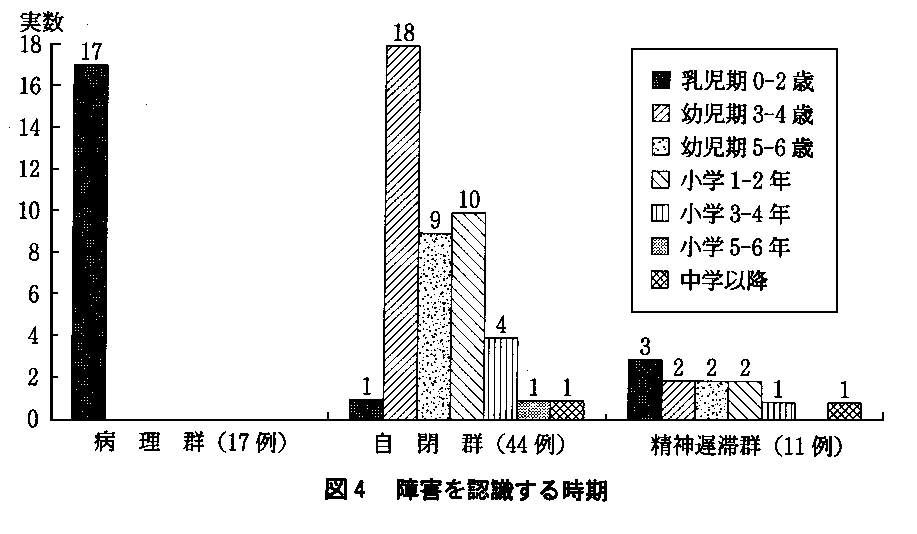
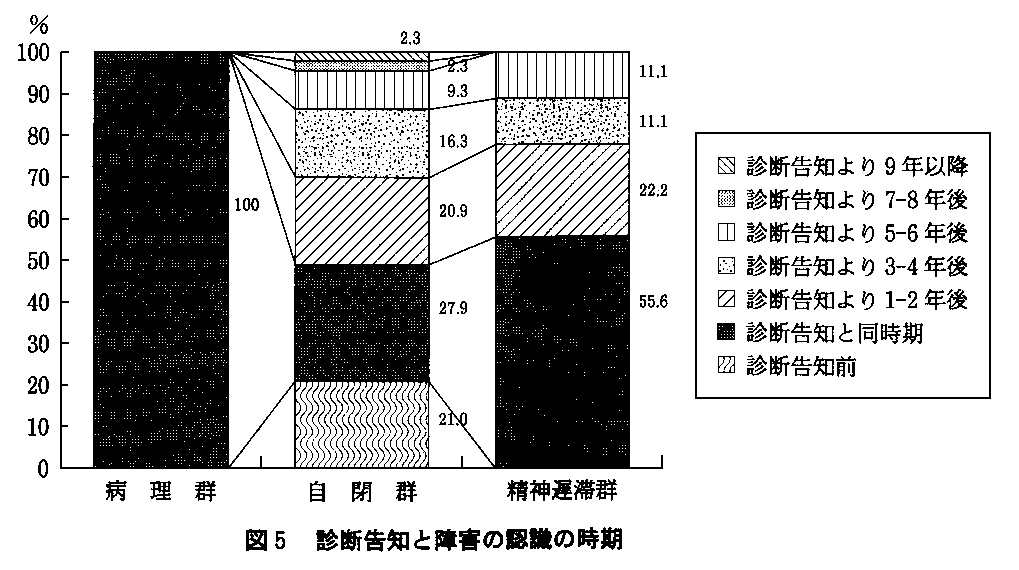
また、病理群の親はわが子の異常に気づかないうちに医師等から子どもの異常を伝えられ、受診後ほぼ1ヵ月のうちに障害が明らかになる。この状況は、親にとっては突然にしかもいちどきに不安な出来事がおそってくる感じであろう。そのため、病理群のほとんどの親は障害を告知されたときに極度の精神的混乱を経験し、その後、段階説で述べられているような悲しみや否認や怒りなどの感情を報告している。このように、確定診断が早期に可能な疾患は障害告知の衝撃を強く受け、段階説に近い反応が生じるといえる。
(2)障害の種類による状態の解りにくさ
確定診断が容易な疾患は検査結果が明瞭でまた外見に特徴がある場合が多く、そのため親は障害を認めやすい。ところが自閉症や精神遅滞の一部は外見には異常が認められず発達の経過から障害が理解される場合が多い。そのため障害を認識するためには子どもの発達に関する知識がある程度必要となる。一般的に親は発達に関する知識が少ないため、親にとって状態像を客観的に理解し障害を認めることは容易ではない。
また、病理群と異なり自閉群や精神遅滞群では障害の確定が困難で、多くの事例は医療・相談機関をめぐり歩いた末に診断されていた。診断を期待して医療・相談機関を訪れた親にとっては、この経過は「はっきり言ってくれず物足りない」「専門的な知識が乏しく親の疑問に答えられない」「通うだけの価値があるのか疑問だった」という印象を与えている。自閉群・精神遅滞群の多くの事例にとって障害の告知は障害認識のきっかけとはならなかった。たとえば、「徐々にわかってきた。普通学級に入れぬことが大きい出来事」(精神遅滞男児 18歳 重度)と述べた事例のように、障害を認識するにはある時間の経過が必要であり、また通常の生活への期待を裏切られる出来事がきっかけとなっている。おそらくこのような群の親が障害を認めにくい要因に、前述のように親にとって障害の状態が理解しにくいこと、また確定診断が困難なために専門機関での状態や経過の説明が暖昧であったり不十分であったりすることが関連していると思える。
(3)障害の確定の困難さと慢性的悲哀の関連
診断の確定が困難で状態が理解しにくい疾患の場合、わが子の状態が一時的なものではなく将来にも及ぶことを認めるために、親は子どもの発達がいつか正常に追いつくのではないか、あるいは自閉が「治る」のではないかという期待を捨てることが必要となる。それまでは、親は否定と肯定の入り交じった感情の繰り返しを経験せざるをえない。これは、いわば親にとって慢性的なジレンマの状態といえる(Willner et al. 1979、Murphy 1982)。
このようなジレンマの経験は、障害を認めた後にも外部の条件によって悲哀が呼び覚まされやすい傾向をつくるのではないだろうか。たとえば、ある事例が「ショックはその都度あって、期待やあきらめの両方があると思う。今ももしかしてという期待もあるし、普通に追いつかないこともあるんだというあきらめの部分がある。今だって悲しい気持ちや落ち込むけれどその波がだんだん緩やかになっている感じかと思う」(自閉症男児 11歳 中度)、「成長の節々で結局は落ちこぼれの方を選ばざるをえず、だんだん覚悟ができてきた。発達はするが普通にはなれないということを受け入れるのは難しい。ショックを受け泣きながら立ち直る繰り返しかと思う」(精神遅滞および自閉症女児 12歳 重度)と述べている。このふたつの例の期待と落胆の繰り返しの過程は前述した慢性的悲哀の概念に近い状態といえる。
(4)障害受容の過程:螺旋形モデルについて
病理群の経過から明かなことは、早期診断が可能な障害では、診断告知はその唐突さのために衝撃を強め、また診断の確かさのために親の落胆を深める。障害の告知による衝撃とその後の混乱、またそれから回復する過程は段階説で述べられていることとかなり一致する。一方、自閉群や精神遅滞群など診断の確定が困難な事例では、親は慢性的なジレンマの状態に陥りやすい。慢性的悲哀の概念はこれらの群を理解するのに役立つであろう。
しかし、段階説や慢性的悲哀の概念をすべての障害に適用することは、その説が適合しない場合には親の状態の理解を歪め、誤った援助の方法を採用する危険性がある。このふたつの説を包括し広範に適用できる障害受容の過程のモデルがあれば、親の心を理解し援助するための方途を考えるうえで有用ではないかと考えられる。
Copley, et al.(1987)は慢性的悲哀の概念に段階説を取り込んだモデルを報告している。そのモデルの第1の位相は衝撃、否認、悲嘆の循環が生じる時期であり、この循環を親が切り抜けた時に第2の位相に達する、第2の位相では慢性的悲哀がときどき生じるが、親は外界へ目が向き終結へ進むというものである。このモデルは初期の反応と慢性的悲哀を関連づけているが、受容を課題と見なす傾向や最終ゴールを設定するという段階説の特徴を取り入れてしまう結果となっている。
さまざまな障害また事例の個々の違いを考慮しかつ全体的にも適用が可能なモデルが必要である。そのためには、まず障害受容を段階としてとらえないこと、とくに障害受容を課題としないモデル、また、慢性的な悲哀やジレンマが異常な反応ではなく通常の反応であるという理解を促すモデルを考えなければならない。そこで筆者は図6のような障害受容の螺旋形モデルを提案する。このモデルは障害の受容の過程の違いを統合することができ、次のような仮定と特徴をもっている。
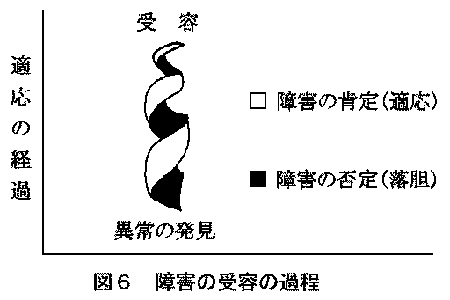
親の内面には障害を肯定する気持ちと障害を否定する気持ちの両方の感情が常に存在する。それはいわば図6に示したように表と裏の関係にある。そのため、表面的にはふたつの感情が交互に現れ、いわば落胆と適応の時期を繰り返すように見える。また、その変化を一次元の平面で見れば否定から肯定への段階のごとくに見え段階説的な理解が生じる。しかし、その過程は決して区切られた段階ではなく連続した過程である。すなわち、段階説が唱えるゴールとしての最終段階があるのでばなく、すべてが適応の過程であると考えられる。
しかし、実際の臨床では受容が困難な事例がある。その背景には家庭環境や親の性格や周りの援助などさまざまな要因が関連している。図6の螺旋形の上下を引いたり押し縮めた形を想像することで受容が困難な事例や逆に容易な事例が理解される。たとえば、受容の困難さは螺旋形が引き延ばされることでより否定の面が多く現れた例である。また受容が容易な例は螺旋形が縮められ、否定が肯定の裏側に隠れることで表現される。つまり適応した状態が表面に現れた例である。
このように受容の困難な事例や容易な事例の違いは、障害の告知・障害の認識・障害の受容という過程にかかる時間的な経過の違いとして表現される。しかし、どの事例も肯定と否定の両面の感情を持っており、すべてが受容の過程を進んでいる点で本質的には違いがないと理解すべきではないだろうか。螺旋形モデルはそのことを主張するものである。
障害受容の過程を段階ではなく、肯定と否定の両面をもつ螺旋状の過程と考えることは親が現実を認識できず障害を受容できない状態を理解することに役立つ。たとえば、いわゆるショッピングと呼ばれる複数の医療・相談機関や療育機関を訪ね歩く親がいるが、それは障害を否認するための行為だとみなされてきた。しかし、それが障害を確かめる積極的な行動である場合も多い。従来、否定的にとらえられてきた親の行為もその裏側に現実を認めようとする親の葛藤が存在するといえるのではないだろうか。
おわりに
今回の調査から得られた印象は、確定診断の困難さや専門家の説明の暖昧さが障害の否認の傾向を助長している場合が少なくないということであった。障害を受容できる親、受容できない親という見方をする以前に、専門家としてはまず現在の状態と将来の発達の経過をわかりやすく説明すること、親の疑問に正確に答える努力をすべきであろう。
また、専門家が親に障害名を言うのを見あわせたり、またときに説明が暖昧になる背景には、衝撃をできれば避けたいという配慮がある。しかし、病理群のように親が障害を予測しないうちに医師から障害を伝えられる場合には告知の衝撃を避けることはできない。その場合、診断告知が単に障害名を伝えるだけであってはならない。治療の方法や今後の予測を伝え、生活面の指導などを同時に行うことが大切ではないだろうか。わが子の障害を知って混乱した状態にある親にどのように事実を伝えていくか、その技術の開発も必要である。また伝えた後の継続した援助の方法を具体的に検討し確立していかなければならないだろう。
障害の受容の過程は、障害の原因の解明や治療方法また療育や援助方法の開発が進み、同時に世間の障害に対する偏見が是正されることによって変化するであろう。障害受容のモデルもその変化につれて変わりあるいは役割を終えるときがあることを期待したい。
謝辞:調査にご協力いただいた親の会の皆様に厚くお礼を申し上げます。また調査の面接を担当された皆様に感謝します。調査やそのまとめに有益なご意見をいただきました国立精神・神経センター精神保健研究所の白井泰子先生に深く感謝いたします。なお、引用の調査は安田生命社会事業団1993年度研究助成(代表:上林靖子)によって「障害の診断と告知」の研究会で行ったものです。
参考文献
Blacher,J. 1984 Sequential stages of parental adjustment to the birth of a child with hand-icaps: fact or artifact? MentalRetardation, 22(2) , 55-68.
Clubb,R. 1991 Chronic sorrow: Adaptation patterns of parents with chronically ill chil-dren. Pediatric Nursing, 17(5) , 461-466.
Copley,M., & Bondensteiner,J. 1987 Chronic sorrow in families of disabled children. Journal of Child Neurology, 2, 67-70.
Damrosch,S., & Perry,L. 1989 Self-reported adjustment, chronic sorrow, and coping of parents of children with Down syndrome. Nursing Research, 38(1) , 25-30.
Drotar,D., Baskiewicz,A., Irvin,N., Kennell,J., & Klaus,M. 1975 The adaptation of par-ents to the birth of an' infant with a con-genital malformation :A hypothetical model. Pe-diatrics, 56(5), 710-717.
Dyson,L.L. 1991 Families of young children with handicaps: Parental stress and family functioning. Arnerican Journal on Mental Retardation, 95(6) , 623-629.
Eakes,G. 1993 Chronic sorrow:A response to living with cancer . OitcologyNursingForum. 20(9) , 1327-1334.
Fraley,A. 1990 Chronic sorrow:A parental response. Journal of Pediatric Nursing, 5(4) , 268-273.
フロイトS.1917 悲哀とメランコリー フロイト著作集 第6巻 井村恒郎他(訳)1975 人文書院 Pp.137-149.
橋本厚生 1980 障害児を持つ家族のストレスに関する社会学的研究-肢体不自由児を持つ家族と精神薄弱児を持つ家族の比較を通して- 特種教育学研究,17(4),22-31.
Hummel,P.A., & Eastman,D.L. 1991 Do parents of preterm infants suffer chronic sorrow? Neonatal Networh, 10(4) , 59-65. Kennedy,J. 1970
Maternal reactions to the birth of a defective baby. Social Casework. 51 , 410-417.
久保紘章 1982 障害児をもつ家族に関する研究と文献 ソーシャルワーク研究,8,49-54.
Lindgren,C., Hainsworth,M., & Eakes,G. 1992 Chronic sorrow: A Iifespan concept. Schol-arly Inquiry for Nursing Practice: An Inter-national Journal, 6(1) , 27-40.
Murphy,M. 1982 The family with a handi-capped child: A review of the literature. Developmentaland ~ehavioral Pediatrics. 3(2) , 73-82.
新見明夫・植村勝彦 1981 就学前の心身障害幼児をもつ母親のストレス-健常幼児の母親との比較- 発達障害研究,3(3),206-216.
新見明夫・植村勝彦 1985 学齢期心身障害児をもつ父母のストレス-ストレスの背景要因- 特種教育学研究,23(3),23-34.
Olshansky,S. 1962 Chronic sorrow: A re-sponse to having a mentally defective child. Social Casework. 43, 190-193.
Olshansky,S. 1962 絶えざる悲しみ-精神薄弱児をもつことへの反応- 松本武竹子訳 1968 家族福祉 家族診断・処遇の論文集 家庭教育社 Pp.133-138.
Orr,R.R., Cameron,S.J., & Day,D.M. 1991 Coping with stress in families with children who have mental retardation : an evalua-tion of the double ABCX model. American Journal on Mental Retardation, 95(4) , 444-450.
Phillips,M. 1991 Chronic sorrow in mothers of chronically and disabled children. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 14, 111-120.
Solnit,A., & Stark,M. 1961 Mourningand the birth of a defective child. Psychoanalytic Study of the Child (16). New York: Inter-national Universities Press. Pp.523-537.
Sloper,P. , Kussen,C. , Turner,S., & Cunningham, C. 1991 Factors Related to Stress and
Satisfaction with life in families of children with Down's syndrome. The Journal of Psychology and Psychiatry, 32(4) , 655-676.
田中千穂子・丹羽淑子 1990 ダウン症児に対する母親の受容過程 心理臨床学研究,7(3),68-80.
谷口政隆 1985 心身障害児家族のストレスと対応 石原邦夫(編) 家族生活とストレス 垣内出版株式会社
鑪幹八郎 1963 精神薄弱児の親の子供受容に関する分析研究 京都大学教育学部紀要,9,145-172.,186-187.
Teel,C. 1991 Chronic sorrow: Analysis of the concept. Journal of Advanced Nursing, 16, 1311-1319.
渡辺久子 1982 障害児と家族過程-悲哀の仕事とライフサイクル- 加藤正明・藤縄昭・小比木啓吾(編)講座家族精神医学 弘文堂 Pp.233-253.
Wikler,L., Wasow,M., & Hatfield,E. 1981 Chronic sorrow revisited: Parent vs. pro-fessional depiction of the adjustment of parents of mentally retarded children. Alnerican Journal of Orthopsychiatry, 51 (1). 63-69.
Willner,S.M.,&Crane,R. 1979 A paretal di-lemma: The child with marginal handicap. Social Casework: The Journal of Contempo-rary Social Work, 60(D , 30-35.
Worthington,R. 1989 The chronically ill child and recurring family grief. The Journal of Family Practice, 29(4) , 397-400.
要田洋江 1989 親の障害児受容過程 藤田弘子編 ダウン症の教育学 同朋舎 Pp.35-50.
主題・副題:
親の障害の認識と受容に関する考察-受容の段階説と慢性的悲哀-
著者名:
中田 洋二郎
掲載雑誌名:
発行者・出版社:
早稲田心理学年報
巻数・頁数:
第27号・抜刷
発行月日:
西暦 1995年3月
登録する文献の種類:
(1)研究論文(雑誌掲載)
情報の分野:
(9)心理学
キーワード:
家族、発達障害、告知、専門的援助
文献に関する問い合わせ:
国立精神・神経センター精神保健研究所
〒272-0827 市川市国府台1-7-3
電話:047-372-0141 FAX:047-371-2900
E-mail:nakata@ncnp-k.go.jp
