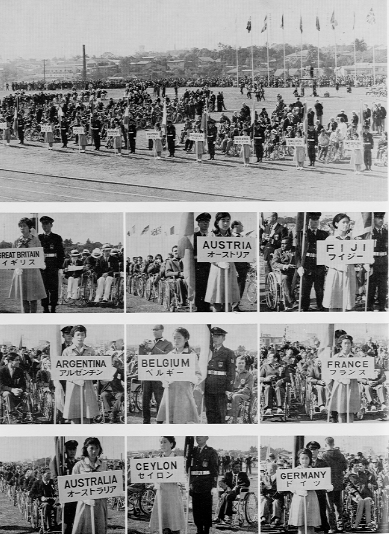THE TOKYO GAMES FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED
PARALYMPIC TOKYO 1964
パラリンピック 国際身体障害者スポーツ大会 写真集
No.2
“上を向いて歩こう”
秋晴れの開会式ひらく
11月8日“東京パラリンピック”はひらかれた。この日、快晴の菊日向。 午前10時、百十発の打ちあげ花火を合い図に、大会旗、参加22カ国の選手役員約560人が“上を向いて歩こう”のマーチにつれて、メイングランドのオダ・フィールドに堂々の入場をした。

開会式プログラム
選手整列完了 (10時)
- 名誉総裁皇太子殿下、同妃殿下ご来場
- 選手入場行進
- 国旗、大会旗掲揚
- あいさつ 葛西大会々長
あいさつ グットマン博士 - 祝辞 神田厚生大臣
祝辞 東東京都知事 - おことば 名誉総裁
- 選手宣誓 青野繁夫選手
- 名誉総裁、選手ご激励
- 名誉総裁 ご退場
- アトラクション
(剣道野試合)(12時)
開幕の花火の音も高らかに


祝辞 |

祝辞 |

あいさつ |

開会宣言 |

選手代表宣誓 |

選手代表宣誓
名誉総裁皇太子殿下のお言葉のあと、選手代表青野繁夫選手(国立箱根療養所)、中村団長に介添され貴賓席前に進みでて、右手を高くあげ”身体の障害を克服し、具りない前進を誓い、正々堂々とたたかいます”と宣誓した。
皇太子殿下のおことば
国際競技大会の開会式にあたり、わが国を含め、各国から参加された選手諸君の、心身ともに元気な姿に接し、一言あいさつすることを、たいへんうれしく思います。
わたくしは、みなさんが日頃の努力によって健康をとりもどし、はるばるこの大会に参加されたことを知っています。また、この中の多くの人たちが、社会の一員として、りっぱに活躍されていることも知っていますが、そうした努力のうちには、スポーツがあなた方の心身のささえとなり、社会復帰される早道であったと確信いたします。
わたくしは、世界中の身体障害者に希望と価値ある生活をもたらすストーク・マンデビル大会の業績と精神に敬意を表します。わたくしは、この名誉ある大会の主催者側であることをうれしく思います。それは、この大会が、わが国の身体障害者に大きな希望と激励を与えてくれると思うからであります。どうぞこの競技会のすべてに全力を発揮するようにして下さい。
第十八回東京オリンピック大会のスローガンであった。「世界は一つ」という理想を、あなた方のスポーツマンシップを通じてなしとげることができましたら、みなさんとともによろこびに堪えないところであります。
終わりに、世界のすべての身体障害者の上に、希望と幸福がもたらされることを念願し、この大会が、あなた方に、楽しく意義あるものになることを望みます。
|
菊花もかおる貴賓席壇上から、 お言葉を述べられる皇太子殿下。 |
お言葉をきく外国選手団(フランス)の列。 |
|
|
|
左、貴賓席にお立ちになり、選手の入場行進にお手をふられる皇太子殿下。右、貴賓席前を第一陣イギリスチームが通過する。なお、入場式の次第はテレビ放送(NHK)された。


この朝、晩秋の快晴。まず、午後9時50分頃までに開会式入場者のすべては入場して、時のいたるのを待った(写真上)。朝風にひるがえる各国旗、色とりどりの色彩も鮮やかな各国選手のユニホーム。キラキラ光る車イスの車輪……。
やがて午前10時、大会名誉総裁皇太子殿下・妃殿下のご来場ご着席と同時に開会を告げる花火が代々木の森にこだまする。つづいて軍楽隊の奏でるマーチによって、選手の入場行進が始る(写真左、中)。この入場行進は、車イス選手という特殊性から、予めグランド中央に待機していて、行進は貴賓席前を通過、トラックを半周して再びもとの中央にもどり、指定の位置に整列するという方法であった。行進の先導は、黄色いユニホームの小・中学生によるバトン鼓笛隊(写真中)。先頭にはまずSMG旗、つづいてこの大会の発祥国イギリスチーム、以下ABC順に参加国選手がつづき、最後は主催国日本チームがつづいた。

|
SMG旗(色彩はカラーページ参照)。旗手は左、小笠原文代選手、右、船田中選手、中はイギリス選手。

|
行進を先導した全日本バトン鼓笛連盟の小・中学生隊員。

|
グランドのメインポールに掲揚された東京大会旗、日章旗、SMG旗。
“入場行進”が終って整列する参加22ヵ国
|
|
|
|
明るく健やかに堂々の行進
行進する各国チームの隊形は、その先頭に自国の国旗を掲げ(旗手は自衛隊支援群式典係)、さらに自国名プラカードがつづき(持手はガールスカウト)、その後に車イスの隊列がつづいた。

|

|

|

|

|
行進は先頭をSMG旗、つづいてこの大会の発祥国イギリス、以下ABC順で、最後は主催国日本チーム。
入場行進は、貴賓室前にさしかかると、まず旗手が旗を水平にあげ、そして選手は“頭右”の敬礼で注目する。このとき、プラカードも貴賓席側に向きを変え、通過後は再び前方に向け直す。(写真上)
親しくご激励
選手宣誓が終ると、皇太子殿下ご夫妻は、葛西大会々長の先導でフィールドに降りられ、各国選手をそれぞれ激励された。

|
 あこがれのプリンスにおめにかかれる! 女子選手ではお化粧を直している者もいた。 |
北から南から
色とりどり、さまざまなユニホームがあるように、またヒフの色もそれぞれに違っていた。地球の東から西から、そして裏から表から……しかし、共通の目的はただ一つ……。


左、全日本バトン鼓笛連盟の小・中学生。可愛らしい黄色のユニホームで、たいへん人気があった。右、日本チーム。下、イスラエルチーム。

参加人員はイギリス(103)アメリカ(92)イタリア(55)のような大勢のところもあるが、またフイジーやセイロンのように、ただ1名のところもあった。(写真下右上)

|
|
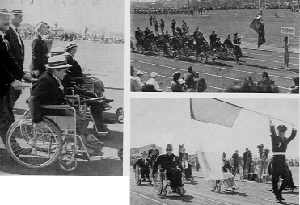 |

|
左、入場行進するローデシア。中上、オーストラリア、ベルギー。右、ドイツの各チーム。
この感激をいつまでも
この感激は出場選手ばかりではなかった。スタンドをうめた約5千の観衆、それは身障者の家族であり関係者であって、はるばる地方から上京してきた者が多く、早朝6時頃から渋谷口ゲートに待機して警備員を驚かせていた。そして残念なことは、この開会式参観希望者の全部を収容できなかったことだった。それは、スタンドの収容人員の関係から、整理券が発行され、自由参観ができなかった。

|
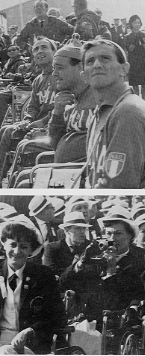
|
スタンドのわれるような拍手に感激する外国選手たち。

|
スタンドのわれるような拍手

|
入場行進するアメリカの選手
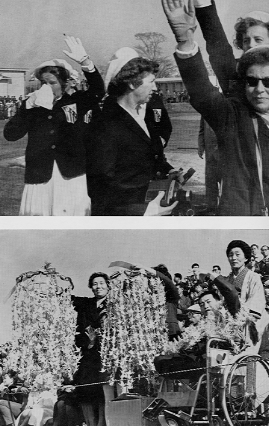
|
上、自国(米)の少女選手の入場行進ぶりに、涙で手を振る付添い者。その下、この日のために千羽ヅルをつくり、外国選手にあげようと、富山県から上京してきた身障者。
|
側面からみた開会式
皇太子殿下は、大会の名誉総裁としてのおことばの中に「世界中の身障者に希望と価値ある生活をもたらす大会の精神と業績に敬意を表し、大会の主催者側であることをうれしく思う」とのべられているように、この大会には当初から深い関心をよせられ、全会期中をとおして各会場におみえになられた。そして常に報道機関に囲まれた中で、大会の盛りあがりに気をくばられた。


陸上自衛隊パラリンピック支援群(担当第1師団)は、この大会の進行に全面的に協力、“親身の労りと力強い激励”をモットーとして大いに活動した。その編成は、競技関係230名、警衛関係230名、送迎関係106名で、軍楽隊のファンファーレ吹奏や、式典関係の各種演技も見事な出来であった。写真は各種支援に活躍中の隊員。
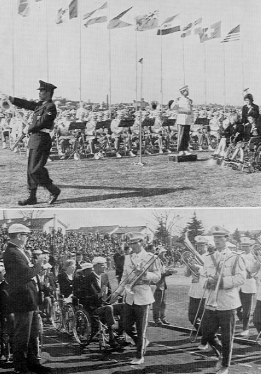
|

|

|
|
オリンピックのこうふん、まださめやらぬ東京で、はじめての身体障害者スポーツ大会がひらかれるというので、開会式のオダフィールドには、報道関係者がどっと押し寄せた。 (写真上2枚)各社新聞雑誌の他、テレビ、ニュース映画、あるいは外国からの取材班などでごったがえした。なかでもイタリアからの特派カメラマンの空色の制服が目立った。 下は緊張する当日の式典係。最下は実況報送中のマイク席、富田忠良氏も助言に活動。 |
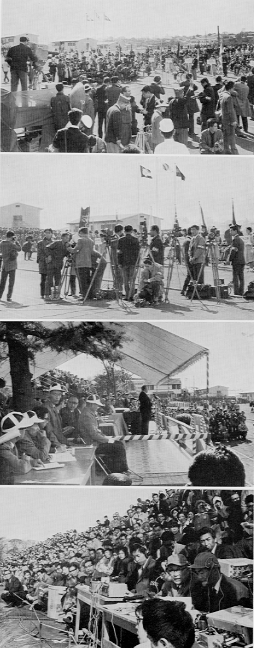
|
剣道野試合は、メンにつけた風船を割りあうもので、紅白選手が入り交って、約1時間にわたって競技した。
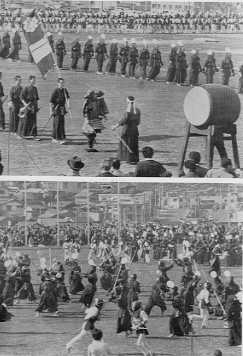
|
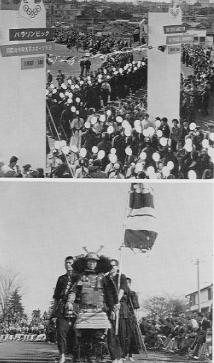
|

|
|
アトラクションには、日本調の“剣道野試合”が行われた。これは都剣道連盟の協力によるもので、中・高・大学などの学生600名が、紅白に分れて、勇壮な野試合(頭につけたふうせんを割りあう)を展開した。とくに大将の鎧武者には、外国選手がヤンヤの拍手を贈り、写真スナップに余念がなかった。

|

|
感激の開会式も終って、ホッとした選手たち。さっそく選手村では、親しげな交歓風景が展開された。とくにアルゼンチンの選手たちは陽気で、なかなか人気があった。

|
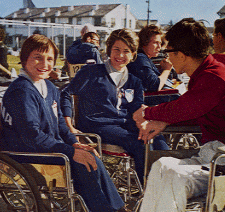
|
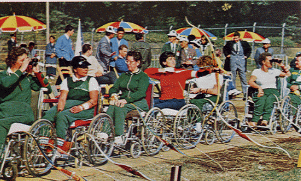
|
|
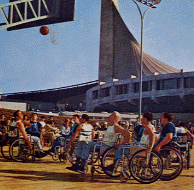
|

|

|
|
上、美しいコスチュームがならぶ第五会場洋弓場。中右、洋弓場をご覧になる皇后、皇太子、同妃殿下。中左、第4会場でのバスケットボール。下左、ウイリアム・テルのようなスイス選手。右下、オダ・フィールドでの槍投げ。
主題:
PARALYMPIC TOKYO 1964 パラリンピック 国際身体障害者スポーツ大会 写真集 No.2
35頁~52頁
編集発行者:
パラリンピック・国際身体障害者スポーツ大会編集委員会
発行年月:
文献に関する問い合わせ先:
財団法人 国際身体障害者スポーツ大会運営委員会