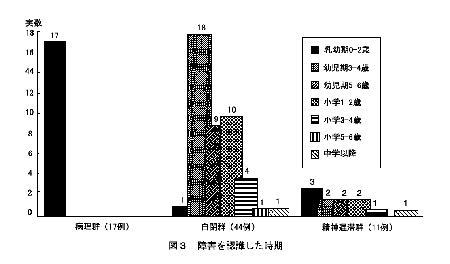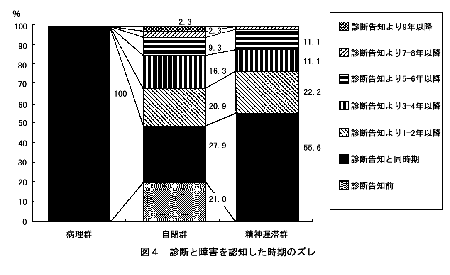親の障害認識の過程-専門機関と発達障害児の親の関わりについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 執筆者 | 中田洋二郎、上林靖子、藤井和子 |
| 所属先 | 国立精神・神経センター精神保健研究所 |
| 執筆者 | 佐藤敦子 |
| 所属先 | 千葉県市川児童相談所 |
| 執筆者 | 井上僖久和 |
| 所属先 | 千葉県柏児童相談所 |
| 執筆者 | 石川順子 |
| 発表年月 | 1995年12月 |
| 転載元 | 日本小児精神神経学会・ 国際医書出版 小児の精神と神経第35巻 |
原著
要旨:千葉県東葛地区の2つの障害児親の会の会員72家族を対象に,子どもの障害に関して医療・相談機関との関わりと親が子どもの障害を認識する過程について障害の種類による比較調査を行った障害の種類はダウン症など病理型の精神遅滞(病理群17例),精神遅滞を伴っ広汎性発達障害(自閉群44例)それ以外の精神遅滞(精神遅滞群11例〕の3群に分類した.病理群と自閉群・精神遅滞群では障害に気づき,医療・相談機関を受診し,診断と障害を告げられる時期が異なり,それに関連して医療・相談機関の家族への対応も異なった,また,家族が子ともの障害を認識する時期やきっかけにおいても病理群は専門機関の診断が大きく関与するが自閉群・精神遅滞群では主として家族自らの生活の経験から障害を認識することが明らかとなった1さらに本文ではそれぞれの障害に応じた専門的な援助のあり方について考察した.
はじめに
わが子に障害があることを知ったとき,家族はその事実をどのように受けとめるのだろうか.たとえば,Drotar(文献1)らは子どもが先天性奇形をもつことを知ったときの親の反応を衝撃・否認・悲哀と怒り・適応・再起の5つの段階で説明している.この反応は先天性奇形ばかりでなく多くの障害にも通じると考えられ,発達障害児の親の適応の過程として引用されることが多い(文献2-5).しかし,実際の臨床の場で障害を知らされた親の反応や障害を認識する経緯をみると,必ずしもこの過程が発達障害児のすべての親にあてはまるものではないことを経験する.特に障害の種類によっては親が障害を知る経過はかなり異なり,障害の受容に至る過程も障害によって大いに異なるように感じる.
そこで私たちは,障害の違いに焦点をあてて,医療・相談機関の告知や援助の関わりが親の障害受容の過程にどのような影響を与えているかを知るための調査を実施した.本報告ではその調査結果によって障害の種類による家族と医療・相談機関の関わりの経過の違いを明らかにし,それぞれの障害に即した専門的な援助のあり方について考察する.
1.方法と手続き
調査の内容が多岐にわたり個々の事例によって体験した事柄が多様であることを考慮し,調査の方法は自記式の調査票によらず,あらかじめ用意した質間項目に基づき被面接者が白由に口述する半構成的面接法(semi-structured interview)で行った.質問内容は,主として発見から障害を認識するまでの経過を知ることを目的とし,異常に気づき最初に受診した機関とそこでの応対の内容,また最初に告知を受けた機関とその時の印象,さらに受診や相談歴また治療や教育の経緯,また障害を認識した時期やきっかけについて尋ねた.
対象は,千葉県東葛地区の2つの障害児(者)親の会の会員(全体686世帯)の中から協力者を募り,調査時6~20歳の障害児(者)のいる72組の家族を対象とした.これは親の会に所属する調査該当年齢の22.4%にあたる.ただし,正確な協力率については協力者の斡旋を親の会に依頼したため不明である.なお,被面接者はすべて母親であった.面接は日頃発達障害の診断や相談に携わり障害児の親の面接の経験をもつソーシャル・ワーカーと臨床心理の専門家が行った.調査期間は平成6年1~4月であった.
2.結果
結果を整理するにあたって障害の種類を3つの群に分類した.まずダウン症を中心とする病理型の精神遅滞を病理群(17例)とした.この群にはダウン症の他に小頭症(2例),水頭症(2例),ウイリアムス症候群(1例),脳性小児麻痺(1例)が含まれている.次に精神遅滞を伴う自閉傾向および自閉症を自閉群(44例)とした.この群はSDM-Ⅲ-Rによる診断では広汎性発達障害にあたる.さらに,上の2つの群に含まれないその他の精神遅滞を精神遅滞群(11例)とした(表1).障害の程度は現在の障害児者療育手帳の程度によったが,各群の障害の程度の分布には特に有意な差は認められなかった.
| 表1 対象の性質 | ||
|---|---|---|
| 障害児(者)の年齢:6~20歳 平均年齢:13.2歳 性別 男子52名 女子20名 |
||
| 障害種別 | 病理型精神遅滞 | 17人 |
| 広汎性発達障害 | 44人 | |
| その他の精神遅滞 | 11人 | |
| 障害の程度 (療育手帳から): |
軽度 | 13人 |
| 中度 | 14人 | |
| 重度 | 36人 | |
| 手帳未申請 | 9人 | |
1. 障害の種類による医療・相談機関との関わりの違い
異常に気づいてからそのために医療・相談機関を受診し,また診断されるまでの各群の時間経過を図1に示した.病理群では異常の発見と最初の受診と診断の3つの出来事が平均して出生時からほほ1ヵ月までに生じていた.それに対し自閉群と精神遅滞群では,平均してほほ1歳半前後に異常に気づき,異常に気づいてから最初に医療・相談機関を受診するまでに約半年ほど経過し,さらに診断には自閉群で最初の受診から平均1年2ヵ月,精神遅滞群で平均1年10ヵ月ほどを要した.自閉群と精神遅滞群の異常の発見と受診と診断の時問経過は類似し,またこの2群と病理群とは医療・相談機関の関わりの時期が明らかに異なった.
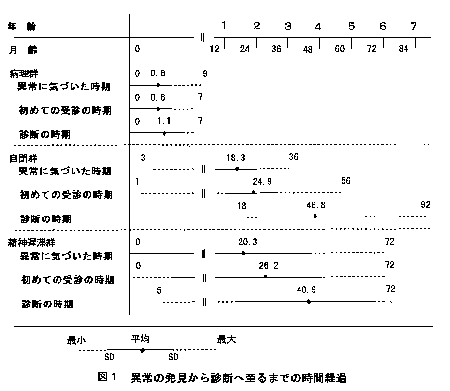
2. 医療・相談機関の対応の違い
上述のように障害の種類によって医療・相談機関との関わりの時期が異なる.そのため,最初に受診した機関も障害の種類によってさまざまであった病理群は異常を発見される時期が乳児期初期であるため.子どもを出産した産婦人科あるいはそこから紹介された小児科を最初の受診機関としていた.一方,異常に気づく時期が事例によりまちまちであった自閉群や精神遅滞群では,最初の受診機関は保健所あるいは乳幼児健診,小児科・内科,耳鼻科,眼科,神経・精神科,児童相談所,療育センター,教育センター,大学の心理相談室など多岐にわたった.
それぞれの機関が各事例に対してとる措置は受診機関の性質によって異なる.障害の種類によって最初の受診機関の対応が最も異なった点は,最初の受診機関で診断され障害を伝えられたか否かであった(表2).最初の受診機関で診断され障害を伝えられた事例は病理群で15例(88.2%)であり,自閉群では5例(11.4%),精神遅滞群では1例(9.1%)であった.病理群の大半は最初の受診機関で診断され障害を伝えられたが,自閉群・精神遅滞群では最初の受診機関で診断され障害を伝えられた事例は少なかった.
| 表2 最初に受診した機関の対応 | |||
|---|---|---|---|
| 病理群 | 自閉群 | 精神遅滞群 | |
| 1.診断と障害を知らされた | 15(88.2) | 5(11.4) | 1(9.1) |
| (その内訳) | |||
| 診断と疾患名の告知のみ | 5(29.4) | - | - |
| 診療の継続の勧め | 5(29.4) | 4(9.1) | - |
| 他の機関の紹介 | 5(29.4) | - | 1(9.1) |
| 状態の説明 | - | 1(2.3) | - |
| 2.診断と障害を知らされなかった | 2(11.8) | 39(65.9) | 8(45.4) |
| (その内訳) | |||
| 状態の説明 | - | 4(9.1) | 1(9.1) |
| 診療の継続の勧め | - | 10(22.7) | 1(9.1) |
| 訓練等の勧め | - | 5(11.4) | 1(9.1) |
| 諸検査の勧め | 2(11.8) | 10(22.7) | 2(18.2) |
| 3.異常ない・わからない | - | 10(22.7) | 3(27.3) |
| 4.回答なし | - | - | 2(18.2) |
| 計 | 17(100) | 44(100) | 11(100) |
| ()は列に対するパーセント,結果は診断や障害が知らされたか否かに分け, またその際とられた他の対応をその下の欄に示してある. |
|||
3.病理群における最初の受診機関が障害を伝える際の問題
病理群のうち最初の受診機関で診断されなかった2例は,子どもを出産した病院や最初に受診した小児科からそれぞれの疾患の專門外来へ受診を勧められ,いずれもその病院で診断され疾患名を伝えられていた.これらの例を含めると病理群の全例が,最初の受診機関かそこから紹介された病院で診断が確定し家族に子どもの障害が知らされていた.
専門家が障害を知らせる時には単に障害名を伝える以外に障害の状態や今後の療育などについても説明し,またそのことに関して家族の質問に答えることが多い.しかし,病理群の調査結果では障害を伝える際に受診機関がこの点において十分に家族に対応しきれなかったことを示唆した.つまり,病理群では疾患・障害名のみを伝えられたが他に説明がなかったとした事例が5例あり,診断や障害を伝えることと併せて他の助言があったと述べた10例においても,その助言の内容は5例が診療の継続を勧められ,また残る5例は他の機関を紹介されたというもので,障害の状態や今後の対応の仕方についての説明はなかったとしていた.
それらの事例の中には実際は障害名を伝えられた時に他にもいろいろな説明がされたが,障害を知らされたために生じた混乱で家族がそれを記憶していない例も含まれている.しかし,障害を伝えられたときの家族の情緒的な混乱は当然予想できることであり,調査結果は専門家が家族の情緒的な混乱をできる限り少なくするような配慮のもとで障害を知らせていなかったことを示唆している.
4. 自閉群と精神遅滞群における最初の受診機関の対応の特徴と問題
一方,自閉群・精神遅滞群では最初の受診機関で診断され障害を伝えられた事例は病理群と比較すると極めて少ない.その理由のひとつは,異常の原因が家族によ<わからないため眼科や耳鼻科を受診した例や最初に受診したのが本来診断機能をもたない乳幼児健診であったためと思われる.また,受診の時点では症状が明確でなくそのため専門家も診断を確定することが困難な場合も考えられる.
しかし,確定診断が困難であっても子どもの発達や行動に異常が認められた場合,最初に受診した機関は精密な検査のために他の機関を紹介したり,状態を説明し経過をみることを勧めるなどの処置をとることが多い.調査の結果から自閉群の29例(65.9%)また精神遅滞群の5例(45.4%)に,「状態を説明された」「診療を続けるようにいわれた」「訓練や集団指導のグループヘの参加を促された」などの処置がなされていた.これらの処置は自閉群や精神遅滞群においては診断が確定するまでのいわば診断に代わる対応といえる.
しかし,それらの処置の必然性が専門家によって家族に暖味にしか説明されない場合,家族は「子どもには特に問題はなかった」という印象を受けるようである.その例が最初の受診機関で「異常ない」あるいは「わからない」といわれた事例であろう.そのような事例は自閉群で10例(22.7%),精神遅滞群で3例(27.3%)あった.
5. 自閉群における受診機関の対応の違いに関わる要因の分析
自閉群と精神遅滞群では最初に受診した機関で診断された例もあるが診断されなかった例や異常が見逃された例も少なくなかった.このような専門機関の対応の違いはどのような要因から生じるのであろうか.この点を明らかにするために比較的例数の多い自閉群を最初の受診機関の対応に従って「障害を伝えられた群」(5例)「異常ないといわれた群」(10例)「診断に代わる対応を受けた群」(29例)の3つの群に分け,受診機関とその後の診断までの経過を調べた(図2).
異常に気づいた時期は「障害を伝えられた群」で19.2ヵ月,「診断に代わる対応を受けた群」で18.9ヵ月,「異常ないといわれた群」で15.9ヵ月であった.統計的に有意な差は認められなかったが,「異常ないと言われた群」がもっとも早く子どもの異常に気づいていた,しかし,受診時期をみると「障害を伝えられた群」で平均19.2ヵ月,「診断に代わる対応を受けた群」で平均27.8ヵ月,「異常ないといわれた群」で平均19.3ヵ月であった.「診断に代わる対応を受けた群」と「異常ないといわれた群」の間に有意な差(T=-2.24df=37 p<0.05)が認められたが,「障害を伝えられた群」と「異常ないといわれた群」には受診時期に有意さが認められなかった.
最初に受診した機関が障害を発見できなかった群とその対極にあるともいえる診断が可能であり障害を伝えることができた群は受診時期の平均ではほぼ同じ時期であった.このことは発見時期や受診時期が遅ければ状態がそれだけ明確であり障害を診断することが容易であるという単純な仮説を否定する.
受診時期が同じであるにもかかわらず,一方は異常が見逃され,また一方は診断され障害が伝えられたという違いが生じた原因として,子どもの症状と受診時期の相互作用が考えられる.つまり子どもの障害の状態が重ければ,受診時期が早くてもすでに異常や障害が顕現しており,専門家も異常や障害を見逃すことは少なく診断も容易であろう.
当時の発達や行動の状態を知る客観的記録がないため現在の障害の程度から判断すると,「障害を伝えられた群」は現在の障害児者療育手帳の判定において重度が4例と中度が1例であった.「異常ないといわれた群」では重度が4例と中度が5例,障害児者療育手帳を取得していない事例が1例であった.「障害を伝えられた群」には程度の重い者の比率がより高いが,「異常ないといわれた群」にも重度の事例が含まれており,受診時の年齢と障害の程度の相互作用が両群の対応の違いを説明する決定的な要因とはいえない.「障害を伝えられた群」の5例のうち4例は,受診した機関が家族に診療を続けることを勧め,診療が継続された結果,受診から平均5カ月後に診断がされていた.受診した機関から診療を継続するように促された事例は「診断に代わる対応を受けた群」にもあったが,それらの事例では家族がそれに従わず診断の時期が遅れていた,「障害を伝えられた群」で診断が可能だったことに関連する最も大きな要因は,受診機関の指示に従い家族が診療を継続したことにあるといえる.自閉群や精神遅滞群に含まれる障害では医療・相談機関は,子どもの状態や今後の対応について説明 するとともに家族の受診動機を高め診療の継統を促す工夫が大切であり,またそのことが実質的に早期診断に役立つといえるだろう.
6.誰が子どもの異常に気づいたか
障害を発見される以前に家族が子どもの異常に気がついていたか否かは,障害を知らされる時の情緒的な反応に影響を与えると思える.最初に異常に気づいたのが家族か否かを表3に示したが,病理群では大半が医師等によって異常を発見されている.それに対し,自閉群・精神遅滞群の多くの事例では家族が最初に異常に気づいていた.武市(6)は家族が子どもの異常に自ら気づくことでその後の療育に早く結びつくと報告しているが,それは家族が子どもの異常に気づく前に専門家によって障害を指摘された場合,その時の精神的な衝撃が強く親はその衝撃のために家庭へ引きこもり家族の適応が遅れるからであろう.異常を発見することは障害を認識することの出発点といえるが,病理群では半ぼ受動的にまた自閉群・精神遅滞群ではそれと比較して能動的に障害を認識するといえ,それはその後の家族の適応の過程に関連すると考えられる.
図2 自閉群の最初の受診機関の対応と診断が確定するまでの経過
| 表3 最初に異常に気づいた人物 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医師など 専門家 |
父・母親 両親 |
親と専門 家の両方 |
親と親戚 | 親戚や 知人 |
全体 | |
| 病理群 | 14(82.4) | 2(11.8) | 1(5.9) | - | - | 17(100) |
| 自閉群 | 3(6.8) | 33(75.0) | 5(11.4) | 2(4.5 | 1(2.3) | 44(100) |
| 精神遅滞群 | 3(27.3) | 6(54.5) | - | 1(9.1) | 1(9.1) | 11(100) |
| ()は行におけるパーセント | ||||||
7.障害の認識と診断の確定
面接では「子どもの問題(障害)が一時的な問題ではなく将来にも継続すると認識したのはいつだったか」と尋ねた.しかし,親にとって障害の認識の時期を何歳何カ月と特定することは困難な場合が多かった,多くの事例では幼稚園や通園施設の入園や就学の時とか,それからどれくらい経ってからというように語られた.そのため本報告では障害の認識の時期を大きく,乳幼児期0~2歳,幼児期3~4歳,幼児期5~6歳,小学校1~2学年,3~4学年,5~6学年,中学校以降という7つの時期に区分した.それぞれの群の障害の認識の時期は図3に示されている.病理群は17例全員が0~2歳の時に障害を認識している.それに対し,自閉群や精神遅滞群が障害を認識する時期は0~2歳から中学校以降まで広範囲にわたった.
専門機関の診断や障害の説明が家族の障害の認識にどのような影響を与えるのだろうか.そのことを知るうえで,専門機関によって診断され子どもが障害児であることを伝えられた時期と障害を認識した時期のズレを各群で比較することは興味深い.この2つの事象の起きた時期のズレを図4に示した.病理群では障害の認識と障害を伝えられた時期は全例が同じ時期区分であった.しかし,自閉群では12例(27.2%),精神遅滞群では5例(45.4%)が障害を伝えられた時期と障害の認識が同じ時期であり,自閉群の事例の22例(50.0%),また精神遅滞群の4例(36.3%)は,障害の認識の時期が障害を伝えられた時期よりも2年以上遅れた.また,自閉群の中には障害を伝えられる以前に障害を認識していたという事例が9例(20.5%)あった.
病理群が障害を認識した時期はほぼ診断が確定した時期と同じ時期であり,この群では障害の認識に専門機関の診断が大きく関与していることが推測される.しかし,自閉群と精神遅滞群の結果は,この2群では医療・相談機関での診断が家族が障害を認識するきっかけにはならないことを示している.
付表1
[事例203 病理群 ダウン症 女 調査時13歳 療育手帳中度]
異常に気づいた時期ときっかけ:
新生児期.フェニールケトン尿症の検査で陽性反応があり,出産した病院の医師から大学病院の小児科の受診を勧められた.ミルクの飲みが悪いことや上の子と比べどこかおかしいと母親は思ったが,異常と思いたくなかった.
最初に受診した機関:
出産1カ月後産院の医師の紹介で大学病院を受診した.芯電図,染色体検査などの結果が出たときダウン症と説明された.本を読んで予備知識はもっていたが,ダウン症とはどんなものか知らず説明は分かりにくかった.遅れについて「どういう状態ですか」とたずねたら「おとなにはなりますよ」とそっけなく答えられ,「何かしてやれることは?」とたずねたら「入院はできるけどどうやっても同じですよ」と言われた.診断を伝えられた日,若い医者たちが子どもの周りを囲み「これがダウン症だよ」というような説明をされレントゲン検査のときも革バンドで肢体を押さえられ,物みたいな扱いだった.何度か通った病院だったが,主人も私も車でどう行ったか覚えていない,二度と行きたくないと思う.
その後の受診機関:
親戚の紹介で生後2ヵ月後に民間の病院に状態をみてもらうために受診した.月に1度のダウン症の専門医の外来受診を勧められた.そこでこの子の場合,原因が遺伝的なものでないことを説明された.「みんなと同じように育てなさい」と言われ心構えができた.その後はダウン症の親の会を紹介され,おかげで家にこもらず外出するようになった.
障害の認識の時期ときっかけ:
手帳をもらう1歳くらいだったと思う.それまで手帳をもらわなかったのは障害を認めるのが嫌だったからだと思う.本にダウン症の子の写真がありそれと同じ顔をしたダウン症の子が自分の小学校時代にいたことを思い出し,わが子もその子と同じなのだという思いに至った.障害を認識したのは治らないものだと思ってからだと思う.
障害を認識する過程についてのコメント:
ダウン症と診断されたとき医師らの対応が心を傷つけた.一時は沈んでいた.出産後1年くらいは家庭こもりがちだった.当時母親の実母や妹が頻繁に家庭を訪ねたが,それはマンションからの飛び降り自殺を懸念したからだと後で聞かされた.いつか治る,手術でもと思いながら1年くらい過してした.その当時は先を考えたくなかった.今できることだけをやっていた.これから先のことを考えると暗くなるので可能性を信じていた.周囲が自分も子どもも受け入れ,保健婦,医師がこもりがちな母親を外に出かけるように励ましたのが気持ちを変えていった.もっとよくしてやりたいと成長を願うようになってから本児のためにいろいろな訓練機関を探した.よい場所がみつけられたことで本児の今の状態があると思う.
医療相談機関へ望むこと:
障害についての正しい説明と親の立場にたってほしい.
(表 終了)
自閉群や精神遅滞群の家族はどのようにして障害を認識するのであろうか.表4に各群の障害を認識するきっかけを示した.「医療・相談機関で障害を知らされて障害を認識した」のカテゴリーに属する回答が病理群は13例(68.4%)あり,病理群の大半が診断を知らされた時に障害を認識している.しかし,自閉群・精神遅滞群では「健常児の成長と比較して,あるいは他の障害児の行動や発達を見て」のカテゴリーに分類された回答が,自閉群28例(40.6%),精神遅滞群7例(46.7%)で最も多かった.自閉群や精神遅滞群にも「医療・相談機関で障害を知らされて」をきっかけとしてあげた例がそれぞれ13例(18.8%)と3例(20.0%)であったが,それは他のきっかけの付加的な理由として述べられた.このように自閉群・精神遅滞群の障害を認識する過程は専門機関の診断や障害を伝えられることが直接的に結びつかない.その認識の過程はいわば家族自らの生活と経験の中から生じるといえる.
| 表4 障害を認識するきっかけ(重複選択) | |||
|---|---|---|---|
| 病理群 | 自閉群 | 精神遅滞群 | |
| 医療・相談機関で診断されて | 13(68.4) | 13(18.8) | 3(20.0) |
| 健常児の成長と比較して,あるいは 他の障害の行動や発達を見て |
1(5.3) | 28(40.6) | 7(46.7) |
| 本や他のメディアの情報から理解して | 4(21.0) | 12(17.4) | 1(6.7) |
| 入学・就学など進路を決めたり変更する際に, 諦めあるいは覚悟を定めて |
- | 10(14.5) | 4(26.7) |
| 子どもの発達が標準へ追いつかない, あるいは異常な行動が続くことから |
- | 3(4.3) | - |
| 障害を認めた上で個人の自立を促そうと 決心して |
1(5.3) | 3(4.3) | - |
| 全体 | 19(100) | 69(100) | 15(100) |
| ()は各群の回答総数によるパーセント,また病理群の2例は無回答であった. | |||
付表2
[事例103 自閉群 男児 自閉症 調査時11歳 療育手帳未申請]
異常に気づいた時期ときっかけ:
生後8カ月頃に視線が合わないことから異常を感じた.
最初に受診した機関:
1歳の頃,自分から保健所に相談に行った.スキンシップが大事と言われたが,こちらの質問に答えるだけの専門的な知識がなく,相談は何の役にも立たなかった.
その後の受診機関:
その後教育センターに行ったが,ここでもはっきりした診断はなく,様子を見ましょうと言われ月1回の割で半年ほど通ったが,はっきり言ってくれず,物足りなく通うだけの価値がないと思い止めた.
診断された経過:
言語治療室の紹介で子どもの神経科専門のクリニックを紹介された.CTや脳波の検査を受け異常なかった.医師からは自閉傾向児と言われた.
その後の受診機関:
当時の新聞で自閉症に効く薬が病院で開発中と知り,その機関を訪ねた.「小児自閉症児?」と診断され投薬を1年後から受け始めた.
障害の認識の時期ときっかけ:
小学校5~6年生の頃に地域での生きにくさ,受け皿のなさから,障害児としての生き方を選ぶべきだと強く思ってから.
障害告知を受けた時のコメント:
異常に気づいてからいろいろ尋ね歩いた末の診断だったので告知された時はさめていた.やっぱりという感じ.自分のせいだけではないことがわかり気持ちが軽くなった.でもショックだった.今後が不安だった.落ち込んでいる暇はなく,すぐ次の行動に移らなければと思いとにかく行動した.今思うとあのころが一番充実していた.問題のない子どもをもっていたらぼ一っとした母親だだっただろう.
医療相談機関に望むこと:
相談機関から得たものは何もありません.担当された先生方の人間性は別問題で核心的なものを得ることができなかったのが事実です.親はどんなことがあってもわが子に全責任があります,それと同等くらいの重責を担って相談に応じないと真の相談にはならないと思うのです.医療機関と教育機関と親が一緒に組んで原点にある子ともたちのことを考え対処していかなければ社会福祉は進歩しないと思います.
本当のことを知りたいと思う意欲のある親であればオブラートに包むようなことはせず,早く真相を告げた方が良いと思います.その場合も見通しをつけてあげることが大切だと思います.とことん関わってあげようという姿勢で望まなければ中途半端な相談であり危険であると思います.
(表 終了)
8.病理群と自閉群の代表例
以上,障害の種類で受診や診断また家族が障害を認識する経過が明らかに違うことを主に数値の比較によって示した.この違いを示す典型例を病理群と自閉群より1例ずつ選びその面接の内容を付表1と付表2にて提示した.
3.考察
以上の結果が示すように障害の種類によって医療・相談機関との関わりの経過が明らかに異なる.このような違いが生じる主な理由はそれぞれの障害の確定診断の困難性が違うからであろう.たとえばダウン症の場合は身体的な特徴から早期に障害を発見し染色体検査などによって迅速に診断を確定することが可能である.病理群の多くの事例か生後早い時期に診断が確定しているのは,このような外見の特徴や検査結果から確定診断が比較的容易であるためである.一方,自閉群や精神遅滞群に含まれた障害は,ある程度成長した後に異常が発見され,また診断を確定するには状態の変化をある期間観察することが必要である(文献7).そのため,これらの群では発見や受診や診断はそれぞれ少しずつ遅延しながら進行していた.
さらに,調査結果は病理群と自閉群・精神遅滞群で親が障害を認識する時期やそのきっかけに相違があることを示した.受診経過の違いは当然親の認識の時期に影響を与えるが,そのもとにある確定診断の困難性の違いは,確定診断の容易な障害には外見の異常が伴う疾患が多く,確定診断が困難な疾患は見た目では異常を感じないことも多いというように,親が障害を認識する際の障害の状態の理解度にも影響を与える.そのため障害の種類によって障害を認識するきっかけに違いが生じたのであろう.障害児をもつ家族の援助のためにはこれら確定診断の容易さ,また困難さから生じるさまざまな要因の違いを整理し,それぞれの障害にあった方法について再度検討しなければならない.
1.確定診断が比較的容易な障害の場合
病理群のほとんどの事例は障害告知と同時期に障害を認識していた.しかし,それは必ずしも親が障害を受容したことを示すものではない.それは単に,子どもの障害がその身体的な特徴や染色体の検査結果から親にとって動かしがたい事実として提示され,親はその事実が明白なゆえにそれを否定することができないことを意味している.親にとって否定的な事実はそれが明確であるためにかえって家族に強いストレスを与える(文献8-10).また病理群の結果のように多くの家族は異常に気づかず,しかも発見から診断までの期間が短いために心の準備や衝撃からの回復のための時間的なゆとりがなく,その情緒的な混乱は深刻なものと思える.そのため,そこから回復するには特有な段階をふんだ心理的変化が必要であるといわれる(文献3-4).この調査でも事例203のように面接のなかで告知の衝撃とその後の情緒的な動揺や世間からの引きこもりの様子を述懐し,段階的な経過を認めた事例が多数あった.しかし,調査の結果は専門機関の対応の多くがこのような家族の心理的な状況を配慮 していなかったことを示した.
ダウン症の診断告知について中村(文献11)らまた玉井(文献12)らは親の側からの実態調査を行い,告知の時期や場所,告知の相手,告知する際の職種,その時の助言の内容などに配慮すべき点があることを指摘している.また,この告知の問題には遺伝相談の立場からも関心がもたれてきた.Keessler(文献13)によれば,遺伝相談が客観的な事実を正確に伝えるという内容志向的なアブローチから,事実が相談者に対してもつさまざまな意味とこれらの意味の精神内および対人関係への影響に焦点を合わせた個人志向的(person-oriented)なアプローチヘと向かっており,それに従って遺伝相談は医師や遺伝学者のみでなくより広い専門家の関わりが求められるようになっているという.診断の告知において以上のことが強調されるのは,告知の内容を家族に正確に伝えるために伝える側が患者や家族の心理を理解し,いわば精神療法的な接近をする必要があるからである.特に病理群の障害の告知のように家族に大きな衝撃をもたらす場合はこの配慮は欠かせな いものだといえる.
病理群のほとんどが産婦人科かそこから紹介された小児科で障害を知らされているが,先天異常の診断技術が飛躍的に進歩するなかで,産婦人科や小児科で早期に障害を告知される例は今後も増加し,周産期における障害の告知と家族ケアは医療にとっても大切な領域といえる(文献14).しかし,長谷川(文献15)が「現在の医療制度においても多くの患者(家族)自身の意識にも,説明に費やされる時間に対する経済評価は低い」と指摘するように,医療のなかでの告知の重要性はまだ十分に認識されていない.今後,ますます周産期医療における家族のケアの重要さが認識され具体的な対策が検討されなければならないだろう.
2.確定診断が困難な障害の場合
自閉群は平均的にはほぼ1歳半頃に言葉が出ないなどの理由から親が異常に気づく,しかし,結果のようにすぐには受診せず気がついてから半年ほど経過して受診している.親にとって子どもの障害がわかりにくいことや受診し異常を指摘されることへの恐れなどがこの遅延の背景にあると思える.このように恐れや不安を抱きながらも親が医療・相談機関の訪問を決意したときは,専門家の目によって異常の有無を明確にしてもらうことを望んでいるときでもある.しかし,最初に受診した機関で障害を伝えられることは少ない.それは自閉症状や知的な遅れがある年齢になるまではっきりせず早急な診断を避けてある時期まで経過を追う必要があるためだが,受診を逡巡しつつやっと医療・相談機関を訪れた家族にとって,それらの処置は事例103のように「こちらの質問に答えられるだけの専門的な知識がない」という印象を与えるものであった.
医療・相談機関が家族に障害を伝える場合その内容は家族が理解できる内容で納得のいく説明でなければならない.玉井(文献16)は障害の告知の実態を調査し,家族の要望を「告知する側として,親に誤った認識を与えない基本的な専門知識をもっていること,伝えるべき情報を一度に多くを説明しすぎないこと,情報によってはその後の助言・指導の中で両親の疑問間に応える形で伝える,親の理解できる情報と過度に専門的な情報とを整理して伝えること,また図書やパンフレットなど情報を活用すること」とまとめている.これらの内容は,専門機関の継統的な関わりと障害の告知が一方的な伝達ではなく質疑を前提とした相互理解の過程であるという認識があって初めて可能な事柄であろう.そしてそのような認識のもとで行われる説明は家族の専門機関への信頼を高め,また受診の継続を促し確定診断の時期を実質的に早めることにつながるといえる.
ところで,白閉群と精神遅滞群の親があげた障害の認識のきっかけの多くは,わが子と他の子ども達との違いを知り,入園・就学・進学のときに健常児と違う道を選ばざるをえないというように,子どもの成長を見守ることで徐々に障害を認め受容する過程であった.これらの障害はその成因がまだ解明されていないものも多く,専門機関がどのように説明しても家族が子どもの障害を理解することが困難なことも多い,そのため親は子どもの障害を否定することも稀でなく,障害の告知を受けた後も家族は子どもの障害の否定と肯定の繰り返しの過程を過ごさなければならないと考えられる(文献17).この障害の肯定と否定は,確定診断が困難な障害や注意欠陥障害や学習障害など診断に変遷と暖昧さを残した障害をもつ子どもの家族に共通する特徴である.それをWilnerら(文献18)は親のジレンマ(Parental dilemma)の状況とよび,またそのために生じる苦節の繰り返しをOlshansky(文献19)は「慢性的な悲哀」とよんだ.Wing(文献20)は,このような状況にある自閉症の親に対する専門家の援助として,日常に起きるさまざまな事柄に対処する方法を具体的に助言することが大切であり,専門家が親が親としてなすべきことの理解を助けることで,このような親の情緒的な問題の大半は解決していくと述べている.今回の調査では,通園施設の指導員から日常的な問題を解決のための助言をあたえられたことが障害を認識する際の支えとなったと報告した例も多い.家族が子どもの障害を認識し受容する遇程の援助のためには,障害児であるという事実を家族に強いるのではなく,障害の受容の過程で繰り返される家族の苦節を理解し,具体的な援助でそれを乗り越えるよう支持することが要点と思われる.
おわりに
現在関心が高まっているインフォームド・コンセントに関する論議から,告知は一方的な伝達ではなく相互の認識の過程であり,それはすべての医療の過程を通じてなされるものであるとの認識が生まれつつある(文献15後)(文献21).このことは発達に異常のある子どもたちとその家族を対象とした障害告知にも通じる基本的な考えであろう.しかし,この理念を現実のものとし家族の障害の認識や受容に役立てるには,それぞれの障害に応じた医療・相談・療育の連携のあるシステムの充実が必要であり,また個々の家族の二一ドにあった具体的な介入の方法と面接の技法の工夫がなされなければならない.
面接にご協力いただいた親の会の皆様にこの場を借りて厚くお礼申し上げます.また調査の面接を担当していただいた野田すみ子さん,正田雅子さん,冠木久仁子さん,小野寺公子さん,菅谷広子さん,難波江玲子さん,小保方稔子さん,沖山邦子さんに感謝いたします.最後に,この調査の企画からまとめの段階まで貴重な助言とご指導をいただきました国立精神・神経センター精神保健研究所の白井泰子先生に心から感謝いたします,なお,この調査は安田生命社会事業団1993年度研究助成によって行いました.
文献
1)Drotar D,Baskiewicz A,Irvin N et al:The adaptation of parents to the birth of an infant with a congenital malformation:A hypothetical model.
Pediatrics 56:710-717,1975 (本文へ戻る)
2)Klaus MH,Kennell JH:母と子のきずな 母子関係の原点を探る.竹内徹,柏木哲夫訳,医学書院,東京,1981
3)田中千穂子,丹羽淑子:ダウン症児に対する母親の受容過程.心理臨床学研究7:68-80,1990
4)要田洋江:親の障害児受容過程.藤田弘子編:ダウン症の育児学,同朋舎,京都,1989,pp.35-50 (本文へ戻る)
5)渡辺久子:障害児と家族過程-悲哀の仕事とライフサイクル.加藤正明,藤縄 昭,小比木啓吾編:講座 家族精神医学.弘文堂,東京,1982,pp.233-253 (本文へ戻る)
6)武市敏孝:発達障害の発見時期とその後の対応.発達障害研究12:pp.220-224,1990
7)栗田 廣:自閉症.からだの科学 153:65-69,1990 (本文へ戻る)
8)丹羽淑子,失花芙美子,田中千穂子,他:ダウン症乳幼児の母親の適応過程-子どもの発達と母親・治療者関係を通じて-.小児の精神と神経25:85-90,1985
9)正村公宏:ダウン症の子をもって.新潮社,東京,1983
10)山本匡子:障害につながる疾患を持つ小児と母親.小児看護5:1463-1468,1982 (本文へ戻る)
11)中村 正,中根允文,小林 勇:ダウン症候群児をもつ親へのアンケート-初めて診断を告げられたとき-.小児保健研究37:195-198,1978 (本文へ戻る)
12)玉井真理子,日暮 眞:ダウン症の告知の実態-保護者に対する質問紙調査結果から-.小児保健研究53:531-539,1994 (本文へ戻る)
13)Kessler S:遺伝相談の心理学的基礎.Kessller S編,大倉興司,他訳:遺伝相談.新曜社,東京,1984,pp.18-37 (本文へ戻る)
14)白井泰子:出生前診断と人工生殖.唄 孝一,石川 稔編:家族と医療.弘文堂,東京,1995,pp.237-257 (本文へ戻る)
15)長谷川知子:先天異常医療におけるインフォームド・コンセント.小児内科26:549-554,1994 (本文へ戻る) または (文献15後へ戻る)
16)玉井真理子:「障害」の告知の実態-母親に対する質問紙調査の結果および事例的考察-.発達障害研究15:223-229,1993 (本文へ戻る)
17)中田洋二郎:親の障害の認識と受容に関する考察-受容の段階説と慢性的悲哀-早稲田心理学年報27:83-92,1995 (本文へ戻る)
18) Willner SM Crane R:A paretal dilemma:The child with marginnal handicap .Social Casework:The journal of Contemporary Social Work60:30-35,1979 (本文へ戻る)
19)Olshansky S : Chronic sorrow:A response to having a mentally defective child. Social Casework 43:190-193, 1962 (本文へ戻る)
20)Wing L:Autisitic Cild:a guide for parents.中園康夫,久保紘章訳:自閉症児.川島書店,東京,1979,pp.201-206 (本文へ戻る)
21)白井泰子:インフォームド・コンセントの原理と社会意識.小児内科26:498-502,1994 (本文へ戻る)
主題・副題:
親の障害認識の過程-専門機関と発達障害児の親の関わりについて-
著者名:
中田 洋二郎、上林 靖子、藤村 和子、佐藤 敦子、井上 僖久和、石川 順子、
掲載雑誌名:
小児の精神と神経
発行者・出版社:
日本小児精神神経学会・国際医書出版
巻数・頁数:
第35巻・第4号別刷
発行月日:
西暦 1995年12月
登録する文献の種類:
(1)研究論文(雑誌掲載)
情報の分野:
(9)心理学
キーワード:
家族、発達障害、告知、専門的援助、障害認知
文献に関する問い合わせ:
国立精神・神経センター精神保健研究所
〒272-0827 市川市国府台1-7-3
電話:047-372-0141 FAX:047-371-2900
E-mail:nakata@ncnp-k.go.jp