みんなの和21プラン-東大和市地域福祉計画-
みんなの和21プランの策定にあたって
第4章 計画の目標
1 将来フレームと基本サービス
1.将来フレーム
1 人口(推計)
| 区分 | 平成4年度 (平成5年1月1日) |
平成11年度 (平成12年1月1日) |
平成12年度 (平成13年1月1日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 割合(%) | 人 | 割合(%) | 人 | 割合(%) | |
| 総人口 | 75,752 | 100.0 | 84,013 | 100.0 | 58,061 | 100.0 |
| 年少人口(0~14歳) | 12,717 | 16.8 | 13,211 | 15.7 | 13,344 | 15.7 |
| 再掲(0~4歳) | 3,915 | 5.2 | 4,488 | 5.3 | 4,544 | 5.3 |
| 生産年齢人口(15~64歳) | 56,497 | 74.6 | 60,329 | 71.8 | 60,507 | 71.1 |
| 高齢者人口(65歳以上) | 6,538 | 8.6 | 10,473 | 12.5 | 11,210 | 13.2 |
2 高齢者数
| 区分 | 平成4年度 (平成5年1月1日) |
平成11年度 (平成12年1月1日) |
平成12年度 (平成13年1月1日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 割合(%) | 人 | 割合(%) | 人 | 割合(%) | |
| 高齢者数 | 6,538 | 100.0 | 10,473 | 100.0 | 11,210 | 100.0 |
| 前期高齢者 | 4,089 | 62.5 | 7,019 | 67.0 | 7,496 | 66.9 |
| 後期高齢者 | 2,449 | 37.5 | 3,454 | 33.0 | 3,714 | 33.1 |
| 要介護高齢者数(在宅) | 282 | 4.3 | 451 | 4.3 | 483 | 4.3 |
| ねたきり高齢者 | 235 | 3.6 | 377 | 3.6 | 404 | 3.6 |
| 痴呆性高齢者 | 47 | 0.7 | 74 | 0.7 | 79 | 0.7 |
| 虚弱高齢者 | 392 | 6.0 | 628 | 6.0 | 673 | 6.0 |
| 痴呆性高齢者(要介護含む) | 315 | 4.8 | 494 | 4.7 | 527 | 4.7 |
3 障害者数(推計)
| 区分 | 平成4年度 (平成5年1月1日) |
平成11年度 (平成12年1月1日) |
平成12年度 (平成13年1月1日) |
|---|---|---|---|
| 総人口 (人)A | 76,102 | 84,013 | 85,061 |
| 身体障害者手帳所持者 (人)B | 1,490 | 1,934 | 2,005 |
| 対総人口比 (%)B÷A | 1.96 | 2.30 | 2.36 |
| 50~64歳 (人)C | 535 | 650 | 655 |
| 対所持者比 (%)C÷B | 35.9 | 33.6 | 32.7 |
| 65歳以上 (人)D | 557 | 876 | 939 |
| 対所持者比 (%)D÷B | 37.4 | 45.3 | 46.8 |
| 愛の手帳所持者数 (人)E | 219 | 224 | 226 |
| 対総人口比 (%)E÷A | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
2.基本サービスの目標水準と目標量
1 目標数値表
| 項目 | サービスの目標水準 | |||
|---|---|---|---|---|
| ねたきり高齢者 | 痴呆性高齢者 | 虚弱高齢者 | 障害者 | |
| ホームヘルプサービス | 5回/週 52週/年 |
5回/週 52週/年 |
2回/週 52週/年 |
3回/週 52週/年 |
| デイサービス | 2回/週 52週/年 |
3回/週 52週/年 |
2回/週 52週/年 |
2回/週 52週/年 |
| ショートステイ | 7日/回 6回/年 |
7日/回 6回/年 |
7日/回 2回/年 |
7日/回 6回/年 |
| 給食サービス | 7回/週 52週/年 |
7回/週 52週/年 |
||
| 訪問入浴サービス | 1回/週 52週/年 |
- | - | 1回/週 52週/年 |
| 機能訓練 | 2回/週 (65歳以上の3.2%) 26週/年 (40歳~64歳の0.4%) |
2回/週 52週/年 (デイサービスとして実施) |
||
| 訪問看護 | 2回/週 52週/年 |
1回/週 52週/年 |
1回/月 | (40~64歳) 2回/週 52週/年 |
| 訪問指導 (訪問指導・訪問活動) |
16回/年 | 7回/年 | 5回/年 | 4回/年 |
| 訪問口腔衛生指導 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |
| 訪問栄養指導 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 | 1回/年 |
| 健康教育 | - | - | - | - |
| 健康相談 | - | - | - | - |
| 健康診査 | 基本健康診査受診率 60% | |||
| 各種がん検診受診率 10% | ||||
| 在宅サービスセンター | 中学校区に1か所を基本とする | |||
| 在宅介護支援センター | 中学校区に1か所を基本とする | |||
| 特別養護老人ホーム | 65歳以上人口の1.69%程度 | |||
| 養護老人ホーム | 現状のままとする | |||
| 老人保健施設 | 65歳以上人口の1%程度 | |||
| ケアハウス | 65歳以上人口の0.5%程度 | |||
| 訪問看護ステーション | - | |||
| 項目 | サービスの目標量 | サービスの提供体制の確保 | |
|---|---|---|---|
| 平成11年度 | 平成12年度 | ||
| ホームヘルプサービス | 高齢者 149,248時間/年 |
高齢者 159,856時間/年 障害者 48,148時間/年 |
高齢者ホームヘルパー124人(常勤換算) 障害者ホームヘルパー38人(常勤換算) |
| デイサービス | 高齢者 36,020回/年 |
高齢者 3,8563回/年 障害者 16,073回/年 |
地区在宅サービスセンター5か所整備 みのり福祉園 |
| ショートステイ | 高齢者 8,388日/年 |
高齢者 8,985日/年 障害者 1,080日/年 |
高齢者25ベッド、特別養護老人ホームに確保 障害者3ベッド |
| 給食サービス | 高齢者 39,276回/年 |
高齢者 42,079回/年 障害者 22,058回/年 |
特別養護老人ホーム調理・ ボランティア配送、業者調理・配送 |
| 訪問入浴サービス | 高齢者 7,842回/年 |
高齢者 8,403回/年 障害者 5,042回/年 |
委託実施方式の拡大 |
| 機能訓練 | 高齢者 15,291回/年 |
高齢者 16,139回/年 |
地区住宅サービスセンター等(6か所)で実施 |
| 訪問看護 | 高齢者 16,126回/年 40~64歳 1,966回/年 |
高齢者 17,277回/年 40~64歳 1,983回/年 |
法人等による設置を促進する |
| 訪問指導 (訪問指導・訪問活動) |
高齢者 4,822回/年 障害者 1,028回/年 母子 733回/年 |
高齢者 5,122回/年 障害者 1,032回/年 母子 741回/年 |
(新生児検診の優所見児×年3回) |
| 訪問口腔衛生指導 | 高齢者 402回/年 障害者 257回/年 |
高齢者 430回/年 障害者 258回/年 |
委託実施方式の拡大 (訪問指導のなかで実施) |
| 訪問栄養指導 | 高齢者 402回/年 障害者 257回/年 |
高齢者 430回/年 障害者 258回/年 |
委託実施方式の拡大 (訪問指導のなかで実施) |
| 健康教育 | 520回 一般 456回、重点 64回 |
520回 一般 456回、重点 64回 |
実施体制の整備 |
| 健康相談 | 280回 一般 230回、重点 50回 |
280回 一般 230回、重点 50回 |
実施体制の整備 |
| 健康診査 | 受診予定者 8,757人(62.6%) | 受診予定者 9,103人 | - |
| 受診予定者 10,385人(10.7%) | 受診予定者 11,427人 | - | |
| 在宅サービスセンター | 5か所程度 | 5か所程度 | 特別養護老人ホーム、シルバーピア等へ併設 |
| 在宅介護支援センター | 5か所程度 | 5か所程度 | 特別養護老人ホーム、病院等へ併設 |
| 特別養護老人ホーム | 入所者数 190人 | 入所者数 190人 | 市内3施設(既設2+新設1)を中心に確保する |
| 養護老人ホーム | 入所者数 20人 | 入所者数 20人 | 圏域調整のなかで施設を整備する |
| 老人保健施設 | 入所者数 100人 | 入所者数 100人 | 法人等による設置を促進する |
| ケアハウス | 入所者数 50人 | 入所者数 50人 | 法人等への助成を図り、誘致する |
| 訪問看護ステーション | 1か所程度 | 1か所程度 | 法人等による設置を促進する |
※このサービス目標水準は平均的なモデルで、利用の限度を示すものではありません。
※なお、健康診査の受診率は、受診予定者÷東京都の調査による老人保健法「健康診査対象人口」により算出したものです。(30~40歳以上)
2 ケアプラン
《1》高齢者の場合のケアプラン例
●本人
80歳 女性 3か月前に脳梗塞発作を起こして入院、左半身マヒの障害がのこり、1種2級の身体障害者手帳を取得。
痴呆は軽度、日常会話は可。食事は一部介助必要、夜間は紙おむつ使用。
●介護者
長男夫婦(50代、共働き―フルタイム)、孫2人
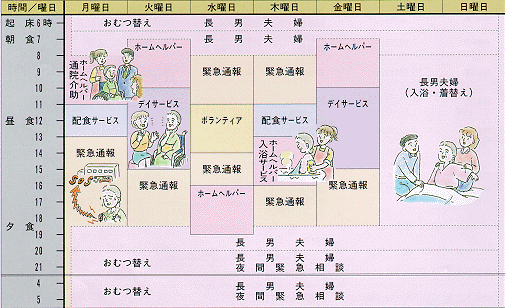
| ●主なサービス ・ホームヘルパー 週5回(計15時間) 介護、調理、相談助言、通院介助 ・デイサービスセンター 週2回 デイサービス、リハビリテーション ・ショートステイ、年6回 ・ボランティア 週1回、話相手 ・配食ボランティア 配食、安否確認 ・訪問入浴 週1回 ・緊急通報システム (在宅介護支援センター) |
●その他のサービス ・ソーシャルワーカーの相談・訪問 ・訪問看護 必要に応じて週2回 ・訪問指導 月1~2回 ・紙おむつ支給 ・理美容サービス 3か月に1回 |
《2》精神薄弱者の場合のケアプラン例
●本人
22歳、男性 愛の手帳3度
養護学校卒業後市内の授産施設に通所
てんかん発作あり、月2回通院
●家族
母親(50歳)と2人世帯(寡婦世帯) 持ち家
母親は就労(平日9時~17時 時々残業あり)
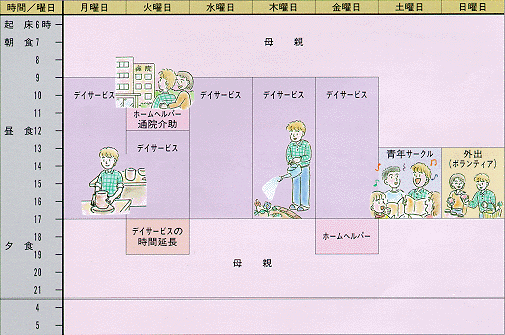
| ●主なサービス ・ホームヘルパー 週2回(計5時間) 調理、相談助言、通院介助 ・デイサービス 週5回 ・デイサービスの時間延長 週1回 ・ショートステイ 年6回 ・ボランティア 週1回 外出 ・青年サークル 週1回 |
●その他のサービス ・ソーシャルワーカーの相談・訪問 ・訪問指導 年4回 |
2 施策の大綱
1 健康で安心して生活するために
在宅生活を支えるサービスシステムづくり
誰もが家族や地域とのつながりをもちながら、住み慣れたところで自立した生活が続けられるよう、在宅生活を支える日常生活支援サービスの充実を図るとともに、健康の保持・増進のための保健・医療サービスの充実に努めます。
2 住み慣れたところで暮らし続けるために
在宅生活を支える施設づくり
地域福祉の各分野にわたる総合的相談、情報提供、保健・福祉・医療の各サービス等に対応する拠点の整備を図ります。
また、サービスができるだけ身近な地域で受けられるように、在宅保健福祉サービス地区単位の提供システムを確保するとともに、施設の整備に努めます。
3 こころ豊かな人生をおくるために
社会参加と生きがいづくり
障害者や高齢者などの就労機会の拡大、社会参加と地域交流の促進、生涯学習の推進を民間団体や市民の理解と協力を得ながら積極的に図っていきます。
4 ふれあいとささえあいのあるまちにするために
コミュニティの形成・地域づくり
市民参加やふれあいに支えられた人間性豊かなコミュニティの形成を図るため、多彩なコミュニティ活動を支援するとともに、それらの活動をとおして人権の尊重、福祉意識の高揚に努めていきます。
5 やさしさのあるまちづくりのために
福祉のまちづくり
子ども、障害者、高齢者などにとって「住みよいまち」とするため、その行動特性にあった生活環境の整備、移動手段の確保を図り、多くの市民にとっても「やさしいまち」となるよう努めます。
6 計画推進のために
地域福祉推進基盤の整備
サービス利用者の立場に立って、身近なところでサービスが提供できる施設整備や体制の確保を図っていきます。
また、本計画の確実な実現を図るため、推進体制の整備、財源の確保にも努めていきます。さらに、高齢社会に対応するため、保健・福祉・医療を担う人材の養成と確保に向けて、積極的に取り組んでいきます。
そして、保健・福祉・医療に関連する団体や市民とも連携し、地域福祉の推進に努めます。
第5章 主要施策の展開
1 健康で安心して生活するために
在宅生活を支えるサービスシステムづくり
1.日常生活支援サービスの充実
| 日 常 生 活 支 援 サ | ビ ス の 充 実 |
在宅基本サービスの拡充 |
|---|---|
| ●ホームヘルプサービスの拡充 ●ショートステイ(短期入所)の拡充 ●デイサービス(ミニデイサービスも含む)の拡充 |
|
| その他の在宅援助サービスの充実 | |
| ●食事サービスの充実 ●デイサービスの充実 ●入浴サービスの充実 ●生活自助具サービスの充実 ●緊急通報システムの充実 ●ガイドヘルパー派遣の充実 ●コミュニケーションサービスの充実 |
|
| 家族・児童の援助サービスの充実 | |
| ●保育内容の充実 ●障害児の保育・療育の充実 ●児童館活動・学童保育の充実 |
障害をもったり身体的機能が低下したときに、介護や介助が必要となっても生活の質を低下させることなく在宅生活が続けられるよう、日常生活を支援するための在宅三本柱ともいわれる基本サービス(ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス)の拡充と、その他の在宅援助サービスの充実に努め、本人と家族への支援を図ります。
また、地域の子どもをもつすべての家族が安心して暮らせるよう、家族・児童の援助サービスの充実を図ります。
1 在宅基本サービスの拡充
(1)ホームヘルプサービスの拡充
障害やその他の事情により日常生活を営むことに支障がある世帯に対して充実したホームヘルプサービスを提供するため、派遣時間帯の延長に努めるとともに、多様なサービスの供給主体となる社会福祉協議会、地区在宅サービスセンター、家政婦協会などとの連携を図りながら、児童のいる世帯、難病患者、精神障害者などへの派遣も検討していきます。
また、地区在宅サービスセンターの整備にあわせたホームヘルパーの計画的な配置に努めるとともに、サービスを円滑に提供するためのチーム方式による提供についても検討していきます。
(2)ショートステイ(短期入所)の拡充
利用希望者の増加に対応できるよう、特別養護老人ホーム、自立生活支援センターなどの受け入れ施設の拡充を図るとともに、介護者が病気等で介護が困難になったときなどの保護期間の延長にも努めます。
また、家族が介護技術を修得するためのホームケアや、夜間の介護が困難な痴呆性高齢者の夜間のみの介護を行うナイトケアについても実施に努めます。
(3)デイサービス(ミニデイサービスも含む)の拡充
高齢者や障害者などの健康状態や身体状況に応じて、基本事業(日常動作訓練、趣味・生きがい活動など)、入浴、食事、機能訓練などのサービスを提供し、健康の維持や機能の回復、孤独感の解消を図っていくとともに、介護にあたる家族の負担を軽減するための地区在宅サービスセンターを整備し、デイサービス事業や痴呆性高齢者デイホームの拡充に努めます。
そして、50歳未満の障害者については、自立生活支援センターでのサービス実施に努めるとともに、精神障害者、難病患者についても実施の検討を行います。
また、老人福祉館などで行う虚弱高齢者等のミニデイサービス事業についても円滑に運営できるよう、支援に努めます。
2 その他の在宅援助サービスの充実
(1)食事サービスの充実
高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、社会福祉協議会が実施している訪問食事サービスの拡充が図れるよう助成の充実に努めます。また、社会福祉協議会には対象者の拡大を要請していきます。
高齢者及び50歳以上の障害者で地区在宅サービスセンターへの通所者については、施設内で食事サービスを実施するとともに、会食型についても検討します。
(2)デイサービスの時間延長
介護者や保護者の事情により介護や育児が困難となる場合に対応するため・デイサービスを実施しているそれぞれの施設で時間の延長を図ります。
(3)入浴サービスの充実
家庭において入浴が困難な高齢者や障害者などに対し、訪問入浴サービス及び施設入浴サービスを充実します。これらの入浴サービスについては回数を増やすなど、その充実に努めます。
(4)生活自助具サービスの充実
生活の自立を助長し日常生活の利便を図るために、身体の状況に適応した日常生活用具などの福祉機器の給付と相談、情報の提供などを行って、生活自助具サービスを充実します。
(5)緊急通報システムの充実
高齢者や障害者などの孤独感の解消や緊急時における安全を確保するために、在宅介護支援センターに連絡でき、ホームヘルプサービスと連携した24時間・365日の生活を支援する緊急通報システムの整備に努めます。
(6)ガイドヘルパーの派遣の充実
視覚障害者などが社会生活上必要な外出をするときに付添いをする、ガイドヘルパー派遣事業の充実に努めます。
障害者の社会参加を促進する観点からも、精神薄弱者など対象者の範囲の拡大を検討していきます。
(7)コミュニケーションサービスの充実
聴覚言語障害者に対する手話通訳やファックスサービスに加え、視覚障害者等に対するコミュニケーションサービスを実施します。
また、そのための人材の確保や機器の活用を図っていきます。
3 家族・児童の援助サービスの充実
(1)保育内容の充実
多様化する保育需要に対応するため、年齢別定員の見直しや産休明け保育実施園の増園、延長保育・一時保育事業を実施します。
また、一般の保育園では保育困難な病後の児童を預かる施設に対して、病児保育助成事業の実施をめざします。
(2)障害児の保育・療育の充実
障害の重度化を防ぎ障害児の発達を促進するために、関係機関との連携のもとに、早期療育事業及び療育相談を行っていきます。
(3〕児童館活動・学童保育の充実
子育て相談など子育て支援事業の実施や、障害児も安心して利用できる施設運営にするなど、児童館活動の充実に努めます。
また、夜間や休日は施設を地域に開放し、子ども会活動などの拠点となるように努めます。
学童保育については、障害児の受け入れなど内容の充実に努めます。
| 事業名 | 対象者 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|---|
| ホームヘルプサービスの拡充 | 高齢者 障害者 児童 |
実施 対象拡大の調査 対象拡大の調査 |
実施 実施 実施 |
| ショートステイの拡充 | 高齢者 障害者 |
実施 実施 |
実施 実施 |
| デイサービスの拡充 | 高齢者 障害者 |
実施 実施 |
実施 実施 |
| 食事サービスの充実 | 高齢者 障害者 |
実施 実施 |
実施 実施 |
| 入浴サービスの充実 通所 | 高齢者 障害者 |
実施 実施 |
実施 実施 |
| 入浴サービスの充実 訪問 | 高齢者 障害者 |
実施 実施 |
実施 実施 |
| デイサービスの時間延長 | 高齢者 障害者 児童 |
実施 調査 調査 |
実施 実施 実施 |
| ガイドヘルパー・手話通訳の充実 | 障害者 | 調査・充実 | 実施 |
2.保健・医療サービスの充実
| 保 健 ・ 医 療 サ | ビ ス の 充 実 |
健康づくりの推進 |
|---|---|
| ●健康づくり運動の展開 ●健康教育・健康相談の充実 |
|
| 保健・予防対策の充実 | |
| ●基本健康診査・各種検診事業の拡充 ●母子保健の充実 ●健康管理システムの導入 ●保健・医療情報の提供 |
|
| 在宅保健・医療サービスの推進 | |
| ●訪問指導の充実 ●訪問看護の促進 ●機能訓練の充実 ●訪問歯科診療の実施 |
|
| 保健・医療体制の充実 | |
| ●保健医療供給体制に関する協議会の設置 ●休日急患診療事業の充実 |
市民のライフステージに応じた健康づくりを推進します。また、すべての市民が住み慣れた地域や家庭で安心して生活が続けられるよう保健所・医療機関などと連携し、疾病予防から早期発見・早期治療、リハビリテーションに至る一貫した保健・医療サービスの充実に努めます。さらに、福祉サービスを必要とする高齢者や障害者の多くは、同時に保健・医療サービスも必要としていることから、これらのサービスが緊密な連携のもとに総合的に提供できるよう支援体制の確立を図ります。
1 健康づくりの推進
(1)健康づくり運動の展開
市民による健康づくり運動を推進するため、健康づくり推進協議会と協議し・健康づくりリーダーの養成、「健康のつどい」の充実、社会教育分野との事業連携を図るほか、地域住民によるレクリエーション活動等の支援強化を行います。また、健康づくりの場を確保するため、学校体育施設の整備・開放を進めるほか、民間における健康づくり施設の開放を要請していきます。
さらに、幼児から中学生までの健康づくりを進めるため、保育園や児童館・小中学校・保健福祉サービスセンター・保健相談所などの関係機関で構成する児童健康づくり推進協議会を設置して、健康づくり事業の連携強化やパンフレットの作成などを行います。
(2)健康教育・健康相談の充実
市民の健康づくり意識を高めるために、成人病予防や肥満解消等の講演会、各種教室を充実するとともに、地域住民団体からの求めに応じて保健婦等を派遣し、相談や教育の機会の拡充を図ります。
また、市民個々の健康保持増進に対応するため、地区在宅サービスセンター等において健康相談を実施します。健康相談は健康管理システムの活用などによって、より個別的な疾病予防や保健衛生・食生活などに関する相談へと内容の拡充を図ります。さらに、老人福祉センター等において、楽しみながら学べる健康講座や軽体操等を主体とした健康教室を開催し、ねたきり等の発生予防に努めます。
2 保健・予防対策の充実
(1)基本健康診査・各種検診の拡充
成人病の早期発見・早期治療のため、基本健康診査や各種検診にかかわる受診定員の拡大・計画検診の導入・個別健康診査の拡充・ミニ人間ドックの実施に努めるとともに、健診後の保健指導の充実を図ります。また、高齢期における歯の健康を守るため、成人歯科健診の実施について検討します。
(2)母子保健の充実
妊産婦や乳幼児を対象とした保健指導・乳幼児定期健康診査を充実し、障害の発生予防から早期発見・早期療育につなげ、乳幼児の健康の保持増進を図ります。
また、育児経験の乏しい母親を対象とした育児相談の充実を図るとともに、やまとあけぽの学園・保育園等の関係機関と連携し、子育て支援のネットワーク化を図ります。
さらに、思春期世代に対しては、相談や母性教育を行って、母子保健に関する意識啓発を図ります。
(3)健康管理システムの導入
市民が生涯にわたって健康を保持していくことができるよう、ブライバシー保護に十分配慮しながら母子健康診査・学校健康診査・成人健康診査などの結果を経年的・一元的に管理し、相談指導できる健康管理システムの導入に努めます。
(4)保健・医療情報の提供
市民に的確な保健医療情報を提供するため、乳幼児や高齢者世帯など世代別のパンフレット等を作成するとともに、ファクシミリ等を活用した情報の即時提供や東京都保健医療情報センターとの連携による情報提供に努めます。
また、在宅介護支援センターと連携し、夜間等における相談にも努めます。
3 在宅保健・医療サービスの推進
(1)訪問指導の充実
ねたきり及び痴呆等の高齢者や障害者がよりよい在宅生活をおくれるよう、保健婦や栄養士・理学療法士・作業療法士等が連携して訪問し、在宅療養上の相談・指導などを行う訪問指導の充実を図ります。この訪問指導については、ホームヘルブサービス等の福祉サービスや訪問看護等の在宅医療サービスとも十分連絡調整を図りながら実施します。また、健診後の要注意者にも必要に応じて訪問指導を行います。
さらに、乳幼児がすこやかに育つよう、育児不安などがある妊産婦・乳幼児に対しても保健婦等による訪問活動の充実を図ります。
(2)訪問看護の促進
訪問看護が必要なねたきり者が主治医の指示のもとに定期的な看護が受けられるよう、医療法人等による訪問看護ステーションの設置を促進します。
また、在宅療養を支えるため、緊急入院ベッドなどの確保を検討します。
(3)機能訓練の充実
心身の機能が低下し医療終了後も継続して機能訓練が必要な人に対しては、地区在宅サービスセンター、保健福祉サービスセンターなどの通所による機能訓練の機会を拡充し、ねたきりの防止に努めます。
また、このような状態の要介護高齢者に機能訓練や看護・介護を中心とした医療ケアと生活サービスを提供するため、老人保健施設の整備を促進します。
(4)訪問歯科診療の実施
在宅医療サービスを充実させるため、歯科医師会の協力のもとに、ねたきり高齢者に対して訪問歯科診療を実施します。
4 保健・医療体制の充実
(1)保健医療供給体制に関する協議会の設置
市民の初期医療の充実や在宅療養の支援強化を図るため、地域における医療供給体制等について検討し医師会や歯科医師会、薬剤師会などの関係機関で構成する協議会を設置します。協議会では、乳幼児や在宅高齢者等に対するホームドクター(かかりつけ医)制の推進、訪問看護・訪問歯科診療等在宅医療の推進、病院と診療所の連携・機能分担等について検討をしていきます。
(2)休日急患診療事業の充実
夜間・休日等の突発的な疾病に対する救急医寮床制の充実を図るため、休日急患診療所の時間延長や準夜間診療事業の実施、休日歯科診療事業の実施について検討を進めます。
| 事業名 | 対象者 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|---|
| 健康教育の充実 | 全市民 | 実施 | 実施 |
| 健康相談の充実 | 全市民 | 実施 | 実施 |
|
基本健康診査・ 各種検診の拡充 |
30~40歳以上 | (個別健康診査については逐次受診年齢を引き下げる) 実施 |
|
| 計画検診の導入 | 節目年齢者 40,45,50,55,60歳 |
早期に実施予定 | 実施 |
| ミニ人間ドックの実施 | 40,50,60歳の者 | 調査 | 実施 |
| 訪問指導の充実 | 高齢者 障害者 母子 |
実施 | 実施 |
| 訪問看護の促進 | 40歳以上の ねたきり者 |
調査 | 実施 |
| 機能訓練の充実 | 18歳以上の障害者 虚弱高齢者 |
実施 | 実施 |
| 母子保健の拡充 | 妊産婦(配偶者) 乳幼児 思春期以降の女性 |
実施 | 実施 |
| 訪問歯科診療の実施 | ねたきり高齢者 | 調査 | 実施 |
2 住み慣れたところで暮らし続けるために
在宅生活を支える施設づくり
1.拠点施設の整備
| 拠点施設の整備 | 保健福祉サービスセンターの整備 |
保健福祉サービスの全市的中核施設を整備し、地域福祉を総合的に展開していきます。
1 保健福祉サービスセンターの整備
保健福祉などの総合的な相談やサービスの決定・調整、デイサービスや訪問サービス・保健サービス等の提供、生活用具の相談等を実施するための保健福祉サービスセンターの整備を検討していきます。社会福祉協議会やボランティア活動の拠点施設についても併設の検討をしていきます。
2.高齢者のための施設
|
高 齢 者 の た め の 施 設 |
地区在宅サービスセンターの整備 |
| 特別養護老人ホームの整備 | |
| 老人保健施設の整備促進 | |
| ケアハウス(軽費老人ホーム)の整備促進 | |
| 痴呆性高齢者デイホームの整備 | |
| 老人福祉館の整備 |
高齢者や障害者が住み慣れたところで安心して生活が続けられるよう、高齢者地域自立生活支援サービスシステムに基づいた施設の整備を進めます。
地区在宅サービスセンターの整備
ねたきり高齢者や虚弱高齢者がデイサービス、入浴サービス、給食サービスなどを身近なところで受けられるよう、地区在宅サービスセンターを「高齢者地域自立生活支援システム」に基づいて、計画的に整備します。
また、介護を行っている家庭を支援するため、身近なところで相談とサービスの調整が受けられるよう在宅介護支援センター(※1)の整備を進めます。
2 特別養護老人ホームの整備
常時介護を要する高齢者が、自宅で適切な介護を受けることが困難な場合に入所する特別養護老人ホームを社会福祉法人への助成によって整備に努めます。
また、この施設がもつサービス機能を地域の高齢者福祉の拠点施設として地域へ展開していけるよう、法人に要請します。
なお、特別養護老人ホーム等については、施設整備はもとより、運営面における財政的援助を国、都に積極的に要請していきます。
3 老人保健施設の整備促進
病状が安定期に入った要介護高齢者に、ねたきり防止のためのリハビリテーションや看護・介護を中心とした医療ケア、ショートステイ、デイサービスなどの日常生活サービスを提供するため、老人保健施設を市内に整備できるよう医療法人または社会福祉法人に積極的に働きかけていきます。
4 ケアハウス(軽費老人ホーム)の整備促進
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が必至となっていることから、住宅対策との整合性を考慮しながら社会福祉法人等へ働きかけ、ケアハウス(※2)の整備の促進を図ります。
5 痴呆性高齢者デイホームの整備
日中の介護が困難な痴呆性高齢者に対して通所による各種サービスを提供するため、特別養護老人ホームに併設された地区在宅サービスセンターに痴呆性高齢者デイホーム(※3)施設を付設して整備を進めていきます。
6 老人福祉館の整備
すべてのコミュニティ区に1館ずつを目標に、老人福祉館を整備することとし、未整備の3地区(北西、北東、南東地域)の整備と、老朽化した南街老人福祉館等の建て替えに努めます。
(※1)在宅介護支援センター
在宅介護に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健・医療・福祉サービスが受けられるよう調整する施設。
(※2)ケアハウス
身体機能の低下のため独立して生活を営むには不安がある高齢者が、自立した生活を維持できるよう、構造や設備の面で工夫された新しいタイプの老人ホーム。
(※3)痴呆性高齢者デイホーム
在宅の痴呆性高齢者のうち、家族による日中の介護が困難な方を、デイホーム施設で 日々通所の方法により、各種サービスを行う事業。
3.障害者のための施設
| 障 害 者 の た め の 施 設 |
自立生活支援センター |
|---|---|
| 精神薄弱者通所更生施設の整備 | |
| 共同作業所の充実 |
障害者地域自立生活支援サービスシステムによる主要施設の整備を次により進めます。
1 自立生活支援センターの整備
地域で障害者が自立生活できるよう、精神薄弱者通所更生施設とあわせてさまざまなサービスを総合的、一体的に提供する自立生活支援センターの整備を進めます。
また、グルーブホームとの一体的運営を検討していきます。
2 精神薄弱者通所施設の整備
障害の重度化に対応するため、重度精神薄弱者等の生活訓練の拡充を進めるとともに、精神薄弱者通所更生施設をみのり福祉園の敷地内に整備していきます。
3 共同作業所の充実
民間の授産施設や小規模作業所に対しては、運営費援助の充実や建設費・用地賃貸料などの援助制度を充実します。
4.家族・児童のための施設
| 家 族 ・ 児 童 の た め の 施 設 |
家庭・子育て支援センターの整備 |
|---|---|
| やまとあけぼの学園の整備の検討 | |
| 児童館・学童保育所の整備 |
家族・児童地域生活支援システムによる主要施設の整備を次により進めます。
1 家庭・子育て支援センターの整備
地域で安心して子育てができるよう、さまざまなサービスを総合的、一体的に提供する家庭・子育て支援センターの整備を検討します。
2 やまとあけぼの学園の整備の検討
肢体不自由児施設及び精神薄弱児施設としての機能を充実するために、施設の整備を検討していきます。
3 児童館・学童保育所の整備
地域における児童の活動や子育ての拠点施設となる児童館を公共施設配置構想に基づいて整備し、あわせて学童保育所の整備を進めます。
| 事業名 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
(平成13~15年度) |
|---|---|---|---|
| 保健福祉サービスセンターの整備 | 調査 | 1か所 | |
| 地区在宅サービスセンターの整備 | 調査6年度に1か所開所 | 4か所 | - |
| 特別養護老人ホームの整備 | 調査6年度に1か所開所 | - | - |
| 老人保健施設の整備促進 | - | 1か所 | - |
| ケアハウスの整備促進 | - | 1か所 | - |
| 痴呆性高齢者デイホームの整備 | 調査6年度に1か所開所 | 2か所 | - |
| 老人福祉館の整備 | 建替 2か所 | 1か所 | 設計 1か所 |
| 自立生活支援センター | 整備 | - | - |
| 精神薄弱者通所更生施設の整備 | 整備 | - | - |
| 共同作業所の充実 | 実施 | 実施 | - |
| 家庭・子育て支援センターの整備 | 調査 | 整備 | |
| やまとあけぼの学園の整備の検討 | 調査 | 調査 | - |
| 児童館・学童保育所の整備 | - | 1か所 | 1か所 |
3 こころ豊かな人生をおくるために
社会参加と生きがいづくり
1.就業機会の拡大
| 就 業 機 会 の 拡 大 |
雇用の促進 |
|---|---|
| ●職業相談体制の充実 ●企業などへの要請 |
|
| 福祉的就業の促進 | |
| ●シルバー人材センターの充実 ●障害者就業センターの整備 |
就業を望んでいる高齢者や障害者、ひとり親などの就業機会の拡大を進めるため、雇用の促進を図るとともに、福祉的就業の充実に努めます。
1 雇用の促進
(1)職業相談体制の充実
関係機関との連携を強化して、専門相談員による定期的な職業相談窓口の充実に努めます。
(2)企業などへの要請
公共職業安定所・商工会等と連携をとりながら、高齢者、障害者、ひとり親などの就業機会の拡充を企業に要請します。
2 福祉的就業の促進
(1)シルバー人材センターの充実
高齢者が社会参加と自らの経験や能力をいかすことができるよう、シルバー人材センター活動への助成を充実します。
また、センターでの新しい事業の開発や会員の語らい・作業の場として「ワークプラザ」が整備できるよう、側面からの援助を図ります。
(2)障害者就業センターの整備
障害者の就業機会を拡充するため、障害者就業センターを整備し、公共事業の受託、売店や喫茶コーナーの経営、リサイクル事業や園芸作業等の実施を検討します。
また、自立生活支援センターと連携しながら、障害者の就労・自立生活訓練を支援します。
2.参加と交流の促進
| 参 加 と 交 流 の 促 進 |
ふれあいと交流の促進 |
|---|---|
| ●世代間交流の促進 ●地域交流事業の充実 |
|
| 社会参加・生きがい活動の促進 | |
| ●高齢者生涯学習・社会活動センターの整備 ●障害者の参加・交流 ●介護者への社会参加支援の推進 |
高齢者や障害者がいきいきとこころ豊かに暮らせるよう、交流の促進を図るとともに、社会参加・生きがい活動を支援するための施策の充実に努めます。
1 ふれあいと交流の促進
(1)世代間交流の促進
子どもたちが高齢者に対する理解を深め豊かな社会性を育めるよう、保育園や学校、施設などで子どもと高齢者の交流を促進します。さらに、さまざまな世代との交流機会の拡充に努めます。
(2)地域交流事業の充実
障害者に対する市民の相互理解・相互交流を深めるため、やまとあけぼの学園やみのり福祉園の施設開放を推進して地域交流事業の充実を図るとともに、福祉祭の充実、障害者の日(12月9日)における事業の拡大に努めます。
また、自立生活支援センターにおいても地域交流事業を実施します。
2 社会参加・生きがい活動の促進
(1)高齢者生涯学習・社会活動センターの整備
高齢者の社会参加・生きがい活動の促進を図るため、組織機関として高齢者地域自立生活支援システムに基づいた高齢者生涯学習・社会活動センターを整備し、活動の拠点とします。なお、市立生涯学習センター、公民館などと連携した運営に努めます。
また、この施設において高齢者大学の開催、シルバーボランティアやジョブコーチャーの養成、都市農山村交流事業、国際貢献や国際交流活動への参加の機会の提供、〔仮称〕地域年金生活者クラブ(いきいき生活者クラブ)などの活動支援を行います。
(2)障害者の参加・交流
障害者の社会参加・生きがい活動を促進するため、活動拠点の整備、障害者団体に対する助成の充実、自主事業への支援強化を図ります。
自立生活支援センターや保健福祉サービスセンターにおいても、このような視点から障害者の社会参加・生きがい活動を支援していきます。
また、障害者の青年学級や青年サークルの活動を支援します。
(3)介護者への社会参加支援の推進
高齢者や障害者の家族・介護者が生きがいをもち社会活動へ参加できるよう、在宅介護者の会の支援、介護者のリフレッシュ時間の確保、介護休暇の制度化要請に努めます。
3.生涯学習の推進
| 生 涯 学 習 の 推 進 |
学習機会の保証 |
|---|---|
| ●推進体制の整備 ●学習施設の整備 |
|
| スポーツ・レクリエーション活動の充実 | |
| ●高齢者のスポーツ・レクリエーション活動の促進 ●障害者のスポーツ・レクリエーション活動の促進 |
高齢者や障害者が生涯学び続けることができるよう、学習の機会を保障するとともに、スポーツ活動等を充実していきます。
1 学習機会の保証
(1)推進体制の整備
高齢者や障害者の自発的な学習活動を支援していくため、その基本的な方針及び各種施策などを総合的に体系化した生涯学習計画を市民参加のもとに策定します。
また、市民自らが新たな学習のつくり手となって学ぶことのできる市民大学や高齢者大学の検討を進めるとともに、公民館での講座の充実や公民館活動における組織づくりに努めます。
(2)学習施設の整備
学習施設の確保を図るため、公民館6館構想の実現や地域集会施設の整備に努めます。
図書館については、点字や音声資料、大活字本等の資料を充実させるとともに、地区図書館の整備に際しては、高齢者や障害者に配慮したバリアフリー(※1)化に努めます。
聴覚言語障害者や視覚障害者などにも配慮して、学習施設を整備します。
(※1)バリアフリー
高齢者や障害者が安全に、快適に日常生活がおくれるように、行動の妨げとなる建築的障害を取り除くこと。
2 スポーツ・レクリエーション活動の充実
(1)高齢者のスボーツ・レクリエーション活動の促進
高齢者が自主的・積極的に参加することができ、心身の健康を保持して豊かな生活を楽しむことができるよう、高齢者に適したスポーツ・レクリエーション活動の充実に努めます。
(2)障害者のスポーツ・レクリエ・ション活動の促進
障害者が参加できるスポーツ教室やレクリエーションの機会の拡充を図るとともに、自主的なスポーツ・レクリエーション活動への援助、相談・指導体制の充実に努めます。
障害者の宿泊訓練や野外活動等についても積極的に支援していきます。
| 事業名 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|
| 職業相談体制の充実 | 実施 | 実施 |
| 障害者就業センターの整備 | - | 調査 |
| 高齢者生涯学習・社会活動センターの整備 | - | 調査 |
| 学習施設の整備 | 2か所整備 | 1か所整備 |
4 ふれあいとささえあいのあるまちにするために
コミュニティの形成・地域づくり
1.コミュニティづくりの推進
| コ ミ ュ ニ テ ィ づ く り の 推 進 |
形成基盤の整備 |
|---|---|
| ●コミュニティ区の設定とカルテの作成 ●コミュニティ施設の充実 ●情報ネットワークの確立 |
|
| 自主活動の支援 | |
| ●組織団体への支援 ●地域活動への支援 |
相互の連帯意識に支えられた地域社会を形成するためには、市民のコミュニティ活動を支援し、行政の推進体制を確立しなければなりません。このため、コミュニティ施設の整備を進めるとともに、市民の自発的で多彩な地域活動が展開されるよう市民組織や団体の育成、活動の支援に努めます。
1 形成基盤の整備
(1)コミュニティ区の設定とカルテの作成
市内の8コミュニティ区ごとに、市民によるコミュニティ委員会を設置します。そして、地区に対する市民の認識を深め、その特性をいかしたまちづくりを推進するため、市民参加によるコミュニティカルテを作成して、地区環境の整備・改善の指針とします。
(2)コミュニティ施設の充実
コミュニティ活動の拠点として、老人福祉館や児童館、集会施設などのコミュニティ施設を公共施設配置構想に基づき整備します。
また、コミュニティ施設の一元的な管理・運営を行うとともに、小学校敷地内への建設の可能性を検討して、学校の地域防災拠点化とあわせてコミュニティの拠点化をめざします。
なお、自治会等の集会施設については、補助制度の充実を図りつつ、自主的な施設確保への支援を行います。
(3)情報ネットワークの確立
市民の多彩なコミュニケーション活動を支援していくため、地域情報や文化・学習情報、スポーツ・レクリエーション情報などを一元的に管理・提供していくための情報ネットワークを確立します。
2 自主活動の支援
(1)組織団体への支援
地区における市民相互の交流と連帯を深めるため、自治会、子ども会、老人クラブなどの地区組織、文化・学習活動やスポーツ・レクリエーション活動を行う自主グループなどへの支援を強化するとともに、こうしたコミュニケーション活動の中心的な役割を担うリーダー・指導者の養成を図ります。
(2)地域活動への支援
コミュニティ活動を推進するため、地域福祉やリサイクル、児童・青少年の健全育成、防犯・防災など地域活動への支援を拡充するほか、これらのコミュニティ活動を支えるボランティアの養成と発掘に努めます。
2.福祉の風土づくりの促進
| 福 祉 の 風 土 づ く り の 促 進 |
福祉教育の推進 |
|---|---|
| ●学校教育・保育園等での推進 ●家庭・地域等での推進 ●企業における福祉活動の推進(フィランソロピー) |
|
| 地域福祉活動の充実 | |
| ●地域高齢者見守り活動の促進 ●地域児童見守り活動の促進 |
|
| ボランティア活動の推進 | |
| ●ボランティア活動の振興 ●ボランティアセンターの整備 |
人権の尊重、福祉意識の高揚を進め、人間性豊かな地域社会を形成するため、福祉教育の推進、地域福祉活動やボランティア活動の充実などを通して、福祉の風土づくりの促進を図ります。
(1)学校教育・保育園等での推進
児童・生徒の福祉への関心を高め参加を進めるために、学習指導要領や保育所保育指針に基づいた福祉教育を教育課程や保育計画に位置づけて、児童・生徒の発達段階に応じて計画的に推進できるよう関係機関へ要請していきます。
また、ボランティア推進校の指定、副読本の作成、地域での交流事業等を実施します。
(2)家庭・地域等での推進
市民の福祉への関心と参加を促すため、福祉祭などを充実するとともに、公民館活動で福祉こ関する教室・講座を開設するなど、家庭・地域等での福祉教育の推進を図ります。
また、老人クラブ等の福祉活動に対する援助にも努めていきます。
(3)企業における福祉活動の推進(フィランソロピー)
地域福祉活動の充実を図るため、市民の理解と協力を得て福祉活動への参加を促進するとともに、企業内での福祉教育の推進などを要請していきます。
2 地域福祉活動の充実
(1)地域高齢者見守り活動の促進
ひとり暮らし高齢者などが安心して生活できるよう、協力員制度の導入を図り、地域見守り活動の促進に努めます。
(2)地域児童見守り活動の促進
PTA、児童委員、児童館職員、父母等の連絡会を設置し、地域における児童の見守り活動を促進します。
3 ボランティア活動の充実
(1)ボランティア活動の振興
福祉・教育・文化などさまざまな分野において、市民が自発的・主体的に参加できるよう、ボランティア活動への支援の充実を図ります。
また、お父さんボランティア、シルバーボランティアの育成を積極的に進めていきます。
(2)ボランティアセンターの整備
ボランティア活動の基盤を整備するため、活動拠点となるボランティアセンターを整備し・ボランティア活動に関する情報提供やPR活動の充実をするとともに、ボランティアスクールを拡充します。
ボランティアセンターの運営にあたっては、運営委員会を設置して住民参加を高めるとともに、専門の職員を配置していきます。
| 事業名 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|
| コミュニティカルテの作成 | 実施 | - |
| コミュニティワーカー(※1)の配置 | 検討 | - |
| コミュニティ委員会の設置 | 13年度目標 8委員会 | |
| 集会施設の整備 | 2か所整備 | 1か所整備 |
| 福祉教育の推進 | 実施 | 実施 |
| ボランティアセンターの整備 | 調査 | 実施 |
(※1)コミュニティワー力ー
地域社会における多種多様なニーズに対して、地域の資源を利用したり、さまざまなサービス提供システムを調整・仲介して、適切なサービスを提供することにより、地域の自治や組織化を援助する専門職。
5 やさしさのあるまちづくりのために
福祉のまちづくりのために
1.生活環境の整備
| 生 活 環 境 の 整 備 |
都市環境の整備 |
|---|---|
| ●福祉のまちづくり整備要綱の制定 ●公共建築物及び公園・道路などの公共施設の整備 ●民間施設の整備促進 |
|
| 安全・防犯対策 | |
| ●交通安全対策の推進 ●防災対策の推進 ●防災対策の推進 |
高齢者や障害者などを含めたすべての市民が安全で快適に暮らすことのできるまちづくりをめざして、公共と民間の協力のもとに生活環境の整備を進めます。
1 都市環境の整備
(1)福祉のまちづくり整備要綱の制定
福祉のまちづくりを進めるため、東京都の「福祉のまちづくり整備指針」に基づいた「福祉のまちづくり整備要綱」を制定し、市立施設の改善計画を作成します。
(2)公共建築物及び公園・道路などの公共施設の整備
「福祉のまちづくり整備要綱」と市立施設の改善計画に基づいて、公共建築物や道路・公園などの公共施設の整備・改善を計画的に進め、高齢者や障害者にとって安全で利用しやすいものとしていきます。
また、公共交通機関が集中している地域や障害者・高齢者のための施設がある地域を選定して、福祉のまちづくりモデル地区整備事業を進めます。さらに、障害者や高齢者が気軽に外出できるようガイドマッブを作成します。
(3)民間施設の整備促進
金融機関や一定の床面積以上の店舗などをもつ民間施設に対して、「宅地開発等指導要綱」による指導とあわせて「福祉のまちづくり整備要綱」に基づく助言・指導を行うとともに、施設整備費の助成を検討し、高齢者や障害者が利用しやすい施設整備への働きかけを行います。
2 安全・防犯対策
(1)交通安全対策の推進
高齢者や障害者が安心して外出できるよう、交通安全思想の普及に努めるとともに、交通安全施設の整備を関係機関に働きかけていきます。
(2)防犯対策の推進
高齢者や障害者に、悪質商法に関する販売方法や契約などのトラブルに関する情報を提供し、犯罪の予防に努めていきます。
(3)防災対策の推進
災害時における高齢者や障害者の安全を確保するため、避難行動計画の策定を検討します。
2.住宅の整備
| 住 宅 の 整 備 |
公的住宅の確保 |
|---|---|
| ●市営・都営住宅への入居促進 ●公社住宅の整備・改善 |
|
| 民間住宅対策 | |
| ●民間借り上げ住宅の供給 ●住み替え家賃の助成 ●住宅改造費助成の充実 |
|
| グループホームの設置援助・充実 | |
| ●精神薄弱者グルーブホームの設置援助 ●精神障害者グルーブホームの設置援助 |
「東大和市住宅マスタープラン」の方針に基づき、高齢者や障害者などの住宅整備に努めます。
また、高齢者に配慮した住宅を「東大和市地域高齢者住宅計画」に基づいて整備していきます。
(1)市営・都営住宅への入居促進
市営・都営住宅の建て替え時において、生活協力員(※1)の配置や緊急通報システムを整備した高齢者住宅(シルバーピア)や障害者などの住宅の確保を図ります。
(2)公社住宅の整備・改善
高齢者や障害者などに配慮した住宅の整備や既存団地の改善を東京都住宅供給公社に要請していきます。
2 民間住宅対策
(1)民間借り上げ住宅の供給
バリアフリー化や緊急通報システム化、生活協カ員の配置など高齢者や障害者に配慮した住宅の確保を図るため、福祉型借上公共賃貸住宅制度(※2)を活用した民間アパートの借り上げ事業を進めます。
(2)住み替え家賃の助成
高齢者や障害者などが地域で安心して住み続けられるよう、民間借家の取り壊しで立ち退きを迫られた場合に新しい家賃との差額を助成する住み替え家賃助成制度の充実に努めます。
(3)住宅改造費助成の充実
住宅改造が必要な高齢者や障害者に対しては、改造費用の助成の充実を図るほか、住宅改造に関する助言・指導を地区在宅サービスセンターや保健福祉サービスセンターなどで行っていきます。
(※1)生活協力員
公営住宅において、高齢者や障害者などの入居者に対し、緊急時の対応や安否の確認等を行う人。
(※2)福祉型借上公共賃貸住宅制
高齢者などが、地域のなかで安心して住み続けられる住宅を確保するため、市が高齢者などに配慮された民間アパートを借り上げ、住宅に困窮する高齢者などに提供する。
3 グループホームの設置援助・充実
(1)精神薄弱者グループホームの設置援助
精神薄弱者が就労や日常生活について必要な援助・指導を受けながら、地域のなかで自立して生活し続けられるよう、グルーブホームの設置を援助していきます。
(2)精神障害者グループホームの設置援助
精神障害者が就労や日常生活について必要な援助・指導を受けながら、地域のなかで自立して生活し続けられるよう、グループホームの設置を援助していきます。
3.交通アクセスの改善
| 交 通 ア ク セ ス の 改 善 |
公共交通機関への要請 |
|---|---|
| ●鉄道駅エレベーター設置の要請 ●低床式バスの要請 ●市内循環バス路線の要請、補助 |
|
| 市内輸送システムの確立 | |
| ●リフト付バスの運行 | |
高齢者や障害者が安全かつ円滑に日常生活を営み生活圏の拡大が図られるよう、公共交通機関の利便性の確保や市内移送システムの確立など、交通アクセスの改善に努めます。
(1)鉄道駅エレベーター設置の要請
高齢者や障害者が自由に外出できるよう、駅舎にエレベーター等の設置を要請していきます。
(2)低床式パスの要請
高齢者や障害者の安全性と利便性を高めるため、低床式バスの導入を関係機関に要請していきます。
(3)市内循環バス路線の要請、補助
既存路線バスの停留所増設や増便、運行時間の延長、多摩都市モノレールの運行にともなう市内循環路線の新設などを関係機関に要請していきます。
2 市内移送システムの確立
(1)リフト付きバスの運行
市内の高齢者や障害者施設などを循環するリフト付きバスの運行を検討します。
| 事業名 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|
| 福祉のまちづくり整備要綱の制定 | 要綱制定・実施 | 実施 |
| 公共施設の改善整備計画の策定 | 計画策定 | 実施 |
| モデル地区整備 | 調査 | 実施 |
| 高齢者を対象とした交通安全教育の充実 | 継続実施 | |
| 避難行動計画の策定 | 策定の検討 | |
| 高齢者住宅の確保 | (13年度目標 200戸) | |
| 市営・都営住宅への入居促進 | ||
| 障害者住宅の確保 | 調査 | 実施 |
| 住み替え家賃の助成 | 継続実施 | |
| 住宅改造費の助成の充実 | 実施 | 実施 |
| 精神薄弱者グループホームの設置援助 | 調査 | 実施 |
| 精神障害者グループホームの設置援助 | 調査 | 実施 |
| リフト付きバスの運行 | 調査 | 実施 |
第6章 地域福祉推進基盤の整備
1.総合的サービス提供体制の構築
1 サービス利用者である住民の立場に立った提供体制の確立
地域で在宅自立生活を継続していくためには、公的な保健福祉サービスが利用しやすい身近な場で提供されることが重要となります。
24時間・365日の生活のすべての場面で各種サービスを包括的な連携をもって提供するため、保健福祉の各領域で総合的・一元的なサービスの提供に努めるとともに、医療サービスとの連携システムの構築、高齢者・障害者・ひとり親・児童等の相談窓口やサービス提供を統合化した在宅保健福祉サービスシステムの構築などに努めます。
また、身近な在宅保健福祉サービス地区でソーシャルワーカー(※1)、保健婦、 ホームヘルパー、看護婦等がチームとなって、総合的・継続的なサービス計画立案、提供、調整をしていくというケースマネージメント(※2)体制の確立を図ります。
さらに、各種サービスを利用しやすくするため、利用券方式(※3)の採用など手続の簡素化に努めます。
なお、柔軟で有効なサービスを確保するため、民間の能力を活用します。民間委託にあたっては、経費の節減を目的とすることなく、行政責任を明確にしていきます。
(※1)ソーシャルワーカー
社会福祉の諸分野で、指導的従事者として、あるいは相談援助などの専門職としてその実践に関わっている人の総称。
(※2)ケースマネジメント
要介護者の在宅ケアの継続をめざし、援助を必要とする者の側に立って、サービス利用に関し、情報の提供・相談、ニーズの評価、サービス計画の立案、サービスの実施、再評価などを統合的に行うこと。その際の調整役がケースマネージャー。
(※3)利用券方式
利用の登録(利用券の発行)をすることにより、サービス利用にあたって、その都度、市役所等の窓口で利用申込みをせずに、サービス提供機関へ直接申込み、そのサービスが利用できる方法。
2 行政の福祉的展開の推進
住民にとって身近で利用しやすい施設・生活環境を整備していくとともに、保健福祉サービスを必要とする住民への利用しやすさ(アクセシビリティ)を保障するために、すべての行政分野を社会福祉の視点から見直し、配慮したものとしていきます。
また、市内すべての公共施設や生活環境を利用しやすくすることとあわせて、社会福祉施設を高齢者だけ、障害者だけという対象別・専有的に利用することを改めるため、多目的な利用のあり方を検討していきます。
さらに、福祉教育研修を計画的に実施し、行政職員の資質の向上に努めます。
3 効率的財政運営の推進
市民生活において普遍化し多様化する福祉ニーズに的確に応え、本計画に掲げられた諸施策を実現していくためには、保健福祉サービスに要する財源の確保に努力するとともに、限りある財源を有効に活用していくことが極めて重要となります。そのために、国及び都の事業の積極的な活用や経常的な経費を見直して、より一層の行政経費の効果的配分に努めるなど、行財政の効率的な運営を推進します。
なお、在宅自立生活での“求めと必要に応じた”保健福祉サービスの提供にあたっては、所得が少ない者への十分な配慮をしつつ、所得に応じた適正な自已負担を求めていきます。
また、計画に基づく事業の進捗状況等を積極的に公開するなど、計画の着実な推進に向けて、市民の理解と協カが得られるように努めていきます。
4 保健福祉サービスの利用者範囲の拡大
これまでの福祉サービスは、経済的要件や世帯要件などによっては公的サービスの利用が困難な場合があり、また、障害者施策においても、その対象が狭く「愛の手帳」・「身体障害者手帳」の取得者に限定されていました。本計画では在宅自立生活の確保に向けて、社会生活上で何らかの支障をもつ人すべてを保健福祉サービスの利用者とし、その範囲を拡大していきます。例えば、精神障害者、難病患者等についても包含することを検討し、総合的な在宅保健福祉サービスを推進していきます。
2.計画の進行管理
1 計画推進組織の整備
福祉・保健の充実、住環境の整備、各種団体の育成、住民意識の啓発など広範囲にわたる本計画を効果的に推進するため、組織機構の整備に努めます。
そして、地域福祉計画の推進管理、社会福祉にかかる各種施策の推進を行うため、住民参加による地域福祉審議会を条例により設置します。
なお、要援護者の権利の擁護を図るため、保健福祉サービスに対して個別に出される苦情を処理する機関(苦情処理機構)の設置を検討します。
また、当事者及びその関係者も主体的に計画の推進に参加できるよう、当事者団体の機能を強化して推進状況の検討・問題点の提起等を行って、協働体制の推進を図ります。
2 計画の見直し
本計画の推進を図るため、毎年度その推進状況を集約して進行管理を行います。また、社会状況や高齢者・障害者などの実態をより反映させるため、関係機関・団体との調整を行って3年単位で計画を見直していきます。
3.マンパワーの確保策
1 マンパワーの確保
来たるべき超高齢社会に対して積極的に対応するため、保健福祉を担う社会福祉人材の養成・確保とともに、保健福祉の充実のために要する人材が膨大となることから、マンパワーの質の向上にも積極的に取り組んでいきます。
特に、在宅保健福祉サービス地区構想を考えた場合、各地区ごとにサービスを提供するためのケースマネージメント体制の確立が必要となることから、その中心的な役割を担っていくソーシャルワーカーやホームヘルパー・保健婦・看護婦の確保に努めます。
さらに、今後ますます多くの専門性の高いサービスが必要とされることから、社会福祉士(※1)、介護福祉士(※2)をはじめ、作業療法士(OT)(※3)、理学療法士(PT)(※4)、言語療法士(ST)(※5)などの専門職の確保を図っていきます。
そのためにも、公的機関での雇用に配慮していくとともに、社会福祉協議会や社会福祉法人、その他の団体においても積極的な雇用が可能となるよう、財政面などへの援助を充実していきます。
なお、社会環境の変化、雇用に対する意識の変化、女性の社会進出などから社会福祉人材の確保が困難な要因も多いため、人材の確保計画を策定し、計画的な人材の確保を図ります。人材の確保計画の策定にあたっては、研修制度の充実、弾力的な雇用体制の検討、嘱託・パート就労に対する各種社会保険の整備など、待遇改善の検討に努めます。
(※1)社会福祉士
専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害かあることまたは環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他援助を行う専門家。
(※2)介護福祉士
専門知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対して、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその介護者に対して介護に関し指導を行う専門家。
(※3)作業療法士(occupatinal therapsit)
心身障害者に対して、手先の訓練・補装具の利用・レクリエーションなどを通し、応用動作能力や社会的適応の促進・回復などを図るための援助を行うことを目的としたリハビリテーション医療に従事している専門職。
(※4)理学療法士(physical therapsit)
身体障害者に対して、治療体操・電気刺激・マッサージ・温熱等を手段として、身体機能の回復を図るための援助を目的としたリハビリテーション医療に従事している専門職。
(※5)言語療法士 (speech therapsit)
言語障害者に対して、発声指導、言語指導を通して失語症や構音障害などの言語治療を行うことを目的としたリハビリテーション医療に従事する専門職。
2 マンパワーの養成
保健福祉に関する社会福祉人材を養成するため、保健福祉関係大学、短大、専門学校などの養成機関に就学する学生に対して、介護福祉士などを中心とした奨学金制度等の検討を行います。
また、中高年者の潜在的な社会福祉人材の掘り起こしなどとあわせて、中高年者のリカレント教育(※1)等を推進します。
ホームヘルパー養成講座(※2)については、3級ヘルパーを中心に取り組み、地区での開催に配慮していきます。2級ヘルパーなどの養成についても、身近なところで実施できるよう関係機関への働きかけを行うとともに、市内での実施も検討していきます。
さらには、小規模な民間団体での人事管理などの効率化・定着化を図るため、可能な限り各団体間の人事交流の促進や研修の充実を支援します。
(※1)リカレント教育
義務教育終了以降も生涯にわたって教育と他の諸活動を交互に行うことを保障するような組織化された教育のあり方。社会人入学制度や放送大学などの例がある。
(※2)ホームヘルパー養成請座
| 課程 | 目的 | 受講対象者 | 受講時間 |
|---|---|---|---|
| 1級 | ホームヘルプサービス事業における基幹的なホームヘルパーの養成 | 処理困難なケースを担当するとともに2級・3級課程修了者の指導等を行う者 | 360時間 |
| 2級 | 主にねたきり高齢者等の身体介護業務にあたるホームヘルパーの養成 | 主にねたきり高齢者等の身体介護業務に従事する者 | 90時間 |
| 3級 | 主に家事援助業務にあたるホームヘルパーの養成 | 主に家事援助業務に従事する者 | 40時間 |
4.相談体制の充実と情報提供
1 総合的な相談窓口の設置
保健・福祉・医療など多様な相談に対応できるよう、保健福祉サービスセンターにソーシャルワーカー、保健婦などの専門職を配置した総合的な相談窓口の設置に努めます。
また、身近なところで気軽に介護などに関する相談ができるよう、地区在宅サービスセンターに在宅介護支援センターを付設するなど、相談機能の充実を図ります。
2 情報提供の充実
保健福祉サービスを住民にとって利用しやすいものとするため・各種サービスに関する情報を一元的に提供できるような広報誌やパンフレットの発行等を行います。
また、情報の的確さ・効果性を確保し、本庁や保健福祉サービスセンター、地区在宅サービスセンター、自立生活支援センター等における窓口の連携を支援するため、プライバシー保護に十分配慮しながらコンピュータ等による情報のデータベース化(※1)・効率化を図ります。
(※1)データベース
コンピュータを使用して、情報や資料を収集・分類・整理し、多目的に利用できるように工夫された統合化ファイル。
5.民間団体の支援
1 民間の社会福祉団体との連携と援助
地域福祉を推進していくうえで民間の社会福祉団体が果たしている役割は大きく、今後も、活発な活動の展開が期侍されていることから、人材や財源の確保などの支援に努めていきます。
特に、社会福祉協議会の果たすべき役割は重要であり、新たな活動の展開も求められていることから、在宅サービスの提供だけでなく、民間の社会福祉活動の中核団体としての役割が果たせるよう、積極的に援助していきます。
また、地域福祉の推進に関連する諸団体との連携を密にするとともに、社会福祉法人による社会福祉施設経営の安定化、市内での社会福祉法人などの設立を援助していきます。さらに、社会福祉法人以外の小規模な任意団体の育成援助にも努めます。
2 保健福祉サービスの主体的利用のあり方の確立
超高齢社会における保健福祉サービスは市民生活の細部にわたって提供される必要があるため、専門的なサービスは市民にとって理解しにくい一面をもっています。したがって、市民には市民の求めと必要に応じた保健福祉サービスを効果的に活用するための主体的利用のあり方を学習していくことが求められます。行政は主体的利用が可能となるような組織(例えば“年金生活者クラブ(いきいき生活者クラブ)”“障害者自立生活クラブ”など)の援助を行い、社会福祉サービスを利用する力の養成を支援します。
また、当事者の相互支援活動によってサービスが提供できる組織を育成、支援し、そうした当事者団体の自立化・活性化のための援助を行います。
6.住民参加の推進
計画の円滑かつ確実な推進に向けて、要援護者自身の参加を含めた市民の参加を一層促進するとともに、福祉活動実践団体との連携と援助の強化を図ります。
さらには、すべての市民が保健福祉の諸問題について理解と認識を深め、主体性をもって計画の推進に参加していくことが必要となることから、今後、住民参加による地域福祉審議会などを設置し、そうした場を通して地域福祉計画をより実行性あるものとしていきます。
また、みのり福祉園を積極的に見直し、それを核とした障害者地域自立生活支援システムを推進するため、新たな組織の運営管理に関して積極的に当事者参加・住民参加の運営委員会を充実させていきます。本システムを担う障害者事業協会の新設にあたっては、法人の理事会のほか、当事者参加・住民参加を高めるための評議員会を設置します。
さらに、市民の福祉意識を把握するため、福祉活動実践団体や住民団体との懇談会・連絡会などを開催していきます。
2 長寿社会福祉基金の充実
地域福祉計画を円滑かつ確実に推進するためには、住民参加と要援護者自身の参加を含めた市民活動の活性化が必要です。そのため、柔軟で即応的な資金となる長寿社会福祉基金の充実を図るとともに、その果実等の運用によって民間団体やボランティア団体が行う新たな保健福祉活動に対する支援をし、地域福祉活動の活性化を図ります。
7.国及び都への要請
本計画を推進するため、交付税措置の充実、補助率の引き上げ、実態に即した補助基準の改善など、財政措置の拡充を国及び都に要請していきます。
また、地域福祉を推進するには、年金・医療・公的扶助など社会保障・社会福祉の基本的な諸制度の整備が不可欠なことから、これらの充実についても要請していきます。
| 事業名 | 前期 (平成6~8年度) |
後期 (平成9~12年度) |
|---|---|---|
| 在宅保健福祉サービスシステムの構築 | 調査 | 実施 |
| 地域福祉審議会の設置 | 実施 | 実施 |
| 苦情処理機構の設置 | - | 調査 |
| マンパワーの確保計画の策定 | 実施 | 実施 |
| 総合的相談窓口の設置 | 調査 | 実施 |
| 社会福祉協議会への支援 | 充実 | 充実 |
| 障害者事業協会の設立 | 実施 | 実施 |
| 長寿社会福祉基金の充実 | 充実 | 充実 |
主題:
みんなの和21プラン
-東大和市地域福祉計画-
40頁~86頁
発行者:
東大和市
発行年月日:
1994.3
文献に関する問い合わせ先:
東大和市福祉部
東京都東大和市中央3丁目930番地
電話 0425(63)2111(代)
