みんなの和21プラン-東大和市地域福祉計画-
みんなの和21プランの策定にあたって
3 障害者と地域福祉の現状
(1)身体障害者
身体障害者手帳の所持者数は、年々増加し人口に占める割合も高まっていますが、18歳未満者の手帳所持者数は微減傾向にあります。
高齢化の進行が顕著で、高齢者は18歳以上の手帳所持者の4割弱に達しています。各5歳級年齢人口に対する障害者の割合は、男女とも50歳前後から高まり始め年齢が増すほど高くなっています。障害の発生時期は1歳未満と10歳前後の各年代で1割前後となっていますが、50歳代は2割近くで他の年齢層に比べて多くなっています。
障害内容は肢体不自由が6割を占めますが、全体としては微減の傾向にあって、むしろ内部障害の割合が増加しています。
障害の程度は重度化の傾向がみられ、1・2級をあわせると半数近くとなります。
表14-0 障害の発生時期(市民意識・実態調査より) 単位:% 件数813
| 1歳未満 | 9.2 |
| 1~10歳未満 | 11.6 |
| 10~20歳未満 | 7.3 |
| 20~30歳未満 | 11.8 |
| 30~40歳未満 | 11.1 |
| 40~50歳未満 | 11.4 |
| 50~60歳未満 | 18.7 |
| 60~70歳未満 | 11.3 |
| 70歳以上 | 7.0 |
| 無回答 | 0.6 |
図14 男女5歳級別身体障害者手帳所持者の対総人口比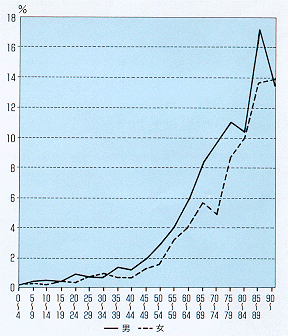
資料:福祉事務所調べ
手帳所持者数は平成5年6月1日現在
総人口は平成5年4月1日現在
表17 年齢階層別身体障害者手帳所持者数
| 区分 | 18~49 | 割合(%) | 50~64 | 割合(%) | 65~ | 割合(%) | 合計 | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 202 | 25.3 | 319 | 40.0 | 276 | 34.6 | 797 | 100.0 |
| 女 | 142 | 22.2 | 216 | 33.8 | 281 | 44.0 | 639 | 100.0 |
| 総数 | 344 | 24.0 | 535 | 37.3 | 557 | 38.8 | 1,436 | 100.0 |
資料:社会福祉課調べ 平成5年6月1日現在
表18 身体障害者手帳の級別内訳及び18歳未満の者
| 区分 | 総人口 (人) |
手帳所 持者数 (人) |
1級 (人) |
割合 (%) |
2級 (人) |
割合 (%) |
3級 (人) |
割合 (%) |
4級 (人) |
割合 (%) |
5級 (人) |
割合 (%) |
6級 (人) |
割合 (%) |
18歳未満の 手帳所持者数 (人) |
18歳未満の所 持者の人口に 占める割合 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 67,957 | 896 | 167 | 18.6 | 176 | 19.6 | 186 | 20.8 | 199 | 22.2 | 104 | 11.6 | 64 | 7.1 | 73 | 0.11 |
| 59年 | 68,475 | 940 | 166 | 17.7 | 200 | 21.3 | 207 | 22.0 | 198 | 21.1 | 106 | 11.3 | 63 | 6.7 | 73 | 0.11 |
| 60年 | 69,435 | 1,005 | 186 | 18.5 | 213 | 21.2 | 212 | 21.1 | 217 | 21.6 | 105 | 10.4 | 72 | 7.2 | 76 | 0.11 |
| 61年 | 70,106 | 1,071 | 199 | 18.6 | 236 | 22.0 | 222 | 20.7 | 229 | 21.4 | 106 | 9.9 | 79 | 7.4 | 76 | 0.11 |
| 62年 | 71,650 | 1,140 | 226 | 19.8 | 250 | 21.9 | 224 | 19.6 | 248 | 21.8 | 101 | 8.9 | 91 | 8.0 | 70 | 0.10 |
| 63年 | 73,199 | 1,212 | 245 | 20.2 | 284 | 23.4 | 224 | 18.5 | 254 | 21.0 | 116 | 9.6 | 89 | 7.3 | 64 | 0.09 |
| 平成元年 | 73,577 | 1,252 | 256 | 20.4 | 284 | 22.7 | 237 | 18.9 | 267 | 21.3 | 112 | 8.9 | 96 | 7.7 | 61 | 0.08 |
| 2年 | 74,450 | 1,301 | 271 | 20.8 | 289 | 22.2 | 244 | 18.8 | 286 | 22.0 | 116 | 8.9 | 95 | 7.3 | 51 | 0.07 |
| 3年 | 75,024 | 1,350 | 290 | 21.5 | 298 | 22.1 | 250 | 18.5 | 294 | 21.8 | 120 | 8.9 | 98 | 7.3 | 48 | 0.06 |
| 4年 | 75,344 | 1,393 | 316 | 22.7 | 313 | 22.5 | 258 | 18.5 | 294 | 21.1 | 120 | 8.6 | 92 | 6.6 | 48 | 0.06 |
| 5年 | 75,822 | 1,456 | 344 | 23.6 | 323 | 22.2 | 263 | 18.1 | 309 | 21.2 | 121 | 8.3 | 96 | 6.6 | 50 | 0.07 |
資料:社会福祉課調べ 各年4月1日
表19 身体障害者手帳所持者の障害区分と等級(18歳~49歳) 単位:人
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肢体不自由 | 58 | 53 | 32 | 47 | 24 | 10 | 224 |
| 視覚 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 聴覚 | 4 | 23 | 6 | 5 | 0 | 4 | 42 |
| 音声・言語 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 心臓 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 呼吸器 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| じん臓 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 直腸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ぼうこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 112 | 79 | 52 | 61 | 26 | 14 | 344 |
資料:社会福祉課調べ平成5年6月1日現在
(2)精神簿弱者
愛の手帳所持者数は微増傾向にありますが、18歳未溝の手帳所持者は近年、横ばいとなっています。
表20 愛の手帳所持者数
| 区分 | 総人口 A (人) |
愛の手帳 所持者数 B (人) |
再掲 18歳未満 C (人) |
B/A (%) |
C/A (%) |
C/B (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 67,957 | 135 | - | 0.20 | - | - |
| 59年 | 68,475 | 148 | - | 0.22 | - | - |
| 60年 | 69,435 | 156 | 67 | 0.22 | 0.10 | 42.95 |
| 61年 | 70,106 | 156 | 62 | 0.22 | 0.09 | 39.74 |
| 62年 | 71,650 | 154 | 53 | 0.21 | 0.07 | 34.42 |
| 63年 | 73,199 | 168 | 54 | 0.23 | 0.07 | 32.14 |
| 平成元年 | 73,577 | 174 | 56 | 0.24 | 0.08 | 32.18 |
| 2年 | 74,450 | 188 | 59 | 0.25 | 0.08 | 31.38 |
| 3年 | 75,024 | 199 | 57 | 0.27 | 0.08 | 28.64 |
| 4年 | 75,344 | 207 | 57 | 0.27 | 0.08 | 27.54 |
| 5年 | 75,822 | 218 | 58 | 0.29 | 0.08 | 26.61 |
資料:社会福祉課調べ 各年4月1日
表21 愛の手帳所持者数の度別内訳
| 区分 | 総人口 (人) |
愛の手帳 所持者数 (人) |
1度 (人) |
割合 (%) |
2度 (人) |
割合 (%) |
3度 (人) |
割合 (%) |
4度 (人) |
割合 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 67,957 | 135 | 9 | 6.67 | 33 | 24.44 | 63 | 46.67 | 30 | 22.22 |
| 59年 | 68,475 | 148 | 11 | 7.43 | 36 | 24.32 | 68 | 45.95 | 33 | 22.30 |
| 60年 | 69,435 | 156 | 10 | 6.41 | 41 | 26.28 | 71 | 45.51 | 34 | 21.79 |
| 61年 | 70,106 | 156 | 11 | 7.05 | 36 | 23.08 | 70 | 44.87 | 39 | 25.00 |
| 62年 | 71,650 | 154 | 11 | 7.14 | 37 | 24.03 | 69 | 44.81 | 37 | 24.03 |
| 63年 | 73,199 | 168 | 9 | 5.36 | 51 | 30.36 | 68 | 40.48 | 40 | 23.81 |
| 平成元年 | 73,577 | 174 | 9 | 5.17 | 49 | 28.16 | 73 | 41.95 | 43 | 24.71 |
| 2年 | 74,450 | 188 | 9 | 4.79 | 52 | 27.66 | 76 | 40.43 | 51 | 27.13 |
| 3年 | 75,024 | 199 | 10 | 5.03 | 56 | 28.14 | 78 | 39.20 | 55 | 27.64 |
| 4年 | 75,344 | 207 | 11 | 5.31 | 58 | 28.02 | 78 | 37.68 | 60 | 28.99 |
| 5年 | 75,822 | 218 | 11 | 5.05 | 62 | 28.44 | 83 | 38.07 | 62 | 28.44 |
資料:社会福祉課調べ 各年4月1日
(3)精神障害者
精神障害者の実数の把握は困難ですが、過去の調査(厚生省昭和38年度精神衛生実態調査)の有病率をもとに推計すると、平成5年4月1日現在で978人となります。
(4)障害者の施設利用の状況
障害者の施設利用の状況をみると、身体障害者は特別養護老人ホームの利用が過半となっていることから、重度身体障害者施設の定員確保が課題となっています。精神薄弱者は比較的授産施設の利用が多く、中でもみのり福祉園の利用者が多くなっており、この施設の重要性があらわれています。
また、市の施設であるやまとあけぼの学園は、学齢期前の障害児の重要な通園施設となっています。
さらに、市内には6か所の共同作業所があり、障害者の就業、社会参加、社会復帰、機能訓練等のための重要な施設となっています。特に精神障害者には数少ない社会復帰の訓練の場となっています。
表22 精神障害者の状況
| 区分 | 総人口 (人) |
精神保健法第32条による 公費負担申請件数 |
精神障害者推計値 総人口の1.29% |
|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 67,957 | 201 | 877 |
| 59年 | 68,475 | 237 | 883 |
| 60年 | 69,435 | 297 | 896 |
| 61年 | 70,106 | 333 | 904 |
| 62年 | 71,650 | 381 | 924 |
| 63年 | 73,199 | 376 | 944 |
| 平成元年 | 73,577 | 487 | 949 |
| 2年 | 74,450 | 518 | 960 |
| 3年 | 75,024 | 549 | 968 |
| 4年 | 75,344 | 577 | 972 |
| 5年 | 75,822 | 579 | 978 |
資料:地域福祉課調べ 各年4月1日
表23 身体障害者手帳所持者の施設利用の状況 単位:人
| 区分 | 入所 | 通所 | 計 |
|---|---|---|---|
| 肢体不自由者更生施設 | 1 | 0 | 1 |
| 身体障害者授産施設 | 0 | 16 | 16 |
| 重度身体障害者授産施設 | 4 | 0 | 4 |
| 身体障害者療護施設 | 3 | 0 | 3 |
| 生活実習所 | 0 | 3 | 3 |
| みのり生活実習 | 0 | 7 | 7 |
| 視覚障害者更生施設 | 1 | 0 | 1 |
| 重症心身障害児施設 | 6 | 0 | 6 |
| 精神薄弱者更生施設 | 2 | 0 | 2 |
| 精神薄弱者授産施設 | 0 | 3 | 3 |
| 肢体不自由児施設 | 1 | 0 | 1 |
| 特別養護老人ホーム | 55 | 0 | 55 |
| 病院 | 4 | 0 | 4 |
| 計 | 77 | 29 | 106 |
資料:社会福祉課調べ 平成5年6月1日現在
表24 愛の手帳所持者の施設利用の状況 単位:人
| 区分 | 入所施設 | 通所施設 | 計 |
|---|---|---|---|
| 精神薄弱者更生施設 | 17 | 0 | 17 |
| 授産施設 | 0 | 34 | 34 |
| 再掲 みのり福祉園 | 0 | 31 | 31 |
| 福祉作業所 | 0 | 4 | 4 |
| 生活実習所 | 0 | 7 | 7 |
| みのり生活実習 | 0 | 15 | 15 |
| 重症心身障害児施設 | 3 | 0 | 3 |
| 精神薄弱者施設 | 9 | 0 | 9 |
| 無認可作業所 | 0 | 1 | 1 |
| 養護老人ホーム | 1 | 0 | 1 |
| 身体障害者授産施設 | 3 | 0 | 3 |
| 身体障害者療護施設 | 1 | 0 | 1 |
| 養護施設 | 2 | 0 | 2 |
| 通勤寮 | 0 | - | 0 |
| 生活寮 | 2 | - | 2 |
| 計 | 38 | 61 | 99 |
資料:社会福祉課調べ 平成5年6月1日現在
表25 共同作業所の状況 単位:人
| 区分 | 利用者数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 総数 | ||
| かたつむりの会作業所 | 1 | 5 | 6 | 精神薄弱者対象 |
| 共同作業所第一みんなの家 | 5 | 9 | 14 | 身体障害者対象 |
| 共同作業所第二みんなの家 | 7 | 5 | 12 | 身体障害者対象 |
| ライブリィ工房 | 5 | 4 | 9 | 精神障害者対象 |
| あとりえトントン | 5 | 4 | 9 | 精神障害者対象 |
| 第2あとりえトントン | 3 | 4 | 7 | 精神障害者対象 |
| 総数 | 26 | 31 | 57 | - |
利用者は市内居住者のみの人数
資料:社会福祉課調べ 平成5年9月1日現在
表26 主な障害者在宅福祉サービス
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 自己 負担等 |
事業実績 平成5年度 |
|---|---|---|---|---|
|
医 療 費 の 助 成 |
更生医療 | 障害程度の軽減、障害の除去のための医療が必要な場合に東京都心身障害者福祉センターの判定に基づいて、指定医療機関で診療を行う。医療費は公費負担、人工血液透析・心臓手術、白内障手術がある。 18歳以上の身体障害者手帳所持者。 |
有 | 9人 |
|
心身障害者医療費・ 付添看護料差額助成 |
保険診療の自己負担分を助成、健康保険等の付添看護料と慣行料金との差額を助成する。 身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級を含む。)愛の手帳1・2度で国民健康保険の被保険者及び健康保険等の本人・被扶養者。 |
有 | 医療費助成対象者 735人 看護料差額 58件 |
|
|
補 装 具 |
補装具の交付・修理 | 身体障害者手帳所持者で東京都心身障害者福祉センターの判定(児童の場合は医師の意見書でも可)により必要が認められた方。 歩行補助つえ、車いす、義足、義手、装具、補聴器、眼鏡、義眼、ストマ用装具、座位保持装置、歩行器、頭部保護帽、電動車いす、盲人安全つえ、収尿器等。 |
有 | 成人 交付 520件 修理 92件 児童 交付 129件 修理 48件 |
| 補装具自己負担の補助 | 補装具の交付・修理を受けた方で、自己負担額のある方。 | - | 410件 | |
|
日 常 生 活 用 具 ・ 住 宅 設 備 改 善 費 の 給 付 等 |
日常生活用具の給付等 | 身体障害者手帳1、2級(内部障害は3級を含む。)で、種目ごとの要件に該当する方。 特殊寝台、特殊マット、浴槽、湯沸器、便器、ワープロ、シャワーチェアー、特殊便器、ルームクーラー、訓練いす、福祉電話、盲人用時計、テープレコーダー、屋内アラームシステム、文字放送用アダプター、電磁調理器、透析液加温器、酸素吸入装置、空気清浄器等。 |
有 | 成人 50件 児童 1件 計 51件 |
| 住宅設備改善費の給付 | 6歳以上で、身体障害者手帳(下肢、体幹)1・2級の方(台所は、18歳以上で家事に従事する方)浴場、便所、玄関、台所、居室、屋内移動設備。 | 有 | 26件 | |
|
日常生活用具・ 住宅設備改善費の 自己負担額の補助 |
上記の制度で日常生活用具・住宅改善費の給付等を受けた自己負担額のある方。 自己負担額全額。(基準額を越えた超過自己負担分は除く。) |
- | 27件 | |
|
酸 素 購 入 費 ・ 装 具 購 入 費 の 助 成 |
酸素購入費の助成 | 酸素吸入を必要とする呼吸器機能障害者に、その費用の一部を助成する。 日常生活用具給付制度による酸素吸入装置受給者で、医師が酸素吸入を必要と認めた方。ただし、生活保護受給者、医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている方を除く。1か月5,150円を限度。 |
有 | 10人 |
|
人口肛門・振興膀胱用装具 購入費の助成 |
人工肛門・人工膀胱造設者に、造設口の衛生処理に要する装具の購入費用の一部を助成する。 疾病により人工肛門・人工膀胱を永久に造設した方。ただし、生活保護受給者を除く。 1か月人工肛門10,180円、人工跨胱11,503円が限度。また、身体障害者手帳所持者で畜便袋の交付を受けた方は10,180円と畜便袋価格との差額を助成する。 |
有 | 10人 | |
|
ホ | ム ヘ ル パ | 等 の 派 遣 |
心身障害者・児 ホームヘルパーの派遣 |
日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害者・児のいる世帯で、家族が介護を行うことが困難な状況の世帯に対し、ホームヘルパーを派遣し介護や家事の援助を行う。 重度の心身障害のため日常生活を営むのに支障があり、かつ、その家族が高齢、疾病、就労、出産、事故等により介護できない状況にあるとき。(調理、用便、食事、掃除、洗濯等が介護なしに行えないとき。) |
有 | 60世帯 2,626回 |
|
重度脳性麻痺者等 介護人の派遣 |
介護人を派遣して屋外への手引、同行及びその他必要な用務を行う。 20歳以上の身体障害者手帳1級の脳性麻痺者または全身性障害者で特別障害者手当受給資格のある方で、かつ、独立して屋外活動をすることが困難な方。 必要があれぱ毎日。ただし、1級の脳性麻痺者で家族を介護人に指定する場合は、1か月12回以内。 |
無 | 4人 573回 |
|
|
視覚障害者 ガイドヘルパーの派遣 |
重度の視覚障害者の方が社会生活上必要不可欠な外出をする場合、付添が得られないときにガイドヘルパーを派遣する。 市内に住所を有する18歳以上の在宅の視覚障害者1級または2級程度の方。月16時聞を限度とする方。 |
有 | 94回 |
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 自己 負担等 |
事業実績 平成5年度 |
|---|---|---|---|---|
|
緊 急 一 時 保 護 等 |
心身障害者・児 緊急保護(都) |
保護者等の事情により、一時的に家庭における介護が困難になった心身障害者・児を緊急保護(宿泊)する。 在宅の重度心身障害者及び中度の精神薄弱者。身体障害者・児は指定病院、精神薄弱者・児は指定病院及び精神薄弱者・児施設で保護。原則として病院保護は1か月、施設保護は7日以内。18歳未満は児童相談所、18歳以上は福祉事務所。 |
有 | 3人 |
|
心身障害者・児 緊急保護(市) |
保護者または家族の疾病等により緊急に保護を必要とする心身障害者.児を一時保護(在宅)する。身体障害者手帳または愛の手帳所持者で、次の要件の一に該当する方。 (1)保護者または家族の疾病、出産及び事故により一時的に保護等が受けられなくなる方。 (2)近親者の冠婚葬祭等により一時的に保護等を必要とする方。 (3)その他、市長が特に必要と認めた方。 介護人を障害者の家庭に派遣し保護等をする場合または介護人の家庭において保護等する場合。 月5日を限度とし、1日8時間以内。 |
無 | 0件 | |
|
生 活 圏 の 拡 大 |
身体障害者自動車 運転免許取得費の助成 |
身体障害者が運転免許を取得する際の費用(入所料、技能・学科教習料及び教材費)の一部を助成する。次の各号に該当する方。 《1》免許取得に直接要する経費 |
所得 制限 あり |
2件 |
| 自動車改造費の助成 | 重度身体障害者が自動車の改造(操行装置及び駆動装置)を行う場合、その費用の一部を助成する。次の各号に該当する方。 (1)18歳以上の身体障害者手帳所持者で、上肢、下肢、体幹に係る障害の程度が1・2級の方。 (2)前年分の所得が特別障害者手当にかかる所得制限限度額の範囲内の方。 (3)自らが所有し、運転する一部を改造する必要があること。 133,900円 |
所得 制限 あり |
4件 | |
| 福祉タクシー券の交付 | 電車・バス等を利用することが困難な心身障害者・児が、市が契約した事業所のタクシーを利用する場合にその料金の一部を助成する。次の各号に該当する方で、東大和市心身障害者自動車ガソリン費助成事業実施要綱に基づくガソリン費の助成を受けていない方。 (1)上肢2級以上、視覚・内部・下肢・体幹3級以上の身体障害者手帳所持者。 (2)愛の手帳3度以上の方。 (3)前2号に準ずる方で、市長が特に認めた方。タクシー利用券(1枚500円)を月5枚交付する。 |
無 | 使用枚数 17,615枚 受給対象者 517人 |
|
|
自動車 ガソリン費の助成 |
心身に障害のある方のために使用する自動車(バイクを含む)の運行にともなうガソリン(軽油を含む)費用の一部を助成する。 (1)身体障害者手帳4級以上、及び平衡・上肢・体幹障害5級以上、下肢6級以上。 (2)愛の手帳4度以上の方。 (3)市長が特に認めた方。 上記各号の一に該当する方またはその方と生計を一にする方が所有する自動車で、その所有者に助成する。ただし、東大和市福祉タクシー事業実施要綱に基づく福祉タクシー券交付者は除く。対象者が支払ったガソリン費のうち税額相当分(現在1リットルにつき53円80銭、軽油は32円10銭)。 |
無 | 受給延べ数 1,464人 受給対象者 725人 |
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 自己 負担等 |
事業実績 平成5年度 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
そ の 他 の 事 業 |
巡回入浴サービス | 入浴困難な在宅重度心身障害者・児に入浴巡回車を派遣し、組立式浴槽によリ入浴介助を行う。入浴困難な在宅心身障害者・児で次の各号の一に該当する方。 (1)身体障害者手帳2級以上。 (2)愛の手帳2度以上。 (3)その他市長が特に認めた方。 市が委託した業者が自宅に行き、入浴車により月2回行う。(7月から9月の間は月4回実施) |
無 | 利用者 32人 (延べ556人) |
||
| 寝具乾燥事業 | 日常生活に支障のある高齢者及び身体障害者に対し、寝具乾燥を行い、衛生と健康を守る。65歳以上の在宅高齢者及び在宅障害者で、寝具の自然乾燥が困難な状況にある方で、次の各号の一に該当する方。 (1)ひとり暮らし高齢者 (2)高齢者のみの世帯で、ねたきり状態またはこれに準ずる方。 (3)単身の障害者及び障害者夫婦を含む世帯で、身体障害者手帳3級以上、愛の手帳3度以上の方。ただし、障害者夫婦で子どもが成人している場合または聴覚・平衡・音声・言語機能障害者は除く。 (4)その他市長が特に認めた方。 市が委託した業者が自宅に行き、乾燥車により月1回行う。対象者が常時使用している寝具類(8枚まで)に限る。 |
無 | 3世帯 延べ利用者 48人 |
|||
| 車いす貸与事業 | 心身の健康を保持に努めるため、ねたきり高齢者及び身体障害者に車いすを貸与する。 次の各号一に該当する方。 (1)東大和市老人福祉手当条例に基づく福祉手当受給者 (2)身体障害者手帳所持者。 (3)市長が特に認めた方。 月1回を限度とし、期間は10日とする。 |
無 | 45件 |
|||
| 巡回相談タクシー送迎 | 東京都心身障害者福祉センターが行う心身障害者・児巡回相談において、その相談を利用しようとする方に対し、タクシーによる送迎を行う。 心身障害者・児巡回相談において、手帳の交付または補装具の交付もしくは雇用の相談を受けようとする方で、自分で行くことが困難な方。 原則として多摩地域で行われる心身障害者・児巡回相談とする。 |
無 | 2人 |
|||
|
身体障害者 電話使用料の助成 |
外出困難な在宅の重度身体障害者に対し、電話料の一部を助成する。 (1)東大和市重度心身障害者・児日常生活用具給付等実施要綱に基づき、身体障害者福祉電話の貸与を受けている世帯。 (2)現に個人所有の電話を設置しており、身体障害者福祉電話の貸与要件に該当する世帯。 ※福祉電話貸与要件 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者または外出困難な方(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方。(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)基本料金+ダイヤル通話料(600円) |
所得 制限 あり |
1件 | |||
|
心身障害者世帯 住み替え家賃の助成 |
賃貸住宅取壊しにより立ち退き要求を受け、住宅に困窮している心身障害者世帯に家賃、転居一時金(礼金・権利金・仲介手数料)、契約更新料、火災保険料(障害者のみの世帯)の一部を助成する。身体障害者手帳4級以上または愛の手帳3度以上に該当する障害者のいる世帯で、下記の要件を満たし、賃貸住宅に転居が必要と認められる方。 (1)取壊しによる立退き要求を受けて住宅に困窮している方。 (2)世帯の所得が2,376,000円以下で、この額を上回る立ち退き料を受けていない方。 |
所得 制限 あり |
29本 | |||
|
視 |
点字図書館給付事業 |
在宅の視覚障害者に対し、点字図書館を給付することにより、点字図書館による情報の入手を容易にする。 |
有 | 1件 | ||
|
聴 覚 障 害 者 |
手話通訳派遣事業 | 健聴者との意思疎通を円滑にするため手話通訳者を必要とする場合に、手話通訳者を派遣する。身体障害者手帳を所持する聴覚障害者または言語障害者及び聴覚障害者等をもって組織する団体。 | 無 | 6人(105回) | ||
|
施 設 援 護 |
心身障害者通所 授産事業運営費補助 |
施設を利用できない在宅の心身障害者を対象として、授産指導(作業指導)を行うために、保護者等が運営する通所授産事業に対し、その経費の一部を補助することにより地域社会における心身障害者の自立更生を促進する。 | - | 3か所 | ||
|
心身障害者・児施設 入所者自己負担額の 一部補助 |
精神薄弱者福祉法第18条、身体障害者福祉法第29条、第30条の2、第30条の3、第30条の4、第31条及び児童福祉法第42条、第42条の2、第43条、第42条の2、第42条の3、第42条の4、第42条の5の規定による施設に入所もしくは通所している心身障害者・児または扶養義務者。施設に入所もしくは通所する心身障害者または扶養義務者がその能力に応じて負担すべき額の2分の1の額。 | 無 | 75件 | |||
|
各 種 手 当 の 支 給 |
各種手当 | 特別児童扶養手当 | 国 | 重度 46,390円 軽度 30,930円 |
所得 制限 あり |
77人 |
| 特別障害者手当 |
国 | 24,630円 13,390円 13,390円 |
101人 | |||
| 重度心身障害者手当 | 都 | 54,000円 | 所得 制限 なし |
60人 | ||
| 心身障害者福祉手当 | 都 | 14.000円 | 所得 制限 あり |
594人 | ||
| 市 | 6,100円 | 521人 | ||||
| 心身障害児福祉手当 | 市 | 6,100円 | 所得 制限 なし |
115人 | ||
| 児童育成手当 | 都 | 育成手当12,000円 | 所得 制限 あり |
510人 | ||
| 障害手当14.000円 | 74人 | |||||
|
共 済 制 度 |
心身障害者扶養年金 | 心身に障害のある方を扶養する保護者が死亡又は、重度障害者となった場合に残された障害者に年金を支給する制度である。なお、この制度には年金(月額3万円)や一時金に1万円が付加される特約付加がある。 | 減免 制度 あり |
掛金額(基本分) 1,700円~7,200円 掛金額(特約分) 700円~3,600円 |
||
| 加入者数 160人 年金受給者数 24人 |
||||||
4 家族・児童と地域福祉の現状
(1)児童のいる世帯
18歳未満の児童数は減少傾向が続いていますが、平成2年の国勢調査によると、18歳未満児のいる世帯は、一般世帯全体の4割を占めて東京都平均を大幅に超えており、6歳児のいる世帯も東京都平均を上回っています。
児童のいる世帯の家族類型をみると核家族がほとんどで、三世代家族等のその他の親族世帯は1割強にとどまっており、母親の就労等により家庭の養育機能が低下しやすい家族環境が進んでいます。
また、平成2年の国勢調査によれば、未婚の20歳未満の子どものいる母子世帯は406世帯で、父子世帯が76世帯ですが、児童育成手当受給世帯数は、近年おおむね横ばいで推移しています。
表27 児童数(18歳未満)の推移
| 区分 | 総人口 (人) |
児童数 (人) |
割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 67,995 | 20,948 | 30.81 |
| 59年 | 68,646 | 20,425 | 29.75 |
| 60年 | 69,484 | 20,309 | 29.23 |
| 61年 | 70,030 | 19,704 | 28.14 |
| 62年 | 71,325 | 19,396 | 27.19 |
| 63年 | 73,147 | 19,227 | 26.29 |
| 64年 | 73,669 | 18,593 | 25.24 |
| 平成2年 | 74,338 | 17,960 | 24.16 |
| 3年 | 75,030 | 17,321 | 23.09 |
| 4年 | 75,430 | 16,659 | 22.09 |
| 5年 | 75,752 | 15,995 | 21.11 |
資料:住民基本台帳 各年1月1日
表28 児童のいる世帯の状況
| 区分 | 一般世帯総数 | 6歳児未満のいる世帯 | 18歳未満児のいる世帯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 (人) |
割合 (%) |
実数 (人) |
割合 (%) |
実数 (人) |
割合 (%) |
||
| 総数 | 24,491 | 100.0 | 3,709 | 15.1 | 10,087 | 41.2 | |
| 内訳 | 核家族世帯 | 17,964 | 73.3 | 3,208 | 86.5 | 8,708 | 86.3 |
| その他の親族世帯 | 2,185 | 8.9 | 501 | 13.5 | 1,359 | 13.5 | |
| 単独世帯 | 4,274 | 17.5 | - | - | 20 | 0.2 | |
| 非親族世帯 | 68 | 0.3 | - | - | - | - | |
| 東京都 | 総数 | 4,693,621 | 100.0 | 478,050 | 10.2 | 1,300,512 | 27.7 |
資料:平成2年国勢調査
表29 ひとり親世帯の状況
| 区分 | 総数 | 子どもの数 | 6歳未満の子ども のいる世帯 (再掲) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人以上 | |||
|
母子世帯 世帯数 世帯員 |
406 1,091 |
176 352 |
184 552 |
46 187 |
62 166 |
|
父子世帯 世帯数 世帯員 |
76 204 |
34 68 |
32 96 |
10 40 |
5 13 |
|
総数 世帯数 世帯員 |
482 1,295 |
210 420 |
216 648 |
56 227 |
67 179 |
注:子どもは未婚の20歳未満の子ども
資料:平成2年国勢調査
表30 児童育成手当等受給世帯数
| 年度 | 育成手当 受給世帯 |
障害手当 受給世帯 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 昭和58年 | 416 | 96 | 512 |
| 59年 | 399 | 99 | 498 |
| 60年 | 401 | 90 | 491 |
| 61年 | 424 | 81 | 505 |
| 62年 | 419 | 81 | 500 |
| 63年 | 378 | 73 | 451 |
| 平成元年 | 413 | 70 | 483 |
| 2年 | 389 | 60 | 449 |
| 3年 | 386 | 61 | 447 |
| 4年 | 439 | 67 | 506 |
資料:児童福祉課調べ
(2)家族・児童施設の利用状況
《1》 保育園
保育園は14施設あり、園児数は年々減少頃向にありますが、対象児童人口に対する園児数の割合は逆に増加傾向にあり、保育需要は高くなっています。特に3歳未満児には待機者がみられます。
表31 保育園の状況
| 区分 | 園数 (園) |
園児総数 (人) |
年齢別措置児童数(人) | 措置率 (%) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
| 昭和58年 | 14 | 1,573 | 56 | 123 | 221 | 357 | 415 | 401 | 22.4 |
| 59年 | 14 | 1,531 | 50 | 132 | 223 | 325 | 401 | 400 | 23.6 |
| 60年 | 14 | 1,531 | 48 | 136 | 215 | 326 | 386 | 402 | 24.7 |
| 61年 | 14 | 1,472 | 52 | 156 | 199 | 313 | 372 | 380 | 25.4 |
| 62年 | 14 | 1,425 | 55 | 123 | 231 | 293 | 343 | 380 | 25.2 |
| 63年 | 14 | 1,386 | 61 | 141 | 187 | 316 | 343 | 338 | 24.6 |
| 平成元年 | 14 | 1,364 | 52 | 139 | 213 | 268 | 351 | 341 | 25.2 |
| 2年 | 14 | 1,319 | 59 | 129 | 196 | 288 | 293 | 354 | 26.6 |
| 4年 | 14 | 1,297 | 54 | 149 | 207 | 277 | 310 | 300 | 26.8 |
| 4年 | 14 | 1,285 | 54 | 146 | 213 | 271 | 296 | 305 | 26.8 |
措置率:園児の0~5歳児人口に対する割合
各年4月1日、児童数については管外受託児を含む。児童福祉課調べ
表32 保育園クラス別在籍児数 単位:人
| 区分 | 公私 | 定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高木保育園 | 公 | 100 | 4 | 14 | 14 | 19 | 19 | 20 | 90 |
| 向原保育園 | 公 | 122 | 9 | 15 | 18 | 20 | 24 | 23 | 109 |
| 狭山保育園 | 公 | 120 | 9 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 109 |
| れんげ保育園 | 私 | 170 | 8 | 15 | 19 | 42 | 38 | 38 | 160 |
| 南街保育園 | 私 | 124 | 6 | 15 | 22 | 18 | 19 | 16 | 96 |
| 大和南保育園 | 私 | 100 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 | 20 | 96 |
| 大和東保育園 | 私 | 97 | 0 | 7 | 13 | 18 | 17 | 21 | 76 |
| 紫水保育園 | 私 | 60 | 0 | 8 | 7 | 13 | 17 | 9 | 54 |
| 誠愛保育園 | 私 | 165 | 9 | 14 | 22 | 31 | 20 | 37 | 133 |
| 上北台こひつじ保育園 | 私 | 128 | 12 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | 114 |
| テマリ保育園 | 私 | 120 | 12 | 15 | 20 | 20 | 23 | 28 | 118 |
| 明徳保育園 | 私 | 78 | 6 | 10 | 13 | 18 | 19 | 7 | 73 |
| 立野保育園 | 私 | 80 | 3 | 7 | 14 | 17 | 21 | 18 | 80 |
| 谷里保育園 | 私 | 90 | 11 | 11 | 14 | 17 | 14 | 25 | 92 |
| 合計 | - | 1,554 | 98 | 174 | 232 | 293 | 294 | 309 | 1,400 |
資料:児童福祉課調べ 平成5年9月1日現在
《2》 学童保育所
学童保育所は各小学校区に1か所ずつ10施設あり、措置児童数には近年大きな変化はみられません。
表33 学童保育の状況
| 区分 | 施設数 (所) |
児童数(人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 昭和58年 | 9 | 345 | 182 | 163 |
| 59年 | 9 | 380 | 188 | 192 |
| 60年 | 10 | 375 | 184 | 191 |
| 61年 | 10 | 398 | 191 | 207 |
| 62年 | 10 | 378 | 182 | 196 |
| 63年 | 10 | 373 | 191 | 182 |
| 平成元年 | 10 | 378 | 181 | 197 |
| 2年 | 10 | 407 | 185 | 222 |
| 3年 | 10 | 393 | 192 | 201 |
| 4年 | 10 | 409 | 203 | 206 |
資料:統計東やまと 各年4月1日
表34 学童保育の利用状況
| 保育日数 (日) |
措置児童数 (人) |
保育総数 (人) |
出席延べ数 (人) |
出席率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 400 | 9,925 | 5,950 | 59.9 |
資料:児童福祉課調べ 平成5年4月現在
5 健康・保健事業の現状
本市の出生率は、近年人口干人に対し10程度で推移しており、東京都や全国の値よりも若干高くなっています。
また、死亡率は人口干人に対し4強で、これは東京都や全国の値よりも若干低くなっています。
主な死因は、東京都や全国と同じく、第1位が悪性新生物、第2位が心疾患、第3位が脳血管疾患で、いわゆる3大成人病が上位3位を占めています。
表35 出生率と死亡率
| 区分 | 出生率(人口千人対) | 死亡率(人口千人対) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大和市 | 東京都 | 全国 | 東大和市 | 東京都 | 全国 | |
| 昭和62年 | 10.8 | 10.1 | 11.1 | 4.3 | 5.4 | 6.2 |
| 63年 | 11.4 | 9.8 | 10.8 | 4.4 | 5.7 | 6.5 |
| 平成元年 | 10.3 | 8.9 | 10.2 | 4.3 | 5.7 | 6.4 |
| 2年 | 10.8 | 8.9 | 9.9 | 4.3 | 6.0 | 6.7 |
| 3年 | 10.4 | 8.7 | 9.9 | 4.7 | 5.9 | 6.7 |
| 4年 | 10.6 | 8.5 | 9.8 | 4.7 | 6.1 | 6.9 |
資料:東京都東村山保健所事業概要
表36 主な死因
| 区分 | 東大和市 | 都 | 全国 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 順位 | 順位 | ||||
| 悪性新生物 | 150.7 | 1 | 172.0 | 1 | 181.6 | 1 |
| 心疾患 | 91.2 | 2 | 116.6 | 2 | 137.1 | 2 |
| 脳血管疾患 | 60.8 | 3 | 82.9 | 3 | 96.2 | 3 |
| 肺炎及び気管支炎 | 47.6 | 4 | 57.8 | 4 | 62.0 | 4 |
| 自殺 | 21.2 | 5 | 15.0 | 6 | 16.1 | 7 |
| 不慮の事故及び有害作用 | 13.2 | 6 | 17.5 | 5 | 26.8 | 5 |
| 慢性肝疾患及び肝硬変 | 13.2 | 6 | 14.5 | 7 | 13.7 | 9 |
| 精神病無記載の老衰 | 10.6 | 8 | 8.9 | 9 | 18.8 | 6 |
| 腎炎・ネフローゼ等 | 6.6 | 9 | 12.3 | 8 | 13.8 | 8 |
| 高血圧疾患・喘息 | 4.0 | 10 | - | - | - | - |
| 糖尿病 | - | - | 7.6 | 10 | 7.8 | 10 |
注 値は人口10万対 資料:東京都東村山保健所事業概要 平成4年版
表37 主な保健・医療サービス
| 区分 | 事業名 | 事業内容 | 事業実績 平成5年度 |
|
|---|---|---|---|---|
|
母 子 保 健 事 業 |
予 防 接 種 |
予防接種 | 予防接種法に基づき急性灰白髄炎、三種混合(百日咳・ジフテリア・破傷風)、二種混合(ジフテリア・破傷風)、ジフテリア、風しん、麻しんを対象に接種 | 延べ 6,228人 |
| 臨時予防接種 | 予防接種法に基づき日本脳炎、インフルエンザを対象者に接種。 | 延べ 6,192人 | ||
| BCG予防接種 | 結核予防法に基づきツベルクリン反応が陰性の方に接種。 | 860人 | ||
|
教 育 |
離乳食・幼児食講習会 | 乳幼児をもつ母親等を対象に離乳食・幼児食講習会を開催。年16回。 | 403人 | |
| 母子講演会 | 乳幼児をもつ母親等を対象に子育て関する講演会を開催。年1回。 | 22人 | ||
| 栄養相談事後指導教室 | 栄養相談に応じた母親等を対象に栄養に関する事後相談の教室を開催。年1回。 | 20人 | ||
|
相 談 |
2か月保育相談 | 2か月児をもつ母親等を対象に育児等の相談を実施。年56回。 | 830人 | |
| 母子保健・栄養相談 | 育児や栄養等に関する相談を実施。月2回。 | 568人 | ||
| 妊婦保健相談 | 妊婦を対象に妊娠中の健康と安心して子どもを産むための相談を実施。 | 401人 | ||
|
検 診 |
1歳6か月児健康診査 | 1歳6か月児を対象に幼児の健康保持及び増進を図るため、健康診査(医科・歯科)を実施。2ヵ月に3回。 | 689人 | |
|
そ の 他 |
家庭訪問 | 乳幼児 妊婦・産婦等を対象に健康や育児等の相談・指導を実施。随時。 | 46人 | |
| 母子栄養食品支給 | 低所得者や低体重児に母体の健康保持や乳児の健全発達を図るために実施。随時。 | 1件 | ||
|
老 人 保 健 事 業 |
教 育 |
高血圧教室 | コレステロールや中性脂肪の高い方を対象に食生活の改善の方法に関する教室を開催。年2回。 | 延べ 261人 |
| さわやかスリム教室 | 肥満の方を対象に生活習慣や食生活の改善の方法に関する教室を開催。 | 延べ 88人 | ||
| はつらつ健康教室 | 運動不足や食生活の改善の必要のある方を対象に運動の実践や食生活の改善の方法に関する教室を開催。年2回。 | 延べ 266人 | ||
| 乳がん自己検査法講習会 | 乳がん自己検査方法についての講習会を開催。年2回。 | 37人 | ||
| 歯周病講演会 | 歯槽膿漏や歯肉炎等を予防し、健康な歯を保つために講演会を開催。年1回。 | 9人 | ||
| 栄養相談事後指導教室 | 栄養相談に応じた成人を対象に栄養に関する事後指導の教室を開催。年1回。 | 13人 | ||
|
相 談 |
成人保健・栄養相談 | 成人を対象に健康等に関する相談を実施。月1回2か所。 | 163人 | |
| 老人保健・栄養相談 | 老人を対象に健康等に関する相談を実施。月1回3か所。 | 382人 | ||
|
健 康 診 査 |
基本健康診査 | 誕生月健康診査... 63歳以上の市民、市内の医療機関で誕生月に受診。 |
3,220人 | |
| 成人健康診査... 30~62歳の市民、集団で保健センターで受診。 |
1,058人 | |||
| 訪問健康診査... 40歳以上のねたきりの市民を対象に訪問して健康診査を実施。9月。 |
51人 | |||
| がん検診 | 胃がん検診... 35歳以上の市民を対象に集団検診により実施。5月と8月と1月。 |
1,268人 | ||
| 子宮がん検診... 30歳以上の市民を対象に市内の医療機関で実施。5月と10月。 |
1,917人 | |||
| 肺がん検診... 40歳以上の市民を対象に集団検診により実施。5月と10月。 |
303人 | |||
| 乳がん検診... 35歳以上の市民を対象に市内の医療機関で実施。5月と11月。 |
775人 | |||
| 大腸がん検診... 40歳以上の市民を対象に市内の医療機関で実施。1月。 |
461人 | |||
| レントゲン撮影 | 結核予防法に基づくレントゲン撮影を集団検診により実施。2月と6月。 | 1,571人 | ||
| 機能訓練 | 40歳以上で心身の機能が低下している方に対して機能の維持回復を図るための訓練を実施。週2回。 | 延べ 800人 | ||
| 訪問指導 | 40歳以上で家庭においてねたきり状態、またはこれに準ずる状態にある方及びその家族に対して必要な保健指導を実施。随時。 | 延べ 1,596人 | ||
6 その他の現状
(1)難病
市単独事業である難病患者福祉手当に関する状況は、平成4年度実績で対象疾病が51、受給者が413人となっています。
(2)生活保護
生活保護受給世帯は、おおむね横ばい傾向で推移していますが、世帯類型別では高齢者世帯が微増、母子世帯・傷病・障害者世帯が微減の傾向にあります。
表38 難病患者福祉手当受給者数と疾病別内訳
| スモン | 2 | 肝硬変・ヘパトーム | 34 |
| ペーチェット病 | 7 | ウイリス輪閉そく症 | 2 |
| 重症筋無力症 | 6 | 点頭てんかん | 3 |
| 全身性エリテマトーデス | 17 | リピドーシス | 0 |
| 多発性硬化症 | 4 | 悪性高血圧(悪性腎硬化症) | 1 |
| 再生不良性貧血 | 5 | ネフローゼ症候群 | 22 |
| はん発性強皮症 | 5 | 後縦じん帯骨化症 | 9 |
| 皮膚筋炎・多発性筋炎 | 9 | ハンチントン舞踏病 | 1 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 2 | ウエゲナー肉芽腫症 | 0 |
| 突発性血小板性紫はん症 | 14 | 母斑症 | 1 |
| サルコイードシス | 5 | シェーグレン症候群 | 3 |
| 激症肝炎 | 0 | 多発性のう胞炎 | 0 |
| 高安病(大動脈炎症候群) | 1 | 膿胞性乾せん | 1 |
| せき髄小脳変性症 | 12 | ミオトニー症候群 | 0 |
| 悪性関節リュウマチ | 4 | 好酸球増多症候群 | 2 |
| 結筋性動脈周炎 | 1 | 強直性脊髄炎 | 0 |
| かいよう性大腸炎 | 12 | 重症急性すい炎 | 0 |
| ビュルガー病 | 9 | 先天性血液凝固因子欠乏症 | 1 |
| 突発性拡張型(うっ血型)心筋症 | 2 | 突発性門脈圧こう進症 | 1 |
| シャイ・ドレーガー症候群 | 0 | 広範脊柱管狭窄症 | 1 |
| 天ほうそう | 1 | 原発性胆汁性肝硬変 | 2 |
| クローン病 | 5 | 表皮ほう症(接合部型及び栄養障害型) | 0 |
| アミロイドーシス(原発性アミロイド症) | 0 | 進行性核上性麻痺 | 0 |
| 人工透析を必要とする腎不全 | 48 | 突発性大腿骨頭壊死症 | 0 |
| パーキソン病 | 34 | びまん性汎細気管支炎 | 1 |
| 慢性肝炎 | 122 | 合計 | 413 |
資料:社会福祉課調べ 平成4年度実績
表39 世帯類型別にみた被保護世帯の推移
| 区分 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
||
|
総 世 帯 |
高齢者世帯 | 72 | 17.87 | 86 | 19.82 | 92 | 20.18 |
| 母子世帯 | 87 | 21.59 | 98 | 22.58 | 106 | 23.25 | |
| 傷病・障害世帯 | 197 | 48.88 | 203 | 46.77 | 208 | 45.61 | |
| その他の世帯 | 47 | 11.66 | 47 | 10.83 | 50 | 10.96 | |
| 計 | 403 | 100.0 | 434 | 100.0 | 456 | 100.0 | |
| 区分 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
||
|
総 世 帯 |
高齢者世帯 | 102 | 22.72 | 99 | 22.50 | 94 | 22.33 |
| 母子世帯 | 102 | 22.72 | 101 | 22.95 | 109 | 25.89 | |
| 傷病・障害世帯 | 187 | 41.65 | 183 | 41.59 | 170 | 40.38 | |
| その他の世帯 | 58 | 12.92 | 57 | 12.95 | 48 | 11.40 | |
| 計 | 449 | 100.0 | 440 | 100.0 | 421 | 100.0 | |
| 区分 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
世帯数 (世帯) |
割合 (%) |
||
|
総 世 帯 |
高齢者世帯 | 101 | 23.49 | 100 | 29.94 | 115 | 29.56 | 128 | 33.33 |
| 母子世帯 | 105 | 24.42 | 88 | 21.94 | 68 | 17.48 | 65 | 16.93 | |
| 傷病・障害世帯 | 169 | 39.30 | 148 | 36.91 | 156 | 40.10 | 153 | 39.84 | |
| その他の世帯 | 55 | 12.79 | 65 | 16.21 | 50 | 12.86 | 38 | 9.90 | |
| 計 | 430 | 100.0 | 401 | 100.0 | 389 | 100.0 | 384 | 100.0 | |
資料:社会福祉課調べ 世帯数は年度内の月平均
表40 生活保護率の推移(年度平均) 単位:対人口千人
| 区分 | 東大和市 | 東京都 | 全国 |
|---|---|---|---|
|
60年 |
13.9 | 11.4 | 11.8 |
|
61年 |
13.6 | 10.9 | 11.1 |
|
62年 |
13.0 | 10.3 | 10.1 |
|
63年 |
12.1 | 9.6 | 9.6 |
|
平成元年 |
11.6 | 8.9 | 8.9 |
|
2年 |
10.1 | 8.2 | 8.2 |
|
3年 |
9.4 | 7.6 | 7.6 |
|
4年 |
8.8 | 7.3 | 7.2 |
資料:社会福祉課調べ
7 人口等の将来推計
(1)将来人口の推計
目標年度における人口等の予測に当たっては、東大和市第二次基本計画(以下では基本計画と略す)の推計を利用することとします。
表41 基本計画人口推計 単位:人
| 区分 | 平成2年 (1990年) |
年間平均 増加率(%) 90~95年 |
平成7年 (1995年) |
年間平均 増加率(%) 95~2000年 |
平成12年 (2000年) |
年間平均 増加率(%) 90~2000年 |
平成13年 (2001年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口 | 74,338 | 1.08 | 78,367 | 1.44 | 84,013 | 1.30 | 85,061 |
| 0~14歳 | 13,808 | -1.32 | 12,900 | 0.48 | 13,211 | -0.43 | 13,344 |
| 対総人口比(%) | 18.57 | - | 16.46 | - | 15.72 | - | 15.69 |
| 15~64歳 | 55,166 | 1.09 | 58,162 | 0.75 | 60,329 | 0.94 | 60,507 |
| 対総人口比(%) | 74.21 | - | 74.22 | - | 71.81 | - | 71.13 |
| 65歳以上 | 5,364 | 7.24 | 7,305 | 8.67 | 10,473 | 9.52 | 11,210 |
| 対総人口比(%) | 7.22 | - | 9.32 | - | 12.47 | - | 13.18 |
| 75歳以上 | 2,037 | 6.02 | 2,650 | 6.07 | 3,454 | 6.96 | 3,714 |
| 対総人口比(%) | 2.74 | - | 3.38 | - | 4.11 | - | 4.37 |
資料:住民基本台帳 各年1月1日
(2)要援護高齢者の推計
ねたきり高齢者等の要援護高齢者の推計に当たっては、それぞれ次の調査結果等を参考にしました。
《1》ねたきり高齢者
「東京者社会福祉基礎調査(平成2年度)」
在宅のねたきり高齢者については、本調査の出現率3.6%を利用して推計しました。
※「東京都社会福祉基礎調査(平成2年度)」の要介護高齢者の出現率
| ねたきリ等の高齢者 | 3.62% | |
| 内 訳 |
ねたきり高齢者 | 1.42% |
| ねたきりに近い高齢者 | 2.20% | |
| 比較的重い障害のある高齢者 | 2.65% | |
| 軽い障害のある高齢者 | 18.01% | |
| 障害のない高齢者 | 72.13% | |
《2》痴呆性高齢者
厚生省通知「老人保健福祉計画策定に当たっての痴呆性老人の把握方法等について」(平成4年2月25日老人福祉計画課長・老人保健課長通知)
在宅の痴呆性高齢者総数及びこの内のねたきりでない要介護の痴呆性高齢者については、本通知の出現率を利用して推計しました。
《3》虚弱高齢者
「東大和市高齢者実態調査(平成2年度)」
虚弱高齢者については、本調査で算出された出現率を利用して推計しました。
※痴呆性高齢者の算出式
表42 在宅痴呆性高齢者の出現率 単位:%
| 区分 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 65~69歳 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
| 70~74歳 | 3.0 | 2.5 | 2.7 |
| 75~79歳 | 5.3 | 5.1 | 5.2 |
| 80~84歳 | 9.7 | 11.8 | 11.0 |
| 85歳~ | 16.7 | 22.9 | 20.9 |
| 合計 | 4.4 | 5.1 | 4.8 |
表43 在宅痴呆性高齢者の出現数 単位:人
| 区分 | 平成4年度 平成5年1月1日 |
平成11年度 平成12年1月1日 |
平成12年度 平成13年1月1日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 男 | 65~69歳 | 19.8 | 34.8 | 36.2 |
| 70~74歳 | 18.4 | 41.7 | 45.6 | |
| 75~79歳 | 26.4 | 36.4 | 41.8 | |
| 80~84歳 | 27.1 | 33.5 | 35.7 | |
| 85歳~ | 24.7 | 40.9 | 42.1 | |
| 合計 | 116.4 | 187.2 | 201.4 | |
| 女 | 65~69歳 | 10.5 | 16.5 | 17.7 |
| 70~74歳 | 23.0 | 34.8 | 37.7 | |
| 75~79歳 | 38.0 | 49.2 | 52.5 | |
| 80~84歳 | 54.6 | 76.1 | 79.2 | |
| 85歳~ | 72.1 | 130.1 | 138.3 | |
|
合計 |
198.3 | 306.7 | 325.4 | |
|
総 数 |
65~69歳 | 30.3 | 51.3 | 53.8 |
| 70~74歳 | 41.4 | 46.5 | 83.3 | |
| 75~79歳 | 64.4 | 85.6 | 94.3 | |
| 80~84歳 | 81.7 | 109.6 | 114.9 | |
| 85歳~ | 96.9 | 171.0 | 180.4 | |
|
合計 |
314.7 | 493.9 | 526.7 | |
表44 要介護の在宅痴呆性高齢者 (在宅痴呆性高齢者の15%) 単位:人
| 区分 | 平成4年度 平成5年1月1日 |
平成11年度 平成12年1月1日 |
平成12年度 平成13年1月1日 |
|
|---|---|---|---|---|
| 男 | 17.5 | 28.1 | 30.2 | |
| 女 | 29.7 | 46.0 | 48.8 | |
| 合計 | 47.2 | 74.1 | 79.0 | |
※虚弱高齢者の算出式
「東大和市高齢者実態調査(平成2年度)」による健康状態、身体の不自由さ等についての設問の回答状況から、虚弱高齢者の出現率を次の通り算出しました。
なお、本調査では、「一般世帯」は抽出で、その他の「ひとり暮らし高齢者」「高齢者」「ねたきり」の各世帯については全世帯を対象にしたことから、高齢者全体における出現率の算出については、抽出率及び回収率を一般世帯と同様になるよう調整し、次の結果を得ました。
単位:人
| 区分 | 総数 | 元気であり 外出している。 A |
隣近所までは 外出している。 B |
自宅の敷地から 外へ出ない。 C |
食事とトイレ 以外は寝ている。 D |
ね た き り で あ る E |
そ の 他 F |
無 回 答 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ひとリ暮らし 高齢者 |
64 | 44 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 高齢者世帯 | 63 | 48 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 一般世帯 | 775 | 551 | 115 | 25 | 8 | 4 | 31 | 41 |
| ねたきり世帯 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 総数 | 923 | 643 | 138 | 32 | 16 | 14 | 33 | 47 |
虚弱高齢者の出現率
| 区分 | 該当項目 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 虚弱でない高齢者 | A+B-Bの一部 | 762 | 90.4 |
| 虚弱高齢者 | Bの一部+C | 51 | 6.0 |
| ねたきり高齢者 | D+E | 30 | 3.6 |
| 総数 | 843 | 100.0 | |
Bの「隣近所までは外出している」の138人については、通院、受診の有無、身体の不自由の有無及び内容を再点検し、このうち19人を虚弱として判定しました。
この結果、虚弱高齢者は、総数から「その他」と「無回答」を除去した843人のうちの51人で、割合は6.0%となります。
(3)障害者数の推計
目標年度における身体障害者手帳及び愛の手帳所持者数については、平成5年6月1日現在における各所持者の年齢5歳級別人口(平成5年4月1日現在)に対する割合を算出し、この割合を目標年度の年齢5歳級別人口に乗じて推計しました。
《1》身体障害者手帳所持者 単位:人
| 区分 | 平成5年度 平成5年6月1日 実数 |
平成11年度 平成12年1月1日 (推計値) |
平成12年度 平成13年1月1日 (推計値) |
|---|---|---|---|
| 0 ~ 4歳 | 7 | 8 | 8 |
| 5 ~ 9歳 | 15 | 15 | 15 |
| 10~14歳 | 16 | 16 | 16 |
| 15~19歳 | 26 | 22 | 22 |
| 20~24歳 | 46 | 37 | 37 |
| 25~29歳 | 45 | 54 | 52 |
| 30~34歳 | 41 | 60 | 62 |
| 35~39歳 | 46 | 61 | 63 |
| 40~44歳 | 59 | 49 | 51 |
| 45~49歳 | 97 | 86 | 85 |
| 50~54歳 | 136 | 148 | 144 |
| 55~59歳 | 199 | 235 | 234 |
| 60~64歳 | 200 | 267 | 277 |
| 65~69歳 | 181 | 295 | 310 |
| 70~74歳 | 107 | 202 | 221 |
| 75~79歳 | 123 | 160 | 178 |
| 80~84歳 | 77 | 101 | 106 |
| 85~89歳 | 50 | 84 | 88 |
| 90歳以上 | 19 | 34 | 36 |
| 計 | 1,490 | 1,934 | 2,005 |
| 0 ~14歳 | 38 | 39 | 39 |
| 15~64歳 | 895 | 1,019 | 1,027 |
| 65歳以上 | 557 | 876 | 939 |
| 15~49歳 | 360 | 369 | 372 |
| 50~64歳 | 535 | 650 | 655 |
《2》愛の手帳所持者
| 区分 | 平成5年度 平成5年6月1日 実数 |
平成11年度 平成12年1月1日 (推計値) |
平成12年度 平成13年1月1日 (推計値) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(人) | 障害者(人) | 割合(%) | 総人口(人) | 割合(%) | 総人口(人) | 割合(%) | |
| 0 ~ 4 | 3,929 | 3 | 0.076 | 4,488 | 3 | 4,544 | 3 |
| 5 ~ 9 | 4,170 | 16 | 0.384 | 4,236 | 16 | 4,338 | 17 |
| 10~14 | 4,572 | 15 | 0.328 | 4,487 | 15 | 4,462 | 15 |
| 15~19 | 5,691 | 40 | 0.671 | 4,984 | 33 | 4,916 | 33 |
| 20~24 | 7,135 | 50 | 0.701 | 5,880 | 41 | 5,749 | 40 |
| 25~29 | 6,170 | 24 | 0.389 | 7,397 | 29 | 7,135 | 28 |
| 30~34 | 4,906 | 24 | 0.489 | 7,049 | 34 | 7,273 | 36 |
| 35~39 | 4,507 | 15 | 0.333 | 5,987 | 20 | 6,278 | 21 |
| 40~44 | 6,069 | 11 | 0.181 | 5,031 | 9 | 5,232 | 9 |
| 45~49 | 6,178 | 7 | 0.113 | 5,510 | 6 | 5,407 | 6 |
| 50~54 | 6,008 | 4 | 0.067 | 6,552 | 4 | 6,364 | 4 |
| 55~59 | 5,523 | 3 | 0.054 | 6,529 | 4 | 6,531 | 4 |
| 60~64 | 4,004 | 3 | 0.075 | 5,410 | 4 | 5,622 | 4 |
| 65~69 | 2,625 | 2 | 0.076 | 4,236 | 3 | 4,468 | 3 |
| 70~74 | 1,563 | 1 | 0.064 | 2,783 | 2 | 3,028 | 2 |
| 75~ | 2,502 | 1 | 0.040 | 3,454 | 1 | 3,714 | 1 |
| 総数 | 75,822 | 219 | 0.289 | 84,013 | 224 | 85,061 | 226 |
平成5年度の総人口は平成5年4月1日現在
2 地域福祉計画の策定経過
1 東大和市地域福祉計画策定委員会設置要綱
(設置)
| 第1条 | 東大和市地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、東大和市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務)
| 第2条 | 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討し、その結果を市長に報告する。 (1)計画の策定に関すること。 (2)その他市長が必要と認める事項。 |
(組織)
| 第3条 | 委員会は、25名以内の委員をもって組織する。 |
(委員)
| 第4条 | 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。 |
| (1)学識経験者 (2)東大和市医師会の代表者 (3)東大和市歯科医師会の代表者 (4)東京都東村山保健所の代表者 (5)福祉団体関係者 (6)福祉施設関係者 (7)公募による一般市民 (8)教育関係者 (9)東大和市職員 |
3名以内 1名 1名 1名 12名以内 1名 3名以内 1名 2名以内 |
(委員の任期)
| 第5条 | 委員の任期は、第2条の報告をもって終了するものとし、委員に事故あるとき又は欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会長及び副会長)
| 第6条 | 委員会に会長及び副会長を置き、その選任方法は、委員の互選による。 2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 |
(会議)
| 第7条 | 委員会の会議は、会長が招集する。 2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
(専門委員)
| 第8条 | 委員会に、専門的事項について調査及び検討するための専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、委員会の委員のうちから委員会で決定された人数の範囲内で、会長が指名する。 3 専門委員会議に委員長を置き、その選任方法は、専門委員の互選による。 4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する専門委員がその職務を代理する。 5 専門委員会議は、委員長が招集する。 6 専門委員は、調査及び検討した結果を委員会に報告する。 |
(意見等の聴取)
| 第9条 | 委員会及び専門委員会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴取することができる。 |
(庶務)
| 第10条 | 委員会及び専門委員会議の庶務は、福祉事務所において処理する。 |
(委任)
| 第11条 | この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別こ定める。 |
付則
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
2 策定経過
(1)地域福祉計画策定委員会
| 回 | 開催日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 4.12.1 | ・地域福祉計画策定委員会の運営について ・社会福祉8法改正のポイントについて ・東京都地域福祉推進計画について |
| 第2回 | 5.1.27 | ・東大和市の福祉関連事業の現状について ・東大和市地域高齢者住宅計画について |
| 第3回 | 5.2.18 | ・東大和市地域福祉計画市民意識・実態調査の単純集計結果について |
| 第4回 | 5.3.15 | ・各委員会の自由発言 |
| 第5回 | 5.4.21 | ・福祉関連事業から見る主な課題について ・専門委員会の設置と今後の福祉計画の進め方につい ・住民懇談会について |
| 第6回 | 5.7.13 | ・主な課題の整理について ・地域福祉計画の基本データについて ・地域福祉計画の基本的な考え方について ・起草委員会について ・今後の日程について |
| 第7回 | 5.9.1 | ・高齢者地域自立生活支援サービスについて ・障害者地域自立生活支援サービスについて ・家族・児童地域生活支援サービスについて ・市民の集いの運営について |
| 第8回 | 5.9.25 | ・東大和市地域福祉計画施策の大綱案について ・東大和市地域福祉計画報告書の全体構成案について ・東大和市における地域福祉推進の基本的考え方について ・市民の集いの運営について |
| 第9回 | 5.11.8 | ・東大和市地域福祉計画の中間報告案の検討について ・基本データによる現況と課題の整理について |
| 第10回 | 5.12.13 | ・東大和市地域福祉計画の中間報告案の検討について |
| 第11回 | 6.1.11 | ・東大和市地域福祉計画の中間報告案について |
| 第12回 | 6.3.2 | ・中間報告書に対する市民の意見について ・計画の愛称について ・東大和市地域福祉計画の最終報告案について ・第2回市民の集いの運営について |
(2)専門委員会
| 回 | 開催日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | 5.6.5 | ・第二次基本計画について ・東大和市地域福祉計画市民意識・実態調査報告書について ・福祉関係団体のヒアリング結果について ・東大和市地域福祉計画の基礎数値について ・今後の日程について |
| 第2回 | 5.6.29 | ・東大和市地域福祉計画の目的、策定作業の進め方について ・基礎数値と課題について ・実施計画について ・みのり福祉園の将来構想について |
| 第3回 | 5.7.23 | ・基本データの追加について ・主な課題の整理について ・地域福祉計画の大綱と体系について |
| 第4回 | 5.8.24 | ・高齢者地域自立生活支援サービスシステムについて ・障害者地域自立生活支援サービスシステムについて ・家族・児童地域生活支援サービスシステムについて ・市民の集いの運営について |
| 第5回 | 5.10.25 | ・市民の集いの開催結果について ・東大和市地域福祉計画報告書の全体構成案について ・東大和市地域福祉計画報告書の大綱と体系について ・現況と課題の整理について |
(3)地区別懇談会
| 地区 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 南街・中央 | 5.4.17 | 市役所 |
| 桜ヶ丘 | 5.5.22 | 桜ヶ丘市民センター |
| 上北台・立野 | 5.5.22 | 上北台市民センター |
| 狭山・清水 | 5.5.29 | 狭山公民館 |
| 清原・新堀 | 5.5.29 | 新堀地区会館 |
| 奈良橋・湖畔・高木 | 5.6.5 | 奈良橋市民センター |
| 芋窪・蔵敷 | 5.6.5 | 蔵敷公民館 |
| 仲原・向原 | 5.6.5 | 向原老人福祉会館 |
(4)市民の集い
| 回 | 開催日 | 会場 |
|---|---|---|
| 第1回 | 5.9.25 | 奈良橋市民センター |
| 第2回 | 6.3.12 | 奈良橋市民センター |
(5)策定委員会の報告
平成6年1月26日 中間報告
平成6年3月12日 最終報告
(6)計画決定
平成6年3月30日
3 報告書(鑑)
東大和市市長
中澤 重一 様
会長 大橋 謙策
東大和市地域福祉計画報告について(報告)
平成4年12月から12回にわたる公開審議、平成6年1月の中間報告書の提出、その後の市民の意見聴衆などを踏まえ、ここに東大和市地域福祉計画の内容をまとめましたので、御報告いたします。
報告にあたり本委員会は、東大和市並びに東大和市民がともに手を携えて、この「みんなの和21ブラン」の実現に努め、21世紀にこの東大和市が「活力ある保健福祉文化のまち」となっていることを、切に期待するものです。
4 委員名簿
(1)策定委員会
| 選出区分 | 氏名 | 選出区分 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 学識経験者 | 大橋 謙策 | 福祉団体関係 | 鈴木 宣子 |
| 学識経験者 | 坂田 周一 | 福祉団体関係 | 小松 富美恵 |
| 学識経験者 | 渡辺 洋一 | 福祉団体関係 | 宇嶋 正春 |
| 医師会 | 高橋 英樹 | 福祉団体関係 | 坂牧 幸子 |
| 歯科医師会 | 片山 均 | 福祉団体関係 | 関田 勝蔵 |
| 保健所 | 上木 隆人 | 福祉団体関係 | 足利 正哲 |
| 福祉団体関係 | 尾又 一夫 | 一般市民 | 松尾 泉 |
| 福祉団体関係 | 佐藤 勲 | 一般市民 | 斎藤 一男 |
| 福祉団体関係 | 山嶋 浩 | 一般市民 | 最上 キクエ |
| 福祉団体関係 | 高橋 澄子 | 教育関係者 | 門屋 信譽 |
| 福祉団体関係 | 渡邊 辰男 | 市職員 | 内野 敏光 |
| 福祉団体関係 | 小須田 光子 | 市職員 | 武智 健治 |
| 福祉団体関係 | 槐 しげみ | - | |
(会長~大橋 謙策、副会長~鈴木 宣子)
順不同、敬称略
(2)専門委員会
| 選出区分 | 氏名 |
|---|---|
| 学識経験者 | 大橋 謙策 |
| 学識経験者 | 坂田 周一 |
| 学識経験者 | 渡辺 洋一 |
| 福祉団体関係 | 鈴木 宣子 |
順不同、敬称略
主題:
みんなの和21プラン
-東大和市地域福祉計画-
103頁~終頁
発行者:
東大和市
発行年月日:
1994.3
文献に関する問い合わせ先:
東大和市福祉部
東京都東大和市中央3丁目930番地
電話 0425(63)2111(代)
