松茂町障害者計画
No.2
―あなたとともに―
平成10年3月
松茂町
4-3 雇用・就業―社会的自立のために
<基本目標>
障害者が適性と能力に応じた職業に就き、社会経済活動に参加し、自立した生活をおくることができるよう、就業の場、雇用機会を確保します。
適性と能力に応じた就業のために、事業所への障害者雇用の理解、職場での障害者に対する理解を求めるとともに、障害者への職業相談、職業訓練の充実など、雇用の促進を図ります。また、東部第1サブ障害者保健福祉圏域での連携のもとに、小規模作業所、障害者の店づくりなど、福祉的就労の場づくりを促進します。
雇用・就業
- 職業能力の開発
- 雇用の促進と安定
- 福祉的就労の促進
<主要施策>
1 職業能力の開発
障害者の就業や職業的自立を促進するため、障害者の能力や障害の状況に応じた幅広い職業訓練の機会が必要です。徳島障害者職業センター、国立職業リハビリテーションセンター、徳島県職業能力開発校などと連携し、障害者への相談・情報提供体制を充実するよう努力します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 障害者の職業能力開発施設等との連携 (国・県・町) |
心身障害者職業センターや県外の障害者職業能力開発校、国立職業リハビリテーションセンター等の職業能力開発関連施設との連携を密にし、障害者への相談、情報提供を行うことを検討します。 |
| 2 精神障害者の社会適応訓練制度の促進 (県・町) |
精神障害者の就労を促進するため、通院患者リハビリテーション事業(職親による社会適応訓練)の周知を図り、事業者の協力を要請します。 |
| 3 「障害者雇用支援センター」の整備 (国、県、広域) |
関係市町村が連携し、就労の困難な障害者や就労定着の困難な障害者に対し、職業的自立を目指して、福祉部門と雇用部門の連携による地域での障害者への職業リハビリテーションの提供と障害者を雇用する事業主、障害者雇用支援者への助言、援助等を行う「障害者雇用支援センター」を委託することを検討します。 |
2 雇用の促進と安定
公共職業安定所等、国・県や関係機関と連携し、障害者への職業紹介・相談や事業者への障害者求職情報の提供などを行い、障害者の就業を支援します。
平成10年7月から、障害者法定雇用率が1.8%となることから、公共機関が率先して障害者雇用を推進するとともに、事業主への障害者雇用について啓発活動を行います。また、知的障害者、精神障害回復者などへの職業リハビリテーションの提供により雇用の促進に努力します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 障害者雇用の啓発活動の推進 (国・県・町) |
「障害者雇用促進月間」(9月)などを中心に、町内の事業者への障害者雇用の理解と積極的な協力を要請します。 |
| 2 障害者の就労支援 (県・町) |
公共職業安定所などの関係機関と連携し、障害者への職業紹介・相談、事業者への障害者の求職情報の提供などを促進し、障害者の就業を支援します。 |
| 3 役場での障害者雇用の推進 (町) |
ゴミ収集業務(委託)、公共施設の清掃・植栽の管理等で、障害者の雇用を推進するとともに、障害者の就労可能な分野への積極的な障害者雇用を図ります。 |
3 福祉的就労の促進
一般的就労が困難な障害者が、身近な地域において、生活指導や職業訓練、就労の場が確保できるよう、東部第1サブ障害保健福祉圏域の連携による授産施設、小規模作業所などの整備・充実を図るとともに、障害者団体等による共同作業所の整備、障害者の店づくりなどを支援します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 授産施設の利用促進 (圏域、町) |
障害者が身近な施設で、生活訓練、職業訓練の場が確保できるよう、鳴門授産センターなどの授産施設の利用を促進します。 |
| 2 小規模作業所の連携、相互利用の促進 (県、圏域、町) |
東部第1サブ障害保健福祉圏域で連携し、小規模作業所の整備を図るとともに、障害者の能力・適性・要望に応じ、相互利用を促進します。 |
| 3 「小規模作業所運営事業」の推進 (県、町、障害者団体等) |
障害者の自立訓練と交流の場として、「小規模作業所運営事業」の実施を検討します。 |
| 4 精神障害者の就労の支援 (保健所、町) |
精神障害者の生活訓練、職業訓練の場が確保できるよう、鳴門保健所精神障害者家族会「わかめ家族会」が運営する共同作業所「ぽてとくらぶ」への参加の促進、活動の支援を図ります。 |
4-4 保健・医療―疾病の予防と社会復帰のために
<基本目標>
障害の原因として、疾病、交通事故、労働災害、高齢化、社会構造の複雑化などの後天的要因が大きな比重を占めています。疾病の予防・早期発見、早期治療、機能回復のため、保健事業の拠点となる保健センターの整備により、保健・医療事業を充実するとともに、保健所と連携して、精神障害者、難病患者への保健・医療の充実を図ります。
保健・医療
- 保健センターの整備
- 疾病の予防・早期発見体制の確立
- 早期療育体制の確立
- 医療・機能回復訓練の充実
- 精神保健対策の充実
- 特定疾患対策の充実
<主要施策>
1 保健センターの整備
保健事業の拠点施設であり、障害者・ボランティアの交流の場ともなる保健センターの整備を推進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 保健センターの整備推進 (町) |
障害者をはじめ、住民の健康増進を図るため、保健事業、在宅介護支援センター機能、交流機能等のある保健センターを整備します。 |
2 疾病の予防と早期発見体制の確立
疾病の予防と早期発見のために保健事業の充実により、乳幼児期から高齢期までそれぞれのライフステージに対応する一貫した保健サービスを提供するとともに、保健所、医療機関などの関連機関との連携による各種健康診査、相談事業、事後指導の充実に努めます。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 出産・育児知識の普及 (町) |
保健と教育の連携による思春期保健対策の充実に努めるとともに、妊娠・出産・育児についての不安解消と正しい知識の普及のために、パンフレット、母子健康手帳の交付等による情報提供、母親学級などの講座・学級の充実、妊婦・育児相談、電話相談など、母子保健事業の充実を図ります。 |
| 2 乳幼児期における疾病の予防・早期発見 (町) |
乳幼児の成長・発達にあわせた各種健康診査を充実し、乳幼児期における疾病の予防・早期発見に努めます。また、発達の遅れ、疾病や障害のあることが疑われる乳幼児については、保健婦による訪問指導を充実し、保健所・児童相談所など関係機関との連絡・調整により、早期の治療・療育に結びつけるように努めます。 |
| 3 生活習慣病の予防・早期発見の促進 (町) |
壮年期、高齢期に、疾病による障害の発生が多く見られる中で、健康管理への指導、日常生活に対する相談・指導を充実するため、健康診査受診率の向上に努めます。また、疾病や早期発見による後遺症の予防に努めます。 |
| 4 在宅療養への支援 (町) |
在宅のねたきり者、身体障害者への訪問指導により、療養指導、介護者の健康管理指導を行うとともに、必要に応じた保健・福祉サービスの連絡・調整を行います。 |
| 5 脳卒中ケアシステムの充実 (町等) |
脳卒中後遺症などによる障害が固定化する前に、適切な指導や機能訓練などを呼びかける脳卒中情報システムの普及を医療機関との連携などにより促進します。 |
3 早期療育体制の確立
障害の実態に応じた早期療育が適切に一貫して提供できるよう、身近で利用しやすい相談体制の整備、療育の場の確保を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 相談機能の充実 (町) |
発達の遅れや障害のあることが疑われる子ども、育児に不安をもつ親などへの相談・指導体制を充実し、障害の理解による不安の解消を図るとともに、家庭療育に関する技術的な相談・指導と、的確な情報提供を行います。また、障害の実態に応じた適切な相談・指導と療育サービスの提供ができるよう、医療機関、福祉施設、児童相談所など、関係機関との連携を強化します。 |
| 2 子育て教室(仮称)の充実 (町) |
乳幼児健康診査の結果、経過観察が必要な乳幼児を対象に、集団での遊びを通じて、定期的・継続的な観察を行うとともに保護者の相談に応じる「プレ療育」の場として、子育て教室(仮称)の整備を検討します。 |
| 3 療育体制の充実 (町) |
保育所や子育て教室と医療機関、保健所、児童相談所など関係機関との連携を強化し、障害児の把握と一人ひとりの障害にあった保育や指導体制づくりを進めるなど、療育体制の充実を図ります。 |
4 医療・機能回復訓練の充実
障害者が、疾病や障害の実態にあった適切な治療やリハビリテーションを受けられるよう、保健センター、医療施設の整備・充実に努めるとともに、緊急事態に対応できる救急体制を充実します。また、重度心身障害者等医療費助成事業など、医療費公費負担制度の継続を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 医療体制の整備 (町等) |
障害の実態にあった治療、リハビリテーションなどが適切に受けられるよう、医院、専門病院など、医療機関の連携を強化するとともに、救急医療体制を充実します。 |
| 2 心身の機能の維持・回復訓練・指導の充実 (町等) |
障害の軽減、心身機能の維持・回復を促進するため、機能回復訓練の実施や継続的な訪問指導を行います。 福祉との連携によりデイサービス、デイケアの活用とも合わせ、相談・指導を充実します。 |
| 3 訪問看護サービスの実施 (町等) |
重度の障害者や寝たきりの高齢者など、通院が困難な患者に対する医療提供として、広域で調整しながら、訪問看護サービスの実施を図ります。 |
| 4 医療費公費負担制度の継続 (県、町) |
重度障害者の健康管理と患者家族の医療費負担の軽減を図るため、重度心身障害者等医療費助成事業など医療費の公費負担制度を引き続き実施します |
5 精神保健対策の充実
精神障害者への適正な医療の確保とともに、福祉分野との連携による精神障害者の社会復帰の促進、自立、社会経済活動の促進・支援などを図ります。また、保健所と連携して、精神保健に関する正しい知識の普及・啓発を進め、心の健康づくりを推進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 精神保健対策の充実 (保健所・町) |
保健所と連携し、住民への精神保健に関する正しい知識の啓発、精神保健相談など、心の健康保持に関する事業の推進に努めます。 |
| 2 精神保健に関するサービスの充実 (保健所・町) |
保健所と連携し、精神障害者への保健婦による相談・家庭訪問、精神障害者保健福祉手帳の交付などの精神保健に関するサービスについて、身近な相談窓口として、充実を図ります。 |
| 3 精神障害者への保健・医療の充実 (保健所・町) |
保健所との連携を図りながら、措置入院、医療保護入院、通院医療費など、医療費の公費負担を継続して実施し、地域での適切な医療の機会の提供と精神病院入院患者への適切な処遇の確保が図られるよう努めます。 |
| 4 精神障害者の社会復帰の促進 (保健所・町等) |
保健所、周辺市町の関係機関、地域との連携により、社会復帰を目指す精神障害者への健康教育・相談事業の充実、デイケア事業(うしお会)、職親制度、精神障害者社会復帰施設運営事業(生活訓練施設)、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)などの推進が図られるよう努めます。 |
6 特定疾患対策の充実
公費負担の対象となる特定疾患治療研究事業対象者に対し、保健所、町の福祉部門との連携による相談体制を充実します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 特定疾患対策の充実 (保健所・町) |
保健所と連携し、住民への特定疾患に関する知識の啓発、相談、情報提供などが図られるよう努めます。 |
| 2 特定疾患患者へのサービスの充実 (保健所・町) |
保健所と連携し、特定疾患患者への医療相談、保健婦による相談・家庭訪問、特定疾患公費負担申請などの特定疾患に関するサービスについて、身近な相談窓口として、充実を図ります。 |
| 3 福祉との連携による相談体制の強化 (町) |
重症の特定疾患患者に対し、他の障害者と同等の介護サービスが受けられるよう、福祉部門との連携によるホームヘルプサービス、ショートステイの実施が図られるよう、相談体制の充実に努めます。 |
4-5 福祉―安心と自立した生活のために
<基本目標>
障害者が、地域社会の一員として安心して暮らせるまちづくりが望まれています。障害者の自立した生活を実現するために、在宅福祉サービスや施設福祉サービスの充実を図ります。
福祉
- 総合相談体制の充実
- 在宅福祉サービスの充実
- 施設福祉サービスの充実
- 経済的支援の充実
- 関連各課・障害保健福祉圏域の連携による施策推進
<主要施策>
1 総合相談体制の充実
サービスを必要とする障害者や家族が、保健・医療・福祉サービスについて、気軽に相談でき、迅速にサービスを受けられるよう、情報提供体制を整備するとともに、県、東部第1サブ障害保健福祉圏域の周辺市町による「生活支援事業」の推進を図るなど、各関係機関との密接な連携による総合的な相談体制を充実します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 相談体制の充実 (町、社協等) |
町民課、健康福祉課、社会福祉協議会、保健所など関係機関・団体との連携を強化し、相談・情報提供からサービスの提供まで一貫して相談に応じる障害者相談体制を促進します。また、匿名による相談にも対応できるよう、専用電話相談の実施を検討します。 |
| 2 総合相談窓口の設置 (町、社協等) | 障害者に関する相談・情報提供からサービスの提供まで総合的な相談に応じる窓口の設置を検討します。 |
| 3 地域での相談窓口の充実 (町・社協) |
社会福祉協議会、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生・児童委員など、地域の相談窓口で障害者や家族が気軽に相談し、的確なアドバイスが受けられるよう、担当者の研修の充実、福祉情報体制の整備などに努めます。 |
| 4 情報提供の拡充 (町・社協)。 |
障害者福祉事業紹介のパンフレットの充実を図るとともに、障害の実態にあった多様な情報提供として、「声の広報」づくり、点字パンフレット、主要施設のFAX番号帳の作成とともに、情報提供手段として、ホームページの活用等を検討します。 |
2 在宅福祉サービスの充実
障害者や難病者が自宅や地域で安心して生活できるよう、介護サービスを推進するとともに、補装具助成、日常生活用具給付・貸与など、自立した生活支援のための在宅福祉サービスの充実に努めます。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 ホームヘルプサービス事業の拡充 (町、社協) |
日常生活に支障のある重度心身障害者や家族が、介護、援助を必要とする場合、ホームヘルパーを派遣し、身体介護や家事援助等を行います。今後、難病患者へのサービス提供を実施するとともに、精神障害者に対しても、前向きに検討します。また、ニーズの動向に対応して、早朝・夜間を含む巡回型サービスの実施を検討します。 |
| 2 ショートステイ事業の実施 (国、県、町、圏域) |
在宅の重度身体障害者の介護者が社会的・私的な理由により、在宅介護ができない場合の短期入所事業を引き続き実施します。今後、利用者の増加などに対応するために、社会福祉法人への委託実施を検討します。 |
| 3 身体障害者デイサービス事業の実施 (国、県、町、圏域) |
障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上を図るため、通所による入浴、機能訓練、創作的活動などのデイサービスの実施については、東部第1サブ障害保健福祉圏域内の共同実施を図ります。 |
| 4 心身障害児通園事業の実施 (国、県、町、社会福祉法人等) |
通園および集団での指導が可能な障害児を対象に、日常生活における基本動作の指導、集団生活への適応訓練を行う「心身障害児通園事業」の、社会福祉法人への委託実施を検討します。 |
| 5 「障害者生活支援事業」の検討 (県、町、圏域) |
在宅の障害者や介護者の地域での生活支援や障害者自身の自立、社会参加を促進するため、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談、情報提供等のサービスを行う「障害者生活支援事業」について、他市町村との共同実施を検討します。 |
| 6 精神障害者地域生活支援センター「虹の里」の利用促進・支援 (町、広域) |
東部第1サブ障害保健福祉圏域の調整により、地域で生活する精神障害者を対象に、日常生活への支援、相談・助言・指導、地域交流生活情報の提供を行う、精神障害者地域生活支援センター「虹の里」の利用を促進します。 |
| 7 重度身体障害者日常生活用具給付等事業の充実 (国、町) |
在宅の重度障害者が日常生活を営むための用具を給付する重度身体障害者日常生活用具給付等事業の充実を図ります。 |
| 8 補装具の給付 (国、県、町) |
身体障害者の機能障害を補う補装具の交付、修理を助成する補装具交付(修理)の制度の利用促進を図ります。 |
3 施設福祉サービスの充実
東部第1サブ障害保健福祉圏域の調整により、障害者等の高齢化、障害の重度化・重複化などに対応できる入所施設、デイサービスセンター、デイケア、授産施設などの通所施設、グループホーム等の生活施設などの整備・充実を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 入所施設の利用促進 (県・法人等) |
障害者の入所施設について、東部第1サブ障害保健福祉圏域内における利用を推進します。 |
| 2 施設機能の地域開放の促進 (法人等) |
ボランティアの受け入れ、介護教室の実施など、入所施設の専門的諸機能の地域開放を促進します。 |
| 3 生活施設の充実 (町、法人等) |
知的障害者、精神障害者の地域での自立生活を支援するため、町営住宅の優先入居など、生活施設の充実を図ります。 |
4 経済的支援の充実
障害者の生活安定のため、年金・手当等の充実を国へ要望するとともに、制度の周知徹底と適切な運用により、経済的な支援を図ります。また、障害者世帯の経済的な自立や生活環境の改善などのために、各種貸付・割引制度の充実を関係機関へ要望します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 各種制度の周知 (国、県、町) |
障害者の所得保障のため、障害基礎年金などの公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当などの各種手当制度の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国、県に働きかけていきます。 |
| 2 手当の充実 (町) |
松茂町福祉手当を支給することにより、経済的支援に努めます。 |
| 3 心身障害者扶養共済制度への加入促進 (県、町) |
心身障害児(者)の保護者に万一のことがあったとき、残された障害者に終身一定額の年金を給付する心身障害者扶養共済制度の周知と加入を促進し、自己負担金の助成を図ります。 |
| 4 生活福祉資金の貸付制度活用の促進 (県、町) |
障害者世帯等の経済的自立と生活の安定を図るため、生業費、住宅改修費、療養費などの必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付事業の周知と利用促進を図ります。 |
| 5 所得税・住民税等の軽減措置の周知 (国、県、町) |
所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税、事業税(あんま・はり等)、預貯金等利子課税の控除、軽減非課税等の措置に対する周知を図ります。 |
| 6 公共施設利用料等の割引制度の活用促進 (県、町、事業者等) |
県の文化・スポーツ・レクリエーション施設・公園、町の文化施設、NHK放送受信料、JR等の旅客運賃・有料道路通行料金等の割引制度の周知と活用促進を図ります。 |
| 7 医療費公費負担制度の継続 (県、町) |
重度障害者の健康管理と患者家族の医療費負担の軽減を図るため、重度心身障害者等医療費助成事業など医療費の公費負担制度を継続します。 |
5 関連各課・障害保健福祉圏域の連携による施策推進
障害者の生活全般にわたる施策の推進には、福祉、保健・医療、教育、雇用、広報、防災、建設など、多くの分野の連携が求められます。また、障害者施策と高齢者施策とは在宅福祉サービスの提供の上でも重複する分野も多く、さらに、介護保険制度導入にともなうサービス提供体制も検討が必要なことから、機構改革等による障害者サービスの一元化、各分野の連携による障害者の視点に立った効率のよいサービス供給体制の充実など、関連機関の連携による推進を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 障害者サービス調整チーム(仮称)の設置 (町・社協等) |
障害者に係わる各種サービスを総合的に推進するため、障害者サービス調整チーム(仮称)の設置、各課ネットワークの強化、専門職員の確保などを図ります。 |
4-6 生活環境―障害者がくらしやすいまちづくりのために
<基本目標>
障害者が自立して生活し、積極的に地域社会への参加を進めるためには、住みやすい住宅づくりと、安全で、自由に外出できるまちづくりが必要です。
「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」等に基づき、公共・公益施設、道路、公園、交通機関などの整備を推進し、整備にあたっては、障害がある人もない人も、すべての人が快適に利用できる設計(ユニバーサルデザイン)のまちづくりを進めます。
生活環境
- 「ひとにやさしいまちづくり」の推進
- 暮らしやすい住宅・生活環境の整備充実
- 防災・防犯体制の整備
- 交通・移動手段の確保
- コミュニケーションに対する支援
<主要施策>
1 「ひとにやさしいまちづくり」の推進
「ハートビル法」、「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」等にもとづき、公共公益的建物、道路・公園、住宅などの整備を進めるとともに、民間事業者の協力を得て、障害者にやさしい店づくりなどを促進します。また、「ひとにやさしいまちガイドマップ(松茂町版)」の発行により、障害者の外出に役立つ情報を提供するとともに、町民の手助けや思いやりの精神に裏打ちされた「ひとにやさしいまちづくり」を推進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」等の推進 (町・県等) |
「ハートビル法」「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」の普及・啓発に努め、公共・公益施設等の整備を推進します。整備にあたっては、事業者や建築士・建設業者の協力を得て、段差の解消、ゆったりトイレ、駐車場の整備など、障害者をはじめ、すべての人が快適に共同利用できる設計(ユニバーサルデザイン)によるまちづくりを進めます。 |
| 2 「ひとにやさしいまちづくり」点検 (県・町・社協等) |
「ひとにやさしいまちづくりアドバイザー派遣制度」を活用し、既存公共施設の点検を行うとともに、車いす使用者などを中心に、ボランティアなどが実際に街を歩き、公共公益施設の点検を行い、改良すべきところ、町民の手助けが必要な場所など、ひとにやさしいまちづくりを推進します。 |
| 3 「ひとにやさしいまちガイドマップ(松茂町版)」の作成 (町・社協) |
「ひとにやさしいまちガイドマップ(松茂町版)」を作成し、障害者が利用しやすい施設、交通機関、道路、商業施設などの紹介を行うとともに、住民が障害者を手助けするマニュアルとしても活用します。東部第1サブ障害保健福祉圏域で連携して、各町版の統合ができるよう、書式の統一、編集会議の開催等を検討します。 |
| 4 「障害者にやさしい店」の認定とPR (町・社協) |
障害者が利用しやすい施設整備や、積極的な介助サービスを実施している店を「障害者にやさしい店」として認定し、「ひとにやさしいまちガイドマップ」などでPRを図ります。 |
| 5 「福祉モデルゾーン」の設置 (町、県、国) |
総合庁舎~松鶴苑~保健センター~松茂運動公園~松茂町歴史民俗資料館を「福祉モデルゾーン」として設定し、車いす使用者や視覚障害者などが安心して歩けるまちづくりを進める努力をします。国・県道や都市計画街路や町道の整備にあたっては、歩行者専用道、バス停、ベンチ、身近な公園、ゆったりトイレなど、障害者をはじめすべての人が快適に共同利用できる設計(ユニバーサルデザイン)による整備を進めます。 |
| 6 公共施設の改善 (町) |
歩道の改修(拡幅、段差解消等)、公共施設周辺への点字ブロックの設置、議会傍聴席の車椅子スペースの確保、低カウンターの設置、通路の手すり設置など、公共施設の改善を計画的に推進します。 |
| 7 集会所等の改善の推進 (町、地域) |
地域住民の交流の場であり、福祉活動の拠点となる地域の集会所の障害者等の配慮した改善に対し、改善費用の補助等の検討を図ります。 |
2 暮らしやすい住宅・生活環境の整備充実
障害者等が生活しやすい町営住宅の整備に努めるとともに、バリアフリー住宅の普及、住宅改造への支援など、障害があっても住み続けられる住宅づくりを進めます。また、身近で集い、憩えるユニバーサルデザインの公園づくりを推進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 障害者に配慮した町営住宅の整備・利用促進 (町) |
老朽した町営住宅の建て替え整備にあたっては、障害者や高齢者の利用に配慮した整備を進めるとともに、自立をめざす知的障害者のグループホームとしての利用促進や障害者世帯等の入居収入基準の優遇措置を検討します。 |
| 2 バリアフリー住宅の啓蒙・普及 (町、関係団体等) |
パンフレット等による情報提供、相談体制の整備、建築士・住宅建築業者、保健婦・医師・ヘルパー等による研究会の設置などにより、バリアフリー住宅の啓蒙・普及に努めます。 |
| 3 リフォームヘルパー派遣制度の活用 (県・町) |
障害者の住宅改造が必要な場合、建築士、保健婦、ソーシャルワーカー等による専門チームの派遣によりアドバイスが受けられる、リフォームヘルパー派遣制度の活用を促進します。 |
| 4 住宅改造のための制度の周知・利用促進 (県・町) |
重度身体障害者への住宅改造助成や障害者が住む住宅改修への低利融資(生活福祉資金貸付制度)の活用を促進します。 |
| 5 「ひとにやさしい住まいづくり助成金制度」の推進 (県・町) |
障害者等に配慮した住宅建設に際し、公庫の対応住宅割増を利用した住宅に対し、借入の一部の利子補給制度の利用を促進します。 |
| 6 身近な公園の整備推進 (町) |
街区公園、農村公園など、住まいに近く、車いすで自由に利用でき、交流や憩いの場となるユニバーサルデザインの公園の整備推進を図ります。 |
3 防災・防犯体制の整備
交通事故や犯罪に対し、社会的弱者である障害者が被害者とならないよう、安全対策を推進します。また、火災、地震災害などに対し、自力で行動できない障害者などに配慮した地域防災計画の見直しや自主防災組織の育成による救助、避難体制づくりを促進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 交通安全教育の充実 (町、県) |
障害者への道路通行ルール学習の実施など、自らの身を守る方法を指導するとともに、ドライバーへの安全運転の啓発パンフレットの作成などにより、障害者に配慮した交通安全教育の実施を図ります。 |
| 2 交通安全設備等の整備 (町、県) |
歩道の設置、歩道の段差解消、視覚障害者の誘導ブロック、音響信号機等の整備を推進するとともに、路上の放置物等の撤去指導などにより、障害者の安全な通行を確保するため、努力します。 |
| 3 防犯体制の整備 (町、県) |
障害者の犯罪被害防止のために、防犯知識の周知徹底に努めるとともに、緊急連絡網、ファックス110番など、緊急通報・連絡体制を整備します。さらに、障害者を狙った消費者被害防止のために、広報やパンフレット等により、悪質商法等についての情報の提供に努めます。 |
| 4 防火・防災予防対策 (町) |
障害者・家族への防火・防災知識の普及に努め、消火器の設置、家具の固定、安全な部屋での就寝など、防火・防災予防対策の充実を促進します。 |
| 5 地域防災計画の見直し (町) |
地域防災計画を見直し、障害者などの災害弱者に対応するため、地域での災害弱者リストの作成検討、情報の伝達、避難誘導体制などの具体的な施策を盛り込みます。 |
| 6 防災体制の充実 (町) |
広報防災無線の充実など、情報機器や地域情報体制の整備に努め、災害時における障害者への的確な災害情報の提供体制を整備するとともに、地域の自主防災組織と連携して、避難誘導体制の確立を図ります。 |
| 7 地域での防災体制づくりの促進 (地域、町、社協等) |
自治会ごとに自主防災組織づくりを促進し、介護・介助が必要な災害弱者の実態の把握、緊急時に対応できる救助、避難誘導体制の整備を図ります。 |
4 交通・移動手段の確保
障害者が自由に外出して、さまざまな活動に参加できるよう、公共交通機関等の移動手段の確保を図るとともに、外出の介助を必要とする障害者へのガイドヘルパー制度の導入、外出ガイドマップの作成など、障害者の外出・移動を支援します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 公共交通機関の確保 (事業者等) |
障害者の通院・買い物などの重要な交通手段として、バス会社と連携しながら、バス路線の維持確保を図るとともに、リフトつきや低床バスの導入、バス停の改善など、障害者が利用しやすい施設・設備の改善を要請します。JRについても、駅舎・車両などの車いす対応やわかりやすい誘導案内装置の導入などを要請します。 |
| 2 貸出用車両の導入と運転ボランティアの確保 (国、県、町、広域、社協等) |
障害者の社会参加を促進する交通手段として、広域でリフトつきワゴン車両等の導入と貸付事業の実施を検討するとともに、運転ボランティアなど住民の協力を求めます。 |
| 3 自家用車による自立の支援 (県) |
身体障害者の自立更生を支援するため、身体障害者が運転する自家用車両の改造費の助成、自動車運転免許取得費用の助成などの制度の活用を促進します。 |
| 4 「ガイドヘルパー派遣事業」の推進 (国、県、町、社協、圏域) |
単独での外出が困難で、外出時に付添いがいない視覚障害者に対し、「ガイドヘルパー派遣事業」の実施を検討します。ガイドヘルパーの養成については、東部第1サブ障害保健福祉圏域による養成を行い、圏域内での相互派遣を検討します。さらに知的障害者の外出時のガイドヘルパー制度の導入を検討します。 |
| 5 交通費の助成・割引制度の活用促進 (国) |
タクシー、JR、バス、国内航空、有料道路交通料金等の運賃の割引制度の活用を促進し、障害者の移動の経済的支援を行います。 |
5 コミュニケーションに対する支援
視覚・聴覚障害者のコミュニケーションや必要な情報収集が自由にできるよう、声の広報紙の発行、点字パソコン・ファックス等の日常生活用具の給付を充実するとともに、点訳・手話通訳者・要約筆記者の養成・派遣を推進し、コミュニケーションの支援を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 広報・情報提供の充実 (町・社協) |
視覚障害者へ点訳パンフレット、「声の広報紙」など音声による情報提供や聴覚障害者へファックス等による情報提供とともに、インターネットなど多様な情報メディアの活用を推進します。 |
| 2 コミュニケーション手段の充実 (町、社協) |
点訳、朗読、手話、要約筆記などのボランティアの要請・派遣を促進するとともに、車いす対応の公衆電話の設置、公衆ファクスの設置を促進し、障害者のコミュニケーションを支援します。さらに、パソコン、ワープロ、ファックス、テープレコーダーなどの情報機器の貸与・給付事業を推進します。 |
| 3 コミュニケーション環境の整備・充実 (町、社協) |
点字図書、字幕入りビデオなどの充実により、社会・文化情報の入手を容易にするとともに、パソコンによる双方向のコミュニケーションが可能な環境づくりのため、障害者へのパソコン講習会の開催、障害者パソコンボランティアの育成など、障害者パソコンネットワークづくりを支援します。 |
| 4 コミュニケーション手段の減免、割引制度の活用促進 (国、事業者) |
NHK放送受信料の減免、郵便料金等の減免制度の活用を促進するとともに、字幕映像や手話つきの番組の拡充を要望します。 |
4-7 社会参加―こころゆたかな生活をおくるために
<基本目標>
障害者がこころゆたかな生活を送るために、スポーツ・レクリエーション活動、芸術・文化活動、交流活動などへの参加を促進します。
障害者自身が積極的に活動に参加し、楽しむ機会を創造していくために、スポーツ・レクリエーション、芸術・文化の鑑賞機会の充実、指導者や活動を一緒に行う支援者(ボランティア)の派遣、使いやすい施設整備などの支援を図ります。
社会参加
- 生涯学習への参加促進
- スポーツ・レクリエーションの振興
- 社会活動への参画
<主要施策>
1. 生涯学習への参加促進
障害者も共に学べるよう、公民館等で開設している生涯学習講座のプログラムの充実を図るとともに、参加しやすい内容、施設の整備、コミュニュケーションの方法の確保、交通手段の確保などの環境・条件の整備を図ります。
障害者の自主的なグループ・サークル活動を支援するために、指導者・支援ボランティアなどによるサポート体制を確保するため、努力します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 生涯学習講座の充実 (町・教委) |
障害者も共に学べるよう、公民館講座などの内容、施設・設備の整備、指導方法・コミュニュケーション方法への配慮など、参加できる条件の整備を図ります。 |
| 2 障害者の自主的グループへの支援 (町・教委) |
障害者の自主的学習グループ活動を支援するために、会場費の減免、文化協会による協力、指導者・支援ボランティアの紹介などの支援を図ります。生涯学習ボランティアの育成とともに、生涯学習ボランティアバンクの創設を推進します。 |
| 3 障害者の文化・芸術活動の振興 (町・教委) |
障害者の自己表現、生きがいとなる文化・芸術活動の活性化を図るため、図書館、公民館、コミュニティセンター、保健センターなどを拠点に、絵画・造形などの創作活動、演劇、音楽活動などへ、指導者の派遣、発表の機会の充実などの支援を図ります。 |
| 4 障害者を対象とした技術習得講座の開催 (町・教委) |
コミュニケーション、就労など、障害者の社会参加を促進するパソコン講座など、技術習得のための講座開設を推進します。 |
2 スポーツ・レクリエーションの振興
スポーツ・レクリエーション・園芸活動などが、リハビリテーション、健康の維持・増進、体力づくり等とともに、障害者の交流機会や生活の楽しみ、生きがいとなるよう、障害者のスポーツ・レクリエーション活動の活性化を促進します。
今後、障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツの振興を図ります。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 障害者スポーツ・レクリエーションの振興 (町、社協) |
障害者も参加しやすいスポーツ・レクリエーションイベントや教室の開催、障害のある人とない人が一緒に楽しめるスポーツの開発・導入、スポーツボランティアの育成など、障害者スポーツ・レクリエーションへの参加を促進します。 |
| 2 障害者スポーツ団体の育成・支援 (町、社協) |
身体障害者会のアーチェリーなどのサークル活動を支援するとともに、障害者の新たな参加や新しいスポーツサークルづくりを促進します。 |
| 3 園芸交流施設の整備検討 (町、社協) |
障害者が園芸活動を通して、リハビリテーションを兼ねた社会参加活動、交流活動ができるよう、園芸交流施設の整備、生活環境課の花づくり等を検討します。 |
3 社会活動への参画
ノーマライゼーションの理念にもとづいた「完全参加と平等」を実現するためには、障害者自身がまちづくり活動へ積極的に参加することが必要です。
障害者の意見を聞く場づくりだけでなく、障害者自身が積極的に政治、町民イベント、地域活動、消費生活、ボランティア活動に、住民として参画することを促進します。
| 施策項目 | 目的・内容等 |
|---|---|
| 1 まちづくり活動への参画促進 (町) |
テレホンサービス、FAXサービス、録音テープ、点訳など、町政の情報提供を充実するとともに、審議会、委員会等へ障害者を起用し、障害者の意見が政策に反映されるよう検討します。 |
| 2 町民イベントへの参画促進 (町) |
成人式、町民運動会などの町主催のイベントへ、住民のひとりとしての障害者の積極的な参加を促進します。 |
| 3 地域コミュニティ活動への参画促進 (町・地域等) |
町内会、子ども会、地域ボランティア活動、まつり等の地域行事に障害者の参加を促進するため、参加しやすい環境づくりや積極的働きかけを行います。 |
| 4 消費生活での受益の確保 (事業者等) |
金融機関、商業施設などへの障害者に配慮した施設整備や応対の改善、メーカーなどへの障害者に配慮した日常生活用品(バリアフリー用品)の開発と販売、商品情報の点訳・録音パンフレットの作成など、障害者が消費者としての受益を確保できるよう、事業者等への要請を図ります。 |
5 実現に向けて
5 実現に向けて
1 障害者の自立と連携に向けて
障害者が誇りを持ち、地域社会の中で自立して生活できるよう、障害者、家族、障害者団体の交流と連携、助け合いを促進します。
2 住民参加の促進に向けて
障害者が社会の一員として、共に生活していける(ノーマライゼーション)社会の実現のためには、行政による福祉施策の充実とともに、町民参加による取り組みが不可欠です。町民、行政、関係機関等の代表による「松茂町障害者施策推進協議会(仮称)」を設置し、計画推進を図ります。
また、保健センター、老人福祉センター、保育所、歴史の里、歴史民俗資料館、運動公園等の一帯を車いす利用可能な福祉ゾーンとして整備し、障害のある人もない人も、ともに楽しみ、交流し、互いに理解を深める拠点とします。
3 関係団体・機関の連携の強化
障害者に対する各種サービスの充実をめざし、町、社会福祉協議会、社会福祉施設、保健・医療施設など、地域福祉の専門的な担い手による連携を強化します。
4 行政推進体制の整備
これからの障害者福祉施策の推進にあたっては、住民に密着した市町村の役割が重要となることから、町が中心となって、「あなたとともに」築く、障害者福祉のまちづくりをめざした総合的な取り組みを進めます。国および県に対しては、保健福祉関係制度の充実と継続的な財源の確保等を要請していきます。
障害者数の増加、障害者サービスの需要の増大、多様化に対応できるよう、機構改革(平成10年度~)により、保健・福祉分野を担当する「健康福祉課」を設置します。健康福祉課の充実とともに、関係各課、関係団体の連携の強化、「松茂町障害者サービス調整チーム(仮称)」の設置、専門職員の育成・確保、職員への福祉研修の充実などに努めます。
なお、計画の実現に向けて、毎年、計画の進捗状況を点検し、実施計画に反映させるとともに、介護保険制度の動向をみながら、必要に応じて、事業方法、推進体制等の見直しを図ります。
5 広域的な連携の強化
東部第1サブ障害保健福祉圏域で、障害者福祉に関わる行政機関、社会福祉法人、関係団体等の連携を図り、障害者福祉施設の適正で効率的な立地を促進するとともに、「市町村障害者生活支援事業」、「市町村障害者社会参加促進事業」、「障害者(児)地域療育等支援事業」、「心身障害児通園事業」、「精神障害者地域生活支援事業」などの共同推進を図ります。
資料編
資料1 松茂町の概要
1 立地条件
松茂町は、明治22年に10村・浦が合併して松茂村になり、昭和36年の町制の施行により現在の松茂町となりました。町は紀伊水道と旧吉野川、今切川に囲まれた平坦な地域で、肥沃な土地を利用した農業地帯として発展してきましたが、徳島市のベッドタウンとして住宅立地が進むとともに、新産都市徳島地区の指定を受け、工業立地が進むなど、空港のある、徳島県の空の玄関口として発展してきています。
位置:徳島県東部 南は県都徳島市、北は鳴門市、西は北島町に隣接している。
町域:総面積13.10平方キロメートル
地勢:紀伊水道、旧吉野川、今切川にはさまれた平坦地
位置図
2 主要指標にみる松茂町の位置
本町人口の徳島県人口に占める割合1.6%を1としてみると、65歳以上人口は、0.65、出生者数は1.35と、若年層の多い特徴を示しています。
障害者は、身体障害者数0.57は人口比を下回り、知的障害者数の1.40は、知的障害者福祉施設が立地しているため、高い比率となっています。
医療は、病院・診療所数が0.87、医師数0.53と低い水準です。
産業については、農業粗生産額1.02、工業製品出荷額等1.22と高く、商業では飲食店従業者数1.06、販売額1.33と水準を上回ります。
住宅着工新設住宅戸数は1.18と高く、住宅開発による人口増加を裏付けています。
| - | 徳島県 | 松茂町 | 県に対する割合 | 指標 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 人数(人)国勢調査(H7) | 832,427 | 13,562 | 1.6% | 1.00 |
| 世帯数 国勢調査(H7) | 273,839 | 4,295 | 1.6% | 0.96 | |
| 65歳以上人口(H7) | 157,461 | 1,677 | 1.1% | 0.65 | |
| 核家族世帯(H2) | 142,454 | 2,946 | 2.1% | 1.27 | |
| 出生者数(H7年度) | 7,406 | 163 | 2.2% | 1.35 | |
| 土地 | 面積(平方キロメートル) 国土地理院(H5) | 4,144.23 | 13.1 | 0.3% | 0.19 |
| 障害者 | 身体障害者数(H8) | 36,673 | 342 | 0.9% | 0.57 |
| 知的障害者数(H8) | 3,940 | 90 | 2.3% | 1.40 | |
| 精神障害者数(H8) | 9,643 | 24 | 0.2% | 0.15 | |
| 医療 | 病院・診療所数(H6) | 851 | 12 | 1.4% | 0.87 |
| 医師数 (人) (H6) | 2,070 | 18 | 0.9% | 0.53 | |
| 住宅 | 着工新設住宅戸数(H6年度) | 9,052 | 174 | 1.9% | 1.18 |
| 農業 | 農業粗生産額(1000万円) (H6) | 15,000 | 250 | 1.7% | 1.02 |
| 工業 | 工場数(H6) | 2,716 | 30 | 1.1% | 0.68 |
| 従業員数(人) (H6) | 65,775 | 970 | 1.5% | 0.91 | |
| 工業製品出荷額等 (100万円) (H6) | 1,441,963 | 28,752 | 2.0% | 1.22 | |
| 商業 | 小売商店数 (H6) | 13,490 | 146 | 1.1% | 0.66 |
| 従業員数 (人) (H6) | 49,934 | 692 | 1.4% | 0.85 | |
| 小売販売額 (100万円) (H6) | 824,765 | 11,208 | 1.4% | 0.83 | |
| 飲食店商店数 (H4) | 3,502 | 46 | 1.3% | 0.81 | |
| 従業員数 (人) (H4) | 12,448 | 215 | 1.7% | 1.06 | |
| 販売額 (100万円) (H4) | 57,245 | 1,244 | 2.2% | 1.33 | |
資料:「地域経済総覧’97」
3 人口の動向
(1) 人口構成
平成8(1996)年の住民基本台帳による人口構成をみると、45~50歳の団塊世代、20歳代の団塊ジュニア世代がやや膨らんだ「つりがね型」を示しています。
| 年齢 | 男性 6,683人 |
女性 6,776人 |
|---|---|---|
| 0~4歳 | 390 | 394 |
| 5~9歳 | 413 | 383 |
| 10~14歳 | 431 | 394 |
| 15~19歳 | 456 | 437 |
| 20~24歳 | 575 | 518 |
| 25~29歳 | 549 | 523 |
| 30~34歳 | 498 | 502 |
| 35~39歳 | 485 | 443 |
| 40~44歳 | 530 | 498 |
| 45~49歳 | 610 | 594 |
| 50~54歳 | 449 | 426 |
| 55~59歳 | 358 | 356 |
| 60~64歳 | 359 | 377 |
| 65~69歳 | 250 | 300 |
| 70~74歳 | 147 | 233 |
| 75~79歳 | 88 | 181 |
| 80~84歳 | 53 | 131 |
| 85~89歳 | 35 | 62 |
| 90~94歳 | 6 | 20 |
| 95~99歳 | 1 | 4 |
| 100歳以上 | 0 | 0 |
資料/住民基本台帳
(2) 人口動態
昭和59(1984)年以降の人口動態をみると、自然動態では、出生数が死亡数を上回る自然増が続いており、社会動態でも、転入が転出を上回る増加傾向が続いています。
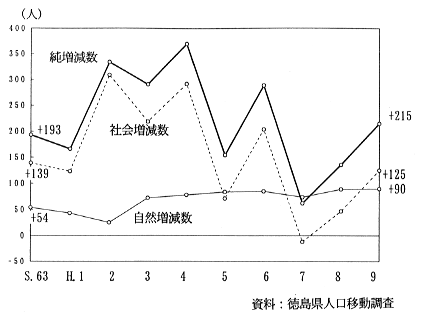
4 世帯の動向
世帯数は昭和50(1975)年の2,240世帯から増加し続け、平成7(1995)年には4,264世帯となっています。
1世帯当たりの人数は、昭和50(1975)年の3.8人から、平成7(1995)年の3.0人に減少しています。
昭和50(1975)年からの世帯型の推移をみると、核家族世帯は60~65%で推移し、大きな変化がないものの、三世代世帯が25.7%から14.6%へ減少、単身世帯が7.0%から20.0%へ増加し、家族介護力の低下が見られます。
| 年度 | 世帯数 | 世帯人員数 |
|---|---|---|
| 50年 (1975) |
2,240 | 3.8 |
| 55年 (1980) |
2,557 | 3.7 |
| 60年 (1985) |
2,987 | 3.5 |
| 平成2年 (1990) |
3,524 | 3.2 |
| 平成7年 (1995) |
4,264 | 3.0 |
資料:国勢調査
| 年度 | 核家族世帯 | 三世代 | 単身 | その他 | 総数(人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和50年 | (63.2%) | (25.7%) | (7.0) | (4.1%) | 2,240 |
| 昭和55年 | (64.6%) | (25.0%) | (7.4) | (3.0%) | 2,557 |
| 昭和60年 | (62.5%) | (21.8%) | (13.0%) | (2.7%) | 2,987 |
| 平成2年 | (62.7%) | (17.9%) | (16.3%) | (3.1%) | 3,524 |
| 平成7年 | (62.4%) | (14.6%) | (20.0%) | (3.0%) | 4,264 |
| 徳島県平成7年 | (55.2%) | (19.6%) | (21.8%) | (3.4%) | 273,839 |
資料:国勢調査
資料2 障害者の状況
1 世帯と住居の状況
(1) 世帯型
「アンケート調査」により障害者の世帯型をみると、身体障害者では「核家族世帯」44.0%、「夫婦のみ世帯」22.8%で、知的障害者では「核家族世帯」が33.3%、社会福祉施設へ入居している「その他」が27.8%などです。
精神障害者では(「在宅精神障害者・家族のアンケート調査」による)、「家族」69.6%が7割をしめ、あとは「施設・寮」14.7%、「単身」12.7%などです。
「ひとり暮らし」の身体障害者、知的障害者がともに13.9%、精神障害者が12.7%おり、特に介助の必要性があります。
| - | ひとり暮らし | 夫婦のみ | 核家族(夫婦のみ以外) | 3世代同居 | その他 | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体障害者 N=202 |
13.9 | 22.8 | 44.0 | 9.4 | 5.4 | 4.5 |
| 知的障害者 N=36 |
13.9 | 2.8 | 33.3 | 13.9 | 27.8 | 8.3 |
| 町民 N=152 |
5.9 | 18.4 | 48.7 | 18.4 | 6.6 | 2.0 |
(2) 住宅
1. 住まいの状況
「アンケート調査」によると、身体障害者の住宅では「持家」が64.8%と多く、あとは「公営住宅」8.9%、「民営借家」5.0%などとなっており、必要ならば障害者仕様への改造が可能な条件を備えている持家の人が約65%をしめています。
2. 改造の意向
住まいの改造や工夫の現状では、「特になにもしていない」が53.9%ですが、「改造をした、改造されている」11.9%、「建てるときから配慮されている」11.4%を合わせると23.3%となり、主に、「トイレ」80.9%、「浴室」66.0%の改造は進んでいる状況です。
今後の住宅改造の必要性について、「必要である」は30.2%で、改造を希望する場所としては「浴室」65.6%、「トイレ」42.6%が高く、あとは、「階段」「廊下」、「玄関」などと続いています。
| - | 住宅の改造や工夫した場所 (N=47) |
今後、改造したいところ (N=61) |
|---|---|---|
| 玄関 | 23.4 | 21.3 |
| 廊下 | 21.3 | 24.6 |
| 階段 | 19.1 | 32.8 |
| 居室 | 21.3 | 11.5 |
| 浴室 | 66.0 | 65.6 |
| トイレ | 80.9 | 42.6 |
| 台所 | 17.0 | 13.1 |
| その他 | 2.1 | 4.9 |
| 無回答 | 6.4 | 1.6 |
住宅の改造が必要であると考えながらも、改造できない理由としては「費用負担が困難」47.5%が特に高く、あとは、「建物の構造上、困難」18.0%、「家族の同意がまだ」、「借家」ともに9.8%などをあげていますが、「依頼業者がわからない」、「設備・改造方法がわからない」、と答えている人も9.9%おり、改造資金の支援体制の整備とともに、総合的な住宅改造の相談窓口が求められます。
| 借家なので改造がむずかしい | 9.8 |
| 費用負担が困難 | 47.5 |
| 建物の構造上困難 | 18.0 |
| 設備・改造方法がわからない | 3.3 |
| 依頼業者がわからない | 6.6 |
| 他の家族が使いにくくなる | 4.9 |
| 家族内で話合いが済んでいない | 9.8 |
| 困難はない | 16.4 |
| 改造は考えていない | 0.0 |
| その他 | 4.9 |
| 無回答 | 8.2 |
2 日常生活と介助の状況
(1) 日常生活
「アンケート調査」によると、日常生活における介助の状況で、「全介助」、「一部介助」が必要な人の割合は、「外出(通勤・買物等)」が身体障害者24.7%、知的障害者22.2%と最も高く、身体障害者では「入浴」13.8%、知的障害者では「食事」13.9%が続いています。
「全介助」が必要な人の割合は、「外出」(身体障害者16.8%、知的障害者8.3%)が最も高く、次いで、「入浴」(身体障害者5.9%、知的障害者5.6%)の順となっています。
| - | 身体障害者 N=202 |
知的障害者 N=36 |
||
|---|---|---|---|---|
| 全介助 | 一部介助 | 全介助 | 一部介助 | |
| 食事 | 6.5% | 13.9% | ||
| 1.5 | 5.0 | 2.8 | 11.1 | |
| 排泄 | 6.0% | 5.6% | ||
| 4.0 | 2.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 入浴 | 13.8% | 11.2% | ||
| 5.9 | 7.9 | 5.6 | 5.6 | |
| 屋内移動 | 9.0% | 5.6% | ||
| 4.0 | 5.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 衣服の着脱 | 12.9% | 5.6% | ||
| 3.0 | 9.9 | 2.8 | 2.8 | |
| 寝起き | 5.0% | 2.8% | ||
| 3.0 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | |
| 意思の伝達 | 6.5% | 8.4% | ||
| 4.0 | 2.5 | 2.8 | 5.6 | |
| 外出(通勤・買物等) | 24.7% | 22.2% | ||
| 16.8 | 7.9 | 8.3 | 13.9 | |
仕事をしていない精神障害者の日常生活について(「在宅精神障害者・家族のアンケート調査」による)、「特に何もしていない」63.3%、「テレビやビデオを見て過ごす」44.9%、「病院に行く」32.7%などが高く、社会参加活動がない状況が伺えます。
将来の生活への心配や不安について、「生活費」52.9%、次いで「健康」47.1%、あとは「食事」、「仕事」24.5%、「住まい」23.5%などで、「心配・不安なし」と答えているのはわずか8.8%に過ぎません。
(2) 介助者の状況
「アンケート調査」によると、身体障害者の主な介助者は「配偶者」が40.0%、あとは「子ども」15.6%、「子どもの配偶者」13.3%などと続いていますが、知的障害者では、「母親」41.7%が多く、あとは「父親」、「兄弟姉妹」です。
介助者の悩みや問題点では、身体障害者では「介助を代わってもらえる人がいない」31.1%、「自分の時間がもてない」28.9%、「障害者の将来が不安」、「介助者の健康に不安」ともに26.7%などとさまざまです。知的障害者では、「障害者の将来への不安」50.0%と高い割合で、親なき後の不安が最も大きいことがわかります。
| - | 身体障害者 (N=45) |
知的障害者 (N=12) |
|---|---|---|
| 自分の時間がもてない | 28.9 | 8.3 |
| 仕事・家事との両立が困難 | 24.4 | 16.7 |
| 疲れる | 24.4 | 25.0 |
| 介助者の健康に不安がある | 26.7 | 33.3 |
| 介助を代ってくれる人がいない | 31.1 | 33.3 |
| 経済的な負担が大きい | 22.2 | 0.0 |
| 相談するところがない | 2.2 | 0.0 |
| 利用できる福祉施設がない | 6.7 | 0.0 |
| あなたの将来に不安をもっている | 26.7 | 50.0 |
| 特にない | 20.0 | 8.3 |
| その他 | 2.2 | 8.3 |
| 無回答 | 6.7 | 25.0 |
(3) 外出の状況
「アンケート調査」によると、日頃の外出の状況は、身体障害者では「ほとんど毎日外出する」30.7%、「時々外出する」28.2%で、あわせて約6割の障害者が外出しています。知的障害者では「ほとんど毎日外出する」27.8%、「時々外出する」16.7%です。
「あまり外出しない」「全く外出しない」人は、身体障害者で18.8%、知的障害者で16.7%おり、外出しにくい理由として、身体障害者では、「健康に不安」25.7%が最も高く、次いで「歩道の段差・障害物が多い」13.4%をあげています。知的障害者では「人の視線」、「とっさの手助けを期待できない」、「歩道の段差・障害物が多い」、「利用できる交通手段が少ない」など、多岐にわたります。
| - | 身体障害者 N=202 |
知的障害者 N=36 |
|---|---|---|
| ほとんど毎日外出する | 30.7 | 27.8 |
| 時々、外出する | 28.2 | 16.7 |
| あまり外出しない | 11.9 | 16.7 |
| 全く外出しない | 6.9 | - |
| その他 | 0.5 | 2.8 |
| 無回答 | 21.8 | 36.0 |
| - | 身体障害者 (N=202) |
知的障害者 (N=36) |
|---|---|---|
| 健康に不安がある | 25.7 | 5.6 |
| 人の視線が気になる | 2.0 | 8.3 |
| 手助けをたのめない | 7.4 | 8.3 |
| 車などに危険を感じる | 6.9 | 8.3 |
| 通行しにくい | 13.4 | 0.0 |
| 利用できる交通手段が少ない | 5.9 | 8.3 |
| 交通料金の負担が大きい | 5.0 | 0.0 |
| 利用しやすい施設が少ない | 5.9 | 2.8 |
| その他 | 3.5 | 8.3 |
| 特にない | 15.3 | 25.0 |
| 無回答 | 48.5 | 50.0 |
外出の目的は、身体障害者では「買い物」50.3%、「通院」39.2%で、知的障害者では「通園・通学・通勤・通所」54.5%、「買い物」45.5%、「通院」22.7%などで、必要な外出が上位をしめていますが、身体障害者では、家族・知人・友人との交流、学習・趣味・スポーツ活動、ハイキングなど、多様な目的での外出も続いて高い割合です。
| - | 身体障害者 (N=143) |
知的障害者 (N=22) |
|---|---|---|
| 通園・通学・通勤・通所 | 21.0 | 54.5 |
| 通院 | 39.2 | 22.7 |
| リハビリ施設などでの訓練 | 9.1 | 4.5 |
| 買い物 | 50.3 | 45.5 |
| 家族や親戚とのつきあい | 28.0 | 13.6 |
| 友人とのつきあい | 32.2 | 0.0 |
| 地域の行事や集まり | 16.1 | 4.5 |
| 障害者団体の活動 | 7.7 | 4.5 |
| ボランティア活動 | 2.1 | 4.5 |
| 学習・趣味・スポーツなどの活動 | 18.2 | 4.5 |
| 旅行・ハイキング・ドライブ | 16.8 | 18.2 |
| その他 | 6.3 | 0.0 |
| 無回答 | 9.1 | 9.1 |
外出の手段は、身体障害者では「自家用車(自分で運転)」40.6%、「自家用車(他の人が運転)」29.4%と自家用車の利用が多く、次いで「自転車」21.0%、「バス」20.3%となっています。知的障害者では「自家用車(他の人が運転)」45.5%が最も高く、あとは「自転車」36.4%、「バス」22.7%の利用です。
| - | 身体障害者 (N=143) |
知的障害者 (N=22) |
|---|---|---|
| 汽車 | 4.2 | 4.5 |
| バス | 20.3 | 22.7 |
| 送迎バス | 4.2 | 4.5 |
| 車いす専用リフトバス | 1.4 | 0.0 |
| タクシー | 10.5 | 0.0 |
| 自家用車(自分で運転) | 40.6 | 0.0 |
| 自家用車(他の人が運転) | 29.4 | 45.5 |
| 自転車 | 21.0 | 36.4 |
| 徒歩・車いす | 16.1 | 13.6 |
| 電動三輪車 | 3.5 | 0.0 |
| その他 | 3.5 | 4.5 |
| 無回答 | 4.9 | 13.6 |
3 障害者保健・医療・福祉にかかわる施設
知的障害児の通園施設「ねむの木療育園」、知的障害者の更生施設「吉野川育成園」・「春叢園」、通勤寮「若竹通勤寮」、グループホーム「若竹ホーム」があり、社会福祉協議会を通じたボランティアとの交流も盛んです。その他高齢者福祉施設として、特別養護老人ホーム「和光園」、老人福祉センター「松鶴苑」が設置されています。現在のところ、障害者のデイサービスセンター、ショートステイの施設はありませんが、平成10年10月より、町外の施設を利用できる予定です。
障害者・高齢者に関する保健・医療・福祉施設の配置図(松茂町)
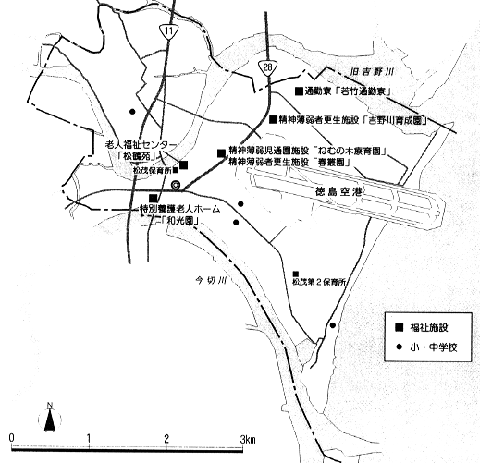
障害者・高齢者に関する保健・医療・福祉施設の配置図(東部障害保健福祉圏域)
4 障害児教育の状況
本町では、知的障害、情緒不安定などの障害をもつ児童・生徒のための障害児学級を、小学校(3校)・中学校すべてに設置しており、能力、適性に応じた障害児教育を行っています。
| - | 小学校 | 中学校 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学級数 | 児童数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 児童数 生徒数 |
|
| 知的障害 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 病弱・虚弱 | 0 | 0 | 0 | |||
| 情緒不安定 | 2 | 0 | 2 | |||
| 合計 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 |
資料:松茂町教育委員会
5 障害者の就業状況
(1) 就業状況
「アンケート調査」によると、身体障害者の就業状況について、身体障害者全体では、高齢者が多いため「自宅にいる」が32.2%、「就職している」が20.8%と就業は低い割合ですが、身体障害者の中で生産年齢にあたる18~64歳では、「就職している」が37.6%となります。
知的障害者では「施設に通所」が19.4%、「就職している」13.9%などとなっています。
また雇用形態をみると、身体障害者では「勤め(正規の社員、職員)」47.6%が最も多く、「自営業・自由業」26.2%、「勤め(臨時雇い、パート等)」19.0%となっています。就職している知的障害者5人はすべて正規の社員、職員として就職しています。
就学・就労の状況
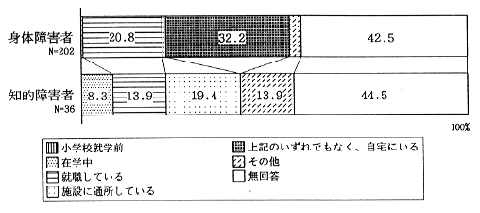
| 町の名前 松茂町 上段:実数 下段:横% |
合計 | 就学・就労の状況 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校就学前 | 在学中 | 就職している | 施設に通所している | 上記のいずれでもなく、自宅にいる | その他 | 無回答 | |||
| 全体 | 202 100.0 |
- - |
1 0.5 |
42 20.8 |
2 1.0 |
65 32.2 |
6 3.0 |
86 42.5 |
|
| 年齢 | 0~17歳 | 1 100.0 |
- - |
1 100.0 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
| 18~64歳 | 93 100.0 |
- - |
- - |
35 37.6 |
2 2.2 |
27 29.0 |
4 4.3 |
25 26.9 |
|
| 65歳以上 | 106 100.0 |
- - |
- - |
6 5.7 |
- - |
38 35.8 |
2 1.9 |
60 56.6 |
|
勤労形態
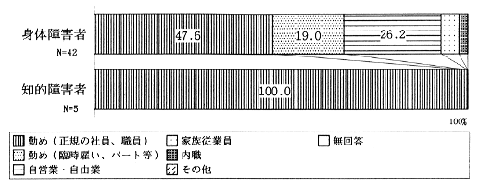
(2) 一般的就労
1. 民間企業
徳島県全体では「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく、障害者雇用率(1.6%)が適用される民間企業(常用労働者数が63人以上)280社の実雇用率は1.76%で、法定雇用率を上回っていますが、雇用率未達成の企業の割合が55.0%あり、障害者雇用の促進が求められます。
| 項目 | 企業数 | 雇用状況 | 雇用率達成企業の割合 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 管内 | 常用労働者数 | 障害者数 | 雇用率 | ||
| 鳴門公共職業安定所 | 46 | 8,752人 | 187人 | 2.14% | 54.35% |
| 徳島県 全体 | 280 | 47,631人 | 836人 | 1.76% | 55.00% |
資料:徳島県
2. 町役場
平成8(1996)年の町役場職員の障害者雇用は1人で、雇用率は0.99%です。地方自治体の雇用義務である雇用率(非現業機関2.0%、現業機関1.9%)を下回っています。
| 項目 年度 |
職員数 | 障害者の数 | 実雇用率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A 重度障害者 (常用) |
B A以外の障害者 |
C 計 A×2+B |
|||
| 平成3年 | 91人 | 0人 | 1人 | 1人 | 1.10% |
| 平成4年 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1.10 |
| 平成5年 | 93 | 0 | 1 | 1 | 1.08 |
| 平成6年 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1.03 |
| 平成7年 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1.01 |
| 平成8年 | 101 | 0 | 1 | 1 | 0.99 |
資料:総務課
(3) 福祉的就労
本町には現在、授産施設、作業所などの福祉的就労の場がなく、町内への職業訓練の施設、小規模作業所などの整備が求められています。
6 地域活動・交流活動
(1) 交流活動
1. 福祉大会など
社会福祉協議会を中心に、年1回福祉大会を開催し、講演や1年間の活動報告、表彰等を行っています。また、中央福祉地区、県、全国の障害者福祉大会などへも積極的に参加し、交流を深めています。
2. タウンマザー活動
「吉野川育成園タウンマザー」(昭和60年~)として、町内のボランティアが、吉野川育成園の身寄りのない園生、遠方で保護者の面会のない園生の里親となり、保護者会への出席、面会、園行事への参加などの活動を行っています。
3. 交流親睦会
吉野川育成園、春叢園とのゲートボール交流試合、和光苑との輪投げ大会などにより、交流を図っています。
4. 身体障害者スポーツ大会
中央福祉管内、県、全国身体障害者スポーツ大会、県身体障害者グランドゴルフ大会、中央福祉、県ゲートボール大会などへ参加しています。
(2) 障害者団体
本町の障害者の団体は、松茂町身体障害者会と松茂町手をつなぐ育成会の2団体があり、活動内容は次のとおりです。
| 団体名 | 対象者 | 会員数 | 活動内容 |
|---|---|---|---|
| 松茂町身体障害者の会 | 町内に居住する身体障害者 | 117人 | スポーツ・レクリエーション、視察研修、交流会 等 |
| 松茂町手をつなぐ育成会 (精神薄弱者育成会) 愛光会 |
町内に居住する精神薄弱者とその家族 | 19人 | 親子遠足、クリスマス会、研修会等 |
資料:社会福祉協議会
主題:
松茂町障害者計画 No.2
32頁~19頁(資料)
発行者:
松茂町住民課
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
松茂町住民課
徳島県板野郡松茂町広島字東裏30
Tel.0886-99-2111
Fax.0886-99-6010
