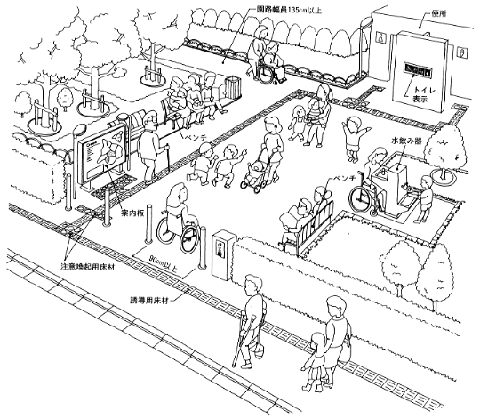脇町障害者福祉計画
No.2
自立と社会参加の促進をめざして
徳島県脇町
第5節 福祉サービスの充実
福祉サービスの充実
(1)生活の安定
(2)在宅福祉サービスの充実
(3)福祉機器サービスの充実
(4)施設サービスの充実
5.福祉サービスの充実
☆現状
これまで福祉基盤の整備充実とホームヘルプサービス・ショートステイ事業、福祉機器給付・貸与等に努めてきました。しかし、こうした制度が十分利用されていないきらいもあります。アンケート調査結果によると、配偶者・父母・子ども等の家族で介助しているのが55.6%であり、ホームヘルパーを利用している人は、わずか3.2%しかありません。今後、高齢化する介助者の負担を軽減するためには、ホームヘルプサービス事業等の介護サービスの一層の充実や各種手当・福祉機器給付、貸与等の制度の周知も大切なことです。
(1)生活の安定
☆課題
- 障害者が地域社会のなかで自立し安定した生活を送るためには、生活の基盤となる所得保障の充実が必要であります。
- 所得保障となるのが年金・手当制度であり、このほかにも経済的自立を支援するため、医療費助成制度・税の減免・運賃の割引制度等があります。今後とも一層の充実が求められています。
☆施策の方向
- 公的年金制度や特別障害者手当などの各種手当制度の有効利用を促進するため周知徹底に努めます。
- 経済的自立と生活の安定向上を図るため、障害者のニーズに応じた資金の貸付を行う「生活福祉資金」制度の効果的な活用を促進します。
- 重度心身障害児(者)などの医療費負担を軽減するため、更生医療等の給付や医療費助成制度の活用周知に努めます。
- 経済的な負担を軽減するため、税の減免制度やJR等の運賃・料金の割引制度の活用周知に努めます。
- 経済的な負担を軽減するため、税の減免制度やJR等の運賃・料金の割引制度の活用周知に努めます。
☆主要事業
〔内部部分の金額は平成9年8月現在〕
事業名 内容 窓口 特別障害者手当の支給 在宅の身体又は精神に重度の障害を有する者を要する状態にある20歳以上の者に対して支給します。 月額26,230円福祉事務所または町保健福祉課 障害児福祉手当の支給 在宅の身体又は精神に重度の障害を有する児童を日常生活活動において著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対して支給します。 月額14,270円特別児童扶養手当の支給 在宅の身体又は、精神に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護する父母又は養育者に対して支給します。 月額1級50,350円
2級33,530円町住民課 心身障害者扶養共済制度 心身障害児(者)の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者が生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡又は、重度障害になった時、生活の安定と福祉の向上を図るため、残された障害者に終身一定額の年金を支給します。
- 加入年齢65歳未満(2口まで加入可)
- 加入者掛金(年齢により区分)
- 年金額1口当たり月額2,000円
町保健福祉課 障害基礎年金の支給 国民年金に加入している間、又は60歳以上65歳未満に病気やけがをして障害者になった時、20歳前からの障害者は、20歳になった時から一定の条件のもとに支給します。
保険料納付済期間(免除期間を含む)又は、他の公的年金制度の加入期間が一定以上であるか、幼い時からの障害者であること。1級…年額981,900円+子の加算
2級…年額785,500円+子の加算
(福祉年金からの移行者及び幼い時からの障害者は、所得制限がある。)町住民課 障害厚生年金の支給 厚生年金保険の加入中の発病で、障害基礎年金が受けられる時。ただし、3級と障害手当金は、厚生年金保険独自給付します。
1級…平均標準報酬月額×7.5/1000 ×被保険者期間
(300月未満は300月)×1.007×1.25+加給年金額(配偶者)
2級…平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間
(300月未満は300月)×1.007+加給年金額(配偶者)
3級…平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間
(300月未満は300月)×1.007(最低保障589,100円)社会保険事務所 障害手当金の支給 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間
(300月)×2.00(最低保障1,170,000円)生活福祉資金の貸付 障害者世帯、低所得世帯、及び日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進等を図るため、生業費・住宅改修費・療養費等の必要な資金を低利で貸付けします。 社会福祉協議会 税の減免制度 1所得税
- 障害者控除(本人又は配偶者、扶養家族が心身障害者の場合)
所得控除270,000円- 特別障害者控除(上記の障害者が1、2級の身体障害者、重度の知的障害者である場合)
所得控除350,000円- 同居特別障害者扶養控除
所得控除680,000円税務署 2住民税
- 障害者控除
所得控除260,000円- 特別障害者控除
所得控除280,000円- 同居特別障害者扶養控除
所得控除520,000円- 前年度所得が125万円以下の障害者
非課税町税務課 3自動車税(軽自動車税) 県自動車税事務所(軽自動車税は町税務課) 4自動車取得税
※その他、旅客鉄道株式会社の運賃・航空運賃・有料道路の通行料金・バス運賃・タクシー運賃の割り引き・NHK放送受信料の減免等、福祉措置があります。
(2)在宅福祉サービスの充実
☆課題
- 障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者が生まれ育った家庭や地域で安心して生活が送れるよう、その障害に応じたさまざまな福祉サービスを充実していくことが重要であります。
- 障害者や介護者の負担を軽減するためのホームヘルプサービス(訪問介護)・デイサービス(日帰り介護)・入浴サービス・給食サービス・ショートステイ(短期入所)等の各種サービスの認知度が低く、利用しにくい傾向があるので周知と利用の拡大を図る必要があります。
- 障害者やその家族の在宅福祉を支えるマンパワーとして、ホームヘルパー・保健婦・看護婦・ボランティアが活動しています。今後、多様なニーズ(要望)にあったホームヘルプ活動を展開していくためには、ホームヘルパーの増員と介護福祉士の養成とともにボランティアの育成も大事な課題となっています。
☆施策の方向
- 障害の重度化・重複化・高齢化等に伴う多様なニーズに適切に対応するため、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、入浴サービス、給食サービス等の各種サービスの充実に努めます。また、今後精神障害者や難病患者にも対応していく必要があります。
- ホームヘルパーの派遣については、高齢者在宅サービスと連携して、利用ニーズに対応できるホームヘルパーの確保とサービスの充実に努めます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏での「市町村障害者社会参加促進事業」の推進のため、関係機関との調整を図り実施にむけて努力します。
- ショートステイ事業については、身体障害者療護施設と委託契約を結び実施していますが、制度の周知を図るとともに利用施設の増加に努めます。
- 在宅の障害児(者)の地域における生活を援助するため県が行う「障害児(者)地域療育等支援事業」を支援します。
- オフトーク通信及び緊急通報装置等の整備を図り、近隣住民や消防署等への連絡手段の確保を検討します。
- 心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るための、心身障害者扶養共済制度の周知と加入促進に努めます。
- 視覚障害者の社会参加の促進のため、付き添いをするガイドヘルパーの養成と確保に努めます。
- 住宅に困窮している障害者に対して、優先的に町営住宅へ入居できるよう努めます。そして、サポート対策としてケア付き住宅については、今後検討します。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏において、生活支援機能を持つグループホームの開設を支援し、障害者の自立生活助長に努めます。
- 各種障害者団体の育成支援をします。
- ホームヘルプ活動を促進するため、ホームヘルパー・介護福祉士そして、ボランティアの養成に努めます。
- 穴吹保健所(事務局)の美馬郡心身障害児父母の会の支援に努めます。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 ホームヘルプサービス事業 日常生活を営む上で支障のある在宅の重度身体障害者・寝たきり高齢者等の家庭に対し、家事の援助や介護等のサービスを行っています。 社会福祉協議会
町保健福祉課身体障害者短期入所事業(ショートステイ) 重度身体障害者を介護している家族が、疾病等の理由により、居宅での介護が困難な場合一時的入所による保護をしています。 町保健福祉課 身体障害者デイサービス事業 自立の促進・生活の改善・身体の機能の維持向上等を図ることができるよう、通所により創作的活動・機能訓練等各種の便宜を提供しています。 巡回相談事業 身体障害者更生相談所や精神薄弱者更生相談所に来所が困難な障害者を対象に医師・看護婦・福祉士・心理判定員等が県下を巡回し、福祉事務所 医学的・心理学的に判定し、手帳交付及び等級変更、補装具の交付等の各種相談と指導を行っています。 福祉事務所
町保健福祉課在宅重度身体障害者訪問診査事業 在宅重度身体障害者に対して、医師・保健婦・理学療法士等を派遣して診査及び更生相談を実施しています。 町保健福祉課 美馬郡心身障害児父母の会事業 美馬郡内の心身障害児をもつ父母がお互いに手をつなぎ合って心身障害児の保健福祉の増進に努めています。 保健所 市町村障害者社会参加促進事業 障害者の自立と社会参加の促進を図るため、点訳奉仕員等養成事業・手話通訳設置事業等を行います。 町保健福祉課
社会福祉協議会
(3)福祉機器サービスの充実
☆課題
- 障害を軽減したり日常生活を容易にする福祉機器の種目の拡大と適用範囲の拡大を図るとともに、制度の周知と普及を進めていく必要があります。
☆施策の方向
- 福祉機器の普及促進を図るため、制度の周知とともに相談体制も整備し、補装具・日常生活用具等の給付を引き続き実施していきます。
- 在宅介護支援センターでは、障害をもつ高齢者をはじめ、家族の介護の負担を軽減するため、介護機器や介護用品の普及、相談指導に応じていきます。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 補装具の給付 身体上の障害を補うための用具の交付や修理を行います。 主な補装具の種目
- 視覚障害…盲人安全つえ・眼鏡点字器義眼
- 聴覚障害…補聴器
- 音声・言語機能障害…人口喉頭等
- 肢体不自由…義肢・義足・義手・装具 車いす・歩行車電動車いす・歩行補助つえ 頭部保護帽等
- 膀胱直腸機能障害…ストマ用装具等
町保健福祉課 日常生活用具の給付事業 在宅の重度障害者(児)の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等を行っています。 主な日常生活用具
- 下肢・体幹機能障害…浴槽・湯沸器 特殊寝台 特殊マット等
- 上肢障害…特殊便器 電動タイプライター 電動ハブラシ ワードプロセッサー
- 視覚障害…電磁調理器 点字タイプライター 音声式体温計・電卓 拡大読書器等
- 聴覚障害…目覚時計 聴覚障害者用通信装置 サウンドマスター 文字放送デコーダー等
- 内部障害…透析液加温器 ネブライザー等
- 共通…火災報知機・自動消火器 緊急通報装置
町保健福祉課
(4)施設サービスの充実
☆課題
- 障害者本人や家族のニーズ(要望)にあった適切な施設への入所と多様なニーズに対応した各種施設の整備充実を図ることも重要な課題であります。
☆施策の方向
- 在宅生活が困難な障害者に対しては、本人及び家族のニーズや障害の状況に応じた施設入所ができるよう指導していきます。
- 西部第1サブ障害保健福祉圏で更生・療護・授産・福祉ホーム等の施設が必要な時に利用できるよう、整備促進を関係機関へ働きかけていさます。
第6節 教育の充実
教育の充実
(1)就学前教育の充実
(2)学校教育の充実
(3)生涯学習の充実
6.教育の充実
☆現状
就学前児童の教育(保育園・幼稚園)については、障害児を受け入れてすべての子どもがお互いに学び合い、生活を豊かにできるよう進めています。学校教育では、小学校3学級・中学校1学級の知的障害児学級を設け、児童・生徒の発達の程度や障害に応じた適正な就学指導に努めています。
(1)就学前教育の充実
☆課題
- 人的配慮や専門的な指導体制を推進するとともに、就学前の障害児をもつ保護者に対する相談体制や受け入れ体制の充実を図ることが必要であります。
- 障害児が社会の構成員として地域で正しい理解と認識を深められるよう、社会経験豊かな地域の人たちと活動を共にする交流教育の充実を図ることが必要であります。
☆施策の方向
- 障害者や高齢者に対し正しい認識を持ち、お互いの立場や気持ちを思いやり、お互いに協力できるよう福祉教育の推進に努めます。
- 保育園・幼稚園での障害児の受け入れに努めます。また、保母等関係者の資質の向上に努めます。
- 障害児が早期から継続して療育や教育相談等の助言や指導が受けられるよう、相談・援助体制の整備に努めます。
- 在宅の重度障害児に対して、保健婦が訪問し、家庭療育に関する助言・指導等に努めます。
(2)学校教育の充実
☆課題
- 障害のある子どもの発達を促進し、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限りの社会参加と自立をめざした教育を推進することが重要なことであります。
- 適正な就学にもとづいて、その障害の種類・程度・能力・適性等に応じた教育を行うことが必要です。
- 小学校・中学校で障害児学級を設けていますが、さらに教育効果を上げていく必要があります。
☆施策の方向
- 障害の実態に即した教育を行うため、本人や保護者の意向を尊重し、積極的に適切な就学指導を引き続き実施します。
- 障害を持つ児童・生徒が安心して学校生活が送れるよう、教育環境や施設の整備改善に努めます。
- 障害者(児)及び保護者の多様な教育相談に対応できるよう、関係機関との連携を深め、相談体制の整備に努めます。
- 障害者(児)に対する正しい理解と認識を深めるため、福祉教育を推進します。
- ボランティア活動指定校での体験学習を通じ、福祉意識の向上を図ります。
- 社会的自立を支援するため、障害の状態に応じた適切な進路指導・相談を引き続き実施します。
(3)生涯学習の充実
☆課題
- 障害者が趣味や教養を高め充実した生活となり、社会参加が促進できるように、生涯学習の機会を広げていく必要があります。
☆施策の方向
- 障害者も障害をもたない人も等しく学習の機会に参加できるよう、教育集会所・公民館・図書館等の施設の改善・整備に努めます。
- 図書館については、資料の充実をはじめ点字図書や弱視者用の大活字図書の充実に努めるとともに公共施設・近隣図書館とのネットワーク化、学校・図書館との連携を図り、利用促進に努めます。
- 課題やニーズにあった講座や講演会の開催等、学習する機会の少ない若い人から高齢者まで誰でも参加できる多様な学習機会を提供します。
第7節 雇用・就業の促進
雇用・就業の促進
(1)雇用・就業の促進
7.雇用・就業の促進
☆現状
障害者雇用に対する事業主の理解と関心が高まり、雇用や就労の状況に着実な改善がみられますが、まだまだ十分とはいえず、多くの障害者が働く場を求めています。平成9年6月1日現在、身体障害者および精神薄弱者の全国平均実雇用率は1.47%、本県は1.66%となっています。(法定雇用率は1.6%)
(1)雇用・就業の促進
☆課題
- 障害者が仕事を通じて自立することは、その社会参加のなかでも最も重要な事項のひとつであります。
- 障害者の雇用促進を図るため、事業主に対する啓発の強化や法定雇用率未達成企業に対する指導及び諸援助制度等の周知を推進する必要があります。
- 一般的就労が困難な障害者も必要な技術を習得して、さまざまなかたちで仕事を通じて社会との係わりを持つことは、自立への第一歩です。福祉的な授産施設・小規模作業所での就労を通じて社会参加を推進していく必要があります。
- 家庭を離れて就労することが困難な障害者に対しては、就労の場の確保を推進していく必要があります。
- 障害者の能力や障害に応じた雇用・就業について、正しい理解と認識を深めるために、啓発活動の推進を図っていく必要があります。
- 社会福祉協議会に設置しているシルバー人材センターにおいても、就労の推進を図っていく必要があります。
- 社会自立をめざした教育については、身辺生活の自立から職業自立に至るまで教育内容を幅広く用意し、その人に応じた指導を展開することが必要であります。
☆施策の方向
- 障害者の雇用を推進するため、広報紙等を利用し、雇用促進月間(9月)を中心に啓発を促進します。
- 脇町公共職業安定所と連携し、就職を希望する障害者の就労の促進に努めます。そして事業所に対して障害者雇用の推進を図り、法定雇用率が達成できるよう働きかけます。
- 自立生活を助けるため、自宅から通える福祉的就労の場として、心身障害者小規模通所作業所の設置に向けて関係機関に働きかけます。
- 職業人として自立を図ることを目的とした公共職業訓練や作業環境に適応することを容易にするための職場適応訓練を支援し、その啓発に努めます。
- 家庭を離れて就労することが困難な障害者に対しては、在宅での就労を支援します。
- シルバー人材センターでの登録者の確保と就労の促進に努めます。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 公共職業訓練 職業に必要な技能を習得することにより、就職を容易にし、職業人として自立を図ることを目的とした訓練を行っています。
- 訓練期間6ヵ月~2年
- 訓練生には、訓練手当が支給されます。
月額12万~13万円- 訓練費用は無料です。
公共職業安定所 職場適応訓練 作業環境に適応することを容易にするため、都道府県が民間事業所に委託して訓練を実施しています。
- 訓練期間6ヵ月(重度心身障害者は1年)
- 訓練生には、訓練手当が支給されます。 月額平均約12万~13万円
- 事業主には、訓練生ひとりにつき月額23,300円(重度24,300円)支給されます。
シルバー人材センター 概ね60歳以上の多彩な技能・知識・経験をもった人が会員となり臨時的かつ短期的な仕事を一般家庭や民間事業所等から、請負または委任の形式で有償により、社会参加をして地域社会に貢献することを目的としています。 主な仕事
公園清掃・福祉家事サービス・集金・あて名書き・大工仕事・植木手入れ・和洋裁等社会福祉協議会 リサイクルプラザ 廃棄物のうち再生可能な家具等を修理販売します。高齢者や障害者の雇用促進を図ることを目的としています。 町保健福祉課
第8節 スポーツ・レクリェーション及び文化活動の支援
スポーツ・レクリェーション及び文化活動の支援
(1)スポーツ・レクリェーションの促進、文化活動の支援
8.スポーツ・レクリェーション及び文化活動の支援
☆現状
障害者による体育大会・ゲートボール大会・お楽しみ会・日帰り旅行などが行われており、参加者が多く盛況をみています。
(1)スポーツ・レクリェーションの促進、文化活動の支援
☆課題
- 障害者がスポーツ・レクリェーション及び文化活動に参加することは、自立と社会参加を促進するだけでなく、生きがいのある豊かな生活を送る上で大変重要であります。
- 多くの障害者が参加できるよう条件整備をすすめていく必要があります。特に精神障害者については、当事者同志及び地域住民との交流を深める機会にもなります。
☆施策の方向
- 障害者と障害を持たない人が、ともにスポーツ・レクリェーション・文化活動に参加ができるよう努めます。
- 障害者団体が開催するスポーツ・レクリェーション・文化活動を支援します。
- 障害者に配慮した各種体育施設等の改善に努めます。
- 文化活動の主催者に対し、障害者に配慮した行事運営についての理解と協力を得られるよう努めます。
- 障害者が参加するスポーツ・レクリェーション・文化活動等の移送・介護には、ボランティアやガイドヘルパー(付き添い介護)等の確保に努めます。
第9節 総合的な福祉のまちづくり
総合的な福祉のまちづくり
(1)福祉のまちづくり事業の推進
(2)都市計画制度・都市計画事業等による取り組み
9.総合的な福祉のまちづくり
☆現状
障害者や高齢者に対し、安全で利用しやすいものとなるよう、これまで公共施設の整備改善に努めてきました。しかし、まだ十分な対応となっていない現状であります。また、日常の運動や休息・遊戯などのレクリェーション活動の場として利用できる多目的体育館・球技広場・多目的広場については順次整備しています。
(1)福祉のまちづくり事業の推進
☆課題
- 障害者が安心して快適に生活できる基本的要件は、「安全性」「利便性」「快適性」が確保されていることであり、より積極的な社会参加ができるような総合的な「福祉のまちづくり」を実現することが求められています。
- 住宅や公共施設・公共交通機関が、障害者や高齢者にとって安全で利用しやすい構造であるとともに、あらゆる人々がふれあいを通じて交流できることが大切であります。
- 安全かつ自由に移動し活動の幅を広げられるよう、障害者に配慮した移動、交通手段を整備するとともに、施設や道路の段差の解消などの推進が必要であります。
☆施策の方向
- 障害者や高齢者を含むすべての町民が、安全で快適な生活を送ることができるよう、総合的な福祉のまちづくりを推進します。
- 「徳島県やさしいまちづくり条例」に基づき、役場や公民館などの建築物、道路などの整備・改善に努めます。
- 「やさしいまちづくり推進月間」(12月)を中心に、やさしいまちづくりの推進について町民に対する普及・啓発活動に努めます。
(2)都市計画制度・都市計画事業等による取り組み
☆課題
- 街路・公園・下水道等の都市施設の整備が長期計画に基づき進められていますが、障害者にとって利用しやすいものとなるよう求められています。
- 障害者が社会の一員として社会参加できるよう、道路構造に工夫を凝らした街路整備を進めていく必要があります。
☆施策の方向
- 町民の憩いの交流の場として、障害者に配慮した利用しやすいやさしさと安全性の高い快適な空間づくりに努めます。
- 道路・公園等の整備推進については、障害者の安全・利便に即したものとなるよう、関係機関の連携のもと一層の実効性の確保に努めます。
第10節 障害者向け住宅の供給
障害者向け住宅の供給
(1)障害者向け町営住宅の供給
(2)民間住宅の住宅改造の促進
■改造場所1
玄関上がり口部分
- 奥行きの小さな式台を幅の広いものに取り替え、上がり下りしやすいように手すりを設置
- 玄関がもっと広いと段数を増やしたり、スロープをつけられたのだが。水平に手すりを設ける方法も有効
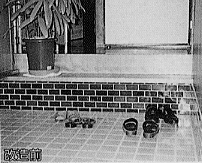 改造前 |
 改造後 |
10.障害者向け住宅の供給
☆現状
最近の住宅建築においては、バリアフリー化に向けた構造に取り組まれており、障害者や高齢者にとっては生活しやすくなりつつあります。既設住宅の改造についても、住宅改造助成制度や生活福祉資金貸付制度等の利用により徐々に改善されています。
(1)障害者向け町営住宅の供給
☆課題
- 障害者の日常生活に便利な立地条件、車いすの利用等に配慮した障害者向け町営住宅の整備を図っていく必要があります。
☆施策の方向
- 今後建設する町営住宅については、床段差の解消や手すりの設置等、障害者や高齢者に配慮した住宅となるよう質的・量的な整備をします。
(2)民間住宅の住宅改造の促進
☆課題
- 障害者が、家庭での自立を助け介護者の負担を軽減するためには、生活に適応できるよう住宅改造を促進していく必要があります。
☆施策の方向
- 重度身体障害者住宅改造助成制度・生活福祉資金貸付制度・住宅金融公庫割増融資制度などの補助制度や融資制度の利用を促進し、障害者の生活環境の改善を支援します。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 重度身体障害者住宅改造助成 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用に対し助成します。ただし、身障手帳の交付を受けた1級または、2級の視覚障害者および肢体不自由者であり、かつ、その者の属する世帯が所得税非課税世帯以下の者。 町保健福祉課 生活福祉資金の貸付 障害者世帯等の経済的自立と生活の安定を図るため、生業費・住宅改修費・療養費等の必要な資金を低利で融資。ただし、低所得世帯・精神薄弱者の属する世帯および日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯。 社会福祉協議会 住宅資金貸付優遇措置 身体障害者の1級~4級、重度の知的障害者と同居する世帯への割増貸付。 住宅金融公庫
第11節 建築物等の整備
建築物等の整備
(1)官公庁施設の整備
(2)民間建築物の整備
11.建築物等の整備
☆現状
公共施設においては、エレベーター・車いす使用者用トイレ・車いす使用者用駐車場・段差のスロープ化等順次整備しています。民間建築物については、出入口の段差の解消や障害者対応のトイレ等公共施設と同様の整備が図られつつあります。
(1)官公庁施設の整備
☆課題
- 公共的な施設について、障害者に配慮した施設内容や構造を整備していく必要があります。
- エレベーター・段差の解消・車いす使用者用トイレの設置・車いす使用者用駐車場の確保等順次整備していますが、さらに計画的に整備を進めていく必要があります。
☆施策の方向
- 「徳島県やさしいまちづくり条例」に基づき、公共的施設の構造や内容が次のようなものとなるよう順次推進します。
- エレベーターの設置
- 誘導表示・案内板・手摺り・スロープの設置
- 車いす使用者用駐車場施設の確保
- 車いす使用者用トイレの設置
- 人と車の動線の分離
- 通行の支障となる段差の解消
- 充分な通路幅の確保
- 滑りにくい床材料の使用
- 危険個所への注意喚起
(2)民間建築物の整備
☆課題
- 多くの人が利用する民間の建築物についても、障害者が円滑に利用できるようなものとなるよう、バリアフリー化を促進していく必要があります。
☆施策の方向
- 町民が多く利用する民間事業所に対し「ひとにやさしいまちづくり」整備・融資・補助制度の周知に努めます。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 やさしいまちづくり整備モデル資金貸付金 民間の建築物に車いす用トイレやスロープ等を設置する際に必要な資金を低利で融資。 県保健福祉部障害福祉課 ひとにやさしいトイレ整備モデル事業費補助金 県内の主要幹線道沿線等に、車いす使用者をはじめ、誰もが使用できるトイレの設置を進めるための補助。
第12節 移動・交通手段の整備
移動・交通手段の整備
(1)移動手段・歩行空間の整備
12.移動・交通手段の整備
(1)移動手段・歩行空間の整備
☆課題
- 障害者の屋外での移動を容易にするため、車道と歩道を分離したり既設歩道についても段差をなくし、また視覚障害者誘導ブロックの設置、階段のスロープ化等を整備していく必要があります。
- 公共施設等は、車いす使用者用駐車場・車いす使用者用トイレ・手摺り・スロープ化等の整備を推進する必要があります。
- 町道については、一部は歩道が整備改善されていますが、なかには、幅員も狭く路面も荒れている状態もあります。今後、順次改良し整備していく必要があります。
☆施策の方向
- 安全で快適な通行を確保するために、町道の段差の解消・視覚障害者誘導ブロックの設置・階段のスロープ化等に努めるとともに、県道・国道については関係機関に要望します。
- 公共施設の車いす使用者用駐車場・案内板・車いす使用者用トイレ等、順次整備・改善に努めます。
- 障害者の移動手段として自家用車の果たしている役割が大きいことから、身体障害者用自動車改造費助成、自動車操作訓練費の助成制度等の周知に努めます。
- 重度障害者の移動を支援するため、リフト付きワゴン車・公営バスの整備を今後検討します。
- 視覚障害者用信号機の設置について・関係機関に要望します。
☆主要事業
事業名 内容 窓口 自動車改造助成事業 重度の上肢・下肢・体幹の機能障害者が所有し運転する車の改造に要する経費の一部を助成します。 1件100,000円以下福祉事務所又は町保健福祉課 自動車操作訓練費助成事業 おおむね4級以上の障害者が自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費の一部を助成します。 限度額20,000円
第13節 防犯・防災体制の確立
防犯・防災体制の確立
(1)防犯・防災体制の確立
13.防犯・防災体制の確立
☆現状
在宅障害者の非常時・災害時等における対応能力を高めるために、パンフレット等の配布や広報・オフトーク通信を利用して啓発に努めています。
(1)防犯体制・防災体制の確立
☆課題
- 災害時の障害者の避難体制の強化や関係機関等との連携によるネットワークの確立が求められています。
- 障害者や高齢者に配慮した防犯・防災対策の確立が求められています。
- 緊急時のオフトーク通信・非常通報装置等の設置促進を図る必要があります。
☆施策の方向
- 障害者に対して、防犯・防災意識の向上を図るとともに、非常時・災害時における的確な対応能力を高めるために啓発に努めます。
- 緊急時に迅速な対応がとれるように、緊急通報装置・火災警報器・自動消火器等の日常生活用具の給付の啓発に努めます。
- 避難・誘導が行えるよう防災行政無線を含めた情報システムの一層の充実を図ります。
- 町内で消防訓練を実施するとともに、婦人防火クラブなど自衛消防団の育成を図り、障害者に対する緊急時の避難・誘導などを行うボランティア団体の確保・支援に努めます。
第14節 国際交流・国際協力の促進
国際交流・国際協力の促進
(1)国際交流・国際協力の促進
14.国際交流・国際協力の促進
(1)国際交流・国際協力の促進
☆課題
- 今日の障害者活動は、国際的な視野に立った活動が求められてきており、国際交流をすすめていく必要があります。
- 外国との交流を通じ、諸外国の障害者との交流を深めていくことが望ましいことです。
☆施策の方向
- 国際理解を深めるため、啓発・情報提供に努めます。
- 障害者が国際感覚を身につけて活躍できるよう支援します。
(参考)
脇町第4次総合振興計画による障害福祉関係事業の実施プログラム
施策名 事業名 事業内容 4.保健・医療サービス
(2)在宅支援体制の強化- 「保健センター」新設 5.福祉サービス
(2)在宅福祉サービスの充実- 「在宅介護支援センター」新設 6.教育 (3)生涯学習 社会教育施設整備事業
- 中央公民館整備
(2)学校教育の充実 公立学校施設整備費国庫補助事業
- 江南小校舎改築
- 江北小校舎改築
9.総合的な福祉のまちづくり
(2)都市計画制度
都市計画事業等による取り組み地域福祉推進特別対策事業(やさしいまちづくり事業) 脇町福祉センター改修工事 都市計画事業 都市マスタープランの策定 都市公園事業
- 新町地区
- 拝原地区
公共下水道事業 - 農業集落排水事業 井口東・別所浜 河川整備事業 親水公園整備費 12.移動・交通手段
(1)移動手段
歩行空間の整備交通安全施設等整備事業 カーブミラー・ガードレール 県道・幹線道路の整備 - 13.防犯・防災対策
(1)防犯体制
防災体制の確立消防水利施設整備事業 防火水槽・消火栓整備
この事業実施プログラムは、脇町第4次総合振興計画を抜粋しています。
資料編
1.脇町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、脇町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
- (1)計画案の策定に関すること
- (2)その他計画策定に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2.委員は、次に掲げる者のなかから町長が委嘱する。
- (1)障害者団体の代表者
- (2)福祉、医療関係者
- (3)学識経験者
- (4)関係行政機関職員
- (5)その他障害者施策に見識を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
- 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
- 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
- この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
- この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。
脇町障害者計画策定委員名簿
区分 役職名 氏名 障害者団体の代表者 身体障害者会会長 梶浦一末 知的障害者会会長 松尾靜雄 福祉関係者 小星園園長 工藤徳明 樫ヶ丘育成園園長 西内義卓 社会福祉協議会事務局 小笠勝雄 身体障害者相談員代表 宇山サダ子 精神薄弱者相談員代表 原 廣 ホームヘルパー 石井富三子 医療関係者 医師会代表 佐藤俊雄 精神病院代表 桜木章司 学識経験者 議会文教厚生常任委員長 小林一郎 民生委員児童委員協議会総務 馬場照市 関係行政機関職員 助役 故島常男 教育長 後藤忠雄 保健福祉課長 内田泰博 その他見識者 - 尾方敬二
木下豊繁
藤岡一雄
2.脇町障害者計画策定作業部会設置要綱
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、脇町障害者計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 部会は、助役及び別表1に掲げる課(事務局)の長にある者をもって充てる。
(会長)
第3条 部会に、会長及び副会長を置く。
- 会長は、助役をもって充てる。
- 副会長は、保健福祉課長をもって充てる。
(会議)
第4条 部会の会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
- この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
- この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。
別表1
総務課・企画課・住民課・商工観光課・耕地課・建設課・教育委員会事務局都市計画室・脇町社会福祉協議会・保健福祉課
主題:
脇町障害者福祉計画 No.2
47頁~103頁発行者:
脇町役場保健福祉課編集:
脇町役場保健福祉課発行年月:
平成10年3月文献に関する問い合わせ先:
脇町役場保健福祉課
徳島県美馬郡脇町大字脇町1303番地の3
電話 (0883)52-1111(代)