三野ノーマライゼーションプラン
No.2
(MINO normalization PLAN)
―お互いを思いやり尊重しあって仲良く共生できるまち・三野―
平成10年3月
三野町
第3編 基本計画
第1章 理解と交流の促進
第1節 普及・啓発活動の充実
「現状と課題」
町広報での「障害者の施策」や「三野町総合福祉・老人福祉大会」の掲載、県パンフレット等の配付を行うとともに、保育所での育児講座、学校での障害者問題を考える機会、高齢者の健康と生きがいづくり事業などを通じ、障害者理解の促進・ふれあい機会の拡充を進めていますが、全般には十分とは言えない状況にあります。
障害者に対するアンケート調査(平成9年本町分)では、障害者への理解が深まったと考える人が半数程度と以前に比べ改善している様子が伺えますが、精神障害者の社会復帰ニーズ調査(平成9年池田保健所)での一般住民向けアンケートでは、啓発活動の必要性を答えた人が64.8%となっており、今後、全ての人を対象にノーマライゼーション推進のための正しい知識と理解の普及をめざすことが必要です。
また、障害者に対する広報活動としては、現在のところ各障害者団体等を通じての実施が中心ですが、点字や音声等の手段による情報提供を促進していく必要があります。特に、障害者福祉サービスの利用方法については、県発行のしおり等を配付していますが、生活圏の中で利用できるサービス内容や施設など具体的な情報提供を促進する必要があります。
「基本方針」
「ノーマライゼーション」の理念を実現するために必要な啓発活動を行うとともに、障害者への情報提供・広聴体制を強化していきます。
「主要施策」
1.広報活動の充実
○「広報みの」等を積極的に活用し、障害や障害者について町民の正しい理解が得られるよう努めるとともに、障害者理解のためのパンフレット等の提供を進めます。
○市町村障害者社会参加促進事業の広域的な導入により、ボランティアの育成を進め、点字広報や声の広報などの発行に努めます。
2.障害者の日等の普及
○障害者の日(12月9日)の周知徹底を進めます。また、「障害者のつどい県民大会」など県事業への参加を継続するとともに、身近な交流イベント等の開催に向け努めます。
3.広聴活動の推進
○アンケート調査の実施・相談窓口の開設等により、障害者を含む多くの町民の意向を把握し、障害者福祉施策に反映させます。また、障害者施策の計画や実施にあたっては障害者の参加のもと進めていきます。
4.新しいメディアによる情報提供の推進
○パソコンのマルチメディア化などに伴い、インターネット等を利用した画像情報なども含め、効果的な情報提供手段について研究していきます。
5.障害者向け広報パンフレット等の作成
○わかりやすいPR活動を行うために、教育・保健・医療・福祉関係機関と連携し、事業内容や利用方法等についてのパンフレット等の作成配布に努めます。
第2節 福祉教育等の充実
「現状と課題」
社会福祉への理解の推進を図るため、県社会福祉協議会より学童・生徒のボランティア活動普及事業に各校が順次指定されています。保育所、小学校、中学校では、地域の老人クラブとの交流・老人福祉施設への訪問などの実施、同和問題学習での障害者問題への取り組み等により、高齢者や障害のある人への理解の醸成や「ともに生きる」ことの意味などを考える機会を設けるなど、子どもの時期からの福祉教育の場の確保に努めています。
今後、池田学園や国府養護学校池田分校等との交流教育を進めるとともに、車いす・アイマスクなど体験を通じた学習機会の拡充、本町での障害児学級を通し、身近なふれあいの機会を拡充していくことが望まれます。
また、生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動においては、障害のある人が参加できるよう条件整備を進めるとともに、日常的にふれあう機会を拡充し、精神保健講座など学習機会の提供や社会福祉協議会による福祉教育の展開等を進めていくことが必要です。
「基本方針」
児童・生徒をはじめとして、全町民が、障害者(児)や高齢者に対して正しい認識を持ち、お互いの立場や心情を思いやり、相互に協力しあう精神や態度が育めるよう、福祉教育等を推進していきます。
「主要施策」
1.心身障害者(児)理解教育の充実
○ボランティア活動の促進等により、社会福祉施設での体験学習や障害児との交流教育の促進を図ります。また、車いす体験等を通じた障害者(児)理解を進めます。
2.関係機関との連携強化
○全世代にわたって、家庭・学校・職場・地域社会の様々な場面において、福祉教育を推進するため、保健・医療・福祉・教育等の行政機関や社会福祉協議会との情報交換を密にし連携を強化します。
3.福祉教育の普及
○障害者(児)に関する教育カリキュラムを作成し、社会福祉協議会の事業において、教育関係者の理解のもと、福祉教育の機会を増やしていきます。また、町職員に障害者理解を深めるため、研修に努めます。
4.児童・生徒のボランティア活動の普及
○児童・生徒の社会福祉への理解と関心を深めるため、学童・生徒のボランティア活動普及協力校を指定し活動を推進します。
第3節 交流・ふれあいの促進
「現状と課題」
障害のある人の社会参加や地域交流の促進を目的に、各種スポーツ・レクリエーション・文化活動の参加機会の拡充を進めています。県や郡単位の各種スポーツ・レクリエーション大会や講習会などへの参加とともに、町身体障害者会ではゲートボール、アーチェリー、グランドゴルフ等の活動を実施しています。また、郡心身障害児父母の会「あゆみ会」のサマーキャンプ、郡精神障害者家族会「やまなみ会」のお花見、「池田博愛会」の博愛まつりなど広域的障害者団体や施設による行事が活発に行なわれています。
しかし、これらのスポーツ・レクリエーション活動、地域の行事や祭事についても、参加したことのない人が多く、今後、各種活動への参加呼びかけや、障害者団体等による活動を支援していくことが必要です。また地域行事への参加促進に向けて、近隣住民のネットワーク形成を進める取り組みが必要です。
なお、現在、ボランティアには、町婦人連合会のひとり暮らし高齢者の食事サービス協力や母子保健推進委員等による活動、本町及び手をつなぐ育成会「つくし会」で開始した作業所へのボランティア活動等が実施されています。さらに、障害者団体によるボランティア活動も行なわれています。障害者を対象としたボランティア活動は、現状では充分とはいえません。
今後、近隣単位やボランティアセンター活動によるグループ・団体単位のボランティア活動の促進をめざし、ボランティア活動メニューや参加機会の拡充をはじめ、障害者のコミュニケーション手段の拡充等に資する専門的なボランティアの確保に努めることが必要です。
「基本方針」
○障害者が積極的に、文化・スポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう条件整備に努めるとともに、障害を持たない人との交流を促進します。
○ボランティア活動の推進を図り、活動の質的拡大に努めます。
「主要施策」
1.スポーツ・文化・レクリエーション事業の推進
○障害者の参加へのバックアップ体制を整備しつつ、だれもが参加できるスポーツ・レクリエーション大会・生涯学習推進事業による講座・教室等を開催します。また、各教育クラブにおいても障害者が参加できるよう配慮を進めます。さらに、県・郡・社会福祉協議会、障害者団体等の開催するスポーツ・レクリエーション活動の情報提供を促進します。
2.地域行事・祭事への参加の促進
○地域行事等への参加の呼びかけをはじめ、参加支援を図るため近隣住民のネットワーク形成を進めます。また、地域の役員等への障害者の登用を促進し、地域社会に入っていきやすい雰囲気づくりに努めます。
3.家族会・障害者団体の交流会等の促進
○会員以外も含め各障害者団体等で実施されている活動の周知を図るとともに活動の促進や相互連携等に向けた支援を進めます。
4.ボランティア活動の推進
○ボランティア活動の活発化をめざし、各種のボランティア活動の展開づくりに努めます。
第2章 教育・育成の充実
第1節 就学前教育・療育の充実
「現状と課題」
障害児が生き生きと個性を発揮し、その能力を最大限に伸ばしていくには、成長のあらゆる段階において、障害児一人ひとりの障害の状況に応じた多様な教育・育成の場と機会が必要です。
本町の障害児保育については、家庭との連携のもとに個々に応じた保育に努めています。また、幼稚園では、現在のところ障害児の入園はありませんが、手話による童謡の練習などを行いつつ、思いやりのある子を育む保育に努めています。
このほか郡内には精神薄弱児通園施設「池田療育センター」や同施設の外来療育相談事業(週1回程度)・訪問療育などがあります。
なお、母子保健サービス分野では、障害の早期発見・早期療育を図るため健康診査等の実施や心身障害児への訪問指導を行うとともに、県の肢体不自由児巡回療育相談、保健所の発達相談事業や障害児を持つ保護者を支援するため心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」への参加へとつなげています。さらに、町教育委員会による教育相談や就学指導、県巡回就学相談などが実施されています。
今後、幼児の発達段階や障害状況に適した教育・育成機会が提供されるよう、また保護者の支援も含め、地域の中で共に育っていくことのできる条件を整備することが必要です。このため、保育所・幼稚園においては受け入れ体制の充実はじめ、個々の障害児の発達に即した保育を進めるとともに、保健サイドからの地域での育児支援機能の拡充、保健所や医療機関・福祉施設・学校など関係機関の連携強化が求められます。
「基本方針」
就学前障害児の適切な療育・教育を進めるとともに、地域との関係の中で、安心して子育てができるよう条件整備を進めます。
適切な就学ができるよう、就学前からの教育相談の充実を図ります。
「主要事業」
1.障害児保育の促進
○保育所・幼稚園における障害児受け入れ体制を整備するため、保母の加配や専門研修をはじめ、施設・設備の充実、民間施設への助成の促進に努めます。障害児の保育にあたっては家庭・専門機関との連携を強化し、個々の障害児の発達に即した指導を進めます。また、母子保健事業や保育所による育児講座での相談機能を強化するとともに、通園施設等に通う子も含めた地域での交流の拡充を進めます。
2.心身障害児通園事業の利用促進
○在宅障害児の日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等を行う通園事業(池田療育センターで実施)の利用促進、保育所などの既存施設の活用も図りながら事業を実施します。
3.障害児就学前教育相談の充実
○保護者・障害児が早期からの指導援助を受けれるように、保健・医療・福祉など各種相談事業の充実を図るとともに、教育委員会等による訪問相談の実施など相談体制を強化します。
第2節 学校教育の充実
「現状と課題」
平成9年現在、本町の小学校では障害児学級が開設されていません。このほか障害児教育諸学校としては、知的障害児の養護学校である国府養護学校池田分校をはじめ、県内に8校2分校が設置されています。
町教育委員会では、障害を持つ児童・生徒の発達の程度や、障害の程度に応じた適正な就学指導に努めていますが、就学前の障害児を持つ保護者には就学や、学校生活に不安を持つ人も少なくありません。また、人数が少ない場合などで障害児学級の設置が困難となり、地元の学校に就学しにくい面もあります。
一方、三好郡内学齢児の保護者を中心とした障害児アンケート(平成8年池田保健所)では、学校に望むこととして、日常生活面で自立できるような教育内容の充実や障害児専門教師の確保、地元の障害児学級の設置希望などがめだっています。
今後、県内障害児教育諸学校への通学が困難という地理的条件も考慮し、該当学齢児がいる場合は、障害に適した教育内容や指導方法の研究、専門教員の確保・教職員研修の促進などを進めていくことが必要です。また、学校の施設環境に関しても、充分配慮したものへと整備し、全ての児童・生徒が安心し楽しく学校生活が送れるような条件を整えていくことが重要です。義務教育学校卒業後については、県下の養護学校高等部(8校2分校)や一般の高等学校への就学、職業能力開発校、就業等といった多様な進路を選択することになり、保護者の大きな心配事となっています。このため、一般高等学校への就学の拡大をはじめ、スムーズな就業や生活の場の確保をめざし、関係機関との一層の連携が求められます。
「基本方針」
児童・生徒が能力を最大限に伸ばし、充実した学校生活が送れるよう教育内容や相談体制の充実を図ります。
職業教育の開発・実践と、労働及び福祉の分野と連携しながら障害の実態に応じた進路指導に努めます。
「主要施策」
1.教育方法・内容の充実
○障害児がその可能性を伸ばし、将来、自立した生活を送ることができるよう、日常生活訓練の基本を習得するための教育を進めます。また、障害児学級の開設を促進するとともに通級等による指導など内容の充実に努めます。
2.就学相談・指導体制の充実
○障害児一人ひとりの実態に即した就学を進めるため、本人・保護者の意向を尊重しながら適切な就学指導に努めます。また、重度障害児の教育機関を保障するよう努めます。多様な教育相談に対応できるよう、県の巡回教育相談の活用等、関係機関との連携を深め、教育委員会において教育相談体制を整えます。
3.障害児教育・教育課程研究の推進
○障害児担当教職員の資質向上を図るため、各種研修会への参加を促進する。
4.学校施設・設備の改善
○障害を持つ児童・生徒が安心して楽しく学校生活が送れるよう、スロープ・手すり・車いす専用トイレ等の改善に努めます。
5.進路指導の充実
○池田公共職業安定所、県障害者職業センター及び各企業や作業所・施設等関係機関との連携を強化し、進路の拡大及び進路指導の充実を図ります。
第3章 雇用・就業の促進
第1節 職業能力の開発
「現状と課題」
障害者の就業や職業的自立を促進するためには、職業能力の開発が重要です。現在、徳島障害者職業センターや県職業能力開発校での職業訓練、養護学校高等部での職業教育をはじめ、福祉施設・作業所による取り組みが行われています。また、精神障害者の就労を促進するため、郡内の民間8企業の協力を得て、池田保健所が通院患者リハビリテーション事業を実施しています。
このほかに、民間企業に委託して行う職場適応訓練などもありますが、全般に、協力事業所の開拓が必要な段階にあります。今後、障害者の働く場の開拓とともに、県機関等による職業訓練の促進や福祉施設・共同作業所における職業訓練機能の確保などを促進していくことが望まれます。
「基本方針」
「主要施策」
1.徳島障害者職業センター等関係機関との連携強化
○徳島障害者職業センターをはじめ、池田職業安定所等との連携を強化し、機関の紹介等を進めます。
2.通院患者リハビリテーション事業等の促進
○池田保健所・池田職業安定所などと連携し、通院中の精神障害者の社会適応訓練などを実施する通院患者リハビリテーション事業、や職場適応訓練などの協力事業所の開拓に努めます。
第2節 雇用の促進と安定
「現状と課題」
障害者の雇用が義務づけられている民間企業における法定雇用率1.6%に対し、県全体は1.76%(平成8年6月)まで上昇しています。しかし、雇用率未達成企業が45%雇用企業数自体が280社と少ない状況にあります。
また、公共団体の法定雇用率は2%ですが、現在のところ、本町では5.38%となっています。
一方、障害者アンケートからは、本町の回答者のうち福祉的就業も含め仕事をしている人は1/3程度、また広域的には就業年齢(18歳~64歳)の人で、仕事をしている人が4割程度となっています。その内容としては家の仕事が約5割を占めており、企業等へ就業している人はあまり多くないのが現状です。
現在、障害者の雇用を促進するための施策としては、池田公共職業安定所が窓口となり、特定求職者雇用開発助成制度をはじめ障害者雇用継続助成金や合同求人選考会などにより、障害者雇用協力事業所の拡大、職場の斡旋・紹介・相談業務を実施しています。
今後、県機関との連携を強化しながら、町内事業所への障害者雇用優遇諸制度の周知と協力事業所の拡大に努めるとともに、障害者が働きやすい職場環境づくりを進めることが必要です。また、町は、民間事業所に率先し障害者雇用を促進すべき立場にあり、計画的な障害者の採用を進める必要があります。
「基本方針」
企業に対し、障害者雇用の促進を図り、法定雇用率が達成できるよう働きかけます。
障害者の就労相談窓口を設けニーズにそった就労の促進を図ります。
「主要施策」
1.雇用啓発事業の重点的推進
○障害者の雇用について、正しい理解と認識を深めるために、広報紙等を活用し啓発活動をより一層推進します。また、パンフレット等の配布、県主催の巡回キャンペーン等の周知を図ります。
2.公共団体等での雇用の促進
○町における障害者雇用を促進するとともに、社会福祉協議会など公的団体を含め、障害者の職域開発や多様な就業形態の開発を進め、雇用拡大に努めます。
3.企業に対する指導の強化
○池田公共職業安定所と連絡を密にしながら法定雇用率未達成企業に対し、雇い入れに関する指導援助を強化し、未達成企業の解消に努めます。また、職場適応訓練制度の導入促進などを通し、企業側の受け入れ能力を高める取り組みを進めます。
4.障害者に対する就業相談、指導の充実
○障害者に対しての就業相談会の実施・指導等を池田公共職業安定所と協力して開催します。また、町内でのパート・アルバイト情報の収集・流通等を検討するなど、多様な就業機会の確保を進めます。
第3節 福祉的就労対策の充実
「現状と課題」
一般企業等への就業が困難な障害者についても、様々なかたちで仕事を通じて社会との係わりや、職業に就くために必要な技術等を習得する場が必要です。
三好郡精神障害者家族会(やまなみ会)等により、平成2年には「すずらん共同作業所」(山城町)が、平成3年には三好町において「末広共同作業所」が開設され、本町からの通所者には交通費の助成をしています。これら精神障害者小規模共同作業所では、地域で自立した生活を送るために、仲間づくりの輪を広げることや、生活リズムを整えたり、簡単な作業を指導したりしています。
また、平成7年度より、本町及び三野町手をつなぐ育成会(つくし会)により、作業所機能をもつ日中の集いの場を開設し、現在のところ4人程度で運営をはじめています。知的障害者や身体障害者のための小規模作業所・授産施設は広域的にも設置されておらず、精神障害者小規模作業所についても本町からの通勤等を考えた場合、不十分な状況にあります。
今後、送迎手段等も考慮しながら自宅から通うことのできる地域において、福祉的就業の場を確保していくことが必要です。
このため、近隣町や広域市町村圏、関係団体との協議の中で、地域的な配分や補助制度の活用等を留意した上、設置に向け準備を進めることが必要です。
また、自宅の仕事を希望する人が相当数いますが、これに対する援助は現段階ではほとんどない状態です。今後、共同作業所等での授産事業の確立や福祉施設での作業訓練、在宅就業の促進など就業多様性を拡大するため、製品受注・手作り作品の開発、販路の確保などをめざし、関係諸機関との連携の中で、総合的に取り組んで行くことが望まれます。
「基本方針」
障害者が、その適正と能力に応じて就労できるように就労支援の充実を図ります。
「主要施策」
1.福祉的就業の場の拡大
○一般就業が困難な障害者に向け、心身障害者小規模通所作業所・授産所、精神障害者小規模作業所等の設置を進めるため、障害者団体や近隣・広域町村、福祉施設との協議の上、町単独・広域設置の両面から検討します。なお、本町における作業所については、障害の枠にとらわれない運営及び障害者デイサービスセンター等拠点施設との一体的運営・整備等の可能性について、関係諸団体・機関と研究を重ねるとともに、短期的には指導員の確保や福祉施設のバックアップ体制の確立などに努めていきます。
2.授産事業への支援
○町内・広域事業所・農家等からの受託作業、公共施設等の清掃等作業情報が円滑化するよう広域的な調整システムの確立を研究します。また、手作り作品等を含めた独自授産品の生産を促進するともに、各福祉施設等との相互委託販売制度の導入や福祉の店の設置支援などを通し、安定した授産事業の確立に努めます。
3.通所手当ての支給促進
○小規模作業所等の通所者支援に向け、交通費の半額補助を継続します。
4.自営業に対する資金援助の検討
○操業支援融資、運転資金等を低利で貸付けるなど、税制面を含めての援助を検討します。
5.障害者雇用企業設立への支援
○広域町村・福祉施設等との連携の上で、広域的な障害者雇用企業(第三セクター等)の組織化について検討していきます。
第4章 保健・医療の充実
第1節 障害の早期発見・早期療育の推進
「現状と課題」
障害の発生予防や早期発見・早期療育、健康づくりについては、大きくは母子保健と老人保健分野に分けられます。特に、平成9年度からの母子保健事業の市町村実施に伴い、ライフステージに沿った包括的健康づくりの確立が必要となっています。
母子の健康づくりとしては、妊婦健康診査や母親学級をはじめ、各期の健康診査・相談事業・訪問指導を実施し、経過観察等が必要な場合などには県・保健所による乳幼児発達相談指導事業・育成医療給付・心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」等へとつなげています。また、障害の発生を予防するためマススクリーニング検査を実施しています。一方、障害の早期発見・療育につなげる健康診査については、未受診児もあり、全員受診に向けての取り組みを必要としています。さらに、病気や障害をもつ小児への一貫した支援を促進するため、学校保健や関係機関との連携強化の中で療育システムの強化を図るとともに、全ての母子が安心し共に子育てができるような地域条件の整備に向け、母子保健推進委員等の協力のもと育児支援機能の強化を必要としています。
成人・老人保健面では、40歳以上(一部30歳以上)を対象に、各種の健康教育・健康相談・健康診査を実施し、脳卒中などの後遺症による後天的障害の発生予防に努めています。今後、特に日常生活の改善を図り生活習慣病の予防をめざした、取り組みを強化していくことが必要です。
「基本方針」
障害の早期発見・早期療育を図るため、母子保健対策を総合的に推進します。
健康教育を推進し、生活習慣等による疾病・障害の発生を予防します。
「主要施策」
1.母子健康診査事業の充実
○妊婦に対し、母子健康手帳の交付・健康診査を実施します。未受診者に対する対策を充実し、妊婦の健康管理を徹底します。また、乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導及び措置を行います。
- 妊婦一般健康診査
- 妊婦超音波検査
- 乳児健康診査(4カ月・7カ月)
- 1歳半健康診査
- 2歳児健康診査
- 3歳児健康診査
- 股脱健診
- 同 精密健康診査
- 妊婦B型肝炎検査
- 神経芽細胞腫検査
- 先天性代謝異常検査 など
2.母子相談指導事業の推進
○保健婦等により、各種健康教育及び訪問指導を実施し、母子の育児支援と病気や障害の早期発見・早期療育、発生の予防に努めるとともに、適切な療育指導へとつなげていきます。
- すこやかママの会(母親学級)
- 育児学級
- 離乳食実習等栄養指導
- 乳幼児相談
- 新生児訪問指導
- 乳幼児訪問指導
- 妊産婦訪問指導
- ハイリスク妊婦訪問指導
- 未熟児訪問指導
3.障害児療育システムの充実
○乳幼児健康診査事後管理システムの構築などを進めつつ、個々の障害児が必要な療育を受けることができるように、保健所等関係機関との連携を強化し、県療育システムへとつなげて行きます。また広域的福祉施設機能を活かした障害児(者)地域療育等支援事業の充実を図ります。
- 乳幼児発達相談指導事業
- 療育の給付と指導
- 心身障害児交流会「チビッ子倶楽部」
- 施設による外来療育相談・訪問療育
- 施設による短期療育事業(池田療育キャンプ)
4.育児支援の充実
○育児教室の充実、電話・訪問育児相談の強化、母子保健推進委員の育成、心理判定医など専門職の確保により、地域の中で安心して子育てができる支援策を強化します。
これらの子育て支援拠点機能を含む、総合的な保健・福祉機能を確保するため、庁舎建設時に整備を進めます。5.成人期の健康づくりの推進
○各種健康診査受診のPRをはじめ、健康教育・相談事業の充実を図ります。
また、障害者の健康診査の受診のしやすさを高める配慮に努めるとともに、訪問健康診査を活用をし、障害者の健康診査を強化します。
このほかに、在宅重度重症心身障害児(者)訪問診査などを促進します。第2節 医療・リハビリテーションの充実
「現状と課題」
本町の医療機関は、町立三野病院が立地しているほか、個人経営の病院・医院が開設され、近隣町村に比べ充実しています。障害者アンケート調査では、本町の障害者の約2割は「入院中あるいは入院することがよくある」、5割の人は「時々病院でみてもらう」となっており、高齢化の進展とともに医療・リハビリテーション(機能回復訓練)の需要が拡大しています。
機能回復訓練としては、老人保健事業として、PT雇上、町立三野病院整形医師・看護婦の協力を得て老人福祉センターで週1回実施しています。このほかに紅葉温泉デイサービスセンター(B型)・ふれあい紅葉センターデイサービス(C型)での日常動作訓練や保健婦の訪問指導による日常動作訓練などもありますが、40歳以下の障害者に対する専門的訓練は医療機関などが中心に実施しています。今後、紅葉温泉デイサービスセンターでの障害者利用の配慮を進めるとともに、広域圏の中で身体障害者デイサービスセンターなどの複数設置を検討し、専門的な機能回復訓練の実施が望まれます。本町では、特別養護老人ホームの移転整備・老人保健施設の整備などにより健康福祉ゾーンの形成を進めていますが、本町における福祉機能の集積と三好郡東部の中心立地であること等を踏まえ、障害者のためのデイサービスセンター等拠点機能を積極的に確保していくことが望まれます。このほかに、障害等を持つ人に対する各種医療給付制度がありますが、重度心身障害者医療費助成を受給している人は135人(平成10年1月1日現在)、小児慢性特定疾患医療や特定疾患医療を受給している難病患者が合わせて17人(平成9年4・5月)となっています。今後、これらの制度の普及を促進するとともに、保健所等との協力の中で地域生活を支援していく体制の整備が望まれます。「基本方針」
心身障害者や難病患者とその家族が、安心して生活できる医療支援体制の整備を促進します。
救急医療を含め、関係医療機関・医師会との連携を一層強化し、医療及び歯科医療体制の整備に努めます。
障害者の医療費負担を軽減するため、一層の充実を国・県へ働きかけます。「主要施策」
1.訪問指導・健康相談の充実
○保健婦・看護婦等により、在宅の心身障害者や難病患者とその家族に対して、訪問して日常的・将来的な不安の解消を含めた精神的支援をし、また、介護者に療養上の介護・看護方法の指導・援助等を積極的に行います。2.難病患者地域保健医療推進事業の充実
○難病患者とその家族に、難病専門の医師・保健婦・ケースワーカーによる医療相談事業を含めた地域保健福祉医療推進事業(保健所)をPRしていきます。また、高齢者サービス調整会議等を活用したケースワークを実施し、生活支援サービスの提供などを促進します。3.機能回復訓練事業の充実
○病院を退院後の在宅の身体障害者が、個別、集団の訓練により、機能の維持向上を図るとともに、交流を深め地域での生活に適応できるよう障害レベル・年齢に応じた指導を充実させます。
また、広域的に山城町が計画する身体障害者デイサービスセンター等の設置に向け調整していくととも、広域東部圏における身体障害者デイサービスセンター等の整備に向け努力します。4.地域保健医療計画の推進
○西部2保健医療圏地域保健医療計画に基づき、地域における総合的な保健医療供給体制の計画的な整備を推進します。5.救急医療体制の整備
○地域保健医療計画に基づき救急体制が整備されるよう働きかけます。6.医療技術者の確保
○医師及び医療技術者が確保されるよう働きかけます。7.関係医療機関との連携強化
○医師会等の協力により関係機関相互の連携強化が図られるよう働きかけます。8.在宅医療体制の整備
○在宅で安心して療養できるように夜間・休日等の体制の整備や訪問看護等が充実するよう働きかけます。9.口腔衛生知識の普及
○歯周疾患の予防等を中心に、口腔衛生知識の普及を図ります。10.歯科医療体制の整備
○歯科医師会の協力を得て、訪問診療が実施できる体制づくりを検討します。11.精神障害者通院医療費公費負担制度の普及
○在宅の精神障害者に対し、通院に要する医療費の一部を公費で負担する制度の周知を図ります。12.重度心身障害者医療費助成
○重度心身障害児(者)が診療を受けた場合の一部自己負担金を助成します。13.更生医療の給付
○身体障害者が、心臓疾患・腎臓疾患等の更生医療が必要な場合、その費用の給付を行います。14.育成医療の給付
○障害児に対し、生活能力を得るために必要な医療を給付できるよう、制度の周知を図ります。15.特定疾患・小児慢性特定疾患医療の給付
○医療保険の自己負担分の公費負担制度について周知を図ります。第3節 精神保健対策の充実
「現状と課題」
精神障害者は特別な存在ではなく、医療の対象であるとともに生活していくうえでたくさんの困難を抱えている「生活障害者」であるといった意識が定着しつつあります。また、全ての住民が精神保健の対象であり、心の健康を保持するため、様々な取り組みがなされつつあります。
しかし、精神障害に対する誤解や偏見により、自立や就労が可能である人が相当数いるにもかからわず、地域社会の中での生活は困難な状況が続いていました。
このような中で、広域的には、三好郡精神障害者家族会(やまなみ会)による、小規模作業所が山城町と三好町に設置され、本町からは三好町の末広共同作業所へ3人が通所しています。小規模作業所は、地域で自立した生活を送るために、通所により、仲間づくりの輪を広げたり、生活リズムを整えることや簡単な作業を行う場として役割を担っています。
また、平成6年には県下2番目に開所した、グループホーム池田(定員6名男性)が池田町に開所し、保健所・医療機関をはじめボランティアの協力のもとに、地域での生活を確立しつつあります。
このほかに、社会復帰を促進するために池田保健所の精神障害者・社会復帰相談事業(デイケア月3回)や通院患者リハビリテーション事業(職業リハ)、保健婦による訪問指導・精神保健相談が実施されています。
なんらかの精神病にかかる人は、おおよそ100人に一人といわれますが、精神障害者保健福祉手帳や通院医療費公費負担制度など諸制度を利用している人はごくわずかな状況にあります。これら諸制度の普及をはじめ、今後、地域の中で社会復帰ができるよう保健所等と協力しつつ生活の場の確保と支援サービス体制の確立を中心とした福祉施策を推進していくことが望まれます。
さらに、心の健康の学習やボランティアの育成を図る精神保健講座の開設や思春期精神保健等への取組みを推進し、精神障害への理解を広げていくことが必要です。「基本方針」
精神保健知識の普及・啓発を推進し、精神障害者の社会復帰を進めるための体制整備に努めます。
「主要施策」
1.精神障害者共同作業所等への支援
○既存作業所の運営を支援するとともに、作業所環境の改善や福祉の店など事業拡大に向け、家族会とともに検討を重ね、社会復帰機能・交流の場としての機能を拡充していきます。また、通勤等を考慮し、本町においても作業所の設置に向け、準備を進めていきますが、障害種を限定しない運営手法等について研究します。さらに、職業訓練などを実施する精神障害者授産施設(通所)については、保健所やみよしの山荘等との連携の上で、広域的な確保に向け検討します。
なお、作業所と授産施設は類似機能もあり地域需要や運営手法等についての充分な調査検討を行います。2.グループホームの確保・支援
○グループホームの設置については、家族会をはじめ、保健所・支援医療機関・近隣町等との連携の中で、広域的に複数施設の確保に向け努めます。3.地域生活支援事業(地域生活支援センター)の確保
○給食サービスなど日常生活支援・相談体制・交流機能などを拡充するため広域圏の中で地域生活支援センターの確保に努めます。なお、医療機関(援護寮)などが運営主体となりバックアップを得ることが望ましいため、関係医療機関との充分な連携をとり検討していきます。4.精神保健知識の普及・啓発
○精神保健に対する地域住民の理解を深めるため、精神保健福祉センター・池田保健所・関係機関等との連携に努めます。
このほか、学童期・思春期・成人などライフステージに応じた心の健康教育等を通じ、知識の普及を図ります。5.社会復帰相談事業等の充実
○保健所による社会復帰相談事業(保健所デイケア)、精神保健相談等の周知に努めます。医療機関による精神科デイケアの拡充を要請していきます。6.家族会等への支援
○家族会活動のPRや作業所でのふれあい行事への支援などを通じ、住民の理解を深めるように努めます。7.各種福祉サービス対象の拡大要請
○手帳制度の創設に伴い、他障害者が利用している福祉サービスの対象となるよう、関係諸団体と連携し国・県に要望していきます。第5章 福祉サービスの充実
第1節 在宅福祉サービスの充実
「現況と課題」
障害者に対する諸制度・福祉サービスなど障害者施策は多岐にわたり、サービスの実施や相談も多様な機関がかかわっています。現在の最も身近な相談窓口としては、身体障害者相談員(2名)・精神薄弱者相談員(1名)、民生・児童委員、役場福祉担当窓口・教育委員会・保健婦・在宅介護支援センター、社会福祉協議会などです。
主な在宅福祉サービスとしては、ホームヘルパーの派遣、紅葉温泉デイサービスセンターなど2施設での入浴・給食・日常動作訓練等の提供、ショートステイ事業(特別養護老人ホーム長生園)などとなっています。また、身体障害者補装具の交付(年43件程)・修理(年5件程)、日常生活用具の給付(年2件程)等を行っています。このほかに、精神薄弱児施設池田学園及び精神薄弱者更生施設博愛ヴィレッジ、箸蔵山荘による心身障害児(者)短期入所事業(ショートステイ)、脇町子星園での重度身体障害者ショートステイ等が実施されています。
現在、本町はホームヘルプサービスやデイサービスなど実施しており、その利用者は高齢者がほとんどを占め、若年層の障害者の利用は少数です。今後、重度障害者の在宅化の傾向も強まることから、介護型を中心としたホームヘルプサービスの拡充や町内福祉施設を利用するデイサービスの拡充などに取り組むことが必要です。また、広域的にサービス需要や通所区域等を勘案しながら西部第2保健福祉圏東部における身体障害者デイサービス事業の実施を検討するとともに、福祉施設(箸蔵山荘等)の専門的な機能を活かし、市町村障害者生活支援事業の導入により、在宅福祉サービスの利用援助や社会生活訓練プログラムなどを実施する生活支援センターの設置を進めていくことが求められます。「基本方針」
障害者の相談に応じ、必要な指導や助言を行うことができるよう相談体制の充実を図ります。
地域社会において自立した生活が送れるよう、ホームヘルプサービス事業等の一層の充実に努めます。
日常生活用具等福祉機器の普及に努め、障害者の日常生活の利便を図ります。「主要施策」
1.専門相談体制の充実
○身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、児童相談所、保健所の精神保健福祉相談、池田福祉事務所の診査更生相談、県更生相談所による巡回相談事業等の周知を図ります。2.在宅重度身体障害者訪問診査事業の充実
○歩行困難等の在宅重度身体障害者に対し、医師等を派遣して必要な診査、更生相談を行います。3.在宅介護支援センター相談機能の拡充
○地域における身近な在宅サービス等の利用促進を図るため、在宅介護支援センターにおける障害者サービスの相談業務を強化します。4.市町村障害者参加促進事業による生活訓練事業の実施
○広域的な市町村障害者参加促進事業の導入により、視覚障害者や聴覚障害者に対して、自立生活に必要な生活訓練事業の実施に努めます。5.ホームヘルプサービス事業の充実
○在宅の介護が必要な障害者・難病患者・家族に対し、ホームヘルパーを派遣し、身体介護・家事援助・外出時の付き添い等を実施します。
また、巡回型ホームヘルプサービスや住民参加型家事援助サービス等の実施について検討していきます。6.ガイドヘルパー派遣の実施
○視覚障害者や脳性まひ等全身性障害者などの外出支援を図るため、ガイドヘルパー派遣を実施します。また、ホームヘルパーやボランティアへのガイドヘルプ研修を充実します。7.デイサービス事業の充実
○在宅の軽度障害者の通所による入浴・給食サービス、創作的活動等を促進するため、各デイサービスセンターでの障害者受け入れ体制を強化します。
また、機能訓練や社会適応訓練、入浴等介護を専門的に実施する身体障害者デイサービス事業については、サービス需要等を検討しつつ広域事業として整備に努めます。8.短期入所事業の充実
○事業の周知を図り、利用者を増やすことにより、介護者の負担を軽減し、在宅の障害児・者の福祉の向上をめざします。また、広域的福祉施設等の機能を活かし、短時間の預かり等を実施するレスパイトサービスなどについて研究していきます。9.市町村障害者生活支援事業の実施
○広域的な市町村障害者生活支援事業の導入により、在宅福祉サービスの利用援助や社会資源の活用支援を行うとともに、障害者の社会生活力を高める社会生活訓練プログラム等を実施します。
- 在宅福祉サービス利用援助
- 施設紹介、福祉機器利用助言、コミュニケーション支援
- 社会生活訓練プログラム
- ピアカウンセリング
10.移送サービスの検討
○本町域の特性から、福祉タクシー券の助成といった形での移動支援を考慮します。
広域的に市町村障害者社会参加促進事業等の導入によりリフト付乗用車の運行等を検討していきます。11.補装具の交付の充実
○身体上の障害を補い、日常生活をしやすくするために必要な補装具の交付・修理の充実を図ります。12.日常生活用具の給付・貸与の充実
○日常生活がより円滑に行われるように、日常生活用具の給付・貸与を拡充するとともに制度の周知を図ります。13.福祉機器展示機能の確保
○在宅介護支援センター等での介護用品の展示・紹介機能の充実を図ります。
また、福祉機器リサイクル事業の実施について検討します。第2節 施設サービスの充実
「現状と課題」
地域に立地する入所福祉施設は、その専門的機能を活かし、入所者のみならず通所型、地域利用型、地域援助型などの形態で、様々な福祉サービスを展開する方向へと変わりつつあります。現在(平成10年1月1日)、本町の障害者では、身体障害者療護施設に4人が入所し、精神薄弱者更生施設・精神薄弱者授産施設、グループホームに合わせて13人が入所・通所しています。児童福祉法等に基づく施設では(平成9年3月31日)、養護施設、精神薄弱児施設、乳児院、精神薄弱児通園施設に合わせて7人程が入所・通所しています。このほかに特別養護老人ホームや養護老人ホームには45人(平成10年1月1日)が入所していますが、障害を持つ高齢者が多くを占めています。
今後、施設整備については県内の地域需要にあう適正配置を求めていくとともに、これらの施設入所者及び学校卒業者、在宅障害者の適切な生活・訓練等の場を確保するため、入所施設・グループホーム等生活施設をはじめ、在宅福祉サービスや作業所等を組み合わせた地域支援体制の整備を進める必要があります。
このため、特に広域的にも設置されていない在宅知的障害者(重度心身障害者)のグループホーム等の確保に向け、福祉施設・障害者・家族会等との連携を強化しつつ計画的な導入に努めます。また、福祉施設の機能を活かした各種の在宅支援事業の展開を支援していきます。「基本方針」
必要な時に必要な施設を利用できるよう各種施設の整備・充実を、関係機関へ働きかけていきます。また、施設が持つ諸機能が在宅福祉サービスの強化につながるように諸事業の導入を図ります。
「主要施策」
1.施設の整備促進
○県及び近隣町村との調整を行い、障害者のもつニーズに応えられるよう、授産・療護・更生・通園等の各種の施設整備を関係機関へ働きかけていきます。特に、広域的に身体障害者デイサービスの整備に努めます。なお、身体障害者療護施設・精神障害者生活訓練施設(援護寮)等については、圏域町村、病院等関係施設とともに協同で調査研究を進めます。2.障害者施設等による在宅支援事業の促進
○在宅障害者の生活支援の充実に向け、施設の専門機能を活かした在宅支援事業の充実・導入を促進します。
- 心身障害児(者)短期入所事業(博愛ビレッジ・池田学園・箸蔵山荘)
- 心身障害児短期療育事業(池田学園)
- 心身障害児(者)療育相談事業(池田学園・箸蔵山荘)
- 心身障害児(者)地域療育等支援事業(箸蔵山荘)
- 市町村障害者生活支援事業
- 精神障害者地域生活支援事業
3.グループホーム等の確保
○箸蔵ホーム・つくしホームなど施設入所者の在宅生活促進に向けたグループホームの確保に加え、在宅の障害者が協同で生活する場として福祉施設等のバックアップを得ながら家族会等とともにグループホームの設置に向け支援策のあり方等を研究していきます。第3節 生活安定のための施策の充実
「現状と課題」
障害者の生活の安定のための施策としては、特別障害者手当(9人)経過的福祉手当(8人)、障害児福祉手当(1人)、特別児童扶養手当(4人)など各種手当、障害者基礎年金など年金制度、各種資金貸し付けなどがあります。
なお、障害者アンケート調査(本町分)では、医療相談等に続き年金・手当の相談体制の充実を約36%の人が期待するとともに、特に必要な福祉施策としても医療費軽減助成に続き経済的援助の促進(1/5)があげられています。
これらの、手当や年金は、地域社会の中で自立した生活を営んでいくために重要な所得保障となりますが、有効利用を促進するため積極的な広報・相談活動を展開し、周知徹底を図る必要があります。また、経済的に自立しうるよう国諸制度の金額の増額に向け、働きかけていくことが必要です。「基本方針」
障害者の所得保障のため、各種手当・年金制度等の周知徹底に努めるとともに、障害者のニーズにそった制度の充実を国に働きかけていきます。
「主要施策」
1.特別児童扶養手当
○障害児を監護する保護者・養育者に対し、特別児童扶養手当制度の周知徹底を図るとともに、相談体制の充実を図る。2.障害児福祉手当
○在宅の重度障害児で日常生活に常時介護を要する20歳未満の人に障害児福祉手当制度の周知徹底を図るとともに、相談体制の充実を図る。3.特別障害者手当
○在宅の最重度障害者で、日常生活に常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人に特別障害者手当制度の周知徹底を図るとともに、相談体制の充実を図る。4.障害基礎年金等
○国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満に障害者になったとき、20歳前に障害者になった人等に対し、20歳から一定条件のもとに障害基礎年金を支給します。なお厚生年金加入者は上乗せし障害厚生年金制度の周知徹底を図るとともに、相談体制の充実を図る。5.心身障害者扶養共済制度の周知
○保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡、または重度障害になったとき、残された障害者に終身一定額の年金を支給する扶養共済事業の周知を図ります。6.生活福祉資金の貸し付け
○障害者が住宅改造や自動車の取得、生業を営む場合、必要な資金を低利で融資し、経済的自立や生活意欲を助長します。制度の周知徹底を図り、円滑な資金運営に努めます。第4節 ひとづくりの促進
「現状と課題」
障害者福祉の推進のためには、保健福祉人材の確保・育成をはじめ、ボランティア組織の育成、住民参加型の福祉サービスの展開や専門協力者の組織的養成を必要とします。特に在宅福祉サービス拡充の要となるホームヘルプサービスについては、障害の重度化や施設から地域へといった流れの中で、家事援助中心から介護中心、サービス時間の拡大などに伴い相当の人員確保が必要となります。このため常勤ヘルパー及び登録ヘルパーの増員をはじめ、介護福祉士等の専門的なヘルパーの確保に努めることが求められます。
また、ボランティアについては、活動の中心となる層の高齢化が進展するとともに、障害ニーズの個別性などに的確に対応していくことが困難な状況となっています。今後は障害者の社会参加等の促進を図るためには点訳・朗読・手話・要約筆記奉仕員等の養成や派遣、情報支援等に取り組むことが望まれます。このため、障害者団体やボランティア連絡協議会、広域町村等との連携の中で圏域共同事業として、専門的な技術によりコミュニケーション等の円滑化を図る人材の確保・養成等をめざし、市町村障害者社会参加促進事業の導入を図ることが必要です。さらに、これらの専門的マンパワーを組織し、各障害者団体や家族会と連携する団体として育成し、それぞれの障害者ニーズに応じた社会活動の支援体制を整えていくことが望まれます。「基本方針」
障害者のニーズに対応できるよう、専門的知識や技能を持った人材の確保・養成に努めます。
地域福祉を一層推進するため、ボランティア活動の振興を図り、ボランティアの量的・質的拡大に努めます。
社会福祉協議会が、地域福祉の推進の主体として重要な役割を果たせるよう支援します。「主要施策」
1.ホームヘルパーの増員
○障害者や高齢者の増大かつ多様化するニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、ホームヘルパーを増員します。2.市町村障害者社会参加促進事業
○西部第二圏域で事業を行ないます。3.ボランティア活動の活性化
○ボランティアセンターの開設に向け努力します。第6章 生活環境の整備
第1節 福祉環境の総合的推進
「現状と課題」
障害者の自立生活を確立し、社会経済活動への参加を促進していくためには、建築物や道路・公園、公共施設などにおける物理的な障害の除去や快適に利用できる諸条件の整備が必要です。
県においては、ハートビル法「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」の施行等を受けつつ、平成8年3月に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を公布し、公共施設や公的施設の環境整備基準を示しています。
本町では、やさしいまちづくり推進事業の導入などにより役場福祉センター等へのスロープ自動ドアー化、点字ブロック等の設置など、障害者等が利用しやすい公共的施設や道路の改善整備等を順次進めていますが、まだ不十分な状況にあります。
また、障害者アンケート調査(本町分)でも、外出時に困ることとして、車などの危険性や歩道の段差、交通機関の利用しづらさなどが指摘されるとともに、公共施設・道路等の改善整備が求められています。
今後、特に利用の多い公共施設・交通機関等の周辺を中心として、重点整備地区等を設定しつつ、通行の妨げとなるものの規制等も進め、安全な環境の整備を進めることが必要です。「基本方針」
障害者が自由かつ容易に社会活動に参加できるよう、福祉のまちづくりを総合的に推進します。
公共性の高い建物、道路・公園などにおいて、施設のバリアフリー化や障害者等の利用に配慮した整備を進めます。「主要施策」
1.ひとにやさしい福祉のまちづくりの推進
○障害者や高齢者を含むすべての町民が、安全で快適な生活を送ることができる生活環境の基盤整備を促進するため、関連各課が連携し、総合的なやさしいまちづくりを推進します。2.公共施設の整備促進
○公共施設の新築又は改築する際には、県の条例に基づく整備を図ります。公共的施設においては、障害者の利用を前提とした専用駐車場、障害者用トイレなど順次整備を進めます。
また、駅など公共交通機関の改善整備について要望していきます。3.安全で快適な歩道の整備
○障害者・高齢者の利用に配慮した幅の広い歩道や段差の解消などの整備に努めます。
また、県道の整備等については、県当局に要請します。4.音響信号機等の設置
○利用頻度が高い箇所や人通りが少なく誘導等が困難な危険箇所などを中心に、音響信号機や誘導ブロックなどを整備し、安心して利用できるような環境整備を進めます。5.放置物等の是正指導
○道路に放置されている自転車や歩道乗り上げ駐車、看板等よる交通障害を解消するため、是正指導を進めます。
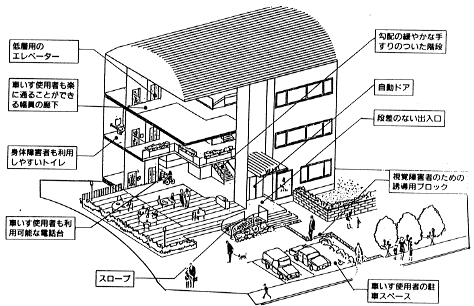
第2節 住宅・生活環境の整備
「現状と課題」
障害者が地域の中で暮らしていくためには、障害があっても自立が促進される住宅が整備されていることが必要です。
本町では、町営住宅については現在185戸を管理していますが、障害者や高齢者が安心して行動できるようバリアフリー化を推進するとともに、既存町営住宅では施設の整備状況や入居者のニーズを把握し、改善を推進することが必要です。
また、住宅改造等の相談を促進するためリフォームヘルパーを設置しており、これらの周知・活動の促進が望まれます。
「障害者アンケート(本町分)」では、今後改造を希望する人が3割強となり、風呂・トイレ・台所などの改造を望むなど、住宅改造に対する需要は相当高いものとなっています。また、住宅についての今後の取り組みとしては、改造資金についての支援体制の充実、住みやすい公営住宅や介護付住宅の整備などへの期待がめだちます。
このため、今後の公営住宅の建て替え等に際しては、需要に配慮しながら高齢者・障害者用住宅を増やしていくこと及び一般住宅の改造支援の周知・充実等が必要となります。「基本方針」
公営住宅の建替えに際しては、障害者等の住宅需要を的確に把握し、構造・設備に配慮した住宅の建設を進めます。
日常生活の環境改善を図るための居室整備を支援する補助や貸付け制度の利用を促進します。「主要施策」
1.公営住宅の整備推進
○公営住宅については、建替えに際し、安全と利便を考慮した住宅を、障害者等の住宅需要に対応して供給するよう計画します。
また、既存住宅の改良整備を推進します。2.住宅資金割増融資制度の普及
○住宅金融公庫による高齢者・障害者割増融資制度の普及に努め、障害者の生活環境の改善や介護の軽減を図ります。3.住宅改造助成制度の普及
○日常生活がより円滑に行われるように住宅改造の助成を行う重度身体障害者住宅改造助成の普及を図ります。また、生活福祉資金の貸付の住宅改造費融資などの周知を図るとともに、リフォームヘルパー派遣制度等の利用を促進するよう努めます。第3節 交通・移動手段の整備充実
「現状と課題」
障害者の多くは、その障害のために外出が困難で、社会参加がしにくかったり通院等においても不便な状況におかれています。
このような中で、公共交通機関の果たす役割が重要視されるとともに、自家用車をはじめとした個別移動手段の利用の促進を図ることや、移送サービス等の充実が求められます。
現在、これらの外出支援策としては、バス路線やJR徳島本線等公共交通機関の運行をはじめ、公共交通機関の運賃・料金の割引、自動車取得税等の減免など経済的支援、身体障害者自動車改造費や自動車訓練費の助成などが実施されています。
なお「障害者アンケート調査(本町分)」では、主な外出手段としては、乗用車、タクシー、施設の送迎バスの利用が目立っています。また、今後の外出支援策としてはタクシー券助成の促進が多くの人から期待されています。
今後、各種割引制度や助成の周知・利用の促進を公共交通事業者等も含め呼びかけていくとともに、公共交通機関の利用のしやすさの改善、個別の移動を促進する施策の展開等に努め、外出の容易さを高めていくことが必要です。「基本方針」
障害者の移動手段の拡充を図るため、福祉タクシー事業の検討、低床路線バスの導入協議、鉄道・バス運賃等の割引制度については周知に努めます。
身体障害者の自家用車利用については、支援制度の周知を進めます。「主要施策」
1.身体障害者自動車運転免許取得費助成の周知
○身体障害者が自動車免許を取得するための教習を受ける場合、県では取得費用の一部を助成しており、この制度の周知を図ります。2.身体障害者自動車改造費助成の周知
○重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費の一部を助成しており、この制度の周知を図ります。3.福祉タクシー事業の導入検討
○公共交通機関の不足などを考慮し、障害者が外出する際に利用するタクシーの料金の一部を助成する福祉タクシー事業の導入検討を行います。4.低床路線バスの導入
○関連町村や関係機関と協議し、リフト付き路線バスの導入を働きかけます。5.運賃、料金の割引制度の周知
○鉄道・バス運賃、航空運賃、有料道路通行料金の割引等の制度の周知を図ります。第4節 防災体制の充実
「現状と課題」
障害者が地域の中で安心して生活できるよう、防犯・防災対策が適切に講じられていることが大切です。
本町では、防災上の問題としては、長期的には中央構造線など活断層をはじめ海洋型の地震など地震災害、短期的には降雨による水害や土砂災害の発生等が懸念されます。これに対し、適切な対応が図られるよう地域防災計画等にもとづき予防対策や応急対策の実行性を高めておくことが重要です。また、高齢者や障害者などに対しては特段の配慮が求められ、特に特別養護老人ホームなど福祉施設の防火管理や避難誘導体制を整えておくことが必要です。
「障害者アンケート調査(本町分)」では、必要な防災対策として、災害時に「安全確認に来てくれる人」(約28%)、「避難誘導に協力してほしい」が約30%となるなど、人的支援を中心とした防災対策の充実が望まれています。
現在、本町では、ひとり暮らしの高齢者宅に緊急通報システムにより、緊急時の安全確保策を講じていますが、今後、障害者等も含め拡大していくことが求められます。また、プライバシー等も配慮しつつ地域における障害者等の把握に努め、近隣住民等による救助体制の確立などに努めることが必要です。「基本方針」
社会福祉施設における防災管理体制の充実・強化を図るとともに、災害時の受け入れ体制の確立を検討します。
防災教育や防災訓練を推進するとともに、障害者等の救出活動が実施できるよう、地域における自主防災組織の拡充を支援します。「主要施策」
1.施設防災体制の強化
○福祉施設等への立入検査及び防火管理指導を行い、防災管理体制の充実を図ります。また、近隣やボランティア等の協力を得る体制の整備を進めます。2.住宅防災対策の推進
○住宅火災による死傷者の発生を予防するため、防火思想の普及を図るとともに、防災機器等の設置を促進し、障害者のいる家庭等の安全対策を推進します。3.防災教育・訓練の推進
○防災知識の向上と災害時の的確な対応を図るため、障害者の実態や地域の実情を把握し、障害者のいる家庭及び施設職員等への防災教育と防災訓練の推進を図ります。4.地域協力体制づくりの推進
○災害発生の緊急時には、災害弱者である障害者等についても、地域住民による自主的な救出・救護等の活動が実施できるよう、自主防災組織づくりへの支援と協力を推進します。また、ボランティアの活動を確保するため、交流会や研修会を開催するよう努めます。5.緊急通報システムの整備
○災害時における迅速な救助活動を行うため緊急通報システムの拡大に努めます。
また、福祉事務所や保健所等との連携を強化し、プライバシーに配慮しながら町内障害者の情報の整理・保管・緊急時の活用などに向け研究します。第4編 推進に向けて
第1章 主要事業の目標設定
「お互いを思いやり尊重しあって、仲良く共生できるまち・三野」の実現を図るため、主要事業の目標を次のように設定します。
主要事業目標1.障害者の社会参加促進
障害者にとって最も身近な町村において、障害者のニーズに応じた事業を実施することにより、障害者の自立と積極的な社会参加の促進を図ることを目的に西部第2サブ障害保健福祉圏域で次のような事業を行う。
1 基本事業
〔第1 コミュニケーション支援〕
1.点訳奉仕員等養成事業
(1) 事業内容点訳又は朗読、手話、要約筆記に必要な技術等の指導を行って、これらに従事する奉仕員(以下点訳に従事する奉仕員にあっては「点訳奉仕員」、朗読に従事する奉仕員にあっては「朗読奉仕員」、手話に従事する奉仕員にあっては、「手話奉仕員」、要約筆記に従事する奉仕員にあっては「要約筆記奉仕員」という。)を養成する。(2) 養成対象者点訳又は朗読の奉仕を申し出た者のうち、適当と認めた者とする。(3) 実施方法等養成対象者に対しては、講習会等の方法により、概ね次の科目について講習を実施する。ア 点訳奉仕員に対する講習(ア)点字図書の基礎知識
(イ)点訳の方法及び実技
(ウ)身体障害者福祉の概要イ 朗読奉仕員に対する講習(ア)声の図書の基礎知識
(イ)朗読の方法及び実技
(ウ)身体障害者福祉の概要ウ 手話奉仕員に対する講習(ア)手話の基礎知識
(イ)手話の方法及び実技
(ウ)身体障害者福祉の概要エ 要約筆記奉仕員に対する講習(ア)要約筆記の基礎知識
(イ)要約筆記の方法及び実技
(ウ)身体障害者福祉の概要(4) 奉仕員の登録ア 講習を終了した者等のなかから、本人の承諾を得て、奉仕員としての登録を行う。
イ 登録された奉仕員に対しては、これを証明する証票を交付する。(5) 奉仕員の協力内容ア 点訳奉仕員
点訳奉仕員は、点字図書の増冊及び普及に協力する。
また、町村等からの依頼による点字による相談文書の翻訳や回答文書の作成、広報活動、文化活動等に協力する。イ 朗読奉仕員
朗読奉仕員は、声の図書の増冊及び普及に協力する。
また、町村等からの依頼による広報活動、文化活動等に協力する。ウ 手話奉仕員
手話奉仕員は、町村等からの派遣依頼を受けて、聴覚障害者と障害のない者との通訳を行う。
また、町村等からの依頼による広報活動、文化活動等に協力する。エ 要約筆記奉仕員
要約筆記奉仕員は、町村等からの派遣依頼を受けて、中途失聴者、難聴者等と障害のない者との意志伝達の仲介を行う。
また、町村等からの依頼による広報活動、文化活動等に協力する。(6) 留意事項奉仕員は、身体障害者の人格を尊重して活動するとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守ること。2.手話奉仕員等派遣事業
(1) 事業内容聴覚障害者等(聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者を含む。以下同じ。)のコミュニケーションの円滑化の推進のため、手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣する。(2) 派遣対象者町村等が必要と認めた場合で、適当な意志伝達の仲介者が得られない聴覚障害者等とする。(3) 留意事項奉仕員は、身体障害者の人格を尊重して活動するとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密は守ること。3.手話通訳設置事業
(1) 事業内容コミュニケーションの円滑化を推進するため、手話通訳を行う者を福祉事務所等、公的機関に設置する。(2) 手話通訳の業務内容聴覚障害者等とその相手方との、意志伝達の仲介を行う。(3) 留意事項ア 手話通訳を行う者には、これを証する証票を発行し携行させること。イ 手話通訳を行う者は、身体障害者の人格を尊重して活動するとともに、当該身体障害者の身上及び家庭に関して知り得た秘密は守ること。〔第2 情報支援〕
4.点字広報・声の広報等発行事業
(1) 事業内容点字や声の広報等の発行により、必要な行政情報等を提供する。(2) 提供内容ア 地方公共団体等の広報
イ 点字・声の図書の関係情報
ウ 視覚障害者関係事業の紹介
エ 生活情報
オ その他必要な情報(3) 留意事項視覚障害者の求めている情報をよく把握して、発行に努めること。
また点字を理解できない視覚障害者に配慮し、録音による情報提供も行うこと。〔第3 移動支援〕
5.自動車運転免許取得助成事業・自動車改造助成事業
(1) 事業内容自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する。(2) 対象者ア 自動車運転免許取得助成事業
免許の取得により、社会参加が見込まれる者とする。イ 自動車改造助成事業
次の要件のいずれかに該当する者とする。(ア)自らが所有し運転する自動車の手動装置等の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(イ)前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者(3) 助成額ア 操作訓練
免許の取得に直接要した費用の2/3以内とする。
ただし、10万円を限度とする。イ 改造助成
自動車の改造に直接要した費用とする。
ただし、10万円を限度とする。(4) 留意事項町村等は、免許取得、改造助成いずれの申請に対しても対応できるように配慮すること。6.重度身体障害者移動支援事業
(1) 事業内容車いす使用者等が利用できるリフト付き乗用車を運行する事業。(2) 利用対象者車いす使用者等で一般の交通手段を利用することが困難な身体障害者とする。(3) 留意事項町村等は、利用対象者の把握に努めるとともに、利用対象者の利便を考えた方法で実施すること。
また、実施に当たっては、他の法令等に抵触しないよう留意すること。〔第4 生活訓練〕
7.生活訓練事業
(1) 事業内容視覚障害者、聴覚障害者に対して、日常生活上必要な訓練・指導を行う。(2) 実施方法等講習会等の方法により、概ね次のような内容の事業を行う。ア 視覚障害者に対する生活訓練(ア)歩行訓練
(イ)身辺・家事管理
(ウ)コミュニケーションに関すること(点字、ワープロ、パソコン等)
(エ)福祉機器の活用方法
(オ)社会資源の活用方法
(カ)家庭生活に関すること(生活設計、家族関係、育児等)
(キ)その他社会生活上必要なことイ 聴覚障害者に対する生活訓練(ア)コミュニケーションに関すること(手話、読語、ワープロ等)
(イ)情報収集に関すること
(ウ)福祉機器の活用方法
(エ)社会資源の活用方法
(オ)社会生活・職業生活に関すること
(カ)家庭生活に関すること(生活設計、家族関係、育児等)
(キ)その他社会生活上必要なこと(3) 留意事項ア 本事業の対象者の中には就労している者が含まれることから、講習会等の開催時期、期間等に充分留意すること。
イ 各々事業について的確な訓練・指導のできる者を講師等として選任すること。〔第5 身体障害者スポーツ振興〕
8.身体障害者スポーツ教室開催等事業
(1) 事業内容身体障害者スポーツの振興と身体障害者のスポーツへの積極的な参加を図るため、身体障害者スポーツ大会・教室の開催、身体障害者スポーツの啓発・普及に関する事業を実施する。(2) 留意事項ア スポーツ教室やスポーツ大会の開催等に当たっては、初心者から経験者まで全ての者がこれに参加できるよう、それぞれの意向を十分把握して実施内容を決定すること。イ スポーツ教室及びスポーツ大会等の開催に当たっては、これに参加する身体障害者の健康管理及び事故の防止に十分留意すること。ウ 本事業の実施に当たっては、身体障害者スポーツ指導員の協力を得て、効果的に実施すること。〔第6 福祉機器リサイクル〕
9.福祉機器リサイクル事業
(1) 事業内容不要になった福祉機器について、これを必要とする他の者等に斡旋する事業。(2) 留意事項ア 実施に当たっては、事業内容を広報紙等により広く周知すること。
イ 斡旋が円滑に行われるよう、受取り者による福祉機器の確認及び引取り等十分な調整を行うこと。
ウ 福祉機器の引渡し等に要する費用については、原則として受取る者の負担とすること。〔第7 その他〕
10.地域のニーズに即した事業
在宅の身体障害者の社会参加を効果的に促進するため、地域の身体障害者のニーズに応じてモデル的・先駆的な事業を実施する。2 リフト付福祉バス運行事業
1.事業内容
身体障害者の社会参加を促進するため、移動支援としてリフト付福祉バスを運行させる。2.利用対象者
原則として、在宅の身体障害者とする。3.利用科
無料とする。ただし、民間輸送業者に運行を委託する場合は、当該リフトバス運行地域内の他のバスの料金を上限に徴収することができる。主要事業目標2.障害者の生活支援
在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に実施し、社会福祉法人等に事業運営を委託する。
1.利用対象者
生活支援事業の対象者は、地域において生活支援を必要とする身体障害者等及びその家族とする。2.事業内容
次に定める事業を行うこととする。(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助ア サービス情報の提供
イ サービス利用の助言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
オ その他必要な保健医療サービスの利用援助(2) 社会資源を活用するための支援〔支援の具体例〕
- 授産施設、福祉工場、作業所等の紹介
- 福祉機器の利用助言
- 情報機器の使用指導
- 料理等の指導(料理、裁縫)
- コミュニケーションの支援(代筆、代読等)
- 外出の支援
- 移動の支援
- 住宅改修の助言
- 住宅の紹介
- 生活情報の提供(交通、ホテル、買物、映画、音楽等)
(3) 社会生活力を高めるための支援社会生活力を高めるために、社会生活訓練プログラム等を実施する。〔プログラムの具体例〕
- 自分と障害についての理解
- 家族関係、人間関係
- 介助サービスと介助者
- 身だしなみ
- 健康管理
- 家事、家庭管理
- 金銭管理
- 安全管理
- 生活情報の活用
- 交通・移動手段の利用
- 趣味、余暇活動
- 人生設計
(4) ピアカウンセリング障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助・支援(5) 専門機関の紹介障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、職業安定所、「障害児(者)地域療育等支援事業」及び「精神障害者地域生活支援事業」の実施主体、医療機関、保健所等専門機関の紹介3.町の役割
(1) 事業実施主体としての役割をふまえ生活支援事業実施者と緊密な連携を図り事業の円滑な実施に努めること。(2) 生活支援事業実施者の意見を十分尊重し、公的保健福祉サービスの提供に努めること。(3) 生活支援事業実施者が他の市町村の障害者等も対象として実施する場合には、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に努めること。主要事業目標3.障害者デイサービスの整備
地域において就労の機会等が得がたい在宅障害者又は介護を行う者を通所させ、創作軽作業、機能訓練、介護方法の指導等を行うことにより、生きがいを高め、その自立を図ることを目的に東部4町で実施し、社会福祉法人等に事業運営を委託する。
1.実施事業
(基本事業と創作的活動事業は必須)(1)基本事業(機能訓練、介護方法の指導、社会適応訓練、更生相談、健康指導等)(2) 創作的活動(手芸、工芸、絵、書、陶芸、園芸等の技術援助及び作業)普通型(週に2日以上実施)(3) 入浴サービス(一般浴、介護浴)(4) 給食サービス(食事の提供)(5) 介護サービス(更衣、排せつ等の身体介助)(6) 送迎サービス(車いす利用者等のリフトバスによる送迎)2.利用定員等
事業の一日あたりの利用人員は、おおむね15人程度とする。主要事業目標4.障害者 小規模通所作業所の充実・整備
現在、週1回(金曜日)町及び町手をつなぐ育成会(つくし会)により、知的障害者作業所を平成7年9月より開設している。
今後は障害の枠にとらわれなく広く開放し、在宅で生活している障害児(者)を通所させ、地域社会の理解と協力を得て、障害の程度に応じた生活指導や訓練を行うと共に、作業収入による工賃収入を確保することによる福祉的就労の場としても機能し、もって障害者の社会参加と生きがいを高めると共に障害者同士の出会いの場・交流の場としても大切な場所で、開設日数を週5日以上となるよう努力する。主要事業目標5.やさしいまちづくり(生活環境の整備)の推進
住み慣れた家庭や地域の中で、生きがいをもって生活し、様々な活動に自由に参加できる。そういう社会に暮らすことは、私たち共通の願いです。そして、このような社会を実現していくためには、障害者や高齢者等の方々をはじめとして、すべての人が安全かつ快適に生活できるひとにやさしいまちづくりを推進することが重要になっております。
障害者が安心して生活でき、かつ自由に活動できる生活環境づくりは「共に生きる社会」の基盤となります。
玄関のスロープや段差のない歩道などは、障害がある人だけでなく、高齢者、妊娠中の女性や幼児、ひいては誰にとっても使いやすく安全な設備です。「やさしいまちづくり」は、すべての人にかかわることなのです。
本町では、平成8年3月に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」が制定されたのを契機に不特定多数が利用する建築物(以下「公共的建築物」という。)の整備に際し、「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」の整備基準に基づき必要な指導及び助言を行う「やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度」を活用し、多くの町民が利用する公共的建築物の福祉的配慮を一層推進するとともに、既存の建築物を含めたなかで整備を進めていきます。やさしいまちづくりアドバイザー派遣制度のしくみ
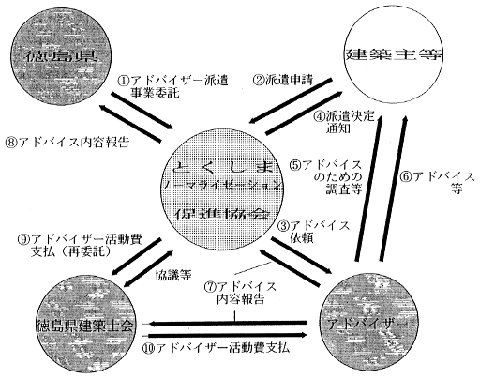
国の障害者プランが示す数値目標(参考)
障害者福祉サービス 平成14年度全国目標 対人口比 圏域目標
(概数)グループホーム・福祉ホーム 2万人分 1人/6,411人 9人分 授産施設・福祉工場 6.8万人分 1人/1,886人 30人分 重症心身障害児(者)通園事業 1,300か所 1か所/98,627人 0.6か所
=1か所精神障害者生活訓練施設(援護寮) 6,000人分 1人/21,369人 3人分 精神障害者社会適応訓練事業 5,000人分 1人/25,643人 3人分 精神科デイケア施設 1,000か所 1か所/128,215人 0.4か所 障害児寮育・精神障害者社会復帰・障害者の総合相談・生活支援事業 人口30万あたり2か所 人口15万人に1か所 0.4か所 障害者の社会参加促進事業 人口5万人規模を1単位 人口5万人に1か所 1.1か所
=1か所ホームヘルパー 4.5万人上乗せ
約14,600人1人/2,849人上乗せ
1人/878人20人上乗せ
63人ショートスティ 4,500人分 1人/28,492人 2人分 ディサービス 1,000か所 1か所/128,215人 0.4か所 身体障害者寮護施設 2.5万人分 1人/5,129人 11人分 精神薄弱者更生施設 9.5万人分 1人/1,350人 41人分 ※対人口比は厚生省人口問題研究所平成14年推計人口(128,215,000人)
※圏域目標は、現在の人口(55,276人)との対比第2章 おわりに
三野ノーマライゼーションプランの策定にあたっては、障害者アンケート調査をはじめ、障害者団体等からの提案シートをいただき計画への反映に努めるとともに、庁内各課・西部第2サブ障害保健福祉圏域の町村・県機関等との連携の中で、計画内容の検討を行なった。
障害者を取り巻く諸環境は、ノーマライゼーション理念の普及とともに、徐々に適切なものへと改善されつつあるが、未だ「完全参加と平等」は実現途上にある。
また、障害者の自立意識の高まりと地域の中で共にあたりまえの生活をしたいといった願いに対し、必ずしも満足な条件が整備されているとは言えない。
このような状況の中で、本町では、「お互いを思いやり尊重しあって、仲良く共生できるまち・三野」をめざし、行政及び全ての町民が身近な問題として様々な配慮やより良い地域を築くための取組みが実践できるよう本プランを策定したものである。
今後、本プランに基づき、行政機関はもとより関係諸団体との連携を強化し、各種の施策・事業の実現に努めるとともに、関係者による連絡会議等で協議の上、適宜、評価・見直しを行い、より水準の高いサービスの提供を推進する。
また、本計画の諸施策を実施するにあたっては、介護保険の施行に伴うサービス体制等の再編に留意し、より適切な事業が実施できるよう整合を図るものとする。そして、諸事業の実現に向け、国・県の補助金を要望するとともに、広域的な連携を強化しながら、自主財源の確保に努め効果的な予算の運用を図るよう努める所存である。
最後に、印刷から製本まで手作りのためお見苦しい点が多々あろうかと存じますがご容赦願いたい。
主題:
三野ノーマライゼーションプラン No.2
(MINO normalization PLAN)
25頁~70頁発行者:
徳島県三野町発行年月:
平成10年3月文献に関する問い合わせ先:
徳島県三野町厚生課
〒 771-23 徳島県三好郡三野町大字芝生1039
TEL (0883)77-4803
