みやぎ障害者プラン
宮城県障害福祉長期計画
地域で自分らしい生活を安心して送れる社会をめざして
| 総論 |
| 1 | 策定の趣旨 |
本県では平成5年3月に策定した「宮城県障害福祉長期計画」(平成5~14年度)に基づき様々な障害者施策を推進してきました。
この間、障害福祉を取り巻く環境は大きく変化し、国や県においても次のような制度の改正や施策が次々と打ち出されました。
このため、県障害福祉長期計画を見直し、前期5か年の施策の評価と社会情勢の変化を踏まえ、新しい計画を策定したものです。
- 平成5年3月に、国において「障害者対策に関する新長期計画」が策定され、さらに同年12月には「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」として改正されました。
- 平成7年5月に「精神保健法」が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正され、精神障害者に対する福祉施策の拡充が法的に位置づけられました。
- 平成7年12月には、国の「障害者対策に関する新長期計画」の重点施策の実施計画として「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」が策定され、具体的な数値目標が示されるとともに、各都道府県ごとに「障害保健福祉圏域」を設定することとされました。
- 平成9年9月に、本県における保健・医療・福祉の横断的・総含的な計画として「みやぎの福祉・夢プラン」が策定され公表されました。
| 2 | 基本的な考え方 |
| 基本理念と視点 |
基本理念 - 地域で自分らしい生活を安心して送れる社会
- ①「地域で生活するために」
- ノーマライゼーション(注.1)の理念を踏まえて、障害のある人が社会の構成員として、地域社会の中で共に暮らせる社会を目指します。
- ②「自分らしい生活をするために」
- 障害を持ちながらも、自らの意志により、自分の生き方を主体的に選択できる自立と社会参加が保障された社会を目指します。
- ③「安心して生活を送るために」
- 障害のある人が地域で生活するために、障害のある本人、その家族、そしてこれらの方々を取り巻く人々すべてが、いつでも安心して暮らせる社会を目指します。
(注・1)下線を引いている用語については、「用語の解説」をご参照願います。
| 3 | 計画期間 |
平成10年度から平成17年度までの8年間とします。ただし、社会情勢等の変化により必要があると認めるときは、その都度見直しを行うものとします。
| 4 | 計画の位置づけ |
この計画は「宮城県総合計画」、県政推進の方向を示した「夢航路未来号」、「みやぎの福祉・夢プラン」を踏まえた、障害福祉施策を総含的に推進するための計画です。「みやぎの福祉・夢プラン」の個別計画となるもので、県障害福祉長期計画を見直し、より具体的な計画を策定したものです。
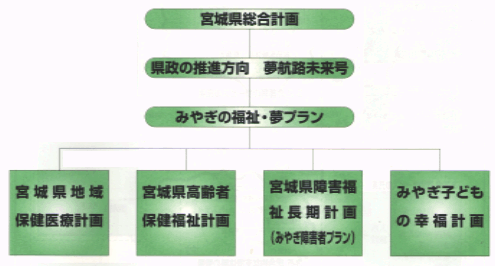
| 5 | 障害福祉圏域の設定 |
障害福祉施策を推進するにあたリ、単独の市町村では対応が難しい事業などを複数の市町村が連携を図りながら、広域圏ごとのネットワークを構築し、各種のサービスを面的・計画的に整備するために「障害保健福祉圏域」を設定します。(詳細は「計画推進のために」の章をご覧下さい。)
| 6 | 対象とする障害者の範囲 |
このプランで対象とする「障害者」とは、障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、精神薄弱(注.2)又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける方」のほか「てんかん及び自閉症を有する方並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する方であって、長期にわたり日常生活上の支障がある方」を含むものとします。
| (注.2) なお、「精神薄弱」という用語については、現在、各方面において議論されているところですが、本プランでは原則」として法令又は事業名として使用する場合を除き、「知的障害」の用語を使用しています。 |
| 7 | 施策の体系 |
| 宮城県障害保健福祉圏域 |
|
| 類型 | 生活施設 | 更生・訓練・治療・療育施設 | 作業施設 | 地域利用施設 | 生活の場 |
| 機能 | 介護等 | リハビリテーション | 訓練・作業 | 地域における社会参加の促進 | 地域における生活の場 |
|
知的障害児・
身体障害児 |
【精神薄弱児施設】 知的障害児を入所により保護するとともにへ自立生活に必要な知識や技能習得のための訓練を行う (2力所-220名) |
【精神薄弱児通園施設】 知的障害児を通所により保護するとともに、独立生活に必要な知識や技能習得のための訓練を行う (5力所-150名) |
【ショートスティ専用床】 家族での介護が一時的に受けられない障害者に精神薄弱児施設等への短期入所による介護的サービスを提供する (7力所-29床) |
||
| 【肢体不自由児施設】 肢体不自由児を治療するとともに独立生活に必要な知識や技能の習得のための訓練を行う (1力所-165名) |
【心身障害児通園事業施設】 障害児に、発達支援のための保育、訓練などを実施する (18力所-375名) |
||||
| 【重症心身障害児施設・委託病床】 重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童を入所により保護するとともに、治療及び日常の指導を行う ◇施設1カ所-50名 ◇委託病床4力所-201床 ※他に筋ジスの委託病床あり(1施設) |
|||||
| 身体障害者 | 【身体障害者療護施設】 身体上の著しい障害のため常時介護を必要とするが家庭ではこれを受けること困難な最重度の障害者が入所により医学的管理の下に必要な援助を受ける (5力所-305名) |
【肢体不自由者更生施設】 障害の程度の如何にかかわりなく相当程度の作業能カを回復し得る者を対象として更生訓練を行う (1力所-30名) |
【身体障害書授産施設】 就労が困難または生活に困窮する人を対象に必要な訓練を行うとともに職業を提供し自活を援助する ◇入所施設 (3力所-220名) ◇通所施設 (6力所-128名) ※入所施設に併設の3ヶ所を含む |
【身体障害者福祉センター】 身体障害者に通所により創作的活動、機能訓練等の各種サービスを提供し自立の促進や生活の質の向上を図る (3力所) |
【福祉ホーム】 身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者が自立した生活を営む施設 (1力所-20名) |
| 【重度身障者更生援護施設】 重度の肢体不自由者に入所により日常生活能カの回復に重点をおいた各種のリハピリテーションサーピスを提供する (1力所-50名) |
【身体障害者福祉工場】 作業能力はあるが一般企業に雇用されることが困難な重度身体障害者に職場を提供する (1力所-70名) |
【ショートスティ専用床】 家族での介護が一時的に受けられない障害者に身体障害者療護施設等への短期入所による介護サービスを提供する (9力所-18床) |
【ケア付き住宅】 重度身体障害者に介助サービスを提供するとともに、障害者に適した設備を有する住宅 (5戸) ※平成10年4月入居予定 |
||
| 知的障害者 | 【精神薄弱者更生施設】 18歳以上の知的障害者を入所・通所により保護するとともにその更生に必要な指導及び訓練を行う ◇入所施 (20力所-1,105名) ※はんとく苑の定員は5名で計上 ◇通所施設 (1O力所-300名) ※分場も1ヶ所として計上 |
【精神薄弱者授産施設】 18歳以上の知的障害者で就職が困難な者に入所・通所による自活に必要な訓練や職業を提供する ◇入所施設 (2力所-100名) ◇通所施設 (11カ所-394名) ※入所施設に併設の3ヶ所を含む |
【ショートスティ専用床】 家族での介護が一時的に受けられない障害者に精神薄弱者更生施設等への短期入所による介護サービスを提供する (22力所-89床) |
【グループホーム】 地域の中にある住宅等において共同生活を営む知的障害者に世話人による食事提供や金銭管理などの日常生活に必要な便宜を提供する (44力所-178名) |
|
| 【小規模作業所】 在宅の障害者に技術習得や就労の機会を提供し社会生活への適用性を高める (43力所-760名) |
【通勤寮】 就労している知的障害者に居室その他の設備を利用させるとともに独立生活に必要な助言・指導を行う (1力所-20名) |
||||
|
|||||
| 精神障害者 | 【精神障害者援護寮】 回復途上にある精神障害者に生活の場を提供するとともに生活指導を行う (1力所-20名) |
【精神障害者通所授産施設】 作業能力のある精神障害者に通所による自活に必要な訓練を行う (3力所-87名〕 |
【精神障害者通所授産施設】 作業能力のある精神障害者に通所による自活に必要な訓練を行う (3力所-87名) |
【精神科デイケア施設】 精神病院等に設置し、医療保険の適用を受けて、作業訓練レクリェーション指導、生活指導等を通じた治療を行う (7力所) |
【グループホーム】 地域の中にある住宅等において共同生活を営む精神障害者に世話人による食事提供や金銭管理などの日常生活に必要な便宜を提供する (9力所-48名) |
| 【小規模作業所】 回復途上にある在宅の精神障害者に生活指導、作業訓練等を提供し社会復帰の促進を図る (34力所-492名) |
【小規模作業所】 回復途上にある在宅の精神障害者に生活指導、作業訓練等を提供し社会復帰の促進を図る (34力所-492名) |
【精神障害者ショートスティ施設】 家庭での介護が一時的に受けられない障害者に精神障害者援護寮等への短期入所による介護サービスを提供する (1力所-2名) |
|||
| 障害者の現状 |
| 1 | 身体障害者 |
平成8年度末現在、本県において身体障害者手帳の交付を受けている身体障害児(者)の総数は71,388人で、県人口に占める割合は3.07%となっています。
| 障害種別の状況 |
障害種別にみると平成8年度末現在では、肢体不自由が最も多く全体の58.4%と約6割を占めています。
また、過去10年間の推移を見ると、視覚障害、聴覚平衡機能障害及び肢体不自由の割合が減少する一方で、心臓機能障害をはじめとする内部障害の割合が増加しています。
身体障害児(者)の障害種別の推移
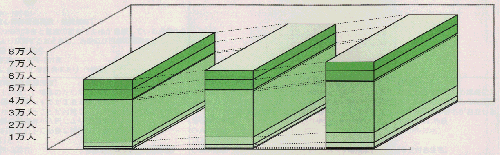
|
||||||
| 昭和61年度末 | % | 平成3年度末 | % | 平成8年度末 | % | |
| 視覚障害 | 7,425 | 13.1 | 7,265 | 11.3 | 7,082 | 9.9 |
| 聴覚平衡機能障害 | 8,450 | 14.9 | 8,324 | 13.0 | 7,858 | 11.0 |
| 音声言語機能障害 | 578 | 1.0 | 711 | 1.1 | 911 | 1.3 |
| 肢体不自由 | 34,755 | 61.2 | 38,176 | 59.6 | 41,692 | 58.4 |
| 心臓・呼吸器機能障害 | 3,398 | 6.0 | 6,069 | 9.5 | 8,811 | 12.3 |
| じん臓機能障害 | 1,711 | 3.0 | 2,511 | 3.9 | 3,418 | 4.8 |
| ぼうこう・直腸・小腸機能障害 | 450 | 0.8 | 988 | 1.5 | 1,616 | 2.3 |
| 合計 | 56,767 | 64,044 | 71,388 | |||
| 障害程度別の状況 |
近年、特に軽度(5・6級の手帳所持者)の割含が減少している一方で、重度(1・2級の手帳所持者)の身体障害児(者)が増加しており、障害の重度化の傾向が見られます。
身体障害者手帳の等級別の推移
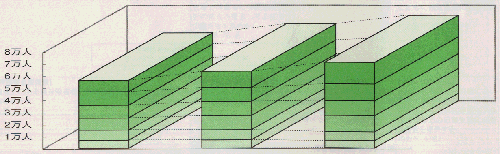
|
||||||
| 昭和61年度末 | % | 平成3年度末 | % | 平成8年度末 | % | |
| 1級 | 9,517 | 16.8 | 13,315 | 20.8 | 18,083 | 25.3 |
| 2級 | 10,940 | 19.3 | 11,966 | 18.7 | 13,693 | 19.2 |
| 3級 | 10、695 | 18.8 | 11,429 | 17.8 | 12,463 | 17.5 |
| 4級 | 10,431 | 18.4 | 12,037 | 18.8 | 13,241 | 18.5 |
| 5級 | 7,990 | 14.1 | 8,099 | 12.6 | 7,504 | 10.5 |
| 6級 | 7,194 | 12.7 | 7,198 | 11.2 | 6,404 | 9.0 |
| 合計 | 56,767 | 64,044 |   | 71,388 |   | |
| 2 | 知的障害者 |
平成8年度末現在、本県において療育手帳の交付を受けている知的障害児(者)の総数は8,996人で、県人口に占める割含は0.39%となっています。
療育手帳所持者数は、昭和61年度末に5,399人でしたが、平成8年度末には、手帳制度の普及もあり、8,996人と約1.7倍に増加しました。
また、障害の程度別を見ると、昭和61年度末の療育手帳A(重度)の手帳所持者の割合は、64.4%でありましたが、平成8年度末には55.8%と10ポイントほど減少しているものの、重度の総数は3,476人から5,016人と約1.5倍に増加しました。
さらに、18歳未満と18歳以上の割合を見ると、18歳以上の割合がここ10年間で約5%ほど伸びています。
知的障害の障害程度別並びに児・者の推移
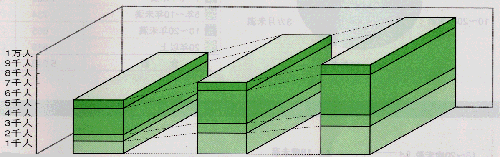
|
||||||
| (単位:人) *Aは重度、Bは中軽度の手帳保持者をいう。 |
||||||
| 昭和61年度末 | % | 平成3年度末 | % | 平成8年度末 | % | |
| A・18歳未満 | 849 | 15.7 | 859 | 11.9 | 951 | 10.6 |
| A・18歳以上 | 2,627 | 48.7 | 3,251 | 45.1 | 4,065 | 45.2 |
| B・18歳未満 | 649 | 12.0 | 962 | 13.4 | 1,113 | 12.4 |
| B・18歳以上 | 1,276 | 23.6 | 2,131 | 29.6 | 2,867 | 31.9 |
| 合計 | 5,399 | 7,203 | 8,996 | |||
| 3 | 精神障害者 |
本県の精神障害者の総数は、平成9年6月末現在の推計で約30,500人(国の障害者プランに基づく推計値)であリ、県人口に占める割含は1.3%となっています。
| (平成9年6月末現在) | |||
| 全体 (推計) |
精神病院入院 | 社会復帰施設入所 グループホーム利用 |
在宅 (推計) |
| 30,500人 | 5,013人 | 57人 | 25,430人 |
| 通院公費負担医療患者数 8,651人 | |||
| 精神障害者保険福祉手帳所持者数 2,319人 | |||
精神病院の入院患者の在院期間は、1年未満が32.9%、1~10年未満が42.5%、l0年以上が24.6%となっており、またその年齢構成を見ると約7割が20~65歳となっています。
また、その入院患者を疾患別で見ると、精神分裂病が58.8%と最も多く、次いで器質性精神病(主に老人性痴呆)、躁うつ病の順となっています。さらに、通院公費負担医療承認者を疾患別に見ると、精神分裂病が46.1%で最も多く、次いでてんかん、躁うつ病となっています。
精神病院の入院患者の在院期間構成
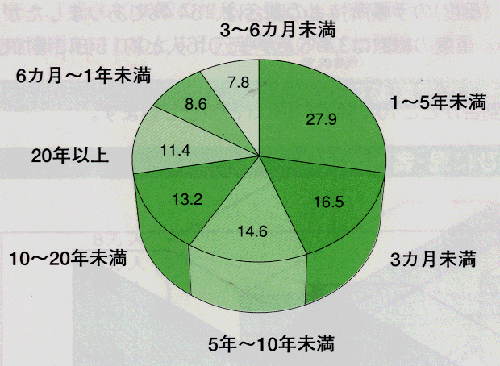
|
(単位:人) | ||
| 3カ月未満 | 828 | (16.5%) | |
| 3~6カ月未満 | 389 | (7.8%) | |
| 6カ月から年未満 | 429 | (8.6%) | |
| 1~5年未満 | 1,399 | (27.9%) | |
| 5年~10年未満 | 734 | (14.6%) | |
| 10~20年未満 | 665 | (13.2%) | |
| 20年以上 | 569 | (11.4%) | |
| 合計 | 5,013 | ||
精神病院の入院患者の年齢構成
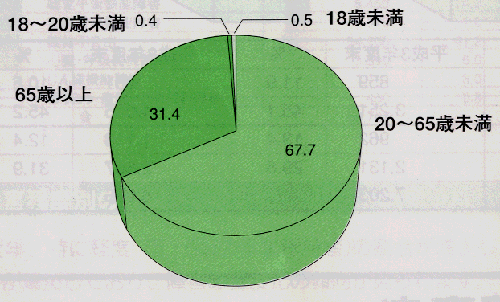
|
(単位:人) | ||
| 18歳未満 | 26 | (0.5%) | |
| 18~20歳未満 | 20 | (0.4%) | |
| 20~65歳未満 | 3,392 | (67.6%) | |
| 65歳以上 | 1,575 | (31.4%) | |
| 合計 | 5,013 | ||
精神障害者の精神疾患の種類別構成
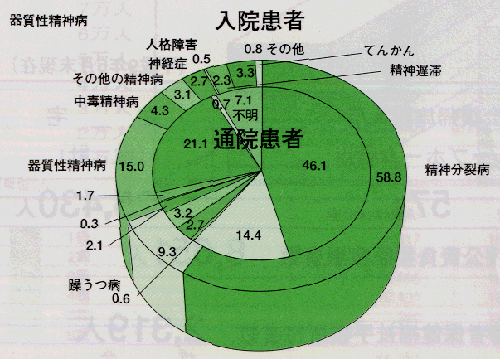
|
(単位:人) | ||||
| 入院患者 | % | 退院患者 | % | ||
| 精神分裂病 | 2,949 | 58.8 | 3,989 | 46.1 | |
| 躁うつ病 | 464 | 9.3 | 1,244 | 14.4 | |
| 器質性精神病 | 752 | 15.0 | 55 | 0.6 | |
| 中毒精神病 | 215 | 4.3 | 237 | 2.7 | |
| その他の精神病 | 155 | 3.1 | 277 | 3.2 | |
| 神経症 | 133 | 2.7 | 181 | 2.1 | |
| 人格障害 | 25 | 0.5 | 27 | 0.3 | |
| 精神遅滞 | 114 | 2.3 | 143 | 1.7 | |
| てんかん | 165 | 3.3 | 1,825 | 21.1 | |
| その他 | 41 | 0.8 | 62 | 0.7 | |
| 不明 | 0 | 0.0 | 611 | 7.1 | |
| 備考:通院は通院公費負担承認件数より 入院は、平成9年厚生省報告例より |
合計 | 5,013 | 8,651 | ||
主題:
みやぎ障害者プラン
発行者:
宮城県
頁数:
1頁~8頁
発行年月:
平成11年3月 第2刷発行
文献に関する問い合わせ先:
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
