みやぎ障害者プラン
宮城県障害福祉長期計画
地域で自分らしい生活を安心して送れる社会をめざして
現状と課題
- 障害者に対する理解は徐々に県民の間に定着しつつありますが、平成8年度に実施した障害者施策推進基礎調査(注.3)(以下「基礎調査」という)によると、障害のある人で「その理解が進んでいる」と感じている人の割合は全体の1割程度にとどまっています。
- また、精神障害者においても、障害を正しく理解されていないことが多く、社会的にも不利な状況におかれています。
- このため、啓発・広報活動を一層推進し、障害者に対する理解の促進を図るとともに、障害のあるなしにかかわらず、すべての人に生涯にわたる福祉教育・学習の機会を提供し、ボランティア活動などを通じた交流を促進することによリ、各人が互いの人格を尊重し思いやる心を醸成する必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「障害や障害者に関する一般県民の理解は?」 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害者 | 知的障害者 | ||
| 進んでいる | 12.0 | 6.6 | |
| かなり進んできたが不十分 | 40.7 | 39.4 | |
| 全く進んでいない | 14.7 | 19.5 | |
| わからない | 24.1 | 25.4 | |
| 不明 | 8.5 | 9.1 | |
施策の方向
-
啓発・広報活動の推進
- 「障害者の日」(12月9日)や「障害者雇用促進月間」(9月)、「精神保健福祉普及月問」(10月)などにおける啓発活動を推進し、障害者に対する理解の促進を図リます。
- 障害者とのふれあい・交流をテーマとした「心の輪を広げる体験作文」や「障害者の日のポスター」の募集を通じ、障害者に対する理解の促進を図ります。
- 県政広報番組を通じ、地域で生活する障害者や福祉活動に取り組む人々を紹介し、その理解の促進に努めます。
- 知事への手紙「知事さんあのね…」などを通じて、障害のある人などから幅広い意見を聴き、それに基づいた施策の展開を図ります。
-
福祉教育と交流の促進
- 学校教育においては、校内での教育活動だけでなく、地域の社会福祉施設等も活用した介護体験、キャップハンディ体験(障害疑似体験)や、高齢者や障害者との交流を通じて、障害者への理解を深めます。
- 相互の理解の促進を図るため、県心身障害者福祉センター等においてキャップハンディ体験学習の開催やボランティアの養成等を積極的に行います。
- 障害者と地域住民のふれあいを通じて、その理解と認識を一層深めるために、「とっておきの芸術祭」や地域交流事業をはじめとする各種のイベントを開催します。
- 障害者が作った製品を地域住民に販売する場を提供したり、地域住民も共に参加できる体験乗馬や市民農園整備などの事業を実施し、障害者に対する理解を深めます。
-
ボランティア活動の振興
- ボランティア活動の場の提供や窓口、情報交換の場の整備に努めながら、自発的な民間活動を支援していきます。
- 多くの住民の参加が得られるように参加しやすい環境づくりを進めるためにも、キャンペーンを中心とした普及啓発活動や福祉教育を積極的に進め、ボランティア活動を支援する世論の形成とボランティア人口の拡大を目指します。
- ボランティア活動の効率的実施に向け、様々なボランティア活動を相互に結び付け調整し、さらには福祉活動そのものをリードするボランティア・コーディネーターの人材を養成します。
- また、手話・要約筆記・点訳・朗読などの情報提供に関わるボランティアやガイドヘルパー(外出介護員)など、特定ボランティアの育成強化にも努めます。
- 平成13年に本県で予定されている「第37回全国身体障害者スポーツ大会」の開催に向け、手話通訳や要約筆記などの大会支援ボランティアを大幅に育成します。
- 住民が積極的にボランティア活動に参加する機会をつくるため、障害者施設等における受け入れ体制を整備します。
- 地域で生活する精神障害者の人権に配慮した社会活動への支援や精神障害者に対する正しい理解を深めるため、メンタルヘルスボランティアの養成を図ります。
| 今回のプラン策定の参考とするために、県内に在住する身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害者とその家族の日常生活、就労、社会参加などの状況を調査したアンケート調査であり、平成8年9月から10月にかけて実施したもので、対象となった障害者数は次のとおりです。 ◇身体障害児(者)3,526人(うち有効回収数 2,885人) ◇知的障害児(者)1,741人( 〃 1,408人) ◇精神障害者 750人( 〃 522人) なお、本プランの本文中でこの調査結果を記載する場含は「基礎調査」という略称を使用することとし、原則として各質問項目に対するその有効回収数の割含(%)で示すこととします。 |
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ② | 交流教育地域推進事業 | 県、市町村 | 特殊教育諸学校及び小中学校の特殊学級と、幼稚園、小中学校及び高等学校や地域社会との多様な交流活動を展開し、児童生徒等の豊かな人間形成を図るとともに、障害のある児童生徒等に対する理解の促進を図ります。 | 実施 | 拡充 |
| ② | 障害者乗馬推進事業 | 県福祉事業団 | 障害者乗馬の拠点施設を整備し、継続的な乗馬療法訓練を実施し、あわせて地域住民等への乗馬体験や移動乗馬教室を実施します。 | 整備中 | 1ヵ所 |
| ② | 園芸遊々ランド整備事業 | 市町村 | 障害者等の体力の維持と機能回復を図り、地域内での交流を促進するために、社会福祉施設の周辺等に地域住民と障害者がともに利用できる市民農園を整備します。 | 3ヵ所 整備中 |
7ヵ所 |
| ③ | 情報ネットワーク事業 | 県社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 |
地域で様々なボランティア・市民活動を展開している方々へまた、その活動を支援する機関・団体をつなぐ情報ネットワークを構築し、常にタイムリーで充実した情報を提供していきます。 | 実施 | 拡充 |

|
| 社会福祉施設での車イスの体験風景 |
第2節 コミュニケーション手段の充実
現状と課題
- 情報、コミュニケーションの確保は、障害者が地域で安心して生活し社会参加をしていく上で極めて重要な意義をもっています。
- 特に視覚障害者や聴覚障害者などは、その障害のため情報の収集・コミュニケーションの確保に大きなハンディキャップがあります。
- このため、社会の高度情報化が進展する中で、障害者もその利便性を十分享受できるよう、各種情報提供手段の充実に努め、障害の程度に応じて、より豊かな情報量を迅速に提供できる体制を整備していく必要があります。
施策の方向
-
コミュニケーション手段の充実
- パソコン講習会などを開催し、障害者の情報機器の利用を促進します。
- 朗読ボランティアによる文書の代読サービス等を実施します。
- 県が設置する手話通訳相談員の充実を図るとともに、市町村における手話通訳者の配置を促進します。
- 手話奉仕員養成事業を充実し、その養成や資質の向上を計画的に図るとともに、派遣体制の整備充実を推進します。
- 要約筆記奉仕員(P79参照)の養成・確保を図るとともに、派遣体制の整備を促進します。
- ファックスや重度障害者用意志伝達装置としてのパソコンなどの日常生活用具(P.79参照)を給付・貸与し、その普及推進に努めます。
- 盲ろう者のコミュニケーション手段を確保するため、指文字、指点字等により通訳を行う通訳者の養成について検討します。
-
情報提供の充実
- 県政テレビヘの手話・字幕の挿入や県広報紙の点字版、録音テープ版の作成などにより、県政の話題や施策に関する情報の提供をさらに推進します。
- 点訳・朗読ボランティアの養成やその資質向上を図るとともに、県点字図書館における点字図書や録音図書の供給体制の充実を図リます。
- 新しい宮城県図書館においては、対面朗読室(P.79参照)等を設置するとともに、朗読テープや字幕付きビデオなどを整備し、障害者が必要な情報をいつでも利用できるように配慮します。
- 障害者にとって必要な情報をインターネットやパソコン通信等を利用して提供します。
- 駅をはじめとする公共施設における視聴覚障害者に対する情報提供手段の整備を促進します。
- 視聴覚障害者に対する情報提供機能の充実に努めるとともに、情報提供施設の設置やその運営方法等について検討します。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 障害者の明るいくらし促進事業(市町村障害者社会参加促進事業) | 県、市町村 | 障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加できるようにするために、コミュニケーション支援や情報提供支援などの必要な援助を行います。 | 実施 | 拡充 |

|
| 新しい宮城県図書館の全景 |
第3節 地域における生活の場や活動の場の確保
| 1 | 地域における生活の場の確保 |
現状と課題
- 障害があっても住み慣れた家庭や地域で自立した生活を送りたいと願っている人が多くおります。
障害者が地域での自立を考える時の最初の問題は生活の場です。グループホームや福祉ホームの制度がありますが、その数はまだまだ不十分で、「ケア付き住宅」もモデル的に建設されている段階です。 - また、在宅で生活している障害者の場合でも現在の住まいについて不便を感じている人が多く、それぞれの障害特性に配慮した生活の場を整備・拡充する必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「将来、同居したい人は?」(知的障害者-本人回答の場合) | ||
| グラフ | (単位:%) | |
| 現在の家族と一緒に暮らしたい | 47.6 | |
| 結婚して家庭をつくって暮らしたい | 14.7 | |
| ひとりで仲間と暮らしたい | 6.7 | |
| 気の合う知人や友人と一緒に暮らしたい | 4.0 | |
| 施設で仲間と暮らしたい | 4.0 | |
| その他 | 2.4 | |
| わからない | 20.6 | |
施策の方向
-
グループホーム等の拡充
- 知的障害者や精神障害者のためのグループホームの大幅な拡充を図るとともに、通勤寮、精神障害者援護寮、福祉ホーム(P.5参照)等の設置について検討を進めます。
- 知的障害者のグループホームについては重度加算制度を活用し、重度障害者の利用機会の拡大を図るとともに、入居用件(就労条件等)の緩和など制度の改善を国に働きかけます。
- また、精神障害者のグループホームについては、グループホーム開設時における経費の助成を行うことによリ、その設置を促進します。
- 公営住宅のグループホームヘの活用を促進します。
-
住環境の整備
- 障害者等のための住宅改造への支援やバリアフリー(P.79参照)住宅の整備など住環境の整備を総含的に推進します。
- 障害者のための住宅の改造については、専門的技術の蓄積が必要であり、保健・医療・福祉・建築の専門家がチームを組んで相談や指導に応じるとともに、地域の建築士や建築業者を含めて地域における専門家の養成に努めます。
- 県営住宅の整備に当たっては全戸に床の段差解消や手摺りの設置を行うなどの配慮をします。
- 障害者向け住宅として公営住宅の活用を図るとともに、ケア付住宅モデルの実施を踏まえて、各圏域への整備を検討します。さらにモデル的に実施しているケア付き住宅の運営に対し支援します。
| ◎基礎調査「住まいについて困っていることは?」(身体障害者の場合)§複数回答 | ||
| グラフ | (単位:%) | |
| 階段や段差に苦労する | 16.6 | |
| 浴室等の家屋内の設備が不便である | 16.5 | |
| 家賃やローンが高い | 7.1 | |
| 入り口や廊下のスペースが狭く移動が困難である | 6.7 | |
| その他 | 5.3 | |
| 特に困っていない | 53.1 | |
| ◎精神保健福祉センター実施のアンケート調査「必要な居住施設や集う場所は?」(精神障害の場合) | ||||
| 図 | (単位:%) | |||
| 居住施設 | 集う場 | |||
| 単身のアパート | 21.3 | 就労できる場 | 35.1 | |
| グループホーム | 20.1 | 通所授産施設・作業所 | 20.1 | |
| 福祉ホーム | 13.0 | ソーシャルクラブ | 14.2 | |
| 援護寮 | 14.8 | デイケア | 9.5 | |
| 老人ホーム | 7.1 | 地域生活支援センター | 8.3 | |
| その他 | 23.7 | その他 | 12.8 | |
| ◎グループホームの設置状況(各年度末現在の設置数) | |||
| 図 | (単位:ヶ所) | ||
| 知的障害者 | 精神障害者 | ||
| H元 | 1 | ||
| H2 | 3 | ||
| H3 | 5 | ||
| H4 | 6 | ||
| H5 | 7 | ||
| H6 | 8 | ||
| H7 | 16 | 2 | |
| H8 | 27 | 5 | |
| H9 | 44 | 9 | |
| 2 | 活動の場の確保 |
現状と課題
- 障害者が充実した地域生活を送るためには、様々な活動の場や学習の機会を確保し、その充実を図る必要があります。
- 小規模作業所や通所授産施設などの通所施設の数は年々増加しているものの、まだまだ不十分であり、さらにその多様なニーズに対応していかなければなりません。
- また、技術革新と情報化の進展、価値観・ライフスタイルの多様化など社会環境の急激な変化の中にあって、人々は新しい状況に的確に対応した知識・技術の習得、生きがいの追求など様々な学習の機会を求めており、今後ますます生涯学習を振興していく必要があります。
- しかしながら、障害者にとって利用できる施設や教材などが十分にない状況にあることから、自分の興味や必要性に応じて、身近な地域で希望する学習機会を得られる環境を整備していくことが重要となっています。
掲載データ
| ◎通所施設の整備状況(各年度末現在の設置数・仙台市分も含む・分場も1ヶ所として計上) | ||||||
| 図 | (単位:ヶ所) | |||||
| 知的障害者 | 精神障害者 | |||||
| 小規模作業所 | 通所授産施設 | 通所更生施設 | 小規模作業所 | 通所授産施設 | ||
| H元 | 29 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| H2 | 31 | 5 | 2 | 8 | 1 | |
| H3 | 32 | 7 | 2 | 12 | 1 | |
| H4 | 34 | 8 | 3 | 17 | 2 | |
| H5 | 36 | 8 | 4 | 19 | 3 | |
| H6 | 38 | 8 | 5 | 22 | 3 | |
| H7 | 40 | 9 | 6 | 27 | 3 | |
| H8 | 42 | 9 | 9 | 30 | 3 | |
| H9 | 43 | 10 | 11 | 34 | 3 | |
施策の方向
-
活動の場の確保
- 一般的就労が困難な障害者に対する就労促進の施策として、通所授産施設や分場施設、小規模作業所や福祉工場等の整備を促進します。
- 在宅身体障害者の自立促進、生活改善、身体機能の維持向上のため、デイサービス(日帰り介護)事業の実施市町村の拡大を図ります。
- 障害者が身近な地域で気軽に余暇・文化活動に参加できるよう通所施設、小規模作業所等の施設を活用した活動の場の確保を図ります。
-
多様な学習機会の提供
- 各団体が実施する各種のスポーツ・レクリエーション事業を支援するとともに、趣味の教室などの文化活動を推進します。
- 新しい宮城県図書館においては、障害者等に配慮した各種設備や機能の充実を図るとともに、生涯学習に関する情報提供や普及啓発を行います。
- 地域における学習の機会を確保するため、障害者等が利用しやすい社会教育施設の整備に努めます。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-① | 精神薄弱者・ 精神障害者地域生活援助事業 |
市町村 他 |
地域社会の中にあるアパート等において、数人の知的障害者等が共同生活を営むグループホームに対し支援し、大幅な拡充を図ります。 | 31ヵ所 | 121ヵ所 |
| 1-① | 精神障害者グループホーム 特別推進事業 |
市町村 民間法人 他 |
グループホームの開設経費に対する助成を行い、グループホームの設置を促進します。 | - | 15ヵ所 |
| 1-① | 精神障害者社会復帰施設整備事業 (生活訓練施設) |
県 市町村 他 |
精神障害者訓練施設等の社会復帰施設を整備し、精神障害者の社会復帰及び自立の促進を図ります。 | 0ヵ所 | 1ヵ所 |
| 1-② | 高齢者・障害者対応公営住宅整備事業 (ケア付住宅整備事業) |
県 市町村 |
重度身体障害者に介助サービスを提供するとともに、障害者に適した設備を有するケア付き住宅の整備を支援します。 | 1ヵ所 整備中 |
拡充 |
第4節 福祉のまちづくりの推進
| 1 | 福祉のまちづくりの総合的推進 |
現状と課題
- 基礎調査によると、障害者の中には歩きにくい歩道、使いにくい建物や交通機関など、まだまだ外出時に不安を感じる人が多くおります。障害者が地域の中で主体性、自主性を持って活動していくためには、生活空間における物理的な障壁を取り除き、障害者等に配慮したまちづくりを総含的に推進していく必要があります。
- 本県では平成8年7月に「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を制定しましたが、障害者等をはじめとするすべての県民が安心して生活を営むことのできる住みよい社会の実現に向け、今後、条例の理念の普及・円滑な施行と支援制度の確立を図る必要があります。
- さらに、今後新築される病院などの公益的施設はもちろんのこと、既存の公益的施設についても、バリアフリー化が求められています。
掲載データ
| ◎基礎調査「外出の際に困ることは?」(身体障害者の場含)§複数回答 | ||
| 図 | (単位:%) | |
| 道路の段差や駅の階段が多い | 29.6 | |
| 利用できる交通機関が少ない | 18.1 | |
| 利用する建物の設備(スロープ、トイレ等)が不備 | 15.1 | |
| 車などに危険を感じる | 14.0 | |
| 経費がかかる | 13.2 | |
| 人と話すことが困難 | 10.6 | |
| 駐車場がない | 9.0 | |
| 人の目が気になる | 8.8 | |
| 介助者がいない | 6.5 | |
| その他 | 5.1 | |
| 特にない | 24.6 | |
| 不明 | 13.2 | |
施策の方向
-
福祉のまちづくリの総含的推進
- 県、市町村、事業者及び県民が一体となってまちづくりを推進する体制を整備するとともに、障害者本人の意見も取り入れながら、まちづくりを計画的・総合的に推進します。
- 障害者等が利用しやすい施設などの情報提供や福祉のまちづくりへの理解を深めるための普及啓発を図リます。
- 市町村が福祉のまちづくりを目指して、地域の人々の合意に基づいて総合的な計画を策定し、公共施設の改善を図るために支援します。
-
公共施設等の整備
- 条例に基づき、県や市町村の設置する施設はもとより、民間の公益性の高い建物のバリアフリー化を促進します。
- また、ハートビル法に基づく建築物の認定により、税制上の特例措置や低利融資などの支援策を活用し、障害者等の利用に配慮した建築物の整備を促進します。
- より総含的・効率的にバリアフリーを進めるために、建物だけでなく、周辺の道路や河川公園・都市公園などの整備についても、障害者等の利用に配慮します。
- 観光地のバリアフリー化を促進し、障害のある人が自由に旅行を楽しめるような観光地を目指します。
| 2 | 交通・移動対策の充実 |
現状と課題
- 障害者が外出しようとする際に、利用できる交通機関が少ないとか、道路の段差や階段が多く歩行の安全が確保されていないというように感じている人が多くおります。
- このため、障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で移動できるように、道路や公共交通機関のバリアフリー化と歩行環境の改善を図る必要があリます。
施策の方向
-
公共交通機関等の整備
- 障害者等にとって大切な移動手段を確保するため、交通事業者が行うリフト付きバス・低床バスの導入の支援を行うとともに、鉄道駅舎等におけるエレベーターの整備を支援します。
- 交通機関に携わる人々の福祉に対する理解を促進するほか、福祉マップの作成・配布を行うなど障害者が外出しやすい環境整備を図ります。
-
道路交通環境の整備
- 幅の広い歩道の整備やわかりやすい道路標識の整備、歩行時間延長信号機など視覚障害者用信号機の設置、福祉施設周辺などの道路環境の整備等を推進します。
- 幅の広い歩道の整備やわかりやすい道路標識の整備、歩行時間延長信号機など視覚障害者用信号機の設置、福祉施設周辺などの道路環境の整備等を推進します。
-
移動手段の確保
- 重度の視覚障害者や脳性まひ者等の全身性障害者が外出する際に付添いを行うガイドヘルパー(外出介護員)の養成及び派遣体制を整備・拡充します。
- 身体障害者の自動車運転免許の取得や自動車改造に対する支援を拡充します。
- 歩行の困難な在宅障害者等の移動手段の確保を図るため、市町村が行うリフト付きワゴン車の運行事業に対して支援するとともに、民間ボランティア団体等の運営する移送サービスを支援します。
- 重度の視覚障害者が安心して生活するために必要な盲導犬を貸与するとともに、盲導犬に対する県民の理解を促進します。
- 盲導犬を育成するために、民間で建設が計画されている盲導犬訓練施設について、関係機関と協議しながらその支援策を検討します。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-① | だれもが住みよい福祉のまちづくり推進事業だれもが | 民間 市町村 県 |
条例を普及し、だれもが住みよい福祉のまちづくりを推進するため、幅広い推進組織を設立し、それを母体とした各種の普及事業を実施します。 | 実施 | 毎年継続実施 |
| 1-② | 「旅たび宮城へ」推進事業 | 県 | 障害者が自由に旅行できるような観光地を目指し、観光のバリアフリー化を推進するための調査・研究等を行います。 | - | 実施 |
| 1-③ | 在宅重度身体障害者等移送サービスシステム整備推進事業 | 県 | 歩行が困難な在宅の重度身体障害者のニーズにあった望ましい移送サービスの実施のため、移送サービスシステムの構築を図ります。 | - | 実施 |
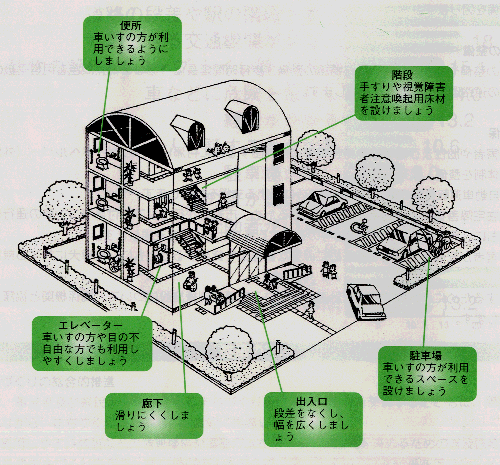
主題:
みやぎ障害者プラン
発行者:
宮城県
頁数:
9頁~19頁
発行年月:
平成11年3月 第2刷発行
文献に関する問い合わせ先:
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
