みやぎ障害者プラン
宮城県障害福祉長期計画
地域で自分らしい生活を安心して送れる社会をめざして
現状と課題
- 基礎調査の結果では、知的障害児をもつ家庭のうち、その約7割が何らかの通園施設等に通わせたいと回苔しており、今後、各種の通園施設を拡充し、療育体制の充実を図る必要があります。
- 障害児の療育は、家庭での生活に基盤を置きながら、療育のための通園施設の充実など、成長の各段階において、地域における療育支援の体制を整備する必要があります。
- 乳幼児期においては早期発見・早期療育に努め、障害児やその保護者に対して早期から一貫した療育支援を行うことが大切です。
- このため、現在、児童相談所や保健所等の機関ごとに行われている地域療育のシステム化を図り、家族や施設等に対する支援体制を充実する必要があります。
- また、学齢期においては、学校教育を受けながらも福祉施設等における訓練・治療が受けられるなど、個々の二一ズに応じて柔軟に対応できる体制を整える必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「平日の昼間の過ごし場所は?過ごしたい場所は?」(就学前の知的障害児の場合) | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 過ごし場所 | 過ごしたい場所 | ||
| 自分の家 | 36.8 | 29.8 | |
| 通園施設 | 28.1 | 29.8 | |
| 保育所 | 28.1 | 34.0 | |
| 幼稚園 | 1.8 | 4.3 | |
| その他 | 5.3 | 2.1 | |
施策の方向
-
地域療育システムの構築
- 現状では障害児の療育支援のためのネットワークシステムやコーディネートする機関が十分に整備されておりません。このため、療育事業を総合的に調整・推進するための地域リハビリテーション支援システムを構築します。
- さらに、障害児(者)施設を中核として広域圏域ごとに療育機関のネットワーク化を図り、早期から一貫した療育指導を目指します。
-
療育の充実
- 在宅の障害児が身近な場所で療育を受けられるよう地域の実情に即した小規模型の通園の場の整備を促進します。
- 在宅の重症心身障害児(者)に対し、通園の方法による場を整備します。
- 地域の幼稚園・保育所における障害のある幼児の教育・保育を支援し、より一層の充実を図ります。
-
家族支援の充実
- ホームヘルプサービス(訪問介護事業)、在宅重症心身障害児の巡回訪問相談事業等を行い、家庭における生活支援を行います。
- ショートスティ(短期入所生活介護事業)、デイケア(日中介護)、ナイトケア(夜間介護)等の施設を活用したレスパイト事業を実施し、障害児(者)をもつ家族に一時の休息を提供します。
|
<<障害児(者)レスパイとケアの概念図>> <いつでも> <どこでも> <だれでも> |
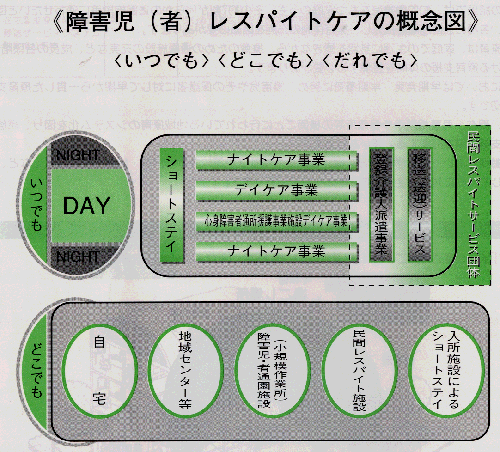
|
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 障害児地域リハビリテーション支援システム策定事業 | 県 | 地域リハピリテーション支援システム策定について広く検討し、障害児が安心して地域で生活するサポートシステムを構築します。 | - | 機能展開 |
| ① | 障害児(者)地域療育等支援事業 | 県 | 身近な地域で療育指導・相談等が受けられる療育機能並びに体制の充実を図ります。 ・療育拠点施設事業…県内1ヵ所 ・療育等支援施設事業…コーディネーターの設置県内7力所 |
2ヵ所 | 1ヵ所 |
| ② | 重症心身障害児(者)通園事業 | 県 | 通園施設を設け、重症心身障害児(者)に必要な療育を提供します。 ・運動機能等の低下を防止するとともに、その発達を支援 ・保護者等に家庭における療育技術を提供 A型施設(定員15人)B型施設(定員5人) |
1ヵ所 | A型 1ヵ所 B型 4ヵ所 |
| 障害児(者)地域療育支援事業展開図 |
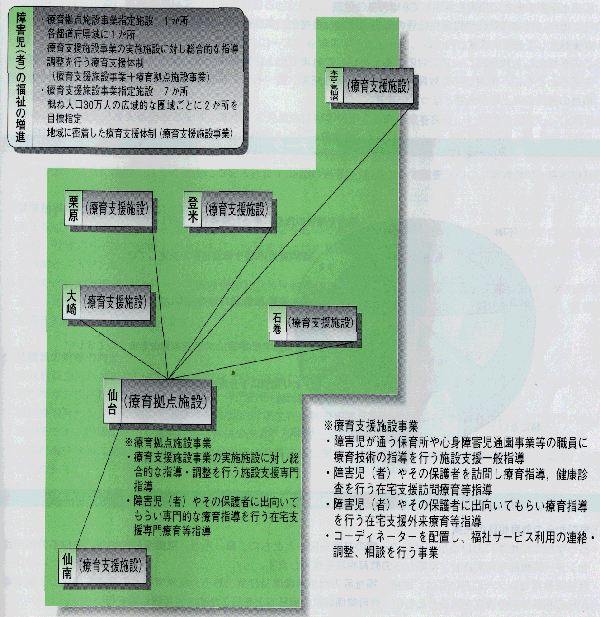
|
第2節 教育の充実
現状と課題
- 障害のある幼児児童生徒については、一人ひとリの障害の状態や発達段階等に応じて、その可能性を最大限に伸ばし、社会参加・自立に必要な力を培う教育が求められています。
- このため、盲学校、ろう学校及び養護学校、小・中学校の特殊学級や通級による指導において、個々の児童生徒等の障害の状態等を考慮し、少人数による学級編制、手厚い教職員配置、障害に配慮した教育課程など、様々な工夫と配慮のもとに指導を展開しています。
- 特に近年、社会の変化や児童生徒等の障害の重度・重複化、多様化が一層進んでいる中で、教育に対するニーズが多様化してきています。
- この多様化した教育的ニーズに対応するために、これまで以上に関係機関との連携を強化し、就学指導の適正化を図るとともに、早期からの教育相談や交流教育の充実、盲・ろう・養護学校の拡充整備、職業教育の充実、教職員の資質の向上等が必要となっています。
掲載データ
| ◎基礎調査「学校教育について要望することは?」§複数回答 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害 | 知的障害 | ||
| 能力や障害の程度にあった指導をしてほしい | 13.5 | 33.0 | |
| 就学(能力)相談や教育相談を充実してほしい | 9.2 | 10.9 | |
| 施設、設備、教材等を充実してほしい | 7.2 | 11.4 | |
| 普通学校(学級)との交流の機会を増やしてほしい | 6.3 | 11.9 | |
| より個別に十分に指導してほしい | 4.8 | 16.5 | |
| その他 | 1.2 | 2.3 | |
| 特にない | 22.7 | 17.5 | |
| 不明 | 51.3 | 32.7 | |
施策の方向
-
早期からの教育相談の充実
- ろう学校の幼稚部における早期教育の一層の充実を図るとともに、盲・ろう・養護学校の地域における教育相談センター的機能を充実させ、早期からの教育相談を推進します。
- 県特殊教育センターにおいては、医療・福祉等の関係諸機関及び盲・ろう・養護学校との連携を強化し、就学前からの相談体制の確立を図るとともに、教育関係職員の資質向上を図るための各種研修等を行います。
-
義務教育段階の教育の充実
- 障害のある児童生徒の多様な二一ズに対応し、きめ細かな教育を行うため個別的な指導計画を工夫するなど一人ひとりに応じた指導や、また、通級による指導など適切な場での教育をより一層推進します。
- 障害のある児童生徒の重度・重複化に適切に対応するため、教育課程の改善や一人ひとリに応じた指導の充実を図ります。また、通学バスの整備を行うとともに、医療行為を必要とする児童生徒の就学環境の整備を図ります。
- 障害の種類や程度に応じた適切な教育を確保しつつ、児童生徒の通学時間の短縮と地域の子供たちとの交流を進めるための施策を検討します。
- 障害のある児童生徒の社会参加・自立に必要な力を培うため、特殊教育諸学校の校舎の改築や修繕を進め、施設設備の整備充実を図ります。
-
後期中等教育段階の教育の充実
- 障害の重度・重複化に対応するため、特殊教育諸学校高等部に重複障害学級の設置を進めるとともに、訪問教育を実施します。
- 障害のある生徒の教育機会を拡充するため、新設する県立高等学校については、エレベーター、障害者用トイレ、スロープ等を設置し施設のバリアフリー化を図るとともに、既設の高等学校についても順次、改修等を行います。
- 特殊教育諸学校の高等部においては、卒業後の社会的・職業的自立に向けた多様な職業教育の充実を図ります。県立2校目の高等養護学校においては、多様なコース制を導入するとともに、弾力的な履修形態とし、職業教育を充実します。
-
交流教育の充実
- 障害のある幼児児童生徒のみならず、すべての児童生徒等の豊かな人間形成を図り、社会性を育成し、人権尊重の意識を高める上でも大きな意義のある交流教育をより一層推進します。
- 交流教育の推進にあたっては、小・中学校の通常学級と特殊学級との交流、小・中・高等学校と特殊教育諸学校との交流、さらに地域社会との交流に力を入れます。
-
就学指導の充実と啓発活動の推進
- 適正な就学は、適切な教育を進めるための基礎となるものであリ、障害児に対する就学指導においては、障害の種類、程度等を的確に判断するとともに、保護者をはじめ教員や一般社会の人々の特殊教育に対する理解・認識を深めるよう努めます。
- このため、特殊教育センターや関係諸機関及び特殊教育諸学校等との連携を図り、適正な就学指導に努めます。また、地域ぐるみの啓発活動を目指し、地域社会、教育団体、関係機関等と協力して、講演会、作品展、広報活動等を組織的・継続的に行います。
-
教職員の資質の向上
- 特殊教育担当教員については、幼児児童生徒の多様な障害の状態に対応して適切な教育を行うために、特にその専門性が要求されることから、基礎的・専門的研修の機会の確保と充実に努めます。
- 県特殊教育センターにおいて障害のある幼児児童生徒の教育相談を行うとともに、特殊教育担当者の資質の向上を図るため、各種の研修や指導内容・方法の充実、改善のための調査研究を行います。
- 特殊教育諸学校において、障害児の教育相談や教員研修に関する地域の拠点的機能が発揮できるよう環境の整備に努めます。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 障害児早期教育・相談充実事業 | 県 市町村 |
幼児期を中心とした低年齢の障害児に係る教育・相談体制の充実を図ります。 | 実施 | 充実 |
| ② | 要医療行為通学児童生徒学習支援事業 | 県 | 経管栄養などを必要とする児童生徒が、養護学校等で訪間看護婦から医療ケアを受ける際に財政的支援を行い、就学環境の整備を図ります。 | 実施 | 拡充 |
障害のある児童・生徒の就学状況(義務教育)
| グラフ | 区分 | 児童数(人) | 比率(%) | |
| 小学校 | 知的障害 | 505 | ||
| 言語障害 | 164 | |||
| 情報障害 | 218 | |||
| その他 | 135 | |||
| (特殊学級)計 | 1,022 | 42.7 | ||
| 中学校 | 知的障害 | 323 | ||
| 言語障害 | 0 | |||
| 情報障害 | 57 | |||
| その他 | 54 | |||
| (特殊学級)計 | 434 | 18.1 | ||
| 養護学校 (小学部・中学部) |
知的障害 | 676 | ||
| 病弱 | 65 | |||
| 肢体不自由 | 93 | |||
| 計 | 834 | 34.9 | ||
| ろう学校 | 75 | (3.1) | ||
| 盲学校 | 21 | (0.9) | ||
| 不就学 | 7 | (0.3) | ||
| 合計 | 2,393 | 100 | ||
| 資料:教育庁総務課学校統計要覧(平成9年5月1日現在) | ||||
第3節 雇用・就労の促進
| 1 | 雇用の促進 |
現状と課題
- 県下の民間企業における障害者の雇用率(1.45%)は、法定雇用率(1.60%)に達しないばかりでなく、全国平均(1.47%)をも下回っています。雇用が進まない理由としては、雇用する側の障害者に対する理解不足も考えられ、法定雇用率未達成企業に対する指導を強化するとともに、障害者の雇用促進について一層の啓発に努める必要があります。
- 近年、中・軽度の障害者の雇用状況は相当改善されていますが、重度の障害者についてはなお、不十分な面が見られます。また、平成10年7月より知的障害者も含めた障害者雇用率制度に改められることから、これを受けてさらに障害者雇用を促進する必要があります。
掲載データ
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施策の方向
-
啓発活動の推進
- 毎年9月の「障害者雇用促進月間」に障害者雇用促進大会を開催するなど、県民、事業主等に対し理解を促すため、障害者雇用について啓発を図ります。
- 毎年9月の「障害者雇用促進月間」に障害者雇用促進大会を開催するなど、県民、事業主等に対し理解を促すため、障害者雇用について啓発を図ります。
-
職業相談、職業紹介の充実
- 公共職業安定所の職業相談員や手話協力員などによる障害に応じた相談指導体制を充実します。
- 個別求人開拓を積極的に行うとともに、求人情報を定期的に本人や家族に提供し、適性や希望に沿った就労を支援します。
-
障害者雇用率の向上と就労の場の確保
- 公共団体等の機関における雇用率を高めるとともに、民間企業における法定雇用率達成のための指導を強化し、雇用の場の拡大に努めます。
- 県職員の採用に当っては、手話通訳や点字受験を実施するなど障害者の受験機会の拡大を図るとともに、市町村職員への障害者の雇用についても働きかけを行います。
- 一定の要件のもとに子会社を設立し、そこに障害者を集中的に雇用し親会社と同一の事業主体を擬制する「子会社特例制度」の活用促進を図ります。
- また、地域における障害者雇用のモデルとして、第3セクター方式の重度障害者多数雇用企業の設立を進めるとともに、未設置の圏域に重度障害者多数雇用企業の設置を推進します。
- 重度身体障害者等がインターネットを活用して自宅で就業できるシステムの研究開発を進め、在宅における就労促進を図ります。
-
福祉的就労の充実と運営の強化
- 一般的就労が困難な障害者に対する就労促進の施策として、適所授産施設や分場施設、小規模作業所や精神障害者福祉工場等の整備を推進します。
- また、これらの福祉的就労の場の運営を安定させるため、授産施設等で構成する社会就労センター協議会の福祉ショップや製品開発研究の支援を進め、宮城県セルプセンターの設立を目指します。
| 2 | 職業リハビリテーションの推進 |
現状と課題
- 障害の重度化等に伴い、働くことが困難な障害者が増加しており、また、就労に対して不安を持っている人も数多くいます。
- 障害者の就業や職業的自立を促進するためには、学校教育や福祉施設における取り組みを強化するとともに、就労に対する不安解消のための相談体制を拡充し、専門的な職業能力開発のための施設を整備するなど、障害者の能力や障害の状況に応じた幅広い職業能力開発の機会を確保する必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「仕事に就く場合に不安に思うことは?」(知的障害者の場合) | ||
| 調査結果グラフ | (単位:%) | |
| 仕事に就くこと自体が不安である | 14.7 | |
| 自分に合う仕事があるか不安である | 13.4 | |
| どういう仕事が向いているかわからず不安である | 9.3 | |
| 職場環境になじめるか不安である | 8.5 | |
| 職場まで通勤できるか不安である | 3.2 | |
| 仕事に就いた場合住宅が確保できるか不安である | 0.3 | |
| その他 | 7.6 | |
| 不明 | 43.0 | |
| ◎基礎調査「現在の仕事を続ける上で必要な援助は?」(精神障害者の場合)§複数回答 | |||
| 回答結果のグラフ | (単位:%) | ||
| すぐに相談できる人や場所がほしい | 82.1 | 援助が必要 66.1 |
|
| 通院のための時間を認めてほしい | 46.2 | ||
| 病気について正しく理解してほしい | 41.0 | ||
| 慣れるまで一緒にいる人がほしい | 25.6 | ||
| 慣れるまで時間を短くしてほしい | 20.5 | ||
| その他 | 10.3 | ||
| 特にない | 23.7 | ||
| 回答なし | 10.2 | ||
施策の方向
-
活動の場の確保
- 県民、企業の障害者職業能力ヘの理解を深めるとともに、障害者自身の技能向上と意欲の高揚を図るため、「身体障害者技能競技みやぎ大会」を開催します。
- 雇用施策と連携し、就労の場の開拓に積極的に取リ組み、就労の意欲がありながらも施設にとどまっている人たちの地域生活への移行を促進するため、職場適応訓練や自活訓練を積極的に行うとともに、就労や自立のための情報把握・提供に努めます。
- 知的障害者や精神障害者を一定期間職親のもとで、仕事や人間関係を通じて生活指導や技能習得訓練を行う職親制度事業を推進します。
- 実際の事業所を職業リハビリテーションの場として活用し、日常生活面から職場での技術面にわたる指導を総含的かつ具体的に行う「職域開発援助事業」を積極的に展開します
- 障害者職業センターにおいて、職業相談や職業評価、職業準備訓練等の職業リハビリテーションを専門的、総含的に実施します。
- 宮城障害者職業能力開発校において、就業に必要な職業能力の開発・向上を図るため、実技を主体とした職業訓練を実施するとともに、就業を促進するため、公共職業安定所等の関係機関との連携を強化します。
- 知的障害者を対象として、その特性に応じた能力開発を行うために、「能力開発センター」の設置を目指します。
- 基本的な労働習慣の習得を図る職業準備訓練から、職場実習や指導・援助等を一貫して行う「障害者雇用支援センター」の設置を推進しながら、職業的自立支援体制の整備を図ります。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-③ | 重度障害者多数雇用企業の設立推進事業 | 民間 | 重度障害者多数雇用企業の設立を推進し、地域の障害者雇用のモデル企業としての機能が発揮できるように支援体制づくりを進めます。 | 6ヵ所 | 10ヵ所 |
| 1-③ | 重度障害者等在宅就労支援事業 | 県 | 重度障害者の就労促進をはかるため、コンピューターネットワークを活用した就労支援システムの研究開発を図ります。 | - | 実施 |
| 1-④ | 障害者福祉ショップ推進事業 | 民間 | 福祉的就労の充実と運営の安定を図るため、販売拠点としての常設福祉ショップを設置し販路開拓を進め、県セルプセンターの設置を目指します。 | 常設店 1ヵ所 |
常設店 セルプセンター 1ヵ所 |
| 2-① | 精神障害者職親制度事業 | 県 市町村 |
精神障害者の社会適応訓練を一定機関事業所に委託し、その精神障害者の社会的自立を促進します。 | 58人 | 100人 (各市町村に1ヵ所) |
| 2-① | 能力開発センター設置事業 | 県 他 | 知的障害者の能力開発と雇用の確保のための拠点施設を整備します。 | 検討 | 1ヵ所 |
| 2-① | 障害者雇用支援センター設置事業 | 市町村 | 重度障害者等の職業的自立に向けて、就職から職場定着までの一貫した支援を行うための拠点を整備します。 | - | 1ヵ所 |
| 障害者雇用支援センターの業務 |
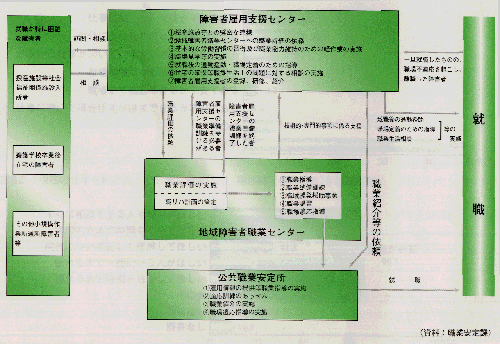
|
第4節 スポーツ・レクリエーションや芸術文化活動の振興
| 1 | スポーツ・レクリエーション活動の振興 |
現状と課題
- 障害のある人とない人とが、スポーツ、レクリエーション、文化活動を通じて交流することによリ相互の理解は一層深まり、また、これらの活動への参加は、障害者自身の心身の機能訓練、生きがいの創造、社会参加意欲の促進という視点からも大きな意味を持っています。
- しかし、情報・移動・施設・指導者等のさまざまな制約があリ、参加の意志がありながら参加できない人も少なくあリません。
- 今後は、障害のある人もない人も共に参加でき、楽しめるスポーツレクリエーションの開発・普及に努めるとともに、障害者の参加を可能にする諸条件の整備に努める必要があります。
- さらに、平成13年に本県で開催される第56回国民体育大会及び第37回全国身体障害者スポーツ大会に向けて、会場施設の整備や大会ボランティア等の養成を計画的に進めていく必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「スポーツや運動をしていて困ることは?」§複数回苔 | |||
| 回答結果のグラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害者 | 知的障害者 | ||
| 施設(場所)がない | 13.6 | 14.9 | |
| 一緒にする仲間がいない | 13.5 | 20.9 | |
| 指導してくれる人がいない | 8.1 | 12.3 | |
| 参加できる催物がない | 7.0 | 11.8 | |
| 介助してくれる人がいない | 3.2 | 8.4 | |
| その他 | 7.6 | 6.8 | |
| 不明 | 60.9 | 48.0 | |
施策の方向
-
スポーツ・レクリエーション活動の振興
- 重度の障害者と障害のない人が一緒に楽しめる新しいスポーツの普及促進を図ります。
- 知的障害者や精神障害者のレクリエーション活動を振興し、仲間づくりを支援します。
- 障害の特性に応じて適切な指導ができるスポーツ指導員を養成・確保し、障害者スポーツの振興を図リます。
- 障害者スポーツ振興の中核的役割を担う各種の障害者スポーツ団体の活動を支援します。
- 競技スポーツの振興を図るため、障害者競技団体が行う大会の支援を行うとともに、「全国身体障害者スポーツ大会」や「ゆうあいピック」などの全国大会に選手を派遣します。
- 県身体障害者福祉協会の運営する障害者用温水プールを支援します。
- 保健医療福祉中核施設整備事業において障害者スポーツセンターを整備します。
- 心身障害者保養施設「七ツ森希望の家」の機能の充実を図るとともに、レスパイト機能等を備えた多機能・レジャー型保養施設を県内に複数設置することを目指します。
-
第37回全国身体障害者スポーツ大会の開催
- 平成13年に本県で開催が予定されている第37回全国身体障害者スポーツ大会が、新しい世紀の幕開けにふさわしい宮城らしい個性的で魅力ある障害者スポーツの祭典となるように努めます。
- 全国から来県する選手団等をまごころを持って迎えるため、各種福祉団体等と連携を図りながら、大会を支えるボランティアなどの養成を推進します。
- 各種競技団体の協力を得ながら、障害者スポーツ指導員の養成や選手強化を推進するとともに、これを契機として障害者スポーツ全体の普及促進を図リます。
-
第56回国民体育大会の開催
- 障害者が気軽に国体に参加し、かつ快適に観戦できるよう国体関連施設のバリアフリー化に努めるとともに、全国から訪れる障害者が安心して宮城の素晴らしさを堪能できるような施策を展開します。
- 障害者が気軽に国体に参加し、かつ快適に観戦できるよう国体関連施設のバリアフリー化に努めるとともに、全国から訪れる障害者が安心して宮城の素晴らしさを堪能できるような施策を展開します。
| 2 | 芸術文化活動の振興 |
現状と課題
- 心の豊かさを求めて、近年、障害者の芸術活動への注目が集まってきていますが、まだ一部の人の参加にとどまっており、障害者の芸術や文化活動への取リ組みは遅れています。
- 本県では、障害者の芸術や文化活動のネットワークを広げる試みとして、平成7年から「とっておきの芸術祭」を開催していますが、これらの活動をさらに促進していくためには、文化施設等の整備をはじめとして、各種の参加の機会を地域の中に整備し、生活の中に根付かせていくことが求められています。
施策の方向
-
芸術文化活動の振興
- 障害・障害をもつ人の書道や写真などの作品の発表の場やコンテスト出展の機会を提供します。
- 障害者の芸術文化活動の場を確保し、その活動を通して県民の理解を促進するために継続して「とっておきの芸術祭」を開催します。
- 障害者の芸術・文化活動の拠点の設立を支援します。

重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-① | 障害者スポーツセンター整備事業 | 県 | 障害者スポーツの場の提供と多様な障害者スポーツプログラム開発や、スポーツ指導員等の人材養成を進める障害者スポーツセンターを整備し、障害者の自立と社会参加を促進します。 | 検討 | 1ヵ所 |
| 1-② | 全国身体障害者スポーツ大会開催事業 | 県 市町村 他 |
平成13年開催予定の全国身体障害者スポーツ大会の準備・開催を通し、障害者スポーツの振興を図ります。 | 一部 | 拡充 |
| 2-① | 障害者芸術祭開催事業 | 県 市町村 他 |
障害者の自立と芸術文化活動への参加を促進するため、障害者芸術の場を提供するとともに、県民に広く障害福祉について啓発を図ります。 | のべ 3圏域 |
のべ 7圏域 |
第5節 障害者当事者団体の支援
現状と課題
- これまでの障害福祉サービスにおいては、障害者は常に受け身でありましたが、近年、障害のある人が地域の中で生き生きと活動していくために、障害者自身が中心となって主体的に様々なサービスを提供し、地域社会に積極的に関与していこうとする動きが出てきており、これらの活動を積極的に支援していく必要があリます。
- また、障害者本人の社会参加や自立を促進していくためには、それを支える家族会の活動なども支援していかなければなりません。
施策の方向
-
障害者当事者団体等への支援
- 障害者の生活経験を生かし、利用者の視点に立った新たなサービスの構築を図るため、障害者が主体となったサービス提供活動に対する支援の在り方について検討します。
- 障害者が地域で主体的な生活を営むことができるよう、障害者自らが運営する障害者自立生活センター等の運営を支援します。
- 障害者本人によって構成されるグループの様々な活動を支援するとともに、様々な障害者本人や家族会等の団体を支援し、障害者の社会参加や自立を促進します。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 障害児(者)自立生活センター支援事業 | 県 市町村 |
障害者自らが運営する自立生活センターの行う事業について支援します。 | - | 4ヵ所 |
| ◎全国における自立生活センターの設立状況 | ||||||
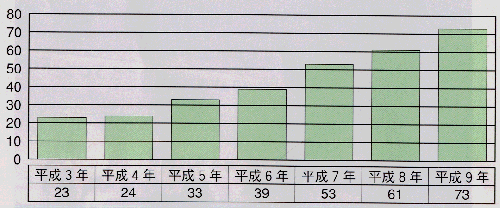
|
||||||
| (単位:ヵ所) | ||||||
| 平成年 | 平成年 | 平成年 | 平成年 | 平成年 | 平成年 | 平成年 |
| 23 | 24 | 33 | 39 | 53 | 61 | 73 |
◇上記の資料は、全国自立生活センター協議会(通称:JIL)への加入状況であり、各年12月末現在の設置数です。
| 『自立生活センター』とは? 自立生活センターは障害を持つ当事者が運営し、障害者の立場に立って、自立生活プログラム、ピアカウンセリング、介助サービス、権利擁護などの様々なサービス事業を、地域の障害を持つ人に提供する組織です。 1972年にアメリカ・カリフォルニア州バークレーに自立生活センターが設立されて以来、日本でも1980年代後半になって全国各地に設立されるようになりました。 |
主題:
みやぎ障害者プラン
発行者:
宮城県
頁数:
20頁~33頁
発行年月:
平成11年3月 第2刷発行
文献に関する問い合わせ先:
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
