みやぎ障害者プラン
宮城県障害福祉長期計画
地域で自分らしい生活を安心して送れる社会をめざして
第3章 安心して生活を送るために
第1節 生活安定のための支援
現状と課題
- 障害者の生活の安定を図り、その社会的自立を促進するためには、雇用の確保とともに所得保障の充実が必要です。
- 基礎調査によると、今後、充実してほしいと考えるサービスとして年金などの所得保障の充実や医療費の軽減を望む声が多く、その充実が求められております。
掲載データ
| ◎基礎調査「今後充実してほしいと考えるサービスは?」§複数回答 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害 | 知的障害 | ||
| 年金などの所得保障の充実 | 37.0 | 20.8 | |
| 障害者に対する周囲の理解を深めるための啓発 | 28.1 | 36.1 | |
| 医療費の軽減 | 20.5 | 10.4 | |
| 障害があっても働ける場の確保 | 20.5 | 30.5 | |
| 障害者に配慮したまちづくりの推進 | 16.0 | 6.2 | |
| 介護施策など在宅福祉サービスの充実 | 13.5 | 11.4 | |
| 家族が休養できるような施策の充実 | 13.0 | 15.4 | |
| (以下略) | |||
施策の方向
-
年金、手当等の充実
- 障害基礎年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当等の充実について国に働きかけるとともに、心身障害者扶養共済制度をはじめとする各種制度の周知を図リます。
-
経済的負担の軽減
- 障害のない人に比べ医療負担の大きい重度心身障害児(者)が医療を受けた場合の自己負担分を助成します。
- 施設への通所・通園、通院などに要する経済的負担の軽減を図るため、各種運賃・料金の割引制度の活用の周知を図ります。
- 通院に介護を必要とする難病患者等に対し、その通院介護に要する経費を助成します
-
生活福祉資金の貸付
- 障害者の経済的自立と社会参加を支援するため、事業を営むために必要な資金や生活安定のための資金、自動車購入資金等を低利で貸し付けます。
-
公費負担医療制度の充実
- 身体の障害を除去、軽減するために必要な更生医療や育成医療を給付します。
- 適正な精神医療を確保、普及するとともに、早期治療効果の発揮と精神障害者の保護を図るため、通院医療費や措置入院に係る医療費の公費負担を行います。
- 難病のうち特定疾患、小児慢性疾患のうち特定の疾患及び遷延性意識障害者等について、患者、家族の経済的負担を軽減するため、医療保険の自己負担分の全部又は一部を公費負担します。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ④ | 更生医療給付事業 | 市町村 | 障害の除去、軽減のために手術等を行う身体障害者の医療費に対して補助します。 | 実施 | 拡充 |
| ④ | 精神科通院医療費公費負担制度 | 県 市町村 |
精神障害者の通院に要する医療費の95%を医療保険と公費で負担し、5%が自己負担となリます。 | 実施 | 拡充 |
| [年金・手当等] | ||
| 施策名 | 対象者及び内容等 | 窓口 |
| 障害基礎年金 | 初診日に国民年金に加入しており、保険料の納付要件を満たしている精神及び身体に障害がある方に年金を支給します。(初診日が20歳以前の場合は保険料納付要件に係わりなく20歳から支給) 年金額 1級 981,900円 2級 785,500円 |
市町村 |
| 障害厚生年金 障害共生年金 |
初診日に厚生(共済)年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている精神及び身体に障害のある方に年金を支給します。支給額は障害程度、保険加入期間により異なります。 | 社会保険事務所 共済組合 |
| 特別障害者手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に手当を支給します。 手当月額 26,230円 |
福祉事務所 |
| 障害児福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の方に手当を支給します。 手当月額 14,270円 |
福祉事務所 |
| 特別児童扶養手当 | 精神又は身体に中度以上の障害を有する在宅の20歳未満の児童の養育者に手当を支給します。 手当月額 1級 50,350円 2級 33,530円 |
市町村 |
| 心身障害者扶養共済制度 | 障害者を扶養する保護者が、生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者の死亡などにより扶養できなくなった場含に、障害者に終身一定額の年金を支給します。 年金月額 1口 20,000円 |
市町村 |
| 生活福祉資金 | 低所得者、高齢者、障害者世帯に対し、生活資金、生業費、修学資金等を貸付ます。 | 市町村社会福祉協議会 |
| (年金、手当の金額は平成9年度末現在) | ||
| [医療費の助成等] | ||
| 施策名 | 対象者及び内容等 | 窓口 |
| 育成医療 | 障害の除去、軽減のための手術等を行う18歳未満の障害児に対して助成します。 | 保健所 |
| 小児慢性特定疾患治療研究事業 | 小児の慢性疾患のうち、国が定めた特定の疾患に罹患している児童に対して助成します。 | 保健所 |
| 更生医療 | 障害の除去、軽減のための手術等を行う18歳以上の身体障害者に対して助成します。 | 市町村 |
| 重度心身障害者医療費 | 重度心身障害者が医療を受けた場合自己負担分に対して助成します。 [助成対象者] ・特別児重扶養手当1級該当者 ・身体障害者手帳1,2級及び3級(内部障害に限る)所持者 ・療育手帳A所持者及び職親に委託されている療育手帳B所持者 |
市町村 |
| 特定疾患治療研究事業 | 国が定めた特定の疾患患者で医療保険の自己負担のある者に対して助成します。 | 保健所 |
| 遷延性意識障害者治療研究事業 | 遷延性意識障害の治療研究を行う医療機関を通じて、その対象者家族に助成します。 | 県 |
| 措置入院医療費公費負担制度 | 精神障害者の措置入院に要する医療費を医療保険と公費で負担します。 | 県・医療機関 |
| 通院医療費公費負担制度 | 精神障害者の通院医療に要する医療費の95%を医療保険と公費で負担します。(5%が自己負担) | 保健所 |
| [税制上の優遇措置] | |||||
| 施策名 | 対象者及び内容等 | 身障手帳 | 療育手帳 | 精神保健福祉手帳 | 窓口 |
| 所得税 | 障害者控除 特別障害者控除 同居特別障害者扶養控除 心身障害者扶養共済制度の所得控除 新マル優制度(預貯金、郵便貯金、公債の各々350万円) |
3~6級 1~2級 1~2級 ○ ○ |
B A A ○ ○ |
2~3級 1級 1級 ○ ○ |
税務署 金融機関 |
| 相続税 | 障害者控除(1年につき6万円税額控除) 特別障害者控除(1年につき12万円税額控除) |
3~6級 1~2級 |
B A |
2~3級 1級 |
税務署 |
| 贈与税 | 特別障害者扶養信託契約により、6,000万円まで非課税 | 1~2級 | A | 1級 | |
| 住民税 | 前年所得125万円以下非課税 障害者控除 特別障害者控除 同居特別障害者扶養控除 |
○ 3~6級 1~2級 1~2級 |
B A A |
2~3級 1級 1級 |
市町村 |
| 自動車税 自動車取得税 |
障害者本人が所有する自動車で、専ら本人が運転するもの及び専ら本人が通学(通所)、通院、生業のために生計同一者が運転するものに係る減免 自動車税が減免される自動車を取得する場合に減免 |
(○) 一定以上の等級に限る |
A | 1級(通院公費負担の承認を受けている方と整形を一にしている方又は単身で生活している人と常時介護している方 | 自動車税 管理事務所 |
| 事業税 | 障害者本人又は障害者を扶養している方のうち、前年度の総所得額が370万円以下の場合減免 | ○ | ○ | ○ | 県税事務所 |
| 重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はリきゅう等医業に類する事業を行う場合は非課税 | ○ | - | - | ||
第2節 介護等のサービスの充実
| 1 | 在宅支援体制の充実 |
現状と課題
- 障害者の介護を家族内だけにとどめることなく、地域社会で支えていくためには、ホームヘルプサービス(訪問介護事業)、ショートスティ(短期入所生活介護事業)、デイサービス(日帰り介護・活動事業)などの介護サービスをはじめ、福祉機器に関する施策等の各種サービスを量・質ともに一層充実することが極めて重要となっています。
- このため、サービスを計画的に提供するとともに、障害種別にとらわれない施策の総合化を視野に入れながら各種サービスの相互利用や、高齢者福祉施策との連携を図りながら、利用者本位の視点に立ったサービス供給体制を構築する必要があります。
- また、介護保険制度の導入を踏まえ、障害者施策においても利用者の権利性、サービス受給の選択性などを考慮しつつ、障害の状況に応じた適切なサービスを用意し、十分な情報提供を行うことも求められております。
掲載データ
| ◎基礎調査「今後利用したい在宅福祉サービスは?」(身体障害者の場合)§複数回答 | ||
| グラフ | (単位:%) | |
| ホームヘルパーの派遣 | 20.5 | |
| 日常生活用具の給付 | 12.1 | |
| 短期入所(ショートステイ) | 10.1 | |
| デイサービス | 9.9 | |
| 入浴サービス | 9.4 | |
| ガイドヘルパー(外出介護員)の派遣 | 8.9 | |
| その他 | 9.4 | |
| 特にない | 38.6 | |
| 不明 | 18.9 | |
| ◎基礎調査「今後、希望する援助は?」(精神障害者の場含)§複数回答 | ||||||
| グラフ | (単位:%) | |||||
| 援助が必要である | 一緒に外出する相手がほしい | 50.0 | 41.1 | |||
| 夜間や休日でも相談できるところがほしい | 35.1 | |||||
| 時々家事を代わりにしてほしい | 25.7 | |||||
| 現金や預金通帳を代わりに管理してほしい | 14.9 | |||||
| 食事等のサービスがほしい | 13.5 | |||||
| その他 | 8.1 | |||||
| 特に援助は必要ない | 48.9 | |||||
| 無回答 | 10.0 | |||||
施策の方向
-
在宅の障害者への支援
- 障害者のニーズを的確に把握したサービスを提供できるよう、ホームヘルパー(訪問介護員)の計画的な増員を図り、あわせて常時介助を要する全身性障害者本人の選んだ介助人が必要なサービスを提供する事業を実施するとともにその拡充に努めます。
- 精神障害者等に対応できるホームヘルパーについても養成を行います。
- 外出時の移動の介助等に必要な知識・技術を持ったガイドヘルパー(外出介護員)の養成を計画的に推進し、必要な時に利用できる体制を整備します。
- 家庭での介護が一時的に困難になった場合などに利用するショートスティ(短期入所生活介護事業)の充実を図ります。
- 障害者に、機能回復訓練や食事、入浴等のサービスを提供するデイサービス(日帰り介護・活動事業)の充実を図るとともに、高齢者との相互利用や広域的な事業運営を促進します。
- 呼吸器機能に障害のある在宅の酸素療法者に対して支援します。
- 在宅療養を行っている難病患者を支援するため、その回りの世話をするホームヘルプサービス(訪問介護事業)や医療機関を活用するショートスティ(短期入所生活介護事業)などの事業を充実します。
- 在宅難病患者の人工呼吸指導管理を行う医療機関に人工呼吸器の購入経費を助成し、在宅療養を支援します。
- 人工呼吸器を装着した重度の在宅難病患者に診療報酬対象外の訪問看護を行い、在宅療養を支援します。
-
介護する人への支援
- 在宅介護者のリフレッシュを図るため、ショートスティ(短期入所生活介護事業)、デイケア(日中介護)、ホームヘルプ(訪問介護)などの各種の支援事業を実施します。
- 在宅療養を行うALS患者の介護を行う家族の休息を確保するための家族支援事業を実施します。
-
各種生活訓練等の充実
- 中途失明者の家庭に訓練指導員を派遣し、感覚訓練、点字指導、福祉用具の使用、歩行指導等の生活訓練の充実を図ります。
- 疾病等による喉頭摘出者の発声訓練やストマ装着者の社会適応訓練等を充実します。
- 視覚障害者、聴覚障害者等に対し、健康、文化、防災など社会生活に必要な知識習得のための講座を充実します。
-
福福祉機器の普及促進
- 特殊寝台、ファックス等の日常生活用具を給付貸与するとともに、種目の拡大などの制度の充実を図リます。
- 難病患者に対する特殊寝台等の日常生活用具の給付事業の充実を図ります。
- 在宅介護支援センター等における福祉用具の展示、助言の充実を図るとともに、保健・医療・福祉の中核施設として計画している福祉機器センターや工業技術センターにおいて、民間企業等と連携しながら福祉用具の技術開発を進めます。
| 《全身性障害者介護人派遣事業概要図》 | |
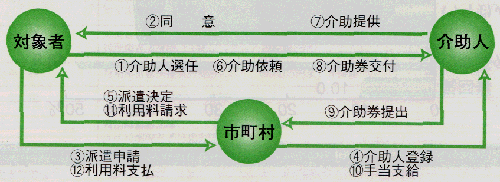
|
*全身性障害者 上肢・下肢・対幹のいずれにも障害が認められる肢体不自由者のことをいいます。 |
| 2 | 施設サービスの充実 |
現状と課題
- 専門的な介護や訓練を必要とする障害者にとって、施設は生活の場、訓練の場として極めて重要です。しかしながら、施設は地域によって偏在しておリ、また通所型は量的にも不足していますので、今後はその需要動向を踏まえ、各圏域への適正配置を計画的に進める必要があります。さらに、精神障害者については、社会復帰のための施設が少ない状況にあるため、早急に整備していく必要があります。
- また、施設は従来のように入所者を対象とするだけでなく、施設が蓄えてきた処遇の知識や経験あるいは施設の持っている様々な機能を地域に開放し、地域で生活する障害者を支援する地域福祉の拠点としての役割も求められております。
- さらに入所型施設は、障害を軽減・克服するための訓練の場としての機能を重視する方向で整備されてきたために、生活の場としての視点が欠けていました。利用者のプライバシーの確保や生活の質の向上ということも視野に入れて整備することが求められています。また、処遇等の状況を比較検討し、運営・サービス内容の施設間格差の解消も求められています。
掲載データ
| ◎基礎調査「今後、利用したい障害福祉施設は?」§複数回答 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害 | 知的障害 | ||
| 治療や介護を受けながら暮らすことのできる施設 | 34.7 | 25.6 | |
| スポーツ・文化等の活動を行う場を提供する施設 | 17.3 | 9.3 | |
| 家から通いながら生活・作業訓練や仕事ができる施設 | 12.6 | 28.8 | |
| 更生相談・健康相談などを行う施設 | 11.7 | 3.8 | |
| 仕事場を提供する福祉工場のような施設 | 6.3 | 8.7 | |
| 作業訓練や仕事をしながら暮らすことのできる施設 | 5.5 | 19.8 | |
| 小人数で作業訓練を行う小規模作業所のような施設 | 2.6 | 7.2 | |
| 地域で共同生活を営むグループホーム | 2.2 | 7.7 | |
| 生活指導を受け、仕事の場に出かける通勤寮のような施設 | 1.7 | 9.2 | |
| その他 | 2.0 | 2.8 | |
施策の方向
-
地域密着型施設の設置推進
- 住み慣れた身近な場所での生活を継続し、あわせて社会参加を促進するために、通所利用の場を全市町村に設置するとともに、福祉施設に入所している人や社会的入院を余儀なくされている人が、地域生活に安心して移行できるように、生活の場(グループホームやケア付住宅等)、活動の場(デイサービスセンターや通所施設等)、働く場(小規模作業所、授産施設や福祉工場等)を計画的に整備します。
- 各圏域ごとの整備を目指し、地域のニーズに応じた規模の施設の設置を推進します。例えば、供給が不足している身体障害者療護施設については、特別養護老人ホームなどとの合築を進めたり、小規模施設の整備も進めます。
- 老朽化の進んでいる県立施設の改築を進めます。「拓杏園」「杏友園」などの身体障害者の援護施設や、「拓桃医療療育センター」「ほたる学園」などの児童福祉施設の改築にあたっては、単に改築にとどまることなく、地域的な偏在の解消・適正規模化・地域で生活する人たちへの支援など利用者のニーズ等を踏まえ、計画的に整備します。
- また、学校のあき教室(余裕教室)などの地域における既存施設を利用し、障害福祉サービス等を提供することについても検討を進めます。
-
施設機能の充実
- 地域で暮らす障害者に、生活訓練、ショートスティ(短期入所生活介護事業)などの各種の在宅サービスを積極的に提供するとともに相談・情報提供機能を強化し、地域福祉の拠点としての施設機能の強化を図リます。
- 施設整備にあたっては、デイサービス(日帰リ介護・活動事業)センターの併設やショートスティ居室、地域交流スペースの整備を進め、施設の持つ介護機能等を地域に提供します。また、重度障害者や呼吸器機能障害などの内部障害者のケアに対応可能な施設整備も促進します。
- 障害の重い人の地域生活の継続を支えるために、重症心身障害児(者)通園事業の実施施設の整備を推進します。
- 強度行動障害等の処遇が難しい人への対応や、高齢知的障害者の処遇の在り方について検討します。
-
適正処遇の確保と処遇向上
- 入所者のプライバシーに配慮し、生活の質を確保した居住環境の向上のため、個室化の推進や居住スペースの拡大などの改善に努めます。
- 精神薄弱者援護施設のうち、通所更生施設において介護度の高い人を受け入れている施設に人件費補助を行いますが、さらにその制度の拡充を図ります。
- 施設職員の研修体制を強化し、専門的な処遇技術を身につけた資質の高い職員の養成を図ります。
-
施設における人権擁護
- 施設利用者の人権を擁護し、質の高いサービスの提供が図られるよう施設運営に関する情報開示を促進し透明性を高めます。
- 利用者側の自己決定権を最大限尊重することを主眼に、利用者本人及びその家族はもちろん、中立的立場の第三者側の意見を取り込む方策について検討します。
|
障害福祉施設の整備イメージ
|
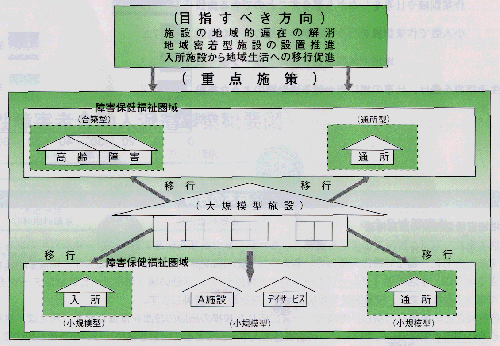
|
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-① | 全身性障害者介助人派遣事業 | 市町村 | 常時介助が必要な全身性障害者が、自分の希望する介助人を選定・登録し、必要に応じてケアサーピスの提供を受けられる事業を実施します。 | 実施 | 拡充 |
| 1-① | 特定疾患訪問看護治療研究事業 | 県 | 在宅で人工呼吸器を装着している患者に対し、必要に応じ診療報酬対象外の訪問看護を行い、重度の難病患者を支援するための研究を行う。 | - | 全県 |
| 1-② | 障害児(者)家族介護支援事業 | 県 市町村 |
介護する家族の疲労を解消するために、通所施設や小規模作業所において、障害者を一時的に預かります。 | デイケア 5カ所 デイケアモデル 3カ所 ナイトケア 4カ所 |
拡充 |
| 1-② | ALS総合対策事業 | 県 | 在宅難病患者が安心して療養できるように在宅医療ネットワークを構築するとともに、人工呼吸器を装着したALS患者の介護を行う家族を支援するため、介護経験の豊富な人を派遣します。 | 9人 | 全県 |
| 2-① | 障害福祉施設の改築・拡充整備事業 | 県 他 | 県立障害福祉施設のうち、老朽化・狭隘化への対処及び機能拡充・整備が必要な拓杏園、否友園、拓桃医療療育センター及びほたる学園などについて、利用者の現状やニーズに対応した改築・整備拡充を図ります。 | 検討 | 整備 |
第3節 保健・医療サービスの充実
| 1 | 障害の予防・早期発見体制の充実 |
現状と課題
- 疾病や障害を早期に発見し、適切な治療を行うことによリ、障害の予防、軽減を図ることが可能です。特に、乳幼児期は心身の諸機能が発達する一方、病気や異常をきたしやすいため、乳幼児の健康診査や相談・指導を充実し、障害の早期発見に努め、早期対応につなげていくことが大切です。
- 一方、がん、脳卒中、心臓病などのいわゆる生活習慣病による死亡者は全死亡者の6割を占めるとともに、特に障害を伴う可能性の多い疾病の多くが生活習慣病に因っており、その予防もますます重要となっています。
- また、現代ストレス社会においては、一般県民も含めた精神疾患の予防が大きな課題となっています。
- このため、妊娠、出産期や幼児期から高齢期に至るまで、一貫した保健・医療サービスを提供し、障害の予防・早期発見体制を充実する必要があります。
掲載データ
| ◎基礎調査「身体障害者における障害の主な原因は?」 | ||
| グラフ | (単位:%) | |
| 出産時の疾患 | 14.3 | |
| 脳血管疾患 | 18.0 | |
| その他の疾患 | 24.4 | |
| 労働災害 | 7.5 | |
| 交通事故 | 4.6 | |
| その他の災害・事故 | 5.7 | |
| 戦傷病・戦災 | 1.7 | |
| その他 | 14.9 | |
| 不明 | 8.9 | |
施策の方向
-
母子保健等の充実
- 先天性代謝異常等の検査を実施し、疾病の早期発見、早期治療を行い、障害の予防を図ります。
- 思春期クリニック等を通じ、結婚・妊娠前からの健康教育を推進します。
- 妊産婦及び児童に対し、市町村母子保健計画に基づき生涯にわたる一貫した健康を確保するため、それぞれの適切な時期に保健指導及び健康診査を行います。
- 心身に障害をもつ、あるいは障害をもつ可能性のある児童に対して、療育に関する相談指導等を保健・医療・福祉及び教育を包含して一元的に行います。
-
精神疾患の予防と早期治療の推進
- 一般県民を対象とした研修等を開催することにより、予防知識の普及啓発を図ります。
-
生活習慣病予防対策の推進
- 壮年期からの健康づくりやがん検診等を促進するとともに、予防知識の普及啓発を進めます。
-
在宅要介護者の歯科保健の推進
- 在宅要介護者の歯と口腔の健康づくりを通し、健康の保持・増進及び生活の質の向上を図ります。
-
障害者の健康診査体制の充実
- 在宅障害者の訪問健康診査等を拡大し、医療機関への受診が困難な障害者の健康維持を図ります。
-
難病対策の推進
- 難病の発生原因の究明や治療方法確立のための調査研究及び難病患者とその家族に対する訪問相談、医療相談、療養生活上の助言・指導を推進します。
-
保健活動の基盤整備
- 地域保健法等に基づき、広域的・専門的・技術的拠点として、保健所の機能強化を図ります。
- 地域保健・福祉活動の拠点となる市町村の保健センターの整備を促進します。
| 2 | 医療・リハビリテーション医療の充実 |
現状と課題
- 障害者のための医療及びリハビリテーション医療は、健康の維持と障害の軽減を図リ、障害者の自立を支援するために重要な意義を持っています。
- 障害者が家庭及び地域社会において生活していくためには、個々の身体機能に合わせた医療的、職業的、教育的、社会的視点からの適切なリハビリテーションの供給が図られることが重要となっています。
- しかし、専門的リハビリテーション提供病院の多くは仙台医療圏に集中しておリ、仙台以外の居住者は退院後、通院等のリハビリテーションヘの移行が円滑に進みにくく、また、保健・医療・福祉の施設間において、リハビリテーション関連情報を提供する体制が十分整備されていないため、対象者の把握が困難な状況も見られます。
- さらに、地域のリハビリテーション活動は、地域に対応する理学療法士等の専門スタッフの配置が少なく、リハビリテーション専門職の視点が入った訓練プログラムの構築が困難となっており、さらに高齢者対応の訓練が中心で、若年層のニーズに応じきれないことも課題となっています。
掲載データ
| ◎基礎調査「受けたい各種訓練やリハビリテーションの種類、方法、内容は?」 (身体障害者でこれを受けたことのない人の場合) |
||
| グラフ | (単位:%) | |
| 身体機能を回復させるための訓練 | 38.4 | |
| 身体の機能を維持するための訓練 | 37.7 | |
| 日常生活動作 (食事、排せつ、移動等のための訓練) |
7.7 | |
| 職業訓練 | 5.0 | |
| 社会生活(外出、お金の管理)のための訓練 | 2.8 | |
| その他 | 2.7 | |
| 不明 | 5.6 | |
施策の方向
-
医療等の充実
- 日常生活圏での必要な医療を確保し、医療供給体制のシステム化を図るため、宮城県地域保健医療計画(第3次)を策定し、県民一人ひとりがそれぞれの地域で適切な保健医療サービスが受けられるよう供給体制の整備を図ります。
- 精神医療の専門施設として県立名取病院の機能の充実を図ります。
- 臓器移植に関する知識の普及・啓発や意思表示カードの普及を図るとともに、骨髄バンクヘの登録を促進し、移植医療体制の整備を進めます。
-
適切なリハビリテーションの供給
- 成人の肢体不自由者を対象とした専門的リハビリテーション医療及び職業前訓練等による積極的機能回復リハビリテーションの提供と、人材派遣等によって地域で行われるリハビリテーションを支援するリハビリテーションセンターの整備を進めます。
- 乳幼児から高齢者まで、自立生活を目的として展開されている地域リハビリテーション事業について、事業量の拡大、質的な向上を支援し、身近な地域や在宅において継続的かつ一貫性をもってリハビリテーションが受けられるシステムを整備します。
- 地域における身体障害者のリハビリテーションの充実を図るため、在宅の重度身体障害者への訪問相談事業を実施します。
- 障害者の自立を支援するための福祉機器、介護用品や自助具の普及促進を行います。
- 医学的リハビリテーションによリ精神障害者の社会復帰を促進するため、精神科デイケア施設の整備や精神医療の充実を図ります。
- 精神保健福祉センターのリハビリテーション機能の充実を図ります。
-
救急医療体制の整備
- 休日・夜間の救急患者にも適切に対応できるよう在宅当番医制・病院群輪番制・休日夜間急患センターの整備を促進して、救急医療体制の充実を図ります。
- 救命救急センターがない仙南、石巻、気仙沼地域については、地域の中核的な病院の整備に合わせて高次救急医療体制の整備を進めて、救急医療の二次医療圏内での完結を目指します。
- 救急医療情報システムの拡充により、より適切な情報を迅速に提供できるよう努めるとともに、住民への身近な救急医療の情報提供や大規模災害時における医療援護活動を支える広域災害救急医療情報システムについて検討します。
- 休日及び夜間において、精神科救急医療を必要とする人のために、県立名取病院、民間精神科病院や関係機関の協力を得て、精神科救急医療システムを構築し、適正な精神科救急医療体制を整備します。
- 在宅の難病患者が日常や緊急時の医療について不安なく療養できるように在宅医療ネットワークの構築を図ります。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | ||
| H9 | H17 | |||||
| 2-② | リハビリテーションセンター整備事業 | 県 | 保健医療研祉中核施設としてリハビリテーションセンター、福祉機器センターを整備し、専門的な視点から地域リハビリテーション活動を支援します。 | 検討 | 全圏域 | |
| 2-② | 福祉機器研究開発及び普及事業 | 民間 市町村 |
各種リハビリテーション機器や介護機器への応用を目的とした技術開発の推進と福祉機器(福祉用具)の普及を図ります。 | |||
| ◇福祉用具産業支援事業 | 県 | 福祉用具産業に新たに取り組もうとする県内中小企業等に対して情報の提供、技術的課題のアドバイス等の支援を行います。 | 実施 | 実施 | ||
| ◇福祉機器センター整備事業 | 県 | 総含リハビリテーション体制の確立をサポートし、福祉機器の普及促進と障害者の自立を支援します。 | 実施 | 1カ所 | ||
| 2-③ | 高次救急医療体制整備事業 | 市町村他 | 仙南・石巻・気仙沼地域の中核的な病院に高次救急医療体制を整備します。 | のべ 1ヶ所 |
のべ 3カ所 |
|
| 2-③ | 精神科救急医療システム整備事業 | 県 | 精神障害者等の休日及び夜間の受診・加療の機会を確保するため適正な精神科救急医療の供給を図る精神科救急医療システムの構築を進めます。 | 実施 | 1カ所 | |
| 保健医療福祉中核施設相互連携イメージ |
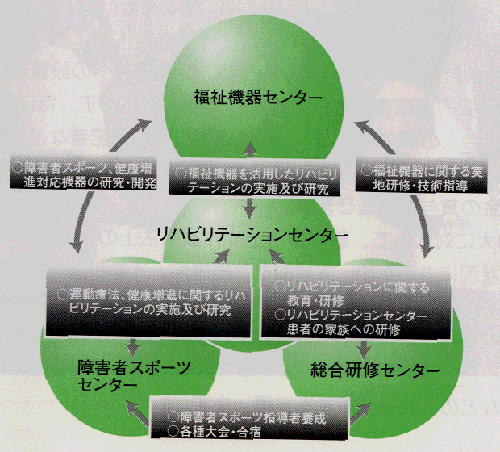
|
第4節 サービスの担い手の確保
現状と課題
- 障害者の重度化や高齢化、社会参加への意欲の高まりなどに伴い、保健・医療・福祉のニーズはますます増大、多様化してきており、その担い手である介護福祉士をはじめとする専門的な職員に対する需要も増加傾向にあるため、今後、これらのサービスの担い手の養成・確保が重要な課題となっています。
- このため、障害者の自立と社会参加を促進するため、高度な技術・知識を備えた介護福祉士やホームヘルパー(訪問介護員)、手話通訳者などをはじめ、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士など、多様なニーズに対応した専門職員の養成・確保を図り、必要なサービスが必要な時に提供できる体制を整備していかなければなリません。また、より質の高いサービスを提供するためには、サービスを担う職員の専門知識・技術の向上を図ることも大切です。
- さらに、誰もが住みよい社会を実現するためには、県民一人ひとりが様々な形で地域福祉に関わりを持つことが必要であり、県民参加の機会を増やしすそ野を広げることが重要です。
掲載データ
| ホームヘルパー(訪問介護員)の年次推移(宮城県) | ||
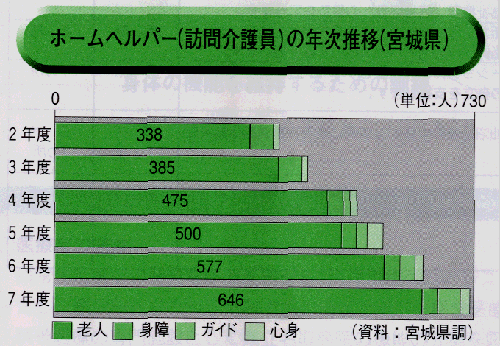
|
(単位:人) | |
| 2年度 | 338 | |
| 3年度 | 385 | |
| 4年度 | 475 | |
| 5年度 | 500 | |
| 6年度 | 577 | |
| 7年度 | 646 | |
| (資料:宮城県調) | ||
| 介護福祉士・社会福祉士の登録者数(宮城県) | ||
| グラフ | (単位:人口10万人対率) | |
| 5年度 | 23.7 | |
| 6年度 | 314 | |
| 7年度 | 41.8 | |
| 8年度 | 49.7 | |
| (資料:宮城県調) | ||
施策の方向
-
養成・確保の推進
- 増大するホームヘルプサービス(訪問介護事業)のニーズに対応するため、県介護研修センターなどを中心にホームヘルパー(訪問介護員)の養成研修を拡充します。
- ガイドヘルパー(外出介護員)の計画的な養成・確保を行い、全市町村への設置を促進します。
- 点訳・朗読奉仕員や手話通訳・要約筆記者の養成・確保対策を充実します。特に平成13年に本県で予定されている「全国身体障害者スポーツ大会」の開催に向けて、手話通訳・要約筆記者などを重点的に養成します。
- 施設や在宅サービスの中核的・指導的役割を担うべき人材として、介護福祉士や社会福祉士を養成するため、養成施設整備への支援、奨学資金の貸与を推進します。
- リハビリテーション需要の増大に対応して、理学療法士や作業療法士の必要性が強くなっていますが、市町村が独自に確保することが困難な状況にあるため、広域的な共同確保、活動システムを創設し、市町村を支援します。
- へき地における医療を確保するため、へき地に勤務する医師など医療従事者の確保を図ります。
- 宮城大学や総合衛生学院などにおいて、ニーズの高度化、多様化に対応できる資質の高い看護職員等の養成に努めます。
- 市町村が行う保健婦や栄養士などの人材確保事業を支援します。
-
資質の向上
- ホームヘルパー養成事業を充実し、障害者や難病患者の特性にも対応できる質の高いホームヘルパーの養成を図ります。
- 身体障害者相談員、精神薄弱者相談員等の研修を充実し、活動の促進を図ります。
- 障害児保育などに従事できる専門性をもった保育職員が求められることから、その養成研修を充実します。
- 保健・医療・福祉総含研修体系に基づく研修プログラムを効果的、効率的に運営するための総含研修センターを整備し、各研修実施機関等と連携を図りながら、高度な専門知識の提供、適切な実技指導など、実践の場に備えた質の高い研修を提供します。
-
魅力ある職場づくり
- 職員の職場定着化や就業促進を進めるため、身分保障、業務見直し、働きやすい勤務体制の整備など処遇の充実のため、経営者の意識啓発を図りながら職場環境の改善を支援していきます。
-
福祉意識の醸成と幅広い人材の確保
- 福祉学習等の推進による意識の醸成や、資格取得のための教育、社会教育の一環としての介護教育やボランティアの充実など、県社会福祉協議会などにおける研修事業等を充実し、意識啓発を図ります。
- 福祉学習等の推進による意識の醸成や、資格取得のための教育、社会教育の一環としての介護教育やボランティアの充実など、県社会福祉協議会などにおける研修事業等を充実し、意識啓発を図ります。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | ||
| H9 | H17 | |||||
| ① | ガイドヘルパー養成研修事業 | 県 | 外出時の移動の介助等に必要な専門的知識・技術を有するガイドヘルパーの養成を図り、必要な時に利用できるサービス体制を整備します。 | - | 実施 | |
| ② | 総合研修センター整備事業 | 県 | 保健・医療・福祉分野における総合研修施設としてへ保健・医療・福祉サービスに従事する人々を対象に、その知識と技術の向上を図るための研修を実施します。 | 検討 | 整備 | |

|
第5節 総合的な支援体制の整備
現状と課題
- 障害者の高齢化や、生まれ育った地域で生活したいという願いの高まリなどに伴い、福祉ニーズが多様化する一方で、生活環境の変化や核家族化、介護者自身の高齢化などのため家庭における介護機能が低下してきておりますが、基礎調査によると介助者が介助できない場合の対応として、依然として同居している家族に頼っている傾向にあります。
- このため、障害者の地域生活を支援して行くためには、住民に最も身近な存在である市町村が、国、県、あるいは企業などと連携しながら総合的なサービスを提供するとともに、それを住民の参加を得ながら地域全体で支え合うシステムの構築が求められています。
- また、これからは障害者自身がサービスを選択するために必要な情報が得られる環境を整備していくことが重要になっており、今後、そのサービスの情報を障害者や家族が的確に入手し、主体的に選択できるよう情報提供体制と相談支援体制を充実する必要があります。
- さらにこれまでは、身体障害者、知的障害者、精神障害者に対する施策は各障害種別ごとに施策の充実が図られ、施策の実施体制についても障害種別により相違がありました。しかしながら、障害者が地域の中で生活を送れるようにするためには、県による支援や障害特性に応じた専門性を確保しつつも、障害者が市町村において地域の実情に応じて総合的に調整されたサービスを受けられる体制を整備することも必要となっています。
掲載データ
| ◎基礎調査「介助者が介助できない場合の対応は?」 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害 | 知的障害 | ||
| 同居している家族に頼む | 46.5 | 54.0 | |
| 施設に入所する | 13.4 | - | |
| 病院に入院する | 11.2 | - | |
| 施設等のショートステイを利用する | - | 25.9 | |
| ホームヘルパーの派遣を頼む | 10.2 | 1.4 | |
| 親戚・友人に頼む | 10.1 | 7.4 | |
| 介助者を雇う | 2.5 | 0.4 | |
| 近所の人に頼む | 1.2 | 1.0 | |
| ボランティアを頼む | 0.9 | 1.4 | |
| その他 | 4.0 | 8.5 | |
施策の方向
-
多様なサービス供給体制の整備
- 住民に身近な市町村が主体的、計画的に福祉サービスを供給できるように、市町村障害者計画の策定について支援するとともに、市町村をはじめとした各種組織、団体等の連携・協力により障害者に対する総合的・効果的な福祉サービス供給体制の充実を図ります。
- 障害者の生活経験を生かし、利用者の視点に立った新たなサービスの構築を図るため、障害者本人が主体となったサービス提供体制の在り方について検討します。
-
地域における相談支援体制の整備
- 地域で生活する障害者を総合的に支援するために、日常生活上の不安解消、在宅サービスの利用援助、働く場や自立のための情報提供等の援助を行う「障害者生活支援センター」を障害保健福祉圏域ごとに設置することを目指します。
- 精神障害者の社会復帰と社会参加を支援するため、新たな総合精神保健福祉センターの整備を行い、日常的な相談への対応や地域交流活動及び地域で生活を営む上で必要とする情報提供等を総合的に行うシステムの構築などを図ります。
- 福祉事務所、保健所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、児重相談所、精神保健福祉センターなどの相談機能の充実を図ります。
- 身体障害者相談員、精神薄弱者相談員や精神保健福祉士等の専門職種によるきめ細やかな相談体制の充実を図ります。
- 知的障害者や精神障害者等からの法的手続きや人権等に関する専門相談事業を実施するとともに、障害者等の財産保全や管理運用のシステムについて検討します。
- 難病患者の在宅療養を支援するため、専門医による医療相談会の開催や訪問による療養指導体制の充実を図ります。
-
地域リハビリテーションの推進
- 障害のある人も自分らしく住み慣れたところで安心していきいきと生活できることを目的として行われる地域リハビリテーションの推進のためのシステムを構築します。
- 市町村に地域リハビリテーションコーディネーターを養成し、利用者から身近なところで、リハビリテーションの目標に基づいてケアプランをたて、保健・医療・福祉等のサービスが総合的に実施、評価されることを目指します。
-
手帳交付制度の普及・促進
- 手帳交付管理システムの見直しや補装具給付のための書類による判定の導入等によリ、福祉サービス提供の迅速化に努めます。
- 手帳交付管理システムの見直しや補装具給付のための書類による判定の導入等によリ、福祉サービス提供の迅速化に努めます。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 障害者生活支援センター設置事業 | 県 市町村 |
各障害保健福祉圏域に、障害種別を越えた障害者の地域生活を支える拠点相談センターを設置します。 | 2カ所 (一部実施) |
7カ所 |
| ② | 総含精神保健福祉センター整備事業 | 県 | 精神保健福祉行政の技術的中核機関として、拡充整備を行います。 | 1カ所 | 1カ所 (移転新築) |
| ③ | 地域リハビリテーション推進事業 | 県 | 作業療法士等を活用し、地域リハビリテーションシステムモデル事業として市町村への助言、技術指導を行うとともに、地域リハビりテーションコーディネータを養成し、効果的な地域リハビリテーション活動の推進を図ります。さらに保健医療福祉中核施設としてリハビリテーションセンター、福祉機器センターを整備し、専門的な視点から地域リハビリテーション活動を支援します。 | 1カ所 | 全圏域 |
| ※リハビリテーションセンター・福祉機器センター整備事業 H8・9 全体施設設計 H10 基本設計 H11 実施設計 H12 建設工事 |
|||||
| グループホームを中心とした地域生活イメージ |
| 障害者生活支援センターのイメージ |
| 精神保健福祉における総合精神保健福祉センターの役割 |
第6節 権利擁護のための施策の充実
現状と課題
- 知的障害者など意思能力や判断能力が十分でない人たちは、自らの意思を正確に表現したり、自ら声をあげて訴えたリ、その解決のために行動を起こすことが困難であるために、周りの人たちからの意図的あるいは無意識の人権・権利の侵害を受けやすい状況にあります。
- さらに、知的障害者や精神障害者の親には、自分なき後、誰が自分に代わって財産管理をやってくれるのか、権利侵害から守ってくれるのか、深刻な不安があります。
- 現行では財産の保護については、民法上「禁治産・準禁治産」の制度があるものの、この制度では各人の残存能力の違いを考慮せず、画一的に行為能力を奪うものであり、かつ戸籍に記載され公示されるので、意思能力にハンディキャップがあるため支援を必要とする知的障害者などには、この制度はなじまない場合が多くあります。
- そこで、本人の行為能力を制限せず、財産の管理・運用に関する助言等を行う新たな援助システムの確立が求められております。
掲載データ
| ◎「お金の管理についての介助の状況は?」(知的障害者の場合) | ||
| グラフ | (単位:%) | |
| 一人でできる | 12.5 | |
| 時間をかければ一人でできる | 6.5 | |
| 一部介助が必要 | 16.4 | |
| 全部介助が必要 | 54.0 | |
| 不明 | 10.6 | |
施策の方向
-
権利擁護の推進
- 知的障害者や精神障害者等からの法的手続きや人権等に関する障害者専門相談事業を実施するとともに、来所、電話、ファックスによる常設の相談窓口を設置します
- 知的障害者や精神障害者等の権利侵害を救済する専門的な機関の設置に向け調査研究を進めるとともに、財産の保全や管理運用システムの構築を図り、財産を本人のために有効活用できる体制の整備を目指します。
- 精神病院や社会福祉施設において、障害者等の金銭管理や処遇が適正に行われるよう、実地指導等の充実を図ります。
- 行政施策の決定に当事者の意向が十分反映されるように、県及び市町村障害者施策推進協議会や関係審議会等への障害者等の積極的な参画を促進します。
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| ① | 知的障害者等権利擁護システム整備事業 | 県 他 | 知的障害者や精神障害者等の人権侵害に対する相談や財産等の保全・管理運用のシステムを構築します。 | - | 整備 |
| <知的障害者等権利擁護システム整備事業のイメージ> |
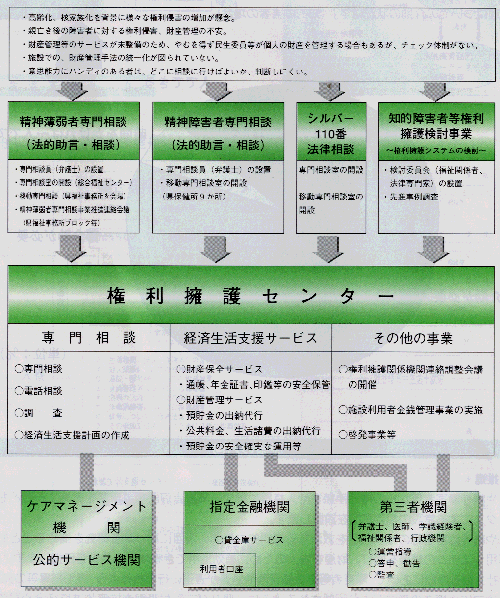
|
第7節 防犯・防災対策の充実
| 1 | 防犯対策の充実 |
現状と課題
- 障害者は警察への通報や相談にも困難を伴うことから、その解消を図ることが大切です。
- このため、地域の防犯活動を一層推進するとともに、情報の提供やコミュニケーション手段の充実を図リ、障害者が安心して暮らせる地域づくりを進める必要があります。
施策の方向
-
防犯対策の充実
- 市町村や防犯団体と連携し、地域や職場における自主防犯活動の活発化を図るとともに、交番等の機能を充実して地域安全活動を推進します。
- 交番・警察署員に対して障害者の介添え及び車いすの取扱要領講習会等を実施するとともに、駐在所等において手話のできる警察宮を育成します。
- 聴覚障害者や音声言語機能障害者などの日常生活の安全を確保するため、県警に設置されている専用ファクシミリによる110番緊急通報受理装置の周知を図リます。
| 2 | 防災対策の充実 |
現状と課題
- 火災や大規模地震などの災害の発生時においては、障害のない人に比べより大きな危険にさらされることが予想されることから、その支援体制を整備する必要があります。
- このため、県、市町村、防災関係機関等がそれぞれの立場で各種の防災対策を講じるとともに、防災知識の普及、地域住民や関係機関の連携・協力体制を整備するなどすべての人が共に助け合い安心して暮らせる社会をつくる必要があリます。
掲載データ
| ◎基礎調査「災害に際して大切だと思う対策は?」 | |||
| グラフ | (単位:%) | ||
| 身体障害者 | 知的障害者 | ||
| 障害者に配慮した避難所の整備 | 30.4 | 31.5 | |
| 地域における緊急通報システムの整備 | 18.8 | 10.6 | |
| 避難所への安全で迅速な避難誘導体制 | 14.7 | 15.6 | |
| 防災に耐えうる建築物、道路などの整備 | 12.1 | 8.2 | |
| ボランティアの支援体制 | 4.5 | 6.2 | |
| 避難訓練や防災知識など事前の啓発 | 3.3 | 3.9 | |
| その他 | 0.6 | 3.3 | |
| 不明 | 15.6 | 20.7 | |
施策の方向
-
総含的な防災・防火対策の推進
- 県や市町村の地域防災計画を随時見直し、社会構造の変化、地域の実情に応じた防災体制の充実を図ります。
- 障害者等の防火対策を強化するため、関係団体との連携のもと、「住宅防火対策推進協議会」を設立し、住宅防火対策を総合的・効果的に推進し、火災の未然防止及び火災被害の低減を図ります。
-
防災知識等の普及
- 障害者が参加する防災訓練の実施などにより、防災意識の高揚を図リます。
-
災害に強い施設の整備
- 災害緊急時への対応が困難な障害者等のため、居住施設の防火や耐震性能の向上に努めます。
-
災害緊急体制の整備
- 日ごろから、障害者の所在・要援護の状況等をプライバシーに配慮しつつ的確に把握できるように市町村の体制づくりを支援します。
- 自主防災組織や民生児重委員など地域の協力を得ながら、災害時に援護を必要とする障害者等の迅速な安否確認や避難誘導などが行えるよう市町村の体制づくりを支援します。
- 福祉救援ボランティアの組織化と支援を図り、災害時における組織的活動が展開できる体制を整備します。
- 災害の影響(薬の紛失、交通機関の寸断、診療所機能の低減等)による服薬中断を防いだり、新たな患者に対応できる医療体制の整備を図ります。
- 災害時やその後のメンタルヘルスに関する相談ができる窓口を必要に応じ設置します。
- 重度身体障害者の災害時の緊急事態に迅速かつ的確に対応するため、緊急通報装置などによる通報システムの整備を促進します。
-
情報提供体制の整備
- 災害情報の提供に際しては、視覚・聴覚障害者への対応も十分配慮します。
- 災害時における精神保健医療に関する情報伝達体制の整備を進めていきます。

|
| 社会福祉施設での避難訓練のようす |
重点事業
| 番号 | 事業名 | 実地主体 | 事業内容 | 整備目標 | |
| H9 | H17 | ||||
| 1-① | 交番等の手話講習会開催事業 | 県 | 聴覚障害者を犯罪や事故等から守り、また困りごと相談や地理案内等に適切に対応するため、聴覚障害者と接する機会の多い地域警察官等を対象に手話講習会を実施します。 | のべ 12人 |
拡充 |
| 1-① | ファックスによる緊急通報受理装置の設障 | 県 | 聴覚障害者、音声言語機能障害者等の日常生活の安全を確保するため、県警本部司令室に専用ファックスを設置し、ファックスによる110番緊急通報を受理します。 | 実施 | 拡充 |
| 2-④ | ひとりぐらし老人等緊急通報システム事業 | 県 市町村 |
ひとりぐらしの重度身体障害者の緊急事態発生に対処するため緊急通報装置を設置します。 | のべ 135台 |
拡充 |
主題:
みやぎ障害者プラン
発行者:
宮城県
頁数:
34頁~54頁
発行年月:
平成11年3月 第2刷発行
文献に関する問い合わせ先:
〒980-8570
仙台市青葉区本町三丁目8番1号
