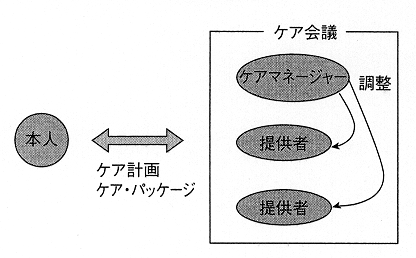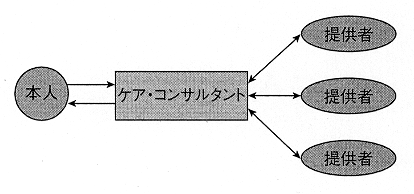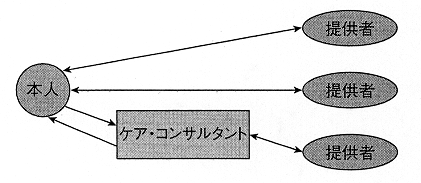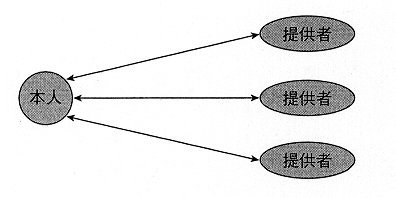特集/身体障害者ケアガイドライン試行事業
報告④
立川市における試行事業
―当事者主体での実施―
高橋 修
圓山里子
立川市における身体障害者ケアガイドライン試行事業の特色
立川市における身体障害者ケアガイドライン試行事業(以下「本事業」とする)の特徴は、当事者主体で実施されたことでしょう。調査研究委員長をはじめ、委員9人のうち障害当事者が4人を占め、ケアマネージャーはピアカウンセラーである障害当事者が担当しました。
本事業のもう一つの特色は、ケアサービスの選択肢の幅が広いことが挙げられます。立川市は、1980年代初頭から始まる障害者運動を背景として、CIL・立川などの福祉サービス提供団体が複数存在し、また、福祉制度についても東京都重度脳性麻痺者等介護人派遣事業など、他地域と比べて活用できる社会資源に恵まれているといえます。
実施報告
(1) セルフ・マネジメントの観点からみた利用者のタイプ
ところで、ケア「サービス」の提供とケア「マネジメント」の実施とは一致するものでしょうか。別の言い方をすると、さまざまな領域のケア「サービス」を必要としている「複合的なニーズ」をもつ者はすべてケア
「マネジメント」の対象者になるのでしょうか。立川市の実施結果から見て、あるいは一般的に考えても、その答えは否です。つまり、個別サービスとしてのケアが必要なことと、ケアマネジメントとしての介入が必要なこととは一致しません。
表1は、本事業の10人の利用者について、訪問票(第一次評価票)で得た障害の状態等の項目、訪問者が判断した利用者のタイプ、そして事後アンケートでの利用者本人のケアマネジメントへの参加希望を示したものです。この表から、利用者のタイプや利用者自身のケアマネジメントへの参加希望は、一般的に要介護状態の指標となるADL等よりむしろ、以前の居住形態や地域での生活年数との関連が強いことが分かります。
そこで、利用者がどのようなケア「ニーズ」をもつのかという観点とは別に、ケア「マネジメント」を利用者自身が行うセルフ・マネジメントの観点から、次の3つのタイプの利用者が考えられます。また、利用者像の違いにともない、ケアマネジメントのモデルも異なることになるでしょう(図)。
第1のタイプとしては、生活のパターンが安定し、セルフ・マネジメントを行う利用者です。本事業の利用者で特徴的なのは、ADL等の得点が高い利用者、すなわち要介護度が高い利用者がこのタイプに多いことです。例えば、Aさんは、視覚障害と四肢体幹機能障害との重複障害の上に、医療的なニーズも抱えており、まさに複合的なニーズをもつ利用者ですが、基本的に日々の生活は自分自身で組み立て、自分の生活を中心においてさまざまなサービスを利用しています。
第2のタイプは、セルフ・マネジメントへの移行期の利用者です。このタイプの例としては、施設生活から地域での自立生活を始めて2~3年の利用者があげられます。本事業では、長年施設で生活してきたが故の社会経験の少なさから、セルフ・マネジメントの形をとるには時間が必要と思われる利用者がいました。
第3のタイプは、困難に直面した最初の時期、または、すべての分野あるいはいくつかの分野においてセルフ・マネジメントが苦手で、ケアマネジメントを必要としている利用者です。本事業では、ホームヘルプサービスなど公的制度をほとんど活用しておらず、家族や特定の介護者がケアの負担を抱え込んでしまっている例がありました。
| 性別 | 障害の内容 | ADL | コミュニケーション | 家事 | 生活動作 | 自己管理 | 生活形態 | 以前の居住 | 生活年数 | ケアマネジメント | ケアマネジメントへの参加希望 |
| 男 | 進行性筋ジストロフィー | 40 | 13 | 20 | 20 | 0 | 就労 | 在宅 | 約10年 | セルフマネジメント | すべての場面で参加したい |
| 女 | 視覚障害、四肢体幹機能障害 | 31 | 9 | 18 | 19 | 0 | 在宅 | 在宅 | 約20年 | ||
| 男 | 脳性麻痺 | 12 | 9 | 19 | 12 | 0 | 就労 | 在宅 | 約6年 | ||
| 男 | 頸髄損傷 | 24 | 0 | 20 | 10 | 0 | 就労 | 病院 | 約10年 | 身近な人と一緒に参加したい | |
| 男 | 脳性麻痺 | 19 | 6 | 20 | 20 | 0 | 在宅 | 施設 | 約3年 | 移行期 | 身近な人と一緒に参加したい |
| 女 | 脳性麻痺 | 16 | 5 | 19 | 14 | 0 | 在宅 | 施設 | 約2年 | 訪問時に十分に希望を伝えてケアマネージャーに依頼したい | |
| 女 | 脳性麻痺 | 13 | 4 | 18 | 13 | 3 | 在宅 | 施設 | 約4年 | ||
| 男 | 脳性麻痺、知的障害 | 40 | 13 | 20 | 14 | 16 | デイサービス | 在宅 | 親元 | ケアマネジメント | すべての場面で本人と一緒に参加したい(母親の希望) |
| 女 | 脳出血による四肢体幹機能障害 | 40 | 9 | 20 | 19 | 0 | 在宅 | 病院 | 1年未満 | 訪問時に十分に希望を伝えてケアマネージャーに依頼したい | |
| 男 | 両下肢機能全廃、右上肢機能障害 | 38 | 9 | 20 | 14 | 0 | 在宅 | 病院 | 約1年 |
(注)
(1)「ADL」、「コミュニケーション」、「家事」、「生活動作」、「自己管理」の項目は、それぞれ訪問票から算出した。得点と項目は以下のとおり。
【得点】 自分一人でできる=0
補助具を使用して可能=1
援助があった方が楽にできる=2
見守り・声かけ=3
部分的に介助が必要=4
動作全体に介助が必要=5
【項目】 ADL:ねがえり、起き上がり、トランスファー、トイレ、身づくろい、着替え、食事、入浴
家事:洗濯、買物、炊事、掃除
コミュニケーション:見る・読む、聞く、書く、話す・意志表示、話しの理解、電話
生活動作、及び、自己管理:金銭管理、服薬、文書管理、育児、危機管理
(2)「ケアマネジメント」は訪問者が利用者の状態を判断したタイプ
(3)「ケアマネジメントへの参加希望」は、訪問後の利用者へのアンケートの結果、利用者が希望した項目
この表をみると、ケアマネジメントのタイプに関連があるのは、ADL等のケアの量的な面よりも、生活形態や生活年数といった項目である。
|
モデルA チーム・アプローチ方式
|
〈モデルA〉 利用者に関わる専門職種やサービス提供者が集まってケア会議を開き、ケア計画をたてる。 難点: |
|
モデルB コンサルタント方式
モデルB’
|
〈モデルB〉 利用者の指示に従って、ケア・コンサルタントが専門職種や必要な情報を集めてケア計画を提案したり、ケア・コンサルタントの紹介や情報にもとづいて、利用者本人がケアをマネジメントする。 〈モデルB’〉 マネジメントするケアの分野は、利用者本人が自分でマネジメントをすることが苦手な分野に限られる。 時間的経過: |
|
モデルC セルフ・マネジメント方式
|
〈モデルC〉 利用者本人がすべての分野にわたって自分でマネジメントする。 時間的経過: |
(2) 利用者のタイプ別の対応
このような利用者のタイプを想定してみることによって、それぞれのタイプへの対応を行うことができます。
第1のタイプの利用者については、ケアサービスは提供しますが、ケアマネジメントとしての介入は行わないことになります。ケアマネージャーは日常的には積極的な対応をしませんが、利用者が何か困ったことがあったらいつでも相談できるという安心感を与える側面的な支援を行うことになるでしょう。本事業では、日頃は自分でケアの調整を行っている利用者について、介助者が辞めることになったという相談にのり、新たなケア体制づくりに協力したという例がありました。
第2のタイプの利用者に対しては、利用者の意向を第1に尊重し、セルフ・マネジメントと同時にケアマネージャーが定期的にフォローする等の対応が考えられるでしょう。このタイプの利用者には自立生活プログラムが有効と思われます。なお、本事業の例として特に指摘しておきたいのは、幼い頃に就学免除によって教育の機会を奪われ、また施設での生活によって社会経験を奪われてきた人たちは、セルフ・マネジメントに移行するのに非常に時間がかかるということです。
第3のタイプの利用者には、ケアサービスの提供と同時に、ケアマネジメントを実施することになるでしょう。しかし、このタイプの利用者の中には、第三者からみてケアサービスが必要と思われるのに、利用者あるいは家族がサービスの提供を拒否することがあります。特に、ホームヘルプのように、利用者の自宅がサービス提供の場になるサービスに関しては抵抗感が強いことがあります。
本事業においてもこういった例がありました。そこで、利用者が希望し、利用にあたっては抵抗感がなく、しかも利用者が行動範囲を広げることのできるサービス、すなわち、移送サービスを最初に提供しました。これにより、利用者自身が自分のニーズを認識し、積極的にサービスを利用するようになることをねらったのです。
アセスメントのありかた
本事業の例を挙げながら、セルフ・マネジメントの観点からみた利用者の3タイプを検討してきました。もちろん、この3つのタイプは時間の経過によって変化するもので、固定的ではありません。いずれにせよ重要なのは、障害者のケアマネジメントの目標は、セルフ・マネジメントだということです。そのためには、ケアマネジメントのプロセスで重要な役割を果たすアセスメントも再構成することが求められます。
援助者が利用者に対してどのような援助を行うかという視点からのアセスメントでは、利用者は常に援助される側にとどまってしまいます。セルフ・マネジメントを実現するためには、援助者がもっている知識や情報を利用者に積極的に提供し、利用者自身の力を高めるといったエンパワメントの視点からのアセスメントが必要です。すなわち、ニーズを利用者自身が把握し、社会資源の所在に関する情報を得た上で、必要となるケアサービスを利用者自身で利用することができるようになるためのアセスメントです。
そこで、必要なサービスごとに対応すべき機関が分けやすいように、そして、自分でマネジメントできる部分はできうる限り自分でマネジメントする領域として取っておけるように、アセスメントの領域としてケアの5分野を提案します(表2)。
| 分野 | 内容 | かかわる専門職 |
| 第1分野 | ADL 身辺処理、起居、屋内移動 |
PT、OT、ST等 |
| 第2分野 | 医療、リハビリテーション 病院の紹介、健康管理 |
保健婦、看護婦、医師 |
| 第3分野 | 住環境設定・補助器具の配備 福祉機器、住宅改造 |
PT、OT、建築士 |
| 第4分野 | 自立生活技能を高めるための活動 コミュニケーション、健康管理、危機管理、家事、金銭管理 |
ピアカウンセラー (自立生活プログラム) |
| 第5分野 | 生産的・創造的生活 教養を高める活動、スポーツ、ボランティア活動、宗教・社会的活動、その他の余暇活動を含む文化活動、教育、就労、外出、旅行 |
ピアカウンセラー それぞれの領域に詳しい人 |
ケアの分野を区別する意義は、障害当事者が社会資源の所在を明確に理解できるように情報提供し、当事者主体のケアマネジメントを行いやすくすることにある。
おわりに
以上、セルフ・マネジメントの観点からの提案を含めて本事業の報告を行ってきました。どの地域に住んでいても障害者が必要なサービスを利用し、自立生活を実現するためには、今後に残されている課題は多いでしょう。本論が、今後の障害者のケアガイドラインの参考となれば幸いです。
(たかはしおさむ・まるやまさとこ 立川市ケアガイドライン試行委員会事務局)
〈付記〉
本論の詳細は、『当事者主体のケアマネジメント―立川市における身体障害者ケアガイドライン試行事業を実施して―』としてまとめました。
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1997年8月号(第17巻 通巻193号)25頁~29頁