民話に見る障害者観
民話に見る障害者観
―日本人と偏見―
村勢雅子*
Ⅰ 伝説に見る障害者観
―奇形伝説と奇形人疎外―
日本の伝説をその素材・対象およびモティーフをもとに分類してみると、巨人伝説、小人伝説、妖怪変化伝説、怪奇伝説等といった奇形人、身体的異常人、それに妖怪の登場するものが非常に多いということに気付く。伝説全体からの割合でいえば約4分の1になろうか。
奇形伝説を中心に怪奇伝説、巨人伝説等に登場する主な奇形人をまとめたのが表1であるが、こうしてみると随分多種多様な奇形人が登場しているものである。
| 1 | 奇形人(半人種、猿人) | 17 | 鱗人 |
| 2 | 連繋双体人 | 18 | 人面動物 |
| 3 | 鬼形人 | 19 | 人面植物 |
| 4 | 獣人 | 20 | 矮人 |
| 5 | 有翼人 | 21 | 怪奇人 |
| 6 | 有尾人 | 22 | 巨人 |
| 7 | 人首獣体 | 23 | ろくろ首 |
| 8 | 人首鳥体 | 24 | 福助大頭 |
| 9 | 人首虫体 | 25 | 多手・多足 |
| 10 | 人首魚体 | 26 | 逆手・逆足 |
| 11 | 獣首人体 | 27 | 唇奇 |
| 12 | 鳥首人体 | 28 | 舌奇 |
| 13 | 魚首人体 | 29 | 歯奇 |
| 14 | 虫首人体 | 30 | 鼻奇・耳奇 |
| 15 | 人首介体 | 31 | 口奇 |
| 16 | 鳥毛人 | 32 | 眼奇(1つ目、5つ目) |
さて、ここで最も気になることは、こうした伝説中の奇形人があくまでも想像上のものであるのか、それともその実在が背景としてあったのかという点であろうが、十分とは言えないまでも、その実在を証明してくれる資料を見つけることはできる。
200年 筑紫に人身翼のものあり、害をなす。(大日本史)
377年 飛騨に奇怪の人あり。一体にして面2つ、たがいに背く。頂合して項なく、4手4足あり。膝あるもふくらはぎなく軽捷にして多力、左右に剣を帯び4手をもって弓矢を使う。(大日本史)
846年 伊勢国鈴鹿郡の女子、2頭4首、顔面向かい合い、腹以下は1体の奇児を産む。(大日本史)
983年 讃岐国に1首2身8足の奇児あり。(大日本史)
1153年 京都に鼻目なく額に1眼あり、なかに2瞳もつ女児うまる。(大日本史)
1800年 江戸にろくろ首の女あり。(閑田耕筆)
―「図説 日本民俗学全集3」―
では、何故こんなにも多くの奇形人が伝説に登場してきたのだろうか。また、そこに奇形人はどのように映しだされているのだろうか。
奇形人が伝説という想像上の、架空上の世界で語られてきたという事実とそこに多少の誇張はあったにしても実際に語られたとおりの実像が現実にあったとして証明づけられたことを、現代にも通じる社会意識(差別)と同じ論理で考察するならば、次のような結論をひきだすことができそうである。
つまり、伝説として語られている奇形人は、実は現実社会から追われた者、いわば実体として現実に存在すべき人間が社会意識の上で差別された者なのではないかということである。その身体の異常性ゆえに現実なる世界に生きることが不可能であり、許されなかった。そのために伝説という架空世界に追われたのではないだろうか。そして、伝説として語られることが彼らにとっての「生存」となっていたのではないのか。「どこどこに奇形人が生まれた」それだけで語り継がれるに十分な伝説となるのであれば奇形伝説は、身体の奇形なる者がその生存を否定されて疎外された場であり、そうした伝説の創造過程は差別意識・行為と展開を同一にするものであると言えるのではないのか。
それでは次に伝説の中の奇形人像を具体的にみていこう。
1.奇形人は異類婚(仏罰)の結果生まれた
奇形は獣畜、昆虫等との通婚の結果生じたものとする見方がある。つまり伝説に登場する奇形人は、極めて原始的な構想(想像)の帰結として動物生態的見地からの異類婚の結晶体と見られていたのである。そして、こうした異類婚は仏罰としてのものと考えられ、悪事に対する罰として人間以外の動物と通婚し、そのために生まれたとされているのである。これは,江戸時代をその最盛期として広がり、「親の因果が子に報い…」といった口上で寺社を中心とする祭りの場の見世物を想起すれば容易に確認できるであろう。
2. 奇形人は超人的能力を持っている
もう一つの見方がある。例えば、伝説上の巨人は、その人一倍大きな身体、大きな手足ということから人並みはずれた力で山をも崩し、岩をも持ち上げ、悪事に立ち向かう人として描かれている。巨人に限らず、古くから奇形な身体は超人的能力を有することの証明になっていたようである。
ここで1、2に共通していえることは「奇形人像」は「原始的宗教」なるものによってうつしだされているということである。不可思議であるばかりで医学的にも科学的にもその誕生の理由が明らかにならなければ、それを一つの単純な(原始的な)「神的現象」としてまとめ上げてしまうのが、最も容易で一般的な解決になるからであろう。
そしてこうした意識のもとでは、身体的に奇形であるということは、同じ人間であるにも関わらずほとんどそれが否定されたまま原始的な宗教上の想像力と結びついた珍奇な事実となってしまうだけなのであろう。これを現実に身体的障害(ここでは「異常」の意)をもった人間に対する観念としての差別だと言い切ってしまったら間違いになるだろうか。さらに奇形伝説は「奇形人」差別の投影であると言えないだろうか。
ただ、伝説を生み、語り伝えた者の中には疎外や差別の意識などなく(神的現象なるものへの差別はないのだから)、ほぼ本能・直観に近い意識(理解力)で奇形人を否定的に特別視したとする方がより精確な論述になるかも知れない。
図1 「伝説」への奇形人の疎外
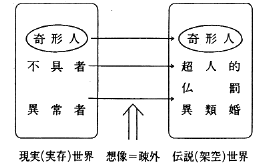
Ⅱ 昔話に見る障害者観
―一寸法師と親指姫―
小さい体というハンディを克服して鬼退治をする一寸法師の話は、子供の頃誰もが耳にして育っている。室町時代から語り継がれている日本の代表的な昔話である。
ところで鬼から貰った打ち出の小槌の一振りで、一寸法師が普通の背丈の人間になって初めて「めでたし、めでたし」となるこの話の結末が問題である。何故大きくならなければ「めでたし」にならなかったか、何故小さいままではいけなかったのか。
ヨーロッパの民話に「親指姫」「親指太郎」がある。親指姫は小さいまま王子様と結婚して幸せになるし、親指太郎も大きくならずに大切に育てられていく。どちらも小さいというハンディが、ストーリー性の要因にならず、むしろ主人公のキャラクターにプラスとなっている。
ここで仮に小さいこと(小人)を障害と見るなら、この日本とヨーロッパの昔話の比較において、はっきりと障害者観の相違を見ることができるような気がする。つまり決定的に異なるこの話の結末から、日本人の障害者観は、障害を持っていること、即ち免れ得ない不幸を背負っていることとするものであり、そこには否定的(悲観的)要素が強く内在している。これに対し、西欧人のそれは肯定的であり、人間として幸せになることと身体に障害を持っていることの間には何の関係もないといったものである。障害者理解の観点がここで大きく違ってしまっている。
さらに小人を異常とし、不幸とし、大きくならなければ幸せになれないとする見方はおとぎの世界だけで終わっているのではなさそうである。障害者を不幸であると見なすことは、結局、障害者自身の自発的な社会的自立への人間的努力を踏みにじってしまっているという現実があるからである。
さて昔話のストーリーとしての面白さということになれば、打ち出の小槌の一振りで小さい人間が一遍に大きくなるということは、確かに超現実的で魔術的ではある。しかし昔話が「それからどうなったのか」という人びとの興味と不安と期待をもって語り継がれてきたものであるならば、結末を決定的にする打ち出の小槌の一振りを単に魔術的として捉えるだけでは物足りなくはないか。打ち出の小槌こそ「こうならねば幸せになれないもの」「こうなって欲しい」という日本人の価値的欲求を表わしているものではないだろうか。昔話の結末というのは、誰にとっても幸福だとして納得し得るものをその究極の目標として顕在的あるいは潜在的に存しているはずであるというならなおさらである。
多少ニュアンスの違いはあるにしても下記の2つの昔話も身体的な障害がなくなって初めてハッピーエンドといった展開のものであるのでここに参考までに揚げておく。
◆盲とつんぼ
昔、あるところに盲とつんぼが、2人でこうしていてもつまらないから、どこかへ行こうと相談しました。そして初めに芝居見物に行きました。ところが盲には役者の声だけ聞こえて、つんぼには手振りなどは見えるが、声が聞こえないのでつまらないと外に出ました。
随分歩いてやっとある家にたどりつきました。中をのぞいてみましたが誰もいないので2人は中に入りました。つんぼがそこやかしこを捜してみて、その家が鬼の家であることに気がつき盲に話しました。だが2人はともかくここへ寝さしてもらわにゃならんと決めました。(省略:しかし鬼に見つかってしまい、なんとか難はのがれる。)2人は今夜のうちに荷物を馬につけ、朝早く発つ相談をして寝ました。
それから2人は、夜明け前に起きて逃げました。ところがむこうから鬼が大勢やって来ました。そして「だましゃあがったな、ぶち殺してやる」と怒って大勢でさかてんでをとりだしました。一番上になった鬼が木に登った盲の耳をひんにぎりました。すると盲も死にもの狂いで鬼の耳をひんにぎりました。
とうとう鬼は逃げてしまい、2人は助かり家に帰ってから鬼の家でとってきた宝物を分けました。盲は手探りで自分の分を触ったら少々少なかったので、多い少ないのけんかが始まりました。盲はつんぼの耳をつぶし、つんぼは盲の目をぶったので、盲は目が見え、つんぼは耳が聞こえるようになりました。
◆鉢かつぎ姫
昔、ある国に鉢かつぎという女の人がありました。この女の人は立派な大尽の家に生まれましたが、どうしてか生まれた時から頭に鉢をかぶっていたのでした。鉢がどうしてもとれなかったので化物と思われていました。そしてとうとう家を追いだされてしまいました。
鉢かつぎは家出してから方々を頼ったのですが、どこへ行っても不思議な格好なので誰も相手にしてくれませんでした。そうこうしているうちにある国へ出てきました。ここに立派な大名がいて、鉢かつぎの身の上をかわいそうに思って養ってやれというので一番悪い風呂焚きの女中にして使いました。
ところがこの大名の子にたいした立派な若殿がいました。若殿は鉢かつぎ頭こそ妙な形ですが、手足は優しいのを見て、普通の人ではないのをみて、ただの者ではないと思い、この女と夫婦になる約束をすると、お父様の大名は大そう怒って若殿と鉢かつぎの間を裂こうとしました。
2人はなかなか別れることはできぬ。2人して家を出ようというので一晩たがいに嘆いて、明け方いよいよ発とうとしますと、不思議や、今まで頭の上についていた鉢がころりと落ちたと思うと、それが2つに割れて、中から金銀が山のようにでてきました。そして2人は望みのように夫婦になり栄えたということです。
―こぶとり爺さん―
教訓的・道徳的モティーフを持つということで、教育、しつけの材料にされる昔話も多いようである。例えば、次の「こぶとり爺さん」もその一つであろうか。
踊りを上手に披露して、打算のない気のいいお爺さんは、命びろいどころか恐ろしい天狗(あるいは鬼)にすっかり気に入られ、ほおにぶら下がって長い間悩みの種となっていたこぶを取ってもらい、大喜び。反対に心掛けが悪く打算的な隣の爺さんは、踊りも下手ときていて、天狗たちの気分を損ね、取ってもらえるものとばかり思っていたこぶをもう一つつけられて追いかえされる。
なかなか愉快な話ではあるが、ここにこめられた教訓とは、心掛けが良ければ幸せになれる、心掛けが悪ければそのバチとしてどんな災難に遭うか解らないといったもので、「人間の幸、不幸は日常の心掛け次第―」というものではないのか。
となると、障害を悪い心掛けに対するバチとしてひとつの災難、禍とする考え方が、障害者を一方的に不幸な人と決めつける日本人の障害者観の背景にありそうな気がしてくる。
このことの証明は、障害者とすれ違った親子が「言うことを聞かないとあんなふうになってしまいます」と言って戒めの会話をする光景や、以下に示す昔話も手伝って容易になし得るのではないだろうか。
◆「おしになった殿さま」―あらすじ―
いつも無理ばかり言って家来など周りの者を困らせている我がままな殿さまがいて、ある時、とうとうその我がままがたたっておしになり、二度と無理が言えなくなったという。
◆「手無し娘」―あらすじ―
継母に憎まれて両手の手首を切り落とされた継子が背中におぶった子供を誤って川の中に落としてしまい、助けようとした途端に手が生え、継母はその時突然両手を落として手無しになってしまったという。
昔話はひとつに面白ければそれでよいのかも知れないが、その語り手が祖母であり、母であり、忠実なる聞き手が子供や孫であったという伝承経歴の中で「~したから…になった、だから~してはいけない」とする論法によって、身体に障害を持つことが道徳上の戒めとなっていてはその面白さも帳消しになってしまうのではないか。身体的障害は、道徳上の悪の象徴などでは決してないのであるし、両者には何の因果関係もないはずである。
さてここで少し民話から離れてしまうが、やはり長い間にわたって伝えられてきたという点で民話と大きな共通性を持つ「迷信的言い慣らわし」にも触れてみよう。
というのは、迷信的言い慣らわしの中にも身体および精神に障害を持つこと、即ち、「バチあたり」とするものが数多くあるからである。その主なものは以下のとおりである。
●夜、梅干を食べるとツンボになる…秋田
●茶碗をならすとオッチ(おし)になる…長野
●庚申の日に味噌汁を食べると目が潰れる…大阪
●夜、梅干を食べると目がうすくなる…富山
●ごはんを食べ残すと片輪の子が生まれる…埼玉
●ナシの芯を食べるとツンボになる…奈良
●毛髪を火に燃やすと気ちがいになる…神奈川、静岡、滋賀、京都、大阪、奈良、徳島、香川、高知
●灰を食べるとオシになる…奈良
●生米を食べるとばかになる…秋田
これらは全て単なる迷信によるものであり、その背景には何の科学的根拠も真理性もない。もし何かが関係していたとしても、恐らく生活上の極めて個人的レベルの「都合」でしかなかったであろう。そしてその「個人的都合」に合わせて障害者が戒めの材料として利用されているのである。
先に昔話が教育やしつけの材料にされているとしたが、さらに正確な言い方をするならば、材料になっているのは昔話というより障害者自身であるとした方がいいかも知れない。
そもそも明確な原罪意識のない、そしてそれゆえ宗教観が混沌としている日本人にとって、身体に障害を持つことは一種の強迫観念としてつきまとう罰でしかないのだろうか。もしそうであるなら日本人は一体いつそれを払拭できるのだろうか。いつまでもこれを怠ることこそ「バチあたり」だと思うのであるが…。
―笑い話―
もし、障害者をその障害ゆえに笑うということになれば、それは一つのはっきりとした差別行為になろう。ところが、こうした笑いがモティーフとなっている昔話は決して少なくない。
例えばここに「三人片輪」「三人協力」といった昔話があり、その題名と登場する障害者を少しずつ変えてあちらこちらで語られてきているようである。
「三人片輪」の伝承範囲(「日本昔話通観16」同朋舎)
●福島県石城郡…片目、びっこ、鼻かけ
●埼玉県川越市…盲、びっこ、鼻かけ
●山梨県北巨摩郡…びっこ、眇(すがめ)、鼻くた
●島根県那賀郡…ちんば、鼻かけ、盲
●香川県三豊郡…目かち、びっこ、鼻かけ
●長崎県上県郡…びっこ、鼻かけ、片目
●大分県(某地)…びっこ、鼻かけ、片目
ちんば、いざり、盲などの障害を持つ者が3人で相談している。「人に見られるのが余れ恥しさかい~この片輪を隠すような芝居をして歩くまいか」3人は結局、互いの身体の欠陥を隠すように協力し合って歩き出す。その光景を面白おかしく語るものである。伝えられる土地によっては、話の途中で「片輪の者は通るべからず」などという立て札まで立たせてしまう。
恐らく語る者も聞く者も差別意識など毛頭なくそこにただ「笑い」を求めているだけなのであろうが、その「笑い」の中に内包されてしまった差別意識がありはしないだうか。あくまでも民話だからとして、差別ほどの強烈なイメージはないはずであると言い切ってしまえない気がするのである。
さてこれが身体障害者への笑いをモティーフにしたものであるなら、一方には愚者を主人公にして彼らを思う存分笑う昔話もいくつかある。(●「日本は広い」●「衣を焼く」)
こうした話は、後に日本の代表的庶民文芸の1つとなる落語に通じていくのであるが、ある種の親しみさえ感じられる与太郎や甚兵衛、喜六がそこでは少し足りない者としてその言動の滑稽さを狙われた笑いの対象でしかない。
では何故彼らを笑うのだろうか。人が人を笑うということには2つの意味があるのではないか。1つには自分と他者との間にキッパリと区別をつけ、相手を「敵」にまわすこと、もう1つは「敵」をつくってしまっても笑う者同志の連帯感、仲間意識を強化して「敵」からの危険やそれへの不安を防ぐこと。つまりこの種の笑いは他者排斤と自己防衛という2つの武器を同時に使ったものとみてよいだろう。
こう考えてくると、昔話の中の身体障害者や愚者(いろいろな資料からそのモデルは精神薄弱者になりそうである(6))に対する笑いが、彼らを笑うことで優越的立場から連帯意識を高めていった健常者側のものでしかないことが解る。この種の昔話では障害者は、健常者に笑い返してやることのできない弱者として映っているだけなのである。
そして何より重要なことは、その背景の現実社会の中で彼らは常に「笑い」のタネにしかされなかったということであろう。
図2 民話にみる障害者観―その視点と障害者像―
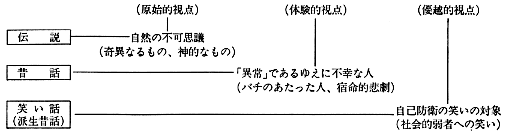
* *
伝説に見ることのできる奇形人像は、人間の本能的、直観的、そして原始的視点における「自然の不可思議な産物」でしかないようである。しかも科学や哲学が整然と体系づけられるのを待ったとしても、さほど変わりようのない原始的(幼稚)な信仰心がそのまま伝説伝承の動機となっている限りは、その素材としての奇形人は「奇異なる存在」ゆえに常に「疎外」対象になる以外、生存の術を得ることのできないものだったと考えられないだろうか。その意味で奇形伝説は障害者疎外の象徴といえるような気がする。
また、昔話に見る障害者は、不幸者であったり、バチのあたった人であったり、滑稽者であったりした。伝説が障害者を自然の不可思議の1つとして原始的視点から見ていたとするなら、昔話のその視点は体験的、心情的なものであり、障害者の生存を宿命的な不幸、悲劇としてしまうものであった。障害者になることを「もし自分がそうであったら」という仮定の体験として捉えてはいるものの「どうにもならない結論」として「不幸である」と一方的に決めつけてしまう。そして問題なのは、そうした見方の域を少しも脱していないことである。「障害を持った人は不幸である。けれども~」といった底の深い人間理解はみられない。
さらに昔話から派生してできた笑い話になると、障害を持たない人間の優越的視点における自己確認がつくりあげた障害者像をそこに見るだけである。
最後に、民話を伝承経緯に沿ってはっきりと種別(伝説・昔話毎)に区別できるか否か定かでないということ、しかし、そこにおおよその伝承時間の同一的経過があるものとして考えるならば、これらの民話を現在も語り継ぎ温在している日本人が前述の3つの視点による障害者観を現実に混在させていることは間違いない。
そして、こうした考察を通して民話を洗い直そうというのではなく、日本人のこの領域における思考形態・経路を明らかにし、今後の障害者福祉充実(偏見の除去)に向けての反省テーマにできればと考える。
参考文献 略
*日本女子大学、社会福祉科研究生
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1981年7月(第37号)22頁~28頁


