処女地における地域リハビリテーションの発展
処女地における地域リハビリテーションの発展
THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY REHABILITATION IN A VIRGIN SOIL
―WITH SPECIAL REFERENCE TO CRIPPLED CHILDREN IN HOKKAIDO―
河邨文一郎 *
地域社会とリハビリテーションというテーマを論じるには、ある地理的に限られた地域を取り上げ、ある特定のリハの分野の歴史を論じることが簡明な手段と言えましょう。私は今日、北海道におけるリハビリテーションの歴史を、肢体不自由児のそれに焦点を当てて論じてみたい。なぜ北海道を取り上げるか、その理由は第1に、それが1つの島として地理的に独立した地域を成すこと、第2に北海道内の大学で整形外科医の養成がはじまったのはわずか40年足らず以前で、それまで肢体不自由児・者のリハビリテーションに関する限り処女地であったこと、そしてその歴史はそのまま私の半生史であり、言わば体験的歴史観について語りうること、最後にリハ発足当時の北海道は明治の開拓開始以来100年を数えるのみで、産業・経済・交通にも後進性が強く、“先進国における発展途上地域”であったことなどです。
さて、私が札幌医大に赴任したのは1949年秋でしたが、ひどい変形をもった肢体不自由者を札幌市の路上に大勢見て驚きました。どこから手をつけたらよいか迷っている矢先、東大時代の恩師高木憲次先生をリーダーとする身体障害者巡回相談チームがやって来たのです。1950年8月のことです。
日本の現行の社会保障制度は第2次世界大戦後、新憲法に保障制度を礎として発展しました。1946年制定の生活保護法、翌年の児童福祉法、1949年の身体障害者福祉法―このいわゆる福祉3法の制定は、身体障害児・者の医療に公的扶助の道を拓き、リハビリテーション施設の設立を保障したため、身体障害者の医学のなかでも整形外科が飛躍的な発展を遂げました。戦前には障害者たちは貧しさの中に孤立していたため不幸にも医学の進歩の恩恵に浴さなかったが、戦後間もない日本政府がこれらの進歩的な社会福祉政策を財政的に支えるには大変な苦心が要ったと思います。その陰にはアメリカ占領軍の強制に近い圧力があったと聞きます。
北海道最初のこの巡回相談も、この政策の一環を成すものでした。整形外科手術でもっとよくならないか、義肢・補装具の給付や修理は要らないか、その他職業再訓練の相談や就職あっせんなどを行うもので、医療関係は東大からの整形外科医2名と札幌医大からの私と他に1名、職業問題は労働省の係官が担当しました。
巡回した場所は、函館を振り出しに、札幌、旭川、帯広、釧路、室蘭でした。巡回診療というものは元来、無医村に対して行うものですが、当時は、整形外科とリハに関する限り、北海道の主要都市がすべて“無医村”に近かったわけです。
巡回相談から帰るとすぐ、私はその報告を北海道新聞に寄せ、肢体不自由児・者の悲惨な状況とリハビリテーション・センターの必要性を訴えました。実は札幌に赴任して間もなく私は一人の脳性まひの少年を診察し、尖足に対する手術を勧めたことがあります。少年は、毎日父親に背負われて通学していましたが、入院すれば学校を休まねばならぬからと手術を拒んだのです。
私が肢体不自由児施設を作ろう、と思い立ったのは、この時でした。恩師高木教授が1941年日本ではじめて作られた整肢療護園―あれと同じスクール・ホスピタルを北海道でも作ろうと、新聞や講演、そして当時の知事にも訴えましたが、施設実現の政策が思いがけぬところで講じられていました。高木先生の強い勧告によって厚生省が全国数カ所に施設建設の方針を立て、その設置を北海道に対しても勧めたのです。
これを受けて北海道は、北海道札幌整肢学院を、成人身体障害者のための更生相談所、更生指導所、職業訓練所とともに設立しました。1952年のことで、日本で第7番目の肢体不自由児施設でした。これらの施設はまさに北海道におけるリハビリテーション発祥の記念碑群です。私は当時札幌医科大学の整形外科教授でしたが、整肢学院の院長兼務を発令されました。整肢学院は50ベッドのささやかな施設でしたが、創立職員たちの献身的活動によって、独創的かつ先覚的な仕事が次々に生れました。1954年夏には天皇・皇后両陛下のお成りをお迎えし、1966年にはアメリカのポートランド市のShriner小児病院と姉妹提携を結ぶなど、活動の輪が拡がる一方では、規模も段階的に拡大されて、現在の道立札幌肢体不自由児総合療育センターにまで発展するのです。
さて、院長就任の時点での緊急事は、道内の肢体不自由児の実態を知ることでした。そこで、札幌医大整形外科と整肢学院とが共同で、1954年札幌市の学齢期肢体不自由児の悉皆調査をしました。就学猶予や病気で入院中の児童も徹底的に調べました。調査対象には6歳から15歳までの6万1,587名でしたが、調査の結果、肢体不自由児は503名、0.82%の出現率でした。
この時の調査結果を1950年の第1回巡回相談の結果(旭川、帯広、室蘭3都市の集計)と比べてみて私は驚きました。巡回相談のとき圧倒的に多かったのは断肢者で33.3%もいました。関節強直も18.2%にのぼっており、骨関節結核は20.4%でした。ところが4年後の札幌市の学齢児調査では、ポリオは29.8%で、巡回相談のときの7.9%をはるかに越えている。また、巡相では5.4%しかいなかった脳性まひが学齢児調査では12.5%もいる。骨関節結核は両者に大差はなかったが、巡相の際あんなに多かった断肢者や関節強直が比率の上では驚くほど少なくて、“その他”の区分けに一括されてしまった。
なぜこんなまちがいが生れたのか?それはつまり、巡回相談には全員が診察に来るわけではない。ではなにがゆえに診察に来ないのか、これが問題です。
そこで肢体不自由児合計503名の治療状況を調べてみると、とにかく1回でも医師の診察を受けたことのある者は401名、80%いるのだが、現在も治療を続けている者はたった35名しかいない。残りの366名は治療を放棄してしまっています。
治らないから治療を中止したのであろうか?ところが調査の結果は、総計503名のうち、整形外科的に現状を改善できるものが、81.9%にものぼっている。改善困難な者3%、特に治療を要しない者が15.1%と出た。
同じことをポリオと脳性まひについて調べてみました。一度でも医師の診察を受けたことのある者は、ポリオでは全例、CPでは73%にのぼっている。ところが現在もなお治療を続行しているのはポリオでたったの6名、CPでは3名、あとはすべて治療を投げ出しています。
しかも、改善可能なものがポリオでは95.2%、脳性まひでは82.5%もありました。治療不要の者がポリオでは7名、脳性まひで5名となっています。
そこで、治療を放棄した理由について調べてみたところ、ポリオでは経済的理由が140名中22.9%、ポリオ後遺症の専門医は整形外科医であることを知らなかったのが22.1%、そして実に40%もの子供たちが、もうこれ以上はどうにもならぬ、とあきらめていたのが分かりました。脳性まひでは経済的理由15%、専門医を知らないが25%、あきらめていたが51.7%でした。すべては整形外科医が養成されていなかった当時の北海道の状況を、ありのまま物語る統計であったと言えます。
適切な治療施設について調べると、病院通院でよい者23.8%、病院入院必要38.1%、入院期間が半年以上にわたり、学業継続の関係上、肢体不自由児施設に入院を要する者が38.1%となりました。
以上の札幌でのデータを北海道全休におきかえますと、全北海道の肢体不自由児の総数は全学齢児童の0.82%、すなわち1万7,000名前後、肢体不自由児施設収容が必要な者は約5,477名ということになる。極めて重度な脳性まひで、いわゆる重症心身障害施設が適当な者は208名となる。
この統計を前にして私たちは思い悩みました。整形外科の病院も施設もほとんどなく、治らぬものとあきらめて家庭にいる児童たちに、どのように救いの手を差しのべるか?克服すべき因子には先ず施設の狭き門がある。5,477名の児童に対する40ベッドという狭き門。第2に北海道の広域性がある。交通事情が未発達であり、しかも冬には積雪のため著しく阻害される。これらが北海道の広さをなお広いものとするのです。
北海道の広域性がもたらす問題を考えてみましょう。先ず僻地に近くなるほど身体障害をひき起しかねない疾病やリハビリテーションの専門家が少なくなります。これは今日もなお言えることですが―。第2に専門家でなくても、リハビリテーションの知識や技術を多少はもっている人がほしいところですが、中央から遠い町や村では、医師も、看護婦、保健婦、ケースワーカー、学校の教師らも研修を受ける機会に乏しい。第3に障害者が専門施設や相談所に相談に行きたくても遠いので、旅費や時間がかかりすぎる。
また、せっかく巡回相談班が近所まで来ても行けないことがある。その原因は経済的なこと、職場の都合や仕事の性質上―例えば農家の農繁期で行けない。家庭内のこと―育児や留守番の問題などいろいろあるし、その日はどうしても行けない日にぶつかったりする。個人の事情や精神的な理由、例えば、無知、無気力、あきらめなどもあるでしょう。
いろいろ考えた末、私たちは先ず、肢体不自由児の援助団体を作ることにしました。1954年に北海道肢体不自由児福祉協会―以下“道肢協”と略しますが―を作りましたが、先ず啓発事業としては、啓発と実益を兼ねた“友情”と“愛”の年賀絵はかきの頒布で、主たる事業資金を取得し、また、全道の小・中学生からの“友情”作文と図画、工作のコンテストと、その表彰と激励の会などを催します。
次は在宅肢体不自由児に対するサービスで、目玉事業は巡回相談と療育キャンプで、現在は両者とも北海道の委託事業として実施しています。
巡回相談は毎年行われ、昨年度は36カ所で、計435名を検診しました。整形外科医に小児科医が加わり、理学療法士を連れて行きます。巡回診療は居宅訓練のfollow-upや、施設への入院または通院あっせん等の機会としても貴重です。しかし限界もあり、年1回きりの相談では指導が徹底しにくいし、またなにかの理由で参加できないと次回まで1年あるいは数年待たざるをえない。ですから、近くに父母の会があれば入会を勧め、療育キャンプや施設の母子入院の利用を指導することにしています。
療育キャンプは、肢体不自由児とその家族との合宿訓練と言えるものです。日程はもちろんレクリエーションを含むが、自宅における子供の精神面の育て方、毎日の機能訓練のやり方、家庭での訓練用器具の作り方などについて学ぶ時間を十分とります。療育キャンプは1959年以来もう30年の歴史をもちます。全国的にも最も古い歴史です。レクリエーションよりも訓練としつけの学習に重点をおくのが北海道の特徴です。道肢協と地元の父母の会との共催で行われ、費用分担は大体1:1です。昨年度は全道20カ所で、親子計491組、1,276名が参加しました。当初は1週間くらいのキャンプもありましたが、最近では2―3日程度のものが多くなりました。
この協会の事業には、このほか肢体不自由の高校生への奨学金や、電動車いすやワープロなどリハ用具の施設や個人への寄贈、また毎年の全道肢体不自由児福祉大会を主催しています。ただし道肢連協には子供と日夜触れあって育て上げてゆくことはできない。それは父母にしかできないことです。
肢体不自由児父母の会の最初のものは、1957年札幌で生まれました。札幌小児まひ母の会がそれです。保健所の一室を借りて月に2回相談日を持ち、整肢学院の副院長らを招いて診察をうけ、機能訓練に励みました。そこで覚えた訓練の知識を自宅で活用したのです。ピクニックや海水浴、雛祭りやクリスマス―楽しい会もいろいろでした。
施設や学校建設の陳情運動や、ポリオの大流行のときは街頭募金をして鉄の肺を札幌市に贈りました。札幌小児まひ母の会はこのように、子供たちの療育に主眼をおき、政治行動は二の次でした。この運営の理念と方式は、その後に生まれた各地の父母の会に受け継がれ、北海道の父母の会の性格を形づくったのです。
とにかく、父母の会の結成によって、少年期はもちろん幼児期の居宅児の指導が効率的になりました。彼らが適切な療育のレールから逸脱するのを防ぐ効果も見のがせません。
道肢協などによる組織化の努力で、父母の会は追々ふえ、1960年夏、7つに達したとき、北海道をポリオの集団発生が襲ったのです。
1960年夏、炭鉱の町夕張に発生したポリオはまたたく間に全北海道に拡がり、総計1,664名の子供が犠牲になりましたが、死者は131名、7.9%にのぼり、まひ者1,364名、後遺症826名という物凄さでした。流行の当初、集団発生地にパニックが起こったのは当然と言えるでしょう。
1年後には発生はおさまり、セービンの経口ワクチン接種を政府が断行することによって、日本におけるポリオの発生はほぼ完全に制圧されました。日本を訪れたセービン教授から私は幸いにも、防疫の上でいろいろインストラクションを受けることができました。
ポリオ後遺症対策のため、発生後3年間私たちは全北海道をかけ廻りました。ポリオの大流行は惨酷な悲劇でしたが、それを飛躍台にして北海道のリハビリテーションが、大きく発展したことは特筆されるべきでしょう。その間、いくたの新機軸が生れました。巡回相談も従来の道肢協と日本赤十字のほかに、北海道衛生部にも新たに生まれました。NHKのテレビによる在宅訓練指導プログラムこれは“テレビ整肢学校”というシリーズで、実は私が担当して出演しましたが、大きな歓迎を受け2年間も続きました。
また、新しい肢体不自由児施設が旭川に、次いで函館に作られ、日本赤十字ポリオセンターが伊達に、そして肢体不自由児養護学校が札幌の真駒内と網走に作られ、札幌および旭川の肢体不自由児施設内の分教室がそれぞれ併設学校として独立しました。著しい整備がなされたことはもちろんです。
大きな収穫は札幌の肢体不自由児施設に母子入院棟が設けられたことです。これは母子20組を通例1回につき2カ月入院させ、家庭における機能訓練や日常生活動作、保育術などを教えこむ。母親の食費のほかは一切無料であり、費用は国と道が負担する。僻地の障害児には特に役立つが、各地の父母の会の会員の利用度も高い。家庭や、地方の小規模通園施設などで訓練中の者が、より難しい技術の習得を必要とする段階にさしかかったとき母子入院し、再び家庭や通園施設に戻ってゆきます。
やがて肢体不自由児施設そのものも、その後の肢体不自由児の重度化、重複化、多様化、幼少化に対応すべく大幅に拡大・改築されました。先ず1972年札幌整肢学院が、また1982年には旭川整肢学院が北海道立肢体不自由児総合療育センターとして再建されたのです。新たに幼児病棟、重度棟も付設されました。なお、北海道にはまだ成人期を控えた者たちのための前職業準備訓練施設がなかったので、札幌の療育センターの隣接地にいわゆる年長児施設として北海道立肢体不自由児訓練センターが建設され、堅実な活動を続けています。
援護団体も適時作られた。集団発生のさなかに作られた北海道子供をポリオから守る会は、予防ワクチンの接種年齢の引き上げ等を国と道に交渉しました。なかでも画期的な役割を果したのは北海道小児まひ財団でした。1961年7月設立され、2億円を上回る募金を達成して、ポリオ集団発生地区中10カ所にいわゆる“マザーズ・ホーム”を建設しました。
マザーズ・ホームは現在は日本全国にある小規模通園施設の先駆で、当時はもちろんまだ法律化されていなかったため、いろいろ大きな問題をまきおこしました。理学および作業療法一式を設備し、運営は所在地の市が当たり、非常勤嘱託の整形外科医と、訓練士2名、助手1名が配置されました。学齢児のための特殊学校を併設したものもあります。利用料金は無料で、すべて小児まひ財団の負担です。マザーズ・ホームは日本全土に大きな反響をまき起し、厚生省もとうとう法律化を急いで、1964年以降は補助金を出すようになりました。
小児まひ財団はまた、後に述べる北海道リハビリテーション学会の協力を得て、1961年独自の訓練士養成講座を開き、終了した者を訓練士としてマザーズ・ホームに配置しました。日本で理学療法士・作業療法士の試験制度が発足したのは1966年ですから、小児まひ財団はここでも法律以前の活動をしたわけです。財団はその後、重症心身障害児施設の北海道療育園を旭川市に作った機会に、一応その目的を達したとして、1974年解散しました。
1461年札幌整肢学院で発足したボランティア・サービスは、施設専属のものとしては日本で最初の成功例と言われます。
ボランティアの互選による委員と施設長等から成る運営委員会が、作業種目、時間、日程など無理のないスケジュールで設定したからだと思われます。
さて、肢体不自由児父母の会が、道肢協などの努力によって年々ふえてきたことは前にも申しましたが、ポリオ集団発生の後遺症対策に当たって、この父母の会育成の経験が実に役に立ったのです。
道肢協が出来たのが1954年、これに対し最初の父母の会が出来たのが3年後の1957年で、数が7つにふえた1959年に全道肢体不自由児父母の会連絡協議会としてまとまりました。その翌年にはポリオの集団発生です。私たちの懸命の呼びかけもあって会の数は急速にふえ、18の父母の会、1,190名の会員数となったところで北海道肢体不自由児父母の会連合会―通称道肢連の旗を掲げました。そして1973年には第1回の全道肢体不自由児者福祉大会を帯広で開き、以後毎年、開催地を変えて催しています。1977年、道肢協と道肢連は合体して、財団法人北海道肢体不自由児者福祉連合協会―通称道肢連協に発展しました。現在41の父母の会を支部として1,466名の会員を擁し、年間約2,600万円の規模で事業を行うまでになりました。最近では、肢体不自由児の疾患構成の変化を反映して会員の子供たちは脳性まひや先天性変形などの、しかも重度、重複障害をもつものが大部分となりました。
ここで福祉村について語らなければなりません。“重度身体障害者がよりよい社会人となるために学ぶことができ、働くことができ、そして親の死後でも安心して生活のできる場”の建設を切望する声が脳性まひの青年たちの間からあがり、北海道重障者福祉村建設推進委員会が1965年設立運動を開始しました。その夢が現実となったのは1979年、敷地100へクタールの丘陵地に重度身体障害者のための更生援護施設、授産施設および療護施設などの総合施設として生れました。明日、皆様の中の希望者に視察して頂き、現地で討議が予定されております。
今日の講演の中で北海道リハビリテーション学会のことを一言御紹介できたのを嬉しく存じます。この学会は日本リハビリテーション医学会より1年早い1963年に発足し、医師だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語治療士、義肢装具士、看護婦、保健婦、心理相談員等々の医学関連専門スタッフをはじめ、学校教員、職業訓練指導員、ケースワーカー、福祉ボランティア、福祉関係公務員、その他あらゆるリハビリテーション分野から会員を集めています。すなわち、発足の時から、総合リハビリテーションの研究を目ざすものでした。年次学術総会のほか、今日的なテーマについて年3―4回、講義と実技指導による特別研修会が催されます。
なお、リハビリテーション技術専門職のうち、理学療法士・作業療法士については養成機関として短期大学が、1982年北大に、翌1983年に札幌医大に付設され、それぞれ理学療法士20名、作業療士法20名を養成しています。
ここで1枚の図の上に、皆さんと共に肢体不自由児父母の会の所在地を見てみましょう。父母の会の子供たちはほとんどが札幌か旭川の療育センターで、指導を受けたことがあり、従ってセンターに登録されているわけです。父母の会はまた道肢連協の支部として、その巡回相談や療育キャンプに参加し、療育センターの技術陣の指導を重ねて受けます。その所在地に小規模通園施設がある場合は当然これを利用しますが、通園施設の訓練士は療育センターで訓練された者がほとんどです。つまり、父母の会に籍を置くかぎり、その子供たちは、肢体不自由症の診療に錬達した専門医や技術者によって一貫した方針のもとで指導を受けることになります。リハビリテーション技術の実施ないし伝達という見地からは、父母の会はその前進基地であり、地域リハビリテーションのネットワークの大切な結び目であることがお分かりかと思います。
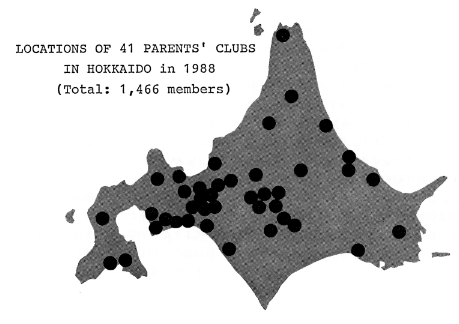
父母の会のネットワークの中心には道肢連協本部があり、これと不可分の関係にある両療育センターがあるわけですが、北海道の場合には、子供たちの教育の場である独立養護学校にも父母の会は、道肢連協の組織を通じ、ないしは単独に連絡を保っています。
このネットワークを堅実に維持してゆくこと以外にも、なさねばならぬ仕事はあまりにも多い。しかも、リハビリテーションの発足当時と現在とではそのtargetが大きく変化しました。起因疾患の変化とリハビリテーション技術的進歩の結果、対象が重度化、重複化、幼小化する他方では、社会の経済的・福祉的成熟化が急速に進みました。医学の第3の段階として位置づけられていたリハビリテーションは、障害者の潜在能力の多角的な開発を通じて、その全人間的復権をはかるものとして理念づけられるようになりました。そしてリハビリテーションからヒューマニテーションへ、さらにノーマリゼーションへと新たに展開して来るにつれて、リハの主流は居宅ケアに移ってきました。事実、先進国においては家族の解体が顕著です。以前のように大家族がその中に生じた障害者を庇護し、ないしはその自立を助けてゆくという伝統は失われつつあります。一方では脱施設の風潮が強まり、居宅ケアの推進に拍車をかけています。北海道でも、保健婦等による家庭訪問、学生ボランティアより成るホーム・ヘルパー活動が活発化しつつあり、また自立生活を支えるケア付き住宅の実験的試みや、施設を中核とするノーマライゼーション・ゾーンの構想の策定が進みつつあります。
ともあれ、本日の私のお話は肢体不自由児に限定しました。しかも、今日作り上げられた体系の土台づくりのお話です。そして子供には通常、家庭があります。家族がその面倒を見るのが通例です。肢体不自由児が成人したとき、家庭崩壊の社会に投げ出されるでしょうか、子供でいる間は家族に守られなければなりません。父母の会と、そのネットワークは、それだから貴重なのです。それに彼らが成人したら、おのおの家庭を作れるようでなければならない。むかし、ある先輩が、“リハビリテーションは家庭に始まり家庭に終わる”といった言葉が、いきいきと蘇えってくるのを感じます。
居宅児童に窮極の的を絞ったアプローチの歴史ともいえる今日のお話を終えるに当って皆さんに一言申し上げたいのは、お話に出てきた数々の出来事に関係なさった方々が、今日この席に大勢おいでになるということです。今日のお話は、それらの方々と私などが一緒に成し遂げた手造りの歴史なのです。私たちがみんなで、このかつての処女地の上につくったリハビリテーションの小さな歴史が、若い世代の方々、さらには海外から御出席の方々の興味をひくことが出来たら幸いです。
*札幌医科大学名誉教授
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1989年3月(第60号)31頁~37頁


