日本における脳性麻痺の発生
日本における脳性麻痺の発生
―疫学的分析と今後の対策―
CEREBRAL PALSY IN JAPAN
―EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS―
竹下研三 *
日本における脳性麻痺発生の減少
脳性麻痺の根底に存在する脳障害発生のリスクは多くが胎生後半から新生児期までの間に生じ、その障害は分娩前後の無(低)酸素症を中心として発症する。この一連の病態の最悪のゴールはもちろん周産期死亡もしくは早期新生児死亡である。したがって、この周産期死亡の状況を理解することは、脳性麻痺脳障害の発生状況を理解することにも一致する。図1は本報告である脳性麻痺の疫学分析を行ったと同じ期間、すなわち1955年から1985年までの30年間の我が国における周産期死亡率と早期新生児死亡率の全国平均の変化である。母子衛生統計からよく理解できるのであるが、各都道府県ごとの変化もすべてこの全国平均値とほとんど変わらない変動を示している。この周産期死亡率の減少はいうまでもなく周産期医療の進歩による。このことは、我が国における周産期医療がこの30年間全国どの地域においてもほぼ同じ質的向上をとげてきた結果ともいえる。さらに、このことは、ある地域の脳性麻痺の疫学資料がたとえ全国的規模ほど大きくはなくとも、その地域の周産期死亡の状況が全国の平均値とほぼ一致していれば、その分析結果は誤りなく全国における脳性麻痺の実状を表現していると解釈できることを意味している。我々はこのような理由から鳥取県における脳性麻痺の疫学的分析結果を全国的な実状に一致するものと評価し、報告を行ってみたい。鳥取県は人口約60万、年間出生数約8,000の地域である。
図1 1955年から1985年までの周産期死亡率と早期新生児死亡率(全国平均)
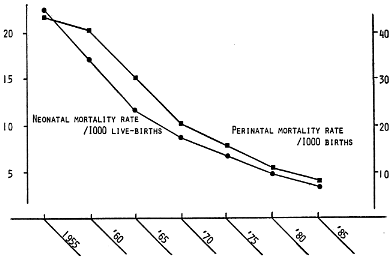
図1と同じ30年間に鳥取県内において出生した児から脳性麻痺となった児の率(出生児数当たりでの発生率)は図2のように変動をみせている。1950年代後半(第1期)、1970年代前半(第2期)と後半(第3期)、1980年代前半(第4期)と4つの時期に区分すると、各期間ごとの発生率は明らかに有意の変動を示した。なお、1960年からの11年間の資料は信頼性に欠けるところがあり分析から除外した。
図2 1956年から1985年までの鳥取県における脳性麻痺の発生率(1,000出生当り)。1960年から1971年までは資料が不明確のため省く。(発生率は2年ごとに算出している)
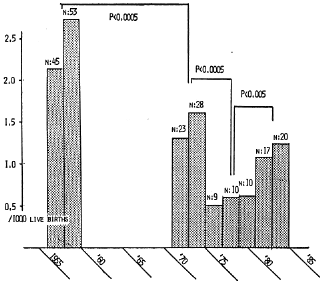
ここで分析の対象とした脳性麻痺の診断基準は、ハーグベルクらの基準や厚生省脳性麻痺研究班の定義に基づいて、受胎から新生児期までに生じた破壊性・非進行性・永続性の脳障害で、3歳までに生じた運動あるいは姿勢での障害を示す児と定義した。知能障害やてんかんの合併は当然あってよいこととしたが、重度の知能障害による運動発達遅滞は除外した。したがって、当然のことながら重症心身障害児の中にはこの分析資料に含めた児と含められなかった児がいることになった。また、この報告の目的から後期新生児期以降にあらたに発症した化膿性髄膜炎や頭蓋内出血などによる後遺症児は除外した。症例の情報は、県下のすべての公立病院小児科、未熟児センター、心身障害児施設、1歳6カ月児と3歳児健診の資料などから得て、小児神経医が複数回にわたって診察を行い確認した。また、3歳までに死亡した児についてはそれまでの所見が診断基準に満ちていると判断されたものは対象とした。全出生児の約6―7%の児が3歳までに他県に転居しているため、周産期リスクのなかった軽症脳性麻痺児のごく一部が脱落している可能性があるが、ほぼ全症例に近い症例が把握されていると考えられた。
図2にみられるように1970年後半までの脳性麻痺発生率の減少は明らかに周産期死亡率や早期新生児死亡率のそれに一致していた。すなわち1950年代後半1,000出生当り2.5の発生率が0.6以下に減少をみせた。図3はこの期間における我が国における周産期医療のおおまかな変化を重ねて図示したものである。1950年代後半から新生児にはいろいろの使用しやすい抗生物質が普及した。1960年代前半からは、全血交換が行われ重症黄疽の治療が可能となり、また、胎児管理の方法がより科学的になり帝王切開分娩が急速に増加する時代になった。1970年代前半からは翼状針が普及し、新生児体循環の管理が容易になり、ショック治療が容易にできるようになった。また、この時期から急速に普及した光線療法はこれ以降典型的な核黄疸による脳性麻痺児を療育施設から一掃した。ハイリスク新生児の病態研究の進歩とともにこのような医療技術の進歩は、結果的に多くの脳性麻痺を救ったことになる。1955年の我が国における年間出生数は約173万であり、1984年のそれは143万であるが、1955年での脳性麻痺発生率を仮に2.5/1,000とし、1984年を1.0とすれば、この30年間にこのような医療の向上がなかったな らば脳性麻痺になったであろう児は約3万3,000と計算された。すなわち、3万3,000の児が脳性麻痺の不幸から予防されたことになる。なお、1970年後半での発生率0.6を考慮すれば、この3万3,000は最低の数字であることが理解されよう。
図3 同じ期間での周産期医療の変化
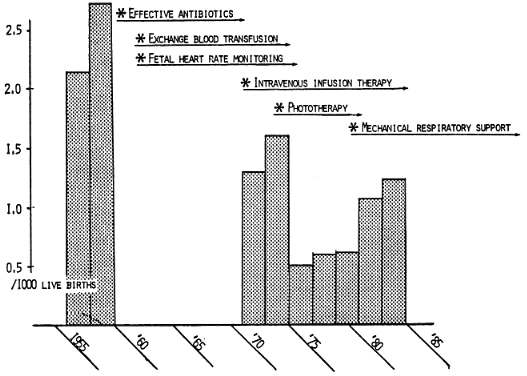
近年の脳性麻痺発生率の再増加傾向
1981年以降、脳性麻痺の発生は明らかに増加の傾向をみせている。1,000出生当り0.6以下に下がっていた発生率は1.0に上昇した。この上昇にもっとも相関している周産期医療の変化は人工換気医療の導入であろう。経験的にも従来なら死亡していると思われるハイリスク児がこの人工換気により生命をとりとめるのを目のあたりにみていると当然の帰結として脳障害を残して生存してくる症例が増えるであろうことが想像される。そして、このような変動はすでにスエーデンや、オーストラリアなどから報告がなされている。なお、この発生率の上昇に有意に関与しているのは2,500g未満の低出生体重児からの脳性麻痺であり、2,500g以上の正常出生体重児からの脳性麻痺ではなかった。この点については後に再びふれてみたい。
周産期医療の変化に伴う脳性まひの症候の変化
脳性麻痺発生率が変動した図1の4期間ごとの症例について彼らのおもな症候の変動をみたのが表1である。麻痺の広がり(quadri plegia,diplegia,hemiplegia,paraplegia,monoplegia)、麻痺の性状(spasticity,dyskinesia,others)、合併症候(精神遅滞、てんかん発作)の有無ごとにそれぞれの期間での1,000出生当りでの発生率を示している。変動として有意であったのはdyskinesiaの減少のみであった。この減少は当然のことながら全血交換と光線療法によるものである。なお、脳性麻痺にみられるいろいろな性状の特徴は、お互いにどのような類似する相関を持つのかについても検討を行っておく必要がある。多変量解析クラスター分析では、四肢麻痺は精神遅滞の重度化と難治てんかんの合併をとくに有意とした(図表省略)。このことは今後脳性麻痺の予防や療育を考える場合このグループへの注目がとくに重要であることを示唆していよう。
| Period | PeriodⅠ (1956-1959) |
PeriodⅡ (1971-1974) |
PeriodⅢ (1975-1980) |
PeriodⅣ (1981-1984) |
Total |
| No.of patients | 98 | 51 | 29 | 37 | 215 |
| No.of total live-births | 40,532 | 35,707 | 50,814 | 32,180 | 159,233 |
| Quadriplegia* | 0.716 | 0.504 | 0.197 | 0.404 | 0.440 |
| Diplegia | 0.592 | 0.420 | 0.197 | 0.373 | 0.383 |
| Hemiplegia | 0.518 | 0.224 | 0.138 | 0.280 | 0.283 |
| Paraplegia | 0.518 | 0.252 | 0.040 | 0.062 | 0.214 |
| Monoplegia | 0.074 | 0.028 | 0.000 | 0.031 | 0.031 |
| Spasticity | 1.604 | 0.980 | 0.354 | 0.932 | 0.930 |
| Dyskinesia** | 0.395 | 0.280 | 0.059 | 0.062**** | 0.195 |
| Others | 0.419 | 0.168 | 0.157 | 0.155 | 0.226 |
| w/severe MR*** | 0.568 | 0.364 | 0.138 | 0.342 | 0.339 |
| w/epilepsy | 0.543 | 0.364 | 0.197 | 0.249 | 0.246 |
| Total | 2.418 | 1.428 | 0.571 | 1.150 | 1.350 |
(Incidence per 1,000 live births)
* Quadriplegia includes double hemiplegia
** Dyskinesia includes both athetosis and tension athetosis
*** Severe MR means IQ below 50
**** P<0.05
表2に周産期医療が近代化した1971年以降での脳性麻痺117例を各麻痺群に分け、周産期症候との比較検討を行った結果を示す。脳性麻痺の病因にむすびつく症候の分析である。重複片麻痺を含む四肢麻痺グループに有意の相関をもつ項目が多くみられたが、これらの項目を総合すると病因の時間的経過に明らかな傾向が認められた。すなわち、四肢麻痺グループの脳障害は、妊娠中毒症を中心とした出生前のリスクでまず発生し、それの連続する流れとして出生時の無(低)酸素症を生み、さらに新生児期での異常徴候を引き起こしてきていると理解された。一方、対麻痺、両麻痺グループでは出生時体重、すなわち低出生体重を中心としていた。彼らは、一部が新生児期でのリスクと他の一部が多胎など出生前でのリスクをもっていた。そして、片麻痺グループでは相関する因子はみつからなかった。これからの脳性麻痺の発生の予防を考えるとき、この出生前合併症の防止は重要な解決すべき問題として理解されるべきであろう。
| QUADRIPLEGIA/DOUBLE HEMIPLEGIA | DIPLEGIA | PARAPLEGIA | HEMIPLEGIA | ||
| PREVIOUS FAILED PREGNANCY | |||||
| MULTIGRAVID MOTHER | * | ||||
| MOTHER AGED>35 | |||||
| TOXEMIA DURING PREGNANCY | ** | ||||
| CAESAREAN DELIVERY | * | ||||
| APGAR<7 | ** | * | |||
| BIRTHWEIGHT | <1999 | * | * | ||
| <2499 | |||||
| 2500≦ | |||||
| SMALL FOR DATE | * | ||||
| RESPIRATORY DISEASE | * | * | * | * | |
| MECHANICAL RESPIRATION | * | ||||
| PHOTOTHERAPY | * | ||||
| NEONATAL CONVULSION | ** | ||||
| N:37 | N:39 | N:16 | N:25 | ||
*<0.05 **<0.01
低出生体重児からの脳性麻痺の問題
すでに欧米諸国からの報告にもみられるとおり、脳性麻痺における低出生体重児の問題は、脳性麻痺を考えるときに絶対に避けて通れない問題となった。図4に、1971年からの14年間における低出生体重児からの脳性麻痺例と早期新生児死亡例を出生体重2,500g未満の全出生児を100として比率分布で表示した。図1と同じ期間ごとにみると、3期間の間に脳性麻痺の発生頻度には有意の差がみられた。同じ期間での2,500g以上の児からの脳性麻痺発生率には有意差がみられていないので、この有意さが、全体の有意差につながっている。1975年以降の周産期医療の進歩は明らかに低出生体重児において脳障害の発症に変化をもたらしていると結論づけられる。一方、このような脳性麻痺の減少と再増加の変動にも関わらず早期新生児死亡率は一定して減少を示していた。周産期医療の進歩は死亡率に関する限り着実にプラスの効果を挙げていると評価できよう。このような変化は外国においても類似するところがあり、スエーデンからの報告にも同じ傾向の報告をみることができる。我々の図4と異なる点は、脳性麻痺での増加幅が死亡率の減少カーブより少なく両者のトータルはなおプラスに、すなわち 正常児が増加している方向に向いている点であった。表3に生下時体重を500gごとにみた脳性麻痺の発生率を示す。2,000g以下での低出生体重児における脳性麻痺の発生率は一般頻度を仮に1,000出生当り1とした場合、約40倍の危険率となっている。幸い?なことに2,000g以下の低出生体重児の絶対数が少ないため、全体での脳性麻痺の増加をこれ以上に高めていくことにはならないと考えられるが、低出生体重児では生下時体重2,000g以下の児に注目が向けられるべきであろう。
図4 1971年から2年ごと14年間の低出生体重児の予後(新生児死亡、出存、脳性麻痺について%算出)
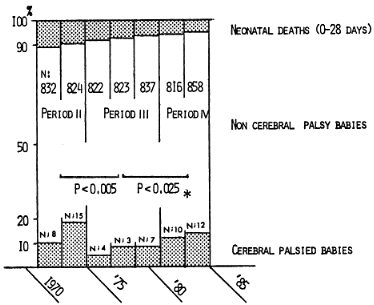
| BIRTHWEIGHT(G) | -1499 | 1500-1999 | 2000-2499 | 2500- |
| NO.OF CP | 20 | 22 | 17 | 58 |
| TOTAL LIVE-BIRTHS | 441 | 561 | 3184 | 112,947 |
| INCIDENCE/1000 | 45.45 | 39.22 | 5.34 | 0.51 |
| RISK OF CP | 1:22 | 1:26 | 1:189 | 1:2000 |
(TOTTORI COHORT 1971-’84)
表4は、この低出生体重児脳性麻痺を各麻痺グループごとに分けた場合の周産期リスク情報の比較である。四肢麻痺グループの妊娠中毒症を除いてすべて有意差なしか新生児リスクの重複に絞られていた。すなわち、このグループの脳性麻痺の予防では如何に低出生体重児の出生を予防するか、如何に新生児ケアでのリスクの重複を少なくさせるかにかかっているといってもよいであろう。
| QUADRIPLEGIA/DOUBLE HEMIPLEGIA | DIPLEGIA | PARAPLEGIA | HEMIPLEGIA | ||
| MULTIGRAVID MOTHER | |||||
| TOXEMIA DURING PREGNANCY | * | ||||
| APGAR<7 | |||||
| RESPIRATORY DISEASE | |||||
| MECHANICAL RESPIRATION | |||||
| PHOTOTHERAPY | |||||
| NEONATAL CONVULSION | |||||
| NO.OF NEONATAL SIGN | 0-1 | ||||
| 2 | * | ||||
| >3 | ** | * | |||
| N:16 | N:24 | N:11 | N:8 | ||
*<0.05 **<0.01
低出生体重児からの脳性麻痺の病態はさきの正常出生体重児脳性麻痺での病態発症とはその内容を大きく異にしている。これからの脳性麻痺発生予防対策は正常出生体重児への出生前対策と低出生体重児への出生前および新生児対策の両面作戦が求められているといえよう。
(この報告は、第4回西太平洋州脳性麻痺会議に“Epidemiological analysis of cerebral palsy in Japan”として発表した。なお、本論文の原著はNeuroepidemiology Vol.8,1989に印刷中である。参考論文は紙面の制限上割愛した。原著を参照されたい。最後に、この発表の機会を与えていただいた会長高橋孝文先生に深謝する。この研究は厚生省心身障害研究費の援助を受けた。)
*鳥取大学医学部脳神経小児科
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1989年3月(第60号)43頁~48頁


