特集/高齢期とリハビリテーション
高齢脊髄損傷者
安藤徳彦*
長谷川良雄*
水落和也*
林輝明*
1.高齢脊髄損傷者の増加傾向
高齢脊髄損傷の増加には二つの側面がある。一つは高齢になって脊髄損傷に受傷する患者の増加傾向であり、もうひとつは脊髄損傷者が高齢化する問題である。一般に脊髄損傷の原因は、過去には落盤や転落などの産業災害、最近では交通事故が多いとされている。確かにオートバイを中心に交通事故による青壮年層の脊髄損傷患者が非常に多いことは欧米でも指摘されており、日本もその傾向が顕著である。最近わが国で報告された労災指定病院を調査対象機関とする脊髄損傷の発生統計調査では、10―20歳代では交通事故とスポーツ事故の多いことが報告されているが、その一方で、高齢受傷患者が多く50歳以上が51.7%を占めるという事実も示されている。健常者の高齢人口の増加にともなって、高齢者特有の変形性脊椎症の罹患率も増加し、この人々が転倒などの比較的軽微な外力で脊髄損傷になる場合の多いことが、最近では指摘され始めている。
わが国の全国的規模の詳細な疫学的統計調査は先の労災指定病院を調査対象機関とするものがあるが、厚生省の全国身体障害者の推計調査によると、全国の脊髄損傷者は6万6,000人、その年齢構成は、50歳代を中心に高齢者に集中している(図―1)。米国での調査結果では脊髄損傷患者は若年者に多いとされているが、労災指定病院と厚生省の調査結果はこれと矛盾する。そこでこの事実を確認する目的で、1986年度の神奈川県身体障害者更生相談所所管区域(横浜・川崎市を除く郡市町村部、人口330万人)の脊髄損傷患者に対する身体障害者手帳の交付状況を調査した。外傷性脊髄損傷患者の手帳交付件数は52件で、これを年齢別にみると、20歳代が27%を占め、続いて60、50歳代となって(図―2)、高齢者でもかなりの多発傾向を認める。麻痺程度は若年者では完全損傷が、高齢者では不全損傷が多く、特に60歳以上では、全例が不全損傷である。損傷高位をみると40、50、60歳代では頸髄損傷が比較的多数を占める。外傷性脊髄損傷に、脊椎症を含む脊椎・脊髄疾病を加えた脊髄障害者の手帳交付件数は145件で、その年齢構成は(図―3)に示すとおリ高齢者に集中しており、厚生省の全国推計調査と一致する。
図1.脊損年齢構成(厚生省)
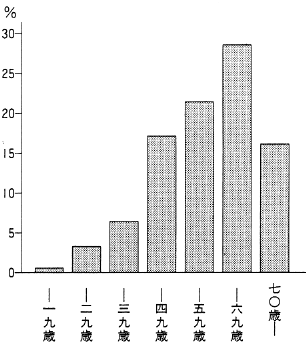
図2.年齢構成と受傷原因
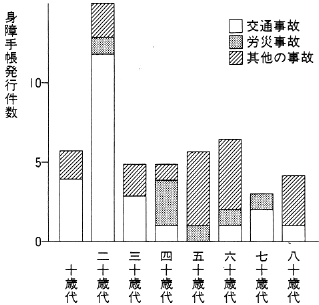
神奈川県障害者更生相談所 1986年度
図3.脊髄障害の年齢と原因
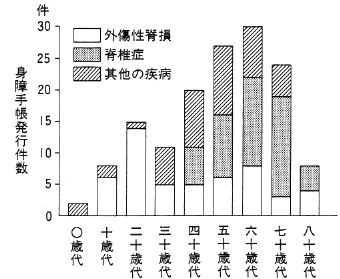
神奈川県障害者更生相談所 1986年度
一方、脊髄損傷に対するリハ医療の普及度が向上するにつれて、受傷早期の死亡率が激減し、脊髄損傷者の生命的予後が飛躍的に延長し、高齢脊髄損傷者の健康管理上の問題が注目されるようになってきている。
Brackenは同調査で年齢別の人口に対する発生頻度を紹介し、最多発生年齢は20―24歳でこの世代の人口100万人に対して年間発生数は68人であるのに対して、65歳以上も人口100万対年間55人で、しかも老人の受傷後死亡率が高いことを報告している。一方、Eisenbergは受傷後高齢化した脊髄損傷者が増加しており、医学的・社会福祉的対策が必要だと述べている。
以上の結果から言えることは、外傷性脊髄損傷は青壮年層に多発する傾向が認められるが、その一方で、高齢の外傷性・非外傷性頸髄損傷患者も非常に多数発生しており、これに対する医療上の対策が必要であることを示している。すなわち、脊髄損傷はもはや特定の人々の特定な疾患や障害ではなく、脳卒中や心臓疾患と同様にすべての人が罹患する確率が高いすべての人々の問題であることを考慮して対策が考えられるべきである。
2.脊髄損傷患者の死亡原因と平均余命
Stoke Mandeville病院のTribeは1945年からの17年間の調査を報告している。それによると、表―1―上段に示すとおりで、脊髄損傷受傷後2ヵ月までに死亡した症例は16人で、8人が呼吸不全、6人が肺塞栓であり、また受傷後2ヵ月以上経過して死亡する例が71人とかなり多く、その3分の2近くが腎不全によっていたと報告している。ところが、同じ病院から出された最近11年間の報告(Ravochandran)によると、表―1―下段にみるように死亡例全体が激減しており、166人の頸髄損傷患者中、3ヵ月の死亡例は4人で、呼吸不全によるもののみであったという。
|
1945‐1962 Stoke Mandeville病院(Tribe) |
|
| ・受傷後2カ月以内死亡 | 16人 |
| 呼吸不全 | 8人 |
| 肺塞栓 | 6人 |
| その他 | 2人 |
| ・受傷後2カ月以後死亡 | 71人 |
| 腎不全 | 53人 |
| 呼吸不全 | 4人 |
| その他 | 14人 |
| 1970‐1981 Stoke Mandeville病院(Ravichandran) | |
| ・受傷後3カ月以内死亡 | 4人 |
| 呼吸停止 | 1人 |
| 呼吸器感染 | 2人 |
| 肺塞栓 | 1人 |
| ・受傷後3カ月以後死亡 | 16人 |
| 腎不全 | 1人 |
| その他 | 15人 |
一方、トロント大学のGeisler等は脊髄損傷に対して、1945年以後35年間の調査対象総数1983年について、4回にわたる調査を行って、各々の調査時点での平均余命を表―2のように報告している。完全・不全、四肢・対麻痺のいずれもが、すべての世代で1980年の調査では、それ以前の調査結果と比較して明らかに平均余命が延長しており、平均寿命で示すと完全四肢麻痺では50―59歳、完全対麻痺では60―65歳である。また、死因を多い順序からみると、心循環器が19.6%、腎疾患15.3%、呼吸器が13.9%となっているが、以前と比較すると腎疾患が減少し、自殺や循環器疾患が増大していると述べている。
| 受傷時年齢 | 四肢麻痺 | 対麻痺 | ||||||
| '58 | '66 | '73 | '80 | '58 | '66 | '73 | '80 | |
| 20歳 | 15 | 21 | 21 | 30 | 27 | 34 | 32 | 40 |
| 30歳 | 11 | 16 | 16 | 23 | 20 | 27 | 25 | 32 |
| 40歳 | 7 | 10 | 10 | 15 | 14 | 19 | 19 | 23 |
| 50歳 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 15 |
Minnesota州のMayo ClinicのGriffinは最近5年間の年間発生率54.8/100万人の中で、生存率は受傷後1時間以内が64%で、受傷直後の死亡率が高くその大多数は受傷現場で死亡しているが、受傷初日に救命できたものの10年間生存率は77%だと報告している。
この事実は脊髄損傷に対する受傷直後の救命処置とその後のリハビリテーション医療の体制が確立すれば、その生存年数は健康者とほとんど同じ余命になることを示しており、逆にそのどちらが欠如しても、生存を脅かす原因になる可能性も示している。
我が国における同様の調査はきわめて乏しいが、東京都神経科学研究所の松井が全国脊髄損傷連合会の加入者を対象に郵送調査によって、生存年数を調査している。結果は麻痺程度を区別していないことと、統計処理の方法が異なっているので、正確な平均余命を紹介できないが、図―4に見るとおりGeislerの報告(表―2)に比較すると生存年数は非常に短い。この報告でみる限り、日本の脊損患者の平均余命は先進諸外国に比較して改善すべき余地が大きく、我が国のリハビリテーション医療の普及が強く望まれる段階にあるようである。
図4.脊損発生年齢別の平均生存年数
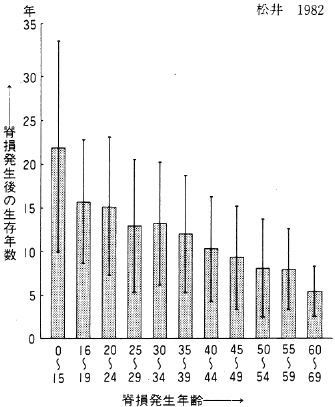
3.高齢脊髄損傷患者の訓練プログラムと医学的諸問題および訓練成果
(1)訓練プログラム
大隈は急性期関節可動域・筋力維持訓練や呼吸器合併症予防、血圧・体温調節管理などの必要性を説いている。高齢脊髄損傷患者では特に立位・坐位での耐久性障害がつよく、これは腹部内臓器に大量にプールされた血流の坐位分布に働く血管運動性調節の不備が重要な原因だとし、さらに高齢者の運動負荷による心肺系の反応は最大下の負荷でも若年者と異なるので、個々の耐久性や医学的リスクを把握して十分な休息をとりながら訓練を実施すべきだと述べている。
(2)医学的諸問題
当院の高齢脊髄損傷患者の現況は過去に水落が報告した。当院10年間の60歳以上の入院脊髄損傷患者は機能訓練目的54名に対し、医学的治療目的が85名であった。
二次的合併症でも最も多いのは褥瘡で51名であった。41名に外科的治療が施行されていたが、残り10名は全身状態、原疾患など健康管理上の阻害因子で積極的治療が不可能なものであった。泌尿器合併症が27名で感染症が11名、結石症が13名を占めた。その他の合併症ではせん妄、抑欝などの精神科的問題が23名であったが、当院に精神科が存在することがこの患者数の多い要因と考えられる。高血圧・糖尿病・新疾患などの成人病が15名にみられた。
Eisenbergは高齢脊髄患者の長期ケアを一定のべッド数を確保して組織的に行う計画を述べており、Fischerもリハ病院に高齢者を対象とする治療グループを設けて心理社会的問題に対処することを述べている。わが国もこのような体制が必要な時期を迎えているようである。
(3)高齢脊髄不全損傷患者の訓練成果
次に、高齢者に多い脊髄不全損傷患者の目標達成について成果を紹介する。対象は1978年以後の9年間に当院にリハビリテーション目的に入院した60歳以上の22名である。60歳代が18名、70歳代が4名、男性20名、女性2名、横断型損傷が9名、中心型損傷が10名、ブラウンセカール型が1名、その他2名。受傷後当院入院までの平均期間は3.8±3.3ヵ月、入院期間は3.8±2.0ヵ月。
結果を図―5に示す。階段昇降と平地歩行、杖歩行が可能となったものが13名存在し、この目標達成期は受傷後1年であった。しかし一方、寝返りも不可能に終わった7名を含めて、ベッド上生活に留まったものが9名存在する。
図5.移動能力の受傷後経過
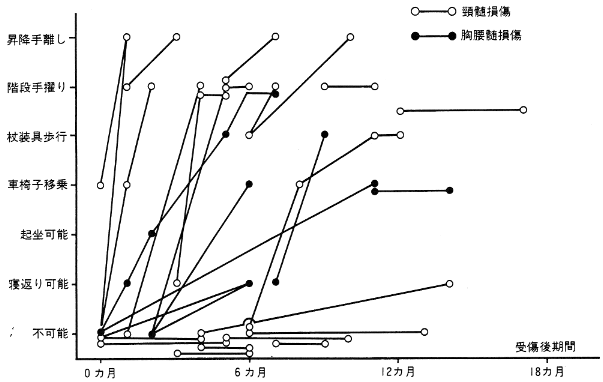
高齢頸髄損傷に対するリハビリテーションは訓練を阻害する因子が既に内在しており、合併症も発生しやすい。不全損傷について示したように、訓練成果は以前に報告した青壮年層の成果と比較して長期間を要し、また、低い能力に留まるものが多い。この原因として関節拘縮が高い相関をもつこと、高齢者では筋力回復の訓練成果が得られにくいことも考えられた。
4.社会的諸問題
高齢脊損者の社会的諸問題については長谷川他の調査がある。調査対象は1889年以後の2年間の当院の外来・入院脊髄損傷患者で60歳以上の118名、有効回答数85名、回収率72%、回答者平均66.0歳、発症後平均経過期間19.4年であった。以下の回答者数は複数回答を許している。
(1)所得・住居・福祉機器・日常の過ごし方
年金受給者が82.4%を占めた。年金以外の所得は不動産11名、就労8名、無収入8名であった。持ち家63名、公営住宅7名、借家9名の中で、全面改築14名、部分改造41名、無改造17名は要介助者で家族の介護を前提にしていると思われた。改造箇所は障害程度と関係し、四肢麻痺では居室が多く、対麻痺ではトイレ・浴室・玄関が多かった。装具は車椅子使用71名、シャワーチェアー使用15名、手離し歩行が6名、ホイスト使用4名、リフター使用2名、寝具は電動ギャッチベッド7名、手動ギャッチベッド19名、その他のべッド39名だった。
45名がテレビラジオで日中を過ごし、家事14名、自営業10名を含めて外出の機会が少ないと答え、社会的活動をしているものは17名に過ぎなかった。
(2)介助・介助者と福祉サービス
日常生活動作に介助をするものは52名であった。介助者の80%が配偶者で、その平均年齢は63.7歳であった。介助者が困っていることでは35名が外出しにくいと述べ、肉体的疲労が25名、精神的疲労が15名であった。介助は家族のみで行っているものが55名で、公的サービスを利用しているものは16名に過ぎなかった。なお、調査対象で単身者が12名おり、在宅者が8名だったがホームヘルパー利用者は4名のみであった。
福祉サービスとして要望される内容は一時的入所施設が最も多く33名、福祉情報が22名、訪問リハが21名、長期入所施設は比較的少数で19名、年金手当が16名、移送サービスと身障住宅が13名であった。
このことは多くの人々が今後も在宅生活を続けて、問題が生じた時のみ短期間の施設入所を希望しており、基本的には長期入所を希望していないことを示している。しかし介護者に対する時間的拘束が大きく、彼女達が高齢化して肉体的にも精神的にも疲労している事実を考えると、必要なものは介助方法の指導ではなく、介護力そのものであることが容易に理解される。介護を実践するものが頻回に家庭に派遣されないと高齢障害者の在宅生活は成立しないことを示している。
5.まとめ
以上の結果を箇条書きにまとめる。
(1)脊髄損傷は特定の人の特定の問題ではなく、脳卒中や心疾患と同様に、高齢化社会のすべての人の問題である。
(2)受傷者に対するリハビリテーションは困難な側面が多く、しかも医療体制としての普及度合は不十分である。
(3)在宅高齢脊髄損傷者には介護を要するものが多く、介護力は貧困な状況であり、在宅生活を保証するためには介護力そのものの支援が必要である。
引用文献 略
*神奈川リハビリテーション病院
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1992年10月(第73号)9頁~14頁
