〔付〕1 身体(肢体);身体論等
-心理劇的演出法によるアプローチ-
《その1》
「ここに私の身体(からだ)がある」ということ。(松村講師Mは中央の円台--聴(観)衆が円形にとりまいてい--上に立ち、補助者Aをよぶ)
M「はい。『ここに私の身体がある』と言ってください。ぼくの代わりに言ってください」(AはMに代わって円台の上に立ち)
A「ここに私の身体がある」
そう言いますと、まわりの人が「あなたの身体がそこにある」とか、「あなたの身体がそこにあるのが私にみえる」とか、それから「私にだけでなく私たちにあなたの身体がみえている」というように感じています。
私は、自分の影をそこに残してきていま、まわりの人、みなさんと共に--
Aさんに影になってもらって、ぼくはここにいて解説をしているわけです。そして、次のようにも言えます。「私たちにみえているから、たしかにあなたの身体がそこにある」「私だけでなく、ほかの人たちにもそうみえる」「そうみえていると感じられて、あなたの身体はそこにある」というように、あるいは「私たちで感じる、私たちで認めあえるあなたの身体がそこにある」
ここで、「たしかに」とか「みえる」「みえている」とか「感じる」「認めあえる」というように、とらえることばを使いました。
《その2》
(Mは円台の上にAをよぶ)
M「ぼくの影をそこに置きます。『ここに私の身体がある』と言って下さい」
A「ここに私の身体がある」
M「『ここに私の身体がある、と私が言う』まで言ってください」
A「ここに私の身体がある、と私が言う」。はい、ここでいま私たちに見えているから、たしかにあなたの身体はそこにある。そう言えるのは、私たちの身体のどこかが働いてそう言えるのである。目がはたらくとか感じるとか、とにかく私たちの身体がはたらいてそう言えるのである。それだけではない。あなたの身体がそこにあるからだ。私たちの身体もここにあるからだ。あなたの身体がそこに、私たちの身体がここにあるからだ。あなたの身体にとっては、あなたの身体のあるここに、そして、私たちの身体は、あなたの身体にとってそこにあるからだ。あなたの身体も、私たちの身体もこの場所にあるからだ。この場所にというこの場所は、あなたの身体も私たちの身体もそれぞれに場所を占めながらつながっている場所である。この場所はあなたの身体のある場所、私たちの私たちひとりひとりの身体のある場所、身体をたしあわせた場所をこえてつながっている。私の身体の占めている場所とあなたの身体の占めている場所との間がつながっている場所である。私の身体がはたらき、あなたの身体がはたらきながらある。はたらき、はたらきかけられながらあるこの場所である。
《その3》
この場所を私が見ていると、私の身体があるこの場所、この私の身体が占めている場所で、あなたの占めている場所をみつめていると、今度は、私の場所はここのここというように段々せばまって、“私の立っているこの場所”“あなたの立っている、あるいは座っている場所”となり、場所と場所との間が離れてくる。間がうすくなる。力が弱まる。そうなると、あなたの身体はあなたの場所にあるあなたの身体であって、私の身体ではないというみえ方、感じ方が強まってくる。そして、私の身体が占めているこの場所にある私の身体、その身体をみつめることのできる身体、この私の身体においてはたらいている私に気づいてくる。この私は、私の身体においてはたらいており、身体からきり離せないのに、身体と私とが離れてくる。間がうすまってくる。さきほどの、人と人との関係の中で、自分の場所をみつめはじめると、場所のつながりがうすくなってくるというのとかなり対応して、あるいは似て、自分をみつめはじめると、自分の身体が占めているこの場所にある私の身体、この身体をみつめることのできる私、この私の身体においてはたらいている私、に気づいてくる。この私は、私の身体 においてはたらいており、身体からきり離せないのに、身体と私とが離れてくる。間がうすまってくる。そうなると、かけがえのない私がある、この私だけがあるとも感じられてくる。
そうなってきても、しかし、私とはきり離せない私の身体があり、私の身体とははきり離せない場所があり、その場所はあなたときり離せない場所であり、あなたの身体も私の身体もある場所であり、あなたの身体のはたらきと私の身体のはたらきとがあってつながっている場所である。そのことを私たちは認めあうことができ、あなたの身体がそこにあることを認めたり、感じたりするのである。
《その4》
目のきかない人、あるいは目も耳もきかない人、目も耳も口もきかない人、そういう人と人との場合では、たとえば、こことかそことかの感じ、近さ、あるいは近接における感じ、さわる、さわられることによって感じる同じさ、類同における感じに程度のちがいがめだつことがあっても、根源的には変わりがない。
人間は、自分の感じ、人とのふれあい、物とのつながりがあることにおいて人間である。自己と人と物とがかかわりあいながら、相互にかかわりながら存在する、接在共存する全体、その全体状況、自己と人と物とがはたらきあいながらある状況において、人間は人間である。
《その5》
自分自身の中でとらえられる身体。手が身体かなと思えることもあれば、自分の手で自分の手をこすると自分自身の中から担っている身体もあると感じられる。その感じは自分にしかわからないところがある。それは内在している身体といえる。
次に内接している身体。それは、自分でながめながら、ながめている自分もあって、だんだんはっきりと育っていくような身体。次に接在している身体は、自分が身体にはたらきかけて、身体もまた自分も育つというような身体、そのことに人も参加できるような、体育における、人の性格形成が可能であるところに成立しているような身体。外接している身体は、手を見ていると、自分の手かと思える、それは人が見ている手でもあるというように、自分の外的なかかわり方に位置づいているような身体。外在している身体は、人にまかせている自分の身体。あきらめて手術をうけているかかわり方において成立しているような身体。
どこから出発することが、5つの身体のどれにも到れるかというと、それは接在からである。
物に即してのべると、外に食べ物があって(外在)、それをガリガリ食べる(外接)、からだの中に入ってはたらき、はたらきかけられて(接在)、身体になり、身体から出ていくものがうまれる。いらないもの、排泄物になって外へ出ていく(外接、外在)。
《その6》
ここでの基本的立場(かかわり方の科学、関係論)からの身体観(身体論)と幾つかの諸他の立場からのその特徴を1表にしたものが表3-4である*)。 表3-4 心身-元的身体論
| フロイト(ユング) | ビンスワンガー | メルロ=ポンティ | 市川 浩 | 松村 康平 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立場 | 精神病理学-深層心理学- | 精神病理学 | 現象学 | 現象学(現実存在論) | 関係学 |
| (主に捉えられている)位相 | 精神(ex.リビドー)が、肉体を操縦する(かのように考えられる)位相 | 身体的状態(ex.睡眠、覚醒)が、意識の状態を規定する(ように考えられる)位相 | (物が同時に捉えられながら)(他)人と自己との関係において、自己に焦点があてられている(と考えられる)位相、(他人の心と自分の心を両極において、そのあいだに自他の身体を抽入して位相) | -現象としての身体- 主体としての身体 客体としての身体 私にとっての私の対他身体 他者の身体 |
自己との関係における身体 イ)(自己の関係状況に)内在している身体 ロ)(自己と)内接している身体 ハ)(自己と)接在している身体 ニ)(自己と)外接している身体 ホ)(自己とは)外在しでいる身体 |
| 人との関係における身体 イ)(人との関係状況に)内在している身体 ロ)(人と)内接している身体 ハ)(人と)接在している身体 ニ)(人と)外接している身体 ホ)(人と)外在している身体 |
|||||
| 物との関係における身体 イ)(物との関係状況に)内在している身体 ロ)(物と)内接している身体 ハ)(物と)接在している身体 ニ)(物と)外接している身体 ホ)(物に)外在している身体 |
|||||
| 場面との関係における身体 イ)自己身体的役割をとっている身体 ロ)心理行為的役割をとっている身体 ハ)対人関係的役割をとっている身体 ニ)場面構成的役割をとっている身体 ホ)社会地位的役割をとっている身体 |
|||||
| Coexis-tence | 錯綜体としての身体 | (4つの位相を)統合する身体 | |||
| 位相こおける関係単位 | 自己-(人) |
自己-(人) |
自己-人-(物)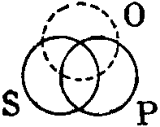 |
自己-人-(物)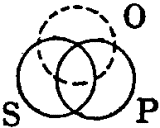 |
自己-人-物、場面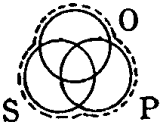 |
| 関係構造(関係単位間、位相間) | 二者的一者関係 | 二者的一者関係 | 三者的二者関係 | 三者的一者関係(または二者関係) | 三者関係的三者関係 |

|

|
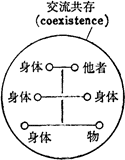
|
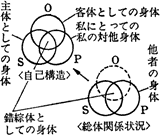
|
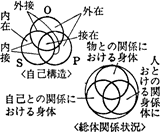
|
|
| 関係分化構造 | 関係単位(構成要素間関係)における身体 | 関係における身体 | 関係におけるかかわり方を担う身体 | ||
| 位方性 | 体系性(現象性) | 志向性 | |||
| 歴史性 | 体系性 | ||||
| 歴史性 | |||||
| 〈一者過去性〉 〈二者現在性〉 〈三者未来性〉 | |||||
表の作製(1979年1月)千あけみ(「仮面の技法に関する研究一能と心理劇(1)」お茶の水女子大学大学院・家政学研究科児童専攻修士論文に掲載のもの)
*)松村康平(監修):「心理現象としての身体」『看護と心理学』(日吉佳代子他)
《その1》
人間の発達とは、自己と人と物との共存が可能な接在的かかわり方が展開する接在共存状況が、あきらかになってくる、あるいはあらわれてくる、顕在化する方向へのかかわり方の変化。関係的な存在のしかたの接在共存への統合的変化である。これまで1のその1からその5までにのべてきたようなことも、接在共存の「全体状況」があることにおいての自己であり身体である。その自己においては、全体状況が段々はっきりしていく。自己も人も物もかかわりながらあることがはっきりしてくる。それが発達である。
人間の発達ということが、しばしば、その人の発達というふうに個人に焦点をあてていわれる場合があり、特に自己に関して、成長とか発達がしばしば問題とされる。その自己に関していうならば、発達とは、自己において、接在共存状況が顕在化すること。接在共存状況への自己における関係の変化のことである。
人生経験を豊かにしている人たちの、のべていることやしていることをよくみていると、それは、全体の状況で、自己と人と物が同時にかかわりながら存在しているという、そういうことを意識的に、あるいは容易に気づけるような状態で、あるいはほとんど気づかれないような状態であっても自分の体験としてはそれがえられている。そういう状態に近づいていくこと、それが発達であり、そういう接在共存状況への自己における関係の変化なのである。
《その2》
関係統合的存在としての自己構造について。ここで、自己における関係の変化、自己と身体との関係についてもう少し詳しく述べる。
根源的には、自己と人と物とかかわりあっている、それを今度は自己の場合には、![]() S(自己)についてなのである。これはO(物)やP(人)ときり離されていないSで、結局、自己とはこのように
S(自己)についてなのである。これはO(物)やP(人)ときり離されていないSで、結局、自己とはこのように![]() 図示できる。その自己の自己的部分、これ
図示できる。その自己の自己的部分、これ![]() が、中央の部分に対応する自己が自己の核心であり、これに関連して、①自己の自己的自己、②自己の自己的人、③自己の人的自己、④自己の自己的物、⑤自己の物的自己、⑥自己の人的物あるいは物的人、のように分化し構造化する。基本的な状況で、自己、人、物が接在共存しているのに対応して、自己においてこのように構造化する。これを自己における発達という。
が、中央の部分に対応する自己が自己の核心であり、これに関連して、①自己の自己的自己、②自己の自己的人、③自己の人的自己、④自己の自己的物、⑤自己の物的自己、⑥自己の人的物あるいは物的人、のように分化し構造化する。基本的な状況で、自己、人、物が接在共存しているのに対応して、自己においてこのように構造化する。これを自己における発達という。
このこと(発達)がはっきりするため(促進する)にはどうしたらよいかというと、自己的自己と人的自己と物的自己がはたらきながらの、自己における変化が発達なのであって、その変化をとらえること、創ること。このことを明確化するためには、はたらきかけ、はたらきかけられながらあること。それをはっきりさせるために使われる接近の方法自身が、はたらきかけ、はたらきかけられることを特色としている方法であることが大切であって、それにはいわゆる行為法、そのひとつとしての心理劇を活用することが有効である。
自分だけで考えている場合には、![]() こういうものが、段々
こういうものが、段々![]() このようにこのSの中にとり入れられてしまう。たとえば、子どもの発達のことを考えているといっても、発達を考えている私が強調されると、そういう方法をとり始める。
このようにこのSの中にとり入れられてしまう。たとえば、子どもの発達のことを考えているといっても、発達を考えている私が強調されると、そういう方法をとり始める。
あるいは、観察法で、自分がむこうにいる人をとらえるようなかかわり方の中でその人の発達を問題にすると、自己と人と物とが関係しながらあることにおける発達であるのに、自分が見てとらえることのできる発達になってしまったり、自分の中だけで展開することを手がかりにする発達論になってしまうおそれがある。
発達をとらえる重要なひとつの方法として、仲間と場面をつくり、自己構造に対応するように、役割をとってふるまう人と共にふるまう方法がある。つまり、自己的自己になってふるまう人、かけがえのない自分自身に対応する役割をとってふるまう人と、自己的人になってふるまう人--これは自己に近い人、お母さんとか恋人とか、それから、もう少し遠い知っている人、人的自己に対応するようにふるまう人といったように。物の方も、自分が非常に好きなもの、ちょっとでも他の人がふれると気になるようなそういう物であるかもしれない、自己的物、それから、もう少し遠い自分自身の物、物的自己、自分の物であっても自分がながめていてそうしていて別に気にならないような物に対応してふるまう人、それから、ほかの人が何かしても、それはほかの人がそうしているのだと自分にとらえられるそうした人的な物、あるいは物的な人の自己領域に対応してふるまう人などの役割をとって、自分たちでふるまう。動いてふるまって考える、研究する。そういうふるまいの中で訓練をして、広がりの中で発達をとらえられるような人に育つこと。そういう人、研究者もそういう人として研究をすすめることが、重要である。
《その3》
発達のプロセスにおける役割の交代について。役割の交代をしながら発達がすすんでいくということ。
見るという役割をとっている時には、見られているという役割もまたとっている。しゃべるのと聞くのとの役割が交代する。それらは、人と人との関係においてで、その時に音のような、物との関係で、低まったり高まったり、調子が変化することのなかで、その変化をとらえながら聞いたり話したりするという役割を全体状況でとりながらふるまっているのである。そのような役割がとられながら成長していく。そういう役割は、かかわり方に対応させていうと、自己身体的役割、心理行為的役割、人間(対人)関係的役割、場面構成的役割、社会地位的役割、この5つがかかわり合い、どれかが主としてとられて、同時にもとられながら、発達がすすんでいく。
《その4》
自己、人、物の接在共存状況が、人間の根源状況である。
[実習] 3人1組の心理劇
Mその1「3人1組になってください」
Mその2「ひとりの人は目がきかない。ひとりは耳がきかない。ひとりは口がきかない。そういう3人がつながりをつけるということをしてみてください」
Mその3「役割を交代してください」
Mその4「もう一度役割を交代して、どこかへ動いていって、他のグループとつながりをつけてください。
《その5》
最近の発達研究の動向をみると、たとえば、物を支配、物に対決するということがはっきりしていて、発達の転換を、接在状況における変化、発展としてとらえることが十分になされていないものがある。他方、現象学的な動向のものでは、自己をはっきりさせる発達の方向の流れが強く、接在共存状況からのとらえ方が十分にはなされていない。しかし、どの立場も、子どもとの活動にとりくむことが重要とされるようになって、それは、ここでいっている接在共存状況活動であって、その活動の発展を志向するようになってきていることにおいて、それらの立場からの主張、発達観もまた、ここでのものに近いものになってきているということを感じながら、ここで話している。
《その1》
一般に、発達的課題とかそういうふうにいわれている場合に、しばしば、発達的課題があるというようにとらえられている。また、子どもの発達的可能性を発見し、促進することととらえられている場合もある。それは、そのようにとらえる人が外接していてである。
外接してはいても、外接しながら、観察している人の位置とか、気持ちとか、そういうものが変化している。外接しながら動いている。向こうの活動に即して、こちらの活動も変化している。それは、人との関係、物との関係で、外接的なかかわり方をしていても、そこにかかわっている自己において、内接-自分自身の活動を発展させていたり、あるいは、働きかけたり、変化をお互いにつくり出してはいなくても、自己の世界においては接在していることもある。自分の在り方なり考え方を考えながら、その方には、また今考えたことに働きかげながら、自分も変わっていくという自己における接在的なかかわり方が成立している場合である。
そういうことが、どうしてできるかというと、たとえば、子どもがいて、私がいて、子どもとまともに向かいあったりする。そうすると、子どもの自己とか、あるいは人との関係が非常に強烈になってきて、物の在ることがおとされたりする。ところが物といっしょにあるということに気づいてふるまえると、直接子どもに向かわなくてもつながっていることの体験が成立する。
《その2》
私がいて、お母さんと子どもがいて、お母さんと私と話をしていると子どもが動揺する。それには、そこに3人でいながら2人で話すことにおいて、たとえば子どもが不安を感じている。そういう不安というのは、もともとかかわりながらある、接在共存しているあり方がそこにあるのに、そのあり方を発展させないではばんでいる、おとなが。そういうふうなところで子どもが不安になったりすることが出てくる。その場合に、子どもが、自分自身の世界をつくって現実のその場の人との関係とか、物との関係をその中にとり入れる状況をつくらないでいれば、一応は安心安定できる、不安定な安定がでてくる。が、それでは現実の生活はできない。そういう状況に子どもをおとなが追いこんでしまっている場合にどうするか。そこに接在しているもの、なお接在してあるもの、たとえばその場面での子どももおとなも共有しているもの、共有できるもの、つまり、子どももおとなもそこにいる足の下の床(ゆか)が動くとか、風が吹いてきて、そういう物に子どももおとなもいっしょに出会う。そういう物、物の変化に出会うと、こんどは自己にとりいれきれないし、とりいれている物との関係だけでは「物」との関係を発展させることが困難である、その困難が体験される。その状況において「人」が参加して、その人が、自己と人と物との関係を転換させるように動く。すると、いま、自己だけでいた、自分の世界にとじこもろうとしている子どもが接在共存している状況にあると、接在共存状況での活動での体験をして、接在共存的な体験をさらに発展するようなふるまい方をその次にしていく、そうなるようにしていく。関係論の立場から、集団指導の立場からは、こういうようにことがらをとらえて、共にふるまう、共にふるまうことにおける指導、集団指導をすすめる。
《その3》
集団のつくられ方--個の関連体系としての--。つまり個人の側から主としてとらえて。
① 子どもがいて何か目立つ事象がある。それが目立つというのは自分に印象づけられていること。それを物との関係でいうと、印象性というのが物において見い出されている。
② それから、目立つものとの関係で情態体験がされる。それを、向こうの側に、物に何か表情があるとか、物を動物のようにみる、同じような人間だという気持ちでみながら自分の気持ちを発展させていたりする。
③ 次に、目立つものとの関係で、こちらには役立つものととらえられていて、物の方には機能性がある、機能性がみられているという状況がある。
④ それから、自分の要求充足の行為を実現するものとして物をみている場合。自分自身のしたいと思うこと、あるいは食べたいと思うこと、そういう気持ちを充足・促進するような性質があるものとして物をとらえている。物の性質からいうと、誘発性、有意性が物においてとらえられている。
⑤ それから、もう1つは、自己参加を促進している。自分自身がそこに参加している、そういう体験が成立する状況がある。物の方からいうと、物自身も動いている。自分自身もそれとかかわりながら動いている。誘動していることがある。
物が子どもの世界に位置つきながら、子どもの世界がそういう性質をもってつくられている。子どもにとって目立つ事象が、直観(直感)的な事象として非常に印象づけられたり、情態体験を成立させたり、役立つものとしてあったり、要求実現の行為を促進するものとしてあったり、自己参加を誘動・促進したりする。そのようにして、子どもの世界がつくられていく。
それは、子どもだけでなくて、大人の世界も、そういうふうにつくられてきている。そういう大人と子ども、あるいは友だちどうしが出会う。出会ったところで、いろいろな人と人との関係がつくられる。それはもとより出会っているところでは、接在共存状況における人と人であって、そこには自己も物もあることにおける出会い、そういう状況があっての出会いであって、もともと接在共存状況があるから、そのようなことも成り立っている。それはそうであっても、ここでは目立つものをとらえて(直観的事象に即して)いえば、子どもがいて、大人がいて、友たちがいて、そこにつながりができる。そういうふうにしてとらえると、子どもの方の世界においても今言ったようなことがあるし、大人の方の世界においても、友だちの世界においでもあって、そういう世界が出会う。出会ったところでどういうふうにそれがかかわって形づくられていくかということ。そのかかわり方に、内在的なかかわり方とか、内接的なかかわり方、接在、外接、外在的なかかわり方がある。
今言ったような世界どうしが、内接的にかかわったりすることもあるし、外接的にかかわったりすることもある。子どもたちの世界では、どちらかというと内在的な性質のかかわり方が顕著であっても、さきの5つの性質に対応するようなかかわり方、みえ方が成立している。それでも、どれかが強調されたみえ方をしていれば、それで、それと関係する大人においてもどれかが強調されながらそこに関係が結ばれる。つまり、子どもの方で印象性がつよいような世界をつくりながら、大人がそこに外接的にかかわるとか、接在的にかかわっているとかによって、子どもの印象性が強化されたり、あるいは、他の性質のかかわり方がそこに展開していればそれはそれで、ちがう組み合わせがでてくる。そういうふうにして、とにかく、かかわって、それで、いわゆる関連体系ができる。そこに集団と呼ぶことのできる状況がある。
集団とは、根源的な自己、人、物の接在共存状況を基盤として、人・人・人の3者関係の展開が可能な状況関係構造の成立し機能しているときの、その状態、それが人間における集団である、それは集団関係状況の展開する状態である。
《その4》
それでは、かかわって関連体系がつくられる場合に、どういうふうなつくられ方をするかということ。
① 同じ性質のものどうしが、つながるというようなつくられ方をする。それは類同構造化である。似たようなもの。同じような性質のものが、だから、かかわり方からいうと、内在的なかかわり方に近いようなもの。赤ん坊がお母さんのおなかの中に入っているときのそれと対応するような活動が出てくる。類同構造化している。お母さんと子どもとに同質的な構造化が成立する。
② ほかに、近接構造化がある。近似したもの、に近いもの、どうしがいっしょになる。
③ それからもう1つは、連結交叉構造化。それぞれが相対的に独立しながら、共通領域を持ちながら構造化していく。たとえばお互いに、印象性が、つまり、他のそとの世界に共通だと思われるような印象性をとらえてその物を見ているような場合には、そこにお互いに共有領域を成立させていて、連結構造化している。領域が共有化しながら、それぞれ相対的に独立した領域もありながら構造化している。
④ それから、形態構造化。それぞれがまとまって形をつくりながら、お互いに即しながら、お互いがはっきり領域を持ちながら、構造化するという場合がある。
⑤ それからもう1つは、閉合構造化。それぞれが自在。だからそこには、あまり、さっきのようには世界の共有領域が成立しにくいような状況があって、しかし、それぞれは自在-自分自身で存在する、開合してまとまりながらある、そういうふうに構造化している。人との関係では、関係が切れている。
お父さんとお母さんと子ども、また子どもは子どもどうしでも、構造化するときにそういうふうにいろいろに構造化する。そういうふうな性質の集団構造化がすすむ。これを図示すると次のようになる。
図3-6
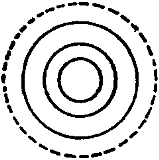
|
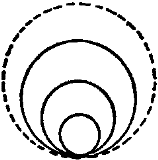
|
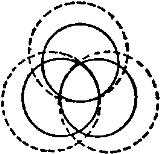
|
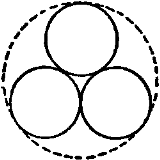
|
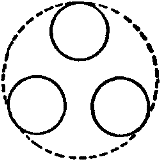
|
| 類同構造化 | 近接構造化 | 連結交叉構造化 | 形態構造化 | 閉会構造化 |
《その5》
どうして、類同、同質構造化していながらも、集団的な関係を保っていられるかというと、
そこでは、主として、生理的な関係とか、肉体(身体)としてのそれぞれの独自の存在、それが働くことにおいて、類同化することがありながら、相対的に独立しながら存在する。それが、接在共存状況の発展をもたらすことにつながっていく。ということで、そこでは、生理的な違いというものが非常に意味を持ってくる。
それで、こんどは交叉構造化する場合、連結構造化する場合で、どちらもが、どちらにも包含されないでありえるためには、さっきもいったような、共通領域が重要である。物とか、第3者-人とか、社会的な環境などがあることにおいて、接在共存状況が発展するような構造化ができる。
それから、こんどは閉合して、自存してしまって、それぞれがはなれてしまっている。そういうふうな構造化をしてしまう場合、それでもそれぞれの関係の発展がもたらされるのには、それぞれに共通の物理的環境が存在し働くことが重要である。閉合、自存して、平行していて、それぞれがポツポツといかにもつながりがないようであっても、物との関係が成立していることにおいて、やはり接在共存状況が保たれながらある。
このようにして集団がつくられていく場合に、生理的な条件、それから、第3者とか、、あるいは、社会的な条件、物理的な条件、そういう条件がはたらき、集団が形成・構造化し機能することに、それらははたらき続ける。
《その6》
集団の性質と集団成員に形成されるものについて。集団の側からみていく。
集団の性質としても、同心的集団というのがある。集団の主導的活動が内在的に展開していく。集団って言っても、集団があるというのではない、これまでのべたような活動自身、自己、人、物の関係が展開する人間の活動の状態である。集団というのがただ物のように存在しているのではない。ただ、それに社会的な意味付与がされると社会的集団として、ほとんど物と同じような意味を持って集団内活動が規制されてしまうことにもなる。
同心的集団というのは、集団の主導的活動が内在的に展開するので、中心集団、近在集団、周辺集団、外接集団というように成層構造化する。そういう構造化をしている集団が、他の集団とかかわって集団活動が展開すると、自集団の活動領域が拡大されて、それへと他集団活動を包含しようとする。そういう集団活動に規制されて形成されやすい成員の傾向として、自己中心性。関係発展をもたらすことにはたらく自己肯定性などがつくられる。
こんどは同接的集団。集団の主導的活動が内接的に展開する。そういうふうな集団に規制されて形成されやすい傾向として、自己開発性とか自発性、あるいは相即性、相対性がつくられる。
それから、接在(交叉)的集団の場合には、集団の主導的活動が接在的に展開する。そこではその集団活動に規制されて形成されやすい傾向として、関係性とか連帯性、間性、3者関係性、変革性、創造性、協同性などがある。
それから、併存的集団というのは、集団の主導的活動が外接的に展開する。集団が併存しながら、それぞれが接しながら展開する集団。そういう場合には、集団活動に規制されて形成されやすい傾向として、相対性、傍観性、群居性などがつくられる。
それから、自存的集団。集団の主導的活動が外在的に展開する場合。そういう場合には、そこで規制されて形成されやすい傾向は、自己閉鎖性、自己肯定性、それから排他性などである。
《その7》
集団を指導するというように言われる場合について。
これまでのべてきたこととの関連でとらえる必要がある。集団を指導すると言われる場合、指導する人が集団の外にいて、集団はこれこれの形であるというようにとらえられて、それを指導するのだとされると、それは、外接的な立場(場合によっては外在的な立場)からの指導になってしまう。
これまでのべてきたこと、発達について、集団についてのべてきたこと、これをきいて、さて自分たちの活動をいざ発展させようとしても、ここでいまきいている人が、ここでその言われているそのことにどうかかわりながらいるかということが十分にとらえられていない場合には、たとえば外接的に整理した発達に関する考え方が成立していて、そのことに気づかずに、聞いた人たちが自分たちの活動を、そこに重ねて展開しようとすると、行き詰ってくる。
集団での活動は、接在共存状況での自己、人、物がかかわりながらの活動であり、子どもたちとかかわりながらあれば自分が変わるということ。変わることが、そこに参加することにおいて展開していく接在共存活動である。それなのに、発達に関してきいたことには外接して、これは適用できるとかいうように、整理してしまう。これはこれまでのべてきたのとは違う立場である。
自分が自身、変わりながらある、自分自身はどう変化しながらあるかということと対応させながら、整理する。その整理が、自己内在的に、あるいは内接的になされる、それも大切であっても、さらに、実践活動を発展させていく人において、重要な立場というのは、やはり、接在共存状況を展開していって、現在自分自身が変わりながらあるということに気づきながら、変化しながらあること。子どもといっしょに変わりながら、創造されていく発達、そこでの課題というのが自分たちの問題になるような、性質のものである。
(松村康平)
参考文献
松村康平「幼児と環境」幼児教育学全集1『幼児教育の理論』小学館、1970
松村康平「集団の発達を促すかかわり方」『特別活動 5』日本文化科学社、1975
主題・副題:幼児の集団指導-新しい療育の実践- 46頁~61頁
