幼児の集団指導-新しい療育の実践-
第2部 集団指導の理論・技法・実践
第1章 集団指導の理論
はじめに
ここでは、どの子とも、どの人とも、ともに活動が創れる「関係発展展*)」「接在共存*)」の集団指導の理論・技法・実践に基づいて、集団指導についての理解をすすめていく。
それはまず第1に、今ここに出会っているひとりの“子ども”としてまた“人間”として、そこにすでに成立している人と人との生き生きとした“かかわり”に気づき、その“かかわり”の可能性をさらに豊かに全体的に広げ深めていくことにおいて、諸問題の解明をはかり発展の道すじを明らかにしていくことであり、子どもを、正常か異常かとか、普通か特殊かとか、障害別などに選別し、そのことを基準として集団指導を始めるのではない。それは、まさに、人間関係的行為のなかから始めることである。つまり、人間発達という、だれにも共通の人間としての根源的な営みを、「関係的に存在」し、ともに状況を担う人間として、ともに発展させていくことのなかでこそ、また、子どもにかかわる指導者のそれぞれの専門性(子どもに成立する臨床的課題あるいは独自的配慮)が生かされ、深められていくからである。
それでは、“ともに活動を創る”ということは、集団活動をすすめるうえで、具体的にはどのようなあり方をすることであろうか。
それは、一般的に陥りがちな、量的、固定的、画一的、能力主義的、差別的、権威主義的な、たとえば、次のような発想とは異なる。つまり、“では、とにかくみないっしょに同じ場に集めてみればどうでしょうか”とか、“いっしょにするためには方向性を強くして統率していかなくては”とか、“それで落ちこぼれる子どもがいれば特別に訓練し全体に何とか追いつくようにしていけばよいでしょう”とか、“それではできる子どもとできない子どもとをいっしょにしたらどうでしょうか”などとは異なるものである。
その立場は、基本的に、どの子どもが参加する集団であっても、「集団のダイナミックスを通して、また指導者が用いる集団変革の諸技法により、集団活動は発展し、個々の成員の変革がもたらされることになり、集団指導の効果をあげることができる*)」ということを基盤にしつつ、さらに、それでは、集団状況において、その「諸要成**))」である自己と人と物とがどのようにかかわりあっていけば発展がもたらされるかという”かかわり方の科学***)的な特質をもつものである。
この立場においては、“ともに活動を創る”ということは、自己と人と物とが共にかかわりながら育ちあう状況(接在共存状況)を明らかにしていくことであり、たとえば、(a)みないっしょにという普遍的共通領域を明確化すること(共通基盤性の視座)、(b)それぞれの存在のしかたが尊重され生かされること(分化独白性の視座)、(c)通路(関係)が明確化されそれぞれが交流しあうこと(交差性の視座)、(d)「差異を関係的に生かし、共通領域を明確にし****)」ながら新しい状況をつくりそれぞれを発展的に位置づけること(統合性の視座)、(e)だれもが状況発展への役割を連担し集団活動をすすめること(社会性の視座)が、同時的、そしてさらに関連的、段階的に展開され集団活動がすすめられていくことである。
- *) この立場(関係学的立場)を基盤とした「集団指導」は、お茶の水女子犬学児童臨床研究室で関係学の創始者である松村康平教授を中心に1960年から“関係療法による小集団活動”として始まり、1964年からは児童集団研究会が発足し、その実践・研究がすすめられ現在に至っている。
- 日本肢体不自由児協会中央療育相談所通園部門では、1970年から上述の集団指導の原理を生かし、加えて各専門分野(動作、言語、心理、保育)からの指導者の参加(チーム)により集団指導活動が行われている。この集団指導活動が行われているのは、中央療育相談所のスタッフの協力においてであり、特に五味重春教授、田口恒夫教授の理解あるご支援によるところが大きい。(詳しくは第2部第2章を参照のこと)
- *) 児童集団研究会「集団指導の理論・技法・実践」、お茶の水女子大学児童臨床研究室『児童臨床学』、1968
- **) 松村康平「発達と接在共存」本書第1部第3章p.31
- ***) 松村康平「児童学」松村康平、浅見千鶴子編『児童学事典』光生館、1972
- ****) 松村康平「発達と接在共存」本書第1部第3章p.31
1 集団指導の意義 *)
通常、子どもが父母の存在のもとに誕生すると、それにともなって家族集団の発達における変化(節)が顕著化し、保育者は意識的に発達の場としての集団づくり(関係の調整、変化、発展)、すなわち集団の新しい構造化を行い、子どもの発達が促進されるように役割を担う。また、子どもの状況により、その集団は施設集団であったり、保育園集団であったり、複数の集団であったりする。いずれの場合においても、子どもの生命が芽ばえ、誕生し、成人へと発達していく過程においては、さまざまな集団状況があり(つくられ)、それらは子どもの生活においてさまざまなかたちで、子どもにおける関係を発展させ全体的発達を促進してゆく基本的、具体的、現実的な場である。
では、子どもが発達していく場を基本的に集団状況として把握する時、それは次のように定義づけられるのではないだろうか。
「人間は関係的存在である。個人は集団的存在であって、特に集団という場合は複数の個人の生活活動体のことである。**)」ということであって、そしてこの集団において成立する状況、すなわち集団状況とは、(個人の)自己と人と物との接在共存関係が根源的に成立している人間関係的状況であるといえる。
集団状況において、この自己と人と物とが接在共存する関係状況が、集団指導の展開により明確化される(発展がもたらされる)と同時に、集団状況の構造化がなされることによりそこに参加する個人の発達が促進され、同時に社会の発展が導びかれると考えられる。
この集団指導の展開による接在共存状況明確化とは、どの子どもの存在の仕方も、集団状況における多様なかかわり方として意味(価値)があるとし、その多様なかかわり方が集団活動の発展に力動的に生かされ、集団全体も、そこに参加するひとりひとりも共に伸び、共に育つような状況の形成を意味し、このような生き生きとしたふれあいの状況形成的関係力動体験が、そこに参加する子どもにも大人にも育ち、日常の生活場面における具体的なふるまい方に生かされ役立つことをひとつの効果としてとらえるものである。
では、具体的には、集団指導が展開する典型的な集団活動は、他の集団活動(たとえば、家庭、幼稚園、保育園、学校など)との関係では特にどのような意義をもつのであろうか。
ひとつは、「家庭中心の生活から友だち集団(幼稚園、保育園、学校での集団)の一員として行為するようになる時期への移行*)」として意義をもつ。そして、これらのことから、通常、集団指導活動に参加するメンバーは、子ども(たち)〈友だち集団〉、母親(たち)〈家庭のなかで密接なかかわりをもつ人((父や祖母も可能))〉、指導者(たち)〈集団指導のリーダー((保育者、臨床者など))〉から成り、集団の大きさは、小集団(3人から12人ぐらいまで)であることに意味がある。
また、この集団活動は、「子どもの日常生活において、人間関係の発展をはばむ状況*)」(たとえば友だちと遊ぶ機会がない、母子関係が固定化している、ことばや動作や情緒の面において問題が起きているなど)が生じ、「役割のとり方が困難になり、関係からの疎外、離脱が生じる、あるいは生じる可能性のある場合にも*)」必要とされる。「このような場合には、発展をもたらす新しい可能性を発見することが困難な状態が打開され、現実の生活のなかでの人間関係的営みの発展を可能にすることが目的*)」となる。
そして、これらのことから、この集団指導が展開する小集団活動は、家庭や施設集団、社会、地域などの交差領域にあり、子どもの生活において領域移動を効果的にする発達的な役割を果たすとともに、その独自の発展が子どもをとりまくこれらの環境へも働きかけて、子どもにとって望ましい環境をつくりだす状況変革的な役割を果たすものであることが要請されているといえよう。
図1-1
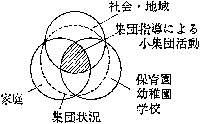
- *) 吉川晴美「個と集団の発達に関する-研究」関係学研究編集委員会『関係学研究』Vol5.No1.1977、同「集団指導の意義とその基本的な考え方」『保育と集団指導』ソシオサイコブックス、1974参照
- **) 松村康平「集団の発達を促すかかわり方」『特別活動』Vol8 日本文化社、1975
- *) 児童集団研究会「集団指導の理論・技法・実践」前掲書p.84
2 集団指導の基本的な考え方-方法と特色
1) 集団状況における子どもの発達*)
個と集団の相即的発展というあり方に立って、集団状況における子どもの発達**)をどのようにとらえ、促進していけばよいか。ここでは前述したように、自己と人と物とが共にかかわりながら育ちあう集団活動の発展に対応的になされていく個の自己構造化(発達)の過程を具体例に即して明らかにしていく。
たとえば、座ったままで左手で上体を支えながら右手で自動車を少しずつ動かして遊んでいる子どもAがいる。同じ部屋のなかの少し離れたところでは、ままごと道具を中心に「うち」ができ、ごちそうをつくったり食べたりする遊びが展開している。「うち」のすぐそばには、ジュースやまんじゅうを売る「店」ができ、「うち」と「店」とでは買ったり売ったりする交流ができ始めている。そのままであれば、Aは、自動車を右手で行ったり来たりさせながら、この自己と物との関係状況に内在化し、同時に、集団状況に外在化する方向でかかわり方の運動がすすみ、位置は部屋のすみに固定したまま、姿勢は徐々に寝ころぶ方向へ変化し、遊びも固定化し、発展しにくくなる。
ここでは、集団状況へのAのかかわり方を、たとえば、次のように全体的にとらえ行為を先に広げて、発達を促進していくことが可能である。
まず、A(自己)と物とのかかわり方から促進される自己構造化について述べてみよう。
集団状況において、Aは特定の物(自動車)にひかれて、自己と物との関係の「起動点***)」(ふし)を成立させ、その物との関係活動が、今の状況におけるAの存在のしかた(安定化)に重要な働きをしている。
Aと人とのかかわり方では、Aの今かかわっている物(自動車)を仲だちとして新しい人との関係が成立しやすい。ここでは、指導者の、今Aのしていることを受け入れて伸ばすような、補助自我的(内接的な)かかわり方により人との関係は発展しやすい。自己的な物を媒介に、人との関係の起動点の成立する可能性がとらえられる。
Aと自己とのかかわり方では、特定の物を媒介に集団状況において安定して遊ぶことがでている。しかし、自分と特定の物との関係にのみまかされてしまうと、自己が内在化し、新たに関係の起動点がつくられたり移動することがされにくく、ふるまい方が固定化しやすい(段階1)。
図1-2 段階1 内在的関係(運動)構造の明確化
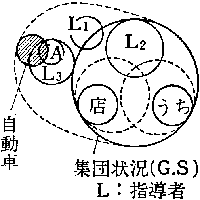
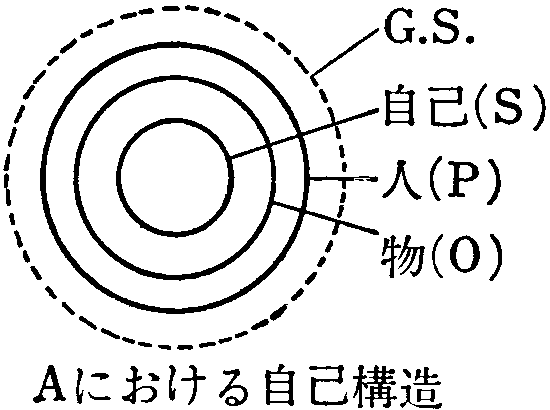
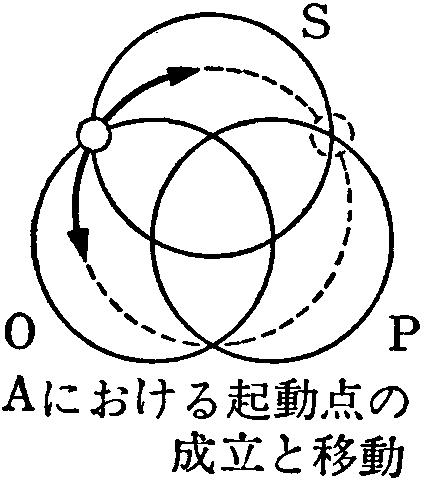
このようにとらえることによって、今Aにおいてできていること、それを可能にしている集団状況全体に気づき、それをきっかけとして先への発展の道すじをつくっていくなかで、Aの全体的発達が促進されていくように指導者はかかわる。
今Aのしている自動車遊びを受け入れ、Aに即しながら、「自動車、ブッブー、あー動いた、あーとまった」などとAと物との関係がすすむようにかかわるとする。そして次に、その先にトンネルをつくり、自動車を通すことのなかで、トンネルの向こう側にいる人に気づくようにかかわったり、Aの傍らで、Aと同じように別の自動車(トラック)を動かしながら、Aがトラックを動かしている人のいることに気づくようにかかわる。このようなかかわりのなかで、Aと物との関係活動からAと人と物との関係活動へと発展し、集団状況においても目立つひとつの領域(コーナー)として明確化してくる(段階2)。
図1-3 段階2 内在的関係(運動)構造から内接的関係(運動)構造への明確化
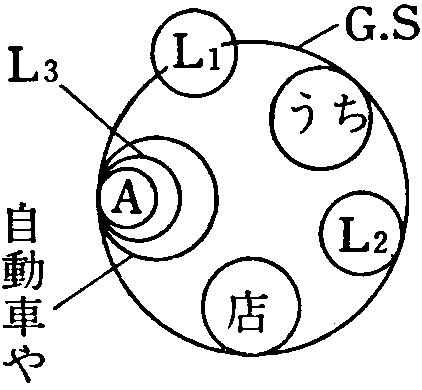
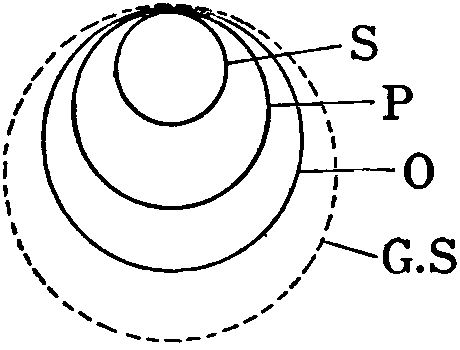
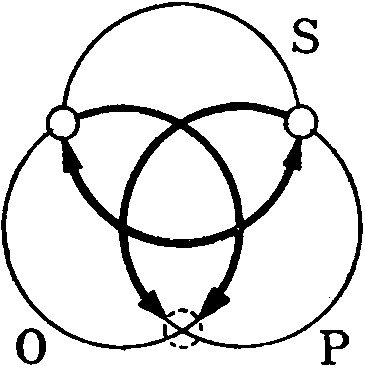
Aのコーナーの性質や領域が明確化してくると、外の「店」のコーナーから「自動車ありますか? このジュースをのせて運んで下さい」などの働きかけがでてくる。ここでは指導者は、外からの働きかけに、Aの補助自我あるいは相談役としてかかわり、Aの気持ちを代弁したり、Aが人の対面的な働きかけに気づいて自発的にかかわっていくように補助する(段階3)。
図1-4 段階3 内接的関係(運動)構造と外接的関係(運動)構造の相即的明確化店
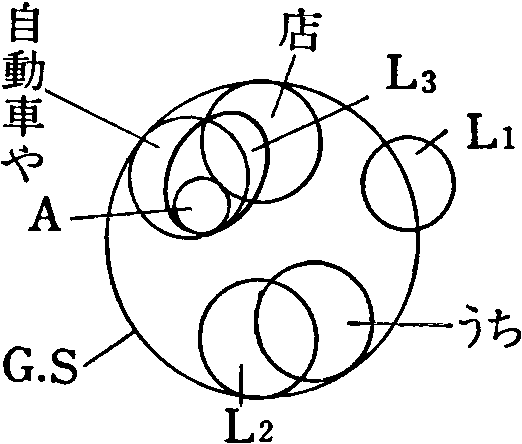
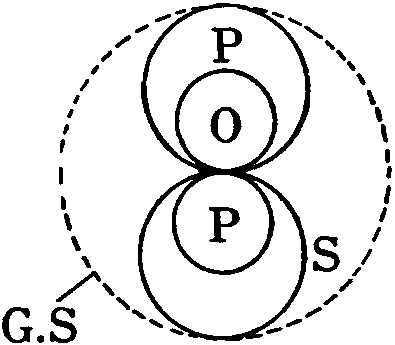
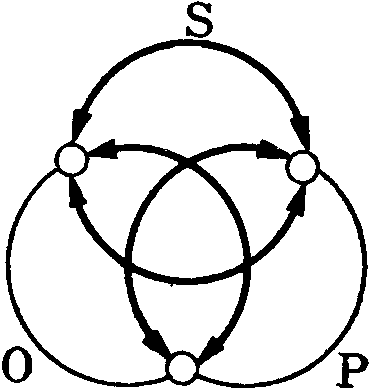
ここでは、Aは、自分と物と人との関係活動を基盤としてさらに新しい人や課題に出会い、さらにこれらの関係が発展していく程、自己の生き生きとした楽しい気持ちが高まったりお容さんと接しやすい姿勢を自発的にとり続けたり、さらに、「うち」のコーナーの人が、待っていることを予測(期待)しながら自動車を自分で寝返りをしながら「うち」へ届けたり、「自動車や」としての役割がはっきりしてきて、お答さんとのことばでのやりとりが促進されたりする(段階4)。
図1-5 段階4 内接的関係(運動)構造、接在的関係(運動)構造、外接的関係(運動)構造の関連的明確化
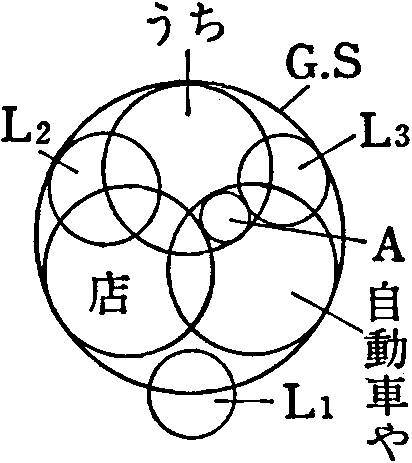
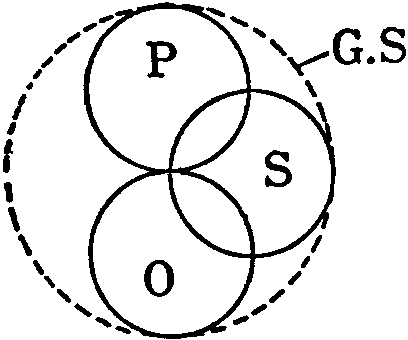
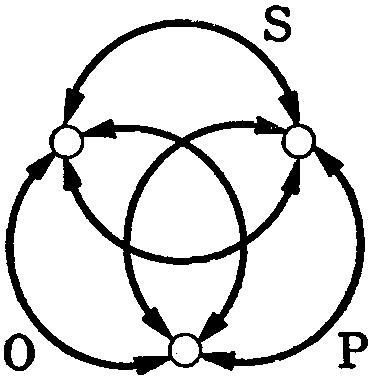
また、集団の統合状況、たとえばみんなで相談して、お弁当を持って自動車でピクニックに行くという活動のなかでも、他のメンバーの活動とともにAの活動の内的発展も全体的に生かされ(運転手の役で参加する)、かかわり方も飛躍的に発展する(段階5)。
図1-6 段階5 接在的関係(運動)構造の明確化
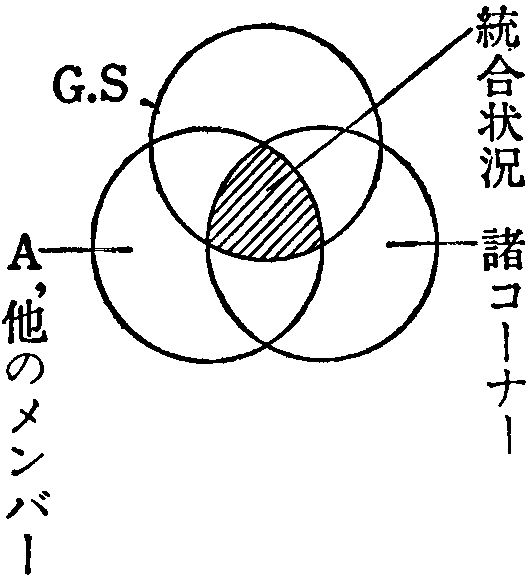
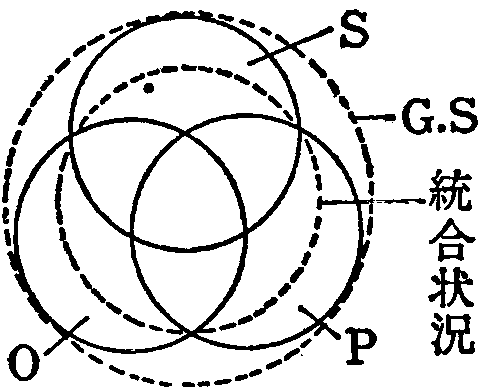
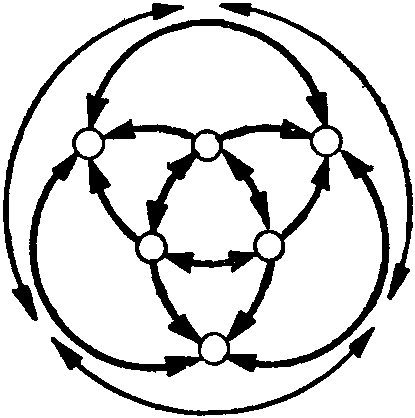
- *) 吉川晴美「集団指導の意義とその基本的な考え方」『幼児集団指導』Vol.3 日本肢体不自由児協会、1973参照
- **) 集団状況における発達の問題は、他に鈴木芙美子、武藤安子「発達に関する研究」『幼児集団指導』Vol6.日本肢体不自由児協会、1976にもふれられてある。
- ***) 松村康平、佐藤啓子「かかわり方の発達にかんする研究(2)-接在共存状況における起動点の成立と移動について」日本応用心理学会第43回大会研究発表論文集、1968
2) 集団状況の発展の過程*)
-接在共存状況の明確化・創造-
ここでは、さらに、集団状況全体に焦点をあて、集団指導が展開することによりどのように集団状況が発展していくか(どのように接在共存状況が明確化・創造されていくか)について、構造的、機能的、内容的に明らかにしていく。
(1) 集団状況の関係力動的構造化
集団状況における接在共存状況の明確化・創造の過程においては、前述してきたように、集団の担い手のどの存在の仕方も集団関係において共存的に位置づき、集団状況が関係力動的に構造化されていくなかで諸関係が発展し、個・集団が相即的に発展することができる。指導者(チーム)は、今成立している集団状況関係(運動)構造を認識し、意図的に発展への関係操作(接在的指導)をする、そのことによりかかわり方の運動が変化発展し、集団状況が、接在的関係(運動)構造へ転換していく。この構造転換のふしを、集団状況における個・小集団・全体集団の分化・交差・統合の関係弁証法的構造化の過程と対応させて、表1-1のように表すことができる。
表1-1 -個、小集団、全体集団の分化、交差、統合の関係弁証法的構造化の過程-〈質的転換の過程の形成〉
| 成立期 | 形成期 | 転換期 | 統合期 | 拡大期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個・小集団、全体集団の関係構造 |
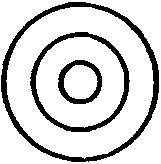
|
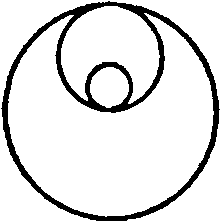
|
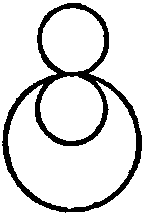
|
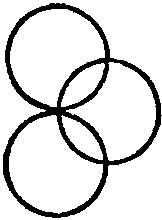
|
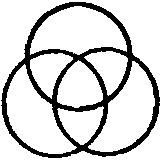
|
| 集団発展の基本的なかたち | 出会い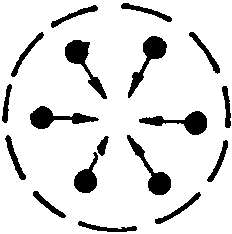 |
遊びをさがす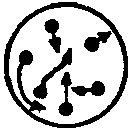 コーナ(活動領域)の成立 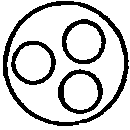 |
コーナー間交流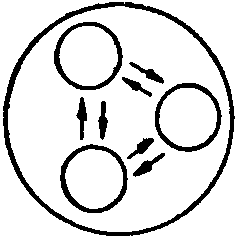 |
コーナー統合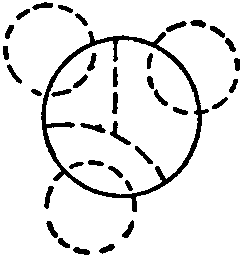 |
他集団との合同活動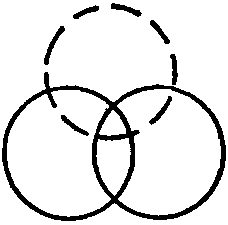 |
| かかわり方の運動の展開 |
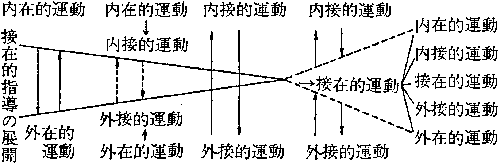
|
||||
| 自己関係の変化 | 内在的 | 内在内接的 | 内接的 | 内接接在的 | 接在的 |
| 役割関係の特色 | 個別的(過去的) | 類同的(過去的→現在的) | 独自的→多様的(現在的) | 総合的(現在的 未来的) | 社会的、未来的 |
| 分化 | 家庭から集団へ。母子関係から集団関係へ。今ここでの関係のしかたを受け入れる。 | それぞれのしたいことを明確化する。物理的活動領域の明確化。自己の確立をはかる。 | 集団状況において機能的に活動領域が分化しその内容的性質も全体に明らかになる。 例.家コーナー、店コーナー、電車コーナーに活動が分化し、交流が始まる。 |
集団状況において、多様な役割分化。集団活動内容の拡大。 例.コーナー内でも父、母、子などの役割がとられながら遊びがすすむ。 |
交差、統合が同時的にも予測においても成立しての分化。例.運動会遊びをすることが相談できまり、そこでの役割を分担する。 |
| 交差 | 新しい集団、人、物領域に出あう。気づく。 例.輪になって手をつなぐ。部屋を探索。オーイと呼びあう。 |
活動領域内の自己、人、物関係の成立、展開。同時に自己領域が明確になるような関係の成立。外から活動領域の窓をとおして「コンニテワ」と呼びかける。 | 媒介的機能の拡大。通路設置。 例.電話を設置。外からお客さんとしてたずねる。 |
多様的なかかわり方を生かして接在領域の拡大。活動領域間機能的交流。チーム状況の成立。 例.家のコーナーの母の役を担って店コーナーで買物し家に持ち帰って生かす。 |
状況発展的役割交代。 例.運動会遊びにおいて状況に応じて可変的。 ・創造的に役割がとられ、活動が展開する。 |
| 統合(全体化) | (共通基盤的活動) 今ここでの集団関係共通基盤に気づく。例.母子いっしょに手をつないで輸になってあいさつする。 母子いっしょに集団活動へのウォーシッブアップ活動をする。 |
(状況共通活動) 全体状況につつまれるなかで他と類同的な役割をにない自己及び集団に気づく。例、夜です。-寝る役割。ジャングルです。-探険する役割。 |
(課題的活動) (物中心的課題、あるいは、焦点活動領域の設定)。内的発展と外をとらえて接在領域を拡大する。 行為の連続化。 |
(統合的活動) 活動領域の内的発展。外の活動領域の発展。その按在領域の発展が生かされて新しい活動領域がつくられる。 例.家コーナー、電車コーナーの発展交流が生かされ、家族が電車にのって目的地に遠足に行く。 |
(社会的活動) 新しい状況にであって接在共存状況が協同的につくりだされる。 例.運動会遊びに参加してきた外集団を発展的に位置づけ、交流がつくりだされる。 |
*) 吉川晴美「小集団活動に関する-研究」(『幼児集団指導』Vol.5 日本肢体不自由児協会、1975)参照。
(2) 集団交差領域状況明確化技法の発見・適用・活用
集団状況の構造化をはかっていくうえで、集団交差領域状況を明確化する技法は、重要な役割(機能)を果たす。
集団交差領域状況明確化技法は、指導者(チーム)が個と個、個と集団、集団と集団、あるいは集団状況こおける自己、人、物との関係発展、変革をもたらすべく、今ここでの活動状況関係機能を領域的に明確化し、その交差する領域に働きかけ(関係操作し)状況を明確化する方法である。交差領域への関係操作の方法(技法)は、集団状況への関係弁証法的発展段階に応じて異なり、それは交差領域からどの領域(共通基盤的領域、分化相対的独自領域、統合領域、拡大杜会化領域)の方向へ特質を付与するか(発展させるか)によっても異なる。つまり、交差領域は集団状況の発展媒介的志向的領域としての機能をもつ(図1-7)。
図1-7
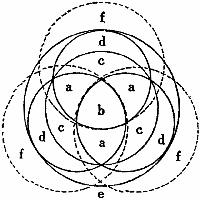
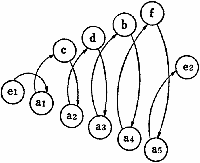
a 交差発展媒介領域
b 統合領域
c 共通基盤的領域
e 集団状況領域
d 分化相対的独自領域
f 拡大社会化領域
(3) 生活縮図的場面役割内容活動の展開
接在共存状況の明確化・創造の過程は、集団活動の内容的観点からも明らかにされうる。
指導者(チーム)は集団の担い手の自発的創造的活動が促進され行為の可能性が広がるように共にふるまいながら内容的発展を促す。集団指導活動内容は、生活縮図的場面役割内容活動として特色づけることができる。指導者は集団の担い手の自発的活動に即して生活縮図的場面役割を設定していくことにより活動内容を深め広げていく。
ここでは、生活縮図的場面役割内容活動を、自己身体的、心理行為的、人間関係的、場面構成的、社会地位的場面役割内容活動として具体例(中央療育相談所集団指導活動より)に記して次のように表示する(表1-2)。
表1-2 接在共存状況の明確化・創造
| 集団 | 構造 | 機能 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技法 | 領域 | 自己身体的 | 心理行為的 | 人間関係的 | 場面構成的 | 社会地位的 | ||
| 成立期 | 1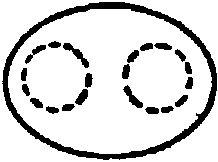 |
1.集団関係共通基盤状況明確化の技法 | 1.舞台にみなで乗り、床をドンドンひびかせる。 母と子で輪になって手をつなぐ。 |
|||||
2 |
2.集団内個焦点化自己確立の技法 | e1 | 2.輪になって順々に布をかぶってイナイイナイをする。 「~ちゃん」と指さしながら名前を呼ぶ歌をする。 |
|||||
3.4.5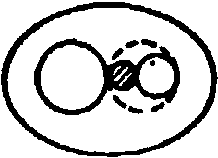 |
3.物媒介対人関係発展の技法 | a1 | 3.テープを手につけて相手を呼んだり鈴を送ったりする。 |
|||||
| 4.関係力動的体験成立の技法 | 4.つなをつかって輪になってみなでひっぱりあう。 |
|||||||
| 5.物媒介自己拡大対人関係認知の技法 | c | 5.ダックボールなど働きかけて変化しやすいものをころがす。ころがっていったところに人がいる。 |
||||||
6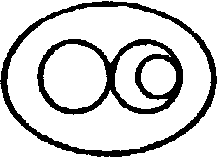 |
6.補助自我的自発性促進の技法 | 6.フラフープを境にして鏡のように動作をまねる。 |
||||||
| 形成期 | 7.8.9. 10 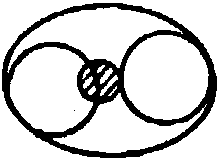 |
7.物焦点化分有行為化促進の技法 | c | 7.焦点にある輪なげの輪を中心からとりすきなように使う。 |
||||
| 8.活動領域(コーナー)設定の技法 | 8.活動の領域を物理的に分化させる。 |
|||||||
| 9.物媒介自他分化の技法 | a2 d |
9.境に窓をおく。内と外とからコンニチワと働きかける。 |
||||||
| 10.状況関係認知体験成立の技法 | 10.窓や円筒から外をのぞいて外のようすに気づく。 |
|||||||
11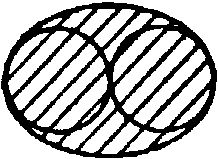 |
11.同一状況設定の技法 | 11.電気を消したりつけたり、あるいは音楽につつまれながら同一状況に気づく。 |
||||||
12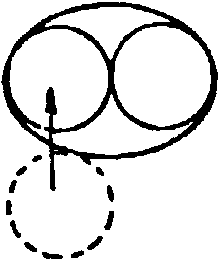 |
12.活動領域位置勾配変動の技法 | 12.舞台などを使って活動領域の位置、高さを変化、調節する。 |
||||||
| 転換期 | 13.14.15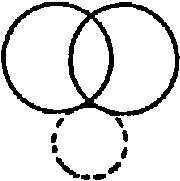 |
13.通路明確化疎通化の技法 | d a3 |
13.コーナー間の道を明確化し、道をとおって他に働きかける。 |
||||
| 14.役割付与の技法 | 14.コーナー活動の発展、子どもの動きに応じて役割を明確化する。 |
|||||||
| 15.活動領域内的発展交流化の技法 | 15.コーナー活動の内的発展をはかり他との交流をはかる。 |
|||||||
16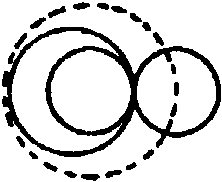 |
16.共通目標設定の技法 | 16.各コーナーに山の方へ行くことをさそう。 |
||||||
17.18.19.20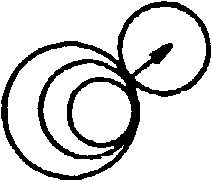 |
17.目標状況構造化の技法 | b |
17.目標にすすむ通路の可能性を拡げ示す。(汽車、船、車etc) |
|||||
| 18.活動領域拡大化の技法 | 18.活動内容発展にそくして行動領域を拡げる。 |
|||||||
| 19.参加誘導、Back up | 19.目標との関連で行為化の方向へ援助、誘導する。 |
|||||||
| 20.迂回軌道敷設による行為化促進の技法 | 20.目標領域と周辺領域の間にエレベーターをつくり行ったりきたりできるようにする。 |
|||||||
| 統合期 | 21.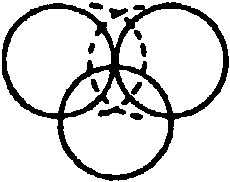 |
21.集団統合化の技法 | 21.各コーナーの活動を生かしてパーティをすることを手紙、電話で知らせる。 |
|||||
22.23.24.25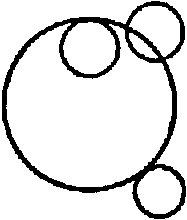 |
22.役割連担の技法 | b |
22.ごちそうをつくる人、おみやげを運ぶ人など役割を連担しながら活動がすすむようにする。 |
|||||
| 23.関係操作体験成立の枝法 | a4 f |
23.「みんなとこれからどうしようか」と集団の活動の方向を問う。 |
||||||
| 24.問題状況成立の技法 | 24.途中で雨が降ってきた状況のなかでみなで相談して解決の方向を考える。 |
|||||||
| 25.状況発展物共有化の技法 | 25.つなを状況の変化に応じていろいろ生かしてみなで使う。 |
|||||||
| 拡大期 | 26.27.28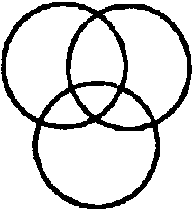 |
26.役割社会化の技法 | f a e |
26.お当番などをきめて集団の役割として遂行する。 |
||||
| 27.役割創造連担交代の枝法 | 27.状況の発展に応じて新しく役割を作り、役割関係が状況の発展をもたらす(ゲームetc)役割交代する。 |
|||||||
| 28.集団間交差の技法 | 28.グループごとに組になって、みんなでルールをつくりながら運動会をする。グループの成果を全体の場で発表する。 |
|||||||
3) 指導者のかかわり方--チーム状況の展開
集団指導活動においては複数の指導者によるチームでの指導がなされる。
「指導者が集団のなかにひとりの場合は、指導者と成員の間で指導する--指導されるという2者関係が成立しやすい。この2者関係的な関係の仕方で集団関係を操作することは、固定的な関係(指導者-被指導者)による指導となりやすい。このことを予測し3者関係を成立させて指導をすすめるのが矛一ムによる集団指導である*)。」
そして、集団の指導者は、集団活動を促進する機能には、次のような「3つの機能**)」があるということを集団活動の具体的な展開のなかで把握して、そのことをふまえてチーム指導をしていく必要がある。
<方向性機能> 集団活動の方向を明らかにする機能
<関係性機能> 集団活動において、人との関係、コーナーとの関係、場面、方向との関係など、さまざまな関係の発展を促進する機能
<内容性機能> 集団活動における子どもたちの自発活動を促進し内容をつくっていく機能
「<L1>は、集団活動の全体をとらえ、その活動の方向を明らかしたり(方向性機能を担う)、コーナー間の関係発展を促進する場面設定、役割付与する(関係性機能を担う)
<L2>は、コーナー活動における、子どもたちの自発的活動を促進したり(内容性機能を担う)、子どもたち同士の関係が発展する役割付与、場面設定をする(関係性機能を担う)
<L3>は、周辺的にいる子どもに即して動き、その子の自発的活動を促進しながら(内容性機能を担う)、他コーナーとの関係、全体集団状況との関係の発展をはかる(関係性機能を担う)
このように、<L1>、<L2>、<L3>が3つの役割(機能)を担い合いながら、子どもたち、物との関係が促進され、集団活動が展開していく**。」
また、「L1、L2、L3の役割が、3名の保育者によって担われない(保育の現場で保育者がひとりの)場合でも、集団活動における諸機能を保育者が認識して、場面設定したり役割付与をするなどすれば、子どもの自発的な動きや物が、集団を促進する機能を担うことができ、また、ひとりの保育者が、ひとりで状況の変化に即して機能的役割を変えながら集団活動を促進することも可能である*)」
集団活動の発展の方向において、臨床的、あるいは専門的な課題が成立する場合には、各専門家(例、言語臨床家、心理臨床家、動作臨床家など)がチーム内に参加することによって、集団活動の力動的発展とそれぞれの専門内容が同時に生かされながら、さらに活動の発展が促進される。
4) 集団指導のかたち(類型*))
「『集団の指導』には、どういうかたち(類型)があるだろうか。集団の活動の展開において、活動の発展に主導的に働く指導活動が、その集団活動とどのようにかかわって指導性を発揮するかという観点から、集団の指導は次のように分けることができる*)。」
①「集団の内在的指導=集団活動の内的発展が、集団活動において主導的に展開する場合*)」
例:保育室で、子どもA、B、Cは、それぞれしたいことを始める。Aはすべり台を昇ったりすべったりし、Bは紙にマジックでかきなぐっている。CはAに近づいていき、Aの活動をじっと見ている。指導者は、A、B、Cのそれぞれの自発活動による内的発展を尊重し、それぞれの子どものしたいようにまかせる。
②「集団の内接的指導=集団の活動に即して、その集団の分節活動が、集団の活動の内的発展にかかわって展開する場合*)」
例:前記①の場面において、指導者は、Cの傍らに近づき、ともにAを見ながら、「私もすべり合しようかな、どうしようかな」とつぶやく。さらに、Bの場所には描画活動が充実しやすいように、「赤のマジックさん踊っているネエ、あ、上手だなあ」などとBの活動に即してかかわっていく。
③「集団の接在的指導=集団の活動とその分節活動とが、あるいは、その集団の活動とは相対的に独立して展開可能な集団活動とが、関連し合い、接在共存状況を担って展開し、指導機能が発揮される場合*)。」
「○『自己・人・物』関係による指導
○『方向提示・関係展開・内容促進』の役割による指導
○『演者・補助自我・監督・観客・舞台』の役割による指導
○『自己身体・心理行為・人間関係・場面構成・社会地位』の役割による指導
○集団交差による指導、その他*)」
例:前記②の場面からさらに指導者はAのすべり台活動、Bの描画活動、Cの観客活動を生かしながらそれぞれの交流を拡大し、内と外との統合的発展をはかっていく。Aがすべり台からすべるとさらにBのコーナーまで行けるような道をつくったり、BのコーナーではBの活動がさらに発展するようにお手紙やさんとして全体に位置づけたり、Cのあり方を生かして、道の途中にあるふみきりの役をいっしょにしたりする。
④「集団の外接的指導=集団の活動において、それと外接して展開する活動によって指導(性)の発揮される場合
○集団活動の枠組による指導
○場面設定による指導
○集団形態操作による指導、その他*)」
例:指導者は、おやつ時間を予定しているので、「これから、おやつを食べましょう。AちゃんもBちゃんもCちゃんも皆手を洗って」と働きかける。
⑤「集団の外在的指導=集団の活動に外在して指導(性)が発揮される場合。もとより全く外在しては、指導活動は機能しない。ここでいう『外在的』指導は次のような場合である。
○物理的環境、社会的環境などの整備による指導
○自然事象の変化、文化的基盤の変動のもたらす指導、その他*)」
例:おやつを皆で食べていると、突然天井から雨もりがしてくる。指導者はやむを得ず皆でおやつを食べる部屋を替える。
以上、このような集団指導のかたちを認識し、どのような指導の仕方がどのような集団構造化をもたらすか(p44参照。内在的指導→類同構造化、内接的指導→近接構造化、接在的指導→連結(交差)構造化、外接的指導→形態構造化、外在的指導→閉合構造化)を日々の実践に対応させつつ、これらの指導の仕方を並列的なものとしてではなく、相互に関連づけ、集団状況の発展において今は、どのような指導をすすめていくことがより望ましいかを考えるのと同時に、さらにどの指導の仕方も集団活動に発展的に生かせる統合的な指導、すなわち指導者の「接在的指導」の立場に基づいて活動をすすめることが重要である。
*) 松村康平「幼児の性格形成」、前掲書(p.104、105)
主題・副題:幼児の集団指導-新しい療育の実践- 65頁~81頁
