幼児の集団指導-新しい療育の実践-
2 集団指導の方法
1) 乳幼児の療育におけるチーム指導体制
乳幼児の療育の方法が、専門科学的に細分化されてくるとともに、その内容をどのように統合化していくか、あるいは、各専門領域間の連携をどのようにとっていくかなど、チーム指導ののぞましいあり方が問題とされるようになった。
中央療育相談所は、肢体不自由児の療育相談機関として発足したが、次第に、相談・治療における、いわゆる“障害の多様化”の傾向と、原則として“障害の種類”を問わない主旨により、相談・治療の方法も専門的に多領域に考えられなければならなくなり、また、関連する施設、機関も多岐にわたり、総合的、組織的療育の体制をとる必要性が生じてきた。現在では集団指導の原理と方法を生かしたチーム指導体制の実践の基盤がほぼかたまりつつある。チーム指導体制の一例として次に紹介する。
(1) チーム指導の形態
チーム指導の体制は、当然のことながら、指導の内容をどのように組織するかということと深い関連がある。乳幼児の療育の指導内容という場合、従来から2つの大きな柱があった。ひとつは、指導の内容を、子どものもつ障害の治療に焦点をあてて、運動療法(機能訓練)、言語治療、心理治療など発達領域別に分類するいはば発達促進領域の柱である。他のひとつは、子どもの生活が具体的に展開する場を中心にして、日常の生活、遊び(保育)、治療のように分類する生活経験領域の柱である。
これらの指導内容をどのように関連させてのぞましいチーム指導体制を実現させていくかということは、どの療育の場でも大きな課題であろう。つまり、発達促進領域の内容が、発達領域別にばらばらに用意されて、全体的発達を促進するために必要な配慮がどうしても欠けてしまうこと、あるいは、生活経験の場が、生活経験領域の内容別に切り離され、相互に生かされにくく、生活全体が非常に発展性の乏しいものになりがちであることなどの問題が、認識されてきた。そこでは療育の内容を全体的に関連づけていこうとする過程で、個々の療育の内容あるいは専門性をどのように生かしながら、その統合化をはかるかという、いわゆる“分(節)化”と“統合化”の二方向を具体的にはどのような指導の形態をとることにおいて満たしていくかが課題となる。
さらに、乳幼児め療育においては、その多様でしかも変化していく発達課題に応じて、療育の内容や生活の基盤図がたえず変化する必要性が生じ、それらに段階的、発展的に対応しうる一貫した体制がとられることが必要となる。
このような課題をふまえたチーム指導の体制と、それを実現させるチーム指導の形態を構造化したものの例を図2-1、表2-1に示す。
図2-1 チーム指導体制の構造
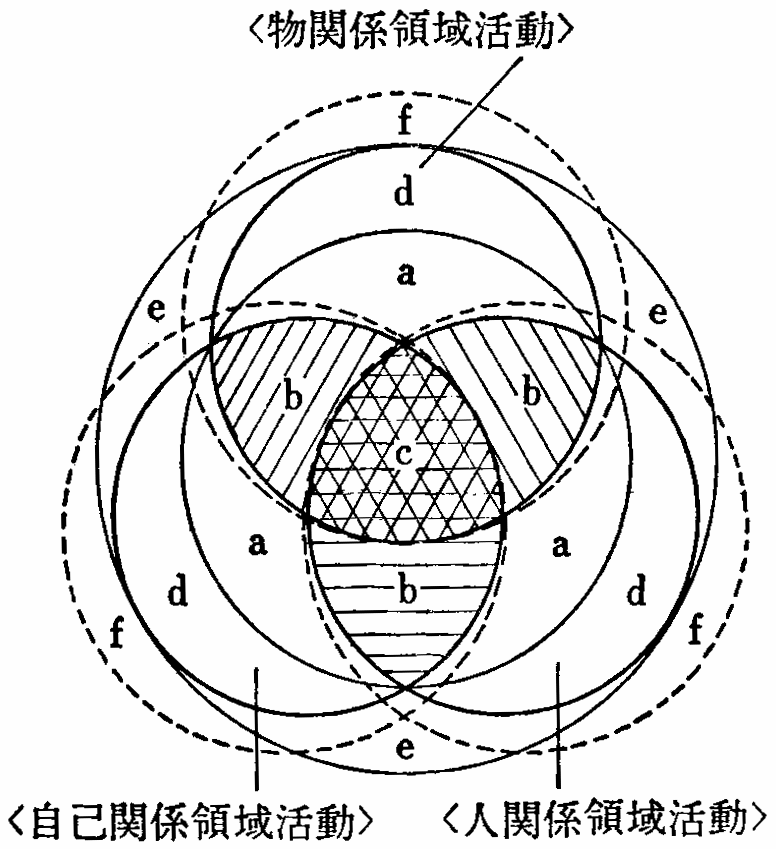
表2-1 乳幼児の療育におけるチーム指導体制 -中央療育相談所の場合-
| チーム指導の形態 | 活動内容 | |
|---|---|---|
| a.共通基盤領域にける指導共通の基盤の充実をはかる活動を展開 | ○生活基盤活動 | 施設内外の環境整備、通園バス、家庭療育、家庭保育 |
| ○家庭訪問指導 | ||
| ○保護者会、療育指導会 | ||
| b.交差連結領域における指導交差、交流をはかりながら活動を展開 | ○母子小集団指導(母子単位のグループ指導) | |
| ○専門領域交差指導(他の専門領域への交流指導) | ||
| c.統合領域における指導共存、共有をはかりながら活動を展開 | ○集団指導 | |
| ・子どもグループ・母親グループ・指導者グループ間関係(分化、交差、統合)指導 | ||
| ・専門領域統合チーム指導 | ||
| ・関係指導グループ、生活指導グループ、役割指導グループ間関係指導 | ||
| d.分化独自領域における指導相対的に独立して活動を展開 | ○専門領域別指導 医療、福祉、言語、心理などの相談(指導、訓練) |
|
| ○個別療育指導 | ||
| e.関連集団領域における指導関連的にある他の領域へ働きかけながら活動を展開 | ○他機関(施設、保育園、幼稚園、学校)との連携、交流 | |
| ○父母の会活動 | ||
| ○療育キャンプ | ||
| ○卒園児交流会 | ||
| ○講演会 | ||
| ○施設間連絡会 | ||
| f.発展社会領域における指導規定する枠組を広げながら活動を展開 | ○社会地域活動(運動) | |
| ○障害児福祉対策(運動) | ||
| ○児童福祉<保育>対策(運動) | ||
(a~fは図2-1のa~f領域と対応する)
この構造図は、人間の根源的な関係(集団)状況と、その発展の法則*)に基づいており、関係状況における人間の諸活動(個と個、個と集団、集団と集団、あるいは自己的・物的・人的諸活動)の発展により、図2-1に示すとおり、6つの関係交差領域が明確化されていく過程を示すものである。
チーム指導体制という場合には、チーム指導の形態を、専門分(節)化の方向または集団統合化の方向の、一極または対極的な視点においてとらえるのではなく、個々の子どもの発達的課題、指導の専門性などの差異性を生かし、相互に交差する領域を設けて、少なくとも6つの指導の形態が用意されることが必要である。つまり、それらは、図2-1、表2-1に示すごとく、a、共通基盤領域における指導、b.交差連結領域における指導、c.統合領域における指導、d.分化独自領域における指導、e.関連集団領域における指導、f.発展社会領域における指導、である。
子どもに即していえば、これら6つの活動領域は、子どもが成長、発達をとげていく上で必要な生活形態と対応するものであり、成長の過程のどこかで、必要に応じてそれらのいくつかが同時に体験されていくことにより、のぞましい発達が促進されていくといえる。
中央療育相談所における指導形態別の具体的な活動内容は、表2-1に示したとおりである。
なお、本書で述べられている集団指導について、その原理と方法は、どの指導の形態にも生かされているが、チーム指導の形態としては、C.統合領域における指導に位置づけられるものである。
*)本書p.75の吉川晴美の構造図を参考にする。
(2)チーム指導を促進する条件
チーム指導の形態が、療育の内容に応じて容易にくみかえられたり、発展的にその機能が発揮されていくために、どのような条件が必要であろうか。
次の3つの条件が特に重要である。第1に、チーム指導としての共働活動が行われやすいような共通基盤がつくられて、チーム体験がつみ重ねられていくこと。第2に、チーム指導技法そのものが開発され、実践的に確かめられていくこと、第3に、チーム指導理論が確立されて、研究・研修がたゆみなくなされていく状況がつくられること(図2-2)。
図2-2 チーム指導を促進する条件
チーム指導理論の確立 ↓ |
○各専門領域からの発達臨床理論の統合 | |
| ○集団指導法の導入展開の実践交流 | ||
| ○チーム指導の機能的役割連担と統合の実践 | ||
| ○チームの相互研修研究活動 | ||
| ↑ チーム指導技法の実践 ↓ |
○チーム指導技法の開発と実践 ・関係発達診断(指導者チームによる評価活動) ・三者面談法(母-子-指導者、母-指導者-指導者面談) ・集団面接法((指導者チームによるグループ面接) ・集団指導技法 |
|
| ○統合カリキュラムの計画・実施、全体行事の計画・実施 | ||
| ○ケーススタディ | ||
| ○他機関、他領域との連携(移行、進路指導の対応) | ||
| ↑ チーム指導体験のつみ重ね |
○指導連絡会 | 日常的連絡 |
| 運営、事務連絡 | ||
| ○学習会・読書会(共通の学習テーマ、自発的学習テーマ、研究報告) | ||
| ○親睦活動 | ||
| ○組合活動 | ||
| ○地域活動との提携 | ||
はじめのチーム指導体験のつみ重ねのレベルでは、ただ単に、指導者が個々に接触をもったり、各専門セクション間の連絡、調整をはかることだけでは不十分であり、チーム内の親密なコミュニケーションを基盤にしながら、チーム指導を促す条件、阻む条件を、統合的見地から見極めていく姿勢を養うことが大切である。次に、チーム指導技法の開発・実践のレベルでは、各専門領域独自の方法や実践が深められることと同時に、子どもの指導の方向、指導カリキュラムの内容、指導内容の実践に、チーム指導技法が確立、適用されることが必要である。さらに、チーム指導理論の確立のレベルにおいて、チーム指導の展開を支える理論、および、実践を通して出てきた諸問題を明確にし解決へ導びく概念の枠組の形成、チーム内外の研究・研修活動が深められていくことが重要である。
(3) チーム指導の実際
施設内におけるチーム指導が、実際にどのような流れにおいて展開するかを、一例をあげて述べると、図2-3のようである。
指導内容の変化と対応して、チーム指導の形態が発展的に組まれていくわけであるが、その際に大切なことは、指導内容や形態の変化の「節」を「チーム」としてどのようにつくっていくかということである。変化の「節」は、当然のこととして、子どもの発達課題の変化に対応した指導課題の転換によりもたらされるものであるが、それらを、個々の専門領域のばらばらな評価にまかせていたり、あるいは、ケース会議などで検討するだけでは十分とはいえない。チーム技法を活用して、子どもの母親もチームの一員としてともに参加しながら、「節」となる活動状況を、積極的、意図的につくり、相互に確認していくことが重要である。
チーム技法のうち、三者面談法については本書の第2部第7章に、関係評価については第2部第1章に記されている。集団面接法については、のちに、本章でふれることにする。
なお、交差保育法については別書*)を参照されたい。
図2-3 チーム指導の例-Cくん(医学的診断名:脳性マヒ)の場合
| 指導内容の変化 | チーム | 看護婦 MSW |
PT |
PTチーム STチーム (OT) (Cl.P) |
集団指導チーム | 集団指導チーム 幼稚園の先生チーム |
||
| 内容 | 栄養指導 家庭療育指導 社会資源の活用の相談 |
運動療法を目的とした母子活動 | 運動療法、言語治療(作業療法)(心理治療)を目的とした母子少集団活動 | 集団指導 | 統合保育 | |||
| チーム指導の形態 | 共通基盤領域 | 分化独自領域 | 交差連結領域 | 統合領域 | 関連集団領域 | |||
| チーム指導の展開 | 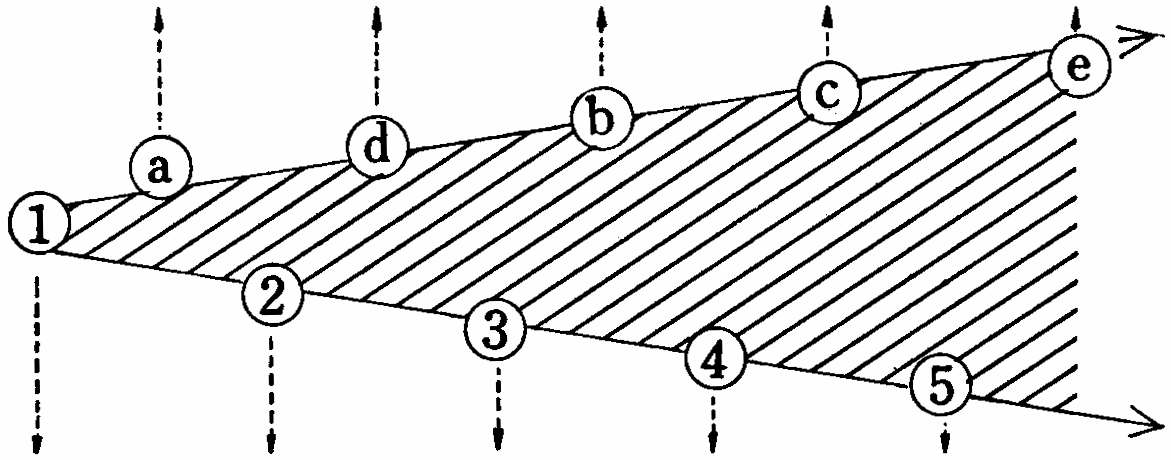 |
|||||||
| チーム技法の活用 | 関係評価法 | 三者面談法 | 三者面談法 | 集団面談法 | 交差保育法 | |||
| 指導課題の変化 | 内容 | 関係枠の評価 要求の統合発達の診断 |
関係枠の充実 療育の基盤の整備 発達課題の成立 |
関係枠の拡大 療育への積極的態度 発達課題の発展 |
関係枠の統合 療育への自主的参加 発達課題の統合 |
関係枠の転換発展 療育の地域の拡大 発達課題の集団的共有 |
||
| チーム | スタッフチーム 医師 医療技術員 各専門職 |
地域の保健婦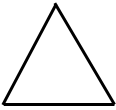 母 MSW (PT) |
PT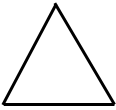 母 ST (MSW)(OT) (Cl.P) |
集団指導チーム |
集団指導チーム 幼稚園の先生 |
|||
| かかわりの経過 | 1歳2か月 | 1歳2か月 | 2歳5か月 | 3歳4か月 | 5歳 | |||
注 PT:理学療法士 CLP:臨床心理士
OT:作業療法士 MSW:医療ソーシャルワーカー
ST:言語治療士
*) 大戸美也子「交差保育諭」関係学研究編集委員会『関係学研究』第1巻第1号、1972
2) 集団指導の内容構成
集団指導の内容構成は、集団指導活動が展開される領域(場)における諸条件により、独自な発展があることがのぞましい。中央療育相談所の場合は、第2部第1章集団指導の理論の項で述べられている考え方に即して行われている。また実践の成果および問題点については、各章の実践の項に分けて、それぞれの観点から整理がなされている。
ここでは、主として集団体験の違いを生かしたグループ編成の仕方、集団指導の目標のたて方を述べることにする。
(1) グループ編成の方法
① グループ編成の基準
集団指導においては「どのようなメンバー編成による集団であっても、集団のダイナミックスを通して、また指導者が用いる集団変革の諸技法により集団活動は発展し、個々の成員の変革がもたらされることになり、集団指導の効果をあげることができる*)。」したがって、「無作為なメンバー編成による集団指導も可能であるといえる*)。」
集団参加に際しては、母親または家族その他、子どもの成育に深くかかわってきた人との面談、あるいは、それまで指導を担当してきた人の専門領域からの治療に関する見通しなどから予備知識を得ておくことも必要であるが、それら(たとえば、過去の生育歴、障害の種類、専門治療の目標など)は、子どもにおける集団活動への参加の仕方を規定する条件であり、すべてではない。大切なのは、どのような集団(関係)体験がなされながらそこにいるか、どのような集団(関係)体験が積まれることがのぞましいかを評価する「関係評価」あるいは「関係成熟度」が問題にされなければならない。また、これらを基準にして集団参加の仕方、グループ編成が考えられる必要がある。「関係評価」あるいは「関係成熱度」は、評価するもの(指導者)と、されるもの(子ども)が出会ってつくられる集団状況において、その状況の担い手として、ともに状況の発展をもたらしながらの評価であり、この診断「即」治療の立場にたった評価法を「集団面接法」とよぶ。
② 集団面接法
集団面接には、複数の子どもと複数の指導者(各専門領域からの指導者チーム)が参加して行われる。その間、母親には、他の指導者(主にケースワーカー)との話し合いがもたれ、活動の主旨、概要の説明、および参加条件の検討(通所方法など)の機会となる。
集団面接の活動は、子どもの自発的な行為が受け入れられ、指導者の介在は最小限にしてすすめられるが、活動の流れのどこかで、参加している子どもたちの集団体験の変化をさそうことを目的に、次の5つの異なる活動場面の設定が考慮される。
1 共通基盤活動(他の人といっしょにいて安定する)
たとえば、ドールハウスに皆で入って喜ぶ、自動車を他の人と一緒に押すなど。
2 役割活動(人や物への多様なかかわり方をする)
たとえば、スロープから自動車、筒、ボールなどをすべらせる、いろいろな人に電話をかけるなど。
3 課題活動(課題に応じたり、問題に対処しようとする)
たとえば、頼まれて人形を自分の車にのせる、積木の道路からおちた自動車の事故をみてパトカーを走らせるなど。
4 場面活動(他の領域と相互交流を活発にする)
たとえば、ボールのごはんを人形の家へ運ぶ、ふみきりが開くのを待って通るなど。
5 統合活動(他の人のしていることをうけ入れ、成果を共有する)
たとえば、人形の家にごはんを食べにいく、なわの汽車に皆でのるなど。
集団面接の結果は、指導者チームにより、表2-2に示す観点において整理される。
それぞれの子どもに関して、関係評価、各専門領域からの発達課題を成立させたのちに、これからどのような集団体験がなされることがのぞましいかという観点から、集団指導課題を成立させ、通園条件、男女差などを考慮しながらグループ編成をする。
集団指導課題およびグループ編成の基準の内容は、81ぺ一ジに細かく記されているので、ここでは省略する。
表2-2 グループ編成の基準
| 関係発展評価枠 | 集団体験の発展 | 1 共通基盤活動 | |
| 2 役割活動 | |||
| 3 課題活動 | |||
| 4 場面活動 | |||
| 5 統合活動 | |||
| かかわりかたの発展 | 自己とめ関係 | ||
| 人との関係 | |||
| 物との関係 | |||
| 各発達領域からの課題 | |||
| 集団指導課題 |
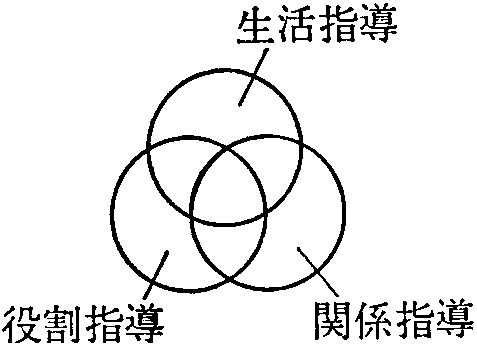
|
||
*) お茶の水女子大学児童臨床研究室編「児童臨床学」、1968
(2) 集団指導の目標および活動内容
集団指導の指導者チームにより作成された、集団の発展段階に応じた指導目標は表2-3に示されている(各発展段階の期間、および段階の区切り方は、各々の集団の発展の様相によって異なる)。
この指導目標をふまえて展開した活動例は、表2-4に示されている。
(武藤 安子)
表2-3 集団指導の目標
| 発展 段階 |
<全体の目標> | <子ども集団の目標> | 母集団活動の目標 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集団場面活動 | <活動のレベル> | |||||||
| 運動-動作活動のレベル | 言語-コミュニケーション活動のレベル | 心理-行為活動のレベル | ||||||
| 一期 | 集団成立期 | 一段階(四~五月) | ○内在的運動の展開。 ・集団で受け入れられたり、包まれたりすることにより安定する。 ・まわりの人や物に気づき自分なりに働らきかけたり試してみる。 ・目立つものとの関係の成立。 |
○共通基盤活動 新しい集団につつまれて安定する。 |
○まわりからの働きかけに気づく。 ○自分の動きの可能性、方法を知る。 |
○集団の中に安定する場をみつけ、活動場面を見たり、聞いたり、触れたりしながら楽しむ体験をする。 | ○自己身体的役割活動 「してしまう」役割が容認されてとれる。 |
○集団での安定 出会いの体験。 |
| 集団形成期 | 二段階(六~七月) | ○内在的、内接的運動の展開。 ・それぞれの活動が集団の中で分化し、内的発展・充実がはかられる。 ・まわりの人や物との関係の中で自分のしたいことがはっきりする。 ・集団における自己の確立。 ・目立つものとの関係の深化。 |
○役割活動 集団における自己・人・物の多様なかかわり方を体験する。 |
○自分の動きをいかしてくり返し行う。 ○物をいろいろに使ってみるためしてみる。 |
○活動の中で、自分のしたいこと、好きな人、関心のあるものなどがはっきりし、自分の気持ちを表現する体験をする。 | ○心理行為的役割活動 「してみる」役割が自発的にとれる。 |
○自集団の確立 集団課題の成立。 |
|
| 二期 | 集団発展期 | 三段階(八~九月) | ○内接的、外接的運動の展開。 ・集団が分節化し(小集団活動の明確化)、内的発展がはかられる。 ・外の状況や方向性に気づき、働きかけたり即してかかわる。 ・集団状況における課題の成立。 ・目立つものとの関係で、全体状況や目立たせているものに気づく。 |
○課題活動 日常生活場面における関心が深まり集団活動に反映される。 |
○自分の動き、方法を確立する。 ○そのものの性質、機能に気づく。 |
○人からの働きかけに応じたり人へ働きかけたりする体験を通して、自分の応答伝達の方法の可能性を知る。 | ○対人関係的役割活動深化 「することができてなされる」役割の可能性を深める。 |
○集団課題の内容の深化 課題状況の構成。 |
| 集団拡大期 | 四段階(十~十一月) | ○内接的、按在的、外接的運動の展開。 ・集団の領域や内容が広がり、全体性、方向性に気づいて積極的にかかわる。 ・役割が機能的に分担され、全体が多様に発展する。 ・目立つものと目立たせているものとの関係が発展する。 |
○場面活動。 活動領域が拡大され集団内の相互の交流が活発になる。 |
○多様な動作体験をする。 ○人や物との関係で使い方が変化する。 |
○多面的な人間関係の中での豊富な相互交渉および伝達体験をする。 | ○対人関係的役割活動拡大 「することができてなされる」役割が相互媒介的にとれる。 |
○集団課題の内容の拡大。 課題解決の方法を知る。 |
|
| 三期 | 集団統合期 | 五段階(十二~一 月) | ○按在的運動の展開。 ・集団状況が統合的に設定され状況中心に役割が連担・交代される。 ・目立つものと目立たせているものが統合され、意味が転換する。 |
○統合活動。 簡単なルールを理解して、集団で目的を達成することを経験する。 |
○自分なりの動作、移動方法の選択をする。 ○物の機能に即して使用し目的に応じて選択的に使い分ける。 |
○場面状況の理解および即応する役割取得体験を通して適切な言語表現力を拡大させる。 | ○場面構成的役割活動 「することが許される」役割が交代してとれる。 |
○集団の統合・連結 自集団外活動をとらえて動く。 |
| 集団転換期 | 六段階(二~三月) | ○内在、内接、按在、外接、外在的運動の展開。 ・新しい状況において社会的役割を連担しながら、主体的にかかわることにより、個と集団の統合的変革が促進される。 |
○成果共有活動。 集団の成果を共有し先の活動へと生かす |
○白分の動きを調整しながら動作の確実性を増す。 ○物の機能を生かして構成的、創造的に使用する。 |
○状況全体を把握したり活動の発展的な方向を予測し、状況操作のための役割をとったり提案ができる。○状況全体を把握したり活動の発展的な方向を予測し、状況操作のための役割をとったり提案ができる。 | ○社会地位的役割活動 「することが必要な」役割が連担してとれる。 |
○集団の創造的発展 自集団と他集団の交流。 |
|
中央療育相談所集団指導チーム作成
表2-4 集団指導の活動内容
| 一期 | 集団成立期 | 発展の節となる活動 | 活動内容 | 活動例 |
|---|---|---|---|---|
| <入園・始園の集い> <春の戸外保育> (公園) |
○集団の中に安定する場をみつける。 | ●ドールハウス、積木、ついたて、しきものなどで仕切って“おうち”にはいる。 | ||
| ○出会いのことばかけ、音のひびきあい。 | ●”コンニチハ・サヨウナラ”あそび。●いろいろな音を出す。●“おうち”間のよびかけごっこ、訪ねあい。 | |||
| ○物のいきかい。 | ●ボール投げ、ボールぶつけ。 | |||
| ○体を大きく動かしてあそぶ。 | ●すべり台、ブランコ、トランポリン、のりものなどの固有玩具あそび。 | |||
| ○つつまれてあそぶ。 | ●音楽(歌)。ビニールプール、ビーチボールにゆられる。 | |||
| 集団形成期 | <遠足> <たねまき→収穫> <七夕まつり> |
○働きかけ働きかけられて変化をたのしむ。 | ●砂、水あそび、フィンガーペイント、粘土などの素材玩具あそび。●ダンボールの家にかくれる。●声をとどかせるあそび。 | |
| ○ことば、動作表現をたのしむ。 | ●身体部位のあてつこ、動物・星など何かになっての表現動作。 | |||
| ○媒介物を使ってのやりとりあそび。 | ●電話ごっこ、伸縮性ロープ、縄、ローラーを使っての大波・小波。 | |||
| ○自発的な探索・移動。 | ●車押し、積木はこび、電車ごっこ●散歩。 | |||
| ○物の多様な性質に気づく。 | ●丸、三角、四角などの形の弁別、野菜のスタンプ。 | |||
| 二期 | 集団発展期 | <プール> <夏休み> |
○身近な生活、動物、道具などに関心をもつ。 | ●動物のあてっこあそび、ものまねあそび。 |
| ○身近な人、家族の役割をとってふるまう。 | ●”おかあさん”あそび、家族人形あそび。 | |||
| ○生活縮図的な場面をたのしむ。 | ●ままごと、お風呂やさん、食堂あそび。 | |||
| ○日常生活習慣に関心をもつ。 | ●衣服の着脱、食事、排泄習慣。 | |||
| ○場面の規定性に即してふるまう。 | ●トンネル、ふみきり、橋わたり、軌道あそび。●体操。●夏休みの体験の発表。 | |||
| ○場面の必要に応じてふるまう。 | ●あそびの相談、あとかたづけ。 | |||
| ○課題場面への対処の工夫をする。 | ●“火事だ”、“病気だ”、“おおかみだ”の事件。 | |||
| 集団拡大期 | <運動会> <秋の戸外保育> (動物園) |
○室内空間(距離、勾配など)を有効にいかしてあそぶ。 | ●三段舞台を使ってあそぶ、スロープの“山”あそび、円台の“島”あそび。 | |
| ○役割の分化(観客、演者)、やりとりをたのしむ。 | ●ごっこ遊びの中での“売り手”“買い手”など。 ●ジェスチャーあそび、サーカスごっこ。 |
|||
| ○場面の目的をみとおして行動する。 | ●玉いれ、つなひきなど。 | |||
| ○場面全体を理解してふるまう。 | ●“うみでおよぐ”“雨がふってきた”“よる”などの空想全体場面。 | |||
| ○素材をくみあわせて、製策する。 | ●木の葉を使って人形つぐり。 | |||
| 三期 | 集団統合期 | <クリスマスの集い> <冬休み> |
○簡単なきまりをいかしてあそぶ。 | ●お金、切符づくり。 |
| ○ルールを理解してあそぶ。 | ●おにごっこ、かくれんぼ。 ●野球、すもうあそび。●正月のゲーム(トランプ、すごろく) |
|||
| ○役割を選択し、分担してあそぶ。 | ●お店やさんごっこ、のりものごっこ | |||
| ○媒介的あそび(つなぎのあそび)。 | ●テレビあそび、郵便あそび。お天気あそび。 | |||
| ○場面全体や目的に応じて道具をそろえる。 | ●積木で動物園づくり、ジューススタンドづくり。 | |||
| ○構成あそび。 | ●福笑い。 | |||
| ○共同でひとつのものをつくりあげる。 | ●展覧会あそび。 | |||
| ○空想場面で創造的にふるまう。 | ●空気のボール、雪なげごっこ、劇あそび。 | |||
| 集団転換期 | <まめまき> <おひなまつりの集い> <卒、終園式> |
○一連の作業を理解し、つくったものであそぶ。 | ●ぺープサートづくり、おひなさまづくり。 | |
| ○場面に必要な役割を創造する。 | ●グループで役割を分担、変身ごっこ。 | |||
| ○遊びの場面を構成する。 | ●“あさ”から次の“あさ”までのあそび。遊びの地図づくり。時間表づくり。 | |||
| ○ゲームや遊びの結果を判定する。 | ●ゲームの得点つけ、学校ごっこ。 | |||
| ○場面に必要な物を想定する。 | ●トランポリンの舟、風呂、電車。 |
(1976年度中央療育相談所集団指導記録より)
参考文献
(1) 松村康平編「児童臨床学」光生館、1971
(2) 「幼児集団指導」Vol.1~8 日本肢体不自由児協会、1970~1978
主題・副題:幼児の集団指導-新しい療育の実践- 102頁~115頁
