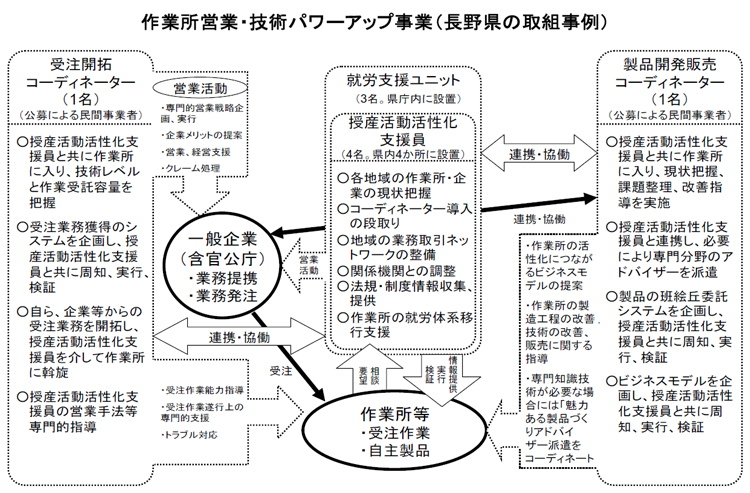2.調査について (1)サービス管理責任者に関するアンケート調査
| ① | 目的 | ||
| サービス管理責任者研修(指導者研修)に対する評価、都道府県研修の状況、支援現場でのサービス管理責任者の業務の課題等を明らかにする。 | |||
| ② | 調査対象者 | ||
| 平成19年度サービス管理責任者研修(指導者研修)修了者232 名 | |||
| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |
46 名 45 名 47 名 47 名 47 名 |
|
| ③ | 調査方法 | ||
| 調査票を232 名に直接郵送(一部メールも含む)により配布し、郵送又はメー ルにより回収した。 | |||
| ④ 調査期間 平成20年1月11日~1月31日 | |||
| ⑤ | 有効回答数 128 件 | ||
| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |
29 件 23 件 22 件 33 件 21 件 |
|
| ⑥ | 回答率 55.2% | ||
| ・分野別内訳 | 介護 地域生活(身体) 地域生活(知的・精神) 児童 就労 |
63.0 % 51.1 % 46.8 % 70.2 % 44.7 % |
|
【介護分野】集計結果
Ⅰ 回答者の事業所等について
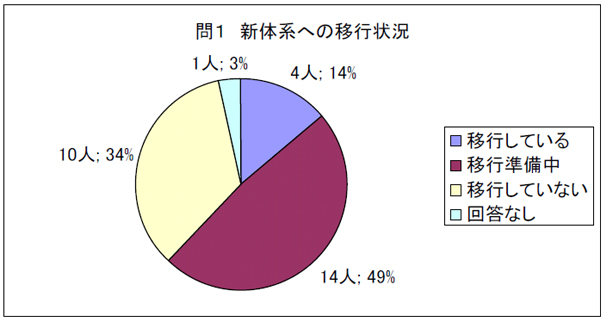
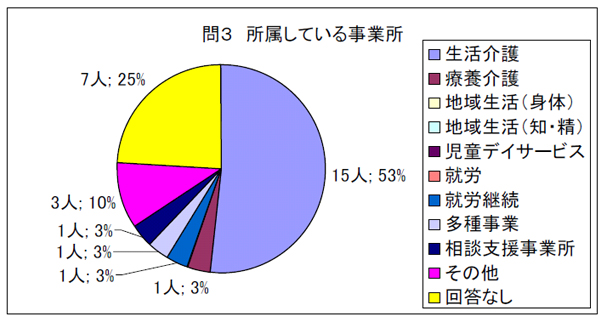
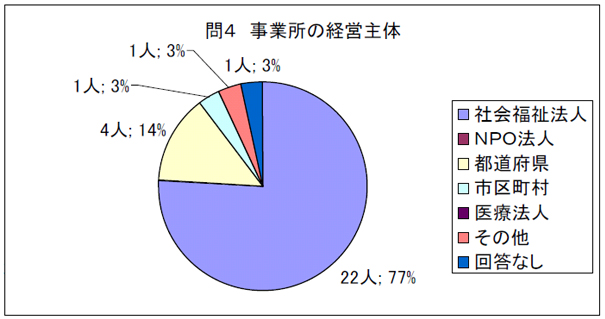
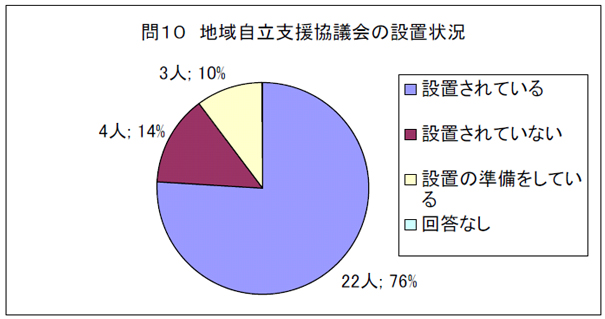
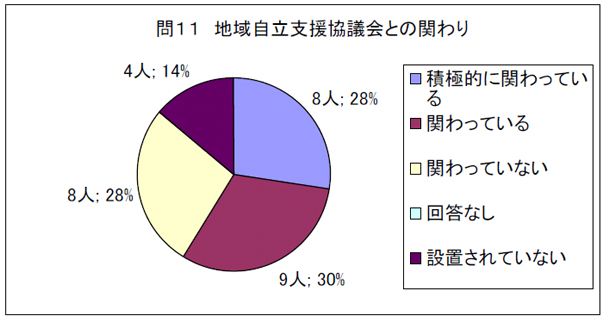
問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由
・基本的な内容は十分に理解ができたが、焦点が定まらない論議があった。
・一方的に講師が語る学究的な講義ではなく、現場の方々を講師とした演習やグループワークだったので
・とても熱心にサビ管のつとめを伝えようと努力され、また、資料もデータで配布され、有効活用できました。
・先進的な取り組みの実際が参考になりました。
・普段耳に馴染みの無い単語や、今まで携わった事の無い障害の方の事例があり難しい面もあったが、他の障害の施設職員との交流など良い刺激になった。・モニタリングの演習を含め、個別支援計画作成についてのスキルアップにつながったと思っています。ロールプレイは自分自身の「気づき」の面でも再確認ができ、今後の相談業務に活かすことができる内容がある研修でした。
・研修における到達点などをもう少し明確にし、県の研修により具体的につなげていただければ、と感じる。
・研修内容が充実していた。
・都道府県レベルで研修の企画・運営を行うノウハウの伝授としては、時間と内容のバランスで盛り沢山すぎたと思う。
当方の力量の問題かもしれないが消化不良の感がある。
・講義ばかりではなく、演習を通してサビ管が具体的に直面する場面を体験することで、これまで漠然としかイメージできなかった役割を感じることができた。また、豊富な知識と経験をお持ちの他府県の方々とお話できたことで、自分のスキルアップにもつながった。
・制度がスタートし間もないこともあり、役割・位置づけ・他サビ管や他機関との関係や連携や介護保険上のケアマネのつくりとの違いにおいて不明瞭な部分がありましたが、本人主体・サービスの質の向上という面においてクリアで全国標準になるとの方向性に賛同しています。
・内容がかなり豊富であり、全体的な把握ができた。また、演習ではロールプレイなど具体的な事例にあわせた内容もあった。講義は資料が豊富でわかりづらい部分もあった。
・障害者自立支援法に基づく、サービス管理責任者の実務と責務、役割について理解できた。
全国からの研修生と出会うことにより、地域の実情等の情報や実務担当者同士の意見交換は有益であった。また、講師やファシリテーターの取り組みに熱意が感じられたところが挙げられる。
・講義形式だけでなく、ロールプレイなど、実践に役立つ内容が良かった。
・(サービス管理責任者として業務はしていないが)サービス管理責任者もしくは、その機能を果たす立場の者の役割が認識でき、業務上役割を意識しながら業務にあたっている。
・サービス管理責任者の役割を理解できた。施設内での個々の利用者への援助、個別支援計画について具体的に知ることが出来た。
・全般的、包括的な内容であった。
・個別支援計画作成および管理の流れが整理できた。
・充実した内容であった。実際の問題点や困難な点の検討や話し合いがあれば良かった。
・満足はしたが、実務をしていないこともあり演習等についていけない面はあった。印象に残った事として、分野別の演習で提出された生活介護の事例(49才、脊髄損傷)が事例としての範疇にとどまらず、人物像へ思いが至りました。また、同様、新しく導入された演習でのロールプレイでは対立する場面、協調を必要とする場面等よく場面を工夫され設定されていたことなどが印象に残っています。また、大塚専門官の講義も福岡にて再度聞くことにより見えていない内容も発見できました。
・前年度出席者の話から今年度の内容について検討の後が見られた。
・介護分野は広範囲であり、種別で分けて欲しかった。
・サービス管理責任者の重要性が認識できた。自分なりに相談支援専門員との役割イメージが明確になった。
・自分の考えや実践が整理された。サービス管理責任者の役割の重要性を認識できた。
・新体系へ事業移行することがあれば、そのときに役立つ内容でした。
・全国的に活躍されている講師から実践に役立つ講義をいただけた。
・個別支援の作成、プロセスについて勉強になったが、サービス管理責任者の指導者研修としての内容としては、不満。
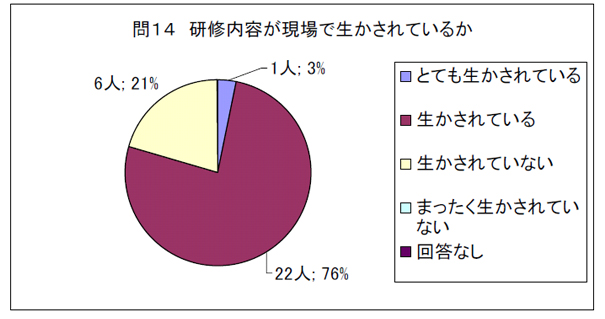
問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由
・相談支援事業を2市1村から委託を受け、また、自立支援協議会の運営にも携わっている。
・支援の技術的な面、視点の置き方など、ああそうだったと思い出す時がある
・生活介護の分野では、重度の施設利用者について、結局こうすれば正解なんだという落としどころがなくて、苦しみながら利用者の生活を向上させようと努力されている現実が浮かび上がって来ているのかなとおもっています。私も今のところ確たる答えが見いだせないでいますので、今後につなげ、ご教授ください。
・私自身はサビ管ではないので、一支援員として、また若い人には先輩として、日々の支援の中で、生かされていると思います。
・新体系への移行準備中ということもあり、サービス管理責任者として充分な役割は果たせていないところであるが、個別支援に関る会議の中で物事の捉え方・考え方という面では生かされていると思う。
・本年度作成した個別支援計画を担当グループ毎にモニタリングを行い、個別支援計画の見直しを早速行いました。
・新事業へ移行しておらず、役割や視点を意識しながら日々の業務をおこなっている状態。
・今後に向けて、職員の研修会等を開き、職員のスキルアップにつなげている。
・現在は旧法で運営しているが、個別支援計画の立案実施は長年のテーマであった。その視点について違っていなかったことが確認でき、スタッフに報告できたこと。
・サビ管としての自覚を持ち、積極的に利用者へのよりよき支援を模索し、ほかの職員に対してもそれを促す言動が自らでてきた。
・前年度県内研修を受講後、課題の整理表様式をモニタリングの整理表作り直して試行しましたが、考え方のメモということへの十分な理解を得られず、今回の研修においても支援会議の持ち方含めて時間という制約の突破口が見出せていません。
・個別支援計画の作成において支援員に助言している。
・個別支援計画は職員が立てているが、それの元になる理論や原理を把握するところまではいっていない。自分が時間をとって指導的に進めていかなければならないと考える。
・新体系移行後、事業所内のサービス管理責任者に対して、まだ十分とは言えないが、個別支援計画に係る取り組みや役割についての周知が行えた点が挙げられる。
・講師をしたとき、実際に役立った。
・県のサービス管理責任者研修の計画の参考にしている。日常の業務の中では、支援計画の見直し、職員の業務状況の把握や職員間のコミュニケーションに意識的にかかわれるようになった。
・個別サービス、利用者中心に個別支援計画を作成することについて、勉強会を行い、実際の場面で指導できつつある。
・個別支援計画
・個別支援計画の必要性が周知できていない。
・支援計画作成の現場での説明に利用できた。サービス管理責任者の立場と内部での地位がはっきりしない。
・新体系に移行していない。
・大型施設なので職場内でサビ管研修を月1回行っている。
・支援計画を立てる際、今までのやり方が再確認できた。
・手法の活用
・自分が実践していることが、あまりずれていない部分が多いと確信がもてた。自分の業務内容がサービス管理責任者に近いと感じた。
・まだ新体系へ事業移行することが、決まっていないため。
・県民への出前講座や学生、サービス事業者への研修に役立っている。
・支援計画の作成についての考え方は役に立っているが、所としては全く取り入れられずにいる。
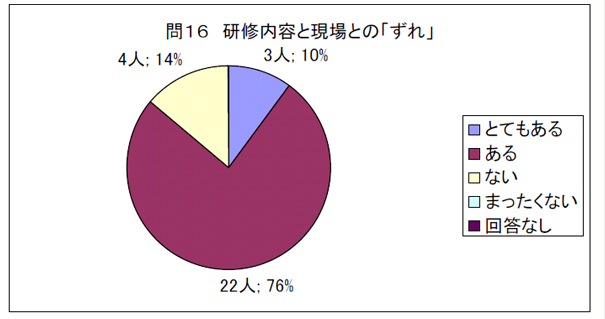
問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容
・自立支援協議会の運営について、事業所(旧法施設)が行政批判を繰り返すことがある。
・理念やあるべき形は理解出来ていても、実際の業務をしながらとなると負担も大きく、モデルのようにはきれいに展開しないことが多い。国で作ったモデルのような一連の流れをするためには、それだけに専念できる環境が必要とはつくづく実感できますが、まだ少数派のためか現実は厳しいようです。
・重度の入所施設利用者のICF、本人のできることに着目した支援。どうしてもできないところを改善していく方向に、計画してしまう。別の図の、阻害因子を取り除くという説明には何となく絡んでいけるかなと思うが、現実の支援計画では結局できないことを穴埋めしようとする行為とどこが違うのかと悩んでしまうことが多い。
・地域移行の進捗状況により、微妙なずれがあると思います。
・地域格差はあると思います。
・重度の障害者であり、社会的入所の現状であり、もっと排泄、入浴、食事、通院に毎日職員が追われている施設の現状にあった研修もしたかった。
・ずれ、というより実際に現場でこの仕事をスムーズに進めていくことができるのかという不安を強く感じる。これまでやってきた仕事の大幅な整理と修正も必要
・研修の内容は充分重要であり、職員、利用者、保護者の勉強会を行い、ソフト面、ハード面での意識改革、環境の調整が今後必要と思われる。
・私が見てきた府内の施設について言えば、「パラダイムチェンジ」ができていないこと。サービス管理を担う人材が育っていないこと。職員の定着が図れていないこと。
・個別支援計画の実効性・サポート及び科学性を見出すために有効だろうと思われる業務マニュアルの作成は、現場の現状では過酷ではないかと思います。新人・転入職員の研修の工夫と毎日実施の業務引継ぎ時の検討事項を不在の関係職員に周知させる工夫を及びチェック体制と指摘による改善で対応して行くことが現実的ではないかと考えるのですが。
問18.国の指導者研修の内容で良かった点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・サービス管理責任者の役割がより明確化された。
・PDCAに関わるサビ管の動きを確認できた。
・法的な確認ができたことと、サビ管の位置づけがよくわかりました。
・自立支援法の再確認にもなった。
・利用者の思いを汲み取り、共有する専門職チームのキーパーソン的役割などチームワークの重要性と管理者、現場 の職員との共通認識の推進をすることなど多義に渡り役割が期待されていることが確認できた。
・これまでの仕事を見直し、その上で役割りを確認することができた。
・とても理解しやすく、今まであいまいであった部分をしっかり学ぶことができた。
・サービスの標準化モデルを国レベルで示したこと。
・事業の中でサビ管がどの部分に法的に責任を持たなければならないかを知ることができた。
・講師の大塚専門官の熱意が伝わりました。
・大変な仕事ということだけでなく、やりがいのある仕事である、というイメージがわくような説明であった。
・障害者自立支援法そのものを確認することができた。
・サービス管理責任者のあるべき姿と講師からの現場への具体的な助言とエール。また、仕事の流儀を通してのマネ ジメント概念について。
・丁寧な説明でわかりやすかった。
・計画立案、モニタリング、修正という一連の流れの繰り返しの重要性と、実施の蓄積から標準化したものを作り出すことの重要性を認識できた。
・発想の転換をしていくこと、措置時代の施設の考え方をかえていくためにはとても勉強になった。
・サービス管理責任者の要件、内容
・役割のイメージができた。
・具体的な提示が良かった。
・最新の障害者自立支援法の流れや考え方・問題点などを聞くことができた。またサービス管理責任者の仕事の流儀 は具体的であり心に響くものがあった。
・「仕事の流儀」の講義は、サービス管理責任者の業務を具体的に説明してくれる内容だった。
2.サービス提供のプロセスと管理
・具体的で良かった。
・体系的にわかりやすく説明していただきました。ニーズの捉え方、本人が主人公の支援のあり方、一連の支援の動き
等サービス管理責任者としての仕事を理解することができました。
・プロセスの項目ごとに目的・手段等を知ることが出来た。
・個別支援計画を作成し、利用者や家族に説明するだけでなく、その計画がそのとおりに実施されているかを確認し、実施されていない場合にはどこに問題があるのか、利用者側か職員側かその他にもあるのか等を見極め、適切に対処しなければならないことがよく理解できた。
・現在、施設で実施してる支援のプロセスに欠けている部分を確認することができた。
・前半の講義では、プロセスの管理、必要性、押さえるポイント等、十分理解できた。後半の実践例を詳しく聞くことにより、サビ管の役割、個別支援計画の必要性、関係機関との連携等充分理解することができた。
・生活介護や療養介護の利用者も契約の当事者であり、利用者主体・参加の原則を示し説明責任を明確にしたこと。しかし方法論は現場の努力で見出すことは困難。西駒郷の取り組み報告。
・モニタリングの大切さを認識できた。
・講師の坂本先生と山田所長の話し方が、丁寧で理解し易かったと思います
3.サービス提供者と関係機関の連携
・具体的で良かった。
・地域ネットワークを活用しての各地域の取り組みを知ることが出来た。
・地域にある社会資源を有効に活用しながら、事業所が相互にネットワークを作り、他の事業所や福祉事務所、病院や学校関係、地域の自立支援協議会などとも連携を密にとることで、チームの一員として支援する大切を研修の中で学んだ。
・実際の連携の様子、特に地域移行に関しての内容は今後の大きなテーマでもあり大変興味深く聞かせていただいた。
・関係機関との必要性を充分理解することができた。
・施設や法人内での自己完結的なサービス提供の視点を社会生活者としての利用者の視点から拡げるような方向を
明示したこと。
・クライエントに必要な支援を提供する上でより多くの機関との連携をとっておかなければならないと感じた。
・サービス管理責任者の役割として、他関係機関との連携の重要性と共に施設内での連携(共有にポイントを置く)の重要性と個別支援計画が水戸黄門の印籠と同様の連携ツールという理解ができました。
・連携なしには利用者の要望をかなえることはできない、ということがよく伝わった。
・さまざまな関係機関との連携が必要なことはよく理解した。
・連携の理念と実際。また、連携への具体的なアドバイス。
地域生活支援への地域資源の活用と創造といった視点について。
・広島大教授の実践報告が面白かった。
・連携の必要性はよく言われるが、連携の定義、そのためのルールが示された。共感できる内容であった。
・連携についてのモデル、取り組み例等
・表示が分かりやすかった。
・田中康雄先生の「誰のための連携なのか」がなるほどなと思わされ、また考えさせられた。
・自立生活には、地域でのトータル支援が必要と理解できた。
・指導者になるほどの技術が身に付かない。5日間くらいは必要。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・具体的で良かった。
・個別支援計画を作成していても、アセスメントやモニタリングができていない現状を再確認できた。
・視点の確認ができた
・分野の特徴を充分理解することができた。実践報告も参考になった。
・横浜の実践報告が、利用者中心と支援者の関係を最も掘り下げて考えさせられた。
・個別支援計画を作成する上でアセスメントの重要性だけでなく、どういう視点に立つ必要があるのか、また、目標によってその視点が変化することを知ることができた。
・介護分野の裾野の広さへの説明があり、特に療養介護について県研修の際、伝達ということで参考にさせていただきました。
・全体的に理解しやすい構成になっていたと思う。
・分野別になるとより具体的な内容であり、よく理解をすることができた。
・施設支援における生活介護についての理念と実際の比較をする中での利用者中心の考え方やニーズについての理解、具体的な視点等。 3事例を通して、サービス管理責任者としての実際の役割、心構えといった点。
・ファシリテーターごとに、職場での実践を聞けて良かった。
・サービス提供のプロセスに対する責任者の役割や視点が明確に共通化され、機能する必要性を学ぶことができた。その実践の中で標準化と個別化が相互補完可能になる点も共感できた。
・実際の事例の流れの中で、大まかなイメージをつかめた。
・内容は理解できた。
・資料が分かりやすかった。
・指導者になるほどの技術が身に付かない。6日間くらいは必要。もう少し踏み込んで欲しい。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・具体的で良かった。
・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わる事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。
・個別支援計画を作ること自体が目的ではなく、一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切で、支援計画自体がその人のニーズに合っているかということが重要であると感じた。
・視点の確認ができた
・5.6の項目が演習1で一気に進み、わかりづらく、グループで話が詰めれないまま時間がなく次に進む状態であっ た。事例も昨年度と同じものであり、変化があったほうが良いと思った。
・事例検討
・具体的な事例を通して見ることで相手の立場に立ってあらゆる方向から物事を見る必要性を実感できた。
・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。
・一連の流れの中でどのような視点が必要か理解できた。
・グループ内で話し合いをしながらアセスメントができたのでよかったと思う。
・サービス管理責任者として、利用者の見えていないニーズの拾い上げや課題の整理についての視点。事例(身体障 害者療護施設)のアセスメントシートの書式および課題の整理表は参考となった。講師、各ファシリテーターの講評 は参考となった。
・グループワークが良かった。また、記録やプレゼンがPC利用なのでとてもスムーズに研修をすすめることができた。
・日常的にかかわる事例とはまったく違うケースであったが、他機関、多職種が集まる演習のため、ニースの整理が可 能となり、多職種の集まりの重要性も認識できた。
・実習はすべてわかりやすく有意義であった。
・事例が多かったのはよかった。
・演習の中で特にロールプレイが良かった。
・内容は理解できた。
・資料が分かりやすかった。
・指導者になるほどの技術が身に付かない。7日間くらいは必要。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・具体的で良かった。
・様式などが具体的に用意されていて、また、完成度も高いと思われるので、活用していきたい。改訂の際には、ぜひ、広報いただき、最新のモノを配布していただきたい。
・講義だけでなく、実際に演習で経験できたことがよかったです。
・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わる事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。
・個別支援計画がその計画とおりに実施されているかを確認し、実施されていない場合にはどこに問題があるのか、利用者側か職員側かその他にあるのかを見極め、適切に対処する大切さを研修で学んだ。
・視点の確認ができた
・5.6の項目を一気に進めることにより、ロールプレーを体験することができ、サビ管の仕事のイメージはつかめたが、代表者による模擬形式程度でもよいのでは…
・事例検討?
・実際にその立場に立つ経験ができ、またそれぞれの立場になった人の実際の気持ちも聞け、相手を理解しようとする心構えがもてた。とても楽しかったし、考えさせられた。
・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。
・ロールプレイを通してサビ管の役割が見えた。
・グループ内で話し合いをしながら作成をしたので、非常に具体的なものとなった。また、パソコンやプロジェクターを使用して、視覚的にすばらしいものであった。
・ロールプレイを通して、実際のサービス管理責任者としてのサービス提供のプロセス管理およびサービス提供職員のマネジメントの臨場感が体験できたこと。また、サービス管理責任者として施設の中でどのような役割を果たすのか、また利用者への支援の可能性や将来の生活に向けた視点など。
・ロールプレイが良かった。グループ毎にファシリテーターが付いたのはとてもよい。
・上記と同様で、意見交換が肯定的にでき、自分の意見を述べることで、自分の中の問題整理ができる体験を、改めてすることができた。現場でのスタンスの動機付けにもなった。
・3日目のロールプレイの事例については実際の事例とズレが大きい。ロールプレイ形式そのものは良かった。
・内容は理解できた。
・資料が分かりやすかった。
・指導者になるほどの技術が身に付かない。8日間くらいは必要。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・具体的で良かった。
・グループ討議の中で各項目、表を使用しながら一連の流れを討議する形で分かりやすかった。また、いままで携わ
る事の少なかった事例に取り組め良い機会となった。
・
福祉・保健・医療のほか、教育・就労などの幅広いニーズと障害者が地域で生活することを支援するためには、生活
ニーズに基づいたケア計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供する必要があることを再確認できた。
・視点の確認ができた
・白い紙一枚渡されるだけであったので、議論の内容が絞りにくかった。一回目のように、ある程度の形式が決まって
いるほうが短時間でまとめるには議論がしやすいように感じた。
・事例検討?
・意見交換できたことが良かった。
・ファシリテーターの的確なアドバイスが参考になりました。
・3日間の研修のまとめという点で、だいたいのことは確認できた。
・サービス管理責任者の役割は非常に多岐にわたるということが理解できた。
・サービス管理責任者の役割、責任、視点、チェックポイントといった総合的な観点。
参考資料のサービス管理責任者のプロセスシートおよびチェックシートはとても参考となった。
講師、各ファシリテーターの講評は、参考・励みになった。
・グループワークが良かった。
・ロールプレイは大変興味深く、自分の行動を見直すとてもよい契機になった。他施設の状況も垣間見え、大変参考 になった。
・まとめの資料があったので良かった。サビ管の体験ができてよかった。
・内容は理解できた。
・資料が分かりやすかった。
・指導者になるほどの技術が身に付かない。9日間くらいは必要。
問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・個別支援計画の作成等に十分な時間を割いてほしい。単位が細切れになってしまう傾向がある。当事者を交えた研修の立案も必要。
・支援法内でのサビ管の位置づけの再確認をしていただけると、ありがたい。
・法人という組織の中で、サービス管理責任者の位置付けをするには限界がある。つまり、施設長、課長、課長補佐、
主任といった階層がすでに定着している。
・対人援助職に必要な福祉倫理を土台に、様々な福祉現場(障害者支援施設・地域生活等)での事例を通して、サービス管理者としての役割を具体的に研修できればと思います。
・役割についてのより具体的な提示がほしい。
・法の改正がいろいろ進む中、何が今一番新しいものかの把握が難しい。
・自立支援法への信頼感が揺らいでいますが、サービス管理の意義などはもっと積極的に評価し強調してもよいと思われる。
・どの講義にも共通することですが、一方通行になりがちで疑問を抱いたものも全て飲み込むことになります。しかし、やはり消化されずに残ってしまうことになります。できれば質疑応答の時間を多く設けていただいてしっかりと理解した上でそれぞれの地域での講習につなげられたらと思います。
・流儀のところは、実際にインタビューするような形がとれれば、より良かったのではないか。
・内容が多すぎ、説明者が早口で説明をしていたため、なかなか理解するのは難しかった。また、個人の流儀はあまり参考にはならない。それぞれの方が流儀を持って仕事についている。このセクションで流儀を話す必要性は疑問に感じる。
・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。
・相談支援専門員との関係性を含め、地域生活支援の中での位置づけが強調されていること。
・資料の中で基本的なことについて少しではあるが分野別等に重なっている資料もある。
・サービス管理責任者の仕事の流儀にでているような方の生の声を聞けるような設定があれが良いのでは。
・資料ばかりであまり内容がない。法律、制度的な位置づけをしっかり押さえていく。
2.サービス提供のプロセスと管理
・当事者を交えながら、アセスメントからのプロセス管理までの一連の流れの研修
・意識変革=概念砕きはできたが、砕け散ったまま。再構築できない状態。ICFの具体例がもっと欲しい。特に知的の重度者→重度者の個別支援計画をどう組み立てるか。
・支援計画が計画通り実施されているか、変化や新たなニーズが発生したときに、適切に対応するために再アセスメントの実施についてのロールプレイも効果的ではないかと感じた。
・特になし。実践例はあったほうがわかりやすい。
・変則勤務や複数の専門職がいる条件下でチームアプローチを進める工夫例などを紹介して欲しい。
・実践報告のところはわかりづらかった。
・従来のモデルとICF的なモデルの違いがよくわからなかった。具体例を用いて説明をしてくれるとかなりよいと思われる。また、長野県の事例は地域移行として理解はできるが、これは相談支援研修ではなく、サービス管理の研修であり、この項目を挙げるのはどうかと思う。
・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。
・ストレングスの視点にふれていただければと思います(まとめでは触れられていますが)。
・介護分野の講義内容に問題はないが、具体的な事例を含めて説明したほうが良かった。理論だけでは業務の中のイメージができにくい。
・ここでの事例は全分野に共通することではないので向かないのでは。
・資料ばかりであまり内容がない。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・各関係機関が共通理解ができるようなマネジメント力が重要と思われる。
・具体的なケースを取り上げて実際に関係機関とどう連携していくか検討することができたら、より分かりやすいと思いました。
・事業所が地域にある社会資源を有効に活用し、課題を共有しながら各事業所が相互にネットワークを作っていくプロセスについて検討できる研修課程も含められたらどうかと感じた。
・今後、「利用の地域移行」は大きな課題であり、介護分野ならではの連携のありかたが知りたいところである。 ・講義内容は大変よかった。具体例を当事者から沢山聞けることが貴重。
・地域自立支援協議会との関わりについてイメージがわきづらかった。
実践報告のところは私には難しかった。
・関係機関と連携を取らなければならないということはわかるが、たとえば教育機関と連携をとるためにはどうしたらよいかなど、方策を提示してもらえるとよい。また、地域自立支援協議会は名ばかりである。活性化を図るためにはどうすればよいか、先進的な市町村の方に発表してもらえるとよかったかと思う。
・1~3は、重複している内容があるため、整理したほうがよい。また、講師よって表現の捉えに違いがあるため、かえって理解の妨げになったりした。
・医療分野との連携、情報の提供についてもう少しふれてほしい。相談支援専門員の領域と重なる部分があったが、その点が明確になった説明があるとなお良かった。
・かなり成熟した事例を取り上げられているので参考にはなるが、なかなかうまく連携がとれずに行き詰まりを感じている参加者も多いので、ヒントになるような話しが聞ければと思う。
・内容は興味深いものが多いが、盛りだくさんであった。
・ここでの事例は全分野に共通することではないので向かないのでは。
・実践報告の説明が専門的すぎ、難しかった。
・資料ばかりであまり内容がない。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・当事者を交えながら、アセスメントからのプロセス管理までの一連の流れの研修
・本人の意思も施設生活の継続を希望され、障害がとても重いケースで家族・親戚からも疎外されている方の入所施設における個別支援計画について考えてみたかった。
・策定まではできてもそれ以降のプロセスがおろそかになっているというたびたびの指摘にも関わらず、演習での時間は少なすぎたように思う。
・療養介護や生活介護では意思能力に課題のある利用者が多いので、意向の引き出し方・確認の手続き、主訴とニーズの違いなど具体的な課題について深められないだろうか。
・介護分野ではアセスメントが特に難しいと感じているが、その辺のところをもう少し詳しく説明してほしかった。事例報告はポイントを明確にしてもらえるともっとわかりやすかった。
・4つの事例が発表されたが、なかなか理解することはできない。短時間では難しい。身体障害と知的障害を1事例ずつ説明することが適当と思われる。
・ファシリテーターの実践報告が多い。1つぐらいでよい。
・事例について、各障害の特性に配慮したポイントなどが絞り込まれたものが提示されるとよりわかりやすいように思う。
・施設の現状を踏まえて、実際の個別支援計画の流れが理解できた。
・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい
・地域移行や在宅の例のとどまらず、施設の実感の伴った例も提示した方がよい。
・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。
・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。
・資料ばかりであまり内容がない。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。
・一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切であると思うが、研修では充分な時間が取れなかったように思う。また、その他にも記録をつける視点についても研修できればと思った。
・アセスメント編、個別計画編は一気に行うのではなく、別々に進める。
・サビ管の役割といった部分では見えにくかったのではないか。
・特に改善の必要はなし(来年度は知的障害者の例で行えるとよい。)
・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)
・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。
・扱ったケースが、身体障害者のケースだったため、知的の施設の方にはイメージつきにくかった。
・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい
・事例を県研修で使えるモデル的なものにしてほしい。
・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。
・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。
・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。
・一連のプロセスを行う中で、モニタリングやサービスのチェックが大切であると思うが、研修では充分な時間が取れなかったように思う。できれば施設入所継続の事例や困難事例の検討もしたい。
・計画内容に正解はないとは思うが、それだけに納得・消化の実感がなかった。
・ロールプレーは代表者による模擬形式でよいのでは
・できれば受講生全員がサビ管の役割を体験できれば良いのでは。
・特に改善の必要はなし。(ただし参加する方が同じ場合があるため、事例は同じようなものでも変えたほうがよいと思われる。)
・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。
・実践の取り組み例(身近な例)が分かりやすい
・事例を県研修で使えるモデル的なものにしてほしい。
・もっと時間が欲しかった。
・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。
・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。
・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。
・生活ニーズに基づいたケア支援計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供していくためのプロセスについての研修課程も大切ではないかと感じている。
・白い紙ではなく、ある程度項目を区切ったもののほうが短時間に議論するときにまとめやすい。
・都道府県における研修への企画・運営に関するより具体的な助言の時間があるとさらに良いか。
・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)
・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。
・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。
・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。
・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・より具体的な事例をもとに、経験を重ねスキル向上がはかれる研修が求められる。
・生活ニーズに基づいたケア支援計画にそって、複数のサービスを一体的・総合的に提供していくためのプロセスについての研修課程も大切ではないかと感じている。
・白い紙ではなく、ある程度項目を区切ったもののほうが短時間に議論するときにまとめやすい。
・都道府県における研修への企画・運営に関するより具体的な助言の時間があるとさらに良いか。
・他グループの様子も見れるように進めたほうがよい。他者比較は参考になる。また、ホワイトボードの利用があると意見をまとめやすいし、トークを集中できる。(自県で実践して、良かった)
・各機関の状況が感じられよかった。現状でも良いのでは。
・演習の話し合う時間が少なかった。次々と作業に追われて時間が不足した。地域移行や在宅の例にとどまらず施設の実感の伴った例も提示した方がよい。
・ここでわかりやすい事例があれば良いのでは。
・プレゼンテーションに時間がかかり、グループメンバーとの議論が深まらなかった。
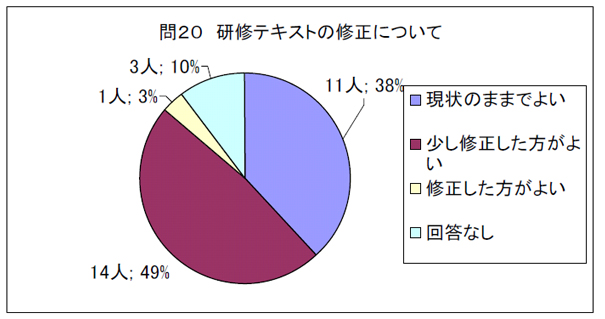
問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・相談支援従事者との役割分担を明確にする必要があるように感じている。サビ管としての業務の視点だけでなく、他事業所の担当者との調整も含むと、相談支援従事者とかなり重なりあう部分があり、しっかりとしたサビ管としての業務を明確にできないものか。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・法の改正に合わせて変えていく。
・地域自立支援協議会への参画の仕方について、資料を増やしていただきたい。
・まず、内容を厳選し、現在の30パーセントで説明をする。そのためにポイントを絞る必要がある。
・共通の視点として、内容が重複しているので、整理したほうがよい。また、講義タイトルごとに簡単に見開きできるよう編集したほうがよい。またテキスト全体の目次も必要。1では、「仕事の流儀」は必要かな?
・事業の内容が示されているが、各事業すべて示された資料があるとなお良いと思う。
・昨年度同様に県の研修ではDVDを使用したいので、新しいものが欲しい。
2.サービス提供のプロセスと管理
・再アセスメントの単元の時間を検討してほしい。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・P15の図はもっと立体的な表現のほうがリアルに伝わるのではないでしょうか。また、アセスメントが機械的な聞き取りや能力調査のようにそれ自体が自己目的化されないよう補足が必要と思われる。
・相談支援事業とサービス管理責任者の役割がごちゃごちゃになっている。内容をサービス管理責任者の研修に合わせて作成することが必要かと思う。
・1と重複しているので、整理したほうがよいのでは。
・全体の流れがわかりやすい。管理の実施方法を具体的に膨らませたものがあると助かる。
・本人中心の考え方をきちんと押さえておく必要性。本来あるべき状況からミスポジション論の活用は有効であると思う。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・ネットワーク作りについての研修内容も検討されてはどうか。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・この分野が一番内容が多い。これだけ多いととこがポイントかもわからず、どこに何が書いてあるかもわからない。
・サービス提供職員、サビ管、地域移行推進員、相談支援専門員らと地域自立支援協議会との連携やら各自の役割分担について、もっと分かりやすい内容にしてほしい。
・カタカナは簡単な和訳が欲しい。
・パワーポイントの資料が多いと感じた。絞ったほうがいいのでは。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・生活介護でかかえる多くの重度の障害者。日々介助に追われている事例も導入する必要があるのでは。
・家族・親戚からも疎外され、施設生活の継続を希望される方の生活の質を考えた入所施設における個別支援計画 について検討できる内容が入れられないか。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・生活介護・療養介護の分野では、やはり意思確認がむずかしい利用者の意向を確認する方法、手続きが大きな課 題だと思いますので、その考え方等を例示してもらえるとありがたい。共通講義以上の深まりが見られないように感じ ました。
・内容を厳選することは上記に同じである。4つの事例についてはそれぞれが書き方が異なっており、当日に理解する ことは困難である。また、重症心身障害児の事例については、国の研修で発表すべき事例かどうかを吟味することも 必要である。この事例から支援者の動きがまったく見えない。
・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい
・生活・療養介護の特性が整理されて示されていると良い。共通の講義部分にあるので必要がないのかも知れない が、サービス提供の管理の際の視点・技術などにもふれてあると良い。
・県の研修で使用する際は、国・県の方向性が統一されていないために、講義の進行が難しかった。
・分野別の講義・演習では地域移行や在宅の例と施設生活の例を提示した方がよい。施設現場での支援を個別支援 計画におとすことで、QOLの向上、支援の専門性アップ、チーム連携に展開していく。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・入所施設が事業移行を検討されるのは、ほとんどが生活介護ではないかと思う。そのようなことから、入所施設で生活を続けられる方への個別支援計画について充分に検討できる研修内容も必要ではないか。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・アセスメント、モニタリングを一気に進める演習でないほうが良い。
・事例の多少の手直しが必要である。社会福祉士の取得に向けての取り組みについても多少一般的な要素が不足している。また、生活介護というサービスの事例のほうがよかったのではないかと思われる。
・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい
・知的のケースを身体のケースにより、イメージするときのギャップが強い。
・実践のモデル例
・話し合いの時間を多くもつために県での研修では宿題を前もって提示した。つまり、個人ワークの時間を短縮して検
討時間を増やした。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・講義時間を短縮し、もう少し単元(個別支援計画作成)の時間を増やせないか。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい
・知的のケースを身体のケースにより、イメージするときのギャップが強い。
・実践のモデル例
・実感の伴った演習の実施、各施設で使用している個別支援計画をもってきてもらい事例発表する。自分たちの支援計画を修正できる演習もいいのではないか。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・基本的にサービス管理責任者は、事業所内における支援計画を作成することになるので、ケアマネジメントは行われないようにも思われるが、地域移行については、医療機関や企業・学校だけでなく、さまざまな事業所とのネットワークも必要となるため、その点について今後検討してほしい。
・内容については特にない。量が多く講義中の扱いがやや困難であった。
・アセスメント、モニタリングを一気に進める演習でないほうが良い。
・4~7については、多様な演習方法が記載されていてもよいのでは。演習方法のツールを知りたい
・事後研修は絶対に必要。研修した成果が現場で生かされているかの実態把握をしてもらわないと
意味がないと思う。
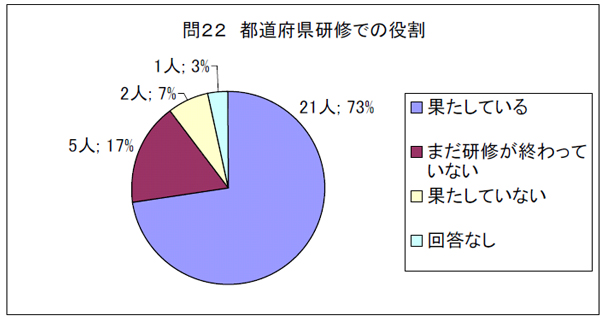
問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題
・障害分野でケアマネジメントを行っている人材が限られ、本業とのバランスを組みながら研修を企画運営している。一部の人材にしわ寄せがいっている。
・予想はついていた訳ですが、受講者の力量に違いがあり、物足りなかった人、わからないまま過ぎてしまった人などあったように思います。グループ編成や演習の進め方には配慮したつもりなのですが。
・私自身まだ未熟で、個別支援計画に係る理念をきちっと伝えられない現実に打ちのめされています。重度の障害を抱える人たちの個別支援計画について、どう改革していくのか。新しい理論(ICF,エンパワメント)らしさをどう組み立てていくかが、上手く説明できていません。
・情報不足あり、もっと地域移行の事例を紹介できたらと思っています。
・自分自身の知識・経験が未熟
・入所施設の実態の中で、どのようにケアマネジメントを定着させるか。あまりの責任や業務の多さに行き詰まりを覚えているのでは。
・都道府県に「障害者自立支援研修委員会」(仮称)のような組織を作ることもひとつではないかと考えている。また、研修については、外部委託も考えられるが、そのときには職業団体(社会福祉士会等)ではなく、身体・知的・精神・育成会等の都道府県各協会とも親密に連携し、講師の育成に努めたらどうか。
・私は研修の内容の計画・準備に専念することができた。この点については良かったが、それでも国研修受講決定から開催までがあまりにあわただしく、また勤務する職場の理解がなければできないと実感した。
・2回の研修が終了し、県内にはサビ管が各事業所に存在し、個別支援計画といったプロセスの管理もある程度浸透していくのかと思われる。すでに、サビ管になっている人のグレードアップの研修も今後必要か
・想定を大きく上回る参加希望があり、急遽2回にわけて実施。(移行予定が不明の事業所には辞退していただいた)会場確保に苦慮。国研修から時間がなくオリジナルの事例が用意できない。
国研修のような上質の印刷テキストが配布できない。
・生活介護分野では知的障害関係者が多く身体障害者関係が少ないため、療養介護としての講師の派遣や具体的な支援内容についての深い講義の提供が難しい。
・療養介護に関する知識不足で、実状への理解がないまま、個別支援計画作成を中心として受講者に 演習していただきましたが、各現場へのサジェスションがどの程度のものなのか?が不明です。
○サービス提供の継続性という現実の中で、評価と個別支援計画の再作成において、本人ニーズに添った(個別性)サービス提供の質の向上とマンネリ化防止(同様の計画の繰り返し)の合意を得るための具体事例の提示をどうするかですが、カリキュラムの構成上、難しいと思っています。
・現任研修やフォローアップ研修の必要性を感じる。
・国の研修をそのまま県に下ろすことは難しい。より具体的な実践が必要である。また、千葉県では6名の講師で介護を受け持ったが、その講師に講習の趣旨と方向性を理解していただくことが非常に難しい。また、受講生のレベルの差が大きく、大変である。
・今年度の研修は、県の担当者を中心に各分野の指導者養成研修受講者で何回かの打合せ会議を持ち、共通講義および3分野別講義での講師については、外部講師を依頼した。分野においては、研修受講者が少なく演習グループが複数の構成ができなかった。
・日常業務と平行しながらのため、かなりのオーバーワークとなる。また、他の所属職員とのチームワークのため、ミーティングなどの日程調整が難しい。ここがきちんとできると、しっかりとした内容がつくれる。本県では、行政担当者との連携もよく、昨年以上に機会を作るように働きかけながら実施している。
・支援の大きな流れ、各障害の特性が非常に多彩な分野であり、研修の目的、習得してもらうべき内容にどう絞り込むか、苦労している。
・県の研修内容が指導者研修と若干違うこと。介護領域の幅の広さの中でどのような視点で進めていくか。
・県と法人の定例的な打ち合わせが必要
・アセスメントの重要性についてしっかり講義、演習できる講師が不足している。相談支援従事者研修の内容の充実が望まれる。
・受講者の施設の障害種類や組織上の地位の違いがある中で、サービス管理責任者の明確な権限を説明しにくい。
・当県は社会福祉士会が県より委託を受け伝達研修を実施しています。伝達研修は昨年度の受講者がケアマネの講師もしており、その方を中心に行われました。ロールプレイ等の仕切役は自分が行いました。また、本研修で連携が強調されたこともあり、連携を求めるグループワークを挿んで実施する、アセスメントはブレストやKJ法などを取り入れる等、主旨は同様でも中央とは違うカラーを出し工夫して行いました。受講者の層はとしては昨年度は施設長等が多かったが、2年目になると本来の実務の担当者が増えました。
・地域生活(身体)の受講者はほとんどいない。生活介護の受講者人数が多くて、今後も増える予定であるので、国の研修の受講枠を増やして欲しい。
・多数の参加者を2名(H18、H19の受講者)で指導しなければならないため不安です。講義が苦手なためどのように話していけばわかりやすいか分からない。全国研修で県での研修企画についてもう少し具体的に指導して欲しかった。
・積み上げが不足している(個別支援計画を立てたことがない)受講者もあり、レベルをどこに置くか。上級研修も必要。更新研修、現任研修があればよ。
・県の担当者について温度差があると聞いている。福井県では県の研修担当者と協働できた。
演習などきめ細やかな対応が出来ない。現時点では対応出来る県職員が少ない。
県レベルでの実践の積み上げがない。
・介護分野を担当したのですが療養介護と生活介護との新体系事業移行の進み方の違い、障害者自立支援法への取り組み
・考え方の違いに戸惑うことがある。
・身障の機能訓練事業所が当県は1カ所でグループ演習にならない。
Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について
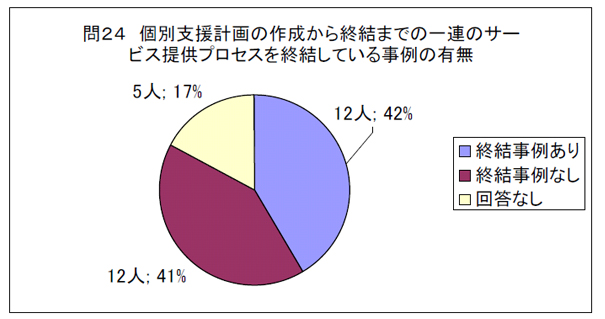
| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 受付時、または随時 | |
| ・ | 利用者の主訴の受付や関係作りに滞りが見られる時。継続利用者については、定期の終了評価後。 | |
| ・ | 入所後これ以降は6か月ごとに見直しを行う | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメントの視点、家族との調整、関係機関との連携。 | |
| ・ | 受付時はサービス提供職員とともに情報収集することもある。担当者からの報告、相談を受けて一緒に情報収集することもある。 | |
| ・ | 利用者と職員が良好な関係が築けるように双方別にして話をしていく。 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | アセスメントの視点、家族との調整、関係機関との連携。 | |
| ・ | 入所後これ以降は6か月ごとに見直しを行う | |
| ・ | アセスメント内容と状態像がマッチングしていないとき | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | その利用者の希望と可能性を十分吟味したものになっているかを検討する。 | |
| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |
| ・ | ニーズの整理表の提出時期を提示し提出してもらい、チェツクをしている。必要に応じて個別的に助言や指導をして いる。 |
|
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | その利用者の希望と可能性を十分吟味したものになっているかを検討する。 | |
| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |
| ・ | ニーズの整理表の提出時期を提示し提出してもらい、チェツクをしている。必要に応じて個別的に助言や指導をしている。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 定期の会議およびミーティングまたは個別的な助言・指導を通して | |
| ・ | 年度の前期と後期に提出してもらい、チェツクをしている。緊急の場合は随時リーダーに確認している。必要に応じて個別的に助言や指導をしている。 | |
| ・ | 評価の視点において指導・助言を行う | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | ケース記録の月所見、日々の引継ぎの場、利用者本人及び環境の変化時。 | |
| ・ | 個別支援計画がうまく実施されているかを定期的にチェックし、それができていないと判断をされたとき。 | |
| ・ | 計画と実施内容が乖離し始めた段階 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 支援経過を見守りながら、適宜のタイミングで個別助言から。 | |
| ・ | 進捗状況や実際の状況をリーダーや主任に確認をする等して情報を得ている。必要に応じて指導や助言をリーダか個別にし、必要に応じてケース会議の開催 | |
| ・ | 月に1度開催されるケース会議で指導をする。また、早急に対応を迫られる場合には、介護長と相談をして対応する。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | モニタリングのタイミングが遅れているとき ・内容が不明なとき | |
| ・ | 6か月ごとの見直しに合わせて実施 または、療養、入院また、環境変化によりご本人の状況が変した際。 |
|
| ・ | モニタリングをチームアプローチで実施。短期3ヶ月、長期6ヶ月 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 関係職種の招集、ご本人を交えての検討会を開催 | |
| ・ | 担当者から一人ひとりの支援計画の実施状況を報告してもらい、担当者の意見、その他のスタッフの意見等を聞きながら全員で評価し、必要に応じて修正する。 | |
| ・ | 本人の状態や環境等に変化があったときには、話し合いを持ち計画を修正する。また、定期的なカンファレンス時に多職種で見直しを行う。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 6ヶ月ごとの見直しにあわせて実施 | |
| ・ | 基本的には1年間が終了するときに、実施する。 | |
| ・ | 退所に向けた取り組み報告が随時あり、本人・家族の最終的・具体的な合意形成が確認されたとき | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | チームリーダーを通しながら、ケア会議を招集する | |
| ・ | 関係職種の招集、ご本人を交えての検討会を開催 | |
| ・ | 提出時期(月日)を提示しているが、終了というより継続や短期目標の修正や支援内容記述を具体的にと個別的に助言や指導をしている。 | |
| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 聞き取り、情報収集の段階 | |
| ・ | 初回相談のアポイント報告時 相談終了後 |
|
| ・ | 利用者・家族の意向や要望やその他の情報が得られたとき | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 個別支援計画の作成について、一連の流れを介護職員を中心に研修し、スムーズにできるよう働きかけを行う。 | |
| ・ | サービス提供職員と一緒に情報収集する。もしくは現場責任者から報告を受ける。 | |
| ・ | 定期の会議およびミーティング、文書連絡による情報交換および適宜の個別的な助言・指導を通して | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 主には入所時、または個別支援計画策定前の情報収集時 | |
| ・ | サービス提供職員の1次アセスメン後 | |
| ・ | ニーズの整理表を全員提出した時必要に応じてアセスが必要な時に(新規・追加) | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 各部署が領域を担当し実施(ex 医務は健康面、ケアワーカーは生活面) | |
| ・ | 教育、医療など必要であれば二次アセスメントにて情報収集。 | |
| ・ | 担当者もしくは関係職員を集めて問題整理を行う。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 6か月ごとの見直しに合わせて実施 | |
| ・ | ラフプラン作成後 | |
| ・ | 利用決定時(暫定) 年度初め 利用者の状況の変化に合わせて。 |
|
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | グループのリーダーを中心に話し合いをしてもらい、実践の優先順位を決定している。サビ管研修終了者へチェックを部分的に任せ助言・指導 | |
| ・ | 作成したものを検討し必要であれば修正などを働きかける。 | |
| ・ | 状況により行政も含む関係機関を交えての支援会議 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 随時(計画に示した期間にそって) | |
| ・ | 個別支援計画がうまく実施されているかを定期的に確認をする。 | |
| ・ | 利用者の状態に変化があったとき。月1回の担当者会議のとき。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 利用者の所属する部署内と関係する他部署との関係調整を行っています。 | |
| ・ | サービス担当者会議の招集 | |
| ・ | うまくいっていないと判断されたときに必要に応じて担当者の会議を開催し、利用者を交えて修正意見を述べる。また、毎月開かれるケース会議で意見を述べる。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 定期(6ヶ月)の評価および利用者の状態や意向の変化が見られるとき。 | |
| ・ | 2ヶ月に1度、班の会議が開かれるので、そのときに参加し、助言をする。 | |
| ・ | 年度の中間時期に行なわれる担当者会議において、4回に分けて実施。 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 状況により行政を含む関係機関を交えての支援会議の実施 | |
| ・ | 職員からの報告を受けた時は、ミニカンファレンスを随時行う。必要時は多職種にも集まってもらうか、個別に意見を求め、現場主任などと話し合いを持つ。 | |
| ・ | 班会議に参加し、一員として意見を言う。また、利用者サイドでの意見を参考にし、双方の考えが食い違っていないかを確認する。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 目標の到達度状況を確認して | |
| ・ | 終了に向けた具体的な取り組みを開始する前、その経過のなか | |
| ・ | 定期(12ヶ月)および終結(退所・地域移行等)に係るとき。 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | チームリーダーと連携しながら個別支援計画会議を開催する。 | |
| ・ | 各部署、各職種を召集し、支援の役割分担をみんなで確認 | |
| ・ | リーダーを中心にグループで話し合う。リーダー会議に報告。リーダー会議は常に報告と記録がある。 | |
| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 本人の主訴が不明なときや必要とされる情報が不明なとき | |
| ・ | 入所、在宅いずれにおいても必要と思われた時。外部機関との連携はまだ十分に図られていない | |
| ・ | 関係機関の情報が不十分、不足しているとき | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 本人承諾をとりながら関係者とやり取りする | |
| ・ | 医師、看護師、OT、STなどに相談、召集を依頼することもある。 | |
| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 相談担当者からの相談や報告を受け、必要と判断したとき | |
| ・ | 専門職や他機関での情報の必要性が有ると判断したとき | |
| ・ | 知的や精神の重複障害で、本人の意見の聞き取りがうまくできないとき | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |
| ・ | 施設内の専門職からの情報や地域関係機関に連絡。研修会等で人との繋がりを積極的にして情報を得ている。 | |
| ・ | 多種多様な機関から再度情報提供を求める。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 例年、次年度の個別支援計画作成に向けて、2~3月の支援会議にて検討しています。 | |
| ・ | 事業所としての暫定案が作成されたとき | |
| ・ | 状況により行政を含む関係機関を交えての支援会議を実施。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 医師、看護師、OT、STなどに相談、召集を依頼することもある。 | |
| ・ | 家族に連絡し、意見を聞く。また、看護師や医師の意見を聞く。 | |
| ・ | 社会福祉士会の事務局や地域の社協・県や県外市町村のワーカーや障害福祉課担当者、医療関係・地域の学校や住民・他施設関係との連携 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | ケース記録の月所見、日々の引継ぎの場、利用者本人及び環境の変化時。 | |
| ・ | 実施から数日、利用調整が必要と判断したとき | |
| ・ | 共通認識がずれ始めたとき | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 利用者の所属する部署内と関係する他部署との関係調整を行っています。 | |
| ・ | 外部からの歯科衛生士・PT・音楽療法士・インストラクター等が個別支援計画に担当者としてや職員指導者として参入し、連携を図っている。地域住民や、小中高大学校との年間計画で連携 | |
| ・ | 再度アセスメントを含め検証する。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | カンファレンス時、必要があればいつでも | |
| ・ | 施設側で中間評価が終了した時点で本人の意見を聞くことができない場合 | |
| ・ | 担当者が判断に迷っているとき 担当者が状況の変化を見逃しているとき |
|
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | モニタリング等の会議参加の依頼や定期的な訪問を行う | |
| ・ | カンファレンス時に各職種に参加してもらい、プランを持ち寄り支援計画と同時に見直しを行う。 | |
| ・ | 担当者への助言、情報提供、機関担当者会議 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 経過が良く、次のステップへすすむ場合、プランの変更が必要な場合 | |
| ・ | 施設側で終了時評価が終了した時点 | |
| ・ | 終了の方向検討の段階 方針として確認された以後随時 |
|
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント表・個別支援計画を活用し、本人家族の同意を得て情報の共有 本人に同行するなどして機関同士の直接面談。その前後での電話、直接交渉など |
|
| ・ | 家族や事業所内の関係部門・医療・専門職等へは、直接的に連携を図り、事業所外については、事業所の窓口を通して連携を図る。 | |
| ・ | 支援会議を通じて話し合う。 | |
問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。
・関係機関等との連携が必要な場合、情報を共有し、チームアプローチができる環境を整える。
・施設外における社会資源の利用や地域生活に関する相談については、相談支援センターの相談支援従事者と連 携し、必ず定期的に調整会議を行い、問題や課題を共有し、チームとして支援をすることに努めている。
・施設内には相談支援専門員は不在であり、施設内にける相談については生活支援員が担当している。また、地域の相談専門員とは、まだ地域移行等についての連携はなく、ショートステイ利用等に関する情報交換、連携また状況に応じてケア会議等への参加にとどまる。
・これからの課題
・事業のサービス利用の相談、終了の窓口の役割と実際のサービス提供、サービス利用中の本人担当業務全般。
・直接的な関わりは、ありません。
・当施設には相談支援専門員が存在しない。
・サービス管理責任者は主に事業所内の利用者を対象とし、相談支援専門員は、主に事業所外の地域の利用者を対象としている。
・ケースバイケースだが、主には利用者が入所中か在宅かで分担している。しかし、精神の退院促進事業については、協働作業で行っている。
・通園事業の場合は、地域の資源などの活用が必要になる相談の場合は、相談支援専門員に繋いでいる。
・相談調査担当のセクションがある
・お互いに相談受付や外部との連絡等、一緒に行っています。
・新規の相談業務や地域への訪問なども、すべて相談支援専門員が担っている。地域関係から施設利用の場合などは連絡相談がある。
・まだ新体系に事業移行されていないため、サービス管理責任者は配置されていません。
問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。
・事業所内で移行した部門に指導監査が入り、サービス管理責任者が対応しましたが、支援計画書の作り方やモニタリングについて細かい指摘がいろいろあったとのこと、ただ、3日間の研修で学んだ事ではそこまで網羅しきれない、とのことでした。本県は圧倒的に旧体系の施設が多く、その日に備えてとの事から受講する人が多い現状ですが、今後現にサビ管として仕事をする人が増えてくれば、フォローアップ研修等も必要なのでは。
・まだ新体系へ移行をしていないため、現段階では課題も見えにくいですが、施設の中での位置づけの明確化と、関係機関との連携が大きな課題だと思います。
・研修を受講しただけで、配置していいのか、もっと多くの経験や知識や技術が」求められているように感じます。
・1.相談支援従事者とサービス管理責任者の違いについて。2.業務内容の明確化。3.サービス管理責任者現任研修の検討。4.理事長及び施設長のサービス管理責任者の業務に対する理解。5.個別支援計画作成における各担当職員との連携と調整会議のあり方。6.個別の指導を含めた支援員の能力開発に関わる人事労務管理能力の向上。7.サービス管理責任者に係わる介護報酬の新設。
・療護のサビ管については、いかにサービスを知りつくし、施設外との連携をうまく図っていくかということだと感じます。長年療護の職員として勤務し、自己(施設内)完結の限界を身にしみて感じているからです。外部との連携、自己完結からの脱却は施設サービスの質の向上にもつながると感じます。
またサビ管の仕事が組織内において認知されて初めて本来の機能を果たせるのでは、と感じます。
・今、園は今後の体制がはっきり定まっていないため、新体系への移行を模索中の段階にある。地域移行を進める中で、職員、利用者、保護者の勉強会を計画し、サービス管理責任者として、どのように今後仕事、役割をこなしていくかが課題と思われる。
・事業所のサービス提供の仕組みが確立していないなかで「責任」が重過ぎる。
管理者がその役割を正しく認識できているとはかぎらない。
事業所の職制制度とのミスマッチはないか。
支援員の力量によってはそのその業務の肩代わりを求められることがある。
利用者60名に1人(生活介護)は専任とはいえ、あまりに非現実的な配置基準。
都道府県の指導監査は書面チェックによるため、現場の事務負担感から形式主義にならないか。
・サビ管を管理する立場の人が存在しないのに等しいと思われるので、いかにモチベーションを保つかが課題だと思います。また、人的に余裕のない職場環境に身をおくサビ管が殆どだと思うのですが、一人であらゆることに配慮しながら判断、行動しなければならないため、精神的ストレスが多くなると思います。そのためのサポート体制が今後の課題になってくると思います。
・○各関係部門や関係機関のサービス管理責任者との役割分担(例えば、個別支援計画のすり合わせまたは連動性をいかに確保して行くか?)○相談支援専門員との役割分担。○サービス管理責任者の質の向上により実効性のあるサービスの質の向上にいかに寄与し、一定以上上のレベルを担保できるか。○サービス管理責任者の役割に関する周囲の理解と仕事に応じたインセンティブの保障。
・サービス管理責任者は非常に重要な役目である。個別支援計画の作成だけでなく、事業所のサービス全体を把握しなければならない。例えば事業所のサービスを向上させるために介護サービスの統一化を図り、介護支援マニュアルを作成し、全ての職員がそれに準じてサービスが出来るように指導をしていく。また、事業所だから出来ないという視点ではなく、事業所だからこそ出来るというプラスの支援を考えていくことが重要である。さらに、利用者のために職員が努力することがある。職員の視点ではなく、利用者の味方になり、利用者の視点でサービスを考えていかなければならない。たとえ職員に批判的に言われようと、それを理論で説得し、サービスの向上を図っていく重要な役目である。
・障害者自立支援法に基づく、新事業体系における日中支援と居住支援における(他事業所等との)連携と役割分担。
サービス管理責任者と管理者・経営者との十分な意思疎通(管理者からのフォローアップ)
サービス提供職員へのマネジメントと助言・指導力(チームアプローチの実現)(人材の育成)
サービス管理責任者自身の仕事に対する自覚(自己啓発)(利用者本位のサービス提供理念)等
・本研修で示されている内容だけでも、多岐にわたっている。これを遂行するだけでもかなりのワーキングである。それに加え、実際には、利用者のサービス業務だけでない部分がかなりある。したがって、ここらの業務分担を制度上からもきちんと捉えた職域を作っていくことが大切ではないかといえる。この部分を事業所のみの判断に委ねていくだけでは、サビ管エンジンはガソリン切れか、燃えつきかになってしまう恐れがある。サビ管の重要性は当然ながら、サビ管のサポート体制も同様に重要だといえる。
・事業所内で、充分に役割を果たすためには、サービス管理責任者の任務・位置付けが他職員、管理者にも具体的に認識されることも、重要な課題である。個別支援計画作成の具体的手法が向上し、各事業所で一定の質が保持できること。(障害種別、各 事業所別、さらには個々により違いがあるので、ツールを統一することは無理があるだろうが)職員集団の中で機能しなければならないことを考えると、実践を積み重ねる中で標準化を図り、その標準の質を向上させ職員に実感として示せるものを作り上げる力量を持つことと、遂行していくための人間性が課題となる。大変な業務であると考えるので、メンタルヘルスのあり方の検討や、福祉施設が安心を持って働ける職場になることが必要だと考える。
・施設の中で新制度をより現実的にとらえ、役割を確立していくことが大きな課題。
・自立支援協議会の設置により、より一層の役割が発揮される。法人内での個別支援計画等のサービス管理のプロセス等は確立されている。
・基礎資格として、介護支援専門員が必要。受講者の能力に差がありすぎる。受講すればサービス管理責任者の資格が取れるが、本当に業務をこなすことができるか不安。
・外部との連絡や連携と支援の目標の明確化と持続性と連続など、利用者に必要なことであり、以前から判っていたことであるが、準備期間が短くすぐに実行されることは難しいが、これからの福祉にとって必要なことであるので、利用者を中心とした有効な福祉のために努力していかねばならない。多くの人は、ミーティングでの利用者の問題発見、課題、方法をを見いだす方法に慣れておらず、長年の漠然とした個人的指導に慣れているので、サービス管理責任者を中心としたチームの協議における方法が定着するには、月日を要すると思う。規模が小さい施設なので、話し合いもしやすく、方針も統一しやすいために文書化せずにやってきたので、改善していきたい。
・まだ、新体系に移行しておらず暗中模索の状況です。しかしながら、可能なかぎり受講する方針のもと、施設長をはじめ職員のかなりの数(6名)が伝達研修を受講しました。そして、全体像を把握しています。ただ、書類や体制等はこれからの課題です。
・当施設では入所利用者が前向きに地域で生活したいと希望される方はほとんどおられず、可能な限り施設での生活を望まれています。そのような方々の理由としては、地域が高齢者への支援体制はできているが、障害者への支援体制ができていないことや住宅がないこと。また、入所していれば衣食住の確保と24時間体制でのケアができており安心ということがあげられていました。施設には最重度の方の生活の場となっておりますので、介護分野を療養介護、施設入所、その他種別に分けてもらい、それぞれの種別でのサービス管理責任者として学べるようにしていただきたいと思います。
今回の県での研修会の開催については、広域であるためにサービス管理責任者として伝達ができるかが不安です。
・相談支援の仕事に携わっている者としてサービス管理責任者がヶマネジメント手法を理解し、地域支援の事業所の窓口として機能することに期待している。そのような仕組みづくりに努力したいと思う。県下でサービス管理責任者の研修を実施したが、分野ごとの差異はあるものの個別支援計画を立てたことのない受講者もあり、また法人(事業所)管理者の姿勢も現実的にはサービス管理責任者に及ぼす影響が大きいと思われるため、現任研修や法人(事業所)管理者への研修なども必要だと思う。
・サービス管理責任者の役割と責任は重いが、業務としては大変やりがいのある仕事と言えると思います。しかし、大変な業務という認識が強く、モチベーションはそれほどあっていないようです。というのは、個別支援計画は質の高い支援と展開していくという認識が少ないのではと思います。なぜなら、個別支援計画を現場サイドで実際にどう組み立てたらいいのか、理解されていない現状だからです。個別支援計画の意義を認識して活用していくと、次第にサービスの質が高くなっていき、自然に現場は活気づいて職員の個々のモチベーションが上がるはずです。そしてチームワークや専門性のツールにもなっていくのです。つまり、個別支援計画とは、施設職員が利用者とのかかわりのなかで感じた必要性や、願いからスタートされるべきでのもので、本来の意義である利用者の思いや要望を吸い上げたものだからです。そして、今までの現場での支援が全部否定されるものではなく、支援がただ継続されていくのではなくて、支援内容がアップしていくものだと実感すべきです。しかし現在の研修では、管理者から支援計画立案経験のない職員まで、具体的に個別支援計画がイメージできない人も含まれいます。そうした状況では、地域移行や在宅の例では人ごとな所があり、なおさら理解が自分のものとしてイメージできないかもしれません。研修を終了しても実際の施設に戻って、職員をどのように指導していけばいいかがわからないのが実態ではないでしょうか。そのためには研修内容の検討の他に、研修実施後の修了者の実践把握、つまり施設に戻ってどのようにしているか、個別支援計画体制はと、研修の効果測定が必要かと考えます。現場に沿った個別支援というものを事後研修は絶対必要です。成果が現場で活かされているかの事態把握をしないと、実践では演習のようにうまく行かないと悩み、それが抱え込みになりついに放置になると思います。また、施設へのアドバイザー派遣、横のつながりによる支え、専門機関のアドバイス等も必要かと思います。つまり、研修自体ももマネジメントの仕組みを当てはめて、振り返ることが自戒として自分自身にも感じております。
・サービス管理責任者の全国共通の立場・仕事内容の明確化が、各事業所に理解され行き届くことが必要だと思います。
・支援職員の意識啓発、資質向上のための教育力。インフォーマルな支援関係の再構築を重視したマネジメント。
・施設においては、サービス管理責任者としての地位よりも施設内の役職としての地位の方が強い位置づけになっている。
【地域生活(身体)分野】集計結果
Ⅰ 回答者の事業所等について
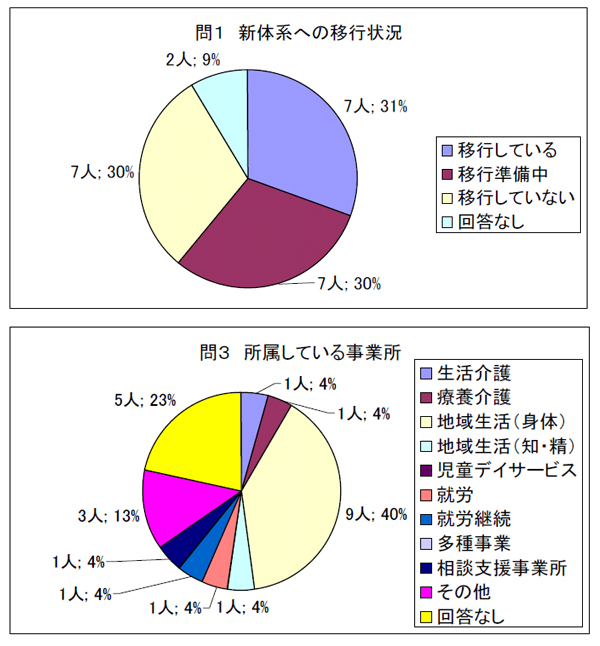
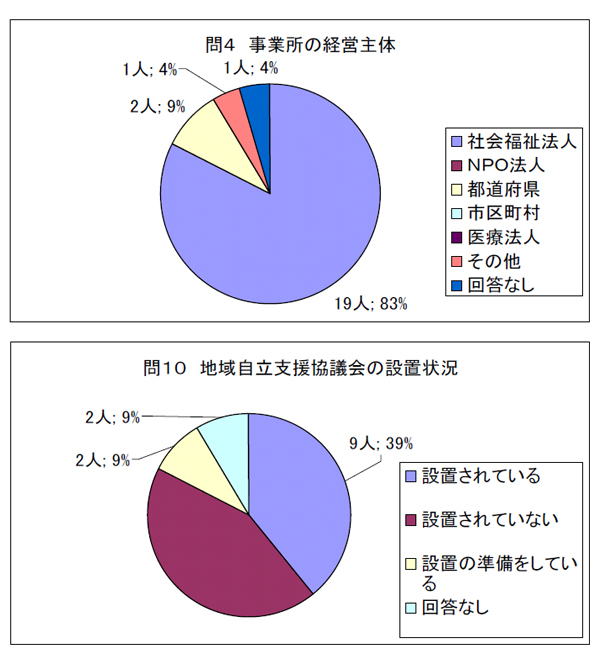
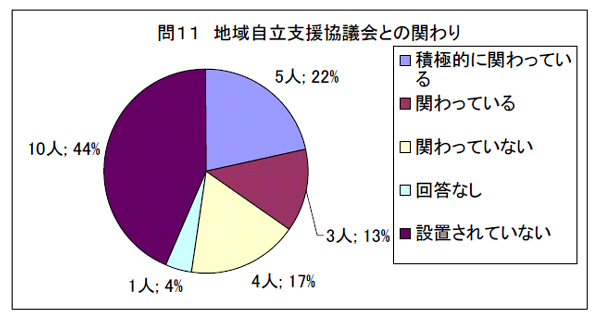
Ⅱ 国の指導者研修の内容について
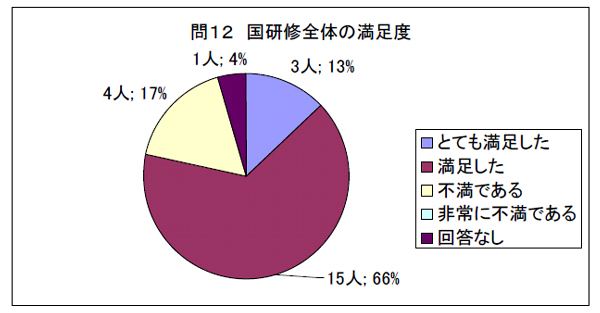
問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由
・サービス管理責任者の役割をはじめ、サービス管理のプロセス等理解しやすく、各地事例等も交え良かったと思い ます。
・サービス管理の重要性を知るとともに、各分野に分かれての研修内容では全国からの参加者と演習を行う中でスー パーバイズを受けるよい機会であったと思う。
・第一線の講師から講義を受けることができたから
・特に分野別の講義・演習におおむね満足できたので。時間が足りなく感じたのが非常に残念。
・サービス管理責任者の位置づけや役割などの基本的な知識を身につけることができた。
・サービス管理責任者の役割・仕事内容等を理解することができた。
・サービス管理責任者の役割として支援を必要とされている方の生活を支える重要性が理解できた。
・サービスのプロセスを管理することの意義を理解することができました。
・総合リハセンター以外で機能訓練事業を行なうという希望者が、県内で少なくとも4箇所ある。
それら事業者への研修内容を加えてほしい。
・現場でご活躍している倫理性の高い方たちの中での研修だったので、良い刺激になりました。
・ただ漠然としていたサビ管像が明確化でき、且つ地域ごとの格差・取り組みの違いを知ることで今後のサービス提供 に活かせる知識が身に付いたため。
・特に分野別の研修では、グループごとに担当指導官が付いていただき、きめ細かな実習ができました。課題等がそ の場ですぐに確認でき、グループ討議にも反映することができるなど、より実践的な研修であったと思います。
・サービス管理責任者の役割、責任、そして、事例を通じてサービス提供のプロセス管理の実際を再認識できた。
・地域の実情とかけ離れている。現状から力量をどのように引き上げるのかの道筋がない。
・新体系移行準備中であり、参考になることが多くあった。
・県の現状に応じて推進状況が違い、全体に同じようにすすんではいないのでは。将来、肢体不自由児施設がどのよ うな方向に変わるのかが明確になっていないのでわからない状態。
・良く理解できた。
・研修を企画する側の立場でポイント等を伝えてほしかった。ss
・説明も分かりやすかった所と分野別研修も意見が出しやすく雰囲気もあり、良かった。
・研修内容が伝達しやすいようにと気配りが随所にみられたこと。
・国で企画していることが理解できた。
・サービス管理についての体系が明確になってきたこと。
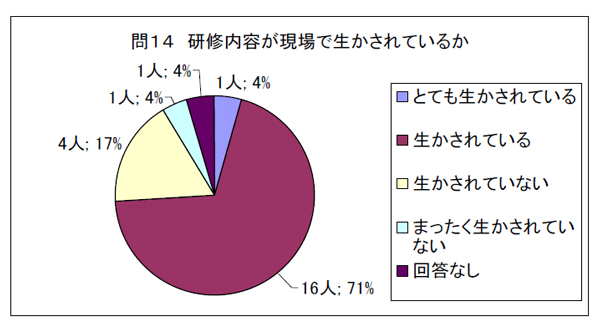
問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由
・サービス管理の役割、プロセスを理解していくことで、仕事していく上での意識は変わってきている。
・サービス提供を意識することで、自分なりに利用者個々の見方が丁寧にできるようになったと思うから。
・現場でタイムリーに助言できる
・利用者に対する自分の考えや思いがいつも自己中心的なのか、自己満足しているだけなのかという自問自答を繰り返していたが、研修に参加することで、悩み考えながら利用者とともに歩むことが大切だと感じたため、より積極的に支援ができるようになったと感じる。
・サービス管理責任者の業務に携わっていないため。
・分野別の「サービス提供の基本的姿勢」・「サービス提供の視点」・「サービス管理プロセスの実際」は大変参考になった。
・当施設は通過方の施設であるため、地域移行に向けた連携と、サービスの構築の基礎として役立っている。
・サービス提供職員に対して、サービス提供の各プロセスの意味を理解させるのに役立っています。
・もともと、研修内容と同様のことを事業所内で行っている。
・仕事を進めていく軸が見えたように思います。
・サービスはただ提供すればよいわけでなく、何を目的に・何時・どの様なアプローチが必要か常に考えることが身に付き従前以上に助言力・実践力が身に付いたこと、また、サービス内容については常に振り返るスタンスが大切であることがわかり、ポイントについても確認できたため。
・自分の法人でも今年4月より新体系に移行することとなっており、また、移行準備にも関わっている関係からとても貴重な経験と知識を得ることができ、移行に関しての課題整理やサビ管の重要性をより深く認識することができました。また、あわせて移行後の課題等も多く見つかり、研修で習得したことがきちんと実践できる体制作りの難しさ(職員の資質の向上等)に悩んでいます。
・研修報告を通じて、障害者自立支援法のポイント、サービス提供におけるプロセスについて職員に受け止めてもらえたと感じている。
・同程度のものを実施中
・個別支援計画の重要性を再確認し、ケースワークのスーパーバイザー的立場である自分にとっても他の職員を指導することに役立つ。
・現在、主に小児外来、入院の医療的リハビリテーションを中心としているため、今後の肢体不自由児施設のあり方を模索している。
・身更相に勤務しており、障害者の相談支援にあたっているため。
・役割の範囲について、ある程度理解できたため。
・まだ、旧制度で運営されているため。
・身体障害者更生指導所相談員の立場にあるため
・ツール等を使用している。
・新体系へ移行していないため、現組織だてとのずれがあるため。
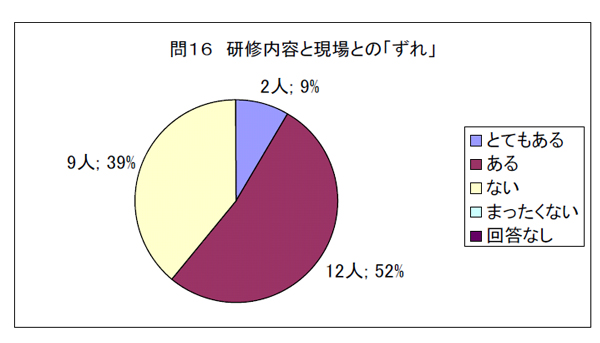
問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容
・新体系移行がまだのためか、サービス管理とは?というとらえ方、大切さに個人差を感じる。イメージが掴めないの か。
・事例の多くが施設利用者とずれがある
・「他の事業所・関係機関との連携が不可欠」と講義でも何度となく繰り返されていたが、現実は事業所ごとに考え方 が違っていたり、支援の方法が違っていることが多く、連携が非常に取りづらい。
・利用者の目標を尊重し、入所から退所までの具体的な支援内容を利用者に時間軸で示し、利用者と事業者が共に 到達目標に向かって協働していくこと。
・サービス提供職員において、サービス提供の一連の流れを意識した支援が十分でないように思います。
・個別支援計画について、事例より詳細に立て実施している。
・業界全体として、収入の面から離職していくスタッフが多いと思います。理念を持って仕事をする職員が少ないと、対人援助技術の職場はうまく機能しません。研修内容と言うよりは、いかんともしがたいところです。
・基本的な考え方そのものにずれがあるとは考えにくい現状ですが、利用者や、家族を取り巻く環境等によって大きく 変わる、もしくは今回学んだもの以前での取り組みに焦点が当たる場合もあり、なかなか研修通りとは行かない現実 もあるため。
・利用者本位、利用者中心の支援、サービス提供についての捉え方、サービス提供のプロセスの中で職員として具体 的にどのような役割を担っていくかという点について認識のずれがある。
・通常の施設運営に研修のような発想が全くない。
・サービス管理責任者の業務内容や責任ということは理解できるが、施設運営という視点から考えるとサービス提供量 と収入とバランスがとれていないと思う。
・現場ではまだ、サビ管本来の業務に携わっていない。
・サービスの更新を強く望まれ、次のステップに移行しずらいケースが多いと聞き及ぶ。
・モニタリング、中間評価の実施が難しい。
問18.国の指導者研修の内容で良かった点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・管理責任者の役割と責任の重さが非常にわかりやすかった。
・基本的なことの復習と、サービス管理責任者とは何か、ということが具体的に認識できたこと。
・サービス管理責任者の役割がほぼ理解できた。
・利用者・職員・関係機関等の調整役という立場が明確にされた点。・「流儀」として実践に基づく業務の紹介があった点。
・障害者自立支援法におけるサービス提供、サービス管理責任者について、サービス管理責任者の仕事の流儀、サービス管理責任者に求められる資質能力(資料)
・サービス管理責任者の資質と情報及び連携の重要性を理解できた。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・サビ管のイメージがついたこと。
・自立支援法上でサビ管がどのような位置付けかを再確認できたこと、また、障害者福祉のの中にあって重責を担うことが確認できたこと。
・自立支援法の基本的な意義とサビ管の役割をきちんと理解することができました。あわせて、サビ管の重要性を認識し、責任の重さを痛感しました。
・従来のサービス提供のあり方と障害者自立支援法の目指すサービス提供の違いがわかりやすく解説されていた。仕事の流儀が日常の業務の中でのサービス管理責任者としての心構えとして、とても参考になった。
・利用者に対する質の高いサービスが提供できるかで責任を果たせること。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・相談支援事業者不在の場合のサビ管の役割の範囲が理解出来た。
・新しいサービスが旧法からこのように変わるという話しが分かりやすく記載、説明された所。
・講義に実感と熱意が感じられた。
・役割について理解できた。
・サービス管理責任者の役割が明確化されたこと
2.サービス提供のプロセスと管理
・西駒郷の地域移行の取り組み等を踏まえ理解することが出来た。
・自分の施設と照らし合わせて講義を聞くことができた。
・プロセスの再確認ができた点。 ・地域以降の実践紹介。
・実践編が良かった。
・サービス提供のプロセス
・施設職員の意識を高めるための説明材料として役立っている。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・個別支援計画の実施の進捗状況の管理の意義。
・具体的な動きがわかった。
・支援プロセスに一定程度の基準が出来たことにより、一定水準を保っていくという国のスタンスを理解できたこと。
・相談支援から個別支援計画の作成、実施そして評価、修正、終了時評価と常に課題意識を持って取り組んでいく姿勢を学びました。
・サービス提供の基本的な考え方を念頭に置き、そのプロセスの過程における実施方法、留意点がよく理解できた。
・地域生活への移行プランの実際例を学べた。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・自分の認識を再認識できた。
・実際に行う段階ごとに整理してあった所。
・説明がやさしく丁寧にされていた点。
・ICFの考え方
3.サービス提供者と関係機関の連携
・各地の事例等と照らし合わせながら確認することができ参考になった。
・施設内だけでなく地域も巻き込んだ体制作りの重要性がよくわかった。
・「連携」することの重要性。それが良い支援につながることが理解できた。
・連携に必要な視点やヒントの紹介。
・実践編が良かった。
・関係機関との連携に関する考え方
・関係機関との連携についてフットワーク良く活動する事への自信となった。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・「連携の仕方がわからない」ということに関して参考になると考えます。
・自施設で完結するのではなく、ネットワークの必要性があらためて認識できた。
・連携がもたらす成果について、実践の報告を通し理解に結びついたこと。また、誰のためにどのような連携が必要か考えさせられたこと。
・専門的な関係機関と連携を密にしてサービスを提供していくことの重要性を認識しましたが、難しことでもあり今後の大きな課題と考えています。特に自立支援協議会との連携は参考にしていきたいと思います。
・関係機関との連携の重要性、連携不足による問題点、連携により改善される点、その中でのサービス管理責任者の役割がよく理解できた。
・自立と共生について地域の社会資源の活用がよく分かった。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・直接サービスを提供する側の役割としての範囲を確認できた。
・連携することでサービスが薄くならず充分な支援ができる。
・実例を交えての話しであった点。
・連携について理解できた。
・連携のあり方とそれによる効果について理解できたこと。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・具体的な例があったのでとても分かり易かった。
・サービス提供の基本的姿勢、サービス提供の視点
・モニタリングについては、相談支援専門員研修と同様で重要性が認識できた。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・医学的なアセスメントの仕方、視点
・具体的には自立訓練事業が対象と思われ、当センターにマッチした内容だった。
・上記1~3については理念や指針は同じであるが、関わる分野によってスタンスは大きく違い求められるものも違うことを痛感したこと。
・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。
・サービス提供のポイント、視点、個別支援計画作成におけるアセスメント、モニタリング技術について、具体的に理解できた。
・個別支援計画作成時の留意点はチェックする際に役立つ。
・具体例があげられていたので分かりやすい。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・身体(地域)に必要な視点を学んだ。
・1文章にわかりやすい例をつけ、説明して頂いた所。
・現実と照らし合わせて講義のあった点。
・事例についてニーズ把握ができていない印象はあった。
・サービス提供のポイントとサービス管理の基本的考え方
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・アセスメントから導き出す課題のまとめ方の視点がわかりやすかった。
・丁寧な説明
・全員でアセスメント内容を検討するのは有意義であった。
・グループの役割分担で「進行役」となり、職種やケアマネジメントの経験等の異なるメンバー間で意見交換を進めるよう努めた点。
・アセスメント項目の検討
・アセスメントについては、相談支援専門員のアセスメントと同様の内容であった。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・支援するためにはアセスメントが重要であるということをあらためて認識できた。
・演習形式で進められたため体得に結びついたこと。また、限られた情報の中で全体像を掴んでいく能力の必要性に気づくことが出来たこと。
・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。
・アセスメント編、個別支援計画編について、課題の整理、到達目標の設定、計画の修正・変更、終了時評価の手順、技術を事例演習を行うことでより実践的に学ぶことが出来た。また、異なる専門職間の情報交換ができ、サービス提供における視点の幅を広げることができた。
・個別支援計画作成までの過程を段階に分け、実践できたのが良かった。グループワークでの役割分担でリーダーシップ等の養成。
・グループで問題点について討論できた。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・ポイントを絞ったアセスメント項目の抽出が大切であった。
・全てはアセスメント、特に初期のアセスメントが大切であるという所。
・実際のケースにそった演習が行えたこと。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・計画書の様式が私にとっては目新しく、今後の参考になった。
・アセスメントから支援計画の導き方
・直接講師の先生に質問できたことが非常にありがたかった。
・頸髄損傷の事例であり、比較的イメージしやすかった点。
・個別支援計画書の作成
・支援を必要とする方を支援者が共通の視点から支援を行なう事が重要であり、これまでの福祉施設にありがちであった感覚による支援とは異なる具体的な援助が可能となった。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・個別支援計画とは「本人のニーズを支援者が十分に受け止め、その人の生活が少しでも豊かになれるよう、支援者の専門的な知識と本人家族の希望を反映させ、これらを一覧表にしたものである」 あらためて重要性を認識できた。
・個別支援計画を作成するプロセスが如何に重要であるかを痛感させられたこと。また、一つの目標達成に必要な機関・期間を設定していく必要性を確認できたこと。
・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。
・アセスメント編、個別支援計画編について、課題の整理、到達目標の設定、計画の修正・変更、終了時評価の手順、技術を事例演習を行うことでより実践的に学ぶことが出来た。また、異なる専門職間の情報交換ができ、サービス提供における視点の幅を広げることができた。
・個別ニーズに対しての支援の優先順位を決定することにより、合理的な支援ができることの理解。グループワープ効果
・グループで討論しながらアドバイスがもらえた。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・訓練計画の中の項目について機関設定の方法がわかった。
・段階を踏まえ、時間軸を必ず通すという所。
・実際のケースにそった演習が行えたこと。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・直接講師の先生に質問できたことが非常にありがたかった。
・頸髄損傷の事例であり、比較的イメージしやすかった点。
・指定事例の発展的な検証作業
・モニタリングと合わせて、定期的な確認と計画の更新が成功への道筋である事が認識できた。
・全般的な理解を得ることができて良かったと思います。
・個別支援計画を作成するからには実際のサービス内容が問われる。こういった、書面に残す手続きは作成者(サビ管)の責任感にも直結していくため、必要な作業であると認識できた。
・実際の事例を通じ、発展的な検証を行えたこと(実際のルーティンの中で行うことは相当に困難)。
・グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることができ、たいへん参考になりました。また、指導教官からの的確な指導(そのグループ討議の内容に見合った指導助言がとても有効に感じました)助言により、より分かりやすい演習となりました。サビ管の重要性と難しさを改めて認識することができました。
・事例におけるサービス内容のチェックを行うことで自らのサービス内容、提供に対する振り返りと修正、マネジメント方法について再確認できた。
・困難なケースについての着眼点や暫定契約について理解できた。グループワープ効果
・具体的症例の結果や失敗例なども学べたことでより幅が広がった。
・内容等、具体的であり、それなりに理解できた。
・自分の認識の再認識ができた。
・実際のケースにそった演習が行えたこと。
問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。
・支援費の請求管理に関する講義があればよい。
・流儀についても触れて頂き、分かりやすかったと思います。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・実際の事例に基づく説明がより分かりやすい。
・サービス管理責任者の負担がすごくあるような感じなので、「やりがいがある仕事」であること、プラスに捉えられる喜びを感じられるようにした内容に。
2.サービス提供のプロセスと管理
・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。
・種別が同じ事業所のサービス管理責任者業務に携わっている方の実践例の紹介を含むこと。
・西駒郷の実践は、この分野の内容とマッチしにくいようです。
・実際のサービス提供職員にどのようにアドバイスしていくか。(サービス管理責任者の視点で)
・事例も使われており、特に改善の必要はないと考えます。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・実際の事例に基づく説明がより分かりやすい。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・理想と現実のギャップがあまりにも大きい。実際にサビ管になった場合を考えると少し不安になった。
・種別が同じ事業所のサービス管理責任者業務に携わっている方の実践例の紹介を含むこと。
・県の研修に使いやすい内容に改善したほうが良いと思います。
・総合リハセンター以外で連携を行っている事例、事業所のモデルを紹介するなど。
・実践報告では実際に関係することが予想される機関の方にも話を聴けたらと考えます。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・相談支援専門員との連携をもう少し具体的に説明して欲しかった。
・内容が抽象的であった。
・(資料編)の説明を少し入れて欲しい。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・全体講義の中では、ICFの考え方やエンパワメントの視点が中心となっていたが、分野別講義になると事例等の説明の中でも中途障害の方の機能回復が中心となり医学的モデルが強い印象を受け、若干整合性としての矛盾を感じた。
・マイクの関係か部屋の構造の関係なのか、話が聞きづらくとても残念だった。
・アセスメントとモニタリングを分離し、まずはアセスメントの視点や技術を磨くことを重視した方がよい。
・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。
・アセスメント項目の例。あまり詳細なところにこだわってもいけないが、モデルがあってもよいか。
・「アセスメント項目の検討」という演習がありましたが、県の研修では行いませんでした。時間が少ない中での研修ですので、アセスメント項目は事前に示し、どのようにまとめていくかというやり方に時間を割いた方が良いと思いました。
・1~2の講義と重なる部分もあり、ここが少し気になりました。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・基本的にその分野はどのようなサービスをどれだけの人員で行う等、目的やコスト面の説明をもっとする必要があると思う。
・内容が抽象的であった。
・事例を多くの人から募ってはどうか。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・演習時間が短かかったこともあり、アセス項目の検討票や支援方針の策定表等のツールについては、的確に使いこなすには至らなかった。
・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。
・利用者の意向の尊重やエンパワメントなどの視点を確認しながらアセスメントを行えるよう、演習を進行管理すること。以下の支援計画やマネジメントも同様。
・シュミレーションに利用している事例に細かいミスがあるため、支援計画のシュミレーションを検討する資料としてはもう少し精度を高めたほうが良い。
・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。
・模擬の評価会議(個別支援会議)を行なうというのはどうか。
・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・もう少し時間が欲しかった。
・自分たちで事例を出し、それにあった研修にすべき。
・大きなポイントが事例に表面化している方が分かりやすい。
・個別支援計画はある程度立案できるとして、修正案等のグループワークから入ってもよいと思われた。
・アセスメント項目(小項目)についての検討ができれば良い。アセスメント項目について改善が必要では。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・サービス提供のプロセスを考えたとき、短い時間のでは一つの事例で継続的に検討していく方がグループ討議等行いやすい面があると思われた。
・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。
・シュミレーションに利用している事例に細かいミスがあるため、支援計画のシュミレーションを検討する資料としてはもう少し精度を高めたほうが良い。
・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。
・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・もう少し時間が欲しかった。
・学ぶべきポイントが不明瞭であった。
・事例のバージョンを幅広くする。サービスの格差など。
・支援計画書の目標の区分がわかりにくい。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・マネジメント内容に関する検討結果とサービス内容に関する検討結果を分け、記録する作業は時間的に非常に困難であった。
・有意義に過ごせた分、時間が足りなかったのが非常に残念。
・内容については、改善点は、特にありませんが、時間的な余裕がなかったと思います。
・5~7については演習時間が足りなかったという感想以外はありません。
・各県においての研修にあたって、教える立場として、分かりやすい具体的な指導助言方法のポイントを教えていただく内容の研修も取り入れてもらいたく思います。以下の設問についても同様の課題としてお願いします。また、分野においては各県での福祉行政やハード面での整備等が異なることも想定されるため、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れていただきたく思います。
・もう少し時間が欲しかった。
・学ぶべきポイントが不明瞭であった。
・他分野での演習のようにロールプレイ等取り入れても良かったのではと思った。
・チェック、マネジメントにより効果の得られたようなケースであっても良いかと考えました。
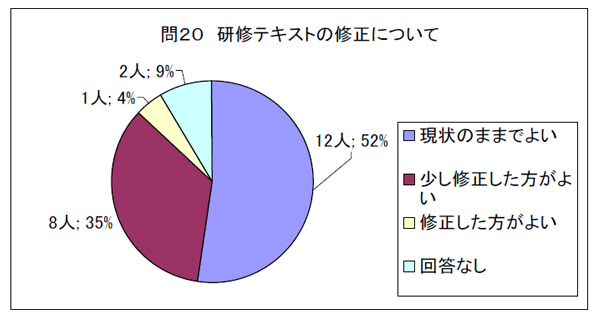
| 問21. | テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。 | |
|---|---|---|
| 1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割 | ||
| ・ | 支援費の請求管理についてを追加する。 | |
| ・ | 誤字脱字が多いのを直すことです。 | |
| 2.サービス提供のプロセスと管理 | ||
| ・ | 分かりやすい例を少し入れる。 | |
| 3.サービス提供者と関係機関の連携 | ||
| ・ | 問19であげたように、連携事例を加えたらどうか。(実際にそのような事例があるかどうかは不明) | |
| ・ | 実践報告に関係機関の方からの発言もあった方がよい | |
| 4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際 | ||
| ・ | ICFやエンパワメントの視点をもう少し強調した事例と、それに伴うアセスメントやモニタリングの実際の方法が学べるよう な内容であった方がよい。 | |
| ・ | 前年の資料を使われていたとのことなので、できるだけ新しいものが良いのでは。 | |
| ・ | 相談支援従事者研修と同様の様式によるアセスメントを確認したほうが効果的か。 | |
| ・ | 全体講義と重なる部分の修正 | |
| 5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編) | ||
| ・ | 事例を多岐に | |
| ・ | 相談支援従事者研修と同様の様式によるアセスメントを確認したほうが効果的か。 | |
| ・ | 4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |
| 6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編) | ||
| ・ | ・4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |
| 7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際 | ||
| ・ | 4が修正されれば時間的にもゆとりが出るのでは | |
問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題
・地域生活(身体)の分野は、移行事業所が少なく研修会参加者も少ない。
・個人的なことになりますが、経験年数が短い私が講師(今年度はサポーターとして参加)をすることに非常に抵抗感がある。研修を受講される方の多くは私よりも経験が長く、各施設の所長などもいらっしゃいます。来月、研修がありますが非常に不安です。良い勉強になるとは思うのですが。
・当然のことだが、ニーズのアセスメントや個別支援計画の作成(そのための視点)について、研修受講者間で基本的な理解に差がある。
・演習を行う場合、参加者の経験に差があるため、演習の内容や進行について気を遣う
・相談支援専門員研修との差異がはっきりしていない。
・限られた時間の中で行なわなければならないため、出来る限り指導者研修の内容を踏襲することとなりますが、県の 研修内容に使用しにくい内容があり、その部分をどのような内容で充当するかが課題です。
・以前の問にあるように、総合リハセンター以外で希望がある。どのように実施していくか悩ましい。
・基本的に忙しい人間が研修講師になっているため、どうしても体に鞭打っての研修になってしまいました。事務的な
部分についてはできる限り県のバックアップをいただき、研修に専念できるようになっていければと思います。
・国の研修の伝達研修的なものではなく、あくまでも地域の特性に配慮したものにすべきであることは言うまでもないが、分野別講義場面では特にこの点が難しかった。
・今後、この分野での受講者が少なくなっていくことが想定されるため隣県との共同開催も視野に入れて検討している。
・地域生活(身体)においては、受講者が18年度は0人、19年度は1人と希望が少なく、研修をどのように企画すべきかという問題がある。
・研修の意図、思考が困難な参加者がほとんど。
・分野によって研修人数に差があり、自分の受け持った分野は少人数で1グループで演習を行った。
・新体系へ準備中であり、具体的には実践していないので役割についてわからない。
・分野別演習におけるアドバイザーの確保が難しい。
・研修内容が各講師に委ねられており、かなり内容がバラつくと考える。
・地域生活(身体障害)の場合、実際にサービス管理責任者をする場面がないためか受講者が少ない。
・通所での支援が多く、個別支援計画がたてづらい。
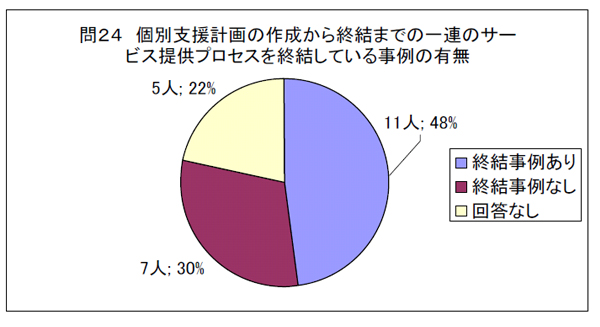
| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 問い合わせで相談受付票に記入された時 | |
| ・ | 予め設定された中期評価の時期(3ヵ月後くらい)・スーパーバイズミィーティング | |
| ・ | 利用者の発言内容に戸惑っている時、または利用者が退室(相談支援終了)後 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 1)係カンファレンス、評価会議2)職員の経験年数によって時期は変わる。2~6ヶ月に1回 | |
| ・ | 戸惑う場面では、施設としての発言をすることでサービス提供職員が自信がもてるよう、また相談支援後は振り返りを行い、サービス提供職員が気付けるような方法をとっている | |
| ・ | 入所相談受付票による報告を確認後必要追加情報チェック | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 1)入所相談から入所に至るまで 2)初期評価期間(初期評価までの3週間から6週間)終了時 | |
| ・ | アセスメント終了後 | |
| ・ | 計画立案時、計画を含めて指導 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント結果を聴き、何を捉えているか確認し、視野の広さや、視点の大切さを確認している | |
| ・ | サービス会議、計画提出の際に指導 | |
| ・ | 相談支援専門員による聞き取り調査と、”履歴書兼入所希望受付表”を家族及び本人に記入していただく。医療アセスメントとして別日に施設医の診察に入ってもらう。それを踏まえて相談支援専門員がアセスメント表にまとめる。この表をもとに入所会議にかけて利用を決定する。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス提供者が原案作成した時点 | |
| ・ | 初期評価会議終了後 | |
| ・ | 利用開始後、1ヵ月以内 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメントと計画書の連動性の視点から直接指導 | |
| ・ | 職員が利用者とかかわり始めた後、各職員からの意見を聞き、また利用者へも説明をしながら支援計画をまとめる。 | |
| ・ | 誰のための支援計画か確認し、業務上の都合を極力排除するよう助言する | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 支援計画の完成後すぐに | |
| ・ | 実施状況(利用者の反応)を見て思わしくない時など | |
| ・ | 随時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 各職員への提示。同時に利用者への提示。 | |
| ・ | 実施前に目的や成果の見立てを聴き、実施後には成果について聴く。今後の支援の改善点について話し合う | |
| ・ | 利用者ニーズに適しているか、総合的にチェック | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 定期(3ヶ月) | |
| ・ | 入所日から2か月目に実施。(期間が1年の場合) | |
| ・ | 計画書の評価の際、またご利用者の状況・ニーズの変化があった際に随時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 係カンファレンス、評価会議 | |
| ・ | 資料提出及びその結果に基づいて | |
| ・ | 入所日か15か月たった際、各訓練プログラム担当者より評価を集める。それに基づいてケアマネが情報をまとめ、ケース会議を開く。もちろん微調整はその都度行っている。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 目標が達成されたと評価された時 | |
| ・ | 契約終了約1ヶ月前 | |
| ・ | 終期評価会議 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | モニタリング表確認 | |
| ・ | 中間評価時に加え、支援が間違いなく終了しているか検証出来るよう働きかける。 | |
| ・ | 計画書を元に個別確認し、最終的に会議時に口頭で | |
| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 相談受付票作成後 | |
| ・ | 相談支援報告を受ける際 | |
| ・ | 相談調整係からの入所面接の相談時 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | スーパーバイザーとしての介入が主。 | |
| ・ | 問題点があれば、会議招集 | |
| ・ | 利用者の意向を聴く中で、どのような支援が必要か考えられるよう促し、必要な機関や職種について気付けるようアプローチしている | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | アセスメント終了時 | |
| ・ | すべてにおいて主に計画立案時および中間評価時 | |
| ・ | ミーティングの際 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント票を元に、情報の欠落がないか等確認。 | |
| ・ | 各職種別に支援の見立てはあるが、それが個人に対するアプローチであることを理解し、チームとして機能できるよう助言している | |
| ・ | すべてにおいてサービス会議が主である。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス提供者が計画書を作成した際 | |
| ・ | 初期評価会議終了後 | |
| ・ | 長期的な展望で悩んでいる時等 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント時にアドバイスをしているため、特に介入はしない。 | |
| ・ | 長期的な計画はここの支援計画が凝縮したものであるため、悩んだときは他職種とも相談するよう促す | |
| ・ | 評価会議 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス提供者間で日程のズレや問題が発生した場合 | |
| ・ | 計画実施導入時、実施時 | |
| ・ | 日常業務の中で随時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | サービス提供者に対し聞き取り | |
| ・ | サービス提供者へ口頭や、会議時に確認 | |
| ・ | 誰が何時行い、チームとしての結果に結びつけられるよう確認を行っている。また、実施に際しては一人の職員が抱え込まないよう、進捗状況の確認の際、助言するようにしている | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 予め予定された中期評価時。方針変更時。 | |
| ・ | 適宜 | |
| ・ | 計画書の評価の際、またご利用者の状況・ニーズの変化があった際に随時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 各プログラム担当者(看護師・OT・PT・ST・生活支援員・職業指導員等)、ケアマネが一堂に集まり、サビ管が全体的なとりまとめを行う。 | |
| ・ | サービス提供者、専門家、関係機関から聞き取り | |
| ・ | 資料作成時には支援してきた実績がもれなく記載できるよう振り返りを行う。会議時には「誰が行うはずだった」という議論ではなくチームとしての結果であるという視点を持つよう助言的に関わっている | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 終了予定月。 | |
| ・ | 資料作成時、会議時 | |
| ・ | 計画の終了時 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | ケアマネや各プログラム担当者からの報告を受け、退所後の生活が円滑に進むよう、最後の調整を行う。具体的に実行するのはケアマネ。 | |
| ・ | 中間評価時に加え、支援のプロセスの検証も行うようにし、各自がチームアプローチの視点で取り組めているかを検証している | |
| ・ | 計画書を元に個別確認し、最終的に会議にて確認 | |
| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス利用希望が出された時点 | |
| ・ | 相談支援センター等からの依頼 | |
| ・ | 相談調整係との入所面接前相談 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 自立訓練の事業所であるため、病院の医療ソーシャルワーカーと常に連携を取っている。 | |
| ・ | 相談支援事業所または実施機関に電話による問い合わせ | |
| ・ | 電話連絡 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス利用希望が出された時点 | |
| ・ | 初期評価期間終了時 | |
| ・ | 来所時 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 電話連絡や訪問させていただき直接話しを伺う。 | |
| ・ | 病院の場合、事前に医師から説明を受けているため、現時点の医療情報及び個別情報も貰いながら、面接を実施している。この連携が大事です! | |
| ・ | 利用者ご本人の了解を得て、関係機関に問い合わせ | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 初期評価会議終了時 | |
| ・ | 担当者からの相談を受けた時 | |
| ・ | 必要に応じて | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 医師等の専門職の見立てとずれがないか検証するようにしている | |
| ・ | 助言および関係職員への助言依頼 | |
| ・ | 評価会議で検討 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 随時。地域の事業者等に関しては、ケースにもよるが、(自宅がない方の場合)自宅が決まって、移動能力(方法)に見極めが付いた時点くらい。 | |
| ・ | 他施設への実習を行う場合は、ケアマネが他事業所とその都度連携を取っている。 | |
| ・ | 地域生活移行や施設転籍を利用者が希望された時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | ケアマネが、他事業所に連絡をいれ、施設見学及び実習の調整を行っている。状態の悪化や、支援方法に迷った際は、他病院への診察(精神科・リハ科など)につなげる。※高次脳機能障害の場合に多い。 | |
| ・ | 職員より、関係機関への連絡。進捗状況に応じて、自宅訪問への同行。 | |
| ・ | 必要な機関との関わりがなされているか検証し、独りよがりな支援となっていないか確認している。当然必要があれば連絡調整している | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 必要に応じて | |
| ・ | 会議前、会議時 | |
| ・ | 予定されていた中期評価時点か、方針変更の時点。 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | ケース会議への参加を要請 | |
| ・ | 高次脳機能障害の場合は、他病院にてMRIをとるなど専門医より画像所見も貰うこともあるが、たいていは自前で可能。 | |
| ・ | 必要な機関との調整は進んでいるか検討し会議に必要な情報が揃うよう配慮している。会議時には修正された計画内に連携が盛り込まれているか確認 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | センター及び対象者が支援の終了とした時 | |
| ・ | 退所予定月の評価会議。外部に関しては、退所予定月(または前月)くらい。 | |
| ・ | 他施設への移行前及び実習の際。 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | これまでの評価をまとめておき、必要な情報を移行先施設宛に情報提供している。 | |
| ・ | 地域生活移行支援に関しては、スタッフを交えてのカンファレンス | |
| ・ | 必要な機関との調整は進んでいるか検討し会議に必要な情報が揃うよう配慮している。会議時には連携がもたらした成果について確認している | |
問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。
・地域移行の際、相談支援専門員が各地にきっちり配置されているとは、限らないのでケースバイケースで連携を図っ ている。
・現状では相談支援専門員と関わることが皆無。
・相談支援事業所の相談支援専門員と特に役割分担はありません。
・平成21年4月から新体系(機能訓練)へ移行予定。平成20年4月から1年間は、準備期間として試行予定。当センターでは各専門職種を均等に3班にチーム編制し、チームが担当する利用者に対して責任をもって入所から退所ま でサービスを提供することにしている。
・同様に業務している。
・同じリハセンター内では、多くの場合、入所前相談から利用調整会議までが相談支援専門員の役割。地域の相談支援専門員とは、退所予定月前月くらいからの役割分担を行う。
・これまでの記載通り、インテークから施設利用直前までは、相談支援専門員(当センターは高次脳機能障害支援普 及事業として専任1名と兼務1名)が行う。
・現状は旧法施設支援を提供しているため、利用者が地域移行することが明確化した段階から相談支援専門員に繋ぐように努力しており、役割分担は明確です。今後居宅からの受け入れ(新法移行後)の中で多少の躓きは予測している現状です。
・現状では、利用者の地域生活移行に向け、利用者が移行を予定している相談支援専門員に連絡し、地域の社会資源、利用者の意向にそったサービスの活用法についてのケア会議で情報提供、検討してもらっている。
・施設利用中の本人の情報を伝えるとともに家族支援を協働している事例がある。
・相談支援専門員、サービス管理責任者の連携は常に必要と考える。
・利用開始及び終了時にケースを引き継ぐ(必要な人のみ)。地域での具体的計画の立案やサービス調整は相談支援専門員が担当する。
・施設の事業体系から相談支援専門員からの相談をあるいは支援依頼を受ける状況となっている。
問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。
・役割、責任が大きく重要なものであることは、今回の研修を通し非常に理解できた。反面、役割責任が多い分、抱えなければならない事項も出てくると思われるため、管理責任者向けのスキルアップのための研修や、他機関との連携等では相談支援専門員との役割分担も一定度明確にできるよう対策が必要と思われます。
・施設を出て、地域で生活するための相談支援事業者を含む社会環境がまだ充実していない
・多くの経験と多くの勉強。机上の論理だけではできない仕事であり、やはり経験や思いが必要。また、人格的にも優れ、利用者様にとって何が一番必要なのかを一緒に考えて、一緒に行動していけるということも大切だと思う。個人的にはもっともっと勉強と経験を積まねばならず、課題も多い。サビ管だけの研修などがあれば・・・と思う。
・マンパワーやコストといった事業所側の事情(制約)を勘案しつつ人材育成もしながら、利用者の意向・ニーズを的確につかみ、いかにサービスの質を高められるか、ということに絶えず心を砕いていかなければならない。そのためには気概と能力(知識・調整力・バランス感覚・交渉力など)が求められるが、やりがいのある半面、過酷でストレスフルな業務と考えている。
・一般的なことはいえませんが、当法人にあってはサービス管理責任者の技能をいかに高められるかが課題と思いま す。
・支援計画が利用者のニーズや将来の目標が反映された支援内容になっているのかのチェック体制。
支援計画が計画通り時間軸で遂行されているのか、各利用者の状況を日々確認できる体制づくり。
利用者の地域移行にむけて、地域の社会資源マップの整備や地域の関係機関や事業所との連携体制がうまく構築できるか。
・サービス管理責任者の業務は、相談支援専門員及び事業所の管理者の業務内容と同様であり、事業所内での位置づけが難しい。また、支援計画やモニタリング等についても、これまで施設で対応してきた相談支援専門員の業務と同様であるため、違いを示す事が難しい。
・管理責任者としては、職員への助言を強化することが、求められていると考える。各事業所とも同様であろうが、業務管理業務や宿舎管理業務、リハセンター内の他の事業の業務との仕事のバランスが難しい。
・責任の所在及び役割が明確になったということは、当事者の方にとって良いことだと思います。ただし、福祉業界として、介護職員が定着しない問題を抱えている以上は、まじめに働いている職員の負担感が増すだけである。 「サー ビス管理者はこうしましょう」という見本としては間違いないと思いますが、現実的に実行できるようにならないと、絵にかいたモチだと思います。
・地域格差を埋める、もしくはサービスの均衡を図る視点で考えたとき、サビ管の役割は大きく重責であると思われま す。介護保険制度でも叫ばれる「どの地域でも同等のサービス」という一定程度以上のサービス提供が原則になるわけで地域格差というハードルをどのように越えるかが一番大きな課題と考えます。利用する方々の権利と地域の実態の狭間で苦労することもあると思われます。また、当然のことながら業務量の多さ、自己実現の難しい実態を「連携」でクリアできるかは相当の不安を抱えています。
・指導者養成研修で習得した内容は、膨大なものがあり実際に現場で実践するためには課題も多いと考えます。サー ビス全体をうまく動かしていく責任者としての技術の習得と合わせて、職員からいかに信頼を得るかということが大き なポイントとなるのではないでしょうか。ただ、福祉職場においては、人材不足が大きな問題となりつつあり、いかにして職員の資質の向上を進めていくかがより大きな課題としてのしかかってきていることも事実です。サビ管だけが頑 張ってもどうしようもない現実があることも想定しつつ、福祉サービスの充実と底上げを目指してそれぞれのサビ管が 連携して努力していくことが必要と思います。県内での研修を受けた受講者からも不安の声は多くありました。現場の現状は厳しいものがあります。
・新体系移行に向け、利用者、家族、サービス提供職員とも意識改革が必要である。そして、サービス管理責任者とし ての役割について明確化し認知度を高めていくこと、そのための質を向上させていくことが課題であると考える。
・施設サービス終了後、施設サービス利用導入にあたってのフォローが必要となる。そのための費用の出所がない。
・事業所によっては、サービス管理責任者という立場で現場の直接処遇や事務的作業も兼ねなければ運営できないところが多く、結局利用者に影響してしまうのではないか。専門性が必要な立場であると思われるため、業務量に見合うコストが発生しても良いのではないか。
・現状ではサビ管についての業務は果たせていないので、実際の課題はわからないのですが、私の理学療法士としての経験や知識のみではおよびもつかない広い専門性が必要であるし、地域と連携してネットワークをつくる技量や器量もいると思います。より相談しやすいアドバイザーが必要です。
・情報の共有化をどのようにすればうまくできるのか。1施設のみならず、他機関、他施設との関わりをどのようにもっていくのかが課題となるだろう。
・各事業所によって能力や位置づけにバラつきが出てくることが予測されるため、一定のレベルを維持するための策は必要と考える。
・まだサービス管理責任者としての役割は果たせておりません。しかし、施設内の個別支援計画を作成するにあたり、研修で学んだことを取り入れながら広めていきたいと思っております。
・管理下の個別支援計画の関わり方や指導の質について管理数によって大きな差がでること。再契約を強く希望された場合の対処。
・地域の関係機関と具体的な連携をとっていくこと。私たちのところでは、相談機関とサビ管の顔合わせや研修を考えています。
・市区町村、関係機関との連携をいかに構築し、役割分担していくかが課題と考えます。対象者の年齢による介護保 険との関係についても同様に考えます。
【地域生活(知的・精神)分野】集計結果
Ⅰ 回答者の事業所等について
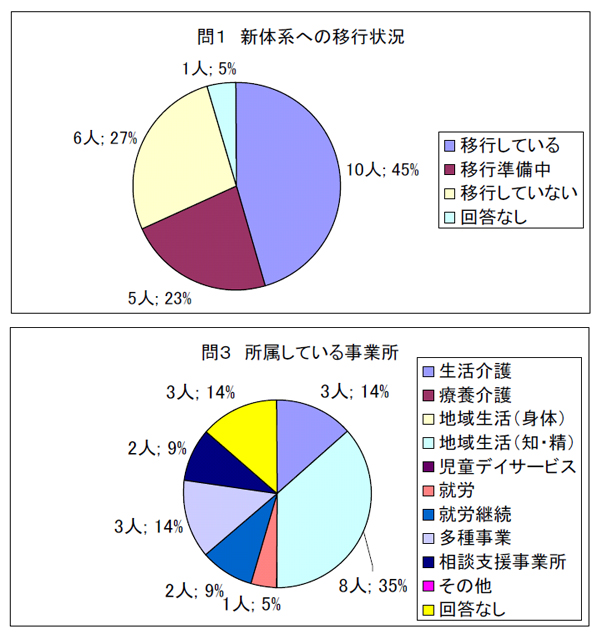
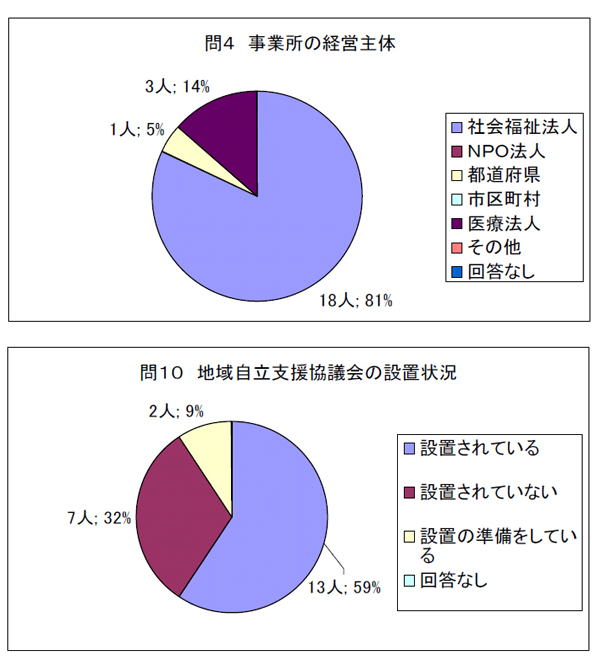
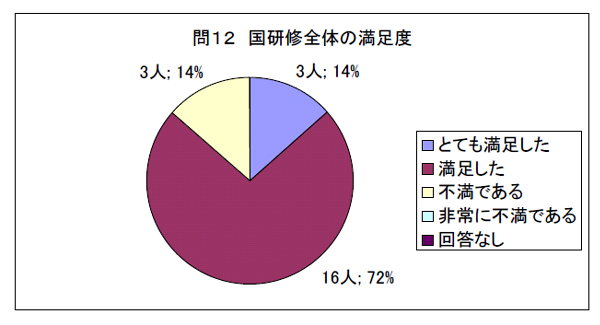
Ⅱ 国の指導者研修の内容について
問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由
・サービス管理責任者の役割が理解できた。
・従来の集団での画一的な援助から,福祉サービスの利用者一人一人ときちんと向き合うことの必要性に確信が持て ました。
・特に演習において、相談支援従事者研修との違いが見い出せなかった。県で研修を開催する際は、研修の特色を 出すことに苦労した。
・地域生活移行のプロセスが具体的に理解できた。長野県の事例等は参考になった。
・実際の個別支援計画の作成の仕方や個別支援計画とサービス利用計画の違いの説明が不十分に感じた。
・内容的に目新しい物ではありませんでしたが、サービス管理責任者としての基本姿勢等の再確認はできたと思いますので…。
・経営面と利用者中心のサービス提供管理といった一見矛盾してしまいがちなテーマについて、役割を分けて専門職としての位置づけをした国の意図とやる気を直接知ることができた。
・県の研修を受け、サービス管理責任者として働く中で、再度自分の業務を客観的に見直すことが出来た。多くの方 と意見交換する中で、いろいろな考え方と知ることができた。
・利用者ときちんと向き合うこと、聴くことの大切さと難しさ、個別支援計画に落としていかなければならないこと…気づかされ、基本に戻れたことがよかった。もう少し研修に余裕がほしい
・地域生活は相談支援事業所の関係が明確でないので、地域移行の研修にて施設のサービス管理責任者としての視点や相談支援専門員との違いや立場の違いをどのように明確に説明したらいいのか戸惑いました。相談支援専門員との連携をどのようにしていくのかを明確にしてほしいと思いました。
・講師の熱意を感じた。障害者自立支援法の真意を学べた。
・個別支援計画の重要性を改めて認識した。
・後からいただいたCDが良かった。
・演習において初めて顔を合わせるメンバーの中で、事例に基づき個別支援計画を立てていく課程でいかに自分が主体的に関わっていくかの大切さを感じた。それができないと自分の県で指導できないと感じた。
・サービス管理責任者の役割について学ぶことができたので。
・特に演習が視点も含めとても分かりやすかった。
・福祉に科学の要素を取り入れるという講義内容に感銘を受けた。
・社会福祉を取り巻く意識の変革の必要性と地域生活移行の重要性を痛感していた折の研修で結果として他県の受講者との差異があまり感じられなかったことがそういう社会になっているのだと感じた。
・参加してみてサービス管理業務に具体的なイメージをもつことができた。
・分野ごとに演習を中心とした組み立てであり理解しやすかったが、全体講義についてはもう少し時間をかけて詳しく聞きたかった。
・演習と模擬ケア会議が実践的でよかったです。あのコマにこの講習で養成したい内容が詰まっていたと感じました。
・制度の運用方法などで不明瞭だった点が整理されたこと。さらに、サービス管理責任者に求められている能力や運用の着眼点が明確になったこと。実践されている方の講義に十分納得した。
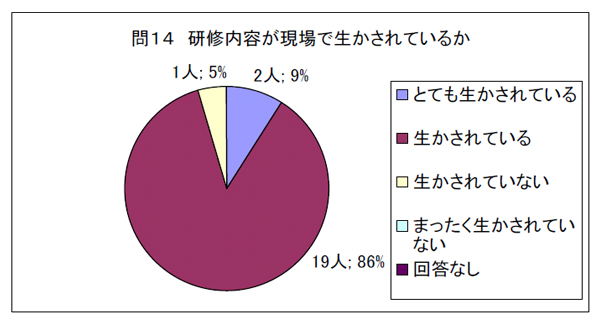
問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由
・サービス管理責任者としての意識で業務にあたるようになった。
・個別支援計画のあるべき姿やその管理の仕方等を,改めて学べた
・サービス管理責任者としてというより、この仕事に携わってる者の心構えとして勉強になった。
・「決めるのは私」という原則を個別支援計画の基本コンセプトにすることができた。
・計画を作る上での考え方のポイントは明確だった。
・既に移行しており、サービス管理責任者として従事していますので…。
・県研修を通して役割を明確に伝えることができたので。
・サービス管理責任者とワーカーを兼任する業務の中で、混同しがちな業務を、それぞれの役割を区分して、任務に携わることができるようになった。
・利用者が本当は何を望んでいるのか、どう支援して欲しいのかこの研修で“待つ”ことの大切さや誰のための支援計画なのか考えるようになった。しかし、なかなか支援計画が立てられないのが現実。
・研修をしないと、サービス管理責任者がどういう立場でどこまでの責任があり支援に対する権限があるのかがわからないが研修することで明確に理解し、利用者や他の施設職員に説明することができる。
・資料(特にパワーポイントによる説明)は良く評価されている。
・これまでの個別支援計画の内容の見直しや様式の変更等をおこない、現場の意識改革に努めている。
・利用者のニーズを聞こうとする思いが強くなった。
・自分だけの考えではなく、常に利用者主体に基づき、また、関係者からの意見を積極的に取り入れるようになった。
・国の書式を参考に事業所の計画書等の様式を作成している。
・福祉の機会について再確認することができ、自立支援法の基礎的な部分も理解できたため。
・新体系移行に向けて職員が共通したレベルで利用者をみつめることができるように助言が可能になったこと。
・個別支援計画の用紙を見直し学んだことを生かすことになったから。
・基本的な考え方や方向性について従事者に助言、説明できるが、利用者の実際の生活に結びつけ、支援を行うには少し時間を要する。
・勤務実態がサビ管と違います。それだけではいられません。研修を受けたことで概念的には整理されましたが、私の現実とはかけ離れています。しかし、計画を作るワークショップは実践的で、仕事に反映されています。
・私自身の職員へのかかわり方に変化(支援について丁寧に説明する・どのような目的でかかわるのかを分かりやすい言葉で伝えるなど)した。
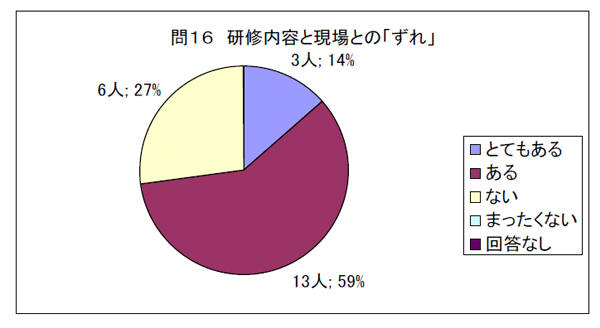
問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容
・地域移行については、まだまだ難しい状況がある。家族への働きかけについても積極的には困難な状況もある。地域の資源も不十分であるため、資源の整備も同時に行う必要がある。
・福祉サービスに従事する者として求められている職員の意識
・一事業所ではなく、地域で支援していくという視点。時間軸に沿った支援ができていなかったこと、支援に関する責任の所存が不明確であったこと等が、あらためて分かったこと。
・先進事例の臨場感を伝えるのが難しい。地域の実情で実効性が変わる。サービス管理は形式的になりがち、特に入所施設から地域生活に移行する場合は、本人の意向とともに事業所の戦略や自治体の意向等も重要な要素となる。
個々の現場職員が処遇以外の領域を計画することには現状では無理があるのでは。したがって、どうしてもトップダウンになりがち。組織としてどう方向性を共有していくかが問われる。逆にこの議論がなく個別支援計画を作成するとルーチンワークの繰り返しになりがちになると思う。
・国の研修の内容では実際に計画書は作成できない。県での研修では、かみ砕いた説明や記入法が必要とされた。
・内容的にある訳ではありません。しかし、現在の単価ではサービス管理責任者が純然と本来の業務ができるようにはなっておらず、結局は「片手間」的な印象が拭えないからです。
・人員配置上、余裕がある事業所や意識が高い受講生は研修内容を実行している状況や研修前からこのレベルを実行しているが、義務的な意識で受講している方には、研修自体が苦痛の様子で、何ら研修効果が期待できない。
・現場の人員配置に起因して、限られた職員で兼任をすることで、業務の境が希薄になる、自分のそのときの立場がどこにあるのかの認識を忘れてしまう
・職員の日々の業務量が多く、個別支援計画の共有や、変化についての情報共有がなかなかできない。施設長という立場でサビ官を任されるのは実際は中途半端に終わるようで良い支援ができないのではと悩んでいる。
・個別支援計画による支援者のネットワークがまだまだ弱いように思います。
・現在は支援員として仕事をしている。
・現場では、研修が学んだほど、丁寧に個別支援計画を立てる時間がない。
・実際の現場では、いまだに以前との変化に戸惑っている状況。
・地域に社会資源が少ないため活用が難しいため。
・スタッフの人員確保が出来ていないこと。計画どおりに進まない。
・理念や考え方に違いはないが地域の環境や情況によって支援しずらい部分もある。まず、現場が変わり、地域を変えていく努力が大事。
問18.国の指導者研修の内容で良かった点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・サービス管理責任者の役割とその考え方がはっきりと理解できた。
・時間軸に沿った支援ができていなかったこと、支援に関する責任の所存が不明確であったこと等が、あらためて分かったこと。個別支援計画の作成、実施のみで終わるのではなく、中間評価を経て終了時評価に至るまでのプロセスが大事であることを実感できたこと。特に、利用者の満足度についてのアンケートが参考になった。山田さんの実践に話がとても分かりやすく参考になった。特に、聞き取りの注意事項については、すぐに実践に使っていこうと思った。
・障害者自立支援法におけるサービス提供・・・分かりやすかった。仕事の流儀は具体的で良かった。
・ベーシック
・人員配置上、余裕がある事業所や意識が高い受講生は研修内容を実行している状況や研修前からこのレベルを実行しているが、義務的な意識で受講している方には、研修自体が苦痛の様子で、何ら研修効果が期待できない。
・法制度の中での、自分のおかれた立場の認識
・『制度は普遍的に支援は個別的に』を合言葉に『科学的な方法を持った支援』『客観的に共通性を持った支援』をベースにサービス提供を行う一連のプロセスPDCAサイクルの重要性が分った。役割として、質の高いサービスが提供されているかチェックするのであって、人を管理するのではないという事を忘れないようにしたい。
・障害者自立支援法の仕組みを理解し、サービスを提供していく理念や視点が明確に。パラダイムを
・大切なイメージがつかめた。
・職員のスーパーバイズの機能もサビ管には含まれることを知った。
・自立支援法について理解しやすかった。
・現場で携わる者としての見方が再認識されたことと障害の持てる意味が理解できた。
・自立支援法の中での位置づけ、業務に向かう姿勢、スタッフの育成
・障害者自立支援法におけるサービス提供の中で、近い将来を見据えた支援、達成目標の明確化、利用者中心の支援について、サービス管理責任者がどのように評価していくか、具体的に示していた点。ICFに関する例示が分かりやすかった。アセスメントの重要性について時間をとり説明されていた点。
2.サービス提供のプロセスと管理
・これまでの措置制度と障害者自立支援法の違いとサービス管理責任者の役割と進行管理についての理解ができた。
・連携を深めるということは、利用者と事業所にとって良いだけでなく、それが地域を作っていくことになることが理解できたこと。支援協議会を活用するのではなく、自ら自立支援協議会に入っていくという視点。
・西駒郷のプロセスは具体的で分かりやすかった。
・ベーシック
・サービス管理責任者の持つべき意識の理解 何を管理すべきなのかの再確認
・◎要望とニーズの捉え方。自己決定の尊重。出来る事に着目する(強さ)など基本がぶれないで計画を立てる。サービス内容のチェック。◎施設から地域移行のために丁寧な聞き取りとその人の言葉で整理。現地見学を実施しイメージを持ってもらう。支援計画はその人の必要性に応じて修正など具体的な話が聞けて良かった。
・インテークからアセスメント、支援計画、モニタリング、支援計画とよく理解できた。
・長野県の事例を通して、知的障害者が地域生活へ移行した具体例がよく分かった。
・できることに着目してのプランになっているか、がよく理解できた。
・スタンダードな話で分かりやすかった。
・過程が大切であることが理解できた。
・一連の流れと過程における業務
・実際に支援している方が、具体例(長野の例)を取り上げて説明していたのでイメージしやすかった
3.サービス提供者と関係機関の連携
・一つの事業所で完結するのではなく、他の機関との連携により、対象者への支援が行われる重要性について理解で
きた。
・山田さんの西駒郷での実践報告はとても参考になった。
・各地の政策は参考になった。西駒郷の紹介も具体的で参考になった。関先生の話は奥が深くてもっと聴きかかった。
・ベーシック
・日ごろの業務で、実践していると感じていた部分に、新たなヒントを得る フットワーク、ネットワーク、チームワークという要素
・よく利用者に「困った事があればSOSを出す」と言ってきたが、連携するということも同じだと思った。当然困る(課題について)前から支援計画を通して同じ言語で共有する事が大切なのだと。それには自分達だけで完結しないことが前提という事を意識したい。ないものはつくっていく(開発的機能)ためには、地域の連携が大切。総合相談室はその人の人生を分野は違っても必然的にトータルに支援する場所になっている。こことの連携もありだと思った。
・サービス調整会議の役割の理解ができた
・ネットワークの重要性が認識できた。
・完結型支援からオープン支援へ、ということでお互いが殻を破りそれぞれの専門性を生かしながら連携して支援するという支援を支援するという視点で、普段からの研鑽の必要性が大事な点。
・事例を通じて説明してくれたので良かった。
・今後の福祉には他機関との連携が必要であることが理解できた。
・県内でトータルな支援会議があるのかどうか認識不足なところもあるが、圏域では何度か参加したことがあり、必要性が高いと考える。
・実践を通して連携を考えるということが講義の中に入っており、人の社会生活を考える(知る・認識するなど)ことについて、社会福祉の観点から説明があったことで、日々の実践に関する学問的な裏づけを感じることが出来た。仕事の流儀について、非常に分かりやすかった。次回も残してもらいたい
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・実際の事例をとおしてアセスメントやモニタリングを行ったことで、サービスの提供者への助言も行いやすくなった。
・多角的な視点でよかったと思うが、内容に欲張りすぎな感があった。
・ベーシック
・事例を挙げて講義されたことで、現実的に感じられた
・資源に合わせるのではなく利用者に合わせるサービス。情報の伝達が、選択肢を広げると思った。それにはフットワーク、ネットワーク、チームワークを機能させる必要性を感じた。ロールプレイは耳からの学習から眼からも学べ、イメージが持てた。ケア会議を何度か行っているが、やはり当事者の方は心強いとの感想だった。
・モニタリングについて、理解が深まった。モニタリングは今現時点のアセスメント
・データに基づく客観的な分析というのが、具体的によくわかった。
・事例を通じての話もあってよく分かった。
・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。
・知的、精神分野での自立支援法の活用の仕方が理解できた。
・実際の場面で支援に関わっている講師の方なので資料にとらわれないで良かった。
・グループワークに移る前に、ロールプレイが実施されていた。サビ管と相談支援専門員の違いが明確で、その後のアセスメントや個別支援計画のグループワークが円滑にすすんだと思う。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・アセスメントの重要性を認識した。
・講師陣による支援会議の開催のロールプレイはとても良かった。
・模擬ケア会議を行ったところ。しかし県ではすでに実施していた。県でも好評である。
・ベーシック
・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た
・アセスメントと課題の整理にかなり時間を費やすが、実際時間を取る事が大事という事で安心した。事例を通して計画をたてたが、時間軸・短期目標は実現可能な内容で・本人と家族の要望も入れる・当事者の言葉で書く・住まいと日中活動の場をどうするか・支援計画は本人と確認しながら…参考になった。
・アセスメントについての理解ができた
・リアルニーズをどう捉えていくかを分析していく課程がよくわかった。
・グループワークはとても良い。
・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。
・そのように情報を集めるかなど理解できた。
・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・個別支援計画の重要性とそのポイントについて再確認ができました。
・武田さんの示したツールは良いと思った。生活暦の表は導入したいと思った。
・ベーシック
・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た
・修正はマイナスイメージが強いがプラスのイメージが大切。変化に対しては柔軟に。個人のところに着目しがちだが環境調整に絞って修正。モニタリングの結果新たなニーズが生じる。そのための修正も大切。
・高齢者から実施など、具体例が印象的
・モニタリングや中間評価の方法、また計画の修正・変更方法等が演習により学べた。
・皆の意見交換、協議の良さを学んだ。
・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。
・どのように個別支援計画をたて、活用し、利用者を支援できるかを理解できた。
・単一の人が集合してのグループダイナミックであるが、どのグループも結果的に共通しているということが多かった。
・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・サービス内容を定期的にチェックし、利用者本人の望む生活の実現を進行管理することの重要性を認識しました。
・フェイディングとナチュラルサポートの視点は就労支援では言われていたが、地域生活移行でも同じであることに
・ベーシック
・グループワークをすることで、多くの方のいろいろな考え方を聞くことが出来た
・自分の事業所だったらどう取り組むかの設問では、他の皆さんの考えが聞けなるほどと考えさせられる事が多々あり良かった。いろんな角度から利用者さんを見る事が見えなかった部分を知る事につながると思った。最後の意見交換も設けていただき、地域の実情も少し理解できた。
・サービス内容の利用者満足度とニーズから、モニタリング、アセスメントへの流れと理解
・模擬支援会議
・世話人や支援者が利用者に寄り添って支援していくのをうまくリードしながら導く視点。
・サービス管理責任者としての視点を考えるのが難しかった。
・実際に支援が行われた事例に基づいた説明が分かりやすかった。ロールプレイがとても良かった。
・実情にあったケアマネジメントをどう立てていくか理解できた。
・現状でよい。
・具体的な事例を基に検討でき理解しやすかった。
問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・サービス管理責任者の役割を明確にする必要があるように思います。より具体的な内容での説明があってもよいと思います。
・相談支援専門員との違いについて、もっと明確にしてほしい。
・仕事の流儀は面白かったが、サビ管の業務の業務分野ごとに時系列で説明するとよいのでは。
・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。
・成年後見制度等、実践的権利擁護論を入れて欲しい。サビ管ができる権利擁護を事例を通して紹介できる講師選定を願う。
・自立支援法はまだ様々な課題を抱えながらのスタート。現実は、サービスを利用するたびに1割負担の問題が発生。この問題を避けずにきちんと国の考えを示してほしい。サービス提供に格差があってはならないし、当事者の立場に立つということはどういうことなのか悩む。
・サービス管理責任者とソーシャルワークの視点
・自立支援法については特に触れなくても参加者は理解していると思う。サービス管理責任者の役割、必要性に絞ってもよいと思う。
・職員のスーパーバイズの方法を具体的に教えてほしい。
・サービス提供にかかる責任の所在について、事例を入れ込む等具体的なものを示さないと県に戻った際に難しいと思う。
・制度が始まってまだ1年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
・厚生労働省が出している基本の図(資料2~10)までや、基本的なサービスの仕組みは説明しなくてもいいと思う。その時間を他の説明にまわしてもいいのではないか。
2.サービス提供のプロセスと管理
・体系的な意味は十分理解できる内容となっていますが、具体の内容があった方がより理解が深まると思います。
・各事業所の見本となるような書式があったら良い。基本的に、書式は各事業所が使いやすいように作成するのが本来のあるべき姿と考えるが、実際に県で研修を行ってみて、書式が不十分な事業所があまりにも多かった。ワーキンググループでも更なるご検討をしていただきたい。
・具体的なツールを用いた実務の説明が欲しい。(演習にゆだねることかも知れないが)障害者ケアマネジメントの手法を再度分かりやすく説明して欲しい。
・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。
・成年後見制度等、実践的権利擁護論を入れて欲しい。サビ管ができる権利擁護を事例を通して紹介できる講師選定を願う。
・個別支援計画は全てサビ官が作成するものと思われている。誰がその人をよく知っているか。だれに主に作成してもらいたいのか。利用者を含めた協働作業ということを周知して欲しい。またサビ官の冷静で客観的な判断や情報量、コーディネートする力(センス)が求められると思う。
・権利擁護の視点
・制度が始まってまだ2年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
・もう少し時間があればよかったと感じる
3.サービス提供者と関係機関の連携
・自立支援協議会の連携と関係機関の連携の重要性が理解でましたが、具体事例についての連携の内容があればより理解でると思います。
・関先生の話は興味深いが難解である。分かりやすく時間をかけて話して欲しい。漠然とした理解に終わったように思う。
・「総論」ですので改善しようがないと思います。相談支援従事者との関係についてもう少し突っ込んだ話があると良かったと思います。
・地域でかかえる問題は地域で解決していくと。地域の力をどう意識するのか。支援会議の持ち方、個人情報について取り扱い方など実践例が聞きたい。自立支援協議会の機能(施策提言の場にもなるのか)をいかすには…各地域の情報を知りたい。
・ネットワークとして関係者がいかに機能していくのか
・漠然とした内容となっていたため、ここも具体的に提示あるものが多い方が良かった。
・大いに参考になった。
・制度が始まってまだ3年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
・なじみのない人に「社会福祉の原理」「相互依存性」の話をした時、伝わるかどうか疑問であるため、もう少し時間をとって分かりやすい方法(具体例を出す)を示したほうがいいと思った。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・サービス管理責任者としての役割の具体性を示して欲しいと思います。
・国の研修で、「基本はこれだ」というツールを示してくれるとありがたい。それを事業所でアレンジして使えるようなもの。あまり詳細であっても実際の業務では使えないので。デマンドとニーズの違いは大切、どうニーズとして把握するかのプロセスを分かりやすく。重度障害の人のアセスメントの具体的な方法、事例を知りたい。支援者が断弁せざるを得ないのであれば、どう本人の意向を確認するか、長野県の地域意向の本人確認はよくわかるが、日常生活の支援においてどう把握するかが現場では欲している。
・時間が限られたなかで、 モニタリングの実際までの講義は無かったかと思ったのですが…時間があればロールプレイの中に取り入れても良かったかと思う。
・精神・知的分野ではあったが、世の中で一番困難ケースとなっているのは、身体障がいの知的・精神の障がいを併せ持っている方々や、精神の障がいのために身体的な障害をもってしまった方々の支援が大変な場青が多く、地域支援は3障がい一緒に学び事が大切と思う。
・サービス管理責任評価についてもう少し具体的なものを聞かせて欲しかった。
・意識の共有ができ、大いに参考になった。
・制度が始まってまだ4年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・アセスメントの必要性について、具体的に示して欲しいと思います。
・地域移行のプロセスが主だったが、GHCHでのサービス管理の具体例の紹介がもっとあってもよい。
・演習全般で、文字だけの情報提供なのかで、イメージつかみにくく、またグループのメンバーも現実的に討論していく人数よりも多く、まとめにくい。時間をもう少し余計に取ってもらいたかった。
・個別支援計画表に落としていくのがなかなかできなかった。まして利用者の方にも分るようにするには、表の工夫が急務だと思った。ある程度の項目がすでに取り入れられていると、ずい分助かる。時間が無く最後までやれなかった。
・記録は大切だが、記録万能ではない。フットワークの大切さ
・良かった。
・制度が始まってまだ5年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
・グループワークを始める前に小ゲーム等を行い、それぞれの参加者が発言しやすいようリラックスさせる工夫も必要だと思う
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・個別支援計画の留意点について詳しい説明が必要と思いました。
・修正はとても大切。修正のタイミング、会議の持ち方、再アセスメント等時間をとって丁寧に説明して欲しい。
・課題の整理表は記入しづらかった。できれば他にも表があると比較しやすく、持ち帰って工夫できればと思う。個別支援計画表は2度目だが、時間が足りなかった。実際モデルを通して、評価していくのも良いのではと思う。
・失敗してこそ人は育つ
・良かった。
・制度が始まってまだ6年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・サービス内容について、より具体的なチェック方法を示して貰いたかったと思いました。
・権利擁護について、もう少し時間を割いてやっていただきたい。自事業所を含め、実際に機能していないところが少なくないように思われる。
・サビ管の業務としてのツールの提案があれば。例えばサビ管業務日誌の提示、日々の記録等
・事例を選択するのではなく、グループのファシリテーターの事例に基づき、検証したほうが良かったのでは。アドバイスもしやすかったと思う。
・利用者に受け入れられる支援内容をどのように創りあげるか
・演習でもスーパーバイズの練習がしたい。
・実際のマネジメントに役立つ内容であった。
・制度が始まってまだ7年が経過した段階なのでこれから修正する部分が明確になってくると思う。多くの意見、情報を集めながら進めて欲しい。
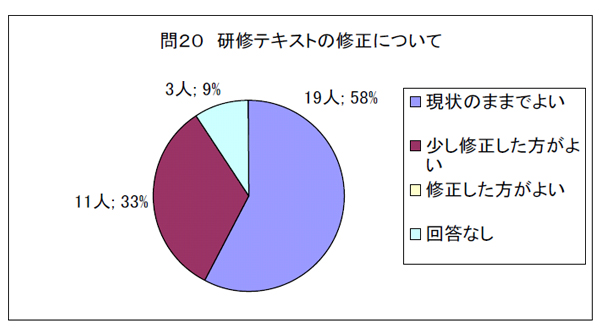
問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・サビ管の業務の説明が現状では内容不足。具体例を示して領域ごとに開設するように。
・成年後見制度、日常生活自立支援事業、行政不服申し立て等、事例を通した実践的権利擁護のしかたを入れるべきである。私個人として、実践的権利擁護を研究していて、実践現場とのずれを大きく感じる。実際のグループワークでも、「お金がないから成年後見につなげない、だから権利擁護ができない」等の誤った考え方が訂正されていかず、当たり前のこととして話が流れてしまうことは、日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ会員であり、社会福祉士国家試験受験対策講座「法学」を担当している私個人としてはどうしても耐えられない。~個人としての見解です~
・パワーポイントの原稿?がそのまま資料になっていて、文字数が少なくても1枚分となっているのは、もったいない。(1以外にも見られました)
・相談支援専門員との関係の整理
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
・サービス管理責任者の役割や必要性を中心にした内容にしてはと思う。
・サービス提供にかかる責任の所在について、事例を入れ込む等具体的なものを示さないと県に戻った際に難しいと思う。
・はっきりとした役割及び認識が十分ではないが、大いに必要であり、キーマンとなり得ると考えられる。
2.サービス提供のプロセスと管理
・ツールの提示 活用できるものを掲載
・成年後見制度、日常生活自立支援事業、行政不服申し立て等、事例を通した実践的権利擁護のしかたを入れるべきである。私個人として、実践的権利擁護を研究していて、実践現場とのずれを大きく感じる。実際のグループワークでも、「お金がないから成年後見につなげない、だから権利擁護ができない」等の誤った考え方が訂正されていかず、当たり前のこととして話が流れてしまうことは、日本社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ会員であり、社会福祉士国家試験受験対策講座「法学」を担当している私個人としてはどうしても耐えられない。~個人としての見解です~
・2だけではないのですが、横文字は確かにスマートで良いのですが、できればもう少し詳しく説明していただくとありがたいです。
・サービス管理責任者が提供するサービス計画の具体例
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
3.サービス提供者と関係機関の連携
・散文的な内容のように思う。内容的には良いと思うが、章立てなど工夫して欲しい。
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
・漠然とした内容となっていたため、ここも具体的に提示あるものが多い方が良かった。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・精神、知的で重複したり、形式が違うこともあって、聴いていて混乱した。
・基本的な事例と、困難事例にたいする実際
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・ツールモデルの掲載
・基本的な事例と、困難事例にたいする実際
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・ツールモデルの掲載 支援会議のモデル
・利用者がワクワクする個別計画立案タイムも必要では
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・サビ管の業務としてのツールの掲載があれば。例えばサビ管業務日誌の提示、日々の記録等
・でも、実際はというサービス内容と、マネジメントの現実を知る
・基本となる部分を毎年大切にしてほしい
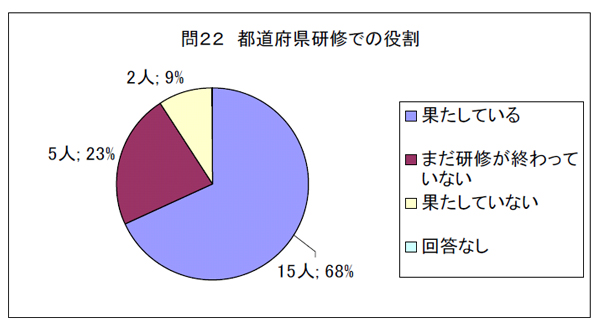
問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題
・受講生のレベルには、差があり内容も難しい。
・県の研修は終了しましたが,国の意向を正確に伝えられたかどうか不安はあります。講義・演習ともに,コピーをしたつもりですが。
・相談支援従事者研修との違いを出すこと。3会場計6日間の開催であったため、グループリーダーの確保(質と量)が大変だった。講師として準備の段階からかなりの日数を費やしたため、自事業所にもかなりの影響があった。
・受講者のレベルの問題 障害者ケアマネジメントを十分理解してない人が多く、基礎的な研修が必要。また、相談面接等のスキルが条件となるが不適切な人が多いのが気になる。事業所ではとにかく5年の実務経験者を送り込んでいるが、実際にサビ管ができるかどうかはとても不安。
・個別支援計画の位置づけなど、他分野の講師と説明や書き方が違った。研修生の知識に差がある。 ・結局、「施設長」クラスの参加が多いのですね。ダメだとは言いませんが、「そもそも」論の部分でご理解いただいていない現状はあると思います。
・相談支援とサビ管の県所管係が異なっているため、様々な問題を抱えている。その結果、我々が批判の的になっている。国研修を一本化して欲しい。
・演習の時間が十分であるかどうか 自分が昨年受講した際も、演習の時間は十分でなかった
・実際国の研修を持ち帰って、講義すると言うことはとても難しくできれば専門家をどんどん増やしていただき県へ出向し講義していただきたい。また当事者の話しをどこかで取り入れても良いのではないでしょうか。集中講義よりある程度日数が取れると助かります。
・研修委員会などの立ち上げと、県レベルの勉強会や組織を創る。社会福祉士会に委託などの検討も必要。
・自分が講師をするとなると非常に体力を要する。
・フォローアップ研修をどのようにしていくかが課題となっている。
・昨年度の受講者や他にも2名ほど手伝ってもらい、無事終了することができた。
・演習のグループ分けでどの程度個別支援計画ができるのか。限られた時間内でカリキュラムを消化できるのか。
・演習の進め方、参加者のレベルと時間設定
・受講者の全体的な質のレベルの差。一定の質を担保するためにもきちんと試験をする方がよいと思う。
・中央の研修の内容を地域に合わせてどう伝えていくか。
・受講者の意識の変革を目指している。
・全国研修の資料がそのまま使えるわけではないので、資料を作成するにあたり県内の状況等を把握する必要がある。
Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について
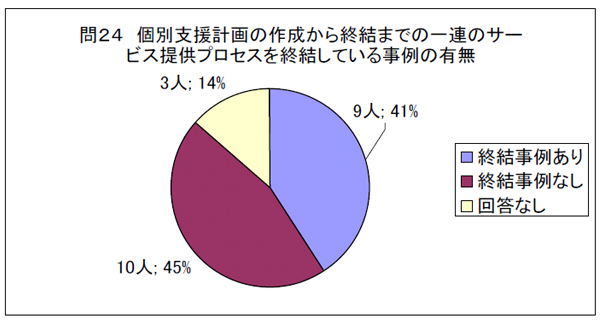
| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 相談受付表を見てまたは職員から状況を聞いたとき、必要な情報が聞き取れていないと思った時 | |
| ・ | 紹介されてくる場合で、当法人の利用が適すか現場で迷っているような場合 | |
| ・ | 相談があった時点で | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 面記録書式の提示、重度障害者の場合の意向の確認は担当職員が情報を収集しイメージして作成。保護者の評価、面談記録の評価を通しての職員の指導助言。 | |
| ・ | 利用者の意向、心理状態等、相談受付表に書かれていない面の状況把握についてのアドバイスをする。 | |
| ・ | 初回の面接で同席する | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 一方的な聴き取りになっていないか、あせって一度に情報収集していないか等に疑問を持った時 | |
| ・ | 利用開始1か月 | |
| ・ | 定例で検討 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 担当PSWより内容把握し、具体的な言葉でアドバイス | |
| ・ | 担当となった職員へ声かけを行う。 | |
| ・ | 必要な領域を把握することに重点を置くようアドバイスする。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 定例で検討するとともに、変化があった時 | |
| ・ | 利用開始時、開始2,3か月 | |
| ・ | 開始時、定期(6ヶ月)又は状況に変化があったとき | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 作成時にミーティングと本人・家族の確認 | |
| ・ | 事業所内のケースカンファレンス。 | |
| ・ | 入所施設の場合、継続しているので定期的に支援計画を評価し、修正するよう指導している。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 実施の段階で○ヶ月後にプラン終了した時点でどう変化しているのか?疑問に思った時介入する。 | |
| ・ | 定例で検討するとともに、変化があった時 | |
| ・ | 定期的な会議、不定期に様子を見にいく | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 聴き取り・実際に状況を確認 | |
| ・ | 申し送り事項に対して今後の方向性を指示 | |
| ・ | 面接の実施。利用者やサービス提供職員と一緒に話し合う。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 3ヶ月~6ヶ月後 | |
| ・ | 6ヶ月に1回は確実に行う | |
| ・ | 本人の状況が変化したときに支援者より報告を受けて介入する。 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | ケース検討会にて報告、意見交換、個別に指導 | |
| ・ | 評価表と修正案の確認 | |
| ・ | 各所ごとに見直しを行ったものに対して意見を付す | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 新たなニーズを見つけだすとき | |
| ・ | 終了時評価における検討会議 | |
| ・ | 地域生活へ移行した場合、退所するとき 終了時面接を行う。 |
|
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 会議のメンバーの一員として最終的な確認を行う | |
| ・ | ケースカンファレンスにて今後の方向性を確認 | |
| ・ | 面談記録の評価、助言、指導 経過記録の作成における指導 |
|
| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 困難と思われるとき | |
| ・ | 必要に応じて行うとともに定例の会議においても把握している。 | |
| ・ | 毎日の申し送り | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 打ち合わせ 文書の情報回覧 ある程度の支援計画のイメージを共有する | |
| ・ | 初回の段階でそのように相談受付するのか、アドバイスを行う。 | |
| ・ | 随時職員ミーティングで情報を共有 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | アセスメントをする前に必要項目の確認と障害特性の把握等必要性 | |
| ・ | 個別支援計画の場など | |
| ・ | 定例で実施 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 1次アセスメントの情報の共有 不明な点等の確認 家族や医療機関等からの情報収集 情報の共有 |
|
| ・ | 担当PSWより報告、協議。 | |
| ・ | 当該担当部署との協議 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 聴き取り終了後、本人の意向に合わせ | |
| ・ | 作成終了時 | |
| ・ | 定例で実施している。また、利用者等に変化があった場合。 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 関係者からの情報も合わせ、まず本人が納得できるよう作成前に会議を開く。 | |
| ・ | 担当PSWより報告、協議 | |
| ・ | 随時職員ミーティングで情報を共有 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 個別支援計画を決裁を受け実施している。 | |
| ・ | 随時 | |
| ・ | スタッフミーティングの実施、毎日の申し送り | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 上手く実施できているか常に支援者と連携して情報交換を行う。 | |
| ・ | 当該担当部署責任者への聴き取り | |
| ・ | ユニット会議 職員会議 ケース会議等での評価 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 緊急の課題が発生したとき 新しい要望や苦情が寄せられたとき 随時 | |
| ・ | 定期的な振り返り(6ヶ月)で | |
| ・ | 評価時・修正案作成終了時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント票に基づき、評価を実施している。 | |
| ・ | ケース会議を開いて関係支援者の意見、本人の意見を聞いてから | |
| ・ | 当該担当部署内での協議・同席 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 新たなニーズを見つけだすとき | |
| ・ | 退所するとき | |
| ・ | 到達目標に近づいたとき、支援者による評価と本人の評価を共有する。 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | ケース会議を開き評価を行う。 | |
| ・ | ケースカンファレンスの状況について担当より報告 | |
| ・ | 評価を行い、目標達成の度合いを確認している。 | |
| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 外部から、サービス利用についての打診があった時 | |
| ・ | 相談内容により、他機関につなぐ方が効果的と思ったとき。 | |
| ・ | 本人や関係機関から相談があったとき | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 関係者を集め、ケース検討会を開いている。(町の自立支援協議会にあげるようにしている) | |
| ・ | 電話・相談支援専門員からの情報聴取 | |
| ・ | 電話や直接面談での確認 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 1ヶ月くらいの間に | |
| ・ | 他の資源の力が必要なとき | |
| ・ | 利用開始時、2,3か月 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメント実施後、ケア会議開催 | |
| ・ | 情報収集 具体的な連携や協働の方法の検討 関係機関の召集 支援会議の開催 |
|
| ・ | 相談する | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 原案から支援計画確定まで | |
| ・ | サービス利用開始時 | |
| ・ | 他機関のサービスを組み合わせる必要がある時 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 関係機関に呼びかけ、ケア会議を実施する。 | |
| ・ | 支援会議に対して原案の提案 関係機関の役割分担 計画への反映 |
|
| ・ | 支援会議を開く | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 計画にあわせて行う | |
| ・ | 約2週間後に正式なチェック | |
| ・ | 随時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 支援会議の開催 | |
| ・ | 本人との面談、職場訪問など | |
| ・ | 毎月の関係者会議で報告する。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 計画がうまく運ばず、あるいは本人のニーズに変更等があったとき連絡する。 | |
| ・ | 少なくとも3ヶ月~6ヶ月 | |
| ・ | 変化時、見直し予定時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 計画に基づいた支援活動の評価と、新たな課題がないかの確認 | |
| ・ | ケース会議を開き、現状報告をし、関係機関からの情報を得たうえで、皆でどの部分を修正するか話し合っている。 | |
| ・ | 支援会議の開催・評価案の提示・修正 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 次のステップが見えた段階で | |
| ・ | 到達目標が達成できた時、あるいは本人が計画実施を中止してほしいと連絡してきたとき | |
| ・ | 利用終了決定時 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 関わっている支援者で関係者を集めいろいろな意見、情報を集めたうえで終了を確認する。 | |
| ・ | 計画に基づいた支援活動の評価と、新たな課題がないかの確認 | |
| ・ | 支援経過の情報の共有 次の支援機関への情報の申し送り |
|
問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。
・利用者が地域にいらっしゃるか施設にいらっしゃるか、または、どちらが深く関わっているか。
・相談の紹介や受付、相談等は協働して行う。支援計画の確認、他機関とのコーディネートは相談支援専門員に依頼することが多い。関係機関が集まる支援会議の収集も依頼している。
・地域の人には相談支援専門員がケアマネの役割を担ってもらう。
・サービス管理責任者 ⇒ 施設(入所系)利用者 相談支援専門員 ⇒ 在宅障害者
・国がばらばらに養成研修をしている影響を受け、県行政も違う係が受け持ち、我々研修企画者が批判されている現状を汲み取って欲しい。相談支援とサビ管の研修を1本化してほしい。
・直接相談支援専門員からの紹介は今のところないが、あれば専門員さんの意向を聞きながら,関わっていきたい。常に話し合うということでしょうか。
・相談支援専門員は地域、サービス管理責任者は住居としています。
・実際やっていることにほとんど変わりはないが、お互いが利用者に向ける視点、また関係機関との連携をチェックできるようにしている。
・まだ関わりがない。
・障害者が地域で普通にくらすことの意味と援助、支援の提供の確かさが求められると思った。そのためにもいろいろな資源(地域的、人的)の活用方法を習得したいと思っています。
・よく分からないので、実際には利用者によって分担している。
・いやがおうにも一緒です。
・サビ管に課せられた役割が多いことや、利用者のみならずスタッフの支援が新たに加わったこと、それがサービスの質確保に繋がる重要なポイントになっています。小さな事業所においては、サビ管とサービス提供職員を兼務する場合も多く、さらに負担は大きくなると考えます。求められるものが増える程、心理的疲労のために心の健康を害しないか心配です。サビ管のメンタルヘルスのためにもせめて一事業所に複数のサビ管が配置されるような工夫(配置基準、報酬の見直しなど)があってもいいと思います。または、サビ管の全国研修だけではなく、管理者にも研修の受講(管理者研修:サビ管の役割やフォローの仕方を盛り込む)を義務付けるなどして、管理者がサビ管を支える仕組みも必要だと思う。
問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。
・サービス管理責任者がすべての進行管理を行うことは困難である。他職員との役割の分担が必要となる。
・①一人一人のサービス管理責任者が,サビ管として求められている様々な役割の精度をいかに上げていくかではないかと思います。サビ管本人の努力はもちろんですが,事業所の管理者の責務でもあるし,むしろ逆に社会の要請によってサビ管が育つというような風土・風潮になればいいなと思います。それは自立支援法の目的が達成されたとも言えると思いますが。②例えば,このようなアンケートを都道府県単位でも実施するというような,いわゆる「検証」は必要かと思います。
・個別支援計画の一連のプロセスの更なる理解と実行。自事業所の適正な評価とサービスの改善・改良・開発。サービス管理責任者が求められる役割や責任性は非常に大きいが、事業所内における立場は保障も確立もされていない。まずは上司や法人に理解してもらえる働きかけが必要と考える(国としても何らか示す必要があるのではないか)。
・報酬上、専任といいながらもサビ管以外の業務に従事している。専門職として、アカデミックな分野として職場や社会で認知されるまでには、かなり時間を要すると思う。エビデンスが研修では強調されたが、サビ管の水準を上げる継続研修がぜひとも必要。サビ管のレベルを上げるには、個人的には試験制度が必要ではないかと感じている。ともすると、形式的に作られた支援計画の枠に利用者が押し込められるのであれば本末転倒である。あせらずじっくりとサービス管理のあり方を実践的に研究していくことが必要であると思う。
・研修を受ければサービス管理責任者となれるが、明らかにその仕事はできないだろうと思われる人や経験不足の方がいる。まだまだ底上げになっていない。
・これだけ「重要だ!」と言われるのなら(重要だと思っていますが…)、その分の人件費は別で盛り込まれて然るべきだと思います。サービス管理責任者がサービス管理責任者の業務に専念できるだけの財政根拠が必要です。
・人員配置に伴う予算も確保しないと、絵に描いた餅になってしまう。県研修受講生の表面的なアンケートでは評価が高いが、直接本音を聞くと、現実的ではないという意見が多い。本格的にこのサービス管理責任者の業務に当たろうとすると、施設業務から離れて地域コーディネーターとしての位置づけになるのが良いに決まっている。しかし現状では、いくらサービス管理責任者を養成しても、研修で理想論を聞き、現実は既存の施設サービスを繰り返すことにならないだろうか?サービス管理責任者全体に予算配置が難しければ、国研修参加者に対して、自立支援協議会の開発等、より強固な権限を与えていく方が近道かもしれない。
・限られた人員の中で兼任しているので、効率的な支援活動をすること。自分のその時の立場を明らかにしていくこと。
・余裕がないと丁寧な聞き取りもできず、チェックも難しいかと思われる。管理者との兼務で、サビ官だけに集中できないところが課題。中途半端に終わるようで不安。研修を通してサビ官の役割等本当にサボってる場合ではないぞとひしひしと思うのだが、現実はできておらず何とかしなければと焦っている。責任の重さを感じる。ただすぐに結果が出る人もいれば、時間がかかる人もいるので、支援の質で評価してもらいたいのも事実。でも、支援者側がよりよい支援を提供しているか問われている事には間違いない…理想と現実のギャップに頭が痛い。
・私の業務は、総合相談支援センターの相談業務であり、相談支援専門員としての業務である為、施設のサービス管理責任者としての施設内での支援計画や担当者との業務の連携などの実際をもう少ししっかりしたシステムにしていかないといけないように感じました。
・地域移行や就労した場合は、特に連絡を密にしている。
・日頃の業務に追われて、サービス管理責任者としての業務ができていない。施設での人員配置も適切に行われるような基準にする必要がある。施設としては、関係機関との連携やチームアプローチという点にここ数年力を入れているが、職員の力量不足のため、資質向上が急務となっている。
・利用者を中心として、サービス提供職員、法人、地域、関係機関、作業所、就労先等の間に立って、良いサービスが提供されるように関係調整することだと思う。
・個別のニーズに基づいて弾力的な計画として、落とし込んでいくのは重要であるが、現実にリアルニュースに絞るためには、常に利用者の変化に気づけるよう意識しておけなければ、こちらの一方的な計画に陥りやすい。
・職員のスーパービジョンを行う時間がない。同事業所内の他職種への教育、指導をどう行えばよいか。
・相談支援体制の一員としての役割を担うべきではあろうが、現場での雇用のされ方(特に地域生活 知・精)が正職員という身分の方ばかりでなく、会議等い出るのも厳しい現状と見受けられる。管理者、代表者向けの研修も別途必要だと思う。
・少子高齢化による国民的関心が福祉に向けられている現在、障害者福祉はどのような成果を残し、どのような評価を受けるか、とても大事な時期を向かえている。サービス管理責任者の役割をどう理解してもらい意識のあるものにしていけるかを考えていく必要がある。
・サービス管理責任者の働きは何なのか。研修の中でも人によって幅がある。まだ、確立されたものではないと思う。これから、理解と実践を広めていかねばならない。
・サービス管理責任者は専従業務であり、その業務内容をみれば専従でなければならないと思うが、現場からみた場合、人件費の面や人的な面で専従は難しいと思われる。サビ管だけでなく、いろいろな面で充分な支援が行われるような財政面の改正(単価見直し)が必要ではないか。
・国家資格はどこにいってしまったのか。サビ管講習もやらないよりはやった方がいいに決まっているが、このサビ管というものに社会福祉士や精神保健福祉士の国家資格の位置づけが全く無いのはやはりおかしい。社会福祉学を学び、時間と努力を要して取得した資格と、この付け焼刃ともとれる講習会に同等(あるいはそれ以上か)の価値があるとは思えない。サービスとして一般化できる福祉とそうではない高い専門性が求められる福祉事業があると思っている。精神障害にまつわる仕事をしていると、後者の部分が多いようにも思われ、これでいいのかと思ってしまう。
・サビ管の業務が広範囲にわたっているにもかかわらず、業務の中身について具体的なやり方(?)等の情報が少なく、手探り状態です。さらに請求やサービス管理、支援計画等期限のある提出物にも追われ、国の研修で示されるようなサビ管としての動きが出来ていないのが現実です。日頃の業務からみると研修の内容が少ないです。3日間の研修ではその一部しか出来ません。
【児童分野】集計結果
Ⅰ 回答者の事業所等について
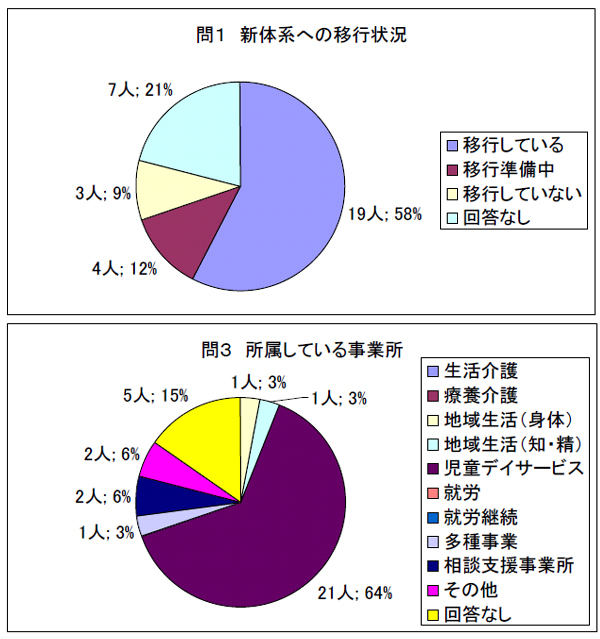
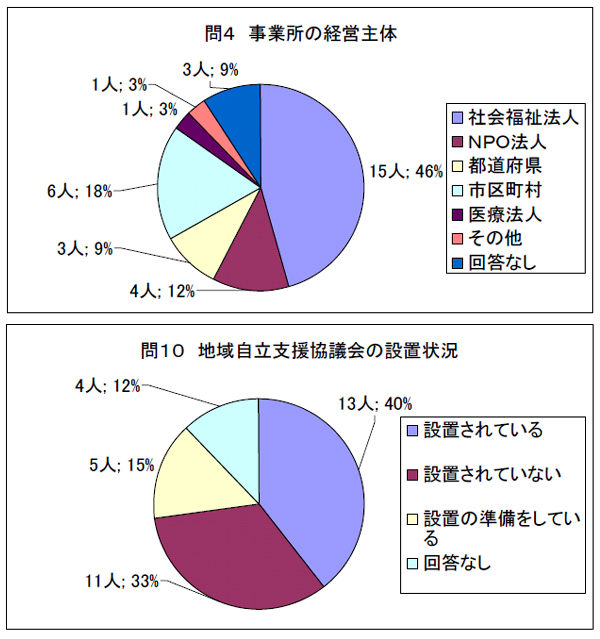
Ⅱ 国の指導者研修の内容について
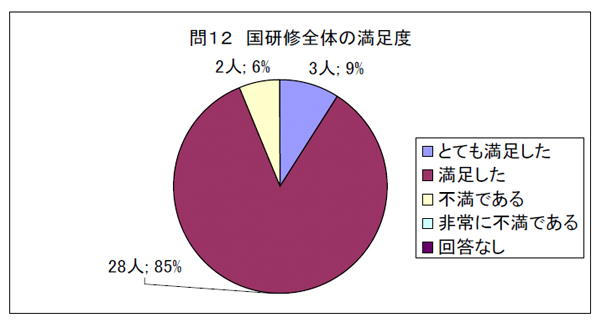
問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由
・サービス管理責任者の仕事の内容等について、講義、演習を通して、たいへん詳しく、いろいろな視点から学ぶこと ができた。
・制度そのものに対する矛盾はあるが、現場の実践のレベルアップにはつながると思えた。
・分野別の講義や演習について・・・講師の方々の実践を基にした熱い思いが伝わってきて、何とかこの内容を県でうまく伝えたいと思いました。厚生労働省の方の児童に関するお話がもう少し聞けるとありがたかったです。
・昨年県の全体研修を受けて理解していた事の確認と責任が明確になったが職場での職務についてはまだ不十分であり、研修内容を生かして生きたい。
・改めてサービス提供プロセスを学習し自分の復習にもなった
・児童デイサービスが今どういう状況に置かれているかを知り、その中でどのようにサービス管理責任者としての役割を担うかを具体的に話しあうことができた。
・他の都道府県の様子が分かったこと、国の最新情報が分かったこと、児童デイの今後の動向が分かったことが良かった。
・研修に参加できて、自分の責任の重さを感じることができました。人間味あふれる講師の方々と、また分野別の同じグループの皆さんと情報交換など出来たこと等。
・前年、県の研修で受けた内容の復習のような形で受講できた。
・全体講義→具体的で尚且つ丁寧だった。
演習→同一の事例を用いて演習を行ったことで、様々な意見や捉えがあることを学んだ。現場にも生かされていく研修内容だった。
・各講師の実践に基づく具体的な演習が良かった。
・当事業所と同じ問題を抱えている事業所があることが理解できたこと。国としての考えをじかに聞くことができた
・自立支援法に伴っての動きが理解でき、自分にとっては勉強になった。
・皆さんと研修を受けて児童デイサービスの有り方とサビ管の役割を改めて思った。
・サービス提供のプロセスが理解できた。
・サービス提供の考え方について深く理解できた。サービス管理責任者の役割を学べた。
・サービス管理責任者の業務内容及びサービス提供のプロセスを学べた。
・指導者としてのあり方や留意点、実際に研修を実施する手法等を学べた。
・演習等実際に行っていく内容等は良かったが、3日間での研修では、消化できていない点も多くある。
・全体講義は、普段の業務内容と異なっているため、大まかな概要を理解するのに留まった。分野別講義・演習は、様々な職種・立場のひとの意見が聞けて良かった。
・満足したが、もう少し絞ってかつ指導の方法、テクニックを教えて欲しかった。
・個別支援計画の立て方など、参考になることが多かった。
・講義と分野別演習により「サービス提供のプロセスと管理」について総合的かつ具体的に学ぶことができた。
・今年度の研修内容では都道府県レベルの実施の際、混乱する可能性が高い。
・全体の概要など学ぶことが出来た。
・方向性がはっきりした。
・演習はベテラン職員の集まりで議論が充実していた。
・自分の不勉強なためでもあると思いますが、理解しづらいことも多かったと思います。資料やテキストは事前にいただいて読みこなしてから参加できれば良かったと思います。
・地域の違う人たちと分野別で2日間語り合えたことは自分たちの立っている位置がよく分かった。
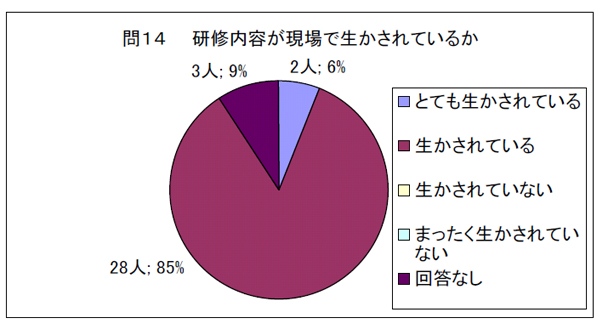
問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由
・現在、職場では、現場で児童の直接支援を行っているが、サービス提供の基本的な考え方、サービス提供のプロセス、管理、連携等について、幅広い観点から支援を考えるようになった。
・制度に応じた事業展開をしていくとき、現場に新人スタッフも増えており、何を大切にしていくのか、その視点も含め生かされていると思われる。
・当市には今年度よりこども課内に「発達支援室」が立ち上がり、室を中心に市全体で支援の必要な児・者に対して個別支援計画の推進がなされておりますが、所属する支援センターや児童デイサービスも室とおなじシステムの中で動くことが多く、個別支援計画について等福祉と教育の間の若干のニュアンスの違いを感じるも、根本は同じという確信は持てたように思います。
・支援者指導、療育体制作りに参考にしている。
・個別支援計画策定時に研修内容を思い直す事ができる
・研修の内容が現場とのずれがなく、そのまま取り入れることができ、また全国の同じ業種の方々と出会え、そこからまた具体的な方法や相談をすることができるようになった。
・サービス管理責任者の仕事のイメージやスタッフの育成など幅広い視点で研修できたこと。
・研修後現在使用しているの書式の改善点、また、職員の仕事量や家族の状況等意識するようになった。
・実務に携わっているので
・演習を通して実際にサービス管理責任者の役割を担っている方々の話や意見を聞けたことが、自分のあるべき姿を見直す機会にもなったし、また当事業所の課題等についても明らかになった。他アセスメント用紙、個別支援計画書を見直すヒントになった。
・発達障害者支援センターという相談機関であるが、利用者のニーズに基づく個別支援計画の作成に役立っている。
・現場の職員に徹底しやすい問題がはっきりつかむことができた
・サービス管理責任者としての利用児,保護者への支援役割としてサービス提供職員と共に行う仕事の内容として生かされている。
・仕事の進め方に見通しがもてた。
・個別支援計画作成にあたり着眼点を得た。
・自分の視点や考え方に広がりができた。
・個別支援計画、事業所のマネジメント等新しい着眼点を持つことが出来た。
・計画立案等は以前から行っていたため、大きくシステムを変える必要はなかったが、考え方やシステムの見直しなどに生かされていると感じる。
・個別支援計画の立て方が勉強になった。
・今までのアセスメント表、個別支援計画表を作り直す作業中である。
・個別支援計画書の様式や内容等の見直しを協議する際には今回の研修内容を生かすことができる。
・現場の実態と理念の乖離の分析がされず、制度がスタートしているため。
・支援内容をはっきりさせられるようになった。
・アセスメントの視野が広がった。
・今、職員が障害のある子供たちに対応することで精一杯であり、経済的な理由からも願うほどの研修・検討などの時間がありません。これからの課題として真剣に取り組みたいと考えております。
・サービス管理責任者としてこれまで以上に全体の流れを見つめることができるようになった。
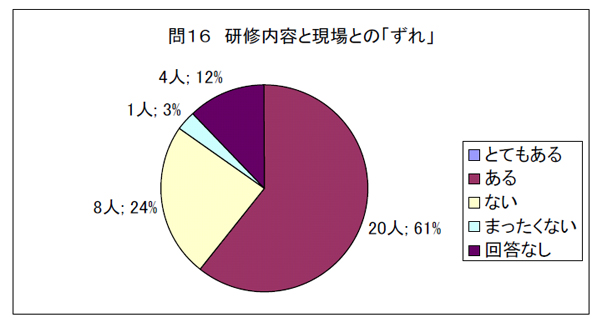
問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容
・分野別の児童デイサービス事業については、経過的に放課後対策的な内容を行っている事業所があるため、
・現場の実態が鹿児島の場合は、児童デイサービス(旧、通園事業)が中心である為、小規模が多く、職員配置や職種などのギャップがある。
・全体講義では難しい学術用語が多く(自分の勉強不足に反省しつつも)わかりづらい講義が一こまあり、つらかったです。
・ 基本的なサビ管の視点は理解できるが、実際の事業所の形態が違うので立場により発揮しにくいところがあると思う。
・サービス管理責任者の配置と事業運営のズレ。サービス管理責任者の配置に伴う財政的なフォローがない
・小規模の施設で業務を行っているため、実務や管理者の業務も行っている。気持ち的には求められるものをこなしていきたいと思うが、時間的に個人の力量的に研修どおりに行えるとは思えない。
・当園では、現在個別指導、集団指導など、また家族への支援、他機関との連携などはこれまでも通常行われているし、やられていないということが不思議な感じがしてしまいます。
・サービス管理責任者をサービス提供に関する管理責任者というばかりでなく、その部署の管理職と位置づけた前提なので、職場としての管理職にないものはその役割が難しい事項もある。
・理想的なサービス管理責任者の役割を理解していても地域性や保護者の特徴などで支援の度合いも様々である。児童デイは利用料金も一律、また一人ひとり支援の度合いも様々であるが程度区分では無く子どもの人数に対し職員数が定められている状態である。重度の児童の利用が増えており、現場や家族支援を行っていくだけで精一杯の状況の中、サービス管理責任者としての役割を十分に果たせないでいる現状である。
・障害者自立支援法の内容とサービス管理責任者の位置づけが理解できた。
・講座内容が臨床の場の問題が同質のことであり、指導しやすい。
・実際支援の中で療育的支援は行えるが、OT,PT等の医療機関が少ないのが地域的な実情である。
・職員全員へまだサービス管理責任者の役割等理解されていない。
・全体講義の部分は成人領域の話が多く、児童の現場にはあてはまらない。
・全くないとは言えない。何回も見直しの会議など時間的な問題が多い。
・職員体制
・職員全体の意識にばらつきがある。
・経済的な事情で大部分の職員が非常勤であり、これだけの内容を伝えたり実践していくことが困難です。
・児童デイサービスの対象は利用者本人よりも保護者や関係者との連携が求められるため、馴染む部分とそうでない部分があると思う。
問18.国の指導者研修の内容で良かった点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・サービス管理責任者の仕事の流儀は、とても具体的で、サービス管理責任者として仕事をする上でのイメージをしやすかった
・利用者の願いに応える実践をつくっていくという立場を基に、法制度の中身やサービス管理責任者の役割が語られていたこと。
・常に本人中心というベースの中で法の中の管理責任者としての役割がよくわかりました。
・サービス管理責任者が利用者全体の把握をし、個々の質を上げるような視点が明確になった。
・国で考えている制度やサービスのあり方、利用者にサービスを合わせる視点が明確になった。
・サービス管理責任者としての役割と法について、再確認できたこと。
・自立支援法の目的遂行のため、サービス管理者の役割が不可欠であることがよく解った。
・具体的で分かり易かった。
・ICFの考え方に基づいたサービス提供の仕方について
アセスメントから評価への流れが具体的でわかり易かった。
・具体的であったため、県での講習に有効であった
・サービス管理責任者の役割について、考え方等わかりやすかった。
・最初に障害者自立支援法のポイント等を示したなかで、サビ管としての役割はどういうものか、サービス提供のプロセスを分かりやすく矢印で示し、実際にサビ管として動き出す上で、『サビ管としての私の流儀』等を紹介してくれる等、自分として大きな枠としてつかみやすかった。
・制度全体が理解できた。
・サービス提供の基本は利用者中心であること。サービス管理責任者の役割を学べた。
・自立支援法における位置づけやサービス管理責任者の役割が理解できた。
・サービス管理責任者の業務内容、「管理者」と「サービス管理責任者」の関係イメージ図が比較例等で明記されており、理解しやすかった。
・「仕事の流儀」では、具体的な例が挙げられて強い印象を持った。
・自立支援法の理解が深まった。
・サービス管理責任者の役割について、大まかに理解できた。
・サービス管理責任者の目的がはっきりして良かった。
・サービス管理責任者の責務や位置づけ、具体的な業務内容について総論的な理解が得られた。
・相談支援従事者との役割が明確になった。
・再確認の場となった。
・利用者にサービスを合わせようとする視点。
・概ね理解できた。
・何が大切なのかが具体的にわかったこと。厚生労働省の基本的な姿勢や専門的な実践、先駆的な実践例で圧倒された。
・自立支援法が目指している支援の質的向上に、サービス管理責任者の役割が重要であることを再確認しました。
2.サービス提供のプロセスと管理
・サービス提供のプロセスについてとても丁寧に、わかりやすく説明され、ポイントが捉えやすかった。
・現場の実践も紹介されながら、内容が語られた所が良かった。
・相談支援従事者研修と重ねて抑えることが出来たのでよかった。実践報告は具体的で、入所施設関係の方々(当法人の)にもお伝えしたいと思いました。
・説明がわかりやすかった。
・出来ないことではなく、出来ることや強みに着目する視点は新鮮だった。長野県の実践のお話も興味深かった。
・これまでは、全国統一された様式がなく、当園なりのやり方で自己満足していた部分もあったので、時間軸を意識する点に気づくことが出来たこと等。
・図解がたくさんあり、わかりやすかった。
・起承転結でメリハリのある話し方で分かり易かった。ICF的な見方は個別支援計画書を作成するにあたり、大変参考になった。
・地域自立支援協議会を通じての各機関との連携の必要性が良く分かった。
個別支援計画が連携のアイテムになる、その際のフォマットを出来るだけ統一すること。
・実際に臨床経験がある人であり、共通理解できた
・実践編が別途説明があり、イメージしやすかった。
・サビ管としての役割を「エンパワメントの話し」や「実践編」を学習するなかでサービス提供において、その流れプロセスにおいて、個別支援計画が土台にあり、サビ管が流れの管理をすることが重要であるかが感じられた。
・モニタリングやマネジメントの役割が理解出来た。
・一連のプロセスにそって支援を考えていく中で実施方法、視点について理解できた。
・支援会議のイメージを持つことが出来た。
・プロセスの1項目ごとに実施方法や必要なツールまで細かく記載されており理解しやすかった。
・山田氏の実践報告は実際にどのように行っていくか具体的に示され良かった。
・一連の流れが理解できた。
・計画立案についてやや具体的なプロセスが理解できた。
・非常に詳しい資料に基づいた講義であり分かりやすかった。
・サービス提供の基本的考え方を学べた。
・概ね理解できた。
・図式化されていたりして見やすい、事例があり分かりやすい。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・関係機関との連携のあり方の具体的なイメージを持つことができた。
・これまで、孤軍奮闘というところで関係機関との連携を進めていたところもあり、今後は、 自立支援協議会が作られていくことがわかり期待が持てた。
・専門官の講義についてはわかりやすく自分の動きや地域でのかかわり等を想像しながら、また、地元での伝達講習をするときのことを考えながら受講させていただきました。
・連携を改めて考えることができた。
・フットワークやネットワーク、チームワークなど改めて大切さを理解出来た。実践の話。
・地域に暮らして当然知っていると思い込んでいたのですが、実際に施設内に足を運んだことがどれだけあるのか、と思いそのことに大きな発見がありました。
・自らの事業所のある地域の実践はまだまだたが、実践報告もあり、モデルとしては理解できた。
・現場での事例だったため、参考になった。
・現在の実情から支援の方向性まで具体的に説明され、良く分かった。
・連携のあり方、必要性について、改めて考えさせられた。
・療育機関で仕事をしている者にとっては連携がいかに大切であるかはどの参加者も分かっていると思う。しかし、それぞれ対象施設・事業所によって連携の状況が微妙に変わっていくのだと児童分野から参加した自分は改めて感じさせられた。
・地域で支援することの重要性と生涯にわたる連携の意味。
・完結型支援でなく、関係機関と連携することにより情報の共有を図り、専門性が高まり良い支援につながる。
・連携についての重要性をを知った。
・関係機関との連携の重要性を再確認できた。
・地域自立支援協議会や地域との連携等わかりやすく解説されていた。
・サービス管理責任者の相談支援専門員との関わり方が見えた。
・話が具体的でイメージしやすかった。
・関係機関との連携がとても重要だと認識できた。
・実際に実施されている機関の発表はよかった。また、そうできると良いと思った。
・誰のための連携なのかということ。
・概ね理解できた。
・地域にある資源発掘の重要性を感じた。(限局的な関係機関だけでなくもっと広い視野で)
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・児童期の発達の気になる子どもの今日的状況と課題についての講義は、児童デイサービス提供する上で考えなけ
ればいけない課題を整理することができた。
・子どもの分野と言う所では、総論として子育てや国の財政状況なども含め地域での支援のあり方、児童デイサービス
の視点など触れられていてよかったと思われる。
・現場で当事者の涙を見たり声を聞いたりされていらっしゃる先生方の講義が身近な事例を想像でき、わかりやすかっ
たです。
・ファシリテーターのグループでのコメントがもう少しあつた方が県の研修に参考になったと思う。
・児童デイサービスを取り囲む国や財政的な状況が聞けたこと。実際の事業所の状況が聞けたこと。
・ディサービスのアセスメントの視点、モニタリングの視点について再確認できたこと。
・広い視野での講義と具体的な事例研究の二本立てでわかりやすかった。
・特に総論が良かった。現在の国の状況を踏まえながら(国が抱えている借金の問題等)、子どもの出生数の推移、家
族の受容、発達支援の三層構造などを聞かせていただき、国に求める前に、事業所の中で変えていけることはない
か、工夫すべきことはないか、など具体的に考える機会になった。
・事前情報より、出来る事、出来ない事、本人のニーズなどを読み取って、個別支援計画のベースにするということが
分かった。
・アセスメントとモニタリングのケースが異なり、理解しにくさがあった
・基本的視点について、丁寧に説明されていてわかりやすかった。
・総論として講義を聴くなかで、現状と課題として捉えることができたが、出生数の目盛りが上がっていることはどういう
ところに問題があるのか考えさせられた。また「サービス提供の視点の7項目」が後々、我々支援員にとって大切な基
本項目になると思った。
・児童デイサービスの役割の認識、サービス提供の視点の確認が出来た。
・児童デイサービス提供の視点
・実際に計画を立てることにより、知識や技術を学べた。
・総論をとおし、今、児童分野が制度的におかれている状況を再認識できた。
・子どもの発達の視点から児童デイサービス提供の視点と分かりやすく解説され、療育の基本に立ち返ることができ
た。
・広い視点をもてた。
・児童分野に即した内容で、この制度の解釈の仕方などが実直で分かりやすかった。
・アセスメントに対する細かい配慮の方法が勉強になった。
・知らなかった内容がいろいろあったので参考になった。見方、考え方がいろいろあると思った。
・加藤、藤原両先生の講義は具体的また実践的で良かった。
・児童デイサービス提供の視点。
・私が日々考え実践していることと加藤先生の講義内容に共通点が多く、子育て支援、家族支援、地域支援をがんば
ろうと心から思わせていただいた。
・具体的事例で、個別支援計画がイメージでし易かったと思います。
・事例をもとに進められてのでとても分かりやすかった。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・演習の中で、本人の状態やニーズの把握をするアセスメントが大事であること、支援の課題を整理する際には、事例の強みに注目することの大切さを学ぶことができた。
・現場の事業実践を基に語られておりよかった。ただ、全国的にはかなりの違いがある中で、どんな事例がいいのか検討の余地があるように思う。
・幼児期のアセスメントを発達の視点だけでなく生活をベースに考える視点を持って演習してくれていた点
・グループで実際に演習で考えて作成したこと。
・グループ内は全国からベテランの方々が参加されており、これまでの私だけで凝り固まった考え方から脱出し他方面からアプローチできたこと。
・事例が一貫していたことがよかった。
・5.6.7について→同一の事例について演習を実施したことが良かった。様々な意見や捉えまた価値観などを聞いたり、感じたりすることが出来た。役割分担をすることで、記録、司会、発表などそれぞれに経験でき、その経験は全てサービス管理責任者としての動きに生かされていくと思う。提供していただいた資料も具体的で、アセスメントの聞き取りに関しても内容等参考になった。
・保護者にもわかり易い、個別支援計画を立てること。
・資料が少ない分、いろんな側面からの視点が持てるので良い
・⑤⑥については、1事例をもとに、ひとつの流れの中で説明されており、具体事例に即しての解説となっていたので、わかりやすかった。
・実践事例を紹介してもらうなかで、フオーマル発達評価表等を照らし合わせることの必要性。また、サビ管としてのスタッフへの指導助言等を分かりやすく「サービス管理責任者の視点」として、示してくれてあったのが、10月の自分が担当した県内の児童部門サビ管研修会において非常に参考になった。
・情報収集の内容や客観的な評価、保護者(当事者)の思いなどが充分把握できているか自分の仕事を反省できた。
・演習の手順の説明があったことで、取り組みやすかった。グループ討議により、様々な視点でニーズの整理ができ、支援計画につなげることができた。また、班ごとの発表により違った面での支援計画が見られた。
・ニーズを把握し、そのように生かしていくかを学べた。
・グループ討議をとおして、様々な意見交換ができた他、ファシリテーターの助言により、考え方が広がった。
・実際の事例で分かりやすかった。療育を中心に発達、家族支援の面から見てもとても良い事例であった。
・事例を基にして、良く理解できた。
・子供を捉えるとき、人によって様々な視点があること、家族支援の重要性など感じられた。ファシリテーターの先生がタイミング良く客観的に意見をまつめるアドバイスをしてくれた。
・演習により人それぞれいろいろな考え方、方法等があり、まとめる工夫が勉強になった。
・グループ内での話し合いでいろいろな着眼点があることがわかり発見があった。
・演習形式のグループ討議が良い経験となった。十分な時間配分も良かった。
・アセスメントとニーズの整理。
・他機関のサービス管理責任者の方の考え方を聴きながら、様々な専門職種の方の意見が聞けて良かったです。
・事例をもとに進められてのでとても分かりやすかった。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・モニタリングによる個別支援計画の修正・変更おいては、支援計画とのずれの原因分析を行うことが大事であることを、演習を通して学ぶことができた。
・事例を基に、実際に個別支援計画作りをしていったことがよかったと思う。
・相談支援研修でも作ってきたとは言うものの始めると無言になってしまいそれぞれの事業所・立場等からなかなか立てづらかった。確認や思い起こし等になりました。
・本人のニーズに合わせてのプランニングであるが、幼児期の子どものニーズをどのように把握する必要があるかは難しいと改めて思った
・グループを中心とした研修だったこと
・グループで実際に演習で考えて作成したこと。
・時間内に意欲的に計画を立てることが出来たこと。
・グループ討議のメンバーの中に相談支援等他の事業種の方も複数おられ、違った角度からの声が聞かれてよかった。
・評価と修正の際の職員へのマネジメントの必要性が分かった。
・時間的に十分話あいができない
・⑤⑥については、1事例をもとに、ひとつの流れの中で説明されており、具体事例に即しての解説となっていたので、わかりやすかった。
・実際の演習のなかで、付箋やパソコンが用意されるなか、視覚情報がはっきり見られる支援計画が作成・完成していくなかで、隣や前に座る同グループの各府県の方々の意見を聞いていて実践が豊富で内容が深いことを知り、勉強になった。資料事例を参考にすることで、分かりやすく捉えられた。
・目標設定は適切か、その判断に利用者の満足度をしることの大切さがわかった。
・中間評価に基づいて支援計画の修正、変更が取り組みやすかった。
・修正、変更の仕方を学べた。
・グループ討議をとおして、様々な意見交換ができた他、ファシリテーターの助言により、考え方が広がった。
・実際にサービス管理責任者として、どのような視点でサービス提供を進めていくかテキストもポイントを押さえていて良かった。
・子供を捉えるとき、人によって様々な視点があること、家族支援の重要性など感じられた。ファシリテーターの先生がタイミング良く客観的に意見をまつめるアドバイスをしてくれた。
・実際に個別支援計画をたてていくうえでの進め方(方法)が詳しくて良かった。
・話し合う中で、利用者中心のニーズの大切さがよく分かった。
・演習事例が1本(共通)であったため、初期計画~中期計画、修正のプロセスをじっくりと学ぶことができた。
・分かりやすかった。
・事例の考察と演習の振り返り。
・他機関のサービス管理責任者の方の考え方を聴きながら、改めて個別支援計画の中で実施順位を検討したことが良かったです。
・事例をもとに進められてのでとても分かりやすかった。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・サービス管理責任者として支援計画の作成の各過程、マネジメントにおいて必要なことを再度整理し、確認することができた。
・各現場ではひとりなので研修の場で集団的に考える機会がありよかったと思う。
・評価機能は忘れがちであるので非常に手法は参考になった
・グループを中心とした研修だったこと
・グループで実際に演習で考えて作成したこと。
・誰にでも分るように専門用語を出来るだけ控えて、誰が見ても分り易い計画を立案することを再確認できた。
・演習のサポーターとして、多方面の方がおられてよかった。
・時間が少ない
・(サービスの評価)
最後に評価に当たっての視点をまとめてもらっているのはわかりやすい。
・「サビ管の業務内容11項目」や「サービス提供の視点の7項目」が基になり、サービス提供管理を行うなかで利用児・保護者支援,そして職員の支援状況チェックをすることが可能になってくるようなマネジメントが作成できそうである。
・評価と反省が大切であること。
・サービス管理責任者としての支援経過時に留意すべき点、役割について見直すことができた。
・サービス管理責任者の仕事の内容を再確認できた。
・発達や療育支援、家族支援の視点による評価に基づき実際にどのように評価していくか詳しく解説されていた。
・様々な立場の人がいたため、研修や会議の方法など、普段はきけない内容を知ることが出来た。
・サビ管に求められているものは何かあらためて考えさせられた。
・サービス管理責任者の役割について
・他機関のサービス管理責任者の方の考え方を聴きながら、サービス管理責任者の業務内容全般を整理できてよかったです。
・事例をもとに進められてのでとても分かりやすかった。
問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・常に本人中心というベースの中で法の中の管理責任者としての役割がよくわかりましたが、逆に「運営」との狭間にある管理者が現実とのギャップに苦しむかも・・・と思ったりもしました。平行して「経営戦略」のあたりの講義があったら心強いと思いました。
・現状のままで良い
・目指していることはよく解ったが、実際の業務のあたり、どうこなすかイメージしきれない部分があった。施行され3年目では、実務に当たられている方の話を取り入れられるのでは…
・役割等についての基本的な内容は講義で。他、実際にサービス管理責任者の業務に携わっている現場のスタッフから分野別に事例を上げて発表する方法を取り入れては。質疑応答もあるとより具体的な研修になるのでは。
・療育の基本理念について
・自立支援法との関係についてややわかりにくい。サービス管理責任者の位置づけを明確に説明してほしい。
・耳慣れない言葉もあり、現場職員の知識とのズレがあった。
・障害者自立支援法におけるサービス管理責任者の役割をもっと具体的に法律に関連させて示すと良いのでは
・実際、サービス管理責任者をしている人の苦労話しなどがあれば良かった。
・共通講義の1日目は心的に緊張感が低くなりがち。分野別の中で学んでいったらどうでしょうか。(サテライト式でもよいので)
2.サービス提供のプロセスと管理
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・現状のままで良い
・障がい受容ができていない幼児期を対象としていると、相談からアセスの過程がテキストのように事務的には行かない。分野別とし、その点を含めた研修として欲しい。
・グループごとに違うケースで研修する
・児童の場合には触れられておらず。保護者を含めての考え方、ライフステージを頭においての考え方についても触れてもらい。
・実践報告をこのまま取り入れ、具体的に示す。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・連携については、大人中心の関係機関との連携が説明されていたが、児童分野の連携についても触れて欲しい。
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・研究事例が多く、大変難しい学術用語(しかもカタカナの)が多く、現場の自分には理解不能でした。またそれを伝えることによってサービス管理責任者の方々の知識が豊富になるとは思いますが、どう現場で生かすのか想像できませんでした。
・連携は大事なポイントになるとは思うが講義形式だと難しい。演習の要素に取り入れて見ては?
・現状のままで良い
・児童デイのように幼児期をおもに対象としている分野では関係機関も大人と異なる物となるので、できれば分野別で受けたい。
・それぞれの分野で連携内容、方法等異なると思うので、分野別で開催してはどうか。
・動き出している地域自立支援協議会の具体的な内容をもっと詳しく知りたい。
・児童分野における場合についても触れてもらいたい。虐待問題等もあり、連携はその点でも重要と思われるため。
(児童に限らないですが)
・連携について学んでいるなかで、各地域で活躍しているはずの「相談支援専門員」が見えてこず、地方の差を感じてしまった。調査事例があればと思った。
・連携について、もっと分かりやすく解説してほしい。
・児童分野における連携、教育との連携についての講義が足りなかった。
・国研修レベルでは、先駆的事例をあげるのではなく、都道府県の共通講義の企画方法を重点的に研修した方がよい。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・平成19年度講義では、今日的課題に重点が置かれ、児童デイサービス提供の視点を簡単に説明されていたが、平成18年度講義のように、課題を含めながら提供の視点を説明したほうがわかりやすいのではないか。
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・県研修ではサービス管理責任者の役割を考えると言う視点でロールプレイニングを実施したがそのような内容を少し入れても良いと思う。
・現状のままで良い
・どのようにという案は浮かばないが、もう少し吟味してほしい気がしました。
・自立支援法における児童分野の現状について触れてもらいたかった。(施設とデイサービス、実施状況について等)
・児童デイサービスは小さい施設が多く、専門職の参加も限られているのでもう少しシンプルなケースの方がわかりやすい。
・発表者の立場、視点からの講義内容で、全体的に基本的な講義内容ではなかったので、パワーポイントで示されたないようについて、もう少し詳しく説明して欲しかった。
・加藤先生の講義をもっと詳しく聞きたかった。
・分野別演習は勉強になるが、シートに書き込むモデルがあった方がよい。また、正解はないにしてもモデル的にどうあるべきか示してもらいたい。各班の発表に対するコメントやアドバイスもほとんどなかったのが不満です。
県の研修では、講師が的確にアドバイスをして中央研修よりずっと丁寧でわかりやすかった。中央研修も分野別演習はもっと充実させた方がよいと思う。各班で作成したシートも未完成ですごくマチマチであった。もう少し方向性をもって有効なものにしてほしい。講師やファシリテーターも打ち合わせが不十分で何をどの程度演習するのかが統一されていないと思った。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・前半は相談支援研修と重なる気がしました。後半をもっと深く知りたい、また、関係機関や地域の中での関係図等(マップなど)の作成等も、個別支援計画を意識した責任者にはとても役立つのでは・と思いました。
・幼児期のアセスメントを発達の視点だけでなく生活をベースに考える視点を持って演習してくれて
・もう少し時間をかけたい
・流れとしては特に問題を感じないのですが、疑問点①基本はプラスの側面に焦点を合わせることである②療育体制に関しても苦肉の策のようである。③特殊学級を勧めるのは今時いかがか。
・基礎情報をもっと詳しくしてはどうか。
・⑤⑥は事例に沿っての説明でわかりやすかった。それぞれの作成時期についても記載があるとよりわかりやすい。
・各グループ発表しただけで終わったのでもう少し各々の計画について意見を言ったり各グループごとに他のグループについて意見を出し合ったりしたかった。(県の実施場面ではそれをするつもりです)
・パソコン入力に時間がかかり大切なことを検討する時間が不足していた。
・アセスメントシート作成時間がもう少し欲しい。アセスメントとニーズの整理が重要と考える。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・前半は相談支援研修と重なる気がしました。後半をもっと深く知りたい、また、関係機関や地域の中での関係図等(マップなど)の作成等も、個別支援計画を意識した責任者にはとても役立つのでは・と思いました。
・演習形式なので理解しやすかった。しかし、児童分野ではアセスメント方法に色々な方法が取られておりニーズの把握も個人差があるように感じる。全てではないが一部でも統一できると良いと思う。
・もう少し時間をかけたい
・③は両親の選択に任せるべきではないか。要はここの5.は特に大切な部分ですので熟慮すべきかと思います。
・ビデオは施設紹介程度でよかったのでは。
・1つの事例を深めていくことは良いが、事例にこだわりすぎないようにサービス管理責任者としての視点を強調していく。
・個別支援計画書の理想的な書式、書き方(模範解答的なもの)があればよかった。
・各グループ発表しただけで終わったのでもう少し各々の計画について意見を言ったり各グループごとに他のグループについて意見を出し合ったりしたかった。(県の実施場面ではそれをするつもりです)
・提供された事例に基づいて具体的な検討ができたことで分かりやすかった。参加者の経験に差があり、性格等もよくわかりました。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・記入様式4のふり返りシートは、事例を自分の事業所であったらどう取り組むかについて記入することになっていたが、事業所の運営状況が異なる中では、記入しにくかった。
・今の所、考える余裕もなく、しばらくはこれでいいのでは・・・・。
・もう少し時間をかけたい
・演習3での時間をきちんとすればより効果的だったのではないかと思います。
・最後のチェック部分がどうしても流れてしまう感がある。前半部分はビデオ等交えて時間取り、じっくりという感じだったが、最終に時間が足りなかったように思う。サビ管としての評価をどう行うのかポイントかな、とも思うので。
・実際にどのような視点で役割を担うのか、具体的にもっと提示してほしい。
・各グループ発表しただけで終わったのでもう少し各々の計画について意見を言ったり各グループごとに他のグループについて意見を出し合ったりしたかった。(県の実施場面ではそれをするつもりです)
・「振り返りシート」の使い方が曖昧で、演習③に生かしにくかった。
・他県の方と知り合う機会となりその後も情報交換しています。
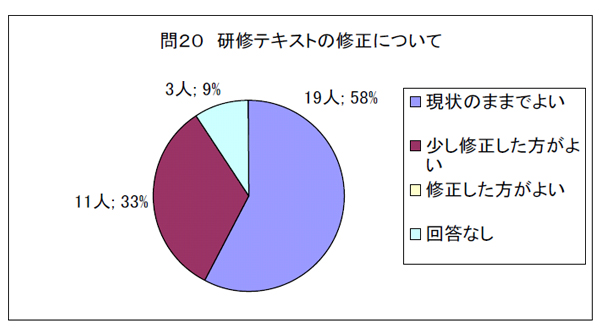
問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・今、そこまで考える余裕がありません。
・現状のままで良い
・しいて挙げれば仕事の流儀のところ。
・全体に見やすくまとめてもらっていたのですが、あまりに膨大な量で、流れとして理解しにくい。①に限らず、縮小し
てもらった方が後で見直しやすい。
・社会福祉サービスの枠組みについての説明をわかりやすく。
・総論的な講義の部分に児童関係のサービス体系について(現状、課題等)触れる資料があっても良いのではない
か。ライフステージのスタートでの立ち遅れを認識する必要があると思う。
・全体的に資料が多すぎる。もう少しコンパクトなテキストにして欲しい。
・詳細がわかり良いテキストだと考えますが、専門用語が多く、理解しにくかった。解説が必要。
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
2.サービス提供のプロセスと管理
・今、そこまで考える余裕がありません。
・具体的に事例の関係図等を書いてみるのもよいのではないでしょうか・・・
・現状のままで良い
・P6~7のイメージとイラストの感じが少ししっくりこないように個人的に感じました。また、イラストを修正し、日本人のものを使用していただきたいと思います。
・①②③と内容が重複していることも多かったように思う。各項目毎の内容が整理されるとよいと思った。(各項目間の整理)
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・今、そこまで考える余裕がありません。
・「連携を考える:実践を返して」よく理解できなかった。
・現状のままで良い
・③ではないですが通しの番号を打って、目次を作ってもらえれば、後で参考資料として活用しやすい。
・地域性を生かすこと(実際に社会資源の地域差は大きい)
・「連携」実践報告をもっと具体的にわかりやすく。
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・今、そこまで考える余裕がありません。
・現状のままで良い
・総論と講師の方の内容が少し不一致のように感じました。また、外国語カタカナが目立ち解りにくいこともあると思います。
・地域との連携についての実際
・使用されていた表が見にくかった。
・国研修レベルでは、先駆的事例をあげるのではなく、都道府県の共通講義の企画方法を重点的に研修した方がよい。
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・今、そこまで考える余裕がありません。
・研修で使用する為の事例の提供は主観的になりやすく難しいと思いますが、客観的に数値と状況を伝えるものであって欲しいと思います。
・事例として提出していただきありがとうございました。しかし、これが国の研修の手本となるかどうかは果たしてどうでしょうか。吟味の程をお願いいたします。
・サービス管理責任者の視点がさらに充実すると良い
・アセスメントのためのチェック項目を、ある程度項目だててあげた方が明確。
・時間配分などは1枚の用紙にまとめたので良いと思う。
・必要なツール(評価表、課題整理票)の見本様式がいくつか参考様式としてほしい。
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・個別支援計画表の様式3の作成するに当たって、当初の計画に対する評価、評価を受けた課題の整理(解決すべき課題)を記入する様式があれば、モニタリングがしやすいと思う。
・今、そこまで考える余裕がありません。
・時間を捻出して本人を取り巻くマップ作り等をしてみるのも面白いのではないかと思います
・現状のままで良い
・期間について詳しい説明がないので、期間の設定の意味について考え方について指導が欲しい
・実際に活用されている表を、資料として添付してもらえると有り難い。
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・今、そこまで考える余裕がありません。
・現状のままで良い
・情報交換の時間になっているが、この時間は有効であった
・活用に当たって、もう少しポイントを絞ってまとめてあると、チェックシート等も考えやすいのではないか。(事業所なりで検討して)
・新しい情報、状況、事例という点で修正して欲しい。
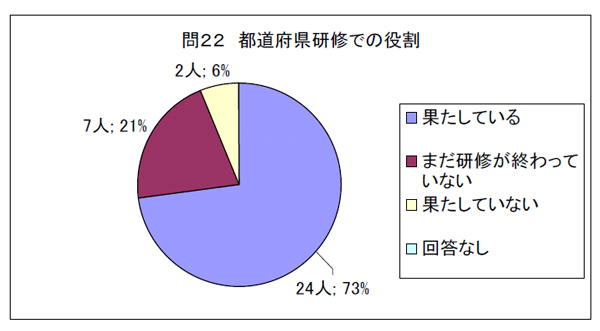
問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題
・現状では、事業所により、内容、受け入れている対象(未就学、放課後対策等)が違うため、実例をどのようなものにするか。また、児童デイサービス事業をよく知る助言者の人材の確保がなかなか難しい。
・今の所、どうにかやれているが課題というところまで行き着かない。
・児童デイサービスは県下で10数箇所で、グループ討議等に工夫が必要だと思います
・演習で個別指導計画の作成とサービス管理責任者のロールプレイニングを実際を取り入れてよかった。
・都道府県の現状と研修内容のずれを都道府県でどのように修正していくかが難しい
・事業所間の発達支援の業務認識に差があり、研修企画が難しい。研修が参加者に「個別支援計画作成研修」と感じられていること。
・9月の研修後に、他の分野の方々とお会いして打ち合わせしたのは1回だけですので、少し不安です。
・児童デイの分野は受講者が少なく、同じ児童デイでも週数回短時間のサービスやほぼ1日を過すタイプ、放課後支援などサービス形態の違いがあり、焦点の置き方が難しい。また、私ごとき立場のものが管理者と兼務の受講者の方に講義するのもおこがましい。
・児童デイを運営している事業所が少ないため、受講者が少ない。演習などグループが1グループ出来れば良い状態である。演習の内容や時間配分など配慮する必要がある。
・児童の事業所が少なく、児童分野は2年続けて県の研修を行っていない。他の分野をフォローする体制で行っている。
・読み聞かせるだけに終わってしまって、関心がもうひとつもてないという意見が多かった
・事業をすでに実施している所、そうでない所と混在し、理解にもかなり差がある中での研修は、同じ研修を受講してもその理解にはばらつきがあると感じる。どこにポイントを当てるのか難しいところかとも思う。また、参加者からはレベルアップのためのフォロー研修の声もあり、今後の検討課題と思われる。
・地域状況のなかで、事業所の数が少ない現状でがあり、さらに療育型が少ない。
・演習のケースをよりよいものにする努力が必要。
・相談支援従事者研修との違いを明確にしていく。
・実際の演習のモデルが紙面上でしか見えない点に苦労が多い。
・自分の事業所でのサービス管理提供のプロセスにおいて必要なツールの不備等、改善すべき点が多いので、県の研修の際、自前の適切な事例の提供が難しい。
・事業所の職員でないため、事例提供に苦慮している。
・直接業務に携わっていない県の職員が国の研修に参加し、伝達研修をしているため、現場に即した説明ができない。
・1年に1度の開催でフォローが必要ではないか。
・障害児通園事業としてもともと療育中心に行ってきた事業所と自立支援法の中でデイサービス事業として立ち上げてきた事業所との格差が大きいので研修の進め方が難しい。
・事例提供の準備が大変だった。
・研修企画のための打ち合わせ時間や作業時間の持ち方
・別に今のところ企画運営上難しいことは見いだしていません。
Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について
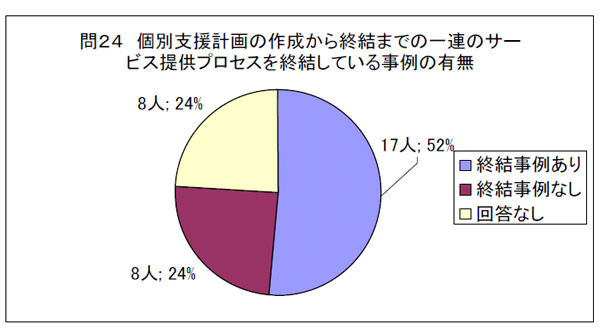
| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 職員会議の報告時・相談時担当から相談があったとき | |
| ・ | 相談終了後 | |
| ・ | 療育相談の報告の際 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | ミーティングを実施し、注意事項等を確認しておく。 | |
| ・ | 面接及び子供との遊びやかかわりの中で観察、助言 | |
| ・ | 調査票(主訴・関係機関・生育暦などの把握)のチェック、保護者との個別面接への同席, | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | アセスメント後、課題等の分析を行う際。 | |
| ・ | ニーズを整理している時 | |
| ・ | 療育相談時の療育の方向が報告された時点 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | クラス別ケース会議への参加,発達検査への協力、処遇会議-報告書作成のチェック, | |
| ・ | 項目ごとに情報が整理されているか職員で話し合う。 | |
| ・ | プラスの側面に目を向けるように、多面に目を向けるように伝える。(検査結果を冷静に分析する事など) | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 年2回(4月、9月)及び適時に | |
| ・ | 年度開始又は、通園開始60日内 | |
| ・ | 療育相談時の療育の方向が報告された時点 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | アセスメントの報告後、その児童の課題について検討し、目標を明確にする。 | |
| ・ | ポイントの置き方や作成においての留意点を助言する | |
| ・ | ミーティングを実施し、注意事項等を確認しておく。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | グループセッション時または終了時 | |
| ・ | 実際の療育の中で。 | |
| ・ | 職員の打ち合わせやケース会議の他、日々の療育の場で気がついたとき。相談を受けたとき。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 計画がうまく実施されていないとき、原因は何か、なぜできないのか、技術的問題なのかなどを話し合いをする。 | |
| ・ | その対象児の発達成長の様子が観ることが可能かチェック表を見ながら評価。 | |
| ・ | 他の支援方法の導入や工夫を助言する。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 対象児に変化の兆しがあったとき | |
| ・ | 児が変化した時、前計画立案から6ヶ月経過した時 | |
| ・ | 月1回 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | ケース会議を開催 | |
| ・ | 担当者と保護者との個別的な話し合いを重視し、原因を探り、対策を具体的に示すようにする。 | |
| ・ | 冷静にソフト面、ハード面のサービスの提供状況結果を分析するよう伝える。環境・技術などに問題があるのか。他の専門機関からアドバイスを受けるべきか話し合うよう伝える。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 卒園時期または、退園の時期に | |
| ・ | 目標を達成した時点 | |
| ・ | 各期ごとの個人面談 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | その対象児の終了時期において発達成長の変化が観られたか初期評価,中間評価と現在の様子を確認するという方法で。 | |
| ・ | 退所直前のミーティングで児についての振り返り・見直しを話し合い、家族に伝えるべき事項をピックアップする。 | |
| ・ | 面談と終了時評価のための検討会、まとめの指示と移行支援の実施 | |
| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 医療機関や行政からの紹介があった時 | |
| ・ | 初回面接時、継続相談時 | |
| ・ | 変化が生じたとき | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | ケースの必要性によって複数スタッフで対応 | |
| ・ | ミーティングを行い、職員間の意志疎通や職員同士の情報交換等に立ち会いながら進める。 | |
| ・ | 職員会議及び実践検討会を組織し、報告していけるようにしている。 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 保護者からの利用ニーズがあった時 | |
| ・ | 保育検討会 | |
| ・ | 利用開始直後 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | ケースの必要性によって複数スタッフで対応 | |
| ・ | 活動を通して、状態像の把握と記録の仕方について助言する。。 | |
| ・ | 職員会、ケース研、指導方法研究会等 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 通園1ヶ月以内 | |
| ・ | 計画立案時 | |
| ・ | 年度始めや各期ごとの見直し | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 専門スタッフや関わっているスタッフが複数で検討作成 | |
| ・ | サービス管理責任者が支援会議を開催する。アセスメント報告を踏まえ、作成された個別支援計画書を支援会議にて検討。 | |
| ・ | 職員に応じて立案を分配、その後、計画書の説明や妥当性を話し合い、内容を決定・共有する。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | グループセッション時または終了時 | |
| ・ | 実施中、質問があれば対処する。 | |
| ・ | 普段の療育の際、療育者からの申し出 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | スタッフが情報交換しあえる場を設ける。 | |
| ・ | 問題点や観察したことを話し合う場での助言等 | |
| ・ | 定期的な専門職導入の際の実践検討 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 児が変化した時、前計画立案から6ヶ月経過した時 | |
| ・ | 年間2期で見直し | |
| ・ | 各期ごとの見直し時、及び緊急時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 言語、認知、社会性、運動面などを取り上げて確実に出来ている点と達成できていない点の目標を取り上げてみるよう指導する。 | |
| ・ | 支援の評価と修正後の支援方法等の説明を行う。 | |
| ・ | 全体の流れ、やり方などについて職員会議を開く。修正点があればそれを加える。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | カンファレンス時 | |
| ・ | 担当者会議、面接場面で | |
| ・ | 各期の中間と終わり | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 記録のまとめを担当者から報告してもらい、評価を考察を全員で行う | |
| ・ | 退所直前のミーティングで児についての振り返り・見直しを話し合い、家族に伝えるべき事項をピックアップする。 | |
| ・ | 面有効な支援方法を確認する。 | |
| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 困難ケースで担当者からの申し出があった場合 | |
| ・ | 保健センターや、医大小児科・発達外来等の紹介で来室した状況で相談開始された場合。 | |
| ・ | 初回相談の前、必要に応じて連携 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 家族から保育所や幼稚園・他機関での様子を聴取。 | |
| ・ | 情報収集の必要な関連機関の把握 | |
| ・ | 他機関のサービス利用の状況を確認(その機関から情報を得てもよいか了解を取る。) | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 保護者の利用ニーズがあった際。 | |
| ・ | 初回面接時,年度開始時・途中又は修了時 | |
| ・ | 他機関の利用が必要と思われるとき | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 対象児が利用している機関から情報を得る。嘱託臨床心理士に発達診断を依頼 | |
| ・ | 学校や他事業所を利用されている場合は、情報交換を行う。 | |
| ・ | 直接又は間接的に情報交換や役割分担を行う | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 各専門機関との検討会 | |
| ・ | 関係機関、保育所など計画作成段階に面接(相互利用の施設) | |
| ・ | 入所2ヶ月以内に | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | PTや心理担当専門職から個別の評価をしてもらう | |
| ・ | 共通理解を深めるために会議に出席してもらう。 | |
| ・ | 保護者を通し関係機関での状況や他機関職員の意見を聞く。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 保護者への説明後。 | |
| ・ | 年2回のケース会議時 | |
| ・ | 専門職の定期的な実践導入時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 主に学齢児は学校まで出向き、担当教員へ個別支援計画について伝え、学校側の指導、療育現場の指導とのズレが無いかを確認している。 | |
| ・ | 個別面談で、保護者を通した関係機関での状況把握、日頃の状況を記入した連絡カードの使用、他機関職員の訪問の受け入れや電話連絡対応、 | |
| ・ | 情報を得ると共に協力依頼をして対応 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 外部との会議の時 | |
| ・ | 随時、再評価実施時 | |
| ・ | 利用者の状況変化のたびに | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 各関係機関とのケア会議を実施 | |
| ・ | 事業所への来所依頼で会議をもったり、電話で話し合いながら。 | |
| ・ | 保護者個別面談で得た関係機関での状況や他機関職員の意見をケース会議で報告する。 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 就学、就労時 | |
| ・ | 終了時評価において、他機関が必要と思われるとき | |
| ・ | 年度末ケース会議・報告書作成、終了ケース報告会 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 就園をする児童や就学を迎える児童については年度末または新年度に担当教員と連絡をとり、学校まで赴く。 | |
| ・ | 利用者了解のうえ、評価表を送付 | |
| ・ | 関係機関での状況や他機関職員の意見を報告資料に記入する。 | |
問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。
・今の所、連携が取れていません。
・(当方が相談支援ですが)逆に考えると、アセスメント時からニーズを元にどういう事業者がかかわっていくのか、選択肢を頭の中におきながら段階的に増やしながらスタートしていっているように思います。相談支援から事業者につないだ時点で個別支援計画を移動しそこで主体的な管理をお願いしています
・当事業所には相談支援専門員の配置がありませんが相談の仕事がダブル場合もあり、支援会議で調整、情報共有、仕事分担など調整することが必要。
・幼児期の子どもの場合、相談支援専門員が関わってくれるケースが少ない
・役割分担はしていません
・役割分担はしていない。(現事業所で分担の必要性については疑問)
・同一人物です。
・対象が幼児である場合には、詳しい相談に入る前に引き継ぐ
・当事業所には児童の相談支援専門員は所属しておらず、サービス管理責任者が主に対応している。相談支援の委託を受けている機関とは電話にてやりとりをしている。当事業所内で少しずつ生活支援センターの相談員と業務の役割分担を行っている。
・相談支援が中心 心理職、ソーシャルワーカー、教員で構成している。
・特に決まっていない
・地域的に公の相談支援専門員はなく、チェック表を参考に事業所内の職員と同等に発達支援を検討し行う。
・配置されていない。
・相談支援専門員は地域との窓口、サービス管理責任者は施設内の業務。
・相談支援業務をしていない
・視点の持ち方(ケアプラン等作成)。相談支援専門員は、トータル名視点。サビ管は事業所の視点(ただし、関係機関との連携)。
・重なっていることが多い。
・支援会議の際は中心的に動いてもらう。
・児童デイサービス事業としての相談支援専門員の配置はありませんが、当施設の中で相談支援専門員の業務にほぼ同等の業務を行う相談員を毎日1~2名を配置して、相談業務を行っています。
・専門員と兼務のため、それぞれの仕事内容を見直せるように他の相談員と話し合う。
問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。
・児童デイサービス事業の中で、サービス管理責任者が事業所内、地域の中でその役割を果たしていく為には、「ねばならない」ではなく、いまできていること、できていないことなどを整理していくことがまず課題だと思います。
・サービス管理責任者は、相談受付からアセスメント、ニーズの把握などケアマネジメントの過程を知り、実施できるという前提ありきで、その指導と職員の指導など幅広い能力を要求されるということだと思います。が、新体系への移行時期が近づいてきてとにかく受講しとかねば・的に参加されている方も多いと感じるなかで、そんな掘り下げた内容を求めるのは難しいのかな・とも思います。運営的には工夫しつつも赤字を免れない中で法律も少しづつちょくちょく変わっていく・・・責任者は大変と思います。また、せっかく福祉への志を持って就職したものの、福祉職のきつさとつりあわない報酬により離職していく職員も多く(正職とは名ばかりで家庭を持った男性職員が16万の手取りでは生きていけません。)研修を受けても離職してしまう可能性が大きいため、事業者もその器でない職員だったとしても年月さえクリアしていれば次々この講習を受けさせておかないと・と聞きました。そんな状態でなく志のある人材が長く勤められる福祉職になることが結果的には職員の方々の質の向上になり、利用者の方々の幸せにつながるのではと思いますが・・・
・サービス管理責任者として実際の仕事での難しさや、悩みなどを県でフォローアップ研修を積み重ねる事が必要と思われる。
・サービス管理責任者の責務は非常に重く重要なポストだと思います。しかし、現状では余剰人員を抱えることが難しい事業所の状況の中、減算はあっても加算のないサービス管理責任者の業務は軽視されていくのではないかと思っています。財政的にもサービス管理責任者の保障をしていく必要があると思います。
・サービス管理責任者として、利用者の人数が増加しても、サービスを必要とする人たちに十分な質を確保し続けること
またサービス管理責任者としての自覚を持ち続けること
・規模の小さな事業所ではサービス管理者が同時にサービス提供者になっていることが多く、時間的に管理者としての業務を行うことが難しい場合がある。
・私たちのよう事業所では、1人で何役もこなしているのが現状です。歌って踊れるサービス管理責任者でなくてはなりません。現場での仕事を終えてから個別支援計画を立てたり、職員の仕事のあれこれにアドバイスしたりして、毎日充実していますが、書類に関して100パーセント完全に作成することができにくとても歯がゆく感じております。療育の内容の書類はとくに求めていないのも気になります。個別支援計画よりも療育計画や個別指導の内容を記入したような書類も大切です。療育の中身に力を注いでいる施設もあることを心におとめいただきたいと思います。乱筆乱文お許しくださいね。
・相談受付時から個別支援計画を作成するまでの流れが、初回は事業所についての情報を得るための来園で、次は複数の事業所を比較検討の結果契約したい。ということが多く、アセスメントのための情報が十分得られないケースが多々ある。上手く情報が引き出せるような面談の仕方を学びたい。当事業所のスタッフは福祉職のみなので、当事業の利用児はST,OT,医療等、他の専門機関を利用しているが、そこでの支援内容と当園での内容を連動させるよう、上手く連携を図っていきたい。他のサービスを並行利用している児童に対しても児童が混乱しないよう、情報を共有したいところだが、保護者の了解を得るのが難しい場合が多く、課題となっている。
・サービス管理責任者の役割を十分に担っていくためには、今抱えている業務内容の見直しをしていかなければいけない。そのためには、行政や医療機関、学校関係との連携、そして何よりも職員一人ひとりのスキル向上が必要になってくる。サービス管理責任者の役割について理解はしているが、自立支援法が施行になる前の業務内容や役割等から抜け出せないでいる。
・発達障害者支援センターで自立支援法の中には、規定されていない。だだ相談支援が中心で行っているが、アセスメントから評価への一連の流れは必要か?しかし年間の相談ケースが多く出来ていないのが現状。発達障害を支援できる人材を養成することが、急務であると考える。
・療育を実際に持ちながらの兼任職務であり、なかなか行き届かない
・私が思うサビ管としての役割と仕事が、これまでの福祉施設・事業所等のなかで今までになかった画期的な大切な役割の仕事であると感じている。これから先、より推進できるように行政と共に進めていくべきであると考える。
・これまで、長い間、園独自の方法で作り上げてきたプロセス管理を全て見直し、本当によい支援となっているかを検討している。職員全てが納得し協力しながら良いシステムにしていくことをリードする事が必要である。
・地域自立支援協議会を設置し、他機関と連携しながらよりよいサービスが提供できるようにしていく必要がある。
・日々の業務に追われ、サービス管理責任者としての業務が充分に行うことができない。そのため、サービス管理責任者とサービス提供スタッフを分けて行えたら良いと思う。
・サービス管理責任者の役割を明確化。事業所での理解と役割等、まだまだ浸透されず理解されていない。今後の位置づけが課題。
・なるべく期待された役割を果たせるよう、様々な意味で自己研鑽に励まなければと思うが、制度としてはあまりにも多くのことをサービス管理責任者に求めすぎていると感じる。各分野を一元化した法律であるがためにそのような印象を受けてしまうかもしれないが、分野や業務に合わせてサービス管理責任者の仕事を分業・専門化していくことも必要。
・サービス提供職員との意見のずれに対し、どのように納得、展開していくか非常に難しい面が多くあります。
・サービス管理における総括責任者として、「職員への技術指導・助言の充実」の他に、関係機関や相談支援専門員との連携等、広いネットワーク調整をどう進めていくかが大きな課題と思われる。
・サビ管と相談支援専門員との役割分担の整理が国レベルでできていない。理想的には「どちらも同じ」と言いたいことは私も納得できるが、現場レベルを考えた場合、きれいにすみ分けしないと法の土台部分が崩れると思います。
・利用者の人権を護り、福祉の向上に寄与する責任ある仕事だと思います。仕事ができるような任務配置や時間、就労条件などを整えていくべきと思います。
・利用者や家族に信頼されるカウンセリングマインドのある対応ができること。多様な障害への理解があり、どう関われば良いのかわかっていること。関係機関との連携が取れること。
・さまざまな分野から常に情報収集できるようなフットワークの良さ、敏感さ(アンテナをはりめぐらせて)等、多様で専門的でそして一般常識センスをもつということを担う大変な課題があると思っています。兼務では大変です。
【就労分野】集計結果
Ⅰ 回答者の事業所等について
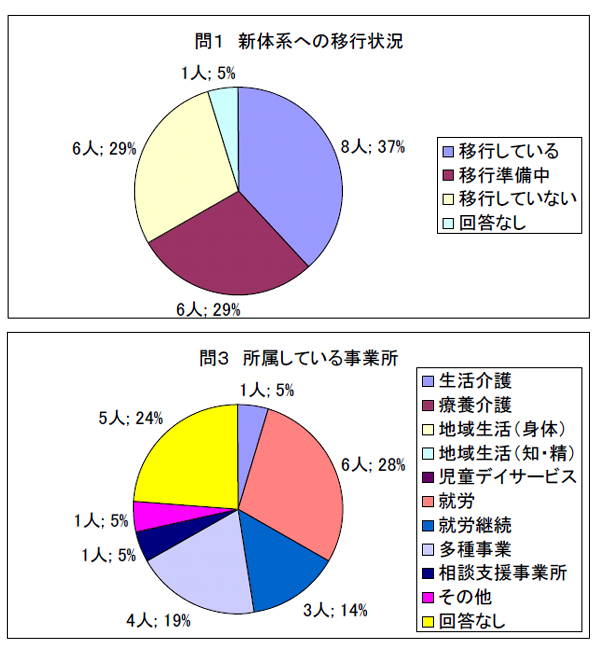
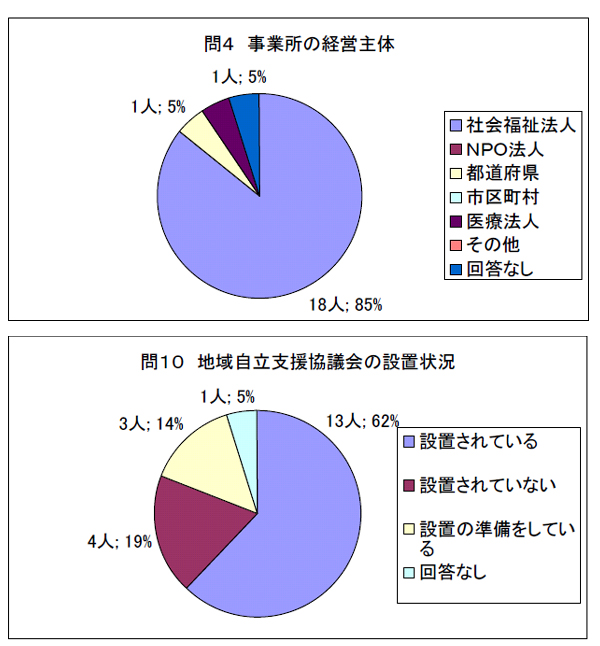
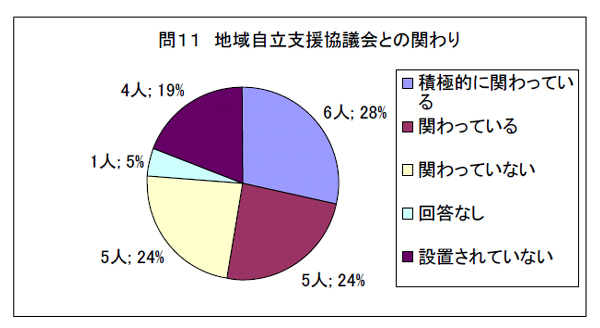
Ⅱ 国の指導者研修の内容について
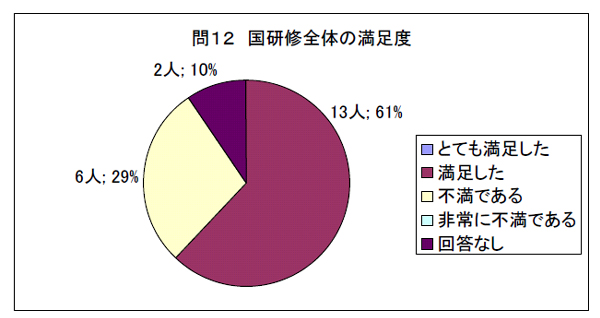
問13.国の指導者研修の満足度(問12)の理由
・グループワークが多く、中途半端に話が終わることもあったが、経験豊富な意見を聞くことができた。
・先進地域の話や新しい試み等が内容に盛り込まれており、刺激にもなり参考にもなった。
・サービス管理責任者の役割がとても明確に理解することができたから。また、理論だけでなく実践に基ずいた話しを聞くことができたから。
・就労支援の制度、また事例等をとおした演習で具体的な支援方法を学べた。
・資料をこなす為に講義(説明)が短すぎる。
・あまりにもメニューが多く、自分自身に入りきらなかった不満もあるが、自分自身の「支援」してきた理念と,支援法の内容がかけ離れていてしっくり来なかったし、そこに入るまでがしんどかった。演習は大変よかったと思う。
・国が示しているサービス管理責任者の役割には疑問や矛盾を感じる部分が多く、それに対応するような研修内容が組まれていないため。
・共通講義は「満足した」、分野別は上記です。以下、別紙記載
・県の研修を計画するにあたり、参考になった。
・就労について 就労・生活支援センターの講師・事例が中心だったため
・就労分野の研修内容は、就労移行支援に関することが中心であった。本来であれば、一番多い就労継続支援B型を中心に進めるべきであったと思う。来年度からは修正していただきたい。
・企業側の講師については、就労支援の立場や視点など明確で分かりやすいが、福祉側の講師は、就労・生活支援センターの事業内容の報告的な研修内容になっている感じがする。また、施設職員の経験しかない者にとっては、3日程度の研修では、情報や知識が多すぎて整理できていないようである。
・内容の充実度・ボリューム度としては、十分すぎるくらいの量であったように思われますが、中身についてすべて理解できるだけの時間が確保されていたかというと、少し消化不良を起こしたように思います。
・18年度県での就労サビ管研修を受講しましたが、私自身その時の理解と違った感覚で、研修内容が頭に入ったと思います。又全国の事業所(施設)や関係機関の方との出会いの場になりネットワーク、連絡の取れる関係ができたことは、自分の大きな財産になりました。
・サービス管理責任者の役割・就労に関する労働行政の考え方・就労の先進地域での取り組み等が学べた事。
・就労支援までのプロセスを再確認できた。
・講師がチームワークをとって研修を組み立ててくださり、「意識改革」という課題が明確に伝わった。分野別講義内容が充実していて、意識改革の大切さを考えさせられた。
・積極的な実践例がとても参考になった。
・全国の情況が理解できた。
・時期的に長期参加は厳しかった。内容が広範囲にわたり全てを吸収・理解するには無理があった。
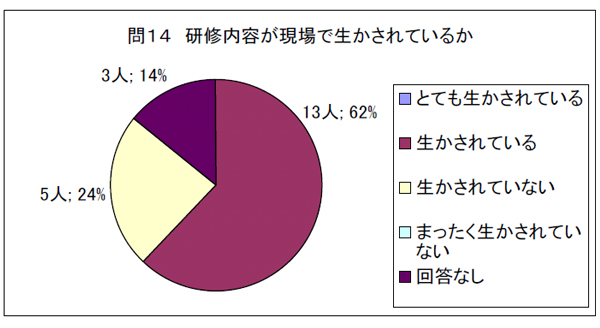
問15.国の指導者研修の内容が現場で生かされているかどうか(問14)の理由
・まだ月日があまり経っておらず、生かされているかどうかはまだ結果が出ていないが、サービス管理責任者として自覚は以前より格段に深くなった。
・支援計画を立てる時にも参考になっている。
・現在、トライアル雇用中の利用者や就職活動中の利用者がいるため。企業へのアプローチや利用者の支援についてとても参考になったから。
・当事業所ではまだサービス管理責任者を配置する事業は実施していないが、他機関と連携して支援を行う場合において生かされている。
・資料の熟読により、現場で役に立っている。
・研修でいただいた様式等、もちろん県の研修でも使わせていただきましたが、現場でも活用させていただいております。
・国の研修内容は目一杯のカリキュラムで読み込むのに苦労した。自分自身で整理した上で県の研修を企画しようとしたが、実際、整理するのも難しく結局国の研修そのままの内容で県の研修も実施したが、受講者からも私同様に目一杯の内容でわかりずらいとの意見も出ていた。
・職場は自立支援法上の施設ではないが、基本的姿勢や知識など参考になったため。
・就労について 就労・生活支援センターの講師・事例が中心だったため
・問13で回答したとおり、就労継続の現場で生かされる内容ではないので。
・工程分析や連携等についての視点などは生かされているが、昨年地元で受講した修了生の仕事内容を見ると、アセスメントやプラン作成に係る会議の時間が十分に持てず、日常の支援業務や作業に追われている実態がある。
・現場では、これから活かされていくと思いますが、今は先日(22日・23日)開催した富山県のサービス管理責任者養成研修の就労部門を無事終了させた安堵感の方が強いといった状況です。
・地域・地方(県内)のスケールで考えていてはいけないと思いますし、国の研修に参加することで自分自身の見方も幅広くなったと思います。施設職員の意識的なものも変化したと思います。県内での事業所(施設)の障害枠を超えた連携も広がりつつあると感じている。
・サービス管理責任者の姿勢・意欲・工夫等で、利用者の方を就労に導く事が出来る可能性を感じた事。
・関係機関との連携がスムーズにできるようになった。
・自己意識が変わり、その面では現場で新しい取り組みに生かされている。一方でその後の研修会運営業務が日常業務にマイナスになっている(他の職員への負担)。
・管理者としての立場が認識できた。
・まだ月日があまり経っておらず、生かされているかどうかはまだ結果が出ていないが、サービス管理責任者として自覚は以前より格段に深くなった。
・支援計画を立てる時にも参考になっている。
・現在、トライアル雇用中の利用者や就職活動中の利用者がいるため。企業へのアプローチや利用者の支援についてとても参考になったから。
・当事業所ではまだサービス管理責任者を配置する事業は実施していないが、他機関と連携して支援を行う場合において生かされている。
・資料の熟読により、現場で役に立っている。
・研修でいただいた様式等、もちろん県の研修でも使わせていただきましたが、現場でも活用させていただいております。
・国の研修内容は目一杯のカリキュラムで読み込むのに苦労した。自分自身で整理した上で県の研修を企画しようとしたが、実際、整理するのも難しく結局国の研修そのままの内容で県の研修も実施したが、受講者からも私同様に目一杯の内容でわかりずらいとの意見も出ていた。
・職場は自立支援法上の施設ではないが、基本的姿勢や知識など参考になったため。
・就労について 就労・生活支援センターの講師・事例が中心だったため
・問13で回答したとおり、就労継続の現場で生かされる内容ではないので。
・工程分析や連携等についての視点などは生かされているが、昨年地元で受講した修了生の仕事内容を見ると、アセスメントやプラン作成に係る会議の時間が十分に持てず、日常の支援業務や作業に追われている実態がある。
・現場では、これから活かされていくと思いますが、今は先日(22日・23日)開催した富山県のサービス管理責任者養成研修の就労部門を無事終了させた安堵感の方が強いといった状況です。
・地域・地方(県内)のスケールで考えていてはいけないと思いますし、国の研修に参加することで自分自身の見方も幅広くなったと思います。施設職員の意識的なものも変化したと思います。県内での事業所(施設)の障害枠を超えた連携も広がりつつあると感じている。
・サービス管理責任者の姿勢・意欲・工夫等で、利用者の方を就労に導く事が出来る可能性を感じた事。
・関係機関との連携がスムーズにできるようになった。
・自己意識が変わり、その面では現場で新しい取り組みに生かされている。一方でその後の研修会運営業務が日常業務にマイナスになっている(他の職員への負担)。
・管理者としての立場が認識できた。
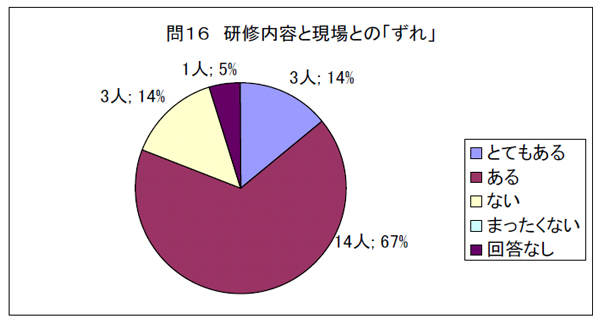
問17.問16で国の指導者研修の内容と現場とのずれが「とてもある」「ある」と回答した人の具体的内容
・人員配置等により研修のようには実際はいかないこともあるように思いますが、理念を知り意識を変えていくことが大切とは思います。
・まだ、○○ができなくては就労ができないと考えている職員がいるため。また、企業側も障害者の雇用について消極的なところも多いため。
・当事業所においてではないが、他施設(前小規模作業所等)では就労を支援するにあたり当地域での障がい者雇用状況等含め必ずしも体制が整っていないとの話を聞く。(現在の利用者が、はたして現実的に就労できるのか)
・一例として、利用者さんを実習に出すために会社訪問をする場合に、利用者さんのことで会社の人に「わからない」と答えることは考えられない。
・サービス管理責任者の役割として理念・意義は十分にわかるし、必要であると思うが。業務量や役割からすると、今後時間をかけていく必要があるように思われた。
・個別支援計画の捉え方であるが、国は生活全般の支援計画と捉えているが、日中計にサービスの場合、現実に親御さんや本人はそこまでの支援は望んではなく、利用している時間帯での支援を望んでいるので、生活全般の支援計画を立てる事は現実的に困難。もっと現実に近い個別支援計画のあり方を示唆して欲しい。
・今回の研修を参考に、県の研修の講師を実施したが、受講生である実務をしている方々の中には、サービス管理責任者の基礎となるところの理解ができてない方もおられるように思われた。
・地域性の違い 施設への減収 マンパワーの不足等
・問13、15で回答したが、現場は就労継続事業B型が中心であるため。
・地元の受講者の多くは新事業体系の就労支援事業を十分に理解してなく、A型やB型の違いから説明が必要である。また、多様な事業主体の参入により専門用語の知識が少ない受講生も多く、高齢者の受講も多いため、対象者によって国の内容をさらに分かりやすくする必要がある。
・まだ、現場においても、県内就労サビ管研修会に参加されている方の中ににおいても、福祉的視点のウエイトが強すぎ、就労的支援のイメージがとらえづらい感じを受ける。
・就労分野は非常に地域性が考えられますので、就労移行支援等への取り組みの遅れ・企業就労に関する考え方・地域ネットワークの考え方等。
・サービス管理責任者の役割が明確でない。
・社会資源の多様さ、その数が違うこと。新体系移行以前から小規模施設が中心であり、補助額の格差から職員に専門職がいない。つまり、経験年数だけでサービス管理責任者の資格を有する者がほとんである。
・システムとして導入するゆとりが現場にはないのでは。
・行政も現場も今あることの対処、対応に追われる中で、研修の本質の部分まで意識出来ていない現状。
問18.国の指導者研修の内容で良かった点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・障害福祉計画、三障害一元化、ニーズ、個別支援計画、PDCAサイクル等の管理責任者として基本的な部分を総論として学ぶことができ、大まかなイメージを掴むことができた。
・サービス管理責任者の役割について明確になった。
・管理者とサービス管理責任者の業務の比較
・PCP
・どの項目もであるが、少しずつでも事例が入っているのはよいと思う。
・地域自立支援協議会の位置づけが理解できた。管理者とサービス管理責任者の関係がよく理解できた。
・「ハコからニーズ」「将来像を見据えた支援」「本人が主人公」などはとても大切なことであり、また何がどう変わったのかがわかりやすく示されていました。
・あらゆる福祉サービスに通じる話で、とてもわかりやすい講演だった。
・詳しくはなかったが要点は抑えていたと思う。(以下同様)
・講師の穏やかだが熱い語りでサービス管理責任者の役割の重要性がしっかりと伝わってきた
・専門官の分かりやすい講義であったことはもちろんですが、仕事の流儀やサビ管としての立ち位置が具体的に理解できたと思います。
・サビ管の業務内容例が具体的に示されていて分かりやすかったと思うし、管理者とサビ菅の業務比較例①②は特に法人側に伝えやすい資料である。又県の講習会においても管理者やサビ管の1人の力では事業は成り立たないことの説明になったと思います。
・サービス管理責任者の業務・立ち位置等が理解できたと思います。
・テキストの内容が明確でよかった。
・役割が明確にされ、理解できた。
・制度の確認ができた。
・自立支援法の目指すものが理解できた。
・サービス管理責任者にとって「連携」の必要性と視点が分かって良かった。
2.サービス提供のプロセスと管理
・本来あるべき利用者中心の支援というものを理解することができた。
・評価を行い、本人の了解のもとに情報提供していくことの大切さと、サービス管理責任者としてサービス内容のチェックや支援会議の運営をしていくことで管理を行っていくことが理解できた。
・利用者への個別支援計画の作成はもちろん、サービス提供職員へのマネジメントにおける留意点
・ICF、山田さんの実例紹介
・テキストで自立訓練の個別支援計画の例を出してくれたのは良かった。
・ICF→エンパワメント→利用者が物語の主人公として如何に動くか、という流れは理解しやすいものでした。各プロセスにおける注意点、留意点も私たちが陥りやすい間違えを押さえていたと思います。
・新しい考え方などについて、わかりやすい説明であった。
・ 説明も分かりやすく理解しやすかった。
・個別支援計画の内容について再確認できただけでなく、長野県の実践事例について聞けたことは、サビ管としての具体的な役割のイメージがつきやすかったと思われます。
・国際医療福祉大学高橋泰氏の従来の障害モデル・サービス(ケア)とは・ICFな(生活機能の)見方・等の図式説明は、理解しやすかったと思います。
・サービス提供の基本的な考え方が学べ、実践編ではリアリテイがあり良かった思います。
・サービスのプロセスが再確認できた。
・必要ツールの例示があり、現場で活用できた。
・フローチャートがわかった。
・プロセスの確認が出来た。
・質の評価と質の向上。個別支援計画の作成。
・個別支援計画の視点が整理できた。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・法律上に規定された連携・調整の重要性が理解できた。個別支援計画が連携のツールであるということで、まさにその通りだと実感した。
・連携について、実践に基づいた話が聞けたことが良かった。
・利用者に対する支援の発展段階のわかりやすさ(事業所内会議~地域自立支援協議会)、また事業所内で支援を完結させない、地域で支援していくという考え方
・地域自立支援協議会の本来の役割
・連携についてはわかりやすかった。ただ、「あとは各地域で」といわれても、支援者不足、支援内容の変化などを考えると、単純に連携といっても、いいことだけを伝えなければならないが、行き詰るような気がしてならない。
・先行地域の例が多くでておりわかりやすく参考になった。
・事例などがあり、わかりやすかった。
・「連携」について改めて考えさせられたことはとてもよかったと思っています。またネットワーク、フットワーク、チームワークについてもよく理解できましたし、就労では、「ハローワーク」も大切であると自分なりに加筆いたしました。
・大塚晃専門官のお話でワークつながりでの説明や、Aさんの場合の実際のサビ管を想定された講義でありすごく伝わることが私自身出来たと思います。又私も田中康雄先生の本を読ませて頂く良いきっかけになりました。地域の自立支援協議会に対しての考えも新たに思うことも出来た。
・地域自立支援協議会・地域との連携等の考え方は勉強になりました。
・質の高いサービス提供において重要であり、当事業所の課題点が見えた。また、現場とのズレを感じ、地域としての課題を考えることが出来た。
・関係づくりがわかった。
・具体的事例がよかった。
・責任者が必要。地域づくり。会議のイメージ。チームワーク。
・連携の定義・必要性を明確に伝えたいと思った。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・働く場合に適材適所を実現するには必ず「人を知る」ということが大切であるということが理解できた。
・就労を支援していく支援者として必要な事柄を具体的に聞くことができ参考になった。
・実際の事例を使った事例研究であり、具体的なケース検討ができた
・労働者か訓練生か
・実際のアセスメントシートが出てきて良かった。
・企業系の講師の話は分かりやすく、就労支援に向けた各種の視点について理解しやすかった。
・関先生をはじめ親しみの持てる講義の背景には、やはり実践が伴っていることをしみじみと痛感させられた次第です。(県の講義では、これを伝えることは難しい)
・分野別講義では、事例や先行事例・就業・生活支援センター・特例子会社の講義であり、講義される方が短時間で変わり内容にメリハリを感じ受け取りやすかった。このような形式はとても良いと思い県内においても3名~4名の講師が進めてまいりました。
・働く事の意味合いや先進地域の取り組み等の説明を良く、頑張ろうと意欲が沸きました。
・アセスメントの事例があり、わかりやすかった。
・工程分析では日頃感じていたことが確信でき、講義、演習で取り入れたいないようであった。
・具体的事例が良かった。
・マネジメント事例、グループワーク。
・アセスメントの定義、モニタリングの手法の整理ができた。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・サービス管理責任者として支援に対する細部にわたっての視点が必要とされていることがよく理解できた。
・具体的に就労につなげていくプロセスを聞くことができ参考になった。
・福祉施設内での作業を工程分析することにより、利用者の能力能力を改めて評価できるという観点。また可能性を探ることで一般就労への道が開けるなど職員の意識が変わること。
・職業アセスメントの視点や手順が分かりやすく説明されていて良かった。欲をいえば、昨年使用した映像も合わせて使用していただければ、さらに分かりやすいと感じた。
・企業的感覚に加え、起業的感覚も必要であり、いずれも経営感覚を意識できたワークはとても有意義であったように思います。また、グループワークでは、結果よりも討議の過程に意識を持てたこともよかったと思います。
・事例を通して、サービス管理責任者の取り組み等が学べ、有意義かつ意欲をかき立てられました。
・事例のその後の展開の話が良かった。
・これからの取り組むべき企業体験をどういかしていくかの指針となった。
・具体的で分かりやすかった。
・簡易事例、グループワーク。
・研修の中でアセスメントの管理まで新しい理解、情報がなかった。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・実際に計画を立てるだけでなく、サービス管理責任者も管理者や他者から評価されるという体験ができ、非常に重要なことであると感じた。
・簡易個別支援計画表を用い具体的な支援計画を作り、討議することによって他事業者との連携や地域で支援することの重要性を再認識できた。
・長期的な支援を見据えて、どうストーリ-(献立て)を作っていくかが必要であるということを学んだように思います。
・事例を通して、サービス管理責任者の取り組み等が学べ、有意義かつ意欲をかき立てられました。
・事例のその後の展開の話が良かった。
・障害ごとの事例など幅広く取り入れており、現場とのつながりが演習できた。
・プロセスの確認が出来た。
・簡易事例、グループワーク。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・提供サービスを定期的に振り返る機会を持つことの重要性を理解できた。
・模擬会議を行い、時間をかけてグループ討議をしたことが印象に残っている。
・1施設、個人で就労に向けての取り組みをするところが多いため、都道府県で働く環境をどのように作っていくかを考えることで、地域でいかに連携ができていないか、どう連携を作っていくのかを改めて考える良い機会になった。
・新規雇用事業体を作るという模擬会議の演習だったが、地域の資源や特性、人的ネットワークを把握しておくことはもちろん、企画・発想力の大切さを感じた。
・新事業のプレゼン
・演習の中では一番盛り上がった内容で良かった。
・新規事業の立ち上げに向けた企画力や経営感覚力に加え、プレゼン能力を意識することができてよかったように思います。
・各施設の現状や今後についての意見交換ができた事が良かったと思います。
・グループ討議をとおして発想の転換を学ぶことが出来た。
・マネジメントの確認が出来た。
・常に利用者の立場に立つ。
問19.国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・どの項目でも、新しい語句・カタカナ語の解説を、できれば用語集としてどこかにまとめてあれば便利と思った。
・やらなければならない内容をきちんと明示し、欠如減算や未作成減算についてもきちんと説明が必要
・なぜ、サービス管理責任者が必要なのかを意識化させることはもちろんですが、ただ義務設置だけではなく、それに対する身分保障やモチベーションが向上するようなメリットも国として、明確に打ち出した内容の資料もいただければと思います。
・就労移行支援だけではなく、就労継続支援事業の説明も必要だと思います。
2.サービス提供のプロセスと管理
・国が示しているような生活全般を捉えた視点での個別支援計画となると複数の事業所を利用している人(例えばグループホームと自立訓練(生活訓練)はどこが主導権を担うのか、それぞれの事業所が同じような計画が打ち出される事になり利用者は困惑するのではないか。このあたりに矛盾を感じる。
・分野ごとに、あり方を明示
・個別支援計画の作成等、一連のプロセスが分かりやすく説明されている。反面、この講義の内容が理解されていな
ければ支援計画の作成が上手くできないため、講義だけではなく簡単に演習を交えて支援計画の作成過程を練習しておくと、後半の個別支援計画の作成が捗ると感じる。
・個別支援計画作成の基礎的な部分というよりは、むしろ実践事例の中で、サビ管がどう関わって作り上げていくのか、そのコツやヒントやサビ管としての視点について、何よりも各県に戻って指導者になる立場として、受講していることを意識した内容のものになっていると嬉しいかと思います。
・もう少しわかりやすく説明して欲しかった。事例発表は具体的に現場の事例を交えて報告して欲しい。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・地域自立支援協議会のイメージは掴めたが、具体的な設置・運営方法など実務的な内容があれば良かった。既存の地域サービス調整会議の今後のあり方など。
・これから就労移行支援事業等で、はじめてサービス管理責任者になる受講者にとっては、話の内容は理解できても実際には困ると感じた。事業所(利用者)を中心に、そこから具体的にどう連携していくかさらに初心者向きのパターン図を用意していただくとありがたい。
・講義の部分については、十分理解できましたが、やはり実践の部分で、連携によってどう成功したのか、また連携がなかったためにどう失敗したのか、さまざまなケースを事例集として1冊にまとめあげてもよいかと思います。その際に、サビ管ポイントメモがほしいと思います。
・県内研修会においても私が講義を受け持ったところであり、実際に県内のサビ管研修にあたり県独自の連携についての○○市町村はこのような連携事例がある、だからこうだ、等の県内事情を講義に盛り込むことが必要であると思う。(国の研修会でなく県の研修会において考えることである。)
・もう少しわかりやすく説明して欲しかった。事例発表は具体的に現場の事例を交えて報告して欲しい。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・就労分野については、内容が多岐にわたっており(必要なことだとは思うが)、講師もめまぐるしく変わりもう少し整理できないものかと思いました。
・一般就労への取り組みも大切であるが、就労継続の事業所での問題や課題についても時間を設けてもよかったのではないかと考える。
・資料の様式について、分かりづらい点あり、より詳しく説明あればありがたかった。
・示されたアセスメントシートの説明にもう少し時間をかけていただきたかった。
・内容や方法を検討すべき
・分野別の講義①のタイトルが「人たるに値する」働き方・・・とあるが、この表現は誤解を招く印象があり、地元の研修では使用しづらい。労働基準法では「人たるに値する生活を営むため・・・」とあるので、表現を変えていただけないか。
・充実しぎるくらいの盛りだくさんの内容であったように思います。その中でも、“「はたらく・働き続ける」をあたりまえに”の冊子のポイントを示してほしかったように思います(時間がとにかくなかった・・・)。
・もう少し講義内容を絞った方が良かったと思います。就労の難しさを感じました。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・時間が足りなかった。
・簡易ではなく、しっかりアセスメントを行うことで、就労に向けての様々な課題を考えるようにした方がよかったのではないかと思う。
・事例が「さおり織り」だったために発想の幅を制限(自分で)してしまった。
・さおり織り自体がメジャーではなく、さおり織りから工程分析や就労、A型事業をイメージさせるには無理がありように感じます。もっとわかりやすい題材の方が考えやすい。
・内容が多岐にわたり、時間が足りないものもあり、やや消化不良であった。
・内容や方法を検討すべき
・就労分野では、いわゆる生活アセスメントと職業アセスメントがあり、「アセスメントが重要」と誰しも言うが意図する内容が異なる講師が入れ替わり教示くださるため頭の整理がしづらい。研修は双方の視点から午前・午後と分け、どちらも重要だと言う形にしていただけると分かりやすい。モニタリングも同様。
・事例については、やはり講師陣の模範的な解答が1枚あって、その中から、サビ管としてのポイントについて気づかせるような演習であればもっとよかったように思います。とにかく、県に戻って指導者となるので、自分達が事例の仕掛けポイントを知らないと、県の受講生への気づきをもたらせないので。
・単純な作業における工程分析の説明が必要だと思います。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・時間が足りなかった。
・事例からすぐに簡易個別支援計画(5カ年計画)を作成するのではなく、アセスメントをしっかり行った方がよかったのではないか。モニタリングによる個別支援計画の修正や変更の時間を設けてほしかった。
・時間的に余裕が無く一つの事例をより丁寧に検討したかった。
・事例ケースの背景が見えなさすぎ(今このケースはどういう立場で、どういう事業所を利用したと想定するのか等)で、個別支援計画を作成させるにはかなり無理があるように感じた。この部分が現場サイドとしては一番聞きたい所、学びたい所なのでもう少し時間をかけ丁寧でわからりやすいものにして欲しい。
・事例の数が多く、取り組む時間が短く、また焦点がしぼれていないように感じたため、内容を絞ってもよかったのではないかと思われる。
・内容や方法を検討すべき
・就業・生活支援センターでの事例を参考に今回の演習事例が作成されているためか、そこにサービス管理責任者が不在の事例が多かった。できれば、旧授産施設や就労移行支援・継続支援事業をモデルにした事例の方が、受講者にとっては身近な事例として取り組みやすいと感じた。
・事例については、やはり講師陣の模範的な解答が1枚あって、その中から、サビ管としてのポイントについて気づかせるような演習であればもっとよかったように思います。とにかく、県に戻って指導者となるので、自分達が事例の仕掛けポイントを知らないと、県の受講生への気づきをもたらせないので。
・障害別の事例研究は良いと思いますが、設定された時間内では無理があったと思います。
・もう少しグループ討議の時間が欲しかった。
・計画作成については、ケアマネ研修でしっかり理解されていると思われるので、ここにあまり時間を費やすと管理者の力量の部分が薄いのではないか。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・時間が足りなかった。
・他グループの発表など参考になったが、特定の事業所の宣伝のようになった感もあった。
・内容や方法を検討すべき
・各種の情報提供の内容や視点が、就業・生活支援センターからのものであり、受講者にとっては現場から遠い話のように感じた。実際に日々利用者の各種支援をしながらも就労支援に向けて頑張ろうとする職員の参考や励みになる内容構成であるとありがたい。
・模擬会議については、それぞれ出たとこ勝負のようなグループ討議にはなりますが、ただ企画を上げるだけではなく、そこには、企画部長であり、事業本部長であり、工場長でもあり、そして営業部長でもある立場がサビ管であることを意識させられるような演習にもっともっとしていただきたいと思います。
・地域性が考えられる仲で、何処にレベルを合わせて説明するかが難しいと思います。
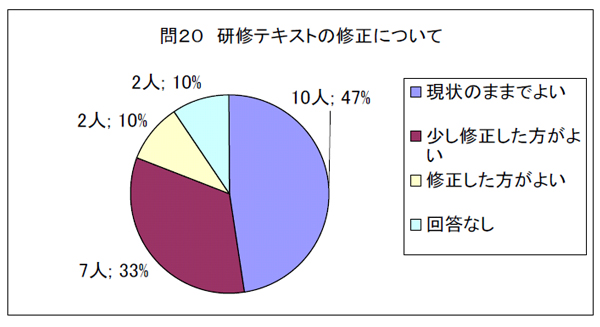
問21.テキストの内容を具体的にどう変えたら良いか。
1.障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
・パワーポイント資料はもったいないような気もするが・・・また、図式はわかりやすいが、概念図が大雑把過ぎてそれが実際誰で、何なのかとかいったことはしっかりと明文化するべきである。といつも思っている。
・暫定支給決定等についてもきちんと説明すべき、サービス管理責任者の意識、責任付けが大切
・県での「指導者」としての立場を意識していただき、ぜひとも伝えなくてはいけないポイントについて、指導者ならではの手引書となるような体裁にしていただけたらと思います。最初の講義の部分なので。
・全体的に縮小した形でのプリントにして欲しい。荷物になる。研修後、データを送って欲しい。
2.サービス提供のプロセスと管理
・自立訓練の他のもう1~2事例の個別支援計画を載せて欲しい。
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・個別支援計画等の様式で詳細な記入例があるものを資料として添付していただきたい(事業別・主たる障害別などにより参考になるものがあると初心者は助かる)
・サビ管の視点が随所に記入してあったので、とても分かりやすかったと思います。
3.サービス提供者と関係機関の連携
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・A型・B型・就労移行のそれぞれを中心にした地域とのネットワーク図があると分かりやすい
・講義部分については、問題ありませんが、各県に持ち帰った場合を意識したワークシートを1枚作成してはどうでしょうか。連携図が書き込めるようなものが作成されたら面白いのではないかと思います。どこの連携が足りないのか1目で分かりますので。
4.分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
・このコマで配布され説明された各資料は就労移行支援事業であれば役立つ可能性はあるのかも知れませんが、それにしても一定の予備知識がないとハイレベルで難解な内容ですので、使いこなすのは容易ではない上に、各都道府県でこれを説明し、受講者に納得してもらうことは至難だと思われます。
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・酒井氏の企業就労への方法論は参考になるため、半日全部を使って、さらに具体的に詳細に就労に向けた流れを説明いただきたい。この講義が深まれば各機関等との「連携」も出るので、具体的に「いつ・だれと・どのように・何のために・どれくらい」連携することが必要か見えてくると期待している。
・サビ管からの素朴な質問をQ&A方式で、まとめたものを伝えるだけでも面白いかと思います。きっとどこの県でも、今ひとつわかっていないのが現状かと思います。
5.サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
・簡易ではなく、しっかりとしたアセスメントを行い、就労に対しての課題を考えてもよかったのではないかと思われる。
・さおり織り自体がメジャーではなく、さおり織りから工程分析や就労、A型事業をイメージさせるには無理がありように感じます。もっとわかりやすい題材の方が考えやすい。
・「工程分析」を研修の一コマに入れることは有効だと思いますが、何を理解し、持ち帰ってもらいたいのか、焦点が今ひとつ絞り切れていなかったように思います。もう少し簡易な作業例を基にすれば理解度は増すのではないでしょうか。
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・生活と就労は一致的なもので切り離せはしないが、受講者の理解を考えれば分かりやすい構成にしていただけるとありがたい。
・昨年同様の事例を活用するのであれば、やはり蓄積された検討内容を公開され、どう議論しつくされたなのか、その裏舞台を解き明かしていただくと、サビ管としての指導教材になるかと思われます。
・テキストの内容の変更ではないのですが、参考に事例の記載例があればと思いました。
・もう少し実例を積み上げて作り上げていくか、それぞれのアセスメントのパターン検証をしたい。
6.サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
・参考として、アセスメントから個別支援計画、モニタリング、終結までの事例を掲載してほしい。
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・事例を分かりやすくするために、「A型・B型・移行支援」と主たる障害別にして用意すると、受講者が自分の業務に直接関係する事例で取り組めるので理解が早まると考えます。法制度の利用は、それぞれの施策をまとめて表などにしたものがあると、時間短縮も図れ、理解できやすいのでは。
・昨年同様の事例を活用するのであれば、やはり蓄積された検討内容を公開され、どう議論しつくされたなのか、その裏舞台を解き明かしていただくと、サビ管としての指導教材になるかと思われます。
・テキストの内容の変更ではないのですが、参考に事例の記載例があればと思いました。
・もう少し実例を積み上げて作り上げていくか、それぞれのアセスメントのパターン検証をしたい。
7.サービス内容のチェックとマネジメントの実際
・就労分野は就労継続支援B型を中心に実施すべき
・各自で考える内容がほとんどであったが、それが良いのかどうか評価的なものがないので、従来の福祉の視点から抜け出せない内容も・・・新規事業にしても声の大きい人のアドバイスが優先され、本当に地元でそれをするのは・・・と心配。就労支援のチェックリスト的なもので評価の演習をしては。
・パワーポイントを活用したプレゼン資料として、企業の見本例もいただくとその違いを意識できて嬉しいかと思います。企業はこんなにも進んでいるということを痛感させられますので。
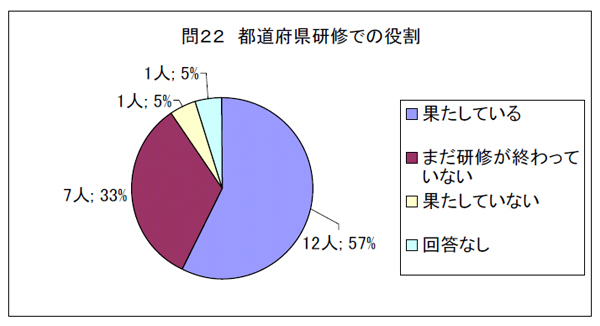
問23.都道府県の研修を企画運営する上での課題
・伝えなければならない最低限のことを挙げていただけるとありがたい。
・就労についての業務を行っていない中で研修を行うので、事例に困っている。
・新体系に移行していない事業所も多く、就労に対してのサービス管理責任者の役割を明確に理解できていない方も多かったように思われる。
・研修の内容・講師の選定など今研修の受講者に任せる部分が大きく、地域的な就労支援の取り組みや今後についての展望などもっと行政(県)としての考えもはっきりして欲しい。
・説明内容をもっと限定しなければ受講者は当日頭に入らない。
・狭山に行かせていただいた義務として滋賀県で研修をさせていただきましたが、一緒にさせていただいた方のおかげで何とか終わった、といった感じです。自分自身では、期間も短かったため、読み込みが十分にできておらづ伝え切れなかったと反省しております。
・国の研修内容に添った形を基本にすると、内容が盛りだくさんで組みにくい。
・受講者が多く、きめ細かい研修ができない。基本的な知識、経験が不足している受講者もおり、グループワークでの成果がでにくい。
・演習をより実践的に・個別支援計画をより利用者のものにするための工夫と時間
・就労分野は就労継続支援B型が中心なので、国の研修内容では不十分であり、どのように進めるかが課題
・受講者の知識・経験年数等に大きな開きがある(受講資格要件は不問?)・演習を実施する際に受講者用のパソコン等機材の充実を。・フォローアップ研修の必要性 ・年1回開催だと受講生が多すぎる(就労分野)
・①おこがましいのですが、国研修の内容が、本当に県の指導者としての養成教材としてふさわしくなっているのかを分析しなければいけないこと、②県で取り組む場合、この研修でよかったのかというフィードバックがもらえにくいこと
・18年度の講師の方との協力も沢山頂き19年度研修会は、スムーズに終えることができました。しかし受講生の中から研修のボリュームの多さから時間の問題や日数が足りないのではとの案もありました。実際私も昨年は同じ感覚でもありました。就労分野に関わらず、どの分野においてもフォローアップ的な一定期間のサイクルで現任者研修を行っていかなければと、感じています。
・私共が直接企画する訳でありませんが、昨年実施した感想としましては、3障害が一緒の研修ですので、演習事例の選定の難しさがありますし、分野別講義の進行方法等も課題と思います。
・サービス管理責任者の役割をどのような事例で分かりやすく伝えるかが課題。
・指導者研修の内容と県内の現場とのずれが大きいため、研修内容を現場に合わせた方がよいか、あくまで理想的サービス管理のあり方として伝えたらよいか迷っている。
・現状での受講者の状況によって、運営内容を考慮しなくては理解度が違う。
・具体的実践に往かせるようポイントを絞って行っている。
・3月に予定されていて、時期的に大変困惑しています。
Ⅲ サービス管理責任者の現場の業務について
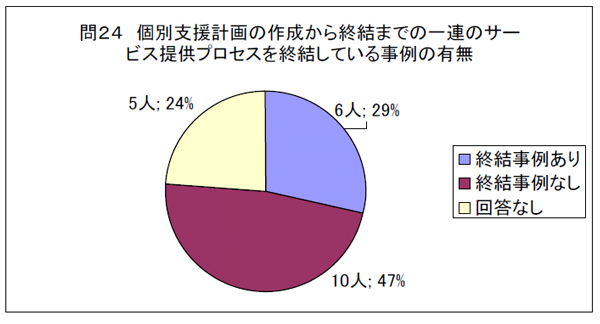
| 問26 | サービス管理責任者として職員への介入に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 相談後 | |
| ・ | 電話予約から来所相談までの間、利用契約時 | |
| ・ | 利用契約締結前後 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 受け入れられるケースかどうかを見極めるということや地域の社会資源や担当者の把握について最新であるかどうかを確認してもらうとともに、説明できるように促す。 | |
| ・ | 個別に状況把握のポイントを再確認する | |
| ・ | 報告に対して助言 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 会議時 | |
| ・ | 作成時 | |
| ・ | 本人のニーズの把握や情報の収集が出来ていない時 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | サビ管と現場職員それぞれに視点のずれはないか調整しながら行っている。 | |
| ・ | とにかく客観的なデータについて、しっかりと把握できるようになるためには、信頼関係をとりつけなければいけないことを意識させる。 | |
| ・ | 利用者ニーズや思いが十分アセスされているかの確認 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 計画作成時と計画作成後 | |
| ・ | 利用契約締結後1週間以内 | |
| ・ | 利用者の意思が反映されているか不安な時、丁寧な説明責任と同意がなされていない時 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 極力視点にずれがないか関係者の意見を聞く | |
| ・ | 個別に目標について話し合う時間を設ける。 | |
| ・ | 利用者の意向がしっかり尊重されたものなのかどうかを第一に考えさせるとともに、ストレングスな視点を捉えているのかについても根拠を説明できるようにすることが必要であることを気づいてもらう。 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 職員からの相談時 | |
| ・ | 定期的および随時 | |
| ・ | 本人や家族、担当職員から質問があった時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 支援計画に対して、職員全員が統一した支援を行うよう、助言、指導を行う | |
| ・ | 職員の支援を観察・支援についての相談に応じる | |
| ・ | どの程度の内容のものなのか、時間と緊急度の確認をしながら、必要に応じて支援スタッフと情報の共有を図ることの大切さをわかってもらう。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 原則として半年後 | |
| ・ | 見直し期間がきた場合や本人や家族から要望があった時 | |
| ・ | モニタリング評価会議等 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 個別に中間評価の再確認と修正について話し合う時間を設ける。 | |
| ・ | 就労移行支援チェックリスト、評価票によりチェック、利用者・保護者個別面談の前に評価についての共通理解を図る | |
| ・ | 相談面接に同席、所内ケース会議 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 定期的利用者相談後の報告時 | |
| ・ | 見直しと拡大ケース会議 | |
| ・ | 利用期間満了、サービス変更、退所時 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 各支援に対して、利用者の意思、満足度を確認する | |
| ・ | 口頭での評価 | |
| ・ | 日々の記録やチェックリスト、ケア会議等で方針を示し、個別面談において利用者・家族との意向を尊重し、双方で今後の進路を決定する | |
| 問27 | サービス管理責任者としてチームアプローチに関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 朝夕のミーティング会議 | |
| ・ | 相談があった時 | |
| ・ | ニーズが出た段階ですぐに | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | ケアマネジメントの手法で | |
| ・ | 全て7名のスタッフで協議、検討、実施 | |
| ・ | 他の職員にも状況を確認する必要があるかどうかというアプローチを理解してもらう。 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 検討時 | |
| ・ | 職員会 | |
| ・ | 生活アセスメント(個別面談時)。職業アセスメント | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 必要な関係機関に電話連絡、訪問相談 | |
| ・ | 他の職員からも客観的なデータを聞きだし、把握する必要があるかどうかを判断してもらい、より精度の高いアセスメント表を作成していくことに気づいてもらう。 | |
| ・ | 保護者・利用者、学校、職員等からの情報提供を得た場合は、毎朝の所属会議において情報の共有化を図る | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 検討時 | |
| ・ | 所内の個別支援会議での発言時 | |
| ・ | 利用契約締結後1週間以内 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | チーム内での目標に対しての意見交換 | |
| ・ | 他の職員からの意見を伺い、個別支援計画がより利用者のニーズを反映したものであるのか、ストレングスな視点で作成されているかを支援に関わるスタッフが全員共有してもらうことが必要であることを意識してもらう。 | |
| ・ | 利用者・家族の意向聴取とアセスメントを基に支援員との支援会議において方針案を作成し、利用者・家族の同意を得て、チームで支援を実施 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス調整会議等で | |
| ・ | 随時 | |
| ・ | 本人や家族、支援スタッフから質問があった時 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | ケース検討会で支援の目標の再確認とチームでの支援内容の確認、周知 | |
| ・ | スタッフ全員で協議、検討、実施 | |
| ・ | 担当職員にどの程度の内容のものなのか、時間と緊急度の確認をしながら、必要に応じて他の支援スタッフも召集し情報の共有を図ってもらうことの大切さを気づいてもらう。 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 半年後、1年後 | |
| ・ | 毎日のミーティングで | |
| ・ | 見直し期間がきた場合や本人や家族から要望があった時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | 現時点での到達目標の評価を他の支援スタッフにも確認してもらい、今後の支援内容の展開について、他の支援スタッフの力が必要であることのアプローチに気づいてもらう。 | |
| ・ | 就労移行支援チェックリスト、評価票によりチェック、利用者・保護者個別面談 | |
| ・ | 必要な関係機関に電話連絡、訪問相談 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 利用期間満了、サービス変更、退所時 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 支援会議等で終了に至る経過を説明し、個別面談において協議された内容等について共通理解を図り、今後の進路や他の支援方法について検討する | |
| 問28 | サービス管理責任者として関係部門・機関との連携に関して(主な回答) | |
|---|---|---|
| 1.相談支援時の状況把握【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 個々の支援の必要があると判断されたとき | |
| ・ | 相談内容により、他機関とすぐに連絡。 | |
| ・ | 利用開始前 | |
| 1.相談支援時の状況把握【どのような方法】 | ||
| ・ | 医療機関や事業所からのアドバイス依頼を所定の様式で情報提供してもらう。 | |
| ・ | 相談内容により、他機関とすぐに連絡。 | |
| ・ | 利用者・家族の同意の下、行政、前利用先、相談支援専門員等から情報提供、あるいは他事業所等を紹介 | |
| 2.アセスメント【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 必要に応じて調整 | |
| ・ | 利用希望・契約時 | |
| ・ | 連携の必要な場合 | |
| 2.アセスメント【どのような方法】 | ||
| ・ | 学校より個別の教育移行支援計画。障害者職業センターにて職業評価。 | |
| ・ | 情報収集時 | |
| ・ | 随時連絡、必要に応じてケア会議 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | サービス利用1ヶ月程度 | |
| ・ | 随時 | |
| ・ | 連携の必要な場合 | |
| 3.個別支援計画の作成【どのような方法】 | ||
| ・ | 関係部門や機関の方たちの日程調整をしながら、集まってもらうことの重要性や、利用者を地域でケアすることの視点について気づいてもらう。 | |
| ・ | 随時連絡、必要に応じてケア会議 | |
| ・ | 必要な関係機関に電話連絡、訪問相談 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 関係部門、機関のスタッフから質問があった時 | |
| ・ | 定期的 | |
| ・ | 必要に応じて調整 | |
| 4.個別支援計画の実施【どのような方法】 | ||
| ・ | 随時連絡、必要に応じてケア会議 | |
| ・ | 電話連絡等にて実施状況把握 | |
| ・ | 必要な関係機関に電話連絡、訪問相談 | |
| 5.中間評価と修正【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 支援計画変更時 | |
| ・ | 必要に応じて調整 | |
| ・ | 見直し期間がきた場合や本人や家族から要望があった時 | |
| 5.中間評価と修正【どのような方法】 | ||
| ・ | ケア会議の開催 | |
| ・ | 随時連絡、必要に応じてケア会議 | |
| ・ | 必要な関係機関に電話連絡、訪問相談 | |
| 6.終了時評価【どのようなタイミング】 | ||
| ・ | 必要に応じて調整 | |
| 6.終了時評価【どのような方法】 | ||
| ・ | 随時連絡、必要に応じてケア会議 | |
問29.相談支援専門員とどのように役割分担していますか。
・相談相手を利用者が上手に選ぶため、臨機応変に対応する。
・ 市町村からの受託である相談支援事業対象者は相談支援専門員、他就労面が主な方は就業・生活支援ワーカー・相談支援専門員は施設内にいない。地域としては連携。
・現状では人不足であるため、その都度必要な事柄で分担している。
・正直言ってこの辺りが良く理解できません。今後研修でこのあたりの関係をしっかりと示して欲しいと思います。
・ケアマネは相談支援専門員 サービス管理はサビ管等臨機応変に
・相談支援専門員はよりよいサービスの仲介役、事業所は適切なサービスの提供を行う。
・重複する内容もあるが、生活面で諸手続や制度面でのニーズ、他の福祉事業所利用について相談・依頼し、就労関係でも就業・生活支援センターと併せて相談している。また、利用者の家族の支援等、直接業務でないものについても相談支援専門員に支援を依頼している。
・相談支援専門員は、ケースワークを中心とするアプローチをとるのに対して、サービス管理責任者は、それだけでなく、地域を含めた全体のサービスとプロセスの管理者である。前者は木、後者は森である。
・サビ管として正式な仕事を行っていませんので、役割分担まではいたっておりません。
・生活支援を依頼するとともにケアプランをもとに情報交換やアドバイスいただいている。
・この部分を研修でしっかり理解して欲しいと思います。
・3事業一体化運営のため、相談支援専門員はチームのまとめ役である。
・サービス管理責任者は事業者であり、相談支援専門員とは別の立場と考えています。
問30.サービス管理責任者の課題についてどのように考えていますか。
・サービス管理責任者として2年、3年に1回適正かどうかを決める試験をしてはどうか。
・新体系へ事業移行をしていないうえに、就労という新しい分野について取り組もうと準備に取り掛かったところであり、実施していない段階では課題も見えにくいが、やはり施設と地域の相談支援専門員との連携と役割分担が重要でないか、またサービス管理責任者も一事業所内だけに目をむけていてはいけないと思っています。
・就労分野では様々な課題や負担が大きいため、新体系への移行が進んでいないのが現状である。就労分野では一般就労への取り組みとあわせて工賃を支払う事業体としての活動も行っていかなくてはいけない。そのため、サービス管理責任者の負担が大きいように感じる。
・今後、当法人も新事業体系へ移行する予定であり、入所施設からの地域移行も含めますます地域や他事業所・行政との連携が必要となってくる。その中でサビ管の役割は重要となってくるが、就労分野に限っていえばまだ福祉の枠を出ていない事業所が多く(当法人の部署も含め)職員の意識を変えていく必要があると思う。
・このアンケートのように、システム化するのは理解できるが、システム化により利用者本来の希望が出づらい状態にするのは好ましくないと考える。講義と実践を整合させる為に我々は努力をすべきと考える。
・調整会議の当初の頃は対象者も少なく、たっぷり時間をとって相談し丁寧な支援ができたいたと思うが、現状人手不足と、あまりにも「サービス提供」に走りすぎているため、本来の「支援」がなくなってきていることに憤りを感じている今日この頃です。是非とも、そういった現状と、福祉の世界で決して忘れてはならない、「個々の支援」(サービスの当てはめではない)の確立も盛り込んでいただければと思いつつ戻ってきた記憶があります。後は忘れました。関先生前野先生が本音を言いたいのに、我慢しながらしゃべっておられて姿、立派だなあと思いつつ拝見いたしました、ご苦労様です。
・複数の事業所を利用している場合のサービス管理責任者のあり方に疑問を感じます。(例えば通所系の事業所とグループホーム)個別支援計画を生活全般の視点で捉えるとなると同じような計画をそれぞれの事業所のサービス管理責任者が立てる事になります。利用者にとっては同じことを複数の事業所に話をしてアセスメントを受ける事になります。また同じような計画が出てくる事になります。サービス管理責任者は本来、その事業所が提供できるサービスの範囲を管理する役目だと思われます。それを生活全般の支援に向けた支援の役目を位置づけた事で矛盾も多く出てきているように思います。給付費の中にこれらの一連のサー管の業務が含まれるとはとても思えません。
・各現場において意欲を持ってサビ管の役どころを実践するに際しては、組織(施設)の中で、管理者及び現場支援員等に「サビ管とは何か、なぜ必要で、どのような取り組みが求められるか」を十分に理解してもらうことが必要になります。それが為されないと意欲は空回りし、失望感や無力感に陥りかねませんし、ややもすればお飾り的な役職として名前だけの存在にもなりかねないでしょう。特に施設長(管理者)の理解と応援は必須です。サビ管=個別支援計画を作る(ことができる)職員、といった認識もまだ一部で罷り通っているのではないでしょうか。逆に、利用者支援については総てサビ管に丸投げしてしまい、結果的にサビ管を潰してしまう危険性も懸念されます。少なくとも施設長に対して、サビ管の役割をきちんと理解認識してもらうための公的なアプローチは不可欠のように思えます。その部分までサビ管に委ねるのは、施設によっては難しいことでしょう
・「福祉」の枠に捉われて、施設の箱の中だけで完結することに違和感がない方々もまだまだ多いように思われる。いろいろなサービスや施設内の資源を生かすようにコーディネートする力のようなものがこの立場には必要だと思う。
・利用者本位のサービス提供をしていくための要であり、これが形骸化され、制度のための必要書類の整備になってしまうおそれが十分ある。このためには3日の研修だけでなく資質の向上・資格等を含めより厳しいものにし、同時に作成の予算的な裏付けを行う必要があると思う。
・問26以降は施設長として必要なことへのアドバイスを行うことはあるが、実際の役割としては行っていない。サービス管理責任者の課題としては経験年数ではなく、介護支援専門員(ケアマネージャー)のような試験とすべきと考える。
・多機能型のサービス管理責任者は、利用者数が少なくても事業内容が異なり、場所も分散しているため業務の遂行がしづらい。法人や事業所の役員および管理者と同じ方針でなければ、移行支援事業を実施していくのは困難だと感じる。「就職=退所=減収」の旧態依然とした考えを変えるためには、サービス管理責任者だけでなく、事業管理者も受講しなければ、サービス管理責任者は板挟みになってしまうと考える。サービス管理責任者の質を担保するために、受講要件を社会福祉士・精神保健福祉士などの有資格者(取得まで数年間猶予期間も)とし、報酬単価に反映し手当を支給することが望まれる。
・ 究極の中間管理職として、どう組織の中で身分保障するのか、モチベーションを高めるためにはどうすればよいのか、その対応がこれから課題であると思っています。そのためには、国が積極的にサビ管の地位向上に向け、具体的救済策を打ち出していただきたく思います。これまでの仕事に加えて、さらに業務量が増えるだけで、まったく給料には反映されないということも現実問題だと思います。設置義務ゆえの存在であるならば、それなりの身分保障策をぜひともよろしくお願いいたします。
・県内研修会実施において、まだまだ受講者側の就労に関する支援が福祉的・保護な考えであったり、チャレンジ的思考を否定したり、関係機関とのある種枠にとらわれる考えを捨てきれず、ワークを進めることは非常に困難であった。又、サビ管受講者の基準事態もある意味甘いのかもしれません(県の研修担当の考えもあるのかも)受講基準に満たしていれば受講資格がある。この部分に関しても、なかなかスキル的に考えるところであった。事業指定基準にサビ管配置されているから、ある人に参加させる的考えで良いのか?アセスメント・モニタリング・個別支援計画・等についても手法やKJ法などをどれだけ使える・・かにおいてもかなりの格差あり疑問を感じた。全く分からない、知らない方も参加されている現状。では、その方々支援員を逆にどうしたら理解して頂き、又地域のスペシャリストの可能性をお持ちの方がいるわけですから、逆にサビ管として頑張って頂くためにも、定期的フォローアップ研修会や現任者研修会が必要なのでは・・・・・・・・特に就労分野は必要ではないかと感じています。
・相談支援専門員との連携関係・管理者との関係・他の業務と兼任で行わなければならない事業所でのサビ管の仕事の立ち位置・サビ管に全て責任を負わせないシステムの構築等。
・サービス管理責任者の役割ではないかもしれないが、介護保険のケアマネジャーのような専門職が自立支援法においても必要ではないかと考える。全体のサービスをコーディネートする専門職が、その事業所のサービス管理責任者と調整することによって役割もはっきりしてくるのではないか。
・自分も含め、現時点でのサービス管理責任者の質の低さでは、今後のサービス管理責任者を育てられない。特に連携やスーパーバイズについては今後も定期的な研修が必要だと思う。
・管理者としての修正の方法、タイミング、職員との関わりについてスーパーバイズしていただけると助かります。この研修には、すでにケアプランは作成できる力量の方が揃っているので、ケアプラン作成に時間をかける必要はない。それをどのように管理して、どのように評価していくかを具体的に演習で行って欲しい。
・就業・生活支援センターのため、とても答えにくいアンケートでした。3事業合わせて年間8000件の相談件数があり、日々処理事項に追われております。当センターの場合はサービス管理責任者はチームのまとめ役です。
・とても重要なポイントであると理解しています。各県単位での情報の共有化が必要と思われます。
・これからサービス管理責任者の実績と必要性が明確になると思いますのであまり制度や手続きを変更せずに落ち着いて取り組めたらいいと思います。
①介護分野
介護分野のアンケートに対する回答者は、29名で回収率は63.0%であった。
a)回答者の属性について
回答者の所属している事業所の新体系への移行は、わずかに4名であった。移行の準備中と回答した者が最も多く、14名で49%を占めていた。事業所の経営主体はほとんどが社会福祉法人で、次に都道府県が多かった。現在所属している事業所は、本来、生活介護あるいは療養介護の事業所が該当事業所であるが、47%の者が他の事業所に配置転換になっている。国の指導者研修を受講して、他の部署に配置転換されている状況を考えると、研修の効果や成果を現場で活かしているかきわめて疑問が残る。今後、受講者の選定に関して、慎重に考える必要がある。また、国の指導者研修を受講して都道府県の研修の中核となるべき人材が少なくなるのではないかと懸念される。
地域自立支援協議会との設置状況では、22名(76%)が設置されていると回答し、17名(58%)が協議会に積極的に関わっているあるいは関わっていると回答している。
自立支援協議会への関わりも研修修了後の課題となっている。
b)国の指導者研修に対する満足度について
国の研修に対する満足度では、26名(90%)が満足していると回答しており、満足度はきわめて高い。サービス管理責任者の業務を具体的に理解できた、他の県の受講者との交流が図られ有意義であった、個別支援計画作成及び管理の流れが理解できた、演習のロールプレイなど具体的で理解しやすかった、サービス管理責任者の重要性を認識できた等の回答があった。一方、資料が多くて消化不良の感がある、介護分野は広範囲であるので種別に分けてほしい等の意見もあった。これらの点を踏まえ、資料を厳選することで内容をもう少しまとめる作業をする必要性があるように思われる。
c)国の指導者研修の内容が現場で生かされているか生かされていると回答した者が、23名(79%)おり、研修内容の理解が深まり、現場への適用ができていると推察される。職員の研修会を開催して職員のスキルアップに繋げている、個別支援計画の立案について今までの視点を再確認した、職員の業務状況の把握や職員間のコミュニケーションに意識的に関われるようになった等の意見があった。ただ、新体系へ移行していないこともあり、まだ、研修の成果が現場で生かされていない人もいる。
d)研修内容と現場とのずれ
研修内容と現場とのずれについて、ずれがあると回答した者が多く、25名(86%)あった。研修内容は現場で生かされているが、現場とのずれがこれほど生じている理由は、国の研修内容のようには現場はいかず、サービス管理責任者の業務に専念する環境を必要とする、研修の内容は十分であるが、職員、利用者、保護者の勉強会を開催し意識改革・環境調整が必要である、現場の多忙さに追われている、所属長及び管理者の研修を行わないとサービス管理責任者として業務が難しい等の意見が出された。多くは、職場環境の劣悪さや激務と戦っており、研修内容のモデルどおりいかないと考えている。
e)国の指導者研修の内容で良かった点
全体的に、サービス管理責任者の役割、サービス提供プロセスの流れ等わかりやすかった。また、演習においては、具体的で理解しやすかった、ファシリテーターの関わりや発言が勉強になった等の意見があった。
f)国の指導者研修の内容で改善したらよい点
講義に関しては、内容が重複していたり、多くて消化不良になる嫌いがあるので、内容を厳選する必要があるとの指摘が多かった。また、変則勤務や複数の専門職がいる条件下でのチームアプローチを進める工夫を入れるとよい、相談支援専門員との関係をはっきりさせる、質疑応答の時間を設けてほしい等の改善点が指摘されている。
演習に関しては、より具体的な事例を用いる、他のグループの様子もみられるように進めるとよい、もっと時間が欲しかった、グループメンバーとの議論が深まらない等の意見があった。
時間的な制約があるので、受講者の要望をすべて実現することは難しいが、時間配分を考慮するとともに、内容を検討し、ポイントを絞る必要があると思われる。
g)テキストの内容について具体的にどのように変えたらよいか
現状のままで良いと回答した者が11名(38%)あったが、少し修正した方がよい、修正した方がよいと回答した者が15名(52%)いた。生活介護・療養介護の分野では、意思疎通ができない利用者がほとんどであり、それらの利用者の意思確認の方法、手続きが大きな課題であるのでその例示を示してほしい、生活介護・療養介護特有のサービス提供の管理の視点・技術について触れるとよい、サービス提供職員、サービス管理責任者、地域移行推進員、相談支援専門員らと地域自立支援協議会との連携や各自の役割分担をわかりやすくしてほしい等の意見が出された。
h)都道府県の研修を企画する上での課題
都道府県の研修での役割について質問したところ、21名(73%)が研修での役割を果たしていると回答している。そこで、研修を企画する上での課題について自由記述で回答を求めた。組織的な点についての意見では、「障害者自立支援研修委員会」のような組織を立ち上げ、職能団体ではなく、3障害の育成団体等と緊密に連携しながら研修を企画し講師の育成を図るとよいのではないか等があった。現状の課題としては、いろいろな意見が出されている。携わる上での体制支援に関して、本来業務とのバランスを考えながら企画・運営しており、一部の人材に負担がきている、勤務する職場の理解がないと無理が生じる、希望者が多く会場の確保の苦労した、県の担当者の温度差がある等指摘されている。
研修の進め方に関しては、まだまだ未熟で研修の講師を務めることに無理がある、国の研修で都道府県研修の進め方まで教えて欲しい、受講者の力量や意識に違いがあり研修を進めるのが難しい、本人のニーズに沿ったサービス提供の質の向上とマンネリ防止の合意を得るための事例の提示が難しい、研修の目的、習得してもらうべき内容をどのように絞り込むか苦労した、受講者の施設の障害の種類や組織上の地位の違いがある中でサービス管理責任者の明確な権限を説明しにくい等が指摘された。
i)サービス管理責任者の課題
施設の中での位置づけの明確化と関係機関との連携が大きな課題である、相談支援専門員とサービス管理責任者の違い・業務内容の明確化・サービス管理責任者現任研修の検討・理事長及び施設長のサービス管理責任者の業務に対する理解、個別支援計画作成における各担当職員との連携と調整会議のあり方・個別指導を含めた支援員の能力開発に関わる人事労務管理能力の向上・サービス管理責任者に係わる介護報酬の新設等の課題がある、60名に一人の配置基準は現実的に無理がある、サービス管理責任者を管理する立場の人がいないのでモチベーションを維持することが難しい、新事業体系における日中活動支援と居住支援との連携と役割分担が課題となる、個別支援計画の重要性をスタッフに理解してもらうことが難しい等の指摘がある。
②地域生活(身体)分野
地域生活(身体)のサービス管理責任者研修修了者は47名であったが、アンケート回答が得られたのは、23名(51.1%)であった。その結果は、
a)事業所等について
新体系への移行状態では、移行している7人(30%)、移行準備中7人(30%)、移行していない7人(30%)、回答なし2人(10%)であり、所属事務所では、9人(40%)が地域生活(身体)、5人(23%)が回答なく、3人(13%)が、その他、残りは、生活介護、療養介護、地域生活(知・精)、児童デイサービス、就労、就労継続、多種事業、相談支援事業所であり、それぞれ1人(4%)ずつであった。事業所の経営主体では、社会福祉法人19人(83%)、都道府県2人(9%)、回答なし、その他が、それぞれ、1人(4%)ずつであり、職員体制では、常勤職員182人から2人、非常勤職員22人から1人であり、入所定員270人から36人、利用者数262人から24人、平均的には、常勤職員20人、非常勤職員5人、入所定員76.6人、利用者71人の施設と考えられ、障害程度区分は、区分1が53人から1人、区分2が38人から2人、区分3が31人から3人、区分4が14人から1人、区分5が18人から1人、区分6が40人から2人、旧支援費での区分、A区分162人から2人、B区分88人から3人、C区分15人から2人である。地域自立支援協議会の設置状況は、設置9人(39%)、準備中2人(9%)、設置されていない10人(43%)、回答なし2人(9%)であり、自立支援協議会との関わりについて、積極的に関わっている5人(22%)、関わっていない4人(17%)、関わっている3人(13%)、設置されていない10人(44%)、回答なし、1人(4%)であった。
b)国の指導者研修に対する満足度について
とても満足3人(13%)、満足15人(66%)、不満4人(17%)、回答なし1人(4%)であり、約80%が満足している。満足している理由は、サービスビ管理責任者の位置づけ、役割、責任、プロセス管理や、地域格差・取り組みの違いを知り、事例演習をグループ討議で行うことで、実践的な研修が出来た(しかし、大変残念なことに、時間が足りなかった)であったが、地域の実情とかけ離れている、事業希望者への研修・企画側のポイント、力量アップの道筋が、研修では、欠けているとの指摘もある。
c)国の指導者研修の内容が、現場で生かされているかについて
生かされている17人(75%)、生かされていない5人(21%)であり、8割の人は、研修が、現場で生かされており、生かされている理由は、仕事の意識が変わった、利用者の見方が丁寧になった、現場でタイムリーに助言できるようになった、積極的に支援ができるようになった、研修前より助言力・実践力が付いた、サービス内容を振り返る大切さが分かった、個別支援計画の重要性を再確認し、アセスメント表等のツールを使用するようになったと、現場での具体的な効果を述べている。
d)研修内容と現場との「ずれ」について
サービス管理のとらえ方・大切さに、事例と実際の施設利用者の間にずれがあり、関係機関との連携では、お互いの考え方や支援方法にずれがあり連携が取りにくい、利用者の目標を尊重し、共に到達目標に向かって協働していくことにずれがある等の指摘がある。
e)国の指導者研修で良かった点
1.「障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割」では、役割、責任の重さが分かり易かった、サービス管理責任者の自立支援法上での位置付けを再確認できた、利用者・職員・関係機関等の調整役という立場が明確にされた、サービス管理責任者の資質、情報及び連携の重要性が理解出来た、従来のサービス提供のあり方と障害者自立支援法の目指すサービス提供の違いが良く分かったである。2.「サービス提供のプロセスと管理」では、プロセスの過程の実施方法、留意点が良く分かった、地域移行の実践紹介編は、大変参考になった、相談支援から個別支援計画の作成、実施、評価、修正、終了時評価と常に問題意識を持って取り組んでいく姿勢を学んだであり、3.「サービス提供者と関係機関の連携」では、施設内だけでなく、地域を巻き込んだ体制作りの重要性、連携が最終的に良い支援に繋がることが理解でき、ネットワークの重要性を再確認できた、専門関係機関と連携を密にしてサービスを提供していくことの重要性がよく分かった、連携により改善される点、その中でのサービス管理責任者の役割がよく理解できたことである。4.「分野別のアセスメント及びモニタリングの実際」では、モニタリングの重要性が認識でき、医学的なアセスメント法、視点を学んだ、グループ内に様々な考えをもった受講者があり、また、具体的な事例に沿っての演習や討議から自分では気づかない課題や方向性を考えることが出来
た、個別支援計画作成におけるアセスメント、モニタリング技術について具体的に理解出来たことである。5.「サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)」では、アセスメントから導き出す課題のまとめ方が分かりやすかった、全員でアセスメント内容を検討するのは有意義であった、支援するためにはアセスメントが重要であることを再認識した、アセスメント、個別支援計画について、課題の整理、到達目標の設定、計画の修正・変更、終了時評価の手順、技術を事例演習により実践的に学ぶことが出来た、異なる専門職間の情報交換ができ、サービス提供の視点、幅を広げることが出来た、個別支援計画作成までの過程を段階に分けて実践出来たである。6.「サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)」では、アセスメントから支援計画の導き方、個別支援計画書の作成、個別支援計画とは「本人のニーズを支援者が十分に受け止め、その人の生活が少しでも豊かになれるよう、支援者の専門的な知識と本人家族の希望を反映させ、これらを一覧表にしたものである」であることの重要性を認識出来た、一つの目標達成に必要な期間を設定していく必要性を確認出来たことである。7.「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」では、モニタリングと合わせて、定期的な確認と計画の更新が成功への道筋である事を認識できた、書面に残す手続きは、作成者(サービス管理責任者)の責任感にも直結しているため、必要な作業であると認識できた、事例におけるサービス内容のチェックを行うことで、自らのサービス内容、提供に対する振り返りと修正、マネジメントを再確認できた、困難なケースについての着眼点、暫定契約について理解出来たことである。
f)国の指導者研修の内容で改善したらよいと思う点
1.「自立支援法とサビ管の役割」では、支援費の請求管理に関する講義があった方が良い、教える立場の分かりやすい具体的な指導助言法の研修や、現実の実態に考慮した内容の研修(地域に見合った手法等のアドバイス)も取り入れるであり、2.「サービス提供のプロセスと管理」では、サービス管理責任者に携わる方の実践例の紹介を入れるであり、3.「サービス提供者と関係機関の連携」では、県の研修に使いやすい内容に改善したほうが良い、総合リハセンター以外で連携を行っている事例や事業所のモデルも紹介する、相談支援専門員との連携をもう少し具体的に説明することである。4.「分野別のアセスメント及びもモニタリングの実際」では、全体講義の中では、ICFやエンパワメントの視点が中心となっていたが、分野別講義になると事例等の説明の中でも中途障害の機能回復が中心となり医学モデルが強い印象を受け、若干整合性としての矛盾を感じた、アセスメントとモニタリングを分離し、まずはアセスメントの視点や技術を磨くことを重視した方がよい、アセスメント項目は事前に示し、どのようにまとめていくかというやり方に時間を割いた方が良いであり、5.「サービス提供プロセスの管理と実際(アセスメント編)」では、時間が短く、アセスメント項目の検討表や支援方針の策定表等のツールについては、的確に使いこなすには至らなかった、利用者の意向の尊重やエンパワメントなどの視点を確認しながらアセスメントを行えるように、演習を進行管理する、模擬の評価会議(個別支援会議)を行なう、自分たちで事例を出し、それに合った研修を行うべきであるであり、
6.「サービス提供プロセスの管理と実際(個別支援計画編)」では、サービス提供のプロセスを考えたとき、短い時間の中では一つの事例で継続的に検討していく方がグループ討議を行いやすい、7.「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」では、マネジメント内容に関する検討結果とサービス内容に関する検討結果を分け、記録する作業は時間的に非常に困難であったである。
g)研修テキストの修正について
現状のままでよい12人(53%)、少し修正した方がよい8人(35%)、修正した方がよい1人(4%)、回答なし2人(8%)であり、6割がすこし修正した方がよいと回答している。具体的には、1.「自立支援法とサービス管理責任者の役割」では、支援費の請求管理について追加する、誤字脱字が多いのを直すことであり、3.「サービス提供者と関係機関の連携」では、連携事例を加える、実践報告に関係機関の意見を加える、4.「分野別のアセスメント及びモニタリングの実際」では、ICFやエンパワメントの視点をもう少し強調した事例と、それに伴うアセスメントやモニタリングの手法が学べるような内容にする、全体講義と重なる部分は、どちらかに整理するであり、5.「サービス提供の管理の実際(アセスメント編)」、6.「サービス提供プロセスの管理と実際(個別支援計画編)」、7.「サービス内容のチェックとマネジメントの実際」では、回答に共通した答えが多いので、まとめると、事例を多岐に、4を修正すれば時間的にゆとりが出るである。
h)都道府県の研修で講師の役割を果たしているか
果たしている15人(66%)、まだ研修が終わっていない4人(17%)、果たしていない3人(13%)、回答なし1人(4%)であった、この回答を見ての問題があるとすれば、1~2割の人が、果たしていないと回答していることである。
i)都道府県研修企画運営上での課題
地域生活(身体)の移行事業所が少なく、研修会参加者も少ない、ニーズのアセスメントや個別支援計画の作成、視点について、受講者間で基本的な理解に差がある、演習を行う場合、参加者の経験に差があるため、演習の内容や進行について問題がある、忙しい人が講師になっているため、研修の事務的な部分については、できる限り都道府県がバックアップを行い、講師は講義・演習だけに専念できるよう改善する、国研修のような伝達講習的内容でなく、地域の特性に配慮したものにすべきであり、受講者が少ない場合、隣県との共同開催も検討する必要があり、研修の意図、思考が困難な参加者にどう対応するかなどが課題である。
j)相談支援専門員との役割分担について
地域移行の際、相談支援専門員が各地にきっちり配置されているとは限らないのでケースバイケースで連携を行う、相談支援事業所の相談支援専門員と特に役割分担はなく、多くの場合、入所前相談から利用調整会議までが相談支援専門員の役割、インテークから施設利用直前までは、サービス管理責任者が行い、地域移行が明確化した段階から、再び相談支援専門員に繋ぐ、利用者の地域生活移行に向け、利用者が移行を予定している相談支援専門員に連絡し、地域の社会資源、利用者の意向に沿ったサービスの活用法について、ケア会議を開き、お互いに情報提供を行い、地域での支援計画を検討する、利用開始時及び終了時にケースを引き継ぎ、地域での具体的計画の立案やサービス調整は、相談支援専門員が担当するである。
k)サービス管理責任者の今後の課題について
サービス管理責任者向けのスキルアップのための研修でもっと勉強を重ね、現場の経験を積む必要がある、サービス管理責任者の知識・技能を、如何に高めるか、支援計画が利用者のニーズや将来の目標が反映された支援内容になっているかのチェック体制、支援計画が計画通り遂行されているか、各利用者の状況を日々確認できる体制作り、業務管理業務や宿舎管理業務、事務所内の他事業業務とのサービス管理責任者の仕事のバランスをどう取るか、地域格差を埋め、サービスの均衡を図っていくことが大切であり、利用者、家族、職員のこれまでの施設とは違うとの意識改革を行うことである。
③地域生活(知的・精神)分野
受講者47名から回答を得た22名(46.8%)について考察する。
a)所属する事業所について
新体系への移行状況は、移行している10人(45%)、移行準備中5人(23%)、移行していない6人(27%)、回答なし1人(5%)であり、所属している事業所は、生活介護3人(14%)、地域生活(知的・精神)8人(35%)、就労関係3人(14%)、多種事業3人(14%)、相談支援事業所2人(9%)、回答なし3人(14%)、経営形態は、社会福祉法人18人(81%)、都道府県1人(5%)、医療法人3人(14%)となっている。
共同生活介護・共同生活援助は新体系で事業開始されていることから、他の分野よりも先行して新体系に移行していると思われたが、国研修の受講者は多様な事業所に所属していることもあり、有意差は見られなかった。問5~問9は基礎データである。所属事業所が多様であり比較検討は困難。むしろ問3の地域生活(知的・精神)事業所に限局して設置数・職員配置・程度区分を抽出してみたがデータ数が少なく検証は不可であった。
自立支援協議会の設置・関わりは、13人(59%)の地域で設置されており、積極的に関わっている6人・関わっている7人といずれも何らかの連携に参加しており、地域生活支援の調整機能を担っていると思われる。設置の準備をしている2名(9%)からは関わっているとの回答はなかった。サービス管理責任者として自立支援協議会とどのように関わっていくかH18年度受講者のアンケートにも見られたが、まずは参加して、日常の支援過程から気づく「あったらいいサービス」「使いやすくしたらいいサービス」等の情報提案・共有化を図るなど行動を起こすことが連携のきっかけになると思われる。
b)国の指導者養成研修の内容について
研修内容について、とても満足している3人(14%)、満足した16人(72%)、不満である3人(14%)。不満足の理由は、相談支援従事者研修との違い・相談支援専門員との立場の違い・連携について明確にならなかったであった。地域生活移行は施設からの移行と在宅からの移行と大きく二つが考えられる。前者は施設に所属するサービス管理責任者が地域生活移行の窓口として関わり、在宅からは通所しているサービス提供事業所のサービス管理責任者か、何も資源を利用していない場合は市町村担当者・相談支援事業所(専門員)が窓口対応し、受け皿となる共同生活介護・生活支援のサービス管理責任者等とのケア会議を経て、利用者ニーズに応えようとしていく経過を、もう少し判りやすく伝える必要がある。満足している理由は、サービス管理責任者の役割の確認と認識・地域生活移行のプロセス・利用者主体となるニーズ把握・他県との比較と情報交換・演習でのロールプレイ等、理解を深めることが出来たとあった。ただ、研修スケジュールに余裕がほしいとの指摘もあった。
研修内容が現場で生かされているかについて、とても生かされている2人(9%)、生かされている19人(86%)、生かされていない1人(5%)と、ほぼ生かされていると回答があった。
生かされていない理由は、「勤務実態がサビ管と違うこと、概念的には整理されたが現実とはかけ離れている。しかし、計画を作るワークショップは実践的で、仕事に反映されている。(編集)」とあり、概ね回答全てが現場で生かされていると評価している。実際の現場とサービス管理責任者の役割が全くずれていないかどうかを判断する基準をここで検証することは出来ないが、利用者ニーズに対する支援の基本な姿勢は繰り返し研修過程で確認していく必要がある。生かされている理由は、サービス管理責任者としての意識・心構え・立場の確認について再確認でき、現場での助言・指導に役立てられているという内容であった。また、個別支援計画作成に当たっても、「決めるのは私」「聴く」「待つ」ことの重要性に気付き、利用者に対して分りやすく説明・思いを受け止めようとしていることと平衡して、職員・関係者との関わりでもそうした姿勢で意見を受け止めるようにしていると、演習過程での狙いが現場で生かされていることを確認できた。ただ、業務に追われ、個別支援計画にまで結び付けるには時間を要するとの指摘もあった。
c)研修内容と現場との「ずれ」について
国研修に満足し、その内容が現場で生かされていると評価しても、現場との「ずれ」を16人(73%)が感じていることをどう考えるか。「ずれ」の意見を、自身のこと・職員・地域資源・施策と4つに分類した。
・自身のこととして、兼務による困難さ・責任体制の未確立・地域へ関わる努力
・職員は、制度の理解不足・力量不足・人員不足・日常業務に余裕なく取り組めない
・地域環境は、支援のネットワークの未成熟・資源不足
・施策は、高度な業務に見合わない報酬単価の低さ・参加者の意識の格差
事業所としての戦略・自治体の意向・職員の意識に「ずれ」を感じながらも、「組織としてどう方向性を共有していくかは避けて通れず、むしろこうした議論しなければ今まで繰り返してきた個別支援計画のルーチンワークから脱しきれない」と肯定的に捉えようと苦悶する意見も見られた。
d)研修内容で良かったこと
分野別演習となる4から7の回答について考察する。
2日目の午前中はアセスメントとモニタリングの実際について講義を行い、後半はロールプレイを行った。5件/12件が具体的にサービス管理責任者と相談支援専門員の役割の違いが認識できたと評価している。アセスメントとモニタリングはサービス提供のニーズ把握と確認に欠かせないが、その意味を再確認できたと3件が評価しており、国研修のツールとして継続する意味があると思われる。演習では、グループワークにて行っているがこの手法は概ね理解されている。他県との交流・考え方・資源の違いが実際の事例検討段階で実感し共有することが出来るため、幅広い視点での理解を深めている。又この演習を通して、サービス管理責任者としての役割が個別支援計画とそのサービス提供管理だけではなく、当事者主体・世話人・支援員へのマネジメントも重要であることに気付いた意見もあった。全体に時間不足の中、あえて意見交換の時間を持ったが、振り返る意味からも時間設定が必要と思われる。
e)研修内容で改善したいこと
分野別演習となる4から7の回答について考察する。
4から7の共通意見として、個別支援計画や日誌等のフォーマット・本人に分りやすい個別支援計画の参考例・サービス内容のチェック方法・スーパーバイスの仕方と演習・GHCHでのサービス管理の実際例・サービス管理責任者の評価方法・重度障害者へのアセスメント方法・利用者の意向の聴き取りかた等、具体的な方法・手法に対するリクエストが寄せられている。より現場実践をイメージした意見として評価したいが、国研修で行うことか、あるいは地方研修で行うか議論が必要である。相談支援従事者研修・フォローアップ研修のカテゴリーとしても検討できようか。
f)指導者研修テキストの内容について
分野別演習となる4から7の回答について考察する。
テキストについて、現状のまま12人(54%)、修正したほうがよい10人(46%)。
具体的な修正提案は分野別に対しては2件だけであった。
具体的な困難事例・支援会議モデル・ツールとしての例えばサビ管日誌・記録用紙・利用者がわくわくするような個別支援計画タイムを加えるよう提案されている。サービス管理責任者として基本となる理念・役割は大切にしてほしいと肯定的意見も寄せられている。
g)都道府県の研修を企画運営する上での課題
受講者の経験・参加意識・参加レベルに差が見られ、グループワークとして課題に上げた内容を消化していくのに苦労をしている。5年の実務経験者をクリヤーしているはずの参加者であるが相談支援スキルに不適切な方がこのままサビ管に従事してよいのかと不安を述べている。研修内容の質を保ちたい思いと地方研修での実際との乖離に悩みが深い。 演習時間の持ち方・研修資料の内容等、基本的に抑えておく部分・地方事情に合わせて変形する部分をある程度例示したほうが、地方研修場面では負担軽減になるのか、演習内容・構成の検討が必要である。
h)相談支援専門員とどのように役割分担しているか
サービス管理責任者は居住系(入所・GHCH)、地域・在宅は相談支援専門員と明確に区分けして連携しているとする回答は13回答中4件、区分けしていないは4件、まだかかわりがないが2件、その他3件で、実際にかかわりがある段階でどう住み分けしていくかであるが、事例が増加していくにつれある程度の業務区分けが出来てくるのではないか。いずれにせよ、つなぎ部分では重複(共有)して相互の専門性を補完しあうことが必要で、利用者に不安を感じさせないように支援を組み立てていくことが肝要であろう。
i)サービス管理責任者の課題について
ほぼ全員から回答があった。意見に込められた総合的な印象は、サービス管理責任者業務の重要性を認め、必要性を充分に評価しているからこそ、その業務にふさわしい専業体制を取りうる報酬単価上の評価が必要であると積極的に提案がされている。サービス管理責任者としての責務が重要と研修で気付かされたが故に、ないがしろに出来ないという思いと現実の業務とのギャップに悩みが吐露されている。また役割が遂行されていくための一定の責任(例えば自立支援協議会への参加義務)を担うとともに、職務に専念できるよう理解・認知を促すための法人・運営管理者向けの国研修と通知、サービス管理責任者の質的向上を求める継続研修(フォローアップ研修)とその参加義務、あるいは一定の基準によるサービス管理責任者自身の評価を求めている。参加者には多くの気付き・促し、そして自覚を促した意味では研修の意味を評価できる。一方だからこそ、立場が尊重されるよう周辺環境を整えるのも資格取得者に対する国の事後フォローが重要になる。
④児童分野
a)回答者の属性について
新体系への移行状況については、新制度での療育型とタイムケア型の2 タイプにわけられ,より単価の高い療育型への移行が望まれたことから,新制度移行が準備中も含めて70%と高くなっている。事業所の経営主体については、社会福祉法人が50%弱で,あとは医療法人なども含め多様な経営主体であるのはこの分野の特徴であろう。
b)国の指導者研修に対する満足度について
児童デイ分野は事業規模が小さく,研修会や業界大会などに出席することが少ないことから障害分野の全体的な動きや制度的な新しい動向等について幅広く見識を広められたチャンスとして肯定的な評価が圧倒的に多かった。また演習についても全国各地の同じ活動をしている者同士の出会いや活動内容について知り合うチャンスとなったことについての評価が高かった。
c)国の指導者研修の内容が現場で活かされているか
回答なしの3 人(9%)を除き,肯定的な回答であった。
活かされているかどうかの理由については、着眼点とか見通しとか見直しのヒントとか日常の活動世界とは異なる世界に参加し体験したことによる高揚心が述べられている。
d)研修内容と現場とのズレとその内容
「ある」の回答が,回答者の69%であったが,これは児童デイのハ-ド,ソフト両面での現場の多様さからくるものであろう。
e)国の指導者研修の内容で良かった点
① 障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
今回の制度の意味や仕組みが良く理解できたなど知らなかったこと,理解できていなかったことが解決・解消された感想が多かった。また人気テレビの「仕事の流儀」風まとめの話しに興味が高かった。
② サービス提供のプロセスと管理
耳新しい概念としての「モニタリング」とか「ICF」とか「エンパワメント」とか「アセスメント」などの理解とイメージが持てたこと等が指摘されている。
③ サービス提供者と関係機関の連携
地域を知ること,連携すること,資源発掘,自立支援会議への道筋などがよく理解できた。
④ 分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
前段の講義編が大人を中心とした世界の話しであったことから,子どもに特化された話しになってほっとした安堵感が述べられている。また混迷する子どもの世界の方向性や見通しや問題点などが良く理解できたという意見が多かった。
⑤ ⑥サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編・個別支援計画編)
具体的な事例を通しての展開だったので,わかりやすく興味をもって参加できたと好評であった。
⑦ サービス内容のチェックとマネジメントの実際
発達支援・家族支援・地域生活支援の視点からの具体的な支援活動について学ぶことで具体的なイメージが持てたようである。
f)国の指導者研修の内容の今後の改善点について
① 障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割についての学習の場であるが,よく分かったという見解がある一方で未だによく分からないという意見もある。
② サービス提供のプロセスと管理
子どものことにもっと触れて欲しいという要望がある。これは前半の講義編に共通している。
③ サービス提供者と関係機関連携
同上
④ 分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
障害者自立支援法下での児童施設の実態についての要望が出ていた。
⑤ サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
グル-プでの検討内容について意見交換する時間が欲しい。
⑥ サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
個別支援計画のモデル的なものを示して欲しかった。
⑦ サービス内容のチェックとマネジメントの実際
振り返りシ-トの記入がしづらかったようである。事業形態の多様さから当てはまらない部分が出てしまうのかもしれない。
f)国の指導者研修のテキストの内容について
テキストの修正について現状でよいが約6 割であった。
改善して欲しい具体的内容は以下の通りであった。
① 障害者自立支援法とサービス管理責任者の役割
量が膨大すぎる。専門用語が多すぎるなどの意見があった。
② サービス提供のプロセスと管理
最新のものを扱って欲しいと言う要望がある。
③ サービス提供者と関係機関の連携
同上
④ 分野別のアセスメント及びモニタリングの実際
同上
⑤ サービス提供プロセスの管理の実際(アセスメント編)
同上
⑥ サービス提供プロセスの管理の実際(個別支援計画編)
同上
⑦ サービス内容のチェックとマネジメントの実際
g)都道府県研修での役割
回答者の73%が果たしていると回答している。実際実務に就いていない人もいることを考えると高い方ではないか。
h)都道府県研修企画上の課題
業界でのマイノリティが講師などの人材難を生んでいるようである。玉石混淆状態での研修のやりにくさがある。またすでに業務を実施しているところと,準備中のところとがあったり,また地域に事業所数そのものが少ないなど運営企画が難しいようである。
i)相談支援専門員とどのように役割分担をしているのか
サービス管理責任者との関係性や違いなどについての混乱がかなりあるようであり,とりわけ児童分野では相談支援専門員の存在もかなり縁遠い存在であることからかなり大きな不安や混乱を来している。
j)サービス管理責任者の課題について
内容の理解の中途半端さ,制度的なぐらつき,仕事の範囲の広さ,専従的な困難さなどからの不安や警戒感とか自信のなさが目立っている。これは時間と理解の浸透が解決することかもしれないが。
④就労分野
長年にわたって踏襲されてきた施設福祉に関する既成概念を改め、労働領域の諸制度や関連する諸機関、雇用主体である企業、先行している福祉施設などに関する情報提供やその活用、あるいは、地域における連携(ネットッワーク化)軸の形成、について伝達することとした。結果として、施設関係者への企業就労への意識づけ、雇用就労に関する情報提供、就労支援のノウハウの提供に重点に置いたため、結果的に「ジョブコーチ(職場適応援助者)」や「就労支援員」の養成研修と酷似したカリキュラムとし、「就労移行支援」を中心に構成することになった。「就労継続支援A型・B型」に関連する課題にも言及したが、就労継続「A型・B型」に関する施策がなおも流動的で、また、講師陣にもそのような現場を抱えている者もおらず、それらが適切なメッセージとして届いているかどうかははなはだ疑問である。
アンケート結果にみるように、「就労分野」におけるサービス管理責任者研修について、賛同や理解を示して頂いたご回答もあったが、賛否相半ばで、特に批判的なご意見を中心に、a)講義・講演に関する課題、b)都道府県研修における課題、c)サービス管理責任者としての課題、について考察する。
就労分野でいえば、参加者47名中21名の回答で、各分野と比較して最も少ない。また、所属している事業所に関していえば、就労分野の回答者が少なく(9名)、今回のアンケートからはその職責や職位を知ることはできない。
主な項目をあげると以下のようになる。
a)講義・演習について
| ■ | 移行支援・A型・B型を同時に実施することへの是非 |
| ■ | スタッフの講義は、障害分野別の講義が必要である |
| ■ | 就労に向けた具体的な個別支援計画の作成方法について学びたい |
| ■ | 就労継続 B 型に関する内容を盛り込むべき |
| ■ | 各障害によっても支援方法が異なったりするため、各障害にあわせての事例検討となるが、深まらないため、もう少し絞った事例検討となるよう演習の時間配分等を考えるべきである。 |
| ■ | 就労分野は、特に情報量・内容が多いため、構成・内容・ねらいを整理し、より明確に伝達すべき |
| ■ | 就労分野全般に時間に追われてあわただしい感がある。研修・講師陣の連携が少ないように思われる。 |
| ■ | 国の研修の半分が役に立たなかったので、作り直すのに苦労した。先進事例ばかりがすべてではない |
| ■ | B型事業者にとって一般就労への移行と工賃アップばかりが強調され、本質的な視点が入っていない研修となり不満 |
| ■ | 事例のねらいが定まっていないこと。アセスメント方法等もっと具体的に実践で学べるよう内容の工夫が必要と思いました。 |
b)都道府県研修における課題
| ■ | 就労支援経験が浅い対象者に伝える必要性があることから、国レベルの研修では専門的用語は最小限にとどめ分かりやすい用語・図を使用すべき |
| ■ | 研修当日、受付・セッティング・運営も行わねばならず大変、複数の配置が望ましい |
| ■ | 国研修の内容をそのまま使うには無理があった。(予算的にも) |
| ■ | サビ管の研修会が一年目であったために、何をどのように研修会で伝えればよいか不安であり国の講師の協力を求めた |
c)サービス管理責任者としての課題
| ■ | 地域ごとの学習会があれば日常業務の中で共同して行うことが連携に結びつく |
| ■ | 講義だけでなく企業内での支援ノウハウを身につける取り組みが重要。サビ管の名 前だけではどうしようもない。 |
| ■ | 事業所内でサビ管の役割が理解されればきちんと役割が発揮できると思う。事業所の管理者がサビ管について理解することが必要 |
| ■ | サービス管理責任者が何をやらなければならないのか、巾が広すぎて消化不良になっている。必要なことをポイントしぼってテキストの作り直しが必要 |
| ■ | 新しい資格だから取っておこうとする傾向が強いので、本当に必要とする人とそうでない人をセレクトするためにも、現任研修や資格の更新等研修を行う必要がある |
| ■ | 国から各都道府県研修への講師派遣をすることにより、情報の共有化(国、県レベル) |
| ■ | 研修がいつでも受けられるよう頻度を多くする |
| ■ | サビ管の待遇改善(最低基準) |
アンケートはサービス管理責任者研修に関する細部にわたる言及があったが、来年度の研修においてはこれらの意見を具体的に反映したカリキュラムとして実施する必要がある。
なお、研修日程、就労支援計画ごとの研修計画、障害種別による研修、移行実態に合わせた情報提供など、さらに検討する必要性を痛感するが、参加者が自らの施設運営に役立つという側面と、国研修受講者として、就労に関する知見や社会資源に関する知識、実践方法、ネットワーク形成など、就労全般に関する幅広い知識や経験が求められていることは言うまでもない。
最後に、国及び都道府県の研修において就労に対する理解不足が全体的にみられる。この点は、障害者自立支援法が就労の強化を取り上げ、今後の障害者福祉施策の課題として叫ばれていることを考えると、就労に対するコンセプトを明確にしておく必要があろう。
(以下の考察は、關宏之氏の執筆による) わが国では、労働政策において、企業や事業所に「社会連帯」という視点から障害者雇用を義務づけるとともに、一般労働市場(雇用就労)に誘導するための「職業リハビリテーション」を実施し、厚労行政においては、労働市場からの締め出しが予想される障害者を雇用不安のない「福祉的就労」に導き、「労働」を保障するという施策がとられてきた。そのため、「雇用就労」は、事業所・企業における「9~5時労働」に象徴される競争事態での労働(competitive employment)に従事できる作業遂行能力の高い障害者のみに適用される概念として一般化し、福祉的就労と称される施設福祉は、時間的な拘束や労働内容が「労働一般」とさほど相違がないにもかかわらず、賃金や諸々の権利の保障は不問に付され、結果として社会的な諸権利から排除(exclusion)されているという現実についてさほど問題にされてこなかった。「雇用就労」の対局に施設福祉による「福祉的就労」があったことから、労働分野は、もっぱら雇用就労が可能な人を特定し、その雇用促進を進めることと同義となった。そのことが「就労できない人」を選別し、結果として施設に誘導する絶好の根拠を与えたといえなくはないが、ILO第159号条約は、職業リハビリテーションにおける支援プロセスについて示すとともに、その対象となる障害者について、「正当に認定された身体的又は精神的障害のため、適当な職業に就きこれを継続しおよびその職業において向上する見込みが相当に減退している者をいう」と定義している。ここから類推される「職業リハビリテーションの実践=就労支援」は、心身機能の損傷・変調のために職業に就けない人やその継続が困難な人が通常の社会生活を構築できるよう支援する社会福祉における行為であって、就労できる人を特定してその人たちを就労に導くことではない。就労分野における「サービス管理責任者」は、就労に特化したケアマネジメントの専門家として、当事者とともに策定した個別移行支援計画に基づいて、「自立支援協議会」の場や地域の社会資源やシステムと連携しながらその実現を支援するという役割を担う。施設からの事業移行を経営・運営的な側面ではなく、「利用者のおもい」に真摯に耳を傾け、「はたらく」ことの実現を妨げている要因を探ってそれを解消するための手だてを講じ、利用者が地域社会の一員として当たり前の生活主体者となるように支援する、という事業遂行上の調整機能を果たす立場である。
サービス管理に関して、ILO第159号条約「職業リハビリテーションの基本原則」に基づいたプロセスがモデルとされることもあるが、これはあくまでも「職業リハビリテーション」のスキームであって、サービス管理責任者は、同条約で言及している障害者、すなわち、「正当に認定された身体的又は精神的障害のため、適当な職業に就きこれを継続しおよびその職業において向上する見込みが相当に減退している者をいう」という規定にみるように、心身機能の損傷・変調のために職業に就けない人やその継続が困難な人を支援して就労に道火し、社会生活を構築できるよう支援することであって、利用者の「能力」を評価して就労できる人を特定して「雇用就労」に導くことではない。そのようにして「就労」を実現することになるが、「働くこと」を至上命令としない「生き方」を容認するという柔軟な態度も求められよう。
金子(1989)は、コミュニティーを「地域性」「共同性」という伝統的な枠組みに加えて、「社会資源の加工によって生み出されるサービスの供給システム」であると規定している。ここでいう社会資源とは、物的資源、人的・サービス資源、関係的資源、情報・文化的資源のことで、これらを形成可能な「サービス」に仕上げ、配分するシステムとして機能的なコミュニティーの役割としている。地域社会における資源を再統合して地域住民主体のネットワークとして再構築し、地域社会における福祉サービスを形成するのが地域社会の役割であり、あるいは、福祉施設やサービス管理責任者のめざすところである。
また、「障害者基本計画」および「障害者プラン」に伴う「市町村障害者計画」や自立支援法による「障害福祉計画」による目標値・進捗状況への関心や、従前の福祉施策とは明らかに異なった施策の展望も示されるようになり、厚生労働省からは、「就労移行支援(資料1)」「就労継続支援A型(資料2)」「工賃一覧(資料3)」も明らかにされ、地域が就業機会を提供する社会的企業(social firm)という新たな仕組みが機能したり、地域の特性や文化を活かして工賃アップをめざすコミュニティー・ビジネスの実現を図ろうとする動きもある(資料4)。
ところで、「雇用就労」をいう場合、企業(事業所)の雇用意欲や産業分野の動向、あるいは、社会貢献活動(CSR:Corporate Social Responsibility)や雇用に関する法的措置、市町村における「障害者福祉計画」や社会資源間のネットワーク化や連携が図られるようになり、最近の雇用動向(厚生労働省;平成19年11月20日)は、ハローワークにおける障害者の雇用者数は着実に伸びており、平成19年度においては、民間企業(56人以上規模の企業)においては、雇用されている障害者の数が、前年に比べて6.7%(約1万9千人)増加し、約30万3千人となり、実雇用率が、前年に比べて0.03%ポイント上昇し、1.55%となった、法定雇用率達成企業の割合が、前年に比べて0.4%ポイント上昇し、43.8%となった。
(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/11/dl/h1120-1a.pdf)。
堅調な経済情勢や企業の雇用への取り組みの高まりに支えられているという側面に加えて、労働関係機関の取り組みの成果とされるが、「自立支援法」における「就労移行支援」の関与も大きいと確信する。
<資料1>
新事業体系への移行状況(就労移行支援)
※19.4.1現在
| 都道府県 | 箇所数 | 人数 | 都道府県 | 箇所数 | 人数 | 都道府県 | 箇所数 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 54 | 674 | 石川県 | 9 | 156 | 岡山県 | 18 | 186 |
| 青森県 | 2 | 60 | 福井県 | 19 | 368 | 広島県 | 17 | 226 |
| 岩手県 | 15 | 198 | 山梨県 | 4 | 24 | 山口県 | 6 | 74 |
| 宮城県 | 11 | 93 | 長野県 | 13 | 207 | 徳島県 | 5 | 60 |
| 秋田県 | 5 | 56 | 岐阜県 | 6 | 63 | 香川県 | 4 | 46 |
| 山形県 | 3 | 36 | 静岡県 | 1 | 50 | 愛媛県 | 11 | 134 |
| 福島県 | 6 | 80 | 愛知県 | 23 | 241 | 高知県 | 5 | 51 |
| 茨城県 | 36 | 554 | 三重県 | 3 | 33 | 福岡県 | 19 | 282 |
| 栃木県 | 17 | 166 | 滋賀県 | 5 | 59 | 佐賀県 | 4 | 35 |
| 群馬県 | 6; | 70 | 京都府 | 14 | 287 | 長崎県 | 9 | 82 |
| 埼玉県 | 21 | 584 | 大阪府 | 54 | 630 | 熊本県 | 13 | 129 |
| 千葉県 | 15 | 205 | 兵庫県 | 29 | 522 | 大分県 | 13 | 116 |
| 東京都 | 41 | 575 | 奈良県 | 8 | 81 | 宮崎県 | 14 | 208 |
| 神奈川県 | 23 | 394 | 和歌山県 | 8 | 97 | 鹿児島県 | 5 | 56 |
| 新潟県 | 7 | 98 | 鳥取県 | 2 | 20 | 沖縄県 | 11 | 135 |
| 富山県 | 10 | 107 | 島根県 | 9 | 97 | 全国計 | 633 | 8,705 |
法人格…社会福祉471箇所6,092人、NPO95箇所1,185人、地方自治体20箇所694人、株式17箇所235人、医療15箇所 113人等
<資料2>
新事業体系への移行状況(就労継続支援A型)※19.4.1現在
| 都道府県 | 箇所数 | 人数 | 都道府県 | 箇所数 | 人数 | 都道府県 | 箇所数 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 16 | 305 | 石川県 | 0 | 0 | 岡山県 | 2 | 30 |
| 青森県 | 2 | 60 | 福井県 | 12 | 388 | 広島県 | 10 | 247 |
| 岩手県 | 1 | 34 | 山梨県 | 1 | 20 | 山口県 | 2 | 30 |
| 宮城県 | 2 | 25 | 長野県 | 6 | 112 | 徳島県 | 2 | 20 |
| 秋田県 | 1 | 13 | 岐阜県 | 4 | 59 | 香川県 | 0 | 0 |
| 山形県 | 2 | 52 | 静岡県 | 3 | 105 | 愛媛県 | 1 | 20 |
| 福島県 | 2 | 20 | 愛知県 | 6 | 88 | 高知県 | 0 | 0 |
| 茨城県 | 2 | 90 | 三重県 | 0 | 0 | 福岡県 | 9 | 140 |
| 栃木県 | 2 | 38 | 滋賀県 | 1 | 32 | 佐賀県 | 0 | 0 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 京都府 | 4 | 40 | 長崎県 | 5 | 90 |
| 埼玉県 | 0 | 0 | 大阪府 | 3 | 48 | 熊本県 | 11 | 274 |
| 千葉県 | 0 | 0 | 兵庫県 | 3 | 60 | 大分県 | 6 | 150 |
| 東京都 | 2 | 30 | 奈良県 | 3 | 41 | 宮崎県 | 0 | 0 |
| 神奈川県 | 5 | 50 | 和歌山県 | 2 | 50 | 鹿児島県 | 2 | 30 |
| 新潟県 | 0 | 0 | 鳥取県 | 1 | 50 | 沖縄県 | 2 | 90 |
| 富山県 | 0 | 0 | 島根県 | 2 | 20 | 全国計 | 140 | 2,931 |
法人格…社会福祉88箇所2,171人、NPO37箇所521人、株式・有限8箇所110人等
<資料3>
平成18年度平均工賃一覧(都道府県別) 円/月額
| 都道府県 | 対象施設 平均工賃 |
都道府県 | 対象施設 平均工賃 |
都道府県 | 対象施設 平均工賃 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 15,304.6 | 石川県 | 15,179.3 | 岡山県 | 10,749.9 |
| 青森県 | 9,310.5 | 福井県 | 15,493.4 | 広島県 | 12,419.1 |
| 岩手県 | 15,224.9 | 山梨県 | 10,735.6 | 山口県 | 12,632.3 |
| 宮城県 | 13,061.3 | 長野県 | 10,548.0 | 徳島県 | 14,636.2 |
| 秋田県 | 12,580.4 | 岐阜県 | 10,067.8 | 香川県 | 11,171.6 |
| 山形県 | 10,283.3 | 静岡県 | 13,660.6 | 愛媛県 | 11,709.6 |
| 福島県 | 9,540.0 | 愛知県 | 14,446.8 | 高知県 | 16,013.5 |
| 茨城県 | 9,241.2 | 三重県 | 10,406.9 | 福岡県 | 11,663.9 |
| 栃木県 | 12,562.9 | 滋賀県 | 15,565.9 | 佐賀県 | 15,395.7 |
| 群馬県 | 11,116.0 | 京都府 | 12,999.9 | 長崎県 | 11,181.5 |
| 埼玉県 | 11,777.8 | 大阪府 | 7,989.7 | 熊本県 | 12,836.1 |
| 千葉県 | 12,024.4 | 兵庫県 | 10,190.0 | 大分県 | 13,489.4 |
| 東京都 | 14,488.1 | 奈良県 | 9,861.1 | 宮崎県 | 11,017.9 |
| 神奈川県 | 12,367.4 | 和歌山県 | 12,045.8 | 鹿児島県 | 12,809.4 |
| 新潟県 | 10,441.2 | 鳥取県 | 13,366.1 | 沖縄県 | 13,552.1 |
| 富山県 | 11,932.6 | 島根県 | 12,548.6 | 全国計 | 12,222.3 |
※工賃倍増計画対象施設(就労継続支援B 型事業所・授産施設・小規模通所授産施設)の平均工賃
<資料4>