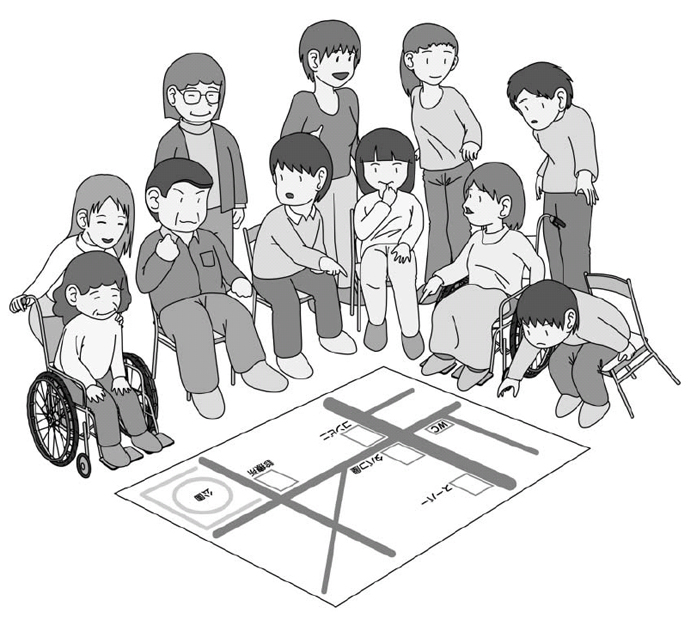第7章 自立支援協議会の今後の目指すべき方向
1)地域自立支援協議会設置の意義
医療保健福祉をめぐる政治の仕組みが大きく変化しつつある現在の段階で、あらためて地域自立支援協議会が持っている意義について、意識的に考えることが大切です。
疾病や障害を持つことで支援を要する人々にとって、わが国の現状では、制度の縦割り、資源の散逸、情報の混乱、対象者とその家族の孤立など、きわめて生きにくい状況にあります。
地域自立支援協議会は、それぞれ特徴的な歴史と風土を持つ地域の中で、具体的な対象者を想定しながら、相談支援活動をマネジメントする立場と機能が付与されています。これによって、サービス利用対象者または支援を要する障害者に関する情報と、サービスを提供する機関や人材の情報と、行政の施策や制度に関する情報が、ひとつの場に集められ調整することが可能になりました。
つまり、地域自立支援協議会のあり方いかんによって、限られた予算であっても、最大限のサービス提供を追究することが可能になったと言えます。
2)地域自立支援協議会の可能性
地域自立支援協議会の構成を見ると、医療保健福祉という境界を越えて、障害種別を越えて、公民が共に加わって形成されています。このことに今後の可能性が込められています。
医療保健福祉ばかりでなく、教育、産業、司法といった様々な人材を招き入れることによって、サービス利用対象者がその地域で暮らすという本来の自立を支援することが可能になるでしょう。また、厳密すぎるほどに規定される障害種別、重症度区分、年齢、収入などによる制度の狭間に関する諸問題も、事例に則した調整によって救出が可能になることもあるでしょう。
行政という公の構成員と、民間人という私の専門職および住民が、活動を共にする仕組みは、制度や施策のオーソリティ(権威性)と、組織や活動のフレキシビリティ(柔軟性)との矛盾を解消できる可能性を持っています。協議会に直接的な行政権限は付与されていませんが、具体的な住民の状況に則して、例えば、監査機能、予算配分、障害福祉計画などに関する情報交換は、今以上に行われるに違いありません。将来は、協議会の情報交換をもとに公私協働のPFI(民間資金等活用事業)が生まれるかもしれません。
3)地域自立支援協議会の形式
設立の趣旨から、地域自立支援協議会は、その形態や機能について事細かく規定されず、その地域の実状に応じた構造と活動を選択することができます。このことは、自由な発想が可能であると同時に、地域に対する責任を負うということを意味しています。
今回のマニュアルによって複数の形式が提案されていますが、これらはそれぞれ各地域の歴史的な展開のもとにたどり着いている構造と機能です。協議会の構造と機能は、関係者が協働して作り上げることが期待されています。さらに、状況の変化に応じて、構造と機能を変化させることも重要です。協議会の構造や構成員について、当面の目標や地域状況に応じて、いつでも変更できる仕組みをあらかじめ持っておく必要があります。
全国の多くの協議会活動において実行される様々な工夫と実践は、先進諸国の真似事ではなく、わが国の風土や価値観に合致した仕組みを生み出すものと期待されます。
4)地域自立支援協議会に関する全国連絡会
地域自立支援協議会は、全国一律ではないだけに、情報がその地域に限定されやすくなっています。地域自立支援協議会および相談支援の活動に関する多様な工夫と見事な実践について、全国レベルで常に情報交換をする仕組みが求められます。今後、何らかの全国連絡会が必要となるでしょう。