I.見えないということ
この冊子を手に取った方は、見えない人・見えにくい人のことを知って「自分にできることを考えてみよう」と思ってくれているだろうか?それとも「ガイドヘルパーにチャレンジしてみよう」と考えてくれているだろうか?
まずは「見えないということ」について話をするが、この冊子を最後まで読んで「見えない人・見えにくい人」のことをより知ってほしい。
「見えない人・見えにくい人」は、当然のことながら「自立」と「社会参加」を強く望んでいる。しかし、そこには法制度のバリア、物理的なバリア、情報とコミュニケーションのバリア、心のバリアがあると言われている。どうすればこうしたバリアがなくなるのだろうか?
我々のまわりではいろいろなところに点字の表示がなされるようになってきているが、気づいているだろうか?
家庭の洗濯機や冷蔵庫の缶ビールに点字はついているだろうか?ほかにはどうか、確かめてほしい。駅の券売機や公共の建物には案内用の触覚地図や部屋の表示に点字表示が義務づけられるようになったので、目にとまることも多くなったのではないだろうか?点字以外でも電話のプッシュボタンの5の数字につけられたポッチも、触覚的な情報として見えない人・見えにくい人にはとても役立つ情報なのである。
見えない人・見えにくい人はどのように本を読んだり、テレビを見たりしているのだろう?と不思議に思っている方も多いのではないだろうか?点字や触覚サインだけではなく、音声や臭いも大切な情報であり、様々な情報を有効に使うことで、見えない人・見えにくい人の移動や文字の読み書きの不自由、つまり「バリア」を低くすることにつながるのである。
目が見えない・見えにくい人とは
全国に目の不自由な人は、約31万人いると言われている。その中には、全く見えない人もいるが、周囲が見えにくい人、真ん中が見えにくい人、大きな文字なら読める人、明るいとまぶしい人、白くにごったように見える人など、いろいろな見えにくさの人がいる。
また、小さいときから見えにくかった人もいるが、大人になってから事故や病気で急に見えにくくなった人もいる。
こうした人たちのことを「視力障害者」や「盲人」とも言うが、一般的には「視覚障害者」と呼んでいる。
視覚障害者の中には「全盲」と言われる「文字はもちろん、明かりさえ全く見えない人やまわりの状況ぐらいはぼやっと見える人」と、「弱視」と言われる「文字を拡大したり、目に近づけることでなんとか読める程度の視力がある人」がいる。
また、文字を読むのにたいへん苦労をしたり、文字が読めるほどの視力はなかったりするものの、晴眼者とあまり変わらないような状態で日常生活を送っている人もいるが、このような人の状態を指して「生活視力がある」と言ったりすることがある。
以上のように「視覚障害者」といってもその程度と、必要とする支援は十人十色である。言い換えれば移動や情報・コミュニケーション支援において、失明年齢やキャリアによって必要とする支援内容は異なる。
日本には「身体障害者手帳」という制度があり、視覚に障害があっても手帳を所持していなければ、法律上は「身体障害者」とは認められない。視覚障害者の場合は1級から6級に分けられており、この障害の程度によって福祉サービスの内容が異なる。一般的に、1級と2級の障害状態は重度障害者と呼ばれ、昨今増加傾向にあり、3級と4級の障害状態は中度(中程度)障害者、5級と6級の障害状態は軽度障害者と呼ばれている。
視覚障害の原因はプライバシーに関わることなので必要のない限り話題にしない方が望ましいのだが、最近は状況の変化が見られる。
視覚障害になる原因は、戦後間もない頃には、はしかやトラコーマなどの病気によって、その後は未熟児網膜症によって、幼い子が視覚障害になるケースが比較的多かったが、近年は糖尿病などのいわゆる生活習慣病や事故によるケースが増えている。厚生労働省の平成19年(2007年)の「国民健康・栄養調査結果」は糖尿病の疑いがある人は全国で推定2210万人でその10パーセントは視力を失う危険性が大であるとしている。視力を失うのは特殊なケースではなく、誰もがその心配を持っているとも言える。
最近は、視力や視野は残っているものの、見えにくさのある人が増えている。以前からある網膜色素変性症に加えて、高齢化と共に緑内障や黄斑変性症などが増えてきている。
視覚障害者は、「高齢化」と「重度化」が顕著であることに留意してほしい。60歳以上の人は全体の7割を超え、重度視覚障害者は6割を超えている。もう一つの特徴は中途視覚障害者の増加である。人生半ばにして視力を失うことは就労や家庭生活の面でもその基盤が崩れることになり、心理的にも大きな打撃を受けることになる。自身の障害を受容することから新たな人生が始まるのだが、そのためにも障害告知と同時に視覚障害者リハビリテーション施設や視覚障害者情報提供施設等、社会福祉施設を訪問されることを勧めたい。
「平成18年身体障害児・者実態調査結果」(厚生労働省が5年毎に実施)では、
(1)在宅の視覚障害児・者は推計31万5千人
全国の在宅の視覚障害者(身体障害者手帳を持つか、それに相当する18歳以上)は推計31万人。視覚障害児(18歳未満)は推計4,900人で、合わせて31万4,900人になる。
身体障害児・者の人数
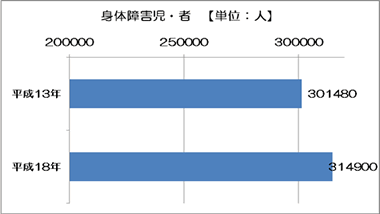
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
(2)年齢別
60歳以上が70%を占めている。この高齢化の背景には、近年、生まれつきや幼少期に視覚障害になる人が減少する一方、特定の疾病などにより中高年期以降に視覚障害になる人が漸増している事実がある。
視覚障害者割合(年齢別)
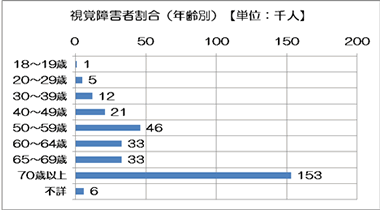
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
(3)障害程度別
1級が35.5%、2級が26.5%で、全盲かそれに近い人が合計61.9%(19万2千人)。弱視に相当する3級~6級の人が34.2%(10万6千人)。(ただし、日本眼科医会によると、「視覚障害者と認定されなくとも、視覚的に日常生活に困難」のある「ロービジョン者」は約100万人いると推定されている。また、視覚障害児・者の中に、聴覚障害を併せ持つ「盲ろう児・者」が推計23,200人いる。)
視覚障害者割合(障害程度別)
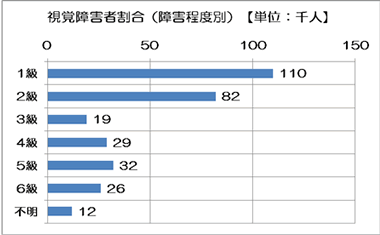
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)


