II.ガイドヘルパーの必要性とその役割
1.視覚障害者の二大不自由
(1)情報の収集
一般的に、視覚障害者が日常生活を営む上で不自由なことが二つあると言われている。一つは文字情報を含む情報摂取である。高度情報化社会と言われる今日、その情報の大部分(一説によると80%)は視覚情報であり、我が国に31万人いるといわれる視覚障害者にとって、その情報の大部分を直接摂取することができないか、あるいは摂取することが極めて困難な状況におかれている。そのため、視覚障害者は情報障害者であるとも言える。
全国各地にある視覚障害者情報提供施設では、多くのボランティアの協力を得て、点字・音声・拡大文字などによる情報提供を行っている。中でも約10万タイトルの点字データと44万タイトルの点字・録音書誌情報を有し全国視覚障害者情報提供施設協会(全視情協)が運営する「ないーぶネット」、1万1千タイトルの音声データを有し日本点字図書館と日本ライトハウス盲人情報文化センターが運営する「びぶりおネット」、毎日の情報を日本盲人会連合が全国に向けて発信する点字JBニュース等、インターネットを活用した情報提供が活発に行われている。これらによって視覚障害者の情報環境は飛躍的に改善されつつあるが、これらを利用できる視覚障害者はごくわずか(「ないーぶネット」利用者約5,500人、「びぶりおネット」利用者約2,300人)なのが実情であり、さらに、個別に必要な情報の提供、たとえば電化製品の取り扱い説明書、家庭に舞い込むさまざまな文字情報などの提供は全く不十分である。
「平成18年身体障害児・者実態調査結果」によると、
ア.情報・コミュニケーション関係
「録音・点字」による情報の入手は14.8%、「パソコンの利用」は12.4%で、「点字ができる」と答えた人は12.7%であるが、点字が特に有用と思われる1・2級の人で見ると20%になる。また、「点字ができない」70.7%の人のうち、「点字を必要としている」と答えた人は6.6%である。
点字の必要性【推計人数】
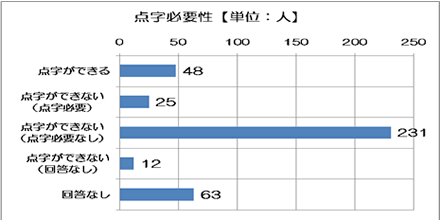
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
イ.「情報の入手方法」(「主に」「特に」利用している方法。複数回答)
- テレビ ・・・・・ 66%
- 家族・友人 ・・・ 55.7%
- ラジオ ・・・・・ 49.3%
- 図書・新聞・雑誌 ・・ 26.9%
- 録音・点字図書 ・・ 14.8%
- 自治体広報 ・・・ 13.7%
- 携帯電話 ・・・・ 7.1%
- HP・電子メール ・・・ 6.6%
情報の入手先【人数】
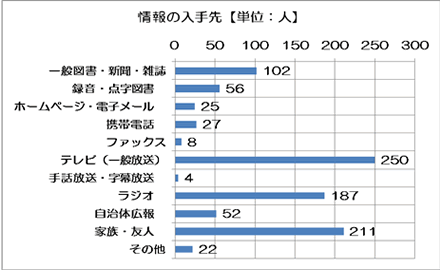
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
(2)移動(歩行)
視覚障害者のもう一つの不自由は、移動(歩行)である。長年住み慣れた家の中であれば問題なく移動できるが、一歩外へ出れば、不自由を通り越して多くの危険を伴うことになる。
なお、厚生労働省の前記調査結果のうち、移動・外出に関わるものは次のとおりである。
ア.「外出する上で、または外出しようとする上で困ること」(複数回答)
- 乗り物の利用が不便・人の混雑や車に危険を感じる(いずれも32.0%)
- 公共の場所を利用しにくい(26.8%)
- 建物の設備が不備(26.5%)
が上位を占めている。
外出する上で、または外出しようとする上で困ること
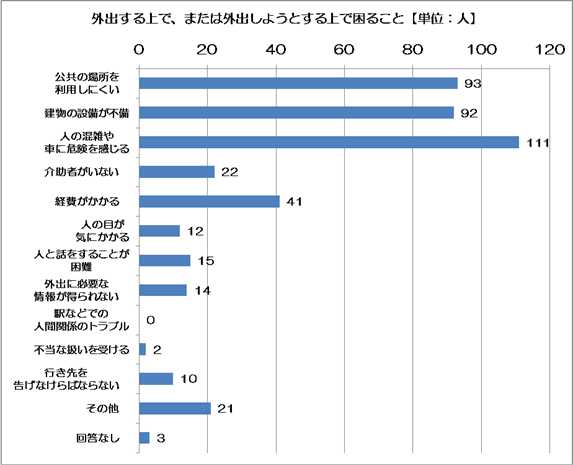
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
イ.「外出の状況」
「ほぼ毎日」か「週2~3回」外出する人が合計59.1%で、前回の56.8%から微増しているものの、「年に数回」しか外出しないか「外出なし」の人が合計16.9%で、外出することが難しい人が多いことが分かる。
外出の状況
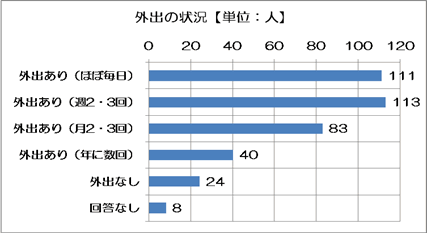
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
ウ.「過去1年間の活動等の状況(複数回答)」では、
- 旅行・キャンプ・つり等 ・・・ 22.7%
- コンサート・映画・スポーツ鑑賞 ・ 19.3%
- 趣味の同好会活動 ・・・・・・ 15.0%
- 障害者団体の活動 ・・・・・・ 12.7%
- 学習活動 ・・・・・・・・・・ 10.8%
- パソコンの利用 ・・・・・・・ 9.0%
過去一年間の活動状況
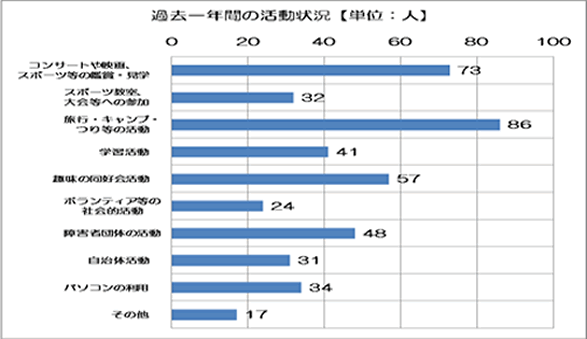
(平成18年度身体障害児・者実態調査結果【厚生労働省】より引用)
住環境や生育歴、視覚障害の程度、発症年齢などによって、日常生活上の不自由はほかにもたくさんあるが、以上見てきたように、共通して言われる不自由は上記2点に集約できる。
2.移動(歩行)の際も情報収集が必要
視覚障害者の移動の不自由さは、歩くという機能の不自由さではなく、歩く際に必要な情報が不足することである。
段差や階段、雨の日の水たまり、突然の道路工事による柵の設置や迂回路の出現、ブロック上の自転車や看板、駅や建物の改修工事、商店の休業や突然の閉店等々、晴眼者ならほとんど無意識に得て移動中に活用している様々な情報が直接得られないか、または得にくい視覚障害者は、移動に大きな不自由を味わうことになる。
3.視覚障害者が安全に移動(歩行)を行うための方法と問題点
視覚障害者が移動(歩行)する場合の方法はいくつかあり、いずれかを選択するか、あるいは併用して移動(歩行)している。
(1)白杖使用
歩行訓練士による白杖を使用しての歩行訓練は、視覚障害者が単独歩行する上で極めて効果的であるが、
- 歩行訓練士の数が少ないために、訓練希望者全員が受けられるわけではないこと。また、訓練を受けた人すべてが単独歩行できるようになるわけではないこと
- 歩行訓練を受けても、全く初めての道を単独で安全に歩くことは非常に困難であること
など、いくつかの問題点が挙げられる。
(2)盲導犬
盲導犬は、視覚障害者が人の手を借りずに移動するための効果的な手段であるが、
- 生理的に犬を受け入れられない視覚障害者には利用できない
- 住環境によっては犬を飼うことができない
- 三療開業者の場合、長期間自宅を離れて訓練を受けるのが困難である
- 盲導犬を使用するには単独歩行ができなければならないため、希望者全員が盲導犬使用者になれるわけではない
- 盲導犬使用中でもガイドが必要な場面がある
などの問題点が挙げられる
安全歩行のパートナーである盲導犬が、平成13年(2001年)の「補助犬法」の成立によって正式に認められ、盲導犬の貸与システムの充実が望まれるところであるが、現在全国で活動中の盲導犬は約950頭で実際の需要には全く追いついていない。
また、盲導犬は非常に優れた犬であることから盲導犬が主人を誘導していると思っている人が意外に多い。実際は主人である視覚障害者が頭の中に地図を描いて盲導犬に指示を与えて移動するのである。つまり、盲導犬は主人の指示通りに歩くのであって、単独歩行ができない視覚障害者は盲導犬を扱うことができないといえる。そして単独歩行と同様に、主人が頭の中の地図をなくしてしまうと道に迷うことがある。
(3)ガイドヘルプ
ガイドヘルプには、障害者自立支援法による移動支援のような公的制度と、全国で展開されているボランティアによる活動があり、白杖や盲導犬使用に比べ、訓練を受けた晴眼者によるガイドヘルプは最も安全な方法であると言える。
ガイドヘルプは人間が関わるため、犬や物と違い会話することによって、より多くの正確な情報が提供できる、臨機応変な対応ができる、などという長所がある反面、ガイドの行為によって得られる様々な個人情報が漏れてしまう恐れがあるという短所を併せ持つことになる。そのため、ガイドヘルパーには厳格な守秘義務を課し、個人情報を保護することによって、利用者の安心・安全を確保する必要がある。
このほかに、環境整備として、ブロック(点状、線状)・音響信号機の設置・各種点字サインの表示などがある。これらのものは視覚障害者が単独歩行をする上で効果を発揮するが、①ブロックの敷設方法が統一されていないので、初めての道では効果が薄い、②音響信号機は設置周辺住民の要求によって、音量や時間が制限されるケースがある、③点字サインをすべての視覚障害者が読めるわけではない、などの問題点が挙げられる。さらに言えば、ブロックや音響信号機が設置され、点字サインが表示されることによって、「視覚障害者はこれらを使って安全に行動できるので、私たちがサポートする必要はない」との一般の方々の誤解を生むおそれがあることにも留意する必要がある。
特に鉄道駅のホームに敷設されるブロックの普及はめざましいものがあるが、ブロックがあってもホームから線路に転落する視覚障害者があとをたたないし、そのうちの何人かは悲惨な結末を迎えているのが実情である。
4.ガイドヘルパーの役割
ガイドヘルパーの役割は、視覚障害者の求めに応じ、安全に安心して視覚障害者が移動できるようサポートをすることであり、そのためには次の点についての十分な知識・技術の習得が望まれる。
(1)サポート技術
視覚障害者への接し方、ガイドの基本、さまざまな場面でのガイド技術など、視覚障害者を安全に目的地までガイドする専門的な技術を習得するとともに、それぞれの場面での状況説明の方法について習得する。
(2)法律や制度の知識
公共交通機関利用のための各種割引制度を始め、視覚障害者福祉に関する法律・制度を熟知し、必要に応じて視覚障害者に伝える。これも大事な情報提供である。
(3)守秘義務
移動先、移動の目的、ガイド中での出来事、当事者との会話で知った障害原因、家族の状況など、知り得た内容を絶対に他に漏らさない強い意識が必要である。人がガイドすることの長所は、すでに述べたようにたくさんあるが、同時に、会話することから起こる秘密の漏洩は、他の移動手段では起こりえない最大の短所なので、ガイドはこのことを肝に銘じておく必要がある。
(4)代読・代筆の技術
目的地やガイドヘルプ終了後の利用者の自宅で依頼される資料や郵便物などの代読の技術、各種書式などへの代筆の技術を習得し、視覚障害者のニーズにきめ細かく対応できるように備える必要がある。
このようにガイドヘルパーは、視覚障害者の個人の尊厳に配慮した上で、視覚障害の特性を理解したサービスを行うことが必要である。
5.ガイドヘルプと情報提供
ガイドヘルプは、利用者が「社会生活を営む上で必要な視覚情報が得られないか、または得にくい人」であることから、「視覚情報の提供及び視覚的確認と共に行う行為に関する援助を内容とするサービス」でなければならない。ガイドヘルプは、目的地までの安全な移動が目的ではあるが、目に映る周囲の景色や通行する人たちの様子、特徴的なファッションやお店のディスプレイなどを伝えることも重要である。そのことにより視覚障害者はいろいろな想像が可能になる。的確な情報を受けることで、歩くことは目的地までの単なる移動ではなく、自分の意志で「歩く」ことになり、気分はずっと楽しくなるものである。
公園などへの散歩が目的のガイドであれば、できる限りいろいろなものを触らせることが必要である。触ることで得られる情報は、目からの情報に比べるとずっとその情報量は少ないが、視覚障害者の指先や手のひらは目の代わりをする重要な情報入手器官である。視覚情報が全体を把握できるのに比べて触覚情報は指先や手のひらが触れているその部分だけに限定されるので、説明をするときには全体がイメージできるよう言葉での補足をしながら触らせることが重要である。
視覚障害者のガイドを行う場合、単に移動先への安全なガイドにとどまらず、移動中の風景や電車などの時刻・運賃、移動先での建物や室内の状況説明、配付資料の代読などの情報提供を必要に応じて行うことが求められる。またガイドそのものについても、移動中の道路や周辺状況の情報を提供する行為ということができる。言い換えれば、視覚障害者のガイドは情報提供であるということができる。そのため、ガイドに当たっては常に情報提供を心がけて行動する必要がある。
情報提供の具体例としては、次のようなものがある。
- 移動中:周辺の風景や建物などについて、また、通行人の服装、店頭の様子などを必要に応じて伝える。目的地までの運賃・時刻表などを伝える。
- 移動先:建物などの概要説明。室内の状況説明。配付資料の代読、知り合いを捜す。
- 帰宅時:自宅に届いた郵便物、ちらし類、電化製品取り扱い説明書、回覧板などを求めに応じて代読。アンケート・提出資料などを求めに応じて代筆。
このように視覚障害者の移動支援は、重度肢体不自由者の移動支援とは異質なものである。それは、基本的に体を支える必要がないことであり、常に情報提供を伴うことである。したがってガイドヘルパーは、視覚障害者が安全に安心して移動目的を実現できるようサポートするとともに、常に周辺に気を配り、視覚障害者が必要とする情報の提供を基本に据えたサービス提供を行う必要がある。
障害者自立支援法の施行に伴い、平成18年(2006年)10月、地方自治体が行う地域生活支援事業の中に「コミュニケーション支援事業」が位置づけられた。本制度は手話通訳者の派遣など聴覚障害者の意思疎通を支援すると同時に視覚障害者への「点訳・音訳等」による支援事業が必要であることを踏まえたものである。
平成20年(2008年)6月~8月に日本盲人会連合が主催した「視覚障害者移動支援事業従業者資質向上研修」では、移動支援技術とともに次のような内容が指導プログラムに追加されている。
- 外出時の移動における情報支援方法
- 文書や表示、映像、情景などについての代読又は口頭説明方法。
- 室内での物の整理や分類及び確認・選び出し、代筆など、視覚的確認・把握と共に行う行為についての支援方法


