第5章 シュミレータの実際 5-1 連携入力の進行
図3.筆記者用の画面
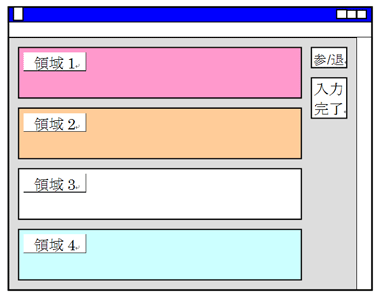
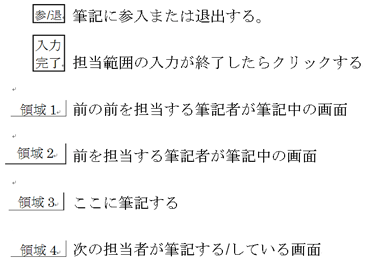
図4.それぞれの筆記者用の入力状況
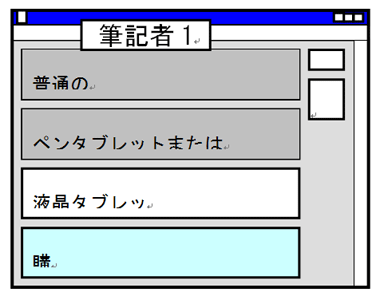
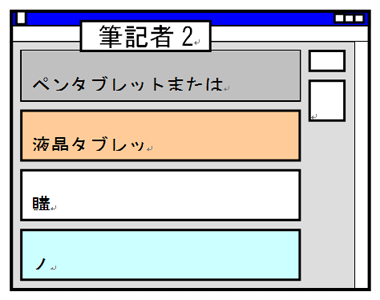
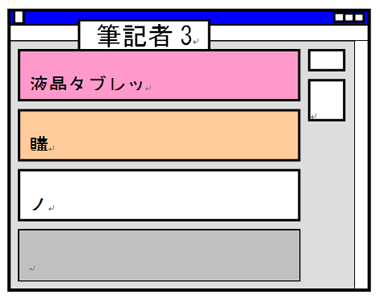
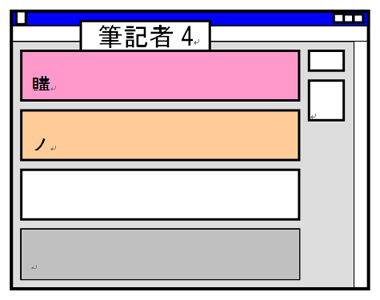
上の図は「普通の/ペンタブレットまたは/液晶タブレットだけを/購入して/ノートパソコンに/連結して」を筆記中の状態。話者は「ノ-ト」と発話しつつある。
筆記者1は「液晶タブレットだけを」の筆記をほぼ終えようとしている。「液晶タブレットだけを購入し」程度を筆記すべき文として記憶しているが、領域4の「購」を見ることで「‥‥だけを」まで書けばよいと判断できる。
筆記者2は「購入して」を筆記している。「購入して すでにノート」までを聞き取りつつ筆記しているが、「購入」を筆記した頃に領域4の「ノ」(「ノート」まで筆記が進んでいるであろう)を見て「購入して」まで筆記すればよいと判断できる。
筆記者3は、「ノート」と聞いて「ノ」をまさ筆記したところである。以降「ノートパソコンに連結して」を聞きつつ、筆記を続けていく。この時点では、領域4に表示すべきものがない(筆記者4はまだ何も筆記していない)ので、領域4はグレーアウトしている。
筆記者4は、領域1及び領域2を見つつ、話者の発話を聞いている。領域1で、2人前の筆記者が「購入して」あたりを筆記するであろうこと、領域2で1人前の筆記者が「ノート」から筆記を始めたことを知る。発話が「に連結」あたりまで進んだところで、筆記領域の幅と発話の区切りから「コンに」までは1人前が筆記し得、筆記者4自身は「連結」以降を筆記するものと決め、「連」以降を筆記して行く。筆記者3の領域4は、筆記者4が「連」の最初の一画を筆記し始めた瞬間、グレーから水色に変わる。
以上は、非常に短い間隔で筆記者が交代する例だが、この仕組み自体は、より長い間隔で交代する場合でも同様に利用し得る。
この例のように短い間隔で筆記者が交代していくと、筆記文を最小限の遅延で提示し得るが、要約は困難であるし、筆記に必要な人数もやや増加する。一方、より長い間隔――文章単位など――で交代するのであれば、高度な要約や校正を行うことも可能となる一方、発話から筆記文提示までのタイムラグは増加する。


