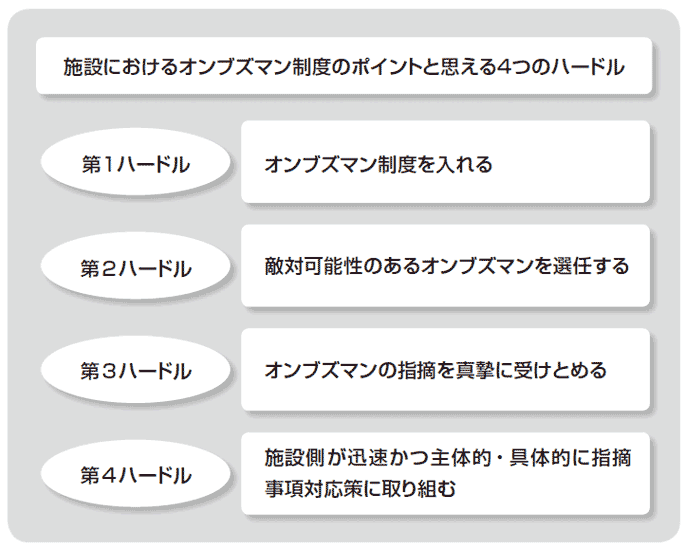第4章 施設内での虐待とその対策
1―現状~事例
施設内虐待は、この十数年、たびたび表沙汰にはなってきたが(例:白河育成園事件(廃園)、札幌育成園事件、鹿児島「みひかり園」事件、福岡「カリタスの家」事件、大阪「高井田苑」事件)、なかなか無くならない。
悲観的かも知れないが、世の中で「犯罪」が無くならないものと想定されて「刑法」や「刑罰」が用意されているのと同じように、障害者に対する「虐待」も無くならないものと想定して、対応策が考えられるべきである。
いわゆる「弱いものいじめ」は、障害の有無に関係なく、世の中から無くならない。加えて後述するように、施設における障害者に対する権利侵害の構造的原因と考えられる、集団的対応性、閉鎖性、密室性、支援者・利用者間の支配・服従的関係性、利益相反性(手厚い支援と過重労働)、マンネリ化といった要素については、それら全てを「ゼロ」にすることは不可能、と思われるのである。
障害者に対する虐待は是非とも根絶されるべきものであるが、人間の弱さゆえ、虐待の「芽」はどうしても残ってしまうように思う。
施設内虐待の具体例としては次のようなものが挙げられる。
①暴行・監禁等
知的障害のあるA1、A2、A3は入所施設で生活していたが、A1は職員の言うことを聞かないことを理由に、日常的に職員Xに顔を殴られていた。A2は日常的に職員Yから性的暴行を受けていた。A3はすぐにあばれるという理由で、外からカギのかかる部屋に日常的に入れられていた。
②薬漬け
自閉症の障害のあるBは入所施設で生活していたが、夜間に、なかなか眠らず、徘徊したり、落ち着きが無い、ということで、大量の精神安定剤を投与され続け、常時よだれを垂らして、ボーっとしていた。
③年金・工賃の奪取
知的障害のあるCは入所施設で生活していたが、Cの障害基礎年金は入所時に当然に施設に寄付されたことになっていた。また、Cが入所中に農作業をしたことによって得られた金銭は、当然に施設の収入になっていた。
④必要なケアの懈怠
知的障害のあるDは入所施設で生活していたが、一人で入浴中に溺死した。Dが入浴したことを知っていた職員はいたが、職員は誰も、少なくとも1時間以上の間、入浴中のDに起きた異変に気づかなかった。
⑤利用者間のトラブル放置
知的障害のあるEは入所施設で生活していたが、他の特定の利用者から繰り返し暴行を受け、負傷したことも何度もあった。しかし、職員らは多忙と直接目撃していないことを理由に、何の対応もしなかった。
⑥「入所施設に入れる」こと自体
知的障害のあるFは、自宅では面倒が見切れないということで、入所施設に入れられた。その結果、一生、居住の自由を奪われ、食事やレクリエーションなども大きく制限される人生となった。加害者は親族だと言われるが、そんな短絡的なものでもない。
⑦その他
利用者の頭に袋をかぶせて遊ぶ。日常的に蔑視的発言・幼児扱いをして、利用者の傷心に気づかない。度重なる自傷行為の繰り返しを放置する。
⑧施設内虐待の類型としては、次のような型が典型として挙げられる。
- 弱い者いじめ型
- からかい・遊び型(人権意識の低さ・信頼関係に関する勘違い・支援のマンネリ)
- 支援技術不足型(もてあまし・・・環境因子も大きい)
2―発見
①内部告発によって発覚
施設内虐待の多くは内部告発によって発覚する。
障害のある人の施設における虐待は、施設の持つ「閉鎖性」や福祉サービスの個別性の裏返しとしての「密室性」ゆえに、表面化しにくく、外部から察知しにくい。そしてそのことが、虐待状態が長くはびこる「温床」を作っている。
虐待事実を表に出すための最も有効な方法は、施設内部で起きていることを現実に見聞きしている施設職員の「内部告発」である。平成9年に発覚した白河育成園事件はその典型である。何人かの施設職員による「捨て身」の内部告発によって、多くの知的障害のある人が虐待施設から脱出し、同施設は消滅した。虐待に関する内部告発は確実に、虐待を受けている人の人権と生命を救う。
②内部告発者の保護が重要
しかし、施設内虐待の内部告発は、現状では、内部告発者の犠牲の上に成り立っている、と言っても過言ではない。内部告発者は、「裏切り者」として、職場で疎まれ、地域や業界でも疎まれ、人生を棒にふる危険にさらされることを、一定程度覚悟しなければならない状況にある。
また、内部告発に関しては一般に、「まず、内部での十分な議論や自浄努力を可能な限り尽くし、それでも改善されない場合に、最後の手段として選択されるべきである」、「内部での意見対立や派閥抗争を有利に展開させるための手段として不当に利用される場合が少なくない」といった考え方が根強い。
しかしながら、「虐待」が現に行われ続けているとき、組織内部の事情や力関係など「二の次」である。一刻も早く「虐待」の状態を解消させることが先決であり、議論の余地などない。現に「虐待」の状態が続いていて止まらない以上、その組織の自浄作用に期待することなどできない。被虐待者本人の救出のためには、「内部告発」という最も迅速かつ有効な選択が是非ともなされるべきであり、かつ、それを確保するために、内部告発者の社会的地位・名誉を最大限に保障する装置が是非とも用意される必要がある。
③公益通報保護法
平成16年6月公布・平成18年4月1日施行予定の公益通報者保護法は、社会における内部告発一般に関する法律である。そこでは、国民の生命・身体・財産など(公益)を守るための内部告発(通報)をした人については、その通報したことを理由にした解雇は無効とされ、不利益な扱いは禁止されることなどが定められている。他方、同法は、公益が侵害されていることの確実さの程度に応じて、通報すべき先(すなわち、内部告発しても保護される場合)を(公益違反を犯した当該組織、関係行政機関、その他有効な通報先、と言う形で)分けていることなど、「不当な内部告発」に対する牽制の規定も用意されており、現存組織を維持する利益と公益通報の意義とのバランスを考慮した構成になっている。
④「不当な内部告発」に関する制限規定は適用除外されるべき
施設における「虐待」の場合、告発対象は通常、現に見聞している事実であり、その人権侵害性は顕著かつ重大であるので、組織維持利益とのバランスを考えるべき余地は(告発内容が虚偽である場合を除き)極めて少ない。したがって、「不当な内部告発」に関する制限規定は適用除外されるべきであるし、内部告発者の保護に関しても、解雇無効、抽象的な不利益扱い禁止では十分でない。内部告発に因果関係のある形での不利益扱い(解雇はその典型であるが、不当な不作為も含めるべき)に対しては、「虐待を助長するもの」と位置づけて、罰則規定を設けて対応すべきである。そのくらいの強い規定がないと、内部告発は促進されず、虐待状態を止めることはできない。
3―家族の思い
施設内虐待については、もちろん、虐待されている障害者本人が声を上げるのが一番良いが、本人がエンパワーされていない、生活支援を失う危険に対する恐怖を無視できない、といった理由から現実には難しい。
障害者本人の家族についてもまったく同様のことが言える。本人が悪いと言えば、丸くおさまる、お世話になっているのだから、たいていのことはがまんしなくては、本人を人質に取られている、文句を言ったら、陰で仕返しをされる恐れがあるし、出ていけと言われたら、行くところがない、といった思い渦巻く中で、施設内虐待を告発することは事実上容易でない。
4―職員の事情
不適切な援助には段階がある
- ① 適切な支援か(技術・意識の不十分もふくめ)
- ② 違法行為(権利侵害)ではないか(過失を含め)
- ③ 虐待ではないか(無意識のものも含め)
- ④ 故意による犯罪ではないか。
施設内虐待には「構造的原因」がある
- ①利益相反(援助を厚くするほど、負担は重くなる)
近くで支援し、本人の情報をよく把握しているだけに、本人の意思に沿って動けば動くほど、支援者にとっては苦しい状況が生じていく、という関係性が生じやすい。 - ②マンネリ(こんなもので十分という意識)
とくに、「施設利用者」のプライバシーに対する軽視や、「障害者」に対する名誉毀損についての「不感症」ともいうべき対応・行動において顕著にみられる場合がある。また、介助や日常的な接し方において、悪しき専門性・「慣れ」から来る、ぞんざいな対応による人権無視・軽視、というべき場面も見られる。小さな権利侵害の「積み重なり」から「虐待」にエスカレートし、そして日常的なものとして、はびこる - ③上下関係性(世話してやってる、教えてやってる)
世話をしてやっている、世話をしてもらっている、という意識・関係性があると、言いたいことが言えないし、反抗できない。 - ④密室性(2人だけの間のこと)・閉鎖性(外に出ない、外からわからない)
誰も見ていない場面・関係性、そとから見ることが難しい環境においては、犯罪的問題が生じやすいし、発覚しにくい。 - ⑤集団画一性
「多数の利用者の利益保障」、「平等」という名のもとに、個人の尊厳が制限され(軽視され、蔑ろにされ)、しかもそれが不当に正当化されやすい。個別性に応じた援助の原則が実現されていないことの裏返しとして、大規模施設の問題性がある。 - ⑥悪意よりも、むしろ構造的な原因があるゆえに、根絶されないのではないか。逆に言えば、構造的な原因を小さくすることがとても重要なのではないか。
施設内虐待根絶にはクリアされるべき要因がある
- ① 環境ないし物理的要因(制度の問題に帰着することもある)の排除
- ② 援助技術・専門性の獲得
- ③ 適切な援助を確保するための標準、しくみ、手続、システムの設定
5―調査1:アセスメント・事実確認調査
アセスメント・事実確認が生命線
① アセスメント・事実確認が生命線である。この部分がきちんと正確になされないと、対応が遅れ、あるいは対応を誤ることになる。時間・場所・行為・行為主体・理由などについて、可能な限り詳しくおさえる必要がある。一件無関係に見える事柄もすべてメモしておくべきである。とくに初期段階では、情報は多ければ多いほどありがたい。
重要なのは聞きとり作業
② アセスメント・事実確認の最重要部分は、障害のある本人・家族・施設・第三者からの聞き取り作業である。
障害のある本人の話は、じっくりと時間をかけて聞く必要がある。コミュニケーションが難しい場合でも、はしょってはいけない。言語以外の表現で把握しうるものもある。家族からの聞き取りは重要だが、近親者ゆえの思い込み、過去の被害体験などに基づく過度に感情的な見方、本人の支援者的な立場からくる利益相反性には注意する必要がある。正確な事実把握の妨げになる恐れがあるからである。
施設側からの聞き取り作業は工夫を要する。むやみに敵対的・攻撃的に行っても実のある成果は期待できないし、恫喝して白状させても、証拠価値に問題が生じる。虐待根絶に向けた取り組みとして協調できる接点を見つけて、聞き取り作業を進めることを目指したい。システム・制度的には、施設内虐待発生の合理的疑いが発生した場合には、施設に協力義務を課すべきである。
証人たりうるような第三者からの聞き取りが可能であれば、確実に有効に証拠化することを念頭に置いて行うべきである。
いずれの聞き取り作業も、虐待発覚から可能な限り早い段階でなされる必要がある。記憶は消費期限の短い生物のようなもので、時間の経過によって、どんどん消えていき、どんどんその価値が下がっていく。
収集可能な客観的な情報・資料
③ 収集可能な客観的な情報・資料は、時間・場所・行為・行為主体・理由などについて前記の聞き取り作業の内容・結果を補強・補充・根拠づけるために、可能な限りたくさん収集する必要がある。
6―調査2:強制力ある情報収集(施設が非協力的な場合)
立ち入り調査
施設内虐待発生の合理的な疑いが生じ、施設側が非協力的な場合、まずは福祉行政、それでもだめなら警察、といった権力を背景とした立入調査を認める必要がある。
シェルター
① 障害者に対する虐待事実あるいはその強い可能性が認識されたときには、権限や手段を慎重に吟味・選択している余裕などない。火事場からの人命救済のようなものである。一刻も早く、虐待状態を解消させるために、対応しなければいけない。虐待は刻々と繰り返されるものであり、虐待を受けている本人の傷は、肉体的にも精神的にも、毎日どんどん深くなっていくからである。
② 虐待状態を解消させるために必要不可欠なものは、虐待から救出した後の逃げ込み場(シェルター)である。それは、虐待状態から脱出させた後の、とりあえずの生活の場である。
虐待者とその仲間は、虐待事実を隠匿し否定しようとして、必死に「もみ消し」に入る。虐待がはびこる「ブラックボックス」への連れ戻しを図る。そのとき、虐待者とその仲間の側の「錦の御旗」は、とにもかくにも、「施設以外には(本人の)生活支援者となる人がいないこと」と「(本人のための)衣食住の確保、生存の保障」である。これに対抗するためには、救済活動側に、「衣食住の確保、生存の保障」プラス・アルファの「場」が必要不可欠なのである。
現実には、この「シェルター」がないために身動きがとれず、虐待状態から救出できないまま、指をくわえたまま、事実上「見て見ぬふり」になってしまっているケースが非常に多いはずである。
この「シェルター」があれば、虐待からの救出事例が格段に増える。そして、虐待事実が表沙汰になることが格段に増え、その反射的な効果として、虐待事例は確実に減る。
③ この「シェルター」は、虐待者とその仲間から、被虐対者本人を十分に守れる「場」でなければならない。物理的に容易に見つけられないような場所であることとともに、虐待による傷が癒され、虐待者とその仲間による心理的な「呪縛」から解放されることに向けられた精神的なケアが必要である。そのような地理的な環境と人的資源が必要不可欠である。
④ このような「シェルター」は、市場経済・競争原理の中で作られるとは考えにくい。また、現在の日本の社会状況の中では(稀なこととは言え)、誰にでも生じる可能性のある事柄と言えるので、ある程度公的な形で、運営資金と適切な人材が確保される必要がある。
⑤ 最後に念のため付言すると、当然ながら、「シェルター」はあくまで、虐待状態から逃がれるための、とりあえずの生活の場である。ずっとそこで生活するというのは異常である。傷を癒し、社会での普通の生活を準備し、実現する方向性をもって、運営される必要がある(そもそも、障害のある人のための入所施設は、障害のある人が現実社会の中で様々な形で受ける虐待から逃れるための「シェルター」としての役割こそ、期待されるものなのではないか)。
7―緊急度の判断
誰が、どのような基準で、虐待の発生ないし発生の合理的危険の存在を認定するのか、という点は、実際の虐待防止活動ではもっとも神経を使うところであろう。
判断主体
直接的に情報収集に集中的に関わる役割の人(たち)とは独立の、必要な有効な目・耳・感性をもち、緊急に集まって検討のできる機関(複数の人の集まり)が必要であろう。人数が多すぎると、船頭多くして舟山を登る。また、実際に虐待からの救出活動をイメージできないメンバーでは机上の空論に拘泥する。
判断基準
虐待発生の場合、判断責任を心配して逡巡していると、取り返しのつかない被害が生じるので、合理的な危険が認定されたならば、すなわち、判断を任されている機関が何らかの根拠に基づいて50%を超える確からしさで虐待発生ないしその危険を認定したら具体的に動く、という原則・基準を明確にすべきである。とくに「分離」・シェルターへの避難を要する可能性のあるケースではそうである。
8―第三者機関の有効性
施設を見守るオンブズマンなどの第三者の存在によって施設内虐待が発覚し、一定の対応がなされる場合もないではないが、1か月に1度程度の定期訪問程度では、施設内部で隠蔽される虐待を発見することはやはり難しい。そして、対応場面ではしばしば「権限」の問題が事実上立ちはだかる(もっとも、虐待が本当に発生しているならば、緊急避難的対応は、権限の問題とは関係なく可能であり、勇気とパワーの有無の問題であろう)。
しかしそれでも、オンブズマンのような第三者機関を設置し、定期的に訪問し、施設の雰囲気・ムード・空気・様子を第三者として把握し、感じ取る「形」(継続的な観察機関、常設相談窓口)を作っておくことは無意味ではない。施設が気づかずに見過ごしている、あるいはマンネリ化し不感症になっている類の虐待を発見できる可能性があるからである。
オンブズマンを虐待防止のオールマイティのように考えるのはあまりにも短絡的だが、「無意味である」として捨象するのもまた、かなり短絡的であろう。
9―行政による指導
虐待からの救出
□虐待からの救出には、
- ① 緊急の動きが必要である。
- ② いろいろな機関が連携した、多面的な動きが必要である。
- ③ 強引な動きが必要な場面がある。
- ④ 短期集中的に大量の動きを要する場面がある。
救出後のケア
□虐待状態から救出した後のことも重要である。救出した後の法的なガードが確保されないと、逆戻りや悪化をおそれて、救出活動にもブレーキがかかってしまう。救出した後の本人の物理的ケア及び精神的ケアについて有効な資源を持つことが必要である。また、とくに性的虐待の場合には、プライバシーとトラウマに非常に気を使う。救出後の本人と家族関係に対する配慮も必要になることも多い。虐待から救出された本人は、その後のフォローを確保すれば、劇的に変わることが多い。それが救出作業者にとっては何よりの報酬である。
福祉行政の「公的責任」
□障害者虐待防止のためには、以上のような「必要」の全てを実現する方向で作用する、強い力が必要であり、そこでは現実的には、権力・強制力をもつ福祉行政の「指導」の果たすべき役割が大きい。そしてその背景・根拠としては福祉に関する「公的責任」がある。
10―施設経営者・職員への支援
施設における身体拘束の実態
京都府において、「身体拘束の実態や廃止に向けての取り組み状況の把握と身体拘束廃止に向けた啓発、支援を行うこと」を目的として、平成20年、障害者支援施設、入所系障害福祉サービス事業所等、218箇所を対象に調査が行われ、208箇所(有効回収率96.4%)からの回答があった。
調査の結果、調査基準日である平成18年4月1日以降において、身体拘束を行った例のある対象施設は69施設(調査有効回収施設の33.2%)であり、施設種別内訳では、知的障害者施設において85%、障害児施設において88.9%という実態が明らかとなった。
身体拘束の内容は、「Y字型拘束帯等の使用」「ベット柵の使用」「居室の施錠」が多く、身体拘束廃止の困難な理由として、「結果として有効な方策がなく、廃止できない事例が残る」(49施設、71%)、「介護を担当する職員が少ない」(17施設、24.6%)であった。
福祉施設利用者に対する身体拘束について、厚生労働省は、「緊急やむをえない理由により身体拘束を行う場合には、『切迫性』『非代替性』『一時性』の用件について検討し、説明・記録等適切に対応するよう」指導しているが、京都府の調査からは、現状として利用者虐待へとつながる可能性のある利用者に対する身体拘束が依然として多くの施設で行われている実態が明らかにされている。
特に知的障害者入所施設において、自分自身の顔面を叩くなどの自傷行為や他者を叩く、蹴るなどの他傷行為など、いわゆる行動障害を伴う利用者に対する隔離や身体拘束、虐待事例が多いことが推測される。
ここでは、平成20年1月に新聞報道で発覚した知的障害者入所更生施設T施設における行動障害を伴う利用者に対する職員の虐待事例を通して、施設における利用者虐待を誘発する要因を明らかにするとともに、虐待防止に向けた取り組みを提案したい。
また、利用者に対する隔離、拘束に対する対応策についても検討したい。
施設における利用者虐待を誘発する要因
新聞報道によると、T施設では平成11年の開所以来、施設幹部ら中心的な職員が虐待行為を行い、「他の利用者や職員に乱暴したり、指示に従わなかったりした障害者を、拳や平手でたたくほか、けることもあった。このほか作業を怠ると胸ぐらをつかんで怒鳴る、すれ違いさま気晴らし的に『邪魔』と頭をたたくなど、施設内では威圧的な対応が日常的で、幹部職員らは『言うことを聞かないのは、なめられているからだ』と力で従わせる必要性を説いていた」との虐待の実態が明らかにされている。
利用者の個別的ニーズを基本として、その実現を支援し、安全・安心・快適な暮らしを支援すべき障害者施設において、このような職員による利用者虐待が長年にわたって発覚することなく続けられていた事実から、以下の要因が考えられる。
要因の考察とともに、その解決策について検討したい。
① 法人・施設としての人権意識に基づく支援理念の必要性
「罰として角材を足に挟んで正座させるなど、開所直後から暴力的な対応は始まっていた」と職員が話したように、T施設では開所時から幹部職員ら中心的な職員が虐待行為を行っている。
即ち、多くの職員にとっては、幹部職員ら中心的な職員の利用者に対する虐待を伴う対応が、いわゆる「利用者支援」の基準になっていた実態がある。
施設を運営する上で重要なことは、その施設を運営する法人が、法人としての明確な「理念」を掲げ、各施設はその理念に基づいた「利用者支援基本方針」「倫理綱領」を示し、その「理念」と「支援基本方針」「倫理綱領」を規範として、職員が利用者支援を行うことが求められる。
T施設においては、利用者支援について、組織的な規範に基づくことなく、個々の職員の価値判断に任せ、結果として幹部職員の利用者に対する対応が規範となっていたといえる。
② 人間理解・障害特性の理解とそれに基づく対人援助専門職としての職員研修・養成に対する組織的取り組み、利用者を中心とした施設外関係機関との連携
T施設の職員たちは、「自分も力に頼っていた。正しい支援方法が分からなかった」と証言している。
新聞記事から虐待の対象となった利用者の多くが重度の知的障害を伴う自閉性障害のある利用者であることが推測される。
施設入所以前から様々な行動障害があり、入所による新しい環境や集団生活など、大きな生活の変化の中で混乱し、更なる様々な行動障害を誘発したのであろうことは十分理解できる。
利用者の示すいわゆる「不適切な行動」は、相手の言っている言葉などの理解の困難性や自分の思いを表現できないというコミュニケーションの障害、社会のルールやマナーなどの理解が困難な対人関係・社会性の障害、先が読めない、見通しが持ち難いなどの想像力の障害など、自閉性障害の障害特性が要因となり、職員の障害特性の理解不足による不適切な対応や障害特性に対する配慮のない環境などとの相互作用によって、行動障害が誘発され、強化されるという循環がある。
T施設の場合、職員の利用者に対する理解不足と虐待という不適切な対応の相互作用の中で、ますます利用者の「不適切な行動」が強化されていったのであろうと推測される。
そして、利用者の示す「不適切な行動」の強化が、職員の利用者に対する虐待行為をますますエスカレートさせるという悪の循環に陥ってしまったのだと思う。
知的障害者施設において、虐待を誘発する要因の一つに、このような職員の利用者の障害特性に対する理解不足がある。
このような虐待防止に対する対策として、利用者の障害特性の理解に基づく支援についての計画的継続的な職員研修の実施と困難事例についてのスーパーヴァイズ体制が確立されていることが重要である。
また内部的にスーパーバイザーがいない場合は、施設外部の専門的な相談支援機関や医療機関などとの連携によるケーススタディをするなど、施設外部の専門機関との連携が有効な方法としてある。
T施設の場合、困難事例についての支援について、外部専門機関との連携もなく、閉塞的な状況の中で、虐待行為が常態化し、その発覚が遅れる結果となったと思われる。
障害者自立支援法の施行により、施設入所施設の利用対象者が障害程度区分4以上となったことで重い障害のある人たちの利用が中心となるとともに、今後ますます行動障害や認知症・アルツハイマー、重複障害を伴う重度の知的障害のある人たちの入所施設利用の増加が予測される中で、スーパーヴィジョン・研修体制を構築することが、虐待を防止し、より専門的な質の高い支援サービスの提供へと繋がっていくと思われる。
③ 利用者虐待が発覚し難い構造的問題とその解決に向けた虐待防止ネットワークなどの創設
T施設における虐待について、事件が発覚する前年には、T施設を訪れていた大阪府職員3名が利用者を叩いている職員を目撃しているという事実があり、発覚5年前に、利用者家族も虐待の実態に気付き施設所管の市に通報している。
また、実習生から報告を受けた大学が人権配慮を施設に申し入れたことも明らかになっている。
特に、家族からの通報を受けていた市や虐待の現場を目撃した府職員が、その後何らかの具体的対応を起こさなかったことは、今後の施設内虐待防止対策を検討する上で重要である。
施設を管理・監督すべき行政機関・職員が、結果として虐待を黙認した背景には、事件発覚に伴う行政責任を問われることへの恐れであったのではないかと推測される。
結局、新聞による虐待事件の報道という社会的に事件が明らかにされない限り、事件が隠蔽され、虐待が続けられていたことになる。
また大阪府の場合、多くの入所施設利用待機者が存在し、行動障害を伴う重い知的障害のある利用希望待機者の施設利用が極めて困難な状況にあることが、事件発覚が遅れた原因としてある。
特に家族など保護者にとっては、本人の示す激しい行動障害と向き合い、地域での孤立無援の生活を続けてきたという経験があり、何とか本人の施設入所によって、普通の暮らしができるようになったとの思いが強くある。
もちろん本人が一番苦しい思いをしていたのだが、保護者としては、施設での虐待の事実を知っていても、施設に苦情の申し立てをしたことで、施設からの退所を強要されると大変だという思いが強く働く。
施設から本人が帰宅されたときに、身体の傷や本人の変化に最初に気付くのは保護者である。
しかし、早期の虐待事実の確認と対応ができる保護者が、退所を強要された場合、他の入所施設での受け入れが困難という状況の中で、一歩踏み込んだ行動ができないというのが、虐待の早期発見、早期解決を阻んでいる構造的な問題としてある。
この問題を解決するためには、地域の身近にある相談支援機関の活用や施設への立ち入り調査など、権限のある第三者機関などを含めた虐待防止のためのネットワークの創造が求められるとともに、行動障害を伴う人たちに対する行動改善や行動障害を誘発させないより専門的な支援が提供できる地域生活支援サービス事業所の支援力強化も重要である。
④ 利用者に対する身体拘束・隔離に対する仕組みと第三者によるチェックシステムの構築
平成18年、日本知的障害者福祉協会生活支援部会更生施設分科会が実施した「入所更生施設の利用者と支援に関する実態調査報告」における自由記述の中で、認知症・アルツハイマーを伴う利用者支援の課題について、「拘束の問題などを含めた人権を意識した支援」「利用者の安全と施錠について、常に課題に感じている」ということが上げられている。
また、強度行動障害を伴う利用者支援についても、「行動制限と人権侵害が紙一重である」との記述も見られる。
上記記述や京都府の調査結果から見られる身体拘束の実態から、施設現場においては、身体拘束についてかなり苦悩している実態が浮かび上がってくる。
前述したように身体拘束について、厚生労働省は、「緊急やむを得ない理由により身体拘束を行う場合には、『切迫性』『非代替性』『一時性』の元で適正な手続き(本人・家族の同意など)と記録の必要性」を条件としているが、現実的にはその明確な基準がなく、実際的にはそれぞれの施設の対応に委ねられているのが実態である。
身体拘束についての明確な基準や公的な第三者機関におけるチェック機能がないという状況下では、人権侵害を誘発する可能性が極めて高いと言わざるを得ない。
虐待防止の取り組みの一つとして、施設内における利用者に対する身体拘束・隔離についての法的な枠組みが必要であると思うが、オーストラリアのビクトリア州における取り組みが参考になると思うので、以下紹介する。
オーストラリアのビクトリア州で、2007年7月に施行された「Disability Act 2006」において、障害者に対する薬物も含めた拘束および隔離を伴う法的な枠組みが明確にされた。
この法律では、州政府のヒューマンサービス省(DHS)に、各種サービス、特に拘束的な介入の対象となる人たちの生活の質と福祉モニタリングをする上級プラクティショナー(Office of Senior Practitioner:OSP)を設置し、事業者が拘束的介入を実施する場合、事前にその実施責任者であるAuthorised Program Officer(APO)を任命して、DHSに登録しなければならないことになっている。
APOは、拘束的介入を実施する前に行動支援計画書を作成しなければならず、その計画書には、具体的な以下の項目の記載が義務付けられている。
- 拘束的介入が用いられるべき状況
- 具体的な方法
- 1回あたりの使用時間
- 選定された方法がクライアント本人にもたらすべき利点
- 選定された方法がクライアントにとって最も拘束度合いの低いものであることの具体的証明
また、作成にあたっては、本人を含む関係者とのコンサルテーションが重要視されている。
第三者機関による拘束的介入に対するチェック体制については、独立した第三者(Independent Person:IP)が行動支援計画書の作成にあたって、本人にその計画書の意図するところを説明し、事業者による独断的な支援計画の作成を予防し、計画書の内容の再審査を裁判所に類似した機関VCAT(Victorian Civil and Administration Tribunal)に求めることができることを本人に説明することが義務付けられている。
日本における利用者に対する身体拘束的介入に対する制度構築は、今後の大きな課題としてあるが、行動支援計画書作成時における上記記述項目は、日常的な支援で活用できる内容である。
また作成時に地域の相談支援事業者を含めたコンサルテーションの実施を行うことで、適切な支援が行える仕組みづくりは可能となると思われる。
⑤ 特に入所施設におけるQOLの課題
施設における虐待防止を考える上で、マンパワーを含めた環境の問題は重要である。
施設における住環境や支援については、「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成2年12月19日)に規定されており、入所更生施設では、以下の内容となっている。
居室:1室の定員は4人を標準とすること。入所者1人当たりの床面積は、収納設備を除き、3.3平方メートル以上であること。
健康管理等:入所者については、1週間に2回以上入浴させ、又は清拭を行わなければならない。
以上は最低基準であるが、実態としては、施設整備補助金額や施設に支払われる報酬単価や職員の配置基準などの枠組みの中で、実際的には上記最低基準が最高基準になっているという現実がある。
このような生活環境自体が人権上の課題であると言わざるを得ない。
特に、自閉性障害を伴う利用者の人たちは、雑多な情報の中から必要な情報を選択することが苦手な上、聴覚的刺激が苦手という障害特性があることから、このような集団的な生活は非常に苦痛の伴うものである。
極端な言い方をすれば、自閉性障害の利用者をこのような環境での生活を強いること自体が、「虐待」といえるのではないだろうか。
また、そのような環境要因が行動障害誘発の要因になっていることが多い。
上記した「入所更生施設の利用者と支援に関する実態調査報告」においても、強度行動障害を伴う利用者の支援を行っている施設の約4割から、環境・設備について、「個別に対応できる環境(個室、療育室)・専用スペース(ユニット)の確保」を課題として上げている。
特に実態調査回答施設の34%の施設において、日常生活単位が1グループ6人~10人での暮らし(ユニットケア)の導入を望んでいる。
施設経営者・職員が一体となって、個室をベースとした6人単位のユニットでの暮らしの実現や毎日の入浴、私物で飾られた部屋、いつも匂いのない清潔な住環境の維持、個々の利用者のニーズをベースとした個別的な日課や活動の提供などという生活の質を少しでも良くしていこうという実践を積み上げることは、結果として、虐待防止に向けた職員の意識改革につながると思う。
逆に考えると、社会におけるノーマルな暮らしからかけ離れた質の低い暮らしを利用者に強いていれば、無意識のうちに「障害のある人たちの暮らしはこの程度でいいんだ」という思いが定着し、そのことが虐待を誘発させる環境を生み出していると言うことができる。
以上、施設内虐待を生み出す構造的な問題の考察を通して、具体的な対策を検討した。
施設内虐待防止に向けては、経営者、職員の一体となった意識改革と取り組みと、それを支える法的制度的仕組み、地域的なネットワークの構築が重要な課題として考えられる。
11―援助について
1)個別性に応じた援助の原則
「援助を要する人」に対する「援助」は、「個別性」に応じたもの、「その人らしさ」にじたもの、でなくてはならない(個別性に応じた援助の原則)。それが、その人を「この社会で幸福を追求していく人」(憲法12,13条)として尊重することであり、そのような「尊重」なくして、「援助」などありえないからである。
2)援助の大前提
そして「個別性に応じた援助」を実行するためには、その前提として何よりもまず、(A)「その人の特徴・特有のニーズを把握し、かつどのような援助が適切かつ有効なのかを知ること」が絶対的に必要である。このAが「援助」の大前提である。
3)コミュニケーションの困難な人に関する援助の「第1段階」
コミュニケーションが困難な人に関するAについては特に、「積極的・個別的な関わり」が必要である。本人の主張や本人との会話によってAを獲得することが困難だからである。そして、この「積極的・個別的な関わり」の場面で、援助者は、資質、意識、最低限の知識を問われる。
この「積極的・個別的な関わり」によってAを獲得するのが、コミュニケーションの困難な人に関する援助の「第1段階」である。
※ 大規模施設でも、「積極的・個別的な関わり」について何とか努力すれば、このAの獲得までは期待できる可能性がある。無論、小規模の方がAは獲得されやすい。家庭はその最たる例である。
※ Aの獲得さえできないとなると、個別性を重視せず全体としての公正・平等な処遇を重視する刑務所と同レベルになってしまう。あるいは要援助性の部分だけに特化して身体的安全を旨とする病院と同質になってしまう。
4)コミュニケーションの困難な人に関する援助の「第2段階」
Aが獲得された上で初めて、「個別性に応じた援助」が物理的・現実的・具体的に可能なのか否か、という問題が出てくる。
試行錯誤の中で、その可否を判断するのが「第2段階」である。
※ 大規模施設ではそもそもア・プリオリに「個別性に応じた援助」が難しいのではないか、利用者の数、職員の数、職員の質、施設の物理的構造、などの要素を考慮したとき、現実的に不可能なのではないか、という問題は、この場面で問われる。
「そもそも大規模施設では、個別性に応じた援助の実行は構造的に不可能である」と断ずるのが「施設解体論」である。
5)コミュニケーションの困難な人に関する援助の「第3段階」
物理的・現実的・具体的に「個別性に応じた援助」が不可能ならば、それが可能な環境に適切につなげなければいけない。
これが「第3段階」である。
※ 「適切につなげない」あるいは「つなげるところを用意しない」ということは、「援助の放棄」、「ネグレクト」、「放置」であり、特にコミュニケーションが困難な人に対しては、一種の「虐待」であり、「人権侵害」である。
※ 現存の大規模施設の存在意義は、「何とか努力してAを獲得し、次の個別性に応じた援助が可能な環境に適切につなげる」ということであろう。
逆に言えば、Aの獲得さえなされれば、もはや物理的・現実的・具体的に個別性に応じた援助が不可能な大規模施設は不要なのである。
※ 現実的には、生育環境の問題性のために、Aの獲得がなされていない要援助者は存在するので、敢えてAの獲得期間・獲得過程を設ける現実的必要性があることは少なくない。
しかし、そのAの獲得期間・獲得過程は大規模施設である必然性はない。むしろ小規模の方がAを獲得しやすいのは当然であろう。ピア・カウンセリングのようなものの有効性を前提とすれば、一定の集団的な関わりはありうるだろうが。
※ 大規模施設の問題性は、
- ① かろうじてAの意義はあるとしても、それが実行されているところは少なく、
- ② また、次の個別性に応じた援助が可能な環境に適切につなげる、そのための最大限の努力をする、ということをできるところは更に少ない、
- ③ むしろ、まるで大規模施設でも個別性に応じた援助ができるような顔をして抱え込み、物理的・現実的・具体的に個別性に応じた援助が可能な環境に適切につなげない、「援助の放棄」、「ネグレクト」、「放置」、「虐待」、「人権侵害」の温床になっているところが大多数である、
というところにある。
12―オンブズマン
1 「オンブズマン」とは元来、権力と広い裁量権を持つ「行政」による「人権侵害」から市民をまもるために設置された、市民の声を代弁する機関のことです。「代弁」の中身は、市民の声を受け止め、調査して、行政に対し改善提言することです。このような「行政」に対する本来的なオンブズマンにならって、事実上権力と広い裁量権を持つ者が存在するさまざまな分野で、その権力主体による人権侵害から個人をまもるために、その声を代弁する機関として、特定分野のオンブズマンが設置されるようになりました。マスコミに対するオンブズマンや消費者オンブズマンなどがその典型です。
2 「福祉オンブズマン」は、その特定分野のオンブズマンの一種です。すなわち、福祉サービス提供者と利用者の間では一般に、サービス提供者側が権力的な立場に立ちやすく、福祉サービスの提供及びその内容について、サービス提供者側が事実上広い裁量権を持っている場合が多いので、そのようなサービス提供者による権力的な横暴や裁量権の濫用・逸脱を防ぎ、利用者側の権利を守ろうということで設置されるのが、福祉オンブズマンです。
3 現在、日本では、次に掲げるように、いろいろな形態の福祉オンブズマン制度があります。オンブズマンの必要性や効果に関する考え方の違いが、このようなバラエティを生んでいるものと考えられます。それぞれメリット・デメリットがあるので、多数のオンブズマン制度が並列的に存在し、障害者・高齢者側が選択できるのが望ましい状態だと思います。
1)行政主導型
福祉サービスに関する根本的な責任主体である行政が、福祉サービス全般にわたり市民の声を受け付けるために設置するオンブズマンの形態があります。例えば東京都中野区、板橋区、大田区、世田谷区、三鷹市、多摩市、神奈川県横浜市などで、この形態が設置されています。
直接的に行政に声が届き、福祉サービスの提供責任の根本に迫れる可能性がある、という意味では、非常に期待できます。他方、守備範囲が非常に広いということもあり、福祉サービス利用者の声を受け止めるうえでの「フットワーク」に難があり、積極的に苦情を申し立てて来れる人だけが恩恵を受けうるという嫌いがあると思います。
2)単独施設嘱託型
福祉施設の責任者が第三者に嘱託して、同施設のサービスについて、施設利用者の声を代弁してもらう制度です。東京都の多摩療護園や秋田県の内潟療護園などが発祥であり、全国各地に多くの実践例があります。
施設はどうしても閉鎖的・密室的になりやすいので、第三者を入れて利用者の声を受け止める必要性の高い場面と言えます。そして、施設の責任者自らが嘱託したオンブズマンからの提言であれば軽視されにくいだろう、と期待されます。ただ、施設の責任者の人権意識が低いと、オンブズマンシステムが形骸化してしまう危険性があります。
3)地域ネットワーク型
これは、上述のような個別施設のオンブズマンの危険を念頭に置いて、地域的に近くにある複数の施設がネットワークを作り、そのネットワークに加盟している各施設に、利用者の声を受け止めて対応する第三者を定期的に施設に派遣し、そこで上がってきた問題を、上記のネットワークと協働して解決して行こうとする形態です。「~ネット」という愛称のもとに、全国的に広がってきています(青森、埼玉、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、徳島、大分など)。
この形態においては、上記2)のメリットのほかに、ネットワークに加盟している各施設が当事者主体などの理念を共有し、情報交換して、施設利用者の権利擁護に努めるとともに、相互チェックする、といったメリットがあります。ただ、ここでも、ネットワークの人権意識が低下していくと、メリットが生きなくなってしまいます。
4)市民活動型
福祉サービスの提供者側と特に関係性のない市民が、人権意識のもとに集まって、純然たる第三者として、福祉サービスをチェックするシステムです。えひめオンブズネット、埼玉市民オンブズネットなどがその例です。
福祉サービス提供者との関係で、立場の「独立性」が明確なので、市民としての一般的な人権意識を基盤とした、強い問題提起・糾弾が期待できます。ただ、対象となる福祉サービスに関する具体的な情報、利用者の具体的な状況に関する情報を把握しにくい場合があり、そのような場合には現実的に有効な活動をしにくい面があります。
5)当事者活動型
障害のある当事者が、福祉サービスを受ける立場の同胞として、福祉サービス利用者の声を代弁していくシステムです。精神障害者の分野では東京の「こらーる・たいとう」のメンバーが、知的障害者の分野では「ピープル・ファースト」のメンバーが、この活動をしている場面があります。
福祉サービス利用者側に立った活動としては理想的な形態です。ただ、その活動について適切な支援が必要な場合が多く、また、この形態を受け入れる福祉サービス提供者側の人権意識の高さが前提になります。
6)その他類似制度
以上のような福祉オンブズマンの制度・システムと類似した、あるいは、運用によっては福祉オンブズマンと同様の効果をある程度期待できるものとして、第三者委員(社会福祉法82条)の制度があります。
この第三者委員は、原則的には、サービス提供者と利用者間の関係調整・調停者的な役割を果たすに止まるものと位置づけられていますが、全ての社会福祉事業者に設置することが求められている点は注目に値しますし、第三者委員が施設を定期的に訪問する、第三者委員に調査権限・提言権限を認めるなどの積極的運営により、福祉オンブズマン類似の効果を期待できます。