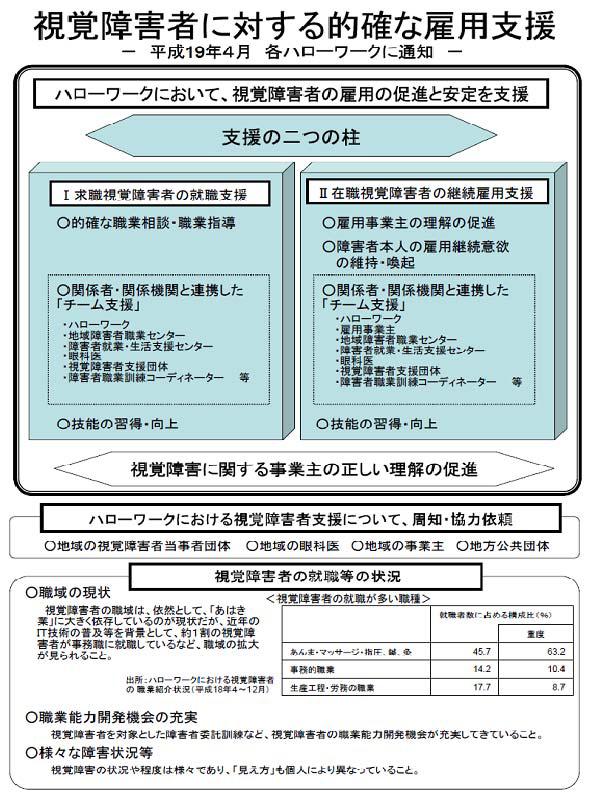参考
≪資料:≫
人事院通知全文
職 職- 35
人研調-115
平成19年1月29日
各府省等人事担当課長 殿
人事院職員福祉局職員福祉課長
人事院人材局研修調整課長
障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて(通知)
標記について、病気休暇(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律【以下「勤務時間法」という】第18条)の運用及び研修(人事院規則10-3【職員の研修】)の運用に当たっては、下記の事項に留意して取り扱ってください。
1 病気休暇の運用について
職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日 職職-328)では、勤務時間法第18条(病気休暇)の「療養する」場合には、「負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする」と定めている。すなわち、社会復帰のためのリハビリテーションであってもそれが医療行為として行われるものであれば、病気休暇の対象となり得るものであること。なお、負傷又は疾病が治る見込みがない場合であっても、医療行為として行われる限り同様であること。
2 研修の運用について
負傷又は疾病のため障害を有することとなった職員が病気休暇の期間の満了により再び勤務することとなった場合又は病気休職から復職した場合において、当該職員に現在就いている官職又は将来就くことが予想される官職の職務と責任の遂行に必要な知識、技能等を修得させ、その他その遂行に必要な当該職員の能力、資質等を向上させることを目的として実施される、点字訓練、音声ソフトを用いたパソコン操作の訓練その他これらに準ずるものは、人事院規則10ー3(職員の研修)の研修に含まれるものであること。
≪参考≫
中途視覚障害者の職場復帰に関する研究会報告
平成9年3月
中途視覚障害者の職場復帰に関する研究会
座長 坂巻 煕 淑徳大学社会学部教授
小松 美智子 東京女子医科大学病院医療社会福祉室課長補佐
篠島 永一 日本盲人職能開発センター次長
菅原 廣司 国立職業リハビリテーションセンター指導員
中村 哲夫 東京都失明者更生館指導訓練課長
松為 信雄 日本障害者雇用促進協会障害者職業総合センター主任研究員
目次
Ⅰ 中途視覚障害者の状況
1 中途視覚障害者の状況
2 中途視覚障害がもたらす影響
3 中途視覚障害者の社会・職場復帰
4 中途視覚障害者の職場復帰のプロセス
Ⅱ 中途視覚障害者の職場復帰の各過程と課題
1 職場復帰の各過程と課題
(1) 発症から治療の過程
(2) 生活訓練の過程
(3) 職業リハビリテーションの過程
(4) 職場復帰・定着のための条件整備
2 中途視覚障害者をめぐる制度の問題
(1) 関係機関の機能の周知体制
(2) 職場復帰を働きかける機能の問題
(3) 包括的なリハビリテーションの実施
(4) 職場適応、定着に関する支援の問題
Ⅲ 職場復帰を促進するために
1 職場復帰の各過程における条件整備
(1) 地域レベルでの条件整備
(2) 医療リハビリテーションに係る条件整備
(3) 生活訓練に係る条件整備
(4) 職業リハビリテーションに係る条件整備
(5) リハビリテーション実施のための包括的な条件整備
(6) 職場復帰・定着に係る制度的な条件整備
(7) 職場における条件整備
2 職場復帰支援システムの構築のために
(1) 視覚障害者の職域開発、職務設計、雇用管理、訓練のノウハウの充実
(2) 関係機関の機能の周知
(3) 中途視覚障害者の職場復帰支援システムの構築
(4) 職場復帰支援のコーディネート
(5) 各機関の位置づけ及び役割分担の明確化
3 支援・助成の課題
(1) 情報交換会の場づくり
(2) 支援機器導入に関する助成の検討
(3) 復帰後の研修制度に関する助成の検討
(4) 人的支援に対する助成の検討
(参考1)職場復帰に係る本人・家族・会社の役割と課題
(参考2)本人を取り巻く関係機関の役割と課題
〔資料〕
1 ヒアリング対象者
2 ヒアリングを通じて得られたポイント
3 訪問ヒアリングを通じて得られた事例
≪報告本文抜粋≫
Ⅲ 職場復帰を促進するために
これまで、中途視覚障害者の職場復帰の各過程とその問題点について整理してきた。
これらを踏まえて以下においては、円滑な職場復帰のための支援の在り方について検討していくこととする。
1 職場復帰の各過程における条件整備
(1) 地域レベルでの条件整備
中途視覚障害者は、その心理的ショック、絶望感等から社会への関わりを絶ち、社会復帰へのきっかけがつかめないまま長時間いた結果、会社等との関係も薄れて社会復帰の糸口を失ってしまうケースがみられるが、地域における各種行事への参加や障害者同士の交流が社会復帰への意欲を高めるケースも多いことを勘案すると、地域レベルでこうした障害者を勇気づけ、意欲を高める場をつくる風土づくりのための行政機関等による働きかけが大切であろう。
具体的には、地方行政機関等による
① 障害者理解のための啓発活動、
② 地域レベルでの中途視覚障害者の把握、
③ ボランティア等を活用した障害者の参加できる各種行事・交流の場づくり、
④ 地域の広報等による各種行事・交流の場の周知などへのきめ細かな対応、働きかけが望まれる。
(2) 医療リハビリテーションに係る条件整備
① 医療段階で、医師、看護婦がソーシャルワーカーと協力、分担して告知から障害受容への方向づけ、社会復帰に取りかかるための動機づけなど、中途視覚障害者を職場復帰に向かわせるメンタルな面を含めた支援を行う体制を整備する必要がある。
② 社会復帰の各過程をになう他部門や関係機関に関する情報の収集、関係機関との間で社会・職場復帰までの一貫した連携体制の構築・強化が望まれる。
③ 医師、看護婦だけでなく医療ソーシャルワーカー、家族、他のリハビリ機関の職員、職場の上司や同僚等がチームを組んで相談にあたる体制の整備が望まれる。
(3) 生活訓練に係る条件整備
① 可能な限り職場関係者、職業リハビリテーション関係者とも連携しつつ、職場復帰後の職務を想定して、生活訓練の内容を職業リハビリテーションカリキュラムへの円滑な移行に配慮したものとすることが望まれる。
② 職場復帰後のフォローアップについて体制を整える必要がある。
(4) 職業リハビリテーションに係る条件整備
① 中途視覚障害者の場合、職業に対する不安や自信喪失、障害の受容面での問題から職業リハビリテーション実施のタイミングを逸する場合があるため、医療機関によるケアや生活訓練と連続性のある職業リハビリテーション実施について、関係機関との連携を図り、復職への意欲を喚起する必要がある。
② 職場復帰後の具体的な職務内容を本人、事業所とともに検討し、それをもとにした訓練内容を設計、実施することが望まれる。
このために、
イ 職場定着を図るための、職務配置や職場環境の改善及び視覚障害を補う機器に関する情報の提供等、ハードとソフト両面にわたる人材の確保
ロ 技能向上のための短期の能力開発セミナーの活用と企業への周知
ハ 中途視覚障害者の休職期間中における復職後に従事する可能性のある職務に係る企業ニーズに応じた訓練サービスの提供
ニ 障害者用支援機器の周知やその貸出事業の充実
ホ 重度視覚障害者を対象とした障害の程度に応じた訓練プログラムの充実と訓練対象職域の拡大、専門の指導員の養成
ヘ 医療機関への職業リハビリテーションに関する情報の提供と地域における関係機関との連携による職業リハビリテーションの実施などの条件整備が必要である。
(5) リハビリテーション実施のための包括的な条件整備
現状では、依然として、医療リハビリテーション、生活訓練、職業リハビリテーションの各過程がそれぞれの機関で縦割り的に実施される傾向がみられるが、このことは、当事者が、3つの異なる機関と連絡・調整をする必要があることとなり、移動、コミュニケーション上の制約が大きい中途視覚障害者にとっては大きな負担となる。
また、会社にとっても、職場復帰のための具体的な計画をたてそれをリハビリテーションの内容に反映させるためには、調整が必要なリハビリテーション機関が多くなり、調整の内容も細分化されることとなる。一方、リハビリテーション実施機関にとっても、それぞれのリハビリテーションの内容が重複したり、それぞれのリハビリテーションの実施以前、以後の状況も把握しにくいため、包括的視点からリハビリテーションの内容を考えにくい状況となっている。
このため、職場復帰に必要となるリハビリ要素の把握とそれをもとにした包括的なリハビリテーションの内容を医療・生活・職業の各リハビリテーション機関が連携をして検討・調整、役割分担をして実施できる体制を整備することが望まれる。
また、これに対応できる専門家を各施設が配置又は他の機関にいる専門家の知識・経験を活用できるような協力・連絡体制を構築することが望まれる。
(6) 職場復帰・定着に係る制度的な条件整備
① 中途視覚障害者の職場適応・定着状況の把握及び支援体制の整備
各関係機関が連携しながら、職場復帰後の中途視覚障害者の職場適応・定着の状況(病状の進行による他の部位の障害による仕事への支障も含めて)についての定期的な把握、職場定着のための支援体制が必要である。
② キーパーソン確保への働きかけ
円滑な職場復帰を図るには、本人の希望・能力に配慮した適切な職種選択、職務設計及び計画的な職域拡大を考慮した配置、無理のない職務分担、障害者用支援機器の整備等、機能喪失・低下を職場において補うこと等の環境整備が必要となるが、これらの解決しなければいけない問題について、障害者と事業所の橋渡し役となるキーパーソンの存在は大きな意味を持ち、事業所においてその役割を果たす者を確保することを働きかける体制の整備が望まれる。
③ 雇用管理情報の確保
配置、職務分担のノウハウについて、企業間で事例報告、情報交換の場をつくることは、条件整備に有用な情報が得られ効果的である。
(7) 職場における条件整備
① 全社的な視覚障害理解への取り組み
社内報の利用、啓発・研修体制の整備、労働組合による勉強会などを通じた啓蒙啓発活動を推進することにより、視覚障害理解への取り組みを当事者意識を持ちつつ全社的なものとすることが、中途視覚障害者を自然に受け入れる土壌づくりとなるものと考えられる。
② 労働条件への配慮
職業リハビリテーション機関が事業所と連携しつつ、職場復帰直後の時差出勤や勤務時間のフレックス化など労働条件を配慮した形で勤務する「リハビリ出勤」の条件設定をするなどの工夫も望まれる。
③ 社内外の情報の入手環境整備
視覚障害による情報アクセス面での制約を補う配慮、たとえば廊下に物が突然置かれる状況になったことを知らせる、また墨字の読み上げの問題、掲示板、回覧等の文書について、電子データがあればできるだけその形で本人に回るような情報の流れを作る、社内がすべて電子メールでやり取りする環境ならば本人のパソコンでもアクセスできるようにするなどの配慮、整備が望まれる。
なお、視覚障害による情報アクセス上の問題は、大部分の視覚障害者が職場においてのりこえなければならない障壁ともいえ、情報の入手環境の整備は、事務的職種の者のみならず、三療やその他の職種に従事する視覚障害者の職場適応、職場定着にも関係するものと考えられる。
④ 職務創出の取組み
職場復帰当初の配置、職務分担については、人間関係づくりにも配慮しつつ本人が「できる仕事」を考慮して職務の再設計を行い、職務試行的に幅広い可能性のなかで検討を行うことが望ましい。
⑤ 職域・業務量拡大及び支援機器の導入への工夫
復帰後の職務・職域は、当初のルーティン的なものから、段階的に複雑化、拡大化が図られることが望ましい。この場合、支援機器の導入についても、職域の拡大、技能の向上に応じて段階的に図られるべきで、障害者への初期の重荷を軽くしておくことに配慮することが必要であると考えられる。
⑥ 技術面の助言者の確保
復職後に使用する情報機器に何らかのトラブルや疑問点が発生した場合に、気軽に相談できる人がいるかどうかは職場定着に密接に関係する要素といえ、職業訓練施設の指導員、職場のシステム周りの担当者、あるいは公的機関の担当者などの助言援助を得られる状態にあることが望ましい。
⑦ 研修機会、公平な処遇の確保
可能な限り、健常者である社員と同等に技能向上などのための研修会や講習会、あるいは展示会などに参加させていくことが望ましい。
見えないからムリではないかといった先入観から研修・行事に参加させないことが、本人の疎外感を募らせる結果となり、定着に支障をきたす場合がみられる。
特に、社内制度的に行われる向上訓練について中途視覚障害者に対しても平等に機会を与えることによって、公正な評価、査定についての検討にもつながってくるものと考えられる。
いずれにしても、職場で視覚障害者を特別視しない社内の風土が中途視覚障害者に対する公正な評価、査定実現の土壌をつくり、処遇改善にも反映されることになるものと考えられる。
⑧ 第三者機関との協力関係の構築
何か問題が発生したとき、社内で解決を図ろうとしてもノウハウがなくその解決過程で壁にぶつかる場合がある。復職後の諸々の問題の解決には、他の第三者機関の智恵を借りることが得策である場合がある。
こうした体制を構築するためには、雇用側、障害者自身、リハビリテーション関係者、定着指導官、職業カウンセラー、医療ソーシャルワーカーなど関係者の間の日頃のコミュニケーションが不可欠であるため、定期的に会合を開くことなどにより、職場復帰後の中途障害者の状況を把握し、アフターケアについて検討することが望まれる。たとえば、仕事の創出、心のケア、処遇の改善、などの目的に応じて適宜構成員を考えつつ検討チームを作ることなどが考えられる。
2 職場復帰支援システムの構築のために
(1) 視覚障害者の職域開発、職務設計、雇用管理、訓練のノウハウの充実
視覚障害者の職域開発、配置・職務分担などの職務設計、雇用管理、向上訓練のノウハウの充実を図ることが必要である。
特に現業的職種が元職である中途視覚障害者の復帰後の職域開発、訓練のノウハウについては取組みが遅れており整備が望まれる。
(2) 関係機関の機能の周知
中途視覚障害者の早期の職場復帰への準備のために、医療機関、事業所等生活訓練機関、職業リハビリテーション機関や公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターなどの関係機関の機能の周知をはかることが必要である。
(3) 中途視覚障害者の職場復帰支援システムの構築
事業所、関係機関との情報交換、連携により、中途視覚障害者の受障の時点から関係者が参加した形で、職場復帰・定着に係る支援が必要な中途視覚障害者の把握、ケースごとの指導援助、支援検討を行うシステムを構築し体制を整備することが望まれる。
例えば、本人、キーパーソン、職場関係者、職業リハ機関の指導員、職場定着指導官(公共職業安定所)、職業センター(職業カウンセラー)、医療ソーシャルワーカーなどによる支援体制を作り、継続的に中途視覚障害者の働くうえでの諸問題を解決していくシステムづくりなどが考えられる。
(4) 職場復帰支援のコーディネート
職場復帰の過程においては、職場のキーパーソンが果たす役割が大きいが、概して職場のキーパーソンが持つ情報が社内情報にとどまることから、職場復帰に対する各機関の支援に関する情報収集を個別に得る必要があり、支援内容の整合性・連続性を保ちつつ、中途視覚障害者の復帰過程をフォローすることは、キーパーソンにとって負担が大きいものと考えられる。
こうしたことから、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターが、本人、医療ソーシャルワーカーなどから情報を得て中途視覚障害者の把握から、職場復帰・定着に至るまでの過程をフォローし、各過程における諸問題の解決について、コーディネート的役割をはたし、本人、キーパーソンに必要な情報の提供、相談援助等を行うことが期待される。
(5) 各機関の位置づけ及び役割分担の明確化
また、中途視覚障害者の職場復帰の過程においては、視覚障害により生じた生活・職業上の制約について本人の受容と機能回復、生活・職場環境における条件整備を段階的に図ることが必要であり、本人、家族、会社関係者、医療・職業リハビリテーション機関関係者の長期的視野にたった連携による問題解決を図ることや各機関の位置づけ、役割分担を明確化することも重要となる。
3 支援・助成の課題
これまでの検討で明らかになったとおり、中途視覚障害者の円滑な職場復帰・定着を図るためには、職域開発・雇用管理に関する情報収集と実践、計画的・段階的な施設・設備等ハード面の整備や職務遂行及び技術面の問題解決に関する人的なサポートの充実などが有効な支援要素となっており、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターなどの関係機関で行っている各種助成措置がこれらの支援ニーズに対応できるものとなるようそのメニューの検討、実際の活用ノウハウの周知などに努めていくことが望ましい。
(1) 情報交換会の場づくり
事務的職種に就労する視覚障害者の雇用者の情報交換のための場づくりのための施策の充実が望まれる。具体的な雇用事例の情報交換については、一企業で抱えている悩みや試行錯誤の経験を持ち寄り相談できるような場を定期的に持つことが、中途視覚障害者の受入れ体制づくりにとって有効である。こうした情報交換会の場づくりについて公共職業安定所など行政機関がイニシアティブをとることにより働きかけることが望ましい。
(2) 支援機器導入に関する助成の検討
復職後に整備する情報機器、支援機器については、復帰後の段階的な職能拡大と仕事の創出に連関して整備をすすめることがより職場定着に貢献するものと考えられ、こうした段階的な機器の充実・更新に対応できる柔軟な助成措置の検討が望まれる。
(3) 復帰後の研修制度に関する助成の検討
中途視覚障害者の職域の拡大のためには、本人の技能の習熟に加えて仕事の中で活用するソフトのバージョンアップや新規ソフトの使用など技能の向上を前提とする場合が多く、一定期間の研修が必要となる。この場合、通常の社員研修はその機会を平等に与えるのは当然であるが、視覚障害者に個別的な研修も併せ行う必要がある。こうした障害者に対する個別的研修の実施を会社に動機づけさせる支援・助成措置の充実を図ることが望ましい。
(4) 人的支援に対する助成の検討
視覚障害者に対する事務補助者の配置など職場における人的支援については、日本の企業では、依然として、職場において介助者を必要とすることは一人前ではないという風土があること、さらに、労務管理が難しいことなどから、その配置が困難な面もあり、外部への委嘱についても、企業の内部に断続的に外部の者が入りこむことを極端に嫌う傾向がある。
また、実際に、職場復帰をした中途視覚障害者自身からも、外部の者が会社内の組織と半ば独立して、障害者の職場介助に専念する人的支援の在り方は、望ましくないとの声もあった。
しかしながら、職場のキーパーソン、職場介助者、技術支援のための助言者などの確保による人的支援体制の整備は、視覚障害者の職域拡大に効果的であり、この面での助成の充実が望まれる。
この場合、単に助成制度を用意するだけでなく、行政サービスとしての人的支援を委嘱機関の斡旋、その制度を利用した具体的な支援体制の構築に関する指導・援助など制度利用のためのソフト面の行政サービスの充実が望まれる。