達障害児の社会性の状態把握、および子育て環境としての安定した家庭作りのための調査研究事業
社団法人 精神発達障害指導教育協会 理事長 金 子 健
(報告書A4版19ページ)
| 事業目的 |
本調査の第一の目的としては、発達障害児における社会性の発達状態と課題をしることである。さらに第二の目的として、家族、特に母親のメンタルヘルスの状態を明確にすることである。
| 事業概要 |
内容:発達に障害のある子の家族に、以下の内容のアンケート調査を実施した。その項目は、子どもの年齢、診断名、診断を受けた時期、記入者の年代、就労の有無、家族構成、家族・親族・地域との関係、記入者の抑うつ状態、育児に関するストレス、育児全般への意識、社会性の状態、不適切行動の実態、親離れ・子離れへの意識と実態、家族として知りたいこと、希望する育児支援である。
方法:アンケート調査用紙を郵送し、返送を依頼した。一部、当協会やクリニックの来院時に持参された方もいた。調査対象者は、当協会指導室および、クリニックのリハビリテーション室を利用している951名である。そのうち、期限までの有効回答は781名であり、回収率は82%であった。
アンケート結果の分析・集計については、大和コンピューターサービス株式会社に委託して行った。
(大和コンピューターサービス株式会社 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-8-4 東商共同ビル)
| 事業結果 |
1.回答者とその年代、対象児・者の年齢層
回答者は781名で、その年齢は、3歳から50歳までであり、年齢層は表1の通りである。家族形態は核家族が77%と最も多く、夫婦間のコミュニケーションや協力関係については、夫婦関係は良好であると答えた人が79%、コミュニケーションも取れていると感じている人が73%、子育てに協力し合っていると感じている人が72%、きょうだい間の関係については良好であると回答したのが72%であった。アンケート調査の記入者については、母が最も多く、95.4%が母親による回答となった。記入者の年代は、表2の通りである。
表1 対象者の年齢層
|
|
人数 |
% |
|
幼児 |
130 |
16.6 |
|
学童 |
447 |
57.2 |
|
中高生以上未成年 |
172 |
22.0 |
|
成人以上 |
32 |
4.1 |
|
合計 |
781 |
100 |
表2 記入者の年代
|
記入者の年代 |
人数 |
% |
|
20代以下 |
- |
- |
|
20代 |
1 |
0.1 |
|
30代 |
257 |
32.9 |
|
40代 |
438 |
56.1 |
|
50代 |
66 |
8.5 |
|
60代以上 |
8 |
1.0 |
|
無回答 |
11 |
1.4 |
|
合計 |
781 |
100.0 |
2.対象者の診断名
保護者の記入する診断名による分布は、表3の通りであるが、自閉症、広汎性発達障害が多く、ついで、知的障害であった。これらについては、複数回答があり、また保護者の記入したものであるため、それらが完全に正しいものであるかについては、やや疑問が残る点もある。
表3 保護者記入による診断名
|
診断名 |
人数 |
% |
|
自閉症 |
282 |
36.1 |
|
広汎性発達障害 |
282 |
36.1 |
|
知的障害 |
252 |
32.3 |
|
注意欠陥多動性障害 |
78 |
10 |
|
アスペルガー症候群 |
59 |
7.6 |
|
学習障害 |
19 |
2.4 |
|
ダウン症候群 |
17 |
2.2 |
|
発達性協調運動障害 |
11 |
1.4 |
|
反抗挑戦性障害 |
2 |
0.3 |
|
その他 |
109 |
14 |
|
無回答 |
23 |
2.9 |
|
複数回答※ |
|
|
表4 診断名によるグループ
診断名 |
人数 |
% |
PDD群 |
399 |
51.1 |
PDD+MR群 |
156 |
20.0 |
MR群 |
107 |
13.7 |
| ADHD群(一部MR含む) | 31 |
4.0 |
その他群 |
63 |
8.1 |
無回答 |
25 |
3.2 |
全 体 |
781 |
100.0 |
また、診断名により、①知的障害の群(ダウン症候群を含む)、②広汎性発達障害の群(自閉症、アスペルガー症候群を含む)、③広汎性発達障害と知的障害の群、④ADHDの群(ADHDと知的障害も一部含む)⑤その他群、の5群にグルーピングした上で、分析等を行った。各群による分布は表4の通りである。
3.子どもの社会性の発達段階について
子どもの能力を、社会性の8段階で評価を行った。これは、本児をよく知る指導担当者による評価である。その分布については、表5の通りである。
表5 社会性の発達段階とその分布
|
社会性段階 |
内容 |
人数 |
% |
|
A |
「チョーダイ」と言われたとき、渡すことができる段階 |
46 |
5.9 |
|
B |
「~して」と言われたときそれを実行できる段階 |
138 |
17.7 |
|
C |
「あとで」で待てる段階 |
155 |
19.8 |
|
D |
順番を守ることができる段階 |
190 |
24.3 |
|
E |
目標を意識し、取り組むことができる段階 |
73 |
9.3 |
|
F |
じゃんけんがわかる段階 |
101 |
12.9 |
|
G |
決められた時間になると寝る、など、行動を起こすことができる段階 |
36 |
4.6 |
|
H |
よそとウチの区別ができ、外では行儀よくできる段階 |
28 |
3.6 |
|
I |
時間に合わせて、計画的に行動することができる段階 |
13 |
1.7 |
4.子どもの様子について
子どもの現在の様子について、社会性を中心とした19項目と、子どもの不適切行動に関する9項目に関して、「しばしばする」「まれにする」「しない」「よくわからない」の4段階について、回答を得た(表6、表7)。
他者とのコミュニケーション手段として、3)自分の思いや要求を伝えようとする手段を持っているかについては、80%近くがその手段を持っていると答えている。
また、社会性に関しては、1)挨拶を自分からする、を「しばしばする」とした人は、42%であったが、2)人からあいさつされたらあいさつを返す、は「しばしばする」とした人が58%であった。また、7)人から「~して」「~しなさい」と言われた時に、言われたことをする、8)「あとで」と言われた時に待つことができたり、順番を守ることができるといった項目について、「しばしばする」と答えた人が、どれも60%以上であった。また、11)一人でいても好きなことや楽しめることがある、という項目についても、「しばしばする」と答えた人が75%と多かった。
不適切行動に関しては、1)自分の体をかむなどの自傷行動、2)人に乱暴するなどの他害的行動は、「しない」と答えた人が60%前後であった。また、6)強迫的行動は「しない」と答えた人が、81%、7)固着的、執着的な行動についても、「しない」とした人が、69%であった。
3)感情のコントロールが悪い、に関しては、「しばしばする」がやや多くなり37%、4)奇声を発する 5)動き回ってしまう、も「しばしばする」が20%強という結果であった。
表6 子どもの現在の様子(社会性について)
|
|
全 体 |
しばしばする |
まれにする |
しない |
よくわからない |
無回答 |
|
1)挨拶を自分からする |
781 |
335 |
271 |
165 |
2 |
8 |
|
100.0 |
42.9 |
34.7 |
21.1 |
0.3 |
1.0 |
|
|
2)人からあいさつをされたら、あいさつを返す |
781 |
460 |
265 |
45 |
3 |
8 |
|
100.0 |
58.9 |
33.9 |
5.8 |
0.4 |
1.0 |
|
|
3)自分の思いや要求を伝えようとする |
781 |
603 |
146 |
10 |
7 |
15 |
|
100.0 |
77.2 |
18.7 |
1.3 |
0.9 |
1.9 |
|
|
4)ほめられたことを理解している |
781 |
639 |
106 |
2 |
20 |
14 |
|
100.0 |
81.8 |
13.6 |
0.3 |
2.6 |
1.8 |
|
|
5)注意されたこと、叱られたことを理解している |
781 |
563 |
163 |
14 |
32 |
9 |
|
100.0 |
72.1 |
20.9 |
1.8 |
4.1 |
1.2 |
|
|
6)「ちょうだい」といわれた時に、持っているものなどを相手に渡す |
781 |
667 |
90 |
11 |
3 |
10 |
|
100.0 |
85.4 |
11.5 |
1.4 |
0.4 |
1.3 |
|
|
7)人から「~して」「~しなさい」といわれたときに、言われたことをする |
781 |
604 |
142 |
18 |
5 |
12 |
|
100.0 |
77.3 |
18.2 |
2.3 |
0.6 |
1.5 |
|
|
8)「あとで」といわれた時に、待つ |
781 |
496 |
231 |
31 |
6 |
17 |
|
100.0 |
63.5 |
29.6 |
4.0 |
0.8 |
2.2 |
|
|
9)「順番」「かわりばんこ」など、といわれた時に、待つ |
781 |
506 |
210 |
42 |
16 |
7 |
|
100.0 |
64.8 |
26.9 |
5.4 |
2.0 |
0.9 |
|
|
10 )やってもいい?などの許可を求める行動をする(言葉と限らない) |
781 |
446 |
241 |
77 |
8 |
9 |
|
100.0 |
57.1 |
30.9 |
9.9 |
1.0 |
1.2 |
|
|
11)一人でいても、好きなことや、たのしめるものがある |
781 |
592 |
131 |
39 |
11 |
8 |
|
100.0 |
75.8 |
16.8 |
5.0 |
1.4 |
1.0 |
|
|
12)○になりたい、上手になりたい、と思っている |
781 |
389 |
186 |
84 |
116 |
6 |
|
100.0 |
49.8 |
23.8 |
10.8 |
14.9 |
0.8 |
|
|
13)じゃんけんの勝ち負けを理解する |
781 |
415 |
79 |
219 |
62 |
6 |
|
100.0 |
53.1 |
10.1 |
28.0 |
7.9 |
0.8 |
|
|
14)勝ち負けにこだわりすぎる |
781 |
131 |
193 |
405 |
49 |
3 |
|
100.0 |
16.8 |
24.7 |
51.9 |
6.3 |
0.4 |
|
|
15)決まりや約束事を守ろうとする |
781 |
285 |
297 |
132 |
54 |
13 |
|
100.0 |
36.5 |
38.0 |
16.9 |
6.9 |
1.7 |
|
|
16)決められた時間に、そって行動しようとする(たとえば、登校したり、寝ようとするなど) |
781 |
327 |
228 |
179 |
36 |
11 |
|
100.0 |
41.9 |
29.2 |
22.9 |
4.6 |
1.4 |
|
|
17)他人の家と自分の家で、態度を使い分ける |
781 |
208 |
235 |
255 |
75 |
8 |
|
100.0 |
26.6 |
30.1 |
32.7 |
9.6 |
1.0 |
|
|
18)時間に合わせて、計画的に行動する |
781 |
133 |
248 |
352 |
41 |
7 |
|
100.0 |
17.0 |
31.8 |
45.1 |
5.2 |
0.9 |
|
|
19)自由な時間に、目を離していても、安心して一人で時間を使う |
781 |
341 |
229 |
167 |
37 |
7 |
|
100.0 |
43.7 |
29.3 |
21.4 |
4.7 |
0.9 |
表7 子どもの不適切な行動
|
|
全 体 |
しばしばする |
まれにする |
しない |
よくわからない |
無回答 |
|
1)自分の体をかむ、などの自傷行動をする |
781 |
73 |
176 |
521 |
8 |
3 |
|
100.0 |
9.3 |
22.5 |
66.7 |
1.0 |
0.4 |
|
|
2 )人に乱暴をするなどの他害的行動をする |
781 |
54 |
280 |
427 |
17 |
3 |
|
100.0 |
6.9 |
35.9 |
54.7 |
2.2 |
0.4 |
|
|
3 )感情のコントロールが悪い(泣いたり、怒ったり、不自然に笑いすぎたりする) |
781 |
292 |
353 |
119 |
14 |
3 |
|
100.0 |
37.4 |
45.2 |
15.2 |
1.8 |
0.4 |
|
|
4 )人に迷惑をかけるような声を出したり、奇声をあげる |
781 |
175 |
332 |
254 |
13 |
7 |
|
100.0 |
22.4 |
42.5 |
32.5 |
1.7 |
0.9 |
|
|
5 )物事に集中せず、じっとしていたほうがよい時でも、動き回ってしまうなどがある |
781 |
206 |
356 |
199 |
15 |
5 |
|
100.0 |
26.4 |
45.6 |
25.5 |
1.9 |
0.6 |
|
|
6 )手を繰り返し洗う、などの強迫的な行動をする |
781 |
23 |
89 |
635 |
30 |
4 |
|
100.0 |
2.9 |
11.4 |
81.3 |
3.8 |
0.5 |
|
|
7 )移動や会話などの際に、体が固まってしまい、動かなくなる |
781 |
39 |
157 |
539 |
42 |
4 |
|
100.0 |
5.0 |
20.1 |
69.0 |
5.4 |
0.5 |
|
|
8 )予定変更などを受け入れられない |
781 |
49 |
352 |
355 |
22 |
3 |
|
100.0 |
6.3 |
45.1 |
45.5 |
2.8 |
0.4 |
|
|
9 )性に関する抑制のきかない行動をする |
781 |
18 |
80 |
522 |
157 |
4 |
|
100.0 |
2.3 |
10.2 |
66.8 |
20.1 |
0.5 |
3.子どもの障害の原因と母親
子どもの障害の原因を母親のせいといわれたかどうかについて、聞いたところ、あると答えた人が、 3割以上いた(表8)。またそれについて、母親自身がそう思っているかどうかについて聞いたところ、今でもそう思っている人、時々そう思う、という人が3割以上いる。
表8 「母親のせい」と言われたことがあるかどうか
|
|
人数 |
% |
|
ある |
275 |
35.2 |
|
ない |
413 |
52.9 |
|
よくわからない |
84 |
10.8 |
|
無回答 |
9 |
1.2 |
表9 子どもの障害を「母親のせい」と思うかどうか
|
|
人数 |
% |
|
以前は思っていたが今は思っていない |
257 |
32.9 |
|
時々そう思う |
236 |
30.2 |
|
思っている |
33 |
4.2 |
|
いつもそう思っている |
4 |
0.5 |
|
その他 |
212 |
27.1 |
|
無回答 |
39 |
5 |
4.周囲からの支えについて
同居している家族以外の、周囲の人たちなどから、支えられていると感じるかどうかについて聞いたところ、表8のとおり、81%は支えがあると感じていることがわかる。また、その支えてくれる人がどのような関係の人たちかを聞いたところ、もっとも多かったのは、血縁関係の人で72%であったが、次に、子どもを通じて得た保護者が51%であった。
表10 周囲からの支えを感じるか
|
人数 |
% |
感じる |
635 |
81.3 |
|
感じない |
76 |
9.7 |
|
よく分からない |
64 |
8.2 |
|
無回答 |
6 |
0.8 |
表11 支えてくれる人の存在
|
支えてくれる人との関係 |
人数 |
% |
|
血縁関係 |
461 |
72.6 |
|
子どもの友人の保護者 |
327 |
51.5 |
|
親の知人または友人 |
248 |
39.1 |
|
有料のヘルパー |
116 |
18.3 |
|
近隣の方 |
82 |
12.9 |
|
ファミリーサポートの会員 |
44 |
6.9 |
|
有料のベビーシッター |
12 |
1.9 |
|
その他 |
156 |
24.6 |
|
無回答 |
2 |
0.3 |
5.抑うつ状態について
記入者の現在の精神状態について、東京大学の鈴木庄亮教授による抑うつ状態チェックリストに基づいて調査をし、それを得点化した結果を、表12に示した。
表12 抑うつ状態と、診断群
|
|
|
全 体 |
22点以上 |
21点以下 |
無回答 |
平均点 |
|
全 体 |
|
781 |
172 |
601 |
8 |
17.1 |
|
100.0 |
22.0 |
77.0 |
1.0 |
|
||
|
診断名 |
MR群 |
107 |
20 |
84 |
3 |
15.6 |
|
100.0 |
18.7 |
78.5 |
2.8 |
|
||
| PDD群 |
399 |
99 |
298 |
2 |
17.6 |
|
|
100.0 |
24.8 |
74.7 |
0.5 |
|
||
| PDD+MR群 |
156 |
24 |
130 |
2 |
16.6 |
|
|
100.0 |
15.4 |
83.3 |
1.3 |
|
||
| ADHD群一部MR群含む) |
31 |
11 |
20 |
- |
19.6 |
|
|
100.0 |
35.5 |
64.5 |
- |
|
||
| その他群 |
63 |
15 |
47 |
1 |
17.3 |
|
|
100.0 |
23.8 |
74.6 |
1.6 |
|
本チェックリストでは、得点が10点から30点の範囲にあり、 その中でも22点以上が抑うつ状態と判断される。発達に障害を持つ子どもの家族では、 全体では22%が抑うつ状態にあるといえる。また、診断群によるちがいとしては、 ADHD(一部MRを含む)群が35%で、ついで、PDD群24.8%であった。 ADHD(一部MRを含む)群では、平均値も19,6点とやや高めの傾向を示している。
6.育児ストレスについて
子育てに関する18項目について、加藤らの行った、育児ストレス尺度を用いて、調査を実施した。 18項目について、「よくあてはまる、ややあてはまる、あてはまる、あまりあてはまらない、全然あてはまらない」の 5尺度で評定してもらい、「よくあてはまる」を1点とし、「全然あてはまらない」を 5点とし、10個の否定項目(*)については、点数を反転させて、集計を行った。さらに、 4点、5点のついている得点が高い人たちを高ストレス群として、診断群による違いなどを検討した(表13)。
表13 診断群ごとの育児ストレス
(表の数値は、「よくあてはまる」と「ややあてはまる」とつけた、高ストレス群の人の比率)
|
|
①MR群 |
②PDD群 |
③PDD+MR群 |
④ADHD群 |
⑤その他群 |
全体 |
参考数値 |
|
n= |
107 |
399 |
156 |
31 |
63 |
781 |
38 |
|
|
高ストレス群のみ(%) |
||||||
|
1)子どもと気持ちが通い合っているように思う |
12.1 |
22.8 |
21.8 |
19.4 |
25.4 |
21.1 |
5 |
|
2)子どもが生まれてよかったと思う |
6.5 |
9.5 |
7.7 |
9.7 |
9.5 |
8.6 |
0 |
|
3)これからの育児が楽しみである。 |
36.4 |
41.6 |
33.3 |
38.7 |
33.3 |
38.2 |
5 |
|
4)子どもと一緒にいると楽しい |
18.7 |
17.5 |
9.6 |
19.4 |
14.3 |
15.9 |
3 |
|
5)子どものことでくよくよ考えてしまう* |
44.9 |
52.6 |
46.8 |
45.2 |
50.8 |
49.7 |
47 |
|
6)子どもがわずらわしいことがある* |
38.3 |
35.3 |
33.3 |
38.7 |
41.3 |
35.5 |
61 |
|
7)育児によって自分も成長していると思う |
7.5 |
7.0 |
4.5 |
9.7 |
7.9 |
6.7 |
11 |
|
8)時間を子どもに取られて、視野が狭くなる* |
26.2 |
23.6 |
26.3 |
25.8 |
25.4 |
24.2 |
39 |
|
9)毎日同じことの繰り返しで息が詰まるような感じがする* |
31.8 |
24.8 |
26.9 |
32.3 |
20.6 |
26.0 |
32 |
|
10 )育児のために自分は我慢ばかりしていると思う* |
22.4 |
18.8 |
25.6 |
29.0 |
17.5 |
20.9 |
26 |
|
11 )自分一人で子どもを育てているように思う* |
21.5 |
16.5 |
19.9 |
38.7 |
19.0 |
18.8 |
24 |
|
12 )子どもは自分の生きがいである |
40.2 |
25.6 |
26.3 |
35.5 |
34.9 |
28.6 |
11 |
|
13 )ちょっとしたことで子どもをしかる* |
34.6 |
39.1 |
32.7 |
48.4 |
39.7 |
37.5 |
63 |
|
14 )子どもをしかるとき、たたいたりつねったりする* |
16.8 |
18.8 |
19.2 |
22.6 |
19.0 |
19.0 |
50 |
|
15 )自分から子どもをあやしたり、遊んであげたくなる |
30.8 |
31.8 |
28.2 |
32.3 |
36.5 |
31.1 |
8 |
|
16 )朝、目覚めがさわやかである |
45.8 |
54.4 |
51.3 |
77.4 |
65.1 |
54.3 |
29 |
|
17)育児につまずくと自分を責める* |
26.2 |
28.8 |
30.1 |
29.0 |
34.9 |
28.4 |
34 |
|
18 )なんとなくイライラする* |
39.3 |
37.1 |
35.9 |
38.7 |
28.6 |
36.1 |
50 |
7.親の負担感・困難感について
表14の33項目について、親の負担感・困難感について、調査を実施した。
各項目に対して、「とても大変、いくらか大変、少し大変、まったく大変ではない、よくわからない」という5段階で回答を得た。
1)お子さんに発達障害があると分かるまでの悩みや、2)お子さんに発達障害があるとはっきりしたときのこと、20)義務教育終了後の進路について、21)学校卒業後の就職先について、22)成人してからの暮らしについて、25)親亡き後のことについて、29)福祉施策などが十分とはいえないことについて、といった項目について、とても大変と感じていることがわかった。また、15)お子さんをめぐっての近隣との関係について、18)園や学校の先生との関係については、まったく大変ではないという人が3割ほどいる、という結果であった。
表14 親が負担・困難さを感じる項目
|
|
全 体 |
とても大変 |
いくらか大変 |
少し大変 |
まったく大変ではない |
よくわからない |
無回答 |
|
1)お子さんに発達障害がある、とわかるまでの悩み |
100.0 |
55.6 |
18.7 |
16.3 |
4.6 |
4.5 |
0.4 |
|
2)お子さんに発達障害がある、とはっきりとしたときのこと |
100.0 |
58.0 |
20.1 |
16.5 |
2.9 |
1.8 |
0.6 |
|
3)お子さんの障害を、家族や親族に理解してもらうこと |
100.0 |
32.9 |
22.4 |
26.6 |
14.7 |
2.7 |
0.6 |
|
4)お子さんの障害について、お子さん自身がそれを認識すること |
100.0 |
25.0 |
9.0 |
11.1 |
5.6 |
48.3 |
1.0 |
|
5)同年齢の子どもと、比較した見方をしてしまうこと |
100.0 |
26.6 |
27.0 |
25.9 |
12.7 |
6.8 |
1.0 |
|
6)奇異な目や偏見の目で見られてしまうこと |
100.0 |
33.9 |
28.7 |
27.5 |
6.8 |
2.7 |
0.4 |
|
7)差別的に扱われたこと |
100.0 |
29.3 |
26.5 |
26.2 |
9.0 |
8.5 |
0.5 |
|
8)お子さんのきょうだいのことについて |
100.0 |
16.0 |
19.5 |
23.3 |
13.7 |
9.9 |
17.7 |
|
9)日々の子どもの世話について |
100.0 |
24.3 |
32.4 |
34.7 |
7.7 |
0.6 |
0.3 |
|
10 )毎日の宿題や課題について |
100.0 |
21.0 |
28.4 |
31.4 |
13.2 |
4.6 |
1.4 |
|
11)学校での勉強について |
100.0 |
15.4 |
24.6 |
23.2 |
19.8 |
14.0 |
3.1 |
|
12)家庭での子どもとのコミュニケーションについて |
100.0 |
11.8 |
27.0 |
41.4 |
18.2 |
0.4 |
1.3 |
|
13)家庭での子どもの行動の問題について |
100.0 |
18.7 |
28.6 |
39.6 |
11.4 |
0.6 |
1.2 |
|
14)家庭での子どもの感情の問題について |
100.0 |
19.7 |
28.3 |
36.7 |
13.1 |
1.2 |
1.0 |
|
15)お子さんをめぐっての近隣との関係について |
100.0 |
8.3 |
13.2 |
31.5 |
36.4 |
9.3 |
1.3 |
|
16)保育園や幼稚園、習い事などの子ども集団に入れることについて |
100.0 |
27.3 |
27.1 |
29.1 |
10.6 |
4.2 |
1.7 |
|
17)他児との友人関係について |
100.0 |
21.9 |
28.7 |
27.9 |
11.9 |
7.8 |
1.8 |
|
18)園や学校の先生との関係について |
100.0 |
13.2 |
20.9 |
30.7 |
31.6 |
1.9 |
1.7 |
|
19)学校入学のときの、学校や学級の選択について |
100.0 |
38.3 |
21.6 |
22.4 |
12.9 |
3.5 |
1.3 |
|
20)義務教育終了後の進路について |
100.0 |
48.0 |
16.9 |
11.5 |
5.5 |
15.4 |
2.7 |
|
21)学校卒業後の就職先について |
100.0 |
59.4 |
11.8 |
4.9 |
1.5 |
19.1 |
3.3 |
|
22)成人してからの暮らしについて |
100.0 |
58.4 |
13.7 |
5.0 |
1.2 |
19.1 |
2.7 |
|
23)親離れについて |
100.0 |
45.3 |
19.1 |
12.2 |
3.5 |
17.7 |
2.3 |
|
24)子離れについて |
100.0 |
37.8 |
20.5 |
17.4 |
5.5 |
16.1 |
2.7 |
|
25 )保護者亡き後のことについて |
100.0 |
68.8 |
9.7 |
4.4 |
0.6 |
14.3 |
2.2 |
|
26)参考にできる子育ての情報が少ないことについて |
100.0 |
28.9 |
28.6 |
27.4 |
8.5 |
5.1 |
1.5 |
|
27)専門的な相談などができる機関が少ないことについて |
100.0 |
33.9 |
26.4 |
25.9 |
9.2 |
3.5 |
1.2 |
|
28)福祉制度の情報がよくわからないことについて |
100.0 |
35.7 |
26.0 |
27.9 |
4.4 |
4.9 |
1.2 |
|
29)福祉施策などが十分とはいえないことについて |
100.0 |
58.4 |
20.2 |
13.1 |
1.9 |
5.1 |
1.3 |
|
30)遊びに行く場などが制限されてしまうことについて |
100.0 |
25.7 |
29.1 |
23.9 |
15.2 |
4.9 |
1.2 |
|
31)安心して受診できる医療機関が少ないことについて |
100.0 |
29.1 |
24.5 |
26.5 |
16.3 |
2.7 |
1.0 |
|
32)地域での交流ができにくいことについて |
100.0 |
26.8 |
25.4 |
30.3 |
10.5 |
5.5 |
1.5 |
|
33)障害を持つ子どもをみてくれたり、預かってくれる施設が少ないことについて |
100.0 |
38.3 |
24.7 |
19.7 |
9.6 |
6.1 |
1.5 |
10.将来の生活スタイルについて
将来の生活に不安を感じると同時に、具体的なイメージを持てているかどうかを調査したところ、将来の生活を考えたことがある人は約79%、考えたことがない人が約7%であった(表15)。その具体的なイメージとしては、グループホームなどでの少人数での暮らしをイメージしている人が、37%であった。具体的にはまだ考えていない、という人も約17%ほどいた(表16)。将来のイメージを描いていない理由としては、本人がどう育つのかのイメージがもてないなどが理由として多かった(表18)。
表15 将来の生活についての考え
|
|
人数 |
% |
|
ある |
614 |
78.6 |
|
ない |
52 |
6.7 |
|
どちらともいえない |
109 |
14 |
|
無回答 |
6 |
0.8 |
表16 具体的なイメージ
|
|
人数 |
% |
|
グループホームなど少人数での暮らし |
229 |
37.3 |
|
具体的にはまだ考えていない |
104 |
16.9 |
|
親や親族と同居 |
92 |
15 |
|
結婚 |
53 |
8.6 |
|
一人暮らし |
37 |
6 |
|
施設での暮らし |
30 |
4.9 |
|
その他 |
18 |
2.9 |
|
無回答 |
51 |
8.3 |
表17 将来の生活についての考えと子どもの年代
|
|
幼児 |
学童 |
中高校生以上の未成年 |
20歳以上成人 |
||||
|
全 体 |
130 |
100 |
447 |
100 |
172 |
100 |
32 |
100 |
|
ある |
97 |
74.6 |
333 |
74.5 |
156 |
90.7 |
28 |
87.5 |
|
ない |
15 |
11.5 |
32 |
7.2 |
2 |
1.2 |
3 |
9.4 |
|
どちらともいえない |
17 |
13.1 |
77 |
17.2 |
14 |
8.1 |
1 |
3.1 |
|
無回答 |
1 |
0.8 |
5 |
1.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
左が人数、右% |
|
表18 将来を考えたことのない理由
|
|
人数 |
% |
|
本人がどう育つのかがよく分からない |
18 |
34.6 |
|
子どもがまだ小さい |
8 |
15.4 |
|
あまり先のことを考えても仕方がない |
6 |
11.5 |
|
本人の希望が最優先だと思う |
5 |
9.6 |
|
あまり先のことを考えたくない |
4 |
7.7 |
|
福祉施策など制度が変わる可能性がある |
1 |
1.9 |
|
本人の希望がいろいろかわる |
0 |
0 |
|
その他 |
3 |
5.8 |
|
無回答 |
7 |
13.5 |
11.親離れについて
親離れ・子離れについて、どのような考えを持っているかについて調査した。自分の子どもの親離れが進んでいると思うかを聞いたところ、進んでいない、と感じている人が43%であった(表19)。親離れについての具体的な取り組みとしては、身辺自立やお手伝いが上位に上がり、車内マナーといった社会性、留守番や一人歩き、一人通学など、実際に一人で活動できる時間を作ることなどに取り組んでいる(表20)。
表19 親離れについての考え
|
|
人数 |
% |
|
すすんでいない |
339 |
43.4 |
|
すすんでいる |
140 |
17.9 |
|
よく分からない |
294 |
37.6 |
|
無回答 |
8 |
1 |
表20 親離れに向けての具体的な取り組み
|
|
人数 |
% |
|
身辺自立 |
620 |
79.4 |
|
家事などのお手伝い |
579 |
74.1 |
|
車内マナー |
418 |
53.5 |
|
留守番 |
360 |
46.1 |
|
一人歩き |
335 |
42.9 |
|
一人通学 |
333 |
42.6 |
|
時計の判断 |
291 |
37.3 |
|
お金の計算 |
266 |
34.1 |
|
自転車などのマナー |
236 |
30.2 |
|
生活時間の自己管理 |
215 |
27.5 |
|
レクリエーションなど余暇の過ごし方 |
201 |
25.7 |
|
お金の管理 |
177 |
22.7 |
|
携帯電話などの使い方 |
104 |
13.3 |
|
その他 |
79 |
10.1 |
|
無回答 |
40 |
5.1 |
12.知りたいこと、知りたかったこと
保護者として、これまでの子育ての中で知りたかったことや、知りたいことについて、さまざまな選択肢の中で、複数回答してもらったところ、表21~表24の結果となった。
また、今後希望する支援としてどのようなものが考えられるかを聞いたところ、表23のような結果となった。
表21 知りたいこと(病気や診断名について)
|
|
人数 |
% |
|
自閉症 |
292 |
37.4 |
|
発達障害 |
256 |
32.8 |
|
知的障害 |
246 |
31.5 |
|
障害を持つ子の医学全般 |
182 |
23.3 |
|
知能検査 |
166 |
21.3 |
|
軽度発達障害 |
158 |
20.2 |
|
てんかん |
116 |
14.9 |
|
アスペルガー症候群 |
110 |
14.1 |
|
高機能自閉症 |
106 |
13.6 |
|
AD/HD |
93 |
11.9 |
|
言語障害 |
79 |
10.1 |
|
LD |
68 |
8.7 |
|
チック |
62 |
7.9 |
|
高次脳機能障害 |
20 |
2.6 |
|
聴覚障害 |
12 |
1.5 |
|
無回答 |
189 |
24.2 |
表22 知りたいこと(制度など)
|
人数 |
% |
将来の生活 |
485 |
62.1 |
障害者自立支援法 |
341 |
43.7 |
保護者支援 |
335 |
42.9 |
特別支援教育 |
299 |
38.3 |
制度全般 |
249 |
31.9 |
個別支援計画 |
230 |
29.4 |
他の専門機関の情報 |
197 |
25.2 |
カウンセリング |
186 |
23.8 |
療育手帳 |
149 |
19.1 |
学級運営 |
125 |
16 |
年間計画 |
82 |
10.5 |
無回答 |
89 |
11.4 |
その他 |
49 |
6.3 |
表23 知りたいこと(子どもの能力など)
|
|
人数 |
% |
|
就労 |
499 |
63.9 |
|
思春期 |
456 |
58.4 |
|
感情やそのコントロールに関すること |
444 |
56.9 |
|
社会性 |
400 |
51.2 |
|
コミュニケーション |
376 |
48.1 |
|
性に関すること |
365 |
46.7 |
|
友人関係について |
332 |
42.5 |
|
発達全般のこと |
312 |
39.9 |
|
言語発達 |
289 |
37 |
|
身辺自立全般 |
289 |
37 |
|
ことば |
271 |
34.7 |
|
行動の問題 |
271 |
34.7 |
|
学習の課題 |
264 |
33.8 |
|
認知 |
222 |
28.4 |
|
清潔やマナーに関すること |
210 |
26.9 |
|
あそび |
172 |
22 |
|
運動の進め方 |
172 |
22 |
|
排泄に関すること |
148 |
19 |
|
食事に関すること |
138 |
17.7 |
|
着脱に関すること |
114 |
14.6 |
|
無回答 |
47 |
6 |
表24 希望する育児支援など
|
|
人数 |
% |
|
子どもの園や教育機関、就労先などとのパイプ役がほしい |
505 |
64.7 |
|
子どもを預けられる場がほしい |
319 |
40.8 |
|
子どものことを相談できる人や場が欲しい |
306 |
39.2 |
|
各地のサービス、制度の情報を教えて欲しい |
282 |
36.1 |
|
同じ障害を持つ子どもの家族などの仲間が欲しい |
149 |
19.1 |
|
子どものことを勉強する場がほしい |
129 |
16.5 |
|
子どもの世話をしてくれる人がほしい |
119 |
15.2 |
|
障害を持たない家族などの仲間がほしい |
42 |
5.4 |
|
子どものことを勉強する書籍などが知りたい |
25 |
3.2 |
|
その他 |
120 |
15.4 |
|
無回答 |
46 |
5.9 |
13.その他の調査項目
そのほか、記入者の生活状況や育児環境に関して、調査を実施した項目は表25に示すとおりである。
表25 その他の調査項目
|
記入者の就労状況 |
親離れについての考え |
|
家族構成 |
子離れについての考え |
|
診断名とそれを受けた時期 |
親離れに向けての具体的な取り組み |
考察および今後の展開
1.社会性の発達とその課題
本調査の目的の一つである社会性の発達とその課題に関して、「しばしばする」としている人の割合を、年代別にならべてみたところ、課題の内容によって、年代を追うごとに変化していくもの、とその割合が変わらないものとに分けることができた。
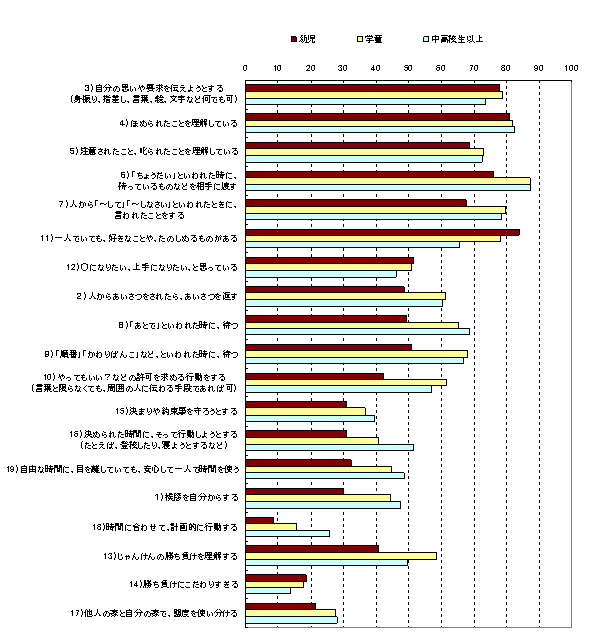
図1 年代別「しばしばする」の割合
図1をみると項目3)自分の思いを伝える手段の有無や、4)5)ほめられること、しかられることの理解、6)7)「ちょうだい」や「~して」と言われたときにそれに応じる、11)一人の時間に好きなものや楽しめるものがある、といった項目では、どの年代についても、ほぼ70%以上の割合で、「しばしばする」ことができる、と判断されている。年齢や障害の程度にかかわらず、障害があってもかなりの人たちがこうした課題を比較的早期から、理解していく可能性を持っていることを示唆している。障害を診断されたばかりの家族を支援するときに、今はできなくても、こうした力はかならず育つものであることを支援者は自信を持って伝える必要があると考えられる。
また、2)人からあいさつをされたらあいさつを返す、8)9)あとで、順番、といわれたら待てる、10)「やってもいい?」などの許可を求める行動については、幼児期にはそう多くないが、年代があがるにつれて「しばしばする」割合が上がり、学童期には、60%を超える人たちが、しばしばするとされている。つまり、これらは、年齢を重ねる中で獲得していく可能性がある課題であると思われる。
さらに、15)16)決まりや時間を自発的に守ろうとする、や18)19)計画的な時間のすごし方、などについては、獲得の率は低いながらも、年代によって獲得していく
可能性があると思われるが、これらについては、時間という抽象概念との関係から、知的障害の程度などの要因も大きく関わってくると思われるため、診断種別やその程度などを考慮したより詳細な検討が必要であろう。
2.家族のメンタルヘルス
先行研究で、渡部らは、対人関係や知的障害を持つ児の母親の育児ストレスや疲労感は、健常児や運動障害を主とした児よりも高いことを示唆している(1)。庄司らの研究においても、一般の育児グループの母と、 1歳6カ月健康診査後の育児支援を必要としているグループの母においては、育児ストレスについて有意な差があることを報告している(2)。また障害児の問題行動についても、母親の育児負担感に影響をあたえ、なおかつ、問題行動のうち、感情統制困難の因子が有意に影響を与えていることを明らかにした報告もある(3)種子田ら、2004)。
また、メンタルヘルスについては、主観的健康調査THIによる結果として、児の障害について、自分のせいと思ったり、母親のせいと言われた人では、抑うつ傾向を認め、家族の協力や夫の支援が少ないと感じている人では心身症状の訴えが多かったという(4)竹内、2000)。
本研究では、表12に示した通り、非抑うつ状態といわれる21点以下の人が、77%という結果となった。同調査によると、1993年に約 1万人の男女に行った結果、96.4%が21点以下に入るとされており、これと比較しても、抑うつ状態の人がかなり多いことがわかる。また、今回の記入者は圧倒的に女性が多いので、一般の女性の平均点13.8点と今回の調査結果の平均点17.1点を比較すると、t検定により5%水準で有意差があると認められた。また、診断種別にみたとき、ADHD群において平均点は19.6点であり、これらを今回の調査対象者全体の平均点と比較したとき、t検定により5%水準で有意差があると認められた。診断名による違いが、どのような要因を生じさせ、抑うつ状態に反映されるのか、詳細な検討は今後の課題といえるが、ADHD児の保護者に対しては、家族のメンタルヘルスに関しても、より配慮した関わりが求められているといえる。
また、障害の原因について、母親のせいと言われた人(表27)、および、周囲からの支えを感じていない(表28)という人たちのグループでは、χ二乗検定により、1%水準で抑うつ状態との関連があることが明らかになった。障害の原因は、ほとんどの場合が原因不明であるにもかかわらず、理由もなく「母親のせい」といわれ、精神状態を悪くすることがないように、家族への障害告知やその後の支援、教育の中で、その原因について誤解が生じないよう、啓発を十分に行ったり、家族全体や周囲の支えなどの環境までも視野に入れた支援を考えていく必要がある。
また、問題行動については、自傷行動や他害行動、強迫的、固着的執着的行動の有無については、抑うつとの関連は見られなかった。しかし、感情のコントロールが悪い群、他人の迷惑になるような奇声を上げる群、多動な行動がコントロールできない群、性に関する衝動の高い群という 4つの項目については、χ二乗検定により、1%水準で抑うつ状態との関連が明らかとなった。
これらは、先行研究の結果を明確に裏付けたことに加え、感情以外の行動の問題についても、保護者のメンタルヘルスと関連することが明確となった。こうした問題行動に関して、支援者は見通しを持った教育、支援を行うことが求められているといえる。
表27 抑うつと障害の原因 (人)
|
母親のせいと言われた |
言われていない |
合計 |
抑うつ22点以上 |
82 |
193 |
275 |
抑うつ21点以下 |
67 |
343 |
410 |
合計 |
149 |
536 |
685 |
χ二乗値=17.56404
表28 抑うつと周囲からの支えの有無 (人)
|
|
支えを感じない |
支えを感じる |
合計 |
|
抑うつ22点以上 |
42 |
105 |
147 |
|
抑うつ21点以下 |
34 |
527 |
561 |
|
合計 |
76 |
632 |
708 |
χ二乗値=61.59784
表29 抑うつと感情のコントロールの問題 (人)
|
|
コントロール悪い |
コントロール悪くない |
合計 |
|
|
抑うつ22点以上 |
82 |
18 |
100 |
|
|
抑うつ21点以下 |
206 |
100 |
306 |
|
|
合計 |
288 |
118 |
406 |
|
χ二乗値=7.877884
表30 抑うつと奇声の有無 (人)
|
|
奇声あり |
奇声なし |
合計 |
|
抑うつ22点以上 |
52 |
39 |
91 |
|
抑うつ21点以下 |
121 |
212 |
333 |
|
合計 |
173 |
251 |
424 |
χ二乗値=12.80945
表31 抑うつと動き回るなどの行動の関係
|
|
多動あり |
なし |
合計 |
|
抑うつ22点以上 |
61 |
35 |
96 |
|
抑うつ21点以下 |
143 |
160 |
303 |
|
合計 |
204 |
195 |
399 |
χ二乗値=7.796421
表32 抑うつと性に関する衝動的な行動
|
|
性への衝動行動あり |
なし |
合計 |
|
抑うつ22点以上 |
9 |
101 |
110 |
|
抑うつ21点以下 |
9 |
414 |
423 |
|
合計 |
18 |
515 |
533 |
χ二乗値=9.805915
また、 育児ストレスについては、表13に先行研究の結果を付記してあるが、それと比較したとき(図2)、子どもとの心理的交流や遊び、子どもとの楽しみ、いきがい感、子どもが生まれたことへの肯定感、これからの育児への楽しみ、目覚めのさわやかさ、といった内容について、障害のある子どもの家族のほうが、ストレスを抱えていることがわかる。支援するものには、子どもと過ごす時間の具体的な関わり方が求められると同時に、記入者の健康上の負担への理解や配慮も必要と思われる。また、保護者が知りたい内容として、就労や将来の生活を挙げている(表25、26)ことともあわせ、将来への不安などに関する情報や、長期にわたる支えの仕組みが必要と考えられる。
しかし、全般的には、先行研究の健常児群の高ストレス群よりも、少ない数値になっているものも多い。つまり、障害のある子の家族だから、といって、必ずしも、高ストレスを抱えている人が多いわけではない。子どもが煩わしいと感じたり、同じことの繰り返しに息が詰まる、一人で育てている感覚、子どもをしかる時にたたいたり、つねったりする、ちょっとしたことで子どもをしかる、子どもによって自分も成長している、といった項目については、今回の検査結果のほうが数値が低い。
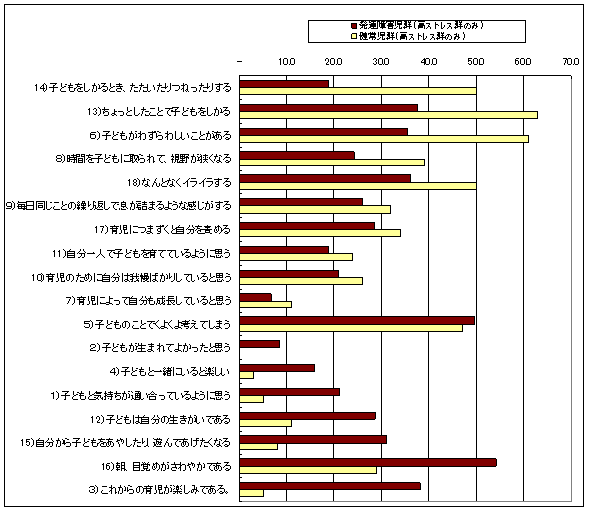
図2 育児ストレスの比較
障害のある子どもを育てていると、毎日同じことを根気よく繰り返す中で、一つのことを学ぶのには時間がかかるが、学べた時の喜びはまた大きいものがある。さらに、「子はかすがい」という言葉があるように、障害があるがゆえに子どもの行動や対応について、家族間で話しをする機会も増え、家族のコミュニケーションや協力関係も良好であるのかもしれない。また、今回の記入対象者は、民間の支援機関で、何らかの支援を受けている人であるが、そういう場合には、一人で育てている感じをもたずに子育てができているともいえる。さらに、年長になった保護者から、「この子のおかげでいろいろなことを学ばせてもらった」「この子がいたから、気付けなかったことに気づかせてもらえた」などの言葉を聞くことがあるが、育児によって自分も成長していると思う、という項目で、高ストレス群が少ないこととも関連があると思われる。
ただ、これらの点については、先行研究の調査対象が、3歳~5歳の幼児38名であることや、保護者が子どもの障害を認識し、受け入れていく過程のどのプロセスにあるかももちろん考慮して考えなければならないと思われるが、障害のある子どもと長期的に生活していった場合には、トータルすれば、そういうストレスが少ないという結果になり、長期的なかかわりを持てるようなシステムを整え、充実させることによって、保護者のメンタルヘルスを軽減させる可能性があるといえるだろう。
参考文献
(1) 渡部奈緒、岩永竜一郎、鷲田孝保 発達障害幼児の母親の育児ストレスおよび疲労感―運動発達障害児と対人・知的障害児の比較―.小児保健研究2002:No.61、第4号、2002
(2) 庄司妃佐 軽度発達障害が早期に疑われる子どもをもつ親の育児不安調査.発達障害研究2007:No.29、第5号、2007
(3) 種子田綾、桐野匡史、矢嶋裕樹、中嶋和夫 障害児の問題行動と母親のストレス認知の関係.東京保健科学学会誌2004:No.7、第2号、2004
(4) 竹内紀子 療育機関に通う発達障害児を持つ母親のメンタルヘルス.小児保健研究2000:No.59、第1号、2000
(5) 眞野祥子、宇野宏幸 注意欠陥多動性障害児の母親における育児ストレスと抑うつとの関連.小児保健研究2007:No.66、第4号、2007
(6)一瀬早百合 障害のある乳児をもつ母親の苦悩の構造とその変容プロセス―治療グループを経験した事例の質的分析を通して―.小児保健研究2007:No.66、第3号、2007
(7) 加藤道代、津田千鶴 宮城県大和町における0歳児を持つ母親の育児ストレスに関わる要因の検討.小児保健研究1998:No.57、第3号、1998
|
事業実施機関 |
社団法人 精神発達障害指導教育協会
〒115-0044 東京都北区赤羽南2-10-20
TEL 03-3903-3800


