日本のリハビリテーション No.7
財団法人
日本障害者リハビリテーション協会
第6章 職業リハビリテーション
1 日本の職業能力開発・雇用制度の概要
1. 制度の背景
(1) 就業者の状況
- 労働力率
- 1985年平均の日本人の人口120,780千人のうち,15歳以上の人口は94,630千人,労働力人口は59,630千人で,労働力率は63.0パーセントとなっている。これらの特徴は,次のとおりである。
- 産業別就業者の構成
- 第1次産業の占める割合は年々低下し,一方,第3次産業が上昇傾向を続けている。第2次産業は1974年以降低下傾向にあるが,1984年以降,僅かに増加している。
- 職業別就業者の構成
- 1965年には全就業者の約4分の1を占めていた農林漁業就業者は,1985年には,8.6パーセントまでに減少し,専門・技術・管理的職業,事務,販売等の職業の割合が増加している。
- 従業者に占める雇用者の割合
- 1965年の60.8パーセントから1985年には74.3パーセントと増加し,自営業主,家族従業者の割合は年々減少している。
| 年 | 実数(万人) | 構成比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 合計 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | |
| 1965年 | 4,730 | 1,113 | 1,507 | 2,109 | 100.0 | 23.5 | 31.9 | 44.6 |
| 1970年 | 5,094 | 886 | 1,791 | 2,409 | 100.0 | 17.4 | 35.2 | 47.3 |
| 1975年 | 5,223 | 661 | 1,841 | 2,710 | 100.0 | 12.7 | 35.2 | 51.9 |
| 1980年 | 5,536 | 577 | 1,926 | 3,020 | 100.0 | 10.4 | 34.8 | 54.6 |
| 1985年 | 5,807 | 509 | 1,992 | 3,283 | 100.0 | 8.8 | 34.3 | 56.5 |
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
| 15歳以上人口 | 9,587万人 | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 労働力人口 | 5,853万人 | ||
| - | 完全失業者 | 167万人 | ||
| 就業者 | 5,837万人 (100.0%) |
|||
| - | 自営業主 | 912万人 (15.6%) |
||
| 家族従業者 | 546万人 (9.4%) |
|||
| 雇用者 | 4,379万人 (75.0%) |
|||
資料出所:総理府統計局「労働力調査」
| 年 | 専門,技術,管理 | 事務 | 販売 | 農林漁業 | 採鉱,採石 | 運輸通信従事者 | 技能工,生産工程作業者 | 労務,保守,サービス職業従事者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965年 | 7.8 | 13.4 | 13.0 | 23.1 | 0.4 | 3.7 | 26.1 | 12.3 |
| 1970年 | 8.4 | 14.8 | 13.0 | 17.3 | 0.2 | 4.6 | 29.7 | 11.9 |
| 1975年 | 10.9 | 15.7 | 14.1 | 12.5 | 0.2 | 4.5 | 30.3 | 11.6 |
| 1980年 | 11.9 | 16.7 | 14.4 | 10.3 | 0.1 | 4.5 | 29.9 | 12.1 |
| 1985年 | 12.9 | 17.6 | 14.8 | 8.6 | 0.1 | 3.9 | 29.1 | 12.6 |
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
(2) 雇用者の状況
- 女子の雇用者
- 1960年以降増加の一途を辿り,1985年には,15,480千人に達した。これに伴い,全雇用者に占める割合も増加し,35.9パーセントとなった。
- 雇用者の年齢別構成
- 55歳以上の高年齢者の増加が目だち,全雇用者に占める割合は,1965年の7.5パーセントから1985年には12.4パーセントに達している。
- 雇用の形態
- 個々の企業や職場で,従来の正規職員の他にパートタイム労働者,アルバイト,出向,派遣労働者などの従来とは異なる雇用形態で働く労働者が増えてきている。
パートタイム労働者は,およそ300万人程度と思われる。パートタイム労働者は,女子が全体の70パーセントを占め,また,女子雇用者の20パーセントに至っている。年齢構成は,男子では,55歳以上が,女子では35~44歳がそれぞれ半数を占めている。
企業に籍を置いたまま,他の企業に出向させる企業は,70パーセントにおよんでおり,特に大企業でその傾向が強い。出向者の年齢は,3分の1が45歳以上で,中高年齢労働者の再就職先の確保の手段となっている。
他の企業の雇用する労働者を就労させている,いわゆる派遣労働者採用企業は,年々増加しており,特に,金融・保険業,サービス業での利用が目だっている。派遣労働者を利用している業務は,ビル管理・警備業務が圧例的に多いが,情報処理業務や事務処理業務でも今後さらに増加してゆくものと予想される。
| 年 | 女子雇用者 | 雇用者中女子の割合 |
|---|---|---|
| 1970年 | 1,096万人 | 33.2% |
| 1975年 | 1,167万人 | 32.0% |
| 1980年 | 1,354万人 | 34.1% |
| 1985年 | 1,548万人 | 35.9% |
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
| 年 | 全雇用者に占める割合(%) | ||
|---|---|---|---|
| 55~59歳 | 60~64歳 | 65歳以上 | |
| 1960年 | 5.9 | 1.5 | |
| 1970年 | 6.8 | 1.0 | |
| 1975年 | 4.6 | 3.0 | 2.4 |
| 1980年 | 5.5 | 2.9 | 2.6 |
| 1985年 | 6.9 | 3.1 | 2.3 |
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
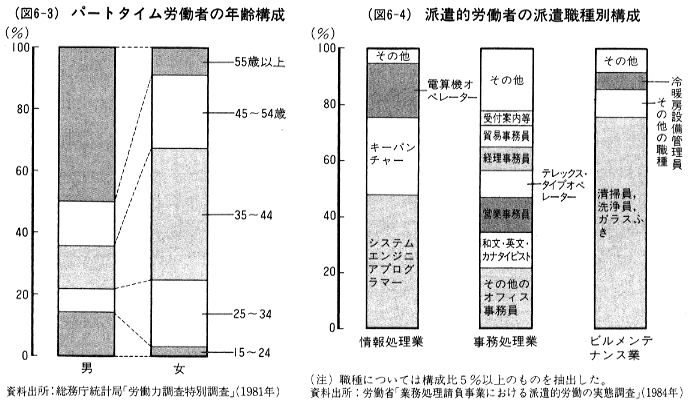
(3)失業の動向
完全失業者はオイルショックの1973年以降,年々増加し,1984年には161万人となり,完全失業率も,2.7パーセントと最高になった。
その後,1985年には,5年ぶりで失業者の減少がみられたものの,鉄鋼,造船等の構造的不況と円高による輸出産業の停滞により,再び,失業率は増加し,1987年5月現在3.2パーセントと史上最悪の状態に追い込まれている。また,日本の場合,労働者の解雇を極力避けるため,日本の製造業は90万人の企業内失業者を抱えているといわれ,海外生産の増加によって失業率の改善は厳しいものがある。なお,ここでいう完全失業とは,調査期間の1週間に1時間以下,もしくはぜんぜん収入を伴う仕事に従事しなかった者で就業の意思と能力を持つ者をいい,国際的比較を行う場合には注意を要する。
一般労働市場における有効求人倍率(有効求人者数/有効求職者数)は,1973年以降低下し,若干の上下はあるものの1倍を下回ったまま推移している。この有効求人倍率は,年齢が高くなるほど低くなり,55歳以上に対しては0.2倍を下回っており,高年齢者がいかに就職困難かを示している。
一方,求人の充足率は10パーセント前後で,未充足求人が多く残されている。すなわち,就業構造の変化,労働力人口の年齢構成の変化などにより,労働市場の需給関係が質的にマッチしにくくなっている。
| 年次 | 求職 | 求人 | 就職 (C) |
有効求人倍率 ((B)/(A)) |
就職率 ((C)/(A)) |
充足率 ((C)/(B)) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新規 | 有効(A) | 新規 | 有効(B) | |||||
| 1970年 | 千件 325 |
千件 1,070 |
千人 521 |
千人 1,507 |
千件 158 |
倍 1.41 |
% 14.8 |
% 10.5 |
| 1975年 | 350 | 1,536 | 339 | 943 | 122 | 0.61 | 7.9 | 13.0 |
| 1980年 | 364 | 1,507 | 390 | 1,128 | 119 | 0.75 | 7.9 | 10.5 |
| 1985年 | 412 | 1,707 | 401 | 1,161 | 130 | 0.68 | 7.9 | 11.2 |
資料出所:労働省「職業安定業務統計」
| 1955年 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | (1987.5月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 3.2 |
資料出所:総務庁統計局「労働力調査」
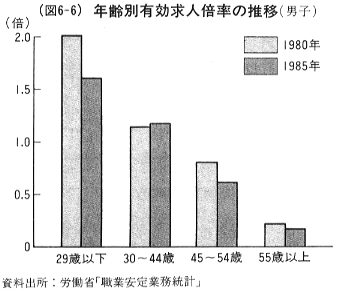
(4) 労働生活の実態
- 賃金
- 1985年の賃金を100とした名目賃金,実質賃金の指数はグラフに示すとおりである。1984年の日本の賃金水準は,イギリス,フランスより若干高くなっている,
1985年6月の賃金を性別,年齢別,企業規模別にみると,男子は,年齢とともに上昇し,45~49歳で最高となり,以後下降するのに対し,女子は,年齢による格差が少なく,30歳以上は同水準で推移する。男女とも大企業ほど高賃金である。企業規模間の賃金格差,男女間の賃金格差いずれも年齢が若いうちはそれほど大きくないが,年齢とともに増大する傾向がみられる。
企業で採用されている賃金体系は,年齢,勤続,学歴など属人的要素のみで基本給を決定する属人給は僅か5.5パーセントで,残りは,職務内容や職務遂行能力などの仕事的要素で基本給を決める仕事給,仕事的要素と属人的要素を総合的に勘案して決める総合給等で占められており,日本的慣行としてよくあげられる年功序列の賃金形態をとる企業は少ないことを示している。
- 労働時間
- 日本人は働き過ぎといわれるが,1人平均の月間所定内労働時間は年々短縮する傾向がみられる。週間所定労働時間が40時間以下の企業の割合でみても,1970年の14.6パーセントから1975年には41.7パーセントに増加し,特に大企業では77パーセントを占めるに至っている。
週休2日制の普及の割合も,1985年には,企業数で49.1パーセント,労働者数で76.5パーセントとなり,大企業では完全週休2日制が多くなっている。
このように,労働時間は短縮の傾向を示しているものの,欧米に比較し,なお,かなり長いといわざるを得ない。
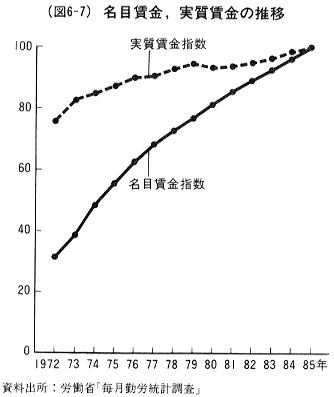
| 年 | 総数 | 所定内 | 所定外 |
|---|---|---|---|
| 1970年 | 186.6 | 169.9 | 16.7 |
| 1975年 | 172.0 | 161.4 | 10.6 |
| 1980年 | 175.7 | 162.2 | 13.5 |
| 1985年 | 175.8 | 161.0 | 14.8 |
資料出所:労働省「毎月勤労統計調査」
2. 障害者対策に関連する労働行政の組織と主管業務
(1) 職業安定機関とその機能
- 職業安定機関の役割
- 各人に,その有する能力に適当な職業に就く機会を与えることによって,工業その他の産業に必要な労働力を充足し,もって職業の安定を図るとともに,経済の興隆に寄与する」という職業安定法の目的を達成するための機関である。
したがって,職業の選択の自由と均等待遇を原則として,公共に奉仕する機関であり,関係行政庁または関係団体の協力を得て,雇用対策の責任を負う機関である。また,労働力の広域移動に対応できるよう,労働省職業安定局を核に全国に各機関が配置され,データ電送装置で結ばれている。ここに働く職員はすべて国家公務員である。
- 公共職業安定所の機能
- 公共職業安定所は職業安定機関の最前線に位置し,職業紹介,職業指導,雇用保険その他職業安定法の目的達成に必要な事項を無料で行う。
- 職業安定行政の行う主要業務
- 現在,特に重要となっている業務には,雇用対策基本計画の策定,職業紹介・職業指導・雇用調整,高年齢者の雇用促進,障害者の雇用促進,不況,産業構造変化等による失業者の雇用促進等があげられる。
(2) 職業能力開発機関とその機能
- 職業能力開発の目的
- 労働者または労働者になろうとする人たちに,職業に必要な技能や知識を習得させることにより,職業能力を開発・向上させる。労働者各人の希望,適性,職業経験等の条件に応じつつ,雇用,産業の動向,技術の進歩,産業構造の変化等に即応して,労働者の職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることが求められている。
- 職業能力開発の種類と内容
- 職業能力開発促進事業は国,都道府県等公共職業訓練施設で行われるものと,事業主等が行うものに分けられる。一般の労働者に関する職業訓練は,養成訓練,向上訓練,能力再開発訓練に大別され,このうち,公共職業訓練施設で行われる訓練および認定職業訓練として事業主等が行う訓練は,準則訓練といって訓練基準が労働省令で定められている。職業訓練は,学校教育で行われる職業教育と重複を避け,実技に重点をおいている。
- 技能検定制度
- 労働者の持っている職業に必要な技能や知識を一定の基準によって検定し,公証する制度で,職種ごとに1級および2級に区別するものと単一等級のものがある。合格者には,技能士の称号が与えられる。
(3) 労働安全衛生対策
- 最低労働条件と労働災害・職業病の予防の規定
- 労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべき労働条件の最低基準が,「労働基準法」で規定されている。そのうち,賃金については「最低賃金法」で,労働災害の防止,職場の労働者の安全と健康の確保に関しては「労働安全衛生法」が制定されている。
- 労働災害に対する補償制度
- 業務上の事由または通勤による労働者の負傷,疾病,障害または死亡に対して必要な保険給付を行い,また,これら労働者の社会復帰の促進,労働者および遺族への援護等が労働者災害補償保険法により行われている。
(4) 雇用保険制度
- 制度の目的
- 労働者が失業した場合に必要な給付を行うことにより,労働者の生活を安定させ,求職活動を容易にしようとするものである。同時に,失業の予防,雇用機会の増大,雇用構造の改善,労働者の能力開発向上等も,この制度の中で行われている。
- 適用の範囲
- 労働者を雇用する事業はすべて適用対象となる。ただし,農林水産事業のうち一部の事業は当分の間任意適用である。適用事業に雇用される労働者は原則として被保険者となる。
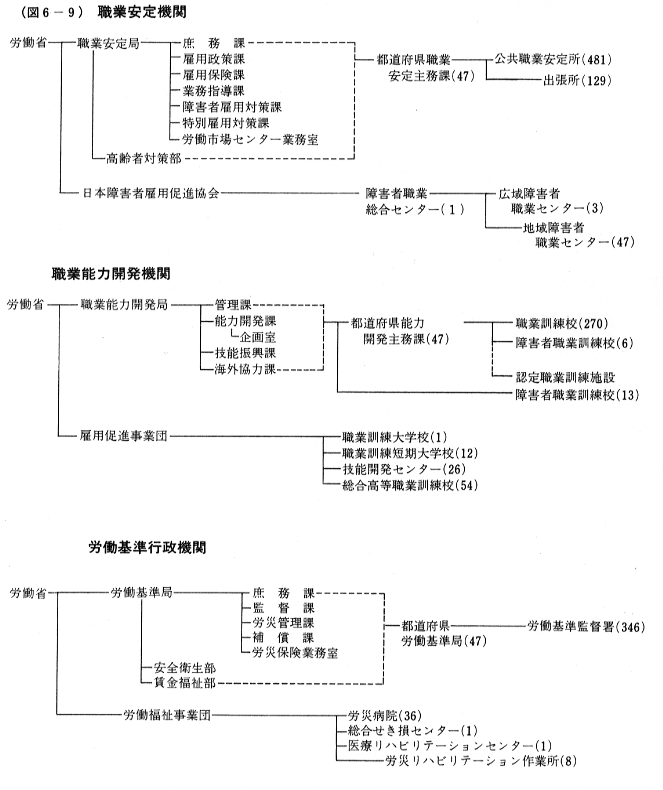
2 職業リハビリテーション
1. 戦後の歩み
障害者に対する職業リハビリテーションは,戦前の経済面の救済的対策と工場法や健康保険法の中でわずかに取り上げられていた労働安全・労災補償的対策,さらに戦争中の傷痍軍人対策を経て,戦後,旧制度が崩壊し,新しい憲法に基づいて1947年職業安定法,労働基準法,労働者災害補償保険法,さらに1949年身体障害者福祉法が制定され,これらにより傷痍軍人対策から一般の身体障害者にも等しくその対策が及ぶようになった。以下,職業リハビリテーションの領域別にその発展を概略しよう。
(1) 職業指導・職業紹介機能の充実
1947年,職業安定法の制定により,公共職業安定所において,職業紹介,職業指導の諸原則が傷痍軍人を含むすべての障害者に適用になる。
1952年,「身体障害者職業更生援護対策要綱」が策定され,障害者の公共職業安定所への登録,積極的求人開拓,ケースワーク方式による職業紹介,残存労働能力の検査の奨励等が示される。
1960年,身体障害者雇用促進法の制定により,求人者指導,就職後の指導,事業主に対する助言を行うことができることとなる。
1968年,公共職業安定所に就職促進指導官を設置,障害者の職業指導,紹介に当たる。同様に,1975年,雇用指導官が配置され,主として身体障害者の雇用促進に関した事業主指導に当たる。1987年度,前者は416人,後者は540人となっている。
1972年,雇用促進事業団において,専門的知識を持つカウンセラーを配置した心身障害者職業センターの第1号が東京に開所,1981年度までに全国各都道府県に1か所ずつ設置完了する。
1973年,聴覚障害者の就職指導に際して,手話通訳を行う手話協力員を公共職業安定所に配置する。1987年度には200人となる。
1976年,主要公共職業安定所に精神薄弱者職業相談員を配置する。同様に,1981年には,身体障害者職業相談員を配置する。1987年度現在,前者は194人,後者は140人となる。
1987年,身体障害者雇用促進法の改正により,同法の職業リハビリテーションに関する規定はすべての障害者を対象とするようになるとともに,障害者職業センターは一元的に日本障害者雇用促進協会が国に代って設置,運営することとなり,これにより,心身障害者職業センターは,地域障害者職業センターと改称されることとなった(1988年4月より)。また,この改正により,障害者職業センターで働くカウンセラーの資格要件が明確に規定されることになった。

戦前の身体障害者に対する職業訓練のひとつ。啓成社における義肢製作指導。
| 年 | 18~64歳 | 64歳以上 |
|---|---|---|
| 1955年 | 662 | 123 |
| 1960年 | 640 | 189 |
| 1965年 | 698 | 350 |
| 1970年 | 871 | 443 |
| 1975年 | - | - |
| 1980年 | 1,150 | 827 |
| 1985年 | 1,346 | 1,067 |
(注)1. 1975年は調査を行っていない。2. 1955~1965年の年齢別の数字は推計値である。
資料出所:厚生省「身体障害者実態調査
(2) 職業訓練等の充実
1947年,職業安定法により,職業補導の原則が示される。すなわち,身体障害者は,その能力に適するよう補導の種目および方法が選定されなければならないことが示された。
1949年,職業安定法の改正により,身体障害者であっても通常の職業補導を受けるものと共に訓練を行うことが原則であること,必要と認められる場合は特別の公共職業補導所を身体障害更生指導所と併設することができること,作業義肢,装具,補助工具の製作,修理を職業補導所で行えることが新たに追加された。しかし,この規定により身体障害者更生指導所に併設された補導所はなく,この規定は1958年,「職業訓練法」の制定と共に削除された。
1958年,「職業訓練法」が制定され,職業安定法で規定されていた職業補導は職業訓練といわれるようになったが,障害者に対して訓練制度は大きな変更はみられない。ただ,身体障害者に対して訓練手当が支給されるようになった。なお,訓練手当は,1969年,精神薄弱者にも支給されることとなる。
1969年,1978年,さらに1985年,「職業訓練法」が改正され,1985年からは「職業能力開発促進法」となった。障害者の職業訓練に関しては,基準の一部を変更して弾力的な訓練が可能になったこと,訓練の対象が「身体または精神に障害がある者等」となり,精神薄弱者等を含むようになったこと,障害者職業訓練校はできるだけ重度の障害者,精神薄弱者を対象にすることなどが主要な変更である。
障害者職業訓練校の数は,1949年の国立5か所から1969年の20年間に11か所に増加した後は,府県立の障害者職業訓練校が6か所設立されたに留まっている。
1979年,中央身体障害者職業訓練校が国立職業リハビリテーションセンターの一部として設立され,職業リハビリテーションとしての位置づけが確立した。同様に,1987年,吉備高原身体障害者職業訓練校が国立吉備高原職業リハビリテーションセンターの一部として設立された。
(3) 労働安全衛生・被災労働者補償対策
1947年,「労働基準法」が制定された。労働条件の最低基準を示したものである。
1947年,労働基準法と同時に,「労働者災害補償保険法」が制定され,労災による被災者の救済について規定された。現在までに40回を越える改正が行われ,給付水準の向上が図られている。また,同法に基づき,労災被災者の療養のため,労災病院が設立され,1986年10月現在36病院が労働福祉事業団により運営されている。
1959年,最低賃金法が制定され,賃金の最低額を保障することで労働者の生活の安定を図ろうとした。ただし,精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者については,労働基準局長の許可を受ければ最低賃金の適用除外を受けられることになっている。
1965年,労災による脊損者等に対し,作業を提供し,その自立更生を援助するため,労災リハビリテーション作業所の第1号が長野に設立された。1987年現在,8か所である。
1972年,「労働安全衛生法」が労働基準法から独立して制定された。これは,災害の重篤化,職業性疾病の増大,中小企業における災害の多発傾向等に対応するためであった。
1972年,労働安全衛生融資制度が発足した。労働災害防止策のための職場環境の改善等に対する融資で,労働福祉事業団が行う。
1973年,労働安全コンサルタント,労働衛生コンサルタントが制度化され,国家試験による資格制度と,登録制度が確立した。1987年7月1日現在,前者546人,後者1,223人が登録されている。
| 年 | 人数 |
|---|---|
| 1975年 | 322 |
| 1976年 | 333 |
| 1977年 | 345 |
| 1978年 | 349 |
| 1979年 | 341 |
| 1980年 | 336 |
| 1981年 | 313 |
| 1982年 | 294 |
| 1983年 | 279 |
| 1984年 | 272 |
| 1985年 | 257 |
| 1986年 | 247 |
資料出所:労働省労働基準局調べ
(4) 障害者雇用促進対策
1952年,「身体障害者職業更生援護対策要綱」が策定されたが,ここで障害者の雇用を強力に推進する方針を打ち出した。すなわち,国民一般の理解を深めるとともに,特に使用者の協力を要請して雇用を勧奨すると同時に,官公庁,公共企業体,自治体等が積極的に雇用するよう勧奨する。特に身体障害者に適する職種を有する事業所や一定規模以上の事業所には強力に勧奨する。また,雇用促進についての重要事項を協議するため,中央と地方に身体障害者雇用促進協議会を設置する。この要綱にしたがい,身体障害者雇用促進協議会では「身体障害者の職業更生に関する意見書」が出され,また,次官会議申合せ等により,官公庁等における取り組みも活発化した。
1960年,「身体障害者雇用促進法」が制定される。同法は,国,地方公共団体および民間企業に対し,身体障害者雇用率を定め,努力目標としたものである。
1976年,「身体障害者雇用促進法」が抜本的に改正され,従来,努力目標であった雇用率を法的義務にすると同時に,雇用率を達成していない企業から納付金を徴収し,これを基金として,障害者を雇用率以上に雇用している企業に対し,調整金,報奨金を支給するとともに雇用促進のための各種助成金を支給するというもので,現行法の基礎を築いた。
1987年,「身体障害者雇用促進法」が再び大改正され,「障害者の雇用の促進等に関する法律」と名称も改正された。この改正で,従来,身体障害者だけが雇用率の対象であったが,精神薄弱者も追加されることとなった他は,雇用促進措置の基本的内容は変わっていない。なお,大きな改正は,同法がすべての障害者を対象とする法律となったこと,従来からあった職業指導等の規定に加え,職業リハビリテーションに関する規定が大幅に盛り込まれたことである。
| - | 1960年 | 1968年 | 1979年 | 1988年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官公庁 | - | |||||
| - | 現業的 | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 1.9% | |
| 非現業的 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | ||
| 民間事業所 | - | |||||
| - | 純粋の民間 | - | ||||
| - | 現場的 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 事務的 | 1.3 | |||||
| 特殊法人 | - | |||||
| - | 現場的 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
| 事務的 | 1.5 | |||||
| 年 | 官公庁非現業 | 官公庁現業 | 純粋の民間事業所 | 特殊法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1977年 | 1.83 | 1.80 | 1.09 | 0.95 |
| 1978年 | 1.84 | 1.85 | 1.11 | 1.20 |
| 1979年 | 1.83 | 1.85 | 1.12 | 1.28 |
| 1980年 | 1.82 | 1.85 | 1.13 | 1.34 |
| 1981年 | 1.85 | 1.89 | 1.18 | 1.56 |
| 1982年 | 1.87 | 1.90 | 1.22 | 1.79 |
| 1983年 | 1.88 | 1.90 | 1.23 | 1.81 |
| 1984年 | 1.89 | 1.90 | 1.25 | 1.79 |
| 1985年 | 1.88 | 1.95 | 1.26 | 1.84 |
| 1986年 | 1.89 | 1.97 | 1.26 | 1.87 |
資料出所:労働省職業安定局調べ
(5) 事業主に対する雇用援護措置の充実
1967年,心身障害者雇用促進融資制度が設けられた。事業主が障害者を公共職業安定所から雇い入れる場合,その必要な住宅,福祉施設,作業施設および職業訓練施設等を建設あるいは改善する時,長期で低利の融資を行うものである。
1973年,心身障害者雇用奨励金の支給が開始されたが,1981年廃止され,特定求職者雇用開発助成金が代わって創設された。これは,新規雇用の障害者の賃金を補填する性格のものである。
1973年,障害者を20パーセント以上雇用する企業に対する減価償却の限度額の増額を始め,各種の税制上の優遇措置が取られるようになった。
1973年,心身障害者多数雇用事業所(モデル工場)に対する特別融資制度が設けられたが,1981年廃止され,納付金制度による重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金に引き継がれた。
1976年,身体障害者雇用促進法の改正により,納付金制度が創設され,障害者を雇い入れる事業主等に対する種々の助成金が設けられた。
(6) 障害者に対する就職援護対策
1960年,「身体障害者雇用促進法」の制定により,身体障害者に対する職場適応訓練が開始された。この職場適応訓練は,1967年,精神薄弱者に,1986年,精神障害者にも拡大適用されるようになった。
1961年,無利子で就職資金の貸付制度が開始された。
1963年,適当な保証人のいない身体障害者に対し,雇用促進事業団が身元保証をする制度が設けられた。
1968年,公共職業安定所に求職登録している身体障害者が自営するにあたって金融機関から融資を受ける場合,雇用促進事業団が債務保証を行う制度が設けられた。
1968年,公共職業安定所の紹介で就職する下肢・体幹・内部障害者のために通勤用自動車の購入資金の貸付制度が設けられた。その後,1973年には,視覚障害者のためのかなタイプライター,1974年には,下肢障害者用工業用ミシン,1976年には,下肢・体幹・内部障害者のための電動車いす,1982年からは上肢障害者のための通勤自動車,さらに1984年には,視覚障害者のためにワードプロセッサーおよび拡大読書器の購入資金の貸付にまで拡大されたが,1988年4月以降この制度は廃止された。
(7) 総合リハビリテーションの考え方の導入
従来は,職業リハビリテーションの中でも職業指導,職業訓練,職業紹介といった領域ごとに,一般対策の一部として考えられてきたが,障害者個々人が一貫した体系的,総合的なサービスを受けられるよう配慮する必要があることが認識され,医療,医学的リハビリテーションから一貫して,また,職業リハビリテーションの中でも一貫してサービスを提供する施設の建設が計画されるようになった。1979年,その第1号である国立職業リハビリテーションセンターが埼玉県所沢市に建設された。同センターは同一敷地内に設立されている厚生省所管の国立身体障害者リハビリテーションセンターと一体的な運営が行われている。すなわち,国立職業リハビリテーションセンターへ入所する身体障害者は,まず国立身体障害者リハビリテーションセンターへ入所し,必要な医学的リハビリテーション,日常生活訓練等を受けた後,国立職業リハビリテーションセンターで,職業評価,職業指導,職業訓練あるいは職業適応指導を一貫した流れの中で受けることができる。
類似の形をとった総合リハビリテーション施設として,1979年,総合脊損センター(福岡県飯塚市)が設立された。この施設は,脊損者のために治療から職業復帰に必要な訓練,職業指導を総合的に行う。また,1987年,国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県賀陽町)が設立された。同センターも,医学的リハビリテーションから,職業指導,職業訓練を一貫して行う。なお,1988年4月からは,各施設の職業指導部門は広域障害者職業センターとして,「障害者の雇用の促進等に関する法律」で位置づけられた。
2 現状
(1) 職業リハビリテーション制度の概要
日本の職業リハビリテーションに関連する法律は多く,各分野について,法令上の規定が相互に入り組んでいる。また,各法律を所管する官庁としては労働省が中心的役割を果しているが,厚生省,文部省なども関与している。
これら各法令のうち,基本的な法律は「障害者の雇用の促進等に関する法律」である。本法は,1960年「身体障害者雇用促進法」として制定された後,1976年,1987年の2回にわたり大きな改正が行われた。
本法では,職業リハビリテーションの推進に関する基本的規定とともに,「身体障害者雇用率制度」と「雇用納付金制度」を中心とする障害者の雇用促進制度が規定されている。
「職業能力開発促進法」は,国および地方自治体が行う公共職業訓練について規定しており,この法律に基づいて障害者職業訓練校が設置されている。なお,障害をもつ児童・生徒を対象とする職業教育については「学校教育法」に基づいて行われる。
「職業安定法」は,公共職業安定所において,特に障害者に対して職業指導を行うことを義務づけているほか,障害者の職業紹介も当所の業務として位置づけられている。
障害者が公共職業安定所の指導を受けたり,職業訓練を受講する場合には,「雇用対策法」または「雇用保険法」の規定により,所定の手当を受けることができる。また,障害者を雇用しようとする事業主に対しては,「障害者の雇用の促進等に関する法律」その他,これら二法の定めるところにより,各種の助成措置がとられる。
労働災害による傷害や疾病の防止については,「労働安全衛生法」による規制があり,また,労働災害により障害者となった者に対しては,「労働者災害補償保険法」により補償が受けられる。
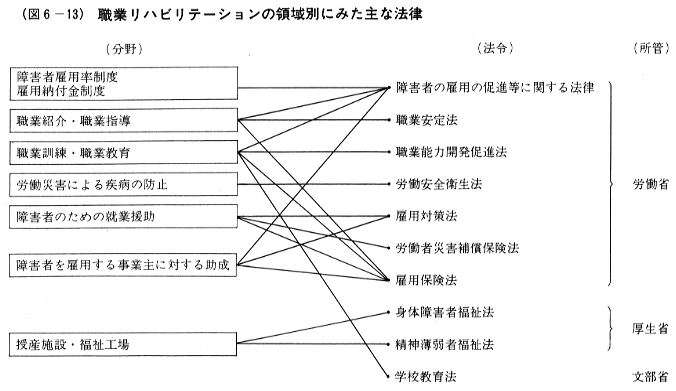
(2) 職業リハビリテーションの流れと関連主要施設
わが国の職業リハビリテーションに関連する機関・施設には,国立のもの,地方自治体が設立・運営するもの,法律により設立された特別の団体(雇用促進事業団,日本障害者雇用促進協会など)により設立・運営されているもののほか,民間団体や企業が運営している施設もあり,さまざまである。
これらの各機関・施設は,職業リハビリテーションの各分野の機能を分担している。各機関・施設相互間の分担関係あるいは連係関係ははなはだ複雑である。図6-14は主な機関・施設について,心身障害者が求職から就職に至るまでの過程を中心に相互の関係を示したものである。
なお,障害者の雇用促進および障害者の職業の安定に関する重要な事項を調査審議し,これらについて関係行政機関に意見を述べることができる「障害者雇用審議会」が労働省内に設置されている。当審議会の委員は,労働者代表,事業主代表,障害者代表,および学識経験者で構成される。
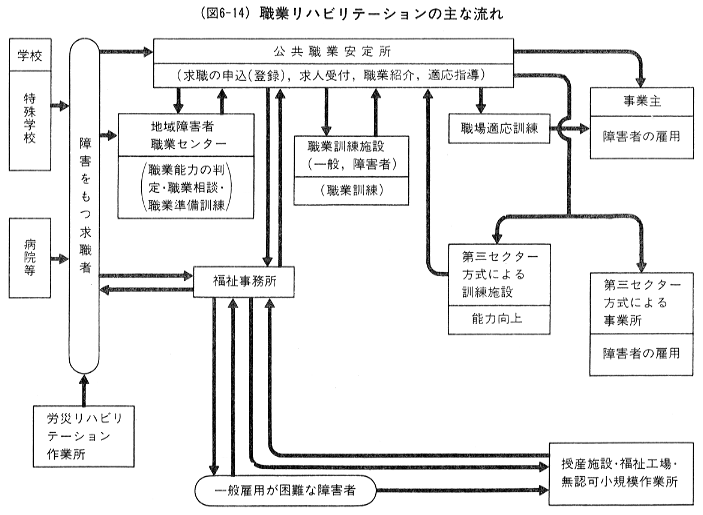
(3) 職業紹介・職業指導
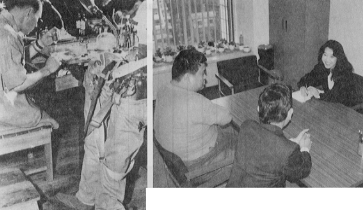
左は昔の神奈川の身体障害者公共職業補導所で義肢製作中の身体障害者。右は現代の職業相談風景。
1) 公共職業安定所でのサービス
公共職業安定所では,障害者に対してケースワーク方式によりきめ細かい職業指導,職業紹介,および,就職後の追指導を行うために,求職登録制度を採用している。すなわち,公共職業安定所の窓口で求職申し込みをした障害者はすべて登録台帳に記載され,本人の障害の状況,職業指導,職業紹介,就職等の経過が記録され,本人からの取り消し申し出がない限り,就職後も保存され,継続的にサービスが行われる。
公共職業安定所で職業指導を行うにあたっては,適性検査,職業指導等を特に専門的な知識および技術に基づいて行う必要があるときには,地域障害者職業センターにその実施を依頼するほか,自らも適性検査の実施,雇用情報の提供等,適切な職業指導を行う。
また,公共職業安定所では,障害者の雇用促進のため障害者の求職情報を収集し,事業主に提供したり,障害者雇用を勧奨するとともに,障害者に適した求人開拓を行っている。
これらのサービスを行うため,各公共職業安定所には障害者のための専門的な担当官として就職促進指導官が配置され,求職の受付,職業指導,紹介を行っている。また,雇用指導官は,主として障害者雇用促進のための事業所指導を行っている。
また,障害者の職業安定を図るために,雇用されている障害者に対して,必要な助言・指導を行ったり,事業主に対して,雇い入れ,配置,作業の設備・環境等の雇用管理に関する技術的事項についての助言指導も行っている。このために主要公共職業安定所に職業相談員が配置されている。
公共職業安定所では,職業訓練を希望する障害者に対する指導,指示,適応訓練へのあっせんなどの窓口としての役割も果している。
2) 地域障害者職業センターにおけるサービス
障害者の職業指導にあたっては,障害者の職業能力の評価・判定や,心理学などの専門知識に基づく職業相談が必要であり,そのために専門的資格を有する障害者職業カウンセラーを配置した地域障害者職業センターが全国に47ヵ所設置されている。
ここでは,公共職業安定所の職業紹介業務と密接な連携を保って,中度,重度の障害者を対象に,次のような業務を行っている。
- 障害者に対する職業評価,職業指導と職業相談
- 障害者に対する職業準備訓練
- 障害者に対する職業講習
- 事業主に対する障害者の雇用管理に関する助言その他の援助
これらの業務を行う障害者職業カウンセラーは,労働大臣が指定する試験に合格し,かつ,労働大臣が指定する講習を修了した者あるいは労働省令で定める資格を有する者とされている。
この地域障害者職業センターは,障害者の職業生活における自立を促進するため,「障害者の雇用の促進等に関する法律」により国が後記の日本障害者雇用促進協会に設置運営を行わせている。
前述の公共職業安定所との連携,協力が障害者の雇用の促進と職業の安定のために強く求められているところである。
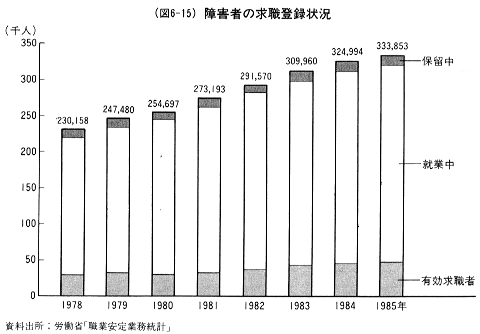
| 年 | 精神薄弱者 | 身体障害者 | 精神障害者・その他 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 6.295 | 7,384 | 1,198 |
| 1981年 | 8,303 | 10,488 | 2,038 |
| 1982年 | 11,792 | 19,436 | 4,481 |
| 1983年 | 11,860 | 21,755 | 5,547 |
| 1984年 | 11,901 | 26,440 | 4,352 |
| 1985年 | 12,649 | 32,101 | 5,284 |
資料出所:労働省「職業安定業務統計」
(4) 職業訓練・職業能力開発等
わが国における障害者の職業訓練は,国または都道府県が設置する障害者職業訓練校によるものが中心であるが,このほか,健常者と一緒に行われるその他の公共職業訓練施設での訓練,民間団体の行う訓練,さらに,学校教育の中で行われる職業教育(前章参照),福祉行政の中で行われる職能訓練等もあげられる。
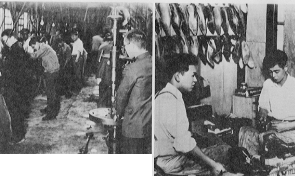
これは両方共啓成社における昔の職業訓練風景。
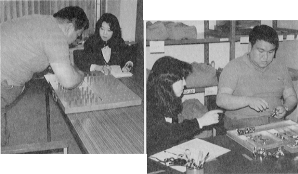
上は地域障害者職業センターにおいて職業適性のテストを受ける訓練生。下は同じく職業の評価テストを受ける訓練生。
1) 国等が行う職業訓練等
- 障害者職業訓練校
- 障害者の障害の程度や能力に応じて適切な職業訓練を専門的に行うため,国立都道府県運営11か所,県立6か所,国立で日本障害者雇用促進協会運営2か所,計19か所が設置されている。
これらのうち,精神薄弱者のための職業訓練校は1校で,精神薄弱者のための訓練科を設置しているものが3校あるほかは,身体障害者を主として対象としている。
訓練期間は,原則として1年であるが,訓練科によっては6か月,2年のものもある。
日本障害者雇用促進協会運営の2か所は,医学的リハビリテーションから一貫した総合的,統一的サービスを提供する施設として設立された国立の職業のリハビリテーションセンターの中に設置されている。すなわち,国立職業リハビリテーションセンター(所沢市)は,同一敷地内にある厚生省所管の国立身体障害者リハビリテーションセンターと連携をとって一体的な運営がされ,国立吉備高原職業リハビリテーションセンター(岡山県)は,隣接する医療リハビリテーションセンターと連携してサービスが提供されている。
公共職業安定所の指示で受講する者に対しては,訓練期間中,手当が支給される。手当の額は,地域および訓練の受講日数などの条件によって異なる。
- 健常者とともに行われる職業訓練
- 障害の程度からみて,障害を持たない人々と一緒に訓練を受けることが可能である場合は,都道府県または雇用促進事業団が設置する公共訓練施設を利用することが奨励されている。
- 精神薄弱者等職業準備訓練
- 精神薄弱者および精神障害者を中心とし,職場のルールに対する理解等の基本的労働習慣を確立させるため,地域障害者職業センターにおいて8週間の模擬的作業場での訓練を行う。1987年度から7年計画で全センターで実施する。
2) 民間団体・企業が行う能力開発訓練
- 職場適応訓練
- 都道府県が民間企業に委託して行うもので,障害者の職場環境への適応を容易ならしめるため,事業所内で実際の作業を行いながら訓練を受け,訓練修了後は引続き当該事業所に雇用されるものである。訓練は原則6か月(重度の場合1年)で,この間,障害者に対して訓練手当が,事業主に対しては委託費が支給される。
- 能力開発訓練事業
- 民間団体や企業が行う障害者のための訓練事業のうち,国の定める基準に適合するものについて,その訓練施設の設置に要する費用,訓練生の訓練に要する費用等を納付金制度により助成するものである。1987年現在,上記のとおり全国で12か所で各種の訓練が行われている。
3) 福祉行政の中で行われる職業訓練
厚生省所管の各種更生援護施設や病院などのリハビリテーション施設では,職業的能力に直接あるいは間接に関係ある訓練を行っている。
前述の職業訓練が,技能の習得に主眼を置いているのに対し,この訓練は,生活訓練や,職業生活への適応性を高める職能訓練,通勤手段の獲得のための自動車運転訓練,社会性の向上訓練等職業前訓練的な色彩が強い。
(5) 労働災害による障害者に対する補償
| 〈国立〉 | 北海道障害者職業訓練校 宮城障害者職業訓練校 東京障害者職業訓練校 神奈川障害者職業訓練校 石川障害者職業訓練校 愛知障害者職業訓練校 大阪障害者職業訓練校 兵庫職業訓練校 広島障害者職業訓練校 福岡障害者職業訓練校 鹿児島障害者職業訓練校 中央障害者職業訓練校(国立職業リハセンター) 吉備高原障害者職業訓練校(国立吉備高原職業リハセンター) |
|---|---|
| 〈県立〉 | 青森県立身体障害者職業訓練校 千葉県立身体障害者職業訓練校 静岡県立身体障害者職業訓練校 愛知県立春日台職業訓練校 京都府立城陽心身障害者職業訓練校 兵庫県立身体障害者職業訓練校 |
(表6-7) 能力開発訓練事業一覧表 (財)肢体不自由者職能開発センター
(福)日本ライトハウス職業生活訓練センター
*(福)アガペ身体障害者作業センター
(株)吉備NC能力開発センター
*(福)南高愛隣会
(財)東厚生会身体障害者運転能力開発訓練センター
*(福)あしたか福祉会 とおがさ作業所
(福)日本盲人職能開発センター
(福)大阪市障害厚生文化協会
心身障害者職業能力訓練センター
#長崎能力開発センター
#阪神友愛食品能力開発センター
#神奈川能力開発センター
注) *印は授産施設と企業との連携によるもの
#印は第三セクターによるもの
18歳以上の身体障害者のうち,労働災害による者は9パーセントを占め,事故による身体障害者ではもっとも大きい割合を示している。このような労働による災害や疾病の予防については,労働安全衛生法が定められ,厳しい規制が行われている。この結果,労働災害の発生件数は減少の傾向にあるが,なお年間2300人程度の死亡者と36万人に近い傷病者を出している。
- 労働災害による被災者に対する補償
- 不幸にして労働災害によって受傷して場合は,労働者災害補償保険法により補償が受けられる。この法律に基づき,労働災害による負傷・疾病の治療に要する費用,療養期間中の賃金に対する費用が支給されるほか,身体に障害が残った場合,その障害の程度に応じた補償として年金または一時金が支給される。
- 労災病院
- 労働災害による負傷・疾病の治療を目的として労災病院が全国に36か所設立されている。
- 総合脊損センター
- 労災等による脊髄損傷者のためには,治療から医学的リハビリテーションを経て,併設の脊損職業センターとの連携で早期社会復帰を図る施設として,総合脊損センターが飯塚市に設置されている。
- 医療リハビリテーションセンター
- 労災等により重度の外傷性の障害を受けた者等を対象に,高度な治療および医学的リハビリテーションを行い,併設の職業リハビリテーションセンターとの連携のものに早期社会復帰を図る施設として吉備高原都市(岡山県)に設置されている。
- 労災リハビリテーション作業所
- 労災により脊髄損傷あるいは両下肢に重度の障害を受けたものを対象にした労災リハビリテーション作業所が全国に8か所設置されている。ここでは,寮を付設し,作業を通じて社会復帰のための援助を行っている。
| 施設名 | 定員(人) | 作業品目 |
|---|---|---|
| 北海道 | 50 | 観光用熊の木彫り,縫製,バルク選別計量,ぬいぐるみ製作 |
| 宮城 | 50 | 電子部品配線・検査,製本 |
| 千葉 | 50 | 模型飛行機用送信機組立 ビデオカメラ用撮像管部品組立 カラーテレビ用部品の溶接・加工 |
| 長野 | 50 | マイクロモーターカーボンブラシ組立 35mmカメラシャッター部品組立 |
| 福井 | 50 | 自動車用ラジオ組立 |
| 愛知 | 50(30) | 自動車用バックブザー・チャイム組立 |
| 広島 | 50 | ステレオ・ラジカセ部品加工 各種マイクロメータ組立検査 |
| 福岡 | 50 | リレーソケット下組作業 製本 |
| 計 | 400(30) | |
資料出所:労働福祉事業団
(注)
- 入所者は,宿舎施設に居住することを原則としているが,本人の希望があり,かつ,作業所長が適当と認めた場合には通所も可能。
- 愛知作業所には,自動車教習所〔( )内はその定員〕を付設。
(6) 就職後のアフタケア
障害者の職業リハビリテーションの最後のサービスである就職後の職場への適応,職場での能力発揮と開発のためのアフタケアには,事業所内部での対応と,公共機関からの相談・指導がある。
- 障害者職業生活相談員の選任
- 障害者を5人以上雇用する事業所では,その従業員であって,労働大臣の行う資格認定講習を受けた者の中から障害者職業生活指導員を選任しなければならない。障害者職業生活指導員は,障害者が職場生活への適応力を高め,本人の能力を最大限に発揮させるよう職業生活に関する必要な相談,指導を行う。
- 障害者職場定着推進チームの設置
- 障害者を雇用する従業員300人以上の事業所においては,障害者の職場適応と定着が円滑に進められるよう,障害者職場定着推進チームの設置が奨励されている。このチームには,事業所の最高幹部,上記障害者職業生活指導員,事業所の管理職,生産現場の指導者および雇用されている障害者の代表などで構成され,公共職業安定所や日本障害者雇用促進協会と連携して活動することとされている。
- 職業相談員等の相談・指導
- 公共機関からの相談・指導としては,前述のように公共職業安定所や地域障害者職業センターからの援助がある。特に,公共職業安定所には身体障害者あるいは精神薄弱者に関する専門知識を持つ職業相談員が配置され,定期的に障害者を雇用する事業所を訪問し,事業主および障害者本人に対して相談,指導を行っている。
このほか,福祉行政の各障害者関係機関や施設,特殊教育諸学校や特殊学級においても,自らがサービスを行った障害者に対して,就職後,同様なアフタケアを行っている。
(7) 障害者雇用促進制度
1) 雇用率制度
日本における障害者雇用促進の中心は,雇用率制度と納付金・助成金制度にあるといってよい。雇用率制度は1960年に身体障害者雇用促進法の制定とともに導入されたが,この規定では単なる努力義務とされていたため障害者雇用の実効は上がらず,1976年の法改正によって雇用率の達成は事業主の法律上の義務とされ,同時に納付金・助成金制度が導入されたものである。
- 法定雇用率
- 障害者の雇用の促進等に関する法律」に定める身体障害者雇用率は表6-9のとおりである。
- 対象となる障害者
- 法律に定められた身体障害者であるが,1987年の改正により,精神薄弱者について特例が設けられ,精神薄弱者を雇用している場合には,その数だけ身体障害者を雇用しているとみなされることとなった。
- 除外率の設定
- 雇用率の算定にあたっては,身体障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種に対しては,除外率が設定されている。また,一定の条件を満足する子会社の雇用する労働者は親会社の労働者とみなして身体障害者雇用率を算定することができる。
- 重度障害者に対する特例
- 障害の重度な者の雇用促進を図るため,雇用率の算定にあたって,身体障害の程度が重い者については1人を身体障害者2人分としてカウントすることとしている。さらに,重度の視覚障害者についてはあんま・マッサージ・指圧師を雇用する事業所(病院等)に対して,70パーセント以上の雇用率を課している。
- 報告の義務
- 雇用率制の実効性を確保するため,事業主は毎年1回,自事業所の障害者雇用状況を公共職業安定所に報告しなければならず,また,公共職業安定所長は,法定雇用率に達していない事業主に対して身体障害者の雇い入れに関する計画の作成を命ずることができる。さらに,公共職業安定所長はこの雇い入れ計画の適切な実施について勧告を行うことができ,事業主が勧告に従わない場合は,その旨を公表し,社会的な制裁を加えることができることになっている。
| 国および地方公共 | 非現業的機関 現業的機関 |
2.0% 1.9% |
| 一般の事業主 | 民間の事業主 政令で定める特殊法人 |
1.6% 1.9% |
| 年 | 民間 | 特殊法人 |
|---|---|---|
| 1977年 | 52.8 | 26.9 |
| 1978年 | 52.1 | 33.7 |
| 1979年 | 52.0 | 35.9 |
| 1980年 | 51.6 | 37.0 |
| 1981年 | 53.4 | 48.5 |
| 1982年 | 53.8 | 72.9 |
| 1983年 | 53.5 | 79.4 |
| 1984年 | 53.6 | 76.3 |
| 1985年 | 53.5 | 82.3 |
| 1986年 | 53.8 | 83.5 |
資料出所:労働省職業安定所調べ
2) 納付金・助成金制度
障害者を雇用するにあたっては,作業設備や職場環境の改善,障害に応じた特別の指導・訓練など,健常者を雇用する場合に比較して経済的な負担を伴うことが多い。このため,雇用義務を誠実に履行している事業主とそうでない事業主との間の経済的負担を調整し,障害者の雇用促進を図るために,この制度が制定されたものである。したがって,この制度では,雇用義務を達成していない事業主から納付金を徴収し,これを基金として身体障害者を雇用している事業主に調整金,報奨金,助成金の形で還元するものである。
調整金,報奨金,助成金の内容は上記の図6-18のとおりである。
なお,この制度においても,精神薄弱者を雇用している場合には,その数だけ身体障害者を雇用しているとみなされて適用される。
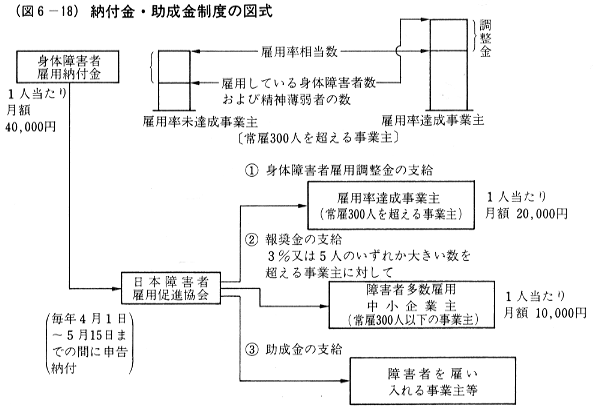
3) 日本障害雇用促進協会の役割
日本障害者雇用促進協会は,障害者の雇用の促進等に関する法律に基づいて設立された法人であるが,国の行う業務のうち,当協会に次の業務を行わせることが規定されている。
- 納付金の徴収,調整金・報奨金・助成金の支給等の納付金関係業務
- 障害者職業センター(障害者職業総合センター,広域障害者職業センター,地域障害者職業センター)の設置運営業務
- 障害者職業訓練校の運営業務
- 障害者職業生活指導員の資格認定講習に関する業務
上記の業務のほか,事業主に対する指導,研修,講習会の開催,調査研究,障害者雇用継続助成金の支給,身体障害者技能競技大会の開催等を行っている。
4) その他の助成・援助
- 事業主に対する助成
- 上記の納付金制度による助成金の他に,「特定求職者雇用開発助成金」と,「障害者雇用継続助成金」の給付がある。
「特定求職者雇用開発助成金」は,身体障害者または精神薄弱者を雇用した事業主に対し,雇用した障害者に支払う賃金の一部を補助するもので,一般の障害者には,雇い入れ後1年間,支払い賃金の2分の1(中小企業は3分の2)を,重度障害者には,雇い入れ後1年6か月の間,支払い賃金の3分の2(中小企業は4分の3)を助成するものである。
「障害者雇用継続助成金」は,雇用している労働者が障害者になった後においても,この障害者を一定期間以上継続して雇用する事業主に対し,雇用を継続するために必要な作業施設・設備の設置,改善のための費用ならびに職場適応措置の実施に要する費用について助成するものである。
- その他
- 障害者を雇用する事業主が,事業施設を設置したり土地を取得する場合,有利な条件で融資を受けられる。また,税制上のさまざまな優遇措置が適用になる。
(8) 一般雇用の困難な重度障害者に対する対策
一般雇用の困難な重度障害者に対する対策としては,身体障害者福祉法,精神薄弱者福祉法に基づいて設置された福祉工場,授産施設等の社会福祉施設における職業リハビリテーションがあげられる。
- 身体障害者福祉工場
- 重度身体障害者で作業能力はあるが,職場,交通環境のため一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え,健全な社会生活を営ませるため,1971年から設置されたもので,1980年までの10年間は急速に増加したもののその後はあまり伸びず,1984年現在21か所,1,060人の定員に留まっている。
- 精神薄弱者福祉工場
- 作業能力はあるものの,対人関係,健康管理等の事由により,一般企業に就労できないでいる者を雇用し,生活指導,健康管理等に配慮した環境下で社会的自立を促進するため,1985年度に制度化された。
- 身体障害者授産施設
- 身体障害者で雇用されることの困難な者または生活に困窮する者に必要な訓練を行い,かつ職業を与え自活させるために設置されたもので,収容させる施設と,通所の施設がある。1984年現在,収容施設は86か所,3,949人の定員に対し,通所施設は58か所,1,161人の定員で,最近は,通所の伸びが大きい。
- 重度身体障害者授産施設
- 重度の身体障害者で雇用されることの困難な者または生活に困窮する者を入所させて,必要な訓練を行い,かつ職業を与え自活させるための施設である。最近の障害の重度化を反映して急速に増加し,107か所,6,328人定員と身体障害者授産施設を上回った。
- 精神薄弱者授産施設
- 精神薄弱で雇用されることが困難な者に,自活に必要な訓練を行うとともに,職業を与えて自活させる施設で,収容施設が133か所,8,720人の定員,通所施設が205か所,7,060人定員となっており,身体障害者の場合と同様,通所施設の伸びが大きい。
- 無認可小規模作業施設
- これは現行の法制度によらない施設である。地域に施設がなかったり,障害が重いために既設の施設に入所できないものを対象に,障害者団体,親,教師等が中心に設立した施設で,その設立の目的,対象者等によってその内容が異なるが,職業的自立の困難な者が主たる対象のため,作業を通しての生活訓練,生活指導が多くなっている。財政的援助もきわめて少ないにもかかわらず,地域の重度障害者のニーズに対応して急速に増加してきており,その数は1987年現在約1,600前後に達すると推測される。
- 社会福祉事業法等による授産施設等
- 障害者を対象にした施設ではないが,社会福祉事業法や生活保護法に基づく授産施設や救護施設などにも,かなりの割合で身体障害者,精神薄弱者,精神障害者が入所している。

デンソウ太陽ではこのようにたくさんの身体障害者たちが働いている
(図表6-19) 授産施設等の施設数,定員の推移 (所)
| 年 | 身障授産 | 身障通所授産 | 重度身障授産 | 身障福祉工場 | 精薄授産(収容) | 精薄授産(通所) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 59 | - | 12 | 0 | - | - |
| 1975年 | 67 | 0 | 43 | 12 | 67 | 45 |
| 1980年 | 79 | 2 | 76 | 19 | 101 | 107 |
| 1985年 | 87 | 64 | 110 | 21 | 144 | 233 |
| 年 | 身障授産 | 身障通所授産 | 重度身障授産 | 身障福祉工場 | 精薄授産(収容) | 精薄授産(通所) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 3,142 | - | 735 | 0 | - | - |
| 1975年 | 3,647 | 0 | 2,436 | 635 | 4,463 | 1,472 |
| 1980年 | 4,104 | 165 | 4,848 | 1,055 | 7,004 | 3,711 |
| 1985年 | 4,479 | 1,485 | 6,713 | 1,215 | 9,352 | 8,132 |
資料出所:厚生省統計情報部「社会福祉施設調査」
3 将来展望
(1)技術革新と障害者雇用
マイクロエレクトロニクス(ME)を中心とした技術革新によって,産業用ロボットや各種オフィスオートメーション(OA)機器が生産現場や事務部門に普及しつつあり,これがいろいろな意味で雇用に影響を及ぼし始めている。
まだ,ME機器の導入を直接の原因とする離職者の発生はほとんどなく,全体として雇用者が減少したり,新規採用の抑制,配置転換の傾向がみられる程度である。
障害者も同様な影響を受けることになるが,障害の故に要求される新しい技能の習得が困難であったり,習得の機会が少なかったり,あるいは,配転等環境の変化に適応しにくいといったハンディキャップのため,一般労働者以上にマイナスの影響を受けやすいといってよい。
一方,ME化により,重筋労働や危険有害作業の減少,機器の監視作業の増大といった作業内容の変化や,先端技術を応用した各種作業機器や障害者のための補助具の開発により,従来困難とされていた作業を遂行できるようになるというプラスの影響も期待されている。
今後は,このようなマイナス面を最小限度にとどめ,プラス面を活用した対策が必要になるものと予想される。その中心となる対策としては,障害者に対する能力開発訓練,職種転換訓練を始めとする職業リハビリテーションの充実とともに,ME機器等の開発研究の推進にあると考えられ,労働省では1985年よりME機器の開発研究委員会を設けて研究中である。

障害者補助具のひとつ「国立職業リハビリテーションセンターで開発した弱視者用ディスプレイ文字拡大装置(PC-WIDE)」
| 計 | 危険有害作業が少なくなった | 重筋作業が少なくなった | 機器の維持・保守作業が多くなった | 機器の監視労働が増えた | 単純繰返し労働が増えた | 単純繰返し労働が減った | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (65.9)100.0 | 30.5 | 36.8 | 43.0 | 51.9 | 18.2 | 35.5 | 4.3 |
資料出所:労働省「技術革新と労働に関する調査」(1982年11月実施)
(注) ( )内の数字は,ME機器導入事業所で作業内容が「変化した」事業所の割合である。
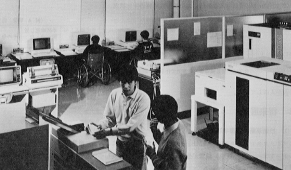
|
|
| 企業の近代化によって作業形態も大きく変貌しつつある。したがって職業にたずさわる者は障害者といえどもこれに対応せざるを得ない。写真は国立職業リハビリテーションセンターにおける訓練風景。上は電子計算科,右は機械製図科である。 |
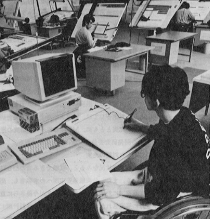
|
| 機器による負傷の発生は増えるか減るかどちらともいえない | 39.1% |
| 労働密度,労働者の精神的負担は高まる | 86.6% |
| 不適応者の発生は増える | 83.7% |
| 職務内容は高度化する層と単純化する層に二極分化する | 91.5% |
| 職場の人間関係は希薄化する | 70.9% |
| 労使間の摩擦は増えるか減るかどちらともいえない | 60.3% |
(注) 2回行ったうちの第2回目調査
資料出所:労働大臣官房政策調査部編「2000年の労働」
(2)障害の重度化に対応した対策の充実
特殊教育諸学校の卒業生の就職状況をみると,就職できる者の割合は年々減少しており,一般雇用の困難なものが増加している。また,公共職業安定所への求職者も,高齢化・重度化の傾向が強くなっており,これらの重度障害者に対するサービスの強化が今後さらに重要な課題となってきている。労働省では,1982年3月に策定された「障害者対策に関する長期計画」に基づき,重度障害者対策に取り組んできている。その主たるものとしては,地方公共団体と民間企業との共同出資による「第三セクター方式による重度障害者雇用企業等の育成」と,企業と授産施設が協力して,当該施設に入所の重度障害者に対して能力開発訓練を行う「授産施設と企業の連携による重度障害者等特別能力開発訓練事業」をあげることができる。第三セクター企業は,1983年から11都府県が労働省から指定を受け,現在までに4企業の設立をみたところであるが,すべての都道府県での設立を目標にしているところから,今後その数の増大が期待される。後者は,1982年から制度化され,現在3か所で実施されているが,修了生の就職率も80パーセント弱と高い実績を示し,今後さらに増設されることが期待されている。また,地域障害者職業センターで行う職業準備訓練も1987年度の6センターから全センターへの拡大充実が期待される。さらに,一般の雇用形態の多様化を反映して,重度障害者を含め,障害者のパートタイム,在宅雇用等の増加が予想される。これらの重度障害者雇用対策によっても一般雇用の困難な重度障害者はなお増加していくと予想される。これらの障害者に対しては,福祉的就労の場である授産施設の増設で対応することとなるが,近年,地域社会に生活しながら通所する通所授産施設の増加とともに,無認可小規模作業所がますます増加するものと思われる。
| - | 就職者 | 無業者 | |
|---|---|---|---|
| 中学 | 盲学校 | 8% | 92% |
| ろう学校 | - | 100% | |
| 養護学校 | 3.82% | 96.18% | |
| 高校 | 盲学校 | 60.30% | 39.70% |
| ろう学校 | 89.42% | 10.58% | |
| 養護学校 | 35.81% | 64.19% | |
(注) 卒業者のうち,進学者,職業訓練機関等への入学者,死亡者等を除外した者を100%とした。
資料出所:文部省「学校基本調査」
(3)研究の充実と専門職の養成
近年,障害の重度化,産業構造の変化等により,障害者の雇用をめぐる情勢は一層きびしさを増しており,これに対処するためには,上記のような対策とともに,高度な知識と技術に支えられた職業リハビリテーションサービスの提供がますます重要である。そのためには,職業リハビリテーションに関する研究開発の充実と,職業リハビリテーションサービスに当たる専門職の質的向上を図ることが先決である。
労働省では,1991年開所を目標に,障害者職業総合センターの設置を計画中である。構想によると,ここでは,障害者の職業適性,職業相談・指導,職業適応に関する研究を始め,各種職業評価技法の開発,職業リハビリテーション機器の開発,障害者の職域拡大のための職務再設計等の研究を行うとともに,職業リハビリテーションサービスに従事するカウンセラー等の養成研修を行うことになっている。
主題:
日本のリハビリテーション No.7
121頁~150頁
発行者:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
編集:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
発行年月:
1992年8月31日
文献に関する問い合わせ先:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162 東京都新宿区戸山1-22-1
電話 03-5273-0601
FAX 03-5273-1523
