日本のリハビリテーション No.1
(財)日本障害者リハビリテーション協会
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発表年月日 | 1992年8月31日 |
| 備考 | 発行者 (財)日本障害者リハビリテーション協会 日本のリハビリテーション No.1 1頁~32頁 |
序言
- このたびアジアではじめてのリハビリテーション世界会議が,東京で開催されることになったが,本書は,同会議を機会に第2次世界大戦後のわが国における医学から職業にわたるリハビリテーション各分野の動向について,各国関係者に紹介することを目的にまとめられたものである。
実は,わが国初のリハビリテーションに関する国際会議ともいうべき,第3回汎太平洋リハビリテーション会議が,1965年に東京で開催された際にも,今回と同じ標題の資料が出されているが,それと本書を読みくらべると,過去20余年間にわが国のリハビリテーション制度が,国民の意識や国の財政事情の好転によって,いかに大きな発展を遂げたかがわかる。とくに,国際障害者年を契機とするリハビリテーションをめぐる展開には,目をみはるものがある。
もっともその反面,1965年当時課題とされていたこと―たとえば,地域社会における一貫したリハビリテーションサービスの供給システムの確立およびリハビリテーション専門職の養成等―がいまだ解決をみていないことに加え,障害者の高齢化・重度化,さらには技術革新等による産業構造の変化等に伴う,新たな問題が発生してきていることもまた事実である。
本書は,一般市民を対象とした対策との関連を踏まえながら,リハビリテーション各分野の戦後の展開を紹介することを編集方針とし,各リハビリテーション分野で活動される多数の方々にご協力を頂いたが,とくに次の方々に多大のご尽力を賜わった。 - (敬称略)
星野侃司 (日本児童問題調査会) 河野康徳 (厚生省社会局更生課) 佐藤久夫 (日本社会事業大学) 二木 立 (日本福祉大学) 小鴨英夫 (淑徳大学) 高木美子 (国立職業リハビリテーションセンター) 大野智也 (日本障害者雇用促進協会)
ご多忙にもかかわらず,本書の刊行にご尽力くださったこれらの執筆者の方々に対してお礼申し上げる次第である。
また,第16回リハビリテーション世界会議組織委員会広報委員長である松井亮輔氏には本書の企画および編集にお力添えを頂いた。なお,本書は英語版でも刊行されているので,あわせてご利用いただければ幸いである。英語版の編集に当っては,用語のチェック等奥野英子氏(国立身体障害者リハビリテーションセンター)に御協力を頂いた。記して厚くお礼を申し上げる。
本書で明らかにされたわが国のリハビリテーション分野での経験が,各国,とくに開発途上国が今後リハビリテーション対策をすすめる上で,参考になれば幸いである。
おわりに,本書の刊行についてご助成いただいた財団法人三菱財団に対して,心から感謝申し上げたい。
改訂版発行にあたって
本書発行から4年が経過し,9月にはケニアのナイロビで第17回リハビリテーション世界会議が開催されることになった。1992年は「国連・障害者の十年」の最終年であり,世界各地で10年間の評価と今後の方向性について論議されている。わが国でも1990年に身体障害者福祉法が改正され,福祉サービスの市町村への移譲という大きな変革期を迎えている。
改訂版では,身体障害者福祉法の改正について,植村英晴氏(厚生省社会・援護局更生課)にご執筆いただき,巻末に追録として掲載した。また英語版編集にあたっては,馬橋由美子氏にご協力いただいた。深くお礼申し上げる。
1992年8月
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
会長 太宰博邦
目次
序言
太宰博邦
第1章 日本の現状
1 はじめに
2 国土
1.絶対的制約
2.自然の恩恵
3.自然の試練
3 国民
1.同質性と定着性
2.言語
4 政治
1.日本国憲法
2.議会民主制
3.明治以降の政治動向
4.活力ある福祉国家
5.国際貢献(“ODA”など)
6.地方自治
5 産業・経済
1.産業社会から情報社会へ
2.貿易
3.財政
4.国民生活
6 文化
1.独特な文化の形成
2.文化史の概要
3.教育
4.信教
5.日本人論
7 むすび
第2章 日本の障害者
1 概要
2 18歳以上の身体障害者
3 18歳未満の身体障害児
4 精神障害者
5 慢性疾患者
6 おわりに
第3章 日本のリハビリテーション
1 リハビリテーションの展開
1.第二次世界大戦前の状況
2.リハビリテーション対策の発足
3.リハビリテーション対策の拡充
4.リハビリテーション対策の近年の動向と課題
2 日本のリハビリテーションの現状
1.心身障害者対策基本法
2.リハビリテーションのための主な法律・制度の一覧
3.政府の各省庁が行っているリハビリテーション対策
4.障害の種類(タイプ)とリハビリテーション対策の対象
3 将来展望
1.政府の「後期重点施策」の概要
2.地方自治体における今後の重点施策
3.障害者団体の後期重点要望項目
第4章 医学的リハビリテーション
1 日本の医療制度の概要
1.医療供給制度の概要
2.医療関係者の概要
3.医療保障制度の概要
2 医学的リハビリテーション
1.戦後の歩み
2.現状
3.将来展望―高齢化社会での「早期リハビリテーション」
第5章 教育リハビリテーション
1 日本の教育制度の概要
1.学校教育
2.各学校段階別の進学過程
3.社会教育
4.教育の量的現状
5.幼稚園、小学校、中学校および高等学校における教育内容
6.日本における最近の教育改革の動向
2 教育リハビリテーション
1.戦後の歩み
2.現状
3.将来展望
第6章 職業リハビリテーション
1 日本の職業能力開発・雇用制度の概要
1.制度の背景
2.障害者対策に関連する労働行政の組織と主管業務
2 職業リハビリテーション
1.戦後の歩み
2.現状
3.将来展望
第7章 社会リハビリテーション
1 日本の社会保障・社会福祉制度の概要
1.社会福祉以外の社会保障制度
2.公的扶助と社会福祉制度
2 社会リハビリテーションの現状
1.所得保障
2.住宅・日常生活用具
3.障害者のための社会福祉施設
4.在宅障害者の介助サービス
5.障害者の社会参加のためのサービス
第8章 障害者運動―障害の種類別主要団体の動向
1 第2次世界大戦後の障害者運動の始まり2 障害別団体の結成3 養護学校義務制実現への運動4 公害と障害者運動5 障害別親の会の誕生6 施設収容から地域ケアへ7 生活と権利を守る運動へ8 働く権利の保障へ9 障害者の自立へ向けて10 国際障害者年日本推進協議会追録 身体障害者福祉法の1990年改正について
★写真提供者一覧
第1章 日本の現状
1 はじめに
それぞれの国にはそれぞれの誇るべき文化がある。日本も同様であり,何千年もの間にこの国土に独特の文化を培ってきた。風土や住民などの自然の設定の上に,政治や産業などの人為的与件が働いて,今日の日本文化が形成されてきた。短い紙面ではあるがそのひとつひとつの制約が,この国の現状にどのように影響しているかを福祉にかかわる大方の皆様の関心に配慮しつつ大観してみたいと思う。
日本人の中には,この文化の独自性(ユニークネス)をことさらに強調する人がいる。しかし明治開国以来の幾多の試練によって,日本の歴史は大いに変わったし現に変りつつある。日本の歴史はこの独自の文化と外来文化とのたびたびの出会いで彩られており,今後もまた同じ道を辿るであろう。
日本には確かに独持の言語があり,風俗があり,政治体制がある。古来,直接・関接に大陸文化の影響をうけ,明治以降は急速に西欧の文化に触れたが,独自の文化をかなり根強く保ちえたのは何故だろうか。まず独特な国土の位置が関係する。同じくユーラシア大陸の東端と西端に位置しながら,英国を大陸から僅かに隔てているドーバー海峡に比べて,日本の朝鮮海峡の場合はその約5倍の距離があり,この微妙な差が一つの自然の障壁となったかの如くである。第二に人為的な与件としては,かの大航海時代以降植民地争奪につながる動乱の近世を通じて,その大半をかたくなに国を鎖し続けた特異な歴史的事実がある。
以上の主題,独自文化と外来文化の二元性を中心として,日本の現状を考えてみたい。
2 国土
1 絶対的制約
日本人は小国意識から抜けきれないといわれる。いやという程に世界の大勢を知らされた明治以降,特に第二次大戦後の40年間は,この傾向が著しかった。戦争直後の飢餓状態が,食糧・資源の不足に対する強迫観念を国民全体に植えつけたためと思われる。
国土の狭小に加えて居住面積も,欧米各国に比して恵まれず(図表1-1),兎小屋といわれる住居はいわずもがな,国民一般のストックは相変わらず低水準で,今直ちに“経済大国としての自覚と責任をもて”といわれても,実感が伴わない。むしろ,後述のごとく,マクロ(国家レベル)の好況とは裏腹に,ミクロ(企業や家計)は,円高に苦しみ,将来に不安を感じ,政府の内需振興のかけ声にもかかわらず,古諺通り“勝って兜の緒を締め”て“財テク”に走り,利殖に励んでいるのが実情で,節約の比率もさほど下らない。
| - | 居住地域(平方キロメートル)に対する人口密度(人) | 居住地域(平方キロメートル)に対するGNP |
|---|---|---|
| 日本 | 1,500 | 16.5 |
| 西ドイツ | 383 | 3.9 |
| イギリス | 362 | 2.9 |
| フランス | 163 | 1.5 |
| アメリカ | 52 | 0.9 |
資料出所:「統計月報」国土地理院
2 自然の恩恵
上記の地理的制約にもかかわらず,自然の恵みは豊かである。まずは気候である。日本は温帯圏に南北に連なる列島で,(主として以下の四島から成り,その面積比は四国を1とすると,おおむね,九州は2,北海道は4,本州は12である),冬の寒さ,夏の暑さは辛うじて凌ぎうる程度といえるし,降水量には特に恵まれている。(図表1-2)
自ら海国日本を名乗る通り,四面海に囲まれて,黒潮(暖流),親潮(寒流)の出会う沿岸の海域は,良い漁場となっている上に,海は原・燃料輸入の天然の経済的な輸送路を形成し,わが国の経済発展に大きく寄与してきた。古来主導的に,機を選んで大陸文化を摂取できた反面,大陸からの侵攻を,13世紀後半の蒙古襲来の一時期を除き,免れることができたのもこの海のおかげである。
以上の自然の恵みが,国民性に及ぼした影響も看過できない。日本の四季は明確に区別でき,ひとつひとつの季節の中ですら早い晩いの微妙な季節感の差異を感じとることができる。このような独特の季節感を季語として句中に読みこむことが,俳句(17音よりなる日本独特の短詩)のルールになっているが,今や日本人はいくばくかの余暇をえて,一億文人とでもいおうか,自然を賞でて俳句をたしなむ人がめっきりふえた。季節感は食物の嗜好においても顕著で,それぞれの季節にはその初物が珍重されるが,このような食生活の季節感も最近の通年の温室栽培や,魚介の養殖で失われつつあることは否めない。
(図表1-2) 気候の数字的比較
|
|
|
資料出所:東京天文台,「昭和61年理科年表(1986科学年表)」丸善
| - | 名称 | 地域 | 死者及び行方不明 | 倒壊家屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1934.9.21 | 室戸 | 日本全土 | 3,066 | 475,634 |
| 1945.9.17 | 枕崎 | 西日本及び関東 | 3,756 | 446,897 |
| 1959.9.26 | 伊勢湾 | 中部 | 5,041 | 567,713 |
| 発生日 | 場所 | 死者 | 行方不明 | 倒壊家屋 |
|---|---|---|---|---|
| 1923.9.1 | 関東 | 99,331 | 43,476 | 702,495 |
| 1933.3.3 | 三陸# | 3,008 | - | 6,404 |
| 1945.1.13 | 三河 | 1,962 | - | 33,824 |
| 1948.6.28 | 福井 | 5,168 | - | 85,445 |
#:地震及び津波
3 自然の試練
このような自然も時折は苛酷である。毎年秋になると訪れる台風と洪水はその一例である(表1-1a)。別の試練は,火山国の特徴としての噴火と地震であろう(表1-1b)。1986年末には,東京の西南110キロの伊豆大島の三原山火山が噴火し,その住民1万人が本土に緊急避難した。また東京は,60年サイクルで大地震に見舞われる運命にあり,1923年の関東大地震は,火災発生により大災害となった。地震の予測も進みつつあるし,耐震耐火の建築も普及しつつあるが,東京から東海地方の住民にとっては,年中行事の台風とは異なり,地震サイクルの到来は,今や現実の悪夢と化しつつある。
3 国民
1 同質性と定着性
日本の原住民については,8世紀の日本最古の史書,古事記や日本書紀にも神話時代の記述があるが,中国にも日本人についての歴史的記述があり(3世紀の“魏志倭人伝”),学界は勿論,素人史家たちの間でも興味ある話題となっている。何れにせよ,南方アジア,朝鮮半島,北方大陸からいろいろな種族が,有史以前に日本列島に住みついて,4世紀頃天皇家の祖先である大和朝廷に統一されたものと思われる。中国,朝鮮半島経由の異民族の渡来は,その後も6~7世紀頃まで続き,渡来人とともに大陸文化が活発に輸入された。日本民族の純血と,その同質性を強調することは,奈良・平安以降についてはおおむね妥当するが,それまでは,この国土が多種族の住居であったことは疑いない。
同質性を意識し合うことは,国土への定着性を助長し,真の国際人に成長できぬ一理由ともなってきた。国土に対する愛着,同質を強調する仲間意識は美徳であるかも知れぬが,殻にとじこもろうとする偏狭な国家意識は反省しなければならない。日本人の帰巣本能も,とかく批判の対象となる。年金生活者を物価の安い外国に定住させようとする通産省の“シルバー・コロンビア計画”も,大勢としての国民の本土定着性を克服するには時間を要しよう。在日外国人に比して,在外日本人の数は遥かに少ないのである(表1-2a,b)。
もっとも,戦後は世代がかわり,西欧の音楽,古典舞踊,服飾デザインなどの分野においてすら日本人の世界的指導者が輩出しており,さらに“新人類”(ニュー・スピーシス)と称せられる若年層は,今や同質性にも定着性にも無頓着で,ある意味では真の国際人に育ちうる素地が生れつつあるともいえよう。
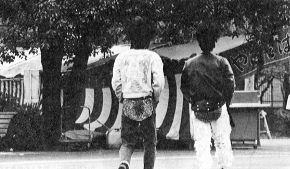
従来の価値観,行動様式,言葉づかいなどにはいっさいこだわらず,自分を対象化し演技化できる若者たちを新人類と称しているが,もちろんどこからが新人類かという線引きはしにくい。仕事や勝負には熱中するという精神主義をもち,パソコンなどのメカには皮ふ感覚的に受けつけるという,生まれながらのメカ感覚ももっている。
| - | 邦人数(1,000) | 割合(%) |
|---|---|---|
| アジア | 58.4 | 12.2 |
| オセアニア | 9.5 | 2.0 |
| 北アメリカ※ | 165.3 | 34.4 |
| 中央アメリカ | 5.3 | 1.1 |
| 南アメリカ | 154.5 | 32.1 |
| 西ヨーロッパ | 68.1 | 14.2 |
| 東ヨーロッパ | 2.1 | 0.4 |
| 中東 | 9.8 | 2.0 |
| アフリカ | 7.7 | 1.6 |
| 合計 | 480.7 | 100.0 |
資料出所:外務省「海外在留邦人数調査統計」,1986
注:長期滞在者及び永住者を含む
※にはハワイ,グアムを含む
| - | 登録者数(1,000) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 韓国及び北朝鮮 | 683.3 | 80.3 |
| 中国 | 74.9 | 8.8 |
| アメリカ合衆国 | 29.0 | 3.4 |
| フィリピン | 12.3 | 1.4 |
| イギリス | 6.8 | 0.7 |
| 西ドイツ | 3.0 | 0.4 |
| インド | 2.5 | 0.3 |
| フランス | 2.4 | 0.3 |
| オーストラリア | 1.8 | 0.2 |
| その他 | 34.6 | 4.2 |
| 合計 | 850.6 | 100.0 |
資料出所:総理府行政管理局「日本の統計」1986
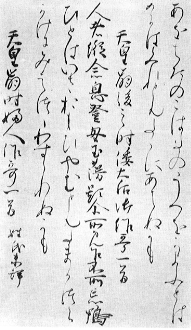
日本の文字は,最初は移入された漢字のみであったが,漢字のみでは日本語の表記に不便であったので,のちに漢字を極度に簡略化して日本独自のかな文字を発明した。現存する日本最古の史書である『古事記』をはじめ,『日本書記』や『万葉集』にも多くのかな文字が記されている。写真は万葉集諸本のうちの「金沢本」の一部分である。〈平凡社「世界大百科事典」万葉集〉より
2 言語
上記の同質性と定着性を支えているのが日本語の特殊性であり,日本文化の特異性の根因ともなっている。日本語の由来については,いまだ定説があるとは思われない。中国は“同文同種”の国といわれているが,古来表音上漢字を借用してきただけで,言語的には,中国語は英語以上に異質とする説もある。現在も短歌(俳句とならび,三十一音の伝統的短詩)をたしなむ者が範としている万葉集は,紀元770年の編集であり,歌集としては最古のもので,表音は漢字を借用しているが,内容は素朴雄渾で,現在でも万人に親しまれている。11世紀初頭の源氏物語も,女流作家紫式部によって“ひらがな”(日本独特のアルファベットで,9世紀中葉から用いられた)で著わされたものであるが,古来読み親しまれてきて,その心理描写など現代でも殆んど異和感がない。このように,文化の粋として誇るべき日本語ではあるが,問題はその特殊性であり,日本人と他の国際社会を隔てる大きな壁となっている。
近時日本語の習得は,外国人にとっても重要な課題となっており,日本語学校及びその教師は,内外に数を増しつつあるが,異質な言語だけに完全な習得は外国人にとって容易ではない。国際社会における日本人の疎外感,日本文化の孤立性は,コミュニケーションの手段である日本語の特殊性によって増幅されている。しかし,この解決には安易な近道があるとは考えられない。むしろ,日本の側から何とか外国語をマスターして,日本文献を翻訳紹介するなどのまともな努力が今後ともに必要であろう。
4 政治
1 日本国憲法
戦後の新憲法は,1947年5月3日施行され,1987年に40周年を迎えるに至り,ようやく国民の間に定着した感がある。戦後政治の動向が,極めて流動的であっただけに,この基本法に対する国民の関心も意外に深く,憲法の解説書がベストセラーの一つであった時期もある。
もっとも,憲法擁護論があると同時に,改憲論もにぎやかである。しかし,日本国憲法は,改正手続上,国民投票に付することが定められており(いわゆる硬憲法),当面は国民の支持も厚いようであるから,極めて流動的な世界の動向からみて,日本の将来を卜する上で最も信頼のおける指針は,この憲法かもしれない。ここに詳しく検討するゆえんである。
改憲の論拠は,戦後の新憲法が占領軍によって押しつけられたものだとする国民感情論が主となり(“自主憲法の制定”が合言葉である),実際には,新憲法の主眼である“象徴天皇”“戦争放棄”などの基本問題に触れているもの(場合によっては現行憲法による改正の限界をこえる),立法府の簡素化(例えば一院制の実施)など技術的側面に留まるもの(通常の改正手続で可能)などがあるが,当面国民の支持がえられそうもないとの理由で,緊急の課題である防衛力増強などは,すべて解釈問題としてわり切り,当分改憲には触れたくないというのが,与党の立場と思われる。(反対党は,圧倒的に“平和憲法”の支持者が多い)
元来新憲法の素案は,占領軍によって与えられたものかも知れぬが,1946年の憲法議会が合法的な改正手続に則って議決したもので,形式的にも実質的にも当時の国民の意思に反して押しつけられたものとはいえない。また現行憲法の内容は,敗戦・占領という非常の事態がなければ,自主的にこのような民主的な内容を盛りえたか否か疑問な程に今においても進歩的である。以下,その特色を拾って,論点を整理する。
第一に象徴天皇の問題であるが,天皇ご自身“日本国と日本国民統合の象徴”として日夜ご精励になっているし,そもそも天皇の歴史上の地位は,永い摂関政治と武家政治の中で特定の一時期を除き,明治までは象徴的なものに過ぎず,現行憲法はこれを追認しただけのもので,圧倒的な国民の支持もうけている。(図表1-3)
第二の戦争放棄は,現行憲法の最大特色で,平和憲法と呼ばれるゆえんであるが,それだけに最も議論の存する所である。自衛隊の創設については,80パーセント以上の国民支持があり(関1-4),自衛力増強の問題も現在の慎重なペースが国民の支持をうけている模様である。理想と現実の狭間にあって,時の経過とともに,国民の合意がこの辺に定着しつつあるのであろうか。
| 現行制度を支持する | 84 |
|---|---|
| 現行制度は廃止すべき | 9 |
| 天皇の権限を増大すべき | 4 |
| その他,わからない | 3 |
資料出所:朝日新聞,1986.4.7
| - | 必要 | 不要 | わからない |
|---|---|---|---|
| 1972年11月 | 73.2 | 11.7 | 15.1 |
| 1975年10月 | 79.6 | 7.8 | 12.6 |
| 1978年12月 | 85.6 | 5.3 | 9.1 |
| 1981年12月 | 81.7 | 7.9 | 10.4 |
| 1984年11月 | 82.6 | 7.5 | 9.9 |
資料出所:総理府「自衛隊,防衛問題に関する世論調査」
| 上 | 0.2% |
|---|---|
| 中の上 | 6.4% |
| 中の中 | 51.8% |
| 中の下 | 29.4% |
| 下 | 8.6% |
| わからない | 3.6% |
資料出所:経済企画庁
第三の基本的人権の保障は,生存権,労働権,男女平等権など,国民生活の質的向上と平等社会の実現に寄与しており,国民の90パーセントまでが中流以上という意識を持つに到っている。(図表1-5)
問題は,このような平等社会が,最近の円高異変,貿易黒字,不動産・証券騰貴などを契機として,大きく揺れ動いており,社会的な不平等(製造業と非製造業,実業と虚業の格差拡大)を招来しつつあるのではないかという懸念と,憲法前文にいわゆる“いづれの国家も,自国のことのみに専念して他国を無視してはならない”という理念が,日本の国際活動において守られているか,果して日本は“国際社会において,名誉ある地位を占め”ることができるのかなどという深刻な反省であろう。要は改憲ではなく,憲法精神の遵守であるといっても良いであろう。
2 議会民主制
日本の議会民主制は,英国を模したものであるが,最大の問題は反対党が脆弱で,与党自由民主党に対して,常時交替の態勢にあるとはいいえない事情である。実績から見ても,主たる反対党である日本社会党が政権を握ったのは,戦争後間もないごく短期間にすぎない。英国の保守党と労働党,米国の共和党と民主党のごとき堂々たる対立があってこそ,議会政治の花は開くのである。
目下の課題は,人口の都市集中に伴い,議席の配分が,都市に薄く,過疎地域に厚くなっており,抜本的な選挙区の議員定数是正が憲法上も要請されており,第2点としては,参議院の存在意義を問う意見もボツボツ浮上し始めたことなどである。行政制度は,“小さい政府”を目指して,その効率化が図られつつあるが,立法府は,参議院のみならず,衆議院も,議席定数削減ないし審議の効率化などが問われている。最近の衆議院における各政党の消長は表1-3の通りであるが,与党自由民主党も多くの派閥をかかえ,その勢力も登りつめた感がある。
| - | 自民党 | 社会党 | 公明党 | 民社党 | 共産党 | 新自由クラブ※ | 諸派 | 無所属 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972年12月10日 | 271 (46.9) |
118 (21.9) |
29 (8.5) |
19 (7.0) |
38 (10.5) |
- | (0.3) |
14 (5.0) |
491 (100) |
| 1976年12月5日 | 249 (41.8) |
123 (20.7) |
55 (10.9) |
29 (6.3) |
17 (10.4) |
17 (4.1) |
0 (0.1) |
21 (5.7) |
511 (100) |
| 1979年10月7日 | 248 (44.6) |
107 (19.7) |
57 (9.8) |
35 (6.8) |
39 (10.4) |
4 (3.0) |
2 (0.8) |
19 (4.9) |
511 (100) |
| 1980年6月22日 | 284 (47.9) |
107 (19.3) |
33 (9.0) |
32 (6.6) |
29 (9.8) |
12 (3.0) |
3 (0.9) |
11 (3.5) |
511 (100) |
| 1983年12月18日 | 250 (45.8) |
112 (19.5) |
58 (10.1) |
38 (7.3 |
26 (9.3) |
8 (2.4) |
3 (0.8) |
16 (4.9) |
511 (100) |
| 1986年7月6日 | 300 (49.4) |
85 (17.2) |
56 (9.4) |
26 (6.4) |
26 (8.8) |
6 (1.8) |
4 (1.0) |
9 (5.8) |
512 (100) |
注:カッコ内の数字は得票率
※新自由クラブは1986年8月に解散。衆議院の5人は自民党に入党。
3 明治以降の政治動向
明治維新以降今日までの120年(1868-1988)を,約40年ごとに3期に分けてみると,その各時期のマクロの国家指標(グランド・デザイン)が,以下のごとく鮮明になる。
- 明治維新から日露戦争まで(1868-1905)。これは,いわゆる“富国強兵”の時期である。
- 日露戦争から第二次大戦終結まで(1905-1945)。これは,“軍国主義”によって政治が偏向された時期である。
- 第二次大戦終結から,最近の大幅黒字定着まで(1945-1988)。これは“経済再建”の時期である。
以上のマクロ指標の評価は一先ずおくとして,現時点のわれわれの課題は,次の40年間のマクロ指標を見出すことであろう。もちろん,それが従来のように鮮明なものでないことも,日本の民主国家の成熟度よりして当然であろう。
しかし,憲法の条項で触れた前文の精神を今後の40年間に21世紀にかけて実現していくことは,国民のかくれた総意であるに違いない。あえてそのようなグランド・デザインを例示するとすれば,国内的には,“活力ある福祉国家”の実現であり,国際的には,経済大国にふさわしい人的・物的の“国際貢献”ではあるまいか。
4 活力ある福祉国家
福祉国家といっても,この狭い国土で1億2千万人もの人間が肩をよせ合って生きていかねばならない日本と,その1.2倍もの国土で,僅々800万人の人間が生活を享受しているスウェーデンとでは,個人個人に対する眼の配り方は自ら異なるであろう。日本は,最近ようやく福祉のメニューが出そろった所で,政治の分野でも,国民意識の上でも,今後この分野で世界から学ぶところは大であろう。
1986年の厚生白書は,前年の男女の平均寿命を74.84歳,80.46歳とし,21世紀の見通しによると,65歳以上の人口(老年人口)の割合は,全人口の1/4に達すると警告している(図1-6)。この老年人口に“いかに健やかに老いて”貰うかは,当面の厚生行政の重要な課題であり,年金などの所得保障も併せて,今後の国庫の負担は並々ではない(図1-7)。最近の世帯構成の変化,なかんずく単独ないし夫婦の老人家庭の増加は,婦人労働の増加と相まって,家庭における老人の介護を著しく困難にしており,この逃げ場を失った老人たちに,どんな形の生活と医療の場を与えていくか,政府も老人保健施設(生活と医療の“中間施設”)の設置など前向きにとり組んでいるが,従来の人生50年を人生80年に切り換える大事業は,今後の日本の政治・行政上の最大課題であるべきである。この場合も,基本としては,ともすれば効率本位,自己本位におちいり易い国民の価値観が改められて,内外の恵まれざる他者に対してもより多くの関心が寄せられるようになることが先決である。
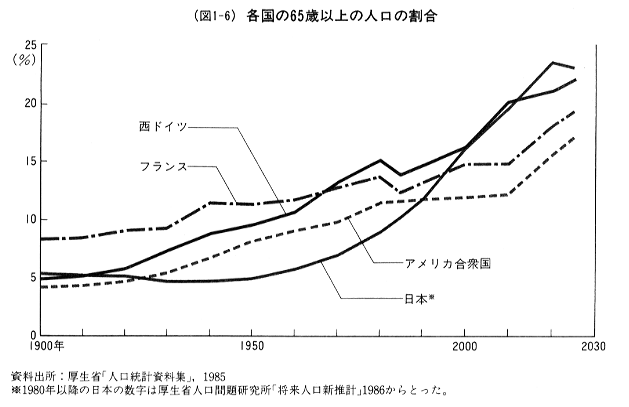
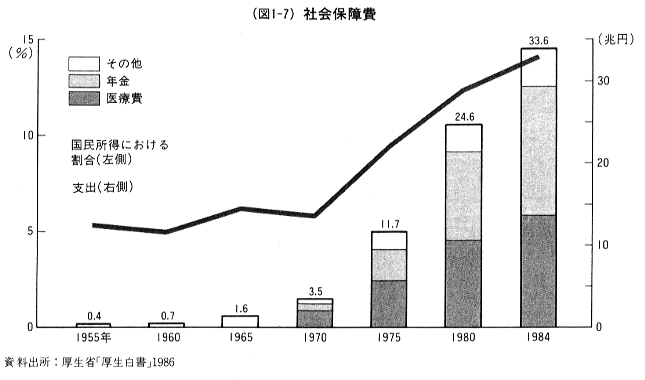
5 国際貢献(“ODA”など)
今後40年の政治の国際的指標たるべき“人的・物的の国際貢献”は,日本としては,国民の合意に基き最も着実に進捗しつつある分野かも知れない。いわゆるODA(政府開発援助)予算は,逐年増加し(図1-8),1986年から1992年までの総額を400億ドルル以上とすることを目指している。(換言すれば,1992年の援助額を1985年の倍とする意欲的な計画である)政府はさらに,この7年の期間を5年に短縮し,有償,無償の資金協力も画期的に増額することを提案した。このような積極的な対応が,赤字財政再建の最中,すなわち一般行政予算削減(マイナス・シーリング)の例外項目として対処されていることは注目されてよい。
勿論,巨額な貿易黒字からすれば,なおスケール・アップの余地もあるかも知れぬが,財政は赤字であるから,国民の合意の上に立って,特別の財源を求めていく必要もあろう。またODAは,社会基盤の充実などの経済開発が重点となり,保健福祉分野における協力は,被援助国側の公式要請として出にくい事情があり,この点は西欧諸国の例にならって,NGO(非政府団体)などの民間活力に期待すべき分野が多いかも知れぬが,後述の通り,円高不況下の日本は,ミクロの個別企業も体力を消耗しつつあり,NGOの物的協力を支える経済的基盤が失われつつある事情は,諸外国とさして異ならない。
しかし,人的協力については,国際協力事業団(JICA)傘下の青年海外協力隊(JOCV)の活動は注目に値する。このような若い世代が育ち,草の根的な人的国際貢献が進んで,始めて憲法前文のいわゆる“国際社会における名誉ある地位”が与えられるというものではあるまいか。
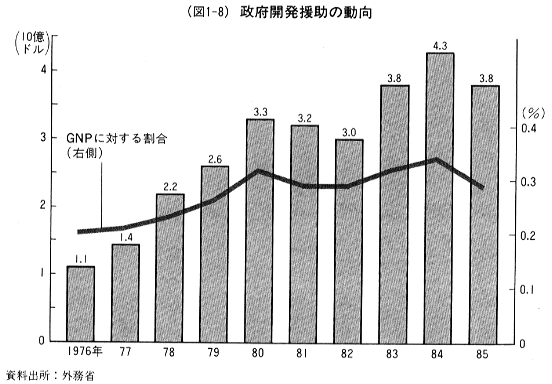
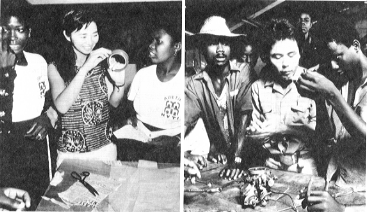
青年海外協力隊は開発途上国の国づくりに活躍している。現在アジア,アフリカ,中近東,中南米,南太平洋などの34か国に約9,000名が派遣されている。写真は2枚ともガーナで技術指導をしている隊員。
6 地方自治
現行憲法が,地法自治の章を新設し,従来の中央集権の政治体制を根本的に改めたのは,政治の民主化の一側面として捉えることができよう。憲法が根づくと同時に,いわゆる“地方の時代”という声もポツポツ聞かれるようにはなったが,その後も人口の都市集中の傾向はやまず,特に東京周辺が経済の情報化・国際化とともに急速に肥大化し,人口集中がさらに諸々のサービス産業をよびこんで,地価の暴騰を招くこととなった。政府は当面“国土の均衡ある発展”を目指して,幹線道路,空港などの整備により地方の過疎化を防止している状況である。
一方では,政治経済の民主化の成熟によって,中央集権的規制は緩和の方向にあり,“公選知事”たちの活力も目立つようになった。(“一村一品運動”などもその一例である)この地方自治の本旨を徹底すれば,コミュニティー活動や,日本が遅れをとっているNGOの活性化にも自然に到達すべきであろう。特に福祉の面では,地方によってそのニーズにも差があるから(例えば老年人口の比率なども地方によって大きな差がある),この面における地方公共団体,NGOの役割は期して待つべきであろう。
| - | 1975 | 1980 | 1985 |
|---|---|---|---|
| 第一次産業 | 6.0 | 4.4 | 3.6 |
| 第二次産業 | 39.6 | 39.4 | 37.4 |
| 製造業 | 29.9 | 30.4 | 30.0 |
| 建設業 | 9.7 | 9.0 | 7.4 |
| 第三次産業 | 54.4 | 56.2 | 59.0 |
| 商業 | 14.8 | 13.3 | 13.8 |
資料出所:経済企画庁
| - | 生産高 | 輸入 | 消費 | 自給率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 野菜 | 16,216 | 790 | 17,005 | 95 |
| 米 | 11,662 | 30 | 10,882 | 107 |
| 魚貝類 | 11,453 | 2,255 | 12,175 | 94 |
| 乳製品 | 7,436 | 1,139 | 8,346 | 89 |
| 果物 | 5,748 | 1,874 | 7,538 | 76 |
| 肉類 | 3,497 | 851 | 4,320 | 81 |
| 小麦 | 874 | 5,194 | 6,101 | 14 |
| 豆類 | 424 | 5,202 | 5,513 | 8 |
| オオムギ | 340 | 2,071 | 2,417 | 14 |
| 粗糖 | 299 | 1,823 | 2,074 | 14 |
資料出所:農林水産省「ポケット農林水産統計」1987
5 産業・経済
1 産業社会から情報社会へ
日本の産業構造は,従来も徐々に高度化の道を歩んできたが,膨大な経常黒字が引き金となって,内外から構造調整への要望が急速に高まってきた。(表1-4)
産業構造の変化は,賃金水準の向上と国際競争力の低下,為替相場の変動などで,第一次産業から第二次産業,その中でも重厚長大から軽薄短小へと移行し,さらに第三次産業が大勢を制するようになった。いわゆる情報産業時代の到来といえるかも知れない。しかし,資本の移動は比較的容易であっても,労働力の転換は困難であり,1987年の3月には,失業率が労働人口の3パーセントをこえ,事態はさらに悪化の兆がある。
第一次産業では,農業は,牛肉・オレンジなどの輸入枠増の問題がある外,大黒柱であるコメも後述するように自由化の外圧にさらされており,漁業も北洋漁業制限を始め,各国の200マイル沿岸規制,捕鯨禁止などで揺れている。鉱業も,各種金属鉱山の世界的な不振を始めとして,炭坑の閉山が相次いでいる。
第二次産業も,重厚長大を代表する鉄鉱,造船,電気,機械などは,下請企業も含めて地域ぐるみの不況に突入しているものもある。地域ぐるみといえば,洋食器とか刄物とかの,特殊化した地域輸出産業も,急速な為替の変動で逃げ場のない苦境に坤吟しているし,前掲の下請中小企業も,親会社のシワよせで倒産寸前のものも多い模様である。
以上の問題産業からはき出された人員を,いわゆる“ハイテク”産業や流通・サービスなどの第三次産業で吸収できるか否かが問題であるが,これには労働者の再教育や,配転の問題が立ちはだかっている。単身赴任や子女の教育問題で,家庭もその犠牲を強いられているのが実情である。
上記のコメの自由化は,農家は与党自由民主党の伝統的な票田であり,大きな政治問題である。一般大衆も輸入米に比べて5~7倍もの割り高な内地米を食べさせられることは抵抗は感じているが,食糧自給率の低下(表1-5)に対しては,戦中戦後の飢餓体験にてらして,せめてコメぐらいは自給していきたいという気持もあるようである。政府も国民の合意のもとに,農政審議会に諮って事態の漸次的改善を企図している。
2 貿易
日本は地質的に天然資源に恵まれず,加工収入で生活必需品や原料を輸入調達する要があり,その購入外貨を輸出貿易で稼ぐことは自活の条件であった。しかし,このようにもともと輸入のための輸出であったものが,国をあげての重商主義的な,外貨蓄積のための輸出となり,海外市場をあてにした設備拡張が競って行われるようになった。日本の一人あたりの貿易額は特に多いとはいえず,輸出依存率もむしろ低位に属するが(図1-9),最近世界的な原・燃料価格の下落で,経常黒字総額が目立つようになったのが実情である。従って,この黒字蓄積の背景も,いつ環境が変わるかも知れず,資源小国の日本としては,節約の美徳は忘れてはならないと力説する人もいるし,世界には未だ飢えに苦しむ国も多いのに,日本人のみが暖衣飽食するのは理に合わぬと反論する向きもあるが,それにしても,年間900億ドルになんなんとする経常黒字は極めて異常で,到底静観できる額ではない。今に至って従来の輸出依存の体質を改めるには大きな痛みを伴うが,世界経済安定のためには,この貿易立国のパラダイム(枠組み)を根本的に修正するより道はない。
但し,この膨大な貿易黒字が,そのまま長期資本輸出という形で環流されており,当面資金面で,先進国,途上国の経済を支えている(表1-6)ことも事実ではあるが,これとても1986年末で日本の対外債権は1,800億ドルをこえ,このまま推移することは危険であるし,いずれにせよ,日本にとっても産業空洞化,失業急増など懸念される事態に立ち至ったことは前述の通りである。
しからば,現時点での処方箋は何か。米国の貿易収支の改善には,ドル安は一応有効であるが,米国が他国で生産しているものはいずれにせよ輸入する要があるから,その効果には一定の限界があり,またドルの崩落は世界大不況につながる。
日本にとっても,例えば1ドル140円を割るようなレートでは,おおむね競争力はないから,この程度で為替を安定させることが日本はじめ各国の緊急の課題であろう。
さらに,米国は財政赤字を縮小することにより,公私の過剰消費が抑えられ,貿易赤字も減るはずだし,日本も,非常対策として大幅な財政出動(建設国債)による内需拡大,上記の一段のODAの拡充などをすでに実施中である。
(表1-9)ひとりあたりの貿易額及び貿易依存率
|
|
1 1984-86年の貿易額の平均を1985年の人口でわったもの
2 貿易額をGNPでわった率
3 1985
4 1984
5 1983-1985
6 輸出は船側渡し
資料出所:「国際比較統計」日本銀行1986
| - | 経常収支 | 貿易収支 | 資本収支 | 保有外貨 |
|---|---|---|---|---|
| 日本 | 49,170 | 55,990 | -53,530 | -290 |
| 西ドイツ | 13,760 | 28,660 | -16,600 | -5,640 |
| イギリス | 5,341 | -2,284 | -7,975 | -3,508 |
| フランス | 907 | -4,532 | 1,413 | -5,677 |
| アメリカ合衆国 | -117,760 | -124,440 | 100,380 | -8,210 |
資料出所:国際通貨基金「国際経済統計」1986年11月
注:日本,アメリカ合衆国,西ドイツの数字は10億ドル単位が基になっているので最終桁数字は不明。そのためここではゼロとしている。

第一次産業の不振:繁栄を誇った筑豊の炭鉱地帯も,いまは夏草におおわれている。写真は赤茶けた選炭場と積込場跡。
| - | 1月あたりの額 | ||
|---|---|---|---|
| 円 | USドル 2 | ||
| 収入 | 452,942 | 2,688 | |
| - | 定期 3 | 291,751 | 1,731 |
| 臨時及び賞与 | 81,517 | 484 | |
| 可処分所得 | 379,520 | 2,252 | |
| 生活費 | 293,630 | 1,742 | |
| - | 食物 | 74,889 | 444 |
| 住居・光熱費 | 31,127 | 185 | |
| 被服費 | 20,554 | 122 | |
| 医療費 | 6,985 | 41 | |
| 教育費 | 13,118 | 78 | |
| 教養娯楽費 | 26,142 | 155 | |
| 貯蓄率 | 16.0% 4 |
1 給与所得者世帯
2 1ドル=168.52円
3 世帯主のみ
4 1985
資料出所:総理府,日本銀行
3 財政
財政については,政府の管理過剰を排し,小さな政府に徹して民間活力に期待する政治の流れは,1980年以降顕著であるが,国債発行残高は各国にくらべて未だ過剰で,公債費も1987年一般予算の20パーセントに及ぶから,内需拡大のための建設国債の発行は,政府としてはやむを得ざる政策の転換であった。(1990年赤字国債脱却の炉シナリオも必ずしも楽観はできない)政府はまた1987年度で,不公平税制是正のため所得税を減額し,あわせて直間比率を他国なみに修正するため,付加価値税の一種である売上税を新設しようとしたが,反対党の国会内外における猛烈な抵抗にあい,いわゆるマル優(少額預金利子非課税制度)の廃止法案とともに廃案となり,出直しを余儀なくされた。
前述の通り,21世紀にかけて長寿社会に対処するための増大する社会保障費支弁の要は目に見えており,国の内外で問題をおこしている不動産の購入や,未曽有の株高を招来している証券投資向けの過剰民間資金を,何らかの方法で国が吸収し(課税か国債か),財政を将来に向けて健全化することは今や不可避であろう。広く薄い消費税を,福祉目的とか、国際貢献の目的で新設することも,例外非課税の多い,比較的高率の売上税の場合とは異なり、国民の合意がとり易いのではあるまいか。
4 国民生活
日本の標準家計は,表1-7の通りであり,食費が可処分所得に占める割合は約20パーセントで,米国に次ぐ低位にある。節約率(16.1パーセント)が各国に比し(西独11.6,仏10.1,英国7.8,米国6.6)著しく高いのは,住居,教育,老後の準備などのための蓄えで,その功罪については上述の通り議論は岐れている。教育と文化・娯楽の面は,今後とも比率は高まることと思う。教育費自体が逐次値上りしているし,教育の項で再述する通り,塾や予備校は,その後も幼児期から益々繁昌の模様である。
娯楽にさく時間の割合は,生活の余裕,週休2日制の普及などにより,逐増しつつあり,1985年の調査では,調査対象の40パーセントが一段の増加を望み,特に20代では60パーセントにものぼる。兎角非難されている“働きすぎ”の問題は,工場労働時間を比較すれば(表1-8),先進各国に比しなお高位にあり,政府はこれを最終的に週40時間まで短縮する方針である。労働については,時間短縮の問題以外に,1986年施行の男女雇用機会均等法にも触れる要がある。この法律は,単なる努力目標であるところに問題は残るが,この一年間,既婚女性の職場進出が家計の事情もあって目立つようになり,母性の保護規定(産休・育児休暇)の改善を促す契機ともなっており,一方家庭における夫婦の役割分担,保育,介護など福祉ニーズにかかわる部分が極めて大きい。
しかし,何といっても当面の国民生活の最大課題は住居である。最近一段と加速した地価の高騰により,一般のサラリーマンは都心近辺に居を構えることは不可能で,通勤時間が片道2時間をこえるものも東京周辺では20パーセントに達しているといわれる。住宅ローンの返済も,1985年の調査では,可処分所得の14.6パーセントに達し,大きな負担となっている。住居の質も問題であり,広さの点はままならぬとしても,下水溝の普及など,社会基盤充実の上から政府(中央・地方)がなすべきことは多い。

米炭鉱住宅は筑豊だけでも一時8万戸もあってにぎわっていた。閉山後は住民も去り,住宅の大半は撤去されて典型的な過疎地となってしまった。
| - | 日本 | イギリス | アメリカ合衆国 | フランス | 西ドイツ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 43.2 | 39.8 | 37.4 | 38.8 | 37.1 |
| 1983 | 43.3 | 40.3 | 37.5 | 37.4 | 36.1 |
| 1985 | 43.6 | 40.7 | 38.0 | 37.2 | 36.5 |
資料出所:日本銀行「国際比較統計」1986
注:数字は企業の工場労働者
6 文化
1 独特な文化の形成
日本の文化は,“カルテュア”の語源が意味するように,数千年もの永い年月の中で培われ,日本人の体と心に浸みついたものである。われわれの文化の起源(外来)を云々して,独自性を否定するものもいるが,有史以来いろいろの外来文化との出会いによって独特の文化を“形成”して今日に到ったことは疑いなく,今後の国際化の時代においても,これを広く世界に紹介すれば,共感を得る分野は意外に多いのではあるまいか。
2 文化史の概要
日本文化の形成の過程を4期に分けて考えてみたい。
(1) 大陸文化摂取の時代
有史以前からも大陸との交流があったことは疑いないが,紀元538年の公式な仏教伝来から同894年に遣唐使の派遣を中止するまでは,積極的な大陸文化の摂取が,中国・朝鮮半島経由,多数の技能者の渡来を伴いつつ活発に続けられたのである。(日本は,いわゆる“絹街道”の終点である)成熟段階にあった大陸の進んだ文化・文明は,4世紀頃から漸く統一・建国するに至った日本を急速に潤すこととなった。仏教文化の渡来に続き,紀元645年の大化の改新により,中国風の中央集権制度を政治にとりいれ,漢字を輸入して歴史(古事記・日本書紀)や文学(万葉集)を書き留めるに至ったのである。
(2) 独自文化形成の時代
9世紀末の遣唐使派遣中止により,文化の日本化が進められることになった。平安の藤原摂関政治から,鎌倉・室町・安土桃山などの武家の時代を経て,徳川氏が安定政権を樹立,次いで直ちにオランダ以外の外国に門戸を閉じるまでの時代である。この期に日本のアルファベットである“かな”が発明され,11世紀初頭には源氏物語が生れたことは前述したが,“かな”はまさしく漢字の日本化であり,同様な日本化が文学以外に,仏教でも,建築でも,絵画でも日本人(後半は主として指導階級たる武家)の好みによって次々と実現したのである。茶道・華道・能・人形浄るりなどの純日本文化が生まれたのもこの頃である。
 歌舞伎は江戸時代に興隆し,発達した日本独特の演劇である。完成された様式美は目も見張るものがある。 |
 ファミリーレジャーとして人気の東京ディズニーランド。ショー形式を主にした笑いと夢の楽園の人気は,国内のみならず,外国からの見物客も絶えない。 |
| - | 家庭教師 | 学習塾 | 趣味※ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | 小学校 | 中学校 | |
| 割合(%) | 1.0 | 5.4 | 16.5 | 44.5 | 70.7 | 27.4 |
| 月額(円) | 14,600 | 18,700 | 7,800 | 10,200 | 5,700 | 5,000 |
資料出所:文部省 ※そろばん及び外国語を含む
(3) 鎖国時代
明治開国(紀元1868年)に至るいわゆる江戸時代は,世界が大航海時代の到来によって揺れ動いた時期であり,日本のみが幸か不幸か国を鎖して,太平の夢をむさぼっていたことになる。しかし,文化的には,それまでに蓄積した文化的素材を日本風に醇化した時期であり,前掲の俳句も,この時代に庶民の中で生れ,国民文化の粋ともいわれる歌舞伎もこの時代を通じて栄えた。独特の日本文化が集大成された時期である。
(4) 明治以降
紀元1868年の明治維新から,第二次大戦の終結,戦後の40年を含めて今日に至る120年間で,政治史的には3期に分けて論じたが,文化史的にはその特徴は西欧化,近代化の一語につきよう。しかし,この西欧化・近代化の過程でも,後述する“和魂洋才”の姿勢で,日本の独自性・主体性を残すことができたのは,各界の先覚者(渋沢栄一・森鴎外など)によるところも大であったが,近世250年の鎖国によって誰に煩わされることもなく,独自の文化と感性の基礎固めをして,圧倒的な西欧の近代文化に対する抵抗力をつけることができたためでもあったろう。先に,鎖国を“幸か不幸か”と評した所以である。
3 教育
戦後教育制度は,おおむね米国風に改められたが,現在政府は審議会に諮って制度の全面的な見直しを行っている。文化にかかわる点にのみ触れてみたい。第一に日米の教育方法の差違であるが,日本側は個性尊重,創造力育成の見地から,丸暗記中心の画一的受験教育を反省中であるが,逆に米国側は従来の日本の経済発展をその独自の教育方法の一成果と評価し,暗記を含む基本的教育の重視を唱える識者もいる。いずれも一長一短があろうが,日本が明治以降,かくも短期間で欧米の近代的文化水準に追いつけたのは,鎖国時代にも普通教育がかなり普及していた(徳川末期の識字率は,男子で45パーセント,女子で15パーセントとかなり高く,寺小屋と称する当今の塾まがいのものが,全国では何万もあったといわれる)事実があり,その教育熱心の伝統は,いわゆる試験地獄の弊害とともに,上述の塾の活況などの異常ともいえる現象をもたらしたものといえよう。(表1-9)この傾向は,保育所・幼稚園などの就学前児童の時期からすでに顕著で,児童の健全育成のための障害ともなっているが,このエネルギーを善導する教育改革は,日本の将来のために極めて重要であることは疑いない。
日本の教育で特に必要なことは,その“国際化”で,日本人に国際化時代にふさわしい教育を与えることと,海外の留学生に対しても開かれた社会・学校であることが肝要である。かつて提唱された“人づくり協力”に対する海外のニーズは極めて高いようであるから,政府は次の10年間に海外からの留学生を10倍にふやす積極姿勢をもっているが,外国留学生の数は逐増中とはいえ,米国の30万人はいうにおよばず,仏の10万人以上と比較しても,後者の約10パーセントにすぎず,日本の在外留学生の数に比べてもその半数にすぎない(図1-10)。しかし,政府の意欲的な計画を実現するには,まず,日本の大学を国際的に開かれた,魅力のあるものにする要があると同時に,官学産のみならず,国民全体が,留学生を心から歓迎する姿勢を示すことが先決であろう。
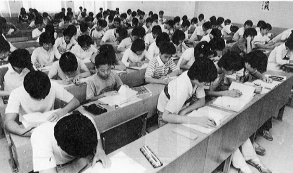
年々過熱する一方の試験地獄に勝ち抜かんと,休日もなく余暇を惜しんで勉強する児童たちで,どこの塾も盛況を極めている。塾といえば以前は数人の児童を対象としていたものだが,現在は写真にみられるとおり,大型・大量化にエスカレートしている。
| - | 全体 | 私費留学 | 公費留学 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 6.5 | 5.2 | 1.3 |
| 1981年 | 7.2 | 5.6 | 1.6 |
| 1982年 | 8.1 | 6.3 | 1.8 |
| 1983年 | 9.5 | 7.5 | 2.0 |
| 1984年 | 10.7 | 8.5 | 2.2 |
| 1985年 | 12.4 | 10.0 | 2.4 |
資料出所:文部省「文部統計要覧」1986
4 信教
信教については,文化史的にもかかわりが大であるし,神道の地位については,外国人に誤解されている面も多々あるので,ここで簡単に触れてみたい。
仏教が6世紀に公式に導入され,次第に日本化されつつ,美術工芸分野においても,日本に多大な貢献を与えたことは前述したが,これに反し神道は,日本古来の民族宗教で,今に至るも仏教と拮抗する勢力を保っている(図表1-10)。多くの仏教信者も,仏壇を設けるとともに,神棚もまつり,子供が生まれれば,氏神にお宮詣りをし,新年には一家で初詣でを欠かさず,春秋の祭りはコミュニティ総出の年中行事である。結婚は神前,葬式は仏式と器用に使いわけるのが一般で,何の違和感もないようである。6世紀の伝来以来,仏教は政府の手厚い保護をうけ,早くも7-8世紀には,神仏混交の動きが現われ,9世紀には,本地垂跡説(ほんじすいじゃく)説)が説かれるまでになった。このような共存は,神道が本来教義も戒律もなく(後に13世紀,15世紀には神道の体系化も行われたが,大勢を制するには至らなかった),作物の豊饒(じょう)と祖先の崇拝を宗とする抱擁力のある民族宗教であり,国民も一神教的な,善悪を峻別する絶対論よりも,多神教的な相対論になじみ易かったためでもあろう。
なおこのような“ウェイ・オブ・ライフ”(生活様式)とも思われる神道が,軍国主義の時代に一時期国家宗教の地位を与えられたこと,徳川時代以降今日に至るまで,儒教が日本の指導者の倫理感の骨格をなしていることなど(渋沢栄一は,“論語を片手に経営に当るべし”と喝破している),日本の信教を論ずる場合に看過できぬ問題である。
| - | 全宗教団体 | 宗教組織 | 指導者 | 信者(単位:千) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 内外国人 | ||||
| 神道等 | 90,832 | 85,835 | 102,032 | 21 | 115,602 |
| 仏教 | 84,613 | 77,422 | 269,470 | 120 | 92,065 |
| キリスト教 | 8,616 | 3,614 | 21,503 | 4,067 | 1,688 |
| その他 | 42,027 | 16,192 | 252,834 | 141 | 14,444 |
| 合計 | 226,088 | 183,063 | 645,839 | 4,349 | 223,799 |
資料出所:「信教年鑑」文化庁,1986
5 日本人論
二度にわたる石油危機を手際よく乗り切ったためか,日本的経営の株があがり,世界的に注目を浴びるようになったが,同時に数多くの日本人論が内外で唱えられるようになった。“タテ”社会,“甘え”の構造,論理性を欠いた“情緒的”社会など,いろいろの視点があるが,すべては,この限られた国土で,同質の国民が多年培ってきた文化や人間関係に組みこまれた個人(西欧流の“インディヴィジュアル”に対置して,“コンテクステュアル”と呼ぶ人もいる)の肌合いの差が根因をなしているようである。日本的経営も,その小集団活動(QC),会社本位の長期戦略,人間尊重の経営など一時は世界の賞讃を浴びたが,その多くは“コンテクステュアル”である愛社精神旺盛の従業員相手の“日本的”経営であって,環境の枠組みがかわれば,日本においてすら,終身雇用も,年功序列も光彩を失いつつある昨今である。
戦前の教育の指針であった教育勅語も,上記のもろもろの人間関係を律する儒教的な行動規範が大宗を占めており,世代が代ったとはいえ,一朝一夕には国民の価値観はかわらない。とかく批判の対象となる日本人の形式主義(挨拶や贈答なども含めて)も,タテヨコの人間関係の中で,永い歴史を通じて沈殿したもので,敬語多用の言語とともに,善かれ悪しかれ文化の根底に横たわる問題であろうか。
7 むすび
日本を訪れる人々は皆一様に,日本には古さと新しさが同居しているという。冒頭で,独自の文化と外来文化との二元性,その絶えざる出会いについて言及したゆえんである。しかし,この二元性のゆえに,われわれは国際交流の中で独り居心地の悪さを味わい続けてきたともいえる。一貫した論理を欠いたあいまいさや実利的ともいえる行動様式で,慌だしく多事多難な時代を駈け抜けてきた。矛盾をふくむこの二元性は,新奇なものへの明るい好奇心と,人間的交流の中での暗い孤立化を意味している。“われわれはユニークだから”という常套のせりふを捨てて,国際交流につとめ,この分かりにくい文化を世界に紹介し,共通の遺産である人類文化をより多彩にすることが,21世紀のわれわれの使命である。
明治の近代化は,“和魂洋才”という旗印のもとで,辛うじてわれわれの独自性,アイデンティティー(同一性)を保ちつつ行われたが,今や,日本には別の合言葉が必要なのである。われわれは問う。何が残された“和魂”であり,何が頼るべき“洋才”であるかを。和魂と称して,頑なになることは禁物であり(いわゆる“新しい国家主義”の抬頭をおそれる人々もいる),これを狭くなった地球家族と同調できるまでに昇華することが必要であり,また“洋才”ならぬ“和才”をもって豊かに世界に貢献していかねばならぬ新世紀を今や迎えんとしている。
〔参考文献〕
Handbook for General Orientation (No.1-7) 国際協力事業団
Facts and Figures of Japan (1987) Foreign Press Center
Japan 1988,An International Comparison 経済公報センター
主題:
日本のリハビリテーション No.1
1頁~32頁
発行者:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
編集:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
発行年月:
1992年8月31日
文献に関する問い合わせ先:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162 東京都新宿区戸山1-22-1
電話 03-5273-0601
FAX 03-5273-1523
