日本のリハビリテーション No.9
財団法人
日本障害者リハビリテーション協会
第8章 障害者運動
―障害の種類別主要団体の動向―
1 第2次世界大戦後の障害者運動の始まり
第2次世界大戦が終ると,人々は家や職を失い,「米よこせデモ」など大衆運動が全国的に広がった。
その中で障害者運動も,生活を守る運動として出発した。その先頭を切ったのが患者運動であった。
国立療養所に入院していた結核患者たちは「生きたい,早くよくなって社会復帰したい」という要求を実現するために,患者自治会を結成し,1948年(昭和23年)には全国組織が設立された。現在の日本患者同盟である。
一方,1949年(昭和24年)頃から熊本,福岡などで結核回復者たちが,アフターケア・コロニーの建設をめざして活動を始め,この運動は兵庫,岡山,東京へと広がっていった。現在のゼンコロの始まりである。
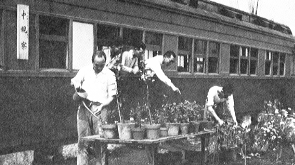
1949年(昭和24年),国立中野療養所の結核回復者たちが,コロニー建設運動を始め,国鉄廃車の払い下げを受けてアフターケア・ホーム(中親寮)を発足させた。現在の東京コロニー。
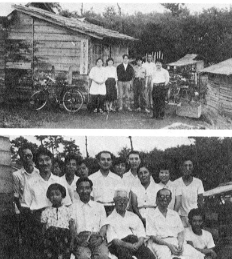 上は鶏小屋改造の日本リハビリテーション協会。下は協会初期のメンバー。 |
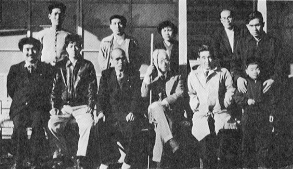 日本リハビリテーション協会を支えた人たち。1953年(昭和28年),清瀬病院の結核回復者が6坪の鶏小屋を改造して,日本レハビリテーション協会を発足させた。当時はリハビリテーションをレハビリテーションといっていた。 |
2 障害別団体の結成
障害別の団体では,盲・聾の全国的組織が,戦後すぐに結成された。これは明治以来の盲・聾教育の長い歴史があったためである。
戦後最初に組織されたのは日本盲人会連合(1948年)であった。この年にはヘレン・ケラーが来日し,盲人福祉法の立法化の動きが高まったが,大勢は身体障害者福祉法の制定に向ったため実現はしなかった。
しかし,ヘレン・ケラーの来日は,障害者雇用促進週間の実現など,戦後の障害者運動に大きなインパクトを与えた。
次いで全日本聾唖連盟が再建され(1949年),刑法,民法の差別条項の改正などを要求した。
この二つの団体は1958年(結成)と日本身体障害者団体連合会を組織している。
肢体障害者の運動では,1946年(昭和21年)に鉄道弘済会の助成で国鉄傷痍者団体連合会が結成され,年金打切り反対運動などが行われた。この会は1953年(昭和28年),機関紙「リハビリテーション」を発刊したが,当時“リハビリテーション”という言葉は周囲に新鮮なひびきを与えた。
1947年(昭和22年)には,東京の肢体不自由児養護学校・光明学校出身者により雑誌「しののめ」が創刊された。この参加者の一部は1957年(昭和32年),「しののめ」での理論活動を実践に移そうと「青い芝の会」を結成,施設での管理反対運動や障害児殺し,安楽死問題などをとりあげ,社会運動に大きく踏み出していった。
精神薄弱の分野では,1949年(昭和24年)に日本精神薄弱者愛護協会(施設の団体)が再建されていたが,1952年(昭和27年)に精神薄弱児を持つ親たちの手で全日本精神薄弱者育成会が結成された。
障害児を持つ親たちが初めて作った団体であり,現在では2,105の支部を持ち,42万人の会員を持つ,最大の親の会になっている。
また1950年代から,各地に肢体不自由児の親の会が活動を始めていたが,1961年(昭和36年)に全国組織として全国肢体不自由児父母の会連合会が結成された。この会は全日本精神薄弱者育成会と並んで,わが国の代表的な親の会である。
この二つの親の会は,当時著しく不足していた施設と養護学校建設の運動に全力をあげていた。
 1948年(昭和23年)8月29日,ヘレン・ケラーが来日した。左の写真は広島原爆ドームの前に立つヘレン・ケラー。 |
 1952年結「しののめ」を発足させた花田春兆氏。日本推進協議会の副代表として福祉映画祭のテープを切る。 |
3 養護学校義務制実現への運動
盲・聾児教育の義務制については,1902年(明治35年)から運動が続けられ,第2次世界大戦後もいち早くこの要求を掲げ,1947年(昭和22年)制定の学校教育法により実現することができた。
しかし肢体不自由と精神薄弱については,学校教育法の中に「養護学校を設置しなければならない」としながらも,その期日を明記せず,31年間の長い運動が必要であった。
養護学校の義務制,社会保障の充実,年金の増額,身体障害者雇用促進法や精神薄弱者福祉法の制定など,こうした共通の要求を実現するための運動が次第に強まり,障害者関係団体が合同で全国大会を開く動きが出てきた。
その中で1960年(昭和35年),身体障害者雇用促進法,精神薄弱者福祉法がようやく制定された。
養護学校の義務制については,1979年(昭和54年)になって,ようやく実現した。しかし,この時間的なズレは大きく,次第にインテグレーションの波が高まる中で,養護学校反対,入学拒否運動にさらされることになった。
 友だちとの外出で動物とのふれ合いを楽しむ養護学校の子どもたち。 |
 教師と親たちが一体となって,特殊学級・特殊学校の義務制を訴えたのが1964年(昭和39年),この15年後,1979年に義務制が実施された。 |
4 公害と障害者運動
1950年代から1960年代にかけて,日本は技術革新,近代化そして高度成長期を迎えた。
しかし同時に,大企業による公害まきちらしが,新らたな障害者を生み出すことになり,障害者問題が社会問題としてクローズアップしてくることになった。
1955年(昭和30年)に森永ヒ素ミルク中毒,1956年(昭和31年)に水俣病といわれる水銀中毒が表面化し,他にも鉱業廃水による富山のイタイイタイ病,四日市コンビナートの大気汚染によるぜん息など,各種公害による障害者を続出させた。
また,この時期は薬害による被害も相つぎ,サリドマイド系睡眠剤による被害,腸内殺菌剤キノホルムによるスモン病発生問題が1963年(昭和38年),1971年(昭和46年)にはそれぞれの患者たちによって告訴された。
さらに1972年(昭和47年)に未熟児網膜症,1973年(昭和48年)に大腿四頭筋拘縮症が医療過誤によるものとして告訴された。
こうした被害に対して,障害者と家族・関係者たちは,自らの要求を実現するため,森永ミルク中毒のこどもを守る会,水俣病訴訟支援公害をなくす県民会議,先天性異常児父母の会(子供たちの未来を開く父母の会),全国スモンの会などを結成し,大きな社会問題となった。
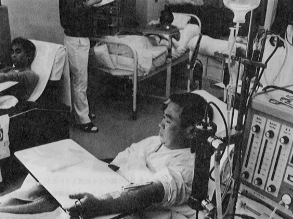
腎臓病患者の団体は,人工透析による副作用を指摘し,腎バンクの充実を訴えている。
5 障害別親の会の誕生
前に述べたように1950年代に精神薄弱児を持つ親たちと,肢体不自由の親たちが,それぞれの親の会を結成していたが,10年後の1960年代になると,谷間に残されていたさまざまな障害別の親の会が,いっせいに結成された。
これは個々の障害児の持つ個有のニーズに法律や行政が対応できず,親たちも問題意識を共有できる仲間の組織化が必要になったからである。
言語障害児をもつ親の会(1962年),心臓病の子どもを守る会,日本筋ジストロフイ協会,先天性異常児父母の会,全国心身障害児をもつ兄弟姉妹の会(1963年),全国重症心身障害児を守る会(1964年),全国精神障害者家族会連合会(1965年),自閉症児親の会(1967年)が次々と活動を開始した。
また,同じ時期に,こどもを小児マヒから守る中央協議会,日本リウマチ友の会(1960年),全日本視力障害者協議会(1967年),腎炎・ネフローゼ児を守る会(1970年)なども発足している。
こうして多数の障害別の親の会が自然発生的に誕生したが,同時に親たちは,それぞれの要望が共通の基盤の上にあることを知り,運動を有利に展開するための連絡協議の場を設けることになった。
全国的な組織をもつ心身障害児関係団体の連絡提携をはかり,必要に応じて実践活動を行うために1965年(昭和40年),全国社会福祉協議会の中に全国心身障害児福祉協議会が設置された。
また親の団体だけの協議会である全国心身障害児父母の会連絡協議会も1966年(昭和41年)に発足,障害の枠を超えて療育相談,指導・研修を行う全国心身障害児福祉財団が設立された。
6 施設収容から地域ケアへ
1960年代前半の親の会の運動目標は,収容施設づくりであった。どこの施設も多くの待機児を抱え,在宅児への福祉サービスは全くなかった。
1964年(昭和39年),第13回パラリンピックが東京で初めて開かれ,翌年には東京で第3回汎太平洋リハビリテーション会議が開かれた。
この二つの行事は,施設一辺倒であった日本の動きを大きく変化させることになった。
1965年(昭和40年)になると,親たちは地域の中に在宅児グループを作り,通園施設づくりの運動を始め,この運動は急速に全国に広がっていった。また幼稚園・保育所へ障害児を入園させる運動も始まった。
親の会も,在宅対策の充実を要求し始め,行政も1966年(昭和41年)から身体障害者地域活動,日常生活用具の給付,社会適応訓練事業,身体障害者福祉センターの設置など,在宅対策に取り組み始めた。
一方,障害者自身が,ボランティアと市民と連帯して,主体的な運動を始めたのが,「車いすで歩ける町づくり」運動である。
1970年(昭和45年),仙台市の重度身体障害者施設の障害者が車いすで町へ出たが,車道と歩道に段差があってどうしても登ることができなかった。これが契機になって翌年,「福祉の町づくり市民のつどい」が開かれ,各地で同様な都市構造の点検活動が行われ,「車いすガイド」の発行を通して,都市環境の不備が告発された。
各地に生まれた生活圏拡大運動は,初めは車いす障害者とボランティアによる「車いすの生活圏拡大」であったが,仙台市で開かれた全国車いす市民集会で,他の障害者の問題が指摘され,「共に生きる街づくり」という市民運動的な広がりを見せ始めた。
この運動は障害者の利益と市民の利益が一致し得ることを発見し,市民との交流を可能にし,交流を通じて共に理解するという,大きな成果をもたらした。
この頃から「障害者とともに生きる」ということが,ボランティアや施設職員の間で強調されるようになった。

肢体不自東京オリンピックの後,1964年(昭和39年)に東京で開かれたパラリンピックは,障害者の社会自立に対して大きなインパクトを与えた。
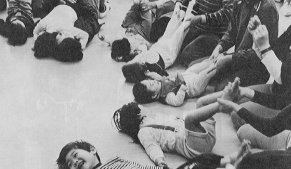 障害幼児の通園施設が各地に生まれたが,早期療育のシステムはまだ不十分である。 |
 ボランティアとともに街を点検する障害者。こうして車いすガイドブックが生まれた。 |
7 生活と権利を守る運動へ
障害者とその家族自らが組織を作って運動を始めた時代は,政治家あるいは行政に対する陳情が運動の中心であった。
1960年後半になって,教職員,市民,労働組合が共通の要求をかかげるようになると,生活権,教育権,労働権といった障害者の権利を守る戦いに,運動が変化していった。
1968年(昭和43年),第17回全国聾唖者大会は初めて「生活と権利を守る」ことをはっきり打ち出した。
それより前,1966年(昭和41年),日本教職員組合の第15次教育研究集会で,参加者の中から,障害児教育にとりくむ教師だけでなく,広く親や施設職員,医師,一般市民に呼びかけ,障害児教育に関する全国的な民間団体を作ろうという提案が出され,翌年,全国障害者問題研究会が結成された。
この研究会は,障害児の生活と発達を権利の問題としてとらえ,それを運動の基本理念とした。これらの会が中心になって,1967年(昭和42年),「障害者の生活と権利を守る全国集会」が開かれ,「障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会」が結成された。
障害の違い,立場の違いを統一した運動の始まりとして,画期的なことであった。
一方,前に述べたように,脳性マヒ者たちが,1957年(昭和32年)に「青い芝の会」を結成していたが,本格的な権利闘争,告発活動を始めたのが,この頃である。
 中央メーデーに参加。左は昭和30年代の参加者。右は1981年(昭和56年)。 |
 障害者雇用促進運動で該当キャンペーン。 |
8 働く権利の保障へ
障害者対策の中で,もっとも立遅れていたのが就労問題であった。
欧米諸国で障害者雇用対策が進む中で,障害者団体は強制割当雇用制度などを要求してきたが,政府は慎重に検討するといい続け,身体障害者雇用促進法が制定されたのは,はるかに遅く1960年(昭和35年)であった。
しかも,この法律は一部の身体障害者だけを対象にしたもので,雇用率も低く,雇用義務もない,内容の薄いものであった。
このため,制定当時から,障害者団体から法改正の強い要求が出され,ようやく1976年(昭和51年)に,雇用義務,1.5パーセントの雇用率,納付金の徴収などを規定した改正法が施行された。
しかし,この改正法でも,対象を身体障害者に限定していたため,すべての障害者を対象とする障害者雇用法を要求する運動が続けられ,1987年(昭和62年)に障害者の雇用促進等に関する法律に改められた。
一方,ワークショップなどによる(最低雇用保障制度としての)保護雇用制度の実現が,障害者団体から強く要望されているが,今のところ,実現の可能性はきわめて少ない。
そのため親たちは,障害者の働く場として,小規模作業所づくりを運動の大きな目標にしている。すでに約1,600の作業所が建設され,2万人以上の障害者が働いている。
これらの作業所に対して,国や自治体から若干の助成金がでているが,経営はきわめて困難である。
さらに最近は,製造業の不振の影響を受けて,受注が減少しており,ますます苦しい立場に追い込まれている。
そのため,これらの作業所に対する援助の要求が,共同作業所全国連絡会などすべての障害者団体からあがっている。

車いす障害者を多数雇用する大型書店が誕生した。(写真はブックセンター「スクラム」,宮城県泉市)
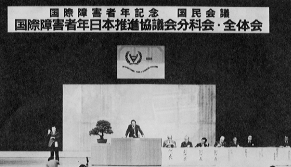 国民会議推進協分科会。 |
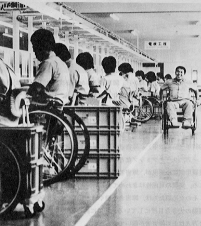 企業と自治体が共同出資して誕生した障害者のための工場,吉備松下株式会社。 |
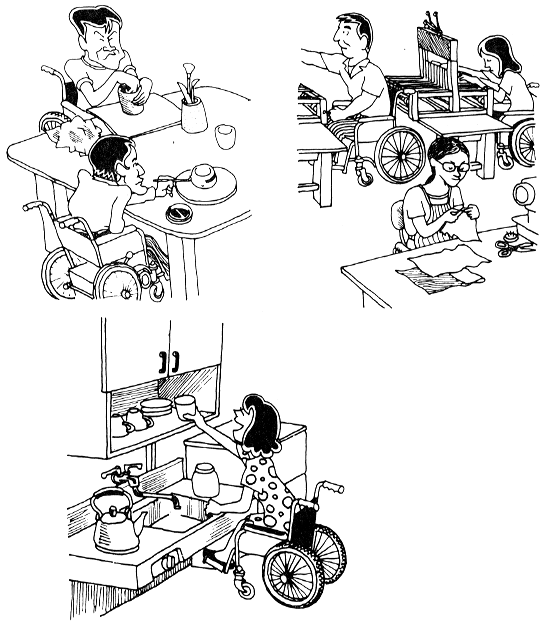
1957年(昭和32年)に誕生した障害者団体「青い芝」は,1965年頃から障害者の施設について検討を始めた。そして1975年,東京都にケア付住宅を要望,1982年八王子自立ホームが開所した。(イラスト作者・東京都八王子自立ホーム・今岡秀蔵)
 所得保障を求める運動が高まり,1981年(昭和56年)に障害基礎年金が実現した。 |
■10月26日所保連行動で厚相、所得保障制度化を約束 |
9 障害者の自立へ向けて
1981年(昭和56年)の国際障害者年の存在は,行政,マスコミに大きな影響を与え,一般市民の障害者に対する理解を前進させた。
特筆すべきことは,これを期に,従来は反目しがちであった各種の障害者団体が,その障害の種別,信条,立場を超えて,ゆるやかな組織ではあるが,国際障害者年日本推進協議会を結成したことである。この点についてはあとで触れることにする。
1983年(昭和58年),国際障害者年日本推進協議会に属する,いくつかの団体が中心になって,アメリカのIL運動(自立生活運動)の活動家を招待,「日米障害者自立セミナー」を開いた。
このセミナーは,障害者の自立と「完全参加と平等」を模索していた,日本の重度障害者に大きなインパクトを与え,各地で自立生活運動が始まるようになった。
同時に,精神薄弱者を含む障害者や家族によるグループ・ホームづくりが積極的に展開されることになった。
作業所づくりとグループ・ホームづくりは,地域で生きることをめざす障害者の最大の課題である。一方,この間,障害者の生活権を守る戦いとして,所得保障の確立があった。
所得保障については,脳性マヒ,ポリオなど稼得能力のない障害者たちが,全国所得保障確立連絡会を組織,1960年(昭和35年)頃から活動を始めていた。
国際障害者年日本推進協議会は,この運動を中心課題として取り組み,ようやく1986年(昭和61年)に,国民年金法を改正させ,国民年金の中に障害基礎年金を確立させることができた。
金額は生活保障とするには不十分であるが,初めて障害者の所得保障が制度化されたことは,大きな意義がある。
これとは別に,全障害者の結集をめざすDPI(障害者インターナショナル)に対して,日本の障害者は,1981年にシンガポールで行われた第1回世界会議以来,連携を強めていたが,1986年(昭和61年)に日本組織としてのDPI日本会議を発足させており,第16回リハビリテーション世界会議にも,障害者の意見を反映させようと協力体制を組んでいる。
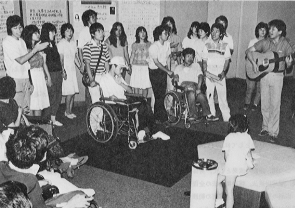
近年,障害者と健常者が音楽やレクリエーション活動を通じて交流し合う自主的な運動が全国各地に広がってきた。
10 国際障害者年日本推進協議会
国際障害者年を前にした1980年(昭和55年),国際障害者年日本推進協議会が結成された。
当初の参加団体は57,全国的な障害者団体のほとんどが加入,その後,加入団体は100を超え,現在は91団体が加盟している。
日本推進協議会は,障害者の完全参加と平等の実現をめざして,多様な障害者団体が連携して,わが国における民間の諸活動を展開することを目的とした運動団体である。
日本推進協議会は1981年,国民会議を開き,長期行動計画を策定した。以後,この行動計画の実現をめざして,毎年,国民会議を開いている。
その他の活動としては,「IYDP情報」の発行,福祉映画祭,福祉ブックェアの開催を定期的に行っている。
この間,運動の成果として,身体障害者福祉法の改正,国民年金法改正による障害者の所得保障実現,雇用促進法,精神衛生法の全面改正などの成果をあげた。
当面の課題としては,障害の範囲を国際レベルにまで拡大して,すべての障害者に対する福祉対策,就労対策を確立することをあげている。
なお日本推進協議会は,国連・障害者の10年の後期行動計画として,次の重点項目をあげている。
- 障害の範囲,等級の見直し
- ライフサイクルに対応する福祉制度の確立
- 政策形成に障害者の参加
- 障害者の権利擁護
- すべての障害者の雇用対策
- 小規模作業所への助成
- 地域福祉対策の充実
- 所得保障と介助システムの確立
- 施設の見直し
- 住宅供給,交通環境の改善
- 早期発見・早期療育と障害児保育の推進
- 統合教育の促進
- 医療の整備
- 啓発活動の推進
追録
身体障害者福祉法の1990年改正について
1.法改正の経過
わが国において「身体障害者福祉法」が制定されたのは1949年で,その後の日本の身体障害者福祉法の基本的枠組みが作られた。しかし戦後40数年を経た今日,国民の生活様式は「人生50年型」から「人生80年型」へと移行し,その価値観も多様化し個性化してきている。さらに,所得水準の向上,年金・医療制度の充実により国民の生活水準は向上し,週休二日制の普及などにより自由時間も増大している。
他方,都市化,過疎化などにより地域社会が旧来もっていた福祉的機能は弱まっている。また,核家族の進行,就労をはじめとする女性の社会進出の拡大,同居率の低下,扶養意識の変化などにより,従来家庭がもっていた福祉的機能も低下してきている。
このような状況の変化を踏まえ,これに的確に対応した社会福祉の制度を構築することが必要なことから,身体障害者福祉審議会企画分科会,中央社会福祉審議会企画分科会,および中央児童福祉審議会企画部会は,合同で企画分科会小委員会を開催し,1986年1月以来社会福祉全般にわたって中・長期的視点に立った見直しを行ってきた。この間,このような全体的な見直し作業と平行して,当面,緊急に対応すべき事項についてはその都度意見具申などにより,とるべき方策について提言を行い,これに基づいて逐次必要な制度改正が具体的に図られてきた。すなわち,この福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申により,1986年には「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整
理及び合理化に関する法律」,1987年には,「社会福祉士及び介護福祉士法」,1988年には,「社会福祉・医療事業団法の一部を改正する法律」が成立している。
この後,残された課題についても検討が進められ,これまでの3年間の審議全体の集約として「今後の社会福祉のあり方について」の基本的方向を1989年3月厚生大臣に意見具申している。
この「今後の社会福祉のあり方について」の意見具申において,次のような基本的考え方に沿った新たな社会福祉の展開を図ることに重要性が指摘された。
- 住民に最も密着した基礎的地方公共団体である市町村の役割重視
- 高齢者や障害者などが住みなれた地域で暮らしていけるように在宅福祉の充実
- 高齢者や障害者などの利用者保護を十分配慮しつつ民間福祉サービスの健全育成
- 地域社会における福祉と保健・医療の連携強化・総合化
- 高度な専門的知識・技術を備えた福祉専門職から一般のボランティアまで福祉の担い手の養成と確保
- サービスの総合化・効率化を推進するための福祉情報提供体制の整備
このように福祉関係三審議会合同企画分科会の意見具申は,ノーマライゼーションの理念の浸透,福祉サービスの一般化普遍化の動き,施策の総合化体系化の促進,そしてサービス利用者の選択の拡大という今後の福祉を考えていくうえで欠くことのできない基本的な方向性を示している。
一方障害者福祉については,1976年の第31回国連総会で1981年を「国際障害者年」とすることが決議されたのを契機として,政府に内閣総理大臣を本部長とする障害者対策推進本部が設置され,1982年に「障害者対策に関する長期計画・後期重点施策」が策定され,障害者福祉施策の推進が図られている。この「国際障害者年」およびその後の「国連・障害者の十年」は,わが国の障害者福祉を大きく進展させる契機となった。
このように,1990年の「身体障害者福祉法」を含む福祉関係八法(身体障害者福祉法,老人福祉法,精神薄弱者福祉法,児童福祉法,母子及び寡婦福祉法,社会福祉事業法,老人保健法,社会福祉・医療事業団法)の改正は,「国連・障害者の十年」の最終年を間近に控え,今後の障害者対策の展望を考えるうえでも重要であった。
2.法の目的の改正
今回の改正により「身体障害者福祉法」の目的は,「身体障害者の更生を援助し,その更生のために必要な保護を行い,もって身体障害者の生活の安定に寄与する等その福祉の増進を図ることを目的とする。」から「身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため,身体障害者を援助し,及び必要に応じて保護し,もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」に改正された。これは,身体障害者の社会参加の促進を図るという方向を積極的に示したものであり,「国際障害者年」及びその後の「国連・障害者の十年」のテーマであった「完全参加と平等」の理念に沿うものであった。また,この身体障害者福祉法と同時に改正された社会福祉事業法の「社会参加の促進,保健・医療関係機関との有機的連携,地域の創意と地域住民の理解を図る。」という地域福祉に関する基本的理念の規定と一体に理解されるものである。
この自立と社会参加の促進は,福祉の分野にとどまらず,あらゆる分野での障害者対策の基本的な目的として理解されるべきものであり,ノーマライゼーションの考え方を身体障害者福祉法の目的に明確に位置づけたものである。
3.在宅福祉サービスの推進
今回の法改正は,障害者の最も身近な行政単位である市町村で福祉サービスが統一的体系的に実施されるようにするため,ホームヘルパー,デイサービス,ショートステイのいわゆる在宅三本柱に補装具や日常生活用具の給付を加えた在宅福祉サービスが法律の中に明確に位置づけられた。ホームヘルパーは,家庭奉仕員の制度として1967年に設けられ,デイサービスは1980年,ショートステイは1987年に制度化された。しかし,今回の改正でホームヘルパー,デイサービス,ショートステイの在宅三事業は,「居宅生活支援事業」として同じ条文の中に総合的に規定された。さらにホームヘルプは,「居宅介護等事業」として介護中心の業務を行っていくことを明確にした。このホームヘルパー,デイサービスおよびショートステイの在宅三事業は,第二種社会福祉事業として改正された社会福祉事業法の中に位置づけられた。これにより,社会福祉法人の行う在宅事業の法的な位置づけが明確になるとともに,税法,開発許可等の各種優遇措置についても明確化され,供給主体整備の環境が整えられた。
次に,補装具や日常生活用具の給付・貸与の事業であるが,今回の法改正により都道府県から市町村に移譲され,住民により身近な自治体で実施されることになった。補装具の給付は,身体障害者福祉法制定当初から,日常生活用具の給付・貸出については1969年より予算措置により実施されていたが,今回の改正により身体障害者福祉法の中に明確に位置づけられ,在宅福祉サービスの一環として市町村で実施されることになった。
これらの在宅福祉サービスが市町村で着実に実施され充実するためには,市町村,とくに,町村の積極的な取り組みと国や都道府県の支援体制が必要である。国が在宅福祉サービスの支援体制を強化するために,今回の身体障害者福祉法の改正とあわせて社会福祉事業法において,社会福祉協議会および共同募金の活動の推進がもりこまれた。また,社会福祉・医療事業団に長寿社会福祉基金が設けられ,総合的な在宅福祉サービスが安定的に提供されるための助成が行われるようになった。この在宅福祉サービスを支える福祉マンパワーの確保は極めて重要な問題なので,その処置の改善,人材の養成・研修などに必要な予算措置を講じている。そして,厚生省に事務次官を本部長とする保健医療・福祉マンパワー対策本部が設けられ,検討が進められている。
4.身体障害者更生援護施設への入所事務等の町村への移譲
今回の法改正により,身体障害者更生施設や身体障害者授産施設など身体障害者更生援護施設への入所事務は,1993年4月1日から都道府県(福祉事務所)から町村に移譲される。この他に更生訓練費の支給,更生医療の給付,補装具の給付等の事務があわせて町村に移譲される。なお,身体障害者手帳の交付,更生医療の担当医療機関の指定,特別障害者手当の給付事務は,法改正後も従来どおり都道府県が行う。今回の法改正により都道府県から町村に移譲される主な事務については表1に,町村への移譲に伴う体制の変更については図1に示す。
この入所事務等の町村への移譲は,今後の福祉サービスを住民に最も身近な自治体である市町村を中心に実施し,在宅福祉サービスと施設福祉サービスを総合的一元的に提供しようとするものである。福祉サービスは,それぞれのニーズへのきめ細かな対応が必要であり,また,地域ごとの創意と工夫を必要とするので,身体障害者の事情をよく把握でき,地理的にも身近なところにある市町村が中心になって提供されるべきであるという在宅福祉サービスの考え方に基づいている。
わが国には約3,300の市町村があり,それぞれの地域の置かれた実情も大都市,地方都市,過疎町村などで非常に異なっている。従って市町村ごとに福祉サービスの水準に不合理な格差が生じないようにしていかなければならない。国としても必要な予算措置やマンパワーの確保,交付税措置などの支援措置を講じ,さらに都道府県においてもバックアップする必要がある。改正された身体障害者福祉法では,都道府県は福祉事務所などを中心に身体障害者の援護を実施するために,市町村相互の連絡調整,市町村への情報提供など必要な援助を行い,必要に応じて市町村に助言することができるとされている。
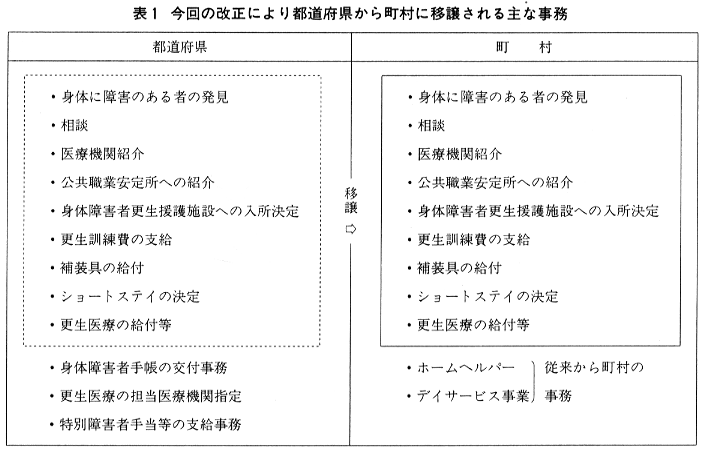
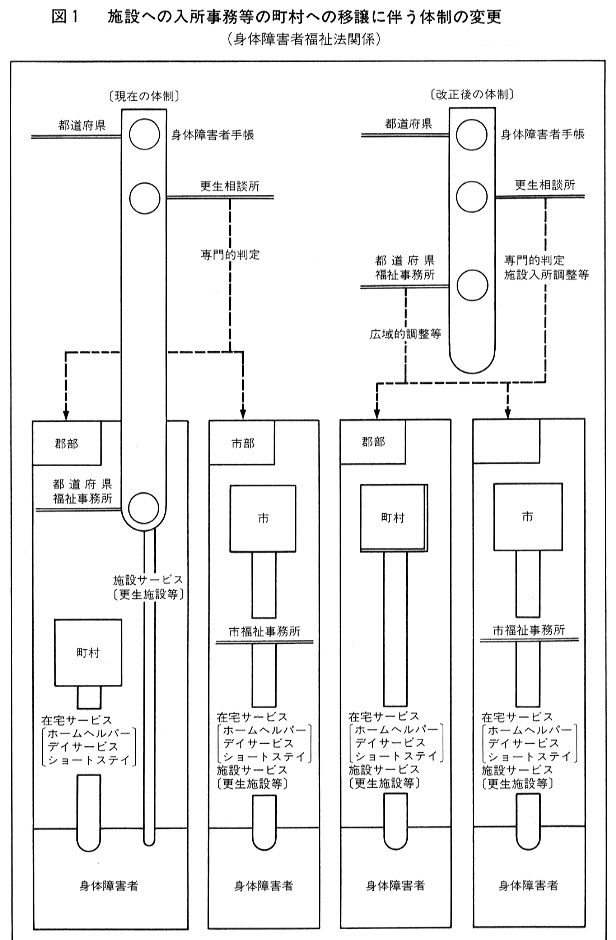
5.身体障害者更生相談所の機能充実
身体障害者更生援護施設への入所事務が町村へ移譲されるに伴い,身体障害者更生相談所は,市町村に専門的技術的援助や助言を行うなど市町村を中心に実施される福祉サービスの技術的中枢の役割を果たすことが求められている。具体的には,身体障害者更生相談所に身体障害者福祉司を置かなければならないとされ,現行の専門的判定業務に加え,身体障害者更生援護施設への入所措置の市町村間の調整,市町村への専門的技術的援助・助言など新たな役割が追加されている。
6.視聴覚障害者情報提供施設の創設
今回の法改正で身体障害者更生援護施設の一つとして,視聴覚障害者情報提供施設が法定化された。この施設は,従来の点字図書館,点字出版施設に新たに「聴覚障害者情報提供施設」を加えた総合的な情報施設として位置づけたものである。従来の法定施設が視覚障害者に対する施設であったことから,聴覚障害者に対しても同様の施設の創設が求められていた。また,近年の情報技術が進展したことから聴覚障害者や視覚障害者など情報の受容が通常の手段では困難な人々への対応が強く求められていたことなどがこの施設創設の基礎にある。
この聴覚障害者情報提供施設は,聴覚障害者用字幕や手話入ビデオカセットの製作や貸出事業を主たる業務とし,あわせて手話通訳者の派遣,情報機器の貸出等コミュニケーション支援事業,聴覚障害者に対する相談事業を行うことになっている。また,関係行政機関および障害者団体などと協力し,聴覚障害者の文化,学習,レクリエーションなどを援助するとともに,その推進に努めることとされている。すなわち,聴覚障害者情報提供施設は,聴覚障害者の情報やコミュニケーションについて総合的なサービスを提供する施設として位置づけられている。
7.まとめ
1949年の身体障害者福祉法の制定以来,その枠組みが形成されてきた身体障害者福祉制度は,現在ひとつの転換期にさしかかっている。人口の高齢化,国民意識の多様化・個性化,家族形態の変化,所得水準の向上等に代表されるようにわが国の生活構造や社会構造は大きく変化してきており,これに対応して国民の福祉に対する需要も多様化高度化してきている。
このような変化に的確に応え,人生80年時代にふさわしい長寿・福祉社会を実現するためには,きめこまやかな福祉行政の展開が急務である。このため,身体障害者福祉法を含む福祉関係八法の一部を改正し,身体障害者福祉をはじめとする福祉の各分野について在宅福祉サービスの一層の充実や市町村において在宅福祉サービスと施設福祉サービスを一元的に供給できる体制の整備を図ることになった。
〔参考文献〕
月刊福祉増刊号『福祉改革〈福祉関係三審議会合同企画分科会意見具申をめぐって〉』全国社会福祉協議会,1989.
厚生省社会局・大臣官房老人保健福祉部・児童家庭局監修『社会福祉8法改正のポイント』第一法規,
1990.
本書に掲載された写真は,以下の団体等の御好意及び御協力によるものです。
(五十音順)
オリエンタルランド
北養護学校
国際協力事業団青年海外協力隊事務局
国際障害者年日本推進協議会
国立職業リハビリテーションセンター
(株)松竹
新宿区あゆみの家
時事通信社
全国社会福祉協議会
全国精神障害者家族連合会
全国特殊教育推進連盟
東京コロニー
東京障害者職業センター
東京映像工房
東京都障害者総合スポーツセンター
東京都福祉局障害福祉部
日本障害者雇用促進協会
日本身体障害者スポーツ協会
福岡県田川市役所
平凡社
主題:
日本のリハビリテーション No.9
173頁~199頁
発行者:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
編集:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
発行年月:
1992年8月31日
文献に関する問い合わせ先:
財団法人 日本障害者リハビリテーション協会
〒162 東京都新宿区戸山1-22-1
電話 03-5273-0601
FAX 03-5273-1523
