青年期の精神薄弱者を対象としたオペラント技法の適用
青年期の精神薄弱者を対象としたオペラント技法の適用
─職業行動変容プログラム─
Modification of Vocational Behavior In a Community Agency for Mentally Retarded Adolescents
Reymond J.Trybus,Ph.D.& Patricia B.Lacks,Ph.D.
奥野英子*訳
|
著者について… Dr.Trybus はワシントンにあるGallaudet College のカウンセリング・職業あっせんセンターで臨床心理士として働いている。以前は、St.Louis Jewish Employment and Vocational Service の作業経験センター(Work Experience Center )で心理判定員として働いていた。1971年にセントルイス大学で博士号を修得した。博士はおもに、青年期の精神薄弱者や複合障害のあるろう者のカウンセリングや研究活動に従事してきた。 Dr.Lacks はSt.Louis Jewish Employment and Vocational Serviceの研究部長であり、ワシントン大学では心理学の講師として、行動変容(behavior modification )講座をもっている。同女史は、精神病患者を対象とした、セラピスト、研究者、スーパバイザーとして活躍してきた。同女史は1966年にワシントン大学で臨床心理学の修士号を修得した。現在は、職業リハビリテーションへの簡潔かつ革新的なアプローチに興味をもっている。 |
作業を通して精神薄弱者の行動を修正しようとする技法の効果については、文献でもって実証されている。しかし、精神薄弱者に適用するオペラント技法(operant methods )の大部分は、トイレ訓練、衣服の着脱、食事動作などのような基本的日常動作の単一技能に限られていたようである。最近では、行動変容技法を、精神薄弱者の社会的技能、すなわち、言語問題や人間関係に適用するようになってきた。攻撃的であったり破壊的であるというような、反社会的な行動には懲罰を加え、望ましい行動にはほうびを与えることによって、よい行動を助長するようにしてきた。
Parsons State Hospital and Training Centerで実施された事業を除くと、精神薄弱者の職業技能を伸ばすために行動変容技法を使ったという研究は、ほとんど発表されていなかった。Parsonsで実施された事業は、次のような点において特に意義深いものである。
まず第一番目の理由は、このセンターでは、家事作業やシェルタード・ワークショップに適した単純なくり返し作業の訓練を実施し、精神薄弱者の作業技能を伸ばそうとしたことである。第二番目の理由は、このプロジェクトの目標として、保護・療護の面から扱いやすくするだけでなく、患者が地域社会において生産活動に従事できるようにさせることを掲げているからである。
ここ数年間、精神薄弱者を対象にした行動変容プログラムは、その職業訓練に目を向けるようになってきた。すでに発表されているいくつかの研究によると、焦点は単純作業の生産性をあげることに置かれてきた。まず初めは学校や施設内において、そして次の段階として、シェルタード・ワークショップにおいてである。
一番最近の研究では、より複雑な作業を教えるために作業分析技法と行動変容技法を統合化するばかりでなく、生産性をあげるためのより効果的な技法を各種比較検討したり、より工夫された促進手段(reinforcer)を開発しようとしている。後者の研究においては、時間給・ボーナスの支給、作業における進歩状況の図表化、フィードバック方式の採用、口頭でほめること、などのような促進手段を活用し、継電器板や自転車用ブレーキの組み立てやスケートぐつみがきなどのような、複雑な作業をする能力をも伸ばそうと訓練者は努力している。
リハビリテーション分野の行動変容に関する文献のもう一つの傾向としては、多分野からアプローチする研究方法論が不足していることである。目標行動(target behabior )を計る適切な基本線もないし、対象者の行動制御をデモンストレートする各種体系的手段もないし、行動を客観的に観察できる実証もないし、追跡調査の資料もほとんどない。
まだ絶対的に実証されているわけではないが、精神薄弱者の職業技能を開発するためには、行動変容技法が理想的なようである。したがって、このプロジェクトの目的は、行動上の問題がかなりあるために、精神薄弱者のための地域サービス機関にはいることができず、家族といっしょに暮らさざるをえない若者を対象とし、その職業上の問題点を解決するためにオペラント技法(operant methods )を適用できるかどうかを研究することにある。研究の困難性を緩和するために、ここでは、Sidmanが記述している単一構造・対象者実験法(single organism,within-subject experimental design )を採用した。
方 法
被験者
St.Louis Jewish Employment and Vocational Service の作業経験センターで一年以上にわたって実施され、行動訓練ユニット(Behavioral Training Unit, 略号BTU)と呼ばれる実験的プログラムのなかで、この研究事業を進めてみた。
この機関(St.Louis Jewish Employment and Vocational Service )は、学校を卒業した青年期の精神薄弱者をおもな対象とし、地域社会を基盤とした職業プログラムおよび職業に関連のある臨床サービスを実施している。このプロジェクトが実施された15か月間に、19名のクライエントがBTUで訓練を受けた。その訓練期間は個人個人まちまちであり、3週間の者もいれば、38週間訓練を受けた者もいる。被験者は、知能、行動、生育歴においてかなり差異があったが、19名とも精神薄弱者という範ちゅうにはいる者であった。
すべてのクライエントは、かなりの行動問題(behavior problems )を表出しており、そのために、通常のリハビリテーション・サービスも受けられず、また作業生産性も非常に低くなっていた。彼らのほとんどは、生産性もなく、動きのない生活を家族とともにすごしており、家族にとっては多大な重荷となっていた。
BTUに参加したすべての被験者にオペラント技法(operant technics)が適用されたが、研究のための体系的データは、さいごの5名だけにしぼられた。
被験者1は20才の白人女性で、郊外で生活している中流家庭の出身であった。彼女の計測IQはだいたい60から70であり、精神薄弱児学級ですべての教育を終えていた。彼女の典型的な行動は、彼女と接するほとんどの職員を敬遠させていた。その行動とは、自分の職場、仕事、次の作業などの詳細について、質問を絶え間なくくり返すのである。彼女の質問に対して回答がなされなかったり、自分がじゅうぶんに評価(賞賛)されていないのではないかと感じるときには、作業速度を非常に落とし、〈空想にふけっている〉ふりをする。ときどき、彼女は〈発作〉を起こし、口を絶えず動かし、不覚状態ですわり込んでしまう。医療診断や行動調査によると、この発作の原因は神経損傷によるものでなく、むしろ機能上の原因によるものと判断された。
被験者2は、42才の黒人男性で、青年中期以来地方の州立病院で生活してきた。彼の計測IQは測るごとに、55から65の間を行ったり来たりしている。彼はBTUにはいってくる数か月まえに、病院から寄宿舎に移され、職業リハビリテーション・サービスを受けたが、低い生産性のままで、なんの進歩も見られなかった。ワークショップにはそれなりの需要、規則、スケジュールがあるので、自分で好きなように時間を過ごせる安易な日日の州立病院生活に比べると、ワークショップの生活はきびしく感じたのであろう。
このワークショップで、生産性を上げることによって稼ぐ、という過去20年間放棄してきた権利を、彼はこのBTUで要求されたのである。しかし、自分がやりたくないことを要求されると、自分の胃のあたりをつかみ、「俺は病気なんだ!」と叫び声をあげ、ワークショップからとび出し、診療室のベッドに横になってしまう。いったん診療室に逃げ込むと、激しくマスターベーションし、仕事場に戻ろうともしなければ、ベッドを離れようともしない。
被験者3は、16才の黒人少年で、荒廃した都市部に住む貧困家庭の出身であった。過去についての正確なところがわからないが、1~2才のときにかなり強く頭を打ったのではないかという痕跡がみられる。その後、ひとこともしゃべらず、また、ひとの言うことばもほとんど理解できなくなっていた。身体の協応や全体的な運動機能にはほとんど障害がないようであった。頭部に受傷して以来、学校に通ったこともなければ、家族の世話を受けたこともなかった。その結果、彼に生産的な労働を期待したり、最小限の社会性をさえ望む者はひとりもいなかったようである。実際にBTUで仕事をやらせてみても、彼の生産性は最下位であり、絶えず監視していなければ、ものの3~4分と作業室にとどまってはいない。
被験者4は、20才の白人男性で、労働階級家庭の出身である。彼の計測IQは31であった。6年まえに測ったときはIQが50代であったのに、時がたつに従い、徐々にIQが下がっていった。この被験者は、薬を多量に服用しているにもかかわらず、8日に一度ぐらいずつ悪性のひきつけを起こした。
この被験者4は、身体的にもみにくく、全体的な運動機能や細かな動作の協応が非常に悪かった。彼は、自分のすることはなんであれ、ほめられたり、報いられなければ、承知しないようであった。彼はシェルタード・ワークショップのプログラムに登録されたが、数週間後に次のような理由で退所させられてしまった。生産性が非常に低く、仕事ちゅうにも失禁し、どんな規則や作業過程にも従がおうとしない、という理由で。
被験者5は、20才の白人女性で、ダウン症であり、郊外に住む富裕な中産階級の出身であった。彼女は6人兄弟の末っ子で、ほかの兄弟たちはみなすでに独立しており、彼女だけが両親と生活をしていた。彼女の両親は彼女をあるがままに受け入れ、彼女にはなにも期待してはいなかった。彼女の計測IQは40から50の範囲内であった。
彼女の生産性はグループのなかで常にトップであり、だいたい一日に4ドルぐらいを稼いでいた。彼女が地方のシェルタード・ワークショップで正式被雇用者として受け入れられない唯一の原因は、彼女が絶えずげっぷをするからであった。彼女の近くにいる人に向かって、わざとげっぷをするのだが、それは非常にわずらわしい行動であり、それもしょっちゅうなのである。これは作業ちゅうにし、げっぷをしたあとは必ずにが笑いし、くすくす笑い出すのである。この行動は家庭や学校では起こらなかったが、学校時代にも、同じような挑発的な行動をしていた。
訓練ユニットのスタッフ
訓練ユニットのスーパバイザーを3名の女性がつとめた。そのうちの2名は地方の大学に在籍する学生であり、あとの1名は高校生で、3名いっしょにこの作業研究プロジェクト(work-study projects )に参加した。3名のスーパバイザーのうち、オペラント方法論(operant methodology )に関する教育を受けた者はひとりもなく、また彼女らの学問的背景にしても、一般心理学とか児童心理学の講座をとったこと以上の経験はなかった。彼女らの訓練としては、児童に関する本を読んだり、プロジェクト・コーディネーターである機関の心理職員と討議したり、役割演技をしたり、各種具体的な問題の処理のしかたを話し合ったり、クライエントと実際に接触している心理職員の行動を観察したり、などが行なわれた。
スーパバイザーが、クライエントと実際に作業を開始すると、実験室内で行なわれている活動を、一方からしか見えない特殊スクリーンでへだてられ、サウンドシステムの整ったブースから、心理職員が観察した。この装置というのは、スーパバイザーがつけているミニFMレシーバーと、心理職員が指導を伝える短波FM送信器から構成されている。その後、スーパバイザーの訓練は、特にむずかしいクライエントの問題があった場合にのみ、数時間話し合う、というかたちに徐々に縮小された。
訓練方法
生産性の低さがすべてのクライエントに共通の問題であったので、クライエントが生産性をあげた場合にほうびをあげるという報奨システム(token system)が訓練方法の主要部分となった。この報奨システムとは、生産性が伸びたクライエントにプラスチックの札をあげ、クライエントはこれをほうびのものと交換できるのである。ほうびのものとして、食料品(キャンディー、ナッツ類、少量のサンドイッチ)や、休憩時間やカウンセラーとおしゃべりする時間を与えたり、お金やタバコを与えたり、または、2~3種類の仕事から自分の好きな作業を選べたり、作業中に腰かけられるイスを貸したり、ライトの点滅係というような目新しい任務につかせたり、好きな作業場を選べたり、などである。
この選択項目については、クライエントにリストを渡したり説明をし、それでももしクライエントが報奨項目を選択しようとするときに戸惑うようだったら、また説明したり助言をしたりする。もしリストに載っていたものがなくなれば、リストを改正した。プラスチック札の数も事前に公表し、その経費は、生産性の進歩があがるにつれて増加した。
生産性があがるにつれ、個々のクライエントに合わせた目標行動(target behaviors)を設定した。目標行動を設定する場合には、ユニットにはいってきた第一日目のクライエントの様子をしっかりと観察し、またクライエントに関する参考資料なども参考にして決める。このような目標行動を設定するのは、わりにたやすいのである。
というのは、たとえば被験者5はげっぷをするケースであり、そのためにBTUにまわされて来たことがはっきりしているからである。そのほか共通の目標行動としては、度を越した人まねをすることや、作業台の上の部品がなくなってもそのまますわっていたり、絶えず作業場を離れること、などである。複合問題をもつケースは特に注意され、クライエントとスーパバイザーの両者ができるだけ早く成就感を感じられるような行動を選択する。
また、この目標行動は、報奨システムを活用することによって、途中変更されることもある。そのうえ、目標行動を変えるための有力な手段として、クライエントに対するスーパバイザーの配慮を多くしたり、差し控えたりする。これは明らかに、多くの被験者にとって有力な手段となった。したがって、BTUのスーパバイザーは、スーパバイザーの注意を引こうとして奇異な挙動をするクライエントを無視しなければならない。
たとえば、うしろにそっくり返って、スーパバイザーのひざに顔を押しつけたりする行動である。このような奇異な挙動がなくなったときにすぐ、スーパバイザーの注意が向けられるようにすると、ある被験者は適切な作業活動に従事できるようになった。この段階ではっきり言えることは、15か月間にわたったプログラムにおいて、望ましい行動に修正するために刑罰を用いなければならなかったケースは、19ケースのうち、ただの1ケースだけだった、ということである。
ただ一つの〈装置〉が使用されたが、それはライト点滅機一式であった。この装置を簡単に説明すると、適切な行動が行なわれた場合には黄色のライトを継続的かまたは断続的につけるのである。不適切な行動があった場合には、赤いライトをつけ、ブザーを鳴らすのである。ライトによって二つの状態を区別する方法は、作業遂行方法が正しかったかまちがっていたかを弁別する場合にも用いられることがあるが、しかしそれよりも、作業遂行速度を明示するために利用されることのほうが多い。
たとえば、クライエントが作業に着手したばかりの時期には、一つの作業を終えるのに平均85秒かかったとしよう。もし普通の労働者がその作業をする場合、15秒しかかからないとする。クライエントが85秒内でその作業を終えれば黄色のライトがつく。もし85秒以上かかれば、赤いライトがつき、ブザーも鳴る。徐々に規準遂行速度が下げられ、80秒、75秒、70秒となっていくのである。
これらのオペラント技法(operant technics)のほかに、BTUは典型的なシェルタード・ワークショップを模倣した作業場面を設定した。というのは、ほとんどのクライエントがBTUのあとに配置されるのは、そのようなシェルタード・ワークショップだからである。毎朝、訓練センターに着くと、訓練生はタイムカードを押し、それから訓練室にはいる。そこには彼の仕事を指示するスーパバイザーが待っている。スーパバイザーが割り当てた仕事を一日じゅうするのであるが、同じ仕事は通常、5~6日続く。ここでの仕事は、地方のシェルタード・ワークショップで行なわれるような典型的なもので、単純な組立作業や包装作業である。実際の契約仕事(contract work )をできるかぎり多く取り入れた。そしてその契約仕事で足りないところを、訓練のためだけの作業で補った。
訓練のためだけの作業は、次のような三つの場合に行なわれた。1)特定の訓練生が特殊な活動を必要とした場合、2)訓練生の生産性が非常に低いため、実際の契約仕事をやらせるわけにはいかない場合、3)実際の契約仕事がない場合。
スーパバイザーは常にユニットのなかにいるのではなく、観察室から観察したりもする。シェルタード・ワークショップでは、スーパバイザーが常に同席しているわけではないので、そのような現実的状況にできるだけ近づけるためである。
ほうびは次のような二つの方法でクライエントに与えられる。まず第一番目の方法とは、個々のクライエントごとに設定された行動をしたときにすぐに与える方法である(たとえば、クライエントAが15秒以内に一つの作業工程を終えたたびにとか、クライエントBが作業台の上にある仕事を終えたらすぐにまた必要な部品を補充した場合など)。また第二番目の方法とは、以下のようなさまざまな場面に応じて与えられる。タイマーをセットしておき、10分間ぐらい鳴るしかけにしておく。そのときに適切な仕事に従事していた者はだれでも、ほうびを受け取れるのである。ほうびはクライエントの前にある容器に入れてあり、毎日一定の時刻に取り出せるようになっている。
クライエントの行動が制御されているかどうかをはっきり表示するために、Sidmanが提唱した方法を取り入れた。被験者1および被験者2は、基線(Baseline)―訓練第一期(First Training Period )―逆転期(Reversal)―訓練第二期(Second Training Period)―フォローアップという段階を経る。被験者3の場合は、〈逆転期〉のかわりに〈基線に戻る〉ことにした。被験者4および被験者5については、データ収集の予算がなかったため、このような研究過程を用いなかった。
基線が作業の始まりであり、ときどきスーパバイザーが点検するものとするが、このような状況はセントルイス・シェルタード・ワークショップの状況とほとんど同じである。訓練期間には報奨システムを採用する。逆転期にも報奨システムを続けるが、その条件は変わる。したがって、訓練期間ちゅうに生産性があがっても、逆転期で生産性が下がることになる。基線へ戻るとは、すなわち、報奨システムの停止を意味する。最後に、4週間のフォローアップが被験者ごとに計画される。
このようなすべての条件づけのなかで、スーパバイザーは、クライエントの生産性や特定の行動を記録する。特定の行動とは、たとえば、トイレへ通った回数とか、部品を床へ落とした回数とか、かんしゃくを起こした回数である。しかし、スーパバイザーはオペラント・システムの実施を主要目的としているので、そこに収集されたデータは粗雑であったり、不完全なことがしばしばあった。研究ニードを満たすためには、観察室にある特別データ収集機を使って、より詳細なデータを収集しなければならない。
これらのデータは各クライエントについて、10分間ぐらいの時間を使って収集される。スーパバイザーの観察が正しいかどうかは、四つのデータ収集機でときどきチェックされる。たとえば、げっぷをした回数、一つの作業を終えるのにかかった秒数などである。一定の時間内に起こるすべての活動を記録するために、観察時間を計画化しようとしたが、このようにして比較検討することはむずかしいので、個々のクライエントの特定行動を図表化することにした。
結 果
BTU実施ちゅうに、かなり広範囲にわたる詳細なデータが収集された。本稿では紙面の都合もあって、データのサンプルだけを載せることにした。したがって、次のような三つの図表を、BTUで実験された各種オペラント技法の代表的なものとして、ここに表出した。
図1は、報奨システムを活用することにより、被験者2と被験者3の生産性が上がったことを表示している。その結果は、「普通生産水準のパーセント」**として表示されている。この図をよく検討してみればわかるが、基線における生産性は非常に低く、被験者2と被験者3の両者とも、普通水準の30パーセント以下であった。しかしながら、訓練第一期では、被験者3の生産性は多少上がっており、また、被験者2の生産性の上昇はめざましいものである。被験者2は逆転期で、被験者3は基線へ戻る段階で、その生産性を基点にまで下げている。訓練第二期では、また生産性が伸びている。被験者2および被験者3をフォローアップする予定だったが、管理上の問題で2人をもとの施設にもどさなければならなくなり、フォローアップはできなかった。
図1.報奨システムの採用による生産性の伸び
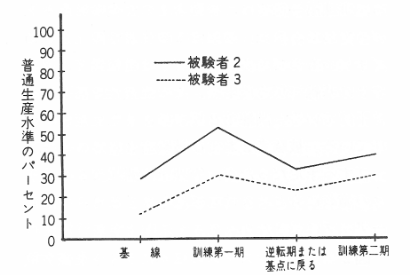
図2は、報奨システムのほかにライト点滅方式を利用した場合の生産性の変化を図表化したものである。基線においては、被験者1の生産性は普通水準の26パーセントであった。訓練第一期に報奨システムだけを採用したが、その期間(8日間)の生産性は伸びなかった。訓練第一期後半には、ライト点滅方式を交互に採用してみたら、ライト点滅方式を採用した期間の生産性は58パーセントにまで上がり、ライト点滅方式を採用しなかった時間の生産性は32パーセントであった。
図2.ライト点滅法の効果
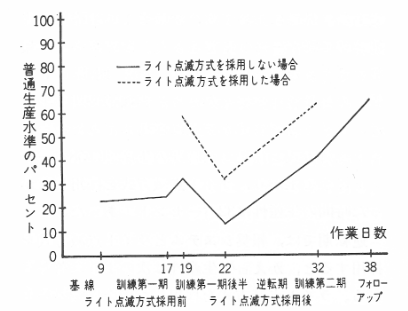
逆転期では、報奨システムとライト点滅方式を採用すると、かえって生産性は次のように落ちている。ライト点滅方式を採用した場合は23パーセント、ライト点滅方式を採用しなかった場合は14パーセントにまで下がっている。訓練第二期には、ライト点滅方式を採用した場合だと64パーセント、ライト点滅方式を採用しない場合だと41パーセント、にまで生産性は上がっている。このような結果をみてみるとよくわかるように、被験者によっては、ライト点滅方式は報奨システムよりもずっと効果をあげられるのである。
このような方法を採用した場合の最終的な成果は、フォローアップの数字で明らかになるであろう。このフォローアップの数字は、訓練室を出て一般のシェルタード・ワークショップで行なわれた仕事の生産性を示している。すなわち、もはや報奨システムやライト点滅方式は採用していないのである。4週間にわたってフォローアップをしたが、被験者1の生産性は平均65パーセントであった。
図3は、作業妨害行動(work-interfering behaviors )をなくすために行なった実験の結果を表わしている。この結果は被験者4に行なったものである。被験者の行動は、人間関係や社会的関係によってかなり制御されているようなので、もし被験者が次のような四つの作業妨害行動をしだしたとき、スーパバイザーはわざとその被験者を無視するようにした。
四つの作業妨害行動とは、作業イスを離れること、作業台に向かわずイスをうしろに向けること、長々とおしゃべりをすること、ネジを作業台に置き仕事をしようとしないこと、である。このような作業妨害行動のあと、適切な作業状況に戻って60秒以上きちんと仕事をしてから、初めてスーパバイザーはその被験者に注意をそそぐのである。図3を見れば明らかなようなに、このような四つの作業妨害行動はたちまちのうちに、完全に消滅している。記録を取らなくなってからも、その後8か月間観察してみたが、この四つの作業妨害行動はまったく表われていなかった。
図3.作業妨害行動の消滅
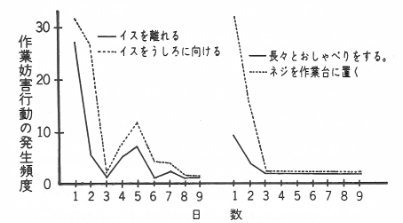
懲罰方法を使ったケースというのは、げっぷをわざとする被験者5だけである。懲罰を課すまえは、一日に平均138 回げっぷをした。初期には、1時間に200 回もげっぷをしたことがあったほどである。げっぷをするのは、自分のまわりにいる人の注意を引くためなので、被験者5がげっぷをしてもスーパバイザーは無視するようにした。でも、いっしょに仕事をしているクライエントが注意を向けてしまうので、これも効果がなかった。げっぷをしないときにほうびを出すようにしたが、これもあまり効果がなかった。
被験者5がげっぷをしても、他の被験者に無視させるようにしたが、これは完全に守られなかったので、やはり失敗に終わった。最後に取り入れた方法は、げっぷをするたびに被験者5の髪の毛を引っ張ることにした。そうすると、げっぷの行動はたちまちのうちに完全になくなってしまった。最初の日は4回だけげっぷをしたが、次の10週間は一日につき1回以下の頻度になった。そしてとうとう発生頻度0に到達したのである。発生頻度が0になってからは、12週間にわたるフォローアップの期間にも、その行動は起こらなくなった。
客観的にかなりはっきりと表現される、このようなクライエントの進歩のほか、一年間にわたったBTU実施の間に、かなり主観的な面での成果があげられた。たとえばある一人のクライエントについて述べてみよう。彼は車イスを使用していたが、車イスを人の向こうずねに当てて、その人を部屋のすみに追い込むという悪癖があった。BTUにはいってからは、作業時間ちゅうは普通のイスにすわらされた。したがって車イスを使ってした以前のいたずらができなくなったのである。
数週間たつと、作業上の行動もより適切になってきたので、ほうびとして車イスの使用が許可された。車イスを使用していたずらをしたら、すぐに車イスを取りあげるという条件を付けた。このようにしても、車イスのいたずらが全くなくなったわけではないが、しかし、いたずらの発生率は非常に減少した。
計測IQが31のもう一人の少女は、指を絶えず動かしながら空想上の人に話しかけたり天井に向かって話すというような、典型的な自閉症状を示していた。BTUのスタッフが呼びかけても、ちっとも反応しようとしなかった。BTUで12週間過ごすと、彼女はまわりの人に普通に反応できるほどになり、自閉症の症状も表わさないようになった。このようなよい結果が、ダウン症の少女にも表われた。彼女は、だれにでも抱きついたり、作業台の下に隠れたり、わけもなくくすくす笑ったりして、非常に未熟な行動を示していた。
ある一人の男性のクライエントは激情に走る傾向があり、学校で常に問題を起こしていた。しかしBTUで進歩し始めると、非常にうれしくなり、新しい進歩があるごとに、学校時代の担任教師に報告にいくようになった。
一つの事件をここに説明することにより、BTUで実施されたオペラント・システムの成果を要約することができよう。一人の女性のクライエントはほかの女性の注意をひこうとして、一時間にわたってその女性にネジを投げつづけた。ネジを投げつけられてもその女性は気を散らさず、仕事をし続けたが、ついに彼女の堪忍袋の緒が切れた。彼女はイスを立ち、ネジを投げた女性をぶとうとして手を振り上げた。しかしその瞬間ちょっと戸惑い、そして、彼女自身がオペラント技法を使おうとしたのである。というのは、仕事を妨害した懲罰として、じゃまをした張本人であるクライエントの机の上から、彼女のほうびを取りあげたのである。
検 討
小規模なリハビリテーション・ユニットでの実験をここに記述してみたが、青年期にある精神薄弱者の職業能力を伸ばすのにオペラント技法が有効であることを理解していただけたであろう。この研究に参加したクライエントは、中度から重度の範ちゅうにはいる精神薄弱者であり、また行動上の問題があるために、シェルタード・ワークショップででも働けなかった者たちであった。BTUの実験によって、オペラント技法は作業妨害行動(work-interfering behaviors)をなくせるとともに、クライエントの生産性をあげられることが実証された。事実、BTUに参加した最後の10名の日給は、参加した当時の1.60ドルから、最後の週には2.35ドルを稼げるまでに上がった。そしてそれを平均すると、一日につき75セント稼げることになる。
また、これらの数字は次のことを示している。オペラント技法を活用すれば、どうしても生産性が上がらず在宅にならざるをえない者と、地域社会で生産的な仕事に従事できる者を判別することができるのである。19名のクライエントの追跡調査をしてみたら、9名はシェルタード・ワークショップで働いており、その生産性も他の入所者に負けていないし(1時間につき40~45セント稼いでいた)行動問題もあまり起こしていない。このような進歩はクライエント本人に役だつばかりでなく、その家族にも大きな影響を与えているのである。クライエントがこのように進歩しなければ、毎日24時間、1週7日間、扱いにくい人の世話を家族がみなければならなかったのである。
19名のクライエントのうち、そのほかの7名は自宅か州立病院に帰されており、残りの3名については、情報を手に入れることができなかった。われわれが扱ったクライエントのうちの40パーセントがなぜシェルタード・ワークショップに就労できなかったのかを分析してみた。その結果、オペラント技法を採用することによりクライエントの生産性を伸ばせたが、それはクライエント自身の内部に恒久的変化をもたらせたのではなかったからである。
ある人がわれわれの社会で〈精神薄弱者〉と呼ばれるようになる理由は、その社会、仕事、学習環境が彼から引き出す行動が、同じような状況に置かれた多くの人びとの行動と比較して、かなり違っていたり、不適切であったりするからである。したがって、個々の人びとがもっと適切な行動を出せるような環境をつくりあげるという課題が生まれてこよう。
このプロジェクトによって、オペラント技法を使ったワークショップは、困難な問題をかかえた者の生産性をあげることができると実証された。また、BTUという特殊な環境で達成された行動変容は、普通環境に戻ったクライエントにも有効であることが実証された。しかしクライエントによっては、その修正された行動がどれくらい続くかは、改善された環境がどれくらい続くかにかかっているようである。
クライエントがBTUに参加している期間ちゅうに、その家族と協議して、クライエントの家庭の環境をより改善するための努力がなされた。一例をあげてみるが、BTUにおいて行動上の進歩があった場合はそれを家庭においても継続させるようにしたり、その逆にしたりするのが有効のようである。
仕事ちゅうに絶えず失禁するクライエントは、家庭での偶発事件を利用して、この行動を改善することができた。このクライエントは毎日午後自宅でソーダ水1本が与えられていた。BTUに来て失禁しなかった日には、ソーダ水をあげることにしたら、その後5、6週間失禁しなかった。そしてその後6か月も失禁がなく、ソーダ水をあげなくても、失禁しなかった。これは被験者4の実例であるが、このクライエントは神経上の問題もあり、また数多くの不適切行動があったのだが、このように進歩したのである。
しかしながら、家庭状況やシェルタード・ワークショップの状況を変えることのできないクライエントもいた。ときには、クライエントが配置されたシェルタード・ワークショップが、BTUで使われたオペラント技法の逆をしている場合もあった。達成された作業やよい行動に対してなんのほめことばもなければ、給料も1か月に2度しか与えられなかった。BTUにいたころと同じぐらいの給料を稼げたとしても、クライエントにとってはもっと薄っぺらなものに思えたであろう。
なぜなら、クライエントにとっては、お金はほうびのしるし以外のなにものでもないからである。クライエントにとっては、5セントのほうが25セントよりも価値があるのである。25セント銅貨では自動販売機でコーラを買えないからである。また、もっとも大きな力づけとなるのは、個人的な注意を向けてもらえることであるが、シェルタード・ワークショップではこれが満たされることが少なく、またクライエントに注意が向けられるのは、適切な行動をしたときよりも、軌道を逸した行動をしたときになりがちである。クライエントの存在を認めてあげるような注意を向ければ、BTUで伸ばされたよい行動をたちまちのうちに呼び戻せるであろう。
もう一つの課題をここで取りあげたい。それは、BTUの成果を客観的に記述することのむずかしさについてである。すでに説明したが、リハビリテーションにおける行動変容研究を進めるには、多面から研究できる方法論が不足している。この研究でも、われわれはこのような現実の困難性を克服しようとしたが、しかし、研究上のニードよりも、事業運営上のニードが先行してしまったきらいがある。
もっとも困難であった点は、プログラムを運営するにあたって、独自の資金がなかったことである。クライエントがこのプログラムに参加できる時間の量は、研究プランの必要性から割り出されるのではなく、職業リハビリテーション政策にのっとった在来の資金の続く期間によって決められてしまった。
たとえば、あるクライエントのフォローアップをしようとしていた矢先に、シェルタード・ワークショップから彼を受け入れるという通知がきた。4週間分の財政保障しかないクライエントには、フォローアップをするだけの時間的余裕がなかった。クライエントが財政的保障される期間が限られているので、クライエントが一日休めば、それだけ研究期間が減ることになった。そのほかにも運営上の問題があった。契約仕事が研究途上でとぎれてしまったために、クライエントはまだ規格化されていない作業に取り組まなければならなかった。簿記などの仕事に対しては、給料は時間給や日給でなく、1か月に2回支払うという形式であった。予算が足りなかったため、データ収集の専門職員を雇うことができなかった。
最後に付記したいが、研究上のニードとクライエントのニードがかみ合わないことがときどきあった。たとえば、クライエントの行動が実験者の制御に反応しているか、オペラント技法が効力を発揮しているかどうかを判別するために、逆転期(reversal period )が必要なのである。われわれの研究では、この逆転期として1週間とったが、この期間には生産性が非常に落ちるため、クライエントは3日目には居ねむりをし始めた。すなわち、訓練第一期にクライエントがあげた成果は、この逆転期に下がってしまうのである。非常にむずかしいケースのクライエントが数か月も訓練を続けた結果、やっと進歩があらわれたときに、この逆転期を迎えなければいけないということは、この訓練に従事しているスタッフにとっても、非常に残念なことであった。
要 約
この研究の被験者となった19名は、施設にはいっていない、中度から重度の精神薄弱をもつ若者であり、多岐にわたる行動問題があるためと生産性が非常に低いために、シェルタード・ワークショップで働けない者たちであった。報奨システム、ライト点滅方式、懲罰など、各種のオペラント技法を駆使することにより、クライエントの生産性が上げられ、ひいては作業妨害行動をなくすこともできた。しかしながら、オペラント技法によって改善された行動を継続させるためには、オペラント技法によって設定された環境をあくまでも保持しつづけなければならない、という結論に帰着する。
(Rehabilitation Literature,September 1972から)
参考文献 略
*日本肢体不自由児協会書記
**クライエントの生産性は、「普通生産水準のパーセント」というかたちで出される。まず一定の作業を、少なくとも2名以上のいわゆる「普通」の労働者(ワークショップのスーパバイザー、専門職員、事務職員など)が10分か15分間隔で何回か実施してみる。これによって出てきた数字を平均化し、それを1時間(実質的には50分)の単位に比例配分した。クライエントの生産性をこの水準と比較して、賃金を決める。平均水準の生産性を達成した場合に、時間給は1.60ドルとなる。
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1973年4月(第10号)16頁~26頁


