脳損傷精神薄弱児の指導計画
脳損傷精神薄弱児の指導計画
―バーシとデラカト―
武田 洋 *
Ⅰ 本稿の目的
本稿の目的は以下のことから導きだされる。
(1) シュトラウス(A.A.Strauss)とレーチネン(L.E.Lehtinen)の脳損傷精神薄弱児に対する研究以来、これらの子どもたちの行動特性の研究が継続的に行われてきて、単に一般的に知能が遅滞しているものとして精神薄弱児をみなすことが少なくなってきた。つまり、ひとりひとりの精神薄弱児の行動特性、学習に関するニードを見極め、それにみあった指導法を用いようとする姿勢が多くなってきたことである。
(2) 肢体不自由養護学校に在籍する子どもたちの中に、脳損傷児である脳性マヒ児が相対的に増加してきたために、(1)と同様の意味で個々の子どもたちの障害の程度と行動特性をみつめて、指導法を研究しつつ指導しなければならなくなってきた。脳性マヒ児の約40%くらいに、知的にも遅滞のみられる子どもがいると考えられていることから、(1)との共通の基盤に立って実践と研究を行う必要性がますます高くなってきている。
(3) アメリカにおいては、「学習障害児」という用語が高い頻度で用いられるようになっていること。これはベートマン(B.Bateman)によると、「明らかに中枢神経系の不全が指摘できる場合でも、そうでない場合でも、または一般的な精神薄弱、教育的なあるいは文化的な経験の不足、重度な情緒障害、感覚の損傷などのために二次的に派生したものではなく、学習過程に基本的な不全があり、そのために、評価された知的能力と現実の知的行動との間に教育的に重要な不一致を示す子どもである」として、「一般的な精神薄弱のために二次的に派生した」特殊な学習問題を示す子どもを除外している。
このことは、次のような認識に立っての定義であることを示している。すなわち、「特殊な学習障害の定義の条件をすべて満たす可能性のある精神薄弱児は確かにいる。しかし、その学習上の困難はより重大な精神薄弱という障害には二次的な位置にあるため、彼らは学習障害児に対するよりも、精神薄弱児に位置づけられているのである。もし、精神薄弱児の最も著しい学習障害が克服されれば、彼はほんとうの意味で自分の精神年齢段階の能力で機能するであろうと仮定できる。このことは、現在教育可能児学級に特殊な学習障害を有する子どもが、誤って判別され、配置されているという意味では全くない。しかし、精神薄弱児学級の教師は自分の学級に、ほかの障害に加えて、学習障害児の定義にあるような障害を有するもののいることを認識し、適切な教育法を心得ていなければならない。」
これとは別に、マイクルバスト(H.R.Myklebust)の見解がある。これは、「精神薄弱児の場合、いかに有効な方法であったにしろ、能力の低さは治療教育が克服できるとは仮定できない。その仕事はこれらの子どもたちが、最も効果的に学習するための手段を確認し、そのもてる潜在力の最大のレベルで学習することを援助されうるように確かめることである。それにひきかえ学習障害児の場合には、正常な潜在力が仮定され、その目的は特殊な治療教育を通しこの潜在力を現実化することにある。潜在力が正常かそれ以上であるが故に、問題は子どもが最も効果的に学習するための過程を確認し、それに応じてその子どもを援助することである」というものである。
前者の場合は精神薄弱児にも、その能力と外部に表れた行動との間に、なんらかの理由で教育上重要な差が予想できる者の存在が考えられるというのであり、後者は精神薄弱児の場合、治療教育では知能の低さがどの程度のものにしろ、学習上の特殊な問題は克服できないために、学習障害は仮定できず、潜在力の最大限まで学習させるのみであるというように、明らかに論旨のくい違いがみられる。
そこで、脳損傷精神薄弱児と学習障害児の行動特性を比較してみると必要がでてくる。
① 脳損傷精神薄弱児の行動特性
脳損傷精神薄弱児の行動特性についての研究はシュトラウスとレーチネンが初めとされ、彼らの研究は現在も高く評価されているところである。彼ら以後、多くの研究者によって、実験的、あるいは臨床的研究により脳損傷精神薄弱児の行動特性が報告されてきた。以下、彼らが概念化した(ア)一般的な行動問題、(イ)知覚障害、(ウ)思考問題という範ちゅうにより、最近までの報告を要約してみる。
(ア) 一般的な行動特性 シュトラウスとレーチネンによれば、脳損傷精神薄弱児には、過活動の、方向性のない、焦点がなく無意味な、不器用な(clumsiness)、ぎこちない(awkwardness)、協応しない(incoordinated)、失敗の多い(erratic)、不適切なくり返しのある、固執的(perseverative)な行動や、ばかげた大笑い、筋肉の自動的運動、絶え間ない無意味な質問、などの行動がよくみられるとしている。さらに、これらの行動については実験的に追求された結果や、臨床的経験からの報告によって確かめられている。
(イ) 知覚障害 部分と全体、図と地の知覚に問題があること、マーブル板テストによると、順序に次元の低さが現れ、さらに乱雑であること、運動の知覚(視覚記憶再生)に問題がみられること。ゴールドシュタインの論じた固執性(作業の要求することへの不適切なくり返し反応があること)などがあげられている。これら知覚問題は視知覚のみでなく聴知覚とも確かめられ、他の知覚(触、味、嗅、筋肉知覚)でも推定されている。
(ウ) 思考障害 分類作業によると、普遍的でない、不自然な、特定のものへの反応がある。シュトラウスとウェルナー(H.Werner)は知的に同じレベルの子ども、つまり神経学上問題のない子どもに比べ、違った分類の仕方、つまり形や色、不必要な細部、あいまいなある想像上のつながりで分類する傾向があると報告している。さらに、物活論的思考の傾向、語い数は神経学上問題のない子どもよりも多い点、などがいわれている。
② 学習障害児の行動特性
学習障害児は、さきに一般的な定義を述べたように、脳損傷児のように脳に損傷を受けたための行動異常を予想しているわけではなく、学習上特殊な問題を有するということから定義されたものである。したがって、学習に特別の配慮を必要とする問題のある子どもはすべて入ってくることになる。一つは知的発達遅滞は伴わないが、神経学上問題があると考えられる子どもの学習問題と、必ずしもそれが予想できないが学習上特別の困難を示すものと大別できる。メイヤ(P.I.Myers)とハミル(D.D.Hammill)によれば、その行動上の特殊な問題は
①運動行為―過活動や協応不全などの問題。
②情緒―運動や知覚などの問題で依存的、など。
③知覚―あらゆる知覚の問題が指摘されている。
④象徴化―受容と表現の問題など。
⑤注意―不十分なあるいは過剰な注意など。
⑥記憶
などである。これを彼らは例として、①過活動→注意散漫→記憶不十分→学業不振→過活動の増加。②注意力不十分→錯覚→識別の困難→理解力の不足→一般化の欠如→学業不振→情緒的ごまかし→より貧弱な理解というふうに、相互の行動特性の関連を示している。
また、マイクルバストは中枢神経系の不全→行動問題→学業不振と生活の不適応→情緒問題というように、一次的なものを中枢神経系の不全による行動問題を、ただしこの場合、知覚問題や言語の表現機能なども含めたものを重視する必要を主張している。学習障害児に脳損傷(中枢神経系の不全)を前提にしている研究者は多いが、中枢神経系の不全を診断する確実性の高い技術が発達していないことと、診断が確実にできたとしても、指導計画や指導技術に大きな変更を余儀なくされるという性質のものでないことが、必ずしも脳損傷の有無を学習障害児の判別に含める必要はない理由とされているようだ。
以上のことから読みとれることは次のようなことだと思われる。つまり、シュトラウス症候群といわれる行動上の問題を有するもので、知的レベルの高いものは学習障害児として、また低いものは教育可能児以下の精神薄弱児として扱われているのではないかということである。
しかし、脳損傷児として行動特性の研究がすすめられてきたが、その改善のための指導方法や指導計画というものは、主として学習障害児として定着しはじめた概念の下に研究、あるいは考案されてきたことに負うものが大きいと言えそうである。
(4) わが国の精神薄弱教育についても、(1)で述べた構えが強くなってきたと言えよう。これは、昭和46年に改訂された「養護学校(精神薄弱教育)小学部・中学部学習指導要領」では、養護・訓練という領域を設け、その内容に「感覚機能の向上」を盛りこみ、感覚機能の改善と向上、認知能力の向上をめざしている。また同資料によると、これは「感覚的・知覚的機能の発達が著しく遅れていたり、あるいはその機能に障害があったりする児童または生徒に対しては、感覚的・知覚的機能の発達を促進し、あるいは障害を改善するための指導が必要である ……」と考えられている。これは、(3)で述べたように、明らかに脳損傷精神薄弱児や学習障害児の行動特性として指摘されているものを念頭においたものということができよう。
以上のことから、今後こうした行動特性を示す子どもたちへの、指導計画と指導技術の確立に努力しなければならないという課題が出てくる。しかし以前にも指摘したように、わが国の取り組みはまだ不十分であり、実践的にも研究上も具体的成果を示すものはごくわずかである。どうしてもこの問題に以前から取り組み、多くの成果を報告しているアメリカにおける研究を調べ、わが国の脳損傷精神薄弱児の指導計画と指導方法をどう組み立てていくべきかを学ぶ必要がある。そういう意味で、多くの研究者の中から代表的なものを選び、その人たちの子どもについての発達の仮説と障害の解釈、それに基づいた指導法と指導計画を整理し、妥当性の高いものであるかどうかを検討していかなければならない。
Ⅱ 仮説と指導計画
学習障害に対する解釈も、その改善のための訓練や指導の方法も、その取り組む人の対象としてきた子どもたち、あるいは研究上影響を受けた考え方によって、大きく異なってくる。知覚―運動を重視する場合(N.C.Kephart,E.Friedus,G.N.Getman,R.Barschら)や感覚のすべてを重視する場合(L.Lehtinen,W.M.Cruickshank,G.Fernaldら)、さらに、言語発達を強調する場合(H.R.Myklebust,H.Barry,M.A.McGinnisら)などがある。
知覚―運動を重視する場合は、知覚と運動の能力を同等に強調しているわけである。また、これらの二つの機能は密接に関係し、一方の領域の改善は他方の領域の改善に刺激を与えるという考えである。そのため、特殊な課題は、両方の能力を同時に用いるように考案され、その結果知覚と運動の反応の統合が増加するように予想されたものである。
しかし、ある場合には、訓練の視点が運動の統合と協応の発達におかれ、その影響で運動の十分な発達による副産物として、かなりの程度まで知覚が発達するという考えも成り立つ。本稿では、知覚と運動の発達を同等に評価する立場に立つといわれているバーシ(R.Barsch)と、知覚は運動発達の副産物として発達してくるとし、運動訓練に独創的な仮説を導入した、ドーマンら(G.J.Doman,I.R.Doman)とデラカト(C.H.Delacato)の仮説と指導法や指導計画を調べてみることとする。
バーシの見解は、ケファート(N.C.Kephart)と異なり、より発達の仮説に生物学的なものを導入したとして知られる。しかし、その指導計画は全くケファートと類似し、知覚―運動の発達を強調したものだと言われている。仮説は異なっていても指導計画が同様のものであるということは、その仮説がケファートの仮説と相補い、その指導計画に、より強固な基盤をもたらすものであるかどうかが、関心の的となる。
(1) バーシの指導計画
バーシは、空間の中での運動を強調している。その用語でさえ、視空間的な現象に環元しようとしているように思えるほどである。たとえば彼によると、「人間は視覚的な空間の存在である。誕生において彼は空間につつまれており、生から死まで空間の中で生きている。人間は象徴的に方向づけられた存在である。シンボルは空間を旅することを記録するための体系である」と定義することから出発している。
バーシの初期の論文をみると、初め脳に障害をもつ子どもに関心をもち、親に対するカウンセリングや、退行現象や、評価と判別の方法などについてのものであった。近年、バーシは対象を脳損傷に限定しなくなり、子どもを学習者として評価することに関心を向けはじめ、生理学的アプローチと呼ばれる教育上の概念的な組み立てに努力を注ぐようになった。movigenicsという名称は精神医学的アプローチに対比する意味で用いられたものである。
その生理学的アプローチを遂行した結果、バーシによるmovigenicsということからひき出された学習の12の側面に基礎をおく実験的なカリキュラムを提案するに至った。このmovigenicsとは「学習能力に導く運動様式の発達や、運動要素の学習」と定義されている。バーシのこれらの理論的根拠と基本的仮定からみていくことにする。
(2) 理論的根拠と仮定
バーシの行動についての理論つまりmovigenicsは、神経学上の理論や多くの訓練経験からもたらされ整理された10の条件に依存している。この10の条件は基本的に人間を空間内で運動する存在とみていることからくる。人間の根本にある基礎的なものは、運動による効果である。そしてそれは、成熟の方向へ進む流れの中で発達する。またそれは姿勢均衡化や運動様式の恒常的保有へ努力によって特徴づけられている。空気の中で残存することは、運動効果ということの第一の目標であり、それは物理的あるいは心理学的な緊張関係という環境の中で発達する。知覚による概念化体系によって情報を処理する能力は運動効果の急変に対し必要である。この体系は認知の連続性にあわせ六つの感覚経路、つまり聴覚、視覚、筋肉運動知覚、触覚、嗅覚、味覚から成っている。それはまた、弁別、分類、一般化を含むものである。
バーシは、フィードバックが十分にできることは、運動効果の発達にとって欠くことのできないものであると述べている。それは「ことばと呼ばれる視覚―空間的な現象を通して、象徴的に伝えられる」ものであるとしている。運動と伝達は、先行する一連の関係の中にみられる。つまり伝達とは、知覚による概念化体系のいろいろの部分からの情報を処理する能力に依存しているし、その能力はまた効果的な運動様式に依存しているのである。以上が、バーシによる基本的な仮定であるが、次にそれから導き出される、人間の学習に関する12の側面を説明する。
姿勢の移動 学習の最初の四つの側面は、身体の統御と、空間内での運動を処理することである。筋肉の強さが最初の側面であるが、これは、身体を支持すること、ころがること、はうこと、すわること、立つことなどの最初の運動をもたらすものである。適切な筋肉の強さとは、筋肉の動ける状態、筋力、持久力を意味し、当然個人の大きさと年齢に応じて変化するものである。適切な筋肉の強さがある場合、次の側面である力動的な均衡が引力に打ち勝つために必要となってくる。
つまり人間は、筋肉の収縮を促進したり抑制したりすることによって姿勢を保とうとする。力動的な均衡を達成することによって作られた適応力は、その性質上左右両側的なものである。というのは、身体の両側が同時に活動させられているからである。しかしその両側性は、別々の側面であると考えられ、それが力動的な均衡のために動員されているものと考えられている。適切な筋肉の強さと均衡を身につけた、発達した子どもは動く用意ができているということになる。しかし、子どもが有意義な方法で自分の周囲と相互交渉ができるようになるには、第3の側面、つまり自分と他の区別である身体の認知(body awareness)ができなければならない。
バーシの説明しているところによれば子どもは「自分がどこにいるのか」という質問に答えることのできる以前に、「自分は何なのか」という質問に答えることができなければならない。これが第4の側面、つまり空間の認識に導くのである。子どもは、自分自身、場所、位置についての情報によって筋肉の強さを調整するようになる。これは自分の欲求と環境の要請に従い自分自身と物体を動かすことになる。
知覚概念の様式 子どもは空間の中を移動することを学ぶにつれて、同時に四つの基本的な様式つまり触覚、筋肉運動感覚、聴覚、視覚からの情報を処理することを学習し始める。バーシは、それぞれの方法が感覚を要素としていても感覚ではなく、受容と表現の機能的な経路と考えられると述べている。
第5の側面である触覚の力動性は、体の表面からもたらされる情報を処理する子どもの能力と定義されている。バーシによれば、触覚の力動性とは、単なる触覚という感覚ではなく、触覚刺激と弁別に限定されているようである。身体のすべての部分が含められ、熱や肌ざわり、圧力などのすべての触覚刺激が論じられている。能動的な触覚と受動的な触覚に分けられるという。
第6の側面は、運動を感じる能力や、運動様式を保有する能力、運動の連続の知覚的なまた概念的な要素を統合する能力である。バーシは筋肉運動感覚を「身体の活動を十分意味のある状態にする運動の特殊な知覚という付加的要素をもつ触覚と自己刺激感受」と考えている。触覚の力動性と筋肉運動感覚は、互いに補いあって完全なものとなるとしている。しかし筋肉運動感覚は身体を他の物と接触させるに必要であろうが、触知覚が第一義的なもので、筋肉運動感覚はそれを促すだけのものであると考えられるのではないだろうか。
第7の側面は、聴覚の力動性である。これは、音の認知と伝達体系の表現を構成するものである。この側面は、音の世界からの情報を処理する能力、つまり受容と表現能力と規定されている。バーシは聴覚を受容と表現の二つの要素に分け、また聴知覚の欠損を学習障害児の条件とする以上のものを、聴覚過程については考えていないようである。これは次のことばからも理解できる。「個人は鼓膜を打ち、聴神経経路を通る音響エネルギーから、意味を得る何らかの方法を発見しなければならない」
これに比較して、バーシの第8の側面である、視覚の力動性については、かなり説明を尽しているようである。この側面は見るという用語で表現できる以上のものを含めている。視覚的な追跡や方向づけ、環境の範囲についての視覚による限定、ある課題の細部の弁別、一つ以上の課題の細部間の関係の解釈などを含む。視覚は空間内の物体間の距離と関係を説明するものである。
バーシは、「視覚は、距離、色、関係、手ざわりを明らかにし、触れることや、筋肉運動感覚、聴覚の真の総合的な代行者となる」と述べ、この視覚に対する重要視には絶対的なものがあると言ってもよい。
他の知覚 運動発達を強調する人たちにしても聴覚経路を重視し、詳細に論じているわけではないが、視覚を学習や発達の第一義的なものとは考えていない。この点にバーシの独自性があるともいえよう。
最後の四つの側面は、バーシによれば「すべてのほかのことを遂行するときの効果を拡大し、豊かにし、広げ、解明する要因を代表する」ものであるという。第9の側面は両側性であるが、これは他の研究者と異なり、バーシは子どもの見るほとんどの物は偏在的であり、子どもが身体の利き側でない方を用いると適切に遂行できないと言う。バーシの場合とくに両側性という点は、身体全体としてなめらかにまた協応した動きができることが強調されている。したがって、これは身体の中心線の両側で効果的で相互的な運動様式を遂行する能力を指す。
第10の側面はリズムである。これは身体の運動を調和的にまた優美に行うために、協応し同時的に行う能力である。第11の側面は適切な運動の流れに修正や変更をすることである。そのためには子どもは場面の要求する変化に対し、運動を変化するだけの反応の広さを有していなければならない。バーシはその変化に速さ、方向、力、時をあげている。
第12の側面は運動計画である。これは、自分自身の運動の範囲の知識を必要とし、示された要求について、空間内の何らかの評価を必要とする、と述べている。これは、遂行よりも計画に強調点がおかれているもので、概念的なものの練習のようなものと考えられている。
(3)指導計画
バーシの提案している教育計画は、その根本的な要素として、上述した12の学習の側面を強調したものである。というよりも、12の側面以外のものには言及していないと言ってよい。次にこの12の側面の指導についてのバーシの計画をみてみることとする。
① 筋肉の強化 これは、「自分の身体の実体と生活年齢に合わせて、日常的な必要性にみあう筋肉の動ける状態、力、持続力の適切な状態を維持する有機体の能力」と定義されている。そのため、この分野の教育は幼児の体育教育と類似したものが提案されている。特殊な問題をもつものについては、ジャンプ、物を持ち上げることや押すこと、平衡をとることなどが勧められている。
② 平衡の力動性 これは「引力の力に対し、直線上の姿勢を保持し、移動運動様式を維持し、姿勢の回復を促進するために、筋肉どうしの適切な関係を活動しうる有機体の能力」と定義されている。そのため、平衡を回復する能力をもたせるためには、平均台の使用、動物の歩きまねやうす暗い部屋で障害物のある場所を歩いたりさせられる。さらに線の上を歩いたり、ツイストやまわれ右、回転が直線上の姿勢の保持のために課され、歩いたりとびはねたり、つまさき歩きなどが移動運動様式の維持のために課される。この運動様式の維持には、メトロノームや太鼓の音に合わせることも指導される。
③ 空間認知 これは、バーシによれば、「自分の周囲に関し、平面、高さ、周辺、前後での方向をもつ自分の位置を識別できる有機体の能力」であるから、指導は以下の8項目となる。
つまり、空間での自転―教師にまねて、左右といろいろな物体の方に回転する、後には教師を見ないでやる。
空間での方向の認知―教師の指示でいろいろの方向を向く。
空間での側面優位性―教師の首の反射作用にまねる。
空間の視覚的認知―目かくしされ物体を説明し、物の特徴と位置を再生する。
空間認知―教師によって教室に配置された物を再配置する。
空間内の物の順序を置き直す―大きな変化のある配置がえを計画どおりに子どもが実行させられる。
空間内を前転する―教師が1~4を唱え、子どもは声にあわせて手をあげ、肩を下げ、腰をあげ、4で前転する。音にあわせて同時にやることが要求される。
空間内でのいろいろの移動―教室内をいろいろの方向に歩いたり、ジャンプしたり、走ったりしながら、移動する。
④ 身体認知 これは「すべての身体の部分を運動に関係して認識することと、身体各部の名称を言えるようになること、いろいろな身体各部の適切な機能を認知する意識的な有機体の能力」と定義されている。この分野での指導は、ゲームや会話で上述の能力を身につけさせるものである。
⑤ 視覚の力動性 視覚の力動性については、バーシは五つの領域に分けてその指導を計画している。以下略述してみる。
(ア) 視覚焦点―標的に向かって歩いたり、前転したり、線の上を歩いたりする。またお手玉を投げたりする。
(イ) 視覚追跡―動いている標的を目で追う。
(ウ) 注意の維持―暗い部屋の中で光に視線をあてて、光のついている間見続ける。
(エ) 視覚の転移―(ウ)と同じであるが、光の位置が変わったら、できるだけ速くスムーズに視線を転ずる。
(オ)視覚記憶―タキストスコープを用いる訓練、さらに、以前見たものの数を再生したり、「レモンは何色?」とか「赤いものを言ってごらん?」というような問いに答えるよう要求される。
⑥ 聴覚の力動性 模倣、識別、理解の課題を通し、受容と表現の改善が図られる。この分野では活動は示されていず、言語を豊富にするための計画に組み込まれている。
⑦ 筋肉運動感覚 粗大運動と微細運動の訓練に分かれ、粗大運動には、前転、両側同時のあるいは交互のはう運動、空中に手、ひじ、足で描くことなどがあり、微細運動には、ペグボード、ハサミの使用、しゃぼん玉を吹いたり、しゃぼん玉をつかまえたりするものがある。また③と④の訓練も有効だとされている。
⑧ 触覚の力動性 物に触れたり、触れられたりしたときの識別が指導される。
⑨ 左右両側性 教師にまねて左右同時に身体部分を動かす活動。
⑩ リズム メトロノーム、太鼓、手拍子などを用いる活動や歩いたり、走ったり、歌ったり、リズミカルにできるような課題が課せられる。
⑪ 安定性 活動は他の活動と異ならないが、教師の指示により運動様式を変更するよう要求される点が、他と違う点である。
⑫ 運動計画 これも他と異ならない活動であるが、子どもが活動しているとき、何が起こったかを教師がチェックし、運動計画が子どもの側で目的にかなったものになるよう指導する。
以上、バーシの教育計画には、特に顕著なものは見あたらない。彼の活動はウィスコンシン州のマディソン市の学校(Longfellow School)で実験的に行われているものである。この訓練期間に最初はできなかった子どもも、終わりにはできるようになると言う。ただ公式化されたテストは行われていない。この訓練についての論評はごくわずかしかみられない。
ペインター(G.Painter)によれば、この訓練を課された子どもたちは、訓練期間の終わりには、ITPAのいくつかの下位項目で、有意差で向上がみられたと報告している。また運動効果の改善は心理言語領域とも関連していると報告している。しかし、この訓練計画が、ほとんど運動発達の遅滞と視―知覚発達を示す子どもを念頭においているとしか考えられないため、この面の遅滞の改善には役立っても、聴知覚の受容に問題を有する子どもには、言語発達に役立つものはみられないように思える。
さらにケファートと比較してみると、その理論に体系的なものの不足を感じる。つまり、学習の重要なある側面をとり出し、その不十分な発達をなんらかの指導によって補おうとしているわけであるが、その不十分さは何に対するものなのか、正常な場合、どういう順序で何が発現するのかが、十分には説明されていないようだ。
Ⅲ 神経組織を重視する場合
デラカトとドーマンはペンシルバニア州のChestnut Hillにある人間能力を成就するための研究所(Institute for the Achievement of Human potential)で、脳損傷児と診断された子どもについて共同で仕事をしている。この研究所の訓練計画は神経組織として説明されている理論的原理に基づいている。また一般に脳損傷児に適用されている会話や身体治療(機能訓練)の方法からもたらされた結果に対する不満から、成長したものであると言われている。終局的には、彼らの治療理論は、1928年に紹介されたオートン(S.T.Orton)の神経組織の理論にさかのぼることができると言う。しかしオートンは、学習障害の扱い方と予防についてはほとんど情報を提供しなかった。
デラカト本人によれば、フィラデルフィアの神経学者として著名なフェイ(T.Fay)の影響がデラカトに読みと言語発達遅滞の処置と予防の理論を形成することを促したと言っている。デラカトの神経組織、診断の手続き、治療技術の原理をその方法の評価とともに、以下論じることにする。
(1) 神経組織の論理
デラカトの神経組織の概念については、神経の発達が「個体発生は系統発生をくり返す」という個体発生説に立脚している。すなわち、個体の発達は人類の進化上の発達の様式をくり返すことから、デラカトは次の結論を導きだしているのである。
「神経組織は、人間の中に独自にしかも完全に存在している生理学的に最適の状態であり、そしてそれは、全体的で連続した個体発生の神経発達の結果なのである」と。
その後、デラカトの基本的な前提は、もし人間が神経発達の連続性に従って成長しなければ、その人間は敏速に運動することや自分のことを相手に伝えることに関して、問題を示すことになろうということになった。
デラカトは下等な脊椎動物からの脳の系統発生的発達を説明している。つまり、軟骨魚類などの運動機能は、脊髄によって統制がとられ、橋や中脳の発達している両生類を通過し、皮質の発達している霊長類に至るわけである。
デラカトは、人間に関して、人間の脳の発達はかなり一貫性のある様式に従っていることを示唆している。生命の出発から始まり、8才前後まで、神経の機能は、髄梢化が起こるにつれて、脊髄から皮質へ発達していく。胎内時や出生時までに、脊髄の発達は神経組織の上限に到達する。この状態での組織の内部に筋肉の活動できる状態、反射運動、その他生命に必要な反射作用がみられる。この組織でも、幼児は敏速ではないが運動をもっている。この幼児の動作は体幹的であり、何かの目的に向かってのものではない。乳児が乳を吸ったり泣いたりする反射運動は、胎内時の残存的なものである。この段階の運動は魚に似ているのであるという。
次の発達段階は、幼児が4か月ぐらいになったときに始まる。それは橋の範囲にある。幼児の運動は大脳優位性のないもので、はらばい運動である。つまり幼児は両眼で見、両耳で聴くのである。動作はは虫類の運動に似ている。神経発達の次の段階は中脳のレベル(mid brain level)と称される。これらは子どもが10か月のときである。彼の運動は交互に手足を動かしてはうことによって特徴づけられる。彼の視覚は両眼同等で、両眼の連合が始まる。聴覚は両耳による。
デラカトの理論では、1才児は初期の皮質段階に入る。その運動は霊長類のものに似てくる。たどたどしく歩けるようになるし、目の初期の連合がでてくるし、聴力が立体的になってくる。正常な8才の子どもは、発達した皮質の大脳の半球の優位性による統御を有するようになる。彼は交互に歩き、すぐれた目、手足、そしてすぐれた耳による立体的な聴力をもつ。上手に読み書きができるようになる。系統発生的な神経組織の発達とデラカトによる研究の人間の神経発達の比較が表1に示してある。
人間の神経の成長は、霊長類の成長以上に継続的なものであり、また人間だけがことばという記号的なものを発達させている。デラカトにとって特に重要なことは、人間だけが神経機能について大脳半球の優位性を発達させている創造的生物であるということである。
| 最高度の神 経の段階 |
運動能力 | 視 覚 | 聴 覚 | |
| 新生児 | 脊 髄 | 体幹運動 | 反射的 | 反射的 |
| 魚 | 脊 髄 | 体幹運動 | 反射的 | 反射的 |
| 4か月児 | 橋 | 両側性のはらばい運動 | 両側的 | 両側的 |
| 両生類 | 橋 | 両側性のはらばい運動 | 両側的 | 両側的 |
| 10か月児 | 中 脳 | 交互性のはい歩き | 両側性連合 | 両側的 |
| は虫類 | 中 脳 | 交互性のはい歩き | 両側性連合 | 両側的 |
| 1才児 | 初期皮質 | たどたどしい歩き | 初期の結合 | 立体的 |
| 霊長類 | 初期皮質 | たどたどしい歩き | 初期の結合 | 立体的 |
| 8才児 | 半球皮質優位性 | 交互歩き | 優位性のある目による立体視 | 優位性のある耳による立体聴覚 |
デラカトは表2、3に示すように、正常児が動作やことばの発達の過程で現す、いろいろの成長の段階での連続性と持続期間を示した。これらの発達の過程は、たいてい8才ごろまでに完了するが、この完了は、子どもが神経組織のある状態に到達することを意味する。もしどの段階ででも脳に損傷があれば、あるいは子どもに自然の発達があっても、環境要因が子どもの発達を限定してしまうようなことがあれば、その子どもは言語か運動のいずれかに、神経学的不全あるいは混乱の証拠を示すことになろう。
| 段 階 | 水 準 | 基本的特徴 | 年齢範囲 | 脳の段階 |
| Ⅰ.泣くこと | 1.泣く―生きていることを表わしていること以外に何ら意味を伝えない反射的な音の創造 | 反射作用 無意識的 |
誕 生 | 脊 髄 |
| Ⅱ.おどろいて泣くこと | 2.生命を守ろうとする自然な泣き | 生命―脅威から身体を守るため | 3~20週 | 橋 |
| Ⅲ.知的な声 | 3.ことばなしに気分を示す意味ある声を創造する能力 | 知的な―意味ある目的 | 16~60週 | 中 脳 |
| Ⅳ.記号的なことば | 4.二つの有意味のかつ理解できることばを考えて話す能力 | 意味の深さ | 36~80週 | 人間の皮質 |
| 5.二つのことばを組み合わせて使う能力10から25の単語の保有 | 人間にとっての独自の意味の深さ | 50~120週 | 人間の皮質 | |
| 6.文法的には不正確でも意味ある文を組みたてる能力、ほぼ200以上の単語の保有 | 75~200週 | |||
| 7.完全で文法的な意味のある文を組みたてる能力無数の単語を保有 | 150~350週 |
| 段 階 | 水 準 | 年齢範囲 | 脳の段階 |
| Ⅰ.能力としての運動なしの動き | 1.(ころがる) 2.(円内であるいは後方への動き) |
4~20週 | 脊 髄 |
| Ⅱ.はらばい運動 | 3.(様式なしの運動) 4.(相同性の運動) 5.(両側性の運動) 6.(交互性の運動) |
6~40週 | 橋 |
| Ⅲ.はい歩き | 7.(様式なしのはい方) 8.(相同性のはい方) 9.(両側性のはい方) 10.(交互のはい方) |
16~60週 | 中 脳 |
| Ⅳ.歩 行 | 11.(ぎこちない歩行つかまり歩き) 12.(援助と様式のない歩行) 13.(交互歩き) |
皮 質 |
言語の問題でもとくに読みの問題のある子どもは、ほとんどいつも大脳皮質の半球優位性が不十分にしか完了していない。この大脳優位性を確立していない子どもは、目の発達に先行する一つ以上の発達上の不十分さをもっている。
デラカトの神経組織の理論に従えば、決して損傷は損傷部位全部の細胞に及んでいるわけではない。そこなわれていない残された部分が訓練されることによって、破壊された部分の機能を補償することができる。このような仮定に基づいているため治療効果を楽観視することとなる。
以下診断手続きを説明する。
(2) 診断的な評価
脳損傷や神経学的機能不全と思われる子どもは、第一に研究所において3日間にわたる完全な診断的な評価のために観察される。子どもの発達の詳細な生育歴がとられ、両親と同胞の状態、幼児期の病気や損傷、運動と会話の発達、睡眠の様子と調子が調べられる。子どもはそれから皮質以前の段階から皮質段階、大脳優位に至る臨床的な検査を受けるわけである。以下、生育歴と臨床検査についてデラカトの述べていることに従い説明する。
① 生育歴
両親に対する質問は有効な診断に導くことができ、病因学的な要因をときどき示唆するものであると言う。妊娠時期の状況が非常に重要だと考えられている。外傷性のものやRh因子に加え、母親のできもの、はしか、体重の大幅な増加などの有無その他の病気などが診断を下す上に最大の重要なものと言える。出産の過程における多くのことがらが考慮に入れられる。この場合時間の長さと様子、用いられた麻酔の種類と量、胎位の型などが重要である。出生児のうぶ声とその起こった時点も調べられるが、これも重要なものである。
乳児期の初期に関する発達と病気の情報も集められる。デラカトによれば、とくに生後6か月間の食事、睡眠、排泄の様子を入念に調べる必要があると言う。発熱の影響が記入される。生後数か月の子どもの運動の開始時期と量が考慮に入れられる。絶え間ない運動や不完全な動きが不完全な子どもの神経組織のあらわれであろうと思われている。
つまり両手を同時に用いるはらばい運動、交互のはい歩き、歩行の様式が、その開始時期段階と同様記入される。ときには両手を用いるはらばい運動の年齢と様式は、育児書や小児科医の記録が有効でなければ、正確には決定されえない場合も多い。
子どもの運動様式に関するケースの生育歴は一般に母親から得られる。立ち上がりの開始時の詳細な情報が母親から集められる、というのは立ち上がりは子どもがはい歩きをした量をときに示すからである。
② 臨床検査
デラカトの診断についての考えは、皮質以前の段階、皮質段階、大脳優位段階の評価をすすめることにある。というのはこの手続きが神経組織の発達の筋道をさかのぼって調べることになるし、そこに含められる治療の連続を描写することになると考えられているからである。言語や読みや数量の尺度としてWISCのようなテストも行われる。これらのテストの結果、知能指数が知られる。そして行動の潜在力が評価されるのである。標準化されたテストに加え、デラカト―ドーマンの連合テストが行われる。それらは以下に示すとおりである。
橋段階 睡眠中の子どもの観察が不可欠であるという。この橋段階でよく発達していれば、彼は正しく眠る。デラカトは子どもが眠っている間、頭の向きをかえてみると、次の行動の一つが起こると述べている。
(ア)頭の向きをかえ、胴体の配置が逆であり子どもは眠ったままである。
(イ)頭の向きがかえられると、子どもはその反転に逆らい、もとの位置にもどし、子どもは眠ったままである。
(ウ)子どもは起きてしまう。
子どもが眠ったままで、頭をかえさせるままでいるなら、さらに胴体の位置も変わらないなら、子どもはこの段階でよく発達しているとはいえないと仮定される。この段階で組織ができ上がっていない子どもはたいてい重度の障害を有するという。
中脳レベル 次の評価の段階は中脳レベルで、子どもが交互のはい方ができない場合、目がまだ連合していない。また自国語を組み立てる音の構造を生みだすことができないし、中脳レベルの組織が完全に確立していないという。
初期の皮質段階は次のようにして評価される。
この段階でよく組織が発達していれば、子どもは交互歩きが正しく、無理なくできるし、手の中であまり抵抗なく両手の親指と人差し指を対置させることができる。
以下のような一般的な身体活動と遊びで子どもの全体の行動が評価される。彼は普通の幼稚園にみられるおもちゃと遊び場で遊ぶことができるかどうか、身体の周囲の危険に注意を払うことができるどうかである。
この段階の評価では、子どもは筋肉の不均衡、遠い点と近い点の横と縦、連合と連合的配列、適応と集中性などのテストを含めた完全な視知覚テストが行われる。目は別々に調べられる。しかしこれは検査される目が目標を知覚している間検査されていない方は同じ遠景を見ているというものである。この段階の組織がよく発達している子どもは、いくつかの病理的妨げがないなら、これらのテストを難なく通過できる。
大脳半球皮質の優位性 次にデラカトは大脳半球皮質の優位性の領域を評価する。それは手と目と足の優位性を確かめることによって行われる。目の優位性をみることは我々の考えるのと同じではない。しかし、優位の方の目は、目と手の関係が言語発達に欠くことのできないものであるが故に、決定されなければならないという。
大脳半球皮質の優位性を評価するのに、次のような題材が用いられる。ボール投げ、ハサミの使用、円をなぞること、いろいろなものを取り上げることなどがきき手をみるために行われる。両親は、子どもが食べたり、書いたり、歯をみがいたりする行動を観察しなければならない。きき足をみるためには、ボールけり、イスにのぼること、前後に歩くこと、階段をのぼること、小さいものをつまむこと、ときにはつまさきで鉛筆をもって円を描くことなどが観察される。
評価による資料はドーマン―デラカト発達プロフィールに記録される。子どもの行動の六つの領域の表現を受容行動についてわかりやすく記入されるようになっている。6領域とは、運動、言語、手指の巧緻性、視覚能力、聴能、触覚能力である。プロフィールは研究所の評価過程の範囲と程度を示すようになっている。このプロフィールは、教育や診療場面で用いるのに、特別のプロフィールの使用訓練を受けたものでないと、用いるようにすすめられないと言っている。
(3) 訓練技術
発達プロフィールを用いての損傷の段階を確認すると、特殊な訓練による経験が特殊な脳の段階に影響を及ぼすという仮定の下に訓練が行われる。それは子どもが欠陥をもっている神経学上の発達段階を診断的に決定するということから始められる。子どもは次の段階に移る以前に、各連続する段階の課題ができるようにならなければならない。たとえば、交互にはうテストは交互にはうことができるということである。
処置の原理は以下のようなものである。
(ア)代表的な脳の段階が損傷している領域に正常な発達の機会を与える。
(イ)損傷した脳の代償である身体の活動様式を外的に賦課する。
(ウ)神経組織を高める付加要因を用いる。
損傷した脳の結果の代わりに、脳そのものを扱う方法、研究所では「様式化(patterning)」と呼ばれる方法が発達した。一連の運動を様式化することは、損傷された段階の代償である運動を生みだすよう脳損傷児の手足をとり扱うために考察されたものである。
考えられた段階は、脊髄、橋、中脳、皮質の各段階である。様式化(腕、足、頭の取り扱い)は、脳の一つの領域は損傷の影響でたいていはすべての細胞がそこなわれたわけでなく、生きた細胞の活動が可能であるという理論に基づいているのである。訓練の強度、期間、頻度は脳が感覚により伝導されているものを受け入れることを可能にするだろう。デラカトはこの方法を「それが中枢神経系に存するのであり、末梢神経系に存するのでない、中心的な問題を扱うもの」と規定している。
ドーマンらによれば、様式化に用いられる運動はゲゼル(A.L.Gesell)やフェイの発達様式の修正であるという。様式化の過程は図1と2に示す。
図1.交互様式―3人で行う 両側性―5人で行う
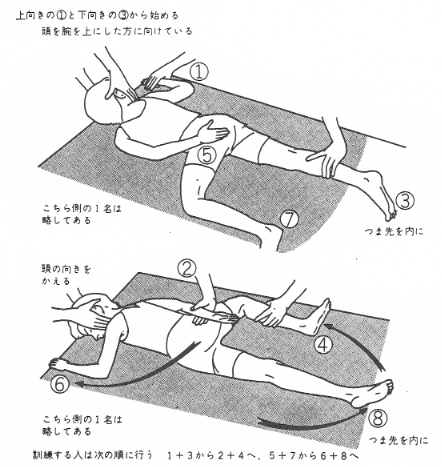
図2.図1の続き
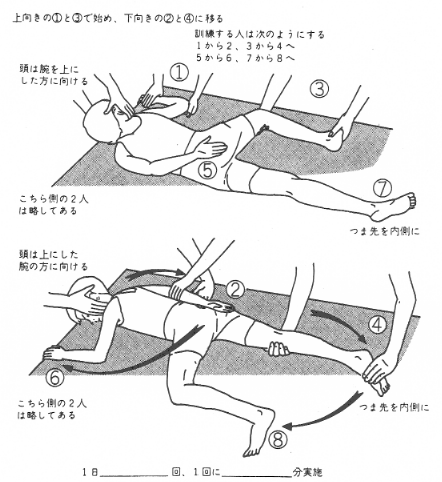
① 訓練以前の段階
訓練以前の段階では、訓練の原理は次のような神経組織の発達の特殊な段階に応用される。移動能力が重度に損傷されていて、脊髄段階の組織化がうまくいっていない子どもの場合、床の上に一日中置いて彼に役立つ基本的な反射運動ができるような機会が与えられる。それに加えて、うねり運動や魚のような運動がその指定された時間、子どもの身体に加えられる。
脊髄段階 同様の手続きが管理されながら脊髄段階、つまり大脳優位が確立しない段階でも用いられる。大人が頭を一方から他方に向け、もう一人が腕と脚を頭の向けられた側に曲げ、もう一人が反対側の腕と脚をのばす。これは適切な睡眠の姿勢をとった後に行われる。片方の目の視覚の発達は2~3週に一日、さらに一日3~4分、おのおのの目を閉じることで、自己指示的視覚刺激を通じ、子ども自身により促進される。
中脳段階 中脳段階では、処置の目的は大脳優位の活動ができるようになることで、次のような有効な活動に要約される。交互にはう方法が教えられる。この活動の実践時間は一日に10分から1時間まで変化がある。自分か他の人が動いている場合の視覚刺激を追って両眼の視覚的連絡の訓練が促進される。発音問題と聴知覚の基本に困難を示す場合には、音調と旋律の識別や音のゲームなどの音楽が課される。
初期の皮質段階 皮質段階では様式化は一日10分以上の訓練で診断に基づいて交互歩きをすることである。子どもは空間関係について学習することを求められる。遊戯場のゲームによって、視覚的な立体視を発達させられる。彼はまた読みの準備が必要な場合になると適切な近距離の視覚が発達されなければならないとし、クレヨンによる単純なテーブル活動も必要なことが示されている。
大脳半球皮質の優位 最後の神経組織の段階は大脳半球皮質の優位が確立したときに達成する。この段階では、側面性優位から成る睡眠の様式が強調されている。脚の優位性を発達させるのに、蹴ること、ステップを踏む、障害物歩行などの活動が課される。投げたり、切ったり、道具を用いたり、物を取り上げたりする技能がきき手の発達のために課される。目の優位性は遠距離については望遠鏡、近距離の場合に顕微鏡などを使った遊びによって指導される。
デラカトは、Keystone View Companyによって作られたStereo-Readerと言われるものを考案したことで有名である。両眼が訓練材料を見ているとき幻覚を与えて妨害することによる効果を期待している。この材料は視知覚―運動協応、家族単語、言語識別、文節読み、興味読み、速読の練習カードから成る。一日に20分ずつ2回がそのために定められている。
② 訓練段階
さきの手続きは訓練以前の段階を含んだものである。神経組織が完了するとき、問題は理論的に解決する。訓練教師の唯一の機能は、子どもを学級に入れるようにする段階まで、できるだけ早く高めることである。
デラカトは治療読みの特殊な規則を述べている。会話と読みの両方で、子どもは自分の経験に帰因する全体の単語に最初に導入されるべきで、次の段階で単語を他の単語や文中の意味、つまり文脈の手がかりとの関係で認識することを援助される。この治療の次に、言語を構成しているより小さな構成内容を分析することに移り、最後に聴覚的な分析に至る。このようにして、読みの指導は概念と単語全体からその細部の基礎に進むべきであると言う。
子どもがプラトー状態に至ったなら、教師は概念全体にもどり、再びその過程を始めるべきである。それがくり返されると、そのサイクルが子どもが学級で学習課題を処理できるようになる程度に長くなるまで継続されるというものである。
Ⅳ まとめと今後の課題
バーシの仮説の指導計画については、さきにも述べたように多くの批判はみられない。それに比べ神経組織の理論と訓練計画には多くの批判がみられる。それは、後者があまりにも特徴のある仮説と訓練計画を提案しているからであろう。前者も含めて詳しい検討は、最初にあげたいろいろの立場の研究者の仮説と指導計画をは握してからとするため、ここでは後者に対する代表的な批判を要約しておくこととする。
カーシナー(J.R.Karshner)の研究によると、訓練可能の精神薄弱児に、デラカトらの技術を用いて約5か月間訓練した結果、両側性と交互性のはらばい運動とははい歩きの統御で、実験群はPeabody Picture Vocabulary Testの結果、有意差で向上したが、Vineland Oseretsky Motor Developement Testによる運動発達については統制群以上のものはみられなかったと報告している。
このことは、言語活動を含まない訓練で運動発達はみられず、語いの理解は増加したという皮肉な結果を示す。フリーマンは、デラカトらに対する批判を要約している。それは、(ア)脳損傷を有する患者たちの自然の臨床経過を無視する傾向がある、(イ)他の方法が症候に対するものであるのに比べ、彼らの方法は脳そのものを扱うという仮定に成り立っている、(ウ)脳損傷による知的遅滞の場合でも、平均以上の潜在性を仮定している、(エ)子どもの自己に動機づけられた活動を強制的に妨げる、(オ)両親に不安と懸念をもたらす、などである。とくに1968年に、研究所に対する公式の非難の決議が続出し、これに対し研究所からも公的に応答が出された。
また、デラカトらが自らの方法を肯定する評価法そのものについても、批判が出されている。しかし、公式の意見や批判の交換、また方法の評価も含めて、総合的な位置づけと評価は、先にも述べたように今後の課題とすることとし、今後の課題は他の仮説と指導計画をは握することが先決となろう。
(Barsch,R. A movigenic curriculum,Wise:State Department of public Instruction,1965,並びにDelacato,C.H. The diagnosis and treatment of speech and reading problems.Springfield,Ill:Thomas,1963,Myers,P.I., & Hammill, D.D.,Methods for Learning Disorders,Tohn Wiley & Sons,Inc.,1969を主要参考文献とし、一部翻訳使用した。)
参考文献 略
*秋田大学教育学部講師
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1973年10月(第12号)12頁~25頁


