シンポジウム/肢体不自由児者―特に脳性マヒの職業的能力開発について 職業的能力開発と医学的リハビリテーション
シンポジウム/肢体不自由児者―特に脳性マヒの職業的能力開発について
<その1>
職業的能力開発と医学的リハビリテーション
小池文英*
1. はじめに
脳性マヒ者(以下CPとよぶ)の職業的能力開発と医学的リハビリテーションというのが私に与えられた課題である。
詳細な論議は省かせていただくが、せんじ詰めれば、この課題は、医学的リハビリテーションによってCPの身体的能力を最大限に開発するにはその方策いかん、ということに帰着するのではないかと思考される。
すなわち、職業的リハビリテーションにおいては、障害者の職業的能力を最大限に開発することを目標とするのであるが、その基盤を最大限に開発された身体的能力に置くのが理想とされていることは、周知のとおりであるからである。
もちろん、職業的リハビリテーションは本人の身体的ポテンシャルのみにかかわるものではなく、心理的・社会的要因に負うところが少なくないことも申すまでもないところであるが、「職業的能力開発と医学的リハビリテーション」という私に与られた課題から見る限りにおいては、上述のようなことになるであろう。
ところで、CPの身体的能力を開発するのを医学的リハビリテーションの立場から大別すると次の二つとなるであろう。すなわち、1)いわゆる機能訓練(ただし、必要に応じて手術や補装具等をも適宜用いる)によって、その身体的ポテンシャルを伸長する。2)上記1)に加うるに自助具を工夫して、さらに身体的能力を伸ばす。
さらに、これに関連して、職業的工具の構造に手を加え、改善して、個々のCPにマッチした、使いやすい(かつ危険の少ない)ものとすることも重要な一面であろう。このことはオーストラリアのCentre Industriesでも積極的に導入されているところである。このことは極めて重要な点であることを協調するにやぶさかでないが、各論に属することであるので、ここでは重要性を指摘する程度に止めさせていただく。
なお、CPの身体的能力を補うための自助具の開発の問題は、CPの障害の性質上、他の障害のそれと比べて相当立ち遅れていることを率直に申し添えておく。
以上に述べたような次第で、ここでは主として1)の問題、すなわち、医学的リハビリテーションによってCPの身体的能力をいかに開発するか、に重点をおいて考察することとする。
2. 療育の可能性
CPの職業的リハビリテーションを成功させるためには、まずその前に、医学的リハビリテーションを成功させることが大前提になることは前章で示唆したところであるが、実はCPの医学的リハビリテーションは、極めて困難な課題であることは衆目のひとしく認めるところである。
その理由は、一言でいうならば、CPが脳の障害に起因する複合障害児であり、かつ肢体不自由だけについてみても、肢体の全般に障害がまたがっているケースが多い、という事実に帰着するであろう。すなわち、CPは肢体の障害のほかに、言語障害、知能障害、てんかん発作、視覚障害、聴覚障害、行動異常等の随伴障害を頻発するほかに、肢体不自由そのものについてみても、単に一肢あるいは二肢の機能障害ということはむしろ例外で、多くは四肢、体幹のすべてが機能障害に陥っているというのが実情である。
したがって、その医学的リハビリテーションがいかに困難であるかは容易に想像がつくであろう。
かつてLittleが1861年にLancet誌にCPについて報告して以来、多年にわたって、CPは医学的リハビリテーションがほとんど不可能な対象であるとみなされてきた。
たとえば、Freudは1887年にCPに関する327ページにわたる総括的な単行本を著作しているが、その中で彼が治療に費したページはわずか2ページ半に過ぎない。しかも、彼はこの治療の章を「みじめな絶望的な章」とよんだのであった。
その後大正、昭和の代に入り、わが国では高木憲次先生、欧米においてはPhelpsらの先駆的研究・開発によって、CPの医学的リハビリテーションに明るい曙光が投じられたのであった。
しかし、他面において、CPのリハビリテーションがあまりにも困難なるがゆえに、医学に不信を抱くものも必ずしも少なくはなかった。とくにCPの親の側から、この種の声があがった例が外国にあったことも事実である。
それでは、いったい、CPの医学的リハビリテーションは不可能であるのか?つまり、いかに医学的な手段を尽してもCPの肢体の運動機能の改善に寄与するところはないのか?という疑問が生ずるであろうが、答えは否である。
確かにCPの医学的リハビリテーションは、困難な課題であることは東西共通しているところであるが、しかし、決して不可能ではない。徐々にではあるが、着実に進歩している、というのが現実の姿であるといってよいと確信する。
このように確信をもって言えるのは、一つには(そして、その大部分は)PT、OTによる機能訓練の技法の進歩に負うところであり、かたや、整形外科的手技(手術や 補装具)に関する考え方(あるいは技術)の前進に負うところであると思考する。
そして、さらに重要なことは、これらを含めて、早期療育の方向に次第にむかってきたという、この一事であろう。この点については次章に述べることとする。
3. 早期療育の重要性
ここ10数年来、世界の趨勢としてCPに対する早期療育の重要性が年と共にますます強調されつつある。Bobathの“Very early treatment”の提唱も、これに拍車をかけることとなった。博士夫妻の考案による独特の早期療育の技法は、CP療育関係者の注目をひくところとなり、早期療育の普及に貢献するところ大なるものがあった。
ここで有名なKoengの早期療育 の成績を紹介しておこう。
Koengはベルン(スイス)のCP通園センターで1958~1962年の間、104例のCP乳児(1才未満)を治療した。(注―重症てんかん、食事摂取の問題または筋緊張度の著しい異常があるようなケースは最初しばらくの間小児病院―Children's Hospital―かまたは近隣の乳児病院―Babies' Hospital―で治療を受けた。)
短期間の治療の後、35例は障害が軽微であることが判明した。彼らは治療を受けなくても本来軽微なケースであったのであろうと思考されたので、この調査シリーズから除外した。
残りの69例については、少なくとも1年間は集中的な訓練を必要とした。
1~4年の治療の後、これらのCP児は表1のごとき運動障害を遺残することとなった。
| 残った運動障害 | ケース数 |
| 軽微 | 53 |
| 軽度 | 9 |
| 中等度 | 3 |
| 重度 | 4 |
| 計 | 69 |
この各クラスの障害に該当するケースのハンディキャップの状況を詳細にわたって説明することは省略させていただくが、この表を一べつしただけで、早期療育(1才未満で治療をスタート)の効果がはなはだ顕著であることが観取されるであろう。
早期療育が、このように顕著な効果を挙げるという事実、換言するならば、CPの療育における早期療育の重要性が強調される理由は何か?これを二つの面から説明し得るかと考える。
一つは神経発達的な側面であるが、脳の発育は一般的にいって幼少時において最も活発である。たとえば、人間の脳は新生児期から6才児までの間に、重量において360%増加するのであるが、その後12才に至る間にわずかに8%増加するに過ぎない。
神経組織学的な面においても、これと並行して幼少時において最もおう盛な脳組織の構築活動が営まれる(しかも低年齢ほど活発)ことは周知の事実である。
もう一つは臨床的な側面である。
すなわち、CPは幼少の時期には、一般的にいって筋緊張も低く、取り扱いが容易であり、異常姿勢反射の抑制や拘縮の防止等も比較的行いやすい等の利点がある。
したがって、この時期(早期)に十分な治療を行うことが得策であることは自明の理であろう。
4. 整肢療護園における成績
―─型別の考察と青年期にける問題点―─
整肢療護園におけるCP児に対する機能訓練の成果の一端を、以下に紹介することも多少の参考になるかと考える。
CPに対する機能訓練、治療の効果は、本人の重症度、意欲等、種々の要素が介入してくるので一概に論ずることはできないが、ここではこうした個人的差異に基づく分析にまでは立ち入らないで、入園CP児の機能的進歩の状況を概括的に例示すると図1a)、b)のごとくである(五味)。
図1 機能訓練の効果
a) 歩行可能例の進歩段階
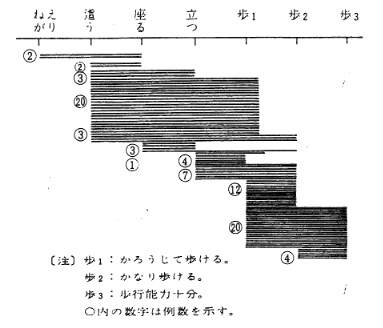
b) 上肢機能の進歩段階
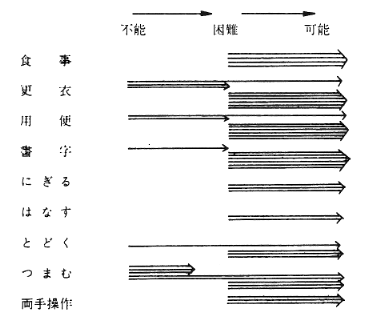
これらCP児の入園期間(すなわち機能訓練を受けた期間)は長短一様ではないが、平均すると2年4か月である。この比較的長期にわたる訓練の効果としては、はなはだ遅々たるものがあるとも感じられる。これは一般入園児(主として6才以上のCP児)の成績を示したのであるが、一方、これと併行して、整肢療護園においては母子入園の制度を多年にわたって実施している。
これは主として学齢前( 注―最近は3才以前の年齢の)CP児を対象とし、母親と共に3か月間収容して訓練を行うと共に、母親を教育して退園後ひき続き家庭において適切な訓練を行うのがねらいである。
この母子入園CP児(すなわち年少CP児)の訓練成績を例示すると、図2のごとくである(五味、浅田)。
図2 母子入園児の動作の進歩
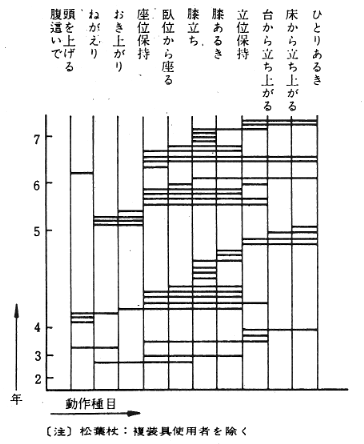
3か月という短期間の訓練としては相当の成果が挙がっていることが観取されたであろう。このことはCPのような慢性的な障害においても、やはり早期治療が重要であることを示唆するものと考える。
ところで、しかし、上記母子入園児は、この成績発表の当時は少なくとも平均年齢が必ずしもそう低くはなかった。すなわち、学齢前ではあったが、前記Koengのごとく0才児と比べればむしろ高年齢児というべきであったかもしれない。
最近はこれより低年齢化して1~2~3才児の辺に集中してきている。
Very early treatmentの意味からはこれでもいまだなお遅いのであるが、今後はいっそう低年齢CP児に手をつけることに努力が払われていくであろうし、またそうあらねばならない。そして、これが全国おしなべての状況、推移をある程度代表する姿であるとみてよいであろうか。
ここで、特にアテトーゼ型について注意を喚起したい。というのは、CPのうち、とくにアテトーゼ型は運動機能面(したがって、おそらく職業面についても)の予後が痙直型に比べて思わしくない、という事実である。
たとえば、整肢療護園において浅田が調査した結果は図3に示すごとくである。
図3 0歳、1歳児CPの運動機能
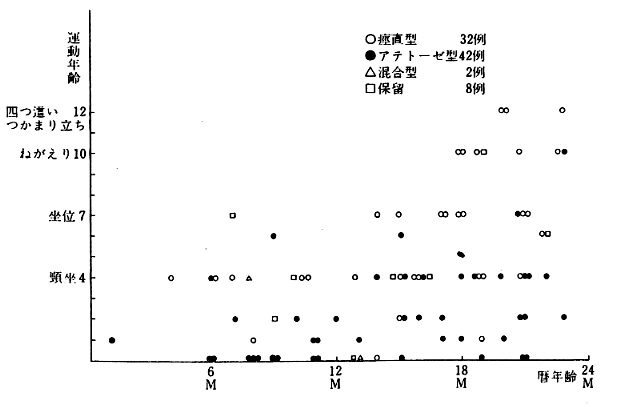
この図は、昭和38年以降整肢療護園を受診した0~1才のCP児84例につき、その初診時の状況を縦軸にM.A.(運動年齢)、横軸に暦年齢をとって表したものである。初診時タイプの決定ができず、その後の経過観察中明らかになったもの、なお保留しているものもある。M.A.の低いものはアテトーゼ型に多く、痙直型では首のすわりや、坐位のバランスが比較的早く可能となったことは予想どおりであった(もちろん、それでも正常児と比較すればかなりの遅れを示すことは事実であるが)。
それでは 、年長児の学齢に達した際に肢体の機能がアテトーゼ型と痙直型と比べてどのようになるか?年少の時期にアテトーゼ型の機能が低かったのが年長期に達すると回復し、取り戻せるか?という点であるが、高橋(勇)の調査によれば図4a)、b)のごとくである。
図4 年齢別にみた機能修得状況(整肢療護院、光明養護学級、東京小児療育病院)
a)歩行機能
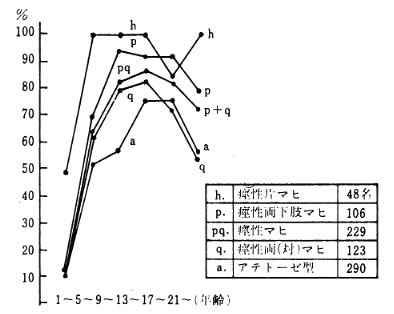
b)上肢総合機能
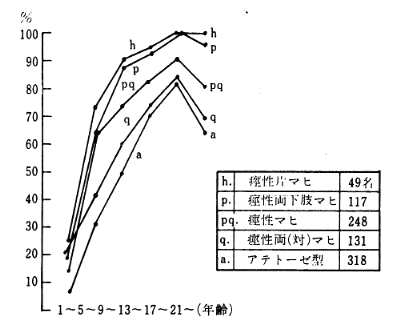
この図は整肢療護園、都立光明養護学校および東京小児療育病院の入園児ならびに退園児合わせて692名のCPについて、歩行能力と上肢機能に関する調査を行った成績である。
歩行機能、上肢総合機能(衣服の着脱、食事、洗面、書字などの能力を総合したもの)がそれぞれある程度可能なケースを年齢別、病型別にプロットして百分率を出したものである。歩行機能については5~6才、上肢機能については5~9才の時期に、それぞれの能力がある程度可能となった者の比率が急激に上昇しているのが観取される。
これに関連して統計的分析を行ったところ、上記各年齢までにそれぞれの能力(歩行能力、上肢機能)をある程度まで獲得することができなかった者の予後は楽観を許されないと考えられた。
また、この図において、片マヒを除くと、いずれも21才から以後にかけて歩行や上肢機能の能力の示すかのごとき結果がみられる。この点については今後さらに検討を要するところであるが、青年期における職業的リハビリテーションと密接な関連を有することが推察される。
すなわち、施設においてリハビリテーションのサービスを受け、ある程度肢体の運動機能の改善をみたものの、それから先の職業的自立においてつまずき、結局家庭に引きこもって無為徒食の生活を余儀なくされ、フラストレーションと運動不足のために機能退化の状態に落ち込んだ、と一般的に解せられるのではなかろうか。
この点からも、CPの医学的リハビリテーションと職業的リハビリテーションの間に相当のギャップが存在していることを否定し難いように思われる。
ともあれ、上図から年長期に入ってからもかつアテトーゼ型が痙直型に比べてハンディキャップの強いことが観取されるであろう。このことからも、CPのうち、とりわけアテトーゼ型について早期療育の重要なことが強調されなければならないと考える。
5. 行政上の諸問題
これまでCPの早期療育の重要性について強調してきたのであるが、これを実施に移すためには行政の関与が不可欠である。
ただし、この問題を詳説するとおびただしい紙数を費すこととなるので、ここでは単に2~3の点につき要約して述べるに止めることとする。
1) 早期発見について
早期療育を成功させるためには早期発見が前提条件となるが、幸いにも最近はCPの早期発見が著しく滲透してきた観がある。
これは行政の側における努力の結果というよりも、むしろ母親の側における保健知識の普及によるところが大であると考えられる。また、他方において、心身障害に対する社会の偏見が薄らいできたことも無縁ではないであろう。すなわち、たとえば、わが子が5か月になったがいまだに首がすわらないのでCPではないか?との疑問を抱き、我々の許を訪れて診察を乞う母親が最近は増加の一途をたどりつつある。
たとえば筆者は過去8年間にわたり、毎月1回日曜日にCP相談を実施しているが、受診者の年齢は逐年的に低下しており、最近では0~2才児が圧倒的に多数を占めるに至っている。
また、整肢療護園の外来を昭和45年~47年の3年間に訪れたCPの初診時年齢は表2のごとくである。
| 0~1歳 | 1~2歳 | 2~3歳 | 3歳以上 | |
| 昭和45年 | 23名 | 45名 | 50名 | 94名 |
| 昭和46年 | 16 | 37 | 32 | 86 |
| 昭和47年 | 12 | 30 | 31 | 78 |
| 計 | 51名 | 112名 | 113名 | 258名 |
3才以下が3才以上をやや上まわっているという程度である。0~1才の年齢群は全体の10%弱を占めるに過ぎないのであって、早期受診という点からみると、いまだ不満足な状況にあるが、しかし、たとえば10年前には学齢期のCPが大多数を占めていた状況と比べると格段の進歩とみてよいであろう。おそらく今後数年の間に早期受診について著しい進展が期待されるのではないかと思考される。
以上のようにCPの早期発見・受診については放置しておいても、自然の趨勢として次第に良い方向に向かっていくものと思われるが、これに加うるにさらに行政的な施策いかんということになれば、その最たるものは保健婦の再教育であろう。
すなわち、保健婦に対して脳損傷による乳児期の特有な症状を教え、疑わしいものはしかるべきルートに紹介する、というシステムを確立することが望ましいと考える。
2) 早期療育の場
前述のとおり最近はCPの早期発見は着実に進展しつつある。ところで、これに呼応する早期療育の体制がいまだはなはだ不備であること、すなわち、早期発見と早期療育との間に相当のギャップが横たわっていることが当面の重要な課題となっている。
行政的にみて、CPに対する早期療育の場としては次の二つが考えられる。
①肢体不自由児施設における母子病棟
②肢体不自由児通園施設
このうち①は従来早期療育に関して重要な役割を果たしてきたが、しかし、早期療育とはいうもののやや年長児に対する療育に傾くきらいがなきにしもあらずであった。すなわち、3才またはそれ以後の年齢前のCP児を対象とした傾向がなかったとはいえない。最近はこれに反して幼少児の方向に向かいつつあるが、厳密にいうと、0才児の指導という点についての体制はいまだ固まっていない、というのがおしなべての実情であろう。
人員と設備の両面を含めて、この点の再検討が迫られているように思われる。
次に②の通園施設についてであるが、これも年齢的にみると概して3才以後の年齢(はやくても2才以降)を対象としているものが大部分であるようである。早期療育とはいうものの必ずしも十分とはいい難い。
しかし、通園施設に0才児を通園させるということになると、現在の体制では若干の無理がある。今後の研究課題の一つとして取り上げるべきところであろう。
もう一つは職員の問題がある。この通園施設には保母等のソーシャルな面を担当する職員は概して充実しているが、PT、OT、STのように医学的リハビリテーションを担当する職員が不足していることが大きな問題点となっている。これは、これら専門職員の養成制度の遅れを反映するものであるが、では、いかにしてこの欠陥をカバーしてCPの早期療育を達成するかが重大な関心事となる。
3) 肢体不自由児施設の活用
――地域センターとしての性格の強化――
以上の諸点をふまえて、0才児CPに対する早期療育の推進のためには肢体不自由児施設のよりいっそうの活用が要望されると思われる。一般的にいって、医療の問題は大学病院等に援助を乞うのが常道とされているが、CPに関する限り大学病院の医療陣ははなはだ無力であるのがおしなべての実情であり、CPについての知識・技術ならびに興味と意欲を持っているのは、現状においては肢体不自由児施設の関係者がその最たるものであるといってよいであろう。
こうしたわけで、CPの療育に関しては肢体不自由児施設が最も有力なる社会資源であることは、一般論として衆目の認めるところであるが、早期療育についてもこの例外ではない。
さて、肢体不自由児施設が0才(ないしはこれに近い低年齢)のCP児に対する早期療育に関して、どのような貢献ができるか、というと、主として次の三つに大別されよう。
ア.母子入園児の年齢を引き下げる。
すなわち、従来は2~3才以上の年齢のCP児を対象としていたのが大方の施設の実情であったが、この年齢を下げ、0才児を積極的にとるように方向づけるのである。
このためには母子病棟の設備・構造ならびに運営方針等において、改修を要する部面もでてくるであろう。
イ.肢体不自由児施設の外来部門においてCPの早期療育に関する指導(とくに母親に対する)を徹底的に行う。
理想的にいえば、医師、PT、OT、ST、MSW等がチームとなって指導することが望ましい。しかし人手不足でそこまで手がまわらない場合には、せめて医師とPTが十分な時間をとって0才児CPの指導に当たることが要請される。そしてこの指導はもちろん1回のみでは無意味に近く、その後定期的にフォロー・アップすることが必須であることは申すまでもない。
ウ.通園センター、保健所等への指導
上述のように通園施設には専門的スタッフを欠く憾みがあり、かつ通園児もやや年長児(たとえば3才前後)であるのが一般的傾向である。
そこで、これら通園施設一つの新しい機能として、0才のCP児を積極的に招き入れ、その母親に対して定期的に療育指導を行うことも考えられるところである。その場合の技術的な面の担当は、その地域社会における肢体不自由児施設の医師やPT等が巡回して受け持つことにするのが、最も現実的に妥当な行き方であろうと思われる。また同じ趣旨で保健所を利用することも考えられる。
要するに、従来は法律の定めるところにより、肢体不自由児施設は児童相談所から措置されてきたケースを収容して、これを療育していれば一応こと足りていたのであったが(注―実情は必ずしもそのように消極的なものではなかったが)、今後は天下晴れて、積極的に地域社会のリハビリテーション・センターとして活躍し貢献するような体制となることが望まれるのである。
4) その他の諸問題
CPの早期療育に関しては、以上のほかにも種々の問題がからんでいる。
たとえば、専門家(医師、PT、OT、ST等)の深刻な不足の問題がある。この問題の解決のための一策としては、母親の教育を徹底的に行うことである。もちろんこれだけですべてが解決するわけにはいかないが、欧米においても相当の実績があげられており、わが国においても今後もっと推進してよいプログラムの一つであろう。
また、早期療育の技術面、理論面での開発も大いに要請されるところである。このためには海外との交流(人的並びに文献を通じての両面での)をいっそう活発にすることが大切であろう。
6. 青年期における問題点
CPの早期療育についての行政上の問題については、上述のほかにもなお幾多の論議を重ねなければならないのであるが、ここではそれを省かせていただき、次の課題として(途中をとばして)青年期の問題について少し触れておくこととする。
前述の図4のa)、b)にも示したように、片マヒを除くと、青年期に入って歩行や上肢機能の能力の低下を示すかのごとき結果がみられている。このことは、CPが青年期に入っても職業的自立ができない精神的苦悩を、ある程度反映している事実とも受けとられるところである。すなわち、肢体不自由児施設等においてせっかく一応の医学的リハビリテーションを達成したが(ADLが可能となったが)、社会で受け入れる場がないため家庭に閉じこもって無為徒食の生活を余儀なくされ、運動不足とフラストレーションが重なって、せっかく獲得した運動機能が退歩してしまう、というケースが必ずしも少なくないのである。
我々の無策、無力が悔まれる次第である。
次に、青年期以降において、医学的リハビリテーションがCPの職業能力開発と直接に関連する分野としては工具の改修の問題がある。すなわち、職業に用うる工具、器具がそれぞれのCP者に使いやすく(かつまた危険のないように)するための工夫である。さらには工場、作業場の生活環境改善の問題も含められるであろう。
わが国においては、この分野における研究がとくに遅れていることは遺憾である。この問題につき医学関係者と職業的リハビリテーション関係者、さらには工学関係者の密接な協力のもとに、積極的に研究を推進することが要望されるところである。また、行政の側からの強力な援助を必要とすることも申すまでもない。
参考文献 略
*整肢療護園長
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1974年1月(第13号)21頁~28頁


