整形外科的障害をもつ学童の学業成績と対人関係の関連性
整形外科的障害をもつ学童の学業成績と対人関係の関連性
Correlates of Orthopedically Disabled School Children's School Achievement And Interpersonal Relationships
Reginald L. Jones, Ph. D. *
真田英進**訳
整形外科的障害をもつ子どもの学業成績と対人関係に関する研究はほとんどない。これのひとつの説明としては、いろいろに分類される子どもたちの非常に大きな多様性を一般化することは、かえってその信頼性が無くなってしまうといった考えが、もっともらしいようである。こうした考えにもかかわらず、パーソナリティの発達について、障害の程度とパーソナリティ特徴の相互作用について、障害の程度─特に身体的依存性─と学業成績について、などといった非常に多くの問題が存在している。したがって、信頼できる研究結果がそれとして正当化される必要があるのではないかと実感して、以上に述べたような問題に関したデータを提供することを本論文の目的とする。
個々の仮説は後に示されるとおりである。ここでは、本研究を説明する考えがごく一般的な型で概略的に述べられる。それらは次のごとくである。すなわち、身体的依存性の程度が減少するにしたがい、また、可動性が増加するにしたがい、整形外科的障害児は内的に制御され、有意的な他者(例えば、教師とか友人)との彼あるいは彼女の関係における適応が良好となる。また、より高い水準の成績を示す。もちろん、この逆は、身体的依存性が増加し、可動性が減少するにしたがって、子どもは自分の環境に対する関係において外部的に目を向けるようになり、教師や友人との関係に障害をきたし、より低い水準の成績を示すであろう。
文献を検討してみると、以上のように仮説化された関連性を取り扱っている研究が無いということがわかる。事実、Connor、Rusalem、Cruickshankらは肢体不自由児の発達に影響を与えている要因に関する文献を検討して次のように述べている。
「肢体不自由児の発達にあたえるところの、障害程度や持続期間、家族や家庭状況、社会経済的地位などの影響についてほとんど知られていない」と。
方法
被験児。標本は6歳から16歳の102名の子どもから構成されており、彼らは中西部の大都市にある整形外科的障害児のための特殊小学校に在籍している。63名の男子と39名の女子は能力(重度遅滞を除く)や整形外科的障害の程度がすべての範囲にわたっている。
能力の点については、教育委員会の方針では、めいめいの子どもの知能テスト得点を、大まかな範囲でのみ通知できるように命じている。段階構成と各水準での子どもの数は次のとおりである。平均以上(IQ111以上)8名:平均(IQ91-110)23名:準平均(IQ81-90)24名:学業不振(IQ80以下)46名。1名の被験児の能力段階に関する情報は全く得られなかった。以上の知能分布からみると、本研究で対象とする子どもの集団は平均値以下の知能であることがわかる。しかしながら、これらの被験児をもって他の場面での整形外科的障害児の母集団へ匹敵され得るかどうかはもちろんわからない。
手続き すべての被験児はBialer Locus of Control Scaleを行った。この手段は生徒の内的統制対外的統制の方向性を測るように意図している。内的被験児(internal subjects)というのは自分の成績に自から責任をもっていると思っているような子どもであると定義される。一方、外的被験児(external subjects)は自分の成績に影響を与えるには無力だと自分を認知し、支持や指導を求めて他者への依存を感じている。
教師たちは、めいめいの子どもの歩行の状態、成績、本研究での関心事にかかわる他の要因などについてデータを提供する質問用紙を記入した。質問紙の例(スペースの関係で配列は変えた)は以下に示されるとおりである。
教師用質問紙
1.子どもの歩行状態はどうか。(a)歩行できる、(b)支持(例えば、松葉づえなど)で歩行できる、(C)歩行不可能(車いす使用、など)。
2.健常児と比較して、着衣、食事、トイレといった基本的活動で子どもが他者の支持にどの程度依存しているか。(a)これらのことで何ら特別の助けを必要としない、(b)これらのことでいくらかの助けを必要とする、(c)これらのことに常に一貫した注意が必要である。
3.児童の学業成績をどのように評価するか。(a)学年水準に見合った成績を示す、(b)学年水準以下の成績を示す、(c)学年水準以上の成績を示す。
4.教師、セラピスト、学校の他の大人たちと児童の一般的関係を評価せよ。たいへん良い─たいへん悪い(7得点尺度)。
5.他の児童や友人たちと児童の一般的関係を評価せよ。たいへん良い─たいへん悪い(7得点尺度)。
6.ある子どもたちは〈内的〉に統制化されていると分類できる。彼らは自分の成績に責任を負っていると認知している。他方、ある子どもは〈外的〉に分類できる。彼らは自分の成績に影響をあたえていないと認知し、他者に指導や支持を求め依存感を持っている。もちろん、これらは明確な型となっているわけではないが、しかし上のようにあげた場合、児童をどのように分類できるか。(a)外的に動機づけられている、(b)内的に動機づけられている。
7.だいたいいつごろ障害が生起したか。(a)出生時あるいは出生のころ、(b)出生後から2歳まで、(c)2歳以後、(d)不明
以上の質問に対する解答に加えて、教師はそれぞれの子どもの性別、年齢、能力段階などの資料も提供した。
データ分析 表に載せられた変数間の相互作用はカイ自乗(chi square)を使用して決定された。また、表中の各変数とBialer Locus of Control Scaleの相関は共分散分析(ANCOVA)の使用により検定された。共分散分析は最後にlocus of control得点に対する年齢効果をコントロールするために必要とされた。この手続きによる先行研究から、子どもたちは年齢があがるにつれてより多く内的な方向性をもってくることがわかった。本研究ではlocus of controlが年齢以外の他の諸変数と関係づけられているわけであるから、各下位グループのlocus of controlの変数がいかなる年齢にも偏らないように、年齢とlocus of controlの関係が統計的にコントロールされた。
結果と考察
変数間の相互作用の分析結果は以下に示される。同時に、これは本研究の主要な仮説に関する資料の考察でもある。
八つの変数の中で、歩行能力の状態、依存の程度、障害が生起した年齢、Bialer Locus of Control、並びに、その教師の評価によるものなどは独立変数と考えられる。他方、成績、教師の評価による児童-教師関係並びに児童-児童関係などは、従属変数であると考えられる。以下の論考では、独立変数と従属変数の関連性に注意が払われる。従属変数間での相互作用は単なる偶然的なものであるとみなされる。
変数の相互作用:カイ自乗、連関係数、共分散分析
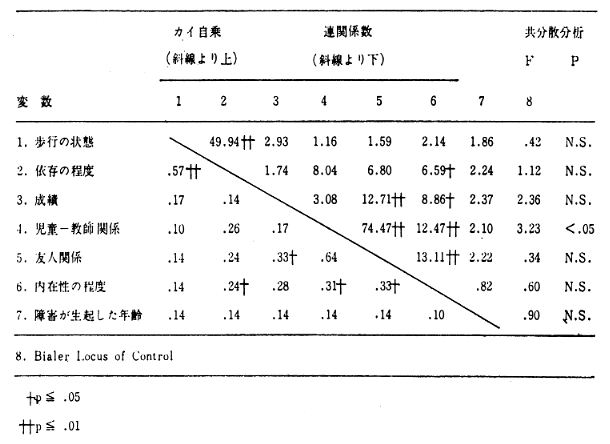
歩行の状態 子どもの段階づけされた可動性の程度と成績、友人や教師との関係、locus of control、すなわち、これは教師とBialer尺度によって算定されたものであるが、これらが最初に分析された。検討された仮説(P<.05)可動性の程度が学業成績、児童-教師関係それに友人関係、あるいは、locus of controlなどと有意な関係はないのではないかということであった。(以上のような各要因とそれらの結果は個々の仮説ごとにそれが構成されるべきものであるが、ここでは便利上一緒に示される)。歩行の状態とlocus of controlに関するもう一つの仮説は以下のとおりである。歩行が遅れたり、初期の歩行問題をもつ子どもは、自分の身体的ニードを満たすために他者に依存するので、内的に統制されるよりもむしろ外的な方向づけがなされるであろう。
予測に反して、表に示されたデータの検討として、何らかの歩行能力の程度が多かれ少なかれ子どもを外的な方向づけをするであろうといった信頼性ある傾向は、認められなかった。さらに、歩行の状態は、教師の評価による成績、児童-教師関係並びに児童-児童関係、あるいは教師とBialerの評価によるlocus of controlなどについても信頼できる関連性は認められなかった。このことは次のように考えられる。可動性の程度のすべてにわたる児童たちは、成績、児童-教師関係や友人関係、内的なlocus of controlまた外的なlocus of controlなどのすべての範囲にわたっていることを示している。つまり可動性の程度は、前述したいかなる変数とも統計的には有意な関係をもっていないことが認められた。
予想されたとおり歩行の程度と身体的依存度の関係に統計的な有意性が認められた(P.<01)、たとえば、可動性が乏しい児童はより依存しがちである。歩行の状態と障害が生起した年齢とはいかなる関係も無かろうと仮定され、そのとおりであった。
身体的依存度 人格発達や機能に対する整形外科的障害の影響を概念化する場合には〈依存〉が重要な変数である。特殊教育者にとって、依存と有意変数の関係についての疑問は、整形外科的障害児における障害の程度と学業、依存度と児童─教師関係並びに児童─児童関係にはどんな関連性があるのだろうか、といったような内容をもっている。児童のパーソナリティ発達には次のような重要な疑問が存在する。つまり、早期のまた長期間の身体的な依存は、整形外科的障害の結果による身体的依存度と関係をもたないlocus of controlの人格よりも、むしろ、外的に志向されたlocus of controlの人格を作るのではなかろうか。
依存と学校での変数に関する仮説は次に述べるようなことが言える。身体的依存度が増すにつれて、教師─児童関係並びに児童─児童関係、成績などにおいてだんだんと悪くなるであろう。この仮定は、さらに次のように短く説明できよう。身体的ニードを満たすことに気がとられていたり、可動性を欠いたりして身体的に他人に依存する子どもは、健常児ほどにも社会的関係や対人関係における技能を発展させることができないであろう。同様に、こうした身体的なニードをもつということは児童の学業課題への注意を減少させるであろう。
以上、最終的な仮説としては、より屈強な友人に比較した場合、身体的な依存をしている子どもは学業成績、教師との関係、友人との関係などであまり良好でないということになる。
この仮説に関するデータは表の2行目に示されている。依存が児童の成績、児童-教師関係ならびに児童-児童関係などに関係しているという仮定については、すべて結果から、あらかじめ決定されていた.05%水準の有意性を満足させることができなかった。子どもの身体的依存の程度の一つが、他のある依存程度の子どもが示す成績より一貫した良い(あるいは悪い)成績と関連するだろうと仮定されたわけであるが、このことは、そういった信頼性がある傾向が得られなかったということを示唆するものである。同様に、評定された依存程度とBialer Locus of Control尺度には統計的に信頼性ある関連は認められなかった。
Locus of Control locus of controlは教師によって、また、Bialer Locus of Control尺度によって評定された。両尺度の使用における疑問としては、locus of controlの測定で教師たちは正確な評価ができるだろうかということである。この疑問は肯定的に答えられなかった。表に示されるデータによれば、年齢が統制されている場合、内在性に関する教師の評定とBialer尺度の得点との間には統計的に有意な関連性は存在しなかった(F=.60、P>.05)。
Bialer Locus of Control得点と他の変数との諸関係についての、その他の結果は表に示されるとおりであり、これは次のような考えから検討されたものである。これは、特殊児童と非特殊児の母集団について、先行結果を考慮した場合に、内在性(Bialer尺度)の程度は成績と積極的に関係している(内的に方向づけられている子どもはその成績がより良好)。また、児童-教師関係や児童-児童関係ともに積極的に関係している(内的に方向づけられている子どもはよりよい程度の関係を保つ)といった考えである。
既述したように共分散分析(年齢は統制している)はBialer Locus of Control尺度を含むところのすべての関係について検定するように使用された。三つの主要な従属変数についてみると、児童-教師関係だけにおいてのみ、locus of controlの諸下位グループにおける統計的信頼性がある相違が認められた。
出てきた結果を検討してみると、内的に方向づけられた被験児は高い水準の児童-教師関係を有しているとみなされる。一方、児童-教師関係についての低い水準あるいは平均的水準の得点をもっていると見なされる子どものlocus of controlの得点では、統計的に有意な何らかの相違が存在していないということがわかった。児童-児童関係にかかわる仮説的関係にあらかじめ決められていた.05%水準の広い信頼限界にも達することができなかった(P<.10)。しかし、成績と内在性について予測された関係は.05%水準(P<.10)に近づいた。健常群に対する結果を考慮した場合、したがって、Bialer Locus of Control得点と学業成績、並びに、学校での対人関係にはある一定の関連性があるだろうという仮定は一部支持できるところもあった。
障害が生起した年齢 障害が生起した年齢は依存の程度や内在性、したがってまた、成績、学校での対人関係などと統計的に有意な関係をもつであろうと仮定された。表の7行目に入る数字を検討してみると、障害が生起した年齢とその他の残りの7変数の関係には何らかの統計的な有意性も存在しなかったことがわかる。仮説が支持されなかったことについては説明のしようがない。しかしながら、本研究のような試みにおいて、障害生起年齢に関する何らかの範疇が設定されたことは注目すべきことである。本研究における障害生起の年齢区分は次のとおりである。a)出生時あるいは出生のころに障害を受けた、b)出生から2歳まで、あるいはc)2歳以後、となる。障害を生じた年齢が早ければ早いほど依存度も大きくなる。そして、学業成績との関連が、仮定されたように認められた。
結果の検討から次のようなことが言えよう。すなわち、より厳密な仮説として、依存度の増加と障害生起年齢は重度身体障害児においてのみ共分散が認められるであろう、ということが考えられるであろう。残念ながら、本研究では、この修正された仮説に対して厳密な検討を加えるためのデータが集められていなかった。しかしながら、この分野における次の研究を行う場合に格好な端緒であるように思われるわけである。
(Rehabilitation Literature, September 1974から)
*カリフォルニア大学(バークレー)アフロアメリカ研究・教育学教授
**東京教育大学教育学部石部研究室
(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「リハビリテーション研究」
1975年4月(第17号)19頁~22頁


